『戦後史の正体』(孫崎享著)をめぐる断想 [本]
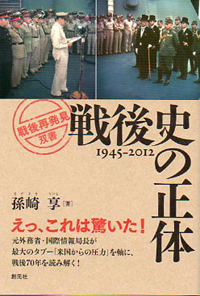
本書を読み終わってわいてくるのは、日本の政治や経済がかくも米国によって牛耳られているのかという思いである。日本はいまだに米国の属国だという思いがぬぐいきれない。そうなった原因は、もちろん日本が無謀な太平洋戦争に敗れたことにある。しかし、情けないのは敗戦から67年もたとうというのに、その状況がいまもつづいていることだ。
ここから脱却するには、新たな憲法をつくり、軍を備え、真の外交を回復しなくてはならない。そもそも米国製の憲法を後生大事に守り、半世紀以上にわたって外国軍隊の駐留を許している国は国家の体をなしていないからだ。日米安保条約を廃棄し、米軍を国防軍(現在は自衛隊)に置き換えるべし。本書はそこまではっきり書いているわけではないし、ぼくの勝手な思い込みにすぎないけれども、著者は心の奥底にはそんな思いをいだいているのではないかと、つい想像してしまうほどだ。
ただし、著者のえがく国家像は、おそらく戦前型のまるで戦争マシーンのような帝国主義国家とは異なる。それは徹底した平和国家だといってよい。たとえ米国がアジアや中東などで戦争をしかけようと、それが誤りだと判断されれば、日本はそれに関与しない。米軍に基地を貸すこともしない。国防軍は海外に派兵せず、まして現在のように米軍のサポート役を果たすわけではない。あくまでも自衛に徹するというものだ。
その点、現在の改憲派が、米国の世界戦略によりよく対応できるよう、第9条を変更して、集団的自衛権なるものを盛り込もうとしている姿勢とは異なっていると想像する。
何はともあれ、著者は事実上米国の属国という立場から日本は自立すべきだと主張しているように思える。米国と敵対しようというのではない。対等の平和友好通商関係を結ぼうというのであって、それは、中国やほかの世界各国に対しても同じである。ちょっとうがちすぎかもしれないが、それが著者の考え方だとみてよいのではないか。
大いに賛成である。最終的に国家が消滅するのなら、もっといい。
白洲次郎は米国べったりの「プリンシプルのない日本」を批判したが、著者の立場も同じといってよいだろう。「力の強い米国に対して、どこまで自分の価値をつらぬけるか」。それが著者の立場であり、「かつては日本の外務省の中心的な思想」でもあったという。
本書は「戦後の日本外交は、米国に対する『追従』路線と『自主』路線の戦い」のせめぎあいであったという視点から、戦後の日本政治史を見つめなおそうというものだ。快刀乱麻を断つといおうか、実にすっきりとわかりやすい。しかも志の高い快著である。
著者によれば、対米追従派の首相として挙げられるのは、吉田茂、池田勇人、三木武夫、中曽根康弘、小泉純一郎などで、概して任期が長い。これに対して、自主派と目されるのは石橋湛山、岸信介、鳩山一郎、佐藤栄作、田中角栄、福田赳夫、宮沢喜一、細川護煕、鳩山由紀夫などで、米国に対して堂々とものを言ったために、概して在任期間が短い。そして1990年以降は、とりわけ米国べったりの姿勢ばかりがきわだつようになったという。
対米追従派しか首相の座に長くとどまることができないという著者のテーゼは、佐藤栄作という例外(逆に三木武夫の場合は短いこと)や、首相が1年交代という最近のていたらくをみれば、どうもあてにならないが、それは深く問わない。しかし、著者が追従派より自主派を高く評価していることはまちがいないだろう。
ここで歴代の首相をすべて取りあげるわけにもいかないから、試みに追従派とされている吉田茂、自主派とされている岸信介を著者がどうとらえているかをみておくことにしよう。
著者は吉田茂が「米側にすり寄っていた」とし、「対米追随路線のシンボル」と断罪する。
〈思えば吉田首相は、占領下の首相に実にふさわしい人物でした。ある意味で占領中の彼の「対米追随路線」は、しかたない面もあるでしょう。問題は彼が1951年の講和条約以降も首相の座に居すわりつづけたことです。その結果、占領中の対米追随路線が独立後もまったく変わらず継続され、むしろ美化されて、ついには戦後60年以上もつづくことになってしまった。ここが日本の最大の悲劇なのです〉
著者は吉田茂を対米追随路線の元凶とみている。さらに「米国のいうことを忠実に聞く」吉田が、講和条約に調印するため、サンフランシスコに出かけたさいに、「独立国が結ぶべきではない」日米安保条約にたった一人で署名し、「米軍の常時駐留を認め」てしまったことも糾弾している。
はたして、この評価はただしいのだろうか。
いっぽう、自主派とされる岸信介は、一見米側にすり寄っているかのようにみえて、実は「米国の力を利用して自分の正しいと思う政策を実現しようと考えていた」と評価は高い。
岸は「不平等な旧安保条約の改訂[ママ]をするため、全力で奮闘し」、「対米従属路線からの脱却」をはかった。それによって、安保条約を「相互契約的なもの」へ変えようとした。それ自体は米国も賛成だった。ところが、岸はさらに在日米軍の「最大限の撤退」と行政協定(のちの地位協定)の見直しに手を着けようとする。そこで、「岸首相の自主独立路線に危惧をもった米軍およびCIA関係者が、工作を行って、岸政権を倒そうとした」というのである。
この指摘もユニークである。
ついでにいうと、ほかに米国が倒そうとした政権としては、田中内閣と細川内閣がある。
米国が田中角栄を切り捨てたのは、田中が日中国交正常化を実現し、「結果としてニクソン訪中の果実を横どりした」ためだ。そのため米国は立花隆の「田中角栄研究」を利用して、田中降ろしを画策した。「米国・新聞・政界がいっしょになって動く構図」がはたらき、経済界も同調して、田中は首相を辞任することになる。さらに、これに追い打ちをかけるように米国は「ロッキード事件」の「謀略」をしかけ、田中を政治的に抹殺したのだという。
細川内閣は「冷戦的防衛戦略から多角的安全保障戦略へ」という路線を打ちだし、それによって米国一辺倒の姿勢から脱却しようとした。そのため米国はまず「北朝鮮に近すぎる」という理由で、武村正義官房長官の更迭を求めるなどして、「細川つぶし」をはかろうとしたが、ほぼ同時に「佐川急便事件」が発覚して、細川が政権を投げだしたという。
これが事実かどうか、部外者であるぼくには判断する材料がない。しかし、外務省の国際情報局長を務めていた著者の記述であるだけに信頼性は高いのだろう。そのほかにも、知らなかった事実の暴露が多々みられる。日本政府に対する米国の圧力は、陰の部分も陽の部分も含めて、思う以上に強かったし、いまも強いのだとみてよい。
だからこそ、「力の強い米国に対して、どこまで自分の価値をつらぬけるか」が問われるというわけだ。
だが、ここでわずかばかりの疑問がわいてくる。はたして日本の首相は、米国の意向に沿うか沿わないかによって、政権を長く維持できたり、あっというまに倒されたりするようにやわいものなのだろうか。外交関係はもちろんだいじであって、それによって内閣の命運が左右されることはあるだろう。だが、内閣は外交だけをになっているわけではない。内政もあるし、経済問題だってだいじだ。だとすれば、米国のゴキゲン次第で、内閣がふっとぶという構図は、ちょっと単純すぎるのではないか。
吉田茂にしても岸信介にしても、著者の評価は、政治家像全体としてみれば、まちがっているのではないか。それに吉田は追随派で、岸は自主派だと単純に割り切れるだろうか。そんな疑問を抑えることができない。佐藤栄作や中曽根康弘の評価についても、首をかしげるところがある。二分法の限界かもしれない。
対米追随ではなく、自主路線を。それは大いにけっこうなことだ。だが、著者の評価する自主路線は、反米ともちがうような気がする。あくまでも日米安保条約の枠を守りつつ、平和国家としての立場から、できるかぎり米軍の撤退を求め、米国の理不尽な要求には抗するというのだろうか。その程度なら(それ自体容易なことでないにしても)、ちょっと寂しい。追随といい、自主といっても、ラケットの裏表みたいなものではないか。
プリンシプルなき日本。「第二の敗戦期」を迎えたとされる日本。自主路線が見かけ倒しに終わらないためにも、いま必要なのは新たな国家(あるいは脱国家)への構想力なのかもしれない。
2012-10-31 16:42
nice!(3)
コメント(0)
トラックバック(0)




コメント 0