『霧の犬』(辺見庸著)を読みながら [本]
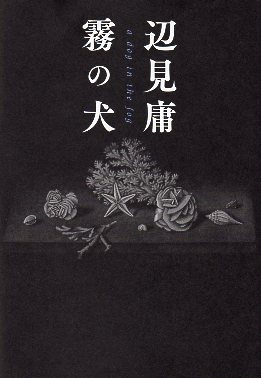
いりえに面した町には霧が立ちこめている。その霧は晴れる気配もなく、ますます濃くなり、家のなかにも侵入してくる。戦争がはじまったらしい。無蓋貨車でつぎつぎ戦車が運ばれていく。近くに核爆弾が落とされたのはまちがいない。霧の色がさまざまに色を変え、濃くなってくるのは、そのせいだろう。町では大勢の人が死に絶えた。すでに町を出ていった人も多い。
この世の終わり。たぶんそうだ。町に残る人も数少なくなった。死者と生者が行き交いはじめている。空間が霧にとざされ、時間が入り乱れる。そのなかを三本肢(あし)の犬が歩く。
わたしは女に足を洗ってもらっている。わたしが女の足をあらうこともある。気持ちがよく、うっとりする。わたしは式神を飛ばすかのように、部屋の外に分身をはなつ。原を押しわけ、町に踏みいって進む分身たち。
それは、たしかに小説の世界だ。シュールな小説の世界。
だが、ほんとうにそうだろうか。
すべてのできごとは、とつぜんはじまる。現にわれわれは3・11の地震と津波で、町や人びとが海に引きずりこまれる風景を目の当たりにしたではないか。原発という魔法の箱がくだけちるのを目撃したのではなかったか。友人が亡くなったり、行きつけのプールが閉鎖されたり、といった日常のできごとも、おこるときはとつぜんだ。
ほんとうは、それまでの長いいきさつがあったのかもしれない。でも、われわれは知らなかった。気づいていなかった。知らないまま、気づかないまま、のんべんだらりとした日常を送っていた。だから、すべてはとつぜんやってくる。気がついたときには、すでにそれがはじまっている。とつぜんの事態に、われわれはおののき、右往左往する。しかし、おこってしまったできごとは、もとに戻らない。
戦争などおこるわけがない、核爆弾など落ちるわけがない、人類は滅びるわけがない、とわれわれは思いこんでいる。しかし、それはとつぜんやってくる。
『霧の犬』でも、とつぜんの滅びの日がはじまっていた。いや、もう終わろうとしていた。
この小説では、わたしとわたしの分身以外にも、多くの人物が登場する。町を牛耳ろうとしているのが恐怖党員の連中だ。最近までわたしのからだをもみほぐしてくれていた女整体師は、行方不明になった。どうやら恐怖党のだれかにつれさられたらしい。わたしの息子と妻は自死した。仕事熱心な、ろくでもないフォトジャーナリスト。ばか医者兼副院長。すなっく「ほ」のママ。霧のなかを三本肢の犬が歩いている。
ここに登場してくる人物は、すべて「ふ」とか「き」とか「あ」とか「む」とか「ゑ」とか「ん」とかの符号で呼ばれる。もはや固有名はない。だれもが国家のもとに管理されているのだ。いま国を動かしている「ふ」は、われわれが毎日いやでもテレビで見せられるだれかとそっくりだ。
それにしても、この小説は美しい。町は霧のなかに閉ざされているのに、犬や動物はもちろん、さまざまな魚や木々、草ぐさの姿と色にあふれかえっている(猫はいない)。これまで見たこともない映画をみているような気分にさせられる。オペラのアリアも聞こえてくる。ラッシャー・キオ・ピアンガー・ミア・クルーダ・ソルテー……。苛酷な運命に涙し、自由にあこがれることを許してください……。
たとえば冒頭の部分を引いてみる。
〈霧であった。無蓋貨車がゆっくりとはしっていく。夜がゆれる。シロツメクサがぬれている。バリケードもぬれている。いつからかずっと霧だった。こまかな絹のくず。霧がどこからともなくわいていた。霧はずっとふりやむことがなかった。……霧の空をアメフラシの群れが一列にゆっくりとはっていた。……夜は青みがかった乳色をしていた。霧はとめどなくながれた。イトミミズが霧の底で赤くよわく発光していた〉
映像化されれば、すばらしい映画が生まれるだろう。殺しやエロスにもことかかない。
三本肢の犬は、たぶん人びとに最期の幸せをくばるために、霧のなかを歩いている。滅びの日。それはとつぜんやってくる。読者はいまを問われるだろう。
2014-12-11 10:02
nice!(7)
コメント(0)
トラックバック(0)




コメント 0