サルトルを読みたい [われらの時代]
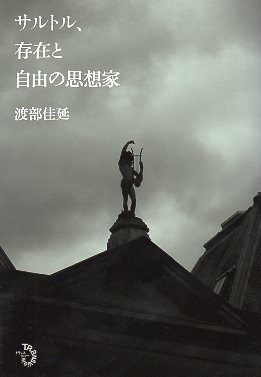
サルトル(1905-1980)を読みたいと思ったのは、1966年秋のころである。高校3年生のときだった。河出書房から発行されていた「世界の大思想」シリーズの1冊にサルトルが含まれていて、少ない小遣いのなかから、それを買った。いまからすればけっこう高かったと思う。訳者は松波信三郎で、そこには『存在と無』の抄訳、それにいくつかの短い哲学論文が含まれていた。
それを高砂から姫路に通学する山陽電車の車中で、毎日読んでいた。まるで歯が立たなかった。けっきょく、ひと月もたたないうちに放棄したのではなかったか。しかし、本を集めるという妙な癖だけは残って、東京の大学にはいってからも、古本屋で人文書院から出ているサルトル全集をみると、何となくほしくなり、それをせっせと買いこんだものである。こうして、ぼくの本棚にはいまでも、『存在と無』や『弁証法的理性批判』、『シチュアシオン』、あるいは『反逆は正しい』が残っていて、いくつかの解説書やサルトル伝まで鎮座している。
よくわからないままに、サルトルというブランドだけで次々と買ってしまった。これはどうみてもブランドに踊らされていたのである。その始まりが高校生時代だった。どうして、1966年だったのだろうとふり返っているうちに、渡部佳延の『サルトル、存在と自由の思想家』を読んで、その理由がやっとわかった。
この年、1966年9月にサルトルが来日し、日本じゅうがサルトル・ブームにわきたっていたのだ。東京・日比谷講堂での講演には、人びとが押し寄せたという。渡部の著書には、新幹線に乗り遅れそうになったサルトルとボーヴォワールの到着を、列車がじっと待ったというエピソードがでてくる。そのため10時発新大阪域の新幹線は、発車時間を3分間遅らせることになった。それほどサルトルは、世界を代表する文化人とみられていたのである。
おそらく新聞や雑誌、テレビもサルトル、ボーヴォワールの来日を、ふた月ほど前のビートルズ来日と同じくらい、にぎやかに報じていたのだろう。その熱狂的な報道ぶりが、いなかの高校生であるぼくにも伝わって、サルトルを読んでみたいという気をおこさせたにちがいない。ふり返ってみれば、もう50年も前のできごとなのに、流行に踊らされるという癖は、困ったことに、それからもつづき、いまだに直っていない。
高校生のとき読んだのは、『存在と無』の抄訳である。当時は、実存はもとより、即自存在や対自存在という概念がまるで理解できず、加えて、その華麗な論理展開にまったく頭がついていかなかった。
最近読んだ渡部の著書は、ぼくのサルトル理解(というより無理解)に大きな光を投げかけてくれた。もし残された時間があるなら、本棚に飾ってある『存在と無』や『弁証法的理性批判』を、今度こそ読んでみたいと思わせたほどである。それは自由な時間を与えられた高齢者の特権というものだろう。
渡部は『存在と無』について、「この膨大な大著をあえて一言で言い表わすとすれば、人間は『無、しかしそれゆえに一切』と表現できるだろう」と言い切っている。
さらに、こんなふうに解説する。
〈この世のあらゆる存在は「物」と「意識」とに分けられる。それは世界と人間のことでもあり、即自存在と対自存在、すなわち存在と無とも表現される。〉
あれほどわからなかった「即自」と「対自」がここではすっきり説明されている。即自とは物のことであり、対自とは意識のことである。そして、意識はそれ自体、かたちをもたない無なのである。
サルトルが無である意識を重視することはいうまでもない。
渡部はいう。
〈意識は自らの裡(うち)に根拠を持たぬ『無』ではあるが、その本源的な否定能力のゆえに、自己や過去から常に自由であり、他者を対象化し続けることで自由を得ようとし、またあるべき世界像を作り出し、その実現に向けて現実を変えようとする自由そのものの存在なのである。〉
ぼくは滑稽なことに、存在とは生きることであり、無とは死ぬことであると思いこんでいた。死ぬ気で生きるというのは、何やら処世訓じみているし、死して生を残すとなれば、三島由紀夫に近くなる。これでは、まったくサルトルが理解できなかったはずである。
サルトルは基本的に明るい。暗そうにみえて、楽観的である。つまり、自由と希望の思想家なのである。人は何ものにも縛られない自由を根源的にもっている。そして、理想世界の実現に向けて、自由にみずからを投企することができる。
投企とは、自分自身を世界に向けて投げかけていくこと、言い換えればアンガージュマン、すなわち世界を変えるために、みずから社会参加していくことを指す。それがサルトルのいう自由であった。単に気ままに遊ぶことだったわけではない。
自由、それは何と魅力的なことばだろう。当時、ぼくはアンガージュマンなどということを考えていたわけではない。一刻も早く、つらい受験勉強を終えて、自由になる日を憧れていた。そうやってみると、サルトルへの憧れは、受験勉強からの解放と関連していたのではないかと思えるほどである。
しかし、ほんとうはいつの時代も、人は自由を求めているのではないだろうか。この場合、自由とは束縛や桎梏(しっこく)からの解放を意味する。戦後のフランスで、サルトルがあれほどもてはやされたのは、フランス人がドイツの占領下から解放されて、これまでにない自由なフランスに向けての希望をいだいたからだろう。1966年に日本人がサルトルを熱狂的に迎えたのは、会社社会を含むさまざまな束縛から逃れて、もっと自由な日本への展望をサルトルが示してくれるのではないかとの期待が、どこかにひそんでいたためだろうか。
いや、あるいは、そうではなくて、それはメディアのつくりだしたブームに、お祭り好きの日本人が、ただ乗っかっただけのことだったのかもしれない。時は高度成長のまっただなかである。世界的な文化人が日本にやってくるというだけで、あのころはみんな沸きたっていた。
ところで、前にも述べたように、ぼくのサルトルへの関心は、高校時代だけで終わったわけではない。1968年にパリでは「五月革命」があり、日本でもベトナム反戦運動と大学闘争がおこっていた。一時、フランス思想界からほとんど無視されていたサルトルは、この「五月革命」によってふたたび脚光を浴びる。しかし、そのことは68年を語るさいに、あらためて取りあげることにしよう。
ここでは1966年に来日するまでのサルトルの軌跡を、渡部の著書によって簡単にふり返っておきたい。
サルトルは猛烈な書き手だった。その執筆活動は哲学、文学だけではなく、評伝、評論、劇作におよび、日本語に翻訳されたものだけで、その総量は何と400字詰めの原稿にして3万6700枚におよぶという。1冊の本が500枚だとすれば、その量はざっと73冊分である(人文書院の『サルトル全集』は38巻)。
その代表作は、哲学では『存在と無』や『弁証法的理性批判』、文学では『嘔吐』や『自由への道』、評伝では『ボードレール』や『聖ジュネ』、評論では『シチュアシオン』、劇作では『蝿』や『出口なし』、『アルトナの幽閉者』など。いちばん量が多いのが評伝というのは意外だが、ここには膨大な未完のフローベル伝、『家の馬鹿息子』が含まれている。その翻訳は、現在にいたっても、途中までしか終わっていない(現段階で全4巻、2400ページ)。サルトルはまさに世界と人間のすべてを自分の頭で把握したいと願っていた。
しかし、『家の馬鹿息子』を除いて、サルトルは1966年の来日までに、ほとんどの仕事を成し遂げていたといってもよい。『存在と無』につづく哲学書『弁証法的理性批判』も完成したのは1960年である(日本語訳は1962〜73年)。日本にやってきたころのサルトルは、世界を又にかけて行動する思想家になっていた。1962年にはアルジェリアの独立を支持して右翼にいのちをねらわれたにもかかわらず、それにひるむことなく、その後もベトナム反戦運動を支援していた。日本にやってきたときも、ベ平連主催の「ベトナム戦争と反戦の原理」という集会に参加したはずである。
その行動には、どのような思想が横たわっていたのだろう。それを知るには『弁証法的理性批判』の概要を知っておく必要がある。
渡部佳延はこう書いている。
〈我々一人一人が歴史の原動力なのであり、その歴史創造のダイナミズムを知の力で掴み取ることができるならば、人間がついに自らの手で歴史を創造することも可能なのではないか。こうした希望を担って書き始められた哲学こそが、『弁証法的理性批判』だったであろう。〉
サルトルの『弁証法的理性批判』は、マルクスやヘーゲルの再検討を通じて、そこから歴史創造の原理を導きだそうとした作品といえる。
残念ながら、ぼくはこの本もきちんと読んでいない。そこで渡部の要約に頼りながら、その内容をかいつまんで紹介しておくと、歴史を動かすのは、個の認識にもとづく実践であり、それが個の領域にとどまらず全体に広がるときに、それはひとつの意味をもつ歴史となるというのである。サルトルがもっとも嫌悪したのは、先験的な観念を押しつけることによって、人びとの実践をしばろうとする教条的マルクス主義の考え方だった。
渡部はいう。
〈『弁証法的理性批判』は、実存主義的立場からなされた、きわめてユニークな社会哲学の試みである。個人の自由な実践を最重要視し、人間が知と力とをもって物質を加工し、また自身をつくることを世界の根底においている。しかし「加工された物質」のネットワークは、「実践的=惰性態」となって社会を形成する。この無気力な組織という巨大な塊の中で、人間もまた惰性的な存在に陥っている。これを打ち破るものこそ、自由の再点火たる溶融集団という革命的エネルギーであり、人はその中でこそ至福の瞬間を味わうことができる。しかし集団は、やがて自らの存在の維持のために惰性を取り込み、規約や制度をつくって国家にまで至る。その惰性の極で、再び革命集団が結成されて循環する──こうした経緯を、弁証法を駆使して説いた書である。〉
むずかしい言い方だが、説明は省略。サルトルが歴史のダイナミズムをとらえようとしたこと、そして、革命的実践に大きな意義を認めたことを感じとればよい。そこには1968年の思想が準備されていた。
サルトルがめざしたのは、自由な社会主義の実現である。しかし、それはもはや妄想に近かったのではないか。あのころから、ほぼ50年たったいま、ふと思うのはそんなことである。
2015-12-19 06:46
nice!(8)
コメント(0)
トラックバック(0)




コメント 0