デヴィッド・ハーヴェイ『〈資本論〉入門』を読む(1) [商品世界論ノート]
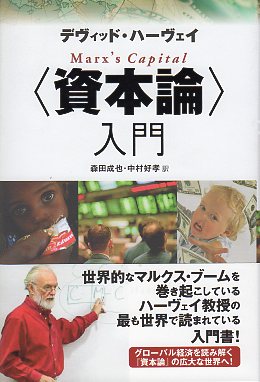
退職後には、はるか昔の学生時代に斜め読みした『資本論』を読んでみたいと思っていた。
しかし、時はまたたくまに流れ、もう残り時間が少なくなってきた。
いまはもう読み通す自信がない。あきらめが肝心である。
それでも、せめて解説書だけでもふれておきたいと思い、先日ハーヴェイの『〈資本論〉第2巻・第3巻入門』を読んでみた。その内容はすでに拙ブログで紹介している。
どこまで理解できたかはともかくとして、とりあえずこの本を最後まで読むことができたのは何よりだった。
しかし、ハーヴェイには第2巻・第3巻に先立って、第1巻の解説書『〈資本論〉入門』がある。やはり、第1巻を読まなければ『資本論』を読んだとはいえないだろう。
たとえ翻訳でも、原著を読むのはおっくうである。そこで、後先が逆になってしまったが、今回もハーヴェイの本を読み、『資本論』を読んだつもりになるという安直な道を選ぶことにした。
ぱらぱらとページをめくりはじめる。
ところが、いっこう頭にはいってこない。よほどやきが回っている。
そこで、メモをとりながら、例によって例のごとく、つぶやいてみることにした。
ハーヴェイの本を通し、『資本論』第1巻で遊び、たわむれてみようというわけである。
『資本論』をどう読むべきか。これが序章の見出しである。
ハーヴェイは先入観にとらわれず、注意深く、虚心坦懐に、直接『資本論』を読むことを勧めている。すると、『資本論』が実に豊かな知的源泉であるかがわかってくるだろう。しかも、だいじなのは断片的にではなく、全体を読みとおすことだという。
遺憾ながら、この忠告は最初から無視する。
老いぼれの言い訳にちがいない。でも気にしない。
先に進む。
ハーヴェイによれば、『資本論』には、異なる3つの知的伝統が流れこんでいるとか。
第1は、スミス、マルサス、リカードなどの古典派経済学の伝統。
第2はとりわけヘーゲルに代表されるドイツ批判哲学の伝統。
第3はサン・シモンやフーリエなどの空想的社会主義の伝統である。
『資本論』が難解であることは、ハーヴェイ自身も認めている。
とくに、最初の数章はむずかしい。
「マルクスは、表層の概観から出発して深部の概念を発見する」と、ハーヴェイはいう。それによって、あたりまえと思われていたことが、あたりまえではなくなる。日常的経験が揺らいでくるのだ。
『資本論』の出発点は商品であり、次に貨幣である。労働でもなければ階級闘争でもない。
なぜ商品や貨幣なのか。それは、マルクスが、資本主義の成長と発展のメカニズムを、全体として把握したかったからである。
商品と貨幣の考察を抜きにして、資本主義の全体をつかむことはできない。
とはいえ、マルクスが『資本論』全3巻で実現することができたのは、ハーヴェイによれば、全構想の8分の1にすぎなかったという。信用制度と金融、国家、税金、国債、人口、植民地、国際関係、輸出入、為替相場、世界市場と恐慌といった問題は、詳細に取りあげられるにいたらなかった。
ハーヴェイはマルクスの方法についてもふれている。
それは弁証法と呼ばれるものである。
「あらゆる歴史的に発展した形態は流動状態、運動状態にある」とマルクスはいう。この運動、矛盾、変転の過程を理解し、表現する方法が弁証法だった。
資本主義のうつろいやすさとダイナミズムは、弁証法なくしては理解できない、とマルクスは考えていた。
とはいえ、この弁証法が『資本論』を難解にしていることもいなめない。
ハーヴェイは、現代でも『資本論』は通用するとみている。
もちろんマルクスが研究を重ねていた1850年代、60年代のイギリスと、2000年代、2010年代の日本とでは、歴史も環境も空間も異なっている。それでも、同じ資本主義文明にのみこまれている点は、昔も今も変わらない。
われわれはどんな文明のなかに生きているのだろう。経済関係はもちろんすべてではない。だいじなのは、人がどう生き、どう死ぬかということだ。
それでも、経済関係はわれわれの生活に大きな影響を与えている。
それがどういう影響なのか、これから、ぼんやりとでも考えてみたいと思うのである。
2016-06-18 09:53
nice!(4)
コメント(0)
トラックバック(0)




コメント 0