竹田青嗣『欲望論』を読む(1) [思想・哲学]
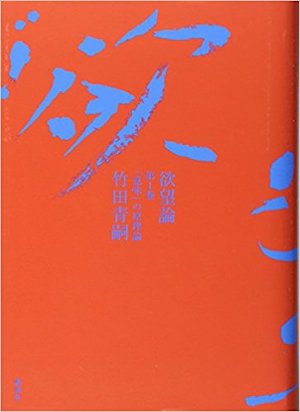
買うか買うまいか迷った末にとうとう買ってしまった。
上下2巻1200ページを超える大作である。
第1巻は「『意味』の原理論」、第2巻は「『価値』の原理論」と銘打たれている。このほかに、続刊として倫理学と社会哲学が予定されているというから、まだ先が残っている。
第1巻と第2巻は4部から構成されている。
第1部 存在と認識
第2部 世界と欲望
第3部 幻想的身体
第4部 審級の生成
著者は1947年生まれの哲学者、文芸評論家。現在、早稲田大学国際教養学部教授の肩書をもつ。哲学に関する多くの著書があるが、本書はその総決算といえるだろう。
オビには「一切の哲学原理の総転換!! 21世紀、新しい哲学がはじまる! 2500年の哲学の歴史を総攬し、かつ刷新する画期的論考!!」とうたわれている。こういううたい文句には、いかにも売らんかなの姿勢がみえみえで、あまり信じたくないのだが、これまでの哲学史を塗り替え、新たな地平を開くというのは、たしかに壮観にはちがいない。
2冊で税別7800円という値段にも、ちとたじろいだ。しかし、なによりためらったのは、これまで哲学など無縁で、それほど先のないぼくなどに、はたしてこの本が理解できるかどうか、まったく自信がもてなかったからである。
でも、思い切って買ってしまった。
人間とはなにかがわかる手がかりになればいいと思ったからである。
誤読の可能性はおおいにあるが、わからないなりにも断続的に1年くらいかけて読んでいけば、人間という親密かつ凶暴な存在について、なにかあらたな知識が得られるのではないか。そんな軽い気持ちで、本書のページをめくることにした。途中で挫折する可能性は高いが、例によって、きれぎれの感想である。
はじめに暴力があり戦争があったと著者は書いている。人間がそのなかを生きていくには、共同体をつくらねばならなかった。暴力や戦争はつねにあり、人はつねに死におびやかされていた。それに対抗するため生まれたのが宗教や哲学だ。宗教はよりよく死ぬための「物語」であり、哲学はよりよく生きるための「原理」だった。
著者はいう。
〈古来、哲学の問いの中心には世界とは何であるか、世界を正しく認識できるかという問いが、すなわち「存在の問い」と「認識の問い」が存在してきた。しかし、この問いの根底には、いかに善き生を生きうるかという問いとともに、いかに人間が潜在的な暴力の不安から逃れうるかという問いが潜んでいる。〉
人間は世界のなかに生きている。その世界とは何なのか。また人間ははたして世界を正しく認識できるのか。それが存在と認識の問いである。だが、その根底には人間とは何であるのかという、さらに根本的な問題がひそんでいる。
だいじなのは哲学的原理という方法なのだ、と著者はいう。つまり考えるためのテコだ。その方法は時代に応じて、つねに再生されねばならず、それが失われれば、混乱が支配する。
現代哲学は、哲学的原理を打ち立てようとした近代哲学を乗り越えるため、批判的相対主義におちいり、批判のための批判をくり返している。だいじなのは哲学的原理という方法を再生することだ。そのためには「一切の哲学と思想の中心的方法と原理を、新しい思想の解剖学によって解体し、これを吟味し尽くさねばならない」と、著者は宣言する。
現代思想の特徴は「相対主義」にあるといってよい。絶対的な認識はありえないとして、すべてを相対化し、批判する考え方だ。そこからは、正当なものは何もない、逆にいえば、あらゆるものは正当化されるという思想が生まれる。
こういう考え方が生まれたのは、20世紀前半に人類が全体主義(スターリニズムとファシズム)という原理主義的思想の災厄をこうむったためだろう。そこから、近代そのものを否定するポストモダン思想が登場した。その標的となったのは、ドイツ観念論に代表されるヨーロッパの形而上学だった。
「このことで、現代の批判思想は、形而上学的、独断論的普遍主義に対抗する批判的相対主義という、決して答えの見出せない哲学的な袋小路に入り込むことになった」と、著者はいう。それは不毛な対立を招いた。
形而上学的独断論と懐疑的相対主義の不毛な対立を回避するには、まず「本体」の観念を解体するところからはじめなければならない。哲学は「本体」なるものが存在すると考えてきた。逆に本体には誰もアクセスできないというのが、懐疑論の思考だった。
著者は、独断論であれ相対主義であれ、「本体」から出発するこれまでの哲学的思考を克服しようとした哲学者として、ニーチェとフッサールの名前を挙げている。
「『本体』の存在が暗黙のうちに想定されているかぎり、認識は可能であるか可能でないかのいずれかでしかない」。このことが、哲学に不毛な論争を招いてきたのだ。
著者は本体論を解体する手がかりとして、「認識相関性」という概念をもちだす。これは認識相対主義とはことなる。認識相対主義は、自分自身の観点からしか対象を見ることができないため、すべての認識は相対的であって、「本体」自体の正しい認識はできないとする。ところが、「認識相関性」の考えでは、人はみずからの身体−欲望に関連づけて「世界」を生成するとみるから、そもそも「本体」を想定することはできず、想定する必要もないのだ。
このとき「世界」は「生世界」となる。だれにとっても個別に存在する世界、それが「生世界」だ。「『生世界』は生きとし生けるものにとっての絶対的、偶有的事実であり、それゆえまったくドクサ(臆見)を含むことのない、『世界意識』の根源的出発点である」と、著者はいう。
そこから新しい認識論が生まれる。「本体」の認識という考え方は廃棄される。それに代わって個々の「世界体験」から間主観的な問題構成に展開し、世界存在の普遍性を理解する方法が開けるのだ。
意味は記号の本体ではない。意味と価値はほんらいひとつのものだ。世界は「生けるもの」の「欲望−身体」相関性としてのみ生成する。したがって、世界は価値と意味のたえず生成変化する連関の総体としてとらえられる、と著者はいう。
世界体験から出発して世界の普遍的理解にいたる「言語ゲーム」を著者は哲学と名づけているようにみえる。それは「暴力原理」にもとづく思考の停止、あるいは懐疑主義によるデカダンとは対極にある努力にほかならず、現実世界の「現実論理」と対抗するものなのだ。したがって、これからえがかれようとするのは、いわば希望の哲学といってもよいものかもしれない。
気の向くままに、少しずつ読んでいきたい。
2017-12-09 18:16
nice!(5)
コメント(0)




コメント 0