今井駿『四川紀行』を読む(1) [本]
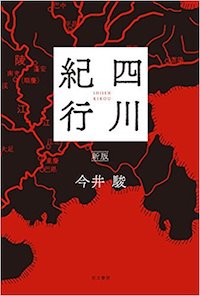
出版社の友人からいただいた本。
いつも不義理している。たまには読まなければ申し訳ないと思い、読みはじめている。まだ、ほんの少しだけ。
略歴によると、著者は1942年生まれ。中国の近代史が専門で、静岡大学の名誉教授だ。汲古書院から『中国革命と対日抗戦』、『四川省と近代中国』という著書を出版している。
『四川省と近代中国』(サブタイトルは「軍閥割拠から抗日戦の大後方へ」)がおもしろそうだと思い、千葉県立図書館のデータベースを引いたら、その内容紹介にこうあった。
〈軍閥割拠体制=防区制の成立から発展・消滅の過程の概観、四川軍閥の搾取その他の四川社会に関する個別研究、日中戦争期を中心にした軍閥無き後の四川における地方行政の実態と新県制下の地方自治問題についての論考を収録。〉
むずかしそうだが、ともかく著者が四川省近代史の専門家であることはまちがいない。
驚くのはそのページ数で6695ページとある。めまいがした。
でも、6695ページとはあまりにもへん。そこで国会図書館のデータベースにあたってみると695ページとわかり、ひと安心した。
県立図書館のデータベースにも打ち間違いがある。それでも本体価格1万5000円というのは、いくら専門書とはいえ、ぼくらにはとても手がでない本だ。
本書『四川紀行』は2014年に旧版がでている。あまり売れなかったらしい。それでも再チャレンジしようというこころざしが、いまどきすばらしい。中身はそのままとして、漢字のルビを増やし、若干注を加えて、版を改めてできたのが、2017年の新版、すなわち本書である。
そのおもな中身は1992年夏の四川省のちいさな町めぐりといっていいだろう。それを中心に、1989年春の北京の様子、2001年夏の四川省再訪の記録がサンドイッチのようにはさまり、春夏秋冬の部に大別されている。季節が移り変わるのは、著者の心象風景をあらわしている。著者のなかでは、いま中国はどうやら冬の時代を迎えているようだ。
この紀行の特徴は、日本のツアー旅行者があまり行きそうもないところを訪れていること、それから旅で出会った「中国のふつうの人たち」がえがかれていることである。
四川省で著者が訪れるのは、大邑(だいゆう)、邛崍(きょうらい)、雅安(があん)、楽山(らくざん)、大足(だいそく)などの県、それに西昌、自貢などの市[中国では市は県に属していない]である。無教養なぼくが四川省で知っているのは成都くらい(重慶は直轄市で四川省に属さないらしい)だから、ちょっと情けない。
だが、著者は日本人観光客にもおなじみの三峡下りもし、四川料理の案内もしてくれているから、これからツアーで四川を訪れる人にも、本書はおおいに役立つかもしれない。
例によって、いいかげんなぱらぱら読みである。最初の「春」の部と、最後の「冬」の部は後回しにして、「夏」と「秋」の部から読みはじめる。
まず著者が向かうのは大邑(だいゆう)県安仁(あんじん)鎮だ。鎮というのは日本でいえば村という感じだろう。
成都から安仁鎮に行くには、まず大邑行きのバスに乗って2時間、そこから三輪車のタクシーに乗って、ようやくたどりつく。
ここは軍閥、劉氏の出身地だ。劉湘(りゅうしょう、1890〜1938)は蒋介石に認められ、四川省を治める。いっぽう、その叔父にあたる劉文彩と劉文輝の兄弟は蒋介石と対立し、劉湘によって追放される。
その劉文彩の屋敷の一角に「収租院」がある。収租院とは小作人が小作料を納める場所だ。そこが、いま博物館になっている。
有名なのは収租院に並べられた一群の塑像だ。著者によれば「『解放』以前の地主の支配がいかに苛酷で冷酷かつ残忍なものであったか一目で分かる」ようになっているとか。文革時には数千万人の人がここに学習にやってきた。
しかし、1992年に著者が訪れたときは、塑像はみなほこりをかぶっていた。

[ヤフオクから。収租院塑像の写真集]
劉文彩の屋敷は広大で、日本の大地主の家とくらべると格段の規模だという。弟の劉文輝が軍閥として台頭すると、劉文彩はその後ろ盾で徴税官になり、金を蓄えて「それを土地や商業(特にアヘンの密売)・金融業に投じてボロ儲けをした」。
したがって、解放後は「階級闘争」を忘れないための格好の教材となった。いわゆる「憶苦思甜(おくくしてん)」運動のモデルだ。憶苦思甜とは、苦い過去を忘れず、現在の幸せを思うこと。
その運動は無謀な「大躍進運動」の悲惨さをおおいかくすための、中国共産党の欺瞞策にすぎなかった。だが、「収租院のような大地主の支配と闘って、新中国が誕生したのも確か」だ、と著者はいう。
「改革・開放」以降、近年は収租院を訪れる人もまばらになっている。中国では、もう「階級闘争」の必要はなくなったというのが当局の見解だという。しかし、近年、貧富の格差はますます広がっている。
いまはひっそりした収租院をおとずれ、現在の貧富の格差に思いを寄せるあたり、著者の風刺はなかなか鋭い。
次に向かうのは邛崍(きょうらい)だ。
成都から西に75キロにある郊外の町(中国の言い方では県)だ。
著者がこの町にひかれたのは、成都の大衆雑誌で、「乞食博士」という一文をみたからだという。
邛崍にある乞食がいた。博士だった。
雑誌にはその経歴がえがかれていた。早稲田大学の「航空学部」で博士号を取得し、東京大学「音楽部」の日本人女性と恋におち、結婚する。だが、日中関係が険悪化するなかで、1937年に帰国し、故郷の邛崍で小学校の教師となった。
かれはうつうつとした日を送るなかで、アヘンを吸うようになり、仕事もやめ、先祖伝来の土地も手放して、乞食になってしまった。そして、雨の日も風の日も、ぼろぼろのスーツを着て、県城のあたりで物乞いをしていたというのだ。
この記事を雑誌に投稿したのは、邛崍中学の教師で、それはかれが子どものころにみた光景だという。日中戦争が終わったあと、博士の妻が子どもを連れて、邛崍県にやってきたとの記述もあった。
そこで、がぜん興味をいだいた著者は、バスに乗って、この町にやってくる。
街の外には南河という川が流れ、左手に回瀾塔という塔が立っていた。近くでみると、お世辞にも美しいとはいえない。明の時代に建てられた塔だ。

[回瀾塔。ウィキペディアより]
著者は最上層をめざして、ひたすら塔をのぼった。ようやく最上層にたどりつき、周囲を見渡すと、野菜や小麦の畑、南河などが「パッチワークのように美しく広がっていた」。
乞食博士のことを思い浮かべた。博士というのは、おそらくウソだった。しかし、乞食博士は実在の人物だ。日中対立というような政治的要因がなければ、かれのような悲劇も生まれなかったのではないか。
だが、そのうち「このような美しい情景のなかで要らぬ詮索をしている自分が恥ずかしく思われ」てきた。数人連れの青年たちが登ってきたのを潮時に、塔をあとにした、と書いている。
乞食博士の消息はたどれなかった。それでも悲劇が物語として伝えられ、それに興味をひかれる自分がいることがだいじなのだ。
旅はテレビなどではわからない、じかのふれあいと発見をもたらしてくれる。日本人も中国人もそれぞれの国を自由に旅することができれば、たがいにもっとおおらかになれるのではないか。日本人も中国人もそれぞれの国のことを、あまりにも情報としてしか知らされていないような気がする。
国はだいじだ。だが、時に国をとっぱずしてみること、ふつうの人間の立場に立つこと。そのほうがずっと視野が広がると思う。
本書をめくりながら、そんなことを感じた。
旅はつづく。
2018-01-14 07:45
nice!(10)
コメント(0)




コメント 0