ラッセル・カーク『保守主義の精神』を読む(1) [本]
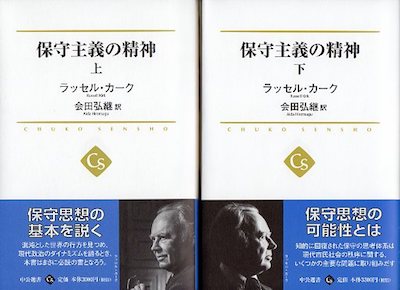
訳者、会田弘継の解説によると、著者のラッセル・カーク(1918〜94)は戦後アメリカを代表する保守思想家だという。原著は1953年に初版が発売され、その後、改訂を重ねて、1986年に第7版が出された。本書はその第7版をもとにした初の邦訳である。
アメリカにはふたつの顔がある。ひとつは自由と民主主義、リベラルのアメリカ、もうひとつは保守的で信仰心にあふれ、なによりも勤勉さを重視するアメリカ。このふたつの顔は別々ではなく、ときに交錯し、複雑な色合いをみせる。そこにさらに資本主義と戦争という創造的破壊の要因が加わると、アメリカ史はまさに熱狂のるつぼと化すのである。
その混沌のなかに、一本の鮮烈な水脈を見いだそうとすれば、それがイギリスの伝統を受け継いだ保守主義の精神ということになるのではないか。
昔、イギリスの歴史家ポール・ジョンソンの本を何冊かつくったことがある。『インテレクチュアルズ』、『現代史』、『近代の誕生』、『アメリカ人の歴史』など。そこに感じられたのは、イギリス保守主義への誇り、深い信仰心、人間本性への洞察、そして何ともいえないユーモアだった。
この本にとりかかろうとして、そんなことを思いだしたのは、ポール・ジョンソンの本を通じて、イギリスとアメリカには、ずいぶんいやな面もありながら、同時にすぐれた面もあると再認識したからだった。そこには、義理と人情と倫理にがんじがらめになってしまう日本の光景とは異なる、一種からっとした理知的な精神が広がっていた。
そんなわけで、この本を購入したときに、なぜか思い浮かべたのは、ポール・ジョンソンの数々の著作だったのである。
前置きが長くなった。中身はまだ1ページも読んでいない。
いつものように、ひまな年寄りの寝言。何回になるかわからないし、途中でやめてしまうかもしれないが、まあ、のんびり読むことにしよう。
原著のタイトルはThe Conservative Mind: From Burke to Eliot(『保守主義の精神──バークからエリオットまで』)。日本語版のタイトルには、このサブタイトル部分が割愛されている。たぶん、日本の読者にはアピールしないと判断されたのだろう。バークはイギリス保守主義の泰斗エドマンド・バーク(1729〜1797)、エリオットは『荒地』の詩人トマス・スターンズ・エリオット(1888〜1965)[なぜか鮎川信夫を思いだす]。本書はそのバークからエリオットまでの保守の系譜をたどろうというものだ。
目次をみると、日本人にはあまりなじみがない英米の人物(ポール・ジョンソンの本ではおなじみだが)の名が並んでいる。日本ではこれまで欧米の保守の系譜が、ほとんど紹介されてこなかったことに、いまさらながら気づく。
そもそも日本では、明治以降、西洋からの輸入思想は反体制を意味した。近代以前の儒学、仏教、国学の教義は、保守を支える側に回った。だから、西洋の保守思想はあまり移入されることがなかったのかもしれない。
おっと、これもよけいなこと。だらだらと年寄りの繰り言がつづく。
第1章を読んでみた。
19世紀の自由主義者、ジョン・スチュアート・ミルは保守主義者のことを「愚かしい党派」と呼んだという。
だが、著者のカークは、「古来の常識」と「古くからの定め」を根拠とした近代の保守主義者エドマンド・バークの側に立つ。バークが著者の原点だといってよい。
バークの生地、ダブリンを訪れた著者は、いまの時代にこんな感慨をいだく。
〈伝統を呪詛し、平等を言祝ぎ、変化を歓迎する世界。ルソーにしがみつき、彼の思想をまるごと鵜呑みにして、そして、より一層過激な預言者を求める時代。産業主義の汚濁にまみれ、大衆によって画一化され、政府にがんじがらめにされた世界。戦争によって傷つき、東西の二大国[本書が出版されたのはまだ米ソ冷戦の時代だった]のあいだで震えおののき、砕けたバリケード越しに瓦解の深淵をのぞく世界。〉
これが著者の感じている世界だ。急進主義、大衆社会、世俗化、産業主義、物質主義、暴力主義、集権主義への怒りに満ちている。こうした世界に対峙し、みずからの精神をたもつには、保守の源流に立ち戻り、そこからの流れをたどるしかない。
そこで、著者は1790年に『フランス革命の省察』を著したバークを再発見することになる。バークこそが保守主義の師だった。近代保守主義の流れはすべてバークから発しているという。
ちなみに、ぼく自身はバークについて、ごく断片的にしか知らない。最初フランス革命を支持していたかれがフランスの民主政を「この世でもっとも恥知らずのもの」と呼ぶにいたったこと、フランス革命が「狂気、不一致、悪、混乱、癒やされることのない悲しみに満ちた殺し合いの世界」であると認識するにいたったことを、わずかに知るくらいである。
それはともかく、近代保守主義の精神史ともいうべき本書は、バークからはじまるのだが、その前に、著者は保守思想の要点をいくつかまとめている。
ややこしいので、ぼくなりに言い換えると、それは個人の良心を信頼し、自然につくられる社会秩序を重んじ、人間存在の多様性を尊重し、人生は生きるに値するものだという感覚をだいじにし、文明社会には身分秩序が必要だという認識に立ち、人の自由と財産は犯してはならないと考え、慎慮にもとづかない変革を拒否する思想だということになる。ぼくらからすれば、これ自体、ずいぶんリベラルだと感じるのはどうしてだろう。国家に面従腹背するアジア的思考がしみついている。
著者はいう。保守主義は急進思想に反対する。急進思想とは、社会は無限に進歩すると考え、伝統を軽蔑し、政治的平等化、経済的平等化を求めるイデオロギーをさす。それは、けっきょくのところ国家による人間の支配をもたらす。
著者は現代の高度資本主義社会のなかで、保守主義は追い詰められ、風前の灯火のようになったと感じている。保守主義こそ「神の摂理」と信じる著者にとって、保守思想の根本的理解が、悲愴ともいうべき使命感となっていることは、第1章の最後に置かれた次のフレーズからも感じられる。
いわく。
〈たとえ保守主義に秩序を再興することができなくとも、保守主義の思想を理解すべきであろう。その理解を通じ、解き放たれた意志と欲望の業火がすべてを焼き尽くした後に残された、焼け焦げた文明の切れ端を、能う限り灰燼のなかからかき集めねばならない。〉
ここからは、もう古き良き時代は戻らないという嘆きさえ聞こえてくるかのようだ。
しかし、時代はめぐりめぐって、いまはまた保守の時代になった。時代はめぐり、思想もめぐる。それが思想の運命というものだろう。
歴史において、否定性の弁証法はつねにはたらく。だが、水脈は消えることがない。
保守主義の水脈を追ってみることにしよう。
2018-06-12 07:41
nice!(10)
コメント(0)




コメント 0