人間とは何か──『ホモ・デウス』を読む(2) [本]
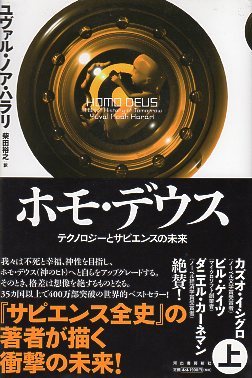
著者の方法の特色は、生物学と歴史学を融合させることによって、人類史を俯瞰的に見渡すところにあるといってよいだろう。
遅々として進まないけれど、きょうは第1部「ホモ・サピエンスが世界を征服する」を読んでみることにした。
われわれの日常で、ライオンやオオカミやトラは、動物園を除けば、もはやおとぎ話やアニメの世界にしか存在せず、実際に「この世界に住んでいるのは、主に人間とその家畜なのだ」と、のっけから著者は指摘している。
〈合計するとおよそ20万頭のオオカミが依然として地球上を歩き回っているが、飼い馴らされた犬の数は4億頭を上回る。世界には4万頭のライオンがいるのに対して、飼い猫は6億頭を数える。アフリカスイギュウは90万頭だが、家畜の牛は15億頭、ペンギンは5000万羽だが、ニワトリは200億羽に達する。〉
この指摘はとてもおもしろい。
過去7万年間、ホモ・サピエンスは地球の生態系に、じつに大きな変化をもたらしてきた。マンモスなど大型動物を絶滅に追いこんだのはホモ・サピエンスの仕業である。
狩猟採集の世界では、アニミズムが人と動物との対話をもたらしていた。それどころか、人間の祖先はヘビやトカゲなどの動物とさえ考えられていた。つまり、人間は動物の一種にすぎないと思われていたのだ。
しかし、いまでは動物はヒトより劣った存在とみなされるようになった、と著者はいう。これは農業革命のもたらした意識変革である。農業革命は家畜をもたらした。「今日、大型動物の9割以上が家畜化されている」
家畜の身になってみれば、人に守られ、育てられる家畜の運命は悲しいものだ。たとえば、イノシシの遺伝子を引き継いだブタは、さまざまな欲求や感覚や情動をもっている。にもかかわらず、かれらは食肉としてしか評価されず、その目的に沿ってだいじに育てられる。
ここで、アルゴリズムという聞き慣れない用語が登場する。
アルゴリズムというのは、はやりのコンピューター用語だ。
人を含む動物は身体をもち、その身体を感覚や情動や欲求にもとづいて動かしている。その動きはアルゴリズムにしたがっている、と著者は考えている。
「アルゴリズムとは、計算をし、問題を解決し、決定に至るための、一連の秩序だったステップのことをいう」
つまり、アルゴリズムとは目標実現に向けての段取りといってもよいのかもしれない。
人を含め、すべての動物は、感覚や情動や欲求をもち、アルゴリズムに沿って行動する。ブタにはブタの、人には人のアルゴリズムがある。
親子の情動的な絆は人もブタも変わらない。にもかかわらず、人は子ブタや子牛を生後すぐに母親から引き離して、もっぱら食肉として育てる。
こうした行動を正当化したのは、有神論の宗教だった、と著者はいう。
古代ユダヤ教では、子羊や子牛が神のいけにえとしてささげられた。ほとんどの宗教は、神だけではなく人間をも神聖視している。魂をもつのは人間だけであり、動物には魂がなく、人のために存在しているとされた。
こうして神は作物や家畜を守り、人は神に収穫をささげるという構図ができあがったという。
動物たちに共感を示したのはジャイナ教と仏教、ヒンドゥー教である。どんなものも殺してはならないと教えた。とはいえ、牛の乳をしぼったり、その力を利用したりすることまでは禁じなかった。
農業革命は経済革命であるとともに宗教革命でもあったという。動物は感覚のある生き物からただの資産へと降格された。そして国家が成立すると、国家は征服した人間集団を資産として扱うようになる。こうして、人間による人間の差別も発生する。
そして、その後の科学革命と産業革命が、人間至上主義を生みだす。人間は神に代わって自然を動かし管理するようになった。
人間がこの世界でいちばん強力な種であることはまちがいない。だが、力のある種の生命が、ほかの種の生命より貴重かどうかは、じつはわからない、と著者はいう。
人間には魂があるが、動物には魂がないという説はあやしい。
ダーウィンの進化論がいまでも恐れられるのは、ダーウィンが魂が存在しないことを立証したからだという。
これはおもしろい見方だ。
進化論は人が分割できない不変かつ不滅の個からなるという信念をしりぞける。ダーウィンは、あらゆる生物学的存在は、小さく単純な部分からできた複雑な器官の集合であり、それは徐々に進化したものだと考えた。進化論によれば、永遠不滅の魂なるものはどこにも存在しない。
動物とちがって人間には心があるという言い方にたいしても、著者は反論する。
〈心は魂とは完全に別物だ。心は神秘的な不滅のものではない。目や脳のような器官でもない。心は、苦痛や快楽、怒り、愛といった主観的経験の流れだ。これらの精神的な経験は、感覚や情動や思考が連結して形作っている。感覚や情動や思考は、一瞬湧き起こったかと思えば、たちまち消える。……永久不変の魂とは違い、心は多くの部分を持ち、たえず変化しており、それが不滅だと考える理由はまったくない。〉
ロボットやコンピューターには心や意識はない。こうした装置は何も感じないし、何も渇望しない。あらかじめ入力されたデータにもとづいて、動くだけである。
いっぽう人を含む動物には感覚と情動がある。人間も動物も感覚と情動にもとづいてデータを処理し、行動する。ここには無意識のアルゴリズムが潜んでいる。
問題は心や意識とは何かということだ。
これが意外と解明されていない。
脳は複雑な器官で、800億を超えるニューロンが結びついて無数の入り組んだ網状組織を形成している。そのニューロンが何十億もの電気信号をやりとりすると、[吉本隆明風にいえば]「心的現象」が発生する。これが脳科学者のもたらした知見だ。
しかし、これは苦痛や快楽、怒り、恐怖といった心的現象それ自体を説明するわけではない。外部の刺激によって脳内の多くのニューロンが相互に信号を発して、心臓の鼓動が高まり、体内にアドレナリンが行き渡るというのは、たしかにメカニズムの説明である。だが、それで心とは何かがわかるわけではない。
心と脳はどういう関係にあるのか。動物に求められるのが行動だとすれば、心など必要としないのではないか、と著者は問う。それなのに、人間はなぜ心的現象を経験するのか。
動物は一連のアルゴリズム(計算と段取り)によって動いている。その多くはコンピューター・プログラムによって置き換えることができる。その典型が自動運転車だ。
神や魂の存在は実証できない。だとすれば心も存在しないのだろうか。そうではない。「どんな科学者も痛みや疑いといった主観的感情は絶えず経験しているので、その存在は否定のしようがない」
心や意識は脳の無用な副産物だとして、生命科学者のなかには、生命とはデータ処理に尽きると断言する人もいる。また、フロイトのように、心を性衝動装置とみて、蒸気機関のようなものとして説明しようとしても、うまくいかないだろう、と著者はいう。いまでは心をデータ処理するコンピューターのように説明することがはやっているが、コンピューターに心がないことはあきらかだ。
心についてはほとんどわかっていない、と著者はいう。
それでは動物には心があるのか。イヌが人と情動的関係を結ぶことを考えれば、イヌに心や意識があることはまちがいないと思われる。それはサルやマウスにしても同じことだ。
動物にはたとえ意識があったとしても自己意識はないという主張も理解しがたい、と著者はいう。どの犬も自分と知らない犬の尿のちがいを臭いで見分けることができる。どうして、動物に自己意識がないといえるのだろうか。
動物も人間も目的をもって行動する。動物の行動を非意識的なアルゴリズムと理解することもできるが、たとえば高度なチンパンジーは、あきらかに自己意識をもち、意識的に計画を立てている。
したがって、動物とちがい、人間だけが魂や心をもつと主張しても、それは説得力に欠ける。人間だけが高度な知能をもち、道具をつくる能力を発達させたというだけでは、サピエンスが世界を征服しえた説明とはならない、と著者はいう。
それでは、ほかの動物にはない人間の特別な能力とは何だったのだろう。
〈人類はその後の2万年間に、石を先端につけた槍でマンモスを狩る段階から、宇宙船で太陽系を探索する段階まで進んだが、それは進化のおかげで手先が器用になったり脳が大きくなったからではない。むしろ、私たちの世界征服における決定的な要因は、多くの人間どうしを結びつける能力だった。〉
ゾウやチンパンジー、ハチやアリにも協力関係はある。しかし、「無数の見知らぬ相手と非常に柔軟な形で協力できるのはサピエンスだけだ」。
古来、勝利を決定づけたのは、目的に向けての人びとの協力と結集だった。それが力をつくりだす。独裁政権を倒した革命も、南極や月に達した偉業も、こうした協力関係抜きには考えられなかった。
なぜ人間だけが、これほど大規模で高度な社会制度を構築できたのか、と著者は問う。
人間でもたがいに見知った人間どうし密接な関係を結べるのは150人が限度だ。顔の見える小集団の原理は、平等主義であり、不平等は憤りや不満を引き起こす。
ところが大集団になると話はちがってくる。ここでは、想像上の秩序、あるいは物語が決め手になる。こうした虚構(フィクション)が認められれば、たとえ社会がエリート層と非エリート層に分かれていても、社会的な協力関係を維持することは可能になる。
想像上の秩序というのは共同主観的な物語だ、と著者はいう。それは、たとえば神や国、おカネなどであり、[吉本隆明流にいえば]「共同幻想」である。社会は共同幻想の上に成り立っている。それらは人が信じなくなった途端に消滅してしまうが、信じられているかぎりは人びとの協力関係を生みだす。
その例として、著者はおカネを取りあげて、こんなふうに書いている。
〈たとえば、お金には客観的な価値はない。[ただの紙切れである]1ドル札は食べることも飲むことも身につけることもできない。それにもかかわらず、何十億もの人がその価値を信じているかぎり、それを使って食べ物や飲み物や衣服を買うことができる。……[しかし、だれもこのお札を受け取らなくなれば]ドルは価値を失う。緑色の紙切れはもちろん存在し続けるだろうが、値打ちはなくなる。〉
実際、通貨の世界ではこうしたことが起きている。たとえば、イタリアの古いリラ札はいまでは市場ではだれも受け取ってくれない。それは古いドル札も同じだ。
通貨はともかく、まさか国が消えることはないだろうと思うかもしれないが、それがそうではない。実際、ソ連やユーゴスラヴィアが消滅したことをみれば、国家もまた消えるのだ。
国家は貨幣と同じく、共同主観的な虚構、言い換えれば「共同幻想」である。そして、神もまた……。
だれもが有意義だと信じれば、それは共同幻想となり、意味のウェブを形づくる。たとえば、キリスト教の神を信じる者にとっては、十字軍でイスラム教徒を槍で刺し殺すことは誇りに思えただろう。しかし、いまでは異教徒と聖地ということばは何の意味ももたなくなっている。
ウェブがほどけると共同幻想も消える。しかし、それでも共同幻想自体は消えることがない。あらたな共同幻想が生まれるからだ。
人間に特有なのは、この共同主観的なものを生みだす能力である、と著者はいう。サピエンスだけが共同主観的な現実、言い換えれば共同幻想による虚構をつくりだすことができる。ライオンは百獣の王であっても「銀行口座を開いたり、訴訟を起こしたりはできない」。
人間を知るためには、「この世界に意味を与えている虚構を読み解く」ことが絶対に必要になってくる、と著者はこの第1部を締めくくっている。
なかなかやっかいな本書を、もう少し読み解いていくことにしよう。
2019-01-08 07:03
nice!(9)
コメント(0)




コメント 0