電子本で橋本治『二十世紀』を読んでみる [本]
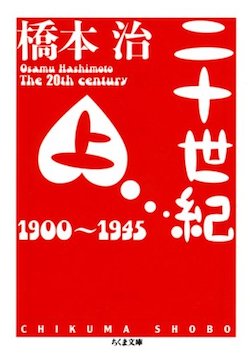
電子本ははたして読書に適しているのか。
頭にはいるのは、やはり紙の本ではないかと思ったりするのは、読みはじめてからの印象だが、これは一種の思い込みかもしれない。最近は何を読んでも頭にはいらないのは、紙の本でも電子本でも変わらないからだ。
電子本のひとつの欠点は紙の本のようにぱらぱらとめくれないことだ。紙の本のように関連本を何冊か並べて、比較することもできない。もっぱら単線的に読むしかない。
ガイドには、電子本では印象深いところに赤線、いやハイライトをつけて、その部分だけを取りだすこともできると書かれている。
そういうが、実際にタブレットでハイライトをつけるのは至難の業。けっきょく、ハイライトをつけるには、パソコンに導入したKindleを利用するほかない。しかも、その前後の脈絡をもう一度見直すのはとても面倒だ。
紙の本とくらべて、電子本のメリットは、場所をとらないこと。それに古典なら、本を探すための時間や手間を節約できること。ぼくの場合でいうなら、マーシャルの『経済学原理』の原文をチェックするときに、ネットでその全文を簡単に見つけることができた。
いまも読んでみたい本はいくらでもある。たとえば熊野純彦の『本居宣長』。これは電子本になっていない。
家の本棚のスペースを考えると、これからそう長くない人生で、また分厚い本を何十冊も買いこむのは、何かとためらわれる(それに買ってしまうと、それだけで満足して、けっきょく何年も積んだままになってしまうという悪癖もある)。
平山周吉の『江藤淳は甦える』は、紙の本で買って読みはじめた。中身がいささかしんどいのに加えて、もつだけで重い。電車のなかでは(といっても、最近、遠出することもほとんどないが)、とても読めない。立ったまま、うとうとしたりすれば、たいへんだ。
いま迷っているのは佐々木実の『資本主義と闘った男──宇沢弘文と経済学の世界』だ。これは紙の本と電子本がでている。紙の本だと642ページだが、電子本だと持ち運べるKindleに収まる。さて、どうしたものか。
相変わらず、そんなつまらぬことをかんがえながら、電子本を読むための実験として、橋本治の『二十世紀』(上)(下)を買ってダウンロードしてみた。
この本は2001年、つまり21世紀になった途端に出版されているから、その素早さといいひらめきといい、橋本治にはやはり脱帽である。かれの本は何冊かもっている。しかし、吉本隆明と同様、いつも流し読みしてきた。
古今東西の典籍を磁石のように引きつけて、いつまでも元気に活躍するだろうと思いこんでいただけに、ことし亡くなったのを知ってショックを受けた。
こちらは、まだのうのうと生きている。それで、橋本治をちゃんと読みなおそうと思って、電子本で『二十世紀』をダウンロードしたわけだ。
ところが、ある日、本棚をながめていたら、すでにちくま文庫の『二十世紀』が上下とも鎮座しているではないか。電子本の返品はできないし、後の祭りである。これも、何かのおぼしめしである。
そうそう、電子本のもうひとつの欠点、それは参考文献を示すさいに、紙の本のように、何ページからの引用というように、引用箇所を示すことができないことだ。ぼくの場合は、文字を大きくし、行間を広くして読んでいるから(これは電子本のメリットである)、ほかの人とはページ数がことなってくる。どこかにオリジナル本のページ数を示してあればいいのだが、参考文献として挙げるときには、どうしていいかわからない。
ごたくはこれくらいにして、さっそく読んでみることにする。もっとも、ぼくの場合は、頭の回転が遅くなっているので、毎日ほんの少ししか読めないのはいたしかたない。
まず「総論」だ。
むずかしい。橋本治には、わかりやすさのわかりにくさがある。じつは難解というのが、最初の印象だ。そのわかりにくさは、おそらく橋本治が頭でかんがえる人ではなく、からだでかんがえる人であるところからきている。
20世紀はどのような時代としてとらえられているか。
これはあたりまえのことなのだが、20世紀になったからといって、19世紀とはまったくことなる時代がやってきたわけではなかった。それは平成が令和に変わっても、何も変わらないのと同じ。
「実際のところ、20世紀とは、終わってしまった19世紀の痕跡を、90年もかけて消そうとしている世紀だったりもする」と、橋本も書いている。
19世紀とは何か。それは戦争と侵略が肯定された時代だった。この国家の膨張を称賛する発想が陳腐に思えるようになったのは、20世紀の終わりになってからだという。
二度の世界大戦と冷戦時代をへて、大国どうしが戦争をおこす可能性はほとんどゼロになった。植民地はなくなり、大国による小国の支配も無意味と感じられるようになった。いいかえれば、20世紀は、19世紀の帝国主義と植民地主義からの脱却をめざす苦闘の世紀だったというわけだ。
たとえば1900年と2000年では、世界の国の数は圧倒的に増えている。現在の国際連合加盟国数は193カ国なのに、かつての国際連盟加盟国数は63カ国にすぎなかった。そのこと自体、帝国主義と植民地主義の時代が終わったことを示している。
とはいえ、新たな国家の誕生は、しばしば戦争をともなう。20世紀に(そしていまも)戦争がなくならなかったのは、そのためでもある。そのことをつけ足しておく必要があるだろう。
それでも、橋本治のいうように、帝国主義と植民地主義の時代は、少なくとも終わりを告げた。
19世紀から20世紀にかけて、国家の膨張と衝突が起きた背景には、何があったのだろう。その背景には「商売」があった、と橋本治はいう。つまり、このころから資本の時代がはじまったのだ。
「貿易と戦争=侵略は切っても切れないもの」だった。そういわれると、ちょっとぎくっとするが、イギリスとインド、中国のいわゆる「三角貿易」を考えると、まさにその通りである。商品は国家の先兵でもあった。
橋本のいうように「植民地獲得競争は、原材料の確保競争でもあるし、輸出商品のマーケット獲得競争でもあった」。
しかし、20世紀には、資本の膨張に後押しされて国家が膨張するといった帝国主義的行動は、徐々に忌避されていく。経済競争が時に貿易戦争にエスカレートしても、それが国家間の戦争に結びつくことは想定されにくくなった。
20世紀には、国家は国家、経済は経済と、分離して考えられるようになった。その反面、国家と経済がますます結びつきを強めているのも事実だ。そうしたGDP至上主義体制のもとで、人は日夜、経済戦争を強いられている。
この先、人はいったいどこに行くのだろうか。
ハイライトした部分を抜き書きしてみよう。
〈世界史に名を残す産業革命は、人間に「作り過ぎたからいらない」という知恵を与えず、「作ったものは、全部、押しつけてでも売れ」という暴力を生んだ。この事態は今でも続いて、「多すぎるゴミの山」という結果を生み出している。〉
〈物は作られ過ぎて、「新たに物を作る」ということ自体が、もう不必要なことになっていた。だからこそ、〝投資先〟というものがなくなって、「新たなる金儲けのために使われるべき金」は行き場をなくした。バブルの金が、株だの不動産だのへと向けられたのは、そのためである。〉
〈必要な物は作る、必要じゃないものは作らない」――こういう原則を確立しないと、このイライラとした落ち着きのない世界は、平静にならない。手っ取り早く言ってしまえば、私は、産業革命以前の「工場制手工業」の段階に戻るべきだと思う。〉
もはや商品には使用価値と交換価値があるなどとすましてはいられない。冷蔵庫や掃除機、クーラー、自動車、パソコンにせよ、いったん使い出したら、それなしにはいられなくなる。商品は世界化されていく。もう、これ以上は必要じゃないという線は、いったいどこに引けばいいのだろう。
橋本治はすでに21世紀の課題を示していたといってよい。すべては「何かへんだ」と思うところから始まるのである。
これで「総論」は終わり、次は1900年から2000年までのできごとが、1年ごとにつづられている。すごい。少しずつでも読まなくちゃ。
ところで、繰り返しのぐちになるが、kindleで読む電子本が、よく頭にはいってこないのはどうしたわけか。
タブレットはたしかに軽くて便利だが、あくまでも流し読み用にしか役に立たないと思う。ハイライトもつけにくい。この原稿を書くだけでも、パソコン上のKindleを利用せざるをえなかった。すると、やっぱり紙の本かと思ってしまうのだが、まだ結論は早い。もう少し、実験をつづけてみることにしよう。
2019-05-30 10:26
nice!(9)
コメント(0)




コメント 0