平山周吉『江藤淳は甦える』断想(1) [われらの時代]
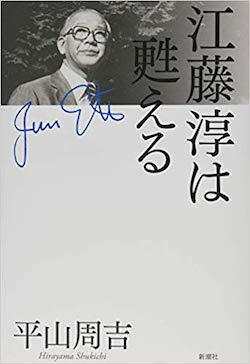
江藤淳(1932〜99)というと、夏目漱石を中心とする文芸評論、西郷隆盛や勝海舟、山本権兵衛などをめぐる歴史評論、戦後民主主義を批判しつづけた保守論客、そういうイメージが思い浮かぶ。
ぼく自身は、ほとんどといっていいくらい、江藤淳の作品を読んでいないなまけものである。愛国の風も苦手なので、たぶんこれからも熱心な読者にはならないだろう。
それでも、この本を買ったのは、江藤淳がどういう人だったかを表面だけでも知りたいと思ったからである。とくに、1960年代後半以降の江藤淳について知りたいというのが、ぼくの興味である。
江藤淳はペンネームで、本名は江頭淳夫(えがしら・あつお)という。祖父の海軍中将、江頭安太郎は将来の海軍大臣と目されていた。父の隆は三井銀行に勤めていた。父の弟、豊はのちにチッソの会長となる。いとこにあたる豊の娘、優美子は外交官の小和田恆と結婚し、現皇后の雅子の母となる。エリート家庭に生まれたといってよい。
日比谷高校時代、結核にかかり1年間休学、慶應義塾大学に進み、英文学を専攻した。1956年に『夏目漱石』でデビュー、結婚し、大学院を中退、文芸評論家の道を選んだ。そして、たちまち売れっ子になった。
1958年には「若い日本の会」を結成している。この会には、江藤を中心に、谷川俊太郎、石原慎太郎、開高健、曽野綾子、大江健三郎、浅利慶太、武満徹などが集まった。
この年、岸信介内閣は60年安保をにらみ、警察官の職務権限を強化するため、いわゆる「警職法」改正案を国会に提出する。
「若い日本の会」は、これに反発し、次のようなアピールを出した。
〈この法案は戦前の治安維持法をはじめとする一連の暗黒法に通ずるものである。私たち世代はそれらのものから直接の被害を受けず、体験を持たないが、戦争によって言いつくせぬ苦痛を味わった。この法案のもたらす危険を恐れることについては個人的体験を越えた重大かつ深刻なものを感じる。私たちはこの法案に絶対反対、その完全な撤回を要求する。〉
言論の自由を抑圧しかねない法案に反対したのだ。
「若い日本の会」は、社会党や総評などで結成される「国民会議」とは別個に行動した。江藤自身はデモ嫌いで、個人の声にこだわるという立場である。
反対運動が盛り上がるなか、警職法改正案は廃案となる。
そのころの江藤は「民主主義社会の建設」というビジョンのために動いていたという。一大ブームを巻き起こした皇太子の婚約についても、冷静に論評している。
だが、江藤は次第に同世代に愛想を尽かしはじめる。
とりわけ石原慎太郎への批判は激烈だった。「おどろくべき自己省察の欠如」(言い換えれば「不遜な自信」)などと切り捨てている。
埴谷雄高や大岡昇平との関係は良好だった。江藤に小林秀雄論を書くよう勧めたのは大岡であり、貴重な資料も提供してもらった。
『小林秀雄論』は60年安保のさなかに書き継がれ、1961年に出版される。それまで江藤は小林秀雄を全面否定していた。それが、この本で、評価ががらりと変わる。
その60年安保の年について、江藤は「危機感にかられて国会の機能回復、反岸政権のために奔走す」と、のちの「自筆年譜」に記している。
このことばに、いつわりはなかっただろう。
当初から全学連の直接行動は支持しなかった。
羽田闘争で多くの逮捕者がでたときも、埴谷雄高への手紙で、全学連は「悲劇的な茶番」であって、「全学連の過大評価はむしろいましめるべきではないでしょうか」と書いている。
安保にたいしては、いろいろな立場があってもいい。江藤は改正安保条約に批判的だったが、やみくもに反対したわけではなかった。吉本隆明との座談会では「僕は絶対に改正しちゃいけないとは言わないんで、いい方向に改定することはあり得ると思う」と発言している。
ただ、5月19日の国会で新条約案が強行採決されると、「岸信介とその一党」の横暴許すまじ、という態度に変わっていく。
国会にデモをかけるという行動には反対した。
6月10日、来日したアメリカのホワイトハウス報道官(当時の言い方では「新聞係秘書」)ハガティの車をデモ隊が取り囲み、ハガティが身の危険にさらされる事件が発生した。
江藤はこれを「非礼」かつ「愚鈍」な行動ととらえ、「進歩派指導者の退廃と無能を露呈した茶番」と非難した。デモ隊の行動は政治的感覚などまったくない無責任な反発でしかないという。
これ以降、江藤淳は安保闘争から手を引く。
樺美智子が死亡した6月15日も、ニュースを見ながら「暗たんたる気持ち」でいたというから、もはや傍観者になっている。
安保条約は6月19日に自然承認となり、23日に岸信介は辞任した。
安保闘争での疲れから、江藤淳は3度目の喀血をする。幸い、これは新しい病巣の出現によるものでなく、数カ月の療養で回復するとされた。
8月下旬、療養先の那須温泉から、江藤は埴谷雄高に私信を書いた。「朝日新聞」に掲載された「若い文学者に望むこと」と題する埴谷のエッセイについて、感想をつづったものである。
埴谷が今回の安保闘争に、若い文学者たちが「個人的自由と生命をまもるために一市民として積極的に参加した点」を評価したのにたいして、江藤はやんわりとこう批判している。
〈埴谷さんは、あたかも「市民」が現実に存在しはじめたかのようにお書きになっている。これは私たちへの御好意ですが、実は、埴谷さんの「革命」がひとつの「虚体」であるように、「市民」もまたこの国ではまだまだ「虚体」です。「虚体」を実体にしようとする努力より、「虚体」が実体だと錯覚するものを権力の具にしようとする政治の力が圧倒的に強く、だからなおさら「虚体」でありつづけるというような悪循環がくりかえされています。〉
この手紙のなかで、江藤ははっきりと「若い日本の会」から離脱することを埴谷に告げている。また全学連が、この社会の破壊をめざすカタリ派のような存在であり、埴谷こそこのカタリ派の教祖のような存在ではないかとさえ述べている。
これで埴谷との決裂は決定的になった。
はっきりいえば、安保闘争のなかで、江藤淳は「転向」したのである。これ以降、かれにとって「戦後知識人」は敵になる。その代表が丸山眞男と清水幾太郎だった。
著者は、安保後の江藤が「江頭家の家庭環境から習得した、帝国海軍と銀行員の経済的リアリズムに戻ろうとするかの如くである」と指摘している。
日本にとって、有用なのは「絶対平和」を求める知識人ではない。変転窮まりない国際世界のなかで、危険な綱渡りを強いられている実務的な「政治的人間」なのだ。安保後の江藤はそんなふうに思いはじめている。
それを日本回帰と呼んでもいいだろう。目の当たりにしたハガティ事件のショックが、国家意識を覚醒させたのだ。
江藤淳は国家なき市民よりも、日本国臣民の立場を選ぶ。埴谷雄高や大岡昇平との対立、小林秀雄への礼賛、三島由紀夫への接近はその延長上にある。
興味深いことに、安保闘争においては、江藤淳と大江健三郎の立場は意外と近かった、と著者は指摘している。
安保条約が露呈したのは、「日本がアメリカの支配下にあって、日本を動かすものが日本人の意志ではないという事実である」と、大江は述べていた。江藤の立場も基本的に変わらない。
そして、その江藤にアメリカの影が迫ってくる。
2019-06-28 06:42
nice!(9)
コメント(0)




コメント 0