平山周吉『江藤淳は甦える』断想(4) [われらの時代]
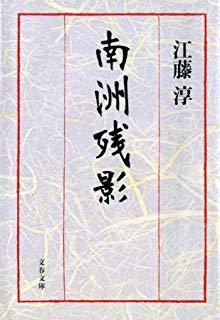
だんだんつらい話になってくるが、最後まで読むことにしよう。
1979年から翌年にかけてのアメリカ滞在時代、江藤は占領史の研究に没頭した。日本人が戦後空間を脱して、みずからの国を取り戻すのだという思いが強かった。
江藤は時折、滞在中のアメリカでも占領政策を批判する講演をしたが、それはとうぜん波紋を広げるものとなった。身の危険を感じることもあったという。アメリカの度量にも限度があった。
平山によれば、1980年代の江藤は「生き埋め」状態にあったという。それはかれが日本国憲法制定の過程、GHQによる検閲の実態を研究し、発表していた時期にあたる。
文壇にも毛嫌いされていた。江藤は1984年の『自由と禁忌』で、丸谷才一や小島信夫、大庭みな子、吉行淳之介、安岡章太郎など大御所の話題作を徹底的に批判している。評価したのは中上健次の『千年の愉楽』だけだった。
1989年には『昭和の文人』を刊行する。平野謙や堀辰雄などが断罪されるなかで、中野重治が再評価されているのが目につく。しかし、その再評価はどこかバランスを欠いている。
この年、昭和天皇が亡くなる。昭和という時代がせり上がってきたのは、このときである。
「天皇崩御に際会して、江藤の中のなにかが堰を切ったように溢れ出た」と、平山は記している。
昭和よ永遠なれとの思いが強かったという。
その思いのもと、江藤は『昭和の宰相たち』を書き継ぐ。かれによると、若槻礼次郎、田中義一から、佐藤栄作、田中角栄にいたるまで、昭和の宰相たちは、すべて天皇の宰相たちにほかならなかった。
この大河昭和史は1985年から90年まで、雑誌に連載され、単行本としては4巻で中絶した。1932年の五・一五事件で、犬養毅が暗殺されるところまでしか書かれていない。
平山によれば、1990年に公開された『昭和天皇独白録』が、それまでの記述の変更を余儀なくさせたからだという。テーマの大きさに思いのたけがおよばなかった。
1991年に還暦前の江藤は芸術院会員に選ばれている。これは大きな栄誉と喜びだったろう。
とはいえ、江藤にとって、平成は象徴天皇制と戦後民主主義におおわれた不愉快な時代となった。日本という国がなくなってしまうのではないかとさえ恐れた。象徴天皇制はかぎりなく共和制に近づいてしまう。戦後民主主義は国家の否定に行きつく。そう思っていた。
この年から、江藤はふたたび『漱石とその時代』に立ち戻り、「新潮」での連載をはじめている。記述はより慎重になっている。漱石の2年をえがくのに1巻がついやされた(第3巻)。そして、ついにこのライフワークは未完のまま、全5巻で断ち切られることになるのだ。『明暗』論が書かれることはなかった。
1994年からは西郷隆盛を論じた『南洲残影』の連載がはじまっていた。「文學界」でのこの連載は21回つづき、1998年に文藝春秋から単行本として出版される。
そのなかで、江藤はこう書く。
〈何故なら人間には、最初から「無謀」とわかっていても、やはりやらなければならぬことがあるからである。日露開戦のときがそうであり、日米開戦のときも同じだった。勝った戦が義戦で、敗北に終った戦は不義の戦だと分類してみても、戦端を開かなければならなかったときの切羽詰った心情を、今更その儘に喚起できるものでもない。況んや「方略」がよければ勝てたはずだ、いや、そもそも戦は避けられたという態(てい)の議論にいたっては、人事は万事人間の力で左右できるという、当今流行の思い上りの所産というべきではないか。〉
江藤は「大東亜戦争」に重ねて、西南戦争での西郷の挙兵を読み解こうとしていた。悲愴である。
このころ、江藤は慶應義塾大学で教えるようになっている。
『漱石とその時代』完成に向けての地道な取り組みがつづくなか、江藤は馬琴や虚子、徳田秋声にも興味をもつようになっている。漱石が終わったら、谷崎に取り組むのを楽しみにしていたという。
途中、病気で半年ほど中断するものの、還暦をすぎてからも、「漱石」の執筆はつづけられた。このころ江藤のえがく漱石は、身ぐるみ朝日新聞に買い取られた、一介の「小説記者」の「急速に老い、病んでいく」姿だった。
みずからも老いを感じるようになっていた。憂国の「逸民」の影も増していた、と平山はいう。
1993年の皇太子成婚では、いとこの長女、小和田雅子が妃に選ばれる。だが、江藤はひたすら沈黙を守っていた。むしろ、この結婚に危惧をいだいていたという。
1995年の阪神淡路大震災では、被災者の前にひざまずいて声をかける天皇と皇后に苦言を呈した。オウム真理教による地下鉄サリン事件をみて、この国が崩壊をつづけていると感じた。
1997年には慶應大学での定年を1年残して、大正大学に移籍する。20年、東工大に勤めたあと、慶應で約8年教えたことになる。
この年、江藤は日本文藝家協会理事長、三田文学会理事長、国語審議会副会長といった要職も引き受けていた。公正取引委員会での再販価格維持制度をめぐる会合にも出席している。いずれも、心身を消耗させる仕事だった。
1998年、夫人に末期がんが発見される。告知はしなかった。8カ月の闘病後、11月7日に夫人は亡くなる。
江藤は病室に泊まり込みながら、『妻と私』の原稿を書きつづけた。妻が亡くなってから、疲労のため、2カ月入院した。
妻の納骨をすませたのは、翌1999年5月である。それから2カ月半後、江藤は7月21日に自死する。
遺書にはこう書かれていた。
〈心身の不自由は進み、病苦は耐え難し。去る六月十日、脳梗塞の発作に遭いし以来の江藤淳は形骸に過ぎず。自ら処決して形骸を断ずる所以なり。乞う、諸君よ、これを諒とせられよ。〉
脳梗塞自体は軽かったという。7月8日には退院している。歩くのは少し不自由になったが、散歩することもできた。
だが、その夜、江藤は死を決意し、湯船にはいり、包丁で左手を切り自裁した。
いったい何があったのだろう。
『幼年時代』の連載がはじまったばかり。『漱石とその時代』は、たぶんもう少しがんばれば完結したのではないだろうか。
形骸というのはことばが強すぎる。あせらず養生すればよかったのにと思う。しかし、そろそろ終わりにしたいという信念を止めるわけにはいかない。
昭和に殉ずるという思いが強くなっていたのかもしれない。
非政治的人間であるぼくなどに、その気持ちははかりがたい。
2019-07-12 07:01
nice!(10)
コメント(0)




コメント 0