ホブズボーム『20世紀の歴史』をかじってみる(1) [われらの時代]
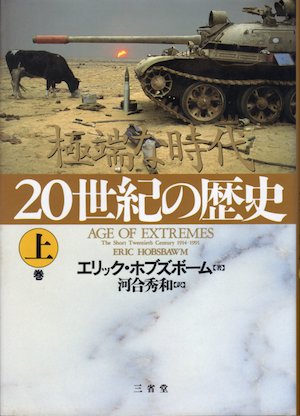
このブログは1968年ごろの「われらの時代」に焦点を合わせている。このころぼくは、いなかの家を離れて、東京で下宿生活をしていたが、すでに大学からドロップアウトしていた。といっても、気のちいさい、二十歳のただのノンポリ学生にすぎなかった。1968年に特別の思い入れがあるわけではない。
ごく単純な数字合わせをしてみる。すると、1968年の23年前は1945年、23年後は1991年ということになる。言い換えれば、1968年は第二次世界大戦の終結と、ソ連邦崩壊の中間点にある。
さらにもっと長く射程をとってみると、1968年の51年前は1917年、51年後は2019年だ。ロシア革命がおこり、下り坂の平成が終わっている。
どのように射程をとるかは自由だが、こんなふうに時間軸をのばしてみると、なぜか1968年が何かの折り返し点だったように思えてくるのが不思議だ。もっとも、それは勝手な思い過ごしかもしれない。
さらに思うのは、かくも長い歴史の大半を、ぼくが世界の片隅で、無事にすごすことができたことだ。これも気がちいさかったことの効用。しかし、そんなことはどうでもよろしい。
本書はErick Hobsbawm, Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991, Pantheon, 1994 を翻訳したものだ。1996年にはVintage からペーパーバックもでている。
著者のエリック・ホブズボーム(1917−2012)はイギリスの大歴史家。その経歴をみると、ポーランド系ユダヤ人の父、オーストリア人の母とのあいだにエジプトのアレクサンドリアで生まれている。ウィーン、ベルリンを経て、1933年イギリスに移住。1936年イギリス共産党に入党、その後60年間、共産党にとどまりつづけた。ケンブリッジ大学で博士号をとり、ロンドン大学教授として歴史を教えた。主な著書として、「長い19世紀」を扱った3部作『市民革命と産業革命』、『資本の時代』、『帝国の時代』、そして「短い20世紀」を扱った本書、その他がある。
「長い19世紀」にたいして、「短い20世紀」という言い方がされるのは、20世紀こそ著者が実際に生きた時代であり、「短い」という形容には、20世紀がめくるめく激動のうちに、あっというまに過ぎ去ってしまったという実感が含まれているのかもしれない。と同時に、20世紀の意味はまだ解明されはじめたばかりで、いまは「短い」歴史しか書けないという感慨から名づけられた可能性もある。
ぼくがもっている(いただいた)のは1996年に三省堂から河合秀和訳で出版されたもので、日本語版上下巻のタイトルは『20世紀の歴史──極端な時代』となっている。
本書には別の翻訳もある。2018年にちくま学芸文庫として大井由紀訳でだされたもので、その上下巻のタイトルは『20世紀の歴史──両極端の時代』となっている。タイトルの微妙なちがいにお気づきだろうか。「極端な時代」か「両極端の時代」か。Extremesが複数形であることを考えれば、「両極端の」のほうがより正確かもしれない。
とはいえ、ぼくがもっているのは三省堂版だ。河合秀和訳と大井由紀訳とを厳密に比較していないので、どちらがいいかについては、何ともいえないが、ここでは河合秀和訳で読書メモをまとめてみることにする。
いずれにせよ、ぼくが読もうとしているのは、後半の第二次世界大戦終結後の部分だけである。つまり、1968年を折り返しにして、1945年から1991年まで。戦前を飛ばしてしまうのは、特に理由があるわけではない。上下巻の大著なので、とても読み切る自信がないというに尽きる。しかも、後半を読むといっても、それはどちらかというと斜め読みだから(とくに翻訳書がそうだが、最近は何を読んでも頭にはいってこない)、以下のまとめは雑な印象にとどまる。期待は禁物である。
とはいえ、まず「総論」にあたる「大局的な見方」だけでも眺めて、いちおう本書の概要をつかんでおいたほうがよさそうだ。
ホブズボームは1914年から1991年までの「短い20世紀」をサンドイッチのように3段階にわけている。(1)1914年から第二次大戦終結までの災厄と二度の大戦に見舞われた「破局の時代」(2)異様なまでの経済成長と社会変容が生じた1945年から70年代はじめまでの「黄金の時代」(3)それ以降の混乱と危機に満ちた「地すべりの時代」である。
20世紀が「両極端の時代」というのは、前半の「破局の時代」と中盤から後半にかけての「黄金の時代」が両極端をなしているようにみえるからだ。
いま読もうとしているのは、(2)と(3)で、ぼくはほぼ同時代を生きてきた。
20世紀を語るうえで、資本主義と社会主義という思想的対立軸は、やはり欠くことができない、とホブズボームはいう。とりわけ、第二次世界大戦後、資本主義が黄金時代を迎えたのにたいして、その後の「地すべりの時代」において、現存する社会主義が没落していったのはなぜかを詳しくみていかねばならないと述べている。
とはいえ、ソ連型社会主義の没落以降、資本主義も完全な勝利を収めたわけではなく、大量失業や深刻な不況、経済格差、財政問題などの重荷をかかえるようになっいる。それにともない、自由民主主義の政治体制も揺らぎはじめている。社会的・道徳的危機も進んでいる、とホブズボームはいう。そのかぎりでは、「地すべりの時代」はいまもつづいているのかもしれない。
1994年に出版された本書は、無論21世紀の現在(2020年)にいたるまでの動きをとらえてはいない。著者は20世紀があまりよい終わり方をしなかったとみていた。これはソ連体制の崩壊に「歴史の終わり」をとらえた楽観的な見方とは対称的なとらえ方だったともいえる。
本書が範囲とする1914年から1990年までを俯瞰してみよう。
1914年の世界と1990年の世界はどうちがっていたのだろう。そのかん、人類は戦争による大量死を経験した。にもかかわらず、世界人口は3倍に増え、60億に達した。人間は過去のいかなる時代よりも長命になり、商品世界が発展して、身の回りの財やサービスも増大した。人びとはかつてよりよい暮らしをするようになった。たいていの人が読み書きができるようになったのも、歴史上はじめてのことである。技術の進歩も著しい。交通通信革命は、時間と距離を事実上、消滅させてしまった。
にもかかわらず、20世紀の終わりが不安な気分に満ちているのはどうしてだろう、と著者は問う。それは20世紀が暴力と殺戮の世紀だったことと関係しているが、それだけではない。何か地すべりのようなものがおきているからではないか、と著者は推察している。
さらに20世紀の初めと終わりには大きなちがいがあるという。第一に世界がヨーロッパ中心ではなくなり、アメリカの世紀となったこと、第二に、グローバル化が加速され、地球が一つの作業単位となったこと、第三に、伝統的な社会関係が崩れ、人間の意識が自己中心的になったことだ。
著者はあまりよい終わり方をしなかった20世紀とはちがい、次の世紀が「よりよい、より公正で、より生命力のある世界であることを希望しよう」と述べている。だが、21世紀の20年はその期待を裏切り、むしろ混沌と不安を増しているように思える。
以上は本書を読むにあたっての前置きである。
それにつけても思うのは、同時代評価のむずかしさである。終生マルクス主義者としての立場をつらぬいたホブズボームは、けっしてソ連に寛容ではなかったが、それでもスターリニズムを徹底して糾弾することはなかった。かれがソ連(や中国)を歴史的にどう評価していたのかも、ひとつのポイントである。
なお、ぼくの手元の本棚には、このころの歴史を扱った本が何冊かある。
ぼく自身が編集を担当したポール・ジョンソンの『現代史』は保守派ジャーナリストによるものでおもしろい。トニー・ジャットの『ヨーロッパ戦後史』はすばらしい本だ。イアン・カーショーの2冊本もある。アン・アプルボームの『鉄のカーテン』はソ連による東欧支配の実態を明かした力作だ。ほかにもいろいろある。こうした本などもちらちら眺めながら、海外旅行に行けないコロナの夏に、ホブズボームの『20世紀の歴史』を少しばかりかじってみようと思っている。
2020-08-17 07:11
nice!(12)
コメント(0)




コメント 0