ケインズ素人の読み方(1) [経済学]
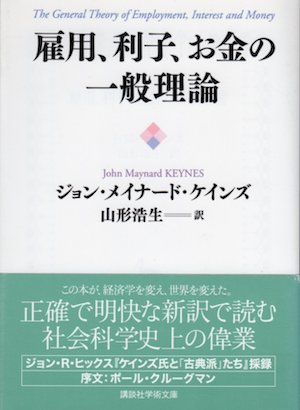
ここで取り上げようと思うのは、ジョン・メイナード・ケインズ(1883〜1946)の、いわゆる「一般理論」である。
正確には『雇用、利子、および貨幣の一般理論』。日本語版のテキストとしては山形浩生訳を利用することにした。山形訳では『雇用、利子、お金の一般理論』となっているほか、です、ます調で訳されており、多少なりとも読みやすい感じがしたからだ。
だが、すこし読みはじめて、とても歯が立つ代物ではないことに気づく。要するに、さっぱりわからないのだ。
えらいものに手をだしてしまったと思わないでもない。しかし、ここであきらめてしまったら、残りの人生で、もう二度とこの本に目をとおす機会はないだろう。最後のチャンスと思って、チャレンジしてみることにした。
けっこうな大著なので、途中で難破する公算は強い。当方の強みは、ひまだけはあるということ。いっぽう、弱みは経済学についてはほとんど知らないということである(大学時代に下宿でマルクスの『資本論』第1巻をかじった程度)。
自分の理解を助けるため、まずケインズの略歴をひろってみよう。
ケインズは1883年6月5日、イギリス、ケンブリッジのハーヴィー通りで生まれた。父親も経済学者だった。この年には、カール・マルクスが死に、ヨゼフ・シュンペーターが生まれている。
名門イートン校からケンブリッジ大学のキングズカレッジにはいり、大学時代は哲学サークル「ザ・ソサエティ」の会員となった。卒業後は大学に残らず、文官試験に合格しインド省に勤務する。しかし、1年ほどで退官し、ケンブリッジ大学に戻り、確率論の研究をつづけ、『エコノミック・ジャーナル』の編集長となった。1913年には処女作『インドの通貨と金融』を出版している。
第1次世界大戦がはじまっていた1915年には財務省にはいり、戦費調達に辣腕をふるった。19年にはイギリスの財務省首席代表としてヴェルサイユ講和会議に出席するものの、首相のロイドジョージと対立し、首席代表を辞任する。その後、ヴェルサイユ条約を批判する『平和の経済的帰結』を出版し、物議をかもした。
財務省をやめて、ケンブリッジ大学(キングズカレッジ)に戻ってからは、株式投資で大儲けする(のちに大損もするが)いっぽう、国民相互保険会社の会長もつとめた。
1921年には『確率論』を出版する。そのころロシア・バレエ団のリディア・ロポコワと親しくなり、それまでの同性愛志向を返上して(完全に返上したとはいえないが)、25年に彼女とついに結婚するにいたる。
1923年には『貨幣改革論』を出版、その前後に、のちの『説得論集』(1931年)にまとめられるかずかずの論説を発表している。30年には大著『貨幣論』、さらに33年には『人物評伝』を出版した。売れっ子の経済学者だったといってよい。
そして、ついに長い時間をかけて1936年に『雇用、利子、お金の一般理論』を出版する。過労がたまって、翌年、心臓病で重態におちいるが、なんとか持ち直した。
第2次世界大戦中も、いくつかの論文を書きながら、財務省諮問会議に出席する。1941年には渡米し、英米間の経済協力関係樹立に努力した。イングランド銀行理事にも就任した。
1942年には男爵に叙任され、自由党の上院議員となった。戦後金融体制の確立をめざし、英米間の話し合いがはじまり、イギリス側の案を作成した。アメリカとの話し合いはうまくいかない。44年、ブレトンウッズ会議に出席したものの、ケインズ案は受け入れられなかった。
1946年、国際通貨基金(IMF)と世界銀行の設立会議に出席。帰国後の4月21日にイースト・サセックスのティルトン・ハウスで心臓病のため急逝した。享年62歳。葬儀はウェストミンスター大聖堂で営まれた。
ごく簡単にケインズの略歴を追ってみた。まさに20世紀の知の巨人といってよいだろう。
ここでは1936年に出版されたケインズの代表作「一般理論」を読んでみようというわけである。ただし、ぼくは経済学の世界にうとい、ただのじいさんにすぎないのだから、その読み方はあくまでも素人の域にとどまる。
いかなる書物も時代と無関係ではありえない。つい前置きが長くなってしまうのだが、ケインズが一般理論を出版した1936年ごろが、いったいどういう時代だったかを振り返っておくのも悪くないだろう。いまとはずいぶん時代がちがう(こじつければ似ている面もあるが)。
1929年10月にはじまったニューヨーク証券取引所での株価大暴落は世界的な大恐慌につながり、その影響は1930年代半ばにいたるまで深い爪痕を残していた。
アメリカの失業率は1933年には24.9%、34年には26.7%に達した。フーヴァー大統領はなす術を知らず退陣し、33年にはフランクリン・ルーズヴェルトが大統領に就任していた。ルーズヴェルトが打ちだした斬新なニューディール政策も、当初はなかなか功を奏さなかった。それでも失業率は徐々に下がり、37年には14.3%になった。不況色が完全に払拭されるのは第2次世界大戦がはじまった39年になってからである。
ルーズヴェルトがアメリカ大統領になったのと同じ1933年に、ドイツではアドルフ・ヒトラーが選挙で国民の圧倒的な支持を得て首相になった。その後、ヒトラーはナチスの一党独裁体制を敷き、ゲシュタポを駆使して、戦争体制を築いていくことになる。いっぽう、ソ連では、1929年にトロツキーを追放し、独裁制を固めたスターリンが、農業集団化に着手し、粛清を武器にした恐怖政治をくり広げていた。
1931年、日本は満洲事変をおこし、満洲を占拠、翌年、満洲国を発足させた。32年、五・一五事件により犬養毅首相が暗殺される。33年、リットン調査団の報告に反発し、日本は国際連盟を脱退する。35年には天皇機関説問題が浮上し、36年にはロンドン軍縮会議を脱退、二・二六事件で高橋是清蔵相らが暗殺された。
高橋はケインズの『貨幣改革論』を読み、積極的な高橋財政を展開していた。二・二六事件をへて、日本では軍事統制色が強まり、1937年には日中戦争がはじまる。
このあたり歴史の流れは驚くほど速い。あれよあれよといううちに、事態が動いていく。
ちなみに、ケインズは「一般理論」発行直後に日本語への翻訳が決まったときに、さっそく日本語版のための序文を書いている。実際にその翻訳書が東洋経済新報社から塩野谷九十九訳ででるのは、それから5年後の1941年のことだった。
歴史的な背景にふれているときりがない。イギリスでも大恐慌の影響は深刻だった。1931年、イングランド銀行の外貨準備高が危険水準となり、イギリスは金本位制の放棄に踏み切った。32年には工業生産の落ちこみにより労働者の5人に1人が職を失っていた。ラムゼイ・マクドナルドの挙国一致政権がつくられる。
ケンブリッジではマルクス主義に傾く知識人が増えていた。かれらは恐慌を克服するには革命が必要だと信じるようになった。だが、ケインズは、それはかならず自由を抑圧する方向へとつながっており、革命がなくても恐慌は克服できると思っていた。
ケインズは劇作家で社会主義者のバーナード・ショーにあてた1934年12月2日の返信で、マルクスの『資本論』について、こう書いている(ロバート・スキデルスキーの「ケインズ伝」による)。
〈『資本論』には『コーラン』と同じような印象をもちます。それが歴史的に重要なものであるのはたしかですが、お調子者も含めて大勢の人はこれを「不動の岩」、かつまた示唆に富むものととらえているようです。しかし、読んでみると、それは不可解で、私は何の感興も覚えないのです。退屈で、時代遅れで、論争だらけのこの本は、とても何かを解明する目的に沿ったものとは思えません。先ほど『コーラン』みたいだと言いましたが、このふたつの書物がどうして世界のほぼ半分の地域に火と剣をもたらしているのでしょうか。辟易します。……たとえ『資本論』に社会学的価値があるとしても、その経済学的価値はゼロです。そう思って、もう一度読みなおしてもらえませんか。〉[拙訳]
このことばをうのみにする必要はない。『資本論』と『コーラン』を同次元に並べるところに、無神論者ケインズの現実主義をとらえれば足りるのかもしれない。
ケインズにはマルクスの理論がリカードの誤った前提の上に構築されたいんちきな伽藍のようにみえていた。
歴史上、革命には必然がある。だが、革命さえおこせば、恐慌や失業や貧困の問題が解決できるというものでもない。いわゆるソ連型社会主義は、経済的には相対的貧困と抑圧しかもたらさない。だとすれば、ほかに解決策はあるのか。ケインズの「一般理論」は、すくなくともその問いに答えるために書かれたといってよいだろう。
これでようやく入口にたどりついた。
いま何の装備ももたず、山形浩生訳で「一般理論」の序文を読んでみる。この序文は1935年12月13日に書かれたものだ。
書き出しはこうだ。
〈この本は主に、経済学者仲間に向けたものです。他の人にも理解してもらえればとは思います。でも本書の主な狙いは理論上のむずかしい問題を扱うことで[あって]、その理論を実践にどう適用するかは二の次でしかありません。〉
この本は経済学に熟知した人しかわかりませんよ、ということがのっけから書かれている。むずかしい問題を扱った理論書ですよ、具体的な対策を論じた本ではありませんよ、とさらに追い打ちがかかる。
これだけで尻込みしそうになるけれど、幸い、当方にはカネはないが、ひまだけはある。ひまつぶしに、のんびり読むことにする。
このあと、序文はおよそ次のようにつづく。
理論の組み立て方に関していえば、既存の経済学はけっしてまちがってはいない。まちがっているのは、その前提なのだ。
争点はきわめて重要な問題にかかわっている。その問題を解決しないと、経済学は先に進めなくなってしまう。
これまでの古典派理論は、お金を経済システムの外部から導入された道具のようにとらえてきた。だが、そうではない。お金の量と生産規模、雇用規模は一体となって結びつき、将来の見通しによって大きく変化する。そこから、われわれは雇用と利子とお金についての一般理論を構築することができる。そう考えると、古典派理論はむしろ特殊ケースなのだ。
序文──といっても、それは実際には、闘いを終えたあとの「あとがき」のようなものなのだが──の締めくくりに、ケインズはこう書いている。
〈本書の構築は著者にとって、脱出のための長い闘いでした。そして読者[経済学の専門家]に対する著者の攻撃が成功するなら、読者にとっても本書は脱出に向けた長い闘いとならざるを得ません──それは因襲的な思考と表現の形からの脱出なのです。ここでくどくど表現されている発想は、実に単純で自明だと思います。むずかしいのは、その新しい発想自体ではなく、古い発想から逃れることです。その古い発想は、私たちのような教育を受けてきた者にとっては、心の隅々にまではびこっているのですから。〉
ケインズは、みずからも囚われていた正統派経済学の「バカの壁」を壊すことを宣言したのである。その正統派経済学は、マルクスにならって、すでに「古典派」と名づけられていた。それは、師といえるアルフレッド・マーシャルの経済学を主たる標的としながら、当面の課題解決に向けて、経済学を根本から組み立て直すための、気の遠くなるような長い作業を意味していた。
いまやケインズ自体が、ひとつの「バカの壁」になっていないか。そんなことも思いながら、数学の苦手な居眠り老人は他愛ないひまつぶし読書をはじめることにする。
2021-09-20 10:36
nice!(13)
コメント(0)




コメント 0