バブルは常に発生する──『バブルの経済理論』つまみ読み(6) [経済学]

バブルの熱狂が金融危機にいたる歴史のメカニズムをえがいたものとしては、チャールズ・キンドルバーガーの『熱狂、恐慌、崩壊』(1978)が知られている。規模はともかく熱狂、恐慌、崩壊はその後もつづき、いまにいたる。市場はかならずしも合理的ではない。市場の不安定化をもたらす群集心理的な投機は常に存在する、とキンドルバーガーは考えていた。
投機の背後には、かならず信用の膨張がある。陶酔のなかで資産価格が高騰する。そして、陶酔はいつかさめ、資産価格が下落すると、連鎖的にパニックが生じる。
資本主義はバブルとその崩壊の連鎖をくり返してきた。もはや恐慌はないという予言は、2008年のリーマン・ショックによって完全に裏切られた。これまでの歴史をみるかぎり、いったん信用の拡大がはじまると、中央銀行は信用の膨張を抑制することができないことが明らかになりつつある。
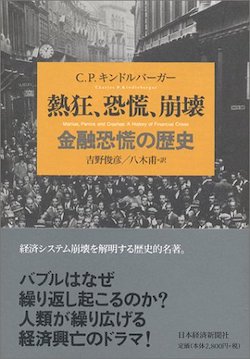
合理性にもとづいて、その体系を築いてきた経済学は、現実のバブルにたいして無力だった、と著者(櫻川昌哉)はいう。というのも、人びとが合理的に行動するかぎり、バブルなど発生するはずがないからである。
〈合理的思考で自らの脳に塹壕(ざんごう)を築いた経済学者にとって、非合理的だとしか思えない人々の行動は理解を超えていた。合理的に行動していたらこんな荒唐無稽なことは起きなかったはずなのにと、バブルを前にして立ち尽くすのみであった。経済政策の論議は、せいぜいバブル崩壊後に生じる危機に対処すればよいというお粗末きわまりないものであった。〉
頭のなかに塹壕を築いてきたとは、言い得て妙である。
そこで、実際のフィールドに立って、経済学的思考からすれば非合理的と片づけられてしまいがちなバブルについて、経済理論を組み立ててみようという著者のこころみがはじまることになる。
バブルの経済理論を、著者はミクロ理論とマクロ理論にわけている。
まずはミクロ理論からみておこう。
〈本来価値を持たない財が価値を保ち続けるとき、価値を支えるのは人々の信念や思い込みであり、その期待はその財が元来備えている利用価値とは無関係であることもしばしばである。我々はこうした財を総称して“バブル”と呼ぶ。〉
「本来価値を持たない財」とは、不動産や株式などの資産商品である。かつてはチューリップもそうした資産商品に含まれたことがある。小麦や綿花などの先物商品も投機の対象になった。
それらに価値がないわけではない。もちろん価値がある。しかし、これらが資産商品となる場合は、流動性が高い、低いにかかわらず、目標とされるのは、あくまでも将来における価値のはねあがりである。
言い換えれば、バブルとは資産商品の価値の高騰を期待しておこなわれる貨幣による投機的行動がもたらす現象だといってもよい。
そうした商品がいつまでも値上がりするわけはない。そのことがわかっていながら、なぜか多くの人が投機に走る。バブルはギャンブルとつながっている。そして、たいていが痛い目にあった。そんな非合理的な行動を、いつもなぜか人はとる。
貨幣がバブルだとしたら、貨幣自体の崩壊もあることを著者は指摘している。それがハイパーインフレーションである。それは戦前のドイツや敗戦後の日本だけで起こった現象ではない。現在もあちこち(たとえばジンバブエやアルゼンチン、ベネズエラなどでも)で生じている。
われわれはふだん意識しないけれども、実はバブルのなかで暮らしている、と著者はいう。たとえば1万円札は10円でできるが、われわれはそれを1万円と信じて使っている。なぜなら、日本銀行券と印刷されているから、それを信用しているわけだ。そして、それが将来も1万円としての価値をもちつづけると信じているからこそ、それを貨幣として認めているのだ。もし、それがじつは紙切れだと気づかされたら、その瞬間、たちまちバブルがすけて見えてきて、1万円札の貨幣価値は暴落する。ハイパーインフレーションは貨幣の信用が失われ、その幻想が暴かれたときに発生する。
バブルは貨幣と商品との関係性において生じる。商品を中心にみれば、資産商品の価値が持続的に上昇すると判断される場合に潜在的なバブルが発生し、その判断が過剰な幻想に過ぎなかったとわかったときに、それがはじめてバブルだったとわかり、バブルの崩壊がはじまる。このときバブルは土地や株式など資産商品に集中して発生するので、物価そのものはさほど上昇するわけではない。
もうひとつは貨幣自体のバブルである。貨幣の価値が下落しつづけ、それが貨幣所有者の不安と結びつくときは、貨幣自体にたいする信頼感が薄らぎ、ハイパーインフレーションが発生する。すべての商品の価格が上昇し、急激な物価高が生じ、貨幣システムが崩壊する。
株式の場合をみておこう。理論的な説明は苦手なので避けて通る。
人が株式を買うのは、配当と株式の値上がりの両方、あるいはどちらかを期待するからである。主流派の経済学は、ここで人びとは市場について正確な情報をもち、合理的な意思決定をすると想定する。そうであるかぎり、企業の価値は正当に判断され、企業価値の上昇、あるいは下落はそのまま株価に反映されるだけであって、バブルなどおこるはずがない。
それなのに、じっさいにバブルが発生するのはなぜか。資産価格が割高になってしまうのはなぜか。逆に、大暴落がおこるのはなぜか。
市場の情報は、じつはすべての投資家に共有されているわけではない。「金融機関と一般投資家の間には情報格差が存在しており、金融機関はその情報の優位性から利益を獲得している」と著者はいう。それだけではない。市場に参加するのはかならずしも合理的に行動する懸命な投資家ばかりとはかぎらない。みずからの感覚だけを優先する自信過剰の投資家も存在する。将来への期待がふくらみ、自信過剰の投資家ばかりが増える市場ではバブルが生じる。
プロの投資家は株価の上昇がバブルだと確信しても、すぐに資産を売却しない。バブルに乗じて利益をあげようとして資産を保有しつづける。そして、多くの人がバブルと気づく直前に資産を売却するのが、プロがプロたるゆえんだ。
ここで紹介されるのが、ケネディ大統領の父、ジョセフ・ケネディのエピソードである。かれはアメリカが株式ブームにわきたっていた1920年代末期、靴磨きの少年がやたら株の話をするのを聞いて、手持ちの株をほとんど売り払った。それは1929年10月23日「暗黒の木曜日」の前日だったという。
現在のヘッジファンドがとろうとしているのも、これと同じ行動だという。できるだけバブルをあおって、たとえばIT株などの株価をつり上げ、そのピーク直前に株を売るのである。
実験経済学は、将来どこかでバブルが破裂することがあらかじめわかっていたとしても、バブルがおこりうることを証明した。キンドルバーガーも、バブルが崩壊して「流動性不足への恐怖[おカネが消えてなくなるという恐怖]がパニック心理と結び付いたとき」に、資産の投げ売りや銀行破綻が実際に起こるととらえていた。売りが売りを呼ぶわけだ。この場合は逆の行き過ぎが生じることになる。
次に論じられるのは、バブルのマクロ経済学についてである。難解なので、はっきり言ってよくわからない。
著者は4つの命題を挙げている。
(1)利子率が経済成長率を下回るとき、合理的バブルが発生する。
(2)合理的バブルの存在する定常状態の経済は、効率的な資源配分を達成する。
(3)定常状態の経済では、合理的バブルの規模はGDPの一定割合となる。
(4)経済に金融市場の不完全性が存在するとき、動学的に効率的な経済にバブルは発生する。
いずれも厳密な経済学用語で述べられているため、ぼくのような素人には、よくわからない。著者のいわんとすることを、ぼくなりに勝手に解釈してみる。
(1)から(3)までは「合理的バブル」についての命題である。
合理的バブルとは一定期間持続するバブルのことである。このときはバブルであることがわかっていても、株であれ不動産であれ、さらに買い手が増えて値が上がるにちがいないという「期待の連鎖」がバブルを持続させていくことになる。
もしバブル資産が利子率より高い収益率を保証するなら、人びとは喜んでこれを購入すると考えられる。またバブル資産が経済成長率と等しい率で上昇するならば、バブル資産の収益率は経済成長率と等しくなる。そして、利子率が成長率を下回るときは、バブル資産の収益率が実物資産の収益率より高くなるから、そこでは合理的なバブルが発生する。著者はそんなふうに説明する。
このとき人びとは実物資産よりバブル資産を購入するが、その結果、利子率は成長率と等しくなるまで上昇する。
こうして経済は利子率と成長率とが等しくなる定常状態に達する。この定常状態においては、合理的バブルのもとで、人びとの消費水準は最大に達し、効率的な資源配分がおこなわれる。
そして、仮にGDPが3%で成長して、バブルも3%膨張するとすれば、バブルは膨張しても持続する。バブルがGDPの一定割合を保つかぎり、バブルは破裂することがない。だが、GDPの成長より早いスピードでバブルが膨張すれば、いずれ経済が支えきれなくなり、バブルは破裂する。
低金利のもとで、ゆるやかなバブルがつづいているといえば、おわかりのように、これは現在2020年代はじめの日本の状況である。しかし、これもあやういバランスの上に成り立っていることはいうまでもない。
しかも、実際の金融の世界は完全性が保たれているわけではない。だれもが等しく情報を共有しているわけではなく、契約は正しく履行されているとはかぎらず、企業統治は完璧になされているとはかぎらない。「金融の世界は、市場の不完全性の“坩堝(るつぼ)”ともいえる」と、著者も指摘する。
そして、いよいよ(4)の本格的バブルの可能性が浮上する。
金融市場が不完全な世界では、バブル資産の存在が投資を刺激する。バブル資産が高騰すると企業のバランスシートは改善され、企業は銀行からの借り入れを増やして投資を拡大することができる。ここでは慎重なはずの銀行が豹変して、バブル資産を担保にして融資を拡大する方向に走り、知らず知らずのうちにマクロリスクを抱えてしまう姿がえがかれている。
著者は過剰な貯蓄がカネ余りバブルを生みやすいことも指摘する。1986年から90年にかけての日本のバブルは、その典型だった。だが、日本のバブルの特徴は、バブルに踊ったのが企業と銀行であって、家計はそれほど誤りを犯さなかったことだという。
また、バブルが経済成長率とおなじスピードで膨張するならば、バブルは持続しうるとするならば、資産商品の対象は不動産や株式とはかぎらない。現在、日本においては、土地バブルに代わって国債が余剰資金を吸収する対象になっている、と著者はいう。
なぜ、こんな現象がおこったのだろう。
〈土地神話の崩壊により、空気が少しずつ漏れ出すようにスローパンクチャーを続ける土地バブルの縮小によって節約できた資金が国債購入に向かい、国債の実質価値を支えたのである。土地バブルの暴落でできた空洞を、国債という霞(バブル資産)で埋め合わせたのである。〉
株式や土地、住宅だけではなく、貨幣(タンス預金)や国債もバブル資産となりうるのだ。
こうしてみると、バブルはけっして昔話ではない。
バブルといってわれわれが思い浮かべるのは1990年前後の日本のバブル崩壊と2008年のリーマン・ショックぐらいだが、じつはバブルはいまも流転している、と著者(櫻川昌哉)はみている。
1980年代に日本はバブル景気を味わったあと、土地バブルが崩壊した。日本企業が生産拠点を東アジアに移すと、こんどは東アジアの株式と不動産の市場がわいた。しかし、1997年にアジア通貨危機がおこると、資金はアメリカに環流し、ITバブルを引き起こした。だが、それも2001年に崩壊し、今度は住宅バブルがはじまり、2008年のリーマン・ショックと世界的金融危機へと帰結した。そのころ、中国では住宅バブルがはじまる。
著者はこう書いている。
〈その時々の経済の主役の交代とともに、バブルの重心は移動しているのである。ある地域で起きたブームは、資金を世界中から引き寄せ、また国内のカネ余りを膨張させ、自信過剰と楽観主義のスパイラルとともに資産価格の高騰を引き起こす。〉
だが、そのバブルもいつか崩壊する。10年以上つづいた中国の住宅バブルもいま崩壊しつつある。
資産バブルが崩壊したあと、先進国政府は財政拡大と金融拡大によって、経済危機からの脱出をはかろうとした。利子率は低下し、巨大な債務残高が残り、経済は長期停滞の局面にはいった。
著者は、現在は、資産バブルの崩壊で生まれた空洞を、現金や国債が埋めている状態だという。そして、それ自体が、国によってつくられたいわば逆バブルであって、将来を先食いした一種の贈与経済なのだという。そうしたなかで、経済はますます長期停滞に落ち込みかねない。経済を動かすのは民間の力である。市場経済に活気を取り戻すには、大きな転換が必要だ、と著者は考えている。
2022-04-30 07:10
nice!(8)
コメント(0)




コメント 0