21世紀の展望──ホブズボーム『20世紀の歴史』をかじってみる(10) [われらの時代]

本書の原書は1994年、翻訳書は96年に出版されている。本書が扱うのは1914年から91年までだ。それ以後についても、多少の言及はあるが、1990年から今日まではや30年立ったかと思えば、時の流れの早さに驚かされる。
あのころから現在までをふり返っただけでも、大きなできごとが頻発した。歴史年表をめくる。
1993年、欧州共同体(EU)発足、イスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)との暫定自治協定、細川連立政権誕生。1994年、金日成死去。1995年、世界貿易機関(WTO)発足、阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件、ラビン・イスラエル首相暗殺、ボスニア和平協定調印。1996年、自民党政権奪還、ペルー日本大使館人質事件。1997年、英ブレア労働党政権発足、香港の中国返還。1998年、韓国大統領に金大中、クリントン米大統領の不倫疑惑。1999年、NATOによるユーゴ空爆。2000年、プーチンがロシア大統領に、平壌で南北首脳会議。
そして21世紀にはいって、2001年、米中枢同時多発テロ、米英軍のアフガニスタン空爆開始、小泉政権発足。2002年、欧州単一通貨ユーロの流通、小泉首相訪朝。2003年、米英軍がイラク攻撃を開始、サダム・フセイン大統領を拘束、中国では胡錦濤が国家主席に、韓国では盧泰愚が大統領に、日本では有事法制関連三法が成立。2004年、サマワに自衛隊派遣、EUが25カ国体制に、スーダン西部のダルフールで殺戮事件。2005年、ロンドンなど世界各地でテロ、京都議定書発効。2006年、北朝鮮が地下核実験、第一次安倍内閣発足、イラクでテロ激化。2007年、安倍首相突然の辞任、原油価格高騰。2008年、リーマン・ショック、麻生内閣、秋葉原で通り魔殺人事件。2009年、オバマが米大統領に当選、鳩山民主党政権発足。2010年、民主党菅内閣、中国がGDPで世界2位に。2011年、東日本大震災と福島第一原発事故、北朝鮮の金正日総書記死去、「アラブの春」。2012年、第二次安倍内閣発足、欧州債務危機、中国国家主席に習近平。2013年、イラン核合意、日本で特定秘密保護法。2014年、ウクライナ危機、ISが勢力拡大。2015年、フランス全土で連続テロ、日本で安全保障関連法成立。2016年、トランプが米大統領に当選、天皇が退位の意向、イギリスがEU離脱選択。2017年、ISの拠点崩壊、韓国に文在寅政権。2018年、オウム松本死刑囚らへの刑執行、初の米朝首脳会談。2019年、平成の終わりと新天皇即位。そして2020年、コロナ禍と安倍首相ふたたび突然の辞任など。
ほんとうにさまざまなことがあった。時はあっというまに過ぎていく。世界では穏やかな年は1年とてなかったといってよい。ぼくは、ありがたいことに、そのなかを凡々と生きてきた。
いまメモしておくのは、1994年に出版された本書でホブズボームが21世紀の世界をどのように展望していたかということである。いいかげんでもメモするのは、書いておかないと、何もかもすぐ忘れてしまうからだ。
20世紀の終わりになって、世界的ドラマの古い役者たちは、ただ一国、すなわちアメリカを除いて消えてしまった、とホブズボームは書いている。だから、第三次世界大戦はもうおこらないだろう、とも。
だが、これは戦争の時代の終わりを意味しない。地球規模での超大国の対決とは関係のない戦争がこれからもずっとつづくだろうという。アフリカ、旧ユーゴスラビア、アフガニスタン、中東などにはいまも戦争の火種が残っており、いつ暴発するかわからない。そして、その火種が世界じゅうに飛び火する可能性もある。この予想は残念ながら、あたった。
非国家的テロリズムの横行もホブズボームは予言していた。テロリスト集団が核兵器を手にいれることも考えられないではない。そして小集団による破壊活動を排除することは、ひじょうに難しくなっている。
世界でも国内でも、豊かな部分と貧しい部分との緊張が高まり、暴力行為が常に発生するだろう。外国人排撃の動きも出てくるかもしれない。
先進国と途上国では、武力と富に圧倒的なちがいがある。途上国は先進国に先制攻撃されればひとたまりもないだろう。だが、先進国は戦闘に勝てても戦争には勝てない。敵の領土を無期限に支配しつづけることはできないからだとも書いている。
世界は戦国時代のように、無秩序で混沌としたままだ。ホブズボームは、世界の危機は深く複雑であり、それを克服する方途はみつかっていないという感慨をいだいていた。
20世紀は世俗的な宗教対立の時代、言い換えればイデオロギー対立の時代だったとも述べている。
ソ連の崩壊は共産主義のこころみの失敗を印象づけた。もはやこれまでのような定式化されたマルクス主義が生き残ることはないだろう。
いっぽう、新自由主義の市場ユートピアも、いわば神学的な信仰にほかならなかった。純粋に自由放任的な社会はこれまで存在したことがなく、それを制度化しようとするこころみは、失敗に終わった。
20世紀に経済の奇跡をもたらした混合経済的な方策も、いまや方向感覚を失ってしまっている。
伝統的宗教も人びとの心の空白を埋めることができず、世界の平和と安定に向けての代替策を出し得ないままでいる。イスラム原理主義は反西欧意識をあおっている。
20世紀の終わりには、知的な無力感が絶望的な大衆感情と結びつき、外国人嫌いとアイデンティティ(民族主義、一国中心主義)、法と秩序を求める政治的傾向が強くなってきた。だが、そうした政治は後ろ向きであり、けっして未来を開くことにはならないだろう、とホブズボームはいう。
21世紀の課題はなんだろう。
長期的に重要なのは、人口と環境の問題である。
世界人口は2060年ごろに100億人のピークに達するとの予測もある(80億がピークという説も。2020年現在は約78億)。はたして、世界がこの人口を維持できるのだろうか。とうぜん貧しい途上国から豊かな先進国への移住も増えてくるだろう。そのときに生じる摩擦をどう解決するかが、これからの政治の大きな課題となってくるだろう。
環境問題も重要である。もし高度経済成長が無期限につづくなら、地球という惑星の自然環境に壊滅的打撃を与えることはまちがいない。だが、ゼロ成長のような提案は実行不可能だろう。それは現在の世界各国間に存在する不平等な関係を凍結してしまうからである。
だが、人間と、人間が消費する資源と、人間の活動の環境にたいする影響という三者のバランスを確立することは必至である。そうした環境バランスは無制限の利潤追求という経済の原則とはあいいれないもので、きわめて政治的・社会的な問題なのだ、とホブズボームは述べている。
次に世界経済についてみていくと、世界経済はまだまだ伸びていく余地がある。問題は豊かな国と貧しい国との格差がますます広がっていることだ。
黄金時代において、世界経済を引っぱったのは、先進国における実質所得の上昇だった。それによって、ハイテクの耐久消費財を買うことのできる大衆消費者が誕生した。しかし、そうした条件は失われつつある。高度な技術化は、雇用者の数を減らす(あるいは賃金コストを下げる)方向に働き、そのいっぽう社会保障のコストは削減されようとしている。
世界人口の約3分の2は、経済成長の恩恵をほとんど受けていない。だとするならば、資本主義の構造的欠陥について再考察し、それを除去する方向を探るべきなのではないか、とホブズボームはいう。このあたりはまだマルクス魂が生きているようである。
ソヴィエト体制の崩壊は、資本主義と自由民主主義の勝利を意味しない。世界の諸国家は冷戦終結以降、かえって不安定になり、たいていの国で政権がくるくると交代するようになるだろうとも予測している。
国民国家は弱体化した。いっぽうでは超国家的組織が、他方では民間のサービスや活動が国家の権力と機能を奪いつつあるようにみえる。
国家が無力になっているわけではない。国家が国民の行動を監視したり規制したりする能力は、むしろ技術によって強化されている。国家は国民の財産や企業の活動、さらにはコミュニケーションですら把捉できるようになった。
それでも国家は必要だろう。社会的不公正をただし、環境問題に対処し、所得の再分配をおこない、経済格差を是正し、万人のために最低限の所得と福祉を保証するのは国家の役割だからである。その意味でも、21世紀における人類の運命は、公共権力がどのような役割をはたすかにかかっている、とホブズボームはいう。だが、その動きは常にウォッチされなければならない。
EUのような超国家的組織、地球規模で適切な決定をおこなえる機関は、これからもますます求められていくようになるだろう。
いま、民主主義は深刻な窮地に立たされている。
ホブズボームはこんな皮肉な言い方をしている。
〈政治家は有権者に向かって彼らが聞きたいとは思っていないことを告げるのを恐れるようになり、政治はますます言い抜けを行使する場になっていった。冷戦の終結以後、公言できないような行動を「国家の安全」という鉄のカーテンの背後にかくすのはもはやそう簡単ではなくなった。このような言い抜けの戦略が今後も広まっていくことは、ほとんど確実であろう。〉
20世紀の終わりには、脱政治現象が生じつつあった。国民の多数が政治に無関心になり、国家のことがらを「政治的階級」、すなわち政治家や官僚、ジャーナリスト、評論家にゆだねつつあると、ホブズボームは書いている。政治から何も得られないと思った人びとは選挙に背を向けた。いっぽう、マスメディアの影響力も大きくなり、人びとの意見はそれに左右されている。
政治を動かすのは、いまや人民主義(ポピュリズム)になりつつある。政治の正統性は、国民の積極的な服従のうえにしか成り立たなくなった。
「政府はますますあいまいな言葉遣いの雲の後ろにかくれ、ぬらりくらりとまるでタコのような言動で有権者を混乱させることになるであろう」
そして、そこに真実を隠された政治的決定がなされる。
歴史は「人類の犯罪と愚行の記録である」とホブズボームはいう。もし世界が過去の歴史を学んで、自らを破壊してしまうことがなければ、未来がよりよい世界になる可能性はきわめて大きい。
だが、そのためには、何らかの社会の変革が必要だ、というのがホブズボームの見方である。
〈われわれの済んでいる世界は、過去2、3世紀を支配してきた資本主義の発展という巨大な経済的、技術−科学的過程によって捕えられ、根こそぎにされ、転換されてしまった世界である。その世界が無限に続くわけがないということをわれわれは知っている。少なくともそう考えるのが合理的であろう。〉
答えは先に残されている。
ソ連の崩壊──ホブズボーム『20世紀の歴史』をかじってみる(9) [われらの時代]
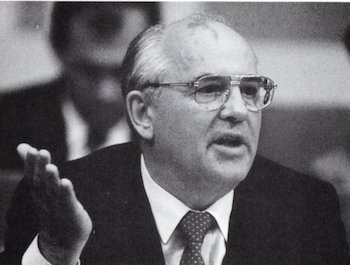
1991年のソ連崩壊は20世紀後半を語るうえで欠かせない大事件だが、それを論じる前にホブズボームは中国の毛沢東時代の悲劇を論じている。
中国は三千年の歴史をもつ国であり、中国人は中国を世界の文明の中心と考えていた。そのため中国の共産主義は、社会的であると同時に、きわめて民族的なものとなったという。
中国は19世紀半ば以降、外国からの侵略を受けており、弱体化した政府のもとで、農民は貧困に苦しんでいた。だが、1930年代半ば以降の日本の侵略は、民族の解放と再生を呼びかける中国共産党の主張に正統性をもたらすことになる。
日本の敗退後、共産党は国民党を破って、中国本土を掌握する。「これは何よりも復活を意味する革命であった」とホブズボームはいう。1949年からの農地改革は、数年のうちに穀物の生産を70%増大させた。1950年からの朝鮮戦争に中国軍は参戦し、その力を見せつけた。
だが、1950年代はじめからはじまった毛沢東の妄想めいた計画が、中国に災厄をもたらすことになる。1956年にはソ連との関係が悪化し、60年代からは中ソ対立がはじまった。
農業集団化のあとにはじまった1958年の大躍進政策は翌年から61年にかけて大飢饉をもたらした。そして、毛沢東が復権を果たすために画策した1966年からの文化大革命は中国全体を混乱におとしいれていく。
とはいえ、皇帝型権力の現実離れした政策のもとでも、中国の平均寿命は1945年の35歳から82年の68歳まで上がったし、人口も1945年の5億4000万人から76年の9億5000万人増加している。就学率もほぼ100%になったことは評価すべきだ、とホブズボームはいう。
文化大革命によって中国は荒廃し、事実上の軍事国家になってしまう。そして、1976年に毛沢東の死によって文化大革命が終息し、その直後に四人組が逮捕されたことにより、中国はプラグマティストの鄧小平のもと、新たな路線が引かれることになる。
これにたいし、ソ連はどうだったろう。1970年代から80年代にはいるにつれ、ソ連経済の成長テンポは目に見えて遅くなっていった。貿易の内容も途上国型に退行していた。1960年には主要輸出品が機械、設備、輸送手段、金属や金属部品だったのに、85年には輸出の60%近くがエネルギー(石油とガス)、輸入の60%近くが機械や金属になっていた。平均寿命も1970年以降ほとんど伸びず、むしろ減少気味になっていた。
さらにこのころ、ソ連ではノーメンクラトゥーラと呼ばれる官僚層が増大し、無能と腐敗ぶりが目につくようになった。東欧圏では1968年以後、社会主義経済を改革しようという熱意も消えてしまう。ブレジネフ時代は「停滞の時代」と呼ばれるが、それは凋落する経済を変革する意欲が失われた時代だった、とホブズボームは評している。
1973年以降の2度の石油危機は、石油生産国であるソ連に思ってもいない幸福な結果をもたらした。石油価格の高騰により、何の努力もしないのに何百万ドルもの外貨が転がりこんだのである。それにより、経済改革は後回しにされ、急速に西ヨーロッパからはいってくる輸入品の代金を、エネルギー輸出で支払うという構造ができあがる。その巨額の大当たりによって、ソ連はアメリカと対抗して、積極的な軍拡競争を展開することになる。だが、このかん省エネは進まず、経済改革は立ち遅れていた。
ソ連圏のアキレス腱は東欧だった。東欧諸国の政権は、ソ連の介入の脅威という強制力によって、かろうじて維持されていた。
だが、ポーランドでは抵抗運動がつづいていた。それを支えていたのは、カトリック教会と労働組合、反対派知識人の集団である。1981年、ポーランドに戒厳令がしかれ、ヤルゼルスキが軍事政権を樹立する。とはいえ、反対派の力を完全に封じることはできなかった。
1985年、ゴルバチョフがソ連共産党書記長の座についた。そのとき、ソ連は「停滞の時代」にあったかもしれないが、けっして政治的、社会的に不安定だったわけではなかった。ソ連体制はつましくはあったが、人びとに生活と包括的な社会保障を提供していた。変革の動きは草の根からではなく、むしろ頂点から生じたのだ、とホブズボームはいう。
根本的な改革をおこなわなければソ連経済は遅かれ早かれ崩れてしまうという危機感をいだいていたのは、共産党の上層部だった。1979年以降のアフガニスタン侵攻や、アメリカとの冷戦が、ソ連経済に大きな負担となっていた。
ゴルバチョフはそうした事態を解決しようとした。経済面では、かれは計画的な指令経済に市場価格や各企業の損益計算を導入して、経済体制をもっと合理的で柔軟なものに変えようとしていた。
ゴルバチョフはペレストロイカ([政治・経済体制の]再構築)とグラスノスチ(情報公開)というふたつのスローガンを掲げ、ソ連社会主義変革の戦いを開始した。
だが、硬直した党と国家の改革は、それ自体が難題だった。改革は体制の再構築どころか崩壊を招きかねなかった。
ゴルバチョフは、法の支配と市民的自由にもとづいた立憲主義的で民主的な国家をめざしていた。そこで問われたのは党と国家の分離であり、実効的な統治権を党から国家に移すことだった。最高ソヴィエトを主権を有する立法議会として確立することも求められていた。
いっぽう、経済面ではいわゆる第二市場、つまり闇市場を認め、国営企業の合理化をはかる方向性が打ちだされた。だが、経済改革のかけ声とは裏腹に、経済状況はますます悪化していった。自律的で活力のある企業や共同組合はそう簡単には生まれなかったのだ。
ホブズボームはこう書いている。
〈ソ連を断崖へ向かってますます急速度で駆り立てていったのはグラスノスチとペレストロイカの結合であった。グラスノスチは権威の解体となり、ペレストロイカは経済を動かしていた古い機構を破壊し、代わりの機構を打ち出さず、その結果、市民の生活水準をいよいよ劇的に崩壊させた。〉
ソ連は分解しはじめる。それまでも実質上、ソ連は「自立した封建諸侯の体制」だった、とホブズボームは評している。地方の首長、連邦共和国の党書記、配下の地域軍司令官、経済を動かす大小の生産単位のボスがいて、それを中央の党が束ね、任命したり異動させたりして、体制を保っていたのだ。その党の命令体制がなくなると、誰も支配する者がいなくなり、服従する者もいなくなった。
本来ならば、党に代わって国家がその役割を果たさなければならない。だが党が国家から切り離されたとき、そこには一種の空白が生まれていた。「暗礁に向かって進んでいく故障した巨大タンカーのように、舵のないソ連はこうして解体をめざして漂流していく」
こんなふうにホブズボームはソ連崩壊の過程をえがいている。もちろん、このあたりは文学的な表現ではすまない。もっと具体的な分析が必要なところである。
ゴルバチョフの改革はソ連を構成している15の連邦共和国の民族主義をも刺激した。連邦共和国を統合しているソ連と各連邦共和国との齟齬が生まれる。そんなときに登場するのがエリツィンである。エリツィンにとって、最高権力への道はロシア連邦を占拠することだった。
それまでソヴィエト連邦とロシア連邦は明確に分離されていなかった。エリツィンはロシアを他の共和国と同じひとつの共和国に変えることによって、事実上ソ連邦の解体を促し、ロシアをソ連にとって代わる国家へとすり替えていくことになる。
中央と党からの命令がなくなると、実効的な国民経済がなくなってしまい、地域や単位がそれぞれ勝手なバーター取引をはじめていた。こうして経済的解体が政治的解体につながり、政治的解体がさらなる経済的解体を呼びさました、とホブズボームは記している。
1989年8月から年末にかけ、ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、ドイツ民主共和国で共産党政権が崩壊する。ユーゴスラビアとアルバニアも同じである。モスクワはすでに不介入を宣言していた。ルーマニアを除いて、一発も弾丸は発射されなかった。
いっぽう、中国はゴルバチョフ流の改革に懐疑的で、逆に共産党の権威を強化する方向に舵を切った。こうして悲劇の天安門事件が発生する。
東欧諸国では共産党に代わって、反対意見を代表していた人びとが政権の座につく。チェコスロバキアでは、劇作家のハヴェルが大統領になる。ポーランドでもまもなく自主管理労組「連帯」を率いたワレサが大統領となるだろう。だが、ロマンの時代はそう長くはつづかない。
ソ連でも1991年8月にかけて、党と国家の解体が徐々に進んだ。ペレストロイカが失敗し、市民はゴルバチョフを見限ろうとしていた。リトアニアは1990年3月に全面独立の宣言を発表する。バルト三国の再独立も近い。
ゴルバチョフの人気が落ちるにつれ、エリツィンの人気が上昇していた。いまや連邦は影のような存在となり、共和国だけが実体だった。
1991年8月、保守派によるクーデターが発生する。ゴルバチョフはクリミア半島の別荘に軟禁された。
だが、この中途半端なクーデターは、ロシア共和国大統領に選出されたばかりのエリツィンによって鎮圧され、その結果、共産党は解散を命じられる。ソ連の資産はロシア共和国に継承された。こうして、1991年12月、ソ連邦は消滅するのである。
ホブズボームはソ連という実験が失敗した原因を、根本的には、ロシア革命がけっきょくのところ「無慈悲で野蛮な命令社会主義しか生み出せなかった」こと、さらには、「ソヴィエト型の中央命令−計画の行き詰り」を「市場社会主義」に改革できなかったことに求めている。
しかし、社会主義は永遠に葬り去られたわけではない、それは姿を変えて、新しい出番を待っている──ホブズボーム自身はそう考えているように思える。
革命とクーデター──ホブズボーム『20世紀の歴史』をかじってみる(8) [われらの時代]

1970年代から20世紀終わりにかけても、世界じゅうで革命とクーデターがつづいていた。国家・社会構造の根本的改変を革命と名づけるなら、クーデターは軍による国家権力の奪取を指している。革命が社会主義を葬り去ることもある。クーデターがもたらすのは、一般に軍事政権である。
世界全体を眺めてみると、本書が対象とする1970年代から90年代にかけても、われわれのふだんあまり意識しない場所で多くの革命やクーデターが発生していた。それは今後もつづくだろう、とホブズボームは予想している。
加えて、戦争である。21世紀も世界に戦雲が絶えることはなさそうだ。
第15章は「第三世界と革命」と題されている。
1970年代から80年代にかけ、第一世界は安定し、第二世界もなんとか共産党の重しがきいていたのにたいし、第三世界では、革命とクーデター、武力紛争が頻発していた、とホブズボームは書いている。その理由は、いうまでもなく第三世界が政治的にも社会的にも不安定な状態に置かれていたからである。
アジアでは、1950年から53年にかけ朝鮮戦争、1945年から75年にかけベトナム戦争がおこり、少なくとも900万人が亡くなっている。アフリカでもモザンビークやアンゴラなどでの戦争で350万人、中東でも多くの人が戦争で死亡した。イラン・イラク戦争の戦死者は少なくとも75万人に達する。無論、中南米も紛争と無縁ではなかった。
多くの革命も生じている。1959年にはキューバ革命、1962年にはアルジェリア革命が発生した。独立した多くのアフリカ諸国は、反帝国主義と社会主義を掲げる指導者を権力の座につけた。アメリカはソ連の影響力がおよぶのをおそれ、それらの国々の反対派を支援し、権力の転覆をはかった。
中ソ対立が激しくなるにつれ、ソ連が選んだのは第三世界の社会主義寄り政権を支持することだった。ヨーロッパの自由主義者も、第三世界の革命と革命家を支持していた。しかし、1964年にはブラジル、65年にはインドネシア、73年にはチリで軍事クーデターが発生し、そのあとにテロがつづいた。
第三世界の革命はゲリラ戦と結びついていた。ゲリラ戦を高く評価していたのは、ソ連よりもむしろ急進左翼のほうだった。
ゲリラ戦の象徴が、1959年のキューバ革命を成功に導いたチェ・ゲバラである。ゲバラは汎ラテン・アメリカ革命を唱え、「二つ、三つ、もっと数多くのベトナム」をと叫んだ。だが、それは失敗に終わる。
ゲリラ戦術はその後も急進派によって採用され、農村部だけではなく、都市部にも広がっていった。
だが、中南米で政治の実権を握ったのはむしろ軍部だった。1960年代、南米ではほとんどの国で軍事政権が成立する。アルゼンチンもブラジルもボリビアもウルグアイもそうだ。国が文民支配に戻るには、かなりの時間を要した。
チリでは1970年に左派のアジェンデが大統領に当選したが、73年にはアメリカの支援を受けた軍部のクーデターによって倒されてしまう。そのあとは、ピノチェト政権による処刑と虐殺、追放がつづいた。
チェ・ゲバラのイメージは、むしろ第一世界の若者たちを引きつけた。ゲバラはアメリカの戦争と支配にたいする抵抗を示す文化的シンボルになっていく。
先進国では、蜂起と大衆運動による社会革命という図式を信じる者はだれもいなくなっていた。ところが、1968年から69年にかけ、新しい社会勢力となった学生たちが叛乱をおこすのである。そのことに各国政府はとまどいを隠せなかった、とホブズボームは論じている。
学生叛乱が真の革命に発展することはなかった。それでも、フランスの学生運動がドゴール退陣に結びつき、アメリカの学生運動がジョンソン大統領を辞任に追いこんだことも事実である。
学生叛乱は学生たちのかなりの部分を政治化した。かれらが向かうのはモスクワではなく、むしろ非スターリン主義的なイコンだった。毛沢東主義にあこがれる者もでてきたし、マルクーゼももてはやされた。しかし、そのユートピア的期待がしぼむと、多くの者が古い左翼政党を支持するようになるか大衆組織にもぐりこんだりしていった。規律のきびしい非合法の前衛武装組織を結成する道を選んだのは、ごく少数だ、とホブズボームはいう。
テロと治安組織による攻防がはじまる。ドイツや日本では赤軍、イタリアでは「赤い旅団」が結成され、北アイルランドや中南米でもテロ活動は盛んになっていた。
1960年代末の学生叛乱は世界的な広がりをもっていた、とホブズボームはいう。「1960年代末の学生叛乱は、古い世界革命の最後の万歳の叫びであった」とも。このとき、世界は「真の意味で地球的だった」。
とはいえ、学生叛乱は、「存在していない何かについての夢想」であり、西欧世界では、もはや誰も社会革命を期待していなかった。
実際には世界は世界的にというより、国家主義的な方向に、言い換えれば自己中心的に動こうとしていた。その意味では国際運動は弱まり、世界革命の機運は衰えつつあった。1968年の「プラハの春」にソ連が介入したことにより、プロレタリア国際主義は雲散霧消し、西ヨーロッパの共産党も、ソ連から距離を置くことになる。
1974年にはポルトガルの長期右翼政権がクーデターによって打倒され、ギリシャでは極右軍事独裁が崩壊した。翌1975年にはスペインのフランコが死去する。
アフリカでは、モザンビークとアンゴラがポルトガルからの独立を果たすが、アメリカと南アメリカの介入によって内戦がはじまった。エチオピアでは皇帝が倒され、左派の軍事革命評議会が実権を握った。
ダホメは人民共和国となり国名をベニンと変える。マダガスカルは軍事クーデターのあと、社会主義国を宣言した。コンゴ(ザイール=現コンゴ民主共和国とは別)も軍部支配のもと、人民共和国を名乗った。
1975年、アメリカ軍のインドシナ撤退により、統一ベトナムが誕生し、カンボジアでも共産主義政権が発足する。だが、カンボジアのポル・ポト政権は、ベトナム軍の侵入によって崩壊した。
中南米では1979年にニカラグア革命が発生、エルサルバドルではゲリラ活動が活発化した。「解放の神学」にもとづく民衆運動が盛んになっていた。
1983年、グレナダでの革命にたいし、アメリカのレーガン大統領は米軍を投入し、それを阻止した。
アメリカはこうした第三世界の動きを、共産主義超大国ソ連による世界攻勢ととらえていた。こうして、1970年代には、いわば「第二次冷戦」がはじまる。
1979年にソ連はアフガニスタンに侵攻した。だが、それはソ連の崩壊を招く第一歩となる。
同じ1979年、イラン革命が発生する。アメリカを後ろ盾とする皇帝は、石油を財源とする工業化によって、強権のもとイランの近代化を進めようとしていた。だが、上からの近代化は、農村の破壊と都市のインフレをもたらし、民衆の反発を招く。民衆はイスラム教聖職者のもとに結集した。その聖職者の指導者がアヤトラ・ホメイニだった。
ホメイニは亡命先から、イスラム革命をおこすことが聖職者の義務だと説いた。聖職者の呼びかけに応じて、100万人もの人が街頭に出て、政府に抗議した。バザールの商人たちも店を閉め、ゲリラ戦士も動きはじめた。イラン革命は、宗教的原理主義の旗印のもとに行われ、かつ勝利した最初の革命だった、とホブズボームはいう。
さらにホブズボームは、20世紀後半の革命の特徴は、大衆が脇役ではなく主役として舞台に帰ってきたことだと書いている。くり返されるテロが革命に果たした役割は小さかった。
むしろ、大衆の大きな波こそが、イラン革命や東欧革命をもたらしたのだ。パレスチナでも1987年からインティファーダと呼ばれる大衆の非協力運動がはじまっていた。1989年の北京では、学生や大衆が天安門広場に集まり、民主化を求めた。
大衆行動だけでは政府を倒すことはできない。大衆が勢力になるのは、指導者や戦略、政治構想が必要だが、何よりも状況を動かすのは、大衆なのだ、とホブズボームはいう。
最後にホブズボームは無気味な予言を残して、この章を終えている。
〈20世紀末は、同時に暴力に満ちている──過去よりも、より多くの暴力がある。そしておそらく同じように重要なこととして、武器に満ちている。……そのうえ、今日では極度に破壊的な武器と爆薬を入手することはきわめて容易で、先進社会では通常は国家が武器を独占するという事態はもはや当然のこととは考えられなくなった。……次の千年紀の世界は、したがってほぼ確実に依然として暴力的な政治と暴力による政治的変革の世界であり続けるだろう。〉
この予言は残念ながら、あたった。ソ連が崩壊しても、世界で暴力がやむことはなかったのである。
問題は、われわれがこれから何を願うのかということである。



