渡邊一民『武田泰淳と竹内好』を読む(5) [われらの時代]
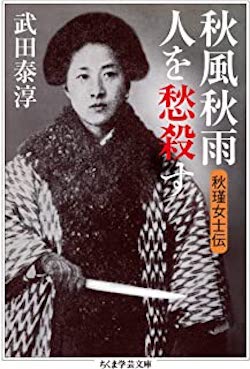
1966年、中国で文化大革命がはじまった。
渡邊はこの中国の動きに最初に注目したのが吉本隆明だったと書いている。吉本は1966年8月の『文芸』に「実践的矛盾について」という皮肉な題名の一文を寄せ、「中共支配下の整風運動」は、「戦争期の日本の農本主義思想の運動と実践がたどったとおなじ命運をたどるだろう」と予言している。しかし、その吉本も文革の実態をつかんでいたわけではない。
1967年2月、川端康成、石川淳、安部公房、三島由紀夫は連名で、文革批判の声明を発表、文化大革命が学問芸術の自由を圧殺していると糾弾した。
そのころ、武田泰淳は雑誌『展望』に秋瑾(しゅうきん)の史伝『秋風秋雨人を愁殺す』を連載しはじめていた。連載は4月から9月までつづき(6月は休載)、翌68年3月に追加の章を発表して、単行本として出版された。
秋瑾(1875〜1907)は、清朝末期の女性革命家。夫と子を捨て日本に留学、実践女学校に入学した。清朝を倒すため浙江省人の革命団体、光復会に入会し、帰国後、1907年7月、徐錫麟(じょしゃくりん)とともに武装蜂起する計画を立てる。
だが、計画に齟齬が生じた。予定より早く7月6日に安徽省安慶で蜂起せざるを得なかった徐錫麟は、安徽巡撫、恩銘の暗殺に成功したものの、たちまち逮捕、処刑されてしまう。当局は秋瑾による紹興での武装蜂起計画を察知し、7月13日に秋瑾が代表をつとめる大通学堂を包囲し、秋瑾を逮捕。31歳の秋瑾は2日後、斬首により処刑された。密告があったとされる。秋瑾は詩人でもあり、「秋風秋雨人を愁殺す」は彼女の遺句である。
武田泰淳は秋瑾が厦門(アモイ)で府長官の孫娘として生まれたところから筆を起こし、彼女が湖南の富豪の家に嫁ぎ、官位を買った夫にしたがって北京に行き、夫にさからって1904年に日本に私費留学、光復会に参加し、武装蜂起を計画するにいたった経緯を最初の2章で丁寧に追っている。
渡邊によれば、この2章を書き終えた段階で、武田泰淳は1967年4月13日から5月17日に帰国するまで、訪中作家代表団の団長として、中国各地を訪れた。杉森久英、永井路子、尾崎秀樹らが同行し、北京、西安、上海、杭州、紹興、長沙をめぐったという。
帰国してから、武田は『展望』7月号に秋瑾伝のつづきを発表する。武田はさっそく杭州から紹興に向かったときの旅行の印象をはさんだ。中国の並木の路は美しく、杭州から紹興までは1時間半の旅程だった。水路には小舟が浮かんでいた。紹興に着くと、武田は魯迅の故居を訪れてから、秋瑾ゆかりの場所に行くが、そこは門が閉ざされていて参観ができなかった。
武田は毎月連載の秋瑾伝を書きつなぐ。魯迅のエッセイ「水に落ちた犬を打て」に触れながら、こう書く。
〈徐錫麟と秋瑾が刑死した年にだけ、秋風秋雨が人を愁殺したのではなかった。その後、魯迅は死に至るまでくらい秋風秋雨が止むことなく人を愁殺しつづけるのを感じつづけていた。さもなければ、「水に落ちた犬を打て」の主張がますます彼の胸中にあって確固たる信条になって行くはずがない。〉
武田は、文化大革命下の中国でも、秋風秋雨が激しく人を打っていると感じていた。
魯迅はその小説「薬」で、夏瑜(かゆ)という青年に托して、秋瑾のことを描いている、と武田はいう。魯迅は日本留学中、さほどことばを交わしたわけではないにせよ、東京で秋瑾の姿を見ていた。
武田はいう。
「勇敢にも刑死直前まで、牢番に向って革命の大義を説こうとした青年の名は夏瑜、秋と夏では季節もつながるし、瑜と瑾は同じ玉へんであるから、すぐさま察しのつくような名にしているのは、用心ぶかい魯迅としては珍しいことである」
さらに武田は魯迅の「酒楼にて」から「今後だって? わからんよ。君はいったい、あのころぼくたちが予想したことで、一つでもその通りになったことがあると思うかい」ということばを引いて、中国革命が当初予想した方向とはちがう道をたどりはじめていることを暗示している。
秋瑾伝を書くにあたって、武田は古くからの友人でもあった夏衍(かえん)の『秋瑾伝』を参考にしていた。その夏衍が、このたびの文化大革命で1年ほど前から激しく攻撃されていることを知った。
やがて夏衍は7年間にわたって投獄されることになる。しかも夏衍を執拗に攻撃していたのが魯迅の妻、許広平であったことが「何とも物がなしい、わりきれない闇となっておそいかかり、いつまでも漂ってはなれない」と武田は書く。そして、魯迅の言にしたがえば、「私などは『落ちるまえに死せる犬』であらねばならないだろう」と嘆いた。
悲しみが伝わってくる。
武田の秋瑾伝からは「秋瑾と魯迅をつうじて、当時だれも考えおよばなかった粛清という文化大革命の本質に迫る、すくなからぬ問題が提起されている」と渡邊は論じている。
1968年8月の『群像』に掲載された「わが子キリスト」でも、渡邊は武田が「『秋風秋雨人を愁殺す』では書きえなかったみずからの現在の中国そのものへの複雑な思いを、イエス復活の故事に託して大胆に吐露した」とみている。そのとき武田の脳裏には自殺した老舎をはじめ、文革で迫害された多くの作家の顔がよぎっていた。
いっぽう、竹内好は1963年2月以来、「中国の会」を結成し、雑誌『中国』を発行しつづけていた。雑誌の中心を担ったのは、竹内をはじめとして、橋川文三や尾崎秀樹などである。雑誌『中国』は、当初、普通社から発行されていたが、普通社が経営不振におちいったため、1964年6月から会員制となり、その後、67年12月から徳間書店が版元となり市販されるようになった。 竹内はここに10年間にわたり「中国を知るために」というエッセイを掲載しつづけた。
竹内好個人は1965年に評論家引退宣言を出していた。とはいえ、時折、中国について語っている。1966年12月の『思想の科学』では、小田実との対談で、中国では新民主主義といわれる過渡期がかなり長くつづくと思っていたのに、「その点では、全く私の予想がはずれたんですよ」と思わずホンネをもらしている。中国社会主義への幻滅が深まっていた。
1967年6月の『文芸』では、文化大革命のはじまった中国を見て帰国した武田泰淳と対談している。竹内はいまや毛沢東が偶像になってしまっていることに疑問を呈しながらも、実権派が国家防衛だけを考えているのにたいし、毛沢東は世界革命を目標としているのではないかとも話している。そのころ日本やフランスでは、学生運動の一部に毛沢東思想が浸透しはじめていた。
中国にいささかの落胆を覚えながらも、竹内は中国を擁護しつづける。筑摩書房から刊行された『講座中国』第1巻には「日本・中国・革命」と題する一文を寄せた。
中国は日本をアメリカ帝国主義の隷属下にあるとみている、と竹内は述べ、中国の危機感をこう説明する。「アメリカからの侵略を既定の前提として、その場合、ソヴェトは頼りにならない、あくまでも自力で抵抗するほかない、と考えていまの行動を割り出している、これが危機感の内容である」
日本人とちがって、中国人は革命を善なるものととらえている、とも書いている。中国人にとって「永続的なのは国家ではなくて、革命である」とも断言する。「世界的規模をもってする帝国主義には、革命を世界的規模に拡大するのが唯一の対抗策である、と中国人がいま考えたとしても、それは空論ではなく、歴史から学んだかれらなりの帰結である」
1968年1月の『思想』で、大塚久雄と対談したときには、竹内は「私は文化大革命はわからない、判断を放棄します」と、あっさり述べている。竹内の気持ちは揺れていた。
竹内は学術訪中団や文芸家協会から訪中のさそいがあっても、からだに自信がないという理由でことわっている。そのくせ、1969年6月10日から7月5日まで、武田泰淳・百合子夫妻といっしょにソ連全土を回っている。官製の中国旅行はしたくないという気持ちが強かった。
だが、竹内の日中国交回復をねがう姿勢は変わらなかった。1970年2月に竹内は日米軍事同盟が強化されるのをみて、「日中国交回復はまったく絶望的になった」と述べ、7月には「たぶん米中戦争は必至であり、その一環としての日中戦争も必死でありましょう」との絶望感を表明していた。1971年10月にも「私個人は、中国との国交回復をあきらめております」と書いていた。ところが、1972年9月に田中角栄首相が訪中し、日中共同声明がだされ、国交回復が実現することになるのである。
テレビで共同声明が発表されるのをみて、竹内は「肩からスーッと力がぬけてゆく感じがした。ほとんど予期のとおり、というよりも、予想以上のものだった。よくもここまでやれた、というのが正直な印象である」と、雑誌『中国』に記した。まさか、アメリカよりも前に、日本が中国との国交回復をはたすとは思ってもいなかったのだ。
雑誌『中国』はとりあえずの目的を果たし、幕を閉じることになった。だが、このとき竹内をとらえていたのは、むしろ非力感だった。
日中関係は、国交回復以降、新たな局面にはいっていく。
日中関係が急転回する直前、武田泰淳は大作『富士』の執筆に取り組んでいた。原稿は1969年10月から71年6月まで雑誌『海』に掲載され、71年11月に単行本として発売された。
この小説は一見、中国とは無関係のようにみえる。しかし、渡邊はいう。
〈たしかに『富士』は、舞台が1944年の春から秋にとられ……敗戦直前の日本にたいする辛辣な批判となっていることを、わたしとて否定するものではない。だがその敗戦直前の日本と重ねあわせるようにして、武田泰淳がそこに文化大革命下の中国を見ていたと考えることは『富士』が『秋風秋雨人を愁殺す』「わが子キリスト」と、ほとんど間をおくことなく書きつがれたことからも、けっして見当はずれではないと、わたしは思う。〉
武田の目にはいま中国は「ワルプルギスの夜」のようにわきたち、権力の陰謀が渦巻く空間と映っていた。渡邊からすれば、武田の『富士』には「変転きわまりない中国のありようから距離をおいて、かつて中国を侵略した兵士であった過去を胸に、ひたすらその罪を贖うため殉教者のように生きようとする」姿が描かれているようにみえるのだった。
竹内好は1974年2月、酒場の階段から転落して、骨折し2カ月間の入院を余儀なくされた。「中国の会」が解散してからは、ふたたび魯迅の新翻訳に没頭するようになっていた。全7巻の『魯迅文集』第1巻がようやく筑摩書房から刊行されたのは1976年10月のことである。
いっぽう武田泰淳は、1971年の谷崎潤一郎授賞式の会場で倒れた。脳血栓だった。1974年には百合子夫人の助けを借りて、口述で『目まいのする散歩』を連載しはじめる。さらに「上海の蛍」などの上海懐古に着手するが、1976年10月5日、胃がんのため死去した。享年64歳。
このとき葬儀委員長をつとめた竹内好は、11月に食道がんが発見され、入院する。その後、病院に『魯迅文集』のゲラを持ち込んで仕事をしていたが、第3巻の解説を口述筆記したあと、1977年3月3日に66歳で亡くなった。魯迅の全面新訳はかなわなかった。
「竹内を表とすれば武田が裏というこのかけがえのない関係は、ふたりの死までつづ」いた、と渡邊は書いている。「死にいたるまで中国と中国人にたいする日本人としての責任を問いつづけたふたりは、戦後の中国が消滅していくまさにそのとき、近代日本にとって貴重な遺産を残して世を去った」
もし、あのころ竹内好と武田泰淳を読まなければ、ぼくもただの反中の徒に成り果てたかもしれない。ぼくにとって、竹内と武田は、いまでも中国への入り口でありつづけている。
渡邊一民『武田泰淳と竹内好』を読む(4) [われらの時代]

1959年11月、筑摩書房の『近代思想史講座』第7巻に、竹内は「近代の超克」と題する論考を寄せた。
もともと「近代の超克」は、太平洋戦争開戦翌年の『文学界』1942年9月号、10月号に掲載された特集のタイトルで、そこには西洋近代主義を克服するための視座を示す論文と、論文にもとづくシンポジウムの記録が掲載されていた。特集に参加したのは、西谷啓治、諸井三郎、鈴木成高、菊池正士、下村寅太郎、義満義彦、小林秀雄、亀井勝一郎、林房雄、三好達治、津村秀夫、中村光夫、河上徹太郎の13人。「近代の超克」という標語は、「大東亜戦争」推進のイデオロギー的役割を果たしたとされる。
『近代思想史講座』の論考で、竹内はこの特集「近代の超克」が、『文学界』グループと日本浪漫派、京都学派の三派によって論じられていることを明らかにし、喧伝されているのに反し、それが「戦争とファシズムのイデオロギイにすらなりえなかった」ほど無内容であること、それゆえ勝手な読みをゆるされ、ムードとして拡散したにすぎないと評する。
竹内はいう。「満洲事変」、「支那事変」以来、日本が中国を侵略しているとみる人は、けっして少なくはなかった。だが、そのころ反戦運動や反ファシズム闘争が組まれることはなかった。中国との戦争には日本民族の「優越意識」がしみついていた。そして、太平洋戦争(「大東亜戦争」)の火蓋が切られると、多くの人びとが欧米との開戦に礼賛の意を示した。
「大東亜戦争は、植民地侵略戦争であると同時に、対帝国主義の戦争でもあった」と竹内はいう。すなわち、大東亜戦争二重構造論。植民地解放闘争ではなく、植民地侵略戦争というところに、竹内らしい誠実さがあるとみてよいだろう。
この二重構造は補完関係と相互矛盾の関係にあったとされる。なぜなら先進国が後進国を指導するというのは西洋的な原理だが、植民地解放運動は日本帝国主義だけを特殊扱いにしないからだ、と竹内はいう。
「アジアの盟主」という主張に、連帯の基礎はなかった。そのため、戦争は解決されることなく無限に拡大し、太平洋戦争は「永久戦争」になるほかなかった。
「わたしは、徹底的に戦争を継続すべきだという激しい考えを抱いていた」と竹内は告白する。これは吉本隆明と同じ考え方である。大東亜戦争は理念としては永久戦争、総力戦であって、抵抗という思想にはいたらなかったと認めている。
京都学派は戦争とファシズムの理論をつくりだしたのではなく、政府の公式見解を擁護しただけだ、と竹内はいう。
いっぽう、かつて交友関係のあった保田与重郎に代表される日本浪漫派の考え方は、京都学派とはことなる。保田は近代日本のすべてを否定し、絶対攘夷を唱え、それによって自己をゼロに引き下げ、思想なるものの武装解除を成し遂げようとしたのだ。
そのため、「近代の超克」は、永久戦争の理念に屈服する思想破壊におわり、強い思想体系を生みだせなかったのだ、と竹内は評する。そして、敗戦ののちは、「近代の超克」はあっさりと見捨てられ、思想的には虚脱と従属化が導かれることになった。
思想に創造性を回復するためには「近代の超克」をアポリアとして、もう一度見据えなければならない、と竹内は論じた。このことは、竹内にとって、アジアを舞台とした「近代の超克」が、戦後においても、ひとつの課題でありつづけたことを意味している。
竹内の「近代の超克」論は、荒正人のような左派の評論家から激しい反発を招いた。荒は自分は当時、少数派だったかもしれないが、日中戦争はもちろん太平洋戦争の開戦には否定的だったとしたうえで、ファシズムへの抵抗こそが、今日につながる普遍的課題だと論じた。したがって、「近代の超克」などというファシズムを支える論議は、たちどころに葬り去らねばならない。
荒の批判は、きわめてまっとうなものだったかもしれない。しかし、竹内はあくまでも当時の雑誌に発表され、評判を呼んだ言説にこだわった。「近代の超克」が、「大東亜戦争」の二重構造を指し示し、西洋近代主義とは異なる理路を提示しようとしていた点は、けっしてないがしろにできないと論じたのである。
その竹内は60年安保闘争に積極的にかかわった。「安保批判の会」に参加し、代表のひとりとして藤山愛一郎外相や岸信介首相とも面会したり、井の頭野外音楽堂で、丸山眞男を講師にかつぎだして、市民集会を開いたりもしている。
竹内が新安保条約に反対したのは、それがソ連だけではなく中国を仮想敵国とする軍事同盟であること、さらに条約の締結によって、いまだ戦争状態のおわっていない中国との国交回復が不可能になることを恐れたためである。
だが、5月19日、自民党は国民の納得が得られないまま、単独採決で衆議院の会期延長を決め、そのまま本会議で新条約の承認可決へとなだれこんだ。その後、参議院で条約が自然承認されるまでの30日間、政府の暴挙に抗議する反対デモが国会を取り巻いた。
5月21日、竹内好は政府に抗議して、勤務する都立大学に辞表を提出した。そして、6月2日には文京公会堂の「民主主義をまもる国民の集い」で講演し、その2日後『図書新聞』に、有名な「民主か独裁か──当面の状況判断」の一文を発表する。
〈民主か独裁か、これが唯一最大の争点である。民主でないものは独裁であり、独裁でないものは民主である。中間はありえない。この唯一の争点に向っての態度決定が必要である。〉
竹内は国民運動による民主主義の再建を求めた。
6月4日には、総評・中立労組460万人、学生・民主団体・中小企業者100万人、計560万人の参加する6・4闘争がくり広げられた。竹内はこのときの闘争に「下からの民主主義」の息吹を感じた。だが、それはあまりに楽天的すぎたのである。
6月10日には、来日したアイゼンハワーの報道官(新聞秘書)ジェームズ・ハガティ(ハガチー)の乗った車をデモ隊が取り囲む事件が発生、6月15日には、全学連主流派が国会に突入し、22歳の樺美智子が死亡する事件が起きた。そして6月19日、参議院での審議がおこなわれないまま、新安保条約が自然成立した。
1961年7月、竹内好は、安保に関する評論や講演記録を集めた『不服従の遺産』を出版する。
1960年9月13日、名古屋公会堂ではこう話していた。
〈戦後の新しい憲法は残念ながら我々が自分の力で勝ちとったものではない。これは歴史の事実でありますけれども、この憲法を蹂躙する勢力があった時に、その蹂躙する勢力が憲法を捨てた時に、つまり相手が憲法は最早要らない、自分には邪魔だというので捨てた場合に、これを我々が拾えば、これは我々のものになるのです。憲法というものは人民が自分で作るべきものです。また、我々はそれを戦後当然すべきであったが、残念ながら歴史の事実としてはできなかった。けれども、今我々が自分の憲法を作る時期です。〉
60年安保をへて、竹内は明治以来の日本とアジアのかかわりを跡づける仕事に着手する。近代主義者やマルクス主義者は、おうおうにしてアジアへの視点を欠落させていたのだ。
1961年に竹内は「日本とアジア」という論考を発表する。
明治以降、日本のエリートは歴史は未開から文明に進むという「文明一元観」にもとづいて日本の近代化を推し進めてきた、と竹内はいう。その最大のイデオローグが「偉大なる啓蒙家」、福沢諭吉だった。
竹内によれば、福沢の「脱亜論」は誤解されている。福沢は「日本がアジアでないと考えたのでもなく、日本がアジアから脱却できると考えたのでもない。むしろ脱却できぬからこそ、文明の基礎である人民の自覚をはげますために、あえて脱亜の目標をかかげたのだともいえる」。
福沢には国家と人民の独立をめざす「緊迫した危機感と、同時に冷静な認識」があった。福沢は「ヨーロッパの眼で世界を眺めたのではなかった。彼のアジア観は、アジアとは非ヨーロッパである、あるいはアジアとはヨーロッパによって蚕食される地である、と考えたことである」と、竹内はいう。
したがって、福沢の「脱亜論」は単純なアジア否定論でも、日本によるアジア支配肯定論でもない。福沢自身、アジアの独立を望んでいた。アジアの原理が「文明の否定を通しての文明の再建」であることを直感していた節もある。だが、「脱亜論」のあと、福沢はそれを理論化することなく、「かえって力による文明の強制を是認する方向に後退していった」と竹内はみる。
さらに竹内は1963年8月に「日本のアジア主義」と題する論考を発表した。
アジア主義は公認の思想ではなく、いわば心的なムードである。竹内の壮大で複雑な論考は、宮崎滔天からはじまって、玄洋社、樽井藤吉、内田良平、福沢諭吉、中江兆民、岡倉天心、北一輝、大川周明、石原莞爾などの考察にいたる。いまや忘れられかけている茫洋とした思想的な流れをつかむことが目標だった。
竹内によれば、アジア主義はもともと右翼の独占物ではなかった。
「アジア主義が右翼に独占されるようになるキッカケは、右翼と左翼が分離する時期に求めるべきだろう。その時期はたぶん明治末期であり、北一輝が平民社と黒龍会の間で動揺していた時期である」
中江兆民と頭山満は生涯親しかった。しかし、その弟子にあたる幸徳秋水と内田良平にいたって、思想は左右にわかれたという。
竹内は日本のアジア主義の大もとには、西郷隆盛の存在があったのではないか、というところまで、想像の翼を広げている。
渡邊一民は、竹内の「日本のアジア主義」をこう評している。
〈「日本のアジア主義」が、ほとんど断定されることのない仮説的な議論から成りたっていることは、あらためて言うまでもあるまい。そもそもこの前人未踏の領野を踏みわけて筋道を立てていこうとする以上、それもまたやむをえなかったことにちがいない。とはいえこの「日本のアジア主義」によって、アジアにかかわる近代日本の精神史が、これまでほとんどかえりみられることのなかった右翼の側に大きく視野を拡げ、じつにさまざまな新しい問題を提起したことは、だれしも認めざるをえまい。〉
50年ほど前のあのころ、ぼくは下宿にこもって、大学の授業にも出ず、わからぬなりにマルクスの『資本論』を読んでいた。
しかし、中国やアジアについて、もっと知りたいと思うようになるのは、やはりあのころ竹内好の著書に遭遇したからだろう。
渡邊一民『武田泰淳と竹内好』を読む(3) [われらの時代]
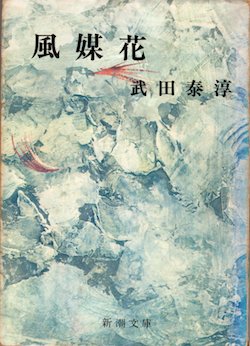
武田泰淳が上海から引き揚げたのは、1946年2月のことである。帰国してから多くの小説を発表するようになった。1946年から48年にかけて発表した「秋の銅像」、「審判」、「蝮のすえ」「滅亡について」などの作品は、日中戦争での兵士(自身)による老人殺害や、上海で経験した敗戦による空虚感、滅亡感を描いている。
渡邊によると、「武田泰淳は、いま上海での『滅亡』経験により『ゼロ』という極限状況に追いこまれ、そこでみずからの内面に甦った『死者のまなざし』を作品に定着することから、小説家としての第一歩を踏みだした」のだった。
いっぽう、堀田善衛は1945年11月に上海で国民政府に留め置かれ、中央宣伝部対日工作委員会に配属され、47年1月に帰国する。そのときの経験を描いた作品が、長編の『祖国喪失』であり、その後、『歴史』や『時間』を書き継ぐことになる。
敗戦を迎えたとき、竹内好は報道班の兵士として、洞庭湖畔の岳州にいた。敗戦で革命運動が巻き起こると予想していたので、天皇の放送にはがっかりした、とのちに語っている。
復員したのは1946年6月、そのとき『中国文学』は同人の岡崎俊夫らにより、すでに復刊されていた。その緊張感のない煮えきらない編集方針に竹内は怒りすら感じる。そして、版元の破産などもあり、竹内と武田があまりかかわらないまま、『中国文学』は1948年5月に第109号を出したところで、けっきょく廃刊となった。
そのころ、竹内は翻訳やエッセイ、評論の執筆で多忙をきわめるようになっていた。魯迅をめぐるエッセイで、竹内は「魯迅の目に、日本文学は、ドレイの主人にあこがれるドレイの文学とみえていたのではないか」と書く。さらに、日本には「あらゆる抵抗の契機を利用した魯迅のような『人民の文学者』はいない」と断言する。
そうしたなか、1948年11月に、竹内は代表的論文のひとつとなった「中国の近代と日本の近代──魯迅を手がかりとして」を発表する。
近代におけるヨーロッパの「自己解放」は、東洋への侵入をともなった。これにたいし、東洋は抵抗を通じて自己を解放した。抵抗の結果は、しばしば敗北をともなった。しかし、敗北を自覚するところから、運動がはじまり、歴史がつくられるのだ。
そのような歴史観を示したあと、竹内は日本の近代においては、魯迅の抵抗にみられるような抵抗がほとんど見られないと指摘する。原理は都合よく次々と塗り替えられ、それが進歩のように思われる。日本文化は優等生文化だ。
竹内はいう。
〈日本は、近代への転回点において、ヨオロッパにたいして決定的な劣勢意識をもった。(それは日本文化の優秀さがそうさせたのだ。)それから猛然としてヨオロッパを追いかけはじめた。自分がヨオロッパになること、よりよくヨオロッパになることが脱却の道であると観念された。つまり自分がドレイの主人になることでドレイから脱却しようとした。あらゆる解放の幻想がその運動の方向からうまれている。そして今日では、解放運動そのものがドレイ的性格を脱しきれぬほどドレイ根性がしみついてしまった。〉
日本文化が優秀なのは、主体性が欠如しているからであり、つまり抵抗を放棄しているからだ、と竹内はいう。「日本文化は……外からくるものを苦痛として、抵抗において受け取ったことは一度もないのではないか」
ここで、竹内が見据えているのは、日本の真の独立である。それは政治的な独立にとどまらず、むしろ精神的な独立といってよいだろう。
1949年10月1日、中華人民共和国が成立した。
1950年1月、コミンフォルムは日本共産党の平和革命路線を批判した。これにより、日本共産党はその批判を受けいれない「所感派」と、批判を受けいれる「国際派」に分かれ、連合国軍によるレッドパージののち、武装革命路線をとるようになった。そして、その後、ふたたび平和路線に戻った。
竹内はコミンテルンの批判に右往左往する日本共産党がコミンテルンのドレイにほかならず、日本の革命についてまともに考えていない、と厳しい評価を下している。そして、そのころから、竹内の思考は中国革命と毛沢東に向かうことになる。
竹内は「毛沢東の魯迅への傾倒の深さは、なみなみならぬもの」と述べている。さらに「中共[中国共産党]がどんなに高いモラルに支えられているか」を強調する。
さらに1951年4月の「評伝毛沢東」では、毛沢東が党内で孤立し、井岡山にこもるなかで、みずからの思想を築いていったことに大きな意義を見いだしていた。
〈毛沢東思想はこの期に形成された。かれの内外生活の一切が無に帰したとき、かれが失うべきものを持たなくなったとき、可能的に一切がかれの所有となったとき、その原型が作られたのである。これまで他在的であった知識、経験の一切が、遠心的から急進的に向きを変えて、かれの一身に凝結したのだ。それによって、党の一部であったかれが、党そのものとなり、党は、中国革命の一部でなくて全部になった。世界は形を変えた。つまり、毛沢東は形を変えたのである。〉
竹内は毛沢東をきわめて文学的にとらえている。渡邊は「こうして中華人民共和国成立の1949年以後、中国共産党そのものである毛沢東が、すでに13年まえに没した魯迅にかわって竹内好の同時代の指標となっていくのだ」と論じている。
このころ、竹内は日本の代表的な評論家として、一目置かれるようになっていた。1952年には国民文学を提唱し、さまざまな論議を巻き起こした。それはとりわけフランスを金科玉条にする文学への批判であり、民族の伝統に根ざす文学の提唱にほかならなかった。だが、論議は次第に拡散し、そのうち雲散霧消してしまうことになる。
1954年5月から1年間、竹内は『思想の科学』の編集長を務めた。前田愛によれば、竹内は「日本人全体の思想をそだてる運動のための共通の広場」をつくろうとしていたのだという。
そのころ武田泰淳は、注目すべき小説を刊行している。1952年10月に講談社から出版される『風媒花』である。
描かれたのは講和条約直後の1951年秋の3日間。架空の「中国文化研究会」をめぐるドラマになっている。
登場するのはエロ作家の峯、そして思想家の軍地、そして会のさまざまなメンバー。峯は蜜枝という女性と同棲している。さらに美貌の三田村青年、右翼の怪物、細谷源之助などもからんで、小説は立体的、ドラマチックに構成される。
峯は武田泰淳本人、蜜枝は武田百合子、軍地は竹内好、細谷は北一輝がモデルになっている。ほかにもモデルはいるはずだが、ぼくなどにはわからない。中国文化研究会は「中国文学研究会」のことだといって、まちがいないだろう。そして、登場人物はたぶんに戯画化されている。
物語は峯(武田)が銀座で開かれた中国文化研究会に久方ぶりに出席するところからはじまる。中国文化研究会は、戦前、「支那」に代わって「中国」という表記をはじめて採用し、中国とのあいだに「新しい橋」を架けようとした。そして、その思いは共産中国が成立したあともつづいているというのが、会の説明だ。
この会を引っぱっているのが、峯の15年来の友人である軍地(竹内)だった。久しぶりに会合に出てきた峯を軍地が茶化す。そんな軽妙なやりとりがあって、会を支えているのが、軍地の熱烈な使命感であることが示される。
日中戦争を忘れて、中国を論ずることはできなかった。会に参加するほとんど全員が、この戦争に参加していた。「何万何千万の中国民衆の家庭を焼き払い、その親兄弟を殺戮したあの戦争」が、いまもつづく会の出発点となっている。
峯は潔癖な軍地を尊敬している。ただ自分と同じ「文学病患者」であることに悲劇性を感じている。「本当の物凄い政治家」が、自分たちを支配しようとして待ち構えていて、「そいつの出現到来を軍地は希望しつつ、また一方ではそれに抵抗し反抗しなきゃならない」引き裂かれた状態に、いつか軍地がおちいるのではないか、と峯は危惧する。
それが毛沢東だと武田泰淳が示しているわけではないが、作家の勘はさすがに鋭い。
会合の途中で峯は席を立つ。電報で親戚(亡き妹のつれあいで、支那哲学者)の危篤を知らされていたためだ。病院に行くと、見舞客のなかに、かつて満洲国を「王道楽土」と唱え、軍の大学に勤めていた男と、老漢学者がいた。かれらは口々に「支那一点ばり」の軍地を批判し、「支那をネタにして、日本を罵倒したってはじまらんですからな」と憎悪に満ちた声をあげるのだった。
いっぽう銀座での会合を終えたあと、軍地をはじめとする3人のメンバーは、有楽町のガード下の焼酎ホールで飲んでいた。そこに現れたのが、中国人を母とする美貌の三田村青年で、はっきりいって純粋行動のテロリストである(いかにも武田泰淳好みの人物)。かれは、日本人を糾弾するため、テロに走ろうと考えている。三田村は軍地に「あなたと僕は同類なんですからね」と言い放ち、いっしょに大磯に行こうと誘った。
その夜、軍地と三田村は、大磯で右翼の怪物、細谷源之助と会う。細谷は戦前、上海、南京、武昌での中国青年の武装蜂起に参加していた。そして日本改革のために、青年将校による武装クーデターをくわだてた。西洋を排撃するアジア革命はこの老人の夢だったといってよい。二・二六事件で刑死した北一輝がモデルである。
翌日、軍地と三田村青年は、霧雨の降る海岸を歩いている。三田村青年の頭にあるのは、細谷老人の唱える「殺、殺、殺」の呪文だ。三田村は軍地に向かって、「真に中国を信じ愛しているとしたら、新中国の文化を研究しているだけじゃ、不充分なはずですがね」といい、いまふたつの計画が進行しているという情報を軍地に明かす。
ひとつは、旧日本陸軍の将校が、中国軍閥の親分と手を握って、反共義勇軍を編成するため、台湾に兵員と武器を集めようとしており、そのための密航船が一両日中に、九州から台湾に向けて出航しようとしているという情報。もうひとつは、これとは逆の動きで、ある美少年が朝鮮戦争で米軍に協力する都内のPD(特需)工場にたいし、食堂のやかんに毒薬を投げ込み、東京じゅうのPD工場を恐怖におとしいれようとしているという情報。
軍地はその美少年が三田村のことだと気づき、「君はやっぱり少し、自分という者を、特別の者に見立てたがっているんじゃないかな」と話し、すでに実行に移ったというその計画を批判する。
この日の昼、作家の峯は、同棲する蜜枝の弟でマルクス青年、守の愛人、細谷桃代に頼まれて、彼女のつとめるPD工場を見学してから、彼女のサークルで話をすることになっていた。ところが、工場の食堂の土瓶に青酸カリが入れられているのがわかって、工場見学は中止となり、峯はそのままサークルで話をする羽目になる。
峯は思わず、こう話しはじめた。
〈実に無数の人間が人間によって殺されている。愛国的殺人であろうと売国的殺人であろうと、殺人行為にかわりはない。自ら手を下さなかった人々といえども、何らかの形で殺人にかかわりのない者はいない。我々日本人のほとんど全部、否世界の人間のほとんど全部が殺人に参加したと言ってもいい。殺されながら殺し、殺しながら殺す。無数の媒介物によって、知らず知らずのうちに、どこかで誰もが人殺しに関係している。しかも現代の一番おそろしい点は、殺人者が時がたてば自分の犯した行為を忘れられるばかりでなく、時によっては、自分が人殺しであることを知らないですむ点にあります。〉
現代では、だれもが殺人者だという武田泰淳の哲学が開陳されている。
物語はさらにつづく。その夜の新宿での蜜枝の痛快な大冒険。三田村の隠匿兵器略奪事件とそれを阻止した少女の話。北京政府とつながりがあるのではないかと中国文化研究会に探りをいれはじめた公安の動き。話はますます混沌としてくる。
そして、だれもが、それぞれの思いを秘めたまま、小説はとつぜん幕を閉じることになる。
渡邊一民はこう述べている。
〈いってみれば『風媒花』は、中国にかかわる1951年以後の日本におけるさまざまなドラマの「序曲」として書かれたと言えるかもしれない。そしてそのためこの作中には、武田泰淳の経験のすべて、あえていえば中国文学研究会同人のすべてが傾注されている〉
『風媒花』は、中国をめぐる未完成の曼荼羅図だったといえるかもしれない。そうした中国への熱い思いは、すでに失われて久しくなっている。
渡邊一民『武田泰淳と竹内好』を読む(2) [われらの時代]
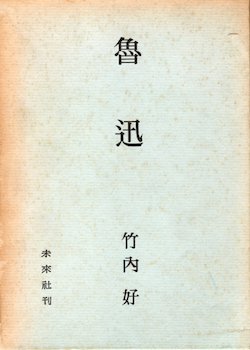
1937年7月、日中戦争がはじまり、日本国内では戦時体制がますます強化されていった。
この年10月、竹内好は外務省の補助金で北京に留学し、武田泰淳は召集され、中国大陸の戦線に送られた。
その間『中国文学月報』は、同人たちの手によって年11冊の割合で刊行されつづけている。
武田は上海と徐州の戦闘に参加、杭州にしばらく駐留し、翌年の徐州会戦、武漢作戦にしたがったあと、1939年10月に除隊となり、日本に戻ってきた。
中国の戦場を経験した武田は、日本であふれている中国関係の出版物に空しさを感じ、『中国文学月報』に「我々が戦地で見た支那土民の顔」は「あまりにも鮮明に眼の底にとどまっているので、活字になった支那評論が色あせて見える」との感想を寄せている。
〈文化とは何と無力なものであらう。その時私は数万の鴉の群れ飛ぶ空を仰ぎ、永遠に濁り流れる無言の江水を見下ろして嘆息しました。我々が研究し愛着を持った支那の文化といふものはかくも無力に破壊され消滅して行くものであろうか。〉
そのころ2年半の留学を終えて、北京から戻ってきた竹内好も混迷を深めていた。
1940年4月に『中国文学月報』は『中国文学』と改題され、生活社から市販されることになった。出版界では、中国ブームが巻き起こっていた。
帰国した竹内は、「文学」の枠を越えて、中国そのものを理解するための雑誌づくりをめざそうとした。「アメリカと中国」特集を組んだのも、そうしたこころみのひとつである。「翻訳時評」のコーナーを設けて、新たな中国理解への道を開こうともした。
1941年12月、日本軍は真珠湾を攻撃、太平洋戦争がはじまる。
竹内は1942年1月の『中国文学』巻頭に、「大東亜戦争と吾等の決意」なる宣言を掲載する。
〈歴史は作られた。世界は一夜にして変貌した。われらは目のあたりにそれを見た。感動に打顫(うちふる)へながら、虹のやうに流れる一すじの光芒の行衛(ゆくえ)を見守つた。胸ちにこみ上げてくる、名状しがたいある種の激発するものを感じ取つたのである。何びとが事態のこのやうな展開を予期したらう。戦争はあくまで避くべしと、その直前まで信じてゐた。戦争はみじめであるとしか考へなかった。実は、その考へ方のほうがみじめだったのである。卑屈、固陋、囚はれてゐたのである。戦争は突如開始され、その刹那、われらは一切を了解した。〉
アメリカやイギリスと戦争をはじめるさいの高揚感は、おのずからわきあがったものだったろう。竹内は「東亜を新しい秩序の世界へ解放するため」、「東亜から侵略者を追へはらふ」、「日支両国万年の共栄のために献身する」のだ、と本気で信じていた。
アメリカと戦争して勝つとか、中国と永遠の共栄を築くとか、西洋列強を追いだして東アジアに新秩序をつくるとかのスローガンには、どこか虚偽が潜んでいる。そのことを竹内好も自覚していなかったわけではなかった。のちには、おおいに反省もしたことだろう。
だが、竹内はこのときの高揚感を忘れることはなかった。戦後になって独自のアジア主義を主張するようになるのはそのためだ。竹内の唱えるアジア主義は、日本も真似しがちな西洋流の拡張主義を乗り越える跳躍台となりうるはずだった。
そのことについては、またあらためてふれる。
竹内好は雑誌『中国文学』を編集しながら、1940年4月以来、回教圏研究所に勤めていた。そして、1942年2月に研究所から派遣されて中国に行く機会に恵まれ、北京、内蒙古、太原、開封、杭州、上海を回り、4月に帰国した。回教事情を調査するのが目的だったが、中国各地の様子を見て回ったのはいうまでもない。帰国してから、武田泰淳など中国文学研究会のメンバーと座談会を開いている。
竹内はそのなかで、「大東亜共栄圏文化の根幹である日本文化と支那文化が……もっと本質的に本当の意味で融合しなければいけない」と語っている。そのためには外部から論評するのではなくて、のっぴきならない根源的なもののなかに、自分自身を投げ入れることが必要だ、と竹内はみずからの決意を示した。
太平洋戦争が進展し、戦局が激化するなか、『中国文学』も1943年3月に廃刊を余儀なくされ、9年間の幕を閉じることになった。
だが、それと同時にふたつの著書があらわれる。武田泰淳の『司馬遷』(1943年4月)と竹内好の『魯迅』(1944年12月)である。
武田泰淳は1940年8月の『中国文学』に載せたエッセイでこう書いていた。「世に殺人ほど明確なものはない。殺された者は横になって動かず、殺した者は生きて動いてゐる」。
渡邊は、戦場のぬきさしならぬ緊張感を抜きにして、武田泰淳の『司馬遷』は語れないと述べている。
司馬遷にとって、歴史とは全体であり、世界にほかならなかった。
武田はこう書く。
〈「人間」の姿を描くことによつて、「世界」の姿は描き出される。「人間」の動きを見つめることにより、歴史全体が見わたされるのである。そして「人間」の姿を見つめて行き、「人間」の動きを描き出してゐるうちに、いつしか「人間」は「政治的人間」と化して、世界を動かし、歴史をつくり出してゐることがわかつて来るのである。〉
ここで、武田は「政治的」を広い意味で使っている。すなわち「世界を動かし、歴史をつくり出」すことが「政治」なのである。
いっぽう竹内好は1943年12月4日に召集され、10日に中支派遣軍の補充兵として、中国湖南省に送られた。その直前に完成した『魯迅』の原稿は、武田泰淳の跋と校正をへて、翌年12月に出版へとこぎつけることになった。
したがって、『魯迅』が出版されたときには、竹内は中国の戦場にいたのである。
魯迅について、竹内はいう。
〈彼は、退きもしないし、追従もしない。まづ自己を新時代に対決せしめ、「掙札(そうさつ)」によって自己を洗ひ、洗はれた自己を再びその中から引出すのである。この態度は、一個の強靱な生活者の印象を与へる。〉
掙札とは、何か。できごとを内在的に把握し、それを否定することによって、新たな何かをしぼりだすことを指しているのではないか。そのかぎりにおいて、魯迅は変わりつづけたが、すこしも変わらなかったともいえる。
そこで、竹内はこうもいう。
〈魯迅の見たものは暗黒である。だが、彼は、満腔の熱情をもつて暗黒を見た。そして絶望した。絶望だけが、彼にとって真実であつた。しかし、やがて絶望も真実でなくなつた。絶望も虚妄である。「絶望の虚妄なることは正に希望と同じい」。絶望も虚妄ならば、人は何をすればよいか。絶望に絶望した人は、文学者になるより仕方ない。〉
魯迅は絶望に安住しなかった。希望も絶望も見捨てて、掙札により無限なる道を求めることにした。それは生きることを意味していた。そして、「無力な文学は、無力であることによつて政治を批判せねばならぬ」という境地にいたった、と竹内は論ずる。
それは竹内自身がたどりついた思想だったといえるだろう。
戦場で戦う竹内を追うように、今度は武田泰淳が1944年6月に上海に赴くことになる。さらに武田と同じく雑誌『批評』の同人となっていた堀田善衛が上海に行くのは1945年3月のことである。
そのころ上海は国民党と共産党に加え、国際的な諜報機関が暗躍する場所で、日本軍占領下とはいえ、すでに無政府状態に近くなっていた。
それから間もなくして日本は敗戦を迎える。
このとき、竹内も武田も堀田も中国にいる。
渡邊一民『武田泰淳と竹内好』を読む(1) [われらの時代]

サブタイトルに「近代日本にとっての中国」とある。
だとすれば、これは昔の話かというと、そうでもあるし、そうでもない。
武田泰淳も竹内好も過去の人である。学生時代、ぼくなども生かじりながら、ふたりの本をよく読んだものだ。竹内と武田は中国への入口であり、ふたりの著作を通じて、ぼくらは日本は中国と二度と戦争をしてはならないと思っていた。
最近の日本は、まるで準戦時体制下にあるかのように息苦しい。アメリカと同盟を結ぶ日本にとって、強大化し帝国化する中国を仮想敵国とし、かといって日本と中国の経済関係は切っても切れぬ関係にある。この微妙な関係のなかで、何につけ、中国との緊張は高まる。日本自身も中国と同様、いわば「中国化」しつつあり、国内では治安体制が強化され、監視と排除の仕掛けが網の目のように広がっている。
ぼくの気分は悲しさ半分、あきらめ半分といったところ。しかし、どこか熾火のように反抗心が残っていて、日々のニュースや解説者のコメントに文句をつける癖は抜けない。
この年になると、世間がどう変わろうと、自分は自分であって、いまさら変えようがない。世間からみると、そんな困った自分はいつつくられたのだろう。ふり返ってみると、それは親のすねをかじって長く過ごした大学生時代だったと思わないわけにはいかない。そして、あのころ、大学闘争が終わりを迎えたころ、わからないなりによく読んでいたのが、竹内好と武田泰淳だった。
戦後の冷戦体制のもと、日本と中国はいわば切断されていた。そんなとき、日本と中国の国交回復を訴えつづけていたのが竹内好だった。時代錯誤ともみえる大きな文明ビジョンのもと、竹内は両国のねじれた関係をただそうと努力をつづけていた。
竹内は武田と同様、文革に失望し、一時は国交回復も諦めていた。だが、アメリカが新外交戦略をとったため、突然、日中回復が実現する運びとなった。それでも、竹内は日本と中国がほんとうに理解しあう関係になるのかを疑っていた。変わらなかったのは、中国を内在的に理解しようという竹内の姿勢である。
本書の著者、渡邊一民(1932〜2013)はフランス文学者で、立教大学教授。ミシェル・フーコーの『言葉と物』の翻訳者として知られていた。さまざまな翻訳のほか、多くの評論を残したが、近代日本の精神史3部作として書かれたのが、『フランスの誘惑』と『〈他者〉としての朝鮮』、そして本書『武田泰淳と竹内好』である。
前置きが長くなったが、のんびりと、あまり深刻がらず、むしろ昔を懐かしむような気分で読んでみることにしたい。
1912年の清朝滅亡後も、日本は中国での権益を求めて、中国に進出しつづけていた。だが、現代中国についての日本人の知識はきわめて乏しく、むしろ偏見に満ちていた、と渡邊は指摘している。
1920年代になって、佐藤春夫や谷崎潤一郎、芥川龍之介なども中国を訪れているが、その中国観は旅行の印象記にとどまっていた。それを一変させたのは1932年に刊行された横光利一の『上海』だったという。
横光は日本人の経営する上海の綿紡績会社、内外綿で発生した1925年2月の中国人労働者によるストライキと、それが巻き起こした抗議活動をこの小説にえがいた。この事件により、上海はほぼ3カ月にわたって麻痺状態となり、イギリス人の指揮する警官隊の一斉射撃により、多数の死傷者がでた。いわゆる5・30事件である。これ以降、上海は革命の舞台へと変じていく。
1935年前後は、日本にとって知の地殻変動がおこった時期だ、と渡邊は書いている。美濃部達吉の天皇機関説が糾弾され、日本は神国であるという国体明徴運動がはじまり、治安維持法によって検挙された小林多喜二が拷問死させられ、獄中の共産党員が相次いで転向している。それは狂瀾の時代だった。
そんな時代に竹内好や武田泰淳らは『中国文学月報』を発刊する。1935年3月のことである。
渡邊によれば、当初「月報」の誌面をにぎわせたのは「漢学論争」だったという。
江戸時代に完成をみた「漢学」に、「月報」はどう向き合うべきかと、ある同人が問いかけたのにたいし、竹内はこう答えている。
いまや漢学は社会の進化の外に置き去りにされ、硬化しているが、もし「溌剌たる外気の流入」がなされれば、硬化を免れる可能性はある。しかし、旧来のような文献考証学的な態度に終始するならば、漢学を昔のように復興するのは無理だし、そもそも無駄だと思う。それよりも自分たちの血をたぎらせるような中国文学を見いだすことこそが、「月報」の課題ではないか。
そのため「月報」は、魯迅、林語堂、周作人、老舎、郁達夫など、現代作家の翻訳に多くのページを割くことになる。
「月報」が軌道に乗りはじめたころ、1936年10月19日に魯迅が上海で亡くなる。翌月の第20号「魯迅特輯」は、たまたま魯迅の訃報と重なった。そこで竹内は急遽、追悼の意味を込めて、魯迅の「死」というエッセイを翻訳した。魯迅はこのエッセイを9月に発表したばかりだった。
渡邊がこのエッセイにふれているわけではない、ここでは、竹内好と魯迅とのかかわりを知るために、雰囲気だけでも紹介しておこう。
エッセイのはじめに、魯迅はケーテ・コルウィッツの版画集を印行することになり、アグネス・スメドレーに序文を頼み、それを茅盾に訳してもらい、読んでみたと書いている。その序文でスメドレーは、コルウィッツの最近の画材には死を主題にしたものが多いと指摘していた。そこで、魯迅も中国人にとって死とは何かを考えてみたという。
魯迅の文章はユーモラスで、たっぷり皮肉がこもっていて味わい深い。金持ちは金持ちなりに、おだやかな成仏を願い、貧乏人は早くこの世とおさらばして、りっぱに生まれ変わることを願う。死にも階級差がある。しかし、多くの人はふだんあまり死のことを考えず、自分も多くの人と同様、これまで成り行きまかせで、臨終の際のことなど深く考えてこなかったという。
ところが、ことし大病を患って、ようやく死というものの予感が湧いた。アメリカ人の医師にみてもらうと、余命いくばくもないとのこと。その宣告は少しも気にならなかったが、物思いにふけるうちに、死について考えるようになった。ただ、思うのは、死ぬとどうなるかというような哲学ではなく、むしろこまごまとしたことばかり。そこで、遺言めいたものを考えてみた、と魯迅はいう。
その遺言めいたものは、1936年の竹内の訳ではこうなっている。
一、葬儀に当り、何びとより、一銭たりとも香奠(こうでん)を受くるを許さず──但、老朋友はこの限りにあらず。
二、速かに棺に納め、葬ればよし。
三、紀念に関する何事もなすべからず。
四、我を憶わず、己の生活に力(つと)めよ──然らざるはたわけ者なり。
五、吾子長じて、才能なくんば、つつましき生業(なりわい)を求めて身を立つべし。ゆめ空頭の文学家、美術家となる勿(なか)れ。
六、他人の汝に許し与えんとするものを真(まこと)とするなかれ。
七、他人の牙と眼とを傷け、却(かえ)って報復に反対し、寛容を主張する者、かれが如きに近づくべからず。
後年、竹内はこの部分を次のように訳しなおしている。
一、葬式のために、誰からも、一文でも受け取ってはならぬ──ただし、親友だけはこの限りにあらず。
二、さっさと棺にいれ、埋め、片づけてしまうこと。
三、何なりと記念めいたことをしてはならぬ。
四、私のことを忘れて、自分の生活にかまってくれ──でないと、それこそ阿呆だ。
五、子どもが成長して、もし才能がなければ、つつましい仕事を求めて世すぎせよ。絶対に空疎な文学者や美術家になるな。
六、他人が与えると約束したものを、当てにしてはならぬ。
七、他人の歯や眼を傷つけながら、報復に反対し、寛容を主張する、そういう人間には絶対に近づくな。
この箇条書きのあとが、さらに痛烈である・
竹内の1936年訳で示しておく。
〈まだあったが、今は忘れた。覚えていることは、熱のあるとき、こんなことを思い出した。よく欧洲人は臨終の席で儀式を行い、他人の赦(ゆる)しを求め、自らも他人を赦すという。私は怨敵が多いといえよう。もしも新しがりの男が来て、自分に問うた場合、私は何と答えたものであろうか。考えてみた。そして決めたのは、彼等をして恨ましめよ、吾また一人も恕(ゆる)すまじ、ということであった。〉
魯迅を通じて、竹内ははじめて中国に触れたのである。



