渡邊一民『武田泰淳と竹内好』を読む(3) [われらの時代]
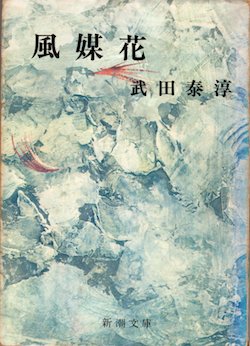
武田泰淳が上海から引き揚げたのは、1946年2月のことである。帰国してから多くの小説を発表するようになった。1946年から48年にかけて発表した「秋の銅像」、「審判」、「蝮のすえ」「滅亡について」などの作品は、日中戦争での兵士(自身)による老人殺害や、上海で経験した敗戦による空虚感、滅亡感を描いている。
渡邊によると、「武田泰淳は、いま上海での『滅亡』経験により『ゼロ』という極限状況に追いこまれ、そこでみずからの内面に甦った『死者のまなざし』を作品に定着することから、小説家としての第一歩を踏みだした」のだった。
いっぽう、堀田善衛は1945年11月に上海で国民政府に留め置かれ、中央宣伝部対日工作委員会に配属され、47年1月に帰国する。そのときの経験を描いた作品が、長編の『祖国喪失』であり、その後、『歴史』や『時間』を書き継ぐことになる。
敗戦を迎えたとき、竹内好は報道班の兵士として、洞庭湖畔の岳州にいた。敗戦で革命運動が巻き起こると予想していたので、天皇の放送にはがっかりした、とのちに語っている。
復員したのは1946年6月、そのとき『中国文学』は同人の岡崎俊夫らにより、すでに復刊されていた。その緊張感のない煮えきらない編集方針に竹内は怒りすら感じる。そして、版元の破産などもあり、竹内と武田があまりかかわらないまま、『中国文学』は1948年5月に第109号を出したところで、けっきょく廃刊となった。
そのころ、竹内は翻訳やエッセイ、評論の執筆で多忙をきわめるようになっていた。魯迅をめぐるエッセイで、竹内は「魯迅の目に、日本文学は、ドレイの主人にあこがれるドレイの文学とみえていたのではないか」と書く。さらに、日本には「あらゆる抵抗の契機を利用した魯迅のような『人民の文学者』はいない」と断言する。
そうしたなか、1948年11月に、竹内は代表的論文のひとつとなった「中国の近代と日本の近代──魯迅を手がかりとして」を発表する。
近代におけるヨーロッパの「自己解放」は、東洋への侵入をともなった。これにたいし、東洋は抵抗を通じて自己を解放した。抵抗の結果は、しばしば敗北をともなった。しかし、敗北を自覚するところから、運動がはじまり、歴史がつくられるのだ。
そのような歴史観を示したあと、竹内は日本の近代においては、魯迅の抵抗にみられるような抵抗がほとんど見られないと指摘する。原理は都合よく次々と塗り替えられ、それが進歩のように思われる。日本文化は優等生文化だ。
竹内はいう。
〈日本は、近代への転回点において、ヨオロッパにたいして決定的な劣勢意識をもった。(それは日本文化の優秀さがそうさせたのだ。)それから猛然としてヨオロッパを追いかけはじめた。自分がヨオロッパになること、よりよくヨオロッパになることが脱却の道であると観念された。つまり自分がドレイの主人になることでドレイから脱却しようとした。あらゆる解放の幻想がその運動の方向からうまれている。そして今日では、解放運動そのものがドレイ的性格を脱しきれぬほどドレイ根性がしみついてしまった。〉
日本文化が優秀なのは、主体性が欠如しているからであり、つまり抵抗を放棄しているからだ、と竹内はいう。「日本文化は……外からくるものを苦痛として、抵抗において受け取ったことは一度もないのではないか」
ここで、竹内が見据えているのは、日本の真の独立である。それは政治的な独立にとどまらず、むしろ精神的な独立といってよいだろう。
1949年10月1日、中華人民共和国が成立した。
1950年1月、コミンフォルムは日本共産党の平和革命路線を批判した。これにより、日本共産党はその批判を受けいれない「所感派」と、批判を受けいれる「国際派」に分かれ、連合国軍によるレッドパージののち、武装革命路線をとるようになった。そして、その後、ふたたび平和路線に戻った。
竹内はコミンテルンの批判に右往左往する日本共産党がコミンテルンのドレイにほかならず、日本の革命についてまともに考えていない、と厳しい評価を下している。そして、そのころから、竹内の思考は中国革命と毛沢東に向かうことになる。
竹内は「毛沢東の魯迅への傾倒の深さは、なみなみならぬもの」と述べている。さらに「中共[中国共産党]がどんなに高いモラルに支えられているか」を強調する。
さらに1951年4月の「評伝毛沢東」では、毛沢東が党内で孤立し、井岡山にこもるなかで、みずからの思想を築いていったことに大きな意義を見いだしていた。
〈毛沢東思想はこの期に形成された。かれの内外生活の一切が無に帰したとき、かれが失うべきものを持たなくなったとき、可能的に一切がかれの所有となったとき、その原型が作られたのである。これまで他在的であった知識、経験の一切が、遠心的から急進的に向きを変えて、かれの一身に凝結したのだ。それによって、党の一部であったかれが、党そのものとなり、党は、中国革命の一部でなくて全部になった。世界は形を変えた。つまり、毛沢東は形を変えたのである。〉
竹内は毛沢東をきわめて文学的にとらえている。渡邊は「こうして中華人民共和国成立の1949年以後、中国共産党そのものである毛沢東が、すでに13年まえに没した魯迅にかわって竹内好の同時代の指標となっていくのだ」と論じている。
このころ、竹内は日本の代表的な評論家として、一目置かれるようになっていた。1952年には国民文学を提唱し、さまざまな論議を巻き起こした。それはとりわけフランスを金科玉条にする文学への批判であり、民族の伝統に根ざす文学の提唱にほかならなかった。だが、論議は次第に拡散し、そのうち雲散霧消してしまうことになる。
1954年5月から1年間、竹内は『思想の科学』の編集長を務めた。前田愛によれば、竹内は「日本人全体の思想をそだてる運動のための共通の広場」をつくろうとしていたのだという。
そのころ武田泰淳は、注目すべき小説を刊行している。1952年10月に講談社から出版される『風媒花』である。
描かれたのは講和条約直後の1951年秋の3日間。架空の「中国文化研究会」をめぐるドラマになっている。
登場するのはエロ作家の峯、そして思想家の軍地、そして会のさまざまなメンバー。峯は蜜枝という女性と同棲している。さらに美貌の三田村青年、右翼の怪物、細谷源之助などもからんで、小説は立体的、ドラマチックに構成される。
峯は武田泰淳本人、蜜枝は武田百合子、軍地は竹内好、細谷は北一輝がモデルになっている。ほかにもモデルはいるはずだが、ぼくなどにはわからない。中国文化研究会は「中国文学研究会」のことだといって、まちがいないだろう。そして、登場人物はたぶんに戯画化されている。
物語は峯(武田)が銀座で開かれた中国文化研究会に久方ぶりに出席するところからはじまる。中国文化研究会は、戦前、「支那」に代わって「中国」という表記をはじめて採用し、中国とのあいだに「新しい橋」を架けようとした。そして、その思いは共産中国が成立したあともつづいているというのが、会の説明だ。
この会を引っぱっているのが、峯の15年来の友人である軍地(竹内)だった。久しぶりに会合に出てきた峯を軍地が茶化す。そんな軽妙なやりとりがあって、会を支えているのが、軍地の熱烈な使命感であることが示される。
日中戦争を忘れて、中国を論ずることはできなかった。会に参加するほとんど全員が、この戦争に参加していた。「何万何千万の中国民衆の家庭を焼き払い、その親兄弟を殺戮したあの戦争」が、いまもつづく会の出発点となっている。
峯は潔癖な軍地を尊敬している。ただ自分と同じ「文学病患者」であることに悲劇性を感じている。「本当の物凄い政治家」が、自分たちを支配しようとして待ち構えていて、「そいつの出現到来を軍地は希望しつつ、また一方ではそれに抵抗し反抗しなきゃならない」引き裂かれた状態に、いつか軍地がおちいるのではないか、と峯は危惧する。
それが毛沢東だと武田泰淳が示しているわけではないが、作家の勘はさすがに鋭い。
会合の途中で峯は席を立つ。電報で親戚(亡き妹のつれあいで、支那哲学者)の危篤を知らされていたためだ。病院に行くと、見舞客のなかに、かつて満洲国を「王道楽土」と唱え、軍の大学に勤めていた男と、老漢学者がいた。かれらは口々に「支那一点ばり」の軍地を批判し、「支那をネタにして、日本を罵倒したってはじまらんですからな」と憎悪に満ちた声をあげるのだった。
いっぽう銀座での会合を終えたあと、軍地をはじめとする3人のメンバーは、有楽町のガード下の焼酎ホールで飲んでいた。そこに現れたのが、中国人を母とする美貌の三田村青年で、はっきりいって純粋行動のテロリストである(いかにも武田泰淳好みの人物)。かれは、日本人を糾弾するため、テロに走ろうと考えている。三田村は軍地に「あなたと僕は同類なんですからね」と言い放ち、いっしょに大磯に行こうと誘った。
その夜、軍地と三田村は、大磯で右翼の怪物、細谷源之助と会う。細谷は戦前、上海、南京、武昌での中国青年の武装蜂起に参加していた。そして日本改革のために、青年将校による武装クーデターをくわだてた。西洋を排撃するアジア革命はこの老人の夢だったといってよい。二・二六事件で刑死した北一輝がモデルである。
翌日、軍地と三田村青年は、霧雨の降る海岸を歩いている。三田村青年の頭にあるのは、細谷老人の唱える「殺、殺、殺」の呪文だ。三田村は軍地に向かって、「真に中国を信じ愛しているとしたら、新中国の文化を研究しているだけじゃ、不充分なはずですがね」といい、いまふたつの計画が進行しているという情報を軍地に明かす。
ひとつは、旧日本陸軍の将校が、中国軍閥の親分と手を握って、反共義勇軍を編成するため、台湾に兵員と武器を集めようとしており、そのための密航船が一両日中に、九州から台湾に向けて出航しようとしているという情報。もうひとつは、これとは逆の動きで、ある美少年が朝鮮戦争で米軍に協力する都内のPD(特需)工場にたいし、食堂のやかんに毒薬を投げ込み、東京じゅうのPD工場を恐怖におとしいれようとしているという情報。
軍地はその美少年が三田村のことだと気づき、「君はやっぱり少し、自分という者を、特別の者に見立てたがっているんじゃないかな」と話し、すでに実行に移ったというその計画を批判する。
この日の昼、作家の峯は、同棲する蜜枝の弟でマルクス青年、守の愛人、細谷桃代に頼まれて、彼女のつとめるPD工場を見学してから、彼女のサークルで話をすることになっていた。ところが、工場の食堂の土瓶に青酸カリが入れられているのがわかって、工場見学は中止となり、峯はそのままサークルで話をする羽目になる。
峯は思わず、こう話しはじめた。
〈実に無数の人間が人間によって殺されている。愛国的殺人であろうと売国的殺人であろうと、殺人行為にかわりはない。自ら手を下さなかった人々といえども、何らかの形で殺人にかかわりのない者はいない。我々日本人のほとんど全部、否世界の人間のほとんど全部が殺人に参加したと言ってもいい。殺されながら殺し、殺しながら殺す。無数の媒介物によって、知らず知らずのうちに、どこかで誰もが人殺しに関係している。しかも現代の一番おそろしい点は、殺人者が時がたてば自分の犯した行為を忘れられるばかりでなく、時によっては、自分が人殺しであることを知らないですむ点にあります。〉
現代では、だれもが殺人者だという武田泰淳の哲学が開陳されている。
物語はさらにつづく。その夜の新宿での蜜枝の痛快な大冒険。三田村の隠匿兵器略奪事件とそれを阻止した少女の話。北京政府とつながりがあるのではないかと中国文化研究会に探りをいれはじめた公安の動き。話はますます混沌としてくる。
そして、だれもが、それぞれの思いを秘めたまま、小説はとつぜん幕を閉じることになる。
渡邊一民はこう述べている。
〈いってみれば『風媒花』は、中国にかかわる1951年以後の日本におけるさまざまなドラマの「序曲」として書かれたと言えるかもしれない。そしてそのためこの作中には、武田泰淳の経験のすべて、あえていえば中国文学研究会同人のすべてが傾注されている〉
『風媒花』は、中国をめぐる未完成の曼荼羅図だったといえるかもしれない。そうした中国への熱い思いは、すでに失われて久しくなっている。



