全国統一への道──網野善彦『日本社会の歴史』を読む(11) [歴史]
16世紀後半、関東では北条氏が北上をこころみ、越後から南下する上杉謙信と激しく競り合っていた。信濃を手にいれた武田信玄は四方に進出する構えをみせ、上杉謙信と川中島で戦いをくり返していた。駿河の今川義元は京をめざして西進を開始した。尾張統一をなしとげた織田信長は1560年に、西進する今川義元を桶狭間で討ち取る。今川家が衰えたあと、徳川家康は三河で自立し、信長と同盟関係を結んだ。
京都では1565年に細川家の家臣三好義継と、三好家の家臣松永久秀が将軍義輝を殺害した。1567年、信長は美濃の斎藤龍興を滅ぼし、本拠地を岐阜に移し、日本統一に向けて野心を燃やした。
信長は将軍として義輝の弟、義昭を擁立し、正親町(おおぎまち)天皇の綸旨を得て上洛する。その途中、近江の六角氏を破り、入京すると摂津、河内を押さえ、さらに北伊勢をも支配した。信長は関所を撤廃し、堺、草津、大津を直轄地とし、本願寺の寺内町にたいしても賦課を求めた。
石山本願寺と一向宗門徒はこうした信長の急速な勢力拡大に懸念をいだいた。越前の朝倉氏、北近江の浅井氏も同じだった。
そのころ、中国地方では、石見銀山を押さえた毛利氏が備中、伯耆まで領土を拡大していた。四国では長宗我部氏が他を圧するようになっていた。
九州には、大村純忠、有馬晴信、大友宗麟のキリシタン大名が生まれていた。イエズス会は、かれらから長崎と茂木を寄進され、畿内にも進出していた。1569年にルイス・フロイスは信長と会い、布教を認められている。
京都では信長と将軍義昭の関係が次第に険悪になる。周囲の勢力に取り囲まれた信長は、1570年にいったん岐阜に戻った。だが、翌年、反撃に転じ、朝倉・浅井と手を組んだ比叡山を焼き討ちした。
そのころ、武田信玄は義昭の要請を受けて、上京しようとしていた。ところが、三方原で徳川家康を打ち破ったあと、1573年に陣中で病没した。信長は義昭を京都から追放、室町幕府は滅んだ。さらに信長は北上して、浅井・朝倉を滅ぼし、北陸を制覇した。
危機感を抱いた本願寺は、信長に抵抗する。これにたいし、信長は1574年に伊勢の長島、翌年は越前で、大虐殺をおこなって一向一揆勢を鎮圧した。そのあと、武田勝頼の軍を長篠で撃破している。
1576年からは石山本願寺への攻撃をはじめた。しかし、信長軍は本願寺に味方した毛利の村上水軍に敗北、いったん和睦が結ばれた。
この年、上杉謙信が急死する。東と北の脅威から逃れた信長は、羽柴秀吉に毛利攻めを命じた。
1580年、信長は石山本願寺を包囲、顕如、教如は本願寺から退去し、本願寺は陥落した。同じころ、柴田勝家が加賀の一向一揆を鎮圧した。そのころ、琵琶湖畔の安土に、信長のつくった大天守閣が姿をあらわした。

[織田信長。ウィキペディアより]
その後、信長は畿内の支配を固め、みずから天下の支配者であることを表明した。1582年には甲斐の武田氏を滅ぼしている。だが、信長は引きつづき、毛利との戦いに出陣しようとしたところ、京都の本能寺で明智光秀に討たれた。それを聞いた秀吉は、急遽軍勢を引き揚げ、山崎で光秀の軍を撃破した。
この戦勝で有利な立場を得た秀吉は、1583年にライバルの柴田勝家を越前北荘で滅ぼし、信長の子、信孝も自殺に追いこみ、日本の支配者となる道を突き進んだ。
秀吉は石山本願寺跡に大坂城を築いた。小牧・長久手で家康と戦うが決着がつかず、和睦を結び、1585年には西国征服に力を注いだ。まず根来・雑賀の一揆を撃破し、高野山を攻め、刀狩令を出して、百姓の武装を禁じた。紀州を征服したあとは、弟秀長に四国を攻めさせ、長宗我部氏を降伏させた。そして、みずからは越中まで進軍し、北陸を手に入れた。
秀吉は関白に就任し、天皇から豊臣の姓を与えられる。「天皇の権威の下に日本国の統治権を掌握する姿勢」が濃厚だった、と網野はいう。
1587年には天皇の名のもとに関東・奥州惣無事令(平和令)を発し、東国統治の姿勢を表明した。そのころから西国諸国にたいする検地がはじまっている。秀吉は流通・貿易を管理し、金銀をみずからのもとに集めていた。
秀吉はみずからの影響力の大きさを見せつけて、家康を帰服させたうえで、家康に惣無事令の実施をまかせた。家康の強さはわかっているので、敵対することはない。そのうえで、秀吉は毛利を丸め込んで、毛利勢とともに九州に攻め入り、抵抗する島津氏を降伏に追いこんだ。こうして、九州を含む西国が支配下にはいる。
九州で秀吉は日本は神国だと宣言し、キリスト教宣教師の追放を命じた。教会領を否定し、ポルトガル人が日本人を奴隷にすることを禁じた。ポルトガルとの貿易自体は禁じていない。1588年には海賊停止(ちょうじ)令を発している。こうした措置は、宗教勢力による騒擾を防ぐとともに、貿易を国の管理下におくことが目的だった、と網野はいう。再度の刀狩令も秀吉の治安意識の強さを物語っている。
1588年、秀吉はみずからの邸宅、聚楽第(じゅらくだい)に後陽成天皇を迎え、天皇の権威を利用して、西国大名たちからあらためて臣従の誓詞をとった。西国の支配を完成させた秀吉は、翌年、家康にゆだねていた東国の平定に乗りだす。
まず、奥羽で戦争をおこした伊達政宗を惣無事令違反だとして追及し、これを服属させた。1590年には、秀吉、家康に対抗していた北条氏を討つため、大軍を率いて関東にはいり、これを滅ぼし、関東に家康を移封した。そのあと、秀吉は陸奥にはいり、東北の大名を服属させ、1591年から東国の検地を強行した。こうして、秀吉は全国を統一する。本能寺で信長が死んでからわずか9年である。その勢いはだれにも止められなかった。
検地はあらためて全国でおこなわれ、これにより石高制にもとづく軍役体制が確立した。
さらに、秀吉は人掃令(ひとばらいれい)を発令する。これにより、武士と町人、百姓の身分がはっきりとわけられた。百姓は自由な移動や商工業への従事を禁じられた(だが、それはあくまでもタテマエだった、と網野はいう)。とはいえ、この身分法令によって、「国民」が把捉されると同時に、身分によって区分けされたことはまちがいない。

[豊臣秀吉。ウィキペディアより]
1591年に秀吉は太閤となり、統治権を甥の秀次に譲った。子の鶴松が死んだために、豊臣家の継承を考慮せざるを得なかった。だが、秀吉は落ちこむことなく、むしろさらなる野望に駆られる。中国征服計画が渦巻き、朝鮮出兵を決意するのだ。
1592年、文禄の役(壬辰の倭乱)がはじまる。日本軍は漢城(ソウル)を占拠し、さらに北部まで侵攻した。だが、やがて李舜臣らの水軍によって後方を攪乱されるようになり、さらに明の救援軍も南下して、戦線は膠着状態となった。明との講和が模索されるようになった。
1593年、秀吉にあらたな子、秀頼が生まれる。秀頼が育つのをみて、1595年に秀次は自殺に追いこまれた。秀吉は伏見城を建設し、秀頼を中心とした次代の体制を構想しはじめる。
明との和平交渉は進展しない。1596年に明の使者が来日するが、その国書をみた秀吉は激怒し、ふたたび朝鮮出兵を命じた。こうして慶長の役(丁酉の倭乱)がはじまる。しかし、今回も日本軍は決定的な勝利を得られない。残虐な行為ばかりが際立つ戦争になった。そのさいちゅうの1598年、秀吉は醍醐寺で花見を開いたあと病気になって、8月に死ぬ。朝鮮に派遣された軍は撤退した。
秀吉は家康を筆頭とする五大老と石田三成などの五奉行に、子の秀頼に臣従するよう遺言を残していた。しかし、1599年には早くも家康と三成のあいだの対立が表面化し、両者は1600年に関ヶ原で激突した。戦いは東軍の家康方の勝利に終わり、天下は東国の王者、家康のものとなった。
秀頼はなお大坂城にあり、東西の対立はつづいていた。1603年に家康は征夷大将軍となり、新たな幕府となった江戸の普請を諸大名に課した。
1605年に家康は将軍職を子の秀忠に譲り、みずからは駿府に移って、大御所となった。秀忠には東国大名を統轄させ、みずからは西国大名を監督した。そして、家康は新たに西国の検地をおこない、家数人別帳をつくらせた。

[徳川家康。ウィキペディアより]
将軍職は譲ったものの、家康のもとには金地院崇伝、天海、林羅山、茶屋四郎次郎、ウィリアム・アダムズ、ヤン・ヨーステンなどが政治顧問として集結し、大きな政治方針の決定に参与していた。
1609年に家康は松前氏による蝦夷支配を認め、島津氏の琉球出兵を承認している。また対馬の宗氏を通じて朝鮮との国交を回復している。ポルトガル、イスパニア、オランダ、イギリスとの貿易も認めていた。
1611年には後陽成が退位し、後水尾が即位した。それを機に家康は上京し、秀頼とも面会した。そのいっぽうで西国大名に徳川家への臣従を誓わせ、豊臣家を孤立に追いこむことも忘れなかった。
1613年、キリスト教勢力が豊臣家と結びつくことを警戒した家康はバテレン追放令を出し、宣教師たちを長崎からマニラに送り返した。そのうえで、方広寺の鐘の銘文に言いがかりをつけ、1614年に豊臣の大坂城を攻めた(大坂冬の陣)。翌1615年の大坂夏の陣により、豊臣氏は滅亡する。
その後、家康は一国一城令を発し、武家諸法度を定め、禁中並公家諸法度を発し、幕府を中心とする国制を強化した。
1616年に家康が死ぬと、秀忠が一元的に統治権を握った。秀忠はキリスト教を禁圧する姿勢を強め、1622年に55人のキリスト教徒を処刑した。
1623年、秀忠は家光に将軍職を譲り、みずからも大御所となった。紫衣事件では後水尾天皇を激怒させている。後水尾は抗議の意志を示すため、娘の明正に位を譲った。
秀忠はキリスト教弾圧はさらに激しいものとなった。イギリス平戸商館の閉鎖につづき、イスパニアとの通商を拒絶し、1628年にはポルトガル・オランダとの貿易も一時途絶している。海外では朱印船が拿捕される事件も多く発生した。ポルトガル、オランダとの貿易はまもなく再開されたが、幕府は次第にポルトガル船を排除するようになる。朱印船も制限されるようになった。
1632年、秀忠が死に、家光が全権を掌握した。家光は代替わりを機に、多くの大名を改易・転封し、大名への統制強化をはかった。老中や年寄、町奉行などの職務を充実させ、軍役令を定め、新たな武家諸法度で大名や旗本の身分を定め、参勤交代を制度化したのも家光の時代である。
こうして、「幕府、諸大名が一体となった公儀として、町人、百姓を支配する武家統一国家がここに確立した」と網野はいう。
1633年から35年にかけ、日本人の海外渡航禁止、外国船貿易の統制、キリスト教の禁止、その他を定めた禁制が出された。1936年にはポルトガル人が長崎の出島に閉じこめられた。
1637年、島原や天草のキリスト教徒が叛乱をおこした。島原の乱である。乱は簡単には平定されない。翌年になって、幕府はオランダ軍艦の砲撃を借りて、12万の軍勢でようやく乱を鎮圧する。これを機にキリスト教徒への弾圧はさらに強まり、1639年にはポルトガル人が追放され、41年には平戸のオランダ商館が長崎の出島に移された。これにより、日本はいわゆる鎖国体制にはいった。
しかし、日本は海外にたいする窓口を完全に閉じたわけではなかった。北方ではアイヌが山丹交易に携わっていたし、琉球は中国大陸との貿易を確保していた。そして、アイヌは松前氏と、琉球は島津氏とつながりをもっていた。対馬もまた朝鮮半島の窓口になっていた。さらに長崎はオランダを通じて欧米とつながっていただけではなく、中国大陸との通商窓口でもあった。
江戸幕府の特徴は東国的色彩が強かったことだ、と網野は書いている。日光の東照宮が徳川の権威の象徴として位置づけられるようになった。
1636年、幕府は宋銭、明銭、その他模造銭の流通を禁止し、独自の通貨、寛永通宝を発行するようになった。貨幣については、まだ東国の金、西国の銀という地域差が残っていたものの、それでも幕府は通貨の統一に努めた。この時代、鉱山からの採掘はきわめて活発だった。
海禁によって、列島外の地域との交流は大きな制約を受けた。それでも列島内では商業はにぎわい、物資の輸送や労働力の移動も活発だった。平和の到来にともない、信用経済も安定度を増した。いっぽう仏教勢力の退潮とともに世俗化が進み、商工業や都市は大きく発展した。
とはいえ、江戸時代の主流は農本主義にちがいなかった。江戸時代の村の数は6万3000ほどだった。三都と呼ばれる江戸、大坂、京都は特別として、各藩には城下町や門前町、港町などがあったが、行政的には町の数は限られ、圧倒的に村が多い。
しかし、村では農業だけがおこなわれていたわけではない。「海村では漁撈・製塩や廻船、山村では木材・木器・薪・炭の生産、平地村でも女性の携わった桑による養蚕や、木綿・菜種の栽培、絹・綿織物の生産が広く行われて」いた、と網野は記している。商人や職人、廻船人、芸能民もいた。
村では庄屋や名主、肝煎などと呼ばれる有力百姓が年貢を請け負っていた。百姓の識字率は高く、少なくとも3割か4割はあったと考えられている。
都市では大衆的な文化が花開いた。とはいえ、武士による締めつけも無視できない。遊女たちや被差別民は一定の場所に集住させられ、差別されるようになった。時代が進むと、若衆狂いや博打、かぶき者などもあらわれる。
17世紀前半には大規模な治水や水田開発がおこなわれた。綿作や菜種栽培、養蚕も盛んになってくる。こうして経済は資本主義に向かって新しい段階にはいっていった、と網野は論じている。
縄文時代から17世紀までを扱う本書『日本社会の歴史』は、これでいちおう幕を閉じる。しかし、さすがに中途半端と感じたのだろうか、最後に網野は17世紀後半から20世紀後半までの歴史を展望する章を設けている。今回はそれも紹介するつもりでいたが、くたびれてしまった。次回をもって最終回とする。
京都では1565年に細川家の家臣三好義継と、三好家の家臣松永久秀が将軍義輝を殺害した。1567年、信長は美濃の斎藤龍興を滅ぼし、本拠地を岐阜に移し、日本統一に向けて野心を燃やした。
信長は将軍として義輝の弟、義昭を擁立し、正親町(おおぎまち)天皇の綸旨を得て上洛する。その途中、近江の六角氏を破り、入京すると摂津、河内を押さえ、さらに北伊勢をも支配した。信長は関所を撤廃し、堺、草津、大津を直轄地とし、本願寺の寺内町にたいしても賦課を求めた。
石山本願寺と一向宗門徒はこうした信長の急速な勢力拡大に懸念をいだいた。越前の朝倉氏、北近江の浅井氏も同じだった。
そのころ、中国地方では、石見銀山を押さえた毛利氏が備中、伯耆まで領土を拡大していた。四国では長宗我部氏が他を圧するようになっていた。
九州には、大村純忠、有馬晴信、大友宗麟のキリシタン大名が生まれていた。イエズス会は、かれらから長崎と茂木を寄進され、畿内にも進出していた。1569年にルイス・フロイスは信長と会い、布教を認められている。
京都では信長と将軍義昭の関係が次第に険悪になる。周囲の勢力に取り囲まれた信長は、1570年にいったん岐阜に戻った。だが、翌年、反撃に転じ、朝倉・浅井と手を組んだ比叡山を焼き討ちした。
そのころ、武田信玄は義昭の要請を受けて、上京しようとしていた。ところが、三方原で徳川家康を打ち破ったあと、1573年に陣中で病没した。信長は義昭を京都から追放、室町幕府は滅んだ。さらに信長は北上して、浅井・朝倉を滅ぼし、北陸を制覇した。
危機感を抱いた本願寺は、信長に抵抗する。これにたいし、信長は1574年に伊勢の長島、翌年は越前で、大虐殺をおこなって一向一揆勢を鎮圧した。そのあと、武田勝頼の軍を長篠で撃破している。
1576年からは石山本願寺への攻撃をはじめた。しかし、信長軍は本願寺に味方した毛利の村上水軍に敗北、いったん和睦が結ばれた。
この年、上杉謙信が急死する。東と北の脅威から逃れた信長は、羽柴秀吉に毛利攻めを命じた。
1580年、信長は石山本願寺を包囲、顕如、教如は本願寺から退去し、本願寺は陥落した。同じころ、柴田勝家が加賀の一向一揆を鎮圧した。そのころ、琵琶湖畔の安土に、信長のつくった大天守閣が姿をあらわした。

[織田信長。ウィキペディアより]
その後、信長は畿内の支配を固め、みずから天下の支配者であることを表明した。1582年には甲斐の武田氏を滅ぼしている。だが、信長は引きつづき、毛利との戦いに出陣しようとしたところ、京都の本能寺で明智光秀に討たれた。それを聞いた秀吉は、急遽軍勢を引き揚げ、山崎で光秀の軍を撃破した。
この戦勝で有利な立場を得た秀吉は、1583年にライバルの柴田勝家を越前北荘で滅ぼし、信長の子、信孝も自殺に追いこみ、日本の支配者となる道を突き進んだ。
秀吉は石山本願寺跡に大坂城を築いた。小牧・長久手で家康と戦うが決着がつかず、和睦を結び、1585年には西国征服に力を注いだ。まず根来・雑賀の一揆を撃破し、高野山を攻め、刀狩令を出して、百姓の武装を禁じた。紀州を征服したあとは、弟秀長に四国を攻めさせ、長宗我部氏を降伏させた。そして、みずからは越中まで進軍し、北陸を手に入れた。
秀吉は関白に就任し、天皇から豊臣の姓を与えられる。「天皇の権威の下に日本国の統治権を掌握する姿勢」が濃厚だった、と網野はいう。
1587年には天皇の名のもとに関東・奥州惣無事令(平和令)を発し、東国統治の姿勢を表明した。そのころから西国諸国にたいする検地がはじまっている。秀吉は流通・貿易を管理し、金銀をみずからのもとに集めていた。
秀吉はみずからの影響力の大きさを見せつけて、家康を帰服させたうえで、家康に惣無事令の実施をまかせた。家康の強さはわかっているので、敵対することはない。そのうえで、秀吉は毛利を丸め込んで、毛利勢とともに九州に攻め入り、抵抗する島津氏を降伏に追いこんだ。こうして、九州を含む西国が支配下にはいる。
九州で秀吉は日本は神国だと宣言し、キリスト教宣教師の追放を命じた。教会領を否定し、ポルトガル人が日本人を奴隷にすることを禁じた。ポルトガルとの貿易自体は禁じていない。1588年には海賊停止(ちょうじ)令を発している。こうした措置は、宗教勢力による騒擾を防ぐとともに、貿易を国の管理下におくことが目的だった、と網野はいう。再度の刀狩令も秀吉の治安意識の強さを物語っている。
1588年、秀吉はみずからの邸宅、聚楽第(じゅらくだい)に後陽成天皇を迎え、天皇の権威を利用して、西国大名たちからあらためて臣従の誓詞をとった。西国の支配を完成させた秀吉は、翌年、家康にゆだねていた東国の平定に乗りだす。
まず、奥羽で戦争をおこした伊達政宗を惣無事令違反だとして追及し、これを服属させた。1590年には、秀吉、家康に対抗していた北条氏を討つため、大軍を率いて関東にはいり、これを滅ぼし、関東に家康を移封した。そのあと、秀吉は陸奥にはいり、東北の大名を服属させ、1591年から東国の検地を強行した。こうして、秀吉は全国を統一する。本能寺で信長が死んでからわずか9年である。その勢いはだれにも止められなかった。
検地はあらためて全国でおこなわれ、これにより石高制にもとづく軍役体制が確立した。
さらに、秀吉は人掃令(ひとばらいれい)を発令する。これにより、武士と町人、百姓の身分がはっきりとわけられた。百姓は自由な移動や商工業への従事を禁じられた(だが、それはあくまでもタテマエだった、と網野はいう)。とはいえ、この身分法令によって、「国民」が把捉されると同時に、身分によって区分けされたことはまちがいない。

[豊臣秀吉。ウィキペディアより]
1591年に秀吉は太閤となり、統治権を甥の秀次に譲った。子の鶴松が死んだために、豊臣家の継承を考慮せざるを得なかった。だが、秀吉は落ちこむことなく、むしろさらなる野望に駆られる。中国征服計画が渦巻き、朝鮮出兵を決意するのだ。
1592年、文禄の役(壬辰の倭乱)がはじまる。日本軍は漢城(ソウル)を占拠し、さらに北部まで侵攻した。だが、やがて李舜臣らの水軍によって後方を攪乱されるようになり、さらに明の救援軍も南下して、戦線は膠着状態となった。明との講和が模索されるようになった。
1593年、秀吉にあらたな子、秀頼が生まれる。秀頼が育つのをみて、1595年に秀次は自殺に追いこまれた。秀吉は伏見城を建設し、秀頼を中心とした次代の体制を構想しはじめる。
明との和平交渉は進展しない。1596年に明の使者が来日するが、その国書をみた秀吉は激怒し、ふたたび朝鮮出兵を命じた。こうして慶長の役(丁酉の倭乱)がはじまる。しかし、今回も日本軍は決定的な勝利を得られない。残虐な行為ばかりが際立つ戦争になった。そのさいちゅうの1598年、秀吉は醍醐寺で花見を開いたあと病気になって、8月に死ぬ。朝鮮に派遣された軍は撤退した。
秀吉は家康を筆頭とする五大老と石田三成などの五奉行に、子の秀頼に臣従するよう遺言を残していた。しかし、1599年には早くも家康と三成のあいだの対立が表面化し、両者は1600年に関ヶ原で激突した。戦いは東軍の家康方の勝利に終わり、天下は東国の王者、家康のものとなった。
秀頼はなお大坂城にあり、東西の対立はつづいていた。1603年に家康は征夷大将軍となり、新たな幕府となった江戸の普請を諸大名に課した。
1605年に家康は将軍職を子の秀忠に譲り、みずからは駿府に移って、大御所となった。秀忠には東国大名を統轄させ、みずからは西国大名を監督した。そして、家康は新たに西国の検地をおこない、家数人別帳をつくらせた。
[徳川家康。ウィキペディアより]
将軍職は譲ったものの、家康のもとには金地院崇伝、天海、林羅山、茶屋四郎次郎、ウィリアム・アダムズ、ヤン・ヨーステンなどが政治顧問として集結し、大きな政治方針の決定に参与していた。
1609年に家康は松前氏による蝦夷支配を認め、島津氏の琉球出兵を承認している。また対馬の宗氏を通じて朝鮮との国交を回復している。ポルトガル、イスパニア、オランダ、イギリスとの貿易も認めていた。
1611年には後陽成が退位し、後水尾が即位した。それを機に家康は上京し、秀頼とも面会した。そのいっぽうで西国大名に徳川家への臣従を誓わせ、豊臣家を孤立に追いこむことも忘れなかった。
1613年、キリスト教勢力が豊臣家と結びつくことを警戒した家康はバテレン追放令を出し、宣教師たちを長崎からマニラに送り返した。そのうえで、方広寺の鐘の銘文に言いがかりをつけ、1614年に豊臣の大坂城を攻めた(大坂冬の陣)。翌1615年の大坂夏の陣により、豊臣氏は滅亡する。
その後、家康は一国一城令を発し、武家諸法度を定め、禁中並公家諸法度を発し、幕府を中心とする国制を強化した。
1616年に家康が死ぬと、秀忠が一元的に統治権を握った。秀忠はキリスト教を禁圧する姿勢を強め、1622年に55人のキリスト教徒を処刑した。
1623年、秀忠は家光に将軍職を譲り、みずからも大御所となった。紫衣事件では後水尾天皇を激怒させている。後水尾は抗議の意志を示すため、娘の明正に位を譲った。
秀忠はキリスト教弾圧はさらに激しいものとなった。イギリス平戸商館の閉鎖につづき、イスパニアとの通商を拒絶し、1628年にはポルトガル・オランダとの貿易も一時途絶している。海外では朱印船が拿捕される事件も多く発生した。ポルトガル、オランダとの貿易はまもなく再開されたが、幕府は次第にポルトガル船を排除するようになる。朱印船も制限されるようになった。
1632年、秀忠が死に、家光が全権を掌握した。家光は代替わりを機に、多くの大名を改易・転封し、大名への統制強化をはかった。老中や年寄、町奉行などの職務を充実させ、軍役令を定め、新たな武家諸法度で大名や旗本の身分を定め、参勤交代を制度化したのも家光の時代である。
こうして、「幕府、諸大名が一体となった公儀として、町人、百姓を支配する武家統一国家がここに確立した」と網野はいう。
1633年から35年にかけ、日本人の海外渡航禁止、外国船貿易の統制、キリスト教の禁止、その他を定めた禁制が出された。1936年にはポルトガル人が長崎の出島に閉じこめられた。
1637年、島原や天草のキリスト教徒が叛乱をおこした。島原の乱である。乱は簡単には平定されない。翌年になって、幕府はオランダ軍艦の砲撃を借りて、12万の軍勢でようやく乱を鎮圧する。これを機にキリスト教徒への弾圧はさらに強まり、1639年にはポルトガル人が追放され、41年には平戸のオランダ商館が長崎の出島に移された。これにより、日本はいわゆる鎖国体制にはいった。
しかし、日本は海外にたいする窓口を完全に閉じたわけではなかった。北方ではアイヌが山丹交易に携わっていたし、琉球は中国大陸との貿易を確保していた。そして、アイヌは松前氏と、琉球は島津氏とつながりをもっていた。対馬もまた朝鮮半島の窓口になっていた。さらに長崎はオランダを通じて欧米とつながっていただけではなく、中国大陸との通商窓口でもあった。
江戸幕府の特徴は東国的色彩が強かったことだ、と網野は書いている。日光の東照宮が徳川の権威の象徴として位置づけられるようになった。
1636年、幕府は宋銭、明銭、その他模造銭の流通を禁止し、独自の通貨、寛永通宝を発行するようになった。貨幣については、まだ東国の金、西国の銀という地域差が残っていたものの、それでも幕府は通貨の統一に努めた。この時代、鉱山からの採掘はきわめて活発だった。
海禁によって、列島外の地域との交流は大きな制約を受けた。それでも列島内では商業はにぎわい、物資の輸送や労働力の移動も活発だった。平和の到来にともない、信用経済も安定度を増した。いっぽう仏教勢力の退潮とともに世俗化が進み、商工業や都市は大きく発展した。
とはいえ、江戸時代の主流は農本主義にちがいなかった。江戸時代の村の数は6万3000ほどだった。三都と呼ばれる江戸、大坂、京都は特別として、各藩には城下町や門前町、港町などがあったが、行政的には町の数は限られ、圧倒的に村が多い。
しかし、村では農業だけがおこなわれていたわけではない。「海村では漁撈・製塩や廻船、山村では木材・木器・薪・炭の生産、平地村でも女性の携わった桑による養蚕や、木綿・菜種の栽培、絹・綿織物の生産が広く行われて」いた、と網野は記している。商人や職人、廻船人、芸能民もいた。
村では庄屋や名主、肝煎などと呼ばれる有力百姓が年貢を請け負っていた。百姓の識字率は高く、少なくとも3割か4割はあったと考えられている。
都市では大衆的な文化が花開いた。とはいえ、武士による締めつけも無視できない。遊女たちや被差別民は一定の場所に集住させられ、差別されるようになった。時代が進むと、若衆狂いや博打、かぶき者などもあらわれる。
17世紀前半には大規模な治水や水田開発がおこなわれた。綿作や菜種栽培、養蚕も盛んになってくる。こうして経済は資本主義に向かって新しい段階にはいっていった、と網野は論じている。
縄文時代から17世紀までを扱う本書『日本社会の歴史』は、これでいちおう幕を閉じる。しかし、さすがに中途半端と感じたのだろうか、最後に網野は17世紀後半から20世紀後半までの歴史を展望する章を設けている。今回はそれも紹介するつもりでいたが、くたびれてしまった。次回をもって最終回とする。
応仁の乱から戦国時代へ──網野善彦『日本社会の歴史』を読む(10) [歴史]
室町幕府が京都の室町にいわば本社を置いていたとすれば、鎌倉府はいわば室町幕府の支社にあたる。鎌倉府の公方には、足利尊氏の子孫が任じられていた。
15世紀にはいると、室町幕府と鎌倉府のあいだに深い溝が生まれはじめたというところから、網野は筆をおこしている。
14世紀末に鎌倉府は陸奥・出羽を支配下においた。鎌倉公方の足利満兼は、弟の満直、満貞を奥羽に下した。ふたりはのちに笹川公方、稲村公方と呼ばれるようになる。陸奥や出羽の公方たちに、伊達氏が逆らい、叛乱をおこした背景には、室町公方(将軍)の支持があったといわれる。
1416年にも上杉氏憲が鎌倉公方持氏にたいし叛乱をおこした。直接の原因は、氏憲が関東管領を罷免されたことにある。だが、このときは室町将軍義持が鎌倉の持氏を支持したため、乱は鎮圧されている。
だが、この乱を収めたことにより、鎌倉の持氏は専制的な姿勢をあらわにし、東国支配を強めた。これにたいし室町方は鎌倉方を牽制する姿勢を示した。そのため、室町と鎌倉は対立を深めた。まるで二つの政府が生まれたようだった、と網野は書いている。
1423年、足利義持は嫡子の義量(よしかず)に将軍職を譲った。だが、義量は2年後に18歳で亡くなる。1428年に義持も後継者を指名しないまま世を去った。重臣たちは議論の末、やむなくくじで将軍を選ぶこととし、出家していた義円が選出された。
義円は還俗し、義教(よしのり)を名乗る。この年、天皇家も称光が亡くなり、後花園が即位していた。
そのころ畿内では土一揆(つちいっき)が巻き起こっていた。南朝の系譜をひく小倉宮が叛乱をおこし、伊勢にはいった。
将軍義教は重臣の有力守護たちを押さえ、将軍専制を確立しようとして、みずからの回りに腹心をそろえた。自分に刃向かう者にたいしては、強硬な姿勢で臨んでいる。それは鎌倉公方にたいしても同じだった。
1438年、義教は後花園天皇の綸旨を取りつけ、東国に軍を送った。鎌倉の持氏は自殺に追いこまれる。その息子たちを結城氏朝がかくまうと、義教は上杉憲実にこれを攻めさせ、結城氏もろともに殺した。これにより鎌倉府は壊滅する。
義教の政治姿勢は苛烈で、公卿、神官、僧侶、女官はじめ、多くの人びとが恐怖におちいっていた。そのひとりに播磨国守護の赤松満祐(みつすけ)がいる。1441年6月、満祐は義教を酒宴に招き、その最中に義教を斬殺した。播磨に戻った満祐は3カ月後、重臣の細川氏、山名氏に討たれた。
京都周辺では、徳政を求める土一揆が巻き起こっていた。負債をかかえて困窮した馬借や土倉、国人、地侍、惣百姓などが、寺院に籠もって幕府に抵抗した。幕府は徳政令を出さざるを得なくなる。
関東では、管領の上杉憲実が自分の蔵書を足利学校に寄進し、諸国遍歴の旅に出てしまった。不安にかられた室町幕府は、足利持氏の遺子、成氏(しげうじ)を鎌倉公方とし、1449年に鎌倉府を再建した。
だが、成氏は次第に管領の上杉氏と対立するようになる。両者は1454年に全面衝突、翌年、鎌倉は炎上した。
東国は動乱の時代にはいった。足利成氏は古河に移り、古河公方と称されるようになる。
京都では義教の死後、1442年に幼い義勝が将軍になった。だが、義勝は翌年亡くなり、弟の義政が跡を継いだ。だが、重臣どうしの争いが激しく、政治は停滞する。そこに義政の妻、日野富子が介入してくる。政府内はめちゃくちゃになり、政治どころではなくなる。
将軍家でも、義政の弟、義視(よしみ)と子の義尚(よしひさ)の主導権争いが激しくなり、それに重臣たちがからむという構図が生まれていた。なかでも、深刻さを増したのが、細川勝元と山名持豊(もちとよ)の対立だった。
1467年、細川と山名の軍は、東軍と西軍に分かれ、京都で激突、これにより京都の大半が焼失した。応仁の乱が発生したのだ。動乱は西国全体におよぶことになる。
.jpg)
[応仁の乱。ウィキペディアより]
1473年に山名持豊と細川勝元が相次いで死ぬ。1477年に畠山義就(よしひろ)が京都を撤収すると、京都の戦乱はいちおう収まった。この動乱のさいちゅう、将軍義政は東山に通称、銀閣寺と呼ばれる山荘を造営した。
そして、まもなく山城国はじめ各地に一揆がおこりはじめる。

[銀閣寺。ウィキペディアより]
全国のほかの動きもみておこう。
1442年、北奥羽の南部氏に攻撃された安藤氏は、北海道南部に移動し、松前や函館などに多くの館を築いた。1457年にはコシャマインを指導者とするアイヌと戦っている。アイヌとのあいだでは、その後、交易の縄張りについての協定がまとまった。この安藤氏にたいし、勝山館に陣取る蠣崎(かきざき)氏(のちの松前氏)が勢力を伸ばしはじめていた。
北奥羽では南部氏が大きな勢力を誇っていたが、南奥羽では会津の蘆名(あしな)氏、16世紀にはいってからは伊達氏が台頭する。
北関東では、常陸の佐竹、下野の宇都宮、小山、下総の結城、安房の里見などの豪族がそれぞれの地に根を張り、南関東の武蔵、相模、伊豆などでは16世紀に後北条氏が強大な領国を形成するようになる。後北条氏を創始したのは北条早雲であり、子の氏綱が勢力を拡大した。
後北条氏に対抗して、駿河の今川氏は遠江から三河まで勢力を伸ばした。甲斐国守護の武田氏は晴信(信玄)の時代に信濃まで領土を拡大した。越後では守護代の長尾氏が守護上杉氏のもとで力をつけてくる。そして、長尾景虎(謙信)は上杉憲政から、ついに上杉の名跡と関東管領の地位を譲られることになる。
尾張では守護代の織田氏が領国の統制に苦しんでいたが、16世紀後半になると信長が出て、領土を広げることになる。その前に、美濃では、守護代斎藤氏の家臣が守護代家を乗っ取り、やがて守護の土岐氏も倒して斎藤道三と名乗っていた。
伊勢では北畠氏、近江の湖南では六角氏、湖北では京極氏の家臣だった浅井氏が領国を形成した。
そうしたなか、一向一揆を背景に浄土真宗が勢力を拡大していた。その指導者蓮如は、1478年、山科に本願寺を建て、各地に真宗の道場寺院を開いた。そして、加賀では1488年の一揆により、加賀一国を支配下に置くことになった。大坂の石山にも本願寺が建てられ、大坂に自治都市が誕生する。
そのころ、細川氏と大内氏は、瀬戸内海と勘合貿易の主導権をめぐって争っていた。和泉の堺は、まさに両者の争いの焦点だった。
1508年、大内義興(よしおき)は堺にはいり、足利義稙(よしたね)を将軍にかついだ。
1518年に義興が帰国すると、こんどは細川高国が義稙に代わり義晴を将軍とした。義晴の弟、義維(よしつな)は堺に滞在し、三好元長らに支えられ、堺公方として、大きな力をふるった。
1523年、中国の寧波(ニンポウ)で、大内氏の勘合貿易船を細川方の船が襲うという事件が発生する。これにより、明は海禁政策を強化し、日本と中国との公的貿易は途絶した。その結果、私貿易が活発になり、明政府は倭寇に悩まされるようになる。
朝鮮半島でも大内氏は活発な貿易をくり広げていた。しかし、16世紀に入ると、朝鮮政府は貿易を統制するようになり、公貿易は衰え、私貿易が活発になってくる。多くの商人に交じって、山陰の尼子氏が貿易に割り込んでくる。
中国地方では、尼子氏と大内氏が敵対するなか、毛利氏が力を伸ばした。1551年に大内義隆が重臣の陶晴賢(すえはるかた)に殺されると大内氏は滅亡する。
これにたいし毛利元就は1555年に厳島で陶晴賢を破り、さらに尼子氏を滅ぼして、中国地方の大半を支配することになる。毛利氏は石見銀山を押さえ、大量の銀を海外に輸出することで、経済的基礎を固めた。
四国では、細川氏の家臣、三好氏に代わって、土佐の長宗我部氏が強大になってきた。
九州は大友氏と島津氏の二大勢力のもとに置かれていたが、肥前では松浦、龍造寺、大村、有馬などの勢力が活発に動いていた。
16世紀にはいると、島津氏は琉球王国に接近し、琉球貿易の独占をねらうようになる。
大友氏、松浦氏は五島列島を根拠地とする倭寇の首領、王直と交流しながら、中国大陸との交易をおこなっていた。1542年とその翌年には、この王直の乗ったポルトガル船が種子島に到着し、日本に鉄砲をもたらした。
1549年にはフランシスコ・ザビエルが鹿児島に来航し、日本にはじめてキリスト教を伝えた。ザビエルは松浦氏や大内氏、大友氏に布教を認められ、活動を開始する。まもなくガスパル・ピレラ、ルイス・フロイスなどもやってくる。大名の大村純忠はみずからキリスト教徒になり、教会領として長崎を寄進した。
九州各地ではポルトガル船との交易が盛んになった。16世紀後半にはスペインがフィリピン征服に乗り出していた。多くの日本人が東南アジアに渡航し、各地に日本人町が生まれた。
アイヌは北海道を拠点として、広く交易をおこない、チャシと呼ばれる砦(聖地)を築いていた。叙事詩『ユーカラ』がまとめられた。
琉球王国では、按司(あじ)と呼ばれる首長が丘の上にグスク(城)を築き、ウタキではノロたちが神事をおこなっていた。
日本列島でも、15世紀から16世紀にかけて、多くの城が築かれた。それは砦であると同時に、民衆が戦乱を避けて籠もる場所でもあった。
村や町は領主への年貢や公事を請け負いながら、高度な自治を築いていた。こうした自治体は惣中(そうちゅう)や老若(ろうにゃく)、公界(くがい)と呼ばれ、町や村での犯罪は「自検断」、すなわち自治体みずからの責任で裁かれていた。
無縁所と呼ばれる大寺院があらわれるのもこのころである。無縁所は世俗の領主とかかわらない寺院で、土地を持たず、金融や勧進、事業によって運営されていた。こうした寺院はしばしば避難所(アジール)や駆込寺としての役割をはたした。
堺や山崎(山城)、大湊(伊勢)、宇治山田などの多くの自治都市は「十楽之津」と呼ばれ、都市自体がアジールの性格をもっていた、と網野はいう。
海や湖では、廻船人や海運業者、商人たちが縄張りをつくって、それを管理していた。そこには独自の慣習が生まれ、そこを通るには礼銭や関銭を払わねばならないこともあった。瀬戸内海ではいくつかの島に海賊の拠点があり、かれらは海上交通の安全を保障するとともに、通過する船から礼銭や関銭を取っていた。
16世紀には、石見や佐渡、生野、院内などから採掘された銀が活発な国際貿易を支えていた。朝鮮半島から輸入されていた木綿は国内でも広く栽培されるようになった。タバコも流入し、喫煙習慣がはじまっている。中国大陸からはいった大鋸(おおが)が製材に革命をもたらした。
化粧品から食品まで、多くの商品に即して商人も分化・専業化してきた。信用経済が定着し、各地に両替屋が生まれている。「十六世紀の列島社会は、『経済社会』ともいうべき状況になってきたといってよかろう」と、網野は書いている。
経済社会の進展に対応して、戦国大名は自治的な都市の自由な市場取引を公認し、楽市を促進することで、みずからの立場を強化した。さらに戦国大名は、村を支配する国人や地侍などを取り込むことによって、地域全体の支配者としての立場を鮮明にしていった。
とはいえ、16世紀半ばになると、戦国大名の公儀化、すなわち権力集中が進んでいったこともまちがいない。「戦国大名は自らの居館、城を中心とした城下町をつくり、できるだけそこに国人たちを集住させ、公儀の一元化をはかった」と網野はいう。官僚組織が生まれ、税制や財政、軍役体制が整備されていった。
ここで、網野は東と西のちがいを強調している。
西と東では貨幣がことなっていた。中国では銀が活発に流通し、銭の役割が低下していた。それを反映して、西国でも銀が流通しはじめるようになったが、銭の信用は下落するいっぽうだった。そのため、米がふたたび貨幣としての役割を果たすようになったという。西国大名のなかでは石高制を採用する者が多くなった。
これにたいし東国では、明の永楽銭が基準通貨となっていた。また陸奥や甲斐で金が採掘され、金が貨幣として用いられはじめた。

[甲州一分金。ウィキペディアより]
こうした東西のちがいは、戦国大名の国制にも大きな違いをもたらす。西国大名が概して石高制を採用したのにたいし、東国大名は武田氏にしても伊達氏にしても貫高制を守っていた。貨幣や税制だけではない。暦や計量尺度、社会意識、政治体制も西と東では大きなちがいがあった。だが、東西のちがいを越えて、人とモノの流れは列島全域、いや列島を越えて、ますます活発になっていった。それが戦国時代の終わりをもたらすことになる。
長々と書いてきたが、次回はいよいよ最終回だ。
15世紀にはいると、室町幕府と鎌倉府のあいだに深い溝が生まれはじめたというところから、網野は筆をおこしている。
14世紀末に鎌倉府は陸奥・出羽を支配下においた。鎌倉公方の足利満兼は、弟の満直、満貞を奥羽に下した。ふたりはのちに笹川公方、稲村公方と呼ばれるようになる。陸奥や出羽の公方たちに、伊達氏が逆らい、叛乱をおこした背景には、室町公方(将軍)の支持があったといわれる。
1416年にも上杉氏憲が鎌倉公方持氏にたいし叛乱をおこした。直接の原因は、氏憲が関東管領を罷免されたことにある。だが、このときは室町将軍義持が鎌倉の持氏を支持したため、乱は鎮圧されている。
だが、この乱を収めたことにより、鎌倉の持氏は専制的な姿勢をあらわにし、東国支配を強めた。これにたいし室町方は鎌倉方を牽制する姿勢を示した。そのため、室町と鎌倉は対立を深めた。まるで二つの政府が生まれたようだった、と網野は書いている。
1423年、足利義持は嫡子の義量(よしかず)に将軍職を譲った。だが、義量は2年後に18歳で亡くなる。1428年に義持も後継者を指名しないまま世を去った。重臣たちは議論の末、やむなくくじで将軍を選ぶこととし、出家していた義円が選出された。
義円は還俗し、義教(よしのり)を名乗る。この年、天皇家も称光が亡くなり、後花園が即位していた。
そのころ畿内では土一揆(つちいっき)が巻き起こっていた。南朝の系譜をひく小倉宮が叛乱をおこし、伊勢にはいった。
将軍義教は重臣の有力守護たちを押さえ、将軍専制を確立しようとして、みずからの回りに腹心をそろえた。自分に刃向かう者にたいしては、強硬な姿勢で臨んでいる。それは鎌倉公方にたいしても同じだった。
1438年、義教は後花園天皇の綸旨を取りつけ、東国に軍を送った。鎌倉の持氏は自殺に追いこまれる。その息子たちを結城氏朝がかくまうと、義教は上杉憲実にこれを攻めさせ、結城氏もろともに殺した。これにより鎌倉府は壊滅する。
義教の政治姿勢は苛烈で、公卿、神官、僧侶、女官はじめ、多くの人びとが恐怖におちいっていた。そのひとりに播磨国守護の赤松満祐(みつすけ)がいる。1441年6月、満祐は義教を酒宴に招き、その最中に義教を斬殺した。播磨に戻った満祐は3カ月後、重臣の細川氏、山名氏に討たれた。
京都周辺では、徳政を求める土一揆が巻き起こっていた。負債をかかえて困窮した馬借や土倉、国人、地侍、惣百姓などが、寺院に籠もって幕府に抵抗した。幕府は徳政令を出さざるを得なくなる。
関東では、管領の上杉憲実が自分の蔵書を足利学校に寄進し、諸国遍歴の旅に出てしまった。不安にかられた室町幕府は、足利持氏の遺子、成氏(しげうじ)を鎌倉公方とし、1449年に鎌倉府を再建した。
だが、成氏は次第に管領の上杉氏と対立するようになる。両者は1454年に全面衝突、翌年、鎌倉は炎上した。
東国は動乱の時代にはいった。足利成氏は古河に移り、古河公方と称されるようになる。
京都では義教の死後、1442年に幼い義勝が将軍になった。だが、義勝は翌年亡くなり、弟の義政が跡を継いだ。だが、重臣どうしの争いが激しく、政治は停滞する。そこに義政の妻、日野富子が介入してくる。政府内はめちゃくちゃになり、政治どころではなくなる。
将軍家でも、義政の弟、義視(よしみ)と子の義尚(よしひさ)の主導権争いが激しくなり、それに重臣たちがからむという構図が生まれていた。なかでも、深刻さを増したのが、細川勝元と山名持豊(もちとよ)の対立だった。
1467年、細川と山名の軍は、東軍と西軍に分かれ、京都で激突、これにより京都の大半が焼失した。応仁の乱が発生したのだ。動乱は西国全体におよぶことになる。
.jpg)
[応仁の乱。ウィキペディアより]
1473年に山名持豊と細川勝元が相次いで死ぬ。1477年に畠山義就(よしひろ)が京都を撤収すると、京都の戦乱はいちおう収まった。この動乱のさいちゅう、将軍義政は東山に通称、銀閣寺と呼ばれる山荘を造営した。
そして、まもなく山城国はじめ各地に一揆がおこりはじめる。

[銀閣寺。ウィキペディアより]
全国のほかの動きもみておこう。
1442年、北奥羽の南部氏に攻撃された安藤氏は、北海道南部に移動し、松前や函館などに多くの館を築いた。1457年にはコシャマインを指導者とするアイヌと戦っている。アイヌとのあいだでは、その後、交易の縄張りについての協定がまとまった。この安藤氏にたいし、勝山館に陣取る蠣崎(かきざき)氏(のちの松前氏)が勢力を伸ばしはじめていた。
北奥羽では南部氏が大きな勢力を誇っていたが、南奥羽では会津の蘆名(あしな)氏、16世紀にはいってからは伊達氏が台頭する。
北関東では、常陸の佐竹、下野の宇都宮、小山、下総の結城、安房の里見などの豪族がそれぞれの地に根を張り、南関東の武蔵、相模、伊豆などでは16世紀に後北条氏が強大な領国を形成するようになる。後北条氏を創始したのは北条早雲であり、子の氏綱が勢力を拡大した。
後北条氏に対抗して、駿河の今川氏は遠江から三河まで勢力を伸ばした。甲斐国守護の武田氏は晴信(信玄)の時代に信濃まで領土を拡大した。越後では守護代の長尾氏が守護上杉氏のもとで力をつけてくる。そして、長尾景虎(謙信)は上杉憲政から、ついに上杉の名跡と関東管領の地位を譲られることになる。
尾張では守護代の織田氏が領国の統制に苦しんでいたが、16世紀後半になると信長が出て、領土を広げることになる。その前に、美濃では、守護代斎藤氏の家臣が守護代家を乗っ取り、やがて守護の土岐氏も倒して斎藤道三と名乗っていた。
伊勢では北畠氏、近江の湖南では六角氏、湖北では京極氏の家臣だった浅井氏が領国を形成した。
そうしたなか、一向一揆を背景に浄土真宗が勢力を拡大していた。その指導者蓮如は、1478年、山科に本願寺を建て、各地に真宗の道場寺院を開いた。そして、加賀では1488年の一揆により、加賀一国を支配下に置くことになった。大坂の石山にも本願寺が建てられ、大坂に自治都市が誕生する。
そのころ、細川氏と大内氏は、瀬戸内海と勘合貿易の主導権をめぐって争っていた。和泉の堺は、まさに両者の争いの焦点だった。
1508年、大内義興(よしおき)は堺にはいり、足利義稙(よしたね)を将軍にかついだ。
1518年に義興が帰国すると、こんどは細川高国が義稙に代わり義晴を将軍とした。義晴の弟、義維(よしつな)は堺に滞在し、三好元長らに支えられ、堺公方として、大きな力をふるった。
1523年、中国の寧波(ニンポウ)で、大内氏の勘合貿易船を細川方の船が襲うという事件が発生する。これにより、明は海禁政策を強化し、日本と中国との公的貿易は途絶した。その結果、私貿易が活発になり、明政府は倭寇に悩まされるようになる。
朝鮮半島でも大内氏は活発な貿易をくり広げていた。しかし、16世紀に入ると、朝鮮政府は貿易を統制するようになり、公貿易は衰え、私貿易が活発になってくる。多くの商人に交じって、山陰の尼子氏が貿易に割り込んでくる。
中国地方では、尼子氏と大内氏が敵対するなか、毛利氏が力を伸ばした。1551年に大内義隆が重臣の陶晴賢(すえはるかた)に殺されると大内氏は滅亡する。
これにたいし毛利元就は1555年に厳島で陶晴賢を破り、さらに尼子氏を滅ぼして、中国地方の大半を支配することになる。毛利氏は石見銀山を押さえ、大量の銀を海外に輸出することで、経済的基礎を固めた。
四国では、細川氏の家臣、三好氏に代わって、土佐の長宗我部氏が強大になってきた。
九州は大友氏と島津氏の二大勢力のもとに置かれていたが、肥前では松浦、龍造寺、大村、有馬などの勢力が活発に動いていた。
16世紀にはいると、島津氏は琉球王国に接近し、琉球貿易の独占をねらうようになる。
大友氏、松浦氏は五島列島を根拠地とする倭寇の首領、王直と交流しながら、中国大陸との交易をおこなっていた。1542年とその翌年には、この王直の乗ったポルトガル船が種子島に到着し、日本に鉄砲をもたらした。
1549年にはフランシスコ・ザビエルが鹿児島に来航し、日本にはじめてキリスト教を伝えた。ザビエルは松浦氏や大内氏、大友氏に布教を認められ、活動を開始する。まもなくガスパル・ピレラ、ルイス・フロイスなどもやってくる。大名の大村純忠はみずからキリスト教徒になり、教会領として長崎を寄進した。
九州各地ではポルトガル船との交易が盛んになった。16世紀後半にはスペインがフィリピン征服に乗り出していた。多くの日本人が東南アジアに渡航し、各地に日本人町が生まれた。
アイヌは北海道を拠点として、広く交易をおこない、チャシと呼ばれる砦(聖地)を築いていた。叙事詩『ユーカラ』がまとめられた。
琉球王国では、按司(あじ)と呼ばれる首長が丘の上にグスク(城)を築き、ウタキではノロたちが神事をおこなっていた。
日本列島でも、15世紀から16世紀にかけて、多くの城が築かれた。それは砦であると同時に、民衆が戦乱を避けて籠もる場所でもあった。
村や町は領主への年貢や公事を請け負いながら、高度な自治を築いていた。こうした自治体は惣中(そうちゅう)や老若(ろうにゃく)、公界(くがい)と呼ばれ、町や村での犯罪は「自検断」、すなわち自治体みずからの責任で裁かれていた。
無縁所と呼ばれる大寺院があらわれるのもこのころである。無縁所は世俗の領主とかかわらない寺院で、土地を持たず、金融や勧進、事業によって運営されていた。こうした寺院はしばしば避難所(アジール)や駆込寺としての役割をはたした。
堺や山崎(山城)、大湊(伊勢)、宇治山田などの多くの自治都市は「十楽之津」と呼ばれ、都市自体がアジールの性格をもっていた、と網野はいう。
海や湖では、廻船人や海運業者、商人たちが縄張りをつくって、それを管理していた。そこには独自の慣習が生まれ、そこを通るには礼銭や関銭を払わねばならないこともあった。瀬戸内海ではいくつかの島に海賊の拠点があり、かれらは海上交通の安全を保障するとともに、通過する船から礼銭や関銭を取っていた。
16世紀には、石見や佐渡、生野、院内などから採掘された銀が活発な国際貿易を支えていた。朝鮮半島から輸入されていた木綿は国内でも広く栽培されるようになった。タバコも流入し、喫煙習慣がはじまっている。中国大陸からはいった大鋸(おおが)が製材に革命をもたらした。
化粧品から食品まで、多くの商品に即して商人も分化・専業化してきた。信用経済が定着し、各地に両替屋が生まれている。「十六世紀の列島社会は、『経済社会』ともいうべき状況になってきたといってよかろう」と、網野は書いている。
経済社会の進展に対応して、戦国大名は自治的な都市の自由な市場取引を公認し、楽市を促進することで、みずからの立場を強化した。さらに戦国大名は、村を支配する国人や地侍などを取り込むことによって、地域全体の支配者としての立場を鮮明にしていった。
とはいえ、16世紀半ばになると、戦国大名の公儀化、すなわち権力集中が進んでいったこともまちがいない。「戦国大名は自らの居館、城を中心とした城下町をつくり、できるだけそこに国人たちを集住させ、公儀の一元化をはかった」と網野はいう。官僚組織が生まれ、税制や財政、軍役体制が整備されていった。
ここで、網野は東と西のちがいを強調している。
西と東では貨幣がことなっていた。中国では銀が活発に流通し、銭の役割が低下していた。それを反映して、西国でも銀が流通しはじめるようになったが、銭の信用は下落するいっぽうだった。そのため、米がふたたび貨幣としての役割を果たすようになったという。西国大名のなかでは石高制を採用する者が多くなった。
これにたいし東国では、明の永楽銭が基準通貨となっていた。また陸奥や甲斐で金が採掘され、金が貨幣として用いられはじめた。

[甲州一分金。ウィキペディアより]
こうした東西のちがいは、戦国大名の国制にも大きな違いをもたらす。西国大名が概して石高制を採用したのにたいし、東国大名は武田氏にしても伊達氏にしても貫高制を守っていた。貨幣や税制だけではない。暦や計量尺度、社会意識、政治体制も西と東では大きなちがいがあった。だが、東西のちがいを越えて、人とモノの流れは列島全域、いや列島を越えて、ますます活発になっていった。それが戦国時代の終わりをもたらすことになる。
長々と書いてきたが、次回はいよいよ最終回だ。
後醍醐・尊氏時代の混沌──網野善彦『日本社会の歴史』を読む(9) [歴史]
1333年5月、後醍醐は京都に帰還し、六波羅攻略の功労者、足利尊氏を鎮守府将軍に、子の護良(もりよし)親王を征夷大将軍に任じた。新政権の初仕事は朝敵の所領没収である。だが、幕府御家人の所領をすべて奪うわけにもいかなかった。没収は北条氏一門とその与党の所領に限らざるを得なかった。多くの守護の所領はそのまま認められたが、戦功のあった者や腹心が、あらたな守護や国司に任じられた。
しかし、まもなく尊氏と護良の対立が激しくなりはじめる。護良派の北畠親房は奥州に陸奥将軍府を置くことを提案、いっぽう尊氏も鎌倉に鎌倉将軍府を置くことを提案した。これはともに認められ、陸奥将軍府には親房の子顕家(あきいえ)が、鎌倉将軍府には尊氏の弟、直義(ただよし)がおもむくことになった。どちらの将軍府も将軍には後醍醐の子が奉じられていた。
1334年、後醍醐は子の恒良(つねよし)を皇太子に立て、年号を建武とした。大内裏を造営し、銅銭を新たに鋳造し、紙幣を発行することも計画されていた。
後醍醐は中国にならい、天皇専制体制の樹立を目指していた、と網野はいう。諸国の検地をおこない、収穫を銭(貫高)で評価し、その20分の1を天皇直属の倉に納税させる方式を実施しようとしていた。
だが、武家政権時代の契約や慣習の破棄を前提とする政策は、猛烈な反発を生んだ。国中に混乱が広がっていく。1334年10月には護良による後醍醐打倒計画が発覚し、護良は排除された。
1335年、かつて関東申次を務めていた西園寺公宗(きんむね)が後醍醐を暗殺しようとして失敗し、処刑される。北条高時の子、時行が信濃で叛乱をおこし、鎌倉を占領した。
鎌倉将軍府の足利直義は、幽閉されていた護良を殺し、三河に脱出した。直義を助けるため京都から駆けつけた兄の尊氏は、ただちに鎌倉を奪回し、後醍醐の帰京命令にしたがわず鎌倉にとどまった。そのため、後醍醐はこれを明確な謀反と断定し、新田義貞の軍を鎌倉に送った。だが、新田軍は足利軍に敗れる。
1336年、足利軍は敗走する新田軍を追って、京都に突入した。しかし、足利軍は楠木正成や名和長年らの組織する「悪党」の軍に翻弄され、さらに奥州から参戦した北畠顕家の軍にも攻撃されて、京都を逃げだし、兵庫から船に乗って、九州に向かった。

[『融通念仏縁起絵巻』に描かれた異形の人びと]
九州に向かう途中、足利尊氏は後醍醐に没収された武士の所領を返還することを約束し、みずからが幕府の継承者であることを鮮明にした。後醍醐によって天皇位を奪われた持明院統の光厳天皇の院宣も得ている。
九州で軍を整えた尊氏は、ふたたび京都に向かった。兵庫の湊川では楠木正成を撃破し、京都を攻略すると、光厳の弟、光明を天皇に立てた。後醍醐は延暦寺を頼って、しばらく戦ったが、形勢はますます不利となるいっぽうだった。そこで後醍醐は尊氏にいったん降伏し、その後、京都を脱出して、吉野山にはいり、あらたな朝廷を開いた。
こうして、京都と吉野にふたつの政府が生まれる。京都では、持明院統の天皇をいだく、足利氏を中心とする幕府ができ、吉野では大覚寺統の天皇が朝廷を開いたことになる。京都は北朝、吉野は南朝と呼ばれるが、その実体は武家と公家の二つの王権だった、と網野はいう。
室町幕府には、最初から尊氏と直義の路線対立があった。尊氏と直義の二頭政治はその後、深刻な混乱をもたらすことになる。
二つの政府のあいだで激戦がくり広げられた。吉野側は熊野海賊を引き入れ、瀬戸内海に勢力を広げた。
東国では、武家勢に攻められた北畠顕家が多賀城を放棄し、大軍を率いて鎌倉にはいった。そして、そのまま東海道を進んで、美濃の青野ヶ原で幕府軍と戦った。敗れた顕家は、それでも伊賀から奈良に向かい、最後は1338年に和泉堺の戦いで敗死することになる。
北陸の新田義貞は越前の国府を占領し、守護の斯波高経(しばたかつね)を攻めたが、藤島城で戦死した。
こうして、後醍醐側は、北畠顕家と新田義貞の有力武将を失うことになる。
吉野の後醍醐は劣勢を挽回すべく、東国や遠江(とおとうみ)、四国などに子息や武将を派遣する。しかし、1339年に後醍醐は吉野で死去、息子の義良(のりよし)が後村上天皇となった。その後、南朝側は劣勢を挽回することができず、京都の幕府によって追い詰められていくことになる。
室町幕府で実質的に政治を担っていた足利直義は、徐々に幕府の体制を強化していた。新たに地頭となった者による勝手な年貢徴収を禁止し、引付(ひきつけ、裁判機関)を拡充することで訴訟を公正・迅速におこなうことにも努めている。律宗・禅宗寺院を中心に寺院制度も整え、後醍醐の冥福を祈るため京都に天竜寺を建立した。
ところが、直義の統治権が強化されるのをみて、尊氏配下の高師直(こうのもろなお)、さらには佐々木道誉(どうよ)や土岐氏などが勝手な振る舞いをしはじめる。直義派と師直派が生まれる。それを尊氏は傍観していた。
そのころ、南朝方の北畠親房(顕家の子)は、常陸の小田城で『神皇正統記』を書き上げた。だが、親房は幕府軍の攻勢に耐えきれず、拠点とする城を失い、1343年に吉野に逃げ帰った。
敗色が濃かったとはいえ、南朝側は攻撃をやめなかった。1347年には熊野水軍が堺を攻撃し、さらに薩摩にもあらわれた。四国の忽那島(くつなじま)にいた懐良(かねよし)親王は熊野水軍とともに九州にはいり、九州で勢力を拡大していく。楠木正成の子、正行(まさつら)は摂津を攻撃していた。
これにたいし、高師直と弟、師泰の軍勢は1348年に河内の四條畷で正行を破った。その勢いで師直は吉野を攻め、後村上を麓の賀名生(あのう)に追い払った。
幕府内で力を強めた師直らにたいし、直義は1349年に、みずからの養子(尊氏の子)直冬を中国探題に任じた。そして、幕府の人事権を掌握する尊氏に迫って、師直を執事の職から外させた。
だが、師直はクーデターをおこし、直義を失脚させてしまう。尊氏は息子の義詮(よしあきら)を鎌倉から呼び戻し、みずからの後継者とした。
いっぽう、直義の養子、直冬は九州に逃れ、そこで勢力を蓄えていた。これを討つため、こんどは尊氏と師直の軍が西に向かう。ところが畿内で直義党の武将が蜂起し、尊氏・師直軍を討ち、師直と弟の師泰が殺された。
これにより直義が政権を握ったかにみえた。しかし、尊氏派の武将が京都を包囲したため、直義は北陸を経て、鎌倉に向かった。
尊氏はいったん吉野の政府に降伏したのち、鎌倉の直義を討ち、1350年に鎌倉を占領し、直義を死に追いやった。
室町幕府の混乱に乗じて、吉野方は1352年に京都に進軍し、北朝の上皇らを捕らえ、河内に送った。さらに、鎌倉を占領し、鎌倉から尊氏を追い出した。だが、それもつかのま、尊氏は鎌倉を回復、京都を追われた尊氏の息子、義詮もひと月足らずで京都を回復した。
こうして、京都、吉野、九州に三つの政府が分立した。京都では連れ去られた上皇と皇太子に代わって、後光厳が天皇に立てられた。東北では足利氏一門の斯波氏と畠山氏の対立がつづいていた。九州では、鎮西探題の一色氏と対抗しながら、足利直冬がみずからの勢力を築いていた。
吉野方は九州に懐良(かねよし)親王を送り、まず直冬を討ち、ついで一色氏を撃破した。1355年に懐良は太宰府に拠点を置き、吉野からも京都からも自立する動きを示した。
賀名生に移っていた吉野方では1354年に北畠親房が亡くなり、強硬派と融和派の対立もあって、急速な弱体化が進んでいた。しかし、その京都でも畿内の守護どうしの対立が激化するなか、幕府の権威は地に墜ちていた。
そんななか、1358年に足利尊氏が死ぬ。そのあと、京都と吉野は一進一退の戦いをくり広げ、一時は吉野方が京都を奪回することもあった。だが、たちまち幕府方に奪還され、その後、畿内の吉野方はほとんど無力になっていく。
足利義詮はようやく混乱を切り抜ける。1362年には一門の斯波義将(しばよしまさ)を将軍執事としている。執事職はまもなく管領と呼ばれるようになる。山陰の山名氏や山陽の大内氏が幕府に招き入れられた。管領の斯波氏は幕府財政の充実に力をそそいだが、延暦寺や興福寺の反発を招き、1366年に失脚した。
1367年、義詮は10歳になる息子、義満に政務を譲った。管領には細川頼之が任じられた。鎌倉府では公方基氏が死に、その子、氏満が跡を継ぎ、上杉氏が管領として、これを補佐する体制が生まれた。こうして、東西にわたり、ようやく安定のきざしがみえてきた。
1368年、元の皇帝は北方に追われ、朱元璋が明を建国した。そのころ倭寇の集団が高麗を襲い、高麗は滅亡の危機に瀕していた。明に倭寇の禁圧を求められた九州の懐良はこれに応じ、日本国王の名を与えられている。
幕府では、管領の細川頼之が瀬戸内海の海上権を掌握しながら、寺社と守護との勢力均衡をはかるとともに、南朝を吸収する方策を練っていた。
1371年、頼之は今川了俊を九州探題とし、懐良に対抗しようとした。京都では検非違使の権限を奪い取り、京都を将軍の直轄下におくことが課題になっていた。
1379年、斯波氏は鎌倉公方氏満と結んで、頼之排斥の動きに出た。頼之は自宅を焼いて、四国にくだった。じつは、この計画を密かに推進していたのが将軍の義満にほかならなかったとされる。
頼之がいなくなったあと、義満は新たな管領として斯波義将(よしまさ)を迎えるが、そのときはすでにみずからの権力を振るうようになっていた。義満が将軍直轄軍(奉公衆)をおいたのも、みずからが守護の力を抑える実力をもつためだった。
1380年、京都の室町に「花の御所」が完成した。これが室町幕府という名称の由来である。義満は後円融上皇から洛中の行政裁判権を奪い、京都における将軍の支配権を確立した。
1385年から90年にかけ、義満は各地を巡覧し、将軍の権威を誇示した。有力守護の土岐氏や山名氏の勢力を削ぐことにも成功している。そのころ九州探題の今川了俊も懐良の死後、弱体化していた征西府を押さえこんでいる。さらに、義満は南朝の後亀山天皇に働きかけ、1392年に南北朝の合一に成功した。
1401年には西園寺家の山荘があった北山に壮麗な邸宅を建設した。これが金閣寺である。この年、義満は明に使いを出し、翌1402年に明の皇帝により正式に日本国王に奉じられた。勘合貿易がはじまる。

[足利義満。ウィキペディアより]
1407年、義満の正室、日野康子は准母(じゅんぼ)となり、その子、義嗣が親王の待遇を受けた。すなわち天皇になりうる位である。だが、1408年に義満は急死、それにより天皇位奪取は未遂に終わった。
義満の死後、貴族たちは義満に太上天皇の称号を贈ることを決定するが、重臣会議はそれを辞退し、義持を義満の後継者とし、足利家の家督とした。重臣たちは、将軍と天皇の権威が合体することで、専制的権力が出現することを恐れた、と網野は記している。
義満の死後、義持は明の皇帝から日本国王の称号を受けることを拒否し、それにより日本と明との公式の国交、勘合貿易は一時とだえた。
やっかいなのは倭寇の動きだった。倭寇に手を焼いた朝鮮の太宗は1419年に倭寇の根拠地、対馬を攻撃した。対馬の守護代、宗氏がこれに応戦し、朝鮮軍は引き揚げた。その後、朝鮮国王の代替わりを待って、日本と朝鮮の国交は回復する。
13世紀以降、日本では貨幣経済が活発になり、各地の荘園・公領の年貢は市場で売却され、公事、夫役などの負担も銭に換算されるようになった。税は銭で計算されて支配者に送られていた。14世紀以降は、その銭も替銭(かえぜに)や割符(さいふ)のような手形、小切手のかたちで送られるのが普通になった。
荘園・公領の多くは大名(たいめい)と呼ばれる守護の支配下にはいっており、実際には代官たちがそれらを請け負っていた。代官たちはすでに経営者だったといってもよい、と網野は書いている。
代官たちは年貢の納期に商人から割府を入手して送った。請負を円滑にするため有力者や百姓たちと酒宴を開くのも、代官のだいじな仕事だった。守護が現地にやってこないようにするため、守護には一献料や酒肴料を贈っていた。
年貢の納期になると市庭での相場を見定め、できるだけ高い値段で納入物を売るのが腕の見せ所だ。荘園の収入や経費はその都度、細かく帳簿に記入され、年末に散用状という決算書をつくって、本所(土地所有者)の決裁を受けなければならなかった。
このころは六文子(ろくもんこ、月利六分)と呼ばれる金貸しも多くなり、有徳人(うとくじん、金持ち)もでてくる。銭自体を神仏のように崇める風潮が広がろうとしていた。
商業や金融に携わる僧や山伏まで登場してくる。交通の要所、寺社の門前などに、町がつくられていた。15世紀には商人や問丸(倉庫業者)が中心になって、自治都市が誕生する。
貨幣経済、信用経済の発達に伴い、村落の自治傾向も強まってくる。乙名(おとな)百姓、長(おさ)百姓、あるいは名主が、みずから村の掟を定めるようになる。つくられていたのは米だけではない。養蚕や製糸、製紙、造林、果樹栽培、鉱物採取、製塩など、村では多様な生産活動がくり広げられていた。
「荘園公領制に代わる新たな村町制がしだいにその姿をあらわしはじめた」と、網野は書いている。

[『七十一番職人歌合』から。ウィキペディア]
14世紀末から15世紀にかけ、諸国の守護は大名に成長していく。九州では島津、大友、四国・中国では細川、大内、山陰では山名、北陸では斯波、東海では今川などである。ほかにも一色、武田、畠山など、東西にまたがる領地をもつ守護大名もいた。東国は鎌倉府の管領、上杉氏の力が強かったが、千葉、三浦、佐竹、小山など鎌倉時代以来の氏族も残っていた。
中国大陸との関係では、とりわけ禅僧が大きな役割をはたしていた。僧たちは詩文や庭園、水墨画、書籍出版などに貢献しただけではない。外交文書の作成や勘合貿易の実務をおこない、荘園・公領の経営を請け負ったりもしている。
このころ中国に輸出されていたのは金、銅、太刀、扇など。いっぽう中国から輸入されていたのは銅銭、陶磁器、絹などである。海外との貿易は中国と朝鮮半島だけにとどまらず、アジア全体に広がっていた。
1420年代には、中山王が三山を統一し、琉球王国が誕生した。北方ではアイヌの動きが活発化し、民族としてみずからを形成しつつある。津軽から道南にはいった安藤氏はアイヌとの交渉を通じて、大きな政治勢力を築こうとしていた。
いっぽう、この時代に差別観が広がったことにも網野は注目している。村や町が自治の傾向を強めるなかで、遍歴・漂泊をつづける宗教民や芸能民、商工民への警戒が広がり、それが差別につながった、と網野は書いている。穢れもまた忌避されるようになった。聖なる者としてキヨメをおこなっていた者も賤視されるようになる。
女性たちは金融や商工業の面でも、引きつづき活躍していたが、女性の社会的地位は低下しつつあった。かつては宮廷に出入りし、天皇や貴族に接していた遊女たちは、次第に社会から賤視されるようになった。
だが、こうした差別される者のなかから芸能が生まれてくる。御庭者のなかからはすぐれた築庭家があらわれる。立花(華道)や茶道も、非人の流れをくむ人びとによってつくられた。観阿弥や世阿弥は猿楽と呼ばれた芸能を能に高めていった。東山文化のほとんどは被差別民と何らかのかかわりをもっていた、と網野は指摘している。
しかし、まもなく尊氏と護良の対立が激しくなりはじめる。護良派の北畠親房は奥州に陸奥将軍府を置くことを提案、いっぽう尊氏も鎌倉に鎌倉将軍府を置くことを提案した。これはともに認められ、陸奥将軍府には親房の子顕家(あきいえ)が、鎌倉将軍府には尊氏の弟、直義(ただよし)がおもむくことになった。どちらの将軍府も将軍には後醍醐の子が奉じられていた。
1334年、後醍醐は子の恒良(つねよし)を皇太子に立て、年号を建武とした。大内裏を造営し、銅銭を新たに鋳造し、紙幣を発行することも計画されていた。
後醍醐は中国にならい、天皇専制体制の樹立を目指していた、と網野はいう。諸国の検地をおこない、収穫を銭(貫高)で評価し、その20分の1を天皇直属の倉に納税させる方式を実施しようとしていた。
だが、武家政権時代の契約や慣習の破棄を前提とする政策は、猛烈な反発を生んだ。国中に混乱が広がっていく。1334年10月には護良による後醍醐打倒計画が発覚し、護良は排除された。
1335年、かつて関東申次を務めていた西園寺公宗(きんむね)が後醍醐を暗殺しようとして失敗し、処刑される。北条高時の子、時行が信濃で叛乱をおこし、鎌倉を占領した。
鎌倉将軍府の足利直義は、幽閉されていた護良を殺し、三河に脱出した。直義を助けるため京都から駆けつけた兄の尊氏は、ただちに鎌倉を奪回し、後醍醐の帰京命令にしたがわず鎌倉にとどまった。そのため、後醍醐はこれを明確な謀反と断定し、新田義貞の軍を鎌倉に送った。だが、新田軍は足利軍に敗れる。
1336年、足利軍は敗走する新田軍を追って、京都に突入した。しかし、足利軍は楠木正成や名和長年らの組織する「悪党」の軍に翻弄され、さらに奥州から参戦した北畠顕家の軍にも攻撃されて、京都を逃げだし、兵庫から船に乗って、九州に向かった。

[『融通念仏縁起絵巻』に描かれた異形の人びと]
九州に向かう途中、足利尊氏は後醍醐に没収された武士の所領を返還することを約束し、みずからが幕府の継承者であることを鮮明にした。後醍醐によって天皇位を奪われた持明院統の光厳天皇の院宣も得ている。
九州で軍を整えた尊氏は、ふたたび京都に向かった。兵庫の湊川では楠木正成を撃破し、京都を攻略すると、光厳の弟、光明を天皇に立てた。後醍醐は延暦寺を頼って、しばらく戦ったが、形勢はますます不利となるいっぽうだった。そこで後醍醐は尊氏にいったん降伏し、その後、京都を脱出して、吉野山にはいり、あらたな朝廷を開いた。
こうして、京都と吉野にふたつの政府が生まれる。京都では、持明院統の天皇をいだく、足利氏を中心とする幕府ができ、吉野では大覚寺統の天皇が朝廷を開いたことになる。京都は北朝、吉野は南朝と呼ばれるが、その実体は武家と公家の二つの王権だった、と網野はいう。
室町幕府には、最初から尊氏と直義の路線対立があった。尊氏と直義の二頭政治はその後、深刻な混乱をもたらすことになる。
二つの政府のあいだで激戦がくり広げられた。吉野側は熊野海賊を引き入れ、瀬戸内海に勢力を広げた。
東国では、武家勢に攻められた北畠顕家が多賀城を放棄し、大軍を率いて鎌倉にはいった。そして、そのまま東海道を進んで、美濃の青野ヶ原で幕府軍と戦った。敗れた顕家は、それでも伊賀から奈良に向かい、最後は1338年に和泉堺の戦いで敗死することになる。
北陸の新田義貞は越前の国府を占領し、守護の斯波高経(しばたかつね)を攻めたが、藤島城で戦死した。
こうして、後醍醐側は、北畠顕家と新田義貞の有力武将を失うことになる。
吉野の後醍醐は劣勢を挽回すべく、東国や遠江(とおとうみ)、四国などに子息や武将を派遣する。しかし、1339年に後醍醐は吉野で死去、息子の義良(のりよし)が後村上天皇となった。その後、南朝側は劣勢を挽回することができず、京都の幕府によって追い詰められていくことになる。
室町幕府で実質的に政治を担っていた足利直義は、徐々に幕府の体制を強化していた。新たに地頭となった者による勝手な年貢徴収を禁止し、引付(ひきつけ、裁判機関)を拡充することで訴訟を公正・迅速におこなうことにも努めている。律宗・禅宗寺院を中心に寺院制度も整え、後醍醐の冥福を祈るため京都に天竜寺を建立した。
ところが、直義の統治権が強化されるのをみて、尊氏配下の高師直(こうのもろなお)、さらには佐々木道誉(どうよ)や土岐氏などが勝手な振る舞いをしはじめる。直義派と師直派が生まれる。それを尊氏は傍観していた。
そのころ、南朝方の北畠親房(顕家の子)は、常陸の小田城で『神皇正統記』を書き上げた。だが、親房は幕府軍の攻勢に耐えきれず、拠点とする城を失い、1343年に吉野に逃げ帰った。
敗色が濃かったとはいえ、南朝側は攻撃をやめなかった。1347年には熊野水軍が堺を攻撃し、さらに薩摩にもあらわれた。四国の忽那島(くつなじま)にいた懐良(かねよし)親王は熊野水軍とともに九州にはいり、九州で勢力を拡大していく。楠木正成の子、正行(まさつら)は摂津を攻撃していた。
これにたいし、高師直と弟、師泰の軍勢は1348年に河内の四條畷で正行を破った。その勢いで師直は吉野を攻め、後村上を麓の賀名生(あのう)に追い払った。
幕府内で力を強めた師直らにたいし、直義は1349年に、みずからの養子(尊氏の子)直冬を中国探題に任じた。そして、幕府の人事権を掌握する尊氏に迫って、師直を執事の職から外させた。
だが、師直はクーデターをおこし、直義を失脚させてしまう。尊氏は息子の義詮(よしあきら)を鎌倉から呼び戻し、みずからの後継者とした。
いっぽう、直義の養子、直冬は九州に逃れ、そこで勢力を蓄えていた。これを討つため、こんどは尊氏と師直の軍が西に向かう。ところが畿内で直義党の武将が蜂起し、尊氏・師直軍を討ち、師直と弟の師泰が殺された。
これにより直義が政権を握ったかにみえた。しかし、尊氏派の武将が京都を包囲したため、直義は北陸を経て、鎌倉に向かった。
尊氏はいったん吉野の政府に降伏したのち、鎌倉の直義を討ち、1350年に鎌倉を占領し、直義を死に追いやった。
室町幕府の混乱に乗じて、吉野方は1352年に京都に進軍し、北朝の上皇らを捕らえ、河内に送った。さらに、鎌倉を占領し、鎌倉から尊氏を追い出した。だが、それもつかのま、尊氏は鎌倉を回復、京都を追われた尊氏の息子、義詮もひと月足らずで京都を回復した。
こうして、京都、吉野、九州に三つの政府が分立した。京都では連れ去られた上皇と皇太子に代わって、後光厳が天皇に立てられた。東北では足利氏一門の斯波氏と畠山氏の対立がつづいていた。九州では、鎮西探題の一色氏と対抗しながら、足利直冬がみずからの勢力を築いていた。
吉野方は九州に懐良(かねよし)親王を送り、まず直冬を討ち、ついで一色氏を撃破した。1355年に懐良は太宰府に拠点を置き、吉野からも京都からも自立する動きを示した。
賀名生に移っていた吉野方では1354年に北畠親房が亡くなり、強硬派と融和派の対立もあって、急速な弱体化が進んでいた。しかし、その京都でも畿内の守護どうしの対立が激化するなか、幕府の権威は地に墜ちていた。
そんななか、1358年に足利尊氏が死ぬ。そのあと、京都と吉野は一進一退の戦いをくり広げ、一時は吉野方が京都を奪回することもあった。だが、たちまち幕府方に奪還され、その後、畿内の吉野方はほとんど無力になっていく。
足利義詮はようやく混乱を切り抜ける。1362年には一門の斯波義将(しばよしまさ)を将軍執事としている。執事職はまもなく管領と呼ばれるようになる。山陰の山名氏や山陽の大内氏が幕府に招き入れられた。管領の斯波氏は幕府財政の充実に力をそそいだが、延暦寺や興福寺の反発を招き、1366年に失脚した。
1367年、義詮は10歳になる息子、義満に政務を譲った。管領には細川頼之が任じられた。鎌倉府では公方基氏が死に、その子、氏満が跡を継ぎ、上杉氏が管領として、これを補佐する体制が生まれた。こうして、東西にわたり、ようやく安定のきざしがみえてきた。
1368年、元の皇帝は北方に追われ、朱元璋が明を建国した。そのころ倭寇の集団が高麗を襲い、高麗は滅亡の危機に瀕していた。明に倭寇の禁圧を求められた九州の懐良はこれに応じ、日本国王の名を与えられている。
幕府では、管領の細川頼之が瀬戸内海の海上権を掌握しながら、寺社と守護との勢力均衡をはかるとともに、南朝を吸収する方策を練っていた。
1371年、頼之は今川了俊を九州探題とし、懐良に対抗しようとした。京都では検非違使の権限を奪い取り、京都を将軍の直轄下におくことが課題になっていた。
1379年、斯波氏は鎌倉公方氏満と結んで、頼之排斥の動きに出た。頼之は自宅を焼いて、四国にくだった。じつは、この計画を密かに推進していたのが将軍の義満にほかならなかったとされる。
頼之がいなくなったあと、義満は新たな管領として斯波義将(よしまさ)を迎えるが、そのときはすでにみずからの権力を振るうようになっていた。義満が将軍直轄軍(奉公衆)をおいたのも、みずからが守護の力を抑える実力をもつためだった。
1380年、京都の室町に「花の御所」が完成した。これが室町幕府という名称の由来である。義満は後円融上皇から洛中の行政裁判権を奪い、京都における将軍の支配権を確立した。
1385年から90年にかけ、義満は各地を巡覧し、将軍の権威を誇示した。有力守護の土岐氏や山名氏の勢力を削ぐことにも成功している。そのころ九州探題の今川了俊も懐良の死後、弱体化していた征西府を押さえこんでいる。さらに、義満は南朝の後亀山天皇に働きかけ、1392年に南北朝の合一に成功した。
1401年には西園寺家の山荘があった北山に壮麗な邸宅を建設した。これが金閣寺である。この年、義満は明に使いを出し、翌1402年に明の皇帝により正式に日本国王に奉じられた。勘合貿易がはじまる。

[足利義満。ウィキペディアより]
1407年、義満の正室、日野康子は准母(じゅんぼ)となり、その子、義嗣が親王の待遇を受けた。すなわち天皇になりうる位である。だが、1408年に義満は急死、それにより天皇位奪取は未遂に終わった。
義満の死後、貴族たちは義満に太上天皇の称号を贈ることを決定するが、重臣会議はそれを辞退し、義持を義満の後継者とし、足利家の家督とした。重臣たちは、将軍と天皇の権威が合体することで、専制的権力が出現することを恐れた、と網野は記している。
義満の死後、義持は明の皇帝から日本国王の称号を受けることを拒否し、それにより日本と明との公式の国交、勘合貿易は一時とだえた。
やっかいなのは倭寇の動きだった。倭寇に手を焼いた朝鮮の太宗は1419年に倭寇の根拠地、対馬を攻撃した。対馬の守護代、宗氏がこれに応戦し、朝鮮軍は引き揚げた。その後、朝鮮国王の代替わりを待って、日本と朝鮮の国交は回復する。
13世紀以降、日本では貨幣経済が活発になり、各地の荘園・公領の年貢は市場で売却され、公事、夫役などの負担も銭に換算されるようになった。税は銭で計算されて支配者に送られていた。14世紀以降は、その銭も替銭(かえぜに)や割符(さいふ)のような手形、小切手のかたちで送られるのが普通になった。
荘園・公領の多くは大名(たいめい)と呼ばれる守護の支配下にはいっており、実際には代官たちがそれらを請け負っていた。代官たちはすでに経営者だったといってもよい、と網野は書いている。
代官たちは年貢の納期に商人から割府を入手して送った。請負を円滑にするため有力者や百姓たちと酒宴を開くのも、代官のだいじな仕事だった。守護が現地にやってこないようにするため、守護には一献料や酒肴料を贈っていた。
年貢の納期になると市庭での相場を見定め、できるだけ高い値段で納入物を売るのが腕の見せ所だ。荘園の収入や経費はその都度、細かく帳簿に記入され、年末に散用状という決算書をつくって、本所(土地所有者)の決裁を受けなければならなかった。
このころは六文子(ろくもんこ、月利六分)と呼ばれる金貸しも多くなり、有徳人(うとくじん、金持ち)もでてくる。銭自体を神仏のように崇める風潮が広がろうとしていた。
商業や金融に携わる僧や山伏まで登場してくる。交通の要所、寺社の門前などに、町がつくられていた。15世紀には商人や問丸(倉庫業者)が中心になって、自治都市が誕生する。
貨幣経済、信用経済の発達に伴い、村落の自治傾向も強まってくる。乙名(おとな)百姓、長(おさ)百姓、あるいは名主が、みずから村の掟を定めるようになる。つくられていたのは米だけではない。養蚕や製糸、製紙、造林、果樹栽培、鉱物採取、製塩など、村では多様な生産活動がくり広げられていた。
「荘園公領制に代わる新たな村町制がしだいにその姿をあらわしはじめた」と、網野は書いている。

[『七十一番職人歌合』から。ウィキペディア]
14世紀末から15世紀にかけ、諸国の守護は大名に成長していく。九州では島津、大友、四国・中国では細川、大内、山陰では山名、北陸では斯波、東海では今川などである。ほかにも一色、武田、畠山など、東西にまたがる領地をもつ守護大名もいた。東国は鎌倉府の管領、上杉氏の力が強かったが、千葉、三浦、佐竹、小山など鎌倉時代以来の氏族も残っていた。
中国大陸との関係では、とりわけ禅僧が大きな役割をはたしていた。僧たちは詩文や庭園、水墨画、書籍出版などに貢献しただけではない。外交文書の作成や勘合貿易の実務をおこない、荘園・公領の経営を請け負ったりもしている。
このころ中国に輸出されていたのは金、銅、太刀、扇など。いっぽう中国から輸入されていたのは銅銭、陶磁器、絹などである。海外との貿易は中国と朝鮮半島だけにとどまらず、アジア全体に広がっていた。
1420年代には、中山王が三山を統一し、琉球王国が誕生した。北方ではアイヌの動きが活発化し、民族としてみずからを形成しつつある。津軽から道南にはいった安藤氏はアイヌとの交渉を通じて、大きな政治勢力を築こうとしていた。
いっぽう、この時代に差別観が広がったことにも網野は注目している。村や町が自治の傾向を強めるなかで、遍歴・漂泊をつづける宗教民や芸能民、商工民への警戒が広がり、それが差別につながった、と網野は書いている。穢れもまた忌避されるようになった。聖なる者としてキヨメをおこなっていた者も賤視されるようになる。
女性たちは金融や商工業の面でも、引きつづき活躍していたが、女性の社会的地位は低下しつつあった。かつては宮廷に出入りし、天皇や貴族に接していた遊女たちは、次第に社会から賤視されるようになった。
だが、こうした差別される者のなかから芸能が生まれてくる。御庭者のなかからはすぐれた築庭家があらわれる。立花(華道)や茶道も、非人の流れをくむ人びとによってつくられた。観阿弥や世阿弥は猿楽と呼ばれた芸能を能に高めていった。東山文化のほとんどは被差別民と何らかのかかわりをもっていた、と網野は指摘している。
蒙古襲来と鎌倉幕府の崩壊──網野善彦『日本社会の歴史』を読む(8) [歴史]
このころの社会について、網野はおよそ次のようにまとめている。
13世紀後半には文字が普及し、多くの人が文字を読み書きできるようになった。中国大陸から流入した銭貨が広く流通し、貨幣世界が浸透していた。氏族ではなく、イエを中心とする考え方が一般化しつつある。
荘園・公領の支配者は、それを広く一円領として支配するとともに、紛争の起こらぬよう下地を分割し、借上(金融業者)や商人を代官として、年貢や公事の徴集をゆだねていた。
京都、鎌倉、博多をはじめ、各地の津や泊、宿には土倉が立ち並び、多くの商工民が集まり、町が形成されていた。金融業者や商人のあいだでは為替や手形が流通するようになる。代官たちは徴集した多様な物品を市庭で売り、その現銭を手形に変えて、京都や鎌倉に送るようになった。
金融ネットワークの広がりを支えていたのは、廻船、馬借、車借などによる海陸交通の発展である。熊野神人や伊勢神人などと呼ばれる人びとが、紀伊半島を拠点に、房総半島から南九州にいたるまでの太平洋沿岸にわたり、海上交通を担っていた。日本海から琵琶湖にかけても、日吉神人、賀茂社供祭人、石清水八幡宮神人のような神人が活躍していた。
律禅僧は寺社や橋、港湾などをつくるため、勧進によって金を集めた。関所を設け、神物や仏物の名目で関料や関銭を集めることも認められていた。勧進上人が唐船をつくり、船に砂金や水銀、刀剣、織物などを積み込んで、海を渡り、貿易をおこなうこともあった。
「律僧、禅僧などの勧進上人は、一面では冒険的な貿易大商人という性格をもっていた」と網野はいう。宋や元からは膨大な青白磁や銭だけでなく、さまざまな工芸品や実用品、書籍などがもたらされた。
この時代、商業や金融の部門では女性が数多く活躍していた。なかには神人と認められた者もいる。家主や名主に名を連ねる女性も多かった。しかし、14世紀になると、女性の社会的地位は次第に低下していく。
それは、穢れを処理する人びとも同じだった。かれらはもともと神人や寄人の呼称をもち、天皇や神仏に結びついて浄めに携わっていた。しかし、穢れにかかわる職能民を賤視する空気が次第に強くなってくる。
時代とともに欲望や穢れ、罪を悪として排除する姿勢が顕著になっていく(それはおそらく市場経済が朝廷や寺社の枠組みから分離されていく過程と関係している)。市場経済が次第に広がり、救済を求める人びとが増えていくなかで、親鸞や一遍、日蓮は「悪」と呼ばれる人びとの側に身を置いて、仏の教えを広めていったのだ、と網野は記している。

[一遍聖絵。ウィキペディアより]
ここで、少し時代をふり返ってみよう。
1242年はひとつの転換点だった。四条天皇が死去し、後嵯峨天皇が即位する。鎌倉では北条泰時が世を去り、孫の経時が執権となった。成長した将軍頼経が力をもちはじめている。
1244年、朝廷では西園寺公経(きんつね)が死に、頼経の父でもある関白九条道家が専権をふるうようになった。頼経と道家の結託を恐れた北条経時は、将軍職を頼経の6歳の子、頼嗣(よりつぐ)に譲らせた。
1246年に病弱な経時が死ぬと、弟の時頼が執権となり、前将軍の頼経を京都に送還した。その年、後嵯峨は退位して上皇となり、4歳の後深草が即位した。
執権となった北条時頼は、敵対する三浦氏と千葉氏を討滅した。1252年、九条道家が幕府への謀反に関与したとして、時頼は将軍頼嗣を廃して京都に送還した。その後、道家は急死した(毒殺ともいわれる)。こうして、朝廷にも幕府にも大きな力を及ぼしていた九条家が没落する。
時頼は後嵯峨に申請して、その子、宗尊(むねたか)親王を東国の将軍に迎えることで、北条氏一門の立場を強固なものとした。いっぽう、後嵯峨も西園寺家を関東申次にしながら、「治天の君」として朝廷を掌握した。
鎌倉は繁栄し、多くの唐船が入津するようになった。1252年には宋の禅僧、蘭渓道隆を迎えて、建長寺が建立されている。鎌倉新大仏の鋳造もはじまった。

[建長寺。ウィキペディア]
しかし、大陸からみれば、何といっても日本の窓口は博多だった。博多にはいった大量の文物と銭貨は、瀬戸内海を経て畿内にもたらされた。西園寺家は北条氏一門、金沢氏の協力を得て、瀬戸内の交通網を統制し、みずからも中国との貿易をおこなった。
宋から流入した膨大な銅銭は、日本全体に大きな影響をもたらした。「十三世紀も後半に入ると、銭そのものを神仏と扱うほどに、社会は銭貨に対する欲望、富の欲求にかき立てられるようになり、それが一方で、商人や借上、博打、それらと結びついた悪党・海賊の動きを活発化させた」と、網野は記している。
1258年から翌年にかけ、各地で疫病と飢饉が蔓延した。百姓たちが逃散し、年貢・公事がとどこおった。そのころ日蓮は『立正安国論』を書き、幕府に提出した。しかし、幕府はその主張に不穏なものを感じ、日蓮を伊豆に流した。
1261年から63年にかけ、幕府と朝廷は相次いで新政策を発表した(弘長の新制)。神仏の尊重、訴訟の公正迅速な解決、撫民が強調されるいっぽう、商人、金融業者、「道々の細工」、博打、派手な衣装などに規制がかけられた。
「これは、農本主義の立場に立ち、さまざまの面で『未開』の世界にも通じる得体の知れない力に動かされた度の外れた行動を『悪』とし、それを事とする集団を『悪党』としてきびしく禁圧する姿勢を明確にした法令」だったと、網野はいかにも網野らしい筆致で記している。
東国政権は京都の朝廷と協調する姿勢を示した。いや、それ以上に朝廷と幕府は固く結びついているかのように思わせていた。実際、このころ上皇と将軍は親子関係にある。
1263年、北条時頼が死ぬ。時頼は評定衆を中心とした執権政治を推し進め、北条一門の寄合を基盤に得宗(北条本家)専制体制を築いた。
このころ朝廷では後嵯峨上皇が実権を掌握していたが、後嵯峨は1259年に後深草に代えて、その弟、亀山を即位させた。
大陸では広大なモンゴル帝国が形成されつつある。チンギスハンの息子、フビライハンは南宋に圧力を加えながら高麗を支配下に置き、高麗を通じて1268年に日本にモンゴルへの服属を求める使者を送った。
そのとき、幕府の得宗はまだ18歳の北条時宗で、宿老の北条政村が執権として、これを補佐していた。1266年には将軍宗尊親王が廃されて京都に送還され、3歳の惟康(これやす)王が新将軍に迎えられた。北条家が力を保つためには、将軍が力をもってはならないのだった。
1268年にモンゴルの国書を受けとった幕府は、朝廷にもこれを送ったが、朝廷は幕府の意向に沿って、これを無視することにした。山陽、山陰、西海、南海各道の警備が固められた。若き時宗は執権になった。
国書を黙殺されたフビライは翌年も、2度にわたって使者を送った。しかし、幕府は通交拒絶の姿勢を貫いた。
1271年にはモンゴルの使者が100人ほどの人数を連れて、北九州の今津にやってくる。幕府は国書の受け取りを拒否し、あらためて黙殺の態度を示した。蒙古襲来は必至となった。幕府は九州の防備を固め、国内の治安を強化した。それにより、日蓮はあやうく竜口(たつのくち)で処刑されそうになったが、けっきょく佐渡に流されている。

[日蓮。同]
幕府は1272年、諸国に大田文(おおたぶみ)の作成を命じ、田地の実情と動員しうる兵力を調査した。意外にも数多くの御家人が所領を失っていることを知った幕府は、徳政令を出し、所領を回復させ、それによって兵力の確保をはかった。
前年には「治天の君」として君臨していた後嵯峨上皇が亡くなり、亀山天皇が実権を握った。亀山も関東に呼応して、全国に軍事体制をとるよう呼びかけた。
1274年、フビライは日本侵攻を開始する(文永の役)。多くの高麗兵を含む蒙古軍は、まず対馬と壱岐を落とし、10月20日に北九州の海岸に上陸、待ち構えていた九州の武士たちと激戦を交えた。見知らぬ戦法に武士たちは翻弄され、いったん太宰府までしりぞいた。だが、蒙古軍はそれ以上進まず、にわかに全軍を引き揚げて、高麗に帰った。

[蒙古襲来絵詞。ウィキペディア]
蒙古襲来は朝廷にも幕府にも大きな衝撃を与えた。再度の襲来が予想された。朝廷から軍事指揮権を与えられた幕府は、西国の警備をいっそう強化した。国内の寺社には異国降伏の祈禱をおこなわせ、御家人たちには北九州から長門にかけての沿岸に防塁を築かせた。
1279年、モンゴルは南宋を滅ぼし、中国に元を建国する。日本侵攻をあきらめないフビライは高麗に遠征のための造船を命じ、最後の使者を日本に派遣した。幕府はこの使者を博多で処刑し、戦争体制を固めた。
1281年、ふたたびモンゴル軍が来襲した(弘安の役)。モンゴル・高麗人の東路軍4万につづき、旧南宋の江南軍10万がやってくる。ふたつの軍が合わさって、これから全面的な攻撃がはじまろうとしていた。しかし、そのとき蒙古軍は九州を襲った台風によって壊滅的な打撃をこうむり、高麗に引き揚げた。
フビライはなおも日本攻略をあきらめなかった。だが、1284年に広東・福建で叛乱が発生したため、ついに日本への遠征は中止になった。その年、時宗は(数え)34歳の若さで急死している。
時宗の舅、安達泰盛は、時宗の子で14歳の貞時を執権に据えた。泰盛は経済改革を実施するとともに、御家人の地位を保証するさまざまな処置をとった。
しかし、泰盛は敵対する得宗御内人(北条本家の執事)平頼綱によって誅殺されてしまう。これにより、鎌倉ではさらに得宗家の専制体制が強まっていくことになる。
安達泰盛が殺害されたあと、東国では内管領の平頼綱が得宗御内人として、北条貞時を支える体制が生まれた。実質上の権力を握った頼綱の姿勢は、どちらかといえば、重商主義的だった、と網野はいう。商業を重視し、諸国の津や泊を管理し、禅僧や律僧を援助して、中国との貿易を推進していたからである。
1286年、頼綱は九州の御家人たちの訴訟を処理するための鎮西談義所を設け、九州の支配を強化した。頼綱は弘安の役に貢献した武士たちに恩賞地を与え、泰盛についた者を排除し、みずからの権力基盤を固めた。海上交通の要衝には、多くの御家人が配置され、予想されるモンゴル軍の侵攻に備えた。
このころ京都では亀山上皇が「治天の君」として院政をおこなっていた。1287年、幕府は突如、亀山上皇に異心があるとして、上皇と天皇(後宇多)の交代を求めた。こうして亀山に代わって後深草が「治天の君」となり、その子、伏見が即位し、皇太子にも伏見の子が立った。
これにより、朝廷では持明院統(後深草系)による支配が確立し、これに反発する大覚寺統(後宇多系)が生まれて、天皇家は分裂した。
1292年、元の世祖(フビライ)がまたも使者を送ってきた。危機を感じた幕府は、北条氏一門の北条兼時らを九州に派遣し、のちの鎮西探題の基礎を築いた。だが、その同じ年、23歳になった得宗貞時の命により、独裁的権力をほしいままにしていた平頼綱とその一族が誅殺される。
これにより、北条貞時が幕府を完全に掌握した。貞時は滞っていた訴訟を解決するため、執奏を通じて、みずからが訴訟を即決する体制をとった。この方式が受け入れられたのは、ほんの一時だった。やがて、御家人のあいだから、貞時の独裁にたいする不満が巻き起こってくる。
1297年、貞時は永仁の徳政令を発した。御家人は売却され所領を無償で取り戻せるとし、債権取り立ての訴訟は取り上げないという内容だった。重商主義を否定し、農本主義を志向する政策だった、と網野は評している。このことは、こうした徳政令を出さねばならぬほど、貨幣経済が社会に浸透し、破産した地頭・御家人の所領がいかに多く売却されていたかを示している。
元の世祖は1294年に死亡していたが、貞時は元にたいする警戒をおこたらず、九州にあらたに北条氏一門の金沢実政(さねまさ)を派遣して、鎮西探題の権限を強化した。金沢氏は肥前、豊前、大隅の守護になるとともに、関東から九州におよぶ海上交通路を支配した。
いっぽうで、北条氏一門は唐船を中国に派遣し、多種多様な唐物や銅銭を手に入れていた。そのころ北条氏一門は、全国の半分以上にわたって守護職をつとめ、さらに地頭や領家として、それぞれの国の荘園・公領の半分近くを治めていたという。
北条氏一門の専制支配に強い反発が巻き起こるのはとうぜんだった。そのころ京都では伏見天皇が京極為兼(ためかね)に支えられながら、王朝の改革を推し進めていた。1298年、幕府はこの為兼を捕らえ、佐渡に流した。伏見が落胆すると、ここぞとばかりに大覚寺統が力を盛り返し、関東に働きかけ、1301年に大覚寺統の後二条天皇が誕生する。
その後、持明院統、大覚寺統のはげしいはたらきかけに困惑した幕府は、両統迭立(てつりつ)の方針を立て、両統を交互に天皇の位につけることにした。それにより、後二条のあとは、持明院統の花園が天皇になることが決まった。だが、これにより、かえって天皇家は決定的に分裂する。
関東の北条氏一門でも、暗闘が渦巻いていたことに変わりはなかった。暗殺に継ぐ暗殺が発生する。いやけのさした貞時は1301年に出家し、いわば外から政治をみるようになる。北条氏一門の専制に暗雲がただよいはじめていた。
1308年から翌年にかけ、西国では北条氏への反発から海賊による暴動がおこった。それが鎮圧されたあとも、西国各地では不穏な状態がつづいた。
関東の将軍はひんぴんと交代していた。将軍が成長すると、幼児に交代させるというやり方は変わらなかった。北条氏は政権発足のいきさつから、みずから将軍にはなれない。それでも得宗(北条本家)が実権を握りつづけるというほの暗い政治をつづけるには、成長した将軍をつくってはならなかった。京都に強力な天皇が生まれないようにすることとあわせて、それは幕府政治存続の鉄則だったといってよい。
1308年には、後二条が死に、持明院統の花園が天皇になり、大覚寺統の尊治(たかはる)が皇太子となった。この二人は伏見、後宇多の嫡流ではなく、最初から中継ぎであることを予定されていた。
1311年には、得宗貞時が死に、わずか9歳の高時が得宗の地位を継いだ。宿敵どうしの平、安達両家の子孫(長崎円喜[高綱]と安達時顕)が得宗を補佐することになった。鎌倉幕府は強権的な態度で、全国に臨んだ。
1315年には伏見上皇の側近、京極為兼がまたも逮捕され、前回の佐渡につづき、今回は土佐に流された。二度の配流はめずらしい。
1316年、14歳になった北条高時が執権に就任する。1317年、伏見が死ぬと、大覚寺統の後宇多の申し入れにより、関東は花園を退位させ、後宇多の息子、尊治を即位させ、後醍醐天皇とした。このあたり、めまぐるしい政治のシーソーゲームがくり広げられている。
1320年にはアイヌが蜂起し、22年にはその叛乱が本州の出羽にまで広がった。同じころ、西国でも海賊と悪党による叛乱が発生する。九州では鎮西探題の金沢氏が独自の動きをみせていた。鎌倉幕府はこうした動きを強権で抑えつけようとするが、次第に行きづまってきた。
1324年、関東は寺社・貴族の一円支配下にある所領に強い干渉を加えた。守護が領内に立ち入り、没収した所領に地頭を置く権利を認めさせたのである。王権を否定するこうした関東の動きに、後醍醐天皇はもはや我慢がならなくなった。朝廷の実権を握った後醍醐は、京都を天皇の直轄地とし、商工業者や金融業者などの神人を天皇直属民とした。独自の徳政令なども発して、活発な政策を展開するようになった。
1324年にはいると、後醍醐は日野資朝(すけとも)、千種忠顕(ちくさただあき)、僧の文観などを集め、関東打倒の計画を練りはじめた。六波羅はこれを察知し、乱に加担しようとした土岐氏を討ち、日野資朝を処罰した。これにより叛乱計画は頓挫したかにみえた。
1326年、北条高時は病を得て出家するが、その後も得宗として幕政を監督していた。だが、そのころ高時は田楽と闘犬に明け暮れているありさまだった。
それを聞いた後醍醐は、ふたたび関東打倒の意欲を燃やした。準備は着々と進められた。側近の北畠親房、吉田定房、万里小路宣房(までのこうじのぶふさ)は、これを止めようとしたが、後醍醐は耳を貸さず、文観を通じて楠木正成などの武将を自己の陣営に引き入れた。
1331年、吉田定房の密告により、計画が発覚すると、後醍醐は京都を出て、笠置山に籠もった。その子、護良(もりよし)も楠木正成も挙兵するが、いずれも六波羅の軍勢に敗れた。山中で捕らえられた後醍醐は隠岐に流された。

[後醍醐天皇。ウィキペディア]
これにより、光厳が天皇となり、後醍醐の行動を非難していた花園が院政をとることになった。
後醍醐が隠岐に流されたあとも、吉野にはいった護良は全国に挙兵を呼びかけていた。潜行していた楠木正成がふたたび姿をみせ、1333年にはいると播磨の赤松円心、伊予の河野氏、忽那(くつな)氏が蜂起し、諸国は騒然となった。
叛乱の鎮圧に六波羅は手を焼いた。後醍醐は隠岐から脱出し、伯耆の船上山にこもった。西日本は完全に内乱状態となり、九州にも叛乱が広がった。関東は大軍を編成して西に向かわせたが、その大将のひとり、足利尊氏が反旗をひるがえし、後醍醐の側に寝返って、京都の六波羅を攻めた。六波羅の部隊は崩壊し、尊氏は京都を占拠した。
いっぽう、東国では護良の令旨に応じて、上野(こうずけ)の新田義貞の大軍が鎌倉を攻め、防衛する北条氏一門を破って、北条高時らを自殺に追いこんだ。これにより鎌倉幕府は滅んだ。
13世紀後半には文字が普及し、多くの人が文字を読み書きできるようになった。中国大陸から流入した銭貨が広く流通し、貨幣世界が浸透していた。氏族ではなく、イエを中心とする考え方が一般化しつつある。
荘園・公領の支配者は、それを広く一円領として支配するとともに、紛争の起こらぬよう下地を分割し、借上(金融業者)や商人を代官として、年貢や公事の徴集をゆだねていた。
京都、鎌倉、博多をはじめ、各地の津や泊、宿には土倉が立ち並び、多くの商工民が集まり、町が形成されていた。金融業者や商人のあいだでは為替や手形が流通するようになる。代官たちは徴集した多様な物品を市庭で売り、その現銭を手形に変えて、京都や鎌倉に送るようになった。
金融ネットワークの広がりを支えていたのは、廻船、馬借、車借などによる海陸交通の発展である。熊野神人や伊勢神人などと呼ばれる人びとが、紀伊半島を拠点に、房総半島から南九州にいたるまでの太平洋沿岸にわたり、海上交通を担っていた。日本海から琵琶湖にかけても、日吉神人、賀茂社供祭人、石清水八幡宮神人のような神人が活躍していた。
律禅僧は寺社や橋、港湾などをつくるため、勧進によって金を集めた。関所を設け、神物や仏物の名目で関料や関銭を集めることも認められていた。勧進上人が唐船をつくり、船に砂金や水銀、刀剣、織物などを積み込んで、海を渡り、貿易をおこなうこともあった。
「律僧、禅僧などの勧進上人は、一面では冒険的な貿易大商人という性格をもっていた」と網野はいう。宋や元からは膨大な青白磁や銭だけでなく、さまざまな工芸品や実用品、書籍などがもたらされた。
この時代、商業や金融の部門では女性が数多く活躍していた。なかには神人と認められた者もいる。家主や名主に名を連ねる女性も多かった。しかし、14世紀になると、女性の社会的地位は次第に低下していく。
それは、穢れを処理する人びとも同じだった。かれらはもともと神人や寄人の呼称をもち、天皇や神仏に結びついて浄めに携わっていた。しかし、穢れにかかわる職能民を賤視する空気が次第に強くなってくる。
時代とともに欲望や穢れ、罪を悪として排除する姿勢が顕著になっていく(それはおそらく市場経済が朝廷や寺社の枠組みから分離されていく過程と関係している)。市場経済が次第に広がり、救済を求める人びとが増えていくなかで、親鸞や一遍、日蓮は「悪」と呼ばれる人びとの側に身を置いて、仏の教えを広めていったのだ、と網野は記している。

[一遍聖絵。ウィキペディアより]
ここで、少し時代をふり返ってみよう。
1242年はひとつの転換点だった。四条天皇が死去し、後嵯峨天皇が即位する。鎌倉では北条泰時が世を去り、孫の経時が執権となった。成長した将軍頼経が力をもちはじめている。
1244年、朝廷では西園寺公経(きんつね)が死に、頼経の父でもある関白九条道家が専権をふるうようになった。頼経と道家の結託を恐れた北条経時は、将軍職を頼経の6歳の子、頼嗣(よりつぐ)に譲らせた。
1246年に病弱な経時が死ぬと、弟の時頼が執権となり、前将軍の頼経を京都に送還した。その年、後嵯峨は退位して上皇となり、4歳の後深草が即位した。
執権となった北条時頼は、敵対する三浦氏と千葉氏を討滅した。1252年、九条道家が幕府への謀反に関与したとして、時頼は将軍頼嗣を廃して京都に送還した。その後、道家は急死した(毒殺ともいわれる)。こうして、朝廷にも幕府にも大きな力を及ぼしていた九条家が没落する。
時頼は後嵯峨に申請して、その子、宗尊(むねたか)親王を東国の将軍に迎えることで、北条氏一門の立場を強固なものとした。いっぽう、後嵯峨も西園寺家を関東申次にしながら、「治天の君」として朝廷を掌握した。
鎌倉は繁栄し、多くの唐船が入津するようになった。1252年には宋の禅僧、蘭渓道隆を迎えて、建長寺が建立されている。鎌倉新大仏の鋳造もはじまった。

[建長寺。ウィキペディア]
しかし、大陸からみれば、何といっても日本の窓口は博多だった。博多にはいった大量の文物と銭貨は、瀬戸内海を経て畿内にもたらされた。西園寺家は北条氏一門、金沢氏の協力を得て、瀬戸内の交通網を統制し、みずからも中国との貿易をおこなった。
宋から流入した膨大な銅銭は、日本全体に大きな影響をもたらした。「十三世紀も後半に入ると、銭そのものを神仏と扱うほどに、社会は銭貨に対する欲望、富の欲求にかき立てられるようになり、それが一方で、商人や借上、博打、それらと結びついた悪党・海賊の動きを活発化させた」と、網野は記している。
1258年から翌年にかけ、各地で疫病と飢饉が蔓延した。百姓たちが逃散し、年貢・公事がとどこおった。そのころ日蓮は『立正安国論』を書き、幕府に提出した。しかし、幕府はその主張に不穏なものを感じ、日蓮を伊豆に流した。
1261年から63年にかけ、幕府と朝廷は相次いで新政策を発表した(弘長の新制)。神仏の尊重、訴訟の公正迅速な解決、撫民が強調されるいっぽう、商人、金融業者、「道々の細工」、博打、派手な衣装などに規制がかけられた。
「これは、農本主義の立場に立ち、さまざまの面で『未開』の世界にも通じる得体の知れない力に動かされた度の外れた行動を『悪』とし、それを事とする集団を『悪党』としてきびしく禁圧する姿勢を明確にした法令」だったと、網野はいかにも網野らしい筆致で記している。
東国政権は京都の朝廷と協調する姿勢を示した。いや、それ以上に朝廷と幕府は固く結びついているかのように思わせていた。実際、このころ上皇と将軍は親子関係にある。
1263年、北条時頼が死ぬ。時頼は評定衆を中心とした執権政治を推し進め、北条一門の寄合を基盤に得宗(北条本家)専制体制を築いた。
このころ朝廷では後嵯峨上皇が実権を掌握していたが、後嵯峨は1259年に後深草に代えて、その弟、亀山を即位させた。
大陸では広大なモンゴル帝国が形成されつつある。チンギスハンの息子、フビライハンは南宋に圧力を加えながら高麗を支配下に置き、高麗を通じて1268年に日本にモンゴルへの服属を求める使者を送った。
そのとき、幕府の得宗はまだ18歳の北条時宗で、宿老の北条政村が執権として、これを補佐していた。1266年には将軍宗尊親王が廃されて京都に送還され、3歳の惟康(これやす)王が新将軍に迎えられた。北条家が力を保つためには、将軍が力をもってはならないのだった。
1268年にモンゴルの国書を受けとった幕府は、朝廷にもこれを送ったが、朝廷は幕府の意向に沿って、これを無視することにした。山陽、山陰、西海、南海各道の警備が固められた。若き時宗は執権になった。
国書を黙殺されたフビライは翌年も、2度にわたって使者を送った。しかし、幕府は通交拒絶の姿勢を貫いた。
1271年にはモンゴルの使者が100人ほどの人数を連れて、北九州の今津にやってくる。幕府は国書の受け取りを拒否し、あらためて黙殺の態度を示した。蒙古襲来は必至となった。幕府は九州の防備を固め、国内の治安を強化した。それにより、日蓮はあやうく竜口(たつのくち)で処刑されそうになったが、けっきょく佐渡に流されている。

[日蓮。同]
幕府は1272年、諸国に大田文(おおたぶみ)の作成を命じ、田地の実情と動員しうる兵力を調査した。意外にも数多くの御家人が所領を失っていることを知った幕府は、徳政令を出し、所領を回復させ、それによって兵力の確保をはかった。
前年には「治天の君」として君臨していた後嵯峨上皇が亡くなり、亀山天皇が実権を握った。亀山も関東に呼応して、全国に軍事体制をとるよう呼びかけた。
1274年、フビライは日本侵攻を開始する(文永の役)。多くの高麗兵を含む蒙古軍は、まず対馬と壱岐を落とし、10月20日に北九州の海岸に上陸、待ち構えていた九州の武士たちと激戦を交えた。見知らぬ戦法に武士たちは翻弄され、いったん太宰府までしりぞいた。だが、蒙古軍はそれ以上進まず、にわかに全軍を引き揚げて、高麗に帰った。

[蒙古襲来絵詞。ウィキペディア]
蒙古襲来は朝廷にも幕府にも大きな衝撃を与えた。再度の襲来が予想された。朝廷から軍事指揮権を与えられた幕府は、西国の警備をいっそう強化した。国内の寺社には異国降伏の祈禱をおこなわせ、御家人たちには北九州から長門にかけての沿岸に防塁を築かせた。
1279年、モンゴルは南宋を滅ぼし、中国に元を建国する。日本侵攻をあきらめないフビライは高麗に遠征のための造船を命じ、最後の使者を日本に派遣した。幕府はこの使者を博多で処刑し、戦争体制を固めた。
1281年、ふたたびモンゴル軍が来襲した(弘安の役)。モンゴル・高麗人の東路軍4万につづき、旧南宋の江南軍10万がやってくる。ふたつの軍が合わさって、これから全面的な攻撃がはじまろうとしていた。しかし、そのとき蒙古軍は九州を襲った台風によって壊滅的な打撃をこうむり、高麗に引き揚げた。
フビライはなおも日本攻略をあきらめなかった。だが、1284年に広東・福建で叛乱が発生したため、ついに日本への遠征は中止になった。その年、時宗は(数え)34歳の若さで急死している。
時宗の舅、安達泰盛は、時宗の子で14歳の貞時を執権に据えた。泰盛は経済改革を実施するとともに、御家人の地位を保証するさまざまな処置をとった。
しかし、泰盛は敵対する得宗御内人(北条本家の執事)平頼綱によって誅殺されてしまう。これにより、鎌倉ではさらに得宗家の専制体制が強まっていくことになる。
安達泰盛が殺害されたあと、東国では内管領の平頼綱が得宗御内人として、北条貞時を支える体制が生まれた。実質上の権力を握った頼綱の姿勢は、どちらかといえば、重商主義的だった、と網野はいう。商業を重視し、諸国の津や泊を管理し、禅僧や律僧を援助して、中国との貿易を推進していたからである。
1286年、頼綱は九州の御家人たちの訴訟を処理するための鎮西談義所を設け、九州の支配を強化した。頼綱は弘安の役に貢献した武士たちに恩賞地を与え、泰盛についた者を排除し、みずからの権力基盤を固めた。海上交通の要衝には、多くの御家人が配置され、予想されるモンゴル軍の侵攻に備えた。
このころ京都では亀山上皇が「治天の君」として院政をおこなっていた。1287年、幕府は突如、亀山上皇に異心があるとして、上皇と天皇(後宇多)の交代を求めた。こうして亀山に代わって後深草が「治天の君」となり、その子、伏見が即位し、皇太子にも伏見の子が立った。
これにより、朝廷では持明院統(後深草系)による支配が確立し、これに反発する大覚寺統(後宇多系)が生まれて、天皇家は分裂した。
1292年、元の世祖(フビライ)がまたも使者を送ってきた。危機を感じた幕府は、北条氏一門の北条兼時らを九州に派遣し、のちの鎮西探題の基礎を築いた。だが、その同じ年、23歳になった得宗貞時の命により、独裁的権力をほしいままにしていた平頼綱とその一族が誅殺される。
これにより、北条貞時が幕府を完全に掌握した。貞時は滞っていた訴訟を解決するため、執奏を通じて、みずからが訴訟を即決する体制をとった。この方式が受け入れられたのは、ほんの一時だった。やがて、御家人のあいだから、貞時の独裁にたいする不満が巻き起こってくる。
1297年、貞時は永仁の徳政令を発した。御家人は売却され所領を無償で取り戻せるとし、債権取り立ての訴訟は取り上げないという内容だった。重商主義を否定し、農本主義を志向する政策だった、と網野は評している。このことは、こうした徳政令を出さねばならぬほど、貨幣経済が社会に浸透し、破産した地頭・御家人の所領がいかに多く売却されていたかを示している。
元の世祖は1294年に死亡していたが、貞時は元にたいする警戒をおこたらず、九州にあらたに北条氏一門の金沢実政(さねまさ)を派遣して、鎮西探題の権限を強化した。金沢氏は肥前、豊前、大隅の守護になるとともに、関東から九州におよぶ海上交通路を支配した。
いっぽうで、北条氏一門は唐船を中国に派遣し、多種多様な唐物や銅銭を手に入れていた。そのころ北条氏一門は、全国の半分以上にわたって守護職をつとめ、さらに地頭や領家として、それぞれの国の荘園・公領の半分近くを治めていたという。
北条氏一門の専制支配に強い反発が巻き起こるのはとうぜんだった。そのころ京都では伏見天皇が京極為兼(ためかね)に支えられながら、王朝の改革を推し進めていた。1298年、幕府はこの為兼を捕らえ、佐渡に流した。伏見が落胆すると、ここぞとばかりに大覚寺統が力を盛り返し、関東に働きかけ、1301年に大覚寺統の後二条天皇が誕生する。
その後、持明院統、大覚寺統のはげしいはたらきかけに困惑した幕府は、両統迭立(てつりつ)の方針を立て、両統を交互に天皇の位につけることにした。それにより、後二条のあとは、持明院統の花園が天皇になることが決まった。だが、これにより、かえって天皇家は決定的に分裂する。
関東の北条氏一門でも、暗闘が渦巻いていたことに変わりはなかった。暗殺に継ぐ暗殺が発生する。いやけのさした貞時は1301年に出家し、いわば外から政治をみるようになる。北条氏一門の専制に暗雲がただよいはじめていた。
1308年から翌年にかけ、西国では北条氏への反発から海賊による暴動がおこった。それが鎮圧されたあとも、西国各地では不穏な状態がつづいた。
関東の将軍はひんぴんと交代していた。将軍が成長すると、幼児に交代させるというやり方は変わらなかった。北条氏は政権発足のいきさつから、みずから将軍にはなれない。それでも得宗(北条本家)が実権を握りつづけるというほの暗い政治をつづけるには、成長した将軍をつくってはならなかった。京都に強力な天皇が生まれないようにすることとあわせて、それは幕府政治存続の鉄則だったといってよい。
1308年には、後二条が死に、持明院統の花園が天皇になり、大覚寺統の尊治(たかはる)が皇太子となった。この二人は伏見、後宇多の嫡流ではなく、最初から中継ぎであることを予定されていた。
1311年には、得宗貞時が死に、わずか9歳の高時が得宗の地位を継いだ。宿敵どうしの平、安達両家の子孫(長崎円喜[高綱]と安達時顕)が得宗を補佐することになった。鎌倉幕府は強権的な態度で、全国に臨んだ。
1315年には伏見上皇の側近、京極為兼がまたも逮捕され、前回の佐渡につづき、今回は土佐に流された。二度の配流はめずらしい。
1316年、14歳になった北条高時が執権に就任する。1317年、伏見が死ぬと、大覚寺統の後宇多の申し入れにより、関東は花園を退位させ、後宇多の息子、尊治を即位させ、後醍醐天皇とした。このあたり、めまぐるしい政治のシーソーゲームがくり広げられている。
1320年にはアイヌが蜂起し、22年にはその叛乱が本州の出羽にまで広がった。同じころ、西国でも海賊と悪党による叛乱が発生する。九州では鎮西探題の金沢氏が独自の動きをみせていた。鎌倉幕府はこうした動きを強権で抑えつけようとするが、次第に行きづまってきた。
1324年、関東は寺社・貴族の一円支配下にある所領に強い干渉を加えた。守護が領内に立ち入り、没収した所領に地頭を置く権利を認めさせたのである。王権を否定するこうした関東の動きに、後醍醐天皇はもはや我慢がならなくなった。朝廷の実権を握った後醍醐は、京都を天皇の直轄地とし、商工業者や金融業者などの神人を天皇直属民とした。独自の徳政令なども発して、活発な政策を展開するようになった。
1324年にはいると、後醍醐は日野資朝(すけとも)、千種忠顕(ちくさただあき)、僧の文観などを集め、関東打倒の計画を練りはじめた。六波羅はこれを察知し、乱に加担しようとした土岐氏を討ち、日野資朝を処罰した。これにより叛乱計画は頓挫したかにみえた。
1326年、北条高時は病を得て出家するが、その後も得宗として幕政を監督していた。だが、そのころ高時は田楽と闘犬に明け暮れているありさまだった。
それを聞いた後醍醐は、ふたたび関東打倒の意欲を燃やした。準備は着々と進められた。側近の北畠親房、吉田定房、万里小路宣房(までのこうじのぶふさ)は、これを止めようとしたが、後醍醐は耳を貸さず、文観を通じて楠木正成などの武将を自己の陣営に引き入れた。
1331年、吉田定房の密告により、計画が発覚すると、後醍醐は京都を出て、笠置山に籠もった。その子、護良(もりよし)も楠木正成も挙兵するが、いずれも六波羅の軍勢に敗れた。山中で捕らえられた後醍醐は隠岐に流された。

[後醍醐天皇。ウィキペディア]
これにより、光厳が天皇となり、後醍醐の行動を非難していた花園が院政をとることになった。
後醍醐が隠岐に流されたあとも、吉野にはいった護良は全国に挙兵を呼びかけていた。潜行していた楠木正成がふたたび姿をみせ、1333年にはいると播磨の赤松円心、伊予の河野氏、忽那(くつな)氏が蜂起し、諸国は騒然となった。
叛乱の鎮圧に六波羅は手を焼いた。後醍醐は隠岐から脱出し、伯耆の船上山にこもった。西日本は完全に内乱状態となり、九州にも叛乱が広がった。関東は大軍を編成して西に向かわせたが、その大将のひとり、足利尊氏が反旗をひるがえし、後醍醐の側に寝返って、京都の六波羅を攻めた。六波羅の部隊は崩壊し、尊氏は京都を占拠した。
いっぽう、東国では護良の令旨に応じて、上野(こうずけ)の新田義貞の大軍が鎌倉を攻め、防衛する北条氏一門を破って、北条高時らを自殺に追いこんだ。これにより鎌倉幕府は滅んだ。
東国政権の成立──網野善彦『日本社会の歴史』を読む(7) [歴史]
1156年7月2日に鳥羽上皇が死ぬと、朝廷は後白河天皇側と崇徳上皇側に分裂し、一触即発状態となった。後白河には、関白忠通、信西(藤原道憲)、源義朝、平清盛がつき、崇徳には藤原忠実、頼長、源為義、平忠正がついた。7月11日、両者は激突し、後白河側が圧勝する(保元の乱)。崇徳側についた武士は処刑され、崇徳も讃岐に流された。
その後、後白河の朝廷は信西を中心に動いていく。すぐに新制(保元新制)が発せられた。全国土は天皇の支配下にあると宣言され、新たな荘園整理令が発された。認められた荘園以外は公領とみなされた。
荘園を所有するのは、院や摂関家、大寺社などだった。これを本家という。だが、実際にそれを管理しているのは地元の有力者で、預所(あずかりどころ)や領家と呼ばれる。さらに、実際の徴税や夫役の指示をするのが、公文や田所である。上級者が下級者に年貢や公事(徭役や夫役)を請け負わせる仕組みになっている。
いっぽう公領には知行国主(国司[国守])が任じられ、それを補任する目代(もくだい)が朝廷に納める税や納物を請け負うことになっていた。
1158年、後白河は子に譲位して上皇となり、二条天皇が誕生した。しかし、英明な二条は後白河の意のままにならず、朝廷は分裂の様相を呈する。
天皇派に藤原信頼、源義朝がつき、上皇派の信西、平清盛と対立する。信頼と義朝は、清盛が一族とともに熊野に詣でている隙に信西を襲い、殺した。
帰京した清盛は上皇ばかりか天皇をも抱きこみ、義朝を討った(平治の乱)。義朝は殺され、清盛が政治の中心に踊りでる。二条が退位し、六条が天皇になると、後白河院政のもと、1167年に清盛は太政大臣に昇進した。
清盛は娘の盛子を関白藤原基実の妻としていたが、1166年に基実が死ぬと、その所領を事実上、自分のものとしてしまう。摂関家の権威は失墜し、政治の実権はますます清盛の手に集中した。だが、そのころから、後白河と清盛の関係があやしくなりはじめる。
1168年、清盛は重い病にかかり、出家する。その間、天皇は六条から高倉に代わっている。京都における平家一族の勢力は揺るぎない。
出家後、清盛は摂津の福原に居を構え、大輪田の泊の修築に力を注いでいた。宋から九州にくる商船をこの泊まで引き入れたいと思っていたのだ。
1171年には娘の徳子が高倉天皇の中宮となり、清盛の権力はさらに強まった。だが、平家一門への反発は次第に増していく。後白河の近臣が僧俊寛らとともに平氏打倒の陰謀を企てる。これを察知した清盛は陰謀をつぶすとともに、後白河自身を政治から排除した。
1178年に徳子が高倉天皇の子を産むと、清盛はただちにこれを皇太子に立てた。
1179年には異常な物価騰貴が生じ、京都の民衆が苦しんだ。宋銭があまりに大量に流入したことが原因だった。
後白河は関白基房と手を結び、反撃に転じる。だが、清盛の軍勢に屋敷を取り囲まれ、別荘の鳥羽殿に幽閉された。院政は停止され、清盛が政治権力を完全に掌握した。
1180年、高倉は退位し、清盛の外孫で3歳の皇太子が位を継ぐ(安徳天皇)。反平氏の気運は増すばかりだった。後白河の次男、以仁(もちひと)王が諸国の武士に平氏追討を呼びかける。しかし、計画はすぐに察知され、以仁王と源頼政は宇治で敗死する。
ここで清盛は突然、上皇や天皇を引き連れて、福原への遷都を強行した。
東国では以仁王の呼びかけに応えて、源頼朝が挙兵、続いて頼朝のいとこにあたる義仲が立ち上がった。頼朝は相模の石橋山で平氏軍に完敗する。頼朝はいったん海路で安房に逃げ、そこで態勢を立て直し、武蔵に攻め込み、鎌倉を拠点にした。
肥後や熊野、尾張、美濃でも叛乱が広がる。平氏は頼朝を討つため大軍を送りこむ。だが、富士川の戦いで頼朝軍に敗れた。頼朝はそのまま上洛せず、いったん鎌倉に戻って東国を固めることにした。
清盛はわずか6カ月で、福原を捨てて、平安京に戻った。そして後白河の院政復活を認めることで、危機をしのごうとした。東国との戦争に備えるため、畿内と西国は軍政下に置かれた。だが清盛は1181年閏2月に急死する。そのあと、しばらく源平が対峙する状態が続いた。
事態が動いたのは1183年になってからである。北陸まで勢力を伸ばしていた源(木曽)義仲は、砺波山の倶利伽羅(くりから)峠で平氏軍を撃破し、その勢いで京都に進攻した。平氏一族は京都を捨て、安徳天皇を擁し西国に向かった。
義仲は京都を占拠した。後白河上皇は安徳に代わる天皇として、4歳になるその弟を後鳥羽天皇として即位させた。同時に東国の独立性を認める宣旨を頼朝に送った。
義仲は孤立した。1184年正月、義仲は頼朝が派遣した義経・範頼の大軍と戦い、近江の粟津で敗死した。義経らの軍はその勢いで、平氏を追撃、一ノ谷で平氏を海に追い落とした。義経は屋島の合戦のあと、長門の壇ノ浦で平氏一門を滅亡させる。1185年2月のことである。
だが、頼朝は後白河に接近する義経に疑惑をいだくようになった。両者の対立が激しくなってくる。頼朝は義経を暗殺しようとしたが失敗。これにたいし、義経は後白河から宣旨を得て、西国で頼朝と戦おうとした。だが、これもうまく行かず、けっきょく奥州の藤原秀衡のもとに身を寄せることになった。
頼朝はみずから軍を率いて京に向かい、使者を送って、後白河の裏切りを糾弾し、義経追討に向かった。後白河の周辺は頼朝に近い九条兼実(かねざね)らの公卿によって固められ、朝廷を監視する京都守護が置かれた。
1187年に藤原秀衡(ひでひら)が死ぬと、その子、泰衡は義経を討って、その首を頼朝に送った。だが、頼朝はそれに満足せず、1189年に大軍を送って、平泉の奥州藤原氏を滅ぼした。頼朝は東北に奥州惣奉行、九州に鎮西奉行を置いて、全国にわたる軍事的支配を広げていった。
1190年、頼朝は上洛、後白河から権大納言、右大将に任命されるが、10日後に辞職。鎌倉に戻って、政所を通じて、御家人たちへの所領恩給をおこなった。
1192年、後白河が死に、関白九条兼実の地位が安定し、頼朝も待望の征夷大将軍に任じられた。京都の朝廷と鎌倉の幕府の関係はきわめて円滑になった。
1196年、兼実は失脚。源(土御門)通親(みちちか)が朝廷の実権を握った。だが、京都と鎌倉との関係は変わらない。
1198年、通親の外孫が土御門天皇となり、後鳥羽院政がはじまる。頼朝は自分の娘を後鳥羽の後宮にいれようとしたが、うまく行かない。落馬が原因で、1199年に死んだ。通親は京都における鎌倉勢力の一掃をはかった。
頼朝のあとは頼家が継いだ。だが、有力御家人たちを押さえることができなかった。頼家が頼みとしていた梶原景時も失脚してしまう。
1203年、頼家は征夷大将軍に任じられる。この年、頼家の舅、比企能員(ひきよしかず)が北条時政に殺され、そのとき頼家の長子、一幡(いちまん)も死んだ。有力御家人たちは、頼家を廃して伊豆に流し、頼朝の次男、千幡(実朝)を将軍に立てた。1204年、頼家は伊豆修善寺で暗殺される。
このころ鎌倉の実権を握っていたのは北条時政だ。時政は畠山重忠を謀反の疑いがあるとして誅殺し、さらに将軍実朝を廃して、自身の娘婿、平賀朝雅(ともまさ)を将軍に立てようとした。これを察知した北条政子(頼朝の妻で、頼家・実朝の母)は、朝雅を殺し、父時政を伊豆に流した。
政子がにらみをきかせるなか、北条義時が執権になった。義時と対立していた和田義盛は謀反の疑いをかけられ、滅ぼされる。
源実朝は和歌や蹴鞠を通じて、京都の朝廷に接近していた。宋にあこがれ、宋に渡航する夢さえいだいていた。
1202年に源通親が死んだあと、京都では「治天の君」後鳥羽上皇の力が強くなり、文芸や武芸にも大きな影響をおよぼしていた。『新古今和歌集』が撰されたのもこのころである。
1210年、後鳥羽は土御門を退位させ、順徳を天皇につけた。鎌倉の実朝をも自己の影響下に置き、その存在感を示しそうとしていた。
1219年、実朝が頼家の子、公暁によって暗殺される。北条政子は後鳥羽の子を将軍に迎えようとするが、後鳥羽はこれを拒否。幕府は頼朝とわずかに血のつながっている西園寺公経(きんつね)の外孫で2歳の三寅(九条頼経)を鎌倉に迎え、東国の首長とした。
承久の乱のきっかけは、ごくささいなものだった。後鳥羽が寵愛する白拍子亀菊の所領から地頭を排除するよう鎌倉幕府に求め、これを義時が拒否すると、後鳥羽がいきなり暴力に訴えたのが発端である。
後鳥羽は1221年に順徳を退位させ、その幼い息子を即位させた。そのうえで、朝廷直属の武士などを集めて、京都守護を討ち、諸国に北条義時追討の命を下したのだ。
しかし、北条政子の訴えのもと、東国の御家人たちは北条義時のもとに結集し、京都に向かった。後鳥羽軍と東国軍は木曽川で激突、後鳥羽軍は潰走し、東国軍は近江の瀬戸に引かれた防衛線も突破し、京都になだれ込んだ。
勝利した東国軍は幼い天皇(明治になって仲恭と諡[おくりな]された)を廃し、後鳥羽を隠岐、順徳を佐渡に流し、出家していた後鳥羽の兄を還俗させて後高倉上皇とし、その子を天皇に即位させた(後堀河)。ここで天皇が廃されなかったのが不思議である。
京都の王権は東国の監視下に置かれた。京都を占領した北条義時の子、泰時と、義時の弟、時房はそのまま京都に滞在し、六波羅に探題を設けた。
東国の御家人たちは、地頭として補任された西国の荘園・公領で無法な振る舞いにでた。そのため幕府はそれを規制しないわけにはいかなかった。
1224年、義時が急死し、政子が泰時を執権の地位にすえた。泰時は叔父時房を連署(執権補佐)とし、11人の評定衆を定め、合議と多数決によって、政治を運営することにした。こうして執権政治が確立する。
1230年、未曾有の飢饉が諸国を襲った。とくに京都は惨憺たるありさまになった。幕府はさまざまな対策をとって、これを乗り越えた。
1232年、泰時は関東の基本法として関東御成敗式目を定めた。王朝の律令格式とは別の定めがつくられたことになる。
網野はこう書いている。
〈これはいわば関東は関東、王朝は王朝、すなわち東は東、西は西ともいうべき姿勢を、謙虚ながら確信をもって明らかにしたものであり、ここに独自な法と機構によって、おおよそ三河・信濃・能登以東の東日本に統治権を行使するとともに、従者としての御家人に支えられた鎌倉の将軍、東国の王権を頂点にもつ東国「国家」が、京都の天皇、西国の王権を頂点に西日本を統治する王朝国家と併存しつつ確立したのである。〉
東西を二分し、京都と鎌倉に二つの王権が成立した。日本社会はそれなりに安定した軌道に入った、と網野は記している。
この時代には荘園公領制が定着した。
大田文(おおたぶみ)と呼ばれる田の土地台帳、畠文(はたぶみ)と呼ばれる畠の土地台帳がつくられ、荘園、公領の田や畠の広さ、平民百姓の家屋数なども把握された。
賦課は大田文に記載された田をもとになされた。東西の王権は田地を基本としており、その意味で「農本主義」にもとづいていた、と網野はいう。
天皇家、摂関家、上級貴族は知行国を持っていた。将軍家も東国を中心にいくつかの知行国を持ち、平氏や貴族、武士から没収した荘園や公領を支配下に置いていた。延暦寺、興福寺、伊勢、上下加茂などの大寺社も多くの荘園を抱えていたことを忘れてはならない。
税として徴収されたのは米ばかりではない。各地の特産品が年貢として徴収された。東北では金や馬、東国では絹や綿、西国では米、油、紙、塩、鉄、牛など。畠からも麦、豆、粟、蕎麦などが徴収された。漆や栗、魚貝、わかめなどの海産物、松茸、平茸、柿、胡桃、長芋なども貢納されていた。
網野は同じ荘園・公領でも東と西で大きな違いがあることを強調する。
「西国の荘園・公領は本家を頂点に、領家(国主)、預所(目代)、下司・公文、さらに百姓名の名主などの職が、それぞれ請負、任免の関係をもちつつ重層する『職(しき)の体系』ともいうべき体制によって支配されていた」
東国の荘園・公領の規模は西国よりはるかに大きく、御家人が地頭となって、郡・荘を請け負い、一族や代官を各地に配置していた。西国では東国の地頭への抵抗が強かったという。
この時代の特徴として、網野はさらに、非農業民の広がりと交易の発達をあげている。市場社会が顔をのぞかせはじめている。
製鉄や製塩、製紙、その他数多くの手工業に携わる人びとが増えている。漁撈や水上運輸もそうだ。
米や絹、布が交換手段として用いられていた。市庭(いちば)では、鍋、釜、鎌、鋤、鍬などの鉄製品や陶磁器、小袖、帷子、直垂などの衣類、太刀や弓などの武器も並べられていた。
13世紀前半になると、宋から流入した銭貨が広く流通するようになる。市の開かれる日には、鋳物師、油売、魚貝売、塩売、酒売、小袖売などの商人が市庭に集まってきて商売をはじめた。女性の商人も多かったという。
職能民はもともと朝廷や官、寺社に帰属し、供御人(くごにん)や神人(じにん)、寄人(よりゅうど)などと呼ばれていた。かれらは聖なる者の分身として、各地を放浪しながら交易に従事した。
その代表は鋳物師だが、中には神物としての銭を貸す者も登場した。海上や陸上の要衝に関を設け、関料をとる者は、海賊や山賊、悪党に早変わりした。
13世紀はじめには、商人や金融業者の集まる多くの津や泊が町として発展しはじめる。そこに遊女たちも出入りするようになった。
しかし、年貢物が集まったのは京都、奈良である。このころ洛中南部(下京)には、多くの職能民が住み、酒屋、針磨(はりすり)、銅細工の作業所、借上(金融業者)の仕事をするようになっている。白河には車借(運送業者)が大勢おり、その南の六波羅は武士の拠点となっていた。貴族や官人、寺院の僧侶、商工民、武士、牛飼童、博打、穢れを浄める非人、京都はまさに多くの人びとであふれていた。
東国でも東京湾や利根川などの河川、霞ヶ浦などの湖沼を中心に海上交通が活発になっている。多くの津や泊が生まれ、東海道にはいくつも宿ができていた。こうした海陸の交通網は、鎌倉街道や和賀江の泊などを通じて、鎌倉に収斂していた。
鎌倉には幕府があり、多くの御家人や文筆官人、職能官人が住み、職人や商人も集住していた。ここでは天照大神よりも鶴岡八幡宮、北野社が尊崇され、伊豆山、箱根、三島社、日光などに東国の神々が祭られていた。
鎌倉では宋の文化が積極的に取り入れられていた。頼家も実朝も臨済禅の栄西を通じて、宋にただならぬ関心をいだいた。史書では慈円の『愚管抄』、歌では西行の『山家集』、随筆では鴨長明の『方丈記』が知られる。『平家物語』が生まれたのもこの時代である。
何よりも特筆すべきは仏教界の新しい動きである。法然は山門を離脱し、念仏を唱える易行を唱えた。親鸞は法然の教えを引き継ぎ、悪人正機の思想に行きついた。道元は純粋に禅を求め、越前に永平寺を建てた。明恵上人は法然にきびしい批判を加え、戒律の復興を唱えた。
農業中心の社会ではあったが、商業と金融、交通が発展し、人びとの交流が盛んになりはじめていた。貴族社会と武士政権がせめぎあうなかで、新たな思想や文化が登場するのが、この時代の特徴だ、と網野は論じている。
その後、後白河の朝廷は信西を中心に動いていく。すぐに新制(保元新制)が発せられた。全国土は天皇の支配下にあると宣言され、新たな荘園整理令が発された。認められた荘園以外は公領とみなされた。
荘園を所有するのは、院や摂関家、大寺社などだった。これを本家という。だが、実際にそれを管理しているのは地元の有力者で、預所(あずかりどころ)や領家と呼ばれる。さらに、実際の徴税や夫役の指示をするのが、公文や田所である。上級者が下級者に年貢や公事(徭役や夫役)を請け負わせる仕組みになっている。
いっぽう公領には知行国主(国司[国守])が任じられ、それを補任する目代(もくだい)が朝廷に納める税や納物を請け負うことになっていた。
1158年、後白河は子に譲位して上皇となり、二条天皇が誕生した。しかし、英明な二条は後白河の意のままにならず、朝廷は分裂の様相を呈する。
天皇派に藤原信頼、源義朝がつき、上皇派の信西、平清盛と対立する。信頼と義朝は、清盛が一族とともに熊野に詣でている隙に信西を襲い、殺した。
帰京した清盛は上皇ばかりか天皇をも抱きこみ、義朝を討った(平治の乱)。義朝は殺され、清盛が政治の中心に踊りでる。二条が退位し、六条が天皇になると、後白河院政のもと、1167年に清盛は太政大臣に昇進した。
清盛は娘の盛子を関白藤原基実の妻としていたが、1166年に基実が死ぬと、その所領を事実上、自分のものとしてしまう。摂関家の権威は失墜し、政治の実権はますます清盛の手に集中した。だが、そのころから、後白河と清盛の関係があやしくなりはじめる。
1168年、清盛は重い病にかかり、出家する。その間、天皇は六条から高倉に代わっている。京都における平家一族の勢力は揺るぎない。
出家後、清盛は摂津の福原に居を構え、大輪田の泊の修築に力を注いでいた。宋から九州にくる商船をこの泊まで引き入れたいと思っていたのだ。
1171年には娘の徳子が高倉天皇の中宮となり、清盛の権力はさらに強まった。だが、平家一門への反発は次第に増していく。後白河の近臣が僧俊寛らとともに平氏打倒の陰謀を企てる。これを察知した清盛は陰謀をつぶすとともに、後白河自身を政治から排除した。
1178年に徳子が高倉天皇の子を産むと、清盛はただちにこれを皇太子に立てた。
1179年には異常な物価騰貴が生じ、京都の民衆が苦しんだ。宋銭があまりに大量に流入したことが原因だった。
後白河は関白基房と手を結び、反撃に転じる。だが、清盛の軍勢に屋敷を取り囲まれ、別荘の鳥羽殿に幽閉された。院政は停止され、清盛が政治権力を完全に掌握した。
1180年、高倉は退位し、清盛の外孫で3歳の皇太子が位を継ぐ(安徳天皇)。反平氏の気運は増すばかりだった。後白河の次男、以仁(もちひと)王が諸国の武士に平氏追討を呼びかける。しかし、計画はすぐに察知され、以仁王と源頼政は宇治で敗死する。
ここで清盛は突然、上皇や天皇を引き連れて、福原への遷都を強行した。
東国では以仁王の呼びかけに応えて、源頼朝が挙兵、続いて頼朝のいとこにあたる義仲が立ち上がった。頼朝は相模の石橋山で平氏軍に完敗する。頼朝はいったん海路で安房に逃げ、そこで態勢を立て直し、武蔵に攻め込み、鎌倉を拠点にした。
肥後や熊野、尾張、美濃でも叛乱が広がる。平氏は頼朝を討つため大軍を送りこむ。だが、富士川の戦いで頼朝軍に敗れた。頼朝はそのまま上洛せず、いったん鎌倉に戻って東国を固めることにした。
清盛はわずか6カ月で、福原を捨てて、平安京に戻った。そして後白河の院政復活を認めることで、危機をしのごうとした。東国との戦争に備えるため、畿内と西国は軍政下に置かれた。だが清盛は1181年閏2月に急死する。そのあと、しばらく源平が対峙する状態が続いた。
事態が動いたのは1183年になってからである。北陸まで勢力を伸ばしていた源(木曽)義仲は、砺波山の倶利伽羅(くりから)峠で平氏軍を撃破し、その勢いで京都に進攻した。平氏一族は京都を捨て、安徳天皇を擁し西国に向かった。
義仲は京都を占拠した。後白河上皇は安徳に代わる天皇として、4歳になるその弟を後鳥羽天皇として即位させた。同時に東国の独立性を認める宣旨を頼朝に送った。
義仲は孤立した。1184年正月、義仲は頼朝が派遣した義経・範頼の大軍と戦い、近江の粟津で敗死した。義経らの軍はその勢いで、平氏を追撃、一ノ谷で平氏を海に追い落とした。義経は屋島の合戦のあと、長門の壇ノ浦で平氏一門を滅亡させる。1185年2月のことである。
だが、頼朝は後白河に接近する義経に疑惑をいだくようになった。両者の対立が激しくなってくる。頼朝は義経を暗殺しようとしたが失敗。これにたいし、義経は後白河から宣旨を得て、西国で頼朝と戦おうとした。だが、これもうまく行かず、けっきょく奥州の藤原秀衡のもとに身を寄せることになった。
頼朝はみずから軍を率いて京に向かい、使者を送って、後白河の裏切りを糾弾し、義経追討に向かった。後白河の周辺は頼朝に近い九条兼実(かねざね)らの公卿によって固められ、朝廷を監視する京都守護が置かれた。
1187年に藤原秀衡(ひでひら)が死ぬと、その子、泰衡は義経を討って、その首を頼朝に送った。だが、頼朝はそれに満足せず、1189年に大軍を送って、平泉の奥州藤原氏を滅ぼした。頼朝は東北に奥州惣奉行、九州に鎮西奉行を置いて、全国にわたる軍事的支配を広げていった。
1190年、頼朝は上洛、後白河から権大納言、右大将に任命されるが、10日後に辞職。鎌倉に戻って、政所を通じて、御家人たちへの所領恩給をおこなった。
1192年、後白河が死に、関白九条兼実の地位が安定し、頼朝も待望の征夷大将軍に任じられた。京都の朝廷と鎌倉の幕府の関係はきわめて円滑になった。
1196年、兼実は失脚。源(土御門)通親(みちちか)が朝廷の実権を握った。だが、京都と鎌倉との関係は変わらない。
1198年、通親の外孫が土御門天皇となり、後鳥羽院政がはじまる。頼朝は自分の娘を後鳥羽の後宮にいれようとしたが、うまく行かない。落馬が原因で、1199年に死んだ。通親は京都における鎌倉勢力の一掃をはかった。
頼朝のあとは頼家が継いだ。だが、有力御家人たちを押さえることができなかった。頼家が頼みとしていた梶原景時も失脚してしまう。
1203年、頼家は征夷大将軍に任じられる。この年、頼家の舅、比企能員(ひきよしかず)が北条時政に殺され、そのとき頼家の長子、一幡(いちまん)も死んだ。有力御家人たちは、頼家を廃して伊豆に流し、頼朝の次男、千幡(実朝)を将軍に立てた。1204年、頼家は伊豆修善寺で暗殺される。
このころ鎌倉の実権を握っていたのは北条時政だ。時政は畠山重忠を謀反の疑いがあるとして誅殺し、さらに将軍実朝を廃して、自身の娘婿、平賀朝雅(ともまさ)を将軍に立てようとした。これを察知した北条政子(頼朝の妻で、頼家・実朝の母)は、朝雅を殺し、父時政を伊豆に流した。
政子がにらみをきかせるなか、北条義時が執権になった。義時と対立していた和田義盛は謀反の疑いをかけられ、滅ぼされる。
源実朝は和歌や蹴鞠を通じて、京都の朝廷に接近していた。宋にあこがれ、宋に渡航する夢さえいだいていた。
1202年に源通親が死んだあと、京都では「治天の君」後鳥羽上皇の力が強くなり、文芸や武芸にも大きな影響をおよぼしていた。『新古今和歌集』が撰されたのもこのころである。
1210年、後鳥羽は土御門を退位させ、順徳を天皇につけた。鎌倉の実朝をも自己の影響下に置き、その存在感を示しそうとしていた。
1219年、実朝が頼家の子、公暁によって暗殺される。北条政子は後鳥羽の子を将軍に迎えようとするが、後鳥羽はこれを拒否。幕府は頼朝とわずかに血のつながっている西園寺公経(きんつね)の外孫で2歳の三寅(九条頼経)を鎌倉に迎え、東国の首長とした。
承久の乱のきっかけは、ごくささいなものだった。後鳥羽が寵愛する白拍子亀菊の所領から地頭を排除するよう鎌倉幕府に求め、これを義時が拒否すると、後鳥羽がいきなり暴力に訴えたのが発端である。
後鳥羽は1221年に順徳を退位させ、その幼い息子を即位させた。そのうえで、朝廷直属の武士などを集めて、京都守護を討ち、諸国に北条義時追討の命を下したのだ。
しかし、北条政子の訴えのもと、東国の御家人たちは北条義時のもとに結集し、京都に向かった。後鳥羽軍と東国軍は木曽川で激突、後鳥羽軍は潰走し、東国軍は近江の瀬戸に引かれた防衛線も突破し、京都になだれ込んだ。
勝利した東国軍は幼い天皇(明治になって仲恭と諡[おくりな]された)を廃し、後鳥羽を隠岐、順徳を佐渡に流し、出家していた後鳥羽の兄を還俗させて後高倉上皇とし、その子を天皇に即位させた(後堀河)。ここで天皇が廃されなかったのが不思議である。
京都の王権は東国の監視下に置かれた。京都を占領した北条義時の子、泰時と、義時の弟、時房はそのまま京都に滞在し、六波羅に探題を設けた。
東国の御家人たちは、地頭として補任された西国の荘園・公領で無法な振る舞いにでた。そのため幕府はそれを規制しないわけにはいかなかった。
1224年、義時が急死し、政子が泰時を執権の地位にすえた。泰時は叔父時房を連署(執権補佐)とし、11人の評定衆を定め、合議と多数決によって、政治を運営することにした。こうして執権政治が確立する。
1230年、未曾有の飢饉が諸国を襲った。とくに京都は惨憺たるありさまになった。幕府はさまざまな対策をとって、これを乗り越えた。
1232年、泰時は関東の基本法として関東御成敗式目を定めた。王朝の律令格式とは別の定めがつくられたことになる。
網野はこう書いている。
〈これはいわば関東は関東、王朝は王朝、すなわち東は東、西は西ともいうべき姿勢を、謙虚ながら確信をもって明らかにしたものであり、ここに独自な法と機構によって、おおよそ三河・信濃・能登以東の東日本に統治権を行使するとともに、従者としての御家人に支えられた鎌倉の将軍、東国の王権を頂点にもつ東国「国家」が、京都の天皇、西国の王権を頂点に西日本を統治する王朝国家と併存しつつ確立したのである。〉
東西を二分し、京都と鎌倉に二つの王権が成立した。日本社会はそれなりに安定した軌道に入った、と網野は記している。
この時代には荘園公領制が定着した。
大田文(おおたぶみ)と呼ばれる田の土地台帳、畠文(はたぶみ)と呼ばれる畠の土地台帳がつくられ、荘園、公領の田や畠の広さ、平民百姓の家屋数なども把握された。
賦課は大田文に記載された田をもとになされた。東西の王権は田地を基本としており、その意味で「農本主義」にもとづいていた、と網野はいう。
天皇家、摂関家、上級貴族は知行国を持っていた。将軍家も東国を中心にいくつかの知行国を持ち、平氏や貴族、武士から没収した荘園や公領を支配下に置いていた。延暦寺、興福寺、伊勢、上下加茂などの大寺社も多くの荘園を抱えていたことを忘れてはならない。
税として徴収されたのは米ばかりではない。各地の特産品が年貢として徴収された。東北では金や馬、東国では絹や綿、西国では米、油、紙、塩、鉄、牛など。畠からも麦、豆、粟、蕎麦などが徴収された。漆や栗、魚貝、わかめなどの海産物、松茸、平茸、柿、胡桃、長芋なども貢納されていた。
網野は同じ荘園・公領でも東と西で大きな違いがあることを強調する。
「西国の荘園・公領は本家を頂点に、領家(国主)、預所(目代)、下司・公文、さらに百姓名の名主などの職が、それぞれ請負、任免の関係をもちつつ重層する『職(しき)の体系』ともいうべき体制によって支配されていた」
東国の荘園・公領の規模は西国よりはるかに大きく、御家人が地頭となって、郡・荘を請け負い、一族や代官を各地に配置していた。西国では東国の地頭への抵抗が強かったという。
この時代の特徴として、網野はさらに、非農業民の広がりと交易の発達をあげている。市場社会が顔をのぞかせはじめている。
製鉄や製塩、製紙、その他数多くの手工業に携わる人びとが増えている。漁撈や水上運輸もそうだ。
米や絹、布が交換手段として用いられていた。市庭(いちば)では、鍋、釜、鎌、鋤、鍬などの鉄製品や陶磁器、小袖、帷子、直垂などの衣類、太刀や弓などの武器も並べられていた。
13世紀前半になると、宋から流入した銭貨が広く流通するようになる。市の開かれる日には、鋳物師、油売、魚貝売、塩売、酒売、小袖売などの商人が市庭に集まってきて商売をはじめた。女性の商人も多かったという。
職能民はもともと朝廷や官、寺社に帰属し、供御人(くごにん)や神人(じにん)、寄人(よりゅうど)などと呼ばれていた。かれらは聖なる者の分身として、各地を放浪しながら交易に従事した。
その代表は鋳物師だが、中には神物としての銭を貸す者も登場した。海上や陸上の要衝に関を設け、関料をとる者は、海賊や山賊、悪党に早変わりした。
13世紀はじめには、商人や金融業者の集まる多くの津や泊が町として発展しはじめる。そこに遊女たちも出入りするようになった。
しかし、年貢物が集まったのは京都、奈良である。このころ洛中南部(下京)には、多くの職能民が住み、酒屋、針磨(はりすり)、銅細工の作業所、借上(金融業者)の仕事をするようになっている。白河には車借(運送業者)が大勢おり、その南の六波羅は武士の拠点となっていた。貴族や官人、寺院の僧侶、商工民、武士、牛飼童、博打、穢れを浄める非人、京都はまさに多くの人びとであふれていた。
東国でも東京湾や利根川などの河川、霞ヶ浦などの湖沼を中心に海上交通が活発になっている。多くの津や泊が生まれ、東海道にはいくつも宿ができていた。こうした海陸の交通網は、鎌倉街道や和賀江の泊などを通じて、鎌倉に収斂していた。
鎌倉には幕府があり、多くの御家人や文筆官人、職能官人が住み、職人や商人も集住していた。ここでは天照大神よりも鶴岡八幡宮、北野社が尊崇され、伊豆山、箱根、三島社、日光などに東国の神々が祭られていた。
鎌倉では宋の文化が積極的に取り入れられていた。頼家も実朝も臨済禅の栄西を通じて、宋にただならぬ関心をいだいた。史書では慈円の『愚管抄』、歌では西行の『山家集』、随筆では鴨長明の『方丈記』が知られる。『平家物語』が生まれたのもこの時代である。
何よりも特筆すべきは仏教界の新しい動きである。法然は山門を離脱し、念仏を唱える易行を唱えた。親鸞は法然の教えを引き継ぎ、悪人正機の思想に行きついた。道元は純粋に禅を求め、越前に永平寺を建てた。明恵上人は法然にきびしい批判を加え、戒律の復興を唱えた。
農業中心の社会ではあったが、商業と金融、交通が発展し、人びとの交流が盛んになりはじめていた。貴族社会と武士政権がせめぎあうなかで、新たな思想や文化が登場するのが、この時代の特徴だ、と網野は論じている。
網野善彦『日本社会の歴史』を読む(6) [歴史]
ここから中巻にはいる。
891年に関白藤原基経が死ぬと、宇多天皇はいわば秘書役ともいえる蔵人頭(くろうどのとう)に菅原道真を登用した。寛平(かんぴょう)の改革がはじまる。中央の綱紀をただすとともに、とどこおりがちな調・庸・官物の貢進を国司にしっかりと請け負わせる体制が固められた。京の治安維持にあたる検非違使庁(けびいしちょう)の強化もはかられた。
897年、宇多は13歳の醍醐に譲位した。2年後、藤原時平が左大臣、菅原道真が右大臣に昇進した。藤原家が常に天皇家外戚の地位を保ち、中央政府の実権を握るという仕組みは変わらない。異例なのは、文人である道真が右大臣にまで昇進したことだった。藤原氏はこれを妬み、あらぬうわさをでっちあげて、道真を排除し、901年に太宰府に左遷した。
翌年、時平は広範な改革に乗りだした。数十年中止されていた班田を12年に1度の割で実施するとし、調・庸の品質向上を命じ、院宮や王臣による荘園の拡大禁止や停止を求めた(最初の荘園整理令)。延喜式の編纂を開始し、907年に延喜通宝を鋳造したのも時平の仕事である。
905年、醍醐天皇は紀貫之らに『古今和歌集』の編纂を命じた。このころ『竹取物語』、『伊勢物語』が生まれている。
907年に時平が若くした死んだときには、菅原道真の怨霊だという話がまことらしく伝えられる。時平の死によって、律令制への復帰がなくなったことは確かだった。これ以降、経済面でも軍事面でも、諸国の国司に責任を請け負わせる体制が進んでいく。
政府は班田の実施をあきらめ、国衙(こくが、地方政庁)のつくった土地台帳をもとに、国司に徴税を請け負わせるようになった。政府への官物納入は安定するようになった。
実際には、国司は地元の有力者を官人として採用し、かれらに徴税をまかせていた。税物の運搬も、梶取(かんどり)や綱丁(ごうちょう)などと称される運送業者にゆだねていた。こうして、任命されても赴任しない国司が増えてくる。
醍醐天皇は政治に危機感をもっていた。廷臣や国司に政治上の問題について意見書を述べさせたり、蔵人所を通じて政治の実情を把握しようとしたりしている。しかし、その関心は畿内に集中しがちだった。
中国では907年に唐が滅亡し、五代の騒乱時代がはじまっていた。中国の北方では渤海が滅び、契丹人が遼を建国していた。朝鮮では新羅が統制力を失おうとしていた。
930年、醍醐は8歳の朱雀に位を譲って死ぬ。時平の弟、藤原忠平(ただひら)が摂政についた。そのころ、京都は不安につつまれていた。清涼殿に雷がおち、それも道真のたたりとうわさされた。醍醐につづいて、上皇の宇多が死ぬ。疫病が流行し、群盗が横行し、瀬戸内海では海賊の活動が盛んになっていた。

[菅原道真。ウィキペディアより]
東国では平将門が939年に常陸の国府を焼いて、国司を捕虜にした。その勢いで、将門は下野、上野の国府を襲い、関東一円をほぼ制圧、みずから新皇と称した。同じ年、伊予の藤原純友も備前や播磨の国司を捕虜にし、瀬戸内海を手中にした。東西の叛乱により、朝廷はこれまでにない危機におちいった。
まもなく将門は平貞盛と藤原秀郷によって討たれ、純友の乱も小野好古、源経基によって鎮定される。しかし、この乱を経て、東国は王朝から離れて自立する傾向を強め、西日本でも海上交通を担う豪族や商人が力をつけていく。
京の町には「市の聖(ひじり)」と呼ばれる空也があらわれる。道真の怨霊を鎮める北野神社が建てられた。天皇が賀茂神社に行幸するのが恒例となり、祇園会が夏の行事となった。
946年、朱雀が退位し、村上が皇位についた。949年に関白忠平が死ぬと、村上は天皇親裁をこころみた。958年には乾元(けんげん)大宝が鋳造される。これ以降、江戸時代まで政府による銅銭鋳造はない。
そのころ右京、すなわち京の西半分は荒れ果て、雑人(ぞうにん)たちが出入りする場所になっていた。朝廷が直接支配するのは、畿内と近江、丹波にかぎられていた。左右の大臣をはじめ、公卿のほとんどは藤原氏と源氏が占めている。貴族の役割は、宮中の年中行事をつつがなくおこなうことだった。
村上が967年に死ぬと、冷泉が天皇になる。冷泉には精神障害があったため、関白の藤原実頼(さねより)が政治を担った。
冷泉の後継をだれにするかは当初から課題になっていた。このあたり天皇家の血統は脈々と受け継がれたというより、何が何でも受け継がされてきたという感じである。けっきょく冷泉の弟が11歳で円融天皇となり(969年)、実頼が摂政についた。
実頼の死後は、甥の伊尹(これまさ)が摂政を継ぎ、自分の外孫にあたる冷泉の子、師貞を皇太子とした。これが花山(かざん)天皇で、984年に即位することになる。
伊尹の死後は、弟の兼通が円融天皇の関白を務めた。だが、兼通が死ぬと、一時は退けられていたその弟の兼家が断然有利な立場に立った。その娘が円融天皇の男子を産んでいたためである。
そのため兼家は縁の薄い花山天皇を、即位後2年で早々と引退させ、その外孫を986年に一条天皇として即位させた。このあたり、藤原家の都合で、皇位が動いている。
兼家は一条天皇の摂政となった。このころから藤原家は摂関家と呼ばれるようになった。外戚として天皇家にとりついたのである。
兼家の息子が藤原道長である。兄の道隆、道兼が疫病で亡くなったあと、道長は姉で一条天皇の母、詮子(あきこ)の斡旋により事実上の関白となった。
道長は娘の彰子を(すでに皇后がいたにもかかわらず)強引に一条天皇の中宮とし、一条死去後、折り合いの悪かった三条天皇を退位させ、一条と彰子のあいだに生まれた外孫を後一条天皇とし、娘の威子(たけこ)を後一条の中宮とした。
書いていて気が遠くなりそうである。「自らの娘に天皇の男子が生まれるか否かが高位の貴族の一族全体の運命を左右していた」と網野は記している。
このころ政治の世界は儀式化し、安定していたともいえる。天皇家があり、摂関家があり、公卿の家があり、下級貴族の家があった。国政は儀式、年中行事で満たされ、貴族たちは家格と役割に応じて、行事を分担した。しかし、やがて、地方に根拠を置いて、武を家業とする者もでてくる。
国司(受領、国守)は任国で大きな権限をもっていた。徴税権、租税免除権、裁判権、軍事権、などである。かれらは都と任国を行き来しながら、行政権を発揮して、徴税請負のネットワークを築き、財を蓄積していくことになる。
この時代にはもともと官司に組みこまれていた人びとが職能民として自立する動きもでてくる。徴税人の下級官人のなかには、貢納物を運用して富を得る者もいた。手工業者、運送業者、山民、海民も自立しはじめる。宮廷を離れ、歌姫や遊女として生きる者もいた。宮廷の双六打(すごろくうち)も博党として活動しはじめる。悲田院に収用されていた孤児や病者は、穢れの浄めを職能とするようになった。さまざまな芸と職が生まれたと網野はいう。もちろん、武芸もそのひとつだった。
天皇家は勅旨田や御厨(みくりや)、御牧(みまき)などの直領をもっていた。それは摂関家も同じで、大貴族の荘園は、やがて全国の要衝に広がっていく。畿内の大寺社も諸国に多くの免田や御厨をもつようになった。
藤原道長、頼通親子の時代、都には諸国から多様な物産が集まり、華やかな文化が花開いた。朝廷自体は対外関係に消極的だったが、宋や高麗の商船は年々来航するようになった。そのいっぽう、都の周辺では、群盗が横行し、疫病や天災があふれていた。各地の紛争もしばしば生じている。

[藤原道長。ウィキペディアより]
1027年、藤原道長は念仏を唱えながら世を去る。その翌年、東国の平忠常が乱を起こし、房総半島一帯を支配下におく。その支配は3年に及んだ。この乱は、国司(受領)の支配が豪族の力を無視しえなくなったことを意味している、と網野はいう。東国や西日本では、徴税を請け負いながら、地方に根を張る「弓馬の道」にたけた豪族が力を増していた。このころから国守(国司)と豪族の争い、豪族どうしの争いが増えてくる。
1045年、関白藤原頼通のもと、後朱雀に代わり後冷泉が即位する。朝廷は荘園整理令を発した。荘園の整理はごく限られていた。それは、むしろ豪族や有力者の田畠支配を実質上認めるものだった。
1051年、安倍頼時と貞任(さだとう)の父子が、国守の軍勢を撃破して、陸奥国を手中にした。これも地方での豪族台頭のあらわれだった。源頼義が陸奥守として着任すると、いったん事態は収拾したものの、1056年に両者は激突、安倍頼時は戦死したものの、息子の貞任は屈服せず、戦争は長期にわたった。
この叛乱(前九年の役)が収まるのは、政府側がもうひとりの豪族、清原武則を引き入れ、ようやく貞任を討ちとったときである(1062年)。だが、それによって東北一帯での清原氏の力が強くなった。
1068年には後冷泉が死に、壮年の後三条が天皇に即位した。後三条の母は藤原氏の出身ではなかった。後三条は摂関家との緊張関係のなかで、天皇家の権威再確立と経済的基盤強化をはかった。大胆な荘園整理と荘園の実態把握に努め、国守(受領)の権限を制約しようとしている。寺社と天皇家との関係強化もはかられた。
「後三条の新政を契機にして、朝廷の主導権は天皇家に移り、摂関家の発言権は低下する」と、網野は記している。後三条の即位は、摂関政治からの離脱を促す転換点となった。
1072年、後三条は上皇となり、白河が即位する。だが、翌年、後三条は世を去り、藤原頼通も死ぬ。白河は関白藤原師実(もろざね)と后の父源顕房に支えられながら、後三条の新政を継承していった。
白河は行幸を実施したり、殿上で歌合を催したりして、儀式・行事の主催者としての天皇の立場を鮮明にしていった。荘園の増加を抑えるための荘園整理令を発するのは、もはや恒例となっていた。そのころ、宋や高麗との交流も活発になる。洛北白河には法勝寺が建てられた。御所の警備は源義家、義綱兄弟にゆだねられるようになった。

[白河天皇。ウィキペディアより]
1083年、義家は陸奥守として東北に下った。義家は清原氏の内紛に介入、藤原清衡(きよひら)を助けて、清原家衡を討った。後三年の役と呼ばれる戦いである。
これにより奥羽は奥州藤原氏の支配下にはいる。いっぽう義家とともに戦った弟の義光は関東に根をおろし、東国に源氏の勢力を築いていく。
1086年、白河は子(堀河)に位を譲り、上皇として朝政の実権を握った。院政のはじまりである。院のまわりには有力貴族や武人が集められた。二重権力が生まれようとしている。
そのころ社会は流動化していた。商工民や職能民の動きが活発になり、東国では絹・布、西国では米を物品貨幣とする流通が盛んになり、借上(かしあげ)と呼ばれる金融業者も登場する。摂関家などの貴族、大寺社も多くの荘園をもつようになり、そうした荘園からは米だけでなく、絹や布、鉄、塩、紙などが納められていた。名のある武将にも、多くの田畠が寄進されるようになった。
諸国の国衙(地方政庁)も役所としての機能を整えていた。上級貴族はみずからの子弟を国守に推挙し、その知行による利益を確保した。国守が任地におもむくことは少なくなり、目代(もくだい)を送って、現地の役所での徴税をおこなうのが一般的になった。
大寺社の活発な動きが、朝廷や国衙を揺るがすことが多くなる。「悪僧」と呼ばれた僧兵たちは、しばしば強訴をくり返していた。
牛飼童(うしかいわらわ)、博打、京童などの運送業者、非人は、祇園会や賀茂祭などで、しばしば乱闘をおこした。熊野や吉野、高野山、岩清水などへの参拝が盛んになっている。江口や神崎などの津や泊には、遊女たちが集まっていた。田楽がはやり、白河上皇も新たに建てた鳥羽殿などで、田楽を催している。
1096年、白河は出家して法皇となった。1107年に堀河が死ぬと、白河はわずか5歳の子を立て、鳥羽天皇とした。藤原忠実(ただざね)が鳥羽の摂政となるが、摂関家にはもはやかつての力はなく、実質上、白河の専制がつづいていた。
1099年に白河は荘園を新たに立てることを禁止した。1111年には荘園の記録所を設置した。荘園と公領の区分を明確にすることが目的だった。国司と荘園所有者との紛争を調停する姿勢も示している。あくまでも荘園の増加を抑えるという原則は変えなかったといえる。
このころ、鴨川はしばしば氾濫している。それをとめる手だてはなかった。しかし、さすがに僧侶の勝手な振る舞いは取り締まるようになった。検非違使(けびいし)には、源平の武者が採用された。そのころ伊勢平氏は白河に接近し、瀬戸内海に勢力を伸ばしている。
1123年、白河は鳥羽を退位させ、その子を崇徳天皇とした。だが、白河が1129年に77歳で死ぬと、今度は鳥羽が上皇として、徹底した院政をおこなうこととなる。鳥羽は崇徳が自分の子ではなく、白河の子だと思っていた。
鳥羽は白河以上に人事権をもち、白河時代の近臣を退け、関白の座を追われた藤原忠実を朝廷に復帰させた。とはいえ、このころの官位はほとんど世襲化しつつある。鳥羽はそれを承認することによって、官人をみずからの意志にしたがわせた。
鳥羽は白河とはことなり、荘園の拡大を容認した。そのため、天皇家はじめ、摂関家、寺社、国守自身も積極的に荘園を拡大した。そのいっぽう、国衙は公領の確保につとめたため、国衙と荘園所有者のあいだで、よく紛争が巻き起こった。
ここに「荘園公領制」という土地制度が形成される。各地の有力者や豪族、武将などは公領、あるいは荘園の管理をゆだねられながら、みずからの実力をたくわえていった。
網野が金融のはじまりを寺社にみているところがおもしろい。たとえば、延暦寺の山僧は、荘園の仏物を資本として、これを貸し付け、利を得ていた。日吉社の大津神人や熊野社の神人は、神物である初穂を融通し、借上を業として富を積んだ。
山僧や神人のなかには、手工業や水上交通に従事する者もいた。要するに、寺社は市場経済のひとつの淵源だったのである。
供御人(くごにん)などの職能民も朝廷や国衙に奉仕しつつ、課役や税を免除され、次第にその活動領域を広げていた。
鳥羽上皇に積極的に接近したのが伊勢平氏である。平正盛の子、忠盛は鳥羽上皇のために三十三間堂の造営を請け負い、1132年にこれを完成させている。1135年には、瀬戸内海の海賊を追討し、備前守となって、瀬戸内海沿岸の勢力を固めた。平氏の築いた海の道からは、宋の文物が数多くもたらされた。
いっぽう、後三年の役のあと奥羽の覇者となった奥州藤原氏は平泉に拠点を築き、1126年に清衡(きよひら)が中尊寺を完成させ、つづいて基衡が毛越寺(もおつじ)を建立した。奥州藤原氏は摂関家との結びつきを深め、摂関家に金や馬、北方の産物などを貢納していた。
このころ東国の河内源氏は、源義家の死後、一族の内紛によって京では平氏に押され気味だった。それでも摂関家との結びつきを忘れることはなかった。源為義の子義朝は、東国の豪族などと主従の関係を結びながら、下総、武蔵、相模に拠点を築いていた。
京では寺社の神人や悪僧たちが、何かと武力に訴え、朝廷に波紋を投げかけていた。
1141年、鳥羽上皇は険悪な関係となっていた崇徳天皇に譲位を迫り、みずからの3歳の男子を即位させ、近衛天皇とした。摂関家は跡目相続でもめ、力を失っている。
1155年、近衛天皇が17歳で死ぬと、鳥羽はみずからの第4子を後白河天皇とし、後白河の子を皇太子とした。摂関家の藤原頼長は元天皇の崇徳と結びつき、朝廷は一触即発の事態となった。
1156年7月、鳥羽上皇は死去し、その専制政治は終わりを告げた。しかし、事態はそこから動いていくのだ。
891年に関白藤原基経が死ぬと、宇多天皇はいわば秘書役ともいえる蔵人頭(くろうどのとう)に菅原道真を登用した。寛平(かんぴょう)の改革がはじまる。中央の綱紀をただすとともに、とどこおりがちな調・庸・官物の貢進を国司にしっかりと請け負わせる体制が固められた。京の治安維持にあたる検非違使庁(けびいしちょう)の強化もはかられた。
897年、宇多は13歳の醍醐に譲位した。2年後、藤原時平が左大臣、菅原道真が右大臣に昇進した。藤原家が常に天皇家外戚の地位を保ち、中央政府の実権を握るという仕組みは変わらない。異例なのは、文人である道真が右大臣にまで昇進したことだった。藤原氏はこれを妬み、あらぬうわさをでっちあげて、道真を排除し、901年に太宰府に左遷した。
翌年、時平は広範な改革に乗りだした。数十年中止されていた班田を12年に1度の割で実施するとし、調・庸の品質向上を命じ、院宮や王臣による荘園の拡大禁止や停止を求めた(最初の荘園整理令)。延喜式の編纂を開始し、907年に延喜通宝を鋳造したのも時平の仕事である。
905年、醍醐天皇は紀貫之らに『古今和歌集』の編纂を命じた。このころ『竹取物語』、『伊勢物語』が生まれている。
907年に時平が若くした死んだときには、菅原道真の怨霊だという話がまことらしく伝えられる。時平の死によって、律令制への復帰がなくなったことは確かだった。これ以降、経済面でも軍事面でも、諸国の国司に責任を請け負わせる体制が進んでいく。
政府は班田の実施をあきらめ、国衙(こくが、地方政庁)のつくった土地台帳をもとに、国司に徴税を請け負わせるようになった。政府への官物納入は安定するようになった。
実際には、国司は地元の有力者を官人として採用し、かれらに徴税をまかせていた。税物の運搬も、梶取(かんどり)や綱丁(ごうちょう)などと称される運送業者にゆだねていた。こうして、任命されても赴任しない国司が増えてくる。
醍醐天皇は政治に危機感をもっていた。廷臣や国司に政治上の問題について意見書を述べさせたり、蔵人所を通じて政治の実情を把握しようとしたりしている。しかし、その関心は畿内に集中しがちだった。
中国では907年に唐が滅亡し、五代の騒乱時代がはじまっていた。中国の北方では渤海が滅び、契丹人が遼を建国していた。朝鮮では新羅が統制力を失おうとしていた。
930年、醍醐は8歳の朱雀に位を譲って死ぬ。時平の弟、藤原忠平(ただひら)が摂政についた。そのころ、京都は不安につつまれていた。清涼殿に雷がおち、それも道真のたたりとうわさされた。醍醐につづいて、上皇の宇多が死ぬ。疫病が流行し、群盗が横行し、瀬戸内海では海賊の活動が盛んになっていた。

[菅原道真。ウィキペディアより]
東国では平将門が939年に常陸の国府を焼いて、国司を捕虜にした。その勢いで、将門は下野、上野の国府を襲い、関東一円をほぼ制圧、みずから新皇と称した。同じ年、伊予の藤原純友も備前や播磨の国司を捕虜にし、瀬戸内海を手中にした。東西の叛乱により、朝廷はこれまでにない危機におちいった。
まもなく将門は平貞盛と藤原秀郷によって討たれ、純友の乱も小野好古、源経基によって鎮定される。しかし、この乱を経て、東国は王朝から離れて自立する傾向を強め、西日本でも海上交通を担う豪族や商人が力をつけていく。
京の町には「市の聖(ひじり)」と呼ばれる空也があらわれる。道真の怨霊を鎮める北野神社が建てられた。天皇が賀茂神社に行幸するのが恒例となり、祇園会が夏の行事となった。
946年、朱雀が退位し、村上が皇位についた。949年に関白忠平が死ぬと、村上は天皇親裁をこころみた。958年には乾元(けんげん)大宝が鋳造される。これ以降、江戸時代まで政府による銅銭鋳造はない。
そのころ右京、すなわち京の西半分は荒れ果て、雑人(ぞうにん)たちが出入りする場所になっていた。朝廷が直接支配するのは、畿内と近江、丹波にかぎられていた。左右の大臣をはじめ、公卿のほとんどは藤原氏と源氏が占めている。貴族の役割は、宮中の年中行事をつつがなくおこなうことだった。
村上が967年に死ぬと、冷泉が天皇になる。冷泉には精神障害があったため、関白の藤原実頼(さねより)が政治を担った。
冷泉の後継をだれにするかは当初から課題になっていた。このあたり天皇家の血統は脈々と受け継がれたというより、何が何でも受け継がされてきたという感じである。けっきょく冷泉の弟が11歳で円融天皇となり(969年)、実頼が摂政についた。
実頼の死後は、甥の伊尹(これまさ)が摂政を継ぎ、自分の外孫にあたる冷泉の子、師貞を皇太子とした。これが花山(かざん)天皇で、984年に即位することになる。
伊尹の死後は、弟の兼通が円融天皇の関白を務めた。だが、兼通が死ぬと、一時は退けられていたその弟の兼家が断然有利な立場に立った。その娘が円融天皇の男子を産んでいたためである。
そのため兼家は縁の薄い花山天皇を、即位後2年で早々と引退させ、その外孫を986年に一条天皇として即位させた。このあたり、藤原家の都合で、皇位が動いている。
兼家は一条天皇の摂政となった。このころから藤原家は摂関家と呼ばれるようになった。外戚として天皇家にとりついたのである。
兼家の息子が藤原道長である。兄の道隆、道兼が疫病で亡くなったあと、道長は姉で一条天皇の母、詮子(あきこ)の斡旋により事実上の関白となった。
道長は娘の彰子を(すでに皇后がいたにもかかわらず)強引に一条天皇の中宮とし、一条死去後、折り合いの悪かった三条天皇を退位させ、一条と彰子のあいだに生まれた外孫を後一条天皇とし、娘の威子(たけこ)を後一条の中宮とした。
書いていて気が遠くなりそうである。「自らの娘に天皇の男子が生まれるか否かが高位の貴族の一族全体の運命を左右していた」と網野は記している。
このころ政治の世界は儀式化し、安定していたともいえる。天皇家があり、摂関家があり、公卿の家があり、下級貴族の家があった。国政は儀式、年中行事で満たされ、貴族たちは家格と役割に応じて、行事を分担した。しかし、やがて、地方に根拠を置いて、武を家業とする者もでてくる。
国司(受領、国守)は任国で大きな権限をもっていた。徴税権、租税免除権、裁判権、軍事権、などである。かれらは都と任国を行き来しながら、行政権を発揮して、徴税請負のネットワークを築き、財を蓄積していくことになる。
この時代にはもともと官司に組みこまれていた人びとが職能民として自立する動きもでてくる。徴税人の下級官人のなかには、貢納物を運用して富を得る者もいた。手工業者、運送業者、山民、海民も自立しはじめる。宮廷を離れ、歌姫や遊女として生きる者もいた。宮廷の双六打(すごろくうち)も博党として活動しはじめる。悲田院に収用されていた孤児や病者は、穢れの浄めを職能とするようになった。さまざまな芸と職が生まれたと網野はいう。もちろん、武芸もそのひとつだった。
天皇家は勅旨田や御厨(みくりや)、御牧(みまき)などの直領をもっていた。それは摂関家も同じで、大貴族の荘園は、やがて全国の要衝に広がっていく。畿内の大寺社も諸国に多くの免田や御厨をもつようになった。
藤原道長、頼通親子の時代、都には諸国から多様な物産が集まり、華やかな文化が花開いた。朝廷自体は対外関係に消極的だったが、宋や高麗の商船は年々来航するようになった。そのいっぽう、都の周辺では、群盗が横行し、疫病や天災があふれていた。各地の紛争もしばしば生じている。

[藤原道長。ウィキペディアより]
1027年、藤原道長は念仏を唱えながら世を去る。その翌年、東国の平忠常が乱を起こし、房総半島一帯を支配下におく。その支配は3年に及んだ。この乱は、国司(受領)の支配が豪族の力を無視しえなくなったことを意味している、と網野はいう。東国や西日本では、徴税を請け負いながら、地方に根を張る「弓馬の道」にたけた豪族が力を増していた。このころから国守(国司)と豪族の争い、豪族どうしの争いが増えてくる。
1045年、関白藤原頼通のもと、後朱雀に代わり後冷泉が即位する。朝廷は荘園整理令を発した。荘園の整理はごく限られていた。それは、むしろ豪族や有力者の田畠支配を実質上認めるものだった。
1051年、安倍頼時と貞任(さだとう)の父子が、国守の軍勢を撃破して、陸奥国を手中にした。これも地方での豪族台頭のあらわれだった。源頼義が陸奥守として着任すると、いったん事態は収拾したものの、1056年に両者は激突、安倍頼時は戦死したものの、息子の貞任は屈服せず、戦争は長期にわたった。
この叛乱(前九年の役)が収まるのは、政府側がもうひとりの豪族、清原武則を引き入れ、ようやく貞任を討ちとったときである(1062年)。だが、それによって東北一帯での清原氏の力が強くなった。
1068年には後冷泉が死に、壮年の後三条が天皇に即位した。後三条の母は藤原氏の出身ではなかった。後三条は摂関家との緊張関係のなかで、天皇家の権威再確立と経済的基盤強化をはかった。大胆な荘園整理と荘園の実態把握に努め、国守(受領)の権限を制約しようとしている。寺社と天皇家との関係強化もはかられた。
「後三条の新政を契機にして、朝廷の主導権は天皇家に移り、摂関家の発言権は低下する」と、網野は記している。後三条の即位は、摂関政治からの離脱を促す転換点となった。
1072年、後三条は上皇となり、白河が即位する。だが、翌年、後三条は世を去り、藤原頼通も死ぬ。白河は関白藤原師実(もろざね)と后の父源顕房に支えられながら、後三条の新政を継承していった。
白河は行幸を実施したり、殿上で歌合を催したりして、儀式・行事の主催者としての天皇の立場を鮮明にしていった。荘園の増加を抑えるための荘園整理令を発するのは、もはや恒例となっていた。そのころ、宋や高麗との交流も活発になる。洛北白河には法勝寺が建てられた。御所の警備は源義家、義綱兄弟にゆだねられるようになった。

[白河天皇。ウィキペディアより]
1083年、義家は陸奥守として東北に下った。義家は清原氏の内紛に介入、藤原清衡(きよひら)を助けて、清原家衡を討った。後三年の役と呼ばれる戦いである。
これにより奥羽は奥州藤原氏の支配下にはいる。いっぽう義家とともに戦った弟の義光は関東に根をおろし、東国に源氏の勢力を築いていく。
1086年、白河は子(堀河)に位を譲り、上皇として朝政の実権を握った。院政のはじまりである。院のまわりには有力貴族や武人が集められた。二重権力が生まれようとしている。
そのころ社会は流動化していた。商工民や職能民の動きが活発になり、東国では絹・布、西国では米を物品貨幣とする流通が盛んになり、借上(かしあげ)と呼ばれる金融業者も登場する。摂関家などの貴族、大寺社も多くの荘園をもつようになり、そうした荘園からは米だけでなく、絹や布、鉄、塩、紙などが納められていた。名のある武将にも、多くの田畠が寄進されるようになった。
諸国の国衙(地方政庁)も役所としての機能を整えていた。上級貴族はみずからの子弟を国守に推挙し、その知行による利益を確保した。国守が任地におもむくことは少なくなり、目代(もくだい)を送って、現地の役所での徴税をおこなうのが一般的になった。
大寺社の活発な動きが、朝廷や国衙を揺るがすことが多くなる。「悪僧」と呼ばれた僧兵たちは、しばしば強訴をくり返していた。
牛飼童(うしかいわらわ)、博打、京童などの運送業者、非人は、祇園会や賀茂祭などで、しばしば乱闘をおこした。熊野や吉野、高野山、岩清水などへの参拝が盛んになっている。江口や神崎などの津や泊には、遊女たちが集まっていた。田楽がはやり、白河上皇も新たに建てた鳥羽殿などで、田楽を催している。
1096年、白河は出家して法皇となった。1107年に堀河が死ぬと、白河はわずか5歳の子を立て、鳥羽天皇とした。藤原忠実(ただざね)が鳥羽の摂政となるが、摂関家にはもはやかつての力はなく、実質上、白河の専制がつづいていた。
1099年に白河は荘園を新たに立てることを禁止した。1111年には荘園の記録所を設置した。荘園と公領の区分を明確にすることが目的だった。国司と荘園所有者との紛争を調停する姿勢も示している。あくまでも荘園の増加を抑えるという原則は変えなかったといえる。
このころ、鴨川はしばしば氾濫している。それをとめる手だてはなかった。しかし、さすがに僧侶の勝手な振る舞いは取り締まるようになった。検非違使(けびいし)には、源平の武者が採用された。そのころ伊勢平氏は白河に接近し、瀬戸内海に勢力を伸ばしている。
1123年、白河は鳥羽を退位させ、その子を崇徳天皇とした。だが、白河が1129年に77歳で死ぬと、今度は鳥羽が上皇として、徹底した院政をおこなうこととなる。鳥羽は崇徳が自分の子ではなく、白河の子だと思っていた。
鳥羽は白河以上に人事権をもち、白河時代の近臣を退け、関白の座を追われた藤原忠実を朝廷に復帰させた。とはいえ、このころの官位はほとんど世襲化しつつある。鳥羽はそれを承認することによって、官人をみずからの意志にしたがわせた。
鳥羽は白河とはことなり、荘園の拡大を容認した。そのため、天皇家はじめ、摂関家、寺社、国守自身も積極的に荘園を拡大した。そのいっぽう、国衙は公領の確保につとめたため、国衙と荘園所有者のあいだで、よく紛争が巻き起こった。
ここに「荘園公領制」という土地制度が形成される。各地の有力者や豪族、武将などは公領、あるいは荘園の管理をゆだねられながら、みずからの実力をたくわえていった。
網野が金融のはじまりを寺社にみているところがおもしろい。たとえば、延暦寺の山僧は、荘園の仏物を資本として、これを貸し付け、利を得ていた。日吉社の大津神人や熊野社の神人は、神物である初穂を融通し、借上を業として富を積んだ。
山僧や神人のなかには、手工業や水上交通に従事する者もいた。要するに、寺社は市場経済のひとつの淵源だったのである。
供御人(くごにん)などの職能民も朝廷や国衙に奉仕しつつ、課役や税を免除され、次第にその活動領域を広げていた。
鳥羽上皇に積極的に接近したのが伊勢平氏である。平正盛の子、忠盛は鳥羽上皇のために三十三間堂の造営を請け負い、1132年にこれを完成させている。1135年には、瀬戸内海の海賊を追討し、備前守となって、瀬戸内海沿岸の勢力を固めた。平氏の築いた海の道からは、宋の文物が数多くもたらされた。
いっぽう、後三年の役のあと奥羽の覇者となった奥州藤原氏は平泉に拠点を築き、1126年に清衡(きよひら)が中尊寺を完成させ、つづいて基衡が毛越寺(もおつじ)を建立した。奥州藤原氏は摂関家との結びつきを深め、摂関家に金や馬、北方の産物などを貢納していた。
このころ東国の河内源氏は、源義家の死後、一族の内紛によって京では平氏に押され気味だった。それでも摂関家との結びつきを忘れることはなかった。源為義の子義朝は、東国の豪族などと主従の関係を結びながら、下総、武蔵、相模に拠点を築いていた。
京では寺社の神人や悪僧たちが、何かと武力に訴え、朝廷に波紋を投げかけていた。
1141年、鳥羽上皇は険悪な関係となっていた崇徳天皇に譲位を迫り、みずからの3歳の男子を即位させ、近衛天皇とした。摂関家は跡目相続でもめ、力を失っている。
1155年、近衛天皇が17歳で死ぬと、鳥羽はみずからの第4子を後白河天皇とし、後白河の子を皇太子とした。摂関家の藤原頼長は元天皇の崇徳と結びつき、朝廷は一触即発の事態となった。
1156年7月、鳥羽上皇は死去し、その専制政治は終わりを告げた。しかし、事態はそこから動いていくのだ。
網野善彦『日本社会の歴史』を読む(5) [歴史]
天皇の位は血統によって継承される。継承に決まりがあったわけではない。そこに政治の意志がはたらく。
持統上皇は702年に死ぬ。文武天皇は病弱だった。だが、朝廷の実力者、藤原不比等(ふひと)の娘とのあいだで生まれた首(おびと)皇子が、いずれは天皇になると目されていた。
文武は707年に病死し、首皇子が即位するまでの中継ぎとして、文武天皇の母が元明天皇として即位した。藤原氏の血をひく首皇子が天皇になることに、天皇一族や貴族のあいだから強い反発があったことも影響している。
そのころ日本では天災や疫病がつづき、社会不安が増大していた。不比等はこの危機を減税や綱紀粛正によって乗り越えた。
708年、武蔵から銅が献上されたのを機に、2番目の貨幣、和同開珎(かいちん)が鋳造される。最初の富本銭に儀礼的色彩が強かったのにたいし、和同開珎は本格的な流通貨幣となった。
710年、都は平城京に移される。奈良の都である。
ヤマト政権は勢力を拡大していた。712年には蝦夷を討って日本海側に出羽国をつくり、713年には隼人を討って南九州に大隅国をたてた。
712年には『古事記』が完成する(『日本書紀』は720年)。そのころ、平城京には新羅の使節がたびたび訪れ、日本も唐につぎつぎと遣唐使を派遣していた。
714年に元明は退位し、その娘で文武の姉にあたる元正が天皇となり、首皇子が皇太子となった。藤原不比等にとって、本命はあくまでも藤原家の血をひく首皇子である。不比等は娘の安宿媛(あすかべひめ、のちの光明皇后)を首皇子の妃に送りこんだ。
社会不安が収まらないなか、不比等は律令制を維持し、これに違反する者の取り締まりを強化した。逃散する平民や乞食(こつじき)僧も厳しく処罰した。大宝律令はやがて養老律令へと改正される。しかし、律令制への反発は根強いものがあった。
720年に不比等が死ぬと、天武の孫にあたる長屋王が大きな力をもつようになる。長屋王は律令制の緩和をはかり、豪族や富豪による私的な水田開発を認めた。
722年に元明上皇が死に、724年に元正天皇が退位し、首皇子がようやく即位した(聖武天皇)。光明子とのあいだに生まれた男子は夭折する。藤原氏の野望はついえたが、新たな目標は長屋王追い落としに向けられた。729年、長屋王は謀反の疑いをかけられ、自殺する。その後、藤原4兄弟(武智麻呂、房前、宇合[うまかい]、麻呂)は政権の中枢を握り、光明子を皇后にたてることに成功した。4兄弟はそれぞれ藤原の南家、北家、式家、京家の祖となる。
藤原氏の政府は、律令制を引き締めようとしたが、とりわけ班田制にたいする世間の反発は強かった。諸国に盗賊や海賊が出没し、遊行僧のまわりに人びとが集まった。こうした不穏な風潮にたいし、政府は宥和策と強硬策の組み合わせで臨んだ。
各地では天災と飢饉が相次いでおこった。735年ころから天然痘が流行する。737年には天然痘によって藤原4兄弟が死に、藤原政権は一気に崩壊した。
このときヤマト政権の再建につとめたのが、光明皇后の異父兄、橘諸兄(たちばなのもろえ)である。諸兄は貴族や豪族の規律をただし、東国の防人を郷里に帰すなどして、大胆な負担軽減策を実施した。
738年、聖武天皇は光明皇后とのあいだに生まれた娘、阿倍内親王を皇太子とし、唐から戻った吉備真備らを重用した。
こうした動きにたいし、九州に左遷されていた藤原広嗣(ひろつぐ、宇合の子)が反発し、740年に叛乱をおこした。だが、まもなく鎮圧される。
741年、聖武は諸国に国分寺建立の詔(みことのり)を発する。ここに仏教は鎮護国家の宗教として、大きな力をもつようになった。
743年、墾田永年私財法がだされる。これまでの班田収受の法をあらため、貴族や豪族、寺院が開発した水田を一定限度で私財化することを認めるものだった。
聖武天皇はこのころ紫香楽(しがらき)の離宮や難波宮を転々としていた。5年ぶりに平城宮に戻ったのは、大仏建立のめどがついたからだ。
748年、聖武は退位し、娘の孝謙が即位する。このころ、藤原家はふたたび力を取り戻し、橘諸兄は孤立を深めていた。752年、大仏が完成し、開眼供養がおこなわれた。仏教はいよいよ鎮護国家の宗教という側面を強めていた。
756年、橘諸兄が官を辞し、聖武上皇も世を去ると、藤原仲麻呂が朝廷の実権を握った。仲麻呂は聖武の定めた皇太子を廃し、みずからに近い大炊王(おおいおう)を皇太子とし、祖父不比等の養老律令をふたたび実施し、班田制の立て直しにつとめた。
仲麻呂に反対してきた橘奈良麻呂はクーデターを計画するが、事前に知られ、処刑された。
758年、大炊王が天皇になると(淳仁)、仲麻呂には恵美押勝(えみのおしかつ)の姓名が与えられた。760年、押勝は太上大臣になる。だが、この年、後見人の光明皇太后を亡くなる。
上皇となった孝謙が道鏡と親しくなり、政治に介入しはじめると、押勝との対立が激しくなった。押勝は次第に追い詰められ、764年に軍事的実権を握ろうとして立ち上がるが、先手を打たれて殺された。
天皇は廃され(淳仁の諡号を送られたのは明治になってから)、孝謙がふたたび天皇(称徳)の位につき、道鏡を僧形のまま太政大臣に任じた。女帝はさらに道鏡を天皇にしようとした。だが、和気清麻呂によって阻止された。
770年、称徳が死に、道鏡は追放され、天智の孫、白壁王が天皇(光仁)となる。光仁は百済王の血統をもつ高野新笠(たかのにいがさ)とのあいだに生まれた山部(やまべ)親王を皇太子とした(のちの桓武)。天武の血統は徹底して退けられた。
8世紀にヤマト政権は東北北部に勢力をひろげた。
北海道では、漁撈を中心に、採集、狩猟、農耕を組み合わせた擦文(さつもん)文化の時代がはじまっていた。
渤海は727年から10世紀にいたるまで日本に使者を送り、日本も13回にわたって遣渤海使を送っている。
日本と新羅との関係は険悪になっていた。そのため、日本が遣唐使を送る場合は、朝鮮半島沿いではなく南シナ海を横断するルートをとり、多くの遭難を招いていた。
国府や国分寺を通じて、中国風・仏教風の文化が各地に浸透たことはまちがいない。それでも網野によれば、「平民の生活そのものに根ざした習俗はそれによって変容されつつも根強く生きつづけ、支配者自身に影響を与えて」いた。
さらに、網野は市の重要性を論じる。
〈こうした、人の力の及ばぬ自然、神仏の世界と人間の世界との境界として、河原、中洲、浜や巨木の立つ場所に、人びとは市を立てた。そこは神の力の及ぶ場であり、世俗の人と人、人と物の結びつきが切れるとされており、人びとはそこに物を投げ入れることによって、これを商品として交換しうる物とした。共同体をこえて人びとは市庭(いちば)に集まり、畿内周辺では銭貨も用いたが、米・布・絹などを主な交換手段として、交易を活発に行った。またそこでは神を喜ばせる芸能が行われるとともに、世俗の夫婦・親子の関係も切れるとされており、「歌垣」という歌をともなった男女の自由な性交渉も行われたといわれている。〉
このあたり、網野史学ならではの記述である。
国家の統制は市にまではおよばなかった。市では、多くの女性が商業や金融の仕事を担っていた。8世紀半ばには、海上・湖上の交通を利用し、広域にわたって活動する商人も登場した。
国家は都と各地を結ぶ直線道路をつくり、これによって国司や官人を派遣するとともに、民衆に調や庸を運ばせていた。しかし、8世紀後半にはこうした官道はすたれはじめ、9世紀になると自然の道や海路が復活してくる。
国家による負担が、多くの平民を苦しめていた。その負担から逃れようとして、逃げだす者も増えていた。かれらは畿内の貴族や寺社、富豪に身を寄せるようになる。
墾田永年私財法が出されると、大寺院や上層貴族たちは、未開地に荘を設け、富豪や有力者の助けを借りて、土地開発をおこなった。それが荘園となった。
天智系の新王朝を開いた光仁天皇には、道鏡時代の混乱を収拾する役割が課されていた。だが、社会はいっこうに安定しなかった。
774年には陸奥で叛乱が発生し、これが38年間つづくことになる。780年には、陸奥の郡司、伊治公呰麻呂(いじのきみあざまろ)が立ち上がり、胆沢(いさわ)での築城を阻止し、多賀城を焼いた。
そのさなか光仁は亡くなり、桓武が即位した。782年、桓武は反対派の天武系皇族を謀反の疑いで流罪に処し、これにより天武系の血統は完全に途絶えた。

[桓武天皇。ウィキペディアより]
桓武は天智の定めた法で統治すると宣言し、藤原氏北家の左大臣藤原魚名(うおな)を排除し、藤原氏南家を中心に朝廷を組織した。
784年にはいきなり山背国(やましろのくに)の長岡に遷都した。長岡周辺には、秦氏出身の母と同じ朝鮮半島からの移住民が多かったという。新都の建設は、それらの人びとの協力によって進められた。
長岡京の建設には、それを指揮した藤原種継が暗殺されるなど、暗雲がただよっていた。だが、桓武は早良(さわら)親王ら反対派を粛清し、新都建設を続行する。
788年には東北の乱を収めるため、5万の大軍を派遣した。だが、北上川で首長阿弖流為(あてるい)の反撃にあい、あっけなく敗北。それでも桓武はあきらめず、東北攻略を進めていった。
791年には征夷大使に大伴弟麻呂(おとまろ)、副使に坂上田村麻呂を任じた。それまでの平民軍団に代わって、選抜された強力な軍団が組織され、794年、東北に10万の軍が投入された。
そのころ都の周辺では凶事が相次いでいた。飢饉と疫病が広がり、桓武の母や皇后まで死亡し、皇太子まで病気で倒れた。早良親王の怨霊だといううわさまで広がって、桓武はついに長岡京を放棄した。
新しい候補地はすぐに見つかった。793年に桓武は山背国の宇太(うだ)に遷都すると発表、翌年、みずからその地に移り住んだ。山背国は山城国とあらためられ、新都は平安京と名づけられた。
そこに東北の坂上田村麻呂が圧勝したという知らせが伝わる。796年には新銭として隆平永宝が鋳造され、翌年には『続日本紀』が完成した。
797年、坂上田村麻呂は征夷大将軍に任じられ、801年にふたたび東北に侵攻、アテルイを投降に追いこんだ。アテルイは都に連行され斬られた。それで東北の動揺がおさまったわけでなかった。
桓武は平安京に仏教の新しい風を吹きこもうとしていた。804年、最澄と空海が唐に送られた。最澄は翌年帰国して天台宗を開き、さらにその1年後、空海が密教の教えを携えて戻った。
東北での戦争と新都の建設は民衆に多くの負担を強いていた。桓武の独裁にたいする貴族の反発も強まっていた。そうしたさなか、806年に桓武は70歳で生涯を閉じることになる。
桓武の位を継いだ平城(へいぜい)天皇は、藤原南家を後ろ盾とする異母弟の伊予親王を自殺に追い込み、藤原式家の藤原仲成とその妹薬子(くすこ)を重用した。だが、伊予親王を自殺させた自責の念にかられ、情緒不安定となり、わずか3年で弟の嵯峨に天皇位をゆずり上皇となった(809年)。
だが、まもなく嵯峨天皇と平城上皇のあいだが不仲となる。平城は兵を率いて、薬子、仲成とともに東国に向かおうとするが、嵯峨側に阻止される。仲成は射殺され、薬子は毒を仰いで死んだ。平城上皇は剃髪し、出家した。
嵯峨天皇の権力が強まった。嵯峨は藤原北家の藤原冬嗣を重用し、天皇と太政官とのあいだを取り次ぐ蔵人頭とした。南家や式家が没落しても、今度は北家が台頭するなど、藤原家の持続力には恐るべきものがあった。
嵯峨は823年に異母弟の淳和(じゅんな)に譲位し、淳和は833年に嵯峨の息子、仁明(にんみょう)に位を譲った。そのかんも嵯峨は上皇として権威を保持していたが、国政に関与することはなかった。
東北では811年、文室綿麻呂(ふんやのわたまろ)が本州最北部まで軍を進め、38年にわたる東北戦争に終止符を打った。
嵯峨には50人におよぶ子女がいたが、上級の皇族を除き、そのほとんどに源の姓を与えて、臣籍に下ろした。
嵯峨の時代、宮廷は唐風に染め上げられ、華やかな宴がくり広げられ、大極殿にかわって内裏が政治の儀式の場となった。弘仁期の貴族文化が花開くことになる。
仏教界では天台、真言の両宗が立ち、社会に大きな影響を及ぼした。比叡山に大乗戒壇が設立されるのは、最澄の死後である。真言の秘儀を授けられて帰朝した空海は、聖地高野山に金剛峯寺を建て、京都の東寺に拠点を置いて、朝廷から深く信頼されていた。
-99d67.jpg)
[空海。ウィキペディアより]
弘仁時代の政治は安定していた。班田はおこなわれなくなっている。朝廷は諸国での正税の一部(米や雑物)を京都に運ばせるようになった。受領(現地の行政責任者)が税を請け負う体制が生まれようとしている。
太宰府管内には大規模な公営田がつくられた。その経営は実際には地元有力者に依存していた。
富豪による私出挙(すいこ、籾の貸し出し)や田地経営も認められるようになった。天皇家も直属の勅旨田や氷室、薬園などを所有する。すると、貴族や寺院も富豪を取り込んで、墾田を進め、みずからの荘園を拡大する動きを強めていった。
9世紀半ばに嵯峨が死ぬと、藤原北家の権勢がますます強くなった。藤原冬嗣(ふゆつぐ)の子、良房は陰謀をめぐらせて、仁明(にんみょう)天皇と冬嗣の娘のあいだに生まれた道康親王を皇太子とした。そして、道康が天皇(文徳)になると、良房の孫で9カ月の惟仁(これひと)親王を皇太子とした。
858年に文徳は急死、9歳の惟仁が清和天皇として即位し、太政大臣良房が政務を総攬し、やがて摂政となった。そのかん、伴氏、紀氏、橘氏などの有力氏族は追い落とされ、藤原家がますます政治を掌握するようになった。
良房の時代、すなわち貞観期は、さまざまな紛争や葛藤はあったものの、政治経済や文化はそれなりに安定していた。
872年に良房が死ぬと、その地位は基経が継承した。876年に清和は幼少の陽成に位を譲った。しかし、陽成は成長するとともに奇行が目立つようになり、内裏で近臣を殴り殺す事件まで引き起こした。そのため基経は陽成を退位させ、仁明の子ですでに臣籍に下っていた55歳の時康を天皇家に戻して、位につけた(光孝天皇)。光孝のあとは、その子が宇多天皇となる。このとき、基経は関白に任じられた。
要するに、天皇を握る藤原家が権力を手放すことはないのだった。
9世紀後半になると、国家機構が揺らぎ、分裂傾向が強まっていく。天皇家、有力貴族、寺院、地方の国司、郡司が、それぞれ経済的地盤を教化しようとして、勝手に動きはじめていた。
各地で混乱や衝突が発生し、治安が悪化し、群盗や海賊が出没する。政府の武力機構や天皇直属の検非違使(けびいし)はこれに対応することができず、その取り締まりは次第に国司にゆだねられるようになった。
対外関係では、唐が衰亡の道をたどっていた。しかし、大陸、半島との交流は活発で、9世紀には多くの新羅人が日本に住み、唐の商人もしばしば来航していた。
9世紀後半になると、西日本では新羅人と結んだ国司や郡司が派手な動きをみせて、謀反の疑いを招いている。869年には新羅の海賊船2隻が博多湾に襲来する事件もおこった。瀬戸内海でも貢納船を襲う海賊が増え、朝廷はほとほと手を焼いた。
馬の飼育が盛んな東国では、騎馬の武装集団が登場した。貢納物を輸送する運送業者は、機会さえあれば貢納物を奪う群盗に早変わりした。
「俘囚」や「夷俘」と呼ばれてさげすまれていた東北人が叛乱をおこし、東北の自立を求めるようになるのも9世紀後半からだ、と網野は指摘する。
国司と地域の有力者の衝突も激しくなった。海賊や群盗が横行しはじめた。各地を遍歴遊行して民衆を教化する僧も増えてきた。
京は都として成熟していく。だが、そこには光だけではなく影もあふれていた。それが9世紀後半の状況だった、と網野はいう。
持統上皇は702年に死ぬ。文武天皇は病弱だった。だが、朝廷の実力者、藤原不比等(ふひと)の娘とのあいだで生まれた首(おびと)皇子が、いずれは天皇になると目されていた。
文武は707年に病死し、首皇子が即位するまでの中継ぎとして、文武天皇の母が元明天皇として即位した。藤原氏の血をひく首皇子が天皇になることに、天皇一族や貴族のあいだから強い反発があったことも影響している。
そのころ日本では天災や疫病がつづき、社会不安が増大していた。不比等はこの危機を減税や綱紀粛正によって乗り越えた。
708年、武蔵から銅が献上されたのを機に、2番目の貨幣、和同開珎(かいちん)が鋳造される。最初の富本銭に儀礼的色彩が強かったのにたいし、和同開珎は本格的な流通貨幣となった。
710年、都は平城京に移される。奈良の都である。
ヤマト政権は勢力を拡大していた。712年には蝦夷を討って日本海側に出羽国をつくり、713年には隼人を討って南九州に大隅国をたてた。
712年には『古事記』が完成する(『日本書紀』は720年)。そのころ、平城京には新羅の使節がたびたび訪れ、日本も唐につぎつぎと遣唐使を派遣していた。
714年に元明は退位し、その娘で文武の姉にあたる元正が天皇となり、首皇子が皇太子となった。藤原不比等にとって、本命はあくまでも藤原家の血をひく首皇子である。不比等は娘の安宿媛(あすかべひめ、のちの光明皇后)を首皇子の妃に送りこんだ。
社会不安が収まらないなか、不比等は律令制を維持し、これに違反する者の取り締まりを強化した。逃散する平民や乞食(こつじき)僧も厳しく処罰した。大宝律令はやがて養老律令へと改正される。しかし、律令制への反発は根強いものがあった。
720年に不比等が死ぬと、天武の孫にあたる長屋王が大きな力をもつようになる。長屋王は律令制の緩和をはかり、豪族や富豪による私的な水田開発を認めた。
722年に元明上皇が死に、724年に元正天皇が退位し、首皇子がようやく即位した(聖武天皇)。光明子とのあいだに生まれた男子は夭折する。藤原氏の野望はついえたが、新たな目標は長屋王追い落としに向けられた。729年、長屋王は謀反の疑いをかけられ、自殺する。その後、藤原4兄弟(武智麻呂、房前、宇合[うまかい]、麻呂)は政権の中枢を握り、光明子を皇后にたてることに成功した。4兄弟はそれぞれ藤原の南家、北家、式家、京家の祖となる。
藤原氏の政府は、律令制を引き締めようとしたが、とりわけ班田制にたいする世間の反発は強かった。諸国に盗賊や海賊が出没し、遊行僧のまわりに人びとが集まった。こうした不穏な風潮にたいし、政府は宥和策と強硬策の組み合わせで臨んだ。
各地では天災と飢饉が相次いでおこった。735年ころから天然痘が流行する。737年には天然痘によって藤原4兄弟が死に、藤原政権は一気に崩壊した。
このときヤマト政権の再建につとめたのが、光明皇后の異父兄、橘諸兄(たちばなのもろえ)である。諸兄は貴族や豪族の規律をただし、東国の防人を郷里に帰すなどして、大胆な負担軽減策を実施した。
738年、聖武天皇は光明皇后とのあいだに生まれた娘、阿倍内親王を皇太子とし、唐から戻った吉備真備らを重用した。
こうした動きにたいし、九州に左遷されていた藤原広嗣(ひろつぐ、宇合の子)が反発し、740年に叛乱をおこした。だが、まもなく鎮圧される。
741年、聖武は諸国に国分寺建立の詔(みことのり)を発する。ここに仏教は鎮護国家の宗教として、大きな力をもつようになった。
743年、墾田永年私財法がだされる。これまでの班田収受の法をあらため、貴族や豪族、寺院が開発した水田を一定限度で私財化することを認めるものだった。
聖武天皇はこのころ紫香楽(しがらき)の離宮や難波宮を転々としていた。5年ぶりに平城宮に戻ったのは、大仏建立のめどがついたからだ。
748年、聖武は退位し、娘の孝謙が即位する。このころ、藤原家はふたたび力を取り戻し、橘諸兄は孤立を深めていた。752年、大仏が完成し、開眼供養がおこなわれた。仏教はいよいよ鎮護国家の宗教という側面を強めていた。
756年、橘諸兄が官を辞し、聖武上皇も世を去ると、藤原仲麻呂が朝廷の実権を握った。仲麻呂は聖武の定めた皇太子を廃し、みずからに近い大炊王(おおいおう)を皇太子とし、祖父不比等の養老律令をふたたび実施し、班田制の立て直しにつとめた。
仲麻呂に反対してきた橘奈良麻呂はクーデターを計画するが、事前に知られ、処刑された。
758年、大炊王が天皇になると(淳仁)、仲麻呂には恵美押勝(えみのおしかつ)の姓名が与えられた。760年、押勝は太上大臣になる。だが、この年、後見人の光明皇太后を亡くなる。
上皇となった孝謙が道鏡と親しくなり、政治に介入しはじめると、押勝との対立が激しくなった。押勝は次第に追い詰められ、764年に軍事的実権を握ろうとして立ち上がるが、先手を打たれて殺された。
天皇は廃され(淳仁の諡号を送られたのは明治になってから)、孝謙がふたたび天皇(称徳)の位につき、道鏡を僧形のまま太政大臣に任じた。女帝はさらに道鏡を天皇にしようとした。だが、和気清麻呂によって阻止された。
770年、称徳が死に、道鏡は追放され、天智の孫、白壁王が天皇(光仁)となる。光仁は百済王の血統をもつ高野新笠(たかのにいがさ)とのあいだに生まれた山部(やまべ)親王を皇太子とした(のちの桓武)。天武の血統は徹底して退けられた。
8世紀にヤマト政権は東北北部に勢力をひろげた。
北海道では、漁撈を中心に、採集、狩猟、農耕を組み合わせた擦文(さつもん)文化の時代がはじまっていた。
渤海は727年から10世紀にいたるまで日本に使者を送り、日本も13回にわたって遣渤海使を送っている。
日本と新羅との関係は険悪になっていた。そのため、日本が遣唐使を送る場合は、朝鮮半島沿いではなく南シナ海を横断するルートをとり、多くの遭難を招いていた。
国府や国分寺を通じて、中国風・仏教風の文化が各地に浸透たことはまちがいない。それでも網野によれば、「平民の生活そのものに根ざした習俗はそれによって変容されつつも根強く生きつづけ、支配者自身に影響を与えて」いた。
さらに、網野は市の重要性を論じる。
〈こうした、人の力の及ばぬ自然、神仏の世界と人間の世界との境界として、河原、中洲、浜や巨木の立つ場所に、人びとは市を立てた。そこは神の力の及ぶ場であり、世俗の人と人、人と物の結びつきが切れるとされており、人びとはそこに物を投げ入れることによって、これを商品として交換しうる物とした。共同体をこえて人びとは市庭(いちば)に集まり、畿内周辺では銭貨も用いたが、米・布・絹などを主な交換手段として、交易を活発に行った。またそこでは神を喜ばせる芸能が行われるとともに、世俗の夫婦・親子の関係も切れるとされており、「歌垣」という歌をともなった男女の自由な性交渉も行われたといわれている。〉
このあたり、網野史学ならではの記述である。
国家の統制は市にまではおよばなかった。市では、多くの女性が商業や金融の仕事を担っていた。8世紀半ばには、海上・湖上の交通を利用し、広域にわたって活動する商人も登場した。
国家は都と各地を結ぶ直線道路をつくり、これによって国司や官人を派遣するとともに、民衆に調や庸を運ばせていた。しかし、8世紀後半にはこうした官道はすたれはじめ、9世紀になると自然の道や海路が復活してくる。
国家による負担が、多くの平民を苦しめていた。その負担から逃れようとして、逃げだす者も増えていた。かれらは畿内の貴族や寺社、富豪に身を寄せるようになる。
墾田永年私財法が出されると、大寺院や上層貴族たちは、未開地に荘を設け、富豪や有力者の助けを借りて、土地開発をおこなった。それが荘園となった。
天智系の新王朝を開いた光仁天皇には、道鏡時代の混乱を収拾する役割が課されていた。だが、社会はいっこうに安定しなかった。
774年には陸奥で叛乱が発生し、これが38年間つづくことになる。780年には、陸奥の郡司、伊治公呰麻呂(いじのきみあざまろ)が立ち上がり、胆沢(いさわ)での築城を阻止し、多賀城を焼いた。
そのさなか光仁は亡くなり、桓武が即位した。782年、桓武は反対派の天武系皇族を謀反の疑いで流罪に処し、これにより天武系の血統は完全に途絶えた。

[桓武天皇。ウィキペディアより]
桓武は天智の定めた法で統治すると宣言し、藤原氏北家の左大臣藤原魚名(うおな)を排除し、藤原氏南家を中心に朝廷を組織した。
784年にはいきなり山背国(やましろのくに)の長岡に遷都した。長岡周辺には、秦氏出身の母と同じ朝鮮半島からの移住民が多かったという。新都の建設は、それらの人びとの協力によって進められた。
長岡京の建設には、それを指揮した藤原種継が暗殺されるなど、暗雲がただよっていた。だが、桓武は早良(さわら)親王ら反対派を粛清し、新都建設を続行する。
788年には東北の乱を収めるため、5万の大軍を派遣した。だが、北上川で首長阿弖流為(あてるい)の反撃にあい、あっけなく敗北。それでも桓武はあきらめず、東北攻略を進めていった。
791年には征夷大使に大伴弟麻呂(おとまろ)、副使に坂上田村麻呂を任じた。それまでの平民軍団に代わって、選抜された強力な軍団が組織され、794年、東北に10万の軍が投入された。
そのころ都の周辺では凶事が相次いでいた。飢饉と疫病が広がり、桓武の母や皇后まで死亡し、皇太子まで病気で倒れた。早良親王の怨霊だといううわさまで広がって、桓武はついに長岡京を放棄した。
新しい候補地はすぐに見つかった。793年に桓武は山背国の宇太(うだ)に遷都すると発表、翌年、みずからその地に移り住んだ。山背国は山城国とあらためられ、新都は平安京と名づけられた。
そこに東北の坂上田村麻呂が圧勝したという知らせが伝わる。796年には新銭として隆平永宝が鋳造され、翌年には『続日本紀』が完成した。
797年、坂上田村麻呂は征夷大将軍に任じられ、801年にふたたび東北に侵攻、アテルイを投降に追いこんだ。アテルイは都に連行され斬られた。それで東北の動揺がおさまったわけでなかった。
桓武は平安京に仏教の新しい風を吹きこもうとしていた。804年、最澄と空海が唐に送られた。最澄は翌年帰国して天台宗を開き、さらにその1年後、空海が密教の教えを携えて戻った。
東北での戦争と新都の建設は民衆に多くの負担を強いていた。桓武の独裁にたいする貴族の反発も強まっていた。そうしたさなか、806年に桓武は70歳で生涯を閉じることになる。
桓武の位を継いだ平城(へいぜい)天皇は、藤原南家を後ろ盾とする異母弟の伊予親王を自殺に追い込み、藤原式家の藤原仲成とその妹薬子(くすこ)を重用した。だが、伊予親王を自殺させた自責の念にかられ、情緒不安定となり、わずか3年で弟の嵯峨に天皇位をゆずり上皇となった(809年)。
だが、まもなく嵯峨天皇と平城上皇のあいだが不仲となる。平城は兵を率いて、薬子、仲成とともに東国に向かおうとするが、嵯峨側に阻止される。仲成は射殺され、薬子は毒を仰いで死んだ。平城上皇は剃髪し、出家した。
嵯峨天皇の権力が強まった。嵯峨は藤原北家の藤原冬嗣を重用し、天皇と太政官とのあいだを取り次ぐ蔵人頭とした。南家や式家が没落しても、今度は北家が台頭するなど、藤原家の持続力には恐るべきものがあった。
嵯峨は823年に異母弟の淳和(じゅんな)に譲位し、淳和は833年に嵯峨の息子、仁明(にんみょう)に位を譲った。そのかんも嵯峨は上皇として権威を保持していたが、国政に関与することはなかった。
東北では811年、文室綿麻呂(ふんやのわたまろ)が本州最北部まで軍を進め、38年にわたる東北戦争に終止符を打った。
嵯峨には50人におよぶ子女がいたが、上級の皇族を除き、そのほとんどに源の姓を与えて、臣籍に下ろした。
嵯峨の時代、宮廷は唐風に染め上げられ、華やかな宴がくり広げられ、大極殿にかわって内裏が政治の儀式の場となった。弘仁期の貴族文化が花開くことになる。
仏教界では天台、真言の両宗が立ち、社会に大きな影響を及ぼした。比叡山に大乗戒壇が設立されるのは、最澄の死後である。真言の秘儀を授けられて帰朝した空海は、聖地高野山に金剛峯寺を建て、京都の東寺に拠点を置いて、朝廷から深く信頼されていた。
-99d67.jpg)
[空海。ウィキペディアより]
弘仁時代の政治は安定していた。班田はおこなわれなくなっている。朝廷は諸国での正税の一部(米や雑物)を京都に運ばせるようになった。受領(現地の行政責任者)が税を請け負う体制が生まれようとしている。
太宰府管内には大規模な公営田がつくられた。その経営は実際には地元有力者に依存していた。
富豪による私出挙(すいこ、籾の貸し出し)や田地経営も認められるようになった。天皇家も直属の勅旨田や氷室、薬園などを所有する。すると、貴族や寺院も富豪を取り込んで、墾田を進め、みずからの荘園を拡大する動きを強めていった。
9世紀半ばに嵯峨が死ぬと、藤原北家の権勢がますます強くなった。藤原冬嗣(ふゆつぐ)の子、良房は陰謀をめぐらせて、仁明(にんみょう)天皇と冬嗣の娘のあいだに生まれた道康親王を皇太子とした。そして、道康が天皇(文徳)になると、良房の孫で9カ月の惟仁(これひと)親王を皇太子とした。
858年に文徳は急死、9歳の惟仁が清和天皇として即位し、太政大臣良房が政務を総攬し、やがて摂政となった。そのかん、伴氏、紀氏、橘氏などの有力氏族は追い落とされ、藤原家がますます政治を掌握するようになった。
良房の時代、すなわち貞観期は、さまざまな紛争や葛藤はあったものの、政治経済や文化はそれなりに安定していた。
872年に良房が死ぬと、その地位は基経が継承した。876年に清和は幼少の陽成に位を譲った。しかし、陽成は成長するとともに奇行が目立つようになり、内裏で近臣を殴り殺す事件まで引き起こした。そのため基経は陽成を退位させ、仁明の子ですでに臣籍に下っていた55歳の時康を天皇家に戻して、位につけた(光孝天皇)。光孝のあとは、その子が宇多天皇となる。このとき、基経は関白に任じられた。
要するに、天皇を握る藤原家が権力を手放すことはないのだった。
9世紀後半になると、国家機構が揺らぎ、分裂傾向が強まっていく。天皇家、有力貴族、寺院、地方の国司、郡司が、それぞれ経済的地盤を教化しようとして、勝手に動きはじめていた。
各地で混乱や衝突が発生し、治安が悪化し、群盗や海賊が出没する。政府の武力機構や天皇直属の検非違使(けびいし)はこれに対応することができず、その取り締まりは次第に国司にゆだねられるようになった。
対外関係では、唐が衰亡の道をたどっていた。しかし、大陸、半島との交流は活発で、9世紀には多くの新羅人が日本に住み、唐の商人もしばしば来航していた。
9世紀後半になると、西日本では新羅人と結んだ国司や郡司が派手な動きをみせて、謀反の疑いを招いている。869年には新羅の海賊船2隻が博多湾に襲来する事件もおこった。瀬戸内海でも貢納船を襲う海賊が増え、朝廷はほとほと手を焼いた。
馬の飼育が盛んな東国では、騎馬の武装集団が登場した。貢納物を輸送する運送業者は、機会さえあれば貢納物を奪う群盗に早変わりした。
「俘囚」や「夷俘」と呼ばれてさげすまれていた東北人が叛乱をおこし、東北の自立を求めるようになるのも9世紀後半からだ、と網野は指摘する。
国司と地域の有力者の衝突も激しくなった。海賊や群盗が横行しはじめた。各地を遍歴遊行して民衆を教化する僧も増えてきた。
京は都として成熟していく。だが、そこには光だけではなく影もあふれていた。それが9世紀後半の状況だった、と網野はいう。
網野善彦『日本社会の歴史』を読む(4) [歴史]
推古の死後、蘇我蝦夷は厩戸の子山背大兄を退けて、孫の田村王子(舒明)を大王につけ、その大后に宝王女(のちの皇極・斉明)を選んだ。
630年、舒明は唐に使者を送る。そのころ、唐は新羅と組んで、高句麗や百済に圧力を加えていた。
ヤマトは唐の外交政策に同調するわけにはいかない。新羅が任那(加羅)を滅ぼした仇敵だからである。とはいえ、唐に正面切って反対するわけにもいかない。何といっても唐は大国であり、ヤマトよりはるかに文明の進んだ国だった。
そのころ、20年前に遣唐使として派遣された留学生や留学僧が唐から戻ってくる。かれらは「ヤマト政権の首脳部、とくに舒明の子中大兄や中臣鎌足(のち藤原鎌足)などの若い世代に強烈な刺激と影響を与えた」と、網野は書いている。
641年に大王舒明は死に、大后宝王女が皇極女王として即位した。643年、皇極は飛鳥板蓋宮(あすかいたぶきのみや)を建て、そこに移った。
飛鳥では蘇我蝦夷・入鹿の親子が権勢をふるっていた。有力な大王候補と目されていた山背大兄は殺害される。蘇我氏の専横に宮中では反発が強まっていたと思われる。
645年、大化のクーデターが実行に移される。中大兄と鎌足は宮中で入鹿を斬り、蝦夷を自刃に追いこんだ。

[江戸時代に描かれた絵。『多武峰縁起絵巻』。ウィキペディア]
皇極は退位し、中大兄に大王の地位を譲ろうとした。だが、中大兄は固辞し、皇極の弟軽王子が孝徳大王として即位する。中大兄や鎌足が権力の実権を握っていたことはいうまでもない。
「本格的な中国風の国家の確立に向かって、ヤマト政権はここに間違いなく重大な一歩を踏み出した」と、網野は記している。
新政府は東国をはじめ各地に使者を派遣し、ヤマトの支配を強化しようとした。蘇我氏から次期大王と目されていた古人大兄は、逃亡先の吉野で殺された。
都を難波に移した新政府は、646年にあらたな詔(みことのり)を発した。大王を頂点として、首長たちを官人として組織し、地域ごとに人民を支配する本格的な国家体制をの確立することが宣言された。
しかし、首長たちの反発は強く、新政府への統合はうまく進まない。政権内部の対立も表面化してきた。孝徳大王と中大兄の関係も険悪になるが、中大兄は孝徳を排除して、独裁色を強めていった。
それでも中大兄は大王になろうとしない。退位した母の皇極をふたたび大王の座につけ、斉明とした。
独裁をはかる中大兄への反発が強まっていく。658年、孝徳の子、有間王子は叛乱を計画するが、事前に発覚し、死罪に処された。
この年、唐が高句麗への攻撃を開始する。そうしたなか、ヤマト政権は東北に軍を派遣し、東北の蝦夷(えみし)を制圧した。
高句麗で苦戦した唐は660年に新羅と同盟を結び、まず百済を攻撃する。百済からの救援要請を受けたヤマト政権は新羅を討つことを決意する。
661年、斉明女王をはじめ、中大兄、大海人王子、中臣鎌足らが軍を率いて難波を発った。だが、斉明女王は筑紫で急死する。
663年、ヤマトの水軍は白村江で唐と新羅の連合軍と戦い、壊滅的な敗北を喫する。唐と新羅からの攻撃を恐れた政府は、対馬、壱岐、筑紫、長門に山城を築き、その攻撃に備えた。そのいっぽう、唐に使節を送って外交関係の修復をはかろうとした。
白村江での敗北により、ヤマト政権は朝鮮から手を引き、朝鮮海峡がヤマトと新羅の国境となった。まもなく朝鮮では、新羅が統一国家をつくる。
次は「日本」ができる番である。だが、その前に一波乱がおこる。
斉明の死後、大和政権では7年にわたって大王が不在という異常事態が生じていた。しかし、668年にいたってついに中大兄が近江の大津宮で即位し、天智大王となった。
669年に藤原鎌足が死ぬと、天智と弟の大海人の関係がぎくしゃくしはじめる。大海人は危険を察知して、吉野に逃げた。671年、天智は子の大友王子にすべてを托して、世を去った。
672年、近江の朝廷と吉野との緊張関係が高まる。近江からの攻撃を察知した大海人は吉野を脱出して、東国に逃げ、有力な首長たちを糾合し、大軍勢を率いて大友側を破り、大友を自殺に追いこんだ。勝利した大海人は飛鳥浄御原宮に移り、673年に大王天武として即位した。
勝利した天武は、天智が宣言しただけで実現できなかった国家体制の確立に向けて一歩踏み出した。それまで首長の支配下にあった人民と土地をすべて国家のものとする「公地公民制」を実現しようとしたのである。
公民からの租税徴収権をもつのは国家にほかならない。首長たちは国家の官人として組織され、俸禄として食封(じきふう)が与えられることになった。首長たちの抵抗は強かった。しかし、天武の宮廷は強力な軍事力を背景にこれを抑えこんだ。
中央官制では、隋・唐にならって太政官・大弁官・六官が新設された。だが、あくまでも天武独裁の体制が貫かれた。首長たちには八色(やくさ)の姓(かばね)が与えられ、序列が定められた。朝廷の官人にも四十八階の爵位がつくられた。
畿内を中心に、東海、東山、北陸、山陰、山陽、南海、西海の七道が行政区域として定められ、都から各地に向かう直線的な道路が計画された。
天武は後継者と目した草壁王子に浄御原令(きよみはられい)の編纂を命じた。『古事記』『日本書紀』の執筆がはじまったのも、この時代である。
天武が死ぬと、謀反の疑いをかけられた大津王子が死を賜る。だが、後継者の草壁も病死したため、やむなく太后の鸕野讃良(うののさらら)が政治を担うこととなった。
689年、鸕野讃良は浄御原令を施行する。そこには倭に代わり日本を国号とすること、大王に代わり天皇を称号とすることが明記されていた。皇后、皇太子の名称も定められていた。
重要なのは、ここに戸籍の作成や班田、租税の徴収、兵役義務が規定されていたことである。唐にならい、国家体制が整えられようとしていた。
690年、鸕野讃良は即位して、持統天皇となった。太上大臣には高市皇子が任命された。
692年には藤原京が完成し、持統は遷都する。ここに華やかな白鳳文化が花開く。
696年に高市皇子が死ぬと、持統は15歳の孫、軽皇子(文武天皇)に位を譲り、太上天皇となった。だが、持統が政治を手放すことはない。
701年には元号が大宝と定められ、大宝律令が発せられた。これ以降、日本では元号がつづくことになった。
そのころ、北海道、東北北部、南九州、沖縄には、まだ日本の支配がおよんでいなかった。
大宝律令は唐の影響を強く受けていたが、それでも日本の実情に合わせた部分もみられた、と網野は記している。大宝律令は次第に列島各地に浸透していくが、列島社会には、なお呪術的な未開の素朴さが残っていたという。
天皇にも神聖王としての側面が残り、「大嘗祭の儀礼の一部にうかがわれるように、そこには未開な呪術的特質を色濃く認めることができる」。
それでも大宝律令によって、天皇は国家の頂点に立つ存在へと位置づけられていった、と網野はいう。
大宝令により、中央官庁には、太政官と八省、神祇官、弾正台(官人を査察する機関)、軍事組織が設けられることになった。日本の宮廷には中国のような宦官は存在せず、内廷は女性たちによって統轄されていた。
全国は畿内と地方の七道に分けられ、五十戸一里(郷)を基礎とし、国、郡にそれぞれ政庁(国衙、郡衙)が設けられた。北九州は特別行政区で、太宰府が地区を統轄した。
中央、地方の官人には、30段階の位階が定められた。
都と七道を結ぶため、幅十数メートルの直線道路がつくられ、四里ごとに駅家(うまや)が設けられた。
天皇によって任命される太政官は大きな権限をもっていた。しかし、「その[政府の]実質は律令制以前からの畿内の有力な氏の代表によって構成される合議機関」だったという。それが、天皇の権力を制約していた。律令制はあくまでもタテマエにすぎない。
国家試験に合格すれば、だれでも官人になることができ、勤務評定によって、位階もあがることになっていた。しかし、五位以上の貴族には、最初から子弟をそれなりの位につける特権が与えられていたから、平民から上級の官人になる道は閉ざされていた、と網野は書いている。
官人になると課役を免除され、季禄を与えられた。五位以上は貴族となる。三位以上の上級貴族には多くの特権が与えられ、その地位も代々受け継がれた。五位以上の貴族は100人〜300人だったとされる。
人口の圧倒的部分は平民だった。各官庁に仕える良民もいた。奴婢や賎民は平民や良民から区別されていた。ただし、奴婢や賎民といっても、そのなかには、天皇の陵を守る者は神に仕える者、特異な呪力や芸能で天皇に奉仕する者もいた、と網野は指摘する。
国家の財政と軍事を支えていたのは、人口の圧倒的部分を占める平民(公民)だった。かれらは隷属民ではなく、自由民だった。
大宝律令によると、すべての人民には一定の口分田(6歳以上の男子には2反、女子にはその3分の2)が与えられることになっていた。口分田の売買は禁じられ、死後は収公される決まりだった。口分田は6年に1度の点検を受ける。これが班田収受の法である。
口分田にたいしては、一反につき二束二把(のちに五把)の租が課された。税率は約3%から8%。そう高いわけではない。しかし、重要なのは、土地は国家のものだという考え方である。国家から土地を与えられた公民は、それを耕し、国家に税を納めねばならないという論理が確立された。
口分田に配分された以外の田地は公田とされ、国司が百姓に賃貸し、収穫の5分の1を地子として徴収した。公田地子は太政官に送られ、臨時の支出などにあてられた。
里長(郷長)は課役賦課の基本台帳となる計帳をつくらねばならなかった。そして、この計帳により、成年男子に調、庸、雑徭、軍役などが課された。調はその地方の特産品、たとえば絹や綿、塩、アワビ、海藻、鉄、油、染料、海産物、山の幸などで納められ、庸は年に10日、都に出て使役される歳役とされ、実際には特産物や米で代納されていた。それらはみずから都に運んで、政府に納めなければならないとされていたが、実際はどうだったのだろう。
また、成年男子には、年に60日を限りとして、国司のもとでさまざまな公共的な労役に従事する雑徭も化されていた。
租の稲は国や郡の倉に収められた。その一部を籾として貸し出す制度もあった。籾を借り受けると、秋の収穫期にそれを5割増しで返却しなければならない。これが出挙(すいこ)の制度である。さらに凶年に備えて、一定量のアワを納める義倉の決まりもあった。
成年男子には兵役の義務が課されており、正丁(20歳すぎから60歳までの健康な男子)の3、4人に1人が、国の命じる警備や軍務に従事しなければならなかった。東国の兵士の3分の1は、防人(さきもり)として筑紫や壱岐、対馬に送られていたという。
当時は平民のあいだでも社会的分業が進み、市庭での交易もさかんになっていた。大陸・半島から渡来した者も含め、高度な職能民は課役を免除し、品部、雑戸として扱われていた。宮廷に直属する贄人(にえびと)もいて、かれらは宮廷に魚貝や海藻、果実などの海の幸、山の幸を貢進していた。
中央政府は都から諸国に国司を派遣し、国衙(こくが)と呼ばれる政庁で、かれらに一切の政務をゆだねていた。国司のもとには、かつての首長の雰囲気を残す郡司が任命されていて、旧豪族として一般平民を支配していた。国司による統治は郡司抜きにはありえなかった。しかし、官制のうえでは、郡司の地位は国司よりはるかに低かった。
網野はこう書いている。
〈このように、[中国から移入した律令によって]確立した日本国の国制は最初に成立した本格的な国家の制度として、またそれを実現しようとした支配者層の強烈な意志によって、その後の列島社会に強く深い影響を与えたが、なお未開な素朴さのなかにあり、地域それぞれにきわめて多様な平民の社会生活を実際には組織しえていない早熟な国家だった。〉
8世紀に誕生した日本国は、律令によって人民を支配する体制を整えようとしていた。そして、表向き豪族の支配から切り離された人民の多くは、新たに生まれた国家に租税や貢納、軍役、雑役を提供しながらも、自由民として生きる道を求めつづけていたといえるだろう。
630年、舒明は唐に使者を送る。そのころ、唐は新羅と組んで、高句麗や百済に圧力を加えていた。
ヤマトは唐の外交政策に同調するわけにはいかない。新羅が任那(加羅)を滅ぼした仇敵だからである。とはいえ、唐に正面切って反対するわけにもいかない。何といっても唐は大国であり、ヤマトよりはるかに文明の進んだ国だった。
そのころ、20年前に遣唐使として派遣された留学生や留学僧が唐から戻ってくる。かれらは「ヤマト政権の首脳部、とくに舒明の子中大兄や中臣鎌足(のち藤原鎌足)などの若い世代に強烈な刺激と影響を与えた」と、網野は書いている。
641年に大王舒明は死に、大后宝王女が皇極女王として即位した。643年、皇極は飛鳥板蓋宮(あすかいたぶきのみや)を建て、そこに移った。
飛鳥では蘇我蝦夷・入鹿の親子が権勢をふるっていた。有力な大王候補と目されていた山背大兄は殺害される。蘇我氏の専横に宮中では反発が強まっていたと思われる。
645年、大化のクーデターが実行に移される。中大兄と鎌足は宮中で入鹿を斬り、蝦夷を自刃に追いこんだ。

[江戸時代に描かれた絵。『多武峰縁起絵巻』。ウィキペディア]
皇極は退位し、中大兄に大王の地位を譲ろうとした。だが、中大兄は固辞し、皇極の弟軽王子が孝徳大王として即位する。中大兄や鎌足が権力の実権を握っていたことはいうまでもない。
「本格的な中国風の国家の確立に向かって、ヤマト政権はここに間違いなく重大な一歩を踏み出した」と、網野は記している。
新政府は東国をはじめ各地に使者を派遣し、ヤマトの支配を強化しようとした。蘇我氏から次期大王と目されていた古人大兄は、逃亡先の吉野で殺された。
都を難波に移した新政府は、646年にあらたな詔(みことのり)を発した。大王を頂点として、首長たちを官人として組織し、地域ごとに人民を支配する本格的な国家体制をの確立することが宣言された。
しかし、首長たちの反発は強く、新政府への統合はうまく進まない。政権内部の対立も表面化してきた。孝徳大王と中大兄の関係も険悪になるが、中大兄は孝徳を排除して、独裁色を強めていった。
それでも中大兄は大王になろうとしない。退位した母の皇極をふたたび大王の座につけ、斉明とした。
独裁をはかる中大兄への反発が強まっていく。658年、孝徳の子、有間王子は叛乱を計画するが、事前に発覚し、死罪に処された。
この年、唐が高句麗への攻撃を開始する。そうしたなか、ヤマト政権は東北に軍を派遣し、東北の蝦夷(えみし)を制圧した。
高句麗で苦戦した唐は660年に新羅と同盟を結び、まず百済を攻撃する。百済からの救援要請を受けたヤマト政権は新羅を討つことを決意する。
661年、斉明女王をはじめ、中大兄、大海人王子、中臣鎌足らが軍を率いて難波を発った。だが、斉明女王は筑紫で急死する。
663年、ヤマトの水軍は白村江で唐と新羅の連合軍と戦い、壊滅的な敗北を喫する。唐と新羅からの攻撃を恐れた政府は、対馬、壱岐、筑紫、長門に山城を築き、その攻撃に備えた。そのいっぽう、唐に使節を送って外交関係の修復をはかろうとした。
白村江での敗北により、ヤマト政権は朝鮮から手を引き、朝鮮海峡がヤマトと新羅の国境となった。まもなく朝鮮では、新羅が統一国家をつくる。
次は「日本」ができる番である。だが、その前に一波乱がおこる。
斉明の死後、大和政権では7年にわたって大王が不在という異常事態が生じていた。しかし、668年にいたってついに中大兄が近江の大津宮で即位し、天智大王となった。
669年に藤原鎌足が死ぬと、天智と弟の大海人の関係がぎくしゃくしはじめる。大海人は危険を察知して、吉野に逃げた。671年、天智は子の大友王子にすべてを托して、世を去った。
672年、近江の朝廷と吉野との緊張関係が高まる。近江からの攻撃を察知した大海人は吉野を脱出して、東国に逃げ、有力な首長たちを糾合し、大軍勢を率いて大友側を破り、大友を自殺に追いこんだ。勝利した大海人は飛鳥浄御原宮に移り、673年に大王天武として即位した。
勝利した天武は、天智が宣言しただけで実現できなかった国家体制の確立に向けて一歩踏み出した。それまで首長の支配下にあった人民と土地をすべて国家のものとする「公地公民制」を実現しようとしたのである。
公民からの租税徴収権をもつのは国家にほかならない。首長たちは国家の官人として組織され、俸禄として食封(じきふう)が与えられることになった。首長たちの抵抗は強かった。しかし、天武の宮廷は強力な軍事力を背景にこれを抑えこんだ。
中央官制では、隋・唐にならって太政官・大弁官・六官が新設された。だが、あくまでも天武独裁の体制が貫かれた。首長たちには八色(やくさ)の姓(かばね)が与えられ、序列が定められた。朝廷の官人にも四十八階の爵位がつくられた。
畿内を中心に、東海、東山、北陸、山陰、山陽、南海、西海の七道が行政区域として定められ、都から各地に向かう直線的な道路が計画された。
天武は後継者と目した草壁王子に浄御原令(きよみはられい)の編纂を命じた。『古事記』『日本書紀』の執筆がはじまったのも、この時代である。
天武が死ぬと、謀反の疑いをかけられた大津王子が死を賜る。だが、後継者の草壁も病死したため、やむなく太后の鸕野讃良(うののさらら)が政治を担うこととなった。
689年、鸕野讃良は浄御原令を施行する。そこには倭に代わり日本を国号とすること、大王に代わり天皇を称号とすることが明記されていた。皇后、皇太子の名称も定められていた。
重要なのは、ここに戸籍の作成や班田、租税の徴収、兵役義務が規定されていたことである。唐にならい、国家体制が整えられようとしていた。
690年、鸕野讃良は即位して、持統天皇となった。太上大臣には高市皇子が任命された。
692年には藤原京が完成し、持統は遷都する。ここに華やかな白鳳文化が花開く。
696年に高市皇子が死ぬと、持統は15歳の孫、軽皇子(文武天皇)に位を譲り、太上天皇となった。だが、持統が政治を手放すことはない。
701年には元号が大宝と定められ、大宝律令が発せられた。これ以降、日本では元号がつづくことになった。
そのころ、北海道、東北北部、南九州、沖縄には、まだ日本の支配がおよんでいなかった。
大宝律令は唐の影響を強く受けていたが、それでも日本の実情に合わせた部分もみられた、と網野は記している。大宝律令は次第に列島各地に浸透していくが、列島社会には、なお呪術的な未開の素朴さが残っていたという。
天皇にも神聖王としての側面が残り、「大嘗祭の儀礼の一部にうかがわれるように、そこには未開な呪術的特質を色濃く認めることができる」。
それでも大宝律令によって、天皇は国家の頂点に立つ存在へと位置づけられていった、と網野はいう。
大宝令により、中央官庁には、太政官と八省、神祇官、弾正台(官人を査察する機関)、軍事組織が設けられることになった。日本の宮廷には中国のような宦官は存在せず、内廷は女性たちによって統轄されていた。
全国は畿内と地方の七道に分けられ、五十戸一里(郷)を基礎とし、国、郡にそれぞれ政庁(国衙、郡衙)が設けられた。北九州は特別行政区で、太宰府が地区を統轄した。
中央、地方の官人には、30段階の位階が定められた。
都と七道を結ぶため、幅十数メートルの直線道路がつくられ、四里ごとに駅家(うまや)が設けられた。
天皇によって任命される太政官は大きな権限をもっていた。しかし、「その[政府の]実質は律令制以前からの畿内の有力な氏の代表によって構成される合議機関」だったという。それが、天皇の権力を制約していた。律令制はあくまでもタテマエにすぎない。
国家試験に合格すれば、だれでも官人になることができ、勤務評定によって、位階もあがることになっていた。しかし、五位以上の貴族には、最初から子弟をそれなりの位につける特権が与えられていたから、平民から上級の官人になる道は閉ざされていた、と網野は書いている。
官人になると課役を免除され、季禄を与えられた。五位以上は貴族となる。三位以上の上級貴族には多くの特権が与えられ、その地位も代々受け継がれた。五位以上の貴族は100人〜300人だったとされる。
人口の圧倒的部分は平民だった。各官庁に仕える良民もいた。奴婢や賎民は平民や良民から区別されていた。ただし、奴婢や賎民といっても、そのなかには、天皇の陵を守る者は神に仕える者、特異な呪力や芸能で天皇に奉仕する者もいた、と網野は指摘する。
国家の財政と軍事を支えていたのは、人口の圧倒的部分を占める平民(公民)だった。かれらは隷属民ではなく、自由民だった。
大宝律令によると、すべての人民には一定の口分田(6歳以上の男子には2反、女子にはその3分の2)が与えられることになっていた。口分田の売買は禁じられ、死後は収公される決まりだった。口分田は6年に1度の点検を受ける。これが班田収受の法である。
口分田にたいしては、一反につき二束二把(のちに五把)の租が課された。税率は約3%から8%。そう高いわけではない。しかし、重要なのは、土地は国家のものだという考え方である。国家から土地を与えられた公民は、それを耕し、国家に税を納めねばならないという論理が確立された。
口分田に配分された以外の田地は公田とされ、国司が百姓に賃貸し、収穫の5分の1を地子として徴収した。公田地子は太政官に送られ、臨時の支出などにあてられた。
里長(郷長)は課役賦課の基本台帳となる計帳をつくらねばならなかった。そして、この計帳により、成年男子に調、庸、雑徭、軍役などが課された。調はその地方の特産品、たとえば絹や綿、塩、アワビ、海藻、鉄、油、染料、海産物、山の幸などで納められ、庸は年に10日、都に出て使役される歳役とされ、実際には特産物や米で代納されていた。それらはみずから都に運んで、政府に納めなければならないとされていたが、実際はどうだったのだろう。
また、成年男子には、年に60日を限りとして、国司のもとでさまざまな公共的な労役に従事する雑徭も化されていた。
租の稲は国や郡の倉に収められた。その一部を籾として貸し出す制度もあった。籾を借り受けると、秋の収穫期にそれを5割増しで返却しなければならない。これが出挙(すいこ)の制度である。さらに凶年に備えて、一定量のアワを納める義倉の決まりもあった。
成年男子には兵役の義務が課されており、正丁(20歳すぎから60歳までの健康な男子)の3、4人に1人が、国の命じる警備や軍務に従事しなければならなかった。東国の兵士の3分の1は、防人(さきもり)として筑紫や壱岐、対馬に送られていたという。
当時は平民のあいだでも社会的分業が進み、市庭での交易もさかんになっていた。大陸・半島から渡来した者も含め、高度な職能民は課役を免除し、品部、雑戸として扱われていた。宮廷に直属する贄人(にえびと)もいて、かれらは宮廷に魚貝や海藻、果実などの海の幸、山の幸を貢進していた。
中央政府は都から諸国に国司を派遣し、国衙(こくが)と呼ばれる政庁で、かれらに一切の政務をゆだねていた。国司のもとには、かつての首長の雰囲気を残す郡司が任命されていて、旧豪族として一般平民を支配していた。国司による統治は郡司抜きにはありえなかった。しかし、官制のうえでは、郡司の地位は国司よりはるかに低かった。
網野はこう書いている。
〈このように、[中国から移入した律令によって]確立した日本国の国制は最初に成立した本格的な国家の制度として、またそれを実現しようとした支配者層の強烈な意志によって、その後の列島社会に強く深い影響を与えたが、なお未開な素朴さのなかにあり、地域それぞれにきわめて多様な平民の社会生活を実際には組織しえていない早熟な国家だった。〉
8世紀に誕生した日本国は、律令によって人民を支配する体制を整えようとしていた。そして、表向き豪族の支配から切り離された人民の多くは、新たに生まれた国家に租税や貢納、軍役、雑役を提供しながらも、自由民として生きる道を求めつづけていたといえるだろう。
網野善彦『日本社会の歴史』を読む(3) [歴史]
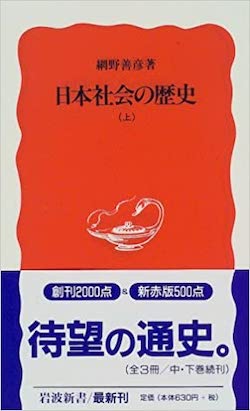
5世紀末から6世紀にかけて、朝鮮半島が揺れ動く。高句麗が南下し、百済は都を南に移した。倭と密接な任那(加羅)は新羅から圧迫を受けていた。こうした状況のなか、倭の大王ワカタケル(雄略)は、中国南朝の宋に上奏文を送り、親交を求めた。
朝鮮半島が激動するなか、吉備の首長連合は近畿の大王に反逆し、これにつづき、播磨、伊勢、出雲、武蔵も反抗の姿勢を示した。
朝鮮半島の動きがなぜ倭国に振動をもたらすのか。問題は任那の存在にある。ぼくなどは、任那とヤマトはむしろノルマンディーとイングランドの関係にあると考えてしまいがちなのだが、むろん何の証拠があるわけでもない。吉備の動きも、よくわからない。新羅との関係があったのだろうか。
それはともかく、ヤマトの大王周辺では、軍事力をもつ大伴氏や物部氏が力をもつようになる。ワカタケルはその軍事力を結集して、各地の叛乱を抑えこみ、その周辺に直轄地(屯倉)を置いて、監視と統制を強めた。
しかし、大王の地位は不安定だった。かならずしも血統で選ばれていたのではないかもしれない。6世紀初頭、越の国からオホドという大王があらわれる。のちに継体と呼ばれる人物である。これに筑紫の大首長、磐井が反対して立ち上がり、大きな戦争がはじまった。
継体が百済と密接な関係をもっていたのにたいし、磐井は新羅と独自の外交ルートをもっていた。オホドは物部氏を中心とする軍勢を北九州に派遣し、1年半の戦いの末、528年に磐井を下した。
朝鮮半島では任那(加羅)が新羅、百済の支配下にはいる。大王の周辺では、大伴氏が没落し、朝鮮の移住民とかかわりの深い蘇我氏が台頭してくる。
当時のヤマト政権について、網野は「大王に率いられた近畿の首長連合」が列島各地の首長集団を支配していたものと理解している。
大王と首長集団のあいだにはミツギ(貢納)を介してのゆるやかな服属関係が保たれていた。大王に服属する首長集団はトモと呼ばれていた。
首長集団は大規模に水田を開発するとともに、狩猟場を大王にささげ、大王の直轄地、すなわち屯倉(みやけ)とした。海民や山民を含む住民は大王に奉仕する者として、大王に贄(にえ)をささげ、時に直属の軍事を担った。
陶作(すえつくり)、錦織(にしごり)、鍛冶などを担う朝鮮半島からの移住民も首長に統轄され、政権に奉仕していた。
血縁集団は氏(うじ)と呼ばれ、大王から姓(かばね)を与えられていた。氏は地名(葛城、平群、蘇我など)や職掌(大伴、物部、中臣など)にもとづいてつけられていた。地名の名をもつ氏には臣(おみ)、職掌の名をもつ氏には連(むらじ)、また各地の首長には君(きみ)、直(あたい)などの姓が授けられた。
ヤマト政権の支配が列島に広がっていくと、大王は交通の要衝や征服地に直轄の屯倉を設けた。また大王や有力氏族は、それぞれの支配地の民を部民とした。これにより、大伴部や蘇我部などができあがる。その民は物資や労働、軍事力を提供するものとされた。そして、地方の屯倉や部民を管理する者として国造(くにのみやつこ)が任命される。国造は各地の有力首長だった。
6世紀が進むと、大王を長とする政府の体制が整えられていく。有力な氏族が大臣(おおおみ)や大連(おおむらじ)として政府を支える。そして、さまざまな職掌や職能をゆだねられた氏族が伴造(とものみやつこ)として、政府に仕えることになる。そのポストは次第に世襲されるものとなっていく。
それは大王という地位も同じだった。血統が優先された。何よりも政治の安定が求められたのである。
巨大古墳はあまりつくられなくなった。関東ではまだ大規模な前方後円墳がつくられていたが、列島の西部では、横穴式石室をもつ古墳が多くなり、これが次第に全国に広がっていく。
古墳は支配者の権威を示すものから、死者を弔うものへと変わっていった。横穴式石室では、羨道を伝って玄室にはいることができ、その玄室には武具や馬具、装身具、土器に盛られた飲食物が備えられていた。
ただし、古墳はあくまでも支配者のものである。一般の平民が共同墓地に埋葬されていたことはいうまでもない。
大王を中心に祭祀や儀礼が整えられていった。農耕儀礼のなかでは、春の種下ろしの祭りと、秋の収穫の祭りがもっとも重要な行事だった。各地の首長が初穂を大王に貢納し、大王が種籾を首長に与える儀礼もおこなわれるようになった。網野はこれを新嘗祭の原型とみている。
水田を破壊したり略奪したりする行為は最大の罪とされた。祭りをけがしたり、人を殺傷したり、母子相姦したりすることも大きな罪だった。罪には相応の処罰がともなう。特異なのは、刑罰とともに、罪による穢れを祓い清めによって除く儀式がおこなわれていたことである。
ここで網野が強調するのが、稲作中心史観からの脱却である。当時も稲作だけが生活の中心だったわけではない。畠地では麦や豆、桑などがつくられ、栗や柿の栽培もおこなわれていた。山の幸、海の幸も採集されていたし、海でも漁がおこなわれていた。
朝鮮半島からは、多くの職能集団が移住していた。玉造をしたのもかれらである。製塩や製鉄、漆器、木器などをつくる専業集団などもあった。そうした点をみると、この時代は分業が盛んになり、流通が活発になり、市庭での交易も広くおこなわれていたことがわかる。
朝鮮半島を経由して、儒教、仏教、道教もはいってきた。医術、暦、易なども伝えられ、本格的な国家形成がはじまっていた。しかし、北海道や東北北部、南九州は、まだヤマト政権の圏外にあった。
ヤマトの政治は朝鮮半島の動きと無関係ではなかった。532年に任那(加羅)は新羅によって併合された。その後、新羅と百済のあいだで、激しい戦闘がくり広げられた。
そのころヤマトでは、対外的危機感にあおられれて、大王の地位の強化と世襲化がはかられていた。
だが、有力首長どうしの争いはやむことなく、とくに蘇我氏と物部氏の対立が激しくなった。敏達のあと大王についた用明が587年に病気で死ぬと、次期大王をめぐって、物部、蘇我が激突し、蘇我が勝利して、崇峻を大王とし、蘇我馬子がみずから大臣の地位についた。
崇峻は任那の再建をはかり新羅に出兵しようとした。馬子はこれに反対し、592年に崇峻を暗殺した。崇峻に替わって大王に立てられたのが、さきの敏達の大后、豊御食炊屋姫(とよみけかしきやひめ)、すなわち女王、推古である。
推古自身は政治にかかわらなかった。大臣馬子と協力しながら、政治を実際に動かしたのが、用明大王の子、厩戸(うまやど)である。
そのころ、中国では隋が全国を統一した。598年、隋は大軍を動かして高句麗を討った。これに呼応して、ヤマトも任那回復をめざして600年に新羅に出兵した。しかし、失敗に終わる。
その同じ年、倭王は100年ぶりに中国に使節を送り、隋に朝貢した。
このころ、ヤマトでは飛鳥寺が完成し、難波にも四天王寺が建立されようとしていた。
王子厩戸は仏教を積極的に受け入れ、603年には十二階の冠位を定め、604年にいわゆる「憲法十七条」をつくって、王権の強化に努めた。
607年、厩戸は小野妹子を使いとし、隋に入貢した。そのときの国書には「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す、恙無きや」と記されていた。
611年から614年にかけ、隋の煬帝はまたも高句麗を攻めたが、失敗し、それ以降、隋は衰えていく。618年に隋は滅び、唐王朝がはじまった。
622年以降、ヤマトは新羅と対立し、政権内に動揺が生じはじめる。理想の政治がほど遠いことを感じながら、この年、厩戸王子は死ぬ。法隆寺金堂の釈迦三尊像は、王子の死後、鞍作鳥(くらつくりのとり)によって完成された。
「厩戸は、多くの伝説とともに人びとの敬仰を集め、のちに『聖徳太子』と呼ばれるようになった」。そう網野は記している。
[法隆寺。ウィキペディアより。]
網野善彦『日本社会の歴史』を読む(2) [歴史]
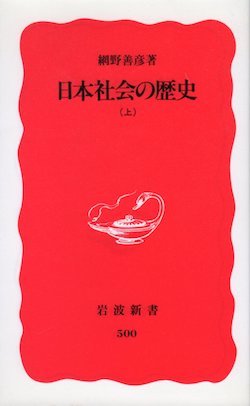
人間の経済生活は、大きく分けて、狩猟採集生活、農耕生活、商品生活の3段階をたどったというのが、ぼくの考えだ。もちろん、それは画然とした区別ではなく、重層的ではあるのだが、あくまでも中心がどこにあるかというのにすぎない。
縄文時代にくらべると、弥生時代はずっと短い。しかし、この時代に、経済生活の中心は狩猟採集から農耕へと移行する。弥生時代が日本の歴史でも大きな曲がり角だったことがわかる。
網野によれば、中国から朝鮮半島に稲作技術がもたらされたのは紀元前1000年以前とされる。紀元前3世紀には、九州北部ではじめて弥生土器が登場している。だが、それ以前から稲作はおこなわれていた。
弥生土器は穀物に欠かせない土器として、九州一円から四国南部にまで急速に広がった。このころの遺跡からは石斧や石包丁も出土する。織布もおこなわれ、鉄器も用いられていた。
弥生文化の流入を支えたのは、朝鮮半島南部、北九州、瀬戸内海をむすぶ海で活躍した海民だった、と網野はいう。そして、東北、南九州をのぞく、列島各地では、弥生時代から古墳時代中期にかけ約800年のあいだ、首長制の社会が展開されることになる。
弥生前期の200年間、列島の東部では依然として稲作への抵抗が強く、縄文文化がつづいていた。いっぽう、西部では朝鮮半島からの流入を含め、急速に人口が増えていく。
紀元前1世紀から紀元後1世紀にかけての弥生中期になると、稲作は関東から東北南部まで広がっていた。水田は低湿地だけではなく谷間にもひらかれる。用水・排水用の溝が掘られ、田植えもおこなわれるようになった。収穫や脱穀のための道具もつくられている。種籾は神聖なものとして高床式の倉庫に保存されていた。
農耕に神事や協働作業は欠かせない。それを指揮するようになったのが、共同体の首長である。
弥生時代につくられたのはコメだけではない。ムギ、アワ、ヒエ、マメ、ソバ、イモなどの穀物のほか、根菜や蔬菜、果実なども栽培されていた。焼畑がおこなわれていたかもしれない、と網野はいう。
織物用として、苧麻(カラムシ)や蚕のための桑も植えられていた。漆やキノコも採集されていた。狩猟や漁撈、海藻や貝の採取も盛んだった。本格的な製塩もおこなわれていた。
こうしてみると、弥生時代には現代の生活の基本となる要素がほとんど出そろっている。
弥生文化にはひとつの大きな特徴がある。
「弥生文化は単に稲作文化というだけでなく、強烈な海洋的特色を持っていた」と網野はいうのだ。
弥生時代は、大陸や半島との交流のなかでつくられていった。ぼくなど、それはイギリス史でいう民族大移動の時代に匹敵するのではないかと勝手に思うほどだ。
近畿や北九州などで有力な首長があらわれる。『後漢書』には、倭の奴国王が漢に使いを送り、光武帝から印綬を授けられたという記述がみられる。
弥生中期の列島西部では、沖積平野の中央部や台地のうえに、かなり大きな集落がつくられていたことがわかっている。その周囲は溝や濠によって囲まれていた。
瀬戸内海沿岸から大阪湾にかけては、二、三百メートルの高台に土塁や空堀をめぐらせた集落もあらわれた。このことは、この地方に何らかの軍事的緊張があったことを推測させるという。
『魏志』は、2世紀の後半、「倭国が大きく乱れ、長期にわたって戦いが続いたと記述する。その大乱は卑弥呼が邪馬台国の女王として立つことによって収まったとされる。邪馬台国の所在については、北九州説と大和説があって、いまだに結論がでていない。
『魏志』の伝える倭人社会は、現代の日本の民俗や韓国の習俗とどこか似ている、と網野はいう。それは「決して稲作一色の農耕社会ではなく、農耕とともに漁撈をはじめとするさまざまな生業に支えられ、呪術に支配されたマジカルな色彩の強い社会であった」。
そこでは「大人」といわれる首長の一族と平民の「下戸」とがはっきりと分かれており、「生口」と呼ばれる奴隷もいた。
邪馬台国はすでに立派な国である。中央には大きな邸閣があり、地方の国々には租税と課役が課されている。国々の産物を交易する市庭(いちば)も設けられている。支配下にある伊都国には役人を置き、中国や朝鮮との交易を取り締まっている。
卑弥呼の宮室には千人の婢がはべり、武装した兵士が警備を怠らず、男はひとり弟のみが出入りを許されていたという。
238年に卑弥呼は魏に多くの贈り物と使いを送り、「親魏倭王」の称号を得ている。247年には戦乱がおこり、そのかんに卑弥呼が死んだ。男王があとを継いだが、首長たちはこれに服することをこばみ、卑弥呼の宗女、壱与(イヨ、あるいは台与=トヨ)が位について、ようやく戦乱がおさまったとされる。
266年、邪馬台国は魏の後続王朝、晋に使いを送っている。しかし、中国の史書では、それ以降約150年間、日本列島に関する記述はなくなる。
網野によると、倭国の大乱は、近畿・瀬戸内海の首長連合と北九州の首長連合とが統合される過程で発生したものではないかという。ただし、どちらがどちらを統合したかについては、まだ結論がでていない。
中国の史書によると、そのころ日本列島西部では青銅製の祭器を用いた祭祀が盛んになっていた。また朝鮮から輸入された鉄によって、鉄製の武器や工具もつくられるようになっていた。土器や木製の道具も大量に生産されている。
社会的分業が進み、市庭(いちば)での交易も日常化している。網野は市庭を現代の市場概念とはっきり区別しているように思われる。弥生時代の市庭とは、はたしてどのようなものだったのだろうか。
4世紀前半、中国大陸は動乱の時代を迎える。朝鮮半島では高句麗、百済、新羅の三国時代がはじまった。かといって、日本と朝鮮との関係が途絶えたわけではない。新羅に倭人がしばしば侵入したという記録が残っている。
このころ近畿から瀬戸内にかけて、大きな前方後円墳がつくられるようになる。埋葬者を収めた木棺のなかには、鏡・玉・剣の副葬品セットが添えられた。
4世紀後半から5世紀にかけ、前方後円墳は東北南部から九州南部まで広がった。古墳に埋葬された首長たちは、近畿の勢力と同盟関係を結びながら、それぞれの地域を支配していた。
とはいえ、列島の東と西では、かなり生活様式が異なっていた。「列島の各地域の個性は、前方後円墳の拡大にもかかわらず、なお失われることなく、その差異はさらに著しくなった」と、網野は書いている。
4世紀後半、朝鮮半島では高句麗、百済、新羅の抗争が激しくなっていた。百済は新羅や倭と同盟関係を結んで、高句麗に対抗しようとした。367年には倭に使いを送り、372年には倭王に七支刀を贈っている。いっぽう新羅も402年に倭と通交している。
倭と朝鮮半島との関係は密接だった。朝鮮半島からはさまざまな職能をもつ人びとが倭に移住してきた。一説では、弥生時代から古墳時代にかけて、100万人から150万人が列島西部にやってきたといわれる。それにより、鵜飼のような漁法、絹や布の織り方や縫い方、製紙、製鉄や鍛冶・鋳造、土器や陶器の製造、土木建築技術、漢字、芸能などがもたらされた。半島からは馬具や鉄の原料なども輸入されている。
5世紀になると、河内に巨大な前方後円墳がつくられるようになった。誉田山(こんだやま)古墳[応神天皇陵?]や大山(だいせん)古墳[仁徳天皇陵?]がよく知られている。古墳の周りには人物や動物をかたどった埴輪が並べられていた。

[大山古墳。ウィキペディアより]
こうした巨大古墳を建設するまでにいたった首長を大王と呼んでもよいだろう、と網野はいう。
このころ中国は南北朝の分裂時代にはいっていたが、南朝の宋の史書には、5人の倭王が479年から502年にかけて、宋に使者を送ってきたことが記録されている。
とはいえ、網野によれば、河内の大王は列島全体に権力をおよぼしているわけでなかった。吉備には大きな勢力をもつ大首長がいた。有明海沿岸や出雲、北陸の首長たちも、独自に半島や大陸との通交ルートをもち、みずからの勢力圏を築いていた。
半島や大陸からは先進的な製鉄技術や農業技術がもたらされ、それらが各地に広がろうとしている。
しかし、民衆の生活は竪穴式住居に住み、素朴な貫頭衣をまとうというものだったという。その日々は稲作にまつわる祭や先祖崇拝、自然崇拝、ミソギやはらい、呪術によっていろどられていた。
5世紀末から6世紀にかけて、大転換がはじまる。大和の大王が、東国、四国、九州へと、支配を広げていく。
つづきはまた。



