文部省留学生に──美濃部達吉遠望(16) [美濃部達吉遠望]

1年で内務省を辞め、1898年(明治31年)9月から東京帝国大学大学院で学ぶことになった美濃部達吉は、内務省試補の扱いで1年ほど内務省から手当をもらうことになった。それによって学費と生活費をまかなうことができたのである。
内務省にはときどき顔を見せるだけでよかった。そのため、省内からは「チョコ参」と呼ばれていたが、たしかに、それほど省内で仕事があったわけではない。法律問題について意見を聞かれる程度で、あとはAlbert Show(アルバート・ショー、1857〜1947)の“Municipal Administration in Continental Europe” という本の翻訳を依頼されたくらいだという。
この本はアルバート・ショウ原著、内務省地方局訳『欧洲大陸市政論』として、1899年(明治32年)10月に有斐閣書房から出版された。翻訳書ではあるが、これが処女作になった、と達吉本人は記している。
ところが、これが達吉の初出版かといえば、そうではない。同じ有斐閣書房から、この年8月に達吉は自身の名義で『改正府県制郡制要義』という本を出版している。厳密には、こちらこそがかれのデビュー作である。しかし、翻訳書のほうが先に原稿が仕上がっていたので、自分にとっては、こちらのほうが最初の作品だという意識が強かったのだろう。
アルバート・ショーはアメリカのジャーナリストで、雑誌編集者、ジョンズホプキンズ大学で講義をしたこともある。1883年にイギリスとヨーロッパ大陸を回り、さまざまな都市の行政を研究し、それをイギリス編とヨーロッパ編の2冊の本にまとめた。『欧洲大陸市政論』はそのひとつである。
大学院で学ぶ達吉は、内務省から依頼を受けて、1895年に発行されたこの本の翻訳に取り組んだ。ショーがヨーロッパに渡って、各地の都市の行政を見て回ったのは、アメリカの都市の腐敗がすさまじかったので、それをただすためのヒントを見つけたかったからだという。
内務省で最初にこの本に着目したのは誰だったのだろう。東大教授であり、内務書記官を兼ねる師の一木喜徳郎だったかもしれないし、あるいは直接の上司で府県課長をしていた井上友一だったかもしれない。井上は帝国大学法科大学の英法科を卒業し、のちに東京府知事となり、自治の第一人者と呼ばれた人物である。
いずれにせよ、達吉はショーの著作に真剣に取り組んだ。ジャーナリストによるヨーロッパ諸都市の生き生きとした記述にひかれたことはまちがいない。
ショーは19世紀後半の特徴は、大都市の急速な膨張だとして、市政の重要性を強調していた。著書にはフランス、ベルギー、オランダ、スペイン、イタリア、ドイツ、スイス、オーストリア・ハンガリーの諸都市の状況が、ジャーナリストの目で事細かに記述されていた。いちばん詳しく書かれているのは、ヨーロッパを代表する都市パリだったが、ミラノやフィレンツェ、ベルリン、ウィーン、ブダペストなどにも筆が及んでいる。
明治の内務省がヨーロッパ各国の市政を視野に入れていたことは、ちょっとした驚きである。中央からの郡県制を敷くだけではなく、地方自治のあり方を模索していたといえるだろう。しかも、達吉にとっては、この本を通じて、パリやベルリンの様子を知ることは、留学の予行演習ともなったはずである。
本書の冒頭はパリ市の概要にあてられていた。達吉はそれを次のように訳している(原文はカタカナ、現代表記とし、多少読みやすくした) 。
〈欧州諸国の都市は第十九世紀において最も偉大なる発達を遂げたり。往事における欧州の市街は実に狭隘にして暗黒なる迷宮の府たるに過ぎざりしが、近世においては即ち道路は整い、公園は飾られ、交通の機関、ガスの供給、下水、上水の設備ことごとく備わらざるなく、これを往事に比すれば霄壌(しょうじょう)もただならず[天地の差であって]、しこうして欧州都市の発達がかくのごときに至りしは皆パリ市にその師導[指導]の恩を荷(にな)えるものにして、パリは実にもって近世的都市の模範となすべきものなり。〉
おそらく内務官僚にとっても、パリの改造は日本にとってもこれからの都市のモデルととらえられていたはずである。
それにしても、本にして600ページ近くになる大著をおそらく半年ほどで訳したところをみると、達吉の語学能力の高さがうかがえる。
これから留学するにちがいないドイツの都市についても、達吉はこの本から多くの知識を得ていた。しかも、この本は市政がどうあるべきかをも語っていた。
たとえば
〈ドイツの市政府は市の各種の利害より独立したる別種の物体にはあらずして、ただちにこれとその生存を同じうするものなり。しこうして市とはその区域内に包含せる人民および人民の利害の集合にほかならず。ドイツの市政府の観念には、そのなしうべき事務の範囲に関してひとつも制限あることなく、いやしくも市の利益を増加し、および市民の幸福を増進しうべきものは、ことごとくこれを実行するの職務を負うものなり。〉
こうしたとらえ方から、達吉が地方自治のあり方を学んだことは、じゅうぶんに推測できる。
ベルリンについては、こんなふうに書かれていた。
〈ベルリン市の進歩の新時期は一八六一年にその端を啓(ひら)けりというを得べし。この都市においてベルリンは新たにその郊外なる一大地域を併合し、旧時の城壁はことごとくこれを毀壊(きかい)して新地域との交通を自由ならしめたり。一八六一年には皇帝ウィルヘルム[一世]新たにプロイセンの王位に登り、しこうしてこの時より以後ベルリン市に対する王国の自由政策は開始せられたるなり。この年において新市庁ははじめて開かれたり。プロイセンの欧州強国の列に加わるやベルリンをしてパリと競争するの希望を起こさしめ、しこうしてパリにおけるハウスマン[ジョルジュ・オスマン]の市街改造は大いにベルリンをして奮起せしめたり。〉
こうした一節を訳出しながら、達吉は大いに留学への夢を膨らませていたと思われる。
この本はいま読んでもおもしろい。当時のヨーロッパ諸都市のありさまが手にとるようにわかる。
自身が著した著書『改正府県制郡制要義』も大冊である。留学を前にした1年足らずの大学院生活のなかで、よくまとめたものだ。
この本は、府県とは何かからはじまって、知事や議会、役所など府県の機関、府県の自治権、府県の監督、さらには郡の政治を論じたものだ。
達吉の出発点が憲法ではなく、むしろ地方自治にあったことがうかがえる。
その緒言に達吉はこう書いている(前と同様、読みやすくした)。
〈維新の後ひとたび地方の権力を削ぎて、これを中央に統一し、万機細大となくこれを中央に帰したるにより、一時自治制の跡を絶ちたりしが、明治十一年(七月)第十八号布告をもって、はじめて府県会規則を制定し、ついで明治十三年(四月)第十八号布告をもって区町村会法を布き、地方自治の制度は再びその端緒を開きたりしが、政府はなお鋭意その制度の完成を勉め、ドイツ人モッセ氏をして市町村制の草案を起草せしめ、案成るの後、明治三十一年(四月)法律第一号および同年法律第二号をもって市制および町村制を公布し……(以下略)〉
そして「本著諭せんと欲するところは即ち新府県制および郡制の規定の実体を説明せんとするにあり」と記している。
達吉のこのデビュー作は、1890年(明治23年)に公布された「府県制・郡制」が1899年(明治32年)に全面改正されたのを受けて、その条文を逐一解説したものである。
明治政府の地方制度、すなわち府県制・郡制はそれ自体、興味のあるテーマだが、いまそれを詳しく述べるのはためらわれる。
ただ、その緒言からもうかがえるように、達吉が地方における「自治」の復活に大きな希望を托していることはあきらかだろう。
本書において、達吉は府県を法人ととらえ、自治体は国家から直接指示されるわけでない独立の意思をもって、公共の事務を処理するという立場を打ち出している。
将来は明るかった。いや、少なくともそうみえた。
こうして大学院在学中にこの2冊の本を仕上げて、達吉は文部省留学生として、1899年(明治32年)8月にヨーロッパに向けて出発することになる。文部省から比較法制史研究のため、3年間、独仏英3国への留学を命ずという指示を受けたのは5月のことである。留学するまでという約束だったので、8月には内務省試補の役職も解除された。
インフレーションをめぐって──ガルブレイス『ゆたかな社会』を読む(7) [経済学]

もともとガルブレイスは「ゆたかな社会」には、インフレーションがつきものだと考えていた。それを克服しようとしても、そこには大きなジレンマがひそんでいるととらえていたのだ。だが、1998年の最終版(第5版)で、この考え方は誤りだったとしている。
戦後はインフレの時代だった。しかし20世紀の終わりからは、低失業・低インフレ、低成長の時代がつづくようになったからである。
その面では、たしかに時代が変わったのである。
そもそもガルブレイスは、戦後インフレの仕組みを賃金・価格の相互作用としてとらえていた(ただし2度の石油ショックによる狂乱物価はあきらかにこれとは異なる)。
全般に物価が上がると、労働組合は経営者と交渉して、賃金上昇を勝ちとる。すると、経営者は賃金上昇分をカバーするため、製品の価格を上げる。こうして価格の上昇が社会全体に波及すると、全般に物価が上がるため、労働組合は労働者の生活を守るため、ふたたび賃金上昇を要求せざるをえない。このようなプロセスがはじまると、賃金と物価の悪循環がはじまる。
インフレが収まらなくなると、政府はそれに対応するため、金融政策や財政政策を発動する。景気の引き締めによって、物価の上昇は抑えられる。しかし、その結果、投資と消費の削減を招き、失業が増加する。物価と雇用はトレードオフの関係にあった。そのため、むやみな金融・財政政策はとれなかった。
しかし、いまでは賃金・物価の悪循環はなくなりつつある、とガルブレイスはいう。それはひとつに労働組合が弱体化したためである。産業の中心は、いまや伝統的な産業からサービス業、通信業、ハイテク産業、娯楽産業などへと移ってしまった。労働組合が弱体化すると、賃金はなかなか上がらなくなる。こうして雇用水準が高いときでもインフレ率が低い状態がつづくようになった。
最終的にガルブレイスは、そのように考えるようになった。
こうした理解が正しいかどうかはわからない。
ここでは、1998年の最終版を中心に、『ゆたかな社会』のインフレーション論を紹介しておくことにする。
ガルブレイスはいう。
戦争や内乱や飢饉のときにはインフレがつきものだった。しかし、いまでは平和と繁栄の時期にもインフレが居座るようになり、とくに戦後はインフレと共存する期間が長かった。
一般にインフレは好ましくないとされる。価格の上昇は人を不安にさせるからだ。だが、その割にインフレを抑えようとする努力がなされなかったのは、インフレによって利益を得る人がいたのと、賃金の上昇がそれをカバーしたこと、さらに、それはいずれ収まると考えられてきたからだ。
やがてそうもいかなくなって、政府が介入するようになった。しかし、それは不況のときほど真剣ではなかった。インフレは自然に収まるという考えは依然として根強かった。むしろ、へたに対策をとれば、不況をもたらすという恐れもあった。それでも、インフレはどこかで抑えなくてはならなかった。
ガルブレイスが経済を寡占部門と競争部門に分けていることに注目すべきだろう。鉄鋼・機械・自動車・化学・非鉄金属などの寡占部門においては、計画的に生産費を価格に転嫁することができる。ところが農業などの競争部門では、生産者は決められた価格に従わなければならない。
そのうえで、ガルブレイスは生産を増やしても、インフレの解決にはならないという。それは投資の増加につながり、需要を増やすことになって、かえって価格上昇に拍車をかけてしまうからだ。
それに大企業は安易に生産を拡充しない。一定の需要があるかぎりできるだけ価格を維持しようとする(価格を上げるのは、むしろ需要が減った場合だ)。これにたいし、競争産業では需要に敏感に反応する。生産高を一定とすれば、需要が大きくなれば価格は上昇し、需要が小さくなれば価格は下落する(逆に需要が一定なら、供給の変化によって価格は上下する)。
ここに登場するのが労働組合だ。そして、企業は賃上げを口実に価格を上げるのが常套手段になっている。ここから賃金と価格の上昇スパイラルがはじまるというわけだ。
インフレでもっとも苦しむのは大企業体制に帰属する人びとではなく、自分を保護する後ろ盾をもたない個人やグループだ、とガルブレイスはいう。農民もインフレの悪影響を受ける。最大の被害者は年金生活者だろう。公務員も被害をこうむりやすい。自由職業の場合は、立場に応じてさまざまである。アメリカの弁護士や医者などはおそらくそのサービス料を上げることができる。
インフレが人びとに与える影響はさまざまだ。しかし、いずれにせよ、インフレを統御しなければならないという意見が浮上し、政府が乗りださざるをえなくなる。
ここで問題になるのは、需要水準を抑えるべきか、それとも賃金と物価の悪循環を断ち切るべきかということだ。両面作戦をとって、需要をある程度抑えながら、賃金・物価の悪循環を止めるなら、インフレは克服できる。しかし、そこにはジレンマがひそんでいる、とガルブレイスはいう。
金融政策についてみていこう。
ガルブレイスはいう。
19世紀、イングランド銀行は公定歩合を動かすことによって、景気の安定をはかるようになった。政治とは一定の距離を保ちながら、金融政策によって経済をコントロールするという考え方が生まれたのは、このころからだ。
金融政策の決定は舞台裏でおこなわれ、人びとはいつのまにかそれによって動かされる。そのため、金融政策は神秘的で魔術的なものとすらとらえられていた。
インフレ退治を期待されたのも金融政策だった。利子率が上がれば貸付用資金の供給が減り、生産者や消費者の借入が減って、需要総額が抑制される。それによって価格は安定すると考えられた。
だが、実際はそう理屈どおりにはいかなかった。多少利率が上がったところで、刺激された消費者の需要は減らなかったし、投資もさほど減らなかったからだ。金融政策の効果を台無しにする方策はいくつもあった。
ただし、金融政策がはたらくとすれば、それは経済活動のなかでも、いちばん移り気な要素にたいしてであり、それが長期の投資だった、とガルブレイスはいう。すると、金融政策はきびしい不況を招くほどに投資を減らしてしまう危険性がある。そうした事態は避けなければならない。
ガルブレイスはさらに、高金利は大企業より、建設業者や中小企業、農民に負担を強いることになると書いている。
そこで、金融政策にたいするガルブレイスの見方は否定的なものとなる。
〈金融システムに魔法は存在しない。どんなにみごとに秘術めかして運用されたとしても、ゆたかな社会ではとうぜんとされる生産と雇用の責務と価格の安定性を調和させることはむずかしいのである。〉
これはインフレ時代の発言だが、現在でもあてはまる教訓だろう。
さらに進もう。次は財政政策だ。
一般に保守派は金融政策を好み、リベラル派は財政政策を好むといわれる。
財政政策は金融政策のような神秘性をもたず、簡明直裁に作用する。財制裁策でも、増税は景気の停滞をもたらす。賃上げは抑えられ、需要は減り、物価は安定する。その効果は金融政策より著しいほどだ。しかし、実際には増税政策が嫌われてきたことはいうまでもない。
インフレ対策のために積極的な財政政策をとろうとすると、それは増税ということにならざるをえない。政府支出の削減はだいたいにおいて認められないからだ。それはかけ声だけで、実際には予算はむしろ膨らんでいく。
不況対策としては減税と公共投資が広く受け入れられるのに、インフレ対策としての公共支出削減はなかなか認められない。増税もまた強い抵抗を受ける。
増税(とりわけ金持ちへの課税)は所得分配に影響をもたらすため、保守派から強い抵抗を受ける。さらに増税は需要の減退をもたらすため、生産にもマイナス作用としてはたらき、ひいては失業を増やす可能性もある。そのため、インフレを抑えるために増税政策がとられることはまずない、とガルブレイスはいう。
とはいえ、財政政策と賃金・価格統制を併用すれば、インフレには効果を発揮するかもしれない、とガルブレイスは述べている。こうした統制にたいする反発は根強い。だが、政府支出をある程度抑えながら、賃金・価格をの統制することは可能だと考えていた。
インフレ対策としては、金融政策も財政政策も、それなりに大きな矛盾をかかえている。本書の最終版が刊行された1998年の段階では、幸い失業率は低く、インフレも抑えられているが、それがどこまでつづくかはわからない、とガルブレイスは述べている。インフレの問題はけっして終わったわけではないのだ。
資本の力とローンの話──ガルブレイス『ゆたかな社会』を読む(6) [経済学]
生産には既得権益があるとガルブレイスは書いている。それにもっともかかわっているのは実業家であり、かれは成功の度合いに応じて報酬を得、同時に社会的な敬意を受ける。これにたいし、公共サービスに携わる人は忘れられがちで、現代社会ではもっぱら実業家に注目が集まっているという。
その実業家は自身の利益のために闘う。そのため国家や知識人には懐疑をいだいてきた。
アメリカのリベラル派(自由主義者)は最近まで実業家を支持してきた、とガルブレイスはいう。それは商品生産の一義的重要性を認識していたからだ。生産を増やせば、失業問題を含むすべての社会問題は解決すると信じられていた。保守派が均衡予算の放棄をためらったのにたいし、リベラル派は政府の役割の拡大を支持した。
このあたり、「リベラル派」あるいは「保守派」というイメージが、アメリカと日本では、かなり食いちがっていることを認識すべきだろう。リベラル派は自由主義者とも訳されるが、そう訳すと、日本ではリベラルと自由主義がちがうようにみえてくるのが不思議である。
だが、その混乱は、アメリカでも同じようで、たとえばハイエクは自分は保守派ではなくリベラル派だと主張したが、そのリベラル派とはあきらかにケインズのようなリベラル派ではなく、もっと古典的なリベラル派である。その古典的なリベラル派、とりわけハイエクを継承したと称するフリードマンなどが「新自由主義者」を名乗るのだから、ぼくのような素人は、ますます混乱が増すばかりである。
そして、当のガルブレイス自身もリベラル派にはちがいない。だが、正統ではなく異端の(ケインズ左派の)リベラル派だったといえるだろう。ほんとうにややこしい。
ガルブレイスは正統リベラル派(日本では自由主義者という)の考え方を次のようにまとめている。
「リベラル派は、生産がすでにありあまる財を増やすだけの時代になっても、生産の増大こそが政治的成功を勝ちとる試金石だと本心から信じつづけていた」
生産至上主義(すなわちGDP至上主義)はいまだに根強い。
アメリカでは、リベラル派が実業家を支持し、保守派が実業家を牽制するという構図が生まれていたようにみえる。ことばのイメージでいうかぎり、これは日本とは逆の構図だったようにみえる。
混乱の海から抜けだそう。政治軸を整理し、再編してみなければならない。
ガルブレイスは実業家の時代はかげりを見せはじめているという。きらびやかな財を誇るのは俗悪とみなされるようになった。社会活動に貢献しない実業家は軽蔑される風潮すらある。そして、実業家と競争関係にある知識人がもてはやされるようになった。
生産の量ではなく、生活の質が問われるようになった。若者たちは、人種の平等や環境問題、公共と民間の役割、社会の持続可能性、さらに率直な芸術的・知的表現に関心を深めるようになっている。
それでも、この社会ではまだ生産が至上の力をもちつづけている、とガルブレイスはいう。この生産の力をわれわれは資本の力と言い換えてもよいだろう。

先に進む。ガルブレイスは小さなスケッチを重ねるように、現代の商品世界の様相をえがいている。
次は「借金とりがやってくる」という章だ。
「ゆたかな社会」は多額の消費者ローンのうえに成り立っていることがあきらかになる。
生産の目的は消費である。この定言からすれば、経済の主体は消費需要であって、生産はあたかも需要に従属するかのようにみえる。しかし、ガルブレイスはそうではないと考えている。現実は生産(資本)こそが主体であり、消費は生産に従属するのである。
だが、生産にとって消費が減るのは、生産自体を脅かすことになる。生産が商品の需要に依存していることはまちがいないからである。そのため経済政策としては失業の増大を避け、できるだけ完全雇用を維持することが求められる。
ガルブレイスは生産が欲望を生みだす複合作用として、消費者負債の増加を指摘している。
アメリカでは消費者負債が戦後、圧倒的に増加したという。不動産貸付を除いても、信用残高は1956年に425億ドルだったものが1967年には991億ドルと倍以上に増えている。その大半は自動車ローンだった。
この間、個人可処分所得も増加したが、その割合をはるかに超えて、個人ローンの割合が増えた、とガルブレイスはいう。いまではその額ははるかに多いはずだ。
「ゆたかな社会」が個人ローンのうえに築かれていることを忘れてはならない、とガルブレイスは警告する。多くの家庭がローンの支払いをかかえている。
〈不可避とはいえ、こうした大衆規模での負債拡大にともなう緊張はかなりのものである。それ自体、外から喚起されて生じた欲望が残したものは、借金であり、それは分割払いで商品を買った人に冬の雪のように舞い下りてくる。全国の何百万の家庭が承知しているのは、通知が届くとまもなく回収人がやってくるということだ。このすばらしい社会では、借金とりこそが中心人物なのではないか。〉(拙訳)
そこまで悲壮にならなくてもよいかもしれない。だが、ローンやクレジットの支払いが、いつもわれわれの生活を追いかけてくるのも事実である。
ガルブレイスは想像する。
あまりにも多くの宣伝に辟易して、宣伝効果が失われてしまうときがやってくるかもしれない。そうなると、人はものを買わず、貯金を殖やして、借金を返済する。すると総支出が減るから、総生産も減って、投資も減り、経済は不況におちいる。逆に欲望が刺激されすぎて、負債が大きくなりすぎるときには、貸し倒れの危険性が生じる。
昔、カネを借りるのは、ほとんど企業が投資するためだった。いまでは消費者が借金を増やしている。それによって、経済の不確実要因が増幅される。なぜなら、消費者は景気のいいときに借金を増やし、景気の悪いときに借金を減らす傾向があるからだ。そうした消費者行動がより大きな景気の山と谷をつくることになる、とガルブレイスは指摘する。
何はともあれ、「ゆたかな社会」では、消費者負債が経済ファクターのひとつとなった。
商品の生産と販売が神聖視される社会では、消費財への融資を抑え、その販売を抑えることになる措置をとるのはきわめてむずかしい。しかし、経済的安定と社会保障の観点からすれば、政府は何らかの予防措置をとる必要がある、とガルブレイスは主張している。
このあたりは、まさに2008年のリーマン・ショックを予想したかのような発言である。
最後にガルブレイスは「ゆたかな社会」のじつに奇妙な特徴を挙げる。それは民間でつくられる財にたいしては、それがどんな商品であっても、負債が奨励されるのにたいし、公共サービスへの支出(学校、病院、図書館、交通機関など)はできるかぎり抑えられていることだという。
こうした社会的アンバランスについては、別の章でまた論じられるだろう。そして、こうしたガルブレイスの発言が、新自由主義を掲げるフリードマンらからの強い反発を受けることになるのである。
このあと、インフレーションの話がはじまる。
『ゆたかな社会』は1958年に初版がだされ、1998年の第5版まで、じつに40年にわたって改訂されつづけたが、そのなかでもっとも変更されたのが、インフレーションをめぐるいくつかの章である。
当初、ガルブレイスは「ゆたかな社会」にはインフレがつきものだと考えていた。ところが、最終版ではその考えが誤っていたことを認めている。
インフレはすっかり収まってしまった。その理由を含め、次回はそのあたりを読み解くことにしよう。
依存効果──ガルブレイス『ゆたかな社会』を読む(5) [経済学]

生産の増加は、職を増やし、不平等を見えなくすることで、「ゆたかな社会」をもたらした。だが、なぜ生産を増やしつづけねばならないのだろうか。
生産を増やすのは、かつては基本的な衣食住をより多く満たすためだった。だが、いまではもっとエレガントな自動車や、エキゾチックな食べものや、エロティックな衣装や、洗練された娯楽、つまり敏感で、伝染性があって刺激的な現代的欲望を満たすことに生産が向けられるようになった、とガルブレイスはいう。
経済学はなによりも生産を重視する。与えられた資本と労働、資源のもとで生産効率をいかに高めるか、生産の阻害要因をいかに排除するかが経済学の大きな課題となってきた。
そして、生産の重要性と消費者需要の切迫性を強調することが、経済学の習い性になっていた。つまり、どんなくだらない生産であろうと、どんなくだらない消費であろうと、生産と消費は、それ自体擁護されなければならなかったのだ、とガルブレイスはいう。
現在認められている消費者需要の理論はどのようなものだろうか。
はっきりいって、それはじゅうぶんに研究されているとはいいがたい。肉体的であれ心理的であれ、人の欲望はかぎりなく、それがどこまで充足されたかを証明することはできない。欲望は消費者の個性にもとづくもので、経済学にとって欲望は与件にすぎないとされる。
経済学にとって重要なのは需要と供給の価格理論であって、いまでは限界効用理論が人間の基本的な経済活動を説明すると考えられている。
なかでも限界効用逓減という概念が重要である。それによると穀物がありあまるようになると、穀物への需要は大きな伸びを示さなくなり、所得はほかのものの消費に回されるということになる。
経済学において限界効用理論はより精緻化され、都合の悪い事実は排除されていった。
そのさい、経済学では商品そのものの評価はされないことになった。必要か不要か、重要か重要でないかは関係ない。それが売買されることだけが問題なのだ。
消費者の関心を引く商品には無限の組み合わせがある。そして個々の商品の限界効用は逓減するけれども、別の新たな商品が比較的に高い限界効用をもたらす。そして、あらたな製品が登場するかぎり、消費者は次々と欲望を満たすように行動する。その行動は商品やサービスの供給がなされるかぎり、どこまでもつづく。
だが、そういう経済学の考え方はまちがっている、とガルブレイスはいう。消費には順番というものがあって、最初に選ばれるのはより優先度の高いものだ。これにたいし、経済学者は消費に優先度などないという。それがいま消費されているという事実だけが重要なのだという。
たしかに限界効用逓減の理論は、欲望と財の価格評価の関係を示すうえでは役立つかもしれない。財を追加で購入しても、それによって得られる満足度が低ければ、人はそれに多くを支払おうとは思わないはずである。そうした個々人の行動を社会的に集計すると、右下がりの需要曲線が得られるだろう。だが、限界効用理論は、消費者の実際行動を無視した仮説にすぎない、とガルブレイスはいう。
いずれにせよ、商品は多いほど、商品が少ないより欲求が満たされる。商品が重要だという仮説は疑われようもなかった。というのは、商品こそが人類の窮乏を救ってきたからである。こうして限界効用理論を含む経済学も生き残ってきた。
それにたいする異議がなかったわけではない。ケインズは人間の欲求がかぎりないものであることを認めながら、もし絶対に不可欠なものが満たされるようになったら、経済は人類にとって重要な問題ではなくなるかもしれないと論じた。しかし、不況対策についてはともかく、この点に関しては、ケインズはまだ支持を得られていない、とガルブレイスは述べている。
このあたりの話はなかなかややこしい。
先に進もう。次は「依存効果」を論じた有名な章である。
欲望は常に固有の現象として、それ自体存在するというのが、経済学の従来の考え方である。生産はそうした欲望を満たすためになされると考えられてきた。
しかし、ほんとうは生産が欲望をつくりだすとしたらどうだろう。「生産が欲望をつくりだすとしたら、生産を欲望を満たすものとして擁護することはできなくなる」とガルブレイスはいう。
ケインズは他人に負けまい、あるいはその先に行こうという気持ちが、はてのない欲望を生みだすと論じている。だれかが何かを買うと、自分もほしくなる。それによって、満たされるべき欲望は次々と広がり、また新しい欲望が生まれていく。
「ゆたかな社会」では、欲望それ自体というとらえ方は後ろに引っこんでしまった。それよりも、もっと生活水準をあげたいという意欲が、社会的な体裁を保つという意識とあいまって増していく。
ガルブレイスはさらに現代社会における宣伝とセールスの重要性を指摘する。そして、その目的は欲望をかき立てることだから、欲望は自立的に決定されるという旧来の考え方は、すでに通用しなくなっているという。
新しい製品を売りだすときには、宣伝費を投入しなければならないことは、もはやだれもが知っている。
だとすれば、「欲望が生産に依存することを認めなければならない」とガルブレイスはいう。「生産は、受け身的な人との競争によってだけではなく、積極的な宣伝その他によって、満たされるべき欲望をつくりだすのだ」
こんなあたりまえのことを従来の経済学は認めてこなかった。宣伝などむしろ不要という見方が強かったのだ。
それ自体決まった欲望という考え方はいまでも生き残っている。そして欲望を満たすための生産がもっともだいじなこととされる。
だが、それでは宣伝に動かされて人がものを買っているという現在の「ゆたかな社会」のできごとを理解できなくなってしまう、とガルブレイスはいう。
ガルブレイスは、欲望が生産に依存する「依存効果」なるものを次のように説明する。
〈次第に社会がゆたかになっていくと、欲望を満足させるプロセスによって、だんだんと欲望がつくりだされるようになっていく。これが受動的に作動する場合もある。消費の増加は生産の増加に対応するものだが、そのさい、提案や競争心が欲望をつくりだすことになる。さらに、生産者が宣伝やセールスを通じて積極的に欲望をつくりだす場合もある。こうして欲望が生産に依存するようになるのである。〉
われわれは、膨張自体を自己目的とする資本主義が次々と欲望を生みだしていくととらえたくなる。
マルクスは資本が生き残り膨張していくのは、労働者の生みだす剰余価値を資本が搾取するからだと考えた。これにたいし、ガルブレイスは資本が生き残り膨張していくのは、生産が商品を通じて欲望を開発していくからだととらえている。そして、ここに「ゆたかな社会」が生まれていく。
資本主義の終焉がささやかれるいま、そのことをどう考えればよいのだろう。倫理的な批判を加えるのは容易である。だが、おそらくそれだけでは、じゅうぶんではない。
いまはそうした現象があることを確認するだけで、もう少し先に進んだほうがいいだろう。ようやく半分ほど読み終わったところである。
内務省をやめ大学院に──美濃部達吉遠望(15) [美濃部達吉遠望]

美濃部達吉は1897年(明治30年)7月に帝国大学法科大学を卒業した。この年、京都にも帝国大学が設立されたため、東京の帝国大学は東京帝国大学(略称、東大)と呼ばれるようになる。
そのとき、同窓の卒業生には、学者では筧克彦(かけい・かつひこ)、加藤正治、立作太郎(たち・さくたろう)、政治家では江木翼(えぎ・たすく)、川村竹治、井上孝哉、熊谷直太、外交官では小幡酉吉(おばた・ゆうきち)、水野幸吉、実業家では小倉正恒、梶原仲治(かじわら・なかじ)、南新吾などがいたという。
いまではほとんどなじみのない、これらの人びとについても、ざっと紹介しておいたほうがいいだろう。
筧克彦(1872〜1961)は長野県出身でドイツ留学後、1903年に東大教授となり、行政法などを担当した。古神道を基礎とする天皇中心の法理、国家論を唱えたというから、達吉のいわばライバルである。
加藤正治(1871〜1952)も長野県出身で、ヨーロッパ留学後、1903年に東大教授となり、主に民事を担当した。定年退職後は、枢密顧問官、三菱本社監査役などを務め、戦後、中央大学学長・総長になっている。
立作太郎(1874〜1943)は東京出身で、ヨーロッパ留学後、1904年に東大教授となり、外交史と国際法を担当した。パリ講和会議やワシントン会議にも随員として出席している。
江木翼(1873〜1932)は山口県出身で、内務省を経て、政治家となった。加藤、浜口、若槻内閣で司法相や鉄道相を務めた。
川村竹治(1871〜1955)は秋田県出身で、内務省入省後、台湾総督府内務局長などをへて、和歌山、香川、青森各県の知事を務めた。のち貴族院議員となり、内務次官、満鉄社長、台湾総督、さらに犬養内閣の司法大臣を歴任した。五・一五事件により政界を引退するが、その妻文子は川村女学院を経営していた。
井上孝哉(1870〜1943)は岐阜県出身で、内務書記官をへて、佐賀、富山、神奈川、大阪の府県知事を歴任し、内務次官となった。達吉の友人である。
熊谷直太(1866〜1945)は山形県出身で、苦学の末、帝国大学を卒業、前橋や東京の地裁判事などを歴任後、衆議院議員となり、加藤、犬養内閣で司法政務次官を務めた。
小幡酉吉(1873〜1947)は石川県出身で、卒業後、外交官となり、天津、シンガポール、ウィーン、ロンドンなどに勤務し、たびたび中国に派遣された。中国側に拒否されたため、中国駐在公使にはなれなかったが、退官後は貴族院議員や枢密顧問官を務めている。
水野幸吉(1873〜1914)は兵庫県出身で、外交官としてワシントンや北京に勤務し、辛亥革命後の善後策にあたった。
小倉正恒(1875〜1961)は石川県出身で、内務省に入るが、住友本店に転じ、住友財閥の最高経営者となった。近衛内閣では大蔵大臣などを務めた。
梶原仲治(1871〜1939)は東京出身で、卒業後、日本銀行に入行し、その後、横浜正金銀行頭取、日本勧業銀行総裁、東京株式取引所理事長などを務めた。
南新吾(1873〜?)は大分県出身で、帝国大学の政治学科を首席で卒業した。三井物産に入り、天津や香港の支店長を務め、のち台湾銀行の理事となった。達吉の親友で、達吉の妹ゑみは南新吾に嫁している。
長々と書いてきたが、その評価はともかく、明治の帝国大学が全国各地から優秀な人材を吸収し、学界や官界、政財界に送りだす窓口になっていたことはまちがいない。そのかぎりでは、たしかに新しい時代が到来したのである。
帝国大学法科大学政治学科を2位で卒業した達吉は、1897年(明治30年)に内務省に入省した。
そのときの気持ちをのちにこうふり返っている。
〈私は在学中からなるべくは一生学究生活を送りたいと希望し、できるならば卒業後も大学院にとどまって研究を続けたいものと思ったのであったが、一方には、学者としての天分に乏しいことを自覚したのと、一方には、在学中こそそのころ農商務省の役人であった舎兄の貧しい俸給の中からその一部を割いての補助と、大学から受けた貸費とによって、苦学の生活も送らずに、勉強することができたけれども、卒業後はじきに自活の途を講ぜねばならぬ必要があり、しかも大学には当時はまだ有給助手の制度も、大学院の給費学生の制度もなく、金をもらって勉強することは、まったく不可能であったのと、両方の理由から、ついに学究生活を断念して、内務省に志願し、幸いに採用せられて、卒業後、直に内務局に任ぜられ、今の地方局、そのころは県治局といったように思うが、そこに奉職することになった。〉
要するに、学究生活をつづけたかったけれども、金銭面でこれ以上周囲に迷惑をかけるわけにはいかなかったので、内務省ではたらくことにしたというわけである。
こんな調子では役人仕事に身がはいらなかったはずである。
内務省は1873年(明治6年)に大久保利通によって設立され、その後の改編をへて、1885年(明治18年)の内閣制度設立とともに内閣の一省となった。内政のうち、地方行政、警察行政、選挙事務などを管轄した。
その県治局(のちの地方局)に達吉は配属された。地方行政を管掌する部署である。
しかし、役所生活にはなじめなかった。
〈幸か不幸か、私には内務局という生活が、どうしても好きになれなかった。毎日朝九時から夕方の四時過ぎまでは、用があってもなくても、必ず役所に出勤していなければならぬが、その間に自分の懸命の力を出して働くような機会はほとんど与えられず、ただ茫然と机に座っている時間の多いのに、わがままな私は、ほとんど堪えがたい感じがしていた。役人生活が嫌になるにつれて、ふたたび学究生活に対するあこがれに悶えていた〉
それなりに仕事はあったと思うが、無聊を感じていたのだろう。達吉が悩んでいる様子を見て手を差し伸べてくれたのが、恩師の一木喜徳郎だった。一木はそのころ東大教授でありながら、内務省参事官を兼任していたのだ。
一木は大学院にはいって、勉強をつづけたらどうかと達吉に勧め、さらに、こんな話も打ち明けた。じつは、大学で比較法制史の講座を担当する教授が必要なのだが、もし大学院にはいって比較法制史を研究する気があるなら、その候補者に推薦してやってもいいというのだった。
達吉にとっては、渡りに舟の話だった。歴史はどちらかというと苦手だったが、法律の歴史的研究に従事するのもおもしろいかなと思いはじめた。それに、何といっても大学院にはいれば学究生活をつづけることができ、さらに学者への道も開けてくる。達吉は決心して、一木に推薦を頼むことにした。
そのさい、ことごとく面倒をみてくれたのは一木だったといってよい。
当時、東大で比較法制史の講座を担当していたのは、宮崎道三郎(1855〜1928)だった。宮崎は比較法制史とともに日本法制史の講座も担当していたので負担が大きく、できれば日本法制史に専念したいという希望をもっていた。そこで、比較法制史を受け持つ候補者を探しており、それを一木にも相談していたのである。その話が達吉に回ってきたというわけである。
ちなみに宮崎は1889年(明治22年)に日本法律学校(現在の日本大学)を創立していたから、いわば東大と日大の兼務で、おそらく多忙をきわめていたとも思われる。
その宮崎とも一木は話をつけ、教授会に推薦された達吉は宮崎の指導のもと、大学院で学ぶことになった。
それだけではない。一木はおそらく内務省にも話をつけていた。達吉の直属の上司、県治局府県課長の井上友一(1871〜1919、のち東京府知事)は、一木の教え子であり、達吉の先輩でもあったが、内務省を辞めたあとも達吉を内務省試補の扱いにし、多少の手当を支給してくれたのである。
達吉の1年ほどの大学院時代は、経済的にも憂いがなくなった。試補として、時折、内務省に顔をだすだけで手当をもらえたからである。
こうして、達吉は1年で内務省をやめ、1898年(明治31年)9月に東京帝国大学の大学院に進むことになった。この時点で教授になることはほぼ約束されている。
一木喜徳郎と穂積八束──美濃部達吉遠望(14) [美濃部達吉遠望]

1894年(明治27年)9月に美濃部達吉は帝国大学法科大学政治学科に入学する。満21歳になっていた。
そのとき国法学の講座を担当していたのが、当時まだ28歳の一木喜徳郎(いっき・きとくろう、1867〜1944)である。一木はドイツ留学から戻ったばかりだったが、国法学を担当していた末岡精一(1855〜1894)がこの年はじめに病気で亡くなったため、急遽(きゅうきょ)、一木が大学で国法学を教えることになった。
達吉は一木の講義に魅了され、大学の3年間を一木の影響下ですごすことになる。
のちに当時をふり返って、こう書いている。
〈その講義は、はじめて教授となられて最初の講義であるから、もちろん十分に練熟したものではなく、瑕瑾(かきん)も少なくなかったことと思うが、しかしその該博な引照と精緻(せいち)な論理とは、われわれ学生の心を魅するに十分であった。
これより先、先生はドイツ留学中に既に『日本法令予算論』の著を公にせられており、それが学界に知られて先生の大学教授に任命せらるる機縁を作ったのであるが、私はそれを幾度か熟読し、その鋭い筆鋒に深い敬意を捧げていたので、いっそう先生の講義に感激を覚ゆることが深かった。
おそらく三年間の大学在学中に、私の聞いた多くの講義の中で、もっとも大なる影響を私に与えたものは、この新進の青年学者の講義であったと思う。私がのちに公法を専門とするに至ったのも、おそらくはこのとき運命づけられていたのであろう。〉
達吉は一木に師事した。
だが、おなじ1年生のときに、達吉は一木とは対称的な憲法の講義に出くわしていた。大日本帝国憲法が公布されたのは、5年前の1889年(明治22年)で、帝国大学ではその直後から憲法学の講座が設けられていた。
達吉自身はこう書いている。
〈憲法の講義は、やはり一年生のときに、故穂積八束(ほづみ・やつか、1860〜1912)先生から受けた。
穂積先生は当時既に憲法学者として名声天下に聞こえており、その講義は、音吐朗々(おんとろうろう)、口をついて出る語が、おのずから玲瓏(れいろう)たる文章をなしており、その荘重な態度とともに、一世の名講義をもって知られていたが、ほとんどすべての点において、一木先生の講義とは、あたかも対蹠的(たいしょてき)であって、論理などにはいっこうかかわらず、力強い独断的の断定をもって終始せらるるのであった。
一例をいうと、国家の本質を説明しては、国家は主権を保有する団体であるといわれながら一方では、主権は天皇に属す、天皇すなわち国家なりといい、国家機関というような概念をもって、天皇の御地位を説明するのは、もってのほかの曲事(きょくじ)であると喝破せられる。
国家が団体であることを認めながら、天皇即ち国家であるとするならば、その論理的な必然の結果は、天皇は団体なりといわねばならぬことになりそうであるが、そんな論理は、先生の頓着せられるところではなかった。
これはほんの一例であるが、先生の講義の中には、こういう非論理的な独断が少なくなかったので、まだ幼稚な一年生でありながら、先生の講義には、不幸にして遂に信服することができないで終わった。〉
達吉が天皇即ち国家という穂積八束の考え方についていけなかったことがよくわかる。ここで、故穂積八束とされているのは、達吉の回想記は1934年(昭和9年)に発表されたもので、穂積がすでに1912年(大正元年)に亡くなっていたためである。
ところで、一木の国法学と穂積の憲法学とでは、講座の内容がどうちがっていたのだろう。
達吉によると、それはどちらも憲法についての講義だった。ただし国法学が西洋、とりわけ英仏独3国の憲法比較に重点を置いたのにたいし、憲法学はもっぱら日本の憲法を取り扱っていた。
ふたつの対称的な講義を聴いたことにより、公法にたいする興味がかきたてられた。大学在学中、達吉は憲法と行政法の勉強に励むこととなる。
その方向は師の一木と同じく、比較法制史をベースとする公法の研究に向けられた。それは「論理的な思索を好む傾向」をもつ「みずからの天性」に合ったものだった、と達吉自身認めている。穂積の心情主義にはなじめなかったのである。
立花隆は『天皇と東大』において、穂積八束について、こう記している。
〈明治憲法が制定されるとすぐに東大には憲法学講座が置かれ、穂積八束が主任教授となった。穂積の憲法学は、憲法の中心的起草者、伊藤博文の憲法論と、ちょっとずれた部分があった。伊藤博文の発想は、憲法以前の天皇制が持っていた絶対君主的要素を、憲法を制定することによって弱め、専制主義的な天皇制を西欧の立憲君主的な制度に変えてしまおうということだった。〉
明治憲法をすべて伊藤博文の発想に帰着させるのは無理がある。しかし、穂積の憲法学が伊藤の憲法論と少し異なっていたのはたしかである。立花にいわせれば、伊藤が天皇を「立憲君主」として位置づけようとしていたのにたいし、穂積はあくまで天皇を「絶対君主」としてとらえていた。
その穂積の主張を、立花はおよそ次のようにまとめている。
(1)天皇は法理論でいう国家であり、主権者である。天皇は法令の上にあって、法令の制限を受けない。
(2)天皇は統治の主体であり、その位自体、独立自存している。天皇は神聖にして侵すべからず。
(3)天皇の位は統治権の機関ではなく、その所在である。君主を統治機関のひとつとする考え方は、君主を主権者ではないとするもので、わが国体に反する。
論理的にはいくらでも批判する余地があるこうした穂積の考え方は、穂積の死後も、天皇を「現人神」とする上杉慎吉によって引き継がれていった。上杉は穂積のあとを継いで、1910年(明治43年)から東大で憲法学を担当するのである。
天皇を「絶対君主」と唱える穂積の帝国大学での憲法講義は、二十数年にわたってつづけられた。
これとは別に、ほぼ同じ時期に天皇を「立憲君主」ととらえる一木の憲法講義が同じ帝国大学でおこなわれていたことが、じつに興味深い。そして、達吉は一木に師事することによって、単にその学説を継承するだけではなく、その後の人生を切り開いていくことになる。
いまでは考えられないが、当時の帝国大学教授は役所の部署を兼任することも多く、一木喜徳郎の場合も同じだった。
立花隆は一木の経歴をこんなふうに紹介している。
一木は1894年(明治27年)に帝国大学教授となるが、同時に内閣書記官、内務省参事官、農商務省参事官などを兼任している。さらに、1902年(同35年)9月から1906年(同39年)1月までの3年半は、法制局長官兼内閣恩給局長、さらに1908年(同41年)7月から1911年(同44年)9月までは内務次官を兼ねるという具合に、大学教授としてだけではなく、次々と高級行政官僚としての途を切り開いていった。
その後、一木は東大退官後は文部大臣、内務大臣をへて枢密顧問官、宮内大臣、枢密院議長を歴任することになる。昭和天皇の信頼も厚かった。昭和天皇が神聖な絶対君主といった発想を嫌っていたことがわかる。
美濃部達吉は、帝国大学入学後、まだ青年教授だったその一木喜徳郎の文字どおり一番弟子だったといってよい。
ガルブレイス『ゆたかな社会』を読む(4) [経済学]

もともと競争社会のモデルに経済的保障は含まれていなかった、とガルブレイスは書いている。人は失敗しないよう努力するのが鉄則とされていたからである。
しかし、問題は経済的損失をこうむるのが、おうおうにして本人より第三者だったことである。本人の努力を超えた、予期せぬ災害はおこりうる。そのため、経済的保障や社会保障の問題が次第に浮上してくる。
経済社会にリスクはつきものである。不安にさらされる人がそれを取り除こうとするのはとうぜんだった。
市場価格の予想しがたい動きに対抗するには、企業が大規模化し、独占体制を築くというのが最終的な答えだった。巨大企業化はかならずしも利潤の極大化をめざすためではなかった。リスクの軽減こそが、近代企業を動かす動機だった、とガルブレイスは書いている。
企業はどのようにしてリスクを軽減しようとしたか。たとえば宣伝によって、消費者に自社商品にたいする嗜好を刷りこんでいく。生産部門の多様化、生産方法の改善。新商品を次々と開発していくこと。個人の権威に頼らない企業の組織管理、資金調達の多元化など。
経済社会の発展につれて近代法人としての企業はいわば防衛力を強化し、リスクを大幅に減らした。これにたいし、いまも農民や労働者、市民は直接リスクにさらされている、とガルブレイスはいう。
とはいえ、1930年代以降は、一般の人びとのあいだでも経済リスクを緩和する動きが出はじめた。失業保険、養老年金、遺族年金などだ。農産物の暴落に対応する支持価格制度もつくられた。労働者の生活を守る労働組合も誕生した。
さらに政府はマクロ経済的な措置に乗り出し、完全雇用水準に経済を安定させる努力を払うようになった。
商品の開発にともなう生産増大に加え、こうした経済的保障措置の導入が、「ゆたかな社会」を生む素地になった、とガルブレイスは考えている。そのはじまりとなったのが1930年代だった。
思想的にみれば、アメリカ経済は保守・リベラルの潮流がぶつかり合うなかで形成されてきた、とガルブレイスはいう。それはいつの時代も変わらない。ただ、両者の関係はねじれている。保守が自由な競争を求めるのにたいし、リベラルは安全な生活を求めるという不思議な構図が生まれた。
それはともかく、すべての人が自分には守るべき何物かがあることに気づいたのは、生活がある程度ゆたかになってからである。裸一貫の時代は、それこそこわいもの知らずだった。経済生活の向上こそが、かえって経済的保障にたいする関心を高めた、とガルブレイスはいう。企業は倒産を恐れ、労働者は失業を恐れ、農民は収入低下を恐れるようになった。
経済的不安はきりがない。だが、「ゆたかな社会」では、おもな経済的保障システムはすでにできあがっている。それでも人びとが不安をいだくのは、現実に経済が動揺すれば、ほんらい頼らなくてもよいはずの経済的保障システムに依存しなくてはならないことを恐れるからである。そのため、政府には常に不況を防止することが求められるようになった。
アメリカではいまも経済的保障にたいする強い反発が残っている。経済的保障が大きくなれば、競争が阻害され、人は働かなくなるというわけだ。
だが、それは完全にまちがっている、とガルブレイスはいう。
「実際には、経済的保障への関心が高まった時代は、これまでになく生産性が高まった時代なのである」
不安の緩和と生産の増大が相伴うことによって、はじめて「ゆたかな社会」がもたらされるのだ。
だが、ガルブレイスはあくまでも生産の重要性を強調する。働く者にとっても、生産とは稼げる仕事があることを意味する。
〈かつて不平等にともなって生じる緊張の解決策となったのは生産だった。しかも、生産は経済的不安定にともなう不快や不安、欠乏にたいする不可欠の救済策となっているのである。〉
ここから生産の話がはじまる。訳文の問題もあって難しい。原著を横に置きながら、まとめてみる。
現代の世界では国境を越えて生産(というより商品生産)の重要性が認識されるようになった。
「ゆたかな社会」に、ものは豊富にある。それでも人はいまでも生産の増大にこだわりつづける。生産は依然として文明の進展度を測る手段になっている、とガルブレイスはいう。
資源、技術、労働、資本が生産のファクターである。これらの結びつきにおいて、とりわけ重視されてきたのは技術開発だ。だが、技術進歩に関しては、産業によって大きなちがいがある。概して巨大企業では技術開発のために大きな投資がおこなわれる。その目的は商品の開発と生産増加だ。
不況は、たとえ小さな景気後退であっても、商品生産に大きな影響をおよぼす。そのとき経済学者は雇用や収入がどれだけ減るかに注目するが、企業が関心を寄せるのは、あくまでも利潤の確保である。
問題は不況のさいには、企業だけでは経済的保障が保たれないことである。そのため、政府の役割は必須となる。
経済において重視されるのは生産性である。怠惰だけではなく、過剰投資や保護関税、特恵、補助金、無駄遣いなどにも、大きな非難が寄せられてきた。だが、それは外部的な要素ではあっても、おそらく生産性の増加とはほとんど関係がない。大企業の時代においては、企業戦略が立てられ、技術導入と資源利用の効率化、適切な労働力配置がはかられ、計画的に投資率と成長率の向上をめざす体制が組まれるようになった。
しかし、ガルブレイスの言いたいことは、むしろここからだ。豊富な商品の生産は、たしかに「ゆたかな社会」をもたらす原動力になってきた。そして、経済においては、一般には民間の生産だけが重要だと考えられている。
そのいっぽう、公共サービスは社会にとっては必要悪であり、それが多くなると民間経済を圧迫すると思われてきた。こうした見方は伝来のもので、きわめて非合理だ、とガルブレイスはいう。
たとえば国民総生産(GDP)は、年間の財とサービスの価値を一括して計算するものだが、そこに含まれているのは民間がつくりだす価値だけでない。政府がつくりだす価値も含まれている。つまり、政府もまた社会に必要な生産価値をつくりだしていることを認識しなければならないのだ、とガルブレイスはいう。
にもかかわらず、何かというと公共サービスは目のかたきにされ、できれば減らしたほうがよいものと思われがちだ。だが、社会のゆたかさを支えているのは、民間の財とサービスだけではない。公共サービスがあってこそ、「ゆたかな社会」が築かれることを忘れてはならない、とガルブレイスは強調する。
経済の発展は衣食住の拡充とともに進み、市場が確立することで(つまりふつうに物やサービスが売り買いできるようになって)、生産と分配のシステムが広がっていった。
そうしたシステムをつくってきたのは民衆であって、これまで政治権力はむしろその力を抑えつけたり収奪したりするばかりだった。そのため、民衆のあいだに国家への不信が生まれるのはとうぜんだった。市場経済が国家に対立するという見方は根強かったし、いまも根強い、とガルブレイスはいう。
〈貧しい世界の悪王たちは、強欲のあまり、民間でつくられたものを破壊したり、損傷したりするのもまったく平気だった。ものをつくる人も資本も破壊された。いまでは経済はそんなにやわではなくなっている。政府はそこまで理不尽ではない。現代の西洋諸国では、経済の成長と公共活動の拡大が、いくつかの例外はあるにしても、並行して進むようになった。経済と公共活動は補完しあうようになっており、実際そうでなくてはならないのだ。〉(拙訳)
ガルブレイスは民間資本の生みだす財やサービスだけでは「ゆたかな社会」は生まれないと考えている。商品が増えるにつれて、公共の投資やサービスがかならず重要になってくる。道路、交通機関、電気、ガス、水道、医療、図書館、警察、さまざまな社会保障など。いや、むしろ公共サービスがまだ少なすぎることこそが問題だという。
ガルブレイスによれば、「われわれは重要な生産の一部門、すなわち公共財に二流市民のような位置づけしか与えていない」。
こうしたリベラルな考え方は、現在主流となっている「新自由主義」の価値観とは正反対のものだ。はたして「新自由主義」はより「ゆたかな社会」をもたらすことができただろうか。
長くなったので、今回はこのあたりでおしまいにしよう。ガルブレイスの考え方は、だいたいわかったのではないか。だが、まだ終わってはいない。ガルブレイスは、われわれはゆたかになったと思っているが、はたしてその内実はどうなのかを次に問うているからである。
ガルブレイス『ゆたかな社会』を読む(3) [経済学]

ここでガルブレイスはアメリカの経済学の歴史を論じる。それは基本的にイギリスの伝統を受け継いだものだった。
例外的にアメリカ的な人物がいるとすれば、それはヘンリー・チャールズ・ケアリー(1793〜1879)とヘンリー・ジョージ(1839〜97)、ソースティン・ヴェブレン(1857〜1929)だという。
ケアリーは楽観論者で、将来は明るいと唱えた。逆にヘンリー・ジョージは、土地が私有であるかぎり、貧困と不況は避けられないと論じた。ヴェブレンは、経済が発展すると、富と貧困の分化がきわだつようになると主張した。有閑階級が生まれ、見せびらかし消費や浪費、不道徳がはびこるというのだ。
ガルブレイスはこうした3人の経済学者に加え、アメリカに影響を与えた思想として社会進化論を挙げている。社会進化論は経済社会を競争の場と考え、そこでの勝者には富が与えられ、敗者はいわば餌食になると論じた。人生の目的は、その戦いに勝つことだとされた。
社会は弱者を淘汰することによってはじめて発展するという社会進化論の考え方を唱えたのはハーバート・スペンサー(1820〜1903)だ。アメリカでは人気を博したという(明治の日本でも)。
19世紀後半のイギリスでは、すでに社会改良の動きが広がっていたのに、アメリカでは競争によるより富の獲得を求める声が強かったのだ。このあたりは、いかにもアメリカである。
その結果、アメリカでは大金持ちが誕生するいっぽうで、貧困と堕落が広がっていった。ガルブレイスはジョン・D・ロックフェラーの「大企業の発達は適者生存にほかならず、多くの犠牲はいたしかたない」ということばを紹介している。
スペンサー流の発想は、やがて民主主義と近代的な公共団体の発達によって見向きもされなくなる。しかし、社会進化論が残した影響はいまだに強い。それはこの世は競争社会だという考え方である。さらに社会進化論は、競争の活力を市場のなかに見いだした。その結果、個人の窮乏を救うための社会手段がおろそかになった、とガルブレイスはいう。
アメリカにおいて、社会進化論が右派を鼓舞したとすれば、左派にとってマルクス主義はどうだったのか。
ガルブレイスによると、マルクスは主流派経済学の伝統を引き継いでいるという。そこから資本主義の欠陥をあばきだし、変革をうながした。
労働者はつねに失業の危機にさらされている。そのため、いくら抵抗しても、けっきょくは資本家の示す賃金をのみこまざるをえない。
技術の進歩や資本の蓄積は労働者に利益をもたらさない。かえって、それは労働者を機械や資本の付属物にしてしまうというのがマルクスの考え方だという。
マルクスは資本主義はほんらい不況への傾向を有するとも論じた。その景気循環の波に労働者は翻弄される。政府の対策も労働者に利するわけではない。だが最後に資本主義は破滅への道をたどる。
「マルクスはその体系を受け入れない人にも大きな影響をおよぼしている。その影響はぜったいマルクスを信じていないと思っている人にもおよんでいる」とガルブレイスは書いている。
その思考は広範囲におよび、しかも知的だった。「多くの点で、マルクスは明らかに正しかった。とりわけ同時代に関しては」とガルブレイスは断言する。
だが、それは1930年代までである。その後、だれもが予期しなかった生活のすばらしい向上が待っていた。マルクスの体系は観念としてはいまも生きているが、もはや状況は変わりつつある、とガルブレイスはいう。
そこで取り上げられるのが不平等の問題である。
いままでがいわば「序論」だったとすれば、ここから『ゆたかな社会』の「本論」がはじまるといってよいだろう。
主流派経済学では有能な者が高い報酬を受け、無能な者が低い報酬しか得られないのはとうぜんと考えられてきた。しかし、しだいに所得の再分配という考え方がでてきた、とガルブレイスはいう。
保守派はあいかわらず不平等を擁護した。地主と資本家が大きな所得をもつのは必然で、これは制度上いたしかたないと主張した。平等がすぎると、文化が大衆化し、同一化してしまう。高額所得者の権利と権力を守るべきだ。そこには平等主義が個人の努力、創意、着想をそこなうという考え方があった。
だが、ガルブレイスはいう。第2次世界大戦後、アメリカの所得税は高かったが、それでも急速な経済成長を遂げることができた。累進課税をやめれば、経済が成長するという保証はない。平等主義が進めば経済の発達が阻害されるという考え方もおかしい。
いずれにせよ所得の再分配をもたらす政策が重要なのであって、真のリベラル派は、けっしてごまかされず、金持ちの言い分に譲歩しないことがだいじなのだ、とガルブレイスはいう。ガルブレイスはもちろんリベラル派を支持している。
しかし、「ゆたかな社会」が進むにつれて、不平等にたいする関心は薄れつつあるとも述べている。これはあくまでも1960年代、70年代の話かもしれない。それでも、アメリカでは戦後、不平等があまり問題にされなくなったというのは、当時のガルブレイスの実感だったろう。
不平等がなくなったわけではない。経済格差は依然として大きかった。とはいえ、戦後、不平等がさらに広がったわけではなかった。中間層の所得が増え、完全雇用と賃金上昇によって、下層の生活が向上したからである。実質所得が増えているときには不満は少なくなり、不満をぶつける相手もなくなる傾向がある。
さらにガルブレイスは、金持ちの地位や権力が変化したことを指摘する。会社の経営権は資本家から経営者へと移った。そのことによって、富を誇る資本家が権力をふるうこともなくなった。これにより、金持ちにたいする反感も減った。金持ちに仕えるという卑屈な仕事も減っていった。
金持ちが増えることによって、金持ちの価値も低下してきた。富にもとづく、みせびらかしの贅沢も過去のものとなった。俗悪とみなされるようになったからである。
その背景には、富の大衆化が進んだことがある。いまでは、だれもが自動車を所有でき、ダイヤモンドを身につけ、高級ホテルを利用することも可能になった。
ガルブレイスはこう書いている。
〈要するに、虚飾あふれるゴタゴタした支出は、それを支える富との関係において、かつては差別化を示す源だったが、いまはそうではなくなったのである。このことが不平等への態度にもたらす影響はあきらかだろう。虚飾の消費は、貧乏人に金持ちの富に注目させること自体が目的だったといえる。だが、虚飾の値打ちが下がり、むしろそれが俗悪なものとみなされるにつれて、富と不平等はともにわざわざ宣伝するほどのものではなくなった。宣伝されることが減るにつれて、それはさほど注目されなくなり、怒りを買うこともなくなっていった。かつて金持ちは不平等をきわだたせる状況を引き起こしたものである。だが、いまではそんなまねをしなくなっている。〉
要するに、ゆたかさが大衆化したのである。それが1960年代、70年代の気分だった。
資本家や創業者一族は、いまや企業のなかの首脳陣ではなくなった。かれらは相変わらず金持ちではある。しかし、トップになろうとすれば、経営陣にはいり、自身が企業のヒエラルキーのなかで戦わなければならなくなった。
ここで、ガルブレイスは不平等がなぜ大きな問題ではなくなったかについて述べている。それはひとえに「生産の増加」が原因だった。経済のパイが大きくなり、現に存在する不平等を覆い隠したのだ。
〈不平等にともなう強い緊張傾向を取り除いたのは、まさに生産である。いまや保守派もリベラル派も、総産出高の増大こそが、再分配あるいは不平等縮小の解決策だと認めるようになった。こうして、もっとも古くて、やかましかった社会問題は、解決されたとはいわないまでも一段落し、論議の焦点は生産性の上昇という目標に移っていった。〉
現時点の2020年代では、また不平等の問題が浮上しつつある。「ゆたかな社会」は分裂し、幻影のかなたに消えようとしている。
だが、そうあっさり決めつけないようにしよう。
ゆっくり先を読んでみる。
飛び級で復学──美濃部達吉遠望(13) [美濃部達吉遠望]
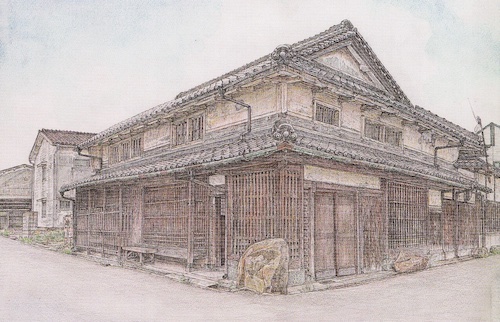
〈きのうまでの高中[高等中学校]生徒が、にわかに月給6円のサラリーマンになったわけだが、この6円を生活費にするわけでなく、小遣いにするか他日の学資のために貯蓄するかであったから、その点は気楽なサラリーマンだった。しかし田舎でこういう生活を送っていると、その中に多少は同僚の人々の感化を受けたらしく、はじめて酒を飲み習ったのもこのころであったと思う。
が、同時に戸籍掛[係]としての仕事は十分真面目(まじめ)に勤めたもので、おかげで戸籍事務には相当精通することができた。今でも区役所の戸籍事務なら担当してみせる自信がある。〉
達吉は高砂の町役場に勤めたころの思い出を、そんなふうにユーモアをまじえて記している。酒を覚えたのもこの時代だった。戸籍係の仕事は、それなりの実務経験をもたらしただろう。地味なようにみえて、国家統治の根幹にかかわる仕事である。
余談ながら、戸籍法は1871年(明治4年)に制定され、翌年施行された。その後たびたび改正され、現在にいたっている。国民個々人の出生から死亡にいたるまでの親族関係を登録公証するこの制度は、日本独特のものであり、明治新政府にとっては、徳川時代の人別帳や過去帳に代わるものだったといえる。
それはともかく、達吉は戸籍係としての事務を同僚とともに楽しくこなしたようである。
そうこうしているうちに、いよいよ健康も回復し、ふたたび東京に出て、以前にもまして学業にはげみたいという気持ちが強くなってきた。1年以上にわたる療養生活は、達吉の肉体を回復させただけでなく、その精神をも鍛えたといってもよいだろう。
こうして、達吉は数えの21歳を迎えた1893年(明治26年)正月に、両親の許しを得て、役場の書記をやめ、ふたたび東京に出ることになった。満年齢でいえばまだ19歳だった。
この年、父の秀芳は2代目の高砂町長となった。山陽鉄道が開通したものの、住民の反対が強く、高砂はその駅にならなかった。そのため、新町長には、急速に衰退している町をどう立てなおしていくかという課題がのしかかっていた。
ここで付記しておかなければならないのは、美濃部兄弟の東京生活を支えたのは、家族だけではなく、高砂の有志だったということである。美濃部家はさほど裕福ではなく、子どもたちに大学教育をほどこすほどの余裕はとてもなかった。そこで、町の金持ちが兄俊吉や弟達吉の学資を助けてくれた。
達吉の息子、亮吉はこう書いている。
〈父は兄俊吉と共に、東京に遊学し、一高及び東大で教育を受けた。その学資は、高砂の金持である岸本、伊藤、松本、松浦の四氏が共同で出資したということである。兄か弟のうち一人が出世したら、元利揃えて返却するという契約であり、兄弟共に期待以上の出世をし、元利揃えて返却を完了したそうである。〉
記述は多分に不正確で、ほんとうにこんな契約があったとすれば、ずいぶん世知辛い話である。だが、いずれにせよ、高砂の金持ちが提供した出世払いの奨学金のおかげで、「末は博士か大臣か」の期待を背負いながら、美濃部兄弟は東京での勉学に励むことができたのである。
こうして達吉は東京に戻ってくる。
だが、その先の方針が立たなかった。
もう一度、第一高等中学の入学試験を受けて、はじめからやり直すのは、あまりにばかげている。かといって、ほかの学校にはいるのも気が進まなかった。めざすのは、あくまでも帝国大学(東京帝国大学と改称されるのは1897年[明治30年])なのである。
達吉は四、五年独学をつづけて高等文官試験を受けてみようかとも考えた。高等文官試験というのは、高級官僚を採用するための試験で、中学校卒業程度の者に受験資格が認められていた。だが、それはあまり得策とは思えなかった。
そこにすでに帝国大学で学んでいた兄の俊吉と、第一高等中学の同級生、井上孝哉があるアイデアをもちだす。それは、うまくすれば、高等中学の最上級である本科2年に復学できるのではないかという妙案だった。
高等中学は予科3級と本科2年の5年制で成り立っている。達吉の同級生はまもなく最終学年の本科2年に進もうかというときである。だが、達吉は予科2級の途中で、腸チフスにかかり、退学を余儀なくされていた。実際には、最初の予科3級しか終えていないのだ。それなのに、いきなり3段階飛びで本科2年に復学するなど、とても無理ではないかと思われた。
学友の井上孝哉は校長の木下廣次のもとに行って談判し、優秀な美濃部の復学を何とか認めてほしいと訴えた。木下は病気の話を聞いて大いに同情し、それでは特別に本科2年への編入試験を認めようということになった。
ただし、無条件にというわけにはいかない。高等中学の1年目でしかない予科3級を終えたというだけでは何の資格もないからだ。そこで、7月にもう一度、他の受験生とともに高等中学の入学試験を受け、それに合格したら、9月に予科3級の試験、予科2級の試験、予科1級の試験、さらに本科1年の試験を受け、それを突破したら本科2年への編入を認めようという、とてつもない条件をもちだした。
やるしかなかった。それにしても入学試験はともかく、復習を含めて高等中学4年分の勉強を1月から8月までの半年あまりではたして準備できるのか不安がつのる。一時は「茫然として自失するほかはなかった」と達吉は記している。
幸い、井上が講義のノートを貸してくれ、本郷追分町の下宿で同居していた兄も叱咤激励してくれた。上野図書館に通えば、参考書を読むこともできる。
英語や漢文、国文は何とかなりそうだった。しかし、勉強しなければならない科目がほかに山ほどあった。
苦手な数学は算術、代数、幾何のほか三角術(三角法)を頭にいれなくてはならない。歴史は日本史のほか、東洋史、西洋史。理科は動物、植物、鉱物、生理、物理、化学の科目。さらに本科1年の心理学と論理学、さらにドイツ語も何とかしなければならない。
兄の下宿の二部屋のうち、2畳の部屋をあてがわれて、達吉は必死に勉強した。苦手な数学がどうしてもわからず、ドイツ語でもつまずいた。見込みがないから、もうやめたいと訴えたこともあった。だが、兄は「そんな意気地のないことでどうする」と叱り、ドイツ語については毎日半時間くらい勉強をみてくれるようになった。三角法は独学するほかなく、いくら教科書をみてもわからなかったが、何度も同じことをくり返しているうちに、だんだん理解できるようになった。
この年には徴兵検査があったが、丁種不合格となり、兵役義務を免除された。
井上から借りたノートを精読し、上野図書館に日参して、参考書を読みあさるうちに、半年間はあっというまにすぎた。そのかんに、4学年間のすべての課程をひととおり習得できたというのは、さすがに秀才である。
7月の再度の入学試験には難なく合格した。そして9月には、次の難関が待っていた。3学年分と何せ科目数が多いのに加え、1科目でも60点以下をとれば、そこで進級はおしまいになる。
予科2級、予科1級の試験は、例によって立体幾何がうまく解けなかったが、物理や化学、三角法は案外すらすらと答案を書くことができた。本科1年の試験は得意なものが多かったので、予科の試験よりもむしろ簡単なほどだった。
だが、試験結果がでるまで安心はできなかった。
そのときの気持ちをふり返って、達吉はこう記している。
〈もしこの試験に落第すれば、将来の方針をどうしたものかと、独り心痛に堪えなかったが、幸いにも一科目も不合格点はなかったということで、全部合格ということを事務室で知らせてくれたときは、ただもう嬉しさに堪えなかった。おそらくは私の生涯の中で最も嬉しかった経験であろう。〉
こうして、達吉は病気でいったん退学した年月を取り戻し、かつての同級生と同じ学年に復学することができたのである。
そして、翌1894年(明治27)年7月には第一高等中学校を卒業し、帝国大学法科大学政治学科に進学することになる。
町の戸籍係に──美濃部達吉遠望(12) [美濃部達吉遠望]

感染症はいまも人類の脅威にちがいないが、明治期において、それはさらに死の影を投げかけるものだった。1890年(明治23年)から翌年にかけては、また感染症におびえる歳月がつづいていた。
内務省の『法定伝染病統計』によると、1890年の法定伝染病(感染症)と患者数および死亡者数は次のようになっている。
病名 患者数 死亡者数 致死率
コレラ 46,019 35,227 76.5
赤痢 42,635 8,706 20.4
腸チフス 34,736 8,464 24.3
痘瘡(天然痘) 296 25 0.8
発疹チフス 251 67 26.6
ジフテリア 2,448 1,438 58.7
安政の開国以来、コレラの波は何度も日本を襲った。
奥武則『感染症と民衆』によると、明治10年(1877年)以降、明治20年代にかけて、コレラは間欠的に大流行をくり返したという。
美濃部達吉が腸チフスにかかった明治23年(1890年)は、コレラが大流行した年でもある。その致死率は76%だったというから、人びとはコレラにかからぬよう神仏に祈るほかなかった。
コレラの流行しない年でも赤痢や腸チフスは常に流行した。当時の衛生環境の悪さを想像できるだろう。そして、その致死率もけっして低くない。達吉が腸チフスにかかったときも患者の24%が亡くなっている。達吉の父、秀芳が息子の死を覚悟したのも、けっして大げさではなかったのである。
しかし、ともかく達吉は生き延び、8カ月の入院後、1891年(明治24年)5月に第一高等中学を退校し、故郷の播州高砂でしばらく療養することにした。
そのころの思い出をこう記している。
〈最初の入院の時から数えると、[1890年(明治23年)]10月から翌年の5月まで、約8カ月の間の病院生活に、身体は骨と皮とに痩せ衰え、体重を計ってみると、8貫[約30キロ]あるかないかで、これで郷里まで無事に帰れるかどうかも危ぶまれるありさまだったが、兄が付き添ってくれるのをたよりに、いよいよ5月の何日かに、永(なが)の病院生活に暇を告げて、帰郷の途に就くことになった。
汽車や船の中で発熱しては困るというので、キニーネか何かの発熱予防薬をもらい、車に乗るにも、車から下りて汽車に乗るのにも、人の背に負われるような憐れな姿であったが、ともかくも新橋(東京駅はまだなかった)から横浜までは汽車、横浜からは汽船で、無事に郷里までたどり着くことができた。
新橋駅まで見送りにきてくれた井上[孝哉]はじめ友人たちは、これがこの世の見おさめだろうと思ったということである。〉
新橋駅頭で、痩せ細った達吉が背負われていく姿を見送った友人たちは、これが永の別れだと思ったにちがいない。
しかし、故郷で半年療養するうちに、達吉は奇跡的に健康を取り戻す。
そのときの「病床日記」が残っているというが、残念ながらそれをまだ見ることができていない。
ここでは、本人ののちの思い出によって、故郷高砂での回復ぶりを知るほかないだろう。
〈郷里に帰って両親や妹に嬉々として迎えられた私は、さすがに両親の慈愛のもとに、ずんずん元気を回復していった。ときどき突然発熱することは、その後も絶えず、その度ごとに母を苦しめたが、それもだんだんまれになって、半年ほどの間には全く起こらなくなり、その年[1891年(明治24年)]の暮れごろまではほぼ健康を回復することができた。〉
病院の病室で孤独に時を数えるよりも、両親に見守られながら、故郷の自宅でゆっくり療養できたのは幸せだった。ときどき熱が出ることもあったが、母の献身的な看病もあって、達吉はめきめき体力を回復していった。
その母、悦が亡くなるのは4年後の1895年(明治28年)8月のことである。享年55歳。達吉が帝国大学法科大学政治学科で学んでるさなかだった。
長男俊吉と次男達吉は連名で、1898年(明治31年)8月、町の共同墓地に母の墓碑を建立した。そこには二人の息子がりっぱに法学士になったことが、母に報告するかのように刻まれている。
母ゑつ(悦)は1843年(天保14年)4月に、加東郡古川村(現小野市)の医者、井上謙斎(けんさい)の次女として生まれ、美濃部秀芳と結婚、2男2女を産んだ。墓碑にはその人となりは明るく貞淑だったと刻まれている。苦しい生活がつづくなか、愚痴ひとつこぼさない人だったという。
高砂町出身で戦後、日本社会党の国会議員となる河合義一(かわい・ぎいち、1882〜1974)は達吉の兄、美濃部俊吉のところで書生をしながら東京外国語学校に通っていたが、子どものころに悦に診てもらった記憶がある。
こんなふうに悦のことを話している。
〈お母さん[悦]がえらかった。お母さんはものをきらいだ、という言葉はなかった。あの人には「きらい」という言葉はなかった。あるとき、誰かがきらいなものをもっていくと、きらいだとはいわずに「あまり好きでないの」とこたえたという話がのこっている。そのうえお医者さんとしてもなかなか上手で、子供のころ耳がいたくて困ったので、でかけていくと、いっぺんになおしてくれた。〉
さらに、達吉の息子、亮吉も祖母悦のことをこう記している。
〈悦という祖母がまた大変な賢夫人だった。並々ならぬ知識と教養を持ち、祖父に代って患者を診たり、書や漢学を教えたりした。達吉さんがあんなにえらくなったのは、悦さんのおかげだということに、高砂では意見が一致していたということである。〉
こんな母に見守られて達吉は健康を回復した。
1892年(明治25年)に達吉は二十歳の春(満19歳)を迎えた。早く東京に帰りたいという願いはつのるばかりだった。だが、まだ健康が十分でない、と父は許さなかった。
しばらくするうちに、町役場で書記が欠員になり、後任を探しているという話があり、何もしないでいるよりも書記になったらどうかと勧める人がいた。
町村制の施行により高砂町が発足したのは1889年(明治22年)のことで、そのときの町長(初代)は加藤幸平といい、小学校時代の先生だった。そこで役場に勤めるのもひとつの経験だと思い、達吉は役場ではたらくことにした。
「町役場書記ニ任ズ、但シ月給金六円ヲ給ス」という辞令をもらい、達吉は戸籍係を担当することになった。月給6円というのは、いまの感覚では4万円か5万円といったあたりだろう。



