バブルは常に発生する──『バブルの経済理論』つまみ読み(6) [経済学]

バブルの熱狂が金融危機にいたる歴史のメカニズムをえがいたものとしては、チャールズ・キンドルバーガーの『熱狂、恐慌、崩壊』(1978)が知られている。規模はともかく熱狂、恐慌、崩壊はその後もつづき、いまにいたる。市場はかならずしも合理的ではない。市場の不安定化をもたらす群集心理的な投機は常に存在する、とキンドルバーガーは考えていた。
投機の背後には、かならず信用の膨張がある。陶酔のなかで資産価格が高騰する。そして、陶酔はいつかさめ、資産価格が下落すると、連鎖的にパニックが生じる。
資本主義はバブルとその崩壊の連鎖をくり返してきた。もはや恐慌はないという予言は、2008年のリーマン・ショックによって完全に裏切られた。これまでの歴史をみるかぎり、いったん信用の拡大がはじまると、中央銀行は信用の膨張を抑制することができないことが明らかになりつつある。
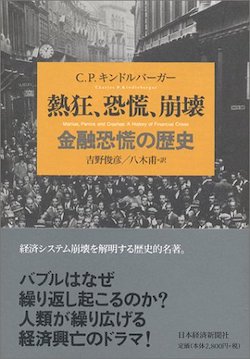
合理性にもとづいて、その体系を築いてきた経済学は、現実のバブルにたいして無力だった、と著者(櫻川昌哉)はいう。というのも、人びとが合理的に行動するかぎり、バブルなど発生するはずがないからである。
〈合理的思考で自らの脳に塹壕(ざんごう)を築いた経済学者にとって、非合理的だとしか思えない人々の行動は理解を超えていた。合理的に行動していたらこんな荒唐無稽なことは起きなかったはずなのにと、バブルを前にして立ち尽くすのみであった。経済政策の論議は、せいぜいバブル崩壊後に生じる危機に対処すればよいというお粗末きわまりないものであった。〉
頭のなかに塹壕を築いてきたとは、言い得て妙である。
そこで、実際のフィールドに立って、経済学的思考からすれば非合理的と片づけられてしまいがちなバブルについて、経済理論を組み立ててみようという著者のこころみがはじまることになる。
バブルの経済理論を、著者はミクロ理論とマクロ理論にわけている。
まずはミクロ理論からみておこう。
〈本来価値を持たない財が価値を保ち続けるとき、価値を支えるのは人々の信念や思い込みであり、その期待はその財が元来備えている利用価値とは無関係であることもしばしばである。我々はこうした財を総称して“バブル”と呼ぶ。〉
「本来価値を持たない財」とは、不動産や株式などの資産商品である。かつてはチューリップもそうした資産商品に含まれたことがある。小麦や綿花などの先物商品も投機の対象になった。
それらに価値がないわけではない。もちろん価値がある。しかし、これらが資産商品となる場合は、流動性が高い、低いにかかわらず、目標とされるのは、あくまでも将来における価値のはねあがりである。
言い換えれば、バブルとは資産商品の価値の高騰を期待しておこなわれる貨幣による投機的行動がもたらす現象だといってもよい。
そうした商品がいつまでも値上がりするわけはない。そのことがわかっていながら、なぜか多くの人が投機に走る。バブルはギャンブルとつながっている。そして、たいていが痛い目にあった。そんな非合理的な行動を、いつもなぜか人はとる。
貨幣がバブルだとしたら、貨幣自体の崩壊もあることを著者は指摘している。それがハイパーインフレーションである。それは戦前のドイツや敗戦後の日本だけで起こった現象ではない。現在もあちこち(たとえばジンバブエやアルゼンチン、ベネズエラなどでも)で生じている。
われわれはふだん意識しないけれども、実はバブルのなかで暮らしている、と著者はいう。たとえば1万円札は10円でできるが、われわれはそれを1万円と信じて使っている。なぜなら、日本銀行券と印刷されているから、それを信用しているわけだ。そして、それが将来も1万円としての価値をもちつづけると信じているからこそ、それを貨幣として認めているのだ。もし、それがじつは紙切れだと気づかされたら、その瞬間、たちまちバブルがすけて見えてきて、1万円札の貨幣価値は暴落する。ハイパーインフレーションは貨幣の信用が失われ、その幻想が暴かれたときに発生する。
バブルは貨幣と商品との関係性において生じる。商品を中心にみれば、資産商品の価値が持続的に上昇すると判断される場合に潜在的なバブルが発生し、その判断が過剰な幻想に過ぎなかったとわかったときに、それがはじめてバブルだったとわかり、バブルの崩壊がはじまる。このときバブルは土地や株式など資産商品に集中して発生するので、物価そのものはさほど上昇するわけではない。
もうひとつは貨幣自体のバブルである。貨幣の価値が下落しつづけ、それが貨幣所有者の不安と結びつくときは、貨幣自体にたいする信頼感が薄らぎ、ハイパーインフレーションが発生する。すべての商品の価格が上昇し、急激な物価高が生じ、貨幣システムが崩壊する。
株式の場合をみておこう。理論的な説明は苦手なので避けて通る。
人が株式を買うのは、配当と株式の値上がりの両方、あるいはどちらかを期待するからである。主流派の経済学は、ここで人びとは市場について正確な情報をもち、合理的な意思決定をすると想定する。そうであるかぎり、企業の価値は正当に判断され、企業価値の上昇、あるいは下落はそのまま株価に反映されるだけであって、バブルなどおこるはずがない。
それなのに、じっさいにバブルが発生するのはなぜか。資産価格が割高になってしまうのはなぜか。逆に、大暴落がおこるのはなぜか。
市場の情報は、じつはすべての投資家に共有されているわけではない。「金融機関と一般投資家の間には情報格差が存在しており、金融機関はその情報の優位性から利益を獲得している」と著者はいう。それだけではない。市場に参加するのはかならずしも合理的に行動する懸命な投資家ばかりとはかぎらない。みずからの感覚だけを優先する自信過剰の投資家も存在する。将来への期待がふくらみ、自信過剰の投資家ばかりが増える市場ではバブルが生じる。
プロの投資家は株価の上昇がバブルだと確信しても、すぐに資産を売却しない。バブルに乗じて利益をあげようとして資産を保有しつづける。そして、多くの人がバブルと気づく直前に資産を売却するのが、プロがプロたるゆえんだ。
ここで紹介されるのが、ケネディ大統領の父、ジョセフ・ケネディのエピソードである。かれはアメリカが株式ブームにわきたっていた1920年代末期、靴磨きの少年がやたら株の話をするのを聞いて、手持ちの株をほとんど売り払った。それは1929年10月23日「暗黒の木曜日」の前日だったという。
現在のヘッジファンドがとろうとしているのも、これと同じ行動だという。できるだけバブルをあおって、たとえばIT株などの株価をつり上げ、そのピーク直前に株を売るのである。
実験経済学は、将来どこかでバブルが破裂することがあらかじめわかっていたとしても、バブルがおこりうることを証明した。キンドルバーガーも、バブルが崩壊して「流動性不足への恐怖[おカネが消えてなくなるという恐怖]がパニック心理と結び付いたとき」に、資産の投げ売りや銀行破綻が実際に起こるととらえていた。売りが売りを呼ぶわけだ。この場合は逆の行き過ぎが生じることになる。
次に論じられるのは、バブルのマクロ経済学についてである。難解なので、はっきり言ってよくわからない。
著者は4つの命題を挙げている。
(1)利子率が経済成長率を下回るとき、合理的バブルが発生する。
(2)合理的バブルの存在する定常状態の経済は、効率的な資源配分を達成する。
(3)定常状態の経済では、合理的バブルの規模はGDPの一定割合となる。
(4)経済に金融市場の不完全性が存在するとき、動学的に効率的な経済にバブルは発生する。
いずれも厳密な経済学用語で述べられているため、ぼくのような素人には、よくわからない。著者のいわんとすることを、ぼくなりに勝手に解釈してみる。
(1)から(3)までは「合理的バブル」についての命題である。
合理的バブルとは一定期間持続するバブルのことである。このときはバブルであることがわかっていても、株であれ不動産であれ、さらに買い手が増えて値が上がるにちがいないという「期待の連鎖」がバブルを持続させていくことになる。
もしバブル資産が利子率より高い収益率を保証するなら、人びとは喜んでこれを購入すると考えられる。またバブル資産が経済成長率と等しい率で上昇するならば、バブル資産の収益率は経済成長率と等しくなる。そして、利子率が成長率を下回るときは、バブル資産の収益率が実物資産の収益率より高くなるから、そこでは合理的なバブルが発生する。著者はそんなふうに説明する。
このとき人びとは実物資産よりバブル資産を購入するが、その結果、利子率は成長率と等しくなるまで上昇する。
こうして経済は利子率と成長率とが等しくなる定常状態に達する。この定常状態においては、合理的バブルのもとで、人びとの消費水準は最大に達し、効率的な資源配分がおこなわれる。
そして、仮にGDPが3%で成長して、バブルも3%膨張するとすれば、バブルは膨張しても持続する。バブルがGDPの一定割合を保つかぎり、バブルは破裂することがない。だが、GDPの成長より早いスピードでバブルが膨張すれば、いずれ経済が支えきれなくなり、バブルは破裂する。
低金利のもとで、ゆるやかなバブルがつづいているといえば、おわかりのように、これは現在2020年代はじめの日本の状況である。しかし、これもあやういバランスの上に成り立っていることはいうまでもない。
しかも、実際の金融の世界は完全性が保たれているわけではない。だれもが等しく情報を共有しているわけではなく、契約は正しく履行されているとはかぎらず、企業統治は完璧になされているとはかぎらない。「金融の世界は、市場の不完全性の“坩堝(るつぼ)”ともいえる」と、著者も指摘する。
そして、いよいよ(4)の本格的バブルの可能性が浮上する。
金融市場が不完全な世界では、バブル資産の存在が投資を刺激する。バブル資産が高騰すると企業のバランスシートは改善され、企業は銀行からの借り入れを増やして投資を拡大することができる。ここでは慎重なはずの銀行が豹変して、バブル資産を担保にして融資を拡大する方向に走り、知らず知らずのうちにマクロリスクを抱えてしまう姿がえがかれている。
著者は過剰な貯蓄がカネ余りバブルを生みやすいことも指摘する。1986年から90年にかけての日本のバブルは、その典型だった。だが、日本のバブルの特徴は、バブルに踊ったのが企業と銀行であって、家計はそれほど誤りを犯さなかったことだという。
また、バブルが経済成長率とおなじスピードで膨張するならば、バブルは持続しうるとするならば、資産商品の対象は不動産や株式とはかぎらない。現在、日本においては、土地バブルに代わって国債が余剰資金を吸収する対象になっている、と著者はいう。
なぜ、こんな現象がおこったのだろう。
〈土地神話の崩壊により、空気が少しずつ漏れ出すようにスローパンクチャーを続ける土地バブルの縮小によって節約できた資金が国債購入に向かい、国債の実質価値を支えたのである。土地バブルの暴落でできた空洞を、国債という霞(バブル資産)で埋め合わせたのである。〉
株式や土地、住宅だけではなく、貨幣(タンス預金)や国債もバブル資産となりうるのだ。
こうしてみると、バブルはけっして昔話ではない。
バブルといってわれわれが思い浮かべるのは1990年前後の日本のバブル崩壊と2008年のリーマン・ショックぐらいだが、じつはバブルはいまも流転している、と著者(櫻川昌哉)はみている。
1980年代に日本はバブル景気を味わったあと、土地バブルが崩壊した。日本企業が生産拠点を東アジアに移すと、こんどは東アジアの株式と不動産の市場がわいた。しかし、1997年にアジア通貨危機がおこると、資金はアメリカに環流し、ITバブルを引き起こした。だが、それも2001年に崩壊し、今度は住宅バブルがはじまり、2008年のリーマン・ショックと世界的金融危機へと帰結した。そのころ、中国では住宅バブルがはじまる。
著者はこう書いている。
〈その時々の経済の主役の交代とともに、バブルの重心は移動しているのである。ある地域で起きたブームは、資金を世界中から引き寄せ、また国内のカネ余りを膨張させ、自信過剰と楽観主義のスパイラルとともに資産価格の高騰を引き起こす。〉
だが、そのバブルもいつか崩壊する。10年以上つづいた中国の住宅バブルもいま崩壊しつつある。
資産バブルが崩壊したあと、先進国政府は財政拡大と金融拡大によって、経済危機からの脱出をはかろうとした。利子率は低下し、巨大な債務残高が残り、経済は長期停滞の局面にはいった。
著者は、現在は、資産バブルの崩壊で生まれた空洞を、現金や国債が埋めている状態だという。そして、それ自体が、国によってつくられたいわば逆バブルであって、将来を先食いした一種の贈与経済なのだという。そうしたなかで、経済はますます長期停滞に落ち込みかねない。経済を動かすのは民間の力である。市場経済に活気を取り戻すには、大きな転換が必要だ、と著者は考えている。
リーマン・ショック再考──『バブルの経済理論』つまみ読み(5) [経済学]

アメリカでは2008年9月に大手投資銀行のリーマン・ブラザーズが破綻し、世界じゅうが金融危機におちいった。リーマン・ショックといわれる。そこでは住宅バブルと証券化商品のバブルという二重のバブルが重なっていた、と著者(櫻川昌哉)は指摘する。
バブルには、それが発生した場所固有の物語がある。
オランダのチューリップ・バブル、イギリスの南海泡沫事件、フランスのミシシッピ計画、ヨーロッパの数々の恐慌、昭和の金融恐慌、1929年の大恐慌、1980年代のチリの経済危機、日本の土地バブル、1990年代のアジア通貨危機、そのほかいくらでも挙げられるが、どのバブルもそれぞれ固有の特徴を背負っている。
著者はバブルの一般理論を組み立てようとしているが、それぞれのバブルがもつ固有の特徴を抜きにして、バブルの歴史を語ることはできないという。そのようなひとつとして取りあげられるのが、2008年にアメリカでおこった、いわゆるリーマン・ショックである。
それはどのようにして発生したのだろうか。
2000年から2006年にかけ、アメリカの住宅価格は実質で57%上昇し、2006年から2010年にかけ34%下落したという。典型的なバブルとその崩壊が生じていた。住宅価格の上昇がとりわけ際立っていたのは、マイアミやロサンゼルス、ニューヨークだ。
〈この時期はちょうど、住宅ローン債権を担保とした証券化商品への需要が高まった時期であった。2000年には5720億ドルであった純粋に民間発行の資産担保証券(MBS)は、その後急速に増加して2006年には2兆6000億ドルへとほぼ5倍に膨れ上がる。……とりわけ劇的に増加したのが、低所得者向け住宅ローンであるサブプライムローンであった。〉
サブプライムローンが膨れ上がり、それが住宅価格を押し上げ、最終的にバブルが崩壊する。しかし、この構図を理解するためには、証券化というアメリカ経済独特の仕組みを知らなければならない、と著者はいう。それは1913年まで中央銀行が存在しなかったアメリカの歴史的事情によるものだ。
詳しい歴史は省略するが、アメリカで全国的な金融制度確立の契機となったのが、1863年に制定された国法銀行法だった。それにより小切手の決済を含め、金融制度は徐々に整備されていくが、それでも金融危機は頻発していた。
アメリカでは表だった民間の国法銀行や州法銀行とは別に、謎に包まれたプライベートバンクがあった。その代表がJPモルガン商会だ。
ジョン・ピアポント・モルガンはJPモルガン商会の頭取として、商業銀行と投資銀行を兼ね備えた組織をつくりあげた。富裕層から預金を集めただけではなく、株式や債券の発行・引受業務を通じて企業の資金調達を助けていた。それに加えて、モルガン商会はいくつもの企業合併を仕掛けることで、巨大な持ち株会社をつくりあげている。
「最後の貸し手」がいなかったアメリカでは、JPモルガンこそが事実上の中央銀行だったという。
だが、巨大銀行JPモルガンへの国民的反発も強く、1913年に連邦準備理事会(FRB)が発足すると、12の連邦準備銀行をテコとして、金融制度全般が統括されるようになる。
第1次世界大戦のあと、国際金融センターはロンドンからニューヨークに移った。アメリカの黄金時代がはじまる。株式市場は活況を呈し、商業銀行は証券子会社を設立して、株式市場に参入した。これにより、株式市場の市場規模が爆発的に拡大し、ウォール街はバブルに躍った。
そして、1929年10月24日の「暗黒の木曜日」に、株価の暴落がはじまる。1933年までにアメリカの実質GDPは29%落ち込み、物価も28%下落、失業率は25%に達した。
大恐慌がおこると、市場を陰であやつっていた巨大銀行に批判が集まった。1933年にはダグラス・スティーガル法が成立、同一銀行の商業銀行業務と投資銀行業務の兼務が禁止される。これにより、JPモルガンは商業銀行となり、投資銀行部門はモルガン・スタンレーとして生き残ることになった。
ニューディール政策は持ち家取得を促進した。そこからアメリカの住宅金融の歴史がはじまる。住宅ローン専門の貯蓄貸付組合(S&L)が誕生した。さらに政府は預金保険制度を導入して、S&Lの信用強化をはかった。こうした裏づけもあって、S&Lは長期低利の固定金利ローンを提供できるようになった。だが、当初、住宅ローンを組めたのは白人の中産階級以上にかぎられていた。
1970年代、2度の石油ショックをへて、S&Lは存続の危機に見舞われる。1980年にレーガンが大統領になると、規制緩和がおこなわれ、S&Lも資産運用対象の拡大、預金金利の自由化を認められるようになる。そのいっぽうで、預金保護は維持されていた。そこでS&Lはハイリスク・ハイリターンの融資案件や金融商品に手を出すようになる。ギャンブル的な不動産開発がはじまった。
いっぽう、S&Lは手持ちの住宅ローンの売却をはじめた。これにより市場に住宅ローン証券が出回るようになる。投資銀行のソロモン・ブラザーズはS&Lから大量の住宅ローン債権を買い取り、住宅ローン担保証券(MBS)として売りだすようになった。
住宅ローンの証券化とは、住宅ローンを担保にして、新しい証券をつくり、それを売りだすという手法である。債権のリスクはあるが、それを大量にまとめれば金融工学の手法でリスクを軽減し、利益が確保できると考えられていた。
まさに先取りしておカネをぐるぐる回して儲けをかすめるといった感じだが、多くの銀行が国債より利回りの高い安全資産として、住宅ローン担保証券を大量に買い入れるようになった。
だが、著者はここに「証券化モデルの致命的な欠陥」があったという。「証券化スキームは、責任を持って借り手から債権を回収する主体が存在しなくなるという致命的な問題点を抱えている」というのだ。
証券化は貸し出しの質の低下という致命的な欠陥を内包していた。証券化では適格な担保は確保されない、と著者はいう。
にもかかわらず、証券化商品は大量に発行されつづけた。2000年に5720億ドルだった住宅ローン担保証券は2006年に2兆6000億ドルへと5倍に膨れあがった。いっぽう、銀行は貸出条件を緩和して、住宅ローンを拡大し、サブプライムローンは劇的に増加した。
しかし、住宅価格の上昇をあてにしたビジネスが長続きするわけがない。住宅価格が下落すると、返済不能の貸出債権が続出し、証券化商品の価値も暴落する。こうして、アメリカの住宅バブル(二重のバブル)が崩壊していく。
アメリカで証券化ビジネスが拡大したのは、中央銀行体制の確立が遅れたアメリカの風土と関係している、と著者は考えているようだ。
規制緩和とともに巨大銀行の時代が到来すると、商業銀行は貸し出しだけではなく、証券化商品の購入に走るとともに、資金調達手段を多様化するようになっていた。子会社を利用して、ABCPと呼ばれる短期性負債を発行し、資金を調達していたのだ。
バブル期特有のシャドーバンキングも生まれる。
〈シャドーバンキングとはいわば、伝統的な銀行部門の外側にできた信用仲介ネットワークである。銀行規制の網をかいくぐろうとして生み出されるのが一般的であり、当局の規制は及ばないため、信用膨張を抑制することができず、金融危機の原因となる。〉
2006年から2007年ごろにはじまった住宅バブル崩壊は、住宅価格を下落させ、同時に住宅ローン担保証券の価格を下落させた。そして、2008年9月にリーマン・ブラザーズが破綻し、いわゆるリーマン・ショックがはじまるのである。MMF(マネー・マーケット・ファンド)は額面割れし、信用不安の連鎖がドミノ状にほぼすべての金融機関を襲った。
〈なぜ、世界で最も効率的で革新的なはずの金融システムは崩壊したのかと問うとしたら、その革新性にこそ崩壊の原因があったのである。長い間、中央銀行を持たなかったアメリカでは、絶えず民間貨幣創造の挑戦が試みられた。安全資産の根拠を安易に政府保証に求めない歴史風土が証券化商品を創り出し、アメリカの金融は一敗地にまみれたのである。〉
しかし、だからといって、2008年のリーマン危機が、すべてアメリカの特殊事情によるものと著者が言っているわけではない。バブルの発生と崩壊、金融危機はそれぞれ国ごとにさまざまな形態をとる。にもかかわらず、近代世界の誕生とともに、経済にバブルはつきものであって、その状況はいまも変わらない。バブルはいつのまにか忘れられるが、けっしてなくなったわけではない。
バブルとは何なのか。ここで、われわれは最初の章に戻って、あらためて著者によるバブルの定義をみていくことにしよう。
第1次天皇機関説論争──美濃部達吉遠望(31) [美濃部達吉遠望]

1912年(明治45年)3月に美濃部達吉の『憲法講話』が出版されたあと、東大で憲法学講座を担当する上杉慎吉は雑誌『太陽』に美濃部の考え方を猛烈に批判する論考を発表した。それは文語での慨嘆調のきわめて感情的な批判だった。いまはそのままの引用では読みにくいと思われるので、以下は口語に直して、上杉の発言を紹介することにする。
上杉はおよそこんなふうに筆をおこしている。
美濃部達吉君が近ごろ『憲法講話』なる本を出版した。以前から美濃部博士が国体論について、私が常々論じているのとはまるで異なる主義見解をもっていることは薄々聞いていた。憲法に示されているとおり、万世一系の天皇が国を統治することは、決まり切ったことで、いかなる人も疑うはずもないところだ。ところが『憲法講話』の序文をみて、美濃部君が特殊な説をもっていることに気づいた。
こんなふうに達吉の考え方がいかにも特殊であるかをにおわせながら、上杉は美濃部の考え方を糾弾していく。
〈統治権の主体が日本国民の団体だとするなら、天皇はいかなるものとして存在するのか。美濃部博士は、天皇は団体の機関だという。また機関とは「団体のために働くところの人」だという。……すると、天皇は国家の機関であり、団体の役員であることになる。その団体は人民全体であって、天皇はこの団体のためにはたらく使用人として存在するという。これが、じつに美濃部博士の考え方なのである。ああ、これがはたしてわが建国の体制といえるのか、はたして国民はそんなふうに確信しているのか。〉
上杉は美濃部が天皇を人民に奉仕する存在のようにとらえていると決めつけ、それを嘆きながら、さらにでっちあげの論陣を張る。天皇はおそれおおい神のごとき君主なのであって、そこらの大統領のような存在ではないというのが上杉の基本的な考え方だ。
〈[美濃部]博士が天皇は国家なるものの使用人ではない、人民団体の「役員」ではない、すなわち他人[国家法人]に属する権利を行使する任にあたるものではないとするのならば、天皇は国家の機関である、統治権の主体は天皇ではなく国家という法人であるという博士の根本原理を改めなければならない。天皇が統治権の主体であれば、国家の使用人ではない。みずから統治権を有するものでなければ、人民団体の使用人である。どちらかひとつをもって、論理を一貫する必要がある。[美濃部は]前には天皇は統治権の主体ではないと断言し、後には他人[国家法人]の権利をおこなうものではないとする。だれがこの明白な矛盾にあざむかれようか。〉
上杉は天皇機関説を自己流に解釈したうえで、勝手な自問自答をつくりあげ、美濃部の主張は矛盾していると決めつける。その目的は、天皇は統治権の主体なのだから、天皇が統治権の主体ではないという美濃部の考え方は、ぜったいにおかしいと印象づけることだ。
さらに上杉は「尊皇心」をもちだして、からめてからも達吉を攻撃する。
〈美濃部博士は、しばしば自分の尊皇心は人後に落ちるものではないと公言し、これを疑われることを恐れているかのようだ。しかし、これはまったく杞憂(きゆう)からする弁解である。だれが博士の尊皇心を疑うだろうか。だが、尊皇心があるなしと学理とはまったく別問題だ。……どんな学理を唱えようと、尊皇心においてやましいところがなければ、深く心を労するに足りないだろう。〉
これもなかなか巧妙なわなである。学理と尊皇心をからめながら、美濃部の尊皇心は口先だけのもので、その学理は尊皇心とはほど遠いものだと暗に示唆しているのだ。
上杉はさらに「国家法人説なるものは民主の思想を法学の篩(ふるい)にかけて圧搾したるもの」だといい、その本義は民主共和にあると断言する。だからこそ、『憲法講話』にみられる国体論はまったくの誤謬で、ぜったいに排撃すべきものだという。
〈美濃部博士がみずからしばしば言われるように、帝国が万世一系の天皇によって統治されるのは、わが建国の体制であって、天地とともに変わらぬところ、憲法の基礎であり、国民の確信である。……博士の衷心(ちゅうしん)がわれわれと異ならないことは、しばしば博士が宣言するところである。尊皇心が人後に落ちぬとは、君がみずから誇るところである。しかし、発表された学説で、天皇は統治者ではない、国民全体が統治権の主体であるというときは、これを誤謬として排斥しないわけにはいかない。〉
上杉は達吉にもし尊皇心があるなら、天皇機関説などという謬説を撤回せよと迫っている。天皇機関説は「民主共和」の説であり、「国体に対する異説」であるというのが上杉の主張だった。
穂積八束を引き継いだ上杉慎吉の憲法思想に早くから反発していた美濃部達吉は、さっそく同じ雑誌『太陽』に反論を書いた。
そもそも、上杉がいうように「君主は人民のためにはたらく使用人」などといった不謹慎な言い方を、達吉はどこにもしていない。それをあたかもそう言ったかのように指摘して、批判するのはよこしまな憶説である。
さらに達吉はほぼ次のようにいう(原文を多少わかりやすくした)。
〈私は「憲法講話」のいかなる場所においても、帝国をもって民主国なりとしたことはなく、また天皇が国を統治するという大義を無視するような発言をしたこともない。それどころか、帝国が古来から常に君主国であり、天皇が国を統治する原則はどんな時代でも動かすべきではない、とくり返し論じている。〉
自分は常に一貫して、日本は君主制の国だといっているのに、上杉が美濃部は日本が民主国だといっていると述べるのは、あきらかな虚言であって、学問上の論説を別にして、きわめて迷惑な発言だ、と達吉は言明した。
そのうえで、国家法人説と天皇機関説をあらためて説明する。
〈私は穂積博士その他の学者と同じように、国家をひとつの団体ととらえ、この団体が法律上の人格を有し、統治権の主体であることを主張している。しかし、その意味は上杉博士がいうように、人民が統治権の主体だとするものではない。団体の性質については『憲法講話』で大要を説明したとおり「目的を同じうする多数人の組織する結合体」をいうのであって、これを国家について言うならば、国家がひとつの団体であるというのは、君主も国会も一般臣民もみな共同目的をもって相結合し、その全体をもって組織的な統一体をなしていることで、君主が統治権をふるうのも、君主ご一身のためになされるのではなく、全団体のためになされるのであるという思想を言い表すものにほかならないのである。〉
達吉にとって、国家が団体としての意志と行動をもつ法人であることは、近代国家であるかぎり自明のことと思われた。また国家が立憲君主制をとる以上、そこには君主だけではなく、国会もあり、権利と義務をもつ国民が存在することも自明のことだった。
その近代国家のなかで、君主が統治権を有するとすれば、その統治権が君主自身の利益のためにではなく、国全体の利益のために発揮されなければならないこともいうまでもなかった。
天皇機関説とは、近代国家においては天皇の統治権が憲法によって定められているということ以外のなにものでもなかったのである。
それなのに上杉は、天皇機関説を民主国、すなわち共和制の考え方だと、こじつけようとする。
天皇を機関と呼ぶのは不穏当であり、それは天皇を「人民の使用人」とみなすのと同じだという上杉の批判にたいして、達吉はそれは誤解だと反論した。
〈私は君主を国家の最高機関とする立場をとるが、けっして上杉博士のように君主を人民の使用人とする者ではない。博士が機関説論者をもって「人民の使用人」とする者とされるのは、じつに三重の誤解(曲解)にもとづいている。
博士が私の国家団体説を取りあげて、国家すなわち人民ととらえ、国家の機関といえば、すなわち人民の機関の意味だとするのは、第一の誤解である。君主と国家とを別人とし、君主が国家の機関であるといえば、すなわち国家という別人のためにはたらく者だとしているのは、その第二の誤解である。別人のためにはたらく者は、すなわちその使用人であるとし、君主が国家の機関であるというのは、すなわち君主は人民の使用人だとしてしまうのは、その第三の誤解である。
上杉博士はじつにこの三重の誤解によって、むりやり私を朝憲を紊乱(ぶんらん)し建国の体制を破壊する言説をなす者とされているのである。私としては、その誤解があまりに意表をつくものであり、筆をとる者の筆禍がどこに潜んでいるかわからないことを嘆くのみである。〉
上杉は国家は即天皇でなくてはならないのに、美濃部は国家即人民だととらえている、国家の機関は即人民の機関だと考えていると糾弾する。もちろん、達吉はそんなことは言っていない。これが第一の誤解。
上杉は天皇を国家の内部にではなく国家の上にある存在と考え、天皇が機関として国家のために働くのはおかしいと考えていた。達吉からすれば、とても立憲君主制を理解しているものとはいえない。それが第二の誤解。
さらに、天皇が国家機関になれば、天皇は人民の使用人になってしまうと上杉がいうのも誤解である。達吉にいわせれば、天皇は近代国家において立憲君主としての役割をはたすのである。
達吉はそのように述べて、上杉の無理解と曲解を批判した。
だが、上杉の憤懣(ふんまん)は収まらない。再度、『太陽』に反論を発表し、大日本帝国は万世一系の天皇これを統治すという帝国憲法の条文をくり返した。
時代は明治から大正へと移っていく。
天皇は立憲天皇かそれとも神聖天皇か、このころはまだ天皇とは何かをおおやけに論じられることができた。だが、それもやがてできなくなる。
第1次天皇機関説論争の波紋は、しだいに外部へと広がっていった。
『憲法講話』をめぐる論戦──美濃部達吉遠望(30) [美濃部達吉遠望]


1912年(明治45年)3月、美濃部達吉は有斐閣書房から『憲法講話』を出版した。前年夏に文部省の委嘱を受け、中等学校教員向けの講習会で10回にわたり憲法について講義した速記に加筆して単行本としてまとめたものだった。
さらに6年後の1918年(大正7年)10月には、その改訂・縮刷版が出版された。現在、岩波文庫に収められている達吉の『憲法講話』(高見勝利解説)は、この改訂・縮刷版を底本にしている。
1912年版は626ページの大冊だったが、1918年版は縮刷版とはいえ560ページもある。達吉は「これを縮刷するについては、なおその以後に行われた法令の改正を追補し、その他前版の誤りはなるべくこれを訂正することに努めた」と記している。
縮刷といっても分量も内容もほとんど変わらない。ただ、「前版の誤り」と称される部分には、論争や言いがかりを招きかねない表現が含まれており、それはカットされた。
そのかんに何があったのだろう。
じつは、1912年版から1918年版とのあいだに、第1次天皇機関説論争と称される、同じ東大教授の上杉慎吉(1878〜1929)との激しい論争がくり広げられていたのだ。時代も大きく変わっていた。第1次世界大戦(当時、日本では欧州大戦と呼ばれていた)からとロシア革命へと時代は激しく動いていたのだ。
ある意味、大日本帝国憲法自体が近代性と伝統主義の妥協のうえに構築されていたといえなくもない。達吉はこの憲法をできるだけ近代の脈絡に沿って読みこむことで、近代国家としての日本の発達を促そうとしていた。ところが、それとは逆に伝統主義のしばりに憲法を押しこめようとする人びともいたのである。
『憲法講話』は次の10講から成っていた。
第1講 国家および政体
第2講 帝国の政体/天皇(その1)
第3講 天皇(その2)/国務大臣および枢密顧問
第4講 帝国議会(その1)
第5講 帝国議会(その2)
第6講 行政組織
第7講 行政作用
第8講 司法/法
第9講 制定法の各種/国民の権利義務
第10講 帝国殖民地(植民地)
1912年の初版序文には、口語に直すと、およそ次のようなことが記されていた。
〈考えてみると、わが国に憲政が施行されてからすでに二十数年が経過しているのに、憲政の知識はいまだに思いのほか、一般に普及していない。専門の学者で憲法のことを論ずる者のあいだですら、国体なるものを持ちだして、ひたすら専制的な思想を鼓吹し、国民の権利を抑えて、国家への絶対服従を要求し、立憲政治の想定のもと、実際には専制政治をおこなおうとする主張を聞くことが少なくない。
私は憲法の研究にしたがう者の一人として、長年、このありさまを嘆き、もし機会があれば国民教育のために平易に憲法の要領を講じた一書を著したいと思っていたが、公務繁忙のため、遺憾ながら、その時間をとることができなかった。たまたま文部省の委嘱により、師範学校の中学校校長と教員諸氏の前で憲法の大意を論ずる機会を得たのは、平生の希望の幾分かを満たしうるものだった。
私は与えられた時間をできるかぎりもっとも有効に利用しようとつとめ、ほぼ予定どおり講演を終えることができた。もとよりわずか十回の講演にすぎないため、法律的な議論の専門にわたるものはなるべく避けたが、それでも憲法上の重要な諸問題はほぼもれなく論ずることができ、それだけでなく、行政組織、行政作用の大略、植民地制度などについても多少論及することができた。なかでも憲法の根本精神を明らかにし、一部の人のあいだに流布する変装的専制政治の主張を排することは、私のもっとも努めたところであった。〉
この序文には、はっきりと達吉のスタンスが読み取れる。「国体なるものを持ちだして、ひたすら専制的な思想を鼓吹し、国民の権利を抑えて、国家への絶対服従を要求し、立憲政治の想定のもと、実際には専制政治をおこなおうとする主張」に対抗して、帝国憲法の真意が中学校の教育現場を通じて、国民のあいだに伝わっていくことを達吉は望んでいた。
「変装的専制政治」の主張と対決することは、最初から覚悟のうえだった。
この初版序文は1918年に改訂・縮刷版が出されたときには、完全に取り除かれている。憲法を論ずる「専門の学者」から強い異議が出されたためである。
1918年の再版では、初版の序文に代えて、本論の前に、次のような言い訳めいた一文が置かれた(表記を除きほぼ原文どおり)。
〈顧みれば、初めて本書を公にした当時には、一部の人々から、本書があたかもわが国体の基礎を揺るがさんとする危険思想を含むもののごとくに攻撃せられ、一時大いに世の視聴を惹(ひ)いた。今ここにこれを再版に付するのは、本書にいかなる欠点があるにもせよ、少なくともかくのごとき危険思想は寸毫(すんごう)だもこれを包含せず、かえって健全なる立憲思想に終始するものたることを確信するからである。〉
再版のまえがきをみると、『憲法講話』の初版があたかも「我が国体の基礎を揺るがさんとする危険思想を含むもの」であるかのように批判されていたことがわかる。これにたいし、美濃部は本書は「健全なる立憲思想に終始する」ものだと反論している。
この反論はとうぜんであって、当時の政府当局もこれを認め、また国民の多くも美濃部を支持した。だからこそ、『憲法講話』の改訂・縮刷版が大々的に刊行される運びとなったのだろう。
国体明徴運動がくり広げられた昭和10年ごろにくらべて、大正の半ばはまだ思想の自由が確保されていた。それにしても、このころからすでに「国体」、すなわち国家の主権者たる天皇の尊厳が思想の踏み絵になっていたことがみてとれる。
美濃部・上杉による第1次天皇機関説論争はどのようにしてはじまったのだろうか。
1911年(明治44年)夏に、達吉が師範学校の教員に憲法の講義をしていたのと同じころ、東大で憲法講座を担任する助教授(1912年から教授)の上杉慎吉は、ある県の教育会から依頼されて、6回にわたり帝国憲法についての講演をおこなっていた。そして、そのときの講演速記録をもとに、その年の12月に有斐閣書房から『国民教育帝国憲法講義』を発行したのだった。
上杉慎吉は1878年(明治11年)、石川県に生まれ、金沢の四高(しこう)を出て、東京帝国大学法科大学に入学し、憲法学教授の穂積八束(ほづみ・やつか)に師事し、政治学科卒業後、ただちに助教授に任命されたという秀才である。
1906年から1909年まで上杉はドイツに留学し、ゲオルク・イェリネックのもとで学び、帰国してから東大の憲法学講座を担当するようになった(1912年に教授)。はじめは国家法人説をとっていたが、次第に天皇即国家を唱えるようになる。
昭和のはじめに51歳でなくなるが、憲法思想のうえで、日本の右翼思想の源流をかたちづくったといえる。戦後、首相となった岸信介は上杉の教え子の一人だった。
立花隆はこう書いている。
〈上杉は学者であるにとどまらず、政治的アクティビストでもあった。現実政治を動かすために、政治家、官僚、軍人などと組んでさまざまに動く策謀家であると同時に、志を同じくする者を糾合して、政治活動体を作ろうとするオルガナイザーでもあった。〉
この上杉の『国民教育帝国憲法講義』を、達吉は1912年(明治45年)5月の『国家学会雑誌』で、こう批評した。
〈本書は国民教育の目的のために編述せられたとのことである。国民教育の書はつとめて穏健なるものでなければならぬ。しかしてこの点において本書は国民教育のために、はなはだしく不適当なものであると信ずる。評者[美濃部]は重ねてこの書を世に推奨することのできぬのを悲しむものである。〉
これによって論争に火がつく。
論争は専門誌ではなく、幅広い読者がいる博友社発行の総合雑誌『太陽』の誌上でくり広げられた。
上杉は「国体に関する異説」と題して、達吉がまるで不逞(ふてい)思想の持ち主であるかのように、その考え方を激しく批判した。
もちろん達吉はそれに猛反論した。
80年代の土地バブル──『バブルの経済理論』つまみ読み(4) [経済学]
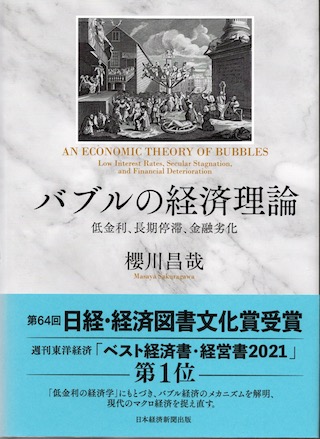
1980年代の日本の土地バブルをふり返ってみる。
戦後の急速な経済成長のなかで、日本の地価は上がりつづけ、地価は下落しないという「土地神話」が生まれた
土地バブル以前に地価が上昇したのは昭和30年代前半(1955〜60年)と昭和40年代後半(1968〜73年)ごろだったという。前半期は工業地の地価上昇が目立ち、後半期は住宅地の地価上昇が目立った。銀行は土地を担保に盛んな融資をおこなっていた。
1980年代にはいると産業の中心は製造業からサービス業に移り、とりわけ大都市の商業地の地価が上昇しはじめる。
〈1980年代になると銀行間の貸し出し競争が激化して、融資額は土地の評価額のせいぜい7割程度とする慣行は次第になし崩しとなった。銀行は、評価額の8割や9割まで貸し出すようになり、さらには、来年には地価が30%ほど上昇するだろうという見込みをもとに、評価額の10割を超えた貸し出しが横行するようになった。そして貸し出しのターゲットとなったのが不動産業である。〉
1980年代後半の巨大バブルはどのように発生したか。著者の櫻川昌哉はいくつかの要因を挙げている。
このころ銀行は預金過剰におちいっていた。製造業を中心とする優良企業はそれまでの借金体質をあらため、銀行からの借り入れを圧縮していた。そのため銀行は新たな融資先として不動産業と不動産購入を手がける金融・保険業への貸し出しを増やすことになる。
このころの日本人は自信過剰におちいっていた。「アメリカに追いつくことを目標に堅実に努力を続けてきたら、気がついたら世界のトップランナーに躍り出ていた」という気分になっていた、と著者は記している。
日米貿易摩擦が生じていて、アメリカは不況にあえいでいた。そんななか1985年にプラザ合意が成立し、それによりほぼ1年のあいだに、日本円の対ドルレートは250円から150円へと大幅に切り上がった。日本国内での景気失速を恐れた日銀は1986年から公定歩合の引き下げに踏み切った。日本経済を輸出主導型から内需主導型に転換すべきだという前川レポートが出された。
国内の不動産ブームに火がつきはじめる。大都市では政府保有の跡地に高層ビルやマンションが林立するようになり、地方ではリゾート開発が進んだ。
1987年になると、株価と地価の上昇が目立つようになった。日米間の貿易不均衡はさほど是正されていない。2月にパリで開かれた先進国首脳会議G7に先立ち、日銀はアメリカと協調するためさらに公定歩合を引き下げた。
日銀は物価には敏感だったが、バブル経済への理解力が乏しかった、と著者は書いている。「誰が見ても、金融引き締めのタイミングの誤りが、バブルに拍車をかけたことは疑いようもない事実である」
1985年末に1万3000円台だった日経平均株価は1989年末に3万9000台をつけた。1985年から1990年にかけ、地価の全国平均は117%高騰した(倍以上になった)。なかでも東京や大阪などの商業地の地価は5〜6倍となった。
1986年から90年にかけてのバブルの大きさを、著者はGDPの2.4倍とみている。1990年のGDPは427兆円だったから、バブルの規模は実に1025兆円だったということになる。未曾有の大きさだった。その巨大なバブルがやがて破れ、日本経済は最悪のシナリオを迎えることになった。
日銀は1989年からようやくバブル対策に乗りだし、5回にわたって公定歩合を引き上げ、1990年に6%とした。金融引き締めと並行して、不動産融資の総量規制も実施された。こうして1991年から地価は徐々に下がりはじめた。
1992年には実質経済成長率がほぼゼロ・パーセントに下落した。地価の下落は巨額の不良債権を生みはじめていたが、積極的な不良債権処理はおこなわれなかった。景気の後退を受けて、日銀は金融緩和に転じた。
だが、地価も株価も反転することはなかった。1995年には住専(住宅金融専門会社)が破綻し、6850億円の公的資金が投入された。1997年にアジア金融危機が発生すると、国内でも金融危機が生じ、三洋証券、山一証券、北海道拓殖銀行の3つの金融機関が破綻した。
1998年には日本長期信用銀行(長銀)の経営不安が表面化し、金融再生法にもとづいて、長銀と日債銀(日本債券信用銀行)が一時、国有化されることになった。
日本では1991年から地価が底打ちするまで13年かかった、と著者は指摘している。これはリーマン危機のときのアメリカが2年後にほぼ地価が底を打ったのと対称的だという。
それだけ、地価の調整に時間がかかった理由として、著者は不良債権の処理が先送りされたことを挙げている。大蔵省は不良債権の処理に積極的ではなく、銀行や企業も不良債権を隠そうとしていた。
だが、それも隠しきれなくなる。2002年には「金融再生プログラム」が出され、不良債権の処理が加速化された。2003年にはりそな銀行、足利銀行が国有化された。しかし、2005年には主要銀行に関しては不良債権の処理が山を越し、それとともに地価の調整もほぼ終了した。
バブル崩壊によって、日本経済が失ったものは想像以上に大きかった、と著者はいう。企業と銀行とのあいだに構築された長期的な融資関係は、土地神話に支えられた「砂上の楼閣」にすぎなかった。
いまも預金は増えつづけているが、企業向けの貸し出しはむしろ縮小している。金融の劣化が進んでいる、と著者はいう。技術進歩に金融がついていけず、投資は低迷している。
日本経済はバブル崩壊以後、30年間にわたり1%程度の成長率に甘んじるようになった。最初の10年ほどは、過剰債務の調整と投資の低迷がつづいた。1990年以降は生産性の上昇率が低下した。不良債権の処理を先送りしたことがゾンビ企業を温存してしまったという指摘もある。
2005年になって、不良債権の処理が見通しがたったあとも、日本経済に活気は戻ってこなかった。
バブル崩壊で楽観主義が失せ、企業家精神が萎縮してしまったのではないか、と著者は危惧している。それとともに「会社」の居心地のよさが、労働力の流動性をはばみ、転職市場を未発達のままにしているともいう。
企業が内部留保を増やしているのも、そうした保守性のあらわれだ。
さらに著者は「無形資本経済」への対応の遅れを指摘している。つまり、日本型システムは新たな時代に対応できなくなったために失速したのではないかというわけだ。
無形資本とは目に見えない知識資本だ。特許や著作権、デザインなどの知的所有権、研究開発、マーケティング、組織資本、データベースやソフトウェアなどをいう。日本はIT化の波に乗り遅れているし、保守的な金融システムが無形資本への投資を阻み、企業の成長を阻害しているという。
日本企業の閉鎖性も問題だという。
日本の金融システムの問題点を、著者は次のように指摘する。
〈まずは、銀行が物的資産を担保とした貸し出しから脱却できないことであり、次に、企業が情報開示の重要性を理解しないことであり、そして、預金保険制度が資金の流れを堰き止めていることである。〉
人間関係のもたれあいのうえに成り立つ日本社会の不透明性が成長の足を引っぱっているのだ、と著者はみている。
だが、はたしてそうなのだろうか。いま欠けているのは、むしろ未来へのヴィジョンだというような気がする。社会主義が惨状に苦しみ、資本主義がバブルでついえるなか、商品世界の次の光がみえてこないことが、現在の停滞と破壊をもたらしているととらえるのは、ぼくのように無知な老人の妄想なのだろうか。
いつまでも財政拡大はできない──『バブルの経済理論』つまみ読み(3) [経済学]
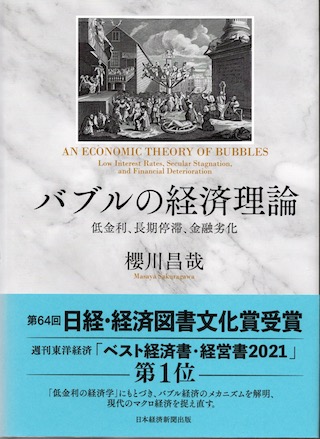
国際的な基準でみると、2020年段階で日本の政府債務・GDP比率は270%に達したという。つまり、日本は名目GDPの2.7倍の国債を発行しているということになる。OECD主要23カ国のなかで、これほどまで多くの割合で国債を発行している国はほかにない。このまま行けば、日本の財政は破綻するのではないか。多くの人が心配しはじめている。
櫻川昌哉の『バブルの経済理論』を読んでみる。
量的緩和がはじまる以前の2012年段階でも、日本の債務残高は対GDPで180%に達していた。にもかかわらず、国債利回りは2%未満と世界的にみても、もっとも低かった。2021年段階でそれは0%台とさらに低くなっている。
ふつうは債務残高が増えると、国家財政のデフォルト・リスクが高まり、国債利回りが上昇する。ところが、日本の場合は、そうならなかった。その理由として、著者はいくつかの仮説を挙げている。
ひとつは消費税率が10%と低く、まだ税率の引き上げ余地があると考えられ、財政破綻のリスクは低いと見積もられていること。
ひとつは金融緩和の効果。とりわけ2013年4月以来の量的緩和による長期国債の買い取りが長期金利を押し下げていること。
さらに日本では90%以上の国債が国内で保有されていること。とりわけ2019年段階で日本銀行の保有率は50%以上となったが、民間銀行や保険会社、ゆうちょなどの公的金融、公的年金基金などの国債保有率も高かった。こうした日本の金融機関が国債の保有を支えている。
日本の国債利回りは他の先進国とくらべて圧倒的に低いが、それでも日本の投資家は日本の国債を買いつづけている。その理由として銀行などの貸し出しの伸び悩みを挙げる人もいる。
だが、著者はいう。
〈利回りが低いからといって、国債は安全な資産ではない。政府に保護された金融機関や時代の流れの中で役割を終えたはずの金融機関が、国債の受け皿機関として温存されたのである。国債市場を構成するのは海外で資金運用する能力を持たない金融機関、つまり「安全資産の欠如」に直面している金融機関であり、市場の情報が価格に正しく反映されていないのである。〉
その結果、市場は骨抜きになったしまった。利回りが上昇しないと、緊張感がなくなり、政治家はますます財政再建を先送りし、国債残高はさらに積み上がっていく。その異常さにもっと気づくべきだ、と著者は警告する。
にもかかわらず、日本の財政が安定しているようにみえるのはなぜか。現在の日本経済は余剰資金がかなりの規模で存在するバブル経済だ、と著者はいう。経済成長がほとんど見込めないなかで、余剰資金は安全資産に向かう。現在の銀行預金は700兆円を超えているが、そのうち貸し出されているのは450兆円ほどで、残りの貯金は国債や日銀への預け入れ(超過準備)に向けられている。
2013年以降の量的緩和以降、デフレはほぼ終息し、名目成長率はプラスに転じたが、国債の利率は成長率を1.5%ほど下回るようになった。現在、「日本国債の価値を支えているのはバブル、つまり借り換えで償還費用を賄うことができるという期待である」と、著者はいう。しかし、余剰資金がだぶついているからといって、いくらでも財政赤字を拡大できるわけではない。
1990年代以降、日本の国債はGDP成長率を上回るペースで発行され、2006年にはすでにGDP比170%を超えていた。その後、リーマン危機、東日本大震災などがつづき、財政再建計画は水の泡となり、2019年段階で国債のGDP比は230%となった。さらに、新型コロナ・ショックが追い打ちをかけて、国債残高はますます積み上がっている。2025年までに基礎的財政収支(国債費を除く歳出から税収・税収外収入を引いた額)を黒字化するという目標もさらに遠のきつつある。
基礎的財政収支の黒字化は、財政健全化のための最小限の指標である。そのなかで、最大の問題となるのが社会保障費の増大だという。増えつづける社会保障費にはたして財政は対応できるのか。
2018年に120兆円だった社会保障給付額は、2040年には190兆円程度に膨れあがるとみられている。その上昇分70兆円のうち半分が税金でまかなわれる。
成長率やインフレ率の算定にもよるが、2040年段階で社会保障費の財政支出は対GDP比5%増になる、と著者は想定している。国債の利払い費は成長による税収増でカバーされるとみたうえで、基礎的財政収支のバランスをとったうえで(プラス2%)、社会保障費をまかなうにはGDP比7%の税収増が必要であり、それをすべて消費税でまかなうと、著者の計算によると、それは17.5%になる。すると、消費税は現行の10%から27.5%に引き上げなくてはならない。
これはもちろん机上の計算である。その計算は利子率が成長率より高いか低いかによっても変わってくるし、さらに国際的な動向も関係してくる。それが実際に実施できるかも問題だ。
しかし、著者は「増え続ける社会保障費を賄うための増税スキームをあらかじめつくっておくこと」がだいじだという。「社会保障費がGDP比で1%上昇すれば、消費税率もまた1%上昇させると法律でルール化するのが望ましい」。
ただし、消費増税のたびに消費不況になる過剰反応を抑えるには、政府による正しい説明が求められる。年金と消費税の問題がつながっていることを国民に理解してもらわなければならない。「政治に求められる見識とは、年金を受給したければ増税を受け入れるべきであり、増税が嫌なら年金受給をあきらめるしかないことを国民に向かって正直に説明することである」
残るは国債問題である。
経済が過剰貯蓄状態にあるなら、いくら国債を発行しても債務不履行にはならないし、インフレを懸念する必要もない。これがMMT(現代貨幣理論)といわれる考え方である。
この考え方は日本経済の現状に即しているようにみえる。国債利回りが成長率を下回っているかぎり、これは正しい。いくら国債を増やしても、財政赤字のコストは小さい。インフレになれば、その時点で財政拡大をやめればいいということになる。
しかし、そううまい話があるのか、と著者はいう。
財政拡大は短期的には民間経済を刺激するが、次第にその効果は薄れていく。クラウディングアウトをおこして、民間需要を収縮させるからである。
中期的には、国債の大量発行は民間の資本蓄積を阻害する。さらに長期的には「財政赤字が持続すると、政府債務が経済の規模に比べて大きくなりすぎるという弊害が生まれる」。
その結果、財政が厳しくなり、長期の成長にとって必要な研究開発、教育、経済のデジタル化といった公共投資が抑制されてしまう。さらに財政余力がなくなり、いざというときの対応が追いつかず、長期的な経済停滞をもたらしかねない。「結局のところ、財政赤字が持続すれば、国債残高は膨れ上がり、経済成長は減速する」
現在、日本は財政と金融の分離を原則とする財政ルールを放棄し、中央銀行が国債を買い支えるという財政ファイナンスの入り口にさしかかっている、と著者はいう。
〈中期的には、国債発行が投資の変化を通じて資本蓄積に影響を与える。国債発行は民間部門に利用可能な資金を政府が奪うので、一般的に考えれば、民間の資本蓄積を阻害する。〉
いつまでも財政を拡大し、国債を増発しつづけるわけにはいかない。政府債務残高がGDP比で260%を超えている現状は異常である。
著者はかつて日本の軍国主義時代におこなわれた日本銀行による財政ファイナンスが、敗戦後のハイパーインフレーションを招いた歴史をふり返って、こう述べている。
〈勝ち目のない戦争は、敗戦がほぼ明らかになっても撤退の判断ができずに、ずるずると最悪の事態へ突き進んでいったのである。……無担保貸出にまで頼って軍拡を推し進めたのは誰かといえば、統帥権独立を盾に権力を牛耳った参謀本部である。今となっては偏狭で傲慢な、そして狂信的な軍国主義者であるかのように描かれる彼ら陸軍の幹部は、難関の試験で選抜されて、陸軍士官学校、陸軍大学を超優秀な成績で卒業した“普通”の秀才でもあった。〉
現在の構図はこれとよく似ているという。足下を見ることなく、経済大国の栄光を追い求めて突っ走った先には何が待っているのだろうか。
いまおこっているのは「経済の贈与化」であり、経済の贈与化が進行すれば、市場経済は縮小し、経済は成長しなくなる、と著者はいう。現在、新規の貯蓄のうち民間投資に回るのは5割強で、4割強は政府債務の購入に回されている。このことは金融の劣化を示す以外のなにものでもない。
「日本経済を筋肉質の経済につくり変えるために、金融の劣化を食い止めなければならない」
日本経済を正常な軌道に戻すために、著者は以下のような提言をしている。ひとつはゼロ金利政策からの離脱。財政拡大政策を打ち切りにすること。基礎的財政収支の黒字化を目標として、消費税を12〜13%に上げること。円の国際化を進め、国債の海外保有を促進すること。
いずれにせよ、いまは経済の変わり目だ。
日本史への視座──美濃部達吉遠望(29) [美濃部達吉遠望]

ほんらいの専門である比較法制史や公法の分野から離れるようだが、美濃部達吉は『日本国法学』の一章で、日本の歴史をふり返りながら、明治維新のもつ意義を強調している。それは天皇が万世一系であることをことほぐ物語ではなかった。日本では、さまざまな政体の変化がありながらも、皇室はそのなかでそれなりの役割をはたすことで存続し、明治になって、ついに立憲君主制という輝かしい形態をとるにいたった。そのことに達吉はむしろ意義をみいだしていた。
はっきりとは書いていないが、達吉が王政復古そのものに重点を置かず、立憲君主制の確立と、そのもとでの議会の発達に期待を寄せていたことは明らかである。万世一系思想の過度の強調が、議会主義の否定につながりかねないことを懸念していたともいえる。しかし、その懸念が、昭和の戦時体制下において事実上の軍事政府樹立となってあらわれることを、現時点の明治末段階で予想できたわけではなかった。明治が落日を迎えるこのころ、目の前に広がろうとしていたのは、むしろ大正デモクラシーの時代だった。
ここではもう少し具体的に明治育ちの達吉が日本の歴史をどのようにとらえていたかをみておくことにする。われわれは戦前の歴史というと、皇国史観を思い浮かべがちだ。それは、記紀の神話から綿々とつづく天皇の国の歴史にほかならなかった。しかし、明治末年に達吉のとらえた日本の歴史は、それとはずいぶんことなっている。
はじめに、こんなふうに書いている。口語に直して紹介してみよう。
〈国初から明治維新にいたるまでの日本の国家体制の発達は、およそ4期に分けることができるだろう。第1期は国初から大化の改新にいたり、第2期は大化の改新から鎌倉開府にいたる。鎌倉開府ののち、徳川幕府の成立にいたるまでは、これを第3期とし、これより明治維新にいたるまでを第4期とする。〉
まるで新井白石を思わせるような書きっぷりである。達吉が明治維新までの歴史を淡々と4期に分け、日本史をできるだけ客観的に記述しようとしていることがわかる。
各期について、達吉のまとめをごく簡単に紹介してみよう。
(1)国初から大化の改新(645年)まで
日本民族がどこからやってきたかはわからない。だが、いずれにせよ海を越えて移住してきたことはたしかだ、と達吉は書いている。そのとき、日本にはすでに先住民がいたかもしれないが、新たな集団はそれを駆逐したり征服したりして、九州から東征し、ついに日本国の基礎を築いたという。ここでは、記紀の神話は排除されている。
日本に移住してきたとき、その新たな集団はすでに農業技術や造船・建築技術などで高い文化をもっていた。地域が統合されていくなかで、「族長的君主」が登場する。かれは、もっとも高貴な氏族の族長として、国じゅうのすべての氏族を統轄支配する権利を有していた。
そのころの社会・政治組織は氏族制を基礎としていた。人びとは多くの氏(うじ)にわかれ、各氏には族長がいて、一定の地域を支配していた。天皇は各氏のもっとも高貴な一族の出身で、国じゅうのすべての氏族の上にあって、各氏族を統轄する役割を果たしていた。
天皇は最高の祭主であり、兵馬の大元帥でもあり、かつまた最高の裁判権者でもあった。氏のあいだに争訟があればその裁決をおこなった。
そのころ朝廷の官職は、決まった氏が世襲していた。各氏はその尊卑に応じて、臣(おみ)や連(むらじ)の姓(かばね)をもっていた。全国は多数の国に分かれていたため、各国には国造(くにのみやつこ)が置かれた。
皇位は父子継承を原則としたが、かならずしも長系相続を原則としていたわけではない。男系男子が本則であり、例外的に女帝を認める。だが、その血統は常に男系の出にかぎられる。
皇位はゲルマン民族などのように民族の総集会によって決められていたわけではなく、あくまでも皇統、すなわち血統にもとづいていた。
これが達吉のえがく天皇の原型である。ここで「国体の基礎いかに強固なりしかを知るに足るべし」と強調するところをみても、達吉がいかに天皇主義者だったかがわかる。
(2)大化の改新(645年)から鎌倉開府(1192年)まで
大化の改新の意義は、氏族制度を一変したことにある、と達吉はいう。そのころ蘇我氏の専横が目立ち、中大兄皇子は中臣鎌足と協力して、蘇我氏を討ち、「大権を皇室に復した」。
大化の改新は、日本の政治に一大変革をもたらした。唐の制度が取り入れられ、氏族制に代わって新たに官制が定められ、土地は国有とされ、地方制度が整備され、各国に国司が置かれた。
だが、大化の改新以降は外国の制度を取り入れるのに急なあまり、政治改革は国の実情に合わないことが多かった、と達吉はいう。
門閥の一掃はたしかに理想ではあったが、官職の世襲は避けられず、次第に藤原氏が摂政、関白の地位を代々受け継ぐようになっていく。土地の私有を禁止した班田収受の法も長く維持できず、土地公法主義は100年足らずのうちに全く失われてしまうことになる。
これに代わって出てくるのが荘園制度だった。荘園は貴族や寺院の所有する私有地で、朝廷はしばしばこれを禁止しようとするが、その勢いをとどめることはできなかった。国司の制度も有名無実となっていく。
達吉はこんなふうに記している(口語に直した)。
〈平安朝の200年(西洋紀元では9世紀から11世紀初めにかけて)は表面は天下泰平で京の朝臣はひたすら栄華にふけっていたが、国権はその力を失うようになり、国勢がまさに一変する機運が、このかんに養成されていた。新たな勢力が勃興しようとしていた。その新しい勢力とは東国における武家にほかならない。〉
中央権力は統治能力を失おうとしていた。これに代わって、各地を武力で支配しようとする勢力が生まれた。その地方豪族のなかでも、もっとも有力だったのが源氏と平氏である。
ただ、政権がまったく武人の手に帰するまでは、なお多くの年月を要した。
そのころ皇室はどのような立場に置かれていたのだろうか。
〈大化の改新から平治の乱にいたるまで、そのかんおよそ500年あまり(第7世紀中葉から第12世紀中葉まで)親しく皇室によって国政がおこなわれたのは、ただその初期にすぎず、中ごろには実権は藤原氏の手に帰し、のちにはさらに転じて平氏に帰した。とはいえ、この政権推移のかんにあっても、皇室はなお厳としてその最高統治者としての地位を失わず、実際に権柄をとる者がだれであっても勢力の中心が皇室にあったことは、わが国体史において特に注目すべき事実である。〉
ここで達吉はヨーロッパでは王朝の変遷が著しかったのにたいし、「わが国体の歴史上の基礎がいかにこれら欧州諸国と異なれるかを知るべし」と論じている。
摂関政治をへて武家政権が成立するにつれ、皇室は次第に衰える。しかし、皇室を抜きにして日本の政治は成り立たなかったというのが、達吉のとらえ方だといってよいだろう。
(3)鎌倉開府(1192年)から徳川幕府成立(1603年)まで
頼朝は天下の実権を握ると、征夷大将軍に任じられ、鎌倉に幕府を開いた。
王朝以来、荘園は国司の管轄外にあり、もっぱら領主と庄司の支配下に置かれていた。
文治元年(1185年)に頼朝は朝廷に奏請して、諸国に守護を置き、荘園に地頭を置くことした。これらはすべて鎌倉幕府の管轄下に置かれた。こうして、朝廷や公卿の所領と荘園、寺社の荘園を除いて、武家の所領の支配が確立する。
頼朝は平氏を討滅すると、平氏の旧領を没収し、関東以外にも莫大な領地を広げ、その領地を御家人に分かち与えた。とはいえ、それ以外にも公卿や社寺の荘園、国司の支配する国衙(こくが)もあって、これらに幕府の権力はおよばなかった。
鎌倉時代の初期は、朝廷はまだ権力を失ったわけではなく、両頭政治の時代がつづいたという。とりわけ叙位任官の権利は朝廷に属していた。朝廷の権力が衰えたのは承久の乱(1221年)以降である。この乱に関係した武家と公家の領地は没収され、幕府の権力はさらに強化された。
鎌倉では源氏の正統は3代で途絶え、北条氏がその実権を握った。だが、その幕府の勢いが衰えると、後醍醐帝が帝権を回復する。しかし、その親政は成功せず、足利氏が新たな帝を立て、57年にわたり南北朝時代がつづいた。
足利氏にいたって武人政治は完成し、朝廷の権力はまったく失われ、公卿や朝臣もみな幕府の権力のもとに服するようになった。諸国の土地はみな武人の所轄となり、朝廷の命じた国司はすべて滅んだ。
室町時代において全国の土地はみな守護の所轄となった。守護は幕府の権力を奉じていた。とはいえ、世襲の大名として、次第に専制的な権力をふるうようになる。
幕府の財政は将軍の所領からの収入と大名の納める租税によってまかなわれていた。足利氏が盛んだったのは義満の時代だけである。その後、守護の勢いが強くなり、下克上の様相が広がり、ついに戦国の世となった。
織田信長は天下を平定しようとしたが、その途中で反逆にあい、豊臣秀吉があとを次いで、国内をはじめて統一した。だが、その権力も長くつづかず、天下は徳川氏に帰すことになる。
そのかん皇室の衰退は極度に達していたが、信長、秀吉は勤王の志あつく、それによって皇室の尊厳はようやく回復した、と達吉は記している。
(4)徳川幕府から明治体制へ
足利時代末期から江戸幕府成立までのほぼ100年を、達吉は中世から近世に移行する過渡期ととらえている。
国家統一の機運が高まるなか、徳川氏はきわめて強固な武家政権を築いた。江戸幕府は鎌倉幕府や室町幕府と同じく武家政権だったが、前の二つとは大きく性格を異にしていた。世襲の大名が将軍から封土を授けられ、諸国を領しているという意味では封建的だったが、将軍が最高領主としての権力を保持し、国全体を統轄していたのである。
それでも将軍は君主ではなかった、と達吉はいう。
〈簡単に当時の国体を説明すれば、まず国家最高の地位としては天皇があった。天皇が国家一切の権力の源泉であるとする信念は、古来から変わることがなかった。とはいえ、天皇は国政をみずからおこなうことなく、すべて将軍に委任していた。将軍は天皇の官吏ではなかった。天皇によって随意任免されるものではなく、世襲職として全国の最高領主であったが、それでも君主ではなかった。その最高領主としての地位は君主の委任にもとづくものとされ、形式上、将軍は宣下の式によって天皇から将軍に任ぜられていた。〉
江戸時代の制度をさらに詳しく述べる必要はないだろう。いずれにせよ長くつづいた徳川政権は明治維新によって瓦解した。大政奉還がなされ、王政復古の大詔が発せられ、「鎌倉幕府以来武門の手に移りたる政治の実権は、ここにおいて始めて朝廷に復したり」と、達吉は記している。
明治元年(1968年)、五カ条の御誓文によって、明治政府の施政方針が示された。それは「我が国未曾有の大改革」であって、「立憲政体の基礎を定め」、「欧州文明の粋を採用するの主義」を確立するものだった、と達吉はいう。
明治維新によって封建制度は覆滅され、階級制度は廃止され、中央官制が整えられ、議事機関が発達する。そして、ついに明治22年(1889年)に憲法が発布され、翌年、帝国議会が召集された。「我が国の立憲政体はかくのごとくにして確立したり」と達吉はいう。
以上ごく簡単に要約した記述をみると、達吉は万世一系という血統主義そのものよりも、皇室が時代に応じてかたちを変え、日本の統合に大きな役割をはたしてきたことに敬意の念をいだいていたことがわかる。しかし、明治体制のもとで組み立てられた立憲君主制が、はたして激動する世界の荒波を乗り切っていけるのか。しばらくの小康をへて、厳しい時代がはじまろうとしている。
明治国家論──美濃部達吉遠望(28) [美濃部達吉遠望]

美濃部達吉の『日本国法学』上巻上は、総論として、いわゆる国家論を論じていた。その内容は数年前から早稲田大学や日本大学で達吉がおこなってきた憲法講義と重なっている。達吉の講義はノートやメモを見ることもなく、理路整然とおこなわれたと伝えられるが、それはおそらくかれが講義の都度、少し角度を変えながらも、同じテーマを何度もくり返し語っていたからである。
『日本国法学』は、それまでいくつかの私立大学でおこなってきた憲法講義の内容について、言い足りなかった部分を含めて、みずからの筆で、さらに精緻化し、学術的にも申し分ないものとして鍛えあげたものだったといえるだろう。それはしっかりした石垣の建設をめざして、あたかもひとつずつ石を積むように綿密に築かれていた。
最初に国家は社会現象であると同時に法律現象であることが示されているが、本書では法律上の観念としての国家を取り扱うという限定がなされている。すなわち「国法学」においては、形式としての国家を論じるものとされている。
国家とは何か。
「国家は一定の地域を基礎とする多数人類より成り自己に固有なる統治権を有する団体なり」(原文カタカナ)
達吉はそう規定する。
領土と国民と統治権が国家の3要素である。
そこから始まって、多くの学説が紹介されているが、やはり重要なのは、達吉が国家法人説を唱えていることである。
天皇機関説も国家法人説抜きには成り立たない。何度も同じ話をくり返すことになるかもしれないが、国家法人説がどういったものかを、もう一度、達吉の説明によってふり返っておこう。
国家は永続的かつ統一的な団体として、統治権を有する法人である、と達吉はいう。法人は抽象的な人格者として固有の意志を有している。団体が個人と同じく意志をもつのは事実であって擬制ではない。その意味で、団体もひとつの人格であって、法人と認められるというのが達吉の考え方である。
そのままの引用では読みづらいので、口語に直しておこう。
〈意志がなければ権利はなく、人格もない。団体を人格者(法人)というときは、必ず団体に意志の力があることを前提とするものだ。団体に意志があるというのは、怪訝(けげん)に思えるかもしれないが、社会の実際を見ると、少しもあやしいことではないことがわかる。団体が一定の目的をもつことを認めるとするなら、団体に意志の力があることを認めるのは論理上の必然だ。……社会生活の実際においては、全団体[国家]の目的のためにおこなわれる意志活動は、その意志を発した個人の意志ではなく、全団体の意志とみなされる。〉
国家という団体は、個人が意志を有するにように、法人としての意志を有し、法人として独立したものである。
ただし、国家という法人が、組合や政党、学会などの法人と異なるのは、国家がそれ自体法人として存在するのにたいし、組合や政党などは国家によって、はじめてその法人性を認められる点にある、と達吉はいう。
さらに、法人としての国家が他の法人と異なるのは、国家という法人が統治権をもっていることだ。
〈国家は単なる法人にとどまらず、統治権の主体なのである。国家は自己の権利として統治権をもち、この権利によって臣民に命令し、その命令を強制する力をもっている。臣民に命令するものは国家自身であって、治者は国家の機関として国家の意志を発するのである。〉
国家を団体ととらえる考え方はもちろん古くからあるが、そのことが意識されたのは19世紀になってからだった。というのも、一般に国家が成立するのは、政治権力が社会を統一的に掌握することによってだが、そのことによって、ただちに国家が共同的意志をもつ団体になるとはかぎらないからである。
国家を団体、さらには法人ととらえる達吉の発想は、国家を外部的な暴力装置としてではなく、国民を構成員とする共通の利益団体ととらえるもので、近代的な発想だったといえるだろう。
国家法人説が正しいのは、この見解を認めることによって、国家に関するすべての法律現象を矛盾なく説明できるからだ、と達吉はいう。
統治者が代わったり、被治者が新陳代謝しても、永続的団体である国家は中断されるわけではない。すなわち国家は不可分の統一的一体性をもっている。また国家が活動力をもっているのも、それが法人だからだ、と達吉は強調する。
本書ではさまざまな政治概念が説明されている。統治権、主権の概念、国家権力の問題、国体、三権分立、国家と法の関係などについては、前に早稲田大学での憲法講義で紹介したところでもあるので(それよりもはるかに厳密な規定となっているが)、省略することにしよう。
国家の機関がどのようにとらえられているかについてだけを、少し詳しくみておく。
国家は統一的な意志を有する法的な人格だ、と達吉はいう。しかし、その統一的な意志が形成されるのは、国家の機関においてである。機関なくして、国家は成立しない。
国家の機関に携わるのはいうまでもなく人である。人は法の定めるところによって、こうした機関のもとで、みずからの意志を表明し、その意志が国家の意志として効力を発揮することとなる。
ただし、国家の機関はそれ自身の目的のために存在するのではなく、あくまでも国家の目的のために存在する。機関はあくまでも国家の一部であって、その職分の範囲内において、国家のためにその意志を表示するのだ、と達吉はいう。
国家の機関は数多くあり、その職分として処理すべき国家的事務を定められているが、その職分に応じて機関としての権限を有している。たとえば法律や予算を議決し、緊急命令に承諾を与えるのは議会の権限である。いっぽう法律を裁可し、議会を召集し、議会の閉会、解散を命じ、官吏を任命するのは君主の権限である。
そうした法律上の権限が定められている点において、立憲君主制のもとでは、君主もひとつの国家機関だということができる、と達吉は論じている。
国家の機関と、機関の地位にあたる個人とは明確に区別されなければならない。たとえ個人の意志がそのまま国家の意志となることがありうるとしても、国家機関の意志は個人の意志とは次元が異なる。国家機関のおこなう権利は国家の権利であり、その負う義務は国家の義務となる。
国家機関の地位に就くことは、憲法あるいはその他の法律によって定められている。たとえば皇位継承もそうであるし、摂政を置く場合もそうである。議員は選挙で当選することによって、議会の一員となる。
君主や議会などの国家機関は直接機関と呼ぶことができる。直接機関は国家存立の要件であって、こうした直接機関が消滅することは、国家の滅亡、あるいは革命による国体の変更を意味する、と達吉は説明する。
国家機関は主動機関と制限機関、第一次機関と第二次機関あるいは直接機関と間接機関に区別することもできる。君主が第一次機関だとすれば、議会は第二次機関である。しかし、たとえ第二次機関だとしても、それが憲法によって独立性を保証されていることはいうまでもない。
こうした区別は国体のちがいによって異なる。君主専制国においては、直接機関は君主のみで、その他のすべての機関は間接機関である。いっぽう、立憲君主国においては、常にふたつ以上の直接機関が存在する。立憲君主国においては、君主と議会とがともに直接機関である。共和国においては議会と大統領が共に直接機関となる。
立憲国においては、君主と議会が並び立つために、その関係は単純ではない。君主専制国においては、国権のすべてが君主の一身に発し、君主だけが国権のすべてを総攬(そうらん)する。立憲国においてはこれに反して、国権は一定の秩序をもって各直接機関のあいだに分配されることになる。
わが国の場合は、主動機関としての直接機関はただ君主のみであって、議会は君主の国権の発動を制限する力を有するにとどまり、立法権が与えられているとしても、みずから直接に国民を拘束する意志発動の力をもっているわけではない。
また、直接機関が並び立つ場合も、ふたつの機関は必ずしも独立対等の地位をもっているとはかぎらない。いずれかが最高の地位をもつものでなければならない、と達吉はいう。
ふたつの機関が対等独立の地位をもつ場合は国権の統一性が失われてしまう可能性がある。そのため最高の地位を有する直接機関が必要となるが、この機関を国家の最高機関と呼ぶ。
国家の最高機関は国家にその原動力を与える機関である。最高機関の意志にもとづくのでなければ、国家はまったく活動することができない。最高機関の活動が停止すれば、国家の活動の停止を招くだろう。
たとえば、わが国においては君主の召集がなければ議会も開会することができない。君主の裁可がなければ法律も命令も条約もまったく成立しない。君主の任命がなければ官吏も生まれない。君主が無為であれば、国家はまったくその活動力をもつことができない。それゆえ、わが国では君主が国家の最高機関である、と達吉はいう。
これにたいし、共和国では、もし国民が選挙をおこなわなければ議会も大統領もなく、したがってまたその他の機関を発生することができない。国家の組織はまったく崩壊してしまうだろう。そのため、共和国では国民が国家の最高機関である。
こんなふうに、国家の機関について論じながら、日本においては天皇こそが国家の最高機関だと達吉は論じている。この考えは終生変わらなかった。
問題は明治憲法体制のもとでは、天皇の非公式な間接機関(明治期には元老、昭和期には軍部)が、しばしば天皇の名のもとに実際の統治権を掌握していたことである。
明治の終末──美濃部達吉遠望(27) [美濃部達吉遠望]


日露戦争が終わったあと、美濃部達吉は東京帝国大学法科大学教授として、比較法制史の講座を受け持つとともに、1908年(明治41年)からは師の一木喜徳郎(いっき・きとくろう)の後任として、行政法第一講座を兼任するようになった。早稲田大学や日本大学、中央大学での講義も引きつづきおこなわれていた。
次々と本も出版している。1907年(明治40年)11月には初の本格的憲法論となるはずの『日本国法学 上巻上』を有斐閣書房から出版、さらに翌年8月には同じ版元から『憲法及憲法史研究』を上梓、そして1909年(明治43年)から1916年(大正5年)にかけて、『日本行政法』全4巻を順次刊行している。なかなかの仕事ぶりといってよい。
また、1911年(明治44年)には、文部省の委嘱を受け、中等学校教員夏期講習会で教員向けに憲法について10回にわたり講義した。それが翌年3月には本のかたちでまとまり、『憲法講話』と題して、有斐閣から公刊されている。これが達吉のもっとも知られる本となった。
だが、その本は同時に天皇主権論者からの激しい攻撃にさらされる。達吉はその批判を堂々と受けて立つことになる。
達吉がそんなふうに奮闘をつづけているあいだに、明治という時代は終わろうとしていた。そのたそがれは、どんなふうだったのだろうか。
中村隆英の『明治大正史』を参考にしながら、日露戦争後の日本の様子をふり返ってみる。
日露戦争前後から目立ってきたのは、社会主義者の動きだったという。社会主義者できわだっていたのは、幸徳秋水と堺利彦(枯川)である。片山潜や西川光二郎、安部磯雄などもいる。かれらの多くは平民社を拠点として活動をおこなっていた。そこに荒畑勝三(寒村)や大杉栄、管野スガらが加わっていった。
社会主義といえば、その中心思想はマルクス主義である。だが、幸徳秋水や大杉栄はむしろアナーキズムに引かれていく。
いっぽう、北輝次郎(一輝)は社会主義から出発しながらも、独自の天皇論と社会主義を結びつけ、アジア主義への道を歩もうとしていた。
日露戦争後、こうした社会主義者の言論活動は次第に制限されるようになり、やがてかれらにとっては冬の時代が訪れることになる。
明治末の大きなできごとといえば、やはり韓国併合と大逆事件を挙げないわけにはいかないだろう。
1909年(明治42年)10月に伊藤博文がハルビンで安重根によって暗殺されたあと、明治政府は翌1910年8月に韓国を強引に併合した。それによって、日本は世界の「帝国」の仲間入りをすることになる。だが、韓国を領土にしたために、かえって面倒な問題が後から後からおこってくるのは必然だった。韓国については、日本は併合して失敗したという気がする、と中村は書いている。
もうひとつの大逆事件は、ほんらい事件ともいえないような事件だった。その経過をいうと、幸徳秋水の思想的影響を受けた宮下太吉、新村忠雄、菅野スガ、古河力作の4人が大言壮語するうちに、天皇暗殺計画で盛りあがったのが始まりだった。そして、ためしにブリキ缶の爆弾をつくって、山のなかで実験したら、それが轟音を立てて爆発したため、警察の知るところとなった。この一件は、幸徳秋水ほか4人の逮捕では終わらなかった。警察による逮捕は、事件とは何の関係もない全国の社会主義者三十数人にもおよんだ。
当時の刑法では、天皇とその直系皇族にたいし暗殺を企てた者は死刑とすると定められていた。この事件の裁判は1910年(明治43年)秋から大審院ではじまり、翌年1月、24名に死刑の判決が下った。そして、そのうち減刑となった12名を除いて、判決から1週間ほどで、12名が死刑となった。
韓国併合と大逆事件はひとつの水脈でつながっていた。帝国への膨張が急速に進展するなか、天皇の神格化がますます強まろうとしていたのである。
そんな明治の終末期を、美濃部達吉は日々あわただしい職務に追われるようにすごしている。
現存国家への否定性を思想的原動力とする社会主義者からすれば、美濃部の学問はたしかに官学にちがいなかった。かれらにとって国家とはみずからを抑圧し強制する外部的存在にほかならなかった。そのような国家が変革されなければならないのは、理の当然だった。
このころは社会主義の理想が信じられていた。絶対的理念をかかげる社会主義国家が閉じられた社会をつくるときの怖さをわれわれが知るのは、20世紀の終わりまで待たなければならないだろう。
それはともかくとして、たとえ官学だったにせよ、いまからみれば美濃部の学が国家を法人としてとらえる新たな地平を有していたことはまちがいない。国家法人説はこれまでにない新しい国家論だった。
法人は機関(組織)をもち、人によって成長するものである。法人としての国家は人が動かすものだという主張は、美濃部の講義を聞く、将来、国を担う若者たちに多くの希望を与えたのではないだろうか。
だが、そうした希望の前に、明治憲法体制が次第に重苦しい現実となって立ちふさがっていくことも事実だった。
明治40年(1907年)11月、達吉はみずからの著書としては、はじめての国家論となる『日本国法学 上巻上』を刊行する。著書はみずからの師である穂積八束(ほづみ・やつか)と一木喜徳郎に捧げられた。穂積の学説は達吉とは相容れない。それでも穂積の名前を挙げたのは、かれが帝国憲法に興味をもつきっかけを与えてくれたからである。
その序文に、達吉はおよそこう記している。口語に直してみた。
〈国法学(憲法学)は公法のどの学科でも、その発足点となり、その基礎学となるべきものだ。わたしは数年来、公務のかたわら、二三の私立大学の依頼を受けて、行政法を教えている。昨年[1906年]は版元の求めで仕方なく、その講義録を手直しして出版することになり、その誤りを訂正したり、自分の勉強のためにまとめようとしたりして、夏季休暇中に急いで原稿の手直しをした。だが、原稿ができあがって、これを印刷にかけようというときに、もういちどこれをじっくりと読んでみると、意に満たない点が多く、これを出版するのはためらわれ、版元にその旨を告げて、原稿をすべて廃棄してもらった。昨年の秋、版元が某紙上に拙著『日本行政法』の近刊を予告しながら、ついにこれを実現できなかったのは、こうした事情があったからである。〉
イェリネックなどの最新学説を取り入れた達吉の憲法講義は人気があり、すでに早稲田大学出版部や日本大学から憲法講義録が出版されていた。この序文をみると、達吉はさらにこれらの私立大学で行政法の講義をこころみており、それをまとめて単行本にしようとする企画がある出版社(おそらく有斐閣)からもちこまれていたようだ。
だが、原稿をまとめ終わり、印刷にかけようとした段階で、これではだめだという思いがわきあがったのにちがいない。大上段に『日本行政法』と題するには、あまりにも不十分な内容であることに気づいた。
おそらく、そのころ東京帝国大学で1908年(明治41年)から、達吉が師の一木喜徳郎の第1行政法講座を引き継ぐことが決まっていたのだろう。そのことも出版をためらわせる動機になったのだと思われる。
そこで、達吉は行政法の公刊をしばらく断念して、その前に行政法の前提となる国法学(および国家論)の編述に着手して、ようやくその一部を書き上げた。それを第1巻上冊として出版することにしたのである。
序文はさらにこう記している。
〈本書は二巻で完結を予定している。第一巻では総論につづいて、領土、国民、君主および議会を論じ、第二巻では官制、自治制、官吏[公務員]法をはじめ、立法、司法および行政の各種の作用について論じる。せめて第一巻だけでも全部完了したうえで出版したかったが、総論編はことに困難な部分が多く、原稿を書きなおすこと再三におよび、脱稿まで意外と手間取ってしまった。だが、版元の要請がはなはだ急なため、やむなく総論編のみを分冊として出版することにした。……この二巻の編述を終われば、つづいて行政法の研究にしたがうことができるだろう。〉
『日本行政法』のゲラをボツにされた版元のうらみが伝わってくるようである。版元の編集者は『日本行政法』の出版を取りやめにした代わりに、別の著作を出版せよと迫っていたのだろう。
ちなみに、ここで達吉が予告していた『日本国法学』の第一巻後半はもとより、第二巻後半もついに出版されることはなかった。売れっ子の達吉はあまりにも多忙だった。だが、たとえその続編が出されることはなかったとしても、その内容は別の著書に盛りこまれることになるから心配はいらない。むしろ『日本国法学』の価値は、達吉が国家とは何かを論じた「総論」にあるといってよいだろう。
その総論において、達吉は国家の性質、国家と法、国家の連合、国家権力、国家機関、国体、国家の作用、憲法などに加えて、明治維新にいたるまでの国制の変遷、憲法を中心とする国法などを論じている。
その全部を紹介するわけにはいかないが、特徴的な論点をいくつか取りあげてみることにしよう。
アベノミクス、クロダノミクスに終止符を──『バブルの経済理論』をつまみ読み(2) [経済学]
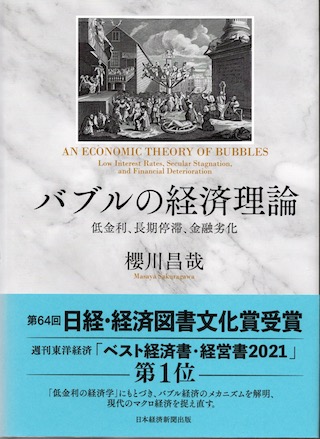
「デフレと流動性の罠」という章を読んでみる。
貨幣には価値尺度、交換手段、価値の貯蔵という機能がある。その貨幣は決済手段として用いられると想定されている。
ケインズは「流動性選好」という概念を打ち立てた。簡単にいってしまえば、流動性選好とは、資産を貨幣のかたちで保有しようとする欲求を指している。
「流動性の罠」とは何か。名目利子率が一定以下に下落すると、中央銀行が供給したベースマネーはそのまま退蔵されてしまい、国債への需要も生まれず、金融政策がきかなくなる。そのため、金融政策による景気回復は不可能となる。これが「流動性の罠」である。
1999年以来、20年以上にわたって、「ゼロ金利政策」をつづけている日本は「流動性の罠」におちいっている、と著者はみている。
金利が名目ゼロになった段階で、人びとは資産としての貨幣を保有するようになった。家計と非金融法人企業の現金残高は1995年段階で45兆円程度だったが、それが2017年には109兆円に膨らんでいる。著者の計算では、いまや日本の名目GDPのおよそ11%にあたる60兆円がタンス預金になってしまっているという。
ここで、むずかしい議論を差し引いていうと、著者は「名目利子率が長期にわたって持続する世界とは、人々が実物資産だけでなくバブル資産を保有するバブル経済なのである」という定式を導きだしている。ぼく流にいうと、バブルとはおカネが実物に向かうのではなく、おカネがおカネ自体の膨張を目的とする経済現象である。
日本経済がバブル経済だとすれば1980年代の資産バブルと1990年代以降のデフレはつながっている。バブルが崩壊しても、利子率が成長率を下回るとバブル経済は残る。その結果、貨幣が退蔵されて、デフレがつづくことになる。金利をゼロにしたからこそ、デフレが起こるという一見意外な結論を著者は導きだしている。
名目金利がゼロになると、人々は債権と実物資本だけではなく貨幣をも資産として選ぶようになる。すると、それは物価を押し下げる力としてはたらき、デフレをもたらす。
アメリカの場合はFFレート(連邦準備制度理事会による政策金利)がほぼゼロに据え置かれたにもかかわらず、インフレ率は2%に保たれた。その理由は、当局者がこの政策を無期限に実施するつもりはないと表明しつづけたためだという。
アメリカ経済は2013年1月にリーマン危機以前の水準を回復した。しかし、その後も雇用回復を重視して、ゼロ金利は維持された。2015年にはニューヨークの株式市場が新高値を更新し、連邦準備制度理事会は7年間におよぶゼロ金利の解除を発表した。市場もまたゼロ金利政策はあくまでも短期だと認識していた。そのかん、アメリカはデフレにおちいらなかった。
日本では2013年4月に黒田東彦が日銀総裁に就任し、大規模な量的緩和を実施し、2年でインフレ率を2%にすると宣言した。
しかし、出口戦略については、いっさい触れなかった。それは一種の賭けだった、と著者はいう。
ゼロ金利のもとで、金融緩和をつづければ、投資は拡大し、景気が拡大して、物価は上昇すると考えられていた。だが、そのもくろみは、みごとに失敗する。経済はデフレを脱却できず、長期停滞におちいった。
人々はインフレ率2%という目標より、ゼロ金利がつづくという展望を信じた。そのため貨幣需要が強まり、デフレがさらにつづくことになった。
〈出口を明示しないまま時間のみが経過すると、人々は名目利子率ゼロが長期化すると予想して、貨幣を保有し続け、決して手放さない。そして経済はデフレに逆戻りしてしまう。〉
インフレ目標が達成されないため、日銀は2015年1月から日銀が金融機関から預かる当座預金にマイナス金利を導入することに決めた。それによって総支出の上昇をはかったのだが、それは逆に信用の収縮を招き、銀行の経営基盤を弱体化することになった。
預金金利がすでにゼロ下限に達しているとき、貸出金利が下がりつづけると、利ざやは縮小され、銀行の経営を圧迫する。
マイナス金利の導入は、金融緩和政策がこれからも長期的につづくことを予想させ、経済はますますデフレ傾向におちいった。
金融緩和政策はさらにずるずるとつづく。その結果、日本経済はついに国の発行した国債を中央銀行が引き受ける、事実上の財政ファイナンス状態となった。
日本の名目GDPの水準はこの20年間ほとんど変わっていない。これは世界で日本だけだという。
国内財における生産性向上の努力が価格を下げ、かえってデフレを進行させている面も否定できない(賃金も低く抑えられる)。
日銀は量的金融緩和によって、2012年から17年にかけ、ベースマネーを147兆円から502兆円に増やした。しかし、そのかん2012年に500兆円ちょうどだった名目GDPは2017年には545兆円へと9%しか増えなかった。したがって異次元の金融緩和はGDPの増加とあまり結びつかなかったといえる。
ベースマネーが急速に増加したのは、日銀が市場から大量に国債を購入したためである。国債の購入によってベースマネーが増えても、それはGDPの増加にはさほどつながらなかった。
金融緩和の目的は実質利子率を引き下げて、経済活動を刺激することである。ところが現実はそうなっていない。それはどうしてか。
銀行は名目利子率がゼロになっても預金金利をマイナスにすることはできないので、利ざやが縮小され、そのため経営が圧迫される。そのため、貸し出しはかえって減ってしまう。
さらに、名目利子率がゼロになると、バブル資産としての貨幣が求められ、タンス預金が増えていく。「逆説的なことに、ゼロ金利の長期化は、金融政策の本来の意図とは真逆に働く力を取り込むこととなり、金融政策からその有効性を奪ってしまう」
いまや日本経済の海図なき航海はいつ難破してもおかしくない、とまで著者は述べている。
ここで著者が提案するのが、ゼロ金利を解除して、名目利子率を引き上げる出口戦略である。具体的には中央銀行が売りオペを実施して、国債を市場に供給し、貨幣を回収する。利上げをすれば、国債の利払い費が増えるため、新企国債の増発が必要となる。純政府債務が増加するため、物価もまた上昇する。タンス預金のうまみはなくなって、人々は貨幣を手放すから、余剰資金が生まれ、実質利子率は押し下げられる。荒唐無稽のようにみえて、これは意外と実効性がある、と著者はいう。
ただし、こうした出口戦略は慎重を要する。まずは金利正常化に向けて舵を切ると宣言することがだいじである。実際にはゼロ金利をしばらく維持したまま、タンス預金を銀行預金に移行させることを先行させるべきだという。そして、インフレ期待が形成された段階で、利上げをおこなう。具体的には400兆円を超える国債を売りオペで市場に売却する。
現在の日銀の政策はケインズ・モデルにもとづいた、近視眼的な景気刺激策にすぎない、と著者はいう。
〈それと引き換えに失ったのは、自律性を欠いた金融政策、財政への信頼の喪失、低金利経済がもたらす将来不安、米ドル依存体質の継続である。さらにつけ加えるなら、需要不足信仰による景気刺激策は、市場規律を弱め、日本経済の足腰を弱体化させた。〉
アベノミクス、クロダノミクスに終止符を。いまこそゼロ金利政策を転換するとともに財政規律を回復し、円の国際化をはからねばならない。直感とはまったく逆に、利上げこそが景気を回復させ、成長を促進するというのが著者の主張である。



