重田園江『ホモ・エコノミクス』を読む(3) [商品世界論ノート]

20世紀にはいると、数理経済学はますます、精緻化され、多様化していく。数理経済学の発想は経済学にとどまらず、それ以外の分野にも広がっのルールとメカニズムにしたがって行動することを余儀なくされるようになる。
ここで著者が取りあげるのが、シカゴ学派の論客ゲイリー・ベッカー(1930〜2014)だ。かれは経済学的思考(ホモ・エコノミクスの論理)をあらゆる人間行為に拡張した。
たとえば、人種差別や犯罪に関する経済学というのもあるが、興味深いのは「人的資本」という考え方である。
それまで人的資本は労働力としか評価されていなかった。しかし、人間は資本なのだ、とベッカーはいう。それは企業にとっては収入を増加させる要素となるし、家計にとっては文化的な消費を増大させる要素となる。
企業は収益改善のために設備投資をおこなうだけではなく、同時に人への投資をおこなう。たとえば職業訓練や研修、あるいは職場環境の改善などだ。モノと同じくヒトも投資すればリターンがある。
人的資本にどれだけの投資がなされるかは期待収益率によって決まる。投資をしても将来、それに見合う収益が得られそうにないと判断されれば、それが投資の限度になる。
つまりこれは、人は資本というより、商品そのもの、あるいは商品を生む商品としてとらえられているということである。
著者は「人的資本論の最大の特徴は、教育を投資と収益の観点からのみ捉えるところにある」としたうえで、みずからの職場である大学をも人的資本を生産する企業とみるベッカーの考え方に強く反発している。しかし、これがいまの大学の現状でもある。
さらに著者はセオドア・シュルツ(1902〜98)の農業経済学にも注目する。シュルツは農業のビジネス化を唱えた。現代のアグリビジネス企業、バイオ企業によるグローバルな農業支配をもたらす経済学を切り開いた人物だ。
慣習的農業の近代化、ビジネス化がシュルツの目標だった。ロックフェラー財団とフォード財団は、このシュルツの考え方にもとづいて、開発途上国での「緑の革命」プロジェクトを立ち上げた。それはあくまでも先進国に都合のよい革命だった。
農民に近代的農業にたいする知識を学ばせ、農家を農業経営者に変える。そのうえで、品種改良した種子や化学肥料、農具や機械を購入させ、大量の農作物をつくらせる。
農業をあくまでも投資と収益でのみとらえるのが、シュルツの考え方だ。 土地は農産物の工場となり、生産性と効率性のみが求められる。
その結果、人びとはますます都市に流れ、農村は再生不可能なほどのダメージをこうむった、と著者は指摘する。
経済学的思考に先導されて、世界の隅々までたえまなく商品世界を浸透させていく圧力は、人びとにはたして何をもたらしたのだろうか。
ゲームの理論、社会的選択理論、行動経済学といった新しい経済学のジャンルについて、ぼくはほとんどわからない。
ここで、著者が論じるのは、そうした新しい経済学が政治学にも適用されているということである。
アンソニー・ダウンズは『民主制の経済理論』において、投票行動を市場における商品売買と同じととらえた。ここでは、有権者の選択によって政治家が選ばれ、多数派をなす与党によって政策が実践されると想定される。
有権者が候補者に投票する基準は、候補者の政策がどれだけ自分のメリット、デメリットになるかである。政党もまた得票の最大化をめざして行動する。つまり、政党のつくりだす政治のイメージは、有権者によって買われるというわけだ。
いっぽう、ジェームズ・ブキャナン、ゴードン・タロックの『公共選択の理論』は、社会的ルールや政策がどのように決定されるかを論じる。
新たな社会的ルールや政策が受け入れられるのは、個人がそれによって課される費用より便益が上回ると考えたときのみだとされる。
政策の決定は、個人と政治共同体との取引、交渉、合意によってなされる。こうして、都市計画や道路計画などにしても、人びとは「利益と費用を勘案しながら政治的アクターとしてさまざまな決定に参加する」。
これがブキャナンらがえがいた民主社会のルールだという。
もちろん、政治過程の経済主義的なとらえ方にたいしては反論もある。
コリン・ヘイは『政治はなぜ嫌われるか』のなかで、ダウンズやブキャナンらの考え方を批判している。
有権者はみずから政治家や政策を選んでいるようにみえて、じつは政党による世論操作に操られているのだ。政党が流すのは、政治家や政策のつかみどころのないイメージにすぎない。
有権者が投票によって、どのような効用を得られるかは定かではない。すると、人気商品をイメージにつられて買うように、政治家を選ぶことにばかばかしさを感じる人もでてきて、棄権が増えてくる、とヘイはいう。
著者はさらにつけ加える。
低成長時代にはいると、民営化、規制緩和、構造改革、財政規律といった新自由主義的な公共選択がいかにも正しいかのように受け止められるようになった。官僚不信が根強いこともあって、民営化論、市場化論はますます広がっていく。民間へのアウトソーシングも推奨されるようになった。
だが、それはほんとうに正しかったのか。公的機能の縮小が生みだした脱政治化のプロセスは、むしろ政治の無責任と民間への責任の押しつけという現象を生みだしたのではないか、と著者は指摘する。
人間をホモ・エコノミクスととらえる見方は、商品世界をさらに進展させた。そこでは人は商品世界のまさに一部となり、そのルール下で競争することを強いられ、そこからはみだす者は排除される。監視社会の傾向がますます強まっている。
著者は最後にこう書いている。
〈相変わらずホモ・エコノミクス[「富を追う人]、「自己利益の主体」]はじわじわといろいろな場所に浸透し、世界を動かす原動力になりつづけている。私たちは知らぬ間に、その人間像を前提とした社会の「構え」にがんじがらめにされている。〉
人間はけっしてホモ・エコノミクスなどではない。それなのに、なぜこんな無慈悲で残忍な人間像が、いまだに世を支配しているのだろうか。
ホモ・エコノミクスの図式からの脱却をはからなければならない。
〈今後は、経済学の自己抑制と社会的価値観の転換が同時に起こらなければ、「人類が生存する地球」という未来は存在しなくなってしまうだろう。私たちはそういうところまで、将来を食い潰して暴利を貪り、取っておくべきものを先取りして蕩尽し、地球上にいる多くの他者を犠牲にしてきたのだ。〉
難解な本ではある。しかし、時に自分もホモ・エコノミクスになっていないかとふり返るのもだいじだろう。
重田園江『ホモ・エコノミクス』を読む(2) [商品世界論ノート]

19世紀にはいると、労働者に支持される社会主義とブルジョア層が擁護する自由主義という二つの陣営が生まれた。
しかし、市場を重視する経済学は、科学主義の立場から、自然と同様に社会のメカニズムを探ろうとした。その前提となったのがホモ・エコノミクス、すなわち経済人の仮説だった、と著者はいう。
リカードは『経済学および課税の原理』(1817年)によって正統派の経済学を確立した。ミルはリカードの理論を引き継ぎ、社会科学としての経済学の樹立をめざした。
ホモ・エコノミクスの原像がつくられている。著者によると、それは「欲望を持ち、その欲望の対象が富であることをあらかじめ定められた個人、そして富の獲得のためにとるべき手段を相互比較し、合理的に選択できる個人である」。
こうしたホモ・エコノミクス仮説にたいして、多くの批判が巻き起こった。富は一概に規定できない。富には歴史的な背景があるし、流行によっても変わる。さらに欲望は自分のためだけともいえない。子どもに財産を残そうとしたり、人のために尽くそうという考えもあるだろう。利己的動機が経済活動の大部分を占める社会は、近代だけだ。それにはたして、個人が市場において完全な情報を把握して、合理的に行動するものとも思えない。
こうした論争は、すでにドイツでもくり広げられていた。とりわけ注目されるのが、オーストリア学派の創始者カール・メンガーだ。メンガーは歴史学派から学びながらも、歴史的な国民経済学ではなく、一般経済学の確立をめざした。
著者によると、メンガーは「経済理論が行うべきは、人間の経済生活の中で最も枢要な、個人の財獲得に向けた努力とそれに基づく経済の仕組みについての体系を作ること」だと考えたという。その前提となるのが、いわば理念型としての経済人だった。
メンガーは一定の前提のうえに純粋経済理論を打ち立てた。だが、それはしばしば前提抜きの一般理論として拡張され、政治的に利用されていくことになる。たとえば、メンガーが「人間がホモ・エコノミクスであると仮定しよう」としたのにたいし、その後、それは「人間は事実としてホモ・エコノミクスだ」、さらには「人間はホモ・エコノミクスとしてふるまうべきだ」という方向に変形されてしまう。それをおこなったのが、メンガーを引き継いだハイエクだという。
19世紀後半になると、経済学はどんどん数学化への道を歩む。数学化を推し進めたのがジェヴォンズとワルラスだ。
経済学が数学化されるさいにも、その根底には抽象化され現実離れしたホモ・エコノミクスの概念が用いられた。快楽は善とされ、そこからさらに限界効用逓減の法則が導入される。労働価値説に代わって、主観価値説、すなわち効用学説が経済学の基本になっていく。
ジェヴォンズの経済学に登場するのは、快楽と苦痛を計量して、商品を購入し消費するホモ・エコノミクスである。その行動基準は効用であり、限界効用は逓減する。
商品の価値はそこに加えられた労働によってではなく、市場での交換によって決まる。ものすごく苦労してつくったものでも、欲しい人がいなければ値段がつかない。逆にどんなつまらないものでも、欲しい人がいれば値がつく。
商品の価格は需要と供給が一致する点において均衡に達する。こうして市場に商品を携えて登場する人間は、てこの原理にしたがって、均衡に達するまで行動することになる。
経済の世界を数学化したワルラスは、限界効用逓減の法則から需要曲線を導きだし、さらに一般均衡を論じていく。そこには古典力学の世界観が反映していた、と著者はいう。すなわち動きつづける経済は、静的な状態に還元してとらえることは可能だという考え方である。
ワルラスは、経済学とは、心的事象を数学的事象として扱う人間科学だと規定した。主観的な効用は計測しうるし、量的な価値を有する富もまた数学的な事象として取り扱うことができる。
ここから効用関数と効用の極大化条件が導きだされる。需要と供給が均衡して交換がおこなわれる点が交換極大点となる。
この力学的世界に登場するのは、典型的なホモ・エコノミクスだ、と著者はいう。
「つまりここには、ただ一つの要素(効用極大化)だけを考慮して正しく意思決定をする、まったくブレないマシーンのような、あるいは運動する質点のような人間しか出てこないのである」
力学との類比がおこなわれたことによって、経済学には何がもたらされただろう。
人間はホモ・エコノミクスとしてとらえられるようになる。すなわち「欲望を所与として厳密な法則にしたがって行動する孤立した単位」。
つまり、 ホモ・エコノミクスたる人間は、市場のメカニズムの一単位となっていく。
もはや欲望とは何かを問う必要はない。
「経済学の解析化は欲望の中身や人の心の内側を問うことを不要にした」。「それはホモ・エコノミクスという人間像の妥当性を問う回路を、数字と関数と方程式によって閉ざし、失わせたとも言える」
近代経済学においては、諸条件の組み合わせからなる実験的状況のもとで、因果メカニズムが追求される。そこでは外部が切り離される。すなわち市場が外部に与える不利益は無視される。
はたして、市場メカニズムはプラスだけをもたらしているのだろうか。じつは、市場交換によって世界じゅうにばらまかれる商品は、自然と労働の搾取によって生みだされ、消費プロセスでそれらをゴミとして排出している。そのことがしばしば無視されている、と著者はいう。
ワルラスの体系には、いわば熱力学第一法則(エネルギー保存の法則)はあっても、熱力学第二法則(エントロピーの法則)はない、とも述べている。
とりわけ産業革命以来の化石燃料の消費は、地球に不可逆なカオスをもたらしつつある。水や砂ももはや無尽蔵ではない。牛という生き物も、いまや牛肉や牛乳、乳製品の製造機のように扱われている。市場メカニズムは、その外部を見ないふりをすることによって成り立っているのだ。
著者はいう。
〈ここで再度確認しておきたいのは、次の事柄だ。[経済学とは]現実の具体的世界から市場を切り離し、生命の循環や自然環境の全体を、「交換可能な財」という孤立し数値化された単位へと縮減してしまうこと。経済学の科学化の思想と運動、そしてその中心にあったホモ・エコノミクスの人間像は、このことに大いに関係してきた。それが私たちが生きる熱くなった地球に起きている、異常気象や環境破壊、動植物の種の絶滅など、「人新世」と呼ばれる時代に生じている末期的事態の、原因の一つであることはたしかだ。〉
つづく。
重田園江『ホモ・エコノミクス』を読む (1) [商品世界論ノート]

タイトルにひかれて買ったが、難解な本だった。むずかしい話はわからない。それにもう時代についていけなくなっている。
そこで、理解できた部分だけについて(ほんとうは理解していないのかもしれないが)まとめることにする。
最初に著者は純粋な「ホモ・エコノミクス」などはいないと書いている。それでも現代人は生きているかぎり、日々何らかの経済行動をとらなければならない。
ホモ・エコノミクスとは合理的な経済人のことだ。「自分の経済的・金銭的な利益や利得を考えて行動する人」のことだという。そうした経済人が登場するのは近代になってからだ。
著者は18世紀から20世紀までの経済学を典拠として、ホモ・エコノミクスの思想史をえがこうとしている。
いまの時代はだれもが多かれ少なかれホモ・エコノミクスで、その頂点にいるのが金持ちである。だが、金儲けをよしとする考え方は、キリスト教的道徳が支配的な時代には、そうすんなりとは受け入れられなかった(日本もおなじ)。
経済第一の時代がはじまるのは、近代になってからである。それまで貨殖や蓄財はいやしまれ、質素や節制、清貧、魂の救済こそが尊ばれていた(単純にそうとは言い切れないかもしれないが、そういうことにしておこう)。
「近代以前の多くの社会で、富の追求は禁圧され、あるいは危険とみなされ、注意深く取り囲まれ、野放図にならないように規制されてきた」
しかし、13世紀ごろになると、商業や利子が次第に認められていく。さらに15世紀になると、自分たちは社会のために有益な仕事をしていると胸を張る商人もでてくるようになった。実際、交易や商業活動、都市化が進み、商人の役割がだんだん大きくなっていった。
さらには、経済競争に勝ち抜いた者は正しく、貧困から抜け出せない者はどこか劣っているという見方すらでてきた。
マンデヴィルの『蜂の寓話』(1714年)は、人びとの利己的な欲望の追求が全体の利益につながると主張したことで知られる。
ハチソンはこれにたいし、信仰心に支えられた節度の欲求を守ることでこそ、人びとは徳を保ちながら、繁栄する社会をつくることができると論じた。
この富と徳をめぐる論争は、その後もつづいた。
ハリントンは『オシアナ』(1656年)のなかで、土地の均等所有と財産の平等を基本とする農本主義的な共和制を擁護していた。そこでは奢侈と商業は危険なものとみなされていた。金銭と富は武勇の徳を奪う危険な媚薬にほかならなかった。
だが、けっきょく勝利したのは「富」派である。
ここに登場するのがヒュームだ。
ヒュームにとって、徳は快楽や効用、利益と結びついている。中世ではそれらはむしろ悪徳ととらえられていた。
それをヒュームは逆転する。快楽や効用、利益は、だれにとっても徳(善きこと)なのだという。この発想は共感をもって受け止められる。
ヒュームは商業社会においては、商業の発展が個人と国家の発展をもたらすという。これにたいし、軍事的な農業共同体であるスパルタでは、徳は武勇に求められ、人びとには富を追求する余地が与えられなかった。
ヒュームはさらに豊かさが洗練と礼儀作法をもたらし、人の情念を穏やかにするという。
奢侈を恐れる必要はない。多少、豊かになったからといって、社会は腐敗するわけでも人間性が毀損されるわけでもない。むしろ、その逆だ。
だが、ヒュームにはブルジョア趣味がある。それはミニ宮廷へのあこがれに似たようなものだ。スミスはヒュームを受け継いだが、ある意味、ヒュームを批判している、と著者はいう。
「それでもスミスがヒュームと異なるのは、富裕は徳とは相容れないものだと考えるようになり、それが立派さを僭称するのは危険だと、かなり真剣に受け止めていたことだ」
スミスは、人びとが富者や権力者をあがめ、貧者を蔑視するのはまちがいだという。富者の傲慢は道徳的頽廃以外の何ものでもない。スミスはむしろ慎ましい生活を送る庶民にこそ徳を認めた。
庶民の徳を体現するのが、時は金なりのベンジャミン・フランクリンだ。フランクリンはその『自伝』(1771〜90)で13の徳を掲げる。すなわち、節制、沈黙、規律、勤勉、誠実、正義、中庸、清潔、平静、純潔、謙譲。懸命にこつこつと働き、富を得るべしとした。
しかし、時代はブルジョアの世紀に向かっていた。ゾンバルトの記述を参照しながら、著者はこう書いている。
〈近代の経済人たちは、子どものように何であれ大きな金額を喜び、大きいものに価値を与える。比較はすべて質を量に還元することで成り立つ。なぜだか分からないが、とにかっく新しければ何でもいいものと見なされる。こうした価値が、人々を投資や投機に向かわせる。売るためのものの生産にのみ関心が持たれるようになり、大衆は買わせるために動員される。商売人は買う気がない人もその気にさせようと躍起になり、新しい需要が実需に反して無理やりにでも喚起される。〉
ホモ・エコノミクスが躍進しようとしている。
つづきはまた。
シベリア出兵と米騒動──美濃部達吉遠望(39) [美濃部達吉遠望]

寺内正毅内閣で知られるのは、何といってもシベリア出兵と米騒動である。
1917年3月(ロシア暦では2月)にロシア革命が発生し、ロマノフ王朝が崩壊した。その半年後の11月(ロシア暦では10月)、レーニンが武装蜂起し、ケレンスキーの臨時政府を倒して、政権を奪取した。
帝国主義列強によるボリシェヴィキ政権への干渉がはじまる。日本もその動きに乗じて、シベリアに出兵した。
ボリシェヴィキに反対するロシアの軍人たちにバイカル湖以東のシベリアを占領させ、かれらがそこに自治国をつくるのを日本が支援する。陸軍参謀本部は、そうした甘い夢と計画を描いた。あわよくば傀儡(かいらい)国家をつくり、シベリアの豊かな資源を手にいれることが目的だった。だが、それが表だってあきらかにされることはなかった。
1918年(大正7年)8月、日本はシベリアに軍を送った。第12師団がウラジオストクに上陸、満鉄沿線駐屯の第7師団、第3師団は内モンゴルの満洲里(マンチュリ)からバイカル湖方面に向かった。その兵力は7万3000にのぼった。
だが、ボリシェヴィキ政権はもちこたえ、ロシアにいつづける日本はイギリスやアメリカなどからも非難を受けることになった。そのため、日本軍はついに1922年(大正11年)10月にシベリアから撤兵することになる。
米騒動が発生したのはシベリア出兵の直前である。景気が悪かったわけではない。むしろ、世界大戦のにわか景気が、製薬や染料、製鉄、製紙、造船、鉱山などの会社をもうけさせ、多くの成金を生み、株価も上昇していた。だが、そうしたなか、インフレが進行し、貧富の格差が拡大していたのである。
米騒動は、富山の漁師の女房たちが、米価のあまりの高さに堪忍袋の緒が切れ、県外に米が搬出されようとするのを阻止するため、資産家や米屋に押し寄せたことからはじまる。
この事件は、新聞にも「越中女一揆」として紹介された。米はさらに上がりつづける。すると8月半ばに京都や名古屋、大阪、神戸などでも、米価引き下げを求める暴動が発生した。騒乱の渦は、秋風が吹きはじめるころまで収まることがなく、一部では軍隊が出動する状況となった。
米騒動は50日におよび、一説によると街頭の騒動に加わった者は100万人におよんだとされる。
寺内内閣は米騒動にからむ記事をいっさい掲載しないよう全国の新聞社に通告した。これにたいし新聞各社は反発し、こぞって政府に掲載禁止処分の取り消しを求めた。寺内内閣退陣要求の動きが強まる。
政界では、寺内は万難を排して留任し、事態の収拾にあたるべきだという意見もみられた。しかし、引きつづく体調不良もあって、寺内は辞任を決意し、在任中、自分を支えてくれた政友会の原敬に政権を引き継ぐ意向を示した。問題は元老、山県有朋がはたしてそれに同意するかどうかだった。
山県は政党内閣を毛嫌いしていた。口が達者なだけで、ろくに行政を知らない政党人が政権を握るのは、想像しただけでむしずが走った。しかし、山県のもとには、すでに手駒がなくなっていた。
清水唯一朗は原敬の評伝で、こう書いている。
〈頼みの西園寺公望は病身であり、後進に道を譲るべきという美辞を重ねて断ってくる。山県が目をかけてきた平田東助[元内務大臣]はこの難局を担う気がなく、清浦奎吾[枢密院副議長]にいたっては、この事態を乗り切れるのは、衆議院のみならず、貴族院、枢密院、陸軍にも良好な関係を築いた原しかいないと強く勧めてくる。それは山県もわかっていた。〉
たしかに、現在のシベリア出兵と米騒動という難局を乗り越えられるのは政友会総裁の原敬おいてほかになかった。こうして、原に組閣の大命が下り、日本初の本格的政党内閣が誕生する。
その後、原はことあるごとに山県と密接な関係を築き、山県の信頼を勝ちとっていく。また原は以前から官僚出身者を党に取りこむことで、政党の質を改善し、政党内閣が機能するための条件を整えていた。
新聞は原を「平民宰相」とほめそやした。これまでの藩閥政治から脱した、新しい政治が生まれると期待したのである。
1918年(大正7年)10月1日に原は総理大臣に就任した。だが、このとき原がかつて親しくことばを交わした大正天皇は、認知症が進み、言語もはっきりしなくなっていた。
そのころ美濃部達吉は相変わらず学務に追われる生活を送っていた。東京帝国大学で行政法の講義を受け持つほか、米国憲法についての研究も進めていた。それでも、雑誌などから憲政をめぐるテーマで執筆を依頼されると、こころよく引き受けている。
米騒動がおこるひと月ほど前、雑誌『太陽』に、達吉の「近代政治の民主的傾向」というエッセイが掲載された。
そこには、こんな一節があった。
〈政治上における民主主義は、近代の世界諸国に共通の趨勢である。その実現せらるる程度の大小傾向には、国により甚大なる差異があるけれども、いずれの国といえども全くその趨勢に影響せられないものはない。その趨勢の殊(こと〉に著しくなったのは、十九世紀の中葉以後であって、世界大戦の勃発以後は、国民一致の努力と犠牲とを要求することが極めて痛切であるがために、その傾向はますます顕著となった。その趨勢はいかなる勢力をもっても、これは抑制することの出来ないもので、しいてこれを抑制せんとするは、かえって革命を醸成するの危険がある。聡明なる政治家は、よろしく大勢にしたがってこれを善導すべく、いたずらに大勢に逆行してこれを抑制すべきではない。〉
達吉がこの一文を記したときは、まだ寺内内閣がつづいていたが、民主主義を求める声は次第に強くなっていた。吉野作造も2年前の『中央公論』に「憲政の本義を説いて其(その)有終の美を済(な)すの途(みち)を論ず」という論文を発表し、「民本主義」という遠慮がちな概念を使って、デモクラシーの意義を説いていた。
達吉はここからさらに踏み込んで、民主主義は世界の趨勢となっており、もはやこれを抑制することはできない、あえて抑制しようとすれば、かえって革命を招く恐れさえある、と論じている。ロシア革命によるロマノフ王朝崩壊が、日本の支配層をも震撼させていた。
それでは民主主義が世界の趨勢だとするなら、民主主義とはそもそも何なのか。それは、けっして恐ろしいものではない、と達吉はいう。
民主主義とは、ひとつに代議制度が設置されていることを指す。
次に選挙権があること。20世紀に入ると、欧米諸国では広く普通選挙がおこなわれ、イギリスなどでは女性にも選挙権が認められるようになった。
「民主主義の大勢のおもむくところ、ことに労働階級の地位の上進した結果は、もはや政権を資産階級の独占たらしむることを不可能ならしめたのである」。日本でも普通選挙権の確立が求められている。
そして、議会の存在。イギリスの慣例にならい、ほとんどの国は二院制の議会をもつようになり、さらに議院内閣制をとる国も生まれている。これは権力の一体性を志向するためで、イギリスなどでは貴族院の権限が制限され、議会はほとんど一院制に近いものになっている、と達吉はいう。
次に国民的政府を実現すること。
「民主主義は立法府について民選議会を要求するすると同時に、行政府についても、また国民的の政府を要求する」
「国民的政府の要求はますます緊切となり、今日においてはまさに近代的民主主義の中心思想をなすものということができる」
それを可能にするには議院内閣制をとる以外にない、と達吉はいう。
民主主義を支えるのは国民の自由である。言論、出版その他、思想発表の自由が認められなくてはならない。さらに結社の自由も認められなければならない。いっぽう国家は治安を維持するだけではなく、進んで社会の福利を増進し、文化を開発する任務を有する。
民主主義は政治の公開を要求する。かつて政治は為政者の独断によっておこなわれていた。だが、近代の民主主義は「政治が国民の批判のもとに行われることを要求するものであって、秘密政治を排斥する」。
民主主義がめざすのは、国民参加による政治の実現である。総選挙は実際には国民投票とほぼ同じ効果を有しており、「議員選挙の結果は、すなわち時の政治問題についての国民の意見の発表たる実際上の効果を有する」。
達吉はこんなふうに民主主義とは何かを述べ、日本ではまだ実現途上にある民主主義を定着させていくことこそが、これからの政治課題だと主張している。
民主主義が国体と両立しない思想だとする考え方は根強かった。これにたいし達吉は反論する。
日本という国が、古来、皇室中心主義を基礎としていることはいうまでもないことだ。しかし、民主主義が明治維新以来、日本の国是であることは、五箇条の御誓文に「広く会議を興し万機公論に決すべし」とあるのをみても明らかだという。その国是を無視して、民主主義を抑圧するのは極めて無謀である。
さらにこう述べている。長くなるが、漢文調の文体からは、当時の緊張感が伝わってくるので、そのまま引用しておこう。
〈今や我が帝国は、東においては旧来の民主国たる米国と相対し、西においては支那およびロシアは相次いで民主政体をとるに至り、四隣ことごとく民主国に囲繞(いにょう)せらるるのありさまにある。もとより我が国体の基礎は盤石の堅き泰山の安きに比すべく、隣国にいかなる政体の変動があるとしても、我が国体はこれによって微塵(みじん)の影響を受くべきではないが、安きが上に安きを加え、鞏(かた)きが上になおいっそう鞏からしめんがためには、維新以来の国是を逐(お)うて、宜(よろ)しきに随(したがい)て近代的民政主義の精神を徹底せしめ、全国民の一致の努力をもって国家の重きに任ぜしむるに如(し)くはない。〉
清朝が倒れ、大戦によってロマノフ王朝が倒れ、太平洋の向こうにはアメリカがあって、日本はすでに周囲を民主国に取り囲まれている。そのなかで、日本がびくともしない政治体制を保っていくには、天皇のもとで、明治以来の国是である民主主義を発展させていかなければならない、と達吉は思っていた。
このエッセイが発表されたのは、米騒動がおこる直前だった。そして、米騒動の全国的な広がりは、むしろ達吉に自分の考え方が正しいことを確信させたのではないだろうか。
なお余分なことを付け加えると、達吉が民主主義を論じるにあたって社会契約説、あるいは天賦人権説をとっていないことにも注目すべきだろう。生まれつき人権を与えられた個人は、国家と契約を結ぶことで、国家に自らの保護を委ねるという社会契約説の考え方は、いわば国家と個人を対等とみなす思想にほかならなかった。
これにたいし、達吉はあくまでも国家を求めるのは人類の必然の要求であって、国家を離れて人類の生活はないと思っていた。民主主義を民政主義と言い換えるのもその考え方を反映している。
人は国家のもとに生まれる。その意味で、国家は個人に先行している。だからこそ、近代国家は民主的な制度をもたなければならない、と達吉は考えていた。
寺内正毅内閣──美濃部達吉遠望(38) [美濃部達吉遠望]

ありていにいえば、第2次大隈重信内閣(1914年4月〜1916年10月)の実績は、第1次世界大戦に参戦し、中国、太平洋のドイツ利権を奪ったこと、さらにその勢いで中国の袁世凱政権に21カ条要求をつきつけ、中国での利権を確保したことだったといえるだろう。
それにより、大隈内閣への評価はいやが応にも高まり、総選挙でも大勝を収めた。だが、そうした対外行動は、いずれも禍根を残し、その後、日本の孤立化をもたらすことになる。そのとき戦争の勝利に有頂天になっている日本は気づいていなかった。
このとき日本の国際戦略を中心になって主導したのは、立憲同志会総裁として大隈内閣の外務大臣の責を担っている加藤高明(1860〜1926)だった。
加藤は三菱の岩崎弥太郎の女婿で、三菱本社の副支配人を務めたあと、政界に転じ、大隈の秘書官や駐英公使を歴任し、西園寺内閣、桂内閣でも外務大臣を務め、桂の結成した立憲同志会を継承した。山県有朋や井上馨などの元老の意向を無視し、独自の判断で政策を推し進める傾向が強かった。
加藤は大浦内務大臣のおこしたスキャンダルと21カ条問題の紛糾によって、大隈が内閣を改造した1915年(大正4年)8月に内閣を離れるが、それでも大隈は加藤をみずからの後継者と目していた。
大正の大礼を無事、成し遂げたあと、大隈は満洲の勢力範囲分割をめぐってロシアとのあいだで第4次日露協約を結んだ。これが、大隈退陣の花道となる。
山県の意向をくんだ貴族院の妨害などにより議会運営がむずかしくなり、いよいよ引き際だと感じた大隈は、参内して大正天皇に加藤高明を次期首相に推薦するという異例の行動をとった。だが、大隈の画策は山県有朋によって阻止される。そして、紆余曲折の末、元老会議により次期首相には元帥で朝鮮総督の寺内正毅(まさたけ)が選ばれることになった。
首相の座を得られなかった加藤は、中正会の尾崎行雄などにも働きかけ、みずからの立憲同志会と合同して、憲政会を結成した。このとき憲政会は198議席を有する衆議院第1党になった。
美濃部達吉は大隈政権時代の大浦内務大臣による議員買収や選挙干渉について厳しく批判したものの、21カ条問題などの外交問題については、いっさい論及を避けている。憲法や行政にからむ問題以外は専門外なので、論評を避けたのだろうか。それとも達吉もまた、日本が獲得した山東半島、南洋諸島、南満洲、内モンゴル東部、その他の利権確保に喜びを隠せなかったのだろうか(山東半島はのち中国に返還、南洋諸島は日本の委任統治領となる)。
こうした日本の海外進出ぶりに、イギリスやアメリカは次第に警戒感をいだくようになる。加えて、中国や朝鮮の内部から巻き起こったナショナリズムが、日本への抵抗意識を高めていくことを懸念する日本人は少なかった。帝国主義の時代がつづいている。
寺内正毅(まさたけ、1852〜1919)は長州の下級武士の家に生まれ、戊辰戦争や西南戦争に従軍したあと、軍事畑を歩み、陸軍大臣、朝鮮総督などを歴任した。元帥となり、山県有朋を中心とする元老会議の推薦により、大命を受けて、総理大臣に就任する。
寺内内閣は政党の基盤をもたない長州閥の内閣で、超然内閣、あるいは非立憲内閣と呼ばれることが多かった。
衆議院からの支持はほとんどなく、憲政会を結成した加藤高明は、さっそく1917年(大正6年)正月に開かれた議会で、犬養毅の国民党に賛同して寺内内閣への不信任案を提出した。だが、犬養自身はこれまでの政治的いきさつや大隈内閣の対華政策への批判もあって、加藤高明の憲政会には、けっして好意をいだいていなかった。
内閣不信任案が可決されると総選挙になった。国民党は議会第1党の憲政会に同調することはなく、むしろ憲政会を批判する側に回った。原敬の率いる政友会は、寺内政権に是々非々の方針をとっていたが、政府の選挙干渉を警戒しながらも、今回の総選挙を党勢回復のチャンスととらえていた。
4月20日の総選挙の結果、政友会は議席を54増やし、165の議席を獲得する。いっぽう憲政会は78減らして121となった。憲政党は第2党に転落した。だが、政友会の議席は過半数に達しなかった。そのため35の議席を確保した国民党がキャスティングボートを握ることになった。
総選挙の結果を受け、6月23日から7月14日まで、第39回議会(特別議会)が開かれる。
この議会について、達吉は『法学協会雑誌』で論評している。
このころ総選挙後に開かれる国会を「特別会」と呼ぶのがすでに通例になっていたが、達吉は帝国憲法には特別会の規定はなく、通常会と臨時会の規定しかないので、あえて特別会としなくても臨時会と呼べばいいのではないかと主張している。
しかし、その後も総選挙後に開かれる国会は特別会(ないし特別国会)と呼ばれ、達吉の提案が受け入れられることはなかった。これは現在もそうである(日本国憲法では総選挙後の国会を「特別会」とすると定められている)。
さらに、達吉は前国会で提出された内閣不信任案についても触れている。寺内首相は不信任案は議会の権限を逸脱し、大権を干犯するものだと発言していた。帝国憲法には議会が不信任案を決議しうることは明記されておらず、そもそも議会が不信任案決議によって大臣の罷免を求めること自体、天皇の大権を犯すものだというのである。
この発言に達吉は論駁を加えた。たとえ憲法に明記されていなくとも、議院に不信任案を提出する権限があるのは当然のことだ。そもそも、立憲制度における議会のもっとも重要な役割は、内閣を監視し、その実績を評価することにあるのだ。また不信任案決議が天皇の大権を犯すものだという批判についても、内閣の失政を弾劾して、その免職を求めるのは、議会に与えられた権限であり、決して天皇の大権を犯すものではないと主張した。
〈もしこれをしも否定せば、これ実にほとんど立憲制度そのものを否定するにことならぬ。吾輩は政府当局者がなお少しく憲法の真義を理解し、我が帝国をしてひとり世界文明国の一般思潮に背戻(はいれい)するの歎なからしめんことを切に希望するものである。〉
古風な言い回しながら、あくまでも議会主義を擁護しようとする息遣いが伝わってくるだろう。
議会主義のもと、日本は決して専制国家、封建国家に逆戻りしてはならない、と達吉は主張した。そのためには議会のルールが国民全体の常識になることが求められた。
達吉は不信任決議案の提出がはたして妥当かどうかを問うてはいない。しかし、議会に内閣不信任案を出す権限はないという考えを時代遅れもはなはだしいと、寺内の考え方をただしたのである。
さらに、達吉は寺内が天皇直属の「臨時外交調査会」なるものを設けるとした提案にも触れている。ていよくいえば、これは議会から遊離する寺内内閣が各党指導者をみずからの陣営に取り込もうとした苦肉の策だったといえる。
寺内は政友会の原敬、憲政会の加藤高明、国民党の犬養毅に働きかけ、いまだにつづく大戦下の国防政策を定めるため、天皇直属の臨時外交調査会に加わるよう求めたのである。これにたいし、原と犬養は応じたが、加藤は天皇を輔弼(ほひつ)する調査会を設置すること自体が憲法違反だとして、これに加わらなかった。
達吉自身は、法律上からいえば、外交調査会の設置は決して憲法に違反するものではないとの見解を示した。
〈吾輩は、単純なる法律論としては、政府の弁明のごとく外交調査会の設置があえて憲法に違反するものにあらざるを信ずるとともに、政治上の問題としては少なくとも大臣責任制度の精神に背反するものなることを信ずるものである。しかしながら、政治上の問題はこと憲政の運用の範囲に属し、しかして憲政の運用は時の必要に応じて進化し変遷すべきものであって、いやしくも直接に憲法に違反するものでない以上は、あえて理論に拘泥してその可否を論ずべきものではない。〉
なかなか理解するのがむずかしい。
憲法が大臣責任制度という建前をとる以上、委員会の決議が大臣の行動に影響を与えるかもしれないという点で、それは大臣の自由輔弼制度を妨げるかもしれない。しかし、すでに教育調査会や産業調査会、国防会議などの委員会が存在することからみても、外交調査会の設置が憲法に違反するものとは思えないと論じた。達吉は憲法の文言解釈よりも、あくまでも政治的実効性に重点を置いた。
憲法にからむ問題は、現実政治とあいまって、次から次にわいてでた。このころ達吉は、それらに目配りをおこたらず、新聞や雑誌にみずからの考えを示すようになっていた。注目すべきは、その見解が立憲制度の促進をめざしていても、特定の政党や勢力に傾いていなかったことである。
寺内内閣は軍事強化の色彩が強い内閣だった。総力戦体制の構築という点から、教育改革にも熱心に取り組んだ。傷病兵や戦死者遺族の困窮を救うための軍事救護令、軍事力の近代化(自動車・飛行機の本格導入)、大艦建造計画、理化学研究所の設立、重工業の育成などである。言論統制には積極的で、そのいっぽう経済政策にはさほど力点を置かなかった。
袁世凱が21カ条要求の一部をのんだことにより、日本はまもなく期限を迎えようとしていた遼東半島(旅順・大連)の租借権、南満洲鉄道(満鉄)の経営権を99年間認められることになった。ロシアとの協約も加えると、これは日本がほぼ半永久的に南満洲を支配できることを意味する。これにより、旅順、大連を中心とする関東省(その軍が関東軍)が実質上、日本の植民地となった。
余分なことかもしれないが、この関東省をめぐっては、1917年(大正6年)の通常国会で、帝国憲法は関東省でも実施されるかという論議がたたかわされている。
達吉の見解は明白だった。関東州には直接、帝国憲法の効力は及ばないと言い切っている。
〈すべて法は社会生活の法則であり、したがいて特定の法は特定の社会に伴うて存在するもので、憲法もまた憲法制定の際における日本の社会を律するがために制定せられたものであるから、憲法制定後に新たに帝国の統治の下に属した新たなる社会に対しては、憲法は当然にはその効力を及ぼすものではない。もし憲法を新社会に施行せんとならば、特にこれを施行すべきことを定むることを要するのである。憲法が関東州に効力を及ばさないのは、ただこの理由によるものであって、しかして同一の理由は朝鮮および台湾にも等しく適用せられるべきものである。〉
美濃部と大隈──美濃部達吉遠望(37) [美濃部達吉遠望]

美濃部達吉は国家主義者ではない。かといって、自由主義者と言い切るにはどこか違和感がある。
その考えは、君民同治を唱えイギリス型議会主義を理想とした大隈重信と似ている。大正天皇は個人としていえば、官僚主義者の山県有朋を嫌い、議会主義者の大隈重信や原敬に好意を寄せていた。大隈は在任中、何度も参内し、政務だけではなく世間話もし、唄まで歌って、天皇を喜ばせている。そんな大隈を山県に近い枢密顧問官の三浦梧楼は警戒した。
思想面において美濃部が大隈とちがうとすれば、大隈が政治家としてはとうぜんのオポチュニストだったのにたいし、達吉があくまでも学者としての原則主義者だったという点かもしれない。
達吉は国家の権力は無制限ではなく、その支配権には限界があり、統治権は国民の権利、自由を侵害してはならないと主張していた。
『憲法講話』では、こう話している。
〈今日においても、いわゆる義務本位の思想がなおかなり強くおこなわれておりまして、ややもすれば国民は絶対に国家に服従する義務があるということを申す者がありますけれども、それは大いなる誤りであります。絶対の服従は奴隷である。〉
国民の権利、自由を重視する達吉にとって、とりわけ警察権の濫用はあってはならないことだった。警察権の行使にはとうぜん一定の限界がある。1913年(大正2年)に『法学協会雑誌』に発表した論文「警察権の限界を論ず」では、しばしば自由裁量権を認められがちな警察権に、その濫用を防止すべき原則を設けなければならないと主張していた。
大正のはじめ、達吉は東京帝国大学で行政法の講座を受け持っていた。その講義内容は1909年(明治42年)から1916年(大正5年)にかけて公刊された4巻の『日本行政法』となって結実する。いずれ、その全体像を示してみたいと思うが、家永三郎は「警察権だけにかぎらず、総じて行政作用には限界があって、行政機関がこれを越えてその権限を行使することは許されない、というのが美濃部法学の一般命題であった」と論じている。
さらに、美濃部が重視したのが、議会の権限強化だったことはいうまでもない。
『憲法講話』では、こう述べている。
〈国会のない国は全く立憲国ではないのであります。もし一口に立憲政体とは何であるかと言うならば、国会の設けてある政体といってよいのであります。しからば国会とはいかなるものをいうのであるかと言えば、国会は二つの性質を備えたものでなければならぬ。第一には国会は国民の代表者たるもので、これが国会の最も著しい性質であります。第二に国会は立法権に参与しおよび行政を監督することを主たる任務としているもので、これが第二の著しい性質であります。この二つの性質を備えているのでなければ、立憲国の意味においての国会ということはできないのであります。〉
しかし、達吉のどちらかといえば自由主義的な考え方は官閥の反発を招き、それが明治末年から大正はじめにかけての上杉慎吉との激しい論争に発展したことは前にも記した。
この論争は達吉の評価を高め、このころから達吉は学術誌だけではなく、多くの新聞や雑誌から時事についての論評を求められるようになった。
そうした論評をまとめたのが、1921年(大正10年)に法制時報社から出版される『時事憲法問題批判』である。ここには山本権兵衛から原敬にいたる歴代内閣にたいするさまざまな批評が収録されている。
大正時代は15年のあいだに11代(再任を含む)の内閣がめまぐるしく入れ替わった。これをみても、日本ではイギリスのような民主政治がなかなか定着しなかったことがわかる。
厳しい時代でもあった。世界では戦争と革命の嵐が吹き荒れはじめていた。そうしたなか、日本の脆弱な議会主義ははたしてもちこたえられるかという課題をかかえていた。
前回記したように、1915年(大正4年)11月に大隈重信は無事、大正の大礼を終えることができた。だが、前年4月の内閣発足以来、大隈内閣には多くの難題がふりかかり、政治運営はそのときすでに困難をきわめるようになっていたのである。
最初の試練は「大戦」(第1次世界大戦)への参加だった。日本はそのころまだイギリスとのあいだで日英同盟を維持していた。
サラエヴォ事件をきっかけに、ヨーロッパでは1914年7月末からドイツ、オーストリア=ハンガリー帝国、オスマン帝国などの同盟国と、イギリス、フランス、ロシアの連合国(協商国)のあいだで、大戦争がはじまっていた。
日本は8月8日に参戦を決定し、8月23日にドイツに宣戦を布告した。
10月に日本海軍は赤道以北のドイツ領南洋諸島を押さえ、11月に陸軍が中国山東省のドイツ軍拠点、青島(チンタオ)を占領した。第1次世界大戦での日本軍の実質的戦闘はこれで終わる。
大隈人気はいやおうなく高まった。
12月の議会解散を受け、1915年(大正4年)3月には、総選挙がおこなわれ、大隈は圧勝する。それまで第1党だった反対党の政友会は一気に議席を減らし、大隈内閣を支える立憲同志会と中正会が議会で多数派を握った。これによって、議会の運営は安定するかに思えた。
総選挙前の1月18日に大隈政権は中国の袁世凱政権にいわゆる21カ条要求をつきつけ、総選挙勝利後の5月9日に、その主要な項目を認めさせていた。これが次第に大問題になっていく。
選挙の結果を受け、5月20日から6月9日まで特別議会(第36議会)が開かれた。
この議会について、達吉は雑誌『太陽』で、こんな感想を述べている。
〈今期の議会はその会期のはなはだ短かったにもかかわらず、種々の事件が起こって、かつて見ざるほどの騒がしき議会であった。その論議に上った重要な問題は、対支外交問題をはじめ、責任支出問題、航路補助問題、予算問題など数々あるが、中にも憲法問題に関して最も論争の目的となったのは、言うまでもなく責任支出の問題である。〉
責任支出とは、政府の責任による予算外の支出をいう。大隈内閣はその金額として、大正3年度分として5300万円、大正4年度の4月1日から5月16日までの分として1250万円余を計上し、議会での承認を求めた。これにたいし、野党の政友会から、これはいままでにない巨額であり、予算制度の蹂躙(じゅうりん)だ、憲法を無視したものだという非難が巻き起こった。
一般論として、国庫剰余金の支出は、はたして憲法違反なのかどうかを、達吉は微に入り細に入り論じている。ここで、それを紹介するのはあまりにわずらわしい。結論だけいうと、憲法の条文に照らして、達吉は剰余金の支出は憲法の禁止するところではないと論じ、政府の主張を支持した。予算外支出はその性質上、あらかじめ見積もることのできない費用で、いかなる必要があっても予算外の支出を許さないとするのは、予算の性質上、無理がある。
とはいえ、政府の責任でおこなわれる剰余金の支出にはおのずから制限があってしかるべきだ。国家の歳出はできる限り予算に準拠しなくてはならず、予算によらない支出はやむを得ない場合にのみ認められる。剰余金の支出が認められるのは、避けられない緊急の場合であること、しかも予備費ではその必要を満たせない場合にかぎられる。
今回の剰余金支出は、主として戦争の突発にもとづくもので、加えて府県への土木費補助、米価調節費、蚕糸会社補助金が含まれていた。これを剰余金で賄うことができたのは、幸いだった。剰余金の支出は法律上では金額に制限がなく、剰余金があるかぎり支出できるが、それが巨額に達する場合は臨時議会を開いて協賛を得るか、議会が開かれていないときは勅令をへなければならない。議会の協賛も得ず、枢密院にも諮詢(しじゅん)せず、たとえ戦争のためとはいえ、政府の独断で支出したのは穏当ではない、と達吉はいう。剰余金支出については、いかなるものであっても論議されるべきものであり、政府もその正当性をはっきりと説明しなければならない。
達吉がこんなふうに剰余金支出の原則を論じたのは、予算を扱う議会の原則を確立しておきたかったからである。日本では議会は政争の場となりやすく、予算問題ひとつをとっても議会制度はまだ確固たるものになっているとは言いがたかった。揺るぎない議会制度をつくることは、近代的な国家を建設するうえで、避けては通れない課題であって、公法学者として、達吉はできる限りそれに寄与したいと考えていた。そのことが達吉が長く憲政評論をつづけた理由だったといえるだろう。
だが、議会が終わったとたんに、またやっかいな問題がもちあがる。
7月下旬、内務大臣の大浦兼武が選挙前の第35議会で、二個師団増設問題にからんで、野党議員を買収したという贈賄問題が暴露されたのである。大浦は元警視総監で、桂内閣でも閣僚となり、立憲同志会の幹部として大隈内閣でも農商務大臣、内務大臣を務めた。
前年、大隈政権は大戦の勃発を契機として、これまで懸案だった陸軍二個師団増設を議会に求めた。だが、多数派の政友会と国民党がこれを否決した。そのとき農商務大臣だった大浦が、野党議員を買収していたことが、いまになって暴露されたのである。
二個師団増設議案が否決されたため、議会は解散され、総選挙となった。大隈は大勝し、大浦は内務大臣となるが、このとき大浦には前年の議員買収だけではなく、選挙違反の嫌疑も加わる。
こうして7月30日に大浦は辞任する。同日、大隈も監督責任から辞表を提出した。大浦の辞任はやむを得なかった。しかし、大熊自身は大正天皇から辞表を却下されることを期待していた。元老の山県や井上も慰留する側に回った。
こうして大隈は辞表を撤回し、内閣改造に踏み切る。辞任に固執した加藤高明外相に代わって、外相は当面大隈が兼任し、新内相には達吉の恩師、一木喜徳郎が就任した。
このあたり、大隈の政治の腹芸である。ところが、達吉はこうした政治のドタバタ劇をきびしく批判した。
野党議員買収の一件は、大浦内相個人の責任として片づけるわけにはいかない。大浦が議会操縦の役割をはたしていたのは事実であって、それが内閣全体の意向、少なくとも暗黙の承認によるものだったのは間違いない。さらに、首相が監督責任を認め、いったん辞表を提出しながら、それを撤回し、その理由として聖旨にもとづくことを挙げたのも、けっして許されることではない。
〈真に去るの意思なくして辞表を捧呈し、もしくはひとたび去らんと決して、たちまち留任をあえてするがごときは、あまりに国務大臣の進退を軽視するものである。……もしその留任が国家のために必要であると思惟(しい)するならば、初めより辞表を捧呈せざるが至当であり、もしその辞任が自己の責任上当然であるとするならば、聖恩優渥(ゆうあく)にして、たとえその罪を宥したもうとしても、その辞意を翻すのは、志尊を輔翼し奉るの職責を全うするものではない。いわんやその留任の理由として、もっぱら聖旨に基づくことをもって弁明の辞となしたに至っては、責を志尊に嫁し奉るもので、恐懼(きょうく)この上もない次第である。〉
こうした一文を読むと、達吉が自由主義的な議会主義者であると同時に、熱烈な尊皇主義者であったことが伝わってくる。
そして、大隈にとっては、自らの手でなんとしても3カ月後に迫る大正の大礼を成し遂げたいと思う気持ちが、辞任をおしとどめたのである。
大正の即位礼──美濃部達吉遠望(36) [美濃部達吉遠望]
大正天皇の即位礼が実施されたのは1915(大正4)年11月10日のことである。場所は京都御所の紫宸殿(ししんでん)。時の首相は77歳になった大隈重信で、20年ほど前のテロ事件で右脚を失っていた大隈は、それでも衣冠束帯を身につけ、正面の階段を上り下りした。
紫宸殿には新たに高御座(たかみくら)が新調され、大正天皇みずから勅語を朗読した。そのあと、大隈が寿詞(よごと)を唱え、万歳を三唱し、儀式は無事終了した。
この即位礼はそれまでのような宮中儀式としてではなく、国民的行事として実施された。そのため即位礼には外国の代表を含め2000人が参列し、紫宸殿の前庭には色鮮やかなのぼり(旙[ばん])がひるがえっていた。
その後、天皇の即位礼は、大正の即位礼を踏襲することになる(ただし平成から場所は東京となった)。その点からすれば、大正の即位礼をどのように実施するかは、重要な問題だった。
大礼をめぐる議論は山本権兵衛内閣の時代からはじまっていた。
1914(大正3)年3月、美濃部達吉は雑誌『太陽』に「大礼使官制問題に就(つい)て」という論考を発表している。大礼使とは、今風にいえば、即位の大礼を司る委員会のようなものだ。それを宮内官とするか、それとも国の官職とするか、またその官制を皇室令で定めるか、それとも勅命で定めるかをめぐって論争があった。
政友会に支えられていた薩摩閥の山本内閣は、大礼使は国の官職とし、内閣総理大臣の監督下に置き、その官制は勅命によって定めるとした。これにたいし、故桂太郎の結成した立憲同志会から猛烈な反対意見が巻きおこり、この問題をめぐって議会でも激しい政府攻撃がなされた。
とりわけ立憲同志会が批判したのは、大礼使の職制を宮中に置くのではなく、内閣総理大臣に属するものとした点だった。大礼のことは、すでに皇室典範や登極令に記されている。したがって、それを担当する大礼使が宮中官であるのはとうぜんで、総理大臣がそれを管轄するのはまちがっているというわけである。
これにたいし達吉は、大礼は単なる皇室の事業ではなく、国家の事業だと論じて、政府の主張を擁護した。
「天皇が国家の元首として行わせたもうところは、たとえこと皇室に関するものといえども、なお国家の事務[事業]にして純然たる皇室の事務ではない」
即位と大嘗祭の大礼は、たとえ皇室令で規定されているとしても、国家の元首としての天皇にかかわることである以上、単なる皇室事業ではなく、国家の事業なのである。もし大礼を国家の事業ではなく、皇室の事業だとするなら、大礼にかかわる費用はすべて皇室費から計上されなければならないことになる。
即位の礼も大嘗祭も新天皇が国家の元首たる地位につかせたもう大礼であって、大礼をおこなう主体は皇室ではなく国家であることは明らかだ、と達吉は主張する。その事務を管掌するのが宮中官ではなく、国の官吏であっても、少しも不思議はない。そして、その官制は最終的に内閣総理大臣の管轄下に置かれるべきだ。
皇室令のひとつである登極令には、天皇の践祚(せんそ)即位にあたっては宮中に大礼使を置くと定められているが、大礼が単なる皇室事業ではなく国家事業である以上、大礼使を宮中に置くという規定は、ただ宮中においてその事務を管掌するというだけのことだ、と達吉はいう。
登極令が大礼の内容について定めていることは確かである。だからといって、大礼そのものが皇室令によらなければならないというわけではない。大礼が政府全体がかかわる国家事業である以上、それが勅命によるべきことはいうまでもない。
そもそも、枢密顧問官も侍従武官もすべて勅命によって定められているのは、いずれもその身分が国の官吏だからである。同様に大礼使がまた国の官制として、勅令によって任命されることはとうぜんである、と達吉は論じた。
皇室令によって定めることができるのは、皇室典範にもとづく諸規則、宮内官制、その他、皇室の事務に関する規定にとどまる。国に関する事業は、たとえ皇室に関連するとしても、皇室典範にもとづく諸規則のほかは、皇室令によって規定されるべきではない。
達吉はそう主張し、山本内閣の措置を妥当とした。
だが、すでに山本内閣はもたなくなっていた。1月にドイツのシーメンス・シュッケルト社東京支社が海軍の高官に賄賂を贈っていたことが発覚し、さらに軍艦「金剛」の建造をめぐるイギリスのヴィッカース社による収賄も明らかになって、政府を糾弾する声が民衆のあいだからも高まっていた。この声に押される格好で3月24日に山本権兵衛内閣は総辞職し、難産の末、4月16日に大隈重信内閣が成立することになる。
ほんらい、大正の大礼はこの年11月におこなわれる予定だった。ところが、その4月9日に沼津御用邸で静養していた明治天皇の皇后、昭憲皇太后(ちなみに大正天皇の生母は柳原愛子)が亡くなったため、1年間延期されることになった。
その後、勅令により、大礼使総裁には伏見宮貞愛(ふしみのみやさだなる)、同長官に侍従長の鷹司熙通(たかつかさひろみち)、以下御用掛、事務官などが任命された。
達吉の提起した大礼使論議は、政局の混乱にまぎれて、ほとんど注目されることがなかった。しかし、この一見煩雑な論議の背後には、憲法上、大きな問題が隠されていたといえるだろう。
明治体制の統治機構は天皇親政がタテマエである。そこには宮内省、内大臣府、侍従長、枢密院などに守られた堅固な天皇の城が築かれていた。
問題は、その天皇の城が、国家の外につくられているのか、それとも国家の内につくられているのかの認識のちがいだったといってもよい。時の権力者はおうおうにして、天皇の城を雲の上の存在にしたがっていた。
達吉は天皇は国家の上にあって国家を統治するものとは考えない。天皇はあくまでも国家の内にあって、統治の最高機関として位置づけられるのだ。
明治天皇のときに倣って即位の大礼を宮中行事とするのは、一見正当なようにみえて、それは皇室を国家の外に、そして国家の上に位置づけようとするこころみなのである。近代国家において、天皇は国家の元首にほかならないのだから、その即位礼ならびに大嘗祭は、まさに国家行事にほかならず、ひいては国民の行事なのだというのが達吉の考え方だった。
こうして、いつのまにか立憲同志会の主張はうやむやとなり、大正の大礼ははじめて国家行事として、さらには国民の行事としておこなわれることになった。山本内閣が海軍汚職事件によって退陣したことも、論戦の収束をうながしたにちがいない。
早稲田を拠点として相変わらず怪気炎を上げていた大隈重信が、16年ぶりに総理大臣の座を射止めるのは、山本権兵衛の次の総理に頭を痛めた元老たちが、大隈にやむなく白羽の矢を立てたからである。
依然として、元老が政府の首班を決定する時代がつづいていた。山県有朋、井上馨、松方正義、大山巌は元老会議を開いて、最初、貴族院議長の徳川家達の名前を挙げたが、徳川は辞退する。つづいて司法大臣などをつとめた貴族院議員の清浦奎吾が推薦され、清浦に大命が下った。だが、組閣工作がうまくいかなかず、清浦は組閣を断念する。その結果、山県有朋が強く推し、井上馨も賛同して、国民に人気のある大隈が、高齢にもかかわらずふたたび総理に選ばれるという結果になった。
こうして、大正の即位礼は大隈内閣のもとで挙行される。
その大礼は、大嘗祭、伊勢神宮、神武天皇陵、伏見桃山陵参拝などを含めると20日以上の日程におよんだ。
大正天皇は1915(大正4年)、11月6日に東京駅を出発し、途中名古屋で1泊し、7日に京都にはいった。沿線では多くの人びとが動員され、奉祝の光景がくり広げられた。
原武史によると、11月10日の即位式では、こんなエピソードがあった。
〈11月10日に行われた紫宸殿(ししんでん)の儀では、高御座(たかみくら)の天皇が勅語を朗読してから、大隈が国民を代表して、寿詞(よごと)を奏上し、天皇に向かって万歳を三唱する午後3時30分に、植民地を含む全国で一斉に万歳を叫ぶことになった。実際には足の不自由な大隈が歩行に時間を費やしたたため、大隈がまだ寿詞を読んでいるうちに万歳を唱える結果となったが、その光景は確かに、京都だけで見られたわけではなかった。〉
この日、京都や東京だけでなく、全国津々浦々、いや台湾や朝鮮でも、祝砲や祝笛、祝鐘が鳴らされ、万歳の声が上がった。
大正の大礼は、天皇をめぐる国民的行事の原型をつくりあげたといえるだろう。
国家と天皇と国民を一体化しようとする動きがますます強まろうとしている。
そのころまだ大正天皇は健康を保っていた。
水野和夫『次なる100年』を読む(6) [本]
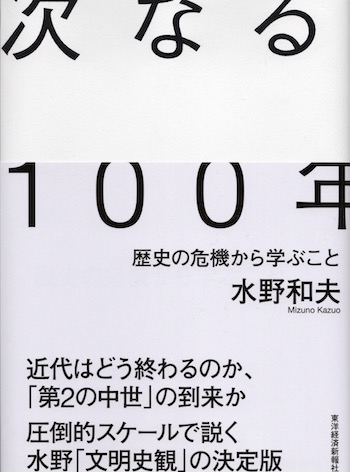
中世の中心はイコン(聖像)だった。これにたいし、近代の中心はコイン(おカネ)である。しかし、21世紀の中心はイコンでもコインでもない。コインはもはや石になりつつある。資本主義からポスト資本主義へ。そのためには何が求められるか、と著者はいう。
資本主義からポスト資本主義への指標となるのが、財政状況の急激な悪化である。これは日本だけの現象ではないが、とりわけ日本が最悪の状況にある。2020年段階で、日本の公的債務残高は対GDP比率で270.4%になっている。つまり、GDPの2.7倍、公的債務が積み上がっていることになる。アジア太平洋戦争の末期でも、公的債務残高はGDPの2倍だったから、それよりもはるかに高い割合だ。
しかし、国債をこれだけ発行しても、国債の利率が上がらないのは、いかに貯蓄(家計の金融資産と企業の資金余剰)が過剰になっているかにほかならない。
PB(基礎的財政収支)が均衡すれば、公的債務残高は減らないにしても、いま以上には増えなくなる。だが、それがいつになるかは、なかなか見通せない。
コロナ禍でも企業は設備投資を抑制し、手元流動性(手元資金)を増やしている。家計も同様で、2021年3月末の個人金融資産は過去最高の1945.8兆円となった。それが日本の財政をかろうじて支えている。
現在求められているのは、課税(とりわけ法人税課税、さらには消費税)によってPBを均衡させること、そのうえで格差・貧困問題を是正するため資産課税を強化することが求められる、と著者はいう。
日本の財政当局が恐れているのは、長期金利が上昇することである。
貿易収支がどうなっていくかも懸念材料だ。現在、日本の貿易黒字を支えているのは車と電気製品だといってよいが、電気製品の力は次第に衰え、自動車産業だけが頼みの綱になりつつある。これにたいし、石油価格の高騰が貿易収支を悪化させている。
2021年度の貿易収支は赤字となった。とはいえ経常収支が黒字を保っているのは、所得収支の黒字幅が貿易収支の赤字幅をいまのところ上回っているからだ。しかし、これからも原油価格は上昇する可能性があるので、貿易収支の赤字幅は拡大する恐れがある。経常収支が黒字のうちに、PBを均衡させていかないと、長期金利が上昇する可能性がある、と著者は懸念する。
現在、「石」と化している個人と企業の膨大な金融資産を動かさなくてはならない、と著者はいう。
世帯でいうと、2021年3月段階で、60−69歳の世帯の金融資産は平均で4985万円、70歳以上は4500万円前後、50−59歳は3000〜3500万円前後だという。もちろん、この数字は平均で、同じ年代でもばらつきがある。年金だけでほとんどじゅうぶん生活している人もいるし、少ない年金で生活に苦しんでいる人もいる。
なぜ、日本人はこれだけの金融資産を残しているのか。教育資金や結婚資金を含め、子どもに遺産を残すという動機も根強い。しかし、老後の生活資金、病気や不時の災害の備えというのがいちばん大きいという。
高齢者人口比率は2055年には36.7%になり、ピークを迎えると予想される。現在の高齢者の金融資産は使い切れない。そのため、それは遺産相続されて、次の世代の高齢者に引き継がれ、金融資産がそのまま「石化」していく可能性が強い、と著者はいう。
おカネは使ってこそ価値がある。相続税を強化(たとえば4000万円超に45%)して、資産を分配すべきだ。親子の関係を日本人全体に広げるという気持ちをもつことがだいじだ。そうすれば、保育園・幼稚園から大学まで無償化して、教育格差を縮めることができる。加えて、大学に行かない選択をした若者に一律500万円を支給するようにすればいいという。
国家がもっともだいじにしなければならないのは正義であり、公共の利益である。中間層が弱体化すると国家は崩壊する。救済こそが国家の役割である。「石」となっている金融資産は、ほんとうの富ではない、と著者はいう。
貧富の格差にともない社会秩序の安定性が失われようとしている。社会の安定化に、あり余る金融資産は寄与すべきである。
近代における所有権は、国家の正当性と結びついてきた。国家は所有権、すなわち「わたしのもの」を保証する仕組みを法的に整えていった。
国家は所有と自由を保護するからこそ、国家として認められる。それはさらに個人の「固有権」、すなわち自由権と社会権という固有の権利を国家が保障するという考え方へと発展していったという。
もちろん、人間は社会的動物として自然法を守らなければならない。人類の保全を目的とするのが自然法だ。
著者は、近代に生まれたロックに代表されるこうした考え方が、今後も継承されなくてはならないと考えている。
そうした観点からすれば、気候変動への対処や、公共善の実現、格差是正、権利侵害への補償は今後とも国家のなすべき義務なのである。
ケインズは「慈愛の義務」を果たさず「財産としての貨幣愛」だけを追求している人は半ば犯罪者だといったという。過剰な富(石と化した貨幣)は困窮者に移転してこそ生きた貨幣となる。そうした役割を果たせるのは国家だけだ、と著者は考えている。
現在の日本でいえば、法人企業利益への課税、消費税引き上げ、相続税の強化、高額所得者へのサーチャージがなされなければならない。そして、それらによって得られた30兆円前後の財源は、最低賃金の引き上げ、低年収世帯やひとり親世帯への支給、大学までの授業料無償化、芸術・文化振興予算、社会保障関連費の自然増などに回されるべきだという。
それらは単におカネの配分を意味するのではない。政治や経済は、善い社会(精神性の高い社会)をつくるための手段にすぎないのだ、と著者は強調する。
近代において、会社は法人格を有するようになり、「永遠の命を獲得した株式会社が利潤の蓄積である資本の所有者となった」。
だが21世紀になると、資金主義者による株式会社支配が露骨になると同時に、株式会社による資本蓄積がますます盛んになっている。そうした必要以上の富(石としての富)は抑制されねければならない、と著者はいう。
パンデミック下において、低所得国では絶対的貧困者が拡大するいっぽうで、先進国では少数のビリオネアの資産が膨張している。こうした状況は、どうみても善い社会の状態とは思えない。ビリオネアたちは少なくとも、パンデミック基金などをつくって、全世界の貧困者救済に寄与すべきではないか、と著者は提言する。
日本でも相対的貧困率の割合が(だいたい年間所得が200万円程度の家庭を想定すればいい)、1985年の12.0%から2018年の15.4%に増えている。なかでも、ひとり親世帯の子どもの貧困率が高い。2018年段階で、ひとり親世帯(とりわけ母子世帯)の子どもは二人に一人が貧困におちいっている。 2090万人の非正規労働者(雇用者全員の37.2%)の生活も苦しい。かれらにたいして、「日本株式会社」はけっして手を差し伸べようとはしていない。
企業の堕落は数多くの粉飾決算や不正行為にあらわれている。それは資本家や企業が貨幣愛に固執する結果である。それによって公共性が踏みにじられ、多くの固有権が侵害されている。
「日本においては、政治家、官僚そして企業経営者は品格がなく、『倫理的な力』が欠けている」。それにたいして、健全な権利感覚を取り戻すべきだ。
人間がつくりあげた秩序を常に正しい方向に是正するには、倫理的な力が求められる。モラル・サイエンスとしての経済を考えるには、倫理学、政治学も視野にいれなければならない。
「20世紀の主流派経済学は効率的な資源配分という名のもとに賃金、利子、利潤について決定してきたが、21世紀の経済学は、『価値判断』を捨象することなく『社会的公正』の観点から分配問題として考え直す必要がある」
かつて、ケインズはこう書いたという。
〈私としては、資本主義は賢明に管理されるかぎり、おそらく、経済的目的を達するうえで、今まで見られたどのような代替的システムにもまして効率的なものにすることができるが、本質的には、幾多の点できわめて好ましくないものであると考えている。〉
著者も資本主義は賢明に管理されていないとみている。貨幣幻想がいまもこの世をおおっている。貨幣愛にとりつかれたビリオネアはあたかも「不死の幻想」を追い求めているかのようだ。
金銭欲ははかない。ゼロ金利社会においては、貯蓄、すなわち我慢する必要もなくなった。
「ゼロ金利は最高の生活水準に到達したことを意味する」。これからは精神生活をだいじにし、「よりゆっくり、より近く、より寛容に」を目標にすべきだ。これからの社会は「成長なくして、分配あり」なのである。
21世紀にめざすべき方向は「堕落してきた人間の精神の向上」である。そして「自己の精神を向上させるのは芸術である」。
近代において生活水準はたしかに向上した。しかし、それに伴って人の精神は失われた。豊かな精神を取り戻すには、自由時間を増やすことが必要だ。
ゼロ金利になって、明日のことなど心配しなくてもいい社会が生まれようとしているいま、毎日を楽しみながら生きる時代が到来しつつある。それが美や芸術、文化に結びつくことはまちがいない、と著者はいう。自然を力ずくで支配するイデオロギーとも訣別しなければならない。
21世紀は資本よりも「芸術の世紀」となるだろう、と著者はいう。
資本主義を打倒せよという主張より、はるかに説得力がある。それはやろうと思えば明日からでも着手できる政治課題だからである。
水野和夫『次なる100年』を読む(5) [本]
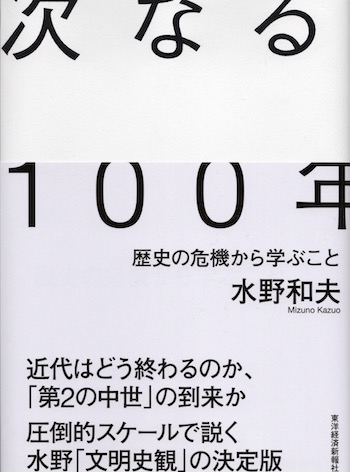
第3章「利子と資本」にはいる。200ページあるが、ごく簡単にまとめてみよう。
日本ではゼロ金利とROE(自己資本利益率)が乖離している。つまり、金利はゼロなのに企業の利潤率は高まっている。
利子の源泉が利潤だとすれば、ふつう利潤率と利子率は連動する。ところが、それが乖離しているのはなぜか。
現在、国債利回りは米国だけがプラスで、日本、ドイツ、フランスはマイナスとなっている。そのほうが、米国に過剰マネーが集まりやすいからだ。
ゼロ金利時代はゼロ成長時代でもある。先進国では、この状態が長くつづくとみられている。
日本では1998年以降、ゼロ金利のもと企業がつねに資金余剰(貯蓄余剰)となり、家計もまた資金余剰(貯蓄余剰)となって、それを政府(大量の国債)と海外(米国の債券市場)が吸い上げるかたちになっている。
いったい何がおきているのだろう。
米国の所得収支が大幅黒字を保っているのは、対外債権の収益率が対外債務の支払い利子率を上回っている(利回りギャップがある)からである。日本の株式市場にたいする外国人株主比率は1990年以降高まり、2020年の時点で20%を超えている。かれらはROE革命の名のもと、企業により高い配当率を求めるようになっている。
グローバリゼーションは植民地主義の新バージョンだ、と著者はいう。ウォール街は世界じゅうから集めた資本をあらゆる地域に投資し、ウォール街に利潤を戻す。中心のウォール街から遠ざかれば遠ざかるほど、成果にあずかることができない仕組みだ。これは一種の暴力装置だ。
いっぽう、日本ではどうか。
〈1990年代前半に急激な円高が進行したにもかかわらず、日本の貿易黒字が減少しなかったのは、実質賃金の下落などによって個人が消費支出を切り詰め、輸出を含めた投資を増やしたからである。日本は供給力を増やし、81年以降経常収支黒字を維持してきた。その結果、対外純資産が世界1位となり、その一部が米国債投資に向かう。国際関係における米国の「例外」は、日本の例外(国内のマイナス金利)によって支えられている。それは、非正規雇用や賃金下落そして預金金利の低下によって中産階級の没落という「反近代」的現象をもたらしている。〉
米国の過剰消費を日本やドイツの過小消費が支えているといってもよいだろう。
日本では中産階級が没落し、「閉ざされた選抜社会」が生まれようとしている、と著者はいう。巨大都市と小都市、地方のあいだ、正規労働者と非正規労働者のあいだに「深い溝」が生じている。
日本のメガロポリス化は1960年代半ばからはじまった。人口は都市に集中した。しかし、経済文明はいっこうに進歩していない。
ほんらい機械化が進むと、生産性が向上し、自由時間が生みだされるはずである。しかし、日本の一般労働者(正規労働者)の年間労働時間は1990年代以降、ほぼ横ばいで、ドイツ、フランス、イギリスより、はるかに高いままだ。
年収200万円以下ではたらく非正規労働者が増えている。それに比例して、中間層の割合が減っている。日本の賃金は名目、実質とも下落傾向がつづいている。
21世紀の日本では、企業が不釣り合いな利益を得ている、と著者はいう。2001年から19年にかけ、労働生産性は年平均0.61%上昇した。しかし、この期間、実質賃金は年平均0.6%減少した。これにたいし、法人企業の当期純利益は2.1倍に増加した。利潤率がますます高まるなかで、利子率はゼロとなった。
1870年代半ばから1970年代半ばにかけての1世紀は特別な時代だった。それは電気・化学・自動車の時代で、一人あたりの実質GDPが劇的に増え、生活水準と労働生産性が一気に上昇したものだ。
しかし、その後のコンピューターの時代は、かつてほどの経済成長をもたらさず、むしろ長期停滞へとつながっている。日本では実質経済成長率がほとんどゼロとなるなか、労働者の実質賃金は減っている。それなのに、大企業、中堅企業の利潤率は高まり、内部留保も増加するという現象が生じている。
利子率は企業利潤率と同じ水準で推移するのが常態だが、21世紀になって、利子率ゼロの例外状態がつづいている。このことは、企業が資本を貸与する銀行、ひいては預金者に相応の利子を払っていないことを意味している、と著者はいう。
それだけではない。
「利潤率が著しく上昇している背景には、賃下げと預金利子ゼロによって資産形成手段を奪われ、壊滅的な打撃を被って中間層からの没落の憂き目にあっている人たちの存在がある」
グローバリゼーションによって、国内での投資機会が少なくなり、海外投資が不可欠となった企業は、海外投資によって企業利益を確保している。いっぽう、国内での純投資はほぼゼロとなるので、経済はゼロ成長、ゼロインフレとなる。
「日本の長期停滞は過剰貯蓄による需要不足ではなく、過剰投資による供給力超過に原因がある」と著者はいう。
そのことは衣食住をみればよくわかる。アパレル産業では毎年10〜15億着が売れ残り、その多くが廃棄されている。日本の食品ロスは2016年推計で646トン(1人50キロ)。住宅の空き家は2018年時点で849万戸。セブンイレブンの店舗数は2018年段階で2万876店だったが、すでに減少に転じている。
設備能力の過剰性は衣料やコンビニだけではなく、日本のあらゆる分野におよんでいる。さらに、実物資産は増えていないのに、金融資産だけが増えている。
通常、利子と利潤は同じ方向に連動する。利子は利潤からしか生まれない。利潤が増えれば利子も増え、利潤が減れば利子も減る。ところが、現在おきているのは、これとは矛盾する減少だ。
利子率はゼロなのに企業の利潤は増えている。成長率はゼロなのに企業の利潤はしっかりと確保されている。
そうした奇妙な現象がつづいているのは、人件費の占める割合が減り、その分、営業利益が増大しているからである。
企業が利益を確保するには、まず人件費を削ればよい。1998年に1173万人だった非正規社員は、2020年には2090万人に増えた。そのため、1998年以降、労働生産性は上昇しているのに、実質賃金は減少している。その分、企業の利潤が増えている。
それを後押しするのが、株主重視の経営だ。しかも借入金利(利息)の低さが企業に一方的な利益をもたらしている。
こうしてゼロ成長、ゼロ金利のもと、実質賃金は低下しているのに、企業利潤と企業の内部留保だけが増えるという現象が生じている。
1999年度から2020年度までの22年間に累積した内部留保金は、154.7兆円にのぼる。それは働く人への「未払い賃金」と預金者に利子として払われなかった預かり金にほかならない、と著者はいう。
グローバルな(米国の)基準に応じたROE(自己資本利益率)と株主重視の経営が、人件費削減を中心としたリストラを継続的に促進させている。その流れは大企業から中小企業へとおよんでいるのだ。
内閣府の調査によると、6割強の人が「物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」と答えている。さらに、6割弱の人が貯蓄や投資など将来に備えるより、これからは「毎日の生活を充実させて楽しむ」と答えている。
だが、それはあくまでも希望であって、じっさいにはほとんどの人が苦労とがまんを強いられている、と著者はいう。この30年間、国民の生活はいっこうによくなっていない。
バブル崩壊後の1990年代以降、日本経済はすでに「静態」、すなわち定常状態にはいっている。利子率はゼロで、毎期、生産、分配、消費がコンスタントに循環する単純再生産の状態にある。
内閣府の世論調査でも、今後の生活がいまと同じようなものと答える人が6割強をしめている。現在の生活が去年と比べて「同じようなもの」と答えた人も2019年には80%にのぼった。
将来の不安は1位が「老後の生活設計」(56.7%)、2位が「自分の健康」(54.2%)、3位が「家族の健康」(42.4%)、4位が「今後の収入や資産について」(42.1%)となっている。
大きな不安をかかえていても将来を達観する人が多く、日本では「足るを知る」生活態度が定着しつつある、と著者はいう。つまり、保守的な傾向が強まっているわけだ。仕事はそつなくこなし、「心の豊かさやゆとりある生活」をしたいと思う人が増えている。
しかし、そこには虚偽の現実が隠されている。
いくら会社が利益を出しても賃金は下がっている。企業では、まず利益が想定されて、そえから人件費が決められるようになる。非正規労働者の解雇や派遣切りがちゅうちょなくおこなわれる。利益追求のためには手段を選ばないという考え方が台頭している。うそも平気につく。
21世紀にはいって、理性は敗北を重ねている、と著者はいう。その結果は、身分社会への回帰だ。中産階級を生みだした20世紀は1977年に終わった。それ以降、不平等度をはかるジニ係数が増加に転じたからだ。現在の資本主義社会は18世紀以上に貨幣欲を原理として動く社会になっているという。
だとするなら、次なる100年はどこに向かうべきか。本書の結論を読んでみよう。
水野和夫『次なる100年』を読む(4) [本]
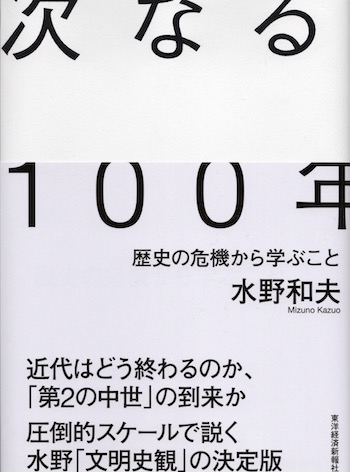
この本はけっして読みやすいとはいえない。歴史と理論、現状分析に加え、おびただしい引用で、頭がぐちゃぐちゃになる。ただでさえ、頭が回らない当方にとっては、何がなんだかわからなくなってしまう。それでも、全体としてはどうやら資本主義の生成と終焉が語られていることが、ぼんやりとながらわかってくる。
昔習った杵柄(きねづか)でいうと、資本主義が終わったら、社会主義だということになりそうだが、そうではないらしい。少なくとも昔ながらの社会主義ははなからしりぞけられている。新しい資本主義というのでもない。そもそも資本主義は終わったのだから。だとすれば、次はどうなるのかというわけだ。
先のことはだれにもわからない。それでも次はどんな時代になるのか、いやなりうるのかを知りたいと思って、この本を少しずつ読んでいる。
きょうは第2章の「グローバリゼーションと帝国──グローバリゼーションは資本帝国建設のためのイデオロギーである」を読んでいる。この章だけで160ページあるが、ポイントだけ紹介してみる。
近代を動かしてきたのは、はてしなく富をつくりだそうとする資本主義システムである。とりわけ19世紀前後からはじまる産業資本主義は、大きな資本をもとに、地下資源の化石燃料をエネルギー化し、機械と結びつけることで商品供給力を増大させてきた。
資本にはもともとグローバリゼーションをめざす傾向がある、と著者は指摘する。中世の13世紀に資本主義が誕生して以来、いやもっと古くから、資本家(商人)は国境にとらわれず経済活動をしてきた。
グローバリゼーションという概念が用いられるようになるのは1980年代からだが、グローバリゼーションの起源は、近代以前の13世紀にさかのぼるという。そのころからフィレンツェの金融業や羊毛組合は、ヨーロッパ全土にわたり、グローバルな活動をはじめていた。15世紀半ばになると、出版業のなかにもすでにグローバル企業が登場している。
16世紀後半、オランダでは近代経済が幕を開ける。オランダはイギリスに先駆けて喜望峰を経由する遠洋航海ルートを切り開き、東アジアに進出した。しかし、やがてイギリスが海を制覇する。
資本の本質はグローバルであり、資本が領土国家の規制から逃れようとするのはとうぜんだ、と著者はいう。
近代は進歩の思想にいろどられている。その信条は変化のスピードと広がりだ。すなわち「より速く、より遠く」が近代のスローガンとなる。
著者によると、そうした近代が生まれたのは、宗教戦争に終止符が打たれた1648年のウェストファリア条約以降である。だが、資本主義はすでに13世紀に生まれていた。13世紀に教会は利子と利潤を認めるようになった。そして、商人たちは遠隔交易を開始し、親方に雇われて働く人も増えていく。
14世紀には「時は金なり」の金言が定着し、富の蓄積も公認されるようになる。節約が美徳となり、資本の「蒐集」もはじまる。機械が考案されるのもこのころだ。
西ヨーロッパはすでに11世紀から貨幣の時代にはいっていた。13世紀には手形や小切手もあらわれ、資本が誕生する。16世紀末には近代国家が登場し、国境を越える貨幣を管理するようになった。
貨幣経済への急速な移行は、東方貿易とスペインのアメリカ侵略に結びついていた。貨幣の時代とともに都市化が進行する。都市市民はおカネがあれば、市場を通じて必要なものは何でも手に入るようになった。都市が帝国から独立していく。
1534年、コペルニクスが科学の時代を開き、近代がはじまる。時間が神のものから人間のものになった。そして、貨幣が世俗の神となる。
都市が資本を集め、その富で文明を築くようになる。ヨーロッパ文明はグローバル化し、資本帝国をめざすようになる。それはかつてのローマ帝国の夢の再現であると同時に、資本に裏づけられた新しい都市文明でもあった。
消費と交易が盛んになればなるほど、貨幣がますます必要になる。新しい金貨や銀貨が発行された。自由都市では封建貴族に代わって商人が行政を握るようになり、「商人の、商人による、商人のための統治」がおこなわれた。
資本主義の原型はすでに13世紀に誕生していた。16世紀になって、資本主義が近代を呼びこんだ。資本主義のほうが近代より歴史が長い、と著者はいう。
資本主義にはもともと暴力性が内在し、わずかのすきも見逃さず、暴走も辞さない。貨幣経済は中世の伝統的精神性と融合することはなかった。そのため、中世に引導を渡し、近代を導き入れる。資本は貧者を生みだしながら膨張していく。
近代は機械だ、と著者はいう。市場も国家も機械である。人はメカニズムのもとで動く。技術と経済が合体し、近代システムが確立する。技術進歩が崇拝され、機械教のもと経済成長こそが神となる。
そうしたなかで、資本は世界市場の創造に向けて動く。そのイデオロギーがグローバリゼーションだ。
「ヒト、モノ、カネの国境を自由に越える移動」がグローバリゼーションだとすれば、それは最近になってはじまったわけではなく、13世紀から存在したといえる。しかし、20世紀末になって、新自由主義のイデオロギーが広がるにつれて、それはより活発化してきた。
グローバリゼーションに明確な定義はない。だが、そこには明確なイデオロギーがある、と著者はいう。
市場の自由化とグローバルな統合。技術進歩のもたらす結果。民主主義の拡大。すべての人の利益。そして、その過程は不可避で非可逆的だという。
こうした大宣伝によって、21世紀にはいると、ほとんどだれもが、グローバリゼーションを善いものと信じるようになった。
だが、その矢先、2008年にリーマンショックがおき、2011年にはギリシア危機が発生した。グローバリゼーションは人びとの生活水準を上昇させるどころか、サブプライム層を路頭に迷わせることになった。
グローバリゼーションの本質が露わになった。
「グローバリゼーションはその推進者、米財務省、世界銀行、IMF、そしてウォール街にとってバブルの生成と崩壊を繰り返す資本を成長させる戦略なのである」
にもかかわらず日本の政策当局者は、相変わらず米国の主導するグローバリゼーションを善だと信じていると、著者はいう。
グローバリゼーションの代表企業がGAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)だ。そして、現在グローバリゼーションを主導しているのがウォール街である。GAFAは国家より巨大な権力をもちはじめており、脱税すれすれの節税をおこなっている、その株式時価総額は日本の名目GDP530兆円を上回る。「GAFA問題とは民主主義に対する挑戦なのである」と著者はいう。つまり、資本帝国による支配だ。
バブルはグローバリゼーションによってつくられる。バブルははじけさせるためにつくられる、と著者はいう。
1970年以降、実物経済にたいし金融経済が膨張しはじめた。米国の「帝国」化を支えているのは、日本の過剰マネーである。
グローバリゼーションによって、世界のマネーは米国に集中し、そのマネーは資本の自由化によって新興国に流れている。対外債権が過剰になると、債務が返済できない国がでてくる。国内でも同じことが生じる(その一例がリーマンショックだ)。
「グローバリゼーションとは、IMFを通じて、米国のワシントン・コンセンサスが世界に伝播し、米国が帝国化していくプロセスそのものである」
米国は21世紀の帝国をめざしている。そして、現在、新たな帝国をめざす中国との戦いがはじまっている、と著者はいう。
経済面からみれば、21世紀の帝国の条件は、世界じゅうからマネーを集め、世界最大の債権国として振る舞えるようになることだ。それによって債権国は債務国を支配することができる。
1991年のソ連崩壊によって、米国は世界帝国の夢を実現しえたかのように思えた。だが、その後のイスラム世界やテロとの戦いによって、その夢はたちまちついえ、2013年にオバマ大統領は「米国は世界の警察官ではない」と宣言するにいたった。
それでも、米国は帝国であることをあきらめたわけではなかった。台頭する中国との戦いがはじまった。
米国は世界最大の債権国であることを通じて、帝国の地位を保とうとしている(日本のマネーがそれを支えている)。恐れるのは現在世界第4位の純債権国である中国が、のしあがってくることだ。
米国が日本を抜いて世界最大の債権国に返り咲いたのは2010年である。
とはいえ、債権・債務関係は複雑である。米国は世界最大の債権国であるにもかかわらず、対中国の所得収支は大幅な赤字となっている。これにたいし、中国は世界4位の債権国であるにもかかわらず、全体の所得収支は世界最大の赤字をだしている。
このことは、中国は米国には債権者だが、ヨーロッパや日本にたいしては債務者であることを意味している。このあたり、国際的な債権・債務関係は入り組んでいて、じつにややこしい。
米国は日本、ヨーロッパ、中国に支えられて金融帝国としての位置を保ち、いっぽう中国は米国、日本、ヨーロッパに支えられて貿易帝国になったといえるだろう。
このああたりの議論は複雑をきわめていて、なかなか理解できないのだが、著者がこれから30年は帝国支配をめぐって、米国と中国の対立が激化すると予想していることはまちがいない。
しかし、著者は「『中国の夢』の一つである米国を総合国力で超えるという『興国の夢』は夢のまた夢である」と断言する。
中国の対外債務の支払い利子率はいちじるしく高く、その観点からみると「グローバリゼーションの勝利者は米国であり、中国が敗者となる」。なぜなら「中国は対外取引において対外資産からは低い収益率を受け取る一方で、対外資産については高い支払い利子率を払っている」からである。
それでも米国の危機感は強い。「米国の危機感は米国がこのまま手をこまねいて中国の台頭を許すと21世紀の半ばには帝国の座を降りなければならないかもしれないという点にある」。そのため自由貿易の原則を破ってでも、対中貿易赤字の増大を抑えようとしている。
ファーウェイをめぐる米中の対立は妥協の余地がなく、いつまでもつづくだろう、と著者はみる。それはサイバー空間だけではなく、リアル空間でも同じである。
帝国はつねに「過剰のはけ口」を求める。21世紀においては、グローバリゼーションというイデオロギーと、情報・通信というテクノロジーが帝国の暴力装置をかたちづくっているという。
中国が帝国をめざしているのは、やはり「過剰のはけ口」を求めているからだ。米国のグローバリゼーションに対応するのが、中国の「一帯一路」計画だ。
米国の財政赤字は減りそうにないし、貿易・経常収支赤字も縮小に転じる気配はない。それに応じて、日本をはじめとする過剰マネーが米国に流入し、ニューヨークダウを押し上げている。過剰マネーは外国企業の買収、中南米、EU、イギリスなどへの投資に向かう。こうして過大な貿易赤字をかかえながらも、米国は全世界の債権者として引きつづき君臨する。だが、そのパワーも次第に落ちはじめている、と著者は指摘する。
話はさらにつづく。



