普通選挙法と治安維持法──美濃部達吉遠望(49) [美濃部達吉遠望]

護憲三派(憲政会、政友会、革新倶楽部)の加藤高明内閣は8年にわたる政党政治の幕を開いた。
だが、三派の結束は1年ほどしかつづかない。今後3、4年はかたく三派の協調を維持し、政界を刷新してもらいたいという美濃部達吉の希望はもろくも崩れていく。その後は政党どうしの争いと、めまぐるしい政権交替がつづいた。日本の民主主義はなぜ定着しなかったのだろうか。
護憲三派は清浦内閣打倒と政党政治実現ではまとまっていたものの、その政策にはばらつきがあった。普通選挙実現に熱心な憲政会と革新倶楽部にたいし、地主と三井財閥を支持基盤とする政友会は、どちらかといえば消極的だった。政友会が貴族院改革に力を入れていたのにたいし、憲政会はそれにさほど同調しなかった。三菱財閥の支援を受ける憲政会が推し進めようとしていたのは、むしろ綱紀粛正と行財政整理だった。
そんな呉越同舟の政権ではあったが、ともかくも総選挙で第1党を勝ちとった憲政会の加藤高明は、松方正義が亡くなって最後の元老となった西園寺公望の推挙を受けて、1924年(大正13年)6月11日に護憲三派内閣を組閣した。
加藤内閣が最初に目指したのは綱紀粛正、行財政整理と普通選挙法案成立である。
この年、51歳になった達吉は東京帝国大学の法学部長になっている。『帝国大学新聞』に加藤内閣への希望を聞かれて、こんなふうに答えている。
〈新内閣に対する希望としては、第一に望むことは悪い事をしないようにしてもらいたいということである。政府はともかくも国家の権力を握り、ことに国の財政を管理しているのであるから、悪事に対する誘惑が非常に多い。もし悪事を行わない内閣があれば、それだけですでに国民の信頼を得るに充分である。不幸にして歴代の内閣はひとつとしてこの要求を満たすものなく、われわれはいつとはなしに、政治家というものは平気で悪事を為すものであるというような感想を抱かしめらるるに至った。加藤新内閣は綱紀粛正を三大政綱のひとつとして標榜している。願わくは忠実にこの政綱を実行して多年の積弊を一掃せられたいものである。〉
達吉の期待に代表されるように、加藤内閣にたいする期待は大きかったといえるだろう。
加藤内閣は対外的には幣原外交の名で知られるように、アメリカの対日移民政策を静観し、中国の内戦には不干渉を貫き(とはいえ、軍部は独自行動をとったが)、ソ連とは国交樹立の方向を探った。
行財政整理については、とりわけ財政の立て直しが大きな課題となっていた。原内閣以来、財政は大きく膨張し、それに震災復興費が加わったため、公債依存の体質が強まっていた。
そのため、政府は緊縮財政方針を打ち出し、行政の整理に取り組んだ。陸海軍の改革や、郵便貯金を原資とする大蔵省預金部の運用明確化、農商務省の分割(農林省と商工省の分離)などに踏みこむが、新たな予算要求への圧力も大きく、思ったほどの緊縮財政は実現できなかった。
いっぽう、内閣最大の綱領だった普通選挙法案は、枢密院と貴族院からの干渉を受け、その成立に至るまで、もめにもめる。
11月には内閣で普通選挙法案の原案がまとまっていた。しかし、翌月、それが枢密院の審議にかけられると、さっそく修正が加えられることになる。25歳以上の男子に選挙権・被選挙権を与えるとしていた政府原案は、被選挙権に関しては30歳以上の男子とすると修正された。
また選挙権の欠格者の範囲が拡大された。「公私の救恤(きゅうじゅつ[助け、めぐみ])を受くる者」と「一定の住居を有せざる者」には選挙権を与えない。学生には選挙権を与えないという姿勢が露わだった。
さらに「教育の普及と思想の善導、国内行政の取締を充分にし、普選実施後の対策に遺憾ならしむこと」という付帯決議もつけられた。
1925年(大正14年)2月20日に修正可決された普通選挙法案は、翌日衆議院に上程され、野党の政友本党の反対を振りきって、3月2日に可決された。しかし、貴族院では反対が強く、欠格事項を拡大するさまざまな文言が加えられた末、妥協がはかられ、会期を延長した3月29日にようやく普通選挙法が成立した。
原内閣のときに実施された小選挙区制はこのとき中選挙区制にあらためられている。より公正な選挙運動への歩みはみられたものの、官憲による選挙干渉の可能性はつきまとっていた。だが、いずれにせよ、この普選法によって、有権者が330万人から1250万人に拡大するのはたしかだった。
そのとき、普通選挙の承認にあたって、枢密院がおこなった付帯決議がきいてくる。普通選挙法成立の10日前に、さほど大きな論議もなく、一つの法律が国会で成立した。治安維持法である。
治安維持法は普通選挙法に対応するためだけに制定されたわけではなかった。この年1月、日ソ基本条約が調印され、日本とソ連との国交が樹立されていた。その交渉過程において、加藤首相はソ連側に日本での宣伝活動をおこなわないことを求めたが、ソ連側は拒否した。そのために、日本としては国内に共産主義が広がらないよう法的措置をとる必要があったのだ。
いずれにせよ、加藤内閣成立以前から司法省や内務省で検討されていた治安維持法が普通選挙法と抱き合わせるかたちで、導入されたのは事実である。その第1条は「国体を変革し、または私有財産制度を否認することを目的として結社を組織し、または情を知りてこれに加入したる者」に10年以下の懲役または禁固を課すとなっていた。あきらかに共産党や無政府党の結成とそれへの参加を禁止したものである。
政府は上程にあたって、この法律は自由主義や穏健な社会運動を抑圧するものではないと説明し、難なく衆貴両院で法案を成立させた。だが、のちに治安維持法は1928年(昭和3年)、1941年(昭和16年)と二度改正され、死刑も加えられて厳罰化されたばかりか、言論、思想信条の取り締まりにまで、適用範囲が広げられていくことになる。
護憲三派内閣のもうひとつの課題である貴族院改革は、政友会の急進案がしりぞけられ、憲政会の意向をくむ穏健なものにとどまった。有爵議員年齢の引き上げ、有爵互選議員(伯爵、子爵、男爵)定数の削減、多額納税議員有権者の拡大、帝国学士院互選議員の新設などが決められた。ちなみに、達吉はこれらとは別枠の勅選議員として、1932年(昭和7年)に貴族院議員に選ばれることになる。
しかし、護憲三派内閣が機能したのは、このあたりまでだった。普通選挙法が成立したあと、4月3日に政友会総裁の高橋是清は総裁を辞任すると加藤高明首相に伝え、農商務省が農務省と商務省に分割されたために兼任していた農相と商務相もやめたいと表明した。
満70歳になっていた高橋はそろそろ政界を引退する潮時だと考えていた。これまで自分を支えていた司法相の横田千之助が2月に54歳で急死したことも、党の運営に自信をなくす要因になっていた。
4月10日、田中義一が新たに政友会総裁の座に就いた。原内閣の陸相を務めた田中は、陸軍を退役して、政界への転身をはかっていた。
その田中は、加藤首相からの入閣要請をことわる。みずからが首相になる野望を秘めていたからである。
5月14日には革新倶楽部と中正倶楽部が政友会と合同し、これによって政友会は議席を139に増やし、政友本党を抜いて、憲政会に次ぐ衆議院第2党となった。革新倶楽部代表の犬養毅は、いつのまにか合同工作が進んでいて、足元をすくわれるかたちとなった。犬養は、27日に政界引退を表明、逓相を辞任した(その後、政友会に復帰する)。
加藤内閣は激震に見舞われた。7月にはいり、浜口蔵相が税制整理案を閣議に提出すると、政友会出身の閣僚はこれに反対し、内閣不統一により、加藤内閣は総辞職に追いこまれた。
政友会総裁の田中義一は、いよいよチャンスがめぐってきたとばかりに、政友本党との連携をはかり、大命が降下するのを待った。しかし、元老の西園寺公望が田中の画策を嫌い、加藤高明をふたたび首相に推薦した。
こうして憲政会単独の第2次加藤内閣が発足する。憲政会の議席は衆議院の3分の1ほどである。憲政会、政友会、政友本党の三派が鼎立(ていりつ)し、政局は不安定になった。かといって、加藤は総選挙に踏み切れない。憲政会は政友本党と提携し、衆議院の過半数を確保し、政局の打開をはかろうとした。
1926年(大正15年)1月22日、第51議会が再開されて2日目、加藤首相は貴族院の議場で倒れ、6日後の28日に亡くなった。死因は心臓麻痺、満66歳になったばかりだった。
内相の若槻礼次郎が首相代理となり、そのまま内閣を引き継いで、1月30日に若槻内閣(第1次)が組閣された。
美濃部達吉は護憲三派以来の政党政治のあやうさをじっと見つめていた。憲法・行政法の専門家としては、政治に無関心ではいられない。日本の政党政治はなぜ脆弱なのか、日本に政党政治が定着するには、どのような制度改革が必要なのか。そのことを考えつづけている。
清浦内閣の不人気──美濃部達吉遠望(48) [美濃部達吉遠望]



山本権兵衛内閣で震災からの復興を中心になって担ったのは、内務大臣の後藤新平だった。
後藤は震災直後に帝都復興審議会を立ち上げ、政界、官界、財界を巻きこみながら、壮大な復興計画を打ちだした。9月末には復興計画の実施にあたる帝都復興院もつくられた。
後藤の計画は焼失地区にかぎらず、東京市全域を対象としたものだった。池袋、新宿、渋谷、目黒のターミナルと都心部を結ぶ幹線道路が計画され、その下に地下鉄を通すことも構想されていた。横浜港を再建するだけでなく、隅田川河口に内港を整備し、そのふたつのあいだに運河を開き、沿岸工業地域を整備することも計画された。
だが、そのプランは現実的制約を前にして、次第にあやふやで中途半端なものになっていく。
事態をややこしくしたのは、後藤による政界再編工作が並行して進んだためである。党内が分裂しているとはいえ、衆議院の議席は政友会が多数派を握っている。後藤は犬養らとともに新党を結成し、あわよくば次の選挙で政友会の追い落としをはかろうとしていた。
後藤の立てた復興計画予算は35億円とも41億円ともいわれていた。現在の感覚でいうと10兆円から12兆円といったあたりだろうか。2年前に東京市長を務めた後藤は、欧米最新の都市計画を採用すると大風呂敷を広げた。そのためには地主の土地所有権にたいしても断固たる措置をとるのをためらわないと広言していた。
だが、後藤の復興計画には、復興審議会のなかから強い反対意見がでる。とりわけ、後藤の親友、伊東巳代治(みよじ)が反対の急先鋒に立った。伊東は理想に走るより民心の安定をはかるべきだと主張し、負担の大きい予算の削減と地主への手厚い補償を求めた。審議会委員になっていた政友会総裁の高橋是清もこれに同調し、後藤の大風呂敷はとたんにしぼんでいく。復興計画は焼け跡の市街地復興に限定されていくことになる。
さらに12月11日に開かれた第47臨時国会でも、第1党の政友会が復興院予算の大幅削減と復興院の廃止を求めた。これにより復興計画予算は最終的に政府の要求した5億7000万円からさらに削られてしまう。しかし、山本内閣は衆議院を解散することもできず、政友会の主張をのむしかなかった。後藤の権威は失墜し、内閣でも信用を失い、帝都復興院も廃止されることが決まった。
そのとき世情を騒然とさせる事件が勃発する。虎ノ門事件である。
12月27日午前11時前、第48通常国会の開院式に出席するため、摂政の裕仁皇太子(のちの昭和天皇)が御召自動車で虎ノ門外にさしかかったところ、群衆のなかからひとりの青年がおどりだし、ステッキ仕込みの散弾銃を摂政めがけて発砲した。弾丸は自動車の窓ガラスを貫き、同乗していた東宮侍従長の入江為守が軽傷を負ったものの、摂政は無事だった。自動車はスピードを上げ、貴族院玄関前にすべり込み、摂政はそのまま貴族院の開院式に臨んだ。
犯人の難波(なんば)大助は「革命万歳」と叫んで、走りだしたところ、警察官によって取り押さえられた。難波は25歳で、その父は山口8区選出で庚申倶楽部(こうしんくらぶ)所属の衆議院議員だった。
難波大助は翌年11月13日に大審院で死刑を宣告され、11月15日に死刑が執行されることになる。
この事件により、山本権兵衛はただちに辞表を提出した。摂政や元老から慰留されたものの、次の内閣成立を待って、1924年(大正13年)1月7日に山本内閣は総辞職した。
その過程で誕生したのが清浦奎吾(きようら・けいご)内閣である。当時、清浦は死亡した山県有朋の後を受けて枢密院議長を務めており、明治の遺臣というべき二人の元老、西園寺公望と松方正義の推挙を受けて、首相に就任した。
このとき清浦は数えの75歳、閣僚の人選を貴族院の会派、研究会にゆだね、貴族院内閣をつくった。とうぜん国民からは不人気で、政党からは猛反発をくらい、さっそく内閣打倒をめざす護憲運動(第二次)が巻き起こる。これにたいし、清浦内閣は1月末にいきなり議会を解散、5月10日に総選挙がおこなわれることになった。
清浦内閣をどうみるかについて、美濃部達吉は雑誌『改造』から執筆依頼を受け、3月1日発行の3月号に「非立憲極まる解散 政治的良心を疑う」と題する評論を発表している(のちに「清浦内閣の成立と衆議院の解散」と改題)。
冒頭、こう記している。
〈山本内閣が不慮の事変のために急に辞職せねばならぬことになってから後、今日に至るまでの政界の変動は、一般民心の激昂を招いたこと、ほとんど憲政実施以来未曽有ともいうべきほどで、しかもそれは単に政党政治家の仲間においてのみではなく、平生はほとんど政治に無関心である学者、実業家、一般知識階級の間にも、これを憤慨する声がすこぶる高い。新聞紙の論調は必ずしも常に国民の感情を正確に表現するものではないにしても、今回のごとく全国のほとんどすべての新聞紙がその論調を一にして内閣の存立を根本的に否定していることは、これまで全く例を見ないところで、それだけでもいかに現在の内閣が、国民の間に不人気であるかを推測することができる。〉
国民は清浦内閣の何に怒っていたのだろうか。
元老の推薦による首相任命という経緯はこれまでどおりの慣例であって、特に人心の激昂を招く理由はない。二大政党があって、内閣が総辞職した場合は反対党の党首に内閣組閣の命が下ることが常識となれば元老の裁定など必要としない。だが、現在の政党政治のていたらくをみれば、そうした理想にはほど遠いといってよい。
実際、衆議院第1党で、原敬の後を継いだ高橋是清の政友会は分裂しかかっていたし、第2党の加藤高明の憲政会は議席の3分の1に満たなかった。けっして良いこととは言えないが、今回も元老による首相推挙という方式はやむを得なかった。天皇の顧問としての内大臣(平田東助)が首相推挙に関与したことも、当然の職責で非難すべき理由はないと達吉はいう。
問題は清浦が政治家としてふさわしい態度を取らなかったことだ。いったんは辞退すると言いながら、数時間のうちにその決心を翻したのも問題だが、内閣の組閣にあたって、貴族院の親しい会派の幹部に内閣の人選を委ねたのも前代未聞の事態だ。「これだけでも国民の軽侮と憤懣を招くに充分である」。しかも、それによってできあがったのは純然たる貴族院内閣だった。これでは国民の共感が得られるはずがない、と達吉は明言する。
さらに、そうした不人気に輪をかけて、清浦は1月31日に衆議院解散の暴挙に出た。今回の解散はその理由においても、その時期においても、はなはだ不当なものである。倒閣の動きが始まり、衆議院で内閣不信任案が出されそうだということをかぎつけ、議場の秩序が乱れたという理由で政府は解散に踏み切った。「ここに至っては、ただ逆上の沙汰と評するのほかはない」
清浦内閣はしきりと国民の思想の善導を唱えていた。思想の善導が政府の果たすべき職分であるかどうかはわからない。しかし、「今の内閣ははたして自ら思想を悪化する原因を作りつつあるものであるという非難を免れうるであろうか」。痛烈な皮肉とともに、『改造』の一文は締めくくられている。
1月末に議会が解散される前に、政友会はまっぷたつに分裂した。政友会は政府に反対する高橋是清の総裁派と、政府を支持する反総裁派に分かれて争っていた。しかし、1月15日に高橋が党全体として反政府の姿勢を固めることを鮮明にすると、それに反発する反総裁派の山本達雄、中橋徳五郎、元田肇、床次竹二郎らが新党、政友本党を結成した。
政友本党は148人の大所帯に膨れ上がり、議会第1党として清浦内閣を支えることになった。清浦が解散に踏み切ったのも、政友会の分裂に乗じて、政局を転換できると考えたためでもある。
しかし、考えが甘かった。政府の暴挙にたいし、政友会(総裁高橋是清)は憲政会(総裁加藤高明)、革新倶楽部(代表犬養毅)と結束して、護憲三派をつくり、反政府の護憲運動に立ち上がった。
5月30日の総選挙の結果は、憲政会151、政友本党116、政友会100、革新倶楽部30、中正倶楽部42などとなり、政府の思惑ははずれた。とりわけ憲政会が躍進、護憲三派が大勝して、議会の絶対多数を握った。
これにより、清浦内閣は退陣し、憲政会総裁の加藤高明に組閣が命じられることになる。6月11日、護憲三派の内閣が発足する。高橋是清が農商務相、犬養毅が逓信相、憲政会からは若槻礼次郎が内相、浜口雄幸が蔵相に就任、駐米大使の幣原喜重郎が外相に就任した。
このとき、達吉は7月1日発行の『改造』で、加藤内閣への期待を述べている。
〈清浦内閣がやめて加藤内閣がこれに代ったのは、長い間の梅雨がようよう晴れて、かすかながらも日光を望むを得たのと、同じような快い感じがする。数年前に寺内内閣が倒れて、原内閣が代ったときと同じような感じだ。ことに今度の内閣において高橋政友会総裁および犬養氏が相携えて、おのれを空しうして無条件に入閣したことは、国民に大なる快感を与えた。ただそれだけでも、前の内閣が(中略)牽強付会の強弁をもって無理に自己の非を掩(おお)わんとした態度と比較して、雲泥の相違と言わねばならぬ。閣員の顔ぶれから言っても前内閣とは比較にならぬほどに国民の信頼を継ぐに足りる。願わくは少なくとも今後三四年の間は堅く三派の協調を維持して、大いに政界の刷新を断行してもらいたい。もしこの内閣にして失敗するようなことがあれば、今後わが国の政治は当分の間は暗黒時代におちいるほかはない。〉
残念ながら不安は的中する。暗黒時代が近づいていた。軍靴の音とともに。
近代産業社会の社会構造──富永健一『近代化の理論』を読む(2) [本]

ぼく自身はばくぜんと、社会とは人間集団の共同体を指すと考えている。国家は社会を包摂する政治組織体にほかならないが、外的にみれば、それ自体、ひとつの共同体であるという面で、ひとつの社会だとみることもできる。
国家と社会は別の存在だが、社会をくるんでいるのは国家であって、社会が国家をくるんでいるわけではない。とはいえ、国家は社会によって支えられており、社会と国家の関係にはつねに緊張感がある。
国家は革命や併合(征服)、分裂によって生成・消滅することはあっても、国家そのものが消滅することはない。こうした考え方は滝村隆一に由来するものだ。
こんなことを考えはじめると、頭がこんがらがってくる。
日本では明治以前に「社会」ということばはなかった。
社会は翻訳語で、福地源一郎がsocietyを社会と訳した。それらしいものをそれまで日本人は「世の中」とか「世間」と呼んでいた。
しかし、社会という翻訳語が登場すると、社会はたちまち日本人のあいだに定着していった。
著者によると、広い意味で、社会とは自然にたいして人間のつくったものを指すとされる。しかし、それではあまりにばくぜんとしている。
そこで、もっと限定的に、社会とは多くの人間によってつくられた関係のシステムだという規定がでてくる。具体的には家族、企業、学校、村落、都市、国民社会、国家などからなるシステムである。さらに、このシステムは群衆や市場、社会階層、民族、国際社会といったサブシステムをもっているという。そして、システム全体を統合するのが国家だ。つまり、国家によってつつまれている社会を研究するのが社会学であって、国家を含むその全体を社会と呼ぶなら、そのシステムは国際関係(国際社会)によって、つねにチャレンジを受けているともいえる。
著者は「社会構造」と「社会変動」というとらえ方を示しているので、それに沿って、問題を整理してみることにしよう。
「社会変動」についてはあとで論じられる。まず「社会構造」とは何かということだ。社会構造は静態的なとらえ方で、いわば社会のいまを断面的かつ抽象的に切り取ったものだ。だが、それはけっして静態的ではありえず、社会変動の波にさらされているという構図が浮かび上がるだろう。
いずれにせよ、社会には構造があるとされている。
しかし、社会構造を定義するのはむずかしい。
著者はこんなふうに言っている。
〈社会構造とは、社会を構成している次のような構成諸要素のあいだの相対的に恒常的なむすびつきとして定義されます。それの構成諸要素としては、個人行為にちかいレベル(ミクロ・レベル)から全体社会のレベル(マクロ・レベル)までいくつかの段階が区別されることになるのですが、それらをミクロからマクロに向かって順次に、役割・制度・社会集団・地域社会・社会階層・国民社会というように配置することができるでしょう。構造分析をこれらの諸段階のどのレベルで考えるかは、社会構造の概念化におけるレベルのとり方の問題であり、構造概念自体としてはどのレベルで考えるかはまったく任意です。〉
残念ながら、ぼくなどには何が書いてあるかさっぱりわからない。
要するに、社会というのは複雑なつくりから成り立っているらしいということがわかる。
その基礎になるのは家族(ミクロ・レベル)だが、そこからはじまって組織(企業や団体)、地域社会、国民社会(マクロ・レベル)にいたる結びつきがあって、社会階層という区分けも厳然とある、その全体の関係を社会構造と呼ぶ、とでも勝手に解釈しておくことにする。
社会構造を考えるには、どのレベルをとってもいい。どのレベルをとっても社会構造の全体が見えてくる。それは一種の透視画法のようなものだ。
また、社会には、決められた制度があり、そのなかで人は割り振られた役割をはたすものと考えられている。
だが、そういっただけではあまりに抽象的だ。
そこで著者は、現代のモデルと考えられる近代産業社会を取りあげて、その社会構造を分析しようとしている。
近代産業社会の特性は、機能分化、すなわち分業だ。近代産業社会は「それ以前の社会構造に比して、格段にこまかく分離した多数の構造的構成要素」から成り立っている。
とりわけ注目されるのが、家族と組織の分離だ。
封建時代においては、家族が共同生活の単位であると同時に経営の単位でもあった。それは農民でも商人でも同じで、そのとき「家」は家父長制の形態をとっていた。
近代産業社会においては、家族は経営的機能を喪失して、消費生活の単位に純化し、経営的機能は組織によって担われることになる。こうした分離は一挙に生じたわけではなく、何十年、何百年かかって起こった。これによって、家父長制家族は解体し、核家族が誕生した。
すると基礎集団である核家族と機能集団である組織(企業など)とのあいだに関係が生じることになる。そのとき家族の成員は組織の成員でもあるというダブル・メンバーシップを得ており、社会的にみればエンプロイー(被雇用者)社会が生まれたことになる、と著者は書いている。
核家族と組織は持続的な相互依存関係にあり、そこには相互交換が発生する。
具体的に、それは
労働市場
消費財市場
金融市場
社会的交換
ということになる。
労働市場において、企業は家族から労働サービスを得、家族は企業から賃金や給与を得る。
消費財市場において、企業は家族に生産物を売り、家族は企業から消費財を買う。
金融市場において、企業は家族の貯蓄から資本を借り、家族は企業から利子や配当を得る。
社会的交換において、家族は企業から与えられた地位や権力、名誉を得る。
ただし、ここで気をつけなければならないのは、家族はひとつではなく、企業もひとつではないということだ。実際には無数の家族と無数の企業があって、その関係は複雑にからみあっている。その複雑にからみあった家族と組織の関係からなる地理的なかたまりを地域社会あるいは国民社会、とらえ方によっては都市と村落と呼ぶことができる。
こうした地域社会あるいは国民社会は、地域行政組織(自治体)や国家によって統合され、税と引き換えにさまざまな行政サービスを受ける関係にある。
近代産業社会のこうした社会構造を、著者は個別の領域にわたって、さらに詳しく論じていくことになる。(つづく)
富永健一『近代化の理論』 を読む(1) [本]

本棚を整理していたらでてきた。1996年に出版された本だが、あのころ何げなく買って、例によって例のごとくの悪い癖で、そのまま読まずじまいになっていたらしい。
ぼくは研究者ではなく、学問といったものは苦手で、物語のほうが好きなので、どちらかというと理論は敬遠したい気分がある。経済学や社会学をまじめに勉強したことはない。
それでも近代化という概念については、なんとなく興味がある。
いまは近代という時代にはちがいない。その近代に半ばどっぷりつかりながらも、時折それがいやになること、別の可能性をみてみたいと願うこともしばしばだ。だから近代化にはどこか懐疑的である。年をとると、ますますそうした傾向が強まっている。
著者の富永健一(1931〜2019)は社会学者で、東京大学文学部の助教授、教授を長く務めた。主な著書に『社会変動の理論』、『社会学原理』、『日本産業社会の転機』、『日本の近代化と社会変動』、『思想としての社会学』などがある。明治の三大記者のひとりとされる東京朝日新聞主筆の池辺三山は、母方の祖父にあたるという(あとふたりは陸羯南と徳富蘇峰)。
本書はもともと放送大学の講義用テキストとして書かれたもの、「ですます」調で読みやすそうだ。社会学の知識のないぼくのような素人でもわかるかもしれないと考えて、ぱらぱらとページをめくりはじめた。いっぺんには読めないので、少しずつ読んでいきたい。
著者によれば、20世紀の前半と後半は対照的な時代だが、両者を貫通するものとして「近代化」と「産業化」というテーマがあった。それは西洋にはじまり、東洋に伝播し、いまや東洋もその担い手になっているというのが、はじめの記述だ。
産業化が出現したのは18世紀後半から19世紀前半にかけての産業革命期で、このころから生産の動力源として、「生物エネルギー(筋力や畜力)に代えて無生物エネルギー(蒸気力から電力から原子力にいたるまで)」が用いられるようになった。同時に機械化も進んでいく。
産業化にともない、経済は自給自足経済から市場的交換経済へと移行していく。さらに第二次産業から第三次産業へと産業構造が発展していくにつれ、コンピューターを軸とする「ポスト工業化」の時代がはじまる。
ポスト工業社会とは、より高度な産業化が実現した社会だ、と著者はいう。けっしてポスト産業社会ではない。農業や工業の生産性が飛躍的に高まり、より少ない人数で必要量を満たせるようになるため、第三次産業従事者の比率が増えていった。人間の頭脳的・肉体的労働は、機械(動力機械および情報処理機械・自動制御機械)に置きかえられるようになる。
「近代化」はどう定義できるのか。近代化は経済(技術)、政治、社会、文化の4つの側面で並行して進む現象としてとらえることができるという。
経済面では人力・畜力中心から動力革命・情報革命にともなう機械化へ、自給自足社会から市場的交換経済へ、そして第一次産業中心から第二次産業・第三次産業中心へ。
政治面では近代的法制度の確立、封建制から近代国民国家への移行、専制君主制から民主主義へ。
社会面では家父長制から核家族へ、未分化な集団から組織へ、村落共同体から近代都市へ、さらには身分制から自由平等の時代へ。
文化面では宗教的・形而上学的束縛から実証的知識へ、非合理主義から合理主義へ。
これらの4つの側面は、それぞれ密接にからみあいながら進行していった、と著者はいう。
近代化され産業化した社会が近代産業社会だ。そして情報化社会は近代産業社会の高度な段階ととらえることができる。
近代産業社会はひとつのモデル(理念型)であって、どの国においてもそれがそっくり実現されているわけではない。東洋では19世紀後半の日本を皮切りに20世紀後半の韓国、台湾、香港、シンガポールにつづき、中国が近代産業社会をめざすようになった。
東洋における近代化と産業化の先頭を切ったのは日本だが、それは西洋を追いかけるかたちをとった。大久保利通は殖産興業政策による「上からの産業化」を推進し、日本は明治末に世界の先進国入りをはたした。
いっぽう中国は半植民地状態となり、ようやく1912年の辛亥革命によって中華民国が成立するものの、内戦がつづいた。1949年に毛沢東による共産党政権が発足する。しかし、大躍進政策が失敗に帰したあと、文化大革命の混乱がつづき、産業化が軌道に乗るのは、鄧小平が対外経済開放政策を打ち出してからだ。
近代化と産業化が中世から自生した西洋とちがい、東洋がいわば普遍的課題である近代化と産業化を受け入れるには意識的な努力を必要とした。
しかも、ヨーロッパの近代化は植民地化をともない、それによる西洋文明の伝播というかたちをとったから、植民地化の危機にさらされた東洋にとっては、西洋文明を受け入れるのは苦渋の選択だった。
日本では倒幕による王政復古というかたちをとったうえで、はじめて近代化と産業化を導入することができた。それはけっしてそのままの西洋化ではなかった、と著者はいう。
〈文化伝播に模倣の要素が含まれていることはたしかですが、しかし文化伝播というのはけっして単なる模倣、つまり「オリジナル」の「コピー」をつくることを意味するものではありません。とりわけ大切なのは(1)文化伝播は選択的な受容である、(2)文化伝播は受容した諸文化項目をもとのものとはちがう文脈の中に移植するのにともなう適応問題の解決を必要とする、という二点ではないでしょうか。これらのことはそれ自体、創造的な能力が要求される課題です。そのような創造的な能力を発揮することができるならば、文化伝播を受容しても、文化のアイデンティティをたもつことは可能なのではないでしょうか。〉
日本は文化的アイデンティティを保ちながら、みずからもつ創造的な能力にもとづいて、近代化と産業化を受け入れることができた、と著者は指摘しているようにみえる。
しかし、そのかん、日本は西洋排斥と西洋崇拝のあいだを揺れ動いた。西洋主義の波とナショナリズムの波が常に入れ替わるのが日本の特徴だ、と著者は書いている。中国が台頭するなかで、その様子はいまもっと複雑になっているといえるかもしれない。(つづく)
関東大震災──美濃部達吉遠望(47) [美濃部達吉遠望]

1923年(大正12年)9月1日正午2分前に関東地方南部を激しい地震が襲った。震源は相模湾北西部、マグニチュードは7.9だった。
ちょうど昼時にあたったため、炊事の火が燃え移ったりして、多くの火災が発生した。東京市は浅草区、本所区、深川区、京橋区、要するに皇居(宮城)の東側がほぼ全焼した。市内の43.5%が焼けたというから被害は深刻である。横浜も市内中心部がほぼ全焼した。
関東一円の死者・行方不明者は約10万5000人で、被災者は340万人にのぼった。住宅は全壊が約10万9000戸、半壊が約10万2000戸、消失が約21万1000戸という数字が残されている。
小石川区竹早町(現文京区小石川)にあった美濃部達吉の自宅は無事だったが、東京帝国大学では赤門近くの医学部の教室から火の手があがり、図書館や法学部の教室、講堂が焼け落ちた。なかでも深刻だったのは図書館の全焼である。旧幕時代の図書、海外からの寄贈本を含め、75万冊の書物が灰燼に帰した。
地震発生の1週間前に加藤友三郎首相が病死したため、後任に推された薩摩閥の山本権兵衛は、地震直後まだ組閣を終えていなかった。臨時首相を務めていたのは外相の内田康哉(こうさい)である。
市内には流言蜚語(ひご)が飛び交っていた。富士山が大爆発したとか、大津波がくるといったうわさも流れたが、なかでも深刻だったのは「不逞鮮人(ふていせんじん)来襲」という流言だった。日本に不満をもつ朝鮮人がやってきて、井戸に毒を投げ入れたり、放火や強盗をしたりするという、でたらめな情報が広がった。民衆のあいだで自警団が結成され、警察と一体となった朝鮮人の取り締まりがはじまろうとしていた。数知れぬ多くの朝鮮人が虐殺された。政府の記録では、死者の数は600人ほどだが、吉野作造の調査によると虐殺された者の数は2600人あまりにのぼる。
9月2日、内田臨時首相のもと、枢密院の審議をへることなく、政府の責任で東京市と府下5郡に戒厳令が布かれた。その夕刻、10年ぶりの第2次山本権兵衛内閣が発足する。内相には後藤新平、逓信相に犬養毅が任命された。
このときの戒厳令について、達吉は詳細な記録を残している。
最初に達吉が、大震災にあたって戒厳令が大きな効果を果たしたと述べている点に注目すべきだろう。長くなるが、引用しておく。
〈震災に際する応急の手段として、非常徴発令、流言浮説取締令、支払延期令、暴利取締令、輸入税免除低減令、府県議員任期延長令、租税減免猶予令、行政処分による権利利益の存続期間延長令、臨時物資供給令、臨時物資供給特別会計令など幾多の重要な緊急勅令が発せられたが、中にも一般人心の鎮静に最も偉大な効果を収め、歴史上未曾有な大変災に際して、人心恟々(きょうきょう)、所によってはほとんど無警察無秩序の状態にも陥ろうとする虞(おそ)れのあった場合に、何よりも大きな安心を与うることのできたのは、言うまでもなく、戒厳令の施行であった。軍隊のありがたみの一般の民心に痛感せられたのは、おそらくこの時ほど著しかったことはなかろう。〉
戒厳令にもとづく軍による秩序維持は大きな効果を発揮した。一般の民心にとって、このときほど「軍隊のありがたみ」が感じられたことはないと記している。
問題がなかったわけではない。
〈ただ戒厳の任にあたった将校軍人の中に思いがけない犯罪事件が起って、これがために突如として戒厳司令官の更迭をまで見るに至ったのは、千秋の遺憾であるが、この変事および国際上に起った多少の恨事を除いては、戒厳令の施行によりよく治安維持、民心鎮静の目的を達し得たことは何人も認めるところで、今回のごときは戒厳令の最も有効に適用せられた実例となすべきであろう。〉
奥歯にもののはさまったような言い方をしているが、ここでいう「思いがけない犯罪事件」とは、著名なアナキスト大杉栄の殺害事件を指している。これについては、あとで触れることにしょう。またそれにともない「国際上に起った多少の恨事」が発生した。
達吉は大杉栄殺害事件に具体的には触れていない。朝鮮人虐殺事件には沈黙している。
戒厳令の緊急勅令は9月2日に摂政名で発布された。達吉によれば、枢密院の諮詢を経ていないが、交通機関も途絶するなかではやむを得ない措置だった。官報の発行もできず、謄写版で印刷されたものが官庁や警察署に配られた。
震災戒厳令公布直後の責を担ったのは東京衛戍(えいじゅ)司令官で、その適用範囲は東京市をはじめとする府内5郡(荏原[えばら]、豊多摩、北豊島、南足立、南葛飾)だった。
このときの東京衛戍司令官は近衛師団長の森山守成(もりしげ)である。
同日夕刻、山本内閣が組織される。翌3日には関東戒厳司令部がつくられ、司令官に福田雅太郎大将が任命された。
戒厳令の施行区域は神奈川県にも拡大された。4日には埼玉県、千葉県にも戒厳令が布かれた。こうして、東京府、神奈川県、埼玉県、千葉県に戒厳令が施行されることになった。
今回の戒厳令は軍事行動の必要にもとづくものではなく、「もっぱら治安維持の必要のために警察だけでは力が足りないために軍隊の力を借りたのであって、行政的戒厳である」と達吉はいう。行政的戒厳であるために、緊急勅令のかたちがとられた。
戒厳令のもとでは、戒厳司令官は行政機関にだけではなく、直接人民にたいしても命令する権利をもっていた。
関東戒厳司令部は9月14日におよそ次のように発表した。
福田雅太郎関東戒厳司令官は、名古屋以東の師団から工兵隊の出動を命じるとともに、歩兵21連隊、騎兵6連隊、工兵17大隊、鉄道、電信各2連隊、航空機、衛生機関、および救護班など3万5000人を動員し、各方面に配置した。これらの部隊は警察官、憲兵と協力して、治安維持にあたるとともに、鉄道、電線、道路、橋梁などの修理を行い、役所による食料分配や避難民の救護にも協力した。それにより当初の流言蜚語も収まり、平穏な状態が確保された。
これにたいし、達吉はこう記している。
〈右(関東戒厳司令部)の発表に見えている通り、戒厳軍の主として活動したのは警備、救護、営造物の修理などであって、人民の自由を拘束する権力は法律上には与えられていても、その権力を実際に活用することは、むしろ稀であった。戒厳司令官から一般人民に対して命令を発したのも、自警団の行動を戒めた9月4日の命令だけであったと思う。これは軍事戒厳ではなく行政戒厳であることから生じた当然の結果であるけれども、戒厳令の施行に対し、一般人民が等しく満足感謝の意を表しているのは、主としてこれがためである。〉
不逞鮮人来襲の流言を信じて、朝鮮人を迫害、殺害した自警団は、戒厳軍により9月4日に解散を命じられたが、朝鮮人の殺傷は7日ごろまでつづいた。
その後は警察や軍によって、朝鮮人は保護の名目で拘束された。その数は10月末までに全国30府県で2万3715人にのぼったとされる。
亀戸事件が発生したのは9月3日から4日にかけてである。亀戸警察署では数十人の朝鮮人が殺害されたが、同時に川合義虎、平澤計七ら10人の社会主義者や組合活動家が、習志野騎兵第13連隊の兵士によって刺殺された。
社会主義者にたいする検束が相次いだ。朴烈と金子文子は9月3日に逮捕された。近藤憲二、福田狂二、浅沼稲次郎、稲村順三、麻生久なども9月5日以降、つぎつぎと検束されている。
そんななか9月16日、大杉栄は妻の伊藤野枝、6歳の甥、橘宗一とともに憲兵隊によって連行され、麹町の憲兵司令部で殺害された。宗一は米国籍だったため、アメリカ大使館からは日本政府への抗議と事態究明要求が突きつけられ、国際問題化した。
甘粕(正彦)憲兵大尉、大杉栄ほか2名を殺害との記事が『時事新報』や『読売新聞』などで大きく報じられたのは9月20日のことである。
この事件により関東戒厳司令官の福田雅太郎は更迭され、山梨半造大将に代わった。
戒厳令は11月15日までつづく。
憲法撮要──美濃部達吉遠望(46) [美濃部達吉遠望]

1923年(大正12年)4月末、美濃部達吉は有斐閣から『憲法撮要』を刊行した。そのいきさつを序文でこう記している。
〈本書は、著者が今年四月から再び東京帝国大学及び東京商科大学において憲法の講座を担任することとなったので、その教科書に充(あ)てるために編述したるものである。著者は一昨年から比較的浩瀚(こうかん)な「日本憲法」の著述に着手しており、第一巻だけは既に公にし、第二巻以下は目下起稿中であって、教科書を書くのはその研究が全部まとまってから後にするのが至当であるが、それはまだ数年の後を待たねばならず、一方には大学での講義の時間がはなはだ乏しいため、教科書の助けをからねば、その講義は極めて簡単なものに終らねばならぬ憾(うら)みがあるので、今年一月欧州から帰朝して後、急にこの書を著すことに決心し、二月中旬から起稿に着手し、昼夜兼行、三月末日をもってようやく全部を書き上げることができたのである。もとより充分の推敲の暇もなく、急速力をもって書き上げたのであるから、往々詳略宜(よろ)しきを得ないところがあるけれども、それは他日版を新たにする機会に譲るのほかはない。〉
欧州出張から帰国早々、4月から東京帝国大学で憲法学講座が再開され、あわせて東京商科大学(現一橋大学)でも憲法学の講義をすることになったので、にわかに憲法解説の教科書をつくらなければならなくなった。2年ほど前から『日本憲法』という大著に取り組んでいるのだが、ひとまずそれをさておいて教科書執筆に専念した。わずかひと月半ほどで全速力で執筆したから、よく練りあげたものとはいえないが、改版のときに訂正を期したいというのである。
ちなみに『日本憲法』は第1巻が出版されただけで、完成することはなかった。それにしても『憲法撮要』は600ページ近くあるから、その原稿をひと月半ほどで仕上げたとはにわかに信じがたい。欧州から帰国中の船のなかでも執筆が進んでいたのではないだろうか。
1912年(明治45年)に出版された『憲法講話』につづき、1923年(大正12年)の『憲法撮要』は美濃部憲法学の代表作となり、1932年(昭和7年)まで5版の改訂を重ねている。そのかん改正箇所はごくわずかだった。
家永三郎はこの『憲法撮要』と、1927年(昭和2年)の『逐条憲法精義』、1934年(昭和9年)の『日本憲法の基本主義』の3冊を美濃部憲法学の集大成としている。そして、1935年の天皇機関説事件のあと、まさしくこの3冊が発禁処分を受ける。1923年から1935年にかけ、時代は急転換したのである。
明治末の『憲法講話』と大正末の『憲法撮要』とのあいだに大きな変化があったとすれば、日本における民主主義の進展がからんでいる。
『憲法講話』と『憲法撮要』とのちがいは、その目次からもうかがうことができる。「講話」では国家と政体につづいて、まず天皇が論じられていたが、「撮要」では国家と政体の説明につづいて、憲法の歴史的由来が説明され、日本国民、国民の権利義務の項目が天皇より先に論じられている。帝国議会と立法権、予算についても、多くのページが割かれている。また「講話」では論じられなかった軍の問題が「撮要」では大胆に取りあげられている。
大日本帝国憲法自体は一度も改正されることはなかったが、達吉のなかでは、その解釈は議会を中心とする民主主義的な方向に深化していたといえるだろう。おそらく1922年(大正11年)の欧州体験が、達吉に国家制度のあり方を再考する機会と刺激をもたらしていたのである。
『憲法撮要』において、達吉は日本の政体を中央集権的な立憲君主制だとしなたがら、しかも君主主義の色彩が強いことが特徴だと論じている。問題は天皇自体の権力ではない。天皇の名の下で政治をおこなう機関の権力が強すぎることが問題だった。
帝国憲法では権力分立を建前とするものの、政府と議会は完全に分離せず、立法にあたっても法律の裁可権を君主が留保している。議院内閣制はとられず、国務大臣はもっぱら天皇の輔弼(ほひつ)にあたることを任としている。軍の統帥権が天皇のもとに独立していることも特徴的だ、と達吉はいう。
憲法では自由平等主義が認められているものの、それはけっして保障されているとはいえず、国民は法律の範囲内において自由を享受しうるとされているにすぎない。政治は中央集権的な色彩が強く、地方自治制度は地方的利益に関する行政においてしか認められていない。
こうした記述は、まるで明治憲法体制の問題性を指摘したかのように思えてくる。大上段に振りかぶったわけではないが、『憲法撮要』で達吉が明治憲法体制の内的刷新を図ろうとしているのを読み取ることは可能だった。
達吉が最初に述べようとするのは、国家における国民の地位についてである。
兵役や納税の義務などからみても、国民が国家の統治権に服従すべきことはいうまでもない。だが、国民は服従するだけではない。一定の範囲において、国家の支配に服従しなくてもよい自由権を有している。さらに国民は国家にたいする一定の受益権、すなわち国家から利益を得る権利、また、国家を構成する一員として、国家の統治権に参与する権利をも有しているのだ。民事訴訟権、行政訴訟権や請願権、参政権などがそれにあたる。
「国民は国家に対し義務の主体たると共に、また権利主体たる地位を有す」ることを達吉は強調する。
いっぽう国家は国民に対し無制限の命令強制権をもっているわけではない。それは制限されなければならない。国家の権利、逆にいえば国民の義務は法律によって定められることを原則とする。
「国民が国家の権力によりても侵害せられざる自由権を有せざるべからずとする思想は近代の立憲制度の最も重要なる根本思想」だと達吉はいう。
国民は元来、国家によって侵害されることのない自由権を有している。その自由権には「居住移転の自由」、「逮捕、監禁、審問、処罰を受けざる自由」、「裁判官の裁判によるにあらざれば刑罰を受けざる自由」、「住所を侵されざる自由」、「信書の秘密を侵されざる自由」、「財産権を侵されざる自由」、「信教の自由」、「言論、出版、集会、結社の自由」が含まれている。国家は原則として、こうした国民の自由権を保障しなければならない、と達吉は断言する。
国民の権利義務につづいて論じられるのが天皇についてである。
帝国憲法ではさまざまな天皇の大権が定められている。なかでも重要なのは、天皇が国の元首として統治権を総覧するという国務上の大権である。この国務上の大権は、国務大臣の輔弼(ほひつ)をへて発揮される。その意味で、天皇は国の最高機関である、と達吉はいう。その大権は立法、行政、司法におよんでいる。
だが、大権事項に議会が参与することは許されないとするのは、なんら根拠のない謬説だ、と達吉は明言してはばからない。議会の協賛によらず天皇が親裁するというのは、近代的な立憲政治とはいえない。議会は予算を審議し、立法をおこなうだけでなく、行政を監視するなど、広く一般の国務に参与する権能を有しているのだ。
達吉は国政を運営するにあたって、議会の役割を強化することを求めていた。天皇の大権をかざして、政府が政治を壟断(ろうだん)することは認められない。
天皇には陸海軍を統帥する大権がある。この大権は憲法によって定められているといっても、慣習と実際の必要にもとづき、国務上の大権とは区別されるものだ。統帥大権が存在するのは、軍の行動の自由と作戦の秘密にたいして、局外者の関与が許されないからだとされている。
しかし、達吉は統帥大権の範囲は、軍隊の指揮と作戦に限定すべきだと主張した。宣戦や講和はもちろん、戒厳令の布告、陸海軍の編成、軍事予算などはすべて国務に関する事項で、統帥大権とは切り離されるべきだと主張している。この主張は本の最終章で軍隊を論じるときにもくり返されるだろう。
達吉が天皇の代表機関のひとつとして達吉が摂政とその役割を取り上げるのは、当時、大正天皇が発病し、政務を取ることが不可能になり、皇太子裕仁親王(のちの昭和天皇)が摂政の地位に就いていたからである。
いうまでもなく帝国憲法では、天皇(場合によってはその代理としての摂政)が国務大臣を輔弼機関とし、枢密院を顧問機関として、国家を統治するかたちをとっていた。皇室の一切の事務を処理するための宮内省と宮内大臣、天皇の常侍輔弼にあたる内大臣も天皇の機関だった。さらに法律外の慣習としては、元老制度があり、内閣が総辞職した場合は、天皇の重臣である元老が後任の総理大臣を推薦する決まりになっていた。
天皇の名の下に国家を統治する天皇の機関は強大な要塞となっていた。これにたいし、できうるかぎり帝国議会が国政への関与の度合いを高めていく方向を模索したのが、達吉の姿勢だったといえるだろう。
「帝国議会は国民の名において国務に参与し政府を監視する国家機関なり」というのが、達吉による議会の規定である。
〈専制君主政においては国家の一切の統治権が君主に専属するに反して、立憲君主政においては君主の外に国民の代表機関として議会を置き、これをして国政に参与するの権を有せしむ。立憲君主政は君民同治の政体なり、君主独り統治権を専行することなく、国民が共にこれに与(あずか)るの権を有することが、その専制政と分るる所以(ゆえん)なり。〉
帝国議会は全国民の総代であって、天皇の統治機関ではない。あくまでも天皇の外にある独立機関である。議会の権能は直接憲法によって与えられ、何人(なんぴと)の指揮に服することなく、自由な意見にもとづいて独立した議決をなすものだ、と達吉はいう。
求められているのは、選挙制度を拡充し、議会の権能を高めていくことである。国務上の大権に属する事項は国務大臣の責任の範囲に属するが、国務大臣の責任に属する事項は議会もまた当然これに参与する権利を持っているというのが達吉の考え方だった。言い換えれば、国家の統治行為にたいし、議会は協賛ないし承諾を示す(逆に示さない)権利を持っているのだった。
それは緊急命令(勅令)についても言えることだった。緊急命令は議会の閉会時に、枢密院での諮詢(しじゅん)を経て発令することができるとされていた。だが、それは次期の議会で、必ず承認を求めることを要し、承認が得られなかった場合は取り消されねばならなかった。
軍についてはふつう言及を避けるものとされていた。ところが『憲法撮要』の最終章に記されている以下のようなごくあたりまえの文言が、のちに軍事体制が敷かれるにつれて、軍部の憤激を呼ぶことになる。
達吉はこう書いていた。
〈軍隊は国家の設くるところにして軍の編成を定むることは国家の行為なること言を俟(ま)たず。軍隊の行動を指揮し、その戦闘力を発揮することは、軍令権の作用に属し、内閣の職務の外にありといえども、軍の編成は内閣の職務に属すること他の一般国務に同じ。ただ従来の我が実際の慣習は必ずしもこの原則に従わず、軍の編成に関しても内閣の議を経ざるもの多し。〉
達吉は軍政と軍令を区別し、軍の暴走に歯止めをかけようとしていた。軍が統帥権の範囲をほしいままに拡大し、天皇の名の下に内閣さらには議会の関与を拒否しようとすることは、けっして認められない。
『憲法撮要』の撮要とは、摘要、すなわち要点だけを書き記したものを意味する。だが、そこには憲法解釈を刷新しようとする気配が濃厚にただよっていた。
吉本隆明『ハイ・イメージ論』断片(4) [商品世界論ノート]

吉本は消費社会を「必需的な支出(または必需的な生産)が50%以下になった社会」と定義している。これは必需的な消費支出が50%を切ると同時に、国内総生産に占める第3次産業の比率が50%を超える社会に対応している。この定義からすれば、1980年代後半の日本はすでに消費社会にはいっていた。
そして、吉本にいわせれば、こうした消費社会の実現は、産業の高度化を反映したものだ。
その例として、吉本は多くの下請けをかかえる自動車産業を取りあげて、そのイメージを次のように説明する。
〈一台の自動車はそのあらゆる小さな部品毎(ごと)に一企業の高度な専門的な製造工程が対応しているという画像をいだかせることになる。これはたとえば自動車産業を産業としての高次化という概念にぴたりと適合せずにはおかないとおもえる。消費者がこのようにシステム細胞化された産業の集大成として、自動車にたいして、選択的な商品として消費支出したとき、かれは部品企業の幾何級数的な増殖によってもたらされた空間的な遅延と時間的な遅延の細胞のように微細な網状の価値物を購買しているのだといってよい。〉
消費社会はかならず産業の高次化に対応している。高次化とは、いってみれば迂回生産である。一台の自動車は高度な部品の集積から成り立っているが、その部品は無数の部品企業によってつくられている。それは空間的・時間的な遅延、すなわち製造工程の切り離しや専門化、特異化によってもたらされる。
動物と人間の消費のちがいはどこにあるか。消費すること自体にちがいはない。問題は動物がほとんど意図的な生産をおこなわないのにたいし、人間が意図的で高度な生産をおこなうことにある、と吉本はいう。
〈[人間と動物との]相違はわたしたちのなかにメタフィジック[形而上学。ここでは創造力というべきか]が存在するということだけだ。このメタフィジックによれば消費は遅延された生産そのものであり、生産と消費とは区別されえないということになる。〉
ここで、吉本はボードリヤールの『消費社会の神話と構造』を取りあげ、それを強く批判している。「そこには大胆な踏みこみといっしょに、ひどい判断停止があり、哲学と経済学の死に急ぎがつきまとっている」という。
ボードリヤールは消費社会を神話の世界としてとらえ、ものが氾濫する消費社会を産業社会の崩壊のはじまりとみている、と吉本は批判する。
ボードリヤールは消費社会で消費されているのは記号だという言い方をする。消費社会は「脅かされ包囲されたエルサレム」だともいう。
ここには、知的エリートによる大衆への侮蔑が感じられる、と吉本はいう。
〈ボードリヤールは消費社会を誇張した象徴記号の世界で変形することで、資本主義社会の歴史的終焉のようにあつかっている。実質的にいえば産業の高次化をやりきれない不毛と不安の社会のように否定するスターリニズム知識人とすこしもちがった貌をしていないとおもえる。〉
吉本にいわせれば、消費社会とは選択的なサービス消費が主体となり、日常必需品の消費支出、また選択的な商品を購買するための消費支出は二義的なものとなった社会を指す。それは生産の高次化にともなうもので、資本主義社会の歴史的終焉をあらわすものでもなんでもない。
ボードリヤールは教育格差の存在を指摘する。しかし、現在では「格差は縮まって相対的な平等に近づいている」と、吉本は反論する。
またボードリヤールは消費社会で格差が縮まっているのは、うわべだけで、社会的矛盾や不平等は隠されているという。だが、吉本にいわせれば、格差は明らかに縮まっており、こういう言い方をするのは「左翼インテリ特有の根拠のない感傷と大衆侮蔑的な言辞にすぎない」と言い切る。
ボードリヤールは肉体労働者と上級管理職のあいだの賃金格差は大きく、休暇がとれる期間についても格差があるという。
「ボードリヤールは消費社会を、所得の平等が実現した共産主義社会でなくてはならないとおもっているのだろうか」と吉本は反論する。吉本にいわせれば、むしろ、現代の特徴は、かつてに比べて格段と平等が進んできたことにあるのだ。
さらに、ボードリヤールは現在の消費社会で、健康や空間や美や休暇や知識や文化が求められているのは、そもそもそれらが奪われたことを示しており、そのうえでそれらが商品として資本主義システムに組みこまれようとしているにすぎないという。だが、何であれ、それが「社会の進歩」であることはちがいない、と吉本は反論する。
「わたしにはボードリヤールの理念は、誰がどうなればいい社会なのか、まったく画像を失っているのに、なお不平のつぶやきが口をついて出るので、それをつぶやいている常同症の病像にみえてくる」
こういうきっぱりした言い方に、かつてのぼくは拍手を送ったものだ。
ボードリヤールは、狩猟採集民が絶対的な貧しさのなかでも真の豊かさを知っていたのにたいし、現代人は市場経済のもとで競争を強いられ、つくりだされた欲求を満たすために四苦八苦しているという。だが、こうした言説は信じられない、と吉本はいう。
〈ボードリヤールの見解と反対に、消費行動の選択に豊かさや多様さ、格差の縮まりが生じていること。そこに核心があるように思える。……わたしたちの倫理は社会的、政治的な集団機能としていえば、すべて欠如に由来し、それに対応する歴史をたどってきたが、過剰や格差の縮まりに対応する生の倫理を、まったく知っていない。ここから消費社会における内在的な不安はやってくるとおもえる。〉
ボードリヤールの『消費社会の神話と構造』は1968年のパリ五月革命のさなかに発表され、吉本の『ハイ・イメージ論』は1880年代後半、日本のバブル絶頂期に執筆されている。
そのことがふたりの論点に影響をおよぼしていることは否定できない。いまからみれば、どっちもどっちである。
吉本隆明『ハイ・イメージ論』断片(3) [商品世界論ノート]

消費社会論。
まず、吉本はマルクスの『経済学哲学草稿』から、人間と自然とのかかわりを考えるところからはじめている。
〈マルクスはヘーゲルの[無機物・植物・動物という]段階化の概念のうえに人間(ヒト)をかんがえた。順序でいえば動物的の上位に人間的をおいたといってもいい。そして人間とそれ以外の自然との関わりは部分的ではなく全面的で普遍的な関係をつくるものとかんがえようとした。これは逆にいってもいい。じぶん以外の自然にたいして、全面的な普遍な関係をもちうるものを人間(ヒト)と定義した。〉
これはどういうことか。
マルクスは無機物が単に自然によってつくられ、植物や動物が周囲の自然に対応するだけの存在であるのにたいして、人間だけは自然と全面的で普遍的な関係をもちうる存在だと考えたというわけだ。
人間は自然を対象化し、それを自己の身体に全面的かつ普遍的に取り込もうとした。そのことは人間が頭脳と身体を用いて、外部の自然を人間的自然に変換しようとしたことを意味している。その前提となるのが自然を認識することだった。「言語は感性的自然である」とマルクスはいう。
さらに吉本は書く。
〈マルクスにとって、すぐにもうひとつの問題があらわれる。人間がまわりの自然とのあいだにこの〈組み込み〉の関係にはいったとき、べつの言葉でいえば自然にたいして行動にうつったとき、この非有機的な肉体である自然と、有機的な自然である自分の肉体との〈組み込み〉の領域から価値化されていくということだ。〉
自然を人間的自然に転換する、いいかえれば価値化するにあたって、人間は身体を道具化することからはじまり、発明された道具や機械、装置を用いるようになる。
自然の人間的自然への転換は、よきもの、すなわちグッズへの無限の可能性を秘めているようにみえた。採集や狩猟、漁撈を軸として、住居や着物が整えられ、集落が形成されていく。さらに、マルクス流にいえば、宗教、家族、国家、法、道徳、科学、芸術などが「生産」される。この段階では、すでに生産の専門化と生産物の贈与や貢納、交換がはじまっている。
生産のための生産はありえない。生産するのは消費するためである。
「人間とそのほかのぜんぶの自然との普遍的な関係は、人間の働きかけの面からは生産といっていいように、働きかけによって有機的な自然となった肉体(筋力)という面からいえば、消費にほかならない」と、吉本は書く。
「生産は同時に消費の行為であり、また逆に消費があるときかならず生産をモチーフとしていて、人間の行為はそれ以外のあらわれ方はしない」とも書いている。
原理的にいえば、生産と消費は一致する。しかし、それが分離しているようにみえるのは、人間的自然の領域が拡大するにつれ、商品がかぎりなく増え、その交換をうながすために貨幣が導入されることによってである。貨幣による媒介が日常化、ルール化されることで、生産は商品の生産となり、消費は商品の消費へと二極化されることになる。
商品は次々と新たな商品を分化していく。商品を得るには商品によるほかないからだ。商品による商品の淘汰もおこなわれる。そして商品化の波は、みずからの労働力にもおよぶだろう。人は働かないかぎり、賃金を得ることができない。労働力が商品になる。
こうして貨幣を媒介として、商品を中心とする人間的自然の拡充が進み、商品世界が形成されていく。その過程は、外的自然による限界が露呈しないかぎり、拡大方向をたどり不可逆的だ。吉本もそうみているように思える。
しかし、商品世界の拡大につれて、「生産の局面とそれに対応する消費の局面とが時間的にか空間的に」隔たる」ようになる。そのことは、「生産と消費の高度化にとって避けることができない」という。
ここから「生産にたいする消費または消費にたいする生産の時空的な遅延」が生まれてくる。つまり、需要と供給のギャップが生じる。
そうしたギャップが生じるとしても、しかし、そのことによって商品世界の拡大が停止するわけではない。商品世界が高度化するにつれて、消費はかならず多様化していく。
「消費支出は高度(産業)化社会になるにつれて、必要的(必需的)支出と選択的支出に分岐してゆき、その分岐の度合はますます開いていく」
現代の消費は必需的支出と選択的支出に分かれる。
この分類は必ずしも厳密ではないが、総務庁の家計調査は、必需的支出には外食を除く食料費、家賃・地代、光熱・水道費、保険医療費、通勤・通学費、塾や補習教材などを除く教育費が含まれるとしている。
いっぽう、非必需的支出が選択的支出である。統計では選択的支出は、選択的サービス支出と選択的商品支出に分類される。選択的サービス支出には、旅行、塾、習い事、外食などが含まれ、選択的商品支出には家電製品、乗用車、衣料品などが含まれる。
1980年代をとおして、消費支出の総額は増えている。しかし、相対的にみれば、必需的支出の割合は50%を切りつつあり、選択的支出の割合は50%を超えつつある。そのなかでも選択的サービス支出の割合が増えつつあるのが特徴的だ。
吉本はこう書いている。
「ここでは生産が同時に消費だというばあいの消費は必需的消費だけをさすことになり、選択的消費は生産にたいして大なり小なり時空的な遅延作用をうけることになるといえよう」
またむずかしいことを書いているが、選択的消費は、それを遅らせても、何とか人がくらしていける消費だということだ。たしかに車やパソコン、食器洗いがなければ、多少不自由かもしれないが、生活に大きな支障があるわけではない。
だが、「高次の価値領域の成立はすなわち高次の生産業の成立を意味している」。つまり、人類は高次の商品世界の領域に達したということだ。
産業の高度化は、末端のところで、「消費にひとりでにスイッチされている」という構図を吉本はえがいている。
産業の高度化は想像以上に進んでいる。高度付加価値化、生産工程の改善、技術開発、多角化、ネットワーク化、情報産業の発達。そうした産業が生みだそうとしている段階が「高次の自然(人工)と高次の人間(情報機械化)」であることを、吉本はかならずしも否定していない。
もう少し話はつづく。
ワイマール憲法をめぐって──美濃部達吉遠望(45) [美濃部達吉遠望]

日本に帰国して早々の1923年(大正12年)2月1日に、美濃部達吉は東京帝国大学の法理研究会で「独逸[ドイツ]新憲法に就いて」と題する講演をおこなった。その内容が『国家学会雑誌』の3月号と6月号に掲載されている。
これを読むと、達吉がワイマール憲法のどのあたりに興味をもっていたかを知ることができる。その内容をかいつまんで紹介しておこう。
達吉の講話は、憲法公布以来のいくつかの改正点の解説を含むものだったが、そこまで細かくみていく必要はないだろう。
ただ、次のように述べていることが注目される。
〈日本の憲法の如き制定以来既に34年を経て未だ1回の修正を加えられず、またいつ修正せられる機運に達するかも予期しがたいのに比べると、発布以来、僅々2、3年ならずして、既に一再ならず改正せられたということは、異様に感ぜられるようでありますが、これはドイツ憲法の内容が日本の憲法などよりははるかに詳細であり、ことに多くの経過法を含んでいること、ドイツが戦敗以後、引きつづき未曾有の国難に遭遇し、予期せられない事変や国際関係などが頻発して憲法の改正を余儀なくしたこと、日本におけるような憲法がひとたび制定せられた上は千載不磨の大典のごとくに考え、憲法を極度に固定的のものたらしめようとする感情が欠乏していることなどに原因しているのであって、あえて新憲法が革命の際、軽率に議決せられたがためとか、または国民の輿論が変わったがためとか言うのではありませぬ。〉
達吉は憲法が時代に応じて改正しうるものであることを認めていたといえるだろう。
そのうえで、まず達吉が注目したのは、旧ドイツ帝国と新生ドイツ国のちがいである。
旧ドイツ帝国は君主的連邦国家だった。帝国は25邦から構成されていた。そのうちハンザ自由市の3邦を除いて、22邦はすべて君主国だったと達吉は指摘する。
だが、それは対等な諸邦の結合体ではなく、あくまでもプロイセンの領主権のもとに服属していた。すなわち、プロイセン国王がドイツ皇帝を兼ね、プロイセンの総理大臣が帝国の宰相を兼ねることが憲法(いわゆるビスマルク憲法)で定められていた。
新憲法(ワイマール憲法)では、そうした点が改められた。プロイセンの優位性は排除され、ドイツは君主的連邦から民主的連邦に変わった。革命によって、帝国においても、各邦においても君主制は廃止された。
だが、民主政体がただちに確定したわけではない。革命党のあいだでは、ふたつの相異なる主張があった。達吉の呼び方では「極端社会党」のカール・リープクネヒトは、労農会を設立し、プロレタリア独裁体制をとるべきだと主張した。これにたいし、多数派の穏健派はできるだけ早く国民議会を開いて、民主政体を樹立すべきだという立場をとった。
最初、ベルリンでは労兵会が設立され、仮政府がつくられたものの、急進派と穏健派の対立は高まる一方だった。しかし、けっきょく急進派の主張は退けられ、1919年1月19日に国民会議の総選挙が行われることになった。選挙の結果、労兵会は解散され、2月6日からワイマールで国民会議が開かれることになり、8月11日に憲法が議決されるにいたった、と達吉は解説している。
〈これを要するに、[1918年]11月9日にドイツの旧君主政が破壊せられたのち、約3ヶ月の間、一時の過渡期として無産者専制主義に基く労兵会制度の共和政が行われていたのが、2月6日に国民会議が開かれて最高の権力を掌握することとなったことによって、民主政体が確定したものと言ってよいのであります。〉
1月にカール・リープクネヒトとローザ・ルクセンブルクらの「スパルタクス団」が鎮圧され、ふたりとも殺害されたことには触れていない。
達吉はワイマール憲法の民主的特徴を列挙している。
(1)連邦議会議員だけでなく大統領をも国民が選挙で直接に選ぶようにしたこと。
(2)立法に関する国民の発案権が認められていること。
(3)場合によっては国民投票の実施が定められていること。
(4)大統領に対する国民のリコール権が認められていること。
(5)国民の代表会議である連邦議会が最高主権者であることが明確にされたこと。そのいっぽう、各邦の代表によって構成される参議院の権限は大幅に弱められたこと。
(6)議院内閣制を基本とすることが定められたこと。
(7)満20歳以上のドイツ人たる男女に選挙権が認められたこと。
(8)プロイセンの優先権、ならびに各邦の特権が廃止されたこと。
こうして、新生ドイツ国が世界でも最も民主的な国家へと変貌したことを達吉は強調している。
しかし、達吉はワイマール憲法のもう一つの特徴が、統一主義、中央集権主義の強化にある点を指摘するのを忘れてはいない。
旧帝国時代は、帝国だけではなく帝国を構成する各邦も一定の立法権をもっていた。これにたいし、新憲法のもとでは、国の立法権の範囲が拡張された。
対外関係に対する立法権は国だけが占有することになり、バイエルン王国がもっていたような各邦の外交権は失われた。
兵役制度や外交権、郵便制度なども、国のもとに一元化されることになった。さらに国の法律が各邦の法律よりも強い効力を有することが定められた。租税権もその一つで、それによって国の財政的独立性が保証されるようになった。福祉の増進や安寧秩序の保護についても、国に権限があることが認められた。
国における立法権の強化は行政権の範囲拡張にもつながっている。
たとえば、従来、軍政は各邦にそれぞれ陸軍省が設けられていたものが、各邦の陸軍は消滅して、国の陸軍だけが存在し、大統領が全陸軍に対する最高命令権を有するようになった(海軍は以前から国の指揮下にあった)。
財政の権限は著しく拡張された。従来、国は関税と消費税だけしか徴収できず、直接税はもっぱら各邦に委ねられていた。それが新憲法のもとでは、租税の徴収と管理はすべて国がおこなうことになり、それまでのような各邦の分担納付金は廃止されることになった。
交通行政についても、各邦のおこなっていた郵便、電信、電話事業は国の専属となった。外交業務が国に一元化されたこともいうまでもない。
各邦の自治権が縮小され、各邦に対する国の監督権が拡張された。それと同時に各邦は自主的立法権を抑えられ、国の憲法にしたがって、民主的共和政体をとるべきことが定められ、連邦議会ならびに地方議会の選出は、比例制にもとづき男女平等の普通選挙の形態をとることとなった。
各邦にたいする政府の監督権が強化された事例として、達吉は次のようなケースを挙げている。かつては、帝国政府とプロイセン政府の首脳が同じであったため、プロイセンに対しては帝国政府の監督権が及ばなかった。ところが、新憲法のもとでは、プロイセンに対しても他邦に対するのと同じように、政府の監督権が及ぶようになったというのである。
連邦政府の行政権が強化されたということは、大統領の権限が強まったことを意味する。大統領は皇帝と同様の権限をもっていた。首相の任免権、国会の解散権、憲法停止の非常大権(緊急事態条項)、国軍の統帥権などである。のちにこれがヒトラーとナチ党の進出につながることを予測する人はほとんどいなかっただろう。その経緯については、あらためて述べなければならない。
1923年の時点で、むしろ達吉が注目したのは、ワイマール憲法下での選挙法だった。
新憲法のもと、ドイツでは大統領と連邦議会議員が選挙によって選ばれることになった。
当時の大統領は社会民主党出身のフリードリヒ・エーベルトで、国民の投票で大統領が選ばれるのは次期大統領からだった。
20歳以上の男女が選挙権をもつ総選挙は、1919年以降、1922年までにすでに2回行われていた。選挙権が男子と女子とにあまねく認められた結果、全人口に対する有権者の割合は6割以上に達し、1919年の投票率は84.2%だったという。
新生ドイツの選挙は比例選挙法をとっていた。1919年の選挙では、ドイツ全国を36の選挙区に分かち、少ない区では6人、多い区では17人が選出された。比例選挙はいわゆる拘束名簿式をとり、ドント方式で票を割り当てた。その欠点についても達吉は指摘しているが、比例代表制が完全な制度であるかどうかは別として、ドイツの選挙法は十分検討に値するものだと述べている。
比例代表制の長所は死票が少なく、民意が正確に議会に反映されることである。いっぽうその欠点は小党分立を生じやすく、議会運営がむずかしくなることだった。それでも、達吉は日本でも比例代表制による普通選挙をめざすべきだと主張しており、ワイマール憲法下の選挙法には強い関心をもっていたことがうかがえる。
しかし、その後10年のあいだにドイツはファシズムの扉を開け、日本は大陸侵攻に舵をきっていくことになるのである。
欧州出張とワイマール憲法──美濃部達吉遠望(44) [美濃部達吉遠望]
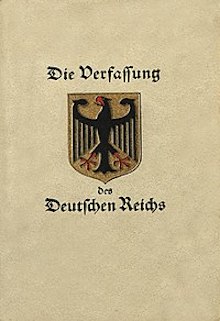
宮先一勝氏の『評伝 美濃部達吉』にはこう書かれている。
〈達吉は、大正11年[1922年]3月から12月まで欧州へ出張している。旅先(ドレスデン、デュッセルドルフ、ロンドン、ブダペスト等)から民子夫人宛に絵はがきで、当時の第一次世界大戦直後のヨーロッパの混乱や街の状況を具(つぶさ)に報告している。そして翌年、「欧州諸国戦後の新憲法」や「憲法撮要(初版)」を刊行し、大正13年には東京帝国大学法学部長(九州帝国大学法学部長兼任)に任命された。〉
宮先一勝、田中由美子編『美濃部達吉博士関係書簡等目録』によると、達吉から民子夫人に宛てた絵はがきは22通残されており、そのうち1通は地名、日付が不明とはいえ、これをたどれば達吉がどこを訪れたかがわかってくる。
残念ながら、目録にははがきの中身まで収録されていないので、達吉が「第一次世界大戦直後のヨーロッパの混乱や街の状況」をどんなふうに伝えていたかは、詳しいことがわからない。そのうち、いなかに帰った折にでも、現物をみせてもらい、その中身を紹介することができればと考えている。
それはともかく目録に沿って列記すると、下関(3月24日)、上海(3月28日、29日)、香港(4月2日)、シンガポール(4月10日)、プラハ(6月3日)、ドレスデン(6月29日)、ブランデンブルク(8月10日)、デュッセルドルフ(8月20日、30日)、パリ(9月10日)、ヴェルサイユ(9月11日)、ロンドン(9月26日、10月2日)、ブダペスト(10月20日、30日)、リヨン(11月18日)といった地名が記されている。国でいえば、チェコスロヴァキア、ドイツ、フランス、イギリス、ハンガリー。日本に帰国したのは1923年(大正12年)1月である。
第一次世界大戦の帰結はヨーロッパに大きな近く変動をもたらした。
ドイツ、オーストリア=ハンガリー、オスマンの3帝国は敗戦国である。ロシア帝国では革命が発生した。その結果、4つの帝国は解体され、皇帝が退位し、ヨーロッパでは、そのなかから多くの独立国が生まれた。
ポーランド、オーストリア、ハンガリー、チェコスロヴァキア、セルビア人・クロアチア人・スロヴェニア人王国(のちユーゴスラヴィア)、エストニア、ラトヴィア、リトアニア、フィンランドである。
帝国が解体されたあとは、とうぜんのように民主化が進むものと期待された。ところが、そう簡単に、ことは進まない。
第1次世界大戦の終結から第2次世界大戦の開始までの1918年11月11日から1939年9月1日までの期間は一般に戦間期と呼ばれるが、その時期はけっして平穏ではなく、つねに戦争の影がつきまとっていた。
この時期について、歴史家のノーマン・デイヴィスはこう書いている。
〈戦間期の政治力学を支配したのは、自由民主主義が独裁主義の餌食になるという光景の繰り返しである。西側列強は自分たちの勝利によって、みずからの姿をモデルとした時代が始まることを期待していた。大戦開始時にヨーロッパ大陸には、19の君主国と3つの共和国があったが、終戦時にはそれが14の君主国と16の共和国になっていた。ところが「民主的改革」は錯覚にすぎなかったことがすぐに明らかになる。民主国家がいろいろなタイプの独裁者に踏みにじられなかった年は1年もないくらい。……ありとあらゆる種類の独裁者が現われた。共産主義者、ファシスト、急進派、反動主義者、左翼権威主義者、右翼軍国主義者……。かれらの唯一の共通点は、西欧民主主義は自分たちのためにはならないという確信だった。〉
歴史は同時代的に動いていく。日本の大正デモクラシーにも暗雲がただよいはじめる。
ここで事実関係についていうと、達吉が『欧洲諸国戦後の新憲法』を有斐閣から上梓したのは、帰国後の1923年(大正12年)1月ではなく、訪欧直前の1922年(大正11年)1月だった。つまり、達吉は欧州視察に出向く前に、世界大戦後、敗戦によって生まれた新生国の憲法を訳出していた。具体的には、ドイツ憲法、プロイセン憲法、チェコスロヴァキア憲法、ポーランド憲法、オーストリア憲法である。それらを予備知識として、達吉は欧州歴訪の旅にでたといってよい。
『欧洲諸国戦後の新憲法』には何の解説も施されていない。新憲法の条文が淡々と訳出されていた。しかし、帝国が崩壊し、皇帝がいなくなった国の新憲法については、少なくとも法学者なら強い関心を寄せるところだったにちがいない。
なかでもドイツ憲法、通称ワイマール憲法には、大きな興味がいだかれてしかるべきだった。皇帝なきあと、はたして国家の運営はうまくやっていけるものなのだろうか。そのころは、まだワイマール体制のなかからヒトラーのような独裁者が浮上してくるなどとは、だれも夢にも思っていなかった。
1919年8月に制定されたワイマール憲法の前文を、達吉はこう訳している。
〈ドイツ国民はその各民族相共同し、かつ自由と正義とによりて国家を改造し、これを強固にし、国内および国外の平和を保持し、および社会の進歩を促さんことを欲し、ここにこの憲法を制定す。〉
第1条は「ドイツ国は共和政体とす。国権は国民より発す」という宣言である。
達吉の訳によれば、ワイマール憲法は全181条の詳細な規定からなる。その大きな内訳は次の通り。
第1篇 ドイツ国の構成および権限
第1章 ドイツ国および各邦
第2章 国議会(ライヒスターグ)
第3章 国大統領および国政府
第4章 国参議院(ライヒスラート)
第5章 国の立法
第6章 国の行政
第7章 国の司法
第2篇 ドイツ人民の基本権および基本義務
第1章 個人
第2章 共同生活
第3章 宗教および宗教団体
第4章 教育および学校
第5章 経済生活
経過規定および附則
達吉は実質半年足らずのヨーロッパ滞在中、3カ月近くをドイツですごした。敗戦後のドイツが苛酷な状況に置かれていることを痛感したのではないだろうか。
ヴェルサイユ講和条約は、誇り高いドイツ人の多くに屈辱感を覚えさせていた。ドイツにたいする懲罰と賠償はあまりに露骨だった。
敗戦によりドイツは東部の農業地域、工業地域を中心に13%の国土を失った。重要な港ダンツィヒ(グダニスク)はポーランドに包摂され、石炭と鉄鉱石を埋蔵するザールラントは実質上フランスの管理下に置かれた。非軍事化が進められ、徴兵制は廃止され、陸軍と海軍は極端にまで削減され、空軍は禁止された。これに加え、1320億金マルクという気の遠くなるような賠償金が課されることになった。
ワイマール憲法下で発足したドイツの民主主義体制は当初から大きな危機にさらされていた。
ヒトラーが国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)の指導者になったのは1921年のことである。その勢力は南部のバイエルン州を中心として急速に拡大していくが、達吉がドイツを訪れたころ、ナチ党のメンバーはまだ2万人ほどだった。
左翼は議会制民主主義を支持する多数派(社会民主党)と徹底したソヴィエト型革命を求める少数派(ドイツ共産党)に分裂し、鋭く対立していた。
1920年3月には、ヒトラーとは別の武闘派右翼の過激派が政府転覆を企てるが、失敗に終わっている(カップ一揆)。
ザクセン、チューリンゲン両州、ルール地方などでは、労働者の「赤軍」と政府軍が激しく衝突した。
右翼テロが横行した。経済人でヴィルト政権の外務大臣を務めていたユダヤ人、ヴァルター・ラーテナウは、1922年6月にベルリン郊外で極右テログループによって暗殺されている。
それでも、1922年の時点では、社会民主党とカトリック中央党を中心に、ドイツの民主主義体制はかろうじて維持されていた。
達吉はそんなドイツを見たのである。



