きょうの1冊 [本]


きょうの1冊
佐高信『上品の壁──人間の器と奥行き』(2018、七つ森書館)
「上品の壁」が真実の追及を甘くする。それが大新聞の限界だ、と佐高はいう。
「極端に言えば、『真実は下品の中にこそ宿る』のである。『上品の壁』を乗り越えなければ、人間の器は大きくならない。」
人間の器が大きくなるかはともかく、「上品の壁」を乗り越えるという主張はまったく正しい。
この本で「魅力なき単色人間」として取りあげられているのは、次のような人たちだ。
安倍晋三、池田大作、ドナルド・トランプ、中曽根康弘、前原誠司、森喜朗、麻生太郎、竹中平蔵、石原慎太郎、曽野綾子、稲森和夫、橋下徹、北野武、佐藤優、司馬遼太郎、相田みつを、長谷川慶太郎、山口那津男、鈴木宗男、織田信長、日枝久、姜尚中、稲田朋美、猪瀬直樹、渡部昇一、松本人志、高橋洋一、三島由紀夫、塩野七生、沢木耕太郎
著者の好みがよくでている。ぼくも似たようなものだ。
5年前に出た本だから、いまならもっとちがう顔ぶれが加わっているかもしれない。
それにしても、へんな言い方かもしれないが、嫌いな人の好みがほぼ一致しているのがこわい。
これにたいし「奥行きのある人びと」として、挙げられているのは、あまり「大物」ではないが、ちょっといい話がある。
たとえば加藤登紀子の話。
〈デビューしてまもない頃、キャバレーをまわってシャンソンを歌っていると、毛唐の歌ばかり歌うなと言われて、全然聴いてもらえなかった。それで21歳の加藤は「一体どうすればいいんでしょうか」と並みいるゴロツキ客に向かって聞いた。すると、「おまえは童謡でも歌ってろ」と言う。
それで加藤は「わかりました」と言って、ステージであぐらをかき、知っている童謡を次々とアカペラで歌った。そうしたら、そのヤクザみたいなおっちゃんたちがボロボロと涙を流して泣き出したのである。忘れられない瞬間だった。〉
いい話だ。
ところで、最近、ぼくは「上品の壁」どころか、遠慮の壁のようなものをメディアの報道に感じてしようがない。
新聞を読んだりテレビをみたりしても、報道されるのは、これから戦争はどうなるとか、法案はどうなるとかいう技術的な話ばかり。あとになって、実はこうだったという話がでてくる。
ほんとうのことは隠されている(いや、隠れている)。あちこちに配慮して、できるだけ波風を立てないというのが報道(組織)の基本姿勢らしい。だから、ぼくなどには、何がおこっているのか、さっぱりわからないのだ。
きょうの1冊 [本]

亀山郁夫『人生百年の教養──自分の人生と戦い続けるために』
タイトルが鼻につく。
教養はいやだ。自分の人生と戦い続けるのもいやだ。
それでも、著者の少年時代、青春時代の読書遍歴はおもしろい。
ドストエフスキーはすばらしい。
ドストエフスキーのことば。
「人間は謎です。それは解き明かさなくてはなりません。もし一生をかけてそれを解きつづけたとしても、時間を浪費したとは言えないでしょう。ぼくはこの謎と取り組んでいきます。なぜかといえば、人間でありたいからです」
スターリンの影。
「マヤコフスキーはスターリンの影に怯えていました。……恐怖から、文学が生まれました。詩の女神の背後には、スターリンの後光が輝いていました。マヤコフスキーは、なぜ自殺したのか、あるいは、謀殺されたのか?」
「20世紀ロシア最高の詩人とされるオーシプ・マンデリシタームは、独裁者スターリンをあからさまに批判する詩を書いたことで逮捕され、極東のラーゲリにて病死します」
「メイエルホリドは、1940年に66歳で処刑されました」
「ソ連を代表する映画監督エイゼンシュテインは、スターリンと摩擦が生じ、遺作となった『イワン雷帝』は公開をさし止められ、50歳の若さでこの世を去ります。心臓麻痺でした」
「キエフに生まれ、しばしば20世紀最高の小説家とまで目されるミハイル・ブルガーコフは、20世紀世界文学の最高とされる『巨匠とマルガリータ』の原稿を机の引き出しに入れたまま、48歳の若さでこの世を去ります」
かれらの無念を伝えなければいけない。
そして「老いの作法」。
乱読の楽しみと忘却の肯定。老醜ではなく老美。
「70代、80代を自信を持って生きるには、やはりそれなりの心構えが必要です。老いて弱者となった人間に活力を与えてくれるのが、読書であり、教養です。読書をしている人間、教養を積もうとしている人間、あるいは地道に自分の趣味の世界に生きる人間、その人たちに『老美』を感じます。単に読書するばかりではなく、衰えを知らぬ創造力が備わっていれば、むろん、何も言うことはありません」
ぼく自身、そんな生き方はできそうもないが、亡くなった母がよく「きれいなおじいさんにならんとあかんよ」と言っていたことを思いだす。まもなく七回忌だ。
ご案内 『美濃部達吉』を発売 [本]
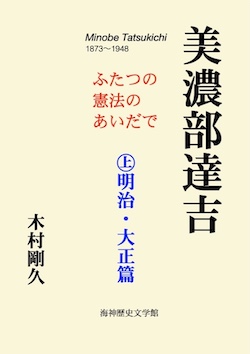
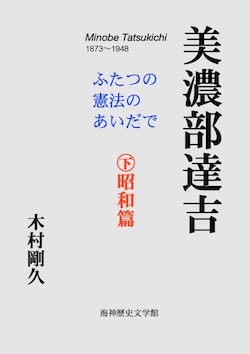
ご案内です。
このブログにずっと連載してきた美濃部達吉遠望をまとめて、Kindle電子書籍版としてアマゾンから上下2巻で発売しました。定価は各150円です。よろしければお読みください。
Kindle専用の端末は高いですが、パソコンやタブレット、スマホなら無料でアプリをダウンロードすれば、読むことができます。もっとも分量があるので、スマホはちょっと無理かも。
これまで、何冊もKindle本を出してきましたが、売れたためしはありません。
だいたい、1冊あたり40部か50部といったあたりです。
ひまなじいさんの書いたものだから、そんなものかもしれませんね。
今回もとりあえず50部をめざして、レッツゴーといったところです。
ポスト・モダン批判──富永健一『近代化の理論』を読む(7) [本]

著者は近代を前期と後期に分け、現在は近代後期にあたるととらえている。近代はまだつづいており、ポスト・モダンははじまっていない。その伝からいえば、多くのポスト・モダン論はたわごとだということになる。
しかし、近代後期とはどんな時代なのか。
それを言いあらわす代表的概念が、ポスト工業社会と情報社会である。ポスト工業社会を唱えたのはダニエル・ベルで、情報社会はコンピューター工学に由来する。往々にしてごっちゃに論じられるポスト工業社会と情報社会という概念は、はっきりと区別されなければならないという。
[ポスト工業社会]
そこで、まずポスト工業社会についてだ。
Post-industrial society を、著者はポスト産業社会(あるいは脱産業社会)ではなく、ポスト工業社会としてとらえる。なぜなら、工業の時代が終わっても産業社会はつづいているからだ。
ポスト工業社会の特徴は、(1)産業が第2次産業から第3次産業中心に移行したこと、(2)ブルーカラーにたいするホワイトカラーの優位、とりわけ専門・技術職が求められるようになったこと、(3)労働形態が経験知識中心から理論中心に移行したこと、(4)技術管理と技術評価が重視されるようになったこと、(5)意思決定に関して新たな知的技術が導入されるようになったこと、などだという。
先進国において工業(第2次産業)が産業の中心でなくなったのは。オートメ化、ロボット化の進展によりブルーカラー労働者が不要になったこと、さらには工場が発展途上国に移転したなどによる。そのため、多くの労働者がサービス産業部門へと移行することになった。
そうした広い意味でのサービス産業、つまり第3次産業には、卸売や小売、飲食店、金融、保険、不動産、運輸、通信、公益事業、公務、保健、教育、研究など多岐な職種が含まる。
[情報社会]
ポスト工業社会は即情報社会を意味するわけではない。ポスト工業社会にたいし、情報社会は日本でコンピューター関係者によってつくられた概念だという。
著者の理解するところでは、「情報社会とはコンピューターと通信ネットワークとがつながれた情報インフラストラクチュアの普及が高度にすすんだ社会」を意味する。つまりパソコンとスマホの世界である。
意外なことに、著者はこうした情報社会の進展に大きな危惧をいだいている。
コンピューターは電気通信メディアで、その機能と広がりは無限であるようにみえるが、情報は経験にもとづく主観的内面をもつ知識とちがい、一方的で瞬間的なものだという。
情報社会化は知識の生産と普及を助けるけれども、はたして人が考えることに役立っているかどうかは疑問だ、と著者はいう。コンピューターの役割は情報によって人間をコントロールすることにあって、人が主観的内面において考えることをむしろ弱めてしまうのではないか。
[ポスト・モダン]
ポスト・モダン、すなわちポスト近代化という思想潮流にも、著者は批判的だ。
ポスト・モダンとは、近代は終わり、次の時代がきているという主張をさす。社会主義や共産主義がもっていた歴史的展望は、20世紀の現実の進展とともに、すっかり失われてしまった。
それでは、いったいポスト・モダンとは何なのか。消費と遊び、ボーダーレス化などといっても、それが近代と異なるまったく新しいものとは思えない、と著者はいう。
近代の成果を資本主義、民主主義、核家族、合理主義に代表させるとすれば、ポスト・モダンはこれらにたいし、いかなる展望を提示しようとしているのか。
ポスト・モダン論者は資本主義のあとについても、民主主義のあとについても、何も語っていない。まさか、社会主義や専制主義のほうがいいとはいえないだろう。
核家族が解体して、まったくの個人化の時代になるとも思えない。合理主義にたいして非合理主義が正しいとも思えない。
近代が揺らいでいるのはたしかだが、それをもって、近代が終わりつつあると主張するのは誇張にほかならない、と著者はいう。
それにもかかわらず、ポスト・モダン論がはやっているのは、反近代イデオロギーが一部の共感を呼んでいるからで、日本ではそれが「西洋化」の排斥、アジアへの回帰、ナショナリズムと結びついているところに、問題の根深さがある。
そこで、著者はこう述べている。
〈私自身は近代化論者ですから、近代が終焉すべきであるとか、近代は超克されねばならないなどとは毛頭考えません。私は近代化と産業化を、西洋文明としてよりは普遍文明として見ていますので、明治の日本の指導者たちが近代化の目的のためにいちはやく西洋化を採用したことを肯定的に評価してきました。〉
日本はもうナショナリズムを必要とせず、これから必要とするのは「ナショナリズムであるよりは、アジアの観点からするリージョナリズム」だ、と著者は述べている。
だが、現状はあきらかにそうした言説から後退し、東アジアでは、むしろ国家間の対立が深まっているようにみえる。
[高齢化社会]
最後に高齢化社会の問題がつけ加えられている。他人事(ひとごと)ではないので、紹介しておく。
高齢化社会が到来したのは、近代化とともに、出産と死亡のパターンが多産多死から少産少死へと変化したためだ。
少産の理由は、かつてのような家族内労働に子どもを必要としなくなったこと、教育水準の上昇により育児のコストが高まったこと、女性の晩婚化が進んだこと、産児調節により出産が抑制されるようになったことなど。少死の理由は医療の進歩、公衆衛生の改善、栄養がよくなったことなどが挙げられる。
日本は1970年ごろから高齢化社会にはいった。1970年の高齢化率(総人口に占める65歳以上の比率)は7.1%、それが2020年には28.7%になった(本書が出版された1995年ころはまだ14.6%だった)。
高齢化は意図しない社会変動で、それ自体として機能的に望ましいものではない、と著者はいう。近代化にともなう家族と組織の分離、核家族化、女性の地位の上昇、家族の解体傾向が少子化を促進する要因になったことはまちがいない。これは近代化がもたらした予期せぬ結果である。
こうして、高齢化が必然的に進むことになるが、問題は高齢化社会のなかで高齢者がどのような役割をはたすようになるかだという。
家父長制の時代とちがって、核家族のなかでは高齢者のはたす役割は次第に縮小して、最後は消滅してしまう。企業においても、年功序列制は次第に見直されている。
だが、長寿社会はけっして悪いことばかりではない、と著者はいう。昔にくらべ、元気な高齢者が多くなった。長い経験が社会に役立つこともある。また定年後に地域社会で何らかの役割をはたすことも期待される。さまざまなボランティア活動に参加することも有益だ。
そして、今後は国と自治体が、金銭面、施設面だけでなく精神面でも高齢者対策に取り組んでいくことが重要だと指摘している。
かつてのように、どんどんハード面での近代化を進めればよいという時代は終わったのかもしれない。いまはハードよりハートである。
近代化の日中比較──富永健一『近代化の理論』を読む(6) [本]

のんびりと読んでいる。気の向くまま、あちこち。
著者は、社会は発展段階を追って進化すると考えている。世界史において、その進化の方向が、これまでのところ近代化というかたちをとったことはまちがいない。
近代化とともに、さまざまな機能集団(学校、企業、役所など)が形成され、家族・親族の結合強度はちいさくなり、個人の自由度が高まるとともに、社会のルールが確立されていく。
村のような閉鎖的な地域共同体は解体され、国民社会(いずれは世界社会?)と国家(いずれは世界国家?)が形成されていく。
身分とか階級とかといった人間関係は消滅し、社会的中間層の誕生とともに平準化された社会階層へと移行していく。
こうした近代化への進化が、社会構造の変動(社会変動)によってもたらされたことはいうまでもない。
では、なぜ社会変動が生じるのか。
「現行の社会構造のもとでシステムの機能的要件が達成され得ないことを当該成員たちが意識した時、そのことが現行の社会システムの構造を変えようとする動機づけ要因となる」と著者はいう。
いまの社会構造ではもうやっていけないと思うのは、あくまでもその共同体にくらす人の主観、あるいは人びとの共同主観であり、そこから社会システムを変えようという動機が生まれるというわけだ。といっても、その方向性はけっしてランダムではなく、社会の進化(具体的には近代化)に沿ったものになるはずだ。
では、なぜ世界は一様に近代化しないのか、あるいはしなかったのか。現実に近代化は西洋(西欧と北米)からはじまり、西洋を起点として、東欧やロシア、日本、アジアへと広がっていった。
著者は近代化のプロセスを「内在的」(内生的)発展によるものと「伝播的」(外生的)発展によるものとに分け、これまで西洋中心に考えられてきた近代化論を、いわば世界史レベルでとらえなおそうとしている。
だが、その作業はあまりにも膨大にわたる。そのため、本書では範囲を限定し、産業化の発生源となった西洋と、早くから西洋を受け入れた日本、近代化のスタートが遅れた中国にしぼって、社会進化の様相が比較検討される。
先発国である西洋にとって、近代化・産業化は内生的なものである。それを起動させた要因としては、(1)資本主義の精神(2)民主主義の精神(3)合理主義の精神(4)科学的精神(経験主義、実証主義)が挙げられる。
こうしたエートスは西洋においてのみ生みだされた、と著者はいう。
これにたいし、後発国であるアジアなどにとっては、近代化・産業化はほぼ外生的なものとなる。それは西洋からの文化的インパクトによって、外からもたらされた。
後発国において、それまで近代的エートスが発現しなかったのは、社会変動の担い手が内部から自生せず、そのために社会停滞がつづいてしまったからだと考えられる。しかし、単なる模倣だけでは近代化は進まない。
後発国において社会発展が実現するためには、いくつかの条件が必要になってくる。
まず、農業社会が内的に成熟していること。次に、すぐれた指導者をもつ政府によって適切な指導がなされること。さらに西洋への危機意識。伝統主義を克服しようとする革新的態度。国内抗争の克服。産業文明を内部化できる人材の育成。そして、従属からの離脱と独立性。
著者は後発国が近代化を達成するために必要な条件として、以上のような項目を挙げている。
それでは、日本の場合はどうだったのか。
日本が産業化の道を歩みはじめたのは1880年代で、イギリスにくらべ約1世紀、フランス、アメリカにくらべ半世紀、ドイツにくらべ30年遅れていた。しかし、ほぼ1世紀のあいだに、日本はそれらの国に追いつく。
日本が農業社会段階にはいったのは弥生式土器の時代で、紀元前200年から300年ごろのことだ。中国はすでに紀元前2000年代ごろから農業社会にはいっていたから、中国との差は歴然としていた。
中国で国家が生まれるのは紀元前1400年ごろ、秦の始皇帝による天下統一が紀元前221年、これにたいし、日本で大和朝廷が誕生するのは西暦400年代で、日本の後発性は歴然としている。
著者によれば、日本で古代専制体制が成立するのは645年の大化改新によるという。このときはじめて天皇は専制君主となり、公地公民制をしいて全国を支配した。
中国と決定的に異なるのは、中国が分裂と統一を繰り返しながら、基本的に2000年間、アジア的専制を維持したのにたいし、日本は平安中期以後、しだいに封建制に移行したことである。
徳川時代の日本は「鎖国」によって外部からのインパクトを弱め、伝統的な農業社会を保ってきた。しかし幕藩体制の困難は、まず財政面から生じ、さらに国防問題におよんだ。
尊王攘夷論が生まれる。尊王論はいわば「古代化」で、攘夷論は伝統主義であって、尊王攘夷論として反幕思想を形づくった。だが、それは近代化とは無縁の考え方だった。
明治維新とともに攘夷論は消えて開国論に移行し、「王政復古」が実現する。この時点では「近代化」は未知数だった。日本が伝統主義を切り捨てて、はっきりと近代化を採用するようになるのは、明治10年の西南戦争が終わってからだ、と著者はいう。
日本が近代的な経済成長を開始するのは明治20年(1887年)からで、それまでは近代への移行期だった。重要なのは、その移行期に「上からの近代化」が推し進められたことだ。西洋の行政制度や経済制度が取り入れられ、インフラが整備された。その路線を敷いたのが大久保利通であり、さらにその後を継いだ伊藤博文や松方正義だった。
上からの近代化は功を奏し、三井、三菱、住友などの財閥が育ち、日本経済は近代化の軌道に乗りはじめる。明治22年(1889年)には憲法が発布され、翌年には帝国議会が開会され、政治面での近代化も進んだ。
しかし、日本の近代化は農村の窮乏化を引き起こした。農村は産業化の恩恵を受けず、近代化から取り残されていた。
大正末期から昭和初期にかけ、農産物価格は下落し、農村はますます窮乏化する。それが日本ファシズムを発生させる源となった。日本の農村が貧困から解放されるには、戦後の農地改革と農業保護政策を待たなければならなかった。
つづいて中国の場合をみていこう。
中国は古代の大先進国だったが、近代になると西洋に遅れをとってしまった。しかも、近代化にさいしては、日本にも遅れをとった。その原因は中国の長期的停滞にある、と著者は指摘する。
中国は基本的に、皇帝が支配する中央集権的統一国家を維持しつづけてきた。いっぽう、郷村では宗族集団による強力な自治・自衛制度が存続し、国家行政の浸透を防いできた。
中国の民衆は国家にたいし高い要求水準をもたず、宗族システムのなかでいちおうの生活水準を満たしてきた。このことが東洋的停滞のメカニズムを生んできた、と著者はいう。
とはいえ、さすがにいつまでも停滞のなかに眠ってはいられない。1911年の辛亥革命は、古代的な家産的権力を一挙に解体し、近代的な共和制を樹立しようとした。だが、いきなりの飛び越えは不可能だった。そこから大きな混乱が生じる。
孫文のくわだてが挫折し、軍閥の袁世凱が中華民国の大総統になったことで、民主化と産業化への芽はつみとられた。その後は軍閥が割拠し、国内はいっそうの荒廃へと向かう。孫文の死後、蒋介石は北伐によって、中国を再統一しようとした。
そこに毛沢東が登場する。毛沢東は都市のプロレタリアートよりも農民の階級闘争を重視する立場をとった。根拠地に軍を組織し、長征をおこなう過程で、中国共産党の主導権を握った。さらに、日本軍との戦いで疲弊し腐敗した国民党を破って、1949年に政権をとり、共産党指導下で一挙に社会主義を実現しようとした。
だが、そのこころみは1958年にはじめた人民公社運動と大躍進が失敗することで挫折する。毛沢東はそれにもめげず、1966年に文化大革命を発動し、さらなる社会主義革命をめざそうとして、経済的大混乱を招いた。
1978年の文革収束後に登場したのが、鄧小平による「四つの近代化」路線だった。これにより、中国はやっと近代化と産業化に向けての再スタートを切ることができた。
米中関係と日中関係が改善され、それまでの「鎖国」状態にピリオドが打たれ、「経済特区」に先進諸国との合弁企業が設立された。こうして対外開放経済がスタートし、その後のめざましい経済発展がはじまる。
ここで著者は日本と中国の比較をおこなっている。
そのさい比較されるのは、伝統社会の構造、近代化にあたっての国内問題、近代化にあたっての国際問題である。
まず伝統社会の構造についていうと、家族・親族に関しては、日本が一子相続と同族制度をとっていたのにたいし、中国は均分相続と宗族制度をとっていたのが大きなちがいだという。
日本の同族がゆるやかな結合体で、権力分散的だったのにたいし、中国の宗族は緊密な内部結合と封鎖性を特徴としていた。
そのことは伝統的な村落にもあてはまる。中国の郷村が氏族的団結による閉鎖性が強かったのにたいし、日本の村落はそれほど血縁意識が強くなく、どちらかというと中央にも開かれていたという。
組織についてみても、中国の商人や職人のギルドは、日本よりもはるかに強い結束力をもっていた。
中国が皇帝とそれに直属する官僚によって支配され、巨大地主のもとに小作人が隷属していたのにたいし、日本では幕藩体制が成立し、村は比較的平等な自営農民によって運営されていた。
また中国の国家が専制的な家産国家であるのにたいし、日本の国家は封建制をとり、中央集権国家ではなかった。しかし、日本では幕藩体制のもとでも天皇が存続し、明治維新後もその伝統的カリスマ性によって国民統合を保つことができた。
近代化がはじまってからの国内事情についてみても、日本と中国の発展には大きなちがいがあった。
明治憲法はかならずしも家族の近代化をうながさなかったが、それでも1920年ごろには日本でも核家族化が進んでいる。中国でもかつての宗族の機能は弱まりつつあった。それでも日中ともに、西洋にくらべ、家族・親族の近代化はずっと遅れていた。
日本では農村は近代化・産業化の恩恵をこうむらず、窮乏のまま取り残された。中国の場合は、はやくから地主と小作の両極分解が進んでいた。そのため農民反乱の伝統があり、毛沢東はそれを活用した。革命後、中国では地主がいなくなるが、人民公社が農民の勤労意欲を動機づけることはなかった。
日本においては政治権力と結びつくかたちで資本家が登場し、産業化を担った。戦後は財閥が解体されるなかで、経済の近代化が促進され、高度経済成長が実現する。
中国でも資本家は政治と結びつくなかで企業活動をおこなっていた。しかし、革命後、こうした資本家は買弁的ブルジョワジーとして排除され、社会主義のもと資本主義的な企業活動自体も否定されることになった。
日本では初期産業化の進展とともに、階層間の格差が拡大した。農村では大地主と小作への両極分解が進み、都市では財閥が形成され、労働者階級が増えていった。
日本と中国のもっとも大きなちがいは、日本の国内が統一されていたのにたいし、中国がほとんど分裂状態にあったことである。1949年の中華人民共和国成立後も、中国は文化大革命のもとで内乱がつづいた。そのことが中国の近代化を遅らせた、と著者はいう。
最後に国際関係についてふれると、日本と中国は西洋先進国から外圧を受けたという面で、共通の経験をもっている。中国がアヘン戦争後、西洋列強の半植民地となったのにたいし、日本は開国によって上からの近代化をなしとげ、植民地化を免れる。そればかりか、日清・日露戦争後、アジアのなかの西洋としてふるまうようになった。
しかし、すべては第二次世界大戦をへて大きく変化する。日本は明治以来の戦争体質を清算して貿易立国に転じ、中国は西洋先進国への従属から脱して、大国への道を歩みはじめた。
日本と中国は、ともにアジアに位置する近代化への後発国として、多くの共通点をもつが、また同時に違いも大きい、と著者は指摘している。
本書が出版されたのは1996年のことである。それ以来、日本と中国の関係も大きく変わった。社会変動論=近代化論の枠組みを採用するとすれば、日本と中国の現状はどうとらえればいいのだろうか。
社会変動の歴史──富永健一『近代化の理論』を読む(5) [本]

著者は人間社会の発展段階を(1)未開社会(紀元前8000年ごろ〜紀元前2000年ごろ)(2)農業社会前期(紀元前2000年ごろ〜紀元1000年ごろ)(3)農業社会後期(1000年ごろ〜1600年ごろ)(4)近代産業社会前期(1600年ごろ〜1900年ごろ)(5)近代産業社会後期(1900年以降)に分類する。
そのうえで、(1)家族・親族(2)組織(3)地域社会(4)社会階層(5)国家と国民社会からなる社会構造を、それぞれ発展段階ごとに変動の様相をとらえようとしている。その変動は一括して社会変動と呼ばれる。
(1)家族・親族の変動
人間社会に通底するのが家族・親族である。どの発展段階でも、家族・親族なしに人間社会は成り立たない。
未開社会では、家族の血統のたどれる親族集団が氏族を形成し、狩猟、労働、防衛、相互扶助、祭祀などの機能を一体的にもつ生活共同体を維持していた。だが、社会が発展するにつれ、そうした一体的機能は次第に分化し、親族の全体的機能は解体・縮小されていく。
農業社会の前期はメソポタミアやエジプトからはじまり、ギリシア、ローマにいたる。後期は中世ヨーロッパがその典型である。
ギリシア、ローマは家父長制の時代だ。
「家父長権は父から男の子へと伝えられ、家父長たるものは家系を絶やさぬように、家の祭祀と家産を管理する責任を先祖に対して負っていたと同時に、家成員に対して絶対の権力をもっていた」
とはいえ、古代ギリシアは長子相続制ではなく、家父長である父が死ぬと均分相続がおこなわれていた。
中国の「家」も、基本的に家父長制だといってよい。家長が死ぬと、男の兄弟だけが均分相続で家産をもらい受けた。しかし、数代にわたって、家産を分けないまま一つの家が持続されることもあったという。そうした大家族を形成するのは、大資産をもつ上層階級だった。
中国では宗族という親族集団があった。宗族が家父長制家族と併存したことが、西洋とは異なる中国の特徴だという。
日本では「家」は家長の直系家族が受け継いだ。その家長権は「嗣子」によって継承される。嗣子のみが家督を相続し、嗣子以外の傍系(次男、三男など)は家から離れなければならない。しかも分家でないかぎり、家産の分与にあずかれなかった。
家父長制は農業社会段階の産物であり、その眼目は土地の相続である。本家と分家は依存関係でしか成り立たないことが多く、本家と分家が同族集団を形成する。東北地方などではこうした同族集団が昭和10年代まで残っていたという。
(2)組織の変動
組織は近代の所産である。未開社会では組織らしきものはない。とはいえ、近代以前でも組織らしきものはあった。
農業社会になると国家が発生し、ある程度の行政事務をおこなう統治組織がつくられる。
古代ギリシアには武器や靴、衣類、家具などをつくる「エルガステリオン」と呼ばれる作業所があった。古代ローマでも、鉱山や大農場などが経営されている。その所有者は個人もしくは団体で、実際の仕事を担っていたのは奴隷だった。
しかし、中世になると、そうしたものはなくなり、農業にしても商業にしても、農家や商家、職人の家による自営業形態をとるようになる。家族が同時に経営体でもあった。そこではしばしば経営上の必要から非親族者が家のなかに迎えられた。日本では奉公人や丁稚、徒弟などがそうした存在にあたる。
近代にいたって株式会社が発生する。それに先立ち、中世にはソキエダスやコメンダと呼ばれる会社形態が生まれた。
最初の株式会社はオランダの東インド会社、つづいてイギリスの東インド会社である。これらはみな貿易会社だったが、産業革命をへると、株式会社が産業資本のかたちをとるようになる。その前駆的形態が問屋制前貸やマニュファクチュアだった。
産業革命はマニュファクチュアを近代的大企業に発展させる契機となった。株式会社制度と工場システムが結合され、官僚制的な組織が導入されることになった。
しかし、産業社会後期になると、情報産業やサービス産業、ハイテク産業が盛んになり、臨機応変に対応する機動性が求められるようになる。官僚制的な組織原理に代わって、新たな組織原理が必要になってきている。
(3)地域社会(村と都市)の変動
都市と農村が生まれるのは、農業社会になってからである。
古代ギリシアやローマの都市国家では、市民は農村の不在地主にほかならなかった。
といっても、古代における都市の形態は多様であり、スパルタとアテネはかなりちがう。スパルタの市民は重層歩兵団として、たえず軍事訓練に従事しなくてはならなかった。これにたいしアテネでは、とくに手工業が発達し、市民のなかには自作農民や商工業自営業者も含まれていた。
古代ギリシアでは小麦とオリーブが主要作物で、不在地主の所有する土地を奴隷が耕作していた。ギリシアの都市は基本的に軍事都市で、ポリスの周辺に広がる農村がこれを経済的に支えていた。
古代ローマの都市も農村地主によってつくられた。ギリシアのポリスとのちがいは、都市在住者が土地所有貴族と平民に分かれていたことである。貴族は門閥氏族の成員で、官職を保持し、戦場では将校として指揮をとった。これにたいし、平民は土地ももたず、手工業や商業に従事し、戦場では重装歩兵団を形成した。
しかし、ポエニ戦争後、ローマでは重装歩兵団が解体され、ゲルマンの傭兵隊が軍事をになうようになる。さらに共和制末期になると、ラティフンディウムと呼ばれる大土地所有制が進み、奴隷制による大農場経営と小作人が生みだされた。
西ローマ帝国の滅亡により、中世がはじまると、ゲルマン社会が農業社会の中心となった。古典古代が都市国家の時代だったのにたいし、中世は荘園領主が農村に居住し、農民を支配する村落優位の時代になった。ゲルマン社会は本来まったくの村落社会だったが、それでも12世紀ごろから都市が生まれるようになった。
中世の都市が古典古代の都市とことなるのは、それが、みずから手工業や商業を営み、村落に土地をもたない人びとによってつくられた自治団体だという点にある。古典古代では、都市が農村を支配していたのにたいし、中世では都市と農村の関係は対等で、市場をとおして相互に結びついていた。
中世の都市では、商工業者がギルドやツンフトのような同業団体を結成していた。こうした同業団体は氏族や奴隷とも無縁であり、その点、より近代に近づいていた。
いっぽう、中世の村落では、土地を私的に専有する農民が、家族で自営的な耕作をおこなっていた。その土地は、宅地、庭畑地、共同耕地、共有地、森林からなり、それは世襲的に相続されていた。農民は農奴と呼ばれているものの、村落共同体の成員として、村落共同体が総有している共同耕地や共有地、森林の分け前にあずかっていた。
封鎖的な村落共同体は、交通関係が発展するにつれ、次第に開かれたものになっていく。近代化・産業化とは、「都市の都市度を高め、村落の村落度を低める過程」だった、と著者はいう。こうして、社会関係の開放性が進み、都市と村落とのあいだの社会移動が増えるにつれ、いよいよ近代がはじまることになる。
(4)社会階層の変動
社会階層が生じるのは社会的資源の分配が不平等だからである。未開社会は比較的に平等社会で、不平等が高まるのは農業社会にはいってからだ。
西洋の古代は、土地所有者階級と奴隷が存在した。ギリシア、ローマは征服国家で、戦争は土地の取り合いを意味し、奴隷は戦争の産物だった。この時代、農業と手工業はほとんど奴隷に依存していた。
東アジアでは奴婢が存在し、賎民として扱われていた。インドにはカーストがあり、シュードラが賎民だった。かれらはアーリア人に征服された民族の末裔と考えられる。
中世は身分制社会で、支配者の封建領主が土地を領地として支配し、土地を通じて農民を支配していた。家産制と封建制が、その主な形態だ。
家産制では、中央に専制君主がいて、そのもとに家臣団がいる。王は家臣に土地と人民を管理させ、そこから貢租を収めさせ、家臣には官職に応じてフリュンデ(秩禄)を与える。
これにたいし、封建制では地域ごとに小規模領主が根をおろし、中央の王の力はさほど強大ではない。それでも領主は安全確保のため王に保護を求めて、王と封臣関係を結び、王は封臣となった領主の土地を保証するという関係を保った。
家産制では君主の力が強いため、国内の富が君主に集中し、人民の側に富が蓄積されにくい。これにたいし、封建制では、君主に富と権力が集中せず、人民の側に富が蓄積され、近代化・産業化の素地がつくられていく、と著者はいう。
近代社会は17世紀のヨーロッパにはじまる。ルネサンス、宗教改革、地理上の発見がその出発点だ。とりわけフランス革命が近代化を切り開いた。サンシモンは社会を貴族、ブルジョワ、産業者(働く人)という三つの階級から成り立つものととらえた。マルクスとエンゲルスは、サンシモンを発展させ、ブルジョワジーとプロレタリアートの対立という考え方を打ち出した。
しかし、20世紀にはいるにしたがって、ブルジョワジーとプロ李足りアートの対立では収まらない現象がでてくる。
これまでの旧中間層(農民、手工業者、小産業者、小商人)に加えて、新中間層が登場するのだ。新中間層は被雇用者という意味では労働者だが、単純肉体労働者ではなく、比較的高い教育水準や技術水準を身につけ、専門技術職や管理職などを担っていた。こうした新旧中間層の拡大によって、階級の区別は次第に見えにくくなり、むしろ階層による区分があてはまるようになった、と著者はいう。
(5)国家と国民社会の変動
未開社会に国家はなかった。国家が登場するのは農業社会になってからである。
古代ギリシアやローマは例外として、古代の国家は原則として王の専制によって成り立っていた。王のもとには行政組織があり、行政幹部は家臣団を形成していた。こうして、家産制国家の原型がつくられる。すべての土地と人民は王ひとりに帰属し、家臣団はフリュンデ(秩禄)をもらうだけである。
王のオイコス(家)が解体され、家臣団が王から独立して、一定の土地と人民を世襲的に支配するようになると封建制が成立する。
ところが17世紀に商業資本が発展し、資本主義の時代がはじまると、閉鎖的だった地域共同体は次第に解体され、国民社会が形成されるようになる。そのとき、農業社会のうえに築かれていた絶対王制は市民革命の挑戦を受け、貴族も支配層としての地位を失って、王制は次第に形骸化、もしくは廃止されるようになる。
こうして近代国家が生まれる。近代国家がそれ以前の国家と異なるのは、第1に国民社会を下部構造にもつ国民国家であること、第2に立法・行政・司法の組織をもつ主権在民の国家であること、第3に多くの機能集団や組織、地域社会を内包する国家であることだ、と著者はいう。
しかし、近代産業社会が後期段階にはいると、国家はこれまでにない新たな対応を迫られるようになる。それは失業、疾病、災害、高齢化などに対応する社会保障、コミュニティの維持、福祉国家の推進、さらにはグローバル化だという。
いまも社会構造は変動しつづけている。
社会変動論──富永健一『近代化の理論』を読む(4) [本]

社会構造論と社会変動論は重なりあっている。社会構造論が空間軸に沿った記述だとすれば、社会変動論は時間軸に沿った記述だ、と著者はいう。
社会変動とは社会構造の変動である。社会変動は長期にわたる変動であり、現在の社会構造を構成する家族・親族(基礎集団)、組織(機能集団)、地域社会(村落、都市)、社会階層、国家と国民社会が、そのなかでどのように変動してきたかをとらえる。
[社会の成長、発展、進歩]
社会は成長、発展、進歩するといわれる。
社会成長は健康、栄養、住居、教育、医療、生活の質、社会保障などの指標がどのように改善されているかを示すものだ。残念ながら、経済のGDPのように、社会全体の状況をあらわす単一指標はない。
産業化の進展とともに、上に挙げたような指標は上昇し、しだいに水平に近づいていく。その一方で、産業化が環境汚染やアノミー化、離婚、犯罪などを促進している側面もあるから、社会成長はどこまでもプラス方向に進むとはかぎらない、と著者はいう。
社会発展は社会システムの質的な変化を指している。著者によれば「社会成長と構造変動とがあいともなっている社会変動を社会発展と呼ぶ」。そして、社会成長と社会発展は社会進歩ととらえることができるという。
しかし、社会はかならずしも常に成長、発展しつづけるわけではない。社会の停滞はよくみられる現象だ。戦争や天災が生じれば、社会が退行することもある。とはいえ、社会退行がどんどん進んで、文明社会が未開社会に戻ってしまったという事例はかつて歴史上ないという。
これとは別に社会進化という言い方もある。社会進化とは未開社会から近代産業社会にいたる発展を進化としてとらえる考え方で、これも社会変動理論の一類型だと考えられる。
そこで、著者はこれまでの近代化理論には、進歩の理論、進化の理論、発展の理論の3つの理論があったとして、これを紹介しながら、最後にこれらを統合して、みずからの考え方として価値中立的な社会変動理論を打ち出すことになる。
[近代化=進歩]
まず近代化を「進歩」ととらえる考え方。
著者は近代をつくりだしたのは西洋であって、「近代」を明示したのは西洋の思想家だと明言する。
封建時代の旧守的な態度からは、進歩の考え方はでてこない。儒学やキリスト教も同様じだ。しかし、西洋では宗教改革がおこり、合理主義と実証的な近代科学をよしとする啓蒙主義が広がっていった。そこからは世代的継続を通じての進歩という発想が生まれた。
フランスのサンシモンとコントは実証主義を唱え、イギリスのロック、バークリー、ヒュームは経験主義哲学をつくりあげた。ともに神学、形而上学を排除する知識哲学だった。重視されたのは、誤りを一歩一歩ただしていく態度であって、進歩はそうした検証から生まれると考えられた。
コントによれば「人間の進歩という合理的な考え」を最初に定式化したのはパスカルだったという。さらにパスカルの考え方を発展させたのが、コンドルセーだ。コンドルセーは、偏見とか迷信といった非合理的なものを取り除き、理性の力を増大させ、自然科学、社会科学を学び、さまざまな技術を開発していくことこそが、文明を進歩させる原動力だと考えていたという。
[近代化=進化]
次に近代化を「進化」ととらえる考え方。進化は内容的には進歩と異なるわけではなく、進歩を環境にたいするより高度な適応と考えたところに思想的な意義があるという。最初に社会進化論を唱えたのはスペンサーだ。人間社会は分業によって進化する。スペンサーは、社会は有機体であって、構造分化によって機能を高め、軍事型社会(個人は国家のためにある)から産業型社会(国家は個人のためにある)に向かうという明るい展望をえがいた。
人類学の分野で社会進化論を唱えたのはモーガンだ。モーガンは人類社会が未開社会から現在の進化した文明にいかに到達したかを明らかにするために、未開人と思われるイロクォイ族の調査研究をおこない、『古代社会』を著した。モーガンは人類の進化を野蛮、未開、文明の3つに分け、原始乱婚から一夫一婦制にいたる6段階の婚姻の進化図式を示した。しかし、いまでは原始乱婚説はマリノフスキらによって否定されているという。
こうした西洋文明社会を絶対的な基準とする単線的な社会進化論は、現在では支持を失っている、と著者は明言している。
[近代化=発展]
これにたいし、近代化をより客観的に「発展」としてとらえる考え方がでてくる。価値中立的に近代化を状態Aから状態Bへの移行としてとらえる考え方だ。その場合、社会が質量両面において、より高次なものになっていくことが想定されている。
社会発展とは、社会が伝統的形態から近代的形態へと移行することを意味する。それは「科学革命・精神革命・技術革命・産業革命・市民革命などのすべてを包含した、多方面にわたる変動の総合的産物」であって、著者はそれを一括して「社会構造の変動としての近代化」と名づけている。
テンニェスは、こうした社会変動を「ゲマインシャフトからゲゼルシャフトへ」と言い表した。しかし、著者によれば、それは「ゲマインシャフトとゲゼルシャフトが未分離である状態から、ゲマインシャフトとゲゼルシャフトが分離している状態へ[家族と組織の分離]」へと言い直すべきだという。いずれにせよ、近代化にあたっては、村落共同体的な社会関係が壊れて、損得と取引とビジネスの世界が誕生したことは疑えないだろう。
いっぽう、ウェーバーは支配の社会学の観点から、近代化を「伝統的支配から合法的支配へ」の移行としてとらえた。伝統的支配は家父長的支配を典型としていた。それは王を家父長として、王にひたすら仕える社会である(家産制)。これにたいし、封建制はそれぞれの地域を世襲的に領有する領主が中央の王と封臣関係を結んで安全を保障してもらう制度だ。だが、家産制も封建制も伝統的支配であって、ウェーバーは近代社会ではこうした支配のかたちが崩壊して、法による支配が原則となるととらえた。
[構造―機能―変動理論]
著者はこうしたさまざまな近代化論を紹介したうえで「構造―機能―変動理論」なるものを打ちだしていく。この理論はパーソンズの構造―機能理論を発展させたものだという。そのもととなるのはスペンサーとデュルケームの考え方だ。
機能の変化は構造の変化と結びついている。たとえば企業が生まれるなどして社会構造が変化すると家族の機能も変化していく。
人は状況に応じて、社会システムの構造を変化させることができる。それによって古代の専制政治が封建制になり、封建制が近代資本主義になっていく。要するに構造変動が起こることが人間社会の特徴だという。
機能的要件が満たされなくなると、諸個人はシステムの現行の構造に不満をもつようになり、何らかのアクションを起こす。しかし、そういう動機が生じない場合は社会システムは安定している。すなわち構造―機能―変動の動学は均衡(平衡)状態にある。
社会変動、すなわち古い社会構造から新しい社会構造への移行過程を理論化して、著者はこう述べている。
〈以上の考察から、次のことが明らかです。すなわち、社会変動は、当該社会システムにおいて、多くの成員が現行の構造のもとで機能的要件が十分充足されていないと思っており、したがってシステム内部に現行の構造を変えるような行為を始動する動機づけが充満するようになると、システムの均衡は崩壊します。システムのそのような現状を認識した成員たちは、新しい均衡を実現することのできる新しい構造を求めて、さまざまな試みをはじめます。それらの試みにはきわめて多くの変異があり、そして最終的にはその中から一つのものが選択されて、新たな構造への収斂が帰結するようになることで、一回の構造変動は収斂するのです。〉
社会変動を促すのは、個々人の欲求水準であり、ひいては国民規模での欲求水準である。徳川幕府から明治政府への体制転換も、この理論によって説明できるという。
こうして社会変動の一般理論をかたちづくったうえで、著者はそれを歴史の発展段階にあてはめていくことになる。
著者によれば、その発展段階は(1)未開社会(紀元前8000年ごろ〜紀元前2000年ごろ)(2)農業社会前期(紀元前2000年ごろ〜紀元1000年ごろ)(3)農業社会後期(1000年ごろ〜1600年ごろ)(4)近代産業社会前期(1600年ごろ〜1900年ごろ)(5)近代産業社会後期(1900年以降)に分類できる。農業社会前期が古代、後期が中世、近代産業社会前期が西洋の近代、後期が現代にあてはまることはいうまでもないだろう。
次回は発展段階ごとの社会変動を扱う。
近代の社会構造──富永健一『近代化の理論』を読む(3) [本]

著者は近代産業社会の社会構造を家族、組織、地域社会、国家の順に並べて論じている。この順は小さな(ミクロ)レベルから大きな(マクロ)レベルへと並べたものだといってよい。さらに、社会階層は全体社会からみた人間の階層(階級)分類である。社会構造はいわば縦軸と横軸からみた社会集団の組み合わせによって形成されている、というのが著者の理解である。
近代産業社会の構造は、しかし、いきなり生じたわけではない。それには未開社会から古代、中世、近代にいたる長い歴史があるのだから、それを無視するわけにはいかない。むしろ、これまでの経緯を踏まえることによって、近代の社会構造の特質が明確になってくる。そこで、著者は社会集団の分類にしたがって、個別に分析を加えていく。
[家族と親族]
まず取りあげられるのが、いわば現代社会の「基礎集団」というべき核家族である。核家族は夫婦(あるいはどちらか)と未婚の子どもからなる家族を指すが、こうした家族形態は近代特有のものである。
古くから家族にはいろいろな形態があった。しかし、いつの時代も家族が親族の一部として成り立っていることはまちがいない。夫婦にはそれぞれ親や兄弟がいて、その親にも親や子がいてという親族関係は、その当人を起点として、集団としての大きな広がりをもっている。
未開社会においては、共通の祖先をもつ家族が、族外婚を通じて氏族社会を形成していた。しかし、農業社会になると、氏族ではなく家父長制家族が中心になる。
大家族、小家族、複婚家族、複合家族、未分家族、家父長家族、直系家族など、家族の形態は実に多様である。だが、重要なのは近代産業社会では、家族が核家族と呼ばれる形態に収斂されてきたことだ、と著者はいう。
家族が核家族の形態をとるようになった理由は、近代産業社会では、家計と企業が分離されたからだ。近代以前においては、農業だけではなく、商業や工業も家族で営まれていた。しかし、家計と経営が分離されると、家族の経済機能はおもに消費になっていく。さらに幼稚園と学校などでの教育が普及すると、家族の教育的機能も補助的なものとなっていく。氏族のもつ政治的権力や祭祀的機能も失われていった。さらに農村共同体が解体すると、親族の相互扶助機能も失われた。
しかし、核家族が中心となった家族そのものが解体することはない。夫婦の愛情、家計、子育てといった家族の役割はほかに代替できないし、核家族は共同性の中心として、これからも持続していくと著者は断言する。
[組織(企業など)]
近代産業社会を切り開いたのは組織、とりわけ企業だといってよい。企業をはじめとする組織は「特定の機能を達成することを目的として」つくられた社会集団である。こうした組織は近代化・産業化によって誕生した。
機能集団としての組織は、支配関係と分業によって成り立っている。分業とは労働の分割と配置にほかならず、その目的は組織の効率を高めることにある。さらに組織は支配関係を組みこむことによって、命令により目的達成を促進する機能を有している。
組織の役割は「合理性すなわち目的達成における効率性を追求すること」にある。こうした合理性は、組織(企業)と家族(家計)が分離されることによって生まれた。社会学的にいえば、ゲマインシャフトからゲゼルシャフトが独立したということになる。
近代産業社会においては、組織は常に競争関係におかれている。そのため組織は外からの刺激によって、たえず合理性を追求する努力を強いられているといってよい。
企業は刻々と変化する市場に対応しなければならず、そのために組織をどうつくりあげていくのが合理的かを問われている。
もう一度まとめてみよう。近代産業社会の構造は「一方で家族(ゲマインシャフト)と企業(ゲゼルシャフト)が分離し、他方で企業が市場の中の無数の小島として大海の中に浮かび、しかもこの市場が家族と企業をつないでいる」という図式によって理解することができる。これが著者のとらえ方である。
[地域社会]
地域社会は社会集団ではなく、政治的に分けられた一定範囲の領域を指している。村落と都市が地域社会を形成している。
村落の特徴は社会関係が封鎖的に集積していることだ、と著者はいう。村落の産業は農業だけとはかぎらない。林業や漁業もあり、まれに工業がある。産業化と近代化が進むと、村落の封鎖性は解体され、次第に村落らしさは失われていく。
歴史的にみれば、村落がつくられたのは中世の農業社会においてである。村落は自給自足が原則であり、そのかぎりにおいて、村民にとって村落は全体社会だった。
日本では1930年代でも村落共同体が残っていた。農業機械や化学肥料、テレビ、自動車などが農村にはいるのは、1955年以降の高度成長期である。それ以降、村落の封鎖性は次第に崩れていった。
いっぽう、都市の特徴は社会関係が開放的だという点にある。都市は結節点だ。人は都市に流入し、都市から流出する。都市の産業は非一次産業、つまり二次産業ないし三次産業である。これは市場があってはじめて成り立つ産業だ。さらに人口規模と人口密度が大きいこともが都市の特徴といえるだろう。
都市は古くから存在した。古代において、都市は政治都市であり、消費都市でもあった。中世では商人や手工業者が都市を形成した。しかし、そのころ巨大都市はできず、社会全体は村落的な性格を色濃く残していた。日本でも徳川時代に江戸や大坂のような大都市が出現したが、それ以外の町はちいさく、人口数万程度にとどまっていた。
だが、産業化と近代化が次第に都市の「都市度」を高めていく。企業や官庁、学校、その他のサービス機関が、都市に人口を吸引する役割をはたしていった。その結果、現在、先進国では、人口の8割以上が都市に住むようになっている、と著者は指摘する。
[社会階層]
人間の社会はこれまでずっと不平等社会だった。ここで著者は社会構造論にいわば垂直的な軸を導入しようとしている。
政治権力や経済力、文化力などの社会資源は、いつの時代も共同体の成員に均等に与えられているわけではなかった。不平等の度合いが高まったのは農業社会にはいってからである。古代ローマなどでは、大土地所有者である地主が奴隷を使役しながら農場を経営していた。中世においては、土地所有権をもつ荘園領主が農奴と呼ばれる農民を支配していた。これにたいし、近代産業社会では資本をもつ資本家が労働者を雇用するようになる。
農業社会における領主と農民の区別は身分と呼ばれ、産業社会における資本と労働者の関係は階級と呼ばれる。
しかし、近代産業社会が進展するにつれて、階級に代わって社会階層という新たな概念が登場すると著者はいう。固定的な身分や階級とちがい、社会階層は流動的で、その地位は世代間で移動する傾向をもつ。
近代産業社会が進むにつれて、人が他者と競争しながら、職業や所得などの社会的地位を求めるという経歴パターンが生まれるようになった。こうした地位達成過程が開かれたことが、これまでの階級とは異なる社会階層概念が生まれるようになった理由だ、と著者はいう。
[国家と国民社会]
最後に登場するのが、国家という概念である。国家は社会を包摂する。国民社会というのは国家のもとで国民的な広がりをもつ全体社会を指しているという。
日本において国民社会が形成されたのは明治以降だ、と著者は書いている。それまでは封建制のもとで領国が形成され、日本全体が国だという意識は希薄だった。国民社会のもとで、はじめて村落共同体の封鎖性が解体され、全国的な規模での資本主義市場が形成されていく。近代化、産業化とともに都市化が進展する。
国民社会が成り立つのは、国家が存在してこそである。しかし、国家と社会は相互依存関係にあり、国民国家は国民社会があってこそ成り立つ、と著者はいう。
国家の形態は多様である。古代エジプト、古代ギリシア、ローマ帝国、秦漢帝国以来、国家は人間に欠くことのできないものとして存在してきた。
著者によれば、国家とは「一定領域の土地を領有しそこに居住している人びとを支配している統治機構である」。そして、国民とは「一定領域の土地の上に居住して、原則として同一の民族に属し、言語と文化を共有し、立法・行政・司法の統一組織を有する人びと」のことである。
近代の国民社会の上に形成されるのが国民国家である。しかも、現代においては、この国民国家が福祉政策を実施することがとうぜんとみなされるようになった。
この国民国家がグローバルな国際関係のなかに置かれていることはいうまでもない。しかし、いまのところ、国民社会に対応する世界社会という社会システムがすでに構築されているわけではない、と著者は指摘している。
近代産業社会の社会構造──富永健一『近代化の理論』を読む(2) [本]

ぼく自身はばくぜんと、社会とは人間集団の共同体を指すと考えている。国家は社会を包摂する政治組織体にほかならないが、外的にみれば、それ自体、ひとつの共同体であるという面で、ひとつの社会だとみることもできる。
国家と社会は別の存在だが、社会をくるんでいるのは国家であって、社会が国家をくるんでいるわけではない。とはいえ、国家は社会によって支えられており、社会と国家の関係にはつねに緊張感がある。
国家は革命や併合(征服)、分裂によって生成・消滅することはあっても、国家そのものが消滅することはない。こうした考え方は滝村隆一に由来するものだ。
こんなことを考えはじめると、頭がこんがらがってくる。
日本では明治以前に「社会」ということばはなかった。
社会は翻訳語で、福地源一郎がsocietyを社会と訳した。それらしいものをそれまで日本人は「世の中」とか「世間」と呼んでいた。
しかし、社会という翻訳語が登場すると、社会はたちまち日本人のあいだに定着していった。
著者によると、広い意味で、社会とは自然にたいして人間のつくったものを指すとされる。しかし、それではあまりにばくぜんとしている。
そこで、もっと限定的に、社会とは多くの人間によってつくられた関係のシステムだという規定がでてくる。具体的には家族、企業、学校、村落、都市、国民社会、国家などからなるシステムである。さらに、このシステムは群衆や市場、社会階層、民族、国際社会といったサブシステムをもっているという。そして、システム全体を統合するのが国家だ。つまり、国家によってつつまれている社会を研究するのが社会学であって、国家を含むその全体を社会と呼ぶなら、そのシステムは国際関係(国際社会)によって、つねにチャレンジを受けているともいえる。
著者は「社会構造」と「社会変動」というとらえ方を示しているので、それに沿って、問題を整理してみることにしよう。
「社会変動」についてはあとで論じられる。まず「社会構造」とは何かということだ。社会構造は静態的なとらえ方で、いわば社会のいまを断面的かつ抽象的に切り取ったものだ。だが、それはけっして静態的ではありえず、社会変動の波にさらされているという構図が浮かび上がるだろう。
いずれにせよ、社会には構造があるとされている。
しかし、社会構造を定義するのはむずかしい。
著者はこんなふうに言っている。
〈社会構造とは、社会を構成している次のような構成諸要素のあいだの相対的に恒常的なむすびつきとして定義されます。それの構成諸要素としては、個人行為にちかいレベル(ミクロ・レベル)から全体社会のレベル(マクロ・レベル)までいくつかの段階が区別されることになるのですが、それらをミクロからマクロに向かって順次に、役割・制度・社会集団・地域社会・社会階層・国民社会というように配置することができるでしょう。構造分析をこれらの諸段階のどのレベルで考えるかは、社会構造の概念化におけるレベルのとり方の問題であり、構造概念自体としてはどのレベルで考えるかはまったく任意です。〉
残念ながら、ぼくなどには何が書いてあるかさっぱりわからない。
要するに、社会というのは複雑なつくりから成り立っているらしいということがわかる。
その基礎になるのは家族(ミクロ・レベル)だが、そこからはじまって組織(企業や団体)、地域社会、国民社会(マクロ・レベル)にいたる結びつきがあって、社会階層という区分けも厳然とある、その全体の関係を社会構造と呼ぶ、とでも勝手に解釈しておくことにする。
社会構造を考えるには、どのレベルをとってもいい。どのレベルをとっても社会構造の全体が見えてくる。それは一種の透視画法のようなものだ。
また、社会には、決められた制度があり、そのなかで人は割り振られた役割をはたすものと考えられている。
だが、そういっただけではあまりに抽象的だ。
そこで著者は、現代のモデルと考えられる近代産業社会を取りあげて、その社会構造を分析しようとしている。
近代産業社会の特性は、機能分化、すなわち分業だ。近代産業社会は「それ以前の社会構造に比して、格段にこまかく分離した多数の構造的構成要素」から成り立っている。
とりわけ注目されるのが、家族と組織の分離だ。
封建時代においては、家族が共同生活の単位であると同時に経営の単位でもあった。それは農民でも商人でも同じで、そのとき「家」は家父長制の形態をとっていた。
近代産業社会においては、家族は経営的機能を喪失して、消費生活の単位に純化し、経営的機能は組織によって担われることになる。こうした分離は一挙に生じたわけではなく、何十年、何百年かかって起こった。これによって、家父長制家族は解体し、核家族が誕生した。
すると基礎集団である核家族と機能集団である組織(企業など)とのあいだに関係が生じることになる。そのとき家族の成員は組織の成員でもあるというダブル・メンバーシップを得ており、社会的にみればエンプロイー(被雇用者)社会が生まれたことになる、と著者は書いている。
核家族と組織は持続的な相互依存関係にあり、そこには相互交換が発生する。
具体的に、それは
労働市場
消費財市場
金融市場
社会的交換
ということになる。
労働市場において、企業は家族から労働サービスを得、家族は企業から賃金や給与を得る。
消費財市場において、企業は家族に生産物を売り、家族は企業から消費財を買う。
金融市場において、企業は家族の貯蓄から資本を借り、家族は企業から利子や配当を得る。
社会的交換において、家族は企業から与えられた地位や権力、名誉を得る。
ただし、ここで気をつけなければならないのは、家族はひとつではなく、企業もひとつではないということだ。実際には無数の家族と無数の企業があって、その関係は複雑にからみあっている。その複雑にからみあった家族と組織の関係からなる地理的なかたまりを地域社会あるいは国民社会、とらえ方によっては都市と村落と呼ぶことができる。
こうした地域社会あるいは国民社会は、地域行政組織(自治体)や国家によって統合され、税と引き換えにさまざまな行政サービスを受ける関係にある。
近代産業社会のこうした社会構造を、著者は個別の領域にわたって、さらに詳しく論じていくことになる。(つづく)
富永健一『近代化の理論』 を読む(1) [本]

本棚を整理していたらでてきた。1996年に出版された本だが、あのころ何げなく買って、例によって例のごとくの悪い癖で、そのまま読まずじまいになっていたらしい。
ぼくは研究者ではなく、学問といったものは苦手で、物語のほうが好きなので、どちらかというと理論は敬遠したい気分がある。経済学や社会学をまじめに勉強したことはない。
それでも近代化という概念については、なんとなく興味がある。
いまは近代という時代にはちがいない。その近代に半ばどっぷりつかりながらも、時折それがいやになること、別の可能性をみてみたいと願うこともしばしばだ。だから近代化にはどこか懐疑的である。年をとると、ますますそうした傾向が強まっている。
著者の富永健一(1931〜2019)は社会学者で、東京大学文学部の助教授、教授を長く務めた。主な著書に『社会変動の理論』、『社会学原理』、『日本産業社会の転機』、『日本の近代化と社会変動』、『思想としての社会学』などがある。明治の三大記者のひとりとされる東京朝日新聞主筆の池辺三山は、母方の祖父にあたるという(あとふたりは陸羯南と徳富蘇峰)。
本書はもともと放送大学の講義用テキストとして書かれたもの、「ですます」調で読みやすそうだ。社会学の知識のないぼくのような素人でもわかるかもしれないと考えて、ぱらぱらとページをめくりはじめた。いっぺんには読めないので、少しずつ読んでいきたい。
著者によれば、20世紀の前半と後半は対照的な時代だが、両者を貫通するものとして「近代化」と「産業化」というテーマがあった。それは西洋にはじまり、東洋に伝播し、いまや東洋もその担い手になっているというのが、はじめの記述だ。
産業化が出現したのは18世紀後半から19世紀前半にかけての産業革命期で、このころから生産の動力源として、「生物エネルギー(筋力や畜力)に代えて無生物エネルギー(蒸気力から電力から原子力にいたるまで)」が用いられるようになった。同時に機械化も進んでいく。
産業化にともない、経済は自給自足経済から市場的交換経済へと移行していく。さらに第二次産業から第三次産業へと産業構造が発展していくにつれ、コンピューターを軸とする「ポスト工業化」の時代がはじまる。
ポスト工業社会とは、より高度な産業化が実現した社会だ、と著者はいう。けっしてポスト産業社会ではない。農業や工業の生産性が飛躍的に高まり、より少ない人数で必要量を満たせるようになるため、第三次産業従事者の比率が増えていった。人間の頭脳的・肉体的労働は、機械(動力機械および情報処理機械・自動制御機械)に置きかえられるようになる。
「近代化」はどう定義できるのか。近代化は経済(技術)、政治、社会、文化の4つの側面で並行して進む現象としてとらえることができるという。
経済面では人力・畜力中心から動力革命・情報革命にともなう機械化へ、自給自足社会から市場的交換経済へ、そして第一次産業中心から第二次産業・第三次産業中心へ。
政治面では近代的法制度の確立、封建制から近代国民国家への移行、専制君主制から民主主義へ。
社会面では家父長制から核家族へ、未分化な集団から組織へ、村落共同体から近代都市へ、さらには身分制から自由平等の時代へ。
文化面では宗教的・形而上学的束縛から実証的知識へ、非合理主義から合理主義へ。
これらの4つの側面は、それぞれ密接にからみあいながら進行していった、と著者はいう。
近代化され産業化した社会が近代産業社会だ。そして情報化社会は近代産業社会の高度な段階ととらえることができる。
近代産業社会はひとつのモデル(理念型)であって、どの国においてもそれがそっくり実現されているわけではない。東洋では19世紀後半の日本を皮切りに20世紀後半の韓国、台湾、香港、シンガポールにつづき、中国が近代産業社会をめざすようになった。
東洋における近代化と産業化の先頭を切ったのは日本だが、それは西洋を追いかけるかたちをとった。大久保利通は殖産興業政策による「上からの産業化」を推進し、日本は明治末に世界の先進国入りをはたした。
いっぽう中国は半植民地状態となり、ようやく1912年の辛亥革命によって中華民国が成立するものの、内戦がつづいた。1949年に毛沢東による共産党政権が発足する。しかし、大躍進政策が失敗に帰したあと、文化大革命の混乱がつづき、産業化が軌道に乗るのは、鄧小平が対外経済開放政策を打ち出してからだ。
近代化と産業化が中世から自生した西洋とちがい、東洋がいわば普遍的課題である近代化と産業化を受け入れるには意識的な努力を必要とした。
しかも、ヨーロッパの近代化は植民地化をともない、それによる西洋文明の伝播というかたちをとったから、植民地化の危機にさらされた東洋にとっては、西洋文明を受け入れるのは苦渋の選択だった。
日本では倒幕による王政復古というかたちをとったうえで、はじめて近代化と産業化を導入することができた。それはけっしてそのままの西洋化ではなかった、と著者はいう。
〈文化伝播に模倣の要素が含まれていることはたしかですが、しかし文化伝播というのはけっして単なる模倣、つまり「オリジナル」の「コピー」をつくることを意味するものではありません。とりわけ大切なのは(1)文化伝播は選択的な受容である、(2)文化伝播は受容した諸文化項目をもとのものとはちがう文脈の中に移植するのにともなう適応問題の解決を必要とする、という二点ではないでしょうか。これらのことはそれ自体、創造的な能力が要求される課題です。そのような創造的な能力を発揮することができるならば、文化伝播を受容しても、文化のアイデンティティをたもつことは可能なのではないでしょうか。〉
日本は文化的アイデンティティを保ちながら、みずからもつ創造的な能力にもとづいて、近代化と産業化を受け入れることができた、と著者は指摘しているようにみえる。
しかし、そのかん、日本は西洋排斥と西洋崇拝のあいだを揺れ動いた。西洋主義の波とナショナリズムの波が常に入れ替わるのが日本の特徴だ、と著者は書いている。中国が台頭するなかで、その様子はいまもっと複雑になっているといえるかもしれない。(つづく)



