竹田青嗣『欲望論』を読む(6) [思想・哲学]
根気がなくて、なにごとも途中で投げだしてしまうのが、ぼくの欠点である。本書も難解なあまり、ついつい途中で断念ということで終わってしまいそうだ。しかし、せっかく買ったのだから、時間はかかっても(たとえ断続的にでも)、なんとか読み切って、多少なりとも理解したいのが人情だろう。
いま読んでいるのは、とりあえず2巻のうち第1巻の半分を越したあたり。まだまだ先は長い。前途多難というべきか。
まず、「神も輪廻も存在しないということになれば、思考は何に向かうべきか」と著者は問うている。神なき時代に、何か確信をもちたいという気持ちはよくわかる。
ここでは、世界において意味と価値が発生するのは、欲望−身体の関係性によってであるということが論じられている。言い換えれば、世界に意味と価値を与えるのは、神でも世間でもなく、何かをしたいと思っている私自身であるということ。
神なきあとの哲学が、神に代わる絶対者の探求、もしくは人間存在の理念化に向かったことはよく知られている。これに真っ向から反対したのがニーチェだというのは、意外の感もある。著者によれば、ニーチェは「超越化」に反対し、「人間の価値の本質を、われわれの現実存在、肉体や身体の現実性に定位して問い直すこと」を求めたという。
19世紀半ばに発生した新カント派は、価値の普遍性を打ちだし、事実ではなく本質の探求に向かった。価値はより低いものからより高いものへと分類された。なまの生活世界、世俗世界、自然世界は価値が低いとされ、「超越的な本質世界」が目指されることになる。これもまた聖なる価値へと上向する本体論にほかならない、と著者はいう。
重要なのは、ニーチェとフッサールの哲学的ラディカリズムに立ち返ること。先構成された(すなわち前もって与えられた)価値や歴史から意味を説くのではなく、欲望―身体の関係性から生成される意味と価値から、「先構成的諸観念の捏造」を暴露する(本体論を批判する)ことだ、と著者はいう。
さらに重要なのは、現代の懐疑論を克服することだ。
分析哲学とポストモダン思想は、論理的相対主義を武器にして、普遍的認識の可能性を否定する。この構図は基本的にゴルギアスの懐疑論と変わらない、と著者は論じる。
前期ウィトゲンシュタインの場合は、論理学において、意味を数学化し、記号=意味の同一性を実現しようとした。しかし、この試みは錯誤でしかなかった。なぜなら、「言語記号の本質はまさしくそれが意味の多義性を含むという点にあるからだ」。
意味の数学化は、ある意味で、特異な作業をともなう。著者によれば、「あらゆる概念は本来多義性をもつが、数学化はこれに厳密規定を与えて一つの客観的な記号の体系、誰もが絶対的に同一の仕方でしか操作し得ない記号の体系へと置き換えるのである」。
しかし、後期ウィトゲンシュタインは懐疑論の立場を強める。言語が多義的であることに立ち戻り、言語によって、現実を再現するのは不可能であると考えるようになる。
つぎにデリダについて。
著者はデリダを「現代のゴルギアス」と名づけている。デリダは「今」はそれ自体として存在しないという。「今」と呼ばれるものは「過去」「今」「未来」といった差異の運動のなかでしか存在しない。厳密な同一性なるものは存在せず、いっさいは差異である。その差異の運動をデリダは「差延作用」と呼ぶ。
しかし、これは相対主義的懐疑論であって、相対主義では本体論、すなわち形而上学を解体できない、と著者は主張する。いくら今はないといっても、人にとって、今という時間があることは否定できない。同一性にたいして差異を主張するだけでは、時間が何であるかを示すことはできない。差異の哲学は、たえざる変革への志向をもつが、そのことによって、力がすべてを決定するという現実論理に対抗するすべを失ってしまうのではないか、と著者はいう。
「現代思想は原理の思考を、つまり思想の正当性や普遍性を問う思考それ自体を放棄し、まさしく否定神学的な、あるいは寓喩−説話的な預言者哲学をつぎつぎに生み出した」
そうした預言者的哲学を展開したひとりがドゥルーズだ、と著者は考えている。
ドゥルーズは、あらゆる事象の根源に「反復としての差異」が存在するという。すなわち反復しつづける差異。世界が硬化し死に向かわないのは、つねにそこにみずからを刷新する運動性があるからだ、とドゥルーズは考える。
ヘーゲルの絶対精神にたいして、ドゥルーズは絶対差異を唱える。その底には、世界にたいして永遠に異議を唱えつづける懐疑論的相対主義がある、と著者はいう。「ここにあるのは、秩序=反動性に対する反秩序=能動性というイメージ上の対抗にすぎ」ない。「ここでの思考は先行者を包括して新しい原理へと超え出ようとするのではなく、理念的対立をこととする預言者的哲学へと退行している」。すなわち永遠の抵抗。
ドゥルーズにはベルクソンに似た時間論もある。ベルクソンは精神の本質を「記憶」の概念で示したが、ドゥルーズはこれを「反復」と「差異」の概念に置き換える。現在は「習慣のうちを生きること」であり、未来は「たえざる革命へと向かう精神」の繰り返しと位置づけられる。「ドゥルーズでは、『未来』とは、一切を革新し、刷新し続ける革命への『希望』と『要請』を表現する理念となる」。
ドゥルーズによれば、この差異化の動きは秩序や制度によって、否定され歪曲される運命にある。そのため、差異の哲学はある局面で「革命」の哲学へと移行する。しかし、その哲学は社会制度の構想を禁じているため、終末論的絶望とシニシズムに彩られた、出口の見えない反抗に終始する、と著者は批判する。
著者は、分析哲学やポストモダン思想に否定的だということができるだろう。
ここからは、意味に関する考察に移る。
まず意味の同一性は成立するかという問題。
意味の同一性は、言語による正しい表象が実現するか、言語による正しい伝達がなされるか、さらにはそもそも普遍的認識なるものがあるのかにかかわっている。
現代哲学はいずれも同一性はないという論理に帰着する。しかし、同一性についての問いは、そもそも本体が存在するかいなかという議論であって、本体がないということになれば、問いそのものが消滅するのだ、と著者はいう。
問題は同一性という概念の本質をいかに考えるかということなのである。
〈「意味」を言語あるいは記号に担われるものと考えるかぎり、言語あるいは記号の「意味」は、対象あるいは認識との「一致」すなわち「一義性」を確定されえない。……「意味」の本質の問題を解明するには、意味の問いを論理学的地平から引き離し、意味の本体論を解体して、これを現象学的−欲望相関的意味論の地平へと差し戻さねばならない。〉
同一性が存在するかいなかと考えるから、おかしくなるのだ。同一性は欲望−身体に相関して現われるとみるべきだ、と著者はいう。
もう一度考えてみよう。数学的概念においては、同一性は成立する。
いっぽう、言語は本質的に多義的な意味の集約にほかならないから、言語によって、対象を一つの意味に還元することは不可能である。これは論理学的には正しい。
とはいえ、言語の実際の場を考えれば、問題はそこに同一性が成立するかいなかということではなく、どのような間主観的な共通了解が成立するのかということだ、と著者は論じる。
感覚の同一性があるかどうかも、なかなか困難な問題である。とはいえ、感覚においても同一性が成立しないわけではない。たとえば人は同じ音楽、同じ顔を一瞥のうちに同定する。そうした情動性の質は比喩によってしか表現し得ない。言い換えれば「感覚的事象の同一性の規定は、『情動の同一性』以外の根拠をもたない」。したがって、「人間間の関係感情の本質を把握するには、主体と対象との間のエロス関係の本質を捉えねばならない」ということになる。つまり、感覚的事象についても、実存的な欲望−身体の関係性からそのあらわれ方を把捉しなければならない。
著者によれば、言語は言語のやりとり、すなわち無数の「言語ゲーム」のなかで成立し、そこには人間どうしの「関係的企投行為」が横たわっている。言葉はそれを媒介的に「代行―表象」しているにすぎない。
後期ウィトゲンシュタインの功績は、「言葉を用いて語り合いつつ生きるということ、そのことが人間にとってもつ意味の核心は何であるのか」を問うたことである。そこから、次のことが明らかになる、と著者はいう。
〈「言語ゲーム」は人間の実践的要求−応答ゲームにおける関係的意味生成に基礎をおき、言語の意味はこの実践関係としての「言語ゲーム」に基礎をおく。〉
人と人の関係を抜きにして、言語は成立しないということだ。
ところで、人を含む動物は対象の存在とその意味−価値を一瞥のうちに把捉するものだ。これを可能にするのが直知的知覚である。直知的知覚が主体のそのつどの欲望−関心に相関していることはいうまでもない。
人にとって、身の回りのものはすでに一般対象意味をもったものとして現出している。と同時に、それは私にとって利用可能性、用途性をもったものでもある。その点でいえば、言語は、「われわれの生の実践的関係のうちで生成する意味の一般痕跡にすぎない」。
身体行動は単なる機械的メカニズムの連鎖によって動いているわけではない。そこには「何らかのエロス的力動の発現、情動、衝迫、目的性の生成、企投的努力、といった諸契機が存在する」。
高度な生き物は視角や聴覚、嗅覚といった「遠隔知覚」をもっており、これによって対象との距離や方向性を保ったまま、対象を認知することができる。
〈生き物が遠隔知覚によって「世界」を空間性・時間性の構造として分節すること。このことこそは、「生世界」が意味と価値のたえざる生成の世界であることの根源である。〉
言語が生動するのは、こうした生世界において意味(ノエマ)と価値が生成されているからである。
生き物が生きるためには外界からエネルギーを取り入れなければならない。そのためには対象を瞬時に認知し、対象に企投するプロセス(衝迫、目標、判断、行為、努力)が必要になってくる。対象の直知的把握が意味をもたらす。意味は実存的範疇である。
意味(ノエマ)の本質は、対象を身体−欲望相関的に把握することである。意味は対象にたいする実存主体の当為において発生する。価値は「対象が指し示すエロス的可能性の強度の了解」であり、「対象が用在性としてもつ『価値』」である。
世界が意味と価値の秩序として生成するのは、生の意識のうちに欲望―衝動が到来することによってである。そして生成する世界から、存在としての世界が間主観的に構成される。
〈「価値」は質的強度の秩序であり、「意味」は目的にいたる優先性や順序性の秩序である。主体における「われ欲す」が発動してはじめて、世界は当の対象をめぐる意味と価値の秩序となる。……この意味と価値の生成の地平においては、「世界」は、「本体としての世界」が決してもちえない絶対的起点と終末、その根源と限界をもつ。〉
人間は「実存世界」と「客観世界」という二重性の世界性のなかで生きている。実存世界が、いわば自身にとっての世界であるのにたいし、客観世界とは「間主観化された一般性の世界」にほかならない。
この世界のどちらが真実かを問うのはばかげている。両方は支え合って世界を構成している。しかし、普遍性はいうまでもなく「客観世界」に求められるべきだろう、と著者は記している。
いま読んでいるのは、とりあえず2巻のうち第1巻の半分を越したあたり。まだまだ先は長い。前途多難というべきか。
まず、「神も輪廻も存在しないということになれば、思考は何に向かうべきか」と著者は問うている。神なき時代に、何か確信をもちたいという気持ちはよくわかる。
ここでは、世界において意味と価値が発生するのは、欲望−身体の関係性によってであるということが論じられている。言い換えれば、世界に意味と価値を与えるのは、神でも世間でもなく、何かをしたいと思っている私自身であるということ。
神なきあとの哲学が、神に代わる絶対者の探求、もしくは人間存在の理念化に向かったことはよく知られている。これに真っ向から反対したのがニーチェだというのは、意外の感もある。著者によれば、ニーチェは「超越化」に反対し、「人間の価値の本質を、われわれの現実存在、肉体や身体の現実性に定位して問い直すこと」を求めたという。
19世紀半ばに発生した新カント派は、価値の普遍性を打ちだし、事実ではなく本質の探求に向かった。価値はより低いものからより高いものへと分類された。なまの生活世界、世俗世界、自然世界は価値が低いとされ、「超越的な本質世界」が目指されることになる。これもまた聖なる価値へと上向する本体論にほかならない、と著者はいう。
重要なのは、ニーチェとフッサールの哲学的ラディカリズムに立ち返ること。先構成された(すなわち前もって与えられた)価値や歴史から意味を説くのではなく、欲望―身体の関係性から生成される意味と価値から、「先構成的諸観念の捏造」を暴露する(本体論を批判する)ことだ、と著者はいう。
さらに重要なのは、現代の懐疑論を克服することだ。
分析哲学とポストモダン思想は、論理的相対主義を武器にして、普遍的認識の可能性を否定する。この構図は基本的にゴルギアスの懐疑論と変わらない、と著者は論じる。
前期ウィトゲンシュタインの場合は、論理学において、意味を数学化し、記号=意味の同一性を実現しようとした。しかし、この試みは錯誤でしかなかった。なぜなら、「言語記号の本質はまさしくそれが意味の多義性を含むという点にあるからだ」。
意味の数学化は、ある意味で、特異な作業をともなう。著者によれば、「あらゆる概念は本来多義性をもつが、数学化はこれに厳密規定を与えて一つの客観的な記号の体系、誰もが絶対的に同一の仕方でしか操作し得ない記号の体系へと置き換えるのである」。
しかし、後期ウィトゲンシュタインは懐疑論の立場を強める。言語が多義的であることに立ち戻り、言語によって、現実を再現するのは不可能であると考えるようになる。
つぎにデリダについて。
著者はデリダを「現代のゴルギアス」と名づけている。デリダは「今」はそれ自体として存在しないという。「今」と呼ばれるものは「過去」「今」「未来」といった差異の運動のなかでしか存在しない。厳密な同一性なるものは存在せず、いっさいは差異である。その差異の運動をデリダは「差延作用」と呼ぶ。
しかし、これは相対主義的懐疑論であって、相対主義では本体論、すなわち形而上学を解体できない、と著者は主張する。いくら今はないといっても、人にとって、今という時間があることは否定できない。同一性にたいして差異を主張するだけでは、時間が何であるかを示すことはできない。差異の哲学は、たえざる変革への志向をもつが、そのことによって、力がすべてを決定するという現実論理に対抗するすべを失ってしまうのではないか、と著者はいう。
「現代思想は原理の思考を、つまり思想の正当性や普遍性を問う思考それ自体を放棄し、まさしく否定神学的な、あるいは寓喩−説話的な預言者哲学をつぎつぎに生み出した」
そうした預言者的哲学を展開したひとりがドゥルーズだ、と著者は考えている。
ドゥルーズは、あらゆる事象の根源に「反復としての差異」が存在するという。すなわち反復しつづける差異。世界が硬化し死に向かわないのは、つねにそこにみずからを刷新する運動性があるからだ、とドゥルーズは考える。
ヘーゲルの絶対精神にたいして、ドゥルーズは絶対差異を唱える。その底には、世界にたいして永遠に異議を唱えつづける懐疑論的相対主義がある、と著者はいう。「ここにあるのは、秩序=反動性に対する反秩序=能動性というイメージ上の対抗にすぎ」ない。「ここでの思考は先行者を包括して新しい原理へと超え出ようとするのではなく、理念的対立をこととする預言者的哲学へと退行している」。すなわち永遠の抵抗。
ドゥルーズにはベルクソンに似た時間論もある。ベルクソンは精神の本質を「記憶」の概念で示したが、ドゥルーズはこれを「反復」と「差異」の概念に置き換える。現在は「習慣のうちを生きること」であり、未来は「たえざる革命へと向かう精神」の繰り返しと位置づけられる。「ドゥルーズでは、『未来』とは、一切を革新し、刷新し続ける革命への『希望』と『要請』を表現する理念となる」。
ドゥルーズによれば、この差異化の動きは秩序や制度によって、否定され歪曲される運命にある。そのため、差異の哲学はある局面で「革命」の哲学へと移行する。しかし、その哲学は社会制度の構想を禁じているため、終末論的絶望とシニシズムに彩られた、出口の見えない反抗に終始する、と著者は批判する。
著者は、分析哲学やポストモダン思想に否定的だということができるだろう。
ここからは、意味に関する考察に移る。
まず意味の同一性は成立するかという問題。
意味の同一性は、言語による正しい表象が実現するか、言語による正しい伝達がなされるか、さらにはそもそも普遍的認識なるものがあるのかにかかわっている。
現代哲学はいずれも同一性はないという論理に帰着する。しかし、同一性についての問いは、そもそも本体が存在するかいなかという議論であって、本体がないということになれば、問いそのものが消滅するのだ、と著者はいう。
問題は同一性という概念の本質をいかに考えるかということなのである。
〈「意味」を言語あるいは記号に担われるものと考えるかぎり、言語あるいは記号の「意味」は、対象あるいは認識との「一致」すなわち「一義性」を確定されえない。……「意味」の本質の問題を解明するには、意味の問いを論理学的地平から引き離し、意味の本体論を解体して、これを現象学的−欲望相関的意味論の地平へと差し戻さねばならない。〉
同一性が存在するかいなかと考えるから、おかしくなるのだ。同一性は欲望−身体に相関して現われるとみるべきだ、と著者はいう。
もう一度考えてみよう。数学的概念においては、同一性は成立する。
いっぽう、言語は本質的に多義的な意味の集約にほかならないから、言語によって、対象を一つの意味に還元することは不可能である。これは論理学的には正しい。
とはいえ、言語の実際の場を考えれば、問題はそこに同一性が成立するかいなかということではなく、どのような間主観的な共通了解が成立するのかということだ、と著者は論じる。
感覚の同一性があるかどうかも、なかなか困難な問題である。とはいえ、感覚においても同一性が成立しないわけではない。たとえば人は同じ音楽、同じ顔を一瞥のうちに同定する。そうした情動性の質は比喩によってしか表現し得ない。言い換えれば「感覚的事象の同一性の規定は、『情動の同一性』以外の根拠をもたない」。したがって、「人間間の関係感情の本質を把握するには、主体と対象との間のエロス関係の本質を捉えねばならない」ということになる。つまり、感覚的事象についても、実存的な欲望−身体の関係性からそのあらわれ方を把捉しなければならない。
著者によれば、言語は言語のやりとり、すなわち無数の「言語ゲーム」のなかで成立し、そこには人間どうしの「関係的企投行為」が横たわっている。言葉はそれを媒介的に「代行―表象」しているにすぎない。
後期ウィトゲンシュタインの功績は、「言葉を用いて語り合いつつ生きるということ、そのことが人間にとってもつ意味の核心は何であるのか」を問うたことである。そこから、次のことが明らかになる、と著者はいう。
〈「言語ゲーム」は人間の実践的要求−応答ゲームにおける関係的意味生成に基礎をおき、言語の意味はこの実践関係としての「言語ゲーム」に基礎をおく。〉
人と人の関係を抜きにして、言語は成立しないということだ。
ところで、人を含む動物は対象の存在とその意味−価値を一瞥のうちに把捉するものだ。これを可能にするのが直知的知覚である。直知的知覚が主体のそのつどの欲望−関心に相関していることはいうまでもない。
人にとって、身の回りのものはすでに一般対象意味をもったものとして現出している。と同時に、それは私にとって利用可能性、用途性をもったものでもある。その点でいえば、言語は、「われわれの生の実践的関係のうちで生成する意味の一般痕跡にすぎない」。
身体行動は単なる機械的メカニズムの連鎖によって動いているわけではない。そこには「何らかのエロス的力動の発現、情動、衝迫、目的性の生成、企投的努力、といった諸契機が存在する」。
高度な生き物は視角や聴覚、嗅覚といった「遠隔知覚」をもっており、これによって対象との距離や方向性を保ったまま、対象を認知することができる。
〈生き物が遠隔知覚によって「世界」を空間性・時間性の構造として分節すること。このことこそは、「生世界」が意味と価値のたえざる生成の世界であることの根源である。〉
言語が生動するのは、こうした生世界において意味(ノエマ)と価値が生成されているからである。
生き物が生きるためには外界からエネルギーを取り入れなければならない。そのためには対象を瞬時に認知し、対象に企投するプロセス(衝迫、目標、判断、行為、努力)が必要になってくる。対象の直知的把握が意味をもたらす。意味は実存的範疇である。
意味(ノエマ)の本質は、対象を身体−欲望相関的に把握することである。意味は対象にたいする実存主体の当為において発生する。価値は「対象が指し示すエロス的可能性の強度の了解」であり、「対象が用在性としてもつ『価値』」である。
世界が意味と価値の秩序として生成するのは、生の意識のうちに欲望―衝動が到来することによってである。そして生成する世界から、存在としての世界が間主観的に構成される。
〈「価値」は質的強度の秩序であり、「意味」は目的にいたる優先性や順序性の秩序である。主体における「われ欲す」が発動してはじめて、世界は当の対象をめぐる意味と価値の秩序となる。……この意味と価値の生成の地平においては、「世界」は、「本体としての世界」が決してもちえない絶対的起点と終末、その根源と限界をもつ。〉
人間は「実存世界」と「客観世界」という二重性の世界性のなかで生きている。実存世界が、いわば自身にとっての世界であるのにたいし、客観世界とは「間主観化された一般性の世界」にほかならない。
この世界のどちらが真実かを問うのはばかげている。両方は支え合って世界を構成している。しかし、普遍性はいうまでもなく「客観世界」に求められるべきだろう、と著者は記している。
竹田青嗣『欲望論』を読む(5) [思想・哲学]
第2部「世界と欲望」にはいる。最初の章は「欲望相関性」だ。
哲学の出発点をめぐる論議。ヘーゲルは経験的意識の直接性から出発するが、この直接性はすでに媒介されており、絶対精神にいたる円環運動をなしている。これにたいし、ハイデガーの出発点は存在である。存在に耳を傾け、思索つづけることが、かれの哲学といえる。
ニーチェはヘーゲルやハイデガーのように始元の理念から出発しない。「生の経験の原初性から出発せよ」という。これこれが存在するはいちばん最後にくる。
ニーチェの本体論解体を支持しながら、著者はいう。
〈ある「力の中心」(生)が自らの世界に決定的な遠近法を与える。力という中心なしには世界も存在もありえない。われわれはこのニーチェの「力による遠近法」の構図を、「欲望−身体相関性」の構図へと位相変様する。〉
ニーチェを批判的に継承しながら、ここに著者の哲学の方向性が示されたことになる。
出発点は情動、感情、衝動、欲望である。
カントは別として、ヒュームやロックをはじめ、多くの哲学者は情動の根源性を認めてきた。ヘーゲルは生きものは欲求をもち、そのことによって自身を疎外(区別)し、その矛盾を解消するために、欲求を満たしたいという願いをもっているが、それがいったん満たされたとしても、その矛盾ははてしなくくり返されるとみていた。とはいえ、そのことが生きるということでもあった。
ここで、著者は情動や情念、欲求、衝動など、自我の外にある「第一動者」を一括して「欲望」と呼ぶと規定している。
ヘーゲルによる自己意識としての欲望論を、フロイトも受け継ぐ。すなわち触発、興奮、不快(不満)、低減欲求、行為。自己意識にはそうした構造があり、しかもその構造は繰り返される。
問題は、こうした人間の欲望を内的に洞察することだ。
「一つの『欲望』の到来によって、世界は始原的に分節される」と、著者はいう。この場合、分節とは私のものとして世界が切り取られる、あるいは開かれるということを意味する。この内的体験、あるいは世界感受は、ひとつのひらめきとなり、意識をもたらす。
それは単なる認知ではなく、感知でもある。快−不快の感知を、著者は「エロス的力動」と名づけている。「触発されること、感知することは内的なエロス的力動の系(セリー)が生成することである」。すなわちエロス的力動による世界生成。
〈生き物はつねにすでにエロス的力動の可能態としての「身体」である。一切の生き物は、衝動、欲求によって世界を時間化し、また「身体」において世界を空間化しつつ生きる。〉
欲望が内的な時間と空間を生みだす。そして、欲望を満たすために身体が投企される。
欲望としての衝動、欲求の情動が「自己」と「世界」を分節する、と著者はいう。対象は自己の欲望の相関者であるとともに、自己の可能性の相関者でもあり、そのようなものとして、みずからが何であるか(同一性)を示す。言い換えれば、対象は「欲望−身体」の相関者としてあらわれる。
〈欲望論的始元論は、生命体におけるエロス的力動の発生についての創造的本質洞察から始発する。世界は、「本体」としてはどんな始元も起原もまた究極原因ももたない。しかし生の「内的体験」は、その体験の内的本質として、必然的に生成の始発点をもつ。あるエロス的力動が生き物のうちに生じるとき、欲求あるいは欲望が到来するとき、世界はそのつど新しい分節を開始する。〉
著者は形而上学対相対主義の構図を捨てるところから出発する。そして、「欲望−身体」という新しい出発点を設定することによって、内的体験として現出する世界を把握しようとする。
「内的体験」にとっては、欲望(感覚、衝迫、情動)の到来がつねに世界生成の根源的始発性を意味する、と著者はいう。内的体験をもたらす「現前意識」こそが出発点となる。その背後に回りこむことは無意味である。
欲望の生成は、生ある存在にとっての絶対的存在理由であって、意味、目的、理由といった概念もそこから生まれる実存的範疇である。欲望の由来を知ることはできない。それはまさに非知的なものとして到来する。
欲望の非知性は、それが意識の現在性(現前意識)の絶対的起点であることを意味する。そして、企投−行為−努力といったものが意識されつつ維持されるのは、駆動性としての欲望が、全過程において持続されるからである。
〈欲望の到来において主体は、エロス的予期に衝迫されること、対象をめがけ目的へとたどること、その困難、可能性、努力、苦しみに耐えることを、絶対の規定性として受けとる。すなわち一つの衝動の到来性が主体と対象を生成し、世界をなんらかの区別、目標、順列、位階、選択項目として生成する。この区別され、分節されたものとしての世界のうちを目的へとめがけて企投すること、そこから世界と対象についての意味と価値の一切の諸相が生成される。〉
欲望を基底として、世界の諸関係は、一つ一つの実存主体にとって、意味と価値の網の目として立ちあがっていく。
世界感受の基本的エレメントはエロス的力動性であり、それはまず快−不快の審級においてあらわれる、と著者はいう。
フロイトによれば、快と不快は生命体の生物学的−生理学的根本機構(生命維持システム)から発生する。不快が危険という信号あるいは警告であるのにたいし、快はその除去あるいは解消である。そして、すべての動物的生は快に向かう本性(快感原則)をもっているとされる。
いっぽう、動物学者は快と不快を、近接行動と離隔行動、求心的行動と遠心的行動の二項性としてとらえる。とはいえ、その情動は内的体験としては直接とらえることはできず、あくまでも自身の内的体験に即して、直感的に洞察(推測)されるだけである。
しかし、著者は、快とは不快の消滅や解消にあるというフロイトの考え方に異論をはさむ。それは、快の重要な契機ではあるが、快そのものではない。快とはあくまでも心的カテゴリーとしてのエロス的情動そのものにある。
欲望−身体としての主体にとって、相関する世界はあくまでも真なるものとして現出する。そのことをあきらかにしたのはニーチェだが、ニーチェには、生命体自体に内在するたえず自己を拡大しようとする暗黙の意志(力への意志)こそ、人間の快−不快などの感情を支える行動である、という発想がある。
しかし、肉体の内なる根本意志が快と不快を生じさせるというのは、一種の本体論的仮説であって納得しがたい、と著者はいう。人間の存在本質を「生の衝動」と「死の衝動」の二元論によって説明するフロイトの仮説も説得的ではない。生き物における内的力を測りうるものは、肉体が覚える快−不快の強度、すなわちエロス的力動の強度以外にない、と著者はいう。
それは根源的到来であって、その生成の背後に回ってみることはできない。
〈内的体験の世界においては、つねに無から有が生じ、有は無へと経緯する。情動はたえずある時点で生起し、そして衝迫、目的指標、企投、成就、充足、衝動の消滅といったサイクルを反復する。……ある欲望の到来(その了解)はつねに一つの絶対的到来、絶対的起点であり、そこから価値と意味の系(セリー)が展開し、この系はある時点で消滅する。〉
フッサールは、知覚、想起、想像という個的直感が認識一般の基盤をなすとした。これにたいし、ハイデガーは実存的欲望=関心の優位を主張し、メルロー=ポンティは世界や身体に内属する意識をその出発点と唱えた。サルトルは情動を周辺世界から受け取る状況的な感情的反作用ととらえた。著者はあくまでもフッサールの立場を継承しようとしている。
フッサールによれば、目の前の対象が実在的な事物であるのは、純粋意識(現前意識)のとらえる像を現実の知覚像とする確信にもとづく。把捉(意味づけ)された対象には、よしあし、優劣などの価値性がつけ加えられる。そこから対象への心情や意欲が生まれるとされる。
たとえば果物を見た場合、まず知覚像(ノエシス)から、これは果物であるという対象意味(ノエマ)があらわれ、さらにうまそうだという価値づけがおこなわれるというのが、フッサールのとらえ方だ。しかし、「一般には、知覚像、対象意味、そしていわば情動所与が一瞥のうちに所与される」のではないかと、著者はいう。言い換えれば、「あらゆる場面において『情動所与』は、人間の対象認識において不可欠な本質契機である」。
意味と情動の一致が乖離するとき、現実性の感覚が異常をきたす。そのことは、統合失調症の経験をみればあきらかである。このとき諸対象は「対象意味の間主観的な共通性を喪失し、『世界』は、その人間のみに固有な意味と情動の秩序なき奔流となる」。
日常生活における自明性の喪失は、明確な自己の希薄化をもたらす。対象が脈絡のないまま次々とあらわれ、その場かぎりの情動と想念の流れのなかにただよう。
著者は現実性の本質的条件を、(1)つねに明確な「自己意識」、すなわち「関係意識」=時間・空間意識や対他意識をともなうこと、(2)定常的な情動をもって対象を一般的意味として把持しうること、(3)周辺の諸事物、諸事象が時間的・空間的整合性を維持していること、と規定している。これらの条件が欠ければ、生き生きした現実性の意識は失われることになる。
情動はやっかいである。情動の希薄や奔流が、現実性の喪失をもたらす。それはコントロールすることができない。
われわれは通常、一瞥によって対象を知覚する。そこには対象の意味や、それにともなう情動、状況関連性が生き生きと与えられている。より注意深い観察(再確証)が必要とされるのは、なんらかの理由で対象確信に疑念が生じる場合である。
揺れる柳の葉を幽霊と見間違えるのは、一瞥的知覚が恐れの情動を喚起するためである。だが、対象意味(ノエマ)が先にあって、それから情動や価値がもたらされるわけではない。それは一挙に出現する。
まったく未知の事物に出会ったとき、われわれは疑い−吟味−確証によって、対象の意味を認識する。そのさいにはエロス的力動(いわば生物的本能)にもとづく内的体験が生じている。しかし、「対象の知覚が同時に対象の意味(対象ノエマ)として現われるのは、生命体におけるエロス的力動とその時間化[いわば経験]、この対象に対してある態度をとりうる、という本質的諸契機においてである」。
ここから、著者はフッサールのとらえ方をひっくり返す。すなわち、知覚よりも情動が優位なのだ。
〈対象知覚における対象意味と情動の関係は、発生的本質においては、この順序は反転されねばならない。すなわち、対象との直接接触はエロス的情動を触発し、このエロス的情動触発の経験的反復が、対象の遠隔知覚(形象的知覚)における予期的情動を形成し、そしてこの予期的情動の発動こそが、対象についての第一義的な「意味」、すなわちそれが「何であるか」についての予期的了解であるからだ。〉
こうして、著者による世界構想の方向性があきらかになる。すなわち欲望−身体の相関性を基盤として、意味と価値が発生し、それから価値審級が形成されるというように論議は進んでいく。
哲学の出発点をめぐる論議。ヘーゲルは経験的意識の直接性から出発するが、この直接性はすでに媒介されており、絶対精神にいたる円環運動をなしている。これにたいし、ハイデガーの出発点は存在である。存在に耳を傾け、思索つづけることが、かれの哲学といえる。
ニーチェはヘーゲルやハイデガーのように始元の理念から出発しない。「生の経験の原初性から出発せよ」という。これこれが存在するはいちばん最後にくる。
ニーチェの本体論解体を支持しながら、著者はいう。
〈ある「力の中心」(生)が自らの世界に決定的な遠近法を与える。力という中心なしには世界も存在もありえない。われわれはこのニーチェの「力による遠近法」の構図を、「欲望−身体相関性」の構図へと位相変様する。〉
ニーチェを批判的に継承しながら、ここに著者の哲学の方向性が示されたことになる。
出発点は情動、感情、衝動、欲望である。
カントは別として、ヒュームやロックをはじめ、多くの哲学者は情動の根源性を認めてきた。ヘーゲルは生きものは欲求をもち、そのことによって自身を疎外(区別)し、その矛盾を解消するために、欲求を満たしたいという願いをもっているが、それがいったん満たされたとしても、その矛盾ははてしなくくり返されるとみていた。とはいえ、そのことが生きるということでもあった。
ここで、著者は情動や情念、欲求、衝動など、自我の外にある「第一動者」を一括して「欲望」と呼ぶと規定している。
ヘーゲルによる自己意識としての欲望論を、フロイトも受け継ぐ。すなわち触発、興奮、不快(不満)、低減欲求、行為。自己意識にはそうした構造があり、しかもその構造は繰り返される。
問題は、こうした人間の欲望を内的に洞察することだ。
「一つの『欲望』の到来によって、世界は始原的に分節される」と、著者はいう。この場合、分節とは私のものとして世界が切り取られる、あるいは開かれるということを意味する。この内的体験、あるいは世界感受は、ひとつのひらめきとなり、意識をもたらす。
それは単なる認知ではなく、感知でもある。快−不快の感知を、著者は「エロス的力動」と名づけている。「触発されること、感知することは内的なエロス的力動の系(セリー)が生成することである」。すなわちエロス的力動による世界生成。
〈生き物はつねにすでにエロス的力動の可能態としての「身体」である。一切の生き物は、衝動、欲求によって世界を時間化し、また「身体」において世界を空間化しつつ生きる。〉
欲望が内的な時間と空間を生みだす。そして、欲望を満たすために身体が投企される。
欲望としての衝動、欲求の情動が「自己」と「世界」を分節する、と著者はいう。対象は自己の欲望の相関者であるとともに、自己の可能性の相関者でもあり、そのようなものとして、みずからが何であるか(同一性)を示す。言い換えれば、対象は「欲望−身体」の相関者としてあらわれる。
〈欲望論的始元論は、生命体におけるエロス的力動の発生についての創造的本質洞察から始発する。世界は、「本体」としてはどんな始元も起原もまた究極原因ももたない。しかし生の「内的体験」は、その体験の内的本質として、必然的に生成の始発点をもつ。あるエロス的力動が生き物のうちに生じるとき、欲求あるいは欲望が到来するとき、世界はそのつど新しい分節を開始する。〉
著者は形而上学対相対主義の構図を捨てるところから出発する。そして、「欲望−身体」という新しい出発点を設定することによって、内的体験として現出する世界を把握しようとする。
「内的体験」にとっては、欲望(感覚、衝迫、情動)の到来がつねに世界生成の根源的始発性を意味する、と著者はいう。内的体験をもたらす「現前意識」こそが出発点となる。その背後に回りこむことは無意味である。
欲望の生成は、生ある存在にとっての絶対的存在理由であって、意味、目的、理由といった概念もそこから生まれる実存的範疇である。欲望の由来を知ることはできない。それはまさに非知的なものとして到来する。
欲望の非知性は、それが意識の現在性(現前意識)の絶対的起点であることを意味する。そして、企投−行為−努力といったものが意識されつつ維持されるのは、駆動性としての欲望が、全過程において持続されるからである。
〈欲望の到来において主体は、エロス的予期に衝迫されること、対象をめがけ目的へとたどること、その困難、可能性、努力、苦しみに耐えることを、絶対の規定性として受けとる。すなわち一つの衝動の到来性が主体と対象を生成し、世界をなんらかの区別、目標、順列、位階、選択項目として生成する。この区別され、分節されたものとしての世界のうちを目的へとめがけて企投すること、そこから世界と対象についての意味と価値の一切の諸相が生成される。〉
欲望を基底として、世界の諸関係は、一つ一つの実存主体にとって、意味と価値の網の目として立ちあがっていく。
世界感受の基本的エレメントはエロス的力動性であり、それはまず快−不快の審級においてあらわれる、と著者はいう。
フロイトによれば、快と不快は生命体の生物学的−生理学的根本機構(生命維持システム)から発生する。不快が危険という信号あるいは警告であるのにたいし、快はその除去あるいは解消である。そして、すべての動物的生は快に向かう本性(快感原則)をもっているとされる。
いっぽう、動物学者は快と不快を、近接行動と離隔行動、求心的行動と遠心的行動の二項性としてとらえる。とはいえ、その情動は内的体験としては直接とらえることはできず、あくまでも自身の内的体験に即して、直感的に洞察(推測)されるだけである。
しかし、著者は、快とは不快の消滅や解消にあるというフロイトの考え方に異論をはさむ。それは、快の重要な契機ではあるが、快そのものではない。快とはあくまでも心的カテゴリーとしてのエロス的情動そのものにある。
欲望−身体としての主体にとって、相関する世界はあくまでも真なるものとして現出する。そのことをあきらかにしたのはニーチェだが、ニーチェには、生命体自体に内在するたえず自己を拡大しようとする暗黙の意志(力への意志)こそ、人間の快−不快などの感情を支える行動である、という発想がある。
しかし、肉体の内なる根本意志が快と不快を生じさせるというのは、一種の本体論的仮説であって納得しがたい、と著者はいう。人間の存在本質を「生の衝動」と「死の衝動」の二元論によって説明するフロイトの仮説も説得的ではない。生き物における内的力を測りうるものは、肉体が覚える快−不快の強度、すなわちエロス的力動の強度以外にない、と著者はいう。
それは根源的到来であって、その生成の背後に回ってみることはできない。
〈内的体験の世界においては、つねに無から有が生じ、有は無へと経緯する。情動はたえずある時点で生起し、そして衝迫、目的指標、企投、成就、充足、衝動の消滅といったサイクルを反復する。……ある欲望の到来(その了解)はつねに一つの絶対的到来、絶対的起点であり、そこから価値と意味の系(セリー)が展開し、この系はある時点で消滅する。〉
フッサールは、知覚、想起、想像という個的直感が認識一般の基盤をなすとした。これにたいし、ハイデガーは実存的欲望=関心の優位を主張し、メルロー=ポンティは世界や身体に内属する意識をその出発点と唱えた。サルトルは情動を周辺世界から受け取る状況的な感情的反作用ととらえた。著者はあくまでもフッサールの立場を継承しようとしている。
フッサールによれば、目の前の対象が実在的な事物であるのは、純粋意識(現前意識)のとらえる像を現実の知覚像とする確信にもとづく。把捉(意味づけ)された対象には、よしあし、優劣などの価値性がつけ加えられる。そこから対象への心情や意欲が生まれるとされる。
たとえば果物を見た場合、まず知覚像(ノエシス)から、これは果物であるという対象意味(ノエマ)があらわれ、さらにうまそうだという価値づけがおこなわれるというのが、フッサールのとらえ方だ。しかし、「一般には、知覚像、対象意味、そしていわば情動所与が一瞥のうちに所与される」のではないかと、著者はいう。言い換えれば、「あらゆる場面において『情動所与』は、人間の対象認識において不可欠な本質契機である」。
意味と情動の一致が乖離するとき、現実性の感覚が異常をきたす。そのことは、統合失調症の経験をみればあきらかである。このとき諸対象は「対象意味の間主観的な共通性を喪失し、『世界』は、その人間のみに固有な意味と情動の秩序なき奔流となる」。
日常生活における自明性の喪失は、明確な自己の希薄化をもたらす。対象が脈絡のないまま次々とあらわれ、その場かぎりの情動と想念の流れのなかにただよう。
著者は現実性の本質的条件を、(1)つねに明確な「自己意識」、すなわち「関係意識」=時間・空間意識や対他意識をともなうこと、(2)定常的な情動をもって対象を一般的意味として把持しうること、(3)周辺の諸事物、諸事象が時間的・空間的整合性を維持していること、と規定している。これらの条件が欠ければ、生き生きした現実性の意識は失われることになる。
情動はやっかいである。情動の希薄や奔流が、現実性の喪失をもたらす。それはコントロールすることができない。
われわれは通常、一瞥によって対象を知覚する。そこには対象の意味や、それにともなう情動、状況関連性が生き生きと与えられている。より注意深い観察(再確証)が必要とされるのは、なんらかの理由で対象確信に疑念が生じる場合である。
揺れる柳の葉を幽霊と見間違えるのは、一瞥的知覚が恐れの情動を喚起するためである。だが、対象意味(ノエマ)が先にあって、それから情動や価値がもたらされるわけではない。それは一挙に出現する。
まったく未知の事物に出会ったとき、われわれは疑い−吟味−確証によって、対象の意味を認識する。そのさいにはエロス的力動(いわば生物的本能)にもとづく内的体験が生じている。しかし、「対象の知覚が同時に対象の意味(対象ノエマ)として現われるのは、生命体におけるエロス的力動とその時間化[いわば経験]、この対象に対してある態度をとりうる、という本質的諸契機においてである」。
ここから、著者はフッサールのとらえ方をひっくり返す。すなわち、知覚よりも情動が優位なのだ。
〈対象知覚における対象意味と情動の関係は、発生的本質においては、この順序は反転されねばならない。すなわち、対象との直接接触はエロス的情動を触発し、このエロス的情動触発の経験的反復が、対象の遠隔知覚(形象的知覚)における予期的情動を形成し、そしてこの予期的情動の発動こそが、対象についての第一義的な「意味」、すなわちそれが「何であるか」についての予期的了解であるからだ。〉
こうして、著者による世界構想の方向性があきらかになる。すなわち欲望−身体の相関性を基盤として、意味と価値が発生し、それから価値審級が形成されるというように論議は進んでいく。
竹田青嗣『欲望論』を読む(4) [思想・哲学]
伝統的「本体論」の解体は、ニーチェによってはじめの扉が開かれ、フッサールによってその完成にいたる、と著者はいう。だとすれば、前回のニーチェにつづき、フッサールの仕事が問われねばならない。
フッサール現象学が批判するのは、ひとつに伝統的な主観−客観構図に立つ哲学的独断論であり、ひとつに現代的な相対主義、懐疑主義である。フッサールはむずかしい。だから、さまざまな誤解がある。しかし、重要なのは、現象学の根本動機とその本質的方法だ、と著者はいう。
現象学の方法とは何か。それは「内在的意識」が「世界確信」の信憑構造をいかにつくりあげていくかという「確信成立の条件」を解明していくことだという。
認識問題における主客一致構図には難問があった。客観認識はありえない。あらゆる認識は相対的なものである。もし、それがありうるとすれば、純粋数学、純粋自然科学においてでしかない。人間社会においては、客観的認識はありえず、「力の論理」だけが正しいものとされる。しかし、力の論理だけがまかりとおり、正義や不正義に普遍的基準がないとするなら、哲学の営みも無意味なものになってしまう。
フッサールは普遍認識はないという考え方を批判し、主客の構図とは異なる新たな構図を提示する。主客の一致はありえない。にもかかわらず、普遍認識はなぜ成立しうるのか。そのためにとられる方法が、いわゆる「現象学的還元」である。
フッサールはいう。絶対的に実在する世界の全体といった観念は背理である。主客の一致を検証することはできない。しかし、認識は「確信」となりうる。そのためには「本体」、すなわち世界の客観存在を想定することをやめ、世界はただ私によって生きられているものとみなすところから出発しなければならない(すなわち現象学的還元)という。そのことによって、「私の意識」は「超越論的構成」にもとづく「世界確信」、すなわち普遍認識へといたりうるのだ。
世界確信には、個人的な体験にもとづく個的確信、共同的確信からなる間主観的確信、それに純粋数学的、純粋自然科学的な普遍的確信がある。
ここでは「本体」としての客観存在という想定はしりぞけられる。さらに、独断的形而上学と懐疑論(相対主義)も否定される。
そのうえで、フッサールの「現象学的還元」がめざすのは、認識における間主観的確信の本質構造にほかならない、と著者はいう。
フッサール自身はこう書いている。
〈世界は、目ざめつつ、つねに何らかのしかたで実践的な関心をいだいている主体としてのわれわれにとって、たまたまあるときに与えられるというものではなく、あらゆる現実的および可能的実践の普遍野として、地平として、眼前に与えられている。生とは、たえず世界確信の中に生きるということなのである。〉
フッサールは、現前する意識から出発する。これこそが世界認識の源泉である。これにたいし、フッサールを引き継いだハイデガーは、意識の背後に実存的生という存在論的基底をとらえる。そこから、フッサール現象学とハイデガー存在論とのちがいがでてくる。
ハイデガーにとって、現象は存在者の存在を隠蔽するものであり、現象学は存在の真理を取りだす方法と考えられた。対象への関心からはじまって、人間存在へと戻り、人間存在および人間存在を可能にしている真理を、取りだすこと。これがハイデガーの発想だ。
ニーチェ、フッサール、ハイデガーの相関性。ニーチェは「力相関性」の構図を示し、フッサールはこれを「意識相関性」の構図へと推し進め、ハイデガーはこの構図を「気遣い〔関心〕相関構図」へと変奏することで実存論へと転換した。しかし、三者の関係は錯綜し、それどころか対立したものとなる。それを解きほぐし、再構築すること。それが著者の課題となる。
しかし、まずはフッサールをハイデガー流解釈から切り離して、より深く理解することである。
フッサールは現出する意識の背後に回ることを禁止する。意識はたしかに身体や歴史性、習慣性、無意識、言語によって先構成されたものである。しかし、フッサールは「けっして現前意識の背後に遡行してはならない」という。根拠の根拠を問う思考が客観主義的独断論におちいるのは、「本体」論的思考がはいりこむからだ。
意識が先構成されているのなら、われわれは「意識」を絶対的な出発点とするわけにはいかない。だが、はたしてそうだろうか。われわれは現前意識から出発することで、むしろその背後にあるとされる感情や無意識、言語、美、文化といった問題を探るべきだ、と著者はいう。
現象学は対象存在それ自体を問うわけではない。対象の存在様態についての確信(信憑)が間主観的に成立する条件を問う。それは本体論(形而上学)とも懐疑主義とも異なる思考方法である。
あくまでも普遍的認識をめざす哲学は、次のような意義をもつ、と著者はいう。
〈問題の核心は一つである。人間社会のあらゆる営みの底には「力の論理」がその強大な現実力を潜めて居座っている。人間の「言葉の営み」の中心的な意義は、この赤裸々な「力の原理」(暴力原理)をいかに抑制するかという点にある。〉
懐疑主義もまた否定の論理である。だが、懐疑主義には根本的な問題がある。
〈あらゆる社会思想は、相対主義=懐疑論的な言説戦略をとることで、現実主義の「力の論理」に対する本質的な対抗力を喪失する。この思想は、やがて行き場を失って形而上学的倫理学へ逃げ込み、そのことでかろうじて現実世界に対する反抗(反感)の思想に留まろうとする。……どれほど過激な思想を口にしていてもそれは思想の本質として「羊のロマン主義」への陥落以外のものではない。〉
これがポストモダン思想にたいする著者の懸念とみてよい。
18世紀以降のヨーロッパ哲学の流れについての著者のまとめもみておこう。
〈18世紀ヨーロッパの啓蒙思想は超越神論を理神論−汎神論へと置き換え、ドイツ観念論哲学はこれを完成させた。このヨーロッパ汎神論を決定的に終焉させた第一の原因は、哲学的な潮流であるよりむしろ19世紀の自然科学(とくにダーウィン)の隆盛である。しかしこれに続く実証主義科学は「事実学」にすぎず、哲学の伝統的主題は危機に陥る。ヨーロッパ哲学は、ニーチェとフッサールの仕事を横目にして通り過ぎつつ、第一に、ヴィンデルバントが示唆した「神」なしの本体論的探求が新カント派以後の流れになり、第二に、科学を標榜するマルクス主義的世界観が台頭し、第三に、反形而上学を旗印とする論理実証主義と論理哲学が現われ、最後に相対主義を論理的武器とする分析哲学(言語哲学)とポストモダン思想が登場する。そしてこの最後の流れは、ヨーロッパの形而上学本体論を完全に終焉させ、これに対抗する哲学的相対主義の最終的勝利を告げる(=大きな物語は終わった)ような様相を呈する。〉
これが近代哲学史の流れである。
このあと第2部の「世界と欲望」がつづく。
よく理解できない部分も多いが、概略だけでもつかみたいものだ。
フッサール現象学が批判するのは、ひとつに伝統的な主観−客観構図に立つ哲学的独断論であり、ひとつに現代的な相対主義、懐疑主義である。フッサールはむずかしい。だから、さまざまな誤解がある。しかし、重要なのは、現象学の根本動機とその本質的方法だ、と著者はいう。
現象学の方法とは何か。それは「内在的意識」が「世界確信」の信憑構造をいかにつくりあげていくかという「確信成立の条件」を解明していくことだという。
認識問題における主客一致構図には難問があった。客観認識はありえない。あらゆる認識は相対的なものである。もし、それがありうるとすれば、純粋数学、純粋自然科学においてでしかない。人間社会においては、客観的認識はありえず、「力の論理」だけが正しいものとされる。しかし、力の論理だけがまかりとおり、正義や不正義に普遍的基準がないとするなら、哲学の営みも無意味なものになってしまう。
フッサールは普遍認識はないという考え方を批判し、主客の構図とは異なる新たな構図を提示する。主客の一致はありえない。にもかかわらず、普遍認識はなぜ成立しうるのか。そのためにとられる方法が、いわゆる「現象学的還元」である。
フッサールはいう。絶対的に実在する世界の全体といった観念は背理である。主客の一致を検証することはできない。しかし、認識は「確信」となりうる。そのためには「本体」、すなわち世界の客観存在を想定することをやめ、世界はただ私によって生きられているものとみなすところから出発しなければならない(すなわち現象学的還元)という。そのことによって、「私の意識」は「超越論的構成」にもとづく「世界確信」、すなわち普遍認識へといたりうるのだ。
世界確信には、個人的な体験にもとづく個的確信、共同的確信からなる間主観的確信、それに純粋数学的、純粋自然科学的な普遍的確信がある。
ここでは「本体」としての客観存在という想定はしりぞけられる。さらに、独断的形而上学と懐疑論(相対主義)も否定される。
そのうえで、フッサールの「現象学的還元」がめざすのは、認識における間主観的確信の本質構造にほかならない、と著者はいう。
フッサール自身はこう書いている。
〈世界は、目ざめつつ、つねに何らかのしかたで実践的な関心をいだいている主体としてのわれわれにとって、たまたまあるときに与えられるというものではなく、あらゆる現実的および可能的実践の普遍野として、地平として、眼前に与えられている。生とは、たえず世界確信の中に生きるということなのである。〉
フッサールは、現前する意識から出発する。これこそが世界認識の源泉である。これにたいし、フッサールを引き継いだハイデガーは、意識の背後に実存的生という存在論的基底をとらえる。そこから、フッサール現象学とハイデガー存在論とのちがいがでてくる。
ハイデガーにとって、現象は存在者の存在を隠蔽するものであり、現象学は存在の真理を取りだす方法と考えられた。対象への関心からはじまって、人間存在へと戻り、人間存在および人間存在を可能にしている真理を、取りだすこと。これがハイデガーの発想だ。
ニーチェ、フッサール、ハイデガーの相関性。ニーチェは「力相関性」の構図を示し、フッサールはこれを「意識相関性」の構図へと推し進め、ハイデガーはこの構図を「気遣い〔関心〕相関構図」へと変奏することで実存論へと転換した。しかし、三者の関係は錯綜し、それどころか対立したものとなる。それを解きほぐし、再構築すること。それが著者の課題となる。
しかし、まずはフッサールをハイデガー流解釈から切り離して、より深く理解することである。
フッサールは現出する意識の背後に回ることを禁止する。意識はたしかに身体や歴史性、習慣性、無意識、言語によって先構成されたものである。しかし、フッサールは「けっして現前意識の背後に遡行してはならない」という。根拠の根拠を問う思考が客観主義的独断論におちいるのは、「本体」論的思考がはいりこむからだ。
意識が先構成されているのなら、われわれは「意識」を絶対的な出発点とするわけにはいかない。だが、はたしてそうだろうか。われわれは現前意識から出発することで、むしろその背後にあるとされる感情や無意識、言語、美、文化といった問題を探るべきだ、と著者はいう。
現象学は対象存在それ自体を問うわけではない。対象の存在様態についての確信(信憑)が間主観的に成立する条件を問う。それは本体論(形而上学)とも懐疑主義とも異なる思考方法である。
あくまでも普遍的認識をめざす哲学は、次のような意義をもつ、と著者はいう。
〈問題の核心は一つである。人間社会のあらゆる営みの底には「力の論理」がその強大な現実力を潜めて居座っている。人間の「言葉の営み」の中心的な意義は、この赤裸々な「力の原理」(暴力原理)をいかに抑制するかという点にある。〉
懐疑主義もまた否定の論理である。だが、懐疑主義には根本的な問題がある。
〈あらゆる社会思想は、相対主義=懐疑論的な言説戦略をとることで、現実主義の「力の論理」に対する本質的な対抗力を喪失する。この思想は、やがて行き場を失って形而上学的倫理学へ逃げ込み、そのことでかろうじて現実世界に対する反抗(反感)の思想に留まろうとする。……どれほど過激な思想を口にしていてもそれは思想の本質として「羊のロマン主義」への陥落以外のものではない。〉
これがポストモダン思想にたいする著者の懸念とみてよい。
18世紀以降のヨーロッパ哲学の流れについての著者のまとめもみておこう。
〈18世紀ヨーロッパの啓蒙思想は超越神論を理神論−汎神論へと置き換え、ドイツ観念論哲学はこれを完成させた。このヨーロッパ汎神論を決定的に終焉させた第一の原因は、哲学的な潮流であるよりむしろ19世紀の自然科学(とくにダーウィン)の隆盛である。しかしこれに続く実証主義科学は「事実学」にすぎず、哲学の伝統的主題は危機に陥る。ヨーロッパ哲学は、ニーチェとフッサールの仕事を横目にして通り過ぎつつ、第一に、ヴィンデルバントが示唆した「神」なしの本体論的探求が新カント派以後の流れになり、第二に、科学を標榜するマルクス主義的世界観が台頭し、第三に、反形而上学を旗印とする論理実証主義と論理哲学が現われ、最後に相対主義を論理的武器とする分析哲学(言語哲学)とポストモダン思想が登場する。そしてこの最後の流れは、ヨーロッパの形而上学本体論を完全に終焉させ、これに対抗する哲学的相対主義の最終的勝利を告げる(=大きな物語は終わった)ような様相を呈する。〉
これが近代哲学史の流れである。
このあと第2部の「世界と欲望」がつづく。
よく理解できない部分も多いが、概略だけでもつかみたいものだ。
竹田青嗣『欲望論』を読む(3) [思想・哲学]
ヨーロッパの中世では、存在の始原的原理は神に置かれていた。しかし、デカルト(「われ考えるゆえに、われあり」)の時代になって、ふたたび哲学の「自由な思考」が再開される。そのころ自然を客観的に認識するための観察、仮説、実験、検証という方法も生まれていた。
フッサールは自然の客観的認識方法を「自然の数学化」と概括している。自然を客観的に認識するとは、自然空間と時間を幾何学的秩序として記述するとともに、自然事物の諸性質を数式化することにほかならなかった。
空間や時間を幾何学的にとらえ、それに基準(長さや高さ、温度、何時間など)といった基準を与えること。それによって「物理主義的合理主義の世界像」を与えることが目指されていた。
「こうして、すべての自然科学的研究はますます数学化された自然の表象体系として展開し、一切の認識を単なる『記号的概念』を操作する技術的思考へと変更する」
しかし、自然認識の方法は、認識とは何かという問題を解決したわけではなかった。そこでは、意味形成の根源についての問いが失われ、いわば「意味の空洞化」が生じていた、と著者はいう。
こうして心身二元論が登場する。すなわち事物と「心の世界」の分裂。主観と客観の対立。
スピノザはこれを統合しようとして、世界の一切は合理的な「神」から流出し、完全な因果関係の秩序のもとに成り立つという合理主義的独断論を打ちだす。これにたいし、ヒュームは、どのような世界観も個々の主体、あるいは諸文化の経験的な構成物にすぎないという経験主義的懐疑論を提示する。
合理主義的独断論と経験主義的懐疑論。「近代哲学の、そしてそれに続く現代哲学の認識論は、まだこの近代認識論における根本的対立構図から一度も解き放たれたことがない」。20世紀のマルクス主義とポストモダン思想の対立、論理実証主義と論理相対主義の対立をみても、そのことがわかる、と著者はいう。
さあ、ややこしくなってきた。
まずは、ヒュームの方法的懐疑論、方法的経験論について。一切の経験的因果性はただ主観のうちの「信念」としてのみ成立する。それは絶対的なものではなく、あくまでも情動(感情)によってもたらされた習慣的傾向としてとらえらえる。これがヒュームの考え方だ。
ものごとの発生する原因は無数に考えられる。しかし、真の原因などというものは「むしろ人間がそのつど何を自分にとって重要なものとみなすかという、生の目的性と相関的にのみ現われ出る」。逆に言い換えれば、力(作用)の因果性は遡行不可能ということになる。
ただし、ヒュームはみずからもゴルギアスのような懐疑論者ではないと述べている。われわれが「なぜ」と原因を問うのは、その根源性を求めるためではなく、その効用性、有用性を求めるためである。そうした原因がつきとめられたなら、それ以上のもの(たとえば神)に遡行する動機は失われる。「われわれは信念のそれ以上遡行できない底板につきあたったなら、そこにとどまるべきである」──著者はこれこそがヒュームの哲学の核心だという。
厳密にいえば、ヒュームを相対主義者、懐疑主義者と呼ぶのはあやまりで、かれの立場は「方法的経験論」にほかならない。著者自身も共感するニーチェとフッサールは、こうしたヒュームの考え方を引き継いでいるという。
とはいえ、ヨーロッパでは、長らく哲学の中心課題は、現象の背後にある「本体」、言い換えれば真の実在を探究することに置かれてきた。
ここで、近代の代表的哲学者として、カントとヘーゲルが登場する。
カントは『純粋理性批判』のアンチノミー(二律背反)の議論で、懐疑論を根本から否定し、世界認識の普遍的可能性を確立しようとした。帰謬論的相対主義は無化され、同時に形而上学的独断論も否定され、それによって哲学的な普遍認識の可能性を示そうとしたのである。
いっぽうで、カントは本質と現象という図式を提示した。世界は現象界と可想界(物自体)に区別される。現象界は客観的認識が可能である。しかし、物自体を完全に認識することはできない。
著者はこう書いている。
〈カントの「物自体」とは何か。絶対的に認識も経験もされえず、しかしその存在の想定なくして「われわれの世界」の存在自体が考えられないもの、われわれの世界の総体を絶対的に可能にしているものとしての「真なる存在」。それは完全にアクセス不可能であるがゆえに「語りえぬもの」であるが、われわれがこの世界を生きて経験する限り、その存在を否認することが決してできない「何かあるもの」。〉
「物自体」とは、人間の経験世界の背後にあって、現象一般を可能にしている何ものか(本体)である。ぼくなどには、かつて神と呼ばれた存在が、カントにおいては可想しうる「物自体」に変換されているのではないかと思えるほどである。神が「物自体」に置き換えられているとすれば、これはおそらくヨーロッパの思想界にとっては、大きな衝撃だったはずである。
次にヘーゲル。ヘーゲルはカントの認識論を批判し、弁証法の概念を展開しつつ、壮大な有神論の体系を築いた。
認識は時間的生成の構造として把握されねばならない。これが弁証法のミソである。意識によって見いだされるものは、すでに「先構成」されている。それはすでに時間的に(歴史的に)構成されたものであり、持続する運動の途中過程にある。世界の存在の根源は、絶対精神から発し、精神的原理を展開しながら、運動を持続しているというのが、ヘーゲルの考え方である。
〈ヘーゲル哲学の体系はむしろさまざまな存在者の認識を超えて、人間と社会の生成変化の総体とその究極的動因(絶対的精神)についての「存在論的解釈学」としてうち立てられる。〉
ここで著者は、普遍認識論を打ち立てるためには、哲学の新たな原理(本体論の解体)を打ちだすとともに、哲学的相対主義ないし懐疑論を根本から批判しなくてはならないと述べている。
カントによる懐疑論の否定は、それ自体は認識できない「物自体」の観念をもたらした。
いっぽうヘーゲルにおいては、認識は本質的に否定の弁証法的運動として現れるのであって、相対主義と懐疑主義は、その一過程で登場するにすぎず、それ自体非本質的で偶然である。
イロニーもまた「正しさの信念」にたいするアンチテーゼである。イロニーは、自我、主観性を絶対とし、「絶対の内面」のみを存在の本質とする。客観性自体は放擲されている。現代のポストモダン思想には、こうしたイロニーの傾向が強い、と著者はいう。
絶対精神を根源とするヘーゲル哲学は、一種の汎神論である。それが自我から出発するのも事実だが、その自我も最終的には絶対精神に吸収されていってしまう。
ヘーゲルのつくりあげた一種の「本体論」に、著者はニーチェを対置する。
〈われわれはニーチェのマニフェストを思い起こさねばならない。近代科学は古い信仰を打ち倒しただろうか。否、それは「絶対神」の像を破壊したがそこに孕まれていた本体的思考、すなわち「真理への意志」を新しい仕方でうち立てたのだと。この自覚によって、はじめてヨーロッパの世界像は超越的な絶対者のみならず世界の「本体」の観念の完全な解体の道を拓いて進む。〉
本体論とは、世界の究極的根拠について語ろうとする独断論的思考だといってよい。
ニーチェは、いっさいの認識を欲望相関的−目的相関的ととらえ、「物自体」の観念を徹底的に破壊しようとする。
〈ニーチェの構図はこうである。「世界」は、さまざまな生命体の身体=欲望と相関的にのみ、それゆえまたさまざまな「生の世界」としてのみ、現出する。完全な認識は存在せず、したがって「物自体」の概念は成立しない。〉
ここには新しい存在論が登場している、と著者はいう。「存在」は生それ自身が構成するものだ。「身体と欲望に相関して絶えず価値と意味とが生成する力動の磁場こそが、われわれにとっての真なる世界にほかならない」
「原因」なるものは人間主体によって導き入れられたもので、原因それ自体はまったく存在しない。したがって、存在の始原原理や物自体、絶対精神などの「可想的理念」を取りあげること自体、意味がない、とニーチェはいう。
実証主義的−実在的世界像だけが残り、有神論的本体論は解体される。だからといって、哲学が終わるわけではない。「生」の相関者として、存在、対象、原因、意味、価値、真、世界といった概念が再編されなければならない。
生の事実は「生成」であり、「存在」はこの「生成」という力動の相関者として現れる。ニーチェはそのことをはじめてあきらかにした。そして、この「力相関性」の存在論を切り拓いたのがフッサールだ、と著者はいう。
こうしてフッサールの現象学への接近がはじまる。
むずかしいが、ついていくことにしよう。
フッサールは自然の客観的認識方法を「自然の数学化」と概括している。自然を客観的に認識するとは、自然空間と時間を幾何学的秩序として記述するとともに、自然事物の諸性質を数式化することにほかならなかった。
空間や時間を幾何学的にとらえ、それに基準(長さや高さ、温度、何時間など)といった基準を与えること。それによって「物理主義的合理主義の世界像」を与えることが目指されていた。
「こうして、すべての自然科学的研究はますます数学化された自然の表象体系として展開し、一切の認識を単なる『記号的概念』を操作する技術的思考へと変更する」
しかし、自然認識の方法は、認識とは何かという問題を解決したわけではなかった。そこでは、意味形成の根源についての問いが失われ、いわば「意味の空洞化」が生じていた、と著者はいう。
こうして心身二元論が登場する。すなわち事物と「心の世界」の分裂。主観と客観の対立。
スピノザはこれを統合しようとして、世界の一切は合理的な「神」から流出し、完全な因果関係の秩序のもとに成り立つという合理主義的独断論を打ちだす。これにたいし、ヒュームは、どのような世界観も個々の主体、あるいは諸文化の経験的な構成物にすぎないという経験主義的懐疑論を提示する。
合理主義的独断論と経験主義的懐疑論。「近代哲学の、そしてそれに続く現代哲学の認識論は、まだこの近代認識論における根本的対立構図から一度も解き放たれたことがない」。20世紀のマルクス主義とポストモダン思想の対立、論理実証主義と論理相対主義の対立をみても、そのことがわかる、と著者はいう。
さあ、ややこしくなってきた。
まずは、ヒュームの方法的懐疑論、方法的経験論について。一切の経験的因果性はただ主観のうちの「信念」としてのみ成立する。それは絶対的なものではなく、あくまでも情動(感情)によってもたらされた習慣的傾向としてとらえらえる。これがヒュームの考え方だ。
ものごとの発生する原因は無数に考えられる。しかし、真の原因などというものは「むしろ人間がそのつど何を自分にとって重要なものとみなすかという、生の目的性と相関的にのみ現われ出る」。逆に言い換えれば、力(作用)の因果性は遡行不可能ということになる。
ただし、ヒュームはみずからもゴルギアスのような懐疑論者ではないと述べている。われわれが「なぜ」と原因を問うのは、その根源性を求めるためではなく、その効用性、有用性を求めるためである。そうした原因がつきとめられたなら、それ以上のもの(たとえば神)に遡行する動機は失われる。「われわれは信念のそれ以上遡行できない底板につきあたったなら、そこにとどまるべきである」──著者はこれこそがヒュームの哲学の核心だという。
厳密にいえば、ヒュームを相対主義者、懐疑主義者と呼ぶのはあやまりで、かれの立場は「方法的経験論」にほかならない。著者自身も共感するニーチェとフッサールは、こうしたヒュームの考え方を引き継いでいるという。
とはいえ、ヨーロッパでは、長らく哲学の中心課題は、現象の背後にある「本体」、言い換えれば真の実在を探究することに置かれてきた。
ここで、近代の代表的哲学者として、カントとヘーゲルが登場する。
カントは『純粋理性批判』のアンチノミー(二律背反)の議論で、懐疑論を根本から否定し、世界認識の普遍的可能性を確立しようとした。帰謬論的相対主義は無化され、同時に形而上学的独断論も否定され、それによって哲学的な普遍認識の可能性を示そうとしたのである。
いっぽうで、カントは本質と現象という図式を提示した。世界は現象界と可想界(物自体)に区別される。現象界は客観的認識が可能である。しかし、物自体を完全に認識することはできない。
著者はこう書いている。
〈カントの「物自体」とは何か。絶対的に認識も経験もされえず、しかしその存在の想定なくして「われわれの世界」の存在自体が考えられないもの、われわれの世界の総体を絶対的に可能にしているものとしての「真なる存在」。それは完全にアクセス不可能であるがゆえに「語りえぬもの」であるが、われわれがこの世界を生きて経験する限り、その存在を否認することが決してできない「何かあるもの」。〉
「物自体」とは、人間の経験世界の背後にあって、現象一般を可能にしている何ものか(本体)である。ぼくなどには、かつて神と呼ばれた存在が、カントにおいては可想しうる「物自体」に変換されているのではないかと思えるほどである。神が「物自体」に置き換えられているとすれば、これはおそらくヨーロッパの思想界にとっては、大きな衝撃だったはずである。
次にヘーゲル。ヘーゲルはカントの認識論を批判し、弁証法の概念を展開しつつ、壮大な有神論の体系を築いた。
認識は時間的生成の構造として把握されねばならない。これが弁証法のミソである。意識によって見いだされるものは、すでに「先構成」されている。それはすでに時間的に(歴史的に)構成されたものであり、持続する運動の途中過程にある。世界の存在の根源は、絶対精神から発し、精神的原理を展開しながら、運動を持続しているというのが、ヘーゲルの考え方である。
〈ヘーゲル哲学の体系はむしろさまざまな存在者の認識を超えて、人間と社会の生成変化の総体とその究極的動因(絶対的精神)についての「存在論的解釈学」としてうち立てられる。〉
ここで著者は、普遍認識論を打ち立てるためには、哲学の新たな原理(本体論の解体)を打ちだすとともに、哲学的相対主義ないし懐疑論を根本から批判しなくてはならないと述べている。
カントによる懐疑論の否定は、それ自体は認識できない「物自体」の観念をもたらした。
いっぽうヘーゲルにおいては、認識は本質的に否定の弁証法的運動として現れるのであって、相対主義と懐疑主義は、その一過程で登場するにすぎず、それ自体非本質的で偶然である。
イロニーもまた「正しさの信念」にたいするアンチテーゼである。イロニーは、自我、主観性を絶対とし、「絶対の内面」のみを存在の本質とする。客観性自体は放擲されている。現代のポストモダン思想には、こうしたイロニーの傾向が強い、と著者はいう。
絶対精神を根源とするヘーゲル哲学は、一種の汎神論である。それが自我から出発するのも事実だが、その自我も最終的には絶対精神に吸収されていってしまう。
ヘーゲルのつくりあげた一種の「本体論」に、著者はニーチェを対置する。
〈われわれはニーチェのマニフェストを思い起こさねばならない。近代科学は古い信仰を打ち倒しただろうか。否、それは「絶対神」の像を破壊したがそこに孕まれていた本体的思考、すなわち「真理への意志」を新しい仕方でうち立てたのだと。この自覚によって、はじめてヨーロッパの世界像は超越的な絶対者のみならず世界の「本体」の観念の完全な解体の道を拓いて進む。〉
本体論とは、世界の究極的根拠について語ろうとする独断論的思考だといってよい。
ニーチェは、いっさいの認識を欲望相関的−目的相関的ととらえ、「物自体」の観念を徹底的に破壊しようとする。
〈ニーチェの構図はこうである。「世界」は、さまざまな生命体の身体=欲望と相関的にのみ、それゆえまたさまざまな「生の世界」としてのみ、現出する。完全な認識は存在せず、したがって「物自体」の概念は成立しない。〉
ここには新しい存在論が登場している、と著者はいう。「存在」は生それ自身が構成するものだ。「身体と欲望に相関して絶えず価値と意味とが生成する力動の磁場こそが、われわれにとっての真なる世界にほかならない」
「原因」なるものは人間主体によって導き入れられたもので、原因それ自体はまったく存在しない。したがって、存在の始原原理や物自体、絶対精神などの「可想的理念」を取りあげること自体、意味がない、とニーチェはいう。
実証主義的−実在的世界像だけが残り、有神論的本体論は解体される。だからといって、哲学が終わるわけではない。「生」の相関者として、存在、対象、原因、意味、価値、真、世界といった概念が再編されなければならない。
生の事実は「生成」であり、「存在」はこの「生成」という力動の相関者として現れる。ニーチェはそのことをはじめてあきらかにした。そして、この「力相関性」の存在論を切り拓いたのがフッサールだ、と著者はいう。
こうしてフッサールの現象学への接近がはじまる。
むずかしいが、ついていくことにしよう。
竹田青嗣『欲望論』を読む(2) [思想・哲学]

2年前、この本を衝動的に買ってしまい、序文だけ読んで放り出してしまった。悪い癖で、本屋に行くと、ついおもしろそうだと思い、買うのだが、買っただけで満足し、けっきょく読まないという本が多い。とくに哲学書がそうだ。買った手前、ぱらぱらとめくってみるのだが、前提となる教養がないため、読みはじめてもさっぱりわからず、すぐに投げだしてしまう。その繰り返し。
本の整理を迫られている。あまり先がなさそうだ。そんなわけで、年寄りの冷や水とからかわれるのを承知で、無謀にもこの本を読んでみることにした。
参考までに、前回の序文だけのまとめを挙げておく。「気の向くままに、少しずつ読んでいきたい」と書いたのに、いったいどうしたことだろう。困ったものだと思う。
https://kimugoq.blog.so-net.ne.jp/2017-12-09
今回は第1部「存在と認識」の第1章「哲学の問い」をまとめてみる。
人が世界をえがこうとするのは言葉をもつからである。最初の世界は宗教的世界としてあらわれる。死の畏怖が神々の世界をつくりだす。
神々の物語は、人のいまを説明する。それは確執と戦い、秩序と混沌、善と悪などからなる物語だ。神々によって、人間は創成されたと信じられる。
死の畏怖と不安から「普遍闘争」、すなわち「生きるために殺す」闘争がはじまる。そして、「共同防衛的集合社会」として国家が誕生する。その国家はもちろん戦争の主体でもある。そのさい、宗教は少なくとも共同体内では「暴力原理に対する根源的な抵抗」を示す平和原理となる。
哲学が登場するのは紀元前6世紀前後だ。それは最初、宗教的説話を受け継ぐかたちで誕生し、世界の始原的原理をさぐる言語ゲームへと発展していく。
インドのウパニシャッド哲学は、「有」から世界が生成し、広がっていくありさまを提示する。中国の老荘思想はわずかに世界の始原をえがくものの、儒教思想にはそうした哲学的思考はみられない。
インドにおける哲学体系の発展と世界原理の把握。そこでは精神と物質の区別、自我と知覚、思考、理性の関連が示される。苦と輪廻、解脱の思想が、その根本だ。
仏教はさらにその哲学を精緻化する。その過程で、一元論と多元論、唯物論と観念論などといった、哲学ならではのさまざまな対立図式が生まれる。
「空」の思想も誕生するが、まだ宗教的色彩が強く、本格的な「認識の謎」や「言語の謎」にはいたらない。もっぱら解脱をめざす便法にとどまる。相手の論の矛盾をつく帰謬論があらたな思索の方法を示したが、それは哲学の問いには発展しない。
ギリシャ哲学において、はじめて哲学の問いがあらわれる。すなわち、存在、認識、言語にたいする問いである。著者によれば、ギリシャで哲学が誕生したのは、そこには少なからず自由な社会が存在したからだという。言論の自由なくして、思索の発展もありえない。
イオニアの哲学者たちは、存在原理の探究から出発した。火と土と水。その発生と運動、展開、消滅、そして無限なるもの。ヘーゲルとハイデガーは、ここに哲学のはじまりをみる。しかし、世界認識の普遍性が問題として立ちあがるまでには、プラトンとアリストテレスの登場を待たねばならない。
ギリシャ的思考の特徴は宗教から離れた思考様式、すなわち自由な思考の展開にある。それは、世間の先入見と臆断を解除しつつ、理性がとらえうる最高の普遍性へと近づいていく。「思考の思考」が繰り広げられる。
パルメニデス。存在するものだけが存在する。人は存在するものしか思索できない。無から存在、存在から無への転移はない。
ヘラクレイトス。万物は永遠であり、不断の流れと運動のうちにある。世界は生成変化している。生成を生みだすのは、対立と調和、統一の動きである。ここには感覚的思考にとどまらない抽象的(超感覚的)思考、認識における時間性の契機が登場している。
認識の正しさ、言語の正しさは何によって保証されるのか。存在論、認識論、言語論の困難な問いから懐疑論が生まれる。
ギリシャにおける懐疑論の代表者はゼノンとゴルギアスである。ゼノンの有名なアキレスと亀のパラドクス。あるいは飛んでいる矢は止まっているというパラドクス。これらのパラドクスは論理学や数学では解決できない。これを解くには本質的な思考が必要となる。ゼノンはパラドクスをしめすことによって、哲学に相対主義的論理(帰謬論)を持ちこんだ。
ゴルギアスのテーゼ。何ものも存在するとはいえない。たとえ存在があるとしても、それを認識することは不可能である。またその認識が可能だとしても、それを言葉で表現するのは不可能である。
「存在と認識と言語の不可能性によって、ゴルギアスは、ギリシャ哲学における最も自覚的かつ本格的な相対主義哲学、懐疑論哲学をうち立てた」と、著者はいう。
懐疑論は形而上的独断論を批判するソフィストたちの武器となった。ソクラテス、プラトン、アリストテレスは普遍的認識論をもちだして、これに対抗することになる。
クセノフォンによれば、ソクラテスは世界とは何か、永遠とは何かといった問題ではなく、美とは何か、勇気とは何か、国家とは何かというような、現実生活に結びつく問題について、人に問いつづけた。生きる知恵を与える人だったという。
これにたいし、プラトンのえがくソクラテスは、対話弁証法を駆使しながら、新しい哲学的地平をひらいた思索者として登場する。ソクラテスは、人びとが自明とする認識に疑いをいだかせる。だが、ソフィストとちがい、真理についての確信をいだいている。
プラトンはソクラテスから認識の普遍性に到達するための方法を受け取る。それは「臆見(ドクサ)」から「真知(エピステーメー)」を導きだす方法だった。それによってプラトンは「イデア」説に行きつく。
プラトンの弟子、アリストテレスは、その代表作『形而上学』で、それまでの知の総体を総括することによって認識の普遍性にいたろうとした。だが、「存在」を規定しようとするその記述は網羅的で、混乱している、と著者はいう。
師プラトンのイデア説を批判するのが、アリストテレスの存在論の特徴である。あらゆる存在の「本体」としてのイデアなるものは、言葉のあそびであり、そんなものはない。
ものには原因(質量因、形相因、動因、目的因)があり、変化(生成と消滅、性質の変化、増大と減少、移動)がある。事物存在の様態は可能態と現実態からなる。人間の存在は、構成要素(精神と質量)、外的原因(父親)、内的原因(太陽)からできている。「実体」は物と宇宙、神である。
存在の総分類、原因から神にいたる考察がアリストテレスの思考の特徴だ。感覚だけでは事物の生成変化をとらえることはできない。それをおこなうには時間的契機を導入し、根本原因にいたり、もう一度事物の総体を見つめなおさなければならない。そこで発見されるのが「力」という概念だ。そして、一切の存在を生成する根本原因は神だという結論に達する。
ここで、もう一度プラトンのイデア説について、考えなおしてみよう、と著者はいう。
〈プラトンのイデア論は、長く、感覚的な世界の上位に超感覚的な世界をおく本質実在論、あるいは実念論であるという通念に支配されてきた。しかしプラトンのイデア論の最も重要な核心は「存在」の思考に対する「価値」の思考の優位という点にある。〉
プラトンは思惑や臆見に左右されやすい人間から出発する。その人間が「善のイデア」という価値に導かれて、「真知(エピステーメー)」、すなわち普遍の認識にいたるにはどうすればよいか。プラトンはそれをさぐろうとした、というのが著者のとらえ方である。
そして、ある意味で、著者もこのプラトンの思いを共有している。著者はニーチェとフッサールに依拠しながら、懐疑論と本体観念を根本的に解体し、間主観的確信にもとづく普遍的認識への道をさぐろうとしているからである。
快刀乱麻、新たな哲学が切り開かれようとしているのではないか。まだ、とば口だが、そんな予感がする。
部族国家から帝国へ、そして中世国家のはじまり──滝村隆一『国家論大綱』を読む(17) [思想・哲学]
ここからは第2巻の歴史的国家論にはいる。ただし、『国家論大綱』には断片的な(といっても膨大だが)論考しか残されていないので、おそらく当初予期されていた全体的考察からはほど遠いものになっている。
「方法としての世界史」において、滝村はヘーゲルとマルクスの方法を踏まえながら、世界史における国家の発展を、原初的、アジア的、古代的、中世的、近代的という段階的区別においてとらえることを提唱していた。それは必然的な歴史的発展というより、あくまでも把握の方法的枠組みだったといってよい。
国家の起源、すなわち原初的国家は部族国家に求められる。部族は氏族の連合から成り立っているが、その部族が祭祀的・政治的・軍事的指導者として王を立て、貴族層とそれ以外の一般成員、奴隷とを包摂するときに、部族国家が成立する、と滝村は書いている。
部族の経済基盤は農耕や牧畜である。部族においては、殺人や傷害、姦通や窃盗をはじめとして、さまざまなもめごとが発生する。自然の猛威も日常茶飯事だ。人間の集団には、内部のもめごとを解決したり、祭祀によって安全を祈ったり、死者をほうむったりする手法が不可欠になってくる。首長や長老が、こうした役割を担っていた。
いっぽうで、部族は他の共同体を略奪したり、逆に他の共同体の侵略を防いだりするために戦争をくり返している。部族の命運のかかる戦争にさいしては、一時的にでも軍事的指導者が必要になってくる。そして、部族が発展し、戦争や防御が日常的に要請されるようになると、当初は一時的だった軍事指導者が、次第に首長の祭祀的・裁判的役割をも吸収して、恒久的な王として擁立されることになる。それが部族国家を成立させる経緯だといってよい。
こうした部族国家は、ギリシャやローマでも、あるいは古代オリエントやゲルマン人共同体でも、はたまたアジア諸民族のあいだでも全世界的に出現したとみることができる。だが、その形態はかなり異なっていた、と滝村はいう。
そこでまず取りあげられるのが、部族国家段階のギリシャである。ギリシャでは諸部族が都市に集住して、独自の地域共同体をつくりあげた。そこでは異部族の連合にもとづく王政、ないし貴族政がおこなわれていた。そうした部族国家が必要とされたのは、たえまない戦争と交易の両面に対応するためである。部族的な王は何よりも軍事指導者であり、内部では祭祀長としてふるまい、裁判に関しては民会にしたがっていた。こうした形態は王政時代のローマも同じである。
だが、ギリシャでもローマでも、王政ないし貴族政は、下層の平民層によってくつがえされることになる。こうして、都市が発展するにつれて、法と共同機関を備えた市民の都市共同体が次第に誕生してくる。それを一般的に古典古代的段階の都市国家と呼ぶ。
次に滝村はマケドニアの場合を紹介している。マケドニアといえば、またたく間に世界帝国を築いたアレクサンドロス大王(BC356-BC323)の名が思い浮かぶ。もともとちいさな部族国家だったマケドニアでは、軍事的、政治的、祭祀的に最高の権能をもつ王が、ヘタイロイと呼ばれる騎士たちを親衛組織としてかかえていた。
アレクサンドロス大王のとき、このヘタイロイは8部隊に分かれ、それぞれが300騎から形成されていた。そして、8名の親衛隊長が、軍の最高幹部として王に仕えていた。従来の血統による貴族とは別に、王はこうした騎士階級をみずからに服属する新貴族として育て、その功績に応じて、かれらに所領を与えた。ここに部族国家が王国、帝国へと転じ、その中心に国家権力が形成されていく契機をみることができる、と滝村はいう。
アレクサンドロスの帝国を、滝村はギリシャ的というよりオリエント的、ないしアジア的[ヨーロッパからみてエーゲ海の東を意味する]なものととらえている。
帝国とは中心共同体が異系文化圏の共同体を従属的に支配する国家体制を意味する。帝国の形成は征服にもとづき、それによって従属共同体から貢納、租税、賦役を徴収する。その体制を維持するには、帝国は強大な軍事組織と行政機構を保持するとともに、それを指揮する帝権を必要とした。
父親のフィリッポス2世から軍事国家マケドニアを引き継いだアレクサンドロスは、強大な軍事力によって、次々と領土を拡張し、エジプト、ペルシャを征服した。広大な領土はすべて王のものとされたが、実質的には貴族層である将軍に下賜された。将軍たちは下賜された領地にたいする地租・地代徴収権と裁判権をもち、その治安維持にあたった。だが、アレクサンドロスの死により、その帝国はたちまち崩壊していく。
ローマ帝国もまたアレクサンドロスの帝国支配方式を受け継ぐ。共和政時代(BC509-BC27)のローマの政治体制は、元老院と上級政務官(執政官と法務官)、民会の三者によってかたちづくられていた。三者の関係は複雑で重層的である。とはいえ、滝村によれば、共和政ローマは、元老院が大きな役割をはたしながら、実質的には上級政務官が支配していたという。
ローマは外部世界への拡張によって発展した。宣戦や和平は元老院の決定にもとづく。だが、戦争の遂行にあたったのは上級政務官の執政官(コンスル)である。さらに属州が拡大するにつれて、属州統治の総督には、前執政官(プロコンスル)が任命された。民会はそれらの決定を承認するにすぎない。とはいえ、古代ローマの政治が、貴族層だけでなく平民層によってもかたちづくられていたのは、それが騎士と重装歩兵からなる戦士共同体の性格をもっていたからである。
しかし、第2次ポエニ戦争(BC219-BC201)以降、領土が飛躍的に拡大するなかで、ローマ帝国の政治体制は次第に変質していく。貴族が大土地所有者になるいっぽうで、自由農民が没落し、無産市民が生まれ、貴族の庇護民となっていく。民会は有名無実の存在に変わっていく。属州にたいする元老院の形式的権限(命令権)は強化されたが、軍事・裁判・徴税を掌握した上級政務官の属州統治権はそれ以上に強大化していった。そのなかでも、とりわけ注目すべきは、イタリア内を統治する執政官(コンスル)と属州を統治する前執政官(プロコンスル)の権限が分化していったことだ、と滝村は指摘している。
〈このような元老院の形式的かつ名目的強大化と、上級政務官権力の独立的強大化および民会の衰退という、共和政諸権力の実質的変形の下で、やがて共和政末期の長期にわたる内乱、すなわち強大な属州クリエンテス[庇護民]を抱える、有力政治家=武将間の血みどろの権力闘争が、展開される。それは、支配共同体の政治的共同体としての実質的解体を証示するものであるとともに、帝国支配としての一元制と統一性を実現するための、新たな政治的共同体としての統一的再編成への、胎動と飛躍の道であった。〉
ローマ帝国が共和政から帝政にいたる道筋をたどるのは必至だった。カエサルが独裁政権を樹立したあと、武将間の権力闘争と内乱に勝ち残ったのはオクタヴィアヌス(BC63-AD14)である。オクタヴィアヌスは初代ローマ皇帝となり、アウグストゥス[元首]の称号を得る。
オクタヴィアヌスは元老院へのかぎりなき忠誠と尊重を誓いながら、その権限を巧妙に奪いつつ、みずからの実質的支配権を確立した。帝国の属州全体への支配権と指揮統帥権を得たオクタヴィアヌスは、さらに元老院の議決権や裁判権を骨抜きにし、元首直属の軍事・官僚組織を確立していった。
いっぽう、帝国の周辺では、ゲルマン人の動きが次第に活発になっていた。紀元前50年ごろに書かれたカエサルの『ガリア戦記』には、ゲルマン人が農耕を嫌って、常に移動しながら、戦争と略奪をくり返していること、その生活様式が狩猟と粗野な牧畜にもとづくきわめて原始的なものであることが記されている。ところが、それから150年後、紀元100年くらいに書かれたタキトゥスの『ゲルマーニア』によると、ゲルマン人はすでに牧畜と農耕を主とする定着民族だとされている。カエサルとタキトゥスのちがいについては多くの論争がある。
だが、それはともかく、滝村が注目するのは、カエサルの記述に、ゲルマン人が戦時には戦争指揮者として首領を選び、首領のいない平時には長老が裁判でもめごとを収めるとされているところだ。いっぽう、タキトゥスは、すでにゲルマン人の多くの部族が王をもち、長老とともに村落を治める体制がつくられつつあると記している。ちいさなもめごとは長老によって処理されるが、宗教上・政治上の犯罪については、王と長老が民会を開き、裁判をおこなっていた。
滝村は次のようにとらえる。ゲルマン人の共同体において、軍事指揮者はもともと戦時においてのみ選出されていた。しかし、外部世界との緊張関係が常態化するにつれて、非日常的だった軍事指揮者が、祭祀の主催者たる地位を包摂することで超越的な部族王へと転成し、それによって萌芽的な部族国家が形成されたのだ、と。
もっとも、宗主権をもつ帝国の強制下で、部族を治めるために王が選出されるケースもないわけではない。この場合、王は帝国の手先ないし代官という性格をもつことになる。だが、帝国の苛酷な支配にたいする部族の抵抗や反発が強まったときには、傀儡首長が追放され、統一部族の首長のもとで独立戦争が戦われ、それが勝利したあかつきには、新たな部族国家が誕生するのである。
滝村は次のように書いている。
〈相次ぐ戦争と征服の只中から、典型的な部族国家を形成させた部族では、部族的・王が……とりもなおさず最高軍事指揮者として、下級の軍事指揮者たる各首長ないし長老を統率し……最高祭祀者として登場した。……そうして、この部族的・王および首長・長老層の、指導的ないし支配的な政治的地位は、直接富裕かつ筆頭的な経済的地位を、決定し保障する。〉
タキトゥスが指摘するように、ゲルマン人の生活は戦争と略奪を中心に回っていた。そして、勇敢に戦うことこそが、戦士としての権威と名誉、褒賞を保証したのである。
日常的な戦時体制によって、ゲルマン人は部族国家を形成し、王と貴族層(首長・長老)、従士を生みだした。とはいえ、「生まれたばかりの王権は、いぜん部族制度のおしめのなかにくるまって」いた、と滝村はいう。
そして、ゲルマン民族は4世紀の民族移動期をへて、部族国家から王国の段階へと突き進む。ローマ帝国が滅亡し、分裂する過程で、いわば戦国の覇者となったのは、ゲルマン民族の一族、フランク人だった。フランク人は5世紀後半にフランク王国を築くことになる。中世国家のはじまりである。
部族国家はどのようにして中世国家に転じていったのだろうか。
民族大移動と戦争は、王のもとに直属従士団をつくりあげていった。直属従士団は新貴族となり大土地を所有するいっぽう、王国には昔ながらの氏族による農民村落も残っていた。新貴族は王権のもと、領主として、租税・警察・裁判権を掌握し、私兵を育成した。王は貴族の上に立ち、徴兵権や裁判権を含む最高の権力を有していたが、その権力は部族共同体的な規範により大きな制約を受けたものだった。
だが、王の権力は次第に強まっていく。王は王国全域にわたる祭祀権(具体的には教会の保護)、外部にたいする戦争と講和の権利、政治秩序維持のための裁判権・警察権、経済面における関税徴税権、貨幣鋳造権、地代徴収権、採塩権などを有するようになる。そして上級貴族にたいしては、君臣関係にもとづき土地を給付して領地の支配をまかせるのと引き換えに、王が貴族にたいする軍役徴収権と官職任命権を握った。
こうして8世紀にはいると、王権と封建領主的支配権が確立し、農奴制にもとづく自給自足的な農村共同体が誕生する。これが中世国家のはじまりである。
[翻訳の仕事がはいったため、しばらくブログを休みます。つづきは後日。]
「方法としての世界史」において、滝村はヘーゲルとマルクスの方法を踏まえながら、世界史における国家の発展を、原初的、アジア的、古代的、中世的、近代的という段階的区別においてとらえることを提唱していた。それは必然的な歴史的発展というより、あくまでも把握の方法的枠組みだったといってよい。
国家の起源、すなわち原初的国家は部族国家に求められる。部族は氏族の連合から成り立っているが、その部族が祭祀的・政治的・軍事的指導者として王を立て、貴族層とそれ以外の一般成員、奴隷とを包摂するときに、部族国家が成立する、と滝村は書いている。
部族の経済基盤は農耕や牧畜である。部族においては、殺人や傷害、姦通や窃盗をはじめとして、さまざまなもめごとが発生する。自然の猛威も日常茶飯事だ。人間の集団には、内部のもめごとを解決したり、祭祀によって安全を祈ったり、死者をほうむったりする手法が不可欠になってくる。首長や長老が、こうした役割を担っていた。
いっぽうで、部族は他の共同体を略奪したり、逆に他の共同体の侵略を防いだりするために戦争をくり返している。部族の命運のかかる戦争にさいしては、一時的にでも軍事的指導者が必要になってくる。そして、部族が発展し、戦争や防御が日常的に要請されるようになると、当初は一時的だった軍事指導者が、次第に首長の祭祀的・裁判的役割をも吸収して、恒久的な王として擁立されることになる。それが部族国家を成立させる経緯だといってよい。
こうした部族国家は、ギリシャやローマでも、あるいは古代オリエントやゲルマン人共同体でも、はたまたアジア諸民族のあいだでも全世界的に出現したとみることができる。だが、その形態はかなり異なっていた、と滝村はいう。
そこでまず取りあげられるのが、部族国家段階のギリシャである。ギリシャでは諸部族が都市に集住して、独自の地域共同体をつくりあげた。そこでは異部族の連合にもとづく王政、ないし貴族政がおこなわれていた。そうした部族国家が必要とされたのは、たえまない戦争と交易の両面に対応するためである。部族的な王は何よりも軍事指導者であり、内部では祭祀長としてふるまい、裁判に関しては民会にしたがっていた。こうした形態は王政時代のローマも同じである。
だが、ギリシャでもローマでも、王政ないし貴族政は、下層の平民層によってくつがえされることになる。こうして、都市が発展するにつれて、法と共同機関を備えた市民の都市共同体が次第に誕生してくる。それを一般的に古典古代的段階の都市国家と呼ぶ。
次に滝村はマケドニアの場合を紹介している。マケドニアといえば、またたく間に世界帝国を築いたアレクサンドロス大王(BC356-BC323)の名が思い浮かぶ。もともとちいさな部族国家だったマケドニアでは、軍事的、政治的、祭祀的に最高の権能をもつ王が、ヘタイロイと呼ばれる騎士たちを親衛組織としてかかえていた。
アレクサンドロス大王のとき、このヘタイロイは8部隊に分かれ、それぞれが300騎から形成されていた。そして、8名の親衛隊長が、軍の最高幹部として王に仕えていた。従来の血統による貴族とは別に、王はこうした騎士階級をみずからに服属する新貴族として育て、その功績に応じて、かれらに所領を与えた。ここに部族国家が王国、帝国へと転じ、その中心に国家権力が形成されていく契機をみることができる、と滝村はいう。
アレクサンドロスの帝国を、滝村はギリシャ的というよりオリエント的、ないしアジア的[ヨーロッパからみてエーゲ海の東を意味する]なものととらえている。
帝国とは中心共同体が異系文化圏の共同体を従属的に支配する国家体制を意味する。帝国の形成は征服にもとづき、それによって従属共同体から貢納、租税、賦役を徴収する。その体制を維持するには、帝国は強大な軍事組織と行政機構を保持するとともに、それを指揮する帝権を必要とした。
父親のフィリッポス2世から軍事国家マケドニアを引き継いだアレクサンドロスは、強大な軍事力によって、次々と領土を拡張し、エジプト、ペルシャを征服した。広大な領土はすべて王のものとされたが、実質的には貴族層である将軍に下賜された。将軍たちは下賜された領地にたいする地租・地代徴収権と裁判権をもち、その治安維持にあたった。だが、アレクサンドロスの死により、その帝国はたちまち崩壊していく。
ローマ帝国もまたアレクサンドロスの帝国支配方式を受け継ぐ。共和政時代(BC509-BC27)のローマの政治体制は、元老院と上級政務官(執政官と法務官)、民会の三者によってかたちづくられていた。三者の関係は複雑で重層的である。とはいえ、滝村によれば、共和政ローマは、元老院が大きな役割をはたしながら、実質的には上級政務官が支配していたという。
ローマは外部世界への拡張によって発展した。宣戦や和平は元老院の決定にもとづく。だが、戦争の遂行にあたったのは上級政務官の執政官(コンスル)である。さらに属州が拡大するにつれて、属州統治の総督には、前執政官(プロコンスル)が任命された。民会はそれらの決定を承認するにすぎない。とはいえ、古代ローマの政治が、貴族層だけでなく平民層によってもかたちづくられていたのは、それが騎士と重装歩兵からなる戦士共同体の性格をもっていたからである。
しかし、第2次ポエニ戦争(BC219-BC201)以降、領土が飛躍的に拡大するなかで、ローマ帝国の政治体制は次第に変質していく。貴族が大土地所有者になるいっぽうで、自由農民が没落し、無産市民が生まれ、貴族の庇護民となっていく。民会は有名無実の存在に変わっていく。属州にたいする元老院の形式的権限(命令権)は強化されたが、軍事・裁判・徴税を掌握した上級政務官の属州統治権はそれ以上に強大化していった。そのなかでも、とりわけ注目すべきは、イタリア内を統治する執政官(コンスル)と属州を統治する前執政官(プロコンスル)の権限が分化していったことだ、と滝村は指摘している。
〈このような元老院の形式的かつ名目的強大化と、上級政務官権力の独立的強大化および民会の衰退という、共和政諸権力の実質的変形の下で、やがて共和政末期の長期にわたる内乱、すなわち強大な属州クリエンテス[庇護民]を抱える、有力政治家=武将間の血みどろの権力闘争が、展開される。それは、支配共同体の政治的共同体としての実質的解体を証示するものであるとともに、帝国支配としての一元制と統一性を実現するための、新たな政治的共同体としての統一的再編成への、胎動と飛躍の道であった。〉
ローマ帝国が共和政から帝政にいたる道筋をたどるのは必至だった。カエサルが独裁政権を樹立したあと、武将間の権力闘争と内乱に勝ち残ったのはオクタヴィアヌス(BC63-AD14)である。オクタヴィアヌスは初代ローマ皇帝となり、アウグストゥス[元首]の称号を得る。
オクタヴィアヌスは元老院へのかぎりなき忠誠と尊重を誓いながら、その権限を巧妙に奪いつつ、みずからの実質的支配権を確立した。帝国の属州全体への支配権と指揮統帥権を得たオクタヴィアヌスは、さらに元老院の議決権や裁判権を骨抜きにし、元首直属の軍事・官僚組織を確立していった。
いっぽう、帝国の周辺では、ゲルマン人の動きが次第に活発になっていた。紀元前50年ごろに書かれたカエサルの『ガリア戦記』には、ゲルマン人が農耕を嫌って、常に移動しながら、戦争と略奪をくり返していること、その生活様式が狩猟と粗野な牧畜にもとづくきわめて原始的なものであることが記されている。ところが、それから150年後、紀元100年くらいに書かれたタキトゥスの『ゲルマーニア』によると、ゲルマン人はすでに牧畜と農耕を主とする定着民族だとされている。カエサルとタキトゥスのちがいについては多くの論争がある。
だが、それはともかく、滝村が注目するのは、カエサルの記述に、ゲルマン人が戦時には戦争指揮者として首領を選び、首領のいない平時には長老が裁判でもめごとを収めるとされているところだ。いっぽう、タキトゥスは、すでにゲルマン人の多くの部族が王をもち、長老とともに村落を治める体制がつくられつつあると記している。ちいさなもめごとは長老によって処理されるが、宗教上・政治上の犯罪については、王と長老が民会を開き、裁判をおこなっていた。
滝村は次のようにとらえる。ゲルマン人の共同体において、軍事指揮者はもともと戦時においてのみ選出されていた。しかし、外部世界との緊張関係が常態化するにつれて、非日常的だった軍事指揮者が、祭祀の主催者たる地位を包摂することで超越的な部族王へと転成し、それによって萌芽的な部族国家が形成されたのだ、と。
もっとも、宗主権をもつ帝国の強制下で、部族を治めるために王が選出されるケースもないわけではない。この場合、王は帝国の手先ないし代官という性格をもつことになる。だが、帝国の苛酷な支配にたいする部族の抵抗や反発が強まったときには、傀儡首長が追放され、統一部族の首長のもとで独立戦争が戦われ、それが勝利したあかつきには、新たな部族国家が誕生するのである。
滝村は次のように書いている。
〈相次ぐ戦争と征服の只中から、典型的な部族国家を形成させた部族では、部族的・王が……とりもなおさず最高軍事指揮者として、下級の軍事指揮者たる各首長ないし長老を統率し……最高祭祀者として登場した。……そうして、この部族的・王および首長・長老層の、指導的ないし支配的な政治的地位は、直接富裕かつ筆頭的な経済的地位を、決定し保障する。〉
タキトゥスが指摘するように、ゲルマン人の生活は戦争と略奪を中心に回っていた。そして、勇敢に戦うことこそが、戦士としての権威と名誉、褒賞を保証したのである。
日常的な戦時体制によって、ゲルマン人は部族国家を形成し、王と貴族層(首長・長老)、従士を生みだした。とはいえ、「生まれたばかりの王権は、いぜん部族制度のおしめのなかにくるまって」いた、と滝村はいう。
そして、ゲルマン民族は4世紀の民族移動期をへて、部族国家から王国の段階へと突き進む。ローマ帝国が滅亡し、分裂する過程で、いわば戦国の覇者となったのは、ゲルマン民族の一族、フランク人だった。フランク人は5世紀後半にフランク王国を築くことになる。中世国家のはじまりである。
部族国家はどのようにして中世国家に転じていったのだろうか。
民族大移動と戦争は、王のもとに直属従士団をつくりあげていった。直属従士団は新貴族となり大土地を所有するいっぽう、王国には昔ながらの氏族による農民村落も残っていた。新貴族は王権のもと、領主として、租税・警察・裁判権を掌握し、私兵を育成した。王は貴族の上に立ち、徴兵権や裁判権を含む最高の権力を有していたが、その権力は部族共同体的な規範により大きな制約を受けたものだった。
だが、王の権力は次第に強まっていく。王は王国全域にわたる祭祀権(具体的には教会の保護)、外部にたいする戦争と講和の権利、政治秩序維持のための裁判権・警察権、経済面における関税徴税権、貨幣鋳造権、地代徴収権、採塩権などを有するようになる。そして上級貴族にたいしては、君臣関係にもとづき土地を給付して領地の支配をまかせるのと引き換えに、王が貴族にたいする軍役徴収権と官職任命権を握った。
こうして8世紀にはいると、王権と封建領主的支配権が確立し、農奴制にもとづく自給自足的な農村共同体が誕生する。これが中世国家のはじまりである。
[翻訳の仕事がはいったため、しばらくブログを休みます。つづきは後日。]
滝村国家論をめぐって(まとめ2) [思想・哲学]
8 国家とは何か
『国家論大綱』には、国家とは国家権力によって組織された社会だという言い方がでてくる。国家権力がないと、国家は存在しない。社会がなくても、国家は存在しない。
ポイントは国家権力である。国家権力とは何か。それは社会全体、すなわち国家を支配する力だといってよい。
滝村はこういう言い方をしている。
〈国家権力が、社会全体を法的規範にもとづいて組織化したとき、この法的に総括された〈社会〉は、他の歴史的社会との区別において、〈国家〉と呼ばれる。〉
論理的には、まず社会があって、次に外部社会との関係で国家が成立し、国家権力が誕生するということになる。
国家権力と国家とは区別されなければならない。
というのも、国家権力の形態が変わり、権力が移行しても、国家は存続しうるからである。逆に、国家権力が完全に消滅すれば、国家もまた消滅する。そのとき、かつての国家すなわち社会全体は、植民地ないし新たな領土として、別の国家に組み入れられてしまうことになるだろう。
国家と社会もまた区別されなければならない。
国家は社会を包みこむかたちで、国家として成立する。いっぽう、社会が国家を包みこむことはありえない。
というのも、完全に国家から隔離された部族社会も存在しうるからである。
また国家権力の正統性が問われるときには、あたかも国家と社会が乖離するような事態が生じてくるかもしれない。
近代においては、一般に国家は政治を担い、社会は経済を担うと思われている。しかし、国家は「法的に統合・総括された社会」なのであって、社会は国家から分離されているわけではないのである。
このように国家と国家権力と社会は別の概念なのだが、実際はからみあっているので、その関係をしっかりと押さえておく必要がある、と滝村はいう。
じつにややこしいが、とりあえず、国家とは国家権力によって法的に組織された社会である、という定義をもう一度頭に入れておこう。
それでは国家と国家権力は、どのようにして生まれてきたのだろうか。
国家の成立は国家権力に先行する、と滝村は書いている。
国家の前は部族社会が存在した。
部族社会は首長をもつ血縁的共同体である。だが、それはたったひとつしかなかったわけではない。多くの部族社会があったと考えられる。
ある部族社会が外部の部族社会との関係を有するようになったとしよう。その関係には、戦争や交易が含まれるが、とりわけ緊張が高まるのが戦争の可能性が生じたときである。そのとき、部族社会は外部の脅威に備えるため始原的な国家を形成する。そして、その内部に部族社会全体を統率する国家権力が生まれてくるのである。
そこで、国家についての滝村の新たな定義が生まれる。
〈〈国家〉は内外危機から〈社会〉全体を維持・遵守するために、〈社会〉を挙げて構成された、統一的で独立的な組織体である。〉
つまり、国家は共同体が外敵に備える体制をつくる必要に迫られたときに誕生するのだ。
国家の存立根拠は外敵にたいして社会を守ることだといってよい。しかし、守ることは攻めることでもある。
国を守ることが、いつの間にか、ほかの国を滅ぼすことへとつながっていく。
こうして、国家は部族国家から王国、帝国へと発展していくのだ。
部族国家は始原的な国家である。その部族国家が他の部族国家を吸収したときには王国が成立する。そして、帝国は「特定の王国が、数種の異系文化圏の諸王国や諸部族国家を、その政治的傘下に包摂した」段階で成立するといってよい。
世界史的にみれば、こうした国家は、アジア的、古代的、中世的といった典型的形態をたどった。いま、それを詳しく述べるのは、やめておくが、近代以前の世界史的国家についていえることは、どの形態の国家においても、国家権力はじゅうぶんに発達していなかったということだ。
国家権力が社会全体を法的に包摂するまでに発達するのは、近代国家にいたってである。
近代国家のひとつの特徴は、社会の構成員が社会的活動と精神的活動の自由を国家によって保証されていることだ。
市民権を付与された個人は、法的には市民と呼ばれ、政治的には国民と呼ばれる。市民権を付与された国民が登場するのは、民主的政治形態のもとにおいてのみである、と滝村は述べている。
近代国家において、国民は多かれ少なかれ国家意識をもつようになる。それは教育などによって培われたものであるが、いくらコスモポリタンだと思っていても、海外に行けば、たとえば自分が日本人であることは、いやおうなく意識させられるものだ。
そうしたことをいわば前置きとして、滝村は自分自身もいやおうなく組みこまれている現代の国家とは何かを説き起こしていく。
9 社会と国家
社会はなぜ国家を必要とするか、と滝村は書いている。
これは頭から国家を抑圧・統制機関とする発想とはことなる。
たしかに、時に国家はいまわしいほどの抑圧・統制機関へと転じる。それでも、なぜ社会は国家を必要とするのだろうか。
国家とは、国家権力によって政治的に(法的に)組織された社会のことだ、と滝村は定義した。それは内外の危難にたいし、社会全体として対応する(その対応はしばしば攻撃のかたちをとるが)ために形成された。
すると、内外に危難がなくならないかぎり(あるいは逆に別の国家に統合されないかぎり)、国家は存続するということになる。
ところで、国家権力を構成するのは公務員と呼ばれる人びとである。中央、地方合わせて、その数は日本では総人口の約7%(米国は約15%、イギリスは17%、フランスは23%)にあたる。かれらは社会的な生産に従事するわけではなく、税金によってその公的活動に当たっている。
それでは国民はなぜ大きな租税負担に耐えてまで、公務員による国家的活動を容認しているのか、と滝村は問う。
それはやはり社会が国家を必要としているからではないのか。
現在の先進国において、社会は近代市民社会の形態をとっている。
近代市民社会では、個人の経済的・社会的・精神的な活動の自由が認められている。こうした社会が築かれるまでには、長い抵抗と闘争の歴史があったことはいうまでもない。そして、近代市民社会が形成されることによって、専制的国家体制は倒され、ようやく民主主義的国家体制が生まれた。
とはいえ、滝村によれば、その自由な社会が「ごく一握りの少数者と大多数の一般大衆との間の、かつてない経済的な格差と〈不平等〉をもたらした」ことも事実だった。その社会は自由であるからこそ、常に苛酷な経済的・社会的闘争がくり広げられる、競争と対立の場になった。
そこで、国家権力は社会において生ずる紛争を処理するためにも必要とされるようになる。
それ以上に重要なのが、外部の国家との関係だった。その関係は常に交易だけではなく紛争を内在させている。そして、紛争は最悪の場合、戦争へと発展しかねない可能性を秘めている。
「他の歴史的社会は、友好・同盟・対立・競合のすべてを超えて、つねに〈敵国〉へと転化しうるというところに、歴史社会の〈国家〉的構成の必要と必然が、内在している」と滝村は述べている。
歴史的にみれば、あらゆる部族国家は、部族国家どうしの対立のなかから、王国ないし帝国へと発展する可能性をもっていた。さもなければ、どこかの王国ないし帝国に従属するほかなかった。
その傾向は近代国家においても変わらない。
「先進諸国相互においては、一方で、かつてない網の目のように緊密な貿易的連関を生み出しながら、同時に他方で、後進諸国を政治的な手中に収めんという世界的覇権をめぐる戦いが、つい半世紀ほど前まで、国民社会の総力を挙げてくり返されてきた」と、滝村は指摘する。
こうして、国家としては、軍事・防衛が政治上、最大の任務となるのである。
次に国家に求められるのが、国民の共通利害を守ることである。その筆頭に挙げられるのは、社会秩序を守るための治安活動である。またインフラを整備するための公共土木工事も求められるだろう。最近は、経済政策や社会政策も重要になってきた。
いっぽう、共通利害が分裂する場合、あるいは特定の利害に国家がかかわることもある。
たとえば社会的紛争や経済的紛争が当事者間で解決しない場合である。この場合は国家が介入することになる。さらに、突然の自然災害や経済危機など、諸個人や地域社会だけでは対応しきれない事態が生じた場合にも、国家が問題解決に乗りだし、社会的救済にあたらなくてはならない。
これらは、実際には国家の名において、国家権力によって対応がなされる。
言い換えれば、どのような国家権力であっても、政治的に組織された社会、すなわち国家の安全を守ることが求められるのである。逆に社会の安全を守れなくなれば、国家権力は解体・変更を余儀なくされる。最悪の場合、国家権力自体の消滅、すなわち国家の崩壊を招くことになるだろう。
国家と国家権力を区別することは重要だ、と滝村は強調している。国家権力が民主的か専制的かによって、国家のかたちはかなり異なってくる。
国家はしばしば国家権力と同一視されがちだった。レーニンは国家を暴力装置と規定し、その暴力装置を取り除きさえすれば、国家は消滅するのだと考えた。この規定は、どうみても国家と国家権力を同一視している。
ところが、どうだろう。レーニンのソヴィエト政権は、それ自体、独裁政権と化し、ソヴィエト政権を守ることがあたかも国家を守ることであり、ソヴィエト政権を対外的に拡張することが、社会主義を広げることだという幻想におちいってしまった。そこでは、近代社会における国民の自由な活動を保証するという、国家としての最低限の役割さえ見失われがちだった。
いっぽう、アナキズムもまた国家と国家権力を同一視しているとみてもよい。そこでは反権力・反国家がどこまでも追求されることになり、その先の展望はまったく見えなくなってしまうのである。パリの五月革命や日大・東大闘争など、1968年当時の雰囲気が思い出される。
国家と国家権力の区別と連関をあきらかにした滝村国家論の意義は大きいといわねばならない。
10 統治と行政
国家活動をおこなうのは、いうまでもなく国家権力である。
国家活動は大きく対外的活動と対内的活動に分けられる。前者を外政、後者を内政と呼ぶことができる。
しかし、より本質的にいうなら、国家の活動は統治と行政から成り立っている、と滝村はいう。
統治は国家の根幹を保持するための対外的な政治活動である。対外的というのは、外部国家の動きに、国家がどう応じるかという問題にほかならない。それは、具体的には、外交、軍事、通商、治安、金融などへの対応を意味している。
これにたいし、行政は国民に向けられた、いわば対内的な政治的対応である。滝村によれば、行政とは「国家権力による当該社会の内部的な統制・支配の全般的活動」と定義されている。
具体的には財政政策や公共土木工事、労働政策、社会保障、警察活動などが含まれるだろう。教育や宗教政策も行政の分野にちがいないが、それは統治にもかかわる問題である。
統治と行政はいちおう区分けできる。しかし、たとえば行政レベルで問題が解決できず、それが国家の根幹を揺るがす事態になれば、問題はとうぜん統治レベルへと格上げされる。また対外的な政策が、国内に影響をもたらすこともたしかである。その点、統治と行政は密接にからんでいる。
それでも、滝村国家論が特徴的なのは、国家権力による国家的活動を、統治と行政に区分けしたところである。統治なき行政、行政なき統治はともに国家の存立をあやうくするだろう。
そこで、まず統治について、見ていくことにしよう。
ここでもっとも重要なのは対外政策(外交・軍事)である。対外政策には国家の存亡と興廃がかかっている。
現実世界では、主要な敵国を念頭において、政治的同盟政策が展開されている。それは軍事同盟の性格をもつから、対外政策は軍備力をともなう軍事政策と関連していく。
現実世界において、はたして非武装中立、あるいは武装中立はありうるんだろうか。
国際政治の世界は、「力の均衡」によって成り立っている、と滝村はいう。その均衡は、「自国の現状に飽き足らない諸国」が「飛躍的な発展」を遂げることによって崩れやすい。
そのために「均衡」政策は、「新興政策による『秩序』の革命的破壊を未然に封殺し、局地での紛争が『秩序』破壊にまで拡大しないよう、強力に制御すること」をめざすという。
しかし、それが抑えられず、国際世界の政治秩序が大きく破壊されるときには、世界戦争が勃発する可能性がある。
国家権力が外交と軍事を掌握するのは、端的にいって、国家を守るためである、と滝村はいう。国際政治の現実は無視できない。外交と軍事にたいする、しっかりした自主性があってこそ、国家は守られるのだ、と滝村は考えている。賢い選択が必要だろう。
滝村はさらに対外政策としての通商問題にも触れている。通商政策はけっきょく自由貿易か保護貿易かの選択に帰着する。具体的にいえば、通商政策は関税や自由化、国内産業の保護育成、輸出奨励などの問題にかかわる。
通商政策は、外交や軍事といちおう切り離すことができる。たとえ政治的に敵対関係にあったとしても、通商関係は経済問題として扱える。だが、いくら経済的に切り離せるといっても、経済関係の対立が深まれば、それは容易に外交問題、さらには軍事問題へと発展する可能性を内在している。
もちろん外交関係の樹立なくして、通商関係がありえないことはいうまでもない。
さらに滝村は、統治にかかわる重要課題として、治安活動に触れ、それが二重に分化するとして、こう述べている。
〈それは、当該社会全体を直接震撼させる、大規模な組織的違法[犯罪]活動を制圧し、また未然に制御するための特殊〈治安警察〉活動と、その他の個別的違法[犯罪]活動に実践的に対応する、一般〈行政警察〉活動との分離である。〉
つまり、治安活動は、治安警察活動と行政警察活動にわけて考えることができる。そして、ここから政府に直属する治安警察と、地方の管轄する行政警察とがわかれることになる。
これはあたりまえのように思えるが、そうではない。軍と警察の分離、治安部門と行政部門への警察の分離と二重化は、きわめて近代的な現象なのである。
言い換えれば、近代以前においては、軍と警察が一体化しており、それはすべて国家権力のための治安活動に向けられており、国民の安寧はほぼ無視されていたといってよい。
次に論じられるのは行政である。
行政は資本主義的生産様式と議会制民主主義とがセットになった近代国家において、はじめて発現する、と滝村は書いている。
行政のなかでも、とりわけ重要なのが経済政策である。
経済政策は財政政策と金融政策に分類することができる。
基本的に国家の財政は、国民から強制的に徴集された租税によって成り立っている。国家財政は予算にもとづいて運営される。その予算は議会において審議され、承認される。
国家予算は外交・軍事・治安など統治にかかわる部分と、公共事業・社会保障・医療・文教・環境・公害防止など行政にかかわる部分から成り立っている。
財政政策が登場するのは1930年代以降である。それによって、予算は社会に還元されるようになった。それまで財政は専制的国家を維持するためにのみ運用されていた。
いっぽうの金融政策は、中央銀行が金融の流れを調節することによって、金融制度全体の維持・安定をはかることを目的としている。
とりわけ1930年以降は通貨が兌換制から管理体制へと移行するなかで、金融政策の重要性が高まってきた。金融政策は景気循環を調整し、とりわけ恐慌を防止する手段として、広く活用されるようになった。
社会政策はもっとも新しい分野である。滝村によれば、社会政策が本格的に展開されるようになったのは第2次世界大戦後であって、「社会的な弱者・貧困者への国家的保護・救済の必要」が高まったためである。
その背景には、普通選挙制度を通じて議会制民主主義が定着し、それによって労働組合が大きな勢力として登場したことがあるという。
とはいえ、社会政策には長い前史がある。それは治安維持と結びついた救貧行政からはじまって、失業者対策などの労働政策、さらに社会保険の導入へとつづき、現在では医療・失業・年金の社会保険に加えて、生活保護の公的扶助が加わるようになった。
滝村によれば、社会政策は「個別資本による労働者への際限なき苛酷な搾取と抑圧に、国家権力が〈平均的な必要労働[つまり雇用]の保障〉という、一定の歯止めをかけるもの」であったという。
つまり、社会政策には、労働者の生活を改善することで、労働者階級の反乱を防ぐとともに、消費市場を拡大するねらいがあった。
そして、最後が公教育である。滝村は、公教育とは単に国家による教育を指すのではないという。それは国民教育でもあって、「国家権力が社会構成員[国民]の全子弟に対して、一定期間明確な目的をもって行なう学校教育」であり、義務教育としての性格をもっている。
さらに滝村は、「〈公教育〉とは、国家権力による目的的な人間形成であり、とりもなおさず〈近代社会〉に対応した社会的人間を、目的的につくりあげるためのものであった」と述べている。
そのため、公教育においては、読み書きそろばんに加えて、自然科学の知識や道徳・倫理、社会・歴史の知識が生徒に注入される。それは、国民になるための「思想的・イデオロギー的教育」の性格をもっている。
以上で、統治と行政からなる、国家権力の実質的構成が概観された。
滝村国家論はいかにもぶっきらぼうである。
しかし、それは国家嫌いの左翼の幻想を打ち破るとともに、国家至上主義の思想を振りまく右翼にも痛棒をくらわす性格をもっているのである。
『国家論大綱』には、国家とは国家権力によって組織された社会だという言い方がでてくる。国家権力がないと、国家は存在しない。社会がなくても、国家は存在しない。
ポイントは国家権力である。国家権力とは何か。それは社会全体、すなわち国家を支配する力だといってよい。
滝村はこういう言い方をしている。
〈国家権力が、社会全体を法的規範にもとづいて組織化したとき、この法的に総括された〈社会〉は、他の歴史的社会との区別において、〈国家〉と呼ばれる。〉
論理的には、まず社会があって、次に外部社会との関係で国家が成立し、国家権力が誕生するということになる。
国家権力と国家とは区別されなければならない。
というのも、国家権力の形態が変わり、権力が移行しても、国家は存続しうるからである。逆に、国家権力が完全に消滅すれば、国家もまた消滅する。そのとき、かつての国家すなわち社会全体は、植民地ないし新たな領土として、別の国家に組み入れられてしまうことになるだろう。
国家と社会もまた区別されなければならない。
国家は社会を包みこむかたちで、国家として成立する。いっぽう、社会が国家を包みこむことはありえない。
というのも、完全に国家から隔離された部族社会も存在しうるからである。
また国家権力の正統性が問われるときには、あたかも国家と社会が乖離するような事態が生じてくるかもしれない。
近代においては、一般に国家は政治を担い、社会は経済を担うと思われている。しかし、国家は「法的に統合・総括された社会」なのであって、社会は国家から分離されているわけではないのである。
このように国家と国家権力と社会は別の概念なのだが、実際はからみあっているので、その関係をしっかりと押さえておく必要がある、と滝村はいう。
じつにややこしいが、とりあえず、国家とは国家権力によって法的に組織された社会である、という定義をもう一度頭に入れておこう。
それでは国家と国家権力は、どのようにして生まれてきたのだろうか。
国家の成立は国家権力に先行する、と滝村は書いている。
国家の前は部族社会が存在した。
部族社会は首長をもつ血縁的共同体である。だが、それはたったひとつしかなかったわけではない。多くの部族社会があったと考えられる。
ある部族社会が外部の部族社会との関係を有するようになったとしよう。その関係には、戦争や交易が含まれるが、とりわけ緊張が高まるのが戦争の可能性が生じたときである。そのとき、部族社会は外部の脅威に備えるため始原的な国家を形成する。そして、その内部に部族社会全体を統率する国家権力が生まれてくるのである。
そこで、国家についての滝村の新たな定義が生まれる。
〈〈国家〉は内外危機から〈社会〉全体を維持・遵守するために、〈社会〉を挙げて構成された、統一的で独立的な組織体である。〉
つまり、国家は共同体が外敵に備える体制をつくる必要に迫られたときに誕生するのだ。
国家の存立根拠は外敵にたいして社会を守ることだといってよい。しかし、守ることは攻めることでもある。
国を守ることが、いつの間にか、ほかの国を滅ぼすことへとつながっていく。
こうして、国家は部族国家から王国、帝国へと発展していくのだ。
部族国家は始原的な国家である。その部族国家が他の部族国家を吸収したときには王国が成立する。そして、帝国は「特定の王国が、数種の異系文化圏の諸王国や諸部族国家を、その政治的傘下に包摂した」段階で成立するといってよい。
世界史的にみれば、こうした国家は、アジア的、古代的、中世的といった典型的形態をたどった。いま、それを詳しく述べるのは、やめておくが、近代以前の世界史的国家についていえることは、どの形態の国家においても、国家権力はじゅうぶんに発達していなかったということだ。
国家権力が社会全体を法的に包摂するまでに発達するのは、近代国家にいたってである。
近代国家のひとつの特徴は、社会の構成員が社会的活動と精神的活動の自由を国家によって保証されていることだ。
市民権を付与された個人は、法的には市民と呼ばれ、政治的には国民と呼ばれる。市民権を付与された国民が登場するのは、民主的政治形態のもとにおいてのみである、と滝村は述べている。
近代国家において、国民は多かれ少なかれ国家意識をもつようになる。それは教育などによって培われたものであるが、いくらコスモポリタンだと思っていても、海外に行けば、たとえば自分が日本人であることは、いやおうなく意識させられるものだ。
そうしたことをいわば前置きとして、滝村は自分自身もいやおうなく組みこまれている現代の国家とは何かを説き起こしていく。
9 社会と国家
社会はなぜ国家を必要とするか、と滝村は書いている。
これは頭から国家を抑圧・統制機関とする発想とはことなる。
たしかに、時に国家はいまわしいほどの抑圧・統制機関へと転じる。それでも、なぜ社会は国家を必要とするのだろうか。
国家とは、国家権力によって政治的に(法的に)組織された社会のことだ、と滝村は定義した。それは内外の危難にたいし、社会全体として対応する(その対応はしばしば攻撃のかたちをとるが)ために形成された。
すると、内外に危難がなくならないかぎり(あるいは逆に別の国家に統合されないかぎり)、国家は存続するということになる。
ところで、国家権力を構成するのは公務員と呼ばれる人びとである。中央、地方合わせて、その数は日本では総人口の約7%(米国は約15%、イギリスは17%、フランスは23%)にあたる。かれらは社会的な生産に従事するわけではなく、税金によってその公的活動に当たっている。
それでは国民はなぜ大きな租税負担に耐えてまで、公務員による国家的活動を容認しているのか、と滝村は問う。
それはやはり社会が国家を必要としているからではないのか。
現在の先進国において、社会は近代市民社会の形態をとっている。
近代市民社会では、個人の経済的・社会的・精神的な活動の自由が認められている。こうした社会が築かれるまでには、長い抵抗と闘争の歴史があったことはいうまでもない。そして、近代市民社会が形成されることによって、専制的国家体制は倒され、ようやく民主主義的国家体制が生まれた。
とはいえ、滝村によれば、その自由な社会が「ごく一握りの少数者と大多数の一般大衆との間の、かつてない経済的な格差と〈不平等〉をもたらした」ことも事実だった。その社会は自由であるからこそ、常に苛酷な経済的・社会的闘争がくり広げられる、競争と対立の場になった。
そこで、国家権力は社会において生ずる紛争を処理するためにも必要とされるようになる。
それ以上に重要なのが、外部の国家との関係だった。その関係は常に交易だけではなく紛争を内在させている。そして、紛争は最悪の場合、戦争へと発展しかねない可能性を秘めている。
「他の歴史的社会は、友好・同盟・対立・競合のすべてを超えて、つねに〈敵国〉へと転化しうるというところに、歴史社会の〈国家〉的構成の必要と必然が、内在している」と滝村は述べている。
歴史的にみれば、あらゆる部族国家は、部族国家どうしの対立のなかから、王国ないし帝国へと発展する可能性をもっていた。さもなければ、どこかの王国ないし帝国に従属するほかなかった。
その傾向は近代国家においても変わらない。
「先進諸国相互においては、一方で、かつてない網の目のように緊密な貿易的連関を生み出しながら、同時に他方で、後進諸国を政治的な手中に収めんという世界的覇権をめぐる戦いが、つい半世紀ほど前まで、国民社会の総力を挙げてくり返されてきた」と、滝村は指摘する。
こうして、国家としては、軍事・防衛が政治上、最大の任務となるのである。
次に国家に求められるのが、国民の共通利害を守ることである。その筆頭に挙げられるのは、社会秩序を守るための治安活動である。またインフラを整備するための公共土木工事も求められるだろう。最近は、経済政策や社会政策も重要になってきた。
いっぽう、共通利害が分裂する場合、あるいは特定の利害に国家がかかわることもある。
たとえば社会的紛争や経済的紛争が当事者間で解決しない場合である。この場合は国家が介入することになる。さらに、突然の自然災害や経済危機など、諸個人や地域社会だけでは対応しきれない事態が生じた場合にも、国家が問題解決に乗りだし、社会的救済にあたらなくてはならない。
これらは、実際には国家の名において、国家権力によって対応がなされる。
言い換えれば、どのような国家権力であっても、政治的に組織された社会、すなわち国家の安全を守ることが求められるのである。逆に社会の安全を守れなくなれば、国家権力は解体・変更を余儀なくされる。最悪の場合、国家権力自体の消滅、すなわち国家の崩壊を招くことになるだろう。
国家と国家権力を区別することは重要だ、と滝村は強調している。国家権力が民主的か専制的かによって、国家のかたちはかなり異なってくる。
国家はしばしば国家権力と同一視されがちだった。レーニンは国家を暴力装置と規定し、その暴力装置を取り除きさえすれば、国家は消滅するのだと考えた。この規定は、どうみても国家と国家権力を同一視している。
ところが、どうだろう。レーニンのソヴィエト政権は、それ自体、独裁政権と化し、ソヴィエト政権を守ることがあたかも国家を守ることであり、ソヴィエト政権を対外的に拡張することが、社会主義を広げることだという幻想におちいってしまった。そこでは、近代社会における国民の自由な活動を保証するという、国家としての最低限の役割さえ見失われがちだった。
いっぽう、アナキズムもまた国家と国家権力を同一視しているとみてもよい。そこでは反権力・反国家がどこまでも追求されることになり、その先の展望はまったく見えなくなってしまうのである。パリの五月革命や日大・東大闘争など、1968年当時の雰囲気が思い出される。
国家と国家権力の区別と連関をあきらかにした滝村国家論の意義は大きいといわねばならない。
10 統治と行政
国家活動をおこなうのは、いうまでもなく国家権力である。
国家活動は大きく対外的活動と対内的活動に分けられる。前者を外政、後者を内政と呼ぶことができる。
しかし、より本質的にいうなら、国家の活動は統治と行政から成り立っている、と滝村はいう。
統治は国家の根幹を保持するための対外的な政治活動である。対外的というのは、外部国家の動きに、国家がどう応じるかという問題にほかならない。それは、具体的には、外交、軍事、通商、治安、金融などへの対応を意味している。
これにたいし、行政は国民に向けられた、いわば対内的な政治的対応である。滝村によれば、行政とは「国家権力による当該社会の内部的な統制・支配の全般的活動」と定義されている。
具体的には財政政策や公共土木工事、労働政策、社会保障、警察活動などが含まれるだろう。教育や宗教政策も行政の分野にちがいないが、それは統治にもかかわる問題である。
統治と行政はいちおう区分けできる。しかし、たとえば行政レベルで問題が解決できず、それが国家の根幹を揺るがす事態になれば、問題はとうぜん統治レベルへと格上げされる。また対外的な政策が、国内に影響をもたらすこともたしかである。その点、統治と行政は密接にからんでいる。
それでも、滝村国家論が特徴的なのは、国家権力による国家的活動を、統治と行政に区分けしたところである。統治なき行政、行政なき統治はともに国家の存立をあやうくするだろう。
そこで、まず統治について、見ていくことにしよう。
ここでもっとも重要なのは対外政策(外交・軍事)である。対外政策には国家の存亡と興廃がかかっている。
現実世界では、主要な敵国を念頭において、政治的同盟政策が展開されている。それは軍事同盟の性格をもつから、対外政策は軍備力をともなう軍事政策と関連していく。
現実世界において、はたして非武装中立、あるいは武装中立はありうるんだろうか。
国際政治の世界は、「力の均衡」によって成り立っている、と滝村はいう。その均衡は、「自国の現状に飽き足らない諸国」が「飛躍的な発展」を遂げることによって崩れやすい。
そのために「均衡」政策は、「新興政策による『秩序』の革命的破壊を未然に封殺し、局地での紛争が『秩序』破壊にまで拡大しないよう、強力に制御すること」をめざすという。
しかし、それが抑えられず、国際世界の政治秩序が大きく破壊されるときには、世界戦争が勃発する可能性がある。
国家権力が外交と軍事を掌握するのは、端的にいって、国家を守るためである、と滝村はいう。国際政治の現実は無視できない。外交と軍事にたいする、しっかりした自主性があってこそ、国家は守られるのだ、と滝村は考えている。賢い選択が必要だろう。
滝村はさらに対外政策としての通商問題にも触れている。通商政策はけっきょく自由貿易か保護貿易かの選択に帰着する。具体的にいえば、通商政策は関税や自由化、国内産業の保護育成、輸出奨励などの問題にかかわる。
通商政策は、外交や軍事といちおう切り離すことができる。たとえ政治的に敵対関係にあったとしても、通商関係は経済問題として扱える。だが、いくら経済的に切り離せるといっても、経済関係の対立が深まれば、それは容易に外交問題、さらには軍事問題へと発展する可能性を内在している。
もちろん外交関係の樹立なくして、通商関係がありえないことはいうまでもない。
さらに滝村は、統治にかかわる重要課題として、治安活動に触れ、それが二重に分化するとして、こう述べている。
〈それは、当該社会全体を直接震撼させる、大規模な組織的違法[犯罪]活動を制圧し、また未然に制御するための特殊〈治安警察〉活動と、その他の個別的違法[犯罪]活動に実践的に対応する、一般〈行政警察〉活動との分離である。〉
つまり、治安活動は、治安警察活動と行政警察活動にわけて考えることができる。そして、ここから政府に直属する治安警察と、地方の管轄する行政警察とがわかれることになる。
これはあたりまえのように思えるが、そうではない。軍と警察の分離、治安部門と行政部門への警察の分離と二重化は、きわめて近代的な現象なのである。
言い換えれば、近代以前においては、軍と警察が一体化しており、それはすべて国家権力のための治安活動に向けられており、国民の安寧はほぼ無視されていたといってよい。
次に論じられるのは行政である。
行政は資本主義的生産様式と議会制民主主義とがセットになった近代国家において、はじめて発現する、と滝村は書いている。
行政のなかでも、とりわけ重要なのが経済政策である。
経済政策は財政政策と金融政策に分類することができる。
基本的に国家の財政は、国民から強制的に徴集された租税によって成り立っている。国家財政は予算にもとづいて運営される。その予算は議会において審議され、承認される。
国家予算は外交・軍事・治安など統治にかかわる部分と、公共事業・社会保障・医療・文教・環境・公害防止など行政にかかわる部分から成り立っている。
財政政策が登場するのは1930年代以降である。それによって、予算は社会に還元されるようになった。それまで財政は専制的国家を維持するためにのみ運用されていた。
いっぽうの金融政策は、中央銀行が金融の流れを調節することによって、金融制度全体の維持・安定をはかることを目的としている。
とりわけ1930年以降は通貨が兌換制から管理体制へと移行するなかで、金融政策の重要性が高まってきた。金融政策は景気循環を調整し、とりわけ恐慌を防止する手段として、広く活用されるようになった。
社会政策はもっとも新しい分野である。滝村によれば、社会政策が本格的に展開されるようになったのは第2次世界大戦後であって、「社会的な弱者・貧困者への国家的保護・救済の必要」が高まったためである。
その背景には、普通選挙制度を通じて議会制民主主義が定着し、それによって労働組合が大きな勢力として登場したことがあるという。
とはいえ、社会政策には長い前史がある。それは治安維持と結びついた救貧行政からはじまって、失業者対策などの労働政策、さらに社会保険の導入へとつづき、現在では医療・失業・年金の社会保険に加えて、生活保護の公的扶助が加わるようになった。
滝村によれば、社会政策は「個別資本による労働者への際限なき苛酷な搾取と抑圧に、国家権力が〈平均的な必要労働[つまり雇用]の保障〉という、一定の歯止めをかけるもの」であったという。
つまり、社会政策には、労働者の生活を改善することで、労働者階級の反乱を防ぐとともに、消費市場を拡大するねらいがあった。
そして、最後が公教育である。滝村は、公教育とは単に国家による教育を指すのではないという。それは国民教育でもあって、「国家権力が社会構成員[国民]の全子弟に対して、一定期間明確な目的をもって行なう学校教育」であり、義務教育としての性格をもっている。
さらに滝村は、「〈公教育〉とは、国家権力による目的的な人間形成であり、とりもなおさず〈近代社会〉に対応した社会的人間を、目的的につくりあげるためのものであった」と述べている。
そのため、公教育においては、読み書きそろばんに加えて、自然科学の知識や道徳・倫理、社会・歴史の知識が生徒に注入される。それは、国民になるための「思想的・イデオロギー的教育」の性格をもっている。
以上で、統治と行政からなる、国家権力の実質的構成が概観された。
滝村国家論はいかにもぶっきらぼうである。
しかし、それは国家嫌いの左翼の幻想を打ち破るとともに、国家至上主義の思想を振りまく右翼にも痛棒をくらわす性格をもっているのである。
滝村国家論をめぐって(まとめ1) [思想・哲学]
1 はじめに
国家とは何かと問われて、簡単に答えられる人はいるだろうか。
滝村隆一(1944-2016)は、アカデミズムに属することなく、生涯をかけて国家とは何かを考えつづけた世界的政治学者である。その思索が『国家論大綱』第1巻としてまとまったのは2003年のことだ。第2巻の歴史編は2014年に出版されたものの未完に終わった。第3巻の思想編は構想だけで終わった。
ここでは『国家論大綱』を中心に、滝村国家論の概要をごく簡単に示すことにする。膨大な学説批判については省略した。あくまでも、ぼくが理解できるかぎりでのメモにすぎない。
大雑把にわけて、「大綱」第1巻は3つの部分と補論から成り立っている。3つの部分のうち、最初のふたつは序論と総説であり、あくまでもメインは一般的な国家を論じることに置かれている。第2巻の歴史編は残念ながら、断片的なものしか残されていないが、これについては、また後日、紹介することにしよう。
(1)政治とは何か
(2)権力とは何か
(3)国家とは何か
これが3つの部分で、きわめてシンプルな構成といえよう。
それに補論として、ファシズム国家論、社会主義国家論、マルクス主義による国家死滅論の批判、国家連合(とりわけEU)の問題などが論じられている。
「はじめに」のなかで、滝村はこう述べている。
〈厳密な学的・理論的方法という点からみれば、〈世界史〉の学的思想において、ヘーゲルとマルクスのみが、社会科学の正当な学的方法、つまり社会的事象の学的・理論的解明を可能にする、唯一の学的方法を確立した。〉
ヘーゲルとマルクスの方法だけが、国家を解明する唯一のカギだというわけだ。ホッブズのように個人を原子として分解し、その衝突や対立から、国家を構成的に論じるやり方はまちがっている、と滝村はみる。
ただし、滝村がヘーゲルやマルクスの国家論を正しいとみているかというと、まったくそうではない。
〈ちなみにヘーゲルは、いまだ憲法さえもたぬ悪名高き、かのプロイセン専制国家を神聖化する、国家主義的な立場から脱却できなかった。マルクスは、すべての階級対立を廃絶する、プロレタリア独裁をテコにして、〈国家が消滅した共産主義社会〉が実現できる、と夢想した。〉
要するに、政治思想的にはヘーゲルもマルクスもまちがっているというわけだ。にもかかわらず、ふたりの国家をとらえる方法は、西洋のほかの学者とはまったく異質、異端であり、「それはまさに、〈正当ゆえの「異端」〉といっていい」と評価している。
こうしたアプローチは、滝村が国家とは何かを考察するさいに生かされることになる。
ここで、本論にはいる前に、滝村の学問的な歩みをふり返っておこう。
滝村が執筆活動を開始したのは、1967年ごろから。大学闘争はなやかなりし時代だった。
このころ、滝村はマルクスやエンゲルスの著作を読みとおし、国家と国家権力が異なること、そして国家権力は第三権力であることを明らかにした。
そのころはやっていたのは、国家とは暴力装置だというレーニン流の考え方だった。そこでは、国家と国家権力は区別されず、むやみやたらに国家が暴力と結びつけられていた。
しかし、滝村はそうではないという。国家権力とは、さまざまな勢力が抗争をくり広げる社会の上に立って、いわば第三者(第三権力)として、社会を統制するものだ。そのことを滝村は明らかにした。
さらに、国家がもっぱら社会を抑圧する装置とかんがえられていたのにたいして、滝村は〈共同体─即─国家〉論を提唱する。すなわち〈内的国家〉にたいする〈外的国家〉論である。
国家は共同体の内部にたいしてだけ存在するのではなく、同時に共同体の外部にたいしても存在する。つまり、国家は外部の国家にたいする存在でもあることを明らかにした。
その後、滝村は国家の歴史の考察へと移った。当時は、いわゆる唯物史観がまだはやっていた。つまり、人間社会は原始的、古代的、中世的、近代的な発展段階をへて、共産主義社会にいたるのが世界史的必然だと考えられていたのだ。これはマルクスのというより、マルクス主義の公式だった。
もともとこの歴史観はヘーゲルに由来している。近代の国家はそれ以前の国家とはあきらかにちがうかたちをしている。ヘーゲルは、国家がさまざまな段階をへて、近代国家へと流れこんでいったととらえていた。すると、たとえば古代国家やアジア的国家は、どういうかたちをしていたのか。こうして滝村は、典型的な歴史国家の具体像を描くことに取り組むことになった。
そうした研鑽のなかから、滝村はマルクス主義史観でいう、世界史的必然として国家なき共産主義社会がやってくるといった発想がいかにたあいないものだったかということに気づく。
滝村はソ連や中国などの社会主義国家が、近代的な三権分立さえ実現していないことを厳しく批判する。三権分立なきプロレタリア独裁は、純粋な専制国家に行き着くしかない。
こうして、それまで信条としていたマルクス主義を捨てた滝村は、歴史理論的作業をつづけながら、国家とは何かを明らかにするために、より高度な研究に向かっていくことになった。
これまでのあらゆる国家学説に検証が加えられ、ウェーバーやラスウェルなども批判された。中途半端に西洋の学説を切り貼りしている丸山真男の政治学も、徹底して解体されていった。
国家論が経済学とはことなる理論的構成を必要とすることに気づいた滝村は、こう書いている。
〈〈国家〉は、最初から、〈社会〉総体の統一的な政治的組織として、歴史的に出現した。〈国家〉と各種社会的権力との共通性は、組織的権力としての一般性という点にしかない。同じく社会的事象に対する学的解明といっても、経済学と政治学とでは、このような資本制社会と〈国家〉とのちがいから、その学的展開・構成方法もまた、大きくことなってくる。〉
要するに国家の歴史は、資本主義の歴史よりはるかに長いということだ。その国家を歴史的、構造的に解明する作業が、資本主義を分析する経済学と根本的にことなることはいうまでもない。
人類史において、長い歴史をもつ国家が、これからいったいどこに向かうのか。東アジアの一体化はありうるのか。はたして世界共和国は成立しうるのか。それらもまた、この著書から浮かび上がる大きな研究テーマといえるだろう。
2 政治とは何か
いざ、政治とは何かというと、なかなか答えるのがむずかしい。
滝村のいうように、政治とは国家にかかわる事象(動きやできごと)だというのが、いちばんシンプルな規定だろう。
したがって、政治の広がりは国家の広がりと重なってくる。
国家といえば、まず外交、軍事、治安を考える。社会全体を管轄する政治機構が国家だとすれば、国家の範囲はますます大きくなってくる。
国家の機構は、それこそ社会にしっかりとかぶさっている。その仕組みは中央と地方とで二重になっている。警察や役所、議会、裁判所にしてもそうだ。そこでは、法の制定と執行、経済政策から社会保障にいたる行政、その他さまざまな社会的統制がなされている。
そこで、政治とは国家による社会的統制を指すという見方がでてくる。
だが、それはあまりにも一面的なとらえ方だ。
新聞や週刊誌などでよく目にするのは、政権争いやら党内のゴタゴタ、その他さまざまなスキャンダル。利権癒着というのもよく聞く。
与野党の攻防、さまざまな裏工作、日々流されるニュースや解説など、それこそ、わたしたちの毎日は政治にあふれているといってもいいくらいである。
そのほか、原発再稼働や沖縄の基地新設にたいする反対運動、さらに政府打倒に向けてのデモだって、りっぱな政治だということができるだろう。
こんなふうに、政治活動は日常のあらゆる場所で、ごくあたりまえにおこなわれている。
政の意味は、もともと征服し支配するということで、それに、ことをおさめる治がともなう。
いっぽう、会社でも政治はつきものではないか、と思ったりもする。実際、ぼくの会社員時代でも、社内政治が横行していた。役員改選の時期になると、次は誰が社長になり、誰が専務になるかに、社員の関心が集まったものだ。
これは、人が集まる組織には、権力が発生し、政治が必要になってくるということなのだろうか。しかし、これはあくまでもたとえといわなければならない。
組織のなかで発生する人間の行動のすべてを、政治と呼ぶわけにはいかない。そこには、ある程度厳密な区別を必要とする。
政治はあくまでも国家と政治権力をめぐる動きととらえるべきだろう。
水のないプールが無意味なように人民のいない国家もまた無意味である。社会があってこそ国家は存在しうるし、国家なくして社会も存続しえない。
ことばの正確な意味で、国家の廃絶はありえない。もちろん、国家のかたちは、いくらでも変わりうる。専制的な国家が民主的な国家に変わるとか、連邦国家をつくるとか、あるいは逆にひとつの国家がいくつもに分裂することも考えられる。しかし、そのこと自体は国家の廃絶を意味するわけではない。
国家がわたしたちにかかわっているように、わたしたちもまた国家にかかわっている。そのかかわりの総体を政治と呼ぶことができるだろう。政治は国家権力から発する場合もあるし、逆に社会(個人や組織)から国家権力に向かっていく場合もある。
政治とは、わたしたちを取り囲みながら日々生起する国家現象ということができる。その源が国家権力にある以上、次に権力とは何かについて考えなければならない。
3 権力とは何か
この世に権力が存在することは否定できない事実である。
権力とはいったいなんなのだろうか。
滝村は権力を「人間主体に対する、外部的・客観的な〈支配力〉」と規定している。
人間社会において、こうした支配力は、当初、「原初的な神的・宗教的権力」のかたちをとって出現した。神(自然)の力と、神の力を律する者が、人びとの生活を支配したのである。
神的・宗教的権力は、次第に強力な政治的権力へと発展していく。その背景に、人間社会の歴史的発展があったことはいうまでもないだろう。
権力は国家だけの現象ではない。職場においても、学校においても、支配−服従関係の発生する場においては、どこでも権力が発生する。
権力が存在するところでは、権力者の指示・命令(支配者の意志)にしたがって人が行動する。逆に、そうした関係がまったくないところでは権力は成立していない。
支配者の意志は単なる個人の考えではない。個人の考えなら、別にしたがっても、したがわなくてもいいことになる。ところが、それが「外部的・客観的な規範」となれば、そうはいかない。自分の意志がどうであれ、おおやけに示された規範にはしたがわなければならない。規範にみずからの意志をしたがわせるところに権力関係が発生する、と滝村は述べている。
規範とは認められた取り決め、ないし約束のことを指す。認めたのだから、守らなくてはならない。たとえば、青信号は進めという交通ルール。おれは反対だからといって、このルールを守らなければ、交通事故をおこす可能性がある。
こうした規範によって、人びとの実践と活動は社会的に規制されている。規範は社会のルールを指すといってもいいかもしれない。法律もこうした規範にあたる。もちろん、こうした規範は、社会の状況が変化するにつれて、変更されていく可能性がある。
近代以降、支配者の意志は国家意志となり、その規範は法律のかたちをとり、それに違反した者を規定にもとづいて罰するようになる。そして、支配者自身もまた法律にしたがわなくてはならなくなるのが近代の特徴だといえる。
そこで、滝村は、権力とは「規範にもとづいた観念的な支配力」にほかならないと規定することになる。
ところで、服従はどのようなかたちで実現されるのだろうか。相手を服従させるには、命令(したがわない場合は処罰)、あるいは説得や教化、さらには利益誘導といったやり方が考えられるだろう。
これにたいし、したがう側も、自己犠牲的献身から面従腹背、あるいは秘めた敵意まで、その態度はさまざまだと思われる。
とはいえ、権力関係が成立しているときには、それが安定的な場合も、不安定な場合でも、いちおうは「規範としての意志」にたいし、被支配者による「意志の服従」がなされていることになる。もっとも、「意志の服従」がいつまでつづくかは、状況次第といえるだろう。
権力が強い力をもつようになるのは、組織があってこそである。組織は個人の集まりにちがいないが、単なる集団ではない。滝村によると、「組織とは、規範にもとづいて結集し構成された特殊な人間集団」ということになる。つまり、組織は特別な目的をもつ集団を指している。
したがって、組織の内部では、支配と従属からなる権力関係が築かれている。
組織は目的をもつため、その意志は内部だけではなく、外部にも向けられている。とはいえ、組織が外部を支配する力は、他の組織との力関係による。これにたいし、組織の内部においては、規範としての組織的意志が貫徹される。これは企業をみればよくわかることだ。
個人が組織に結集するのは、そこでの協同活動によって「倍加された強力な集団力」の獲得が可能になるからだ、と滝村はいう。戦争であれ土木工事であれ、それはけっして個人ではなしえない事業だ。こうした協同活動をおこなうには、組織としての「単一意志」(規範)のもとに全員が服従することが求められ、さらに、それをコントロールするための「指揮中枢」と組織内組織が必要になってくる。
近代国家でいえば、そうした組織的規範は、憲法を基軸として、刑法・民法・商法、あるいは行政法によって定められることになる。企業でいえば、その規範は、社是・社訓、年間計画、定款によって定められるといってよいだろう。
そして、こうした組織的規範に反対する意見をもっていても、現実的な行動として、それに違反しなければ、処罰されることはないというのが、近代の原理だといえる。
権力は大きく分けて、経済権力と政治権力にわかれる。企業や労働組合などの経済権力が、おもに物質的な富の生産と分配にかかわるとすれば、政治権力は思想やイデオロギーなどの観念にかかわっている。ほかに思想やイデオロギーにかかわる権力としては、宗教組織(教団)などが挙げられる。マスメディア権力にも、たぶんにそうした側面がある。
もちろん、経済権力、政治権力、宗教権力、思想権力といっても、その分類は画然としたものではない。たとえば宗教組織が、政治的・経済的役割をもつこともあり、経営者団体や労働組合などの経済権力が政治的性格を帯びることもある。
国家権力には、とうぜん対抗権力が存在する。近代以前では、領主権力とそれにたいする農民反乱組織、近代以降では、議会政党(野党)と革命政党といった主流、反主流の組織がある。
組織においては、意志決定がどのような形態でなされるかが問われる。
滝村によれば、組織における意志決定の方式は、民主制か専制かの、どちらかしかないという。民主主義の場合は、直接民主主義か間接民主主義、専制の場合は、親裁か寡頭制のどちらかによって、意志決定がなされる。
これまでの歴史においては、社会組織はたいていが専制で、民主主義はごく例外だったという。しばしば組織間で深刻な対立と抗争が発生することを考えれば、緊急事態に対応するために、往々にして専制的な意志決定をせざるをえなかったからである。
たとえば古代ギリシアのアテナイでは、都市中枢の支配層のなかで直接民主制がとられていたといわれるが、そうした民主主義は被支配層や周辺の従属共同体にとっては、専制以外のなにものでもなかった、と滝村は指摘する。
民主主義の登場は近代を待たねばならなかった。もともと専制化しがちな国家権力が大きくなるにつれて、それに一定の歯止めをかけることが求められたためである。
国家組織を含め、一般に社会組織は専制形態をとる。その組織は拡大するにつれ、専門化して細かく分かれ、上級幹部層が生まれてくる。組織においては、その上級幹部層の意志をすりあわせて、意志の合意がなされ、組織としての一般的意志が形成されていくことになる。
この調整と妥協はときにきわめて難航することがある。そんなときにワンマンのツルの一声が、組織の意志を決定する場合も少なくない。しかし、その意志決定には成功も失敗もあって、成功するならともかく、あまりにも失敗がつづくようだと、ワンマン追放のクーデターが発生しかねない状況となる。
現代の議会主義には、国民主権と多数支配という原則がある。にもかかわらず、実際には「少数者支配の法則」がつらぬかれている、と政治評論家はしばしば憤慨する。民主主義は表看板だけで、政治はいつも少数者によって牛耳られており、ほんとうの民主主義を取り戻さねばならないという主張もでてくる。
しかし、だからといって専制と民主制を混同してはならない、と滝村はいう。民主制のもとでは、国民から選ばれた議員は、国民各層の意志や利害をまったく無視して、みずからの意志を主張できるわけではない。専制体制とはことなり、民主体制のもとで、国民は市民権を与えられ、中央および地方の議会に代表者を送る権利をもっているからである。
ソ連の体制は民主主義とはかけ離れていた。レーニンやスターリンが主導した共産党は、みずからをプロレタリアートの代表と位置づけ、プロレタリアート独裁の名のもとで、寡頭支配をつづけた。そのツケはあまりにも大きく、その独善的思想によって、もっとも醜悪な「社会主義」専制国家が生まれたことを忘れてはならない、と滝村は述べている。
国家とは何かと問われて、簡単に答えられる人はいるだろうか。
滝村隆一(1944-2016)は、アカデミズムに属することなく、生涯をかけて国家とは何かを考えつづけた世界的政治学者である。その思索が『国家論大綱』第1巻としてまとまったのは2003年のことだ。第2巻の歴史編は2014年に出版されたものの未完に終わった。第3巻の思想編は構想だけで終わった。
ここでは『国家論大綱』を中心に、滝村国家論の概要をごく簡単に示すことにする。膨大な学説批判については省略した。あくまでも、ぼくが理解できるかぎりでのメモにすぎない。
大雑把にわけて、「大綱」第1巻は3つの部分と補論から成り立っている。3つの部分のうち、最初のふたつは序論と総説であり、あくまでもメインは一般的な国家を論じることに置かれている。第2巻の歴史編は残念ながら、断片的なものしか残されていないが、これについては、また後日、紹介することにしよう。
(1)政治とは何か
(2)権力とは何か
(3)国家とは何か
これが3つの部分で、きわめてシンプルな構成といえよう。
それに補論として、ファシズム国家論、社会主義国家論、マルクス主義による国家死滅論の批判、国家連合(とりわけEU)の問題などが論じられている。
「はじめに」のなかで、滝村はこう述べている。
〈厳密な学的・理論的方法という点からみれば、〈世界史〉の学的思想において、ヘーゲルとマルクスのみが、社会科学の正当な学的方法、つまり社会的事象の学的・理論的解明を可能にする、唯一の学的方法を確立した。〉
ヘーゲルとマルクスの方法だけが、国家を解明する唯一のカギだというわけだ。ホッブズのように個人を原子として分解し、その衝突や対立から、国家を構成的に論じるやり方はまちがっている、と滝村はみる。
ただし、滝村がヘーゲルやマルクスの国家論を正しいとみているかというと、まったくそうではない。
〈ちなみにヘーゲルは、いまだ憲法さえもたぬ悪名高き、かのプロイセン専制国家を神聖化する、国家主義的な立場から脱却できなかった。マルクスは、すべての階級対立を廃絶する、プロレタリア独裁をテコにして、〈国家が消滅した共産主義社会〉が実現できる、と夢想した。〉
要するに、政治思想的にはヘーゲルもマルクスもまちがっているというわけだ。にもかかわらず、ふたりの国家をとらえる方法は、西洋のほかの学者とはまったく異質、異端であり、「それはまさに、〈正当ゆえの「異端」〉といっていい」と評価している。
こうしたアプローチは、滝村が国家とは何かを考察するさいに生かされることになる。
ここで、本論にはいる前に、滝村の学問的な歩みをふり返っておこう。
滝村が執筆活動を開始したのは、1967年ごろから。大学闘争はなやかなりし時代だった。
このころ、滝村はマルクスやエンゲルスの著作を読みとおし、国家と国家権力が異なること、そして国家権力は第三権力であることを明らかにした。
そのころはやっていたのは、国家とは暴力装置だというレーニン流の考え方だった。そこでは、国家と国家権力は区別されず、むやみやたらに国家が暴力と結びつけられていた。
しかし、滝村はそうではないという。国家権力とは、さまざまな勢力が抗争をくり広げる社会の上に立って、いわば第三者(第三権力)として、社会を統制するものだ。そのことを滝村は明らかにした。
さらに、国家がもっぱら社会を抑圧する装置とかんがえられていたのにたいして、滝村は〈共同体─即─国家〉論を提唱する。すなわち〈内的国家〉にたいする〈外的国家〉論である。
国家は共同体の内部にたいしてだけ存在するのではなく、同時に共同体の外部にたいしても存在する。つまり、国家は外部の国家にたいする存在でもあることを明らかにした。
その後、滝村は国家の歴史の考察へと移った。当時は、いわゆる唯物史観がまだはやっていた。つまり、人間社会は原始的、古代的、中世的、近代的な発展段階をへて、共産主義社会にいたるのが世界史的必然だと考えられていたのだ。これはマルクスのというより、マルクス主義の公式だった。
もともとこの歴史観はヘーゲルに由来している。近代の国家はそれ以前の国家とはあきらかにちがうかたちをしている。ヘーゲルは、国家がさまざまな段階をへて、近代国家へと流れこんでいったととらえていた。すると、たとえば古代国家やアジア的国家は、どういうかたちをしていたのか。こうして滝村は、典型的な歴史国家の具体像を描くことに取り組むことになった。
そうした研鑽のなかから、滝村はマルクス主義史観でいう、世界史的必然として国家なき共産主義社会がやってくるといった発想がいかにたあいないものだったかということに気づく。
滝村はソ連や中国などの社会主義国家が、近代的な三権分立さえ実現していないことを厳しく批判する。三権分立なきプロレタリア独裁は、純粋な専制国家に行き着くしかない。
こうして、それまで信条としていたマルクス主義を捨てた滝村は、歴史理論的作業をつづけながら、国家とは何かを明らかにするために、より高度な研究に向かっていくことになった。
これまでのあらゆる国家学説に検証が加えられ、ウェーバーやラスウェルなども批判された。中途半端に西洋の学説を切り貼りしている丸山真男の政治学も、徹底して解体されていった。
国家論が経済学とはことなる理論的構成を必要とすることに気づいた滝村は、こう書いている。
〈〈国家〉は、最初から、〈社会〉総体の統一的な政治的組織として、歴史的に出現した。〈国家〉と各種社会的権力との共通性は、組織的権力としての一般性という点にしかない。同じく社会的事象に対する学的解明といっても、経済学と政治学とでは、このような資本制社会と〈国家〉とのちがいから、その学的展開・構成方法もまた、大きくことなってくる。〉
要するに国家の歴史は、資本主義の歴史よりはるかに長いということだ。その国家を歴史的、構造的に解明する作業が、資本主義を分析する経済学と根本的にことなることはいうまでもない。
人類史において、長い歴史をもつ国家が、これからいったいどこに向かうのか。東アジアの一体化はありうるのか。はたして世界共和国は成立しうるのか。それらもまた、この著書から浮かび上がる大きな研究テーマといえるだろう。
2 政治とは何か
いざ、政治とは何かというと、なかなか答えるのがむずかしい。
滝村のいうように、政治とは国家にかかわる事象(動きやできごと)だというのが、いちばんシンプルな規定だろう。
したがって、政治の広がりは国家の広がりと重なってくる。
国家といえば、まず外交、軍事、治安を考える。社会全体を管轄する政治機構が国家だとすれば、国家の範囲はますます大きくなってくる。
国家の機構は、それこそ社会にしっかりとかぶさっている。その仕組みは中央と地方とで二重になっている。警察や役所、議会、裁判所にしてもそうだ。そこでは、法の制定と執行、経済政策から社会保障にいたる行政、その他さまざまな社会的統制がなされている。
そこで、政治とは国家による社会的統制を指すという見方がでてくる。
だが、それはあまりにも一面的なとらえ方だ。
新聞や週刊誌などでよく目にするのは、政権争いやら党内のゴタゴタ、その他さまざまなスキャンダル。利権癒着というのもよく聞く。
与野党の攻防、さまざまな裏工作、日々流されるニュースや解説など、それこそ、わたしたちの毎日は政治にあふれているといってもいいくらいである。
そのほか、原発再稼働や沖縄の基地新設にたいする反対運動、さらに政府打倒に向けてのデモだって、りっぱな政治だということができるだろう。
こんなふうに、政治活動は日常のあらゆる場所で、ごくあたりまえにおこなわれている。
政の意味は、もともと征服し支配するということで、それに、ことをおさめる治がともなう。
いっぽう、会社でも政治はつきものではないか、と思ったりもする。実際、ぼくの会社員時代でも、社内政治が横行していた。役員改選の時期になると、次は誰が社長になり、誰が専務になるかに、社員の関心が集まったものだ。
これは、人が集まる組織には、権力が発生し、政治が必要になってくるということなのだろうか。しかし、これはあくまでもたとえといわなければならない。
組織のなかで発生する人間の行動のすべてを、政治と呼ぶわけにはいかない。そこには、ある程度厳密な区別を必要とする。
政治はあくまでも国家と政治権力をめぐる動きととらえるべきだろう。
水のないプールが無意味なように人民のいない国家もまた無意味である。社会があってこそ国家は存在しうるし、国家なくして社会も存続しえない。
ことばの正確な意味で、国家の廃絶はありえない。もちろん、国家のかたちは、いくらでも変わりうる。専制的な国家が民主的な国家に変わるとか、連邦国家をつくるとか、あるいは逆にひとつの国家がいくつもに分裂することも考えられる。しかし、そのこと自体は国家の廃絶を意味するわけではない。
国家がわたしたちにかかわっているように、わたしたちもまた国家にかかわっている。そのかかわりの総体を政治と呼ぶことができるだろう。政治は国家権力から発する場合もあるし、逆に社会(個人や組織)から国家権力に向かっていく場合もある。
政治とは、わたしたちを取り囲みながら日々生起する国家現象ということができる。その源が国家権力にある以上、次に権力とは何かについて考えなければならない。
3 権力とは何か
この世に権力が存在することは否定できない事実である。
権力とはいったいなんなのだろうか。
滝村は権力を「人間主体に対する、外部的・客観的な〈支配力〉」と規定している。
人間社会において、こうした支配力は、当初、「原初的な神的・宗教的権力」のかたちをとって出現した。神(自然)の力と、神の力を律する者が、人びとの生活を支配したのである。
神的・宗教的権力は、次第に強力な政治的権力へと発展していく。その背景に、人間社会の歴史的発展があったことはいうまでもないだろう。
権力は国家だけの現象ではない。職場においても、学校においても、支配−服従関係の発生する場においては、どこでも権力が発生する。
権力が存在するところでは、権力者の指示・命令(支配者の意志)にしたがって人が行動する。逆に、そうした関係がまったくないところでは権力は成立していない。
支配者の意志は単なる個人の考えではない。個人の考えなら、別にしたがっても、したがわなくてもいいことになる。ところが、それが「外部的・客観的な規範」となれば、そうはいかない。自分の意志がどうであれ、おおやけに示された規範にはしたがわなければならない。規範にみずからの意志をしたがわせるところに権力関係が発生する、と滝村は述べている。
規範とは認められた取り決め、ないし約束のことを指す。認めたのだから、守らなくてはならない。たとえば、青信号は進めという交通ルール。おれは反対だからといって、このルールを守らなければ、交通事故をおこす可能性がある。
こうした規範によって、人びとの実践と活動は社会的に規制されている。規範は社会のルールを指すといってもいいかもしれない。法律もこうした規範にあたる。もちろん、こうした規範は、社会の状況が変化するにつれて、変更されていく可能性がある。
近代以降、支配者の意志は国家意志となり、その規範は法律のかたちをとり、それに違反した者を規定にもとづいて罰するようになる。そして、支配者自身もまた法律にしたがわなくてはならなくなるのが近代の特徴だといえる。
そこで、滝村は、権力とは「規範にもとづいた観念的な支配力」にほかならないと規定することになる。
ところで、服従はどのようなかたちで実現されるのだろうか。相手を服従させるには、命令(したがわない場合は処罰)、あるいは説得や教化、さらには利益誘導といったやり方が考えられるだろう。
これにたいし、したがう側も、自己犠牲的献身から面従腹背、あるいは秘めた敵意まで、その態度はさまざまだと思われる。
とはいえ、権力関係が成立しているときには、それが安定的な場合も、不安定な場合でも、いちおうは「規範としての意志」にたいし、被支配者による「意志の服従」がなされていることになる。もっとも、「意志の服従」がいつまでつづくかは、状況次第といえるだろう。
権力が強い力をもつようになるのは、組織があってこそである。組織は個人の集まりにちがいないが、単なる集団ではない。滝村によると、「組織とは、規範にもとづいて結集し構成された特殊な人間集団」ということになる。つまり、組織は特別な目的をもつ集団を指している。
したがって、組織の内部では、支配と従属からなる権力関係が築かれている。
組織は目的をもつため、その意志は内部だけではなく、外部にも向けられている。とはいえ、組織が外部を支配する力は、他の組織との力関係による。これにたいし、組織の内部においては、規範としての組織的意志が貫徹される。これは企業をみればよくわかることだ。
個人が組織に結集するのは、そこでの協同活動によって「倍加された強力な集団力」の獲得が可能になるからだ、と滝村はいう。戦争であれ土木工事であれ、それはけっして個人ではなしえない事業だ。こうした協同活動をおこなうには、組織としての「単一意志」(規範)のもとに全員が服従することが求められ、さらに、それをコントロールするための「指揮中枢」と組織内組織が必要になってくる。
近代国家でいえば、そうした組織的規範は、憲法を基軸として、刑法・民法・商法、あるいは行政法によって定められることになる。企業でいえば、その規範は、社是・社訓、年間計画、定款によって定められるといってよいだろう。
そして、こうした組織的規範に反対する意見をもっていても、現実的な行動として、それに違反しなければ、処罰されることはないというのが、近代の原理だといえる。
権力は大きく分けて、経済権力と政治権力にわかれる。企業や労働組合などの経済権力が、おもに物質的な富の生産と分配にかかわるとすれば、政治権力は思想やイデオロギーなどの観念にかかわっている。ほかに思想やイデオロギーにかかわる権力としては、宗教組織(教団)などが挙げられる。マスメディア権力にも、たぶんにそうした側面がある。
もちろん、経済権力、政治権力、宗教権力、思想権力といっても、その分類は画然としたものではない。たとえば宗教組織が、政治的・経済的役割をもつこともあり、経営者団体や労働組合などの経済権力が政治的性格を帯びることもある。
国家権力には、とうぜん対抗権力が存在する。近代以前では、領主権力とそれにたいする農民反乱組織、近代以降では、議会政党(野党)と革命政党といった主流、反主流の組織がある。
組織においては、意志決定がどのような形態でなされるかが問われる。
滝村によれば、組織における意志決定の方式は、民主制か専制かの、どちらかしかないという。民主主義の場合は、直接民主主義か間接民主主義、専制の場合は、親裁か寡頭制のどちらかによって、意志決定がなされる。
これまでの歴史においては、社会組織はたいていが専制で、民主主義はごく例外だったという。しばしば組織間で深刻な対立と抗争が発生することを考えれば、緊急事態に対応するために、往々にして専制的な意志決定をせざるをえなかったからである。
たとえば古代ギリシアのアテナイでは、都市中枢の支配層のなかで直接民主制がとられていたといわれるが、そうした民主主義は被支配層や周辺の従属共同体にとっては、専制以外のなにものでもなかった、と滝村は指摘する。
民主主義の登場は近代を待たねばならなかった。もともと専制化しがちな国家権力が大きくなるにつれて、それに一定の歯止めをかけることが求められたためである。
国家組織を含め、一般に社会組織は専制形態をとる。その組織は拡大するにつれ、専門化して細かく分かれ、上級幹部層が生まれてくる。組織においては、その上級幹部層の意志をすりあわせて、意志の合意がなされ、組織としての一般的意志が形成されていくことになる。
この調整と妥協はときにきわめて難航することがある。そんなときにワンマンのツルの一声が、組織の意志を決定する場合も少なくない。しかし、その意志決定には成功も失敗もあって、成功するならともかく、あまりにも失敗がつづくようだと、ワンマン追放のクーデターが発生しかねない状況となる。
現代の議会主義には、国民主権と多数支配という原則がある。にもかかわらず、実際には「少数者支配の法則」がつらぬかれている、と政治評論家はしばしば憤慨する。民主主義は表看板だけで、政治はいつも少数者によって牛耳られており、ほんとうの民主主義を取り戻さねばならないという主張もでてくる。
しかし、だからといって専制と民主制を混同してはならない、と滝村はいう。民主制のもとでは、国民から選ばれた議員は、国民各層の意志や利害をまったく無視して、みずからの意志を主張できるわけではない。専制体制とはことなり、民主体制のもとで、国民は市民権を与えられ、中央および地方の議会に代表者を送る権利をもっているからである。
ソ連の体制は民主主義とはかけ離れていた。レーニンやスターリンが主導した共産党は、みずからをプロレタリアートの代表と位置づけ、プロレタリアート独裁の名のもとで、寡頭支配をつづけた。そのツケはあまりにも大きく、その独善的思想によって、もっとも醜悪な「社会主義」専制国家が生まれたことを忘れてはならない、と滝村は述べている。
竹田青嗣『欲望論』を読む(1) [思想・哲学]
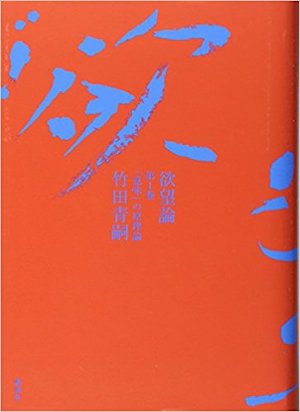
買うか買うまいか迷った末にとうとう買ってしまった。
上下2巻1200ページを超える大作である。
第1巻は「『意味』の原理論」、第2巻は「『価値』の原理論」と銘打たれている。このほかに、続刊として倫理学と社会哲学が予定されているというから、まだ先が残っている。
第1巻と第2巻は4部から構成されている。
第1部 存在と認識
第2部 世界と欲望
第3部 幻想的身体
第4部 審級の生成
著者は1947年生まれの哲学者、文芸評論家。現在、早稲田大学国際教養学部教授の肩書をもつ。哲学に関する多くの著書があるが、本書はその総決算といえるだろう。
オビには「一切の哲学原理の総転換!! 21世紀、新しい哲学がはじまる! 2500年の哲学の歴史を総攬し、かつ刷新する画期的論考!!」とうたわれている。こういううたい文句には、いかにも売らんかなの姿勢がみえみえで、あまり信じたくないのだが、これまでの哲学史を塗り替え、新たな地平を開くというのは、たしかに壮観にはちがいない。
2冊で税別7800円という値段にも、ちとたじろいだ。しかし、なによりためらったのは、これまで哲学など無縁で、それほど先のないぼくなどに、はたしてこの本が理解できるかどうか、まったく自信がもてなかったからである。
でも、思い切って買ってしまった。
人間とはなにかがわかる手がかりになればいいと思ったからである。
誤読の可能性はおおいにあるが、わからないなりにも断続的に1年くらいかけて読んでいけば、人間という親密かつ凶暴な存在について、なにかあらたな知識が得られるのではないか。そんな軽い気持ちで、本書のページをめくることにした。途中で挫折する可能性は高いが、例によって、きれぎれの感想である。
はじめに暴力があり戦争があったと著者は書いている。人間がそのなかを生きていくには、共同体をつくらねばならなかった。暴力や戦争はつねにあり、人はつねに死におびやかされていた。それに対抗するため生まれたのが宗教や哲学だ。宗教はよりよく死ぬための「物語」であり、哲学はよりよく生きるための「原理」だった。
著者はいう。
〈古来、哲学の問いの中心には世界とは何であるか、世界を正しく認識できるかという問いが、すなわち「存在の問い」と「認識の問い」が存在してきた。しかし、この問いの根底には、いかに善き生を生きうるかという問いとともに、いかに人間が潜在的な暴力の不安から逃れうるかという問いが潜んでいる。〉
人間は世界のなかに生きている。その世界とは何なのか。また人間ははたして世界を正しく認識できるのか。それが存在と認識の問いである。だが、その根底には人間とは何であるのかという、さらに根本的な問題がひそんでいる。
だいじなのは哲学的原理という方法なのだ、と著者はいう。つまり考えるためのテコだ。その方法は時代に応じて、つねに再生されねばならず、それが失われれば、混乱が支配する。
現代哲学は、哲学的原理を打ち立てようとした近代哲学を乗り越えるため、批判的相対主義におちいり、批判のための批判をくり返している。だいじなのは哲学的原理という方法を再生することだ。そのためには「一切の哲学と思想の中心的方法と原理を、新しい思想の解剖学によって解体し、これを吟味し尽くさねばならない」と、著者は宣言する。
現代思想の特徴は「相対主義」にあるといってよい。絶対的な認識はありえないとして、すべてを相対化し、批判する考え方だ。そこからは、正当なものは何もない、逆にいえば、あらゆるものは正当化されるという思想が生まれる。
こういう考え方が生まれたのは、20世紀前半に人類が全体主義(スターリニズムとファシズム)という原理主義的思想の災厄をこうむったためだろう。そこから、近代そのものを否定するポストモダン思想が登場した。その標的となったのは、ドイツ観念論に代表されるヨーロッパの形而上学だった。
「このことで、現代の批判思想は、形而上学的、独断論的普遍主義に対抗する批判的相対主義という、決して答えの見出せない哲学的な袋小路に入り込むことになった」と、著者はいう。それは不毛な対立を招いた。
形而上学的独断論と懐疑的相対主義の不毛な対立を回避するには、まず「本体」の観念を解体するところからはじめなければならない。哲学は「本体」なるものが存在すると考えてきた。逆に本体には誰もアクセスできないというのが、懐疑論の思考だった。
著者は、独断論であれ相対主義であれ、「本体」から出発するこれまでの哲学的思考を克服しようとした哲学者として、ニーチェとフッサールの名前を挙げている。
「『本体』の存在が暗黙のうちに想定されているかぎり、認識は可能であるか可能でないかのいずれかでしかない」。このことが、哲学に不毛な論争を招いてきたのだ。
著者は本体論を解体する手がかりとして、「認識相関性」という概念をもちだす。これは認識相対主義とはことなる。認識相対主義は、自分自身の観点からしか対象を見ることができないため、すべての認識は相対的であって、「本体」自体の正しい認識はできないとする。ところが、「認識相関性」の考えでは、人はみずからの身体−欲望に関連づけて「世界」を生成するとみるから、そもそも「本体」を想定することはできず、想定する必要もないのだ。
このとき「世界」は「生世界」となる。だれにとっても個別に存在する世界、それが「生世界」だ。「『生世界』は生きとし生けるものにとっての絶対的、偶有的事実であり、それゆえまったくドクサ(臆見)を含むことのない、『世界意識』の根源的出発点である」と、著者はいう。
そこから新しい認識論が生まれる。「本体」の認識という考え方は廃棄される。それに代わって個々の「世界体験」から間主観的な問題構成に展開し、世界存在の普遍性を理解する方法が開けるのだ。
意味は記号の本体ではない。意味と価値はほんらいひとつのものだ。世界は「生けるもの」の「欲望−身体」相関性としてのみ生成する。したがって、世界は価値と意味のたえず生成変化する連関の総体としてとらえられる、と著者はいう。
世界体験から出発して世界の普遍的理解にいたる「言語ゲーム」を著者は哲学と名づけているようにみえる。それは「暴力原理」にもとづく思考の停止、あるいは懐疑主義によるデカダンとは対極にある努力にほかならず、現実世界の「現実論理」と対抗するものなのだ。したがって、これからえがかれようとするのは、いわば希望の哲学といってもよいものかもしれない。
気の向くままに、少しずつ読んでいきたい。
最晩年の自由論──若森みどり『カール・ポランニー』を読む(6) [思想・哲学]
1954年にコロンビア大学を退職したあと、ポランニーは『自由と技術』と題する著作で、産業文明にたいする考察を進めるつもりでいた。しかし、病気のため、それは完成にいたらず、断片的な草稿が残されるにとどまった。
そのかたわら、弟子のロートシュテインは3年間にわたりポランニーとの対話を書き留めていた。それが「ウィークエンド・ノート」なるものである。
著者はポランニーの断片的草稿や聞き書きのノートをもとに、かれの最晩年の思想をさぐろうとしている。
ポランニーの思考は難解である。だから、そのすべてを理解するのは無理としても、せめてその一端だけでも紹介しておきたい。
ポランニーは、「産業社会における良き生活」という断片のなかで、産業文明における「自由の喪失」に触れて、こう述べている。
〈複雑な社会において、われわれの意図的行為の、意図せざる結果が啓示された。これらのなかには、われわれを脅かす二つのものがある。権力と経済的価値決定がそれである。これらは、われわれが望もうが望むまいが、他者の精神的生活に強制を強いる権力の創出にわれわれを巻きこむ。これこそ、われわれが苦しんでいる自由の喪失である。〉
この謎のようなことばは、いったい何を言わんとしているのだろう。
現代は自由な社会だといわれる。
だが、ポランニーのことばは、それを疑わせるものだ。
自由な社会といっても、人は朝から晩までお金にがんじがらめになっているではないか。お金で好きなものを買うというけれど、ほんとうはどんどんつくられる新規商品を買わされているだけではないか。それに働いているというけれど、それは人に売れるものをつくったり、人にものを売りつけたりしているだけではないのか。それがほんとうに自由な生活なのか。選挙があれば投票するというけれど、ほんとうは選ばされているだけで、それは権力の創出に貢献しているだけではないか。
社会が複雑化すればするほど、人は充満するモノと情報、イメージのなかで自分を見失っているのではないか。そして、何か大きな不安に突き動かされるように、産業文明という監獄をさらに広げることに邁進しているのではないか。
現代人は、与えられた自由という檻のなかで、自由を縛る権力と経済価値(商品)をみずからつくりだしている。そして、その権力と経済価値(商品)が他者=自己の精神を空疎なものとしていることに気づいていない。
平たくいってしまえば、ポランニーのいわんとするのは、そういうことだ。
ポランニーは、複雑な社会における権力・経済価値・自由についての「意識改革」が必要だという。
権力や経済価値(商品)はなくならない。だが、人びとは、みずからが権力や商品の創出にかかわっていることを、せめて意識しなければならない。そして、それが自由を奪うのをできるだけ阻むために、自由の領域を制度的に広げていかなければならない、とポランニーは訴える。
「ウィークエンド・ノート」で、ポランニーは、20世紀の技術的に複雑な社会には、隣人と「異なることの自由」を萎縮させる傾向があり、そうした同調主義的傾向が世論という匿名の権力を生みだす源になっていると指摘している。
ポランニーは、交通手段や電気、ガス、水道など技術に依存した文明が、何かの災害によって、とつぜんストップし、社会がひどく混乱する事態を想定する。そのとき、人間は恐怖におちいるとともに、近代産業文明が脆弱な「機械の絆」によって、かろうじて支えられていることに気づく。
ポランニーによれば、こうした複雑な技術社会は、3段階にわたって促進されてきた。それは、(1)19世紀における機械の導入、(2)日常生活への暖房、電気、水道、輸送などのシステムの導入、(3)全生命の抹殺を可能にする原爆の拡散や、すべての精神を支配しうるテレビ[いまならパソコンがつけ加わるだろう]の普及、によってである。
そして技術文明に固有な全体主義的傾向は、個人の自由を圧殺する方向にはたらく。
こうした全体主義的傾向に対抗するためには、単に個人の精神的自由をかかげるだけでは、とても間に合わない。市民的自由を制度的に拡大することが求められるのだ。
具体的には、それは言論の自由、良心の自由、集会の自由、結社の自由を意味するが、加えて、個人の「不服従の権利」が認められなければならない。
さらにポランニーはルソーにならって、ふつうの人びとを中心として、自由と平等の対立を調整する制度改革のあり方をさぐっている。自由と平等は、抽象的にみれば対立している。だが、ふつうの人びとの文化に依存するかぎり、「自由と平等は、それらがいかに相違していても、文化という具体的な媒介のなかで共存しうるし、同時的な開花を求めることができる」と、ポランニーは論じている。
著者によれば、ポランニーにとって第2次世界大戦後の社会の現実は、自由と平和への大いなる可能性の幕開けではなく、新しい全体主義的傾向の出現であった。戦後の産業社会は、効率第一主義をめざし、自由や生の充足は後回しにされた。
最晩年のポランニーは、ガルブレイスの『ゆたかな社会』に注目していた。というのも、この本が「産業社会は自由で人間的でありうるのか」というテーマを扱っていたからである。
技術的進歩と商品の増大は、むしろ自由をさらに縮小していくのではないか、とポランニーは問いかける。これにたいし、ポランニーがめざすのは「人格的生活」であり「生活に意味と統一を回復すること」である。
『ゆたかな社会』では、人格的自由が私的消費に埋没しようとしていることが指摘されていた。
ガルブレイスはまた、飢餓と失業の脅威にさらされていた19世紀と、大量生産と大量消費に支えられる20世紀が、どのように異なっているかについても論じていた。
著者のまとめによれば、ガルブレイスのいう「ゆたかな社会」では、「完全雇用を達成するために高水準の生産が要請され、高水準の生産に照応する需要を引き出すために生産の側が広告・宣伝を通じた依存効果によって欲求と必要を人為的に創出している」のであった。
しかし、ガルブレイスによれば、「ゆたかな社会」は社会的なアンバランスをもたらしていた。それは私的消費が拡大するかたわら、教育や住宅、医療といった公共的投資が不足する社会だったのである。これはとりわけアメリカ社会にみられる特質だったのかもしれない。だが、ここでもポランニーは、効率優先主義が、「自由への目に見えない妨害になっている」ことを感じている。
ポランニーが求めるのは、産業社会において自由を制度化することである。
著者によれば、ポランニーはそのために、「子供たちのための良い教育、労働・研究・創造的活動の機会、余暇を享受するすべての人のための自然・芸術・詩との広い触れ合い、言語・歴史の享受、自己を賤しめないで暮らすことができる保障、市町村や政府や自発的なアソシエーション[団体]によって提供されるサービス」などが制度化されなければならないと論じた。休暇制度の充実、労働者の保護、職場環境の改善、不服従の権利、その他、さまざまな制度も考えられるだろう。
こうした制度化は、産業社会において自由を保証し、拡大・深化していくには不可欠だった。
物質的豊かさを達成した社会は、良き生活を目標としてかかげなくてはならない、とポランニーはいう。
良き生活の核心となるのは、個人の自由である。そのためには産業社会の効率優先主義はむしろ民主的に制限されるべきだというのが、ポランニーの考え方だったと思われる。
ポランニーは、自由は無償で手に入るのではなく、そのためには費用の増大や産業効率の低下もやむをえないとみていた。
ポランニーは、産業社会を人間化していくための「自由のプログラム」を具体的に構想していくことを提唱していた。それこそが、現代民主主義の最大のテーマだと考えていたのである。
そのかたわら、弟子のロートシュテインは3年間にわたりポランニーとの対話を書き留めていた。それが「ウィークエンド・ノート」なるものである。
著者はポランニーの断片的草稿や聞き書きのノートをもとに、かれの最晩年の思想をさぐろうとしている。
ポランニーの思考は難解である。だから、そのすべてを理解するのは無理としても、せめてその一端だけでも紹介しておきたい。
ポランニーは、「産業社会における良き生活」という断片のなかで、産業文明における「自由の喪失」に触れて、こう述べている。
〈複雑な社会において、われわれの意図的行為の、意図せざる結果が啓示された。これらのなかには、われわれを脅かす二つのものがある。権力と経済的価値決定がそれである。これらは、われわれが望もうが望むまいが、他者の精神的生活に強制を強いる権力の創出にわれわれを巻きこむ。これこそ、われわれが苦しんでいる自由の喪失である。〉
この謎のようなことばは、いったい何を言わんとしているのだろう。
現代は自由な社会だといわれる。
だが、ポランニーのことばは、それを疑わせるものだ。
自由な社会といっても、人は朝から晩までお金にがんじがらめになっているではないか。お金で好きなものを買うというけれど、ほんとうはどんどんつくられる新規商品を買わされているだけではないか。それに働いているというけれど、それは人に売れるものをつくったり、人にものを売りつけたりしているだけではないのか。それがほんとうに自由な生活なのか。選挙があれば投票するというけれど、ほんとうは選ばされているだけで、それは権力の創出に貢献しているだけではないか。
社会が複雑化すればするほど、人は充満するモノと情報、イメージのなかで自分を見失っているのではないか。そして、何か大きな不安に突き動かされるように、産業文明という監獄をさらに広げることに邁進しているのではないか。
現代人は、与えられた自由という檻のなかで、自由を縛る権力と経済価値(商品)をみずからつくりだしている。そして、その権力と経済価値(商品)が他者=自己の精神を空疎なものとしていることに気づいていない。
平たくいってしまえば、ポランニーのいわんとするのは、そういうことだ。
ポランニーは、複雑な社会における権力・経済価値・自由についての「意識改革」が必要だという。
権力や経済価値(商品)はなくならない。だが、人びとは、みずからが権力や商品の創出にかかわっていることを、せめて意識しなければならない。そして、それが自由を奪うのをできるだけ阻むために、自由の領域を制度的に広げていかなければならない、とポランニーは訴える。
「ウィークエンド・ノート」で、ポランニーは、20世紀の技術的に複雑な社会には、隣人と「異なることの自由」を萎縮させる傾向があり、そうした同調主義的傾向が世論という匿名の権力を生みだす源になっていると指摘している。
ポランニーは、交通手段や電気、ガス、水道など技術に依存した文明が、何かの災害によって、とつぜんストップし、社会がひどく混乱する事態を想定する。そのとき、人間は恐怖におちいるとともに、近代産業文明が脆弱な「機械の絆」によって、かろうじて支えられていることに気づく。
ポランニーによれば、こうした複雑な技術社会は、3段階にわたって促進されてきた。それは、(1)19世紀における機械の導入、(2)日常生活への暖房、電気、水道、輸送などのシステムの導入、(3)全生命の抹殺を可能にする原爆の拡散や、すべての精神を支配しうるテレビ[いまならパソコンがつけ加わるだろう]の普及、によってである。
そして技術文明に固有な全体主義的傾向は、個人の自由を圧殺する方向にはたらく。
こうした全体主義的傾向に対抗するためには、単に個人の精神的自由をかかげるだけでは、とても間に合わない。市民的自由を制度的に拡大することが求められるのだ。
具体的には、それは言論の自由、良心の自由、集会の自由、結社の自由を意味するが、加えて、個人の「不服従の権利」が認められなければならない。
さらにポランニーはルソーにならって、ふつうの人びとを中心として、自由と平等の対立を調整する制度改革のあり方をさぐっている。自由と平等は、抽象的にみれば対立している。だが、ふつうの人びとの文化に依存するかぎり、「自由と平等は、それらがいかに相違していても、文化という具体的な媒介のなかで共存しうるし、同時的な開花を求めることができる」と、ポランニーは論じている。
著者によれば、ポランニーにとって第2次世界大戦後の社会の現実は、自由と平和への大いなる可能性の幕開けではなく、新しい全体主義的傾向の出現であった。戦後の産業社会は、効率第一主義をめざし、自由や生の充足は後回しにされた。
最晩年のポランニーは、ガルブレイスの『ゆたかな社会』に注目していた。というのも、この本が「産業社会は自由で人間的でありうるのか」というテーマを扱っていたからである。
技術的進歩と商品の増大は、むしろ自由をさらに縮小していくのではないか、とポランニーは問いかける。これにたいし、ポランニーがめざすのは「人格的生活」であり「生活に意味と統一を回復すること」である。
『ゆたかな社会』では、人格的自由が私的消費に埋没しようとしていることが指摘されていた。
ガルブレイスはまた、飢餓と失業の脅威にさらされていた19世紀と、大量生産と大量消費に支えられる20世紀が、どのように異なっているかについても論じていた。
著者のまとめによれば、ガルブレイスのいう「ゆたかな社会」では、「完全雇用を達成するために高水準の生産が要請され、高水準の生産に照応する需要を引き出すために生産の側が広告・宣伝を通じた依存効果によって欲求と必要を人為的に創出している」のであった。
しかし、ガルブレイスによれば、「ゆたかな社会」は社会的なアンバランスをもたらしていた。それは私的消費が拡大するかたわら、教育や住宅、医療といった公共的投資が不足する社会だったのである。これはとりわけアメリカ社会にみられる特質だったのかもしれない。だが、ここでもポランニーは、効率優先主義が、「自由への目に見えない妨害になっている」ことを感じている。
ポランニーが求めるのは、産業社会において自由を制度化することである。
著者によれば、ポランニーはそのために、「子供たちのための良い教育、労働・研究・創造的活動の機会、余暇を享受するすべての人のための自然・芸術・詩との広い触れ合い、言語・歴史の享受、自己を賤しめないで暮らすことができる保障、市町村や政府や自発的なアソシエーション[団体]によって提供されるサービス」などが制度化されなければならないと論じた。休暇制度の充実、労働者の保護、職場環境の改善、不服従の権利、その他、さまざまな制度も考えられるだろう。
こうした制度化は、産業社会において自由を保証し、拡大・深化していくには不可欠だった。
物質的豊かさを達成した社会は、良き生活を目標としてかかげなくてはならない、とポランニーはいう。
良き生活の核心となるのは、個人の自由である。そのためには産業社会の効率優先主義はむしろ民主的に制限されるべきだというのが、ポランニーの考え方だったと思われる。
ポランニーは、自由は無償で手に入るのではなく、そのためには費用の増大や産業効率の低下もやむをえないとみていた。
ポランニーは、産業社会を人間化していくための「自由のプログラム」を具体的に構想していくことを提唱していた。それこそが、現代民主主義の最大のテーマだと考えていたのである。



