眠る本たち その8 [眠る本たち]
いただいた本は、申し訳ないながら読まないことが多い。
でも、ぱらぱらめくりはじめると、つい引き込まれる。
今回はそんな本をいくつか。
(44)セオドア・ゼルディン『悩む人間の物語』(森内薫訳)1999年、NHK出版
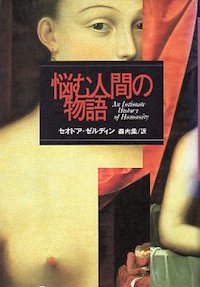
人は過去に呪縛されている。昔から受け継がれてきた「生き方」に手足を縛られている。人間は生まれながら自由ではなく、不安にさいなまれているのだ、と著者はいう。不安、孤独、憂鬱は人生につきものだ。歴史はそんな物語に満ちている。しかし、ほんの少し勇気があれば、ほんの少し思いやりがあれば、あなたの人生は変わってくる。そして、多くの見方ができるようになること。それが悩みから解放される第一歩だ。
(45)ジェラルド&ロレッタ・ハウスマン『猫たちの神話と伝説』(池田雅之、桃井緑美子訳)2000年、青土社
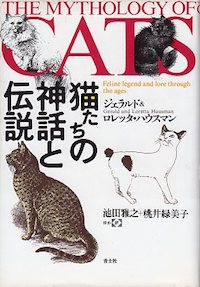
「どうやら猫という霊的存在は、一点曇りなく人間の内奥を映し出す光をたたえた鏡のような生き物、神からつかわされた癒しの使者なのかもしれない」と、訳者のひとりは書いている。そのとおりだと思う。「人間の側にいながら、人間にはわかりがたい存在……しかし、猫の側は、人間をゆっくりと観察し、人間のことは何でもわかっているように見える」とも。そんな猫たちの神話と伝説を集めたのがこの本だ。ぼくにとっても、猫のいなくなった生活はさびしい。たまらなくさびしい。
(46)西研『哲学のモノサシ』(川村易[絵])1996年、NHK出版
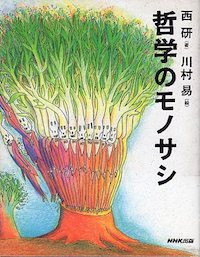
哲学する習慣を身につけること。深く根本的に考えること。自分のなかの風通しをよくすること。真実への意欲をもちつづけること。たぶん、こういう習慣を身につければ、生きることはずっと楽しくなる。自分の感受性を受け入れ、自分なりに生きるためのモノサシをつくること。本書は青年向けに書かれた哲学入門書だが、どっこい意外と深いことが書かれている。
(47)ネリー・ブライ『ケネディ家の悪夢──セックスとスキャンダルにまみれた3代の男たち』(桃井健司訳)、1996年、扶桑社
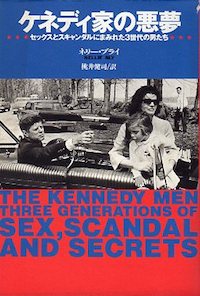
ここに描かれているのは、ケネディ一家のもう一つの顔である。ギャングと手を結び、セックスにふけり、麻薬の力を借りて快楽をむさぼる。JFKはだれかまわず女に手を出したが、圧巻は世紀のスター、マリリン・モンローだった。さらに「女を共有するのがケネディ家の伝統だった」とも。弟のボビーはモンローと深い仲になり、やがてモンローを振る。そして、狂ったようにモンローは死んでしまう。ケネディ家はスキャンダルまみれだ。ひょっとしてトランプ王国もと思うのは、ぼくだけではあるまい。
(48)仲晃『ケネディはなぜ暗殺されたか』1995年、NHK出版

1963年11月のケネディ米大統領暗殺事件の真相はいまも明らかになっていない。本書はオズワルド単独犯行説に疑問を投げかけ、ケネディはなぜ暗殺されなければならなかったかという観点から犯人の姿を追う。そこから浮かび上がるのは、資金を出して実行犯たちをあやつった「巨悪」の存在だ。
(49)羽場久浘子『拡大するヨーロッパ──中欧の模索』1998年、岩波書店
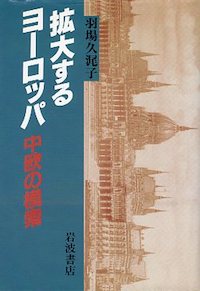
プロローグにはこう書かれている。〈本書は、現在進行中のNATO(北大西洋条約機構)、EU(欧州連合)など「ヨーロッパ」諸機構の拡大の中で、「中欧」がどのような形で「新しいヨーロッパ」に参画しようとしているのか、その中で、少数民族をめぐる民族と国家の再編はどのような形で行われているのか、さらに社会主義体制の崩壊後10年たった旧東欧社会はいかなる方向に進もうとしているのか、などを検討しようというものである。〉中欧というのは、東欧に代わる新しい地理概念だ。それはポーランド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリー、クロアチア、スロヴェニアを指している。バルカン諸国は通常、含まれない。中欧の国々の現状はなかなか伝わってこない。もっとこの国々に関心をもってもいいのではないか。
(50)ラッシュ・W・ドージアJr.『人はなぜ「憎む」のか』(桃井緑美子訳)、2003年、河出書房新社
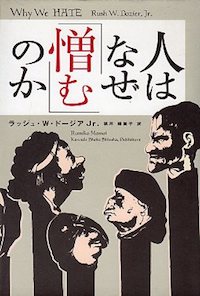
人間だけがもつ最も危険な感情、それは憎悪だ。いじめや自己嫌悪、戦争はすべて憎悪から発する。人間の感情の暗黒部分ともいえる「憎悪」は、人間関係を閉ざし、社会を傷つけ、生命を破壊し、そしてついに地球をも脅かす。この「心の核兵器」をコントロールする手立てはないのかを探る。人間の感情でいちばん最初にやってくるのが憎悪だ。愛はいちばん最後にやってくる。憎悪とは何か、それをコントロールするにはどうすればよいのか。
(51)滝口俊子『夢との対話──心理分析の現場』2014年、トランスビュー
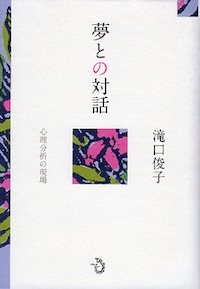
〈私は河合隼雄先生に21年間、754回の分析を受けた。そこでは、夢を解釈するのではなく、夢を生きることで、苦しみを乗り越え、たましいの成長が促された。〉ユング派の分析家、河合隼雄のことをぼくはよく知らない。この本は河合隼雄の心理分析が実際にどのようなものであったかを教えてくれる。河合隼雄のこと、もっと知るべきだ。
(52)ジョナサン・ワイナー『フィンチの嘴──ガラパゴスで起きている種の変貌』(樋口広芳・黒沢令子訳)1995年、早川書房
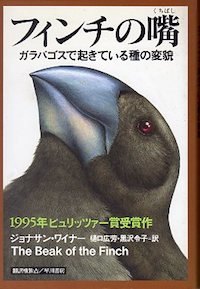
生物はいまも進化しつづけている。〈ガラパゴスの中央に浮かぶ小さな溶岩の島で、研究者夫妻は生きたフィンチ[アトリ科の鳥]を一匹一匹調べた。そして20年におよぶ調査の末に夫妻が直面したのは驚くべき事実だった。フィンチたちは刻々と変貌を遂げ、ダーウィンの予測をはるかに上回る規模と速度で進化していたのだ。〉1995年ピュリツァー賞受賞作。おもしろそうな本だ。
(53)トーマス・アームストロング『脳の個性を才能にかえる──子どもの発達障害との向き合い方』2013年、NHK出版
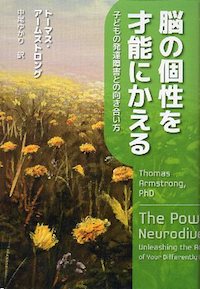
ADHD(注意欠陥多動性障害)や自閉症、ディスレクシア(失読症)、さらには気分障害や不安障害、知的発達の遅れ、統合失調症。こうした問題をかかえた子どもたちは、とかく否定的にみられがちだ。しかし、この子たちは、ほかの人にはない豊かな才能をもっている。その才能を引きだすにはどうすればよいか。脳の個性を認めあい、共生社会を実現するには……。こんな本ももらっていたのだ。これまで読んでいなかったことを反省。
でも、ぱらぱらめくりはじめると、つい引き込まれる。
今回はそんな本をいくつか。
(44)セオドア・ゼルディン『悩む人間の物語』(森内薫訳)1999年、NHK出版
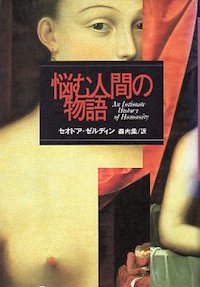
人は過去に呪縛されている。昔から受け継がれてきた「生き方」に手足を縛られている。人間は生まれながら自由ではなく、不安にさいなまれているのだ、と著者はいう。不安、孤独、憂鬱は人生につきものだ。歴史はそんな物語に満ちている。しかし、ほんの少し勇気があれば、ほんの少し思いやりがあれば、あなたの人生は変わってくる。そして、多くの見方ができるようになること。それが悩みから解放される第一歩だ。
(45)ジェラルド&ロレッタ・ハウスマン『猫たちの神話と伝説』(池田雅之、桃井緑美子訳)2000年、青土社
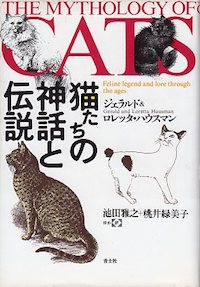
「どうやら猫という霊的存在は、一点曇りなく人間の内奥を映し出す光をたたえた鏡のような生き物、神からつかわされた癒しの使者なのかもしれない」と、訳者のひとりは書いている。そのとおりだと思う。「人間の側にいながら、人間にはわかりがたい存在……しかし、猫の側は、人間をゆっくりと観察し、人間のことは何でもわかっているように見える」とも。そんな猫たちの神話と伝説を集めたのがこの本だ。ぼくにとっても、猫のいなくなった生活はさびしい。たまらなくさびしい。
(46)西研『哲学のモノサシ』(川村易[絵])1996年、NHK出版
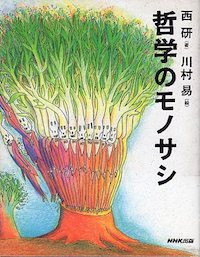
哲学する習慣を身につけること。深く根本的に考えること。自分のなかの風通しをよくすること。真実への意欲をもちつづけること。たぶん、こういう習慣を身につければ、生きることはずっと楽しくなる。自分の感受性を受け入れ、自分なりに生きるためのモノサシをつくること。本書は青年向けに書かれた哲学入門書だが、どっこい意外と深いことが書かれている。
(47)ネリー・ブライ『ケネディ家の悪夢──セックスとスキャンダルにまみれた3代の男たち』(桃井健司訳)、1996年、扶桑社
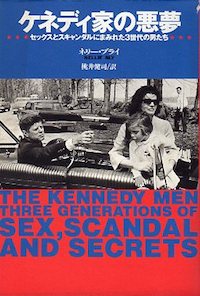
ここに描かれているのは、ケネディ一家のもう一つの顔である。ギャングと手を結び、セックスにふけり、麻薬の力を借りて快楽をむさぼる。JFKはだれかまわず女に手を出したが、圧巻は世紀のスター、マリリン・モンローだった。さらに「女を共有するのがケネディ家の伝統だった」とも。弟のボビーはモンローと深い仲になり、やがてモンローを振る。そして、狂ったようにモンローは死んでしまう。ケネディ家はスキャンダルまみれだ。ひょっとしてトランプ王国もと思うのは、ぼくだけではあるまい。
(48)仲晃『ケネディはなぜ暗殺されたか』1995年、NHK出版

1963年11月のケネディ米大統領暗殺事件の真相はいまも明らかになっていない。本書はオズワルド単独犯行説に疑問を投げかけ、ケネディはなぜ暗殺されなければならなかったかという観点から犯人の姿を追う。そこから浮かび上がるのは、資金を出して実行犯たちをあやつった「巨悪」の存在だ。
(49)羽場久浘子『拡大するヨーロッパ──中欧の模索』1998年、岩波書店
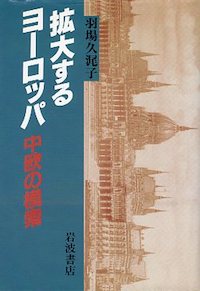
プロローグにはこう書かれている。〈本書は、現在進行中のNATO(北大西洋条約機構)、EU(欧州連合)など「ヨーロッパ」諸機構の拡大の中で、「中欧」がどのような形で「新しいヨーロッパ」に参画しようとしているのか、その中で、少数民族をめぐる民族と国家の再編はどのような形で行われているのか、さらに社会主義体制の崩壊後10年たった旧東欧社会はいかなる方向に進もうとしているのか、などを検討しようというものである。〉中欧というのは、東欧に代わる新しい地理概念だ。それはポーランド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリー、クロアチア、スロヴェニアを指している。バルカン諸国は通常、含まれない。中欧の国々の現状はなかなか伝わってこない。もっとこの国々に関心をもってもいいのではないか。
(50)ラッシュ・W・ドージアJr.『人はなぜ「憎む」のか』(桃井緑美子訳)、2003年、河出書房新社
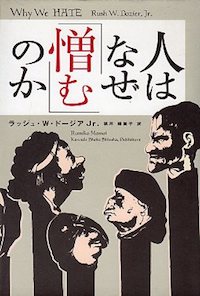
人間だけがもつ最も危険な感情、それは憎悪だ。いじめや自己嫌悪、戦争はすべて憎悪から発する。人間の感情の暗黒部分ともいえる「憎悪」は、人間関係を閉ざし、社会を傷つけ、生命を破壊し、そしてついに地球をも脅かす。この「心の核兵器」をコントロールする手立てはないのかを探る。人間の感情でいちばん最初にやってくるのが憎悪だ。愛はいちばん最後にやってくる。憎悪とは何か、それをコントロールするにはどうすればよいのか。
(51)滝口俊子『夢との対話──心理分析の現場』2014年、トランスビュー
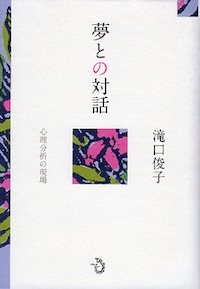
〈私は河合隼雄先生に21年間、754回の分析を受けた。そこでは、夢を解釈するのではなく、夢を生きることで、苦しみを乗り越え、たましいの成長が促された。〉ユング派の分析家、河合隼雄のことをぼくはよく知らない。この本は河合隼雄の心理分析が実際にどのようなものであったかを教えてくれる。河合隼雄のこと、もっと知るべきだ。
(52)ジョナサン・ワイナー『フィンチの嘴──ガラパゴスで起きている種の変貌』(樋口広芳・黒沢令子訳)1995年、早川書房
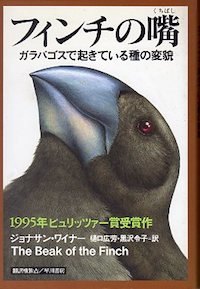
生物はいまも進化しつづけている。〈ガラパゴスの中央に浮かぶ小さな溶岩の島で、研究者夫妻は生きたフィンチ[アトリ科の鳥]を一匹一匹調べた。そして20年におよぶ調査の末に夫妻が直面したのは驚くべき事実だった。フィンチたちは刻々と変貌を遂げ、ダーウィンの予測をはるかに上回る規模と速度で進化していたのだ。〉1995年ピュリツァー賞受賞作。おもしろそうな本だ。
(53)トーマス・アームストロング『脳の個性を才能にかえる──子どもの発達障害との向き合い方』2013年、NHK出版
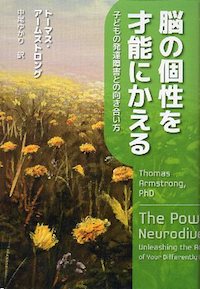
ADHD(注意欠陥多動性障害)や自閉症、ディスレクシア(失読症)、さらには気分障害や不安障害、知的発達の遅れ、統合失調症。こうした問題をかかえた子どもたちは、とかく否定的にみられがちだ。しかし、この子たちは、ほかの人にはない豊かな才能をもっている。その才能を引きだすにはどうすればよいか。脳の個性を認めあい、共生社会を実現するには……。こんな本ももらっていたのだ。これまで読んでいなかったことを反省。
眠る本たち その7 [眠る本たち]
本の整理、なかなか進まない。目を通すだけでも。
(35)ローラ・インガルス・ワイルダー『大草原の小さな町』(鈴木哲子訳)1987年[1957年初版]、岩波書店[岩波少年文庫]
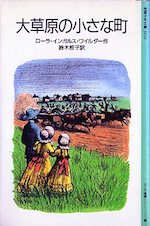
昔、『大草原の小さな家』というテレビドラマを一家でよくみていた。NHKで放送されたのは1975年から82年にかけてのことだという。毎週土曜夕方6時からの放映だったという。長女は1975年生まれだから、再放送を見たのかもしれない。あのころはアメリカのドラマがいまよりもずっと多くテレビで流されていた。この番組は1870年代から80年代にかけての西部開拓時代のアメリカが舞台。原作はローラ・インガルス・ワイルダーの自叙伝で、その1冊がこの『大草原の小さな町』だ。ローラ役の少女がかわいかった。父さん、母さんもかっこよかった。
(36)入江隆則『文明論の現在』2003年、多摩川大学出版部
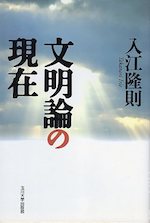
カバー裏の案内に「保守派の論客が、文明論的状況からアメリカとは何か、激動するアジア、ナショナリズムについて、あるいは太平洋文明論など縦横に論じ、存亡の危機に立つ日本の進むべき路を考える」とある。著者いわく。「アメリカは今日世界で唯一の覇権国であって、世界の幸不幸は、この国の動静に懸かっているところが大きい。世俗的なものに形を変えて生き続けるその宗教的情熱と、独立戦争以来培われてきた矜持とが、独善的な方向に向かうと、世界全体の不幸になる。したがってそれをどうコントロールするかに、知恵をしぼらねばならない時期が来ていると思う」。著者は日本こそがアメリカをコントロールすべきだと訴えるのだが、現状は日本がますますアメリカの言いなりになっている。そこが悲しいところだ。
(37)皆川博子『死の泉』1997年、早川書房
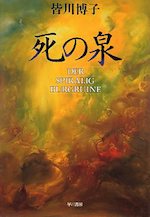
ナチスは金髪で青い目のアーリア人を増やすため、未婚女性の出産を支援するレーベンボルン(命の泉)という施設をつくった。ここには生まれてくる子どもだけではなく、さらわれてきた子どもも収容された。その多くがポーランド人だった。この小説はレーベンボルンを舞台にしたミステリー。レーベンボルンに収容されたポーランド人がナチス時代をふり返ってつづった手記を昔、編集したことがある。そのとき訳者から紹介されて買ったのだと思う。ポーランド語の原著タイトルは「ヤンチャルの学校」で、何のことかよくわからない、と訳者はいっていた。あとで、それはトルコでいうイェニチェリのことだと知った。
(38)長沢和俊『シルクロード・幻の王国』1980年[初版は1976年]、日本放送出版協会[NHKブックスジュニア]

たぶんこれはシルクロードに行きたがっていた義父が買った本だ。このころ義父は心筋梗塞で倒れ、5年後に亡くなったから、シルクロードには行けなかった。中央アジア探検の歴史、シルクロードの町、それに砂漠に消えたローラン王国のことがつづられている。あのころNHKテレビでもシルクロードの大型企画番組が放映されていた。
(39)中山俊明『紀子妃の右手──[お髪直し]写真事件』1992年、情報センター出版局


著者は将来を嘱望される共同通信の写真記者として、1988年に宮内庁嘱託カメラマンとなった。90年の秋篠宮結婚にさいして、偶然、紀子妃が右手で秋篠宮の髪を直そうとする一瞬を撮影した。宮内庁はこの写真を差し止めようとしたが、新聞はそれを掲載した。そのときから記者は非難の嵐にさらされ、ついには退社の道を選ぶ。皇室報道にはまだまだタブーがある。
(40)石山永一郞『フィリピン出稼ぎ労働者──夢を追い日本に生きて』1989年、柘植書房
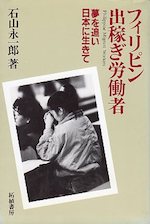
共同通信元マニラ支局長によるルポ。フィリピンから日本に出稼ぎにきた男たち、女たちを名古屋の栄、横浜の寿町、東京の六本木、沖縄の金武、そしてフィリピン・マニラで取材する。〈日本が真に国際化をするということは、日本社会が豊かな多様性を持つことであると私は思っている。多様な価値観を受け入れる社会の柔軟性を育み、少数者の痛みや悲しみへの想像力を増すことが本当の意味での国際化には不可欠である。〉フリーになった著者のこれからの活躍が注目される。
(41)西園寺一晃『青春の北京──北京留学の十年』1971年、中央公論社

1958年から67年までの10年間、著者は北京で過ごした。15歳から25歳にかけての青春時代である。文革時代を含むその時代を、自らの思い出とともに描いたのが本書。あのころ文革は日本では何かあこがれをもって見られていた。ぼく自身は文革に幻想をいだいていなかった。文革は中国共産党のプロパガンダに彩られて、日本に伝えられていた。その実態を知る日本人は少なかったのだ。
(42)本多勝一『極限の民族』1971年[初版は1967年]、朝日新聞社
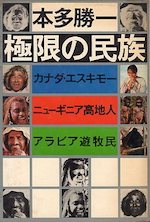
カナダ・エスキモー、ニューギニア高地人、アラビア遊牧民のルポ。取材したのは1963年から65年にかけて。朝日新聞に連載された。本多勝一はその後、南ベトナムや中国も取材している。朝日の看板記者だった。その分、いまは風当たりが強い。でも、この探検ものは読みはじめると、意外とおもしろい。
(43)笹倉明『ニッポン流学』1991年、文藝春秋
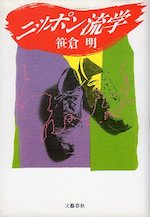
直木賞作家、待望の第一エッセイ集、とある。「揺れ動くニッポンの日常から、自作や隣人、そしてアジア世界に向けられた著者の深いまなざし」とある。高校時代の友人だ。いまはタイで僧侶の修行をしていると聞いた。久しぶりにゆっくり話したいものだ。
(35)ローラ・インガルス・ワイルダー『大草原の小さな町』(鈴木哲子訳)1987年[1957年初版]、岩波書店[岩波少年文庫]
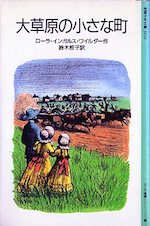
昔、『大草原の小さな家』というテレビドラマを一家でよくみていた。NHKで放送されたのは1975年から82年にかけてのことだという。毎週土曜夕方6時からの放映だったという。長女は1975年生まれだから、再放送を見たのかもしれない。あのころはアメリカのドラマがいまよりもずっと多くテレビで流されていた。この番組は1870年代から80年代にかけての西部開拓時代のアメリカが舞台。原作はローラ・インガルス・ワイルダーの自叙伝で、その1冊がこの『大草原の小さな町』だ。ローラ役の少女がかわいかった。父さん、母さんもかっこよかった。
(36)入江隆則『文明論の現在』2003年、多摩川大学出版部
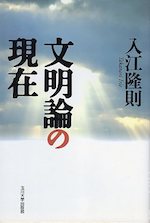
カバー裏の案内に「保守派の論客が、文明論的状況からアメリカとは何か、激動するアジア、ナショナリズムについて、あるいは太平洋文明論など縦横に論じ、存亡の危機に立つ日本の進むべき路を考える」とある。著者いわく。「アメリカは今日世界で唯一の覇権国であって、世界の幸不幸は、この国の動静に懸かっているところが大きい。世俗的なものに形を変えて生き続けるその宗教的情熱と、独立戦争以来培われてきた矜持とが、独善的な方向に向かうと、世界全体の不幸になる。したがってそれをどうコントロールするかに、知恵をしぼらねばならない時期が来ていると思う」。著者は日本こそがアメリカをコントロールすべきだと訴えるのだが、現状は日本がますますアメリカの言いなりになっている。そこが悲しいところだ。
(37)皆川博子『死の泉』1997年、早川書房
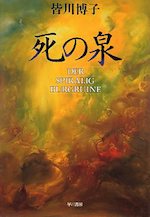
ナチスは金髪で青い目のアーリア人を増やすため、未婚女性の出産を支援するレーベンボルン(命の泉)という施設をつくった。ここには生まれてくる子どもだけではなく、さらわれてきた子どもも収容された。その多くがポーランド人だった。この小説はレーベンボルンを舞台にしたミステリー。レーベンボルンに収容されたポーランド人がナチス時代をふり返ってつづった手記を昔、編集したことがある。そのとき訳者から紹介されて買ったのだと思う。ポーランド語の原著タイトルは「ヤンチャルの学校」で、何のことかよくわからない、と訳者はいっていた。あとで、それはトルコでいうイェニチェリのことだと知った。
(38)長沢和俊『シルクロード・幻の王国』1980年[初版は1976年]、日本放送出版協会[NHKブックスジュニア]

たぶんこれはシルクロードに行きたがっていた義父が買った本だ。このころ義父は心筋梗塞で倒れ、5年後に亡くなったから、シルクロードには行けなかった。中央アジア探検の歴史、シルクロードの町、それに砂漠に消えたローラン王国のことがつづられている。あのころNHKテレビでもシルクロードの大型企画番組が放映されていた。
(39)中山俊明『紀子妃の右手──[お髪直し]写真事件』1992年、情報センター出版局


著者は将来を嘱望される共同通信の写真記者として、1988年に宮内庁嘱託カメラマンとなった。90年の秋篠宮結婚にさいして、偶然、紀子妃が右手で秋篠宮の髪を直そうとする一瞬を撮影した。宮内庁はこの写真を差し止めようとしたが、新聞はそれを掲載した。そのときから記者は非難の嵐にさらされ、ついには退社の道を選ぶ。皇室報道にはまだまだタブーがある。
(40)石山永一郞『フィリピン出稼ぎ労働者──夢を追い日本に生きて』1989年、柘植書房
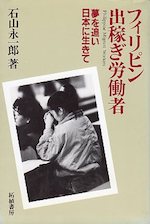
共同通信元マニラ支局長によるルポ。フィリピンから日本に出稼ぎにきた男たち、女たちを名古屋の栄、横浜の寿町、東京の六本木、沖縄の金武、そしてフィリピン・マニラで取材する。〈日本が真に国際化をするということは、日本社会が豊かな多様性を持つことであると私は思っている。多様な価値観を受け入れる社会の柔軟性を育み、少数者の痛みや悲しみへの想像力を増すことが本当の意味での国際化には不可欠である。〉フリーになった著者のこれからの活躍が注目される。
(41)西園寺一晃『青春の北京──北京留学の十年』1971年、中央公論社

1958年から67年までの10年間、著者は北京で過ごした。15歳から25歳にかけての青春時代である。文革時代を含むその時代を、自らの思い出とともに描いたのが本書。あのころ文革は日本では何かあこがれをもって見られていた。ぼく自身は文革に幻想をいだいていなかった。文革は中国共産党のプロパガンダに彩られて、日本に伝えられていた。その実態を知る日本人は少なかったのだ。
(42)本多勝一『極限の民族』1971年[初版は1967年]、朝日新聞社
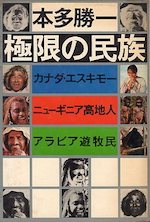
カナダ・エスキモー、ニューギニア高地人、アラビア遊牧民のルポ。取材したのは1963年から65年にかけて。朝日新聞に連載された。本多勝一はその後、南ベトナムや中国も取材している。朝日の看板記者だった。その分、いまは風当たりが強い。でも、この探検ものは読みはじめると、意外とおもしろい。
(43)笹倉明『ニッポン流学』1991年、文藝春秋
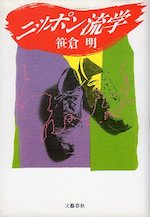
直木賞作家、待望の第一エッセイ集、とある。「揺れ動くニッポンの日常から、自作や隣人、そしてアジア世界に向けられた著者の深いまなざし」とある。高校時代の友人だ。いまはタイで僧侶の修行をしていると聞いた。久しぶりにゆっくり話したいものだ。
眠る本たち その6 [眠る本たち]
(25)『スパルタクス書簡』(中村丈夫、山崎カヲル、船戸満之訳)1971年、鹿砦社

学生時代、ローザ・ルクセンブルク(1871-1919)の書いたものを読みあさったことがある。1914年、第一次世界大戦がはじまったとき、ローザの所属するドイツ社会民主党は戦争を支持し、これに反対するローザたちは新たなグループを結成、それが「スパルタクス団(ブント)」となった。スパルタクス団が発行した非合法冊子が、この『スパルタクス書簡』(1916年9月〜1918年9月)である。その後、ローザは逮捕されるが、獄中でいくつも論文を執筆し、ロシア革命を主導したレーニン流のボリシェヴィズムを批判するとともに、ドイツの労働者に戦争反対への決起を呼びかけた。1918年11月にドイツ革命が発生し、皇帝ヴィルヘルム2世が廃位されると、ローザもブレスラウ監獄から釈放される。しかし、それからすぐ、1919年1月に軍部によって殺害され、ベルリンの運河に捨てられた。貴重な文書だが、読み切れなかった。
(26)デイビッド・ハルバースタム『ネクスト・センチュリー』(浅野輔訳)1991年[原著も1991年]、TBSブリタニカ
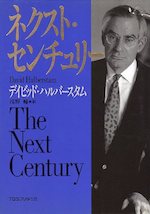
1990年に執筆された本書で、ハルバースタムはこう論じている。〈アメリカは歴史上初めて、他国に後れをとるかもしれないという危機にさらされている。ソ連と比べれば、アメリカの制度や経済は目を見張らされるほど優れている。しかし、いまや勢い盛んな他の国々と比較した場合、アメリカは疲弊し消耗しきって見える。もし純粋に経済的な将来のモデルがあるとすれば、それは日本だ。日本人は猛烈な情け容赦のない競争相手である。教育水準が高く勤勉で、規律の行き届いた社会という点で、日本は他国の見本といってよい。〉ハルバースタムは「アメリカの世紀」の終焉を実感していた。それから四半世紀以上たち、状況はがらりと変わる。本書ではほとんど中国について語られていない。ハルバースタムの予想とは異なり、21世紀は日本の世紀にはならなかった。
(27)リリアーヌ・シエジェル『影の娘──サルトルとの二十年』(西陽子、海老坂武訳)1990年[原著は1988年]、人文書院
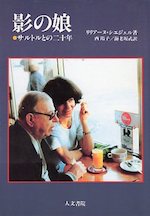
サルトルは一生独身だったが、まわりには多くの愛人が集まっていた。「私がサルトルの生活の中に入ったとき、彼の人生の完全な同伴者であるシモーヌ・ド・ボーヴォワールのほかに4人の女性がいて、私は5番目となった」と、リリアーヌは書いている。愛人の誰もがサルトルと別れなかった。実に複雑だが、濃密な日々だ。訳者のひとりは書いている。〈本書の中でサルトルは実に多くを与えている。と同時に、一人ずつ個性の異なる美女たちに囲まれてなんとも生き生きしている。わがままに手を焼き、おねだりで財布を空にしたが、それに劣らぬものを女性関係から得ていたようだ。〉
(28)藤田紘一郎『空飛ぶ寄生虫』1996年、講談社
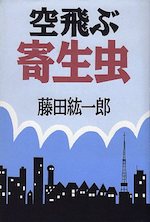
前にみた『笑うカイチュウ』の続編。西郷隆盛はバンクロフト糸状虫症にかかっていたらしい。おそらく、若いころ島流しにあった喜界島で感染したようだ。媒介したのはネッタイイエカ。西郷はこの病気で陰嚢が巨大になり、馬に乗れなかった。西南戦争で敗れたとき城山で西郷は自害するが、首のない遺体を西郷と確認する証拠となったのは巨大な陰嚢だったという。〈検死官は死体の股間を検査した。大きな陰嚢は革の袋でくるんでつるし上げられていた。革袋を開いてみると、ヒトの頭の大きさの陰嚢があらわれたのだった。〉西郷にも人にいえない悩みがあったのだ。
(29)櫻井よしこ『エイズ犯罪──血友病患者の悲劇』1994年、中央公論社

本のオビにこうある。〈「私と一緒にエイズで死んでください」──法廷に悲痛な叫びがこだまする。1800人もの罪なき人々がなぜエイズに感染しなければならなかったのか? 国と製薬会社の責任を問う「東京HIV訴訟」を追い、医の倫理に鋭く迫る。〉切々としたヒューマン・ドキュメントである。いまの櫻井よしこのイメージからみれば、ちょっと意外な感がする。
(30)村松友視『ギターとたくあん──堀威夫流不良の粋脈』2010年、集英社
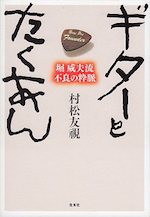
守屋浩、舟木一夫、和田アキ子、森昌子、石川さゆり、山口百恵、榊原郁恵など、数々のスターを送りだしたホリプロ社長、堀威夫の半生をえがく。堀威夫はたくあんが好きで、自分でたくあんをつけていた。1年につける量は300キロ、自宅にはたくあん専用の地下室があった。この手塩にかける姿勢が、タレント養成にもつながっていた。ギターはかれの出発点でもある。タレントの裏話はない。そのへんが、ぼくとしては残念。
(31)宇井純『公害列島 70年代』1972年、亜紀書房

宇井純(1932-2006)は立派だった。東大の都市工学科助手として、水俣病を告発し、1970年からは「公害原論」の公開自主講座を開いていた。東大からは認められず、万年助手(21年間)のままだったが、日本の反公害運動にはたした業績は大きい。もっと顕彰されてしかるべき人物だ。〈被害者にとって公害ほど理不尽なものはない。病気の苦しみの上に社会的な差別が、向こうからやって来る。そして、だまっていれば誰も助けてはくれないのである。自分が立ち上がって抵抗しないかぎり、事態の改善は全く展望がない。学問も、政治も、被害者みずからの行動の前には壁となって立ちふさがる。その壁をのりこえ、突き破って、公害反対運動はここまで進んで来た。〉こういう人こそ表彰すべきではないか。
(32)デニス・スミス『ソング・フォー・メアリー──そしてぼくは自分を見つけた』(別宮貞德、高橋照子訳)2000年、メディアファクトリー
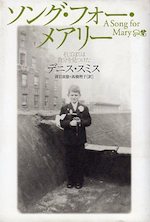
カバー折り返しの説明。〈アイルランド移民の家庭で生まれたデニスは父親の顔を知らない。母メアリーは床に這いつくばって他人の家の掃除をする。やればできると言われても、まじめにやったところで、生活保護を受けている暮らしむきは変わることはない。不登校、酒、麻薬の果てに暴行罪。絶望のデニスを救ったものは──。荒廃した少年時代から消防士という天職を見つけるまでの葛藤の日々を経て、生きていることの燃えるような実感を求めて自分自身を発見していく感動のノンフィクション。〉ぜったいいい本だ。アメリカでベストセラーになったのもわかるような気がする。メディアファクトリーはリクルートがつくった出版社。いまはKADOKAWAグループで、ライトノベルやコミックを出し、ゲームも扱っている。
(33)コリン・パウエル/ジョゼフ・E・パーシコ『マイ・アメリカン・ジャーニー[コリン・パウエル自伝]』(鈴木主税訳)1995年、角川書店
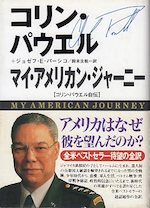
本文だけで700ページ以上あり、しかも2段組。訳者は苦労しただろう。しかし、とうとう読む気力が湧かなかった。訳者あとがきをひいておく。〈コリン・パウエルは、まさにアメリカン・ドリームを体現した新しいヒーローだと言ってもいいだろう。決して裕福ではないジャマイカ移民の家庭に生まれ、黒人ゆえのハンディを背負いながら軍隊で頭角をあらわし、ついには統合参謀本部議長の地位にまでのぼりつめた。さらに湾岸戦争は、パウエルがアメリカのヒーローとして自らを国民にアピールするうえでまたとない舞台を提供したわけである。パウエルがたどったキャリアは、絵に描いたようなサクセス・ストーリーだと言えなくもない。現状に不満を抱く国民にとっては、うってつけのニュー・ヒーローの登場なのだ。〉
(34)共同通信社編『生の時死の時』1997年、共同通信社
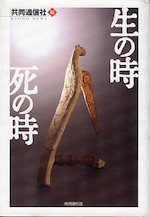
世界の人びとはどのように死と向き合い、その死を受け入れているのか。〈“死に至る病”を公表して、人生の成就に向かったミッテラン前フランス大統領の看取り、登山家をなお前へ進ませた臨死体験、戦争や内乱で虐殺の地となったカンボジア、韓国の島[済州]、ルワンダの人びとの集団的記憶、連続殺人者の父が心の謎を語り、被害者の家族が死刑執行を見つめる米国、貧困や災害が波のように人びとを襲い、打ち砕くアジア、南米──〉焦点が拡散し、印象がひとつにまとまらない。はいりこめなかった。

学生時代、ローザ・ルクセンブルク(1871-1919)の書いたものを読みあさったことがある。1914年、第一次世界大戦がはじまったとき、ローザの所属するドイツ社会民主党は戦争を支持し、これに反対するローザたちは新たなグループを結成、それが「スパルタクス団(ブント)」となった。スパルタクス団が発行した非合法冊子が、この『スパルタクス書簡』(1916年9月〜1918年9月)である。その後、ローザは逮捕されるが、獄中でいくつも論文を執筆し、ロシア革命を主導したレーニン流のボリシェヴィズムを批判するとともに、ドイツの労働者に戦争反対への決起を呼びかけた。1918年11月にドイツ革命が発生し、皇帝ヴィルヘルム2世が廃位されると、ローザもブレスラウ監獄から釈放される。しかし、それからすぐ、1919年1月に軍部によって殺害され、ベルリンの運河に捨てられた。貴重な文書だが、読み切れなかった。
(26)デイビッド・ハルバースタム『ネクスト・センチュリー』(浅野輔訳)1991年[原著も1991年]、TBSブリタニカ
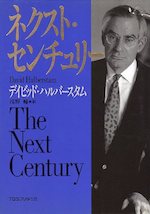
1990年に執筆された本書で、ハルバースタムはこう論じている。〈アメリカは歴史上初めて、他国に後れをとるかもしれないという危機にさらされている。ソ連と比べれば、アメリカの制度や経済は目を見張らされるほど優れている。しかし、いまや勢い盛んな他の国々と比較した場合、アメリカは疲弊し消耗しきって見える。もし純粋に経済的な将来のモデルがあるとすれば、それは日本だ。日本人は猛烈な情け容赦のない競争相手である。教育水準が高く勤勉で、規律の行き届いた社会という点で、日本は他国の見本といってよい。〉ハルバースタムは「アメリカの世紀」の終焉を実感していた。それから四半世紀以上たち、状況はがらりと変わる。本書ではほとんど中国について語られていない。ハルバースタムの予想とは異なり、21世紀は日本の世紀にはならなかった。
(27)リリアーヌ・シエジェル『影の娘──サルトルとの二十年』(西陽子、海老坂武訳)1990年[原著は1988年]、人文書院
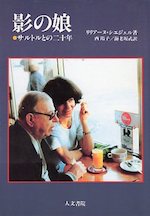
サルトルは一生独身だったが、まわりには多くの愛人が集まっていた。「私がサルトルの生活の中に入ったとき、彼の人生の完全な同伴者であるシモーヌ・ド・ボーヴォワールのほかに4人の女性がいて、私は5番目となった」と、リリアーヌは書いている。愛人の誰もがサルトルと別れなかった。実に複雑だが、濃密な日々だ。訳者のひとりは書いている。〈本書の中でサルトルは実に多くを与えている。と同時に、一人ずつ個性の異なる美女たちに囲まれてなんとも生き生きしている。わがままに手を焼き、おねだりで財布を空にしたが、それに劣らぬものを女性関係から得ていたようだ。〉
(28)藤田紘一郎『空飛ぶ寄生虫』1996年、講談社
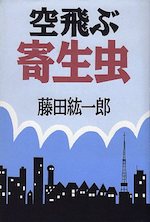
前にみた『笑うカイチュウ』の続編。西郷隆盛はバンクロフト糸状虫症にかかっていたらしい。おそらく、若いころ島流しにあった喜界島で感染したようだ。媒介したのはネッタイイエカ。西郷はこの病気で陰嚢が巨大になり、馬に乗れなかった。西南戦争で敗れたとき城山で西郷は自害するが、首のない遺体を西郷と確認する証拠となったのは巨大な陰嚢だったという。〈検死官は死体の股間を検査した。大きな陰嚢は革の袋でくるんでつるし上げられていた。革袋を開いてみると、ヒトの頭の大きさの陰嚢があらわれたのだった。〉西郷にも人にいえない悩みがあったのだ。
(29)櫻井よしこ『エイズ犯罪──血友病患者の悲劇』1994年、中央公論社

本のオビにこうある。〈「私と一緒にエイズで死んでください」──法廷に悲痛な叫びがこだまする。1800人もの罪なき人々がなぜエイズに感染しなければならなかったのか? 国と製薬会社の責任を問う「東京HIV訴訟」を追い、医の倫理に鋭く迫る。〉切々としたヒューマン・ドキュメントである。いまの櫻井よしこのイメージからみれば、ちょっと意外な感がする。
(30)村松友視『ギターとたくあん──堀威夫流不良の粋脈』2010年、集英社
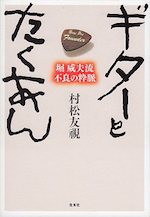
守屋浩、舟木一夫、和田アキ子、森昌子、石川さゆり、山口百恵、榊原郁恵など、数々のスターを送りだしたホリプロ社長、堀威夫の半生をえがく。堀威夫はたくあんが好きで、自分でたくあんをつけていた。1年につける量は300キロ、自宅にはたくあん専用の地下室があった。この手塩にかける姿勢が、タレント養成にもつながっていた。ギターはかれの出発点でもある。タレントの裏話はない。そのへんが、ぼくとしては残念。
(31)宇井純『公害列島 70年代』1972年、亜紀書房

宇井純(1932-2006)は立派だった。東大の都市工学科助手として、水俣病を告発し、1970年からは「公害原論」の公開自主講座を開いていた。東大からは認められず、万年助手(21年間)のままだったが、日本の反公害運動にはたした業績は大きい。もっと顕彰されてしかるべき人物だ。〈被害者にとって公害ほど理不尽なものはない。病気の苦しみの上に社会的な差別が、向こうからやって来る。そして、だまっていれば誰も助けてはくれないのである。自分が立ち上がって抵抗しないかぎり、事態の改善は全く展望がない。学問も、政治も、被害者みずからの行動の前には壁となって立ちふさがる。その壁をのりこえ、突き破って、公害反対運動はここまで進んで来た。〉こういう人こそ表彰すべきではないか。
(32)デニス・スミス『ソング・フォー・メアリー──そしてぼくは自分を見つけた』(別宮貞德、高橋照子訳)2000年、メディアファクトリー
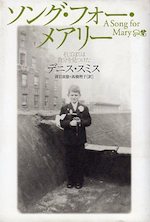
カバー折り返しの説明。〈アイルランド移民の家庭で生まれたデニスは父親の顔を知らない。母メアリーは床に這いつくばって他人の家の掃除をする。やればできると言われても、まじめにやったところで、生活保護を受けている暮らしむきは変わることはない。不登校、酒、麻薬の果てに暴行罪。絶望のデニスを救ったものは──。荒廃した少年時代から消防士という天職を見つけるまでの葛藤の日々を経て、生きていることの燃えるような実感を求めて自分自身を発見していく感動のノンフィクション。〉ぜったいいい本だ。アメリカでベストセラーになったのもわかるような気がする。メディアファクトリーはリクルートがつくった出版社。いまはKADOKAWAグループで、ライトノベルやコミックを出し、ゲームも扱っている。
(33)コリン・パウエル/ジョゼフ・E・パーシコ『マイ・アメリカン・ジャーニー[コリン・パウエル自伝]』(鈴木主税訳)1995年、角川書店
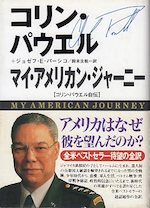
本文だけで700ページ以上あり、しかも2段組。訳者は苦労しただろう。しかし、とうとう読む気力が湧かなかった。訳者あとがきをひいておく。〈コリン・パウエルは、まさにアメリカン・ドリームを体現した新しいヒーローだと言ってもいいだろう。決して裕福ではないジャマイカ移民の家庭に生まれ、黒人ゆえのハンディを背負いながら軍隊で頭角をあらわし、ついには統合参謀本部議長の地位にまでのぼりつめた。さらに湾岸戦争は、パウエルがアメリカのヒーローとして自らを国民にアピールするうえでまたとない舞台を提供したわけである。パウエルがたどったキャリアは、絵に描いたようなサクセス・ストーリーだと言えなくもない。現状に不満を抱く国民にとっては、うってつけのニュー・ヒーローの登場なのだ。〉
(34)共同通信社編『生の時死の時』1997年、共同通信社
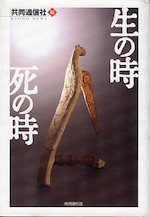
世界の人びとはどのように死と向き合い、その死を受け入れているのか。〈“死に至る病”を公表して、人生の成就に向かったミッテラン前フランス大統領の看取り、登山家をなお前へ進ませた臨死体験、戦争や内乱で虐殺の地となったカンボジア、韓国の島[済州]、ルワンダの人びとの集団的記憶、連続殺人者の父が心の謎を語り、被害者の家族が死刑執行を見つめる米国、貧困や災害が波のように人びとを襲い、打ち砕くアジア、南米──〉焦点が拡散し、印象がひとつにまとまらない。はいりこめなかった。
眠る本たち その5 [眠る本たち]
おそらく、もう読めない本たち。
買ったのに(あるいはもらったのに)読めなかった。
時間がなくなってしまった。ひたすら許しを乞う。
(18)コリン・ウィルソン『わが青春わが読書』(柴田元幸監訳)1997年、学習研究社
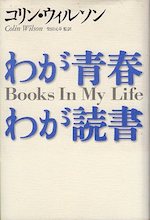
『アウトサイダー』などで知られるコリン・ウィルソン(1931-2013)は本の虫だった。そのウィルソンが青年時代に読んだ本を回顧する。シャーロック・ホームズ、ファウスト、プラトン、ショー、エリオット、ジョイス、ヘミングウェイ、ニーチェ、ジェイムズ兄弟、サルトル、ユイスマンス、ゾラ……。〈人はただ認識しさえすればよいのだ──精神の焦点を合わせるという行為が、より深い意味の認識をもたらし、人類の進化への新しいステップのとば口にたつことを可能にしてくれるということを。文学の目的もまさにここにある。〉写真を撮るときのように、精神の焦点を合わせる。読書も同じ。
(19)俵万智『サラダ記念日』1987年、河出書房新社
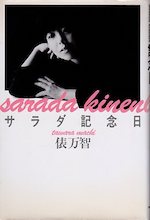
大ベストセラーになった俵万智の歌集。古くさいと思われていた歌が、特別のこの瞬間を切り取る道具に変わったことを知ったときの驚き。〈「嫁さんになれよ」だなんてカンチューハイ二本で言ってしまっていいの〉〈愛人でいいのとうたう歌手がいて言ってくれるじゃないのと思う〉〈「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日〉ここにはどんなドラマがくり広げられていたのだろう。ふだんのことばで歌が詠めることを教えてくれた。
(20)ハリソン・E・ソールズベリー『ヒーローの輝く瞬間(とき)』(柴田裕之訳)1995年、NHK出版

ソールズベリー(1908-93)は気骨のジャーナリストだった。その彼が自分の会った、自分にとってのヒーロー20人を選んで、その人となりをえがいたエッセイ。有名人もそうでない人もいる。だれもが知っている人としては、ロバート・ケネディやソルジェニーツィン、ハルバースタム、マルコムX、劉少奇、フルシチョフ、宋慶齢、サハロフ、エドガー・スノー、劉賓雁、周恩来などがでてくる。有名人、無名人を問わず、だれもが輝く一瞬をもっていた。
(21)グレイグ・ブロード『テクノストレス──コンピュータ革命が人間につきつける代償』(池央耿・高見浩訳)1984年、新潮社
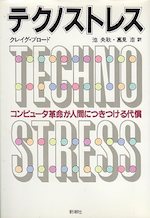
いまはコンピュータがなければ、世の中、にっちもさっちもいかなくなってしまった時代。しかし、コンピュータ文明によって「われわれ自身と次代の子どもたちは、肉体的、心理的、ならびに社会的に、果たしていかなる変化に見舞われたか」。この本が出されたころは、オフィスにパソコンが導入されたばかりで、ぼくなどもこれをマスターしなければ時代に取り残されるのではないかと恐怖をいだいたものだ。コンピュータは多くのことを可能にしたが、人間から奪い取ったものも大きい。一度、それをじっくりふり返ってみるのもいいのではないか。ちなみに、うちの11歳の孫も、すでにコンピュータ・ゲームのとりこになってしまっている。
(22)陳舜臣『北京の旅』1978年、平凡社
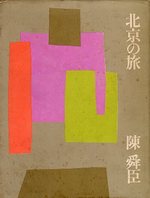
1970年代の北京は緑豊かな町だった。陳舜臣は「北京には人を酔わせる要素がいろいろありますが、緑のゆたかなこともその一つではないでしょうか」と書いている。緑の東直路では、ラバが車をひいてトコトコ歩いている牧歌的な情景が残っていたという。あのころの北京はいまどこにいってしまったのだろう。日中関係が良好だったあの時代がなつかしい。
(23)アリフィン・ベイ『インドネシアのこころ』(奥源造編訳)1975年、文遊社
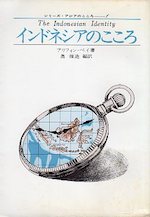
日本人は他国を経済的な観点からしか評価しないきらいがある。著者はいう。〈人々を文化、宗教、さらに非物質的な遺産としての歴史の所産であると認識するよう、日本人にすすめたい。異なった文化を理解し、「異なること」が必ずしも「悪いこと」ではないことをみいだすよう努力してほしいと訴えたい。〉日本をよく知るインドネシアのジャーナリストによるインドネシア紹介の書。あのころ、ぼくはアジアをもっと知りたいと思っていた。
(24)スーザン・ジョージ『なぜ世界の半分が飢えるのか──食糧危機の構造』(小南祐一郎・谷口真里子訳)1987年[初版は1984年]、朝日選書(朝日新聞社)

第三世界の飢餓は人口過剰や天候異変だけが原因ではない。「飢えは天災ではなく、一種の人災である」。世界の食糧を操り、食糧不足をつくりだしているのは、巨大な多国籍企業なのだ。途上国は従属から脱却すべきだと訴える。
買ったのに(あるいはもらったのに)読めなかった。
時間がなくなってしまった。ひたすら許しを乞う。
(18)コリン・ウィルソン『わが青春わが読書』(柴田元幸監訳)1997年、学習研究社
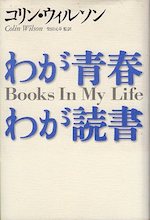
『アウトサイダー』などで知られるコリン・ウィルソン(1931-2013)は本の虫だった。そのウィルソンが青年時代に読んだ本を回顧する。シャーロック・ホームズ、ファウスト、プラトン、ショー、エリオット、ジョイス、ヘミングウェイ、ニーチェ、ジェイムズ兄弟、サルトル、ユイスマンス、ゾラ……。〈人はただ認識しさえすればよいのだ──精神の焦点を合わせるという行為が、より深い意味の認識をもたらし、人類の進化への新しいステップのとば口にたつことを可能にしてくれるということを。文学の目的もまさにここにある。〉写真を撮るときのように、精神の焦点を合わせる。読書も同じ。
(19)俵万智『サラダ記念日』1987年、河出書房新社
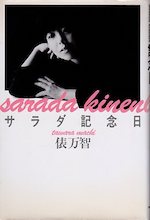
大ベストセラーになった俵万智の歌集。古くさいと思われていた歌が、特別のこの瞬間を切り取る道具に変わったことを知ったときの驚き。〈「嫁さんになれよ」だなんてカンチューハイ二本で言ってしまっていいの〉〈愛人でいいのとうたう歌手がいて言ってくれるじゃないのと思う〉〈「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日〉ここにはどんなドラマがくり広げられていたのだろう。ふだんのことばで歌が詠めることを教えてくれた。
(20)ハリソン・E・ソールズベリー『ヒーローの輝く瞬間(とき)』(柴田裕之訳)1995年、NHK出版

ソールズベリー(1908-93)は気骨のジャーナリストだった。その彼が自分の会った、自分にとってのヒーロー20人を選んで、その人となりをえがいたエッセイ。有名人もそうでない人もいる。だれもが知っている人としては、ロバート・ケネディやソルジェニーツィン、ハルバースタム、マルコムX、劉少奇、フルシチョフ、宋慶齢、サハロフ、エドガー・スノー、劉賓雁、周恩来などがでてくる。有名人、無名人を問わず、だれもが輝く一瞬をもっていた。
(21)グレイグ・ブロード『テクノストレス──コンピュータ革命が人間につきつける代償』(池央耿・高見浩訳)1984年、新潮社
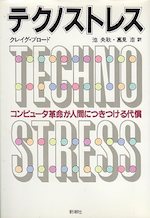
いまはコンピュータがなければ、世の中、にっちもさっちもいかなくなってしまった時代。しかし、コンピュータ文明によって「われわれ自身と次代の子どもたちは、肉体的、心理的、ならびに社会的に、果たしていかなる変化に見舞われたか」。この本が出されたころは、オフィスにパソコンが導入されたばかりで、ぼくなどもこれをマスターしなければ時代に取り残されるのではないかと恐怖をいだいたものだ。コンピュータは多くのことを可能にしたが、人間から奪い取ったものも大きい。一度、それをじっくりふり返ってみるのもいいのではないか。ちなみに、うちの11歳の孫も、すでにコンピュータ・ゲームのとりこになってしまっている。
(22)陳舜臣『北京の旅』1978年、平凡社
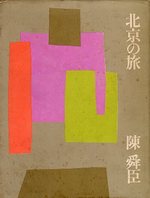
1970年代の北京は緑豊かな町だった。陳舜臣は「北京には人を酔わせる要素がいろいろありますが、緑のゆたかなこともその一つではないでしょうか」と書いている。緑の東直路では、ラバが車をひいてトコトコ歩いている牧歌的な情景が残っていたという。あのころの北京はいまどこにいってしまったのだろう。日中関係が良好だったあの時代がなつかしい。
(23)アリフィン・ベイ『インドネシアのこころ』(奥源造編訳)1975年、文遊社
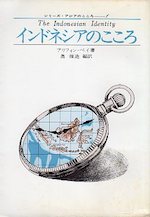
日本人は他国を経済的な観点からしか評価しないきらいがある。著者はいう。〈人々を文化、宗教、さらに非物質的な遺産としての歴史の所産であると認識するよう、日本人にすすめたい。異なった文化を理解し、「異なること」が必ずしも「悪いこと」ではないことをみいだすよう努力してほしいと訴えたい。〉日本をよく知るインドネシアのジャーナリストによるインドネシア紹介の書。あのころ、ぼくはアジアをもっと知りたいと思っていた。
(24)スーザン・ジョージ『なぜ世界の半分が飢えるのか──食糧危機の構造』(小南祐一郎・谷口真里子訳)1987年[初版は1984年]、朝日選書(朝日新聞社)

第三世界の飢餓は人口過剰や天候異変だけが原因ではない。「飢えは天災ではなく、一種の人災である」。世界の食糧を操り、食糧不足をつくりだしているのは、巨大な多国籍企業なのだ。途上国は従属から脱却すべきだと訴える。
眠る本たち その4 [眠る本たち]
これからも読めそうにないのだが、せめてリストだけでも。ひょっとしたら、そのうちまた読む気になることを祈って。
(11)岡並木『舗装と下水道の文化』1985年、論叢社
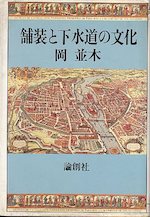
「舗装と下水道。文明の尺度といわれるその二つが、東京の砂漠化にひと役買っていないか」と著者は問う。パリやロンドンも取材、舗装と下水道の歴史から都市のありようを考える。
(12)山口文憲『香港 旅の雑学ノート』1979年、ダイヤモンド社
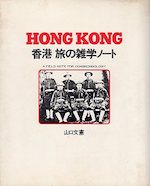
中国に返還される前の香港だ。著者は1年間、この街で暮らして、香港のすみずみを探索する。香港ではひとシーズンに100万匹近いヘビが食べられるというのは、いまもそうなのだろうか。ヘビのポタージュ「蛇羹」がお勧めだという。
(13)V・サンギ編『天を見てきたエヴェンク人の話──シベリアの伝説と神話』(匹田紀子訳)1992年、北海道新聞社
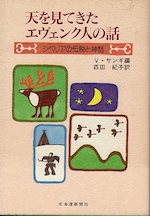
シベリアの北方民族の神話を紹介した貴重な本。シベリアにはいまもケレク人、エヴェンク人、ヌガナサン人、マンシ人、ケート人、ナナイ人など多くの北方民族が暮らしている。その神話はアイヌの神話とよく似ている。天地創造や火の話、クマ祭りの話などもおもしろそうだ。
(14)ヒルデ・シュピール『ウィーン 黄金の秋』(別宮貞徳訳)1993年、原書房
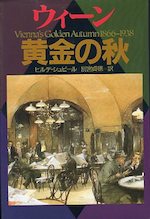
芸術、文学、音楽、哲学、心理学、経済学が猛烈な勢いで花開いた1900年前後のウィーン。この豊穣な時代を再現する。ヨハン・シュトラウス、マーラー、クリムト、ホフマンスタール、ヴィトゲンシュタイン、フロイト、アドラー、ユング、カール・メンガー、シュンペーター、カール・ポランニーなどが活躍したウィーンの輝きの正体はいったい何だったのだろう。
(15)船橋洋一『世界ブリーフィング──同時代の解き方』1995年、新潮社

1992年から95年にかけて『週刊朝日』に連載した世界情勢についてのエッセイを集めたもの。冷戦後の世界の動きを追っている。いまからふり返ると、あのころはこれから平和な時代がやってくると、つかの間の希望をいだいた時代だった。そのため、記事にもどことなく、ほんわかしたムードがただよう。〈私は、鄧小平のプックリした顔を写真で見るたびにクロワッサンを連想してしまう。鄧小平理論とはクロワッサン路線と命名すべきではないか、と思ってしまう。〉「北方領土問題は残り、南方領土問題は解決した」「真珠湾ではしゃぐ日本の女の子たち」といった記事もある。
(16)岩村忍『東洋史のおもしろさ』1976年、新潮選書

岩村忍(1905〜88)は東洋史学者で、内陸ユーラシア史や東西交渉史を専攻した。シルクロード・ブームの先駆者としても知られる。陳舜臣は「これまでおもに東アジアの歴史であった『東洋史』を岩村氏は西アジアに結びつけられた」と絶賛している。本書は歴史エッセイと紀行から成り立っている。遊牧民と農耕民のちがい、東南アジアと西南アジアの比較、モンゴル紀行、アフガニスタン調査旅行、それに茶とマルコ・ポーロ、ヘロドトスと司馬遷など、ちょっと読んでみたくなる本だ。シーア派の一派、イスマイリ暗殺教団はアサシンと呼ばれ、恐れられたが、かれらは大麻の一種ハッシッシを吸っていた。アサシンとハッシッシの語源は同じだという。
(17)エーヴ・キュリー『キュリー夫人伝』(川口篤、河盛好蔵、杉捷夫、本田喜代治訳)1988年、白水社

ラジウムの発見者としてノーベル物理学賞と化学賞を受賞したマリー・キュリー(1867〜1934)の伝記。戦前に訳されたものの改訂版だという。著者のエーヴ・キュリーはマリーの次女。マリーの長女イレーヌも物理学者で、母親と同じくノーベル化学賞を受賞している。〈彼女は女性であった。彼女は被圧迫国民[ポーランド人]のひとりであった。彼女は貧しかった。彼女は美しかった。〉読まれるべき伝記である。捨てられない。
(11)岡並木『舗装と下水道の文化』1985年、論叢社
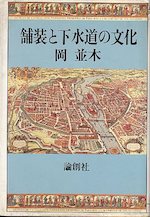
「舗装と下水道。文明の尺度といわれるその二つが、東京の砂漠化にひと役買っていないか」と著者は問う。パリやロンドンも取材、舗装と下水道の歴史から都市のありようを考える。
(12)山口文憲『香港 旅の雑学ノート』1979年、ダイヤモンド社
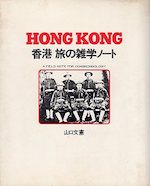
中国に返還される前の香港だ。著者は1年間、この街で暮らして、香港のすみずみを探索する。香港ではひとシーズンに100万匹近いヘビが食べられるというのは、いまもそうなのだろうか。ヘビのポタージュ「蛇羹」がお勧めだという。
(13)V・サンギ編『天を見てきたエヴェンク人の話──シベリアの伝説と神話』(匹田紀子訳)1992年、北海道新聞社
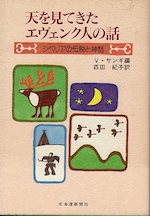
シベリアの北方民族の神話を紹介した貴重な本。シベリアにはいまもケレク人、エヴェンク人、ヌガナサン人、マンシ人、ケート人、ナナイ人など多くの北方民族が暮らしている。その神話はアイヌの神話とよく似ている。天地創造や火の話、クマ祭りの話などもおもしろそうだ。
(14)ヒルデ・シュピール『ウィーン 黄金の秋』(別宮貞徳訳)1993年、原書房
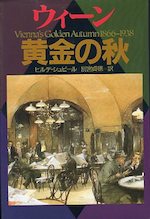
芸術、文学、音楽、哲学、心理学、経済学が猛烈な勢いで花開いた1900年前後のウィーン。この豊穣な時代を再現する。ヨハン・シュトラウス、マーラー、クリムト、ホフマンスタール、ヴィトゲンシュタイン、フロイト、アドラー、ユング、カール・メンガー、シュンペーター、カール・ポランニーなどが活躍したウィーンの輝きの正体はいったい何だったのだろう。
(15)船橋洋一『世界ブリーフィング──同時代の解き方』1995年、新潮社

1992年から95年にかけて『週刊朝日』に連載した世界情勢についてのエッセイを集めたもの。冷戦後の世界の動きを追っている。いまからふり返ると、あのころはこれから平和な時代がやってくると、つかの間の希望をいだいた時代だった。そのため、記事にもどことなく、ほんわかしたムードがただよう。〈私は、鄧小平のプックリした顔を写真で見るたびにクロワッサンを連想してしまう。鄧小平理論とはクロワッサン路線と命名すべきではないか、と思ってしまう。〉「北方領土問題は残り、南方領土問題は解決した」「真珠湾ではしゃぐ日本の女の子たち」といった記事もある。
(16)岩村忍『東洋史のおもしろさ』1976年、新潮選書

岩村忍(1905〜88)は東洋史学者で、内陸ユーラシア史や東西交渉史を専攻した。シルクロード・ブームの先駆者としても知られる。陳舜臣は「これまでおもに東アジアの歴史であった『東洋史』を岩村氏は西アジアに結びつけられた」と絶賛している。本書は歴史エッセイと紀行から成り立っている。遊牧民と農耕民のちがい、東南アジアと西南アジアの比較、モンゴル紀行、アフガニスタン調査旅行、それに茶とマルコ・ポーロ、ヘロドトスと司馬遷など、ちょっと読んでみたくなる本だ。シーア派の一派、イスマイリ暗殺教団はアサシンと呼ばれ、恐れられたが、かれらは大麻の一種ハッシッシを吸っていた。アサシンとハッシッシの語源は同じだという。
(17)エーヴ・キュリー『キュリー夫人伝』(川口篤、河盛好蔵、杉捷夫、本田喜代治訳)1988年、白水社

ラジウムの発見者としてノーベル物理学賞と化学賞を受賞したマリー・キュリー(1867〜1934)の伝記。戦前に訳されたものの改訂版だという。著者のエーヴ・キュリーはマリーの次女。マリーの長女イレーヌも物理学者で、母親と同じくノーベル化学賞を受賞している。〈彼女は女性であった。彼女は被圧迫国民[ポーランド人]のひとりであった。彼女は貧しかった。彼女は美しかった。〉読まれるべき伝記である。捨てられない。
眠る本たち その3 [眠る本たち]
本の整理がいっこうに進まない。片付けようとして、眺めているうちに、つい引き込まれてしまうのだ。それをがまんして、また眠る本たちコーナーへ。
(7)幅允孝(はば・よしたか)『本なんて読まなくたっていいのだけれど』2014年、晶文社

著者の仕事はブックディレクターだという。多くの本を手にとってもらうために、病院や老人ホーム、企業などでライブラリーをつくる仕事をしているとか。本が身近にある生活というのは、とてもいい。最近、ぼくなどは図書館に行くのも、だんだんおっくうになってきた。昔、ためこんだ本を整理して、眠る本たちのコーナーに積み上げるのが、年寄りの日課になっている。〈頭で理解するのではなく、体で感じること。その感触を記念写真のように飾っておくだけでなく、日々の生活に染み込ませること。良い音楽を聴くと、ご飯がおいしくなる。良い本を読むと、眠りが深くなる。なんていうのが結局のところ一番幸せな気がするのだけれど、皆さんはどうだろう?〉
(8)内田樹・鈴木邦男『慨世の遠吠え──強い国になりたい症候群』2015、鹿砦社

新左翼の内田と新右翼の鈴木は、ともに天皇主義者で、日本の将来を憂いている。天皇主義者といっても国家主義者ではない。独立自尊の個を尊ぶ。非戦ということでも共通している。鈴木は内田に合気道の稽古をつけてもらい、映画『仁義なき戦い』をともに鑑賞する。そんなふうに交流しながら、1年にわたって何度か対談してできあがったのがこの本だ。ふたりとも日本がますますアメリカ寄りになり、アメリカに追従するようになっていることに懸念をいだいている。ふたりとも猛烈な読書家だが、とりわけ鈴木の読書量にはおどろく。ぼくには平岡正明や竹中労、三島由紀夫、吉本隆明についての話が懐かしかった。
(9)柄本明『東京の俳優』(聞き書き小田豊二)2008年、集英社
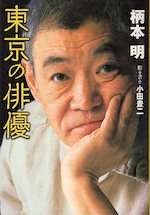
柄本明は何となく田舎の出身だというイメージを持たれがちだが、れっきとした東京出身。それも昭和23年(1948)、銀座の木挽町生まれだという。都立王子工業高校を出て、精密機械の商社に就職したが、社長の新年のあいさつを聞いているうちに、いやになって、じきに会社を辞めてしまったという。21歳のことだ。そのころ柄本は早稲田小劇場と出会い、アングラ演劇に傾倒するようになった。残念なことに、ぼくはあのころ演劇とは縁がなかった。いまでは取り返しがつかない。柄本はその後、東京乾電池という劇団をつくり、ベンガルや高田純次らとともに大活躍した。ぼくが知っているのは、映画やテレビの脇役としての柄本明でしかない。でも、とても存在感のあるいい役者だと思う。最近、その芸にはますます磨きがかかっている。これも演劇人として長く歩んだ成果といえるだろう。
(10)マイク・ダッシュ『難破船バタヴィア号の惨劇』(鈴木主税訳)2003年、アスペクト[原著は2002年]
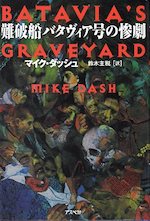
これもいただいた本だ。申し訳ないことに読んでいない。映画化されたというが、日本でも公開されたのだろうか。訳者あとがきによると、バタヴィア号はオランダ東インド会社の貿易船で、1628年にジャワ島に向け、処女航海に出たが、途中で難破し西オーストラリアの珊瑚礁に乗り上げたという。船長が救助を求めるため、補助艇でジャワ島に向かっているあいだに、珊瑚礁ではイエロニムス・コルネリスという男が権力を握り、100名以上を惨殺する事件を起こしていた。イエロニムスは異端思想の持ち主で、サイコパスだったという。極限状況に置かれた人間がどれほど残酷になれるのか。事件を忠実に再現した恐ろしい実話だ。
(7)幅允孝(はば・よしたか)『本なんて読まなくたっていいのだけれど』2014年、晶文社

著者の仕事はブックディレクターだという。多くの本を手にとってもらうために、病院や老人ホーム、企業などでライブラリーをつくる仕事をしているとか。本が身近にある生活というのは、とてもいい。最近、ぼくなどは図書館に行くのも、だんだんおっくうになってきた。昔、ためこんだ本を整理して、眠る本たちのコーナーに積み上げるのが、年寄りの日課になっている。〈頭で理解するのではなく、体で感じること。その感触を記念写真のように飾っておくだけでなく、日々の生活に染み込ませること。良い音楽を聴くと、ご飯がおいしくなる。良い本を読むと、眠りが深くなる。なんていうのが結局のところ一番幸せな気がするのだけれど、皆さんはどうだろう?〉
(8)内田樹・鈴木邦男『慨世の遠吠え──強い国になりたい症候群』2015、鹿砦社

新左翼の内田と新右翼の鈴木は、ともに天皇主義者で、日本の将来を憂いている。天皇主義者といっても国家主義者ではない。独立自尊の個を尊ぶ。非戦ということでも共通している。鈴木は内田に合気道の稽古をつけてもらい、映画『仁義なき戦い』をともに鑑賞する。そんなふうに交流しながら、1年にわたって何度か対談してできあがったのがこの本だ。ふたりとも日本がますますアメリカ寄りになり、アメリカに追従するようになっていることに懸念をいだいている。ふたりとも猛烈な読書家だが、とりわけ鈴木の読書量にはおどろく。ぼくには平岡正明や竹中労、三島由紀夫、吉本隆明についての話が懐かしかった。
(9)柄本明『東京の俳優』(聞き書き小田豊二)2008年、集英社
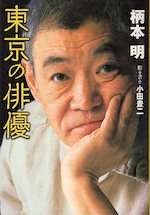
柄本明は何となく田舎の出身だというイメージを持たれがちだが、れっきとした東京出身。それも昭和23年(1948)、銀座の木挽町生まれだという。都立王子工業高校を出て、精密機械の商社に就職したが、社長の新年のあいさつを聞いているうちに、いやになって、じきに会社を辞めてしまったという。21歳のことだ。そのころ柄本は早稲田小劇場と出会い、アングラ演劇に傾倒するようになった。残念なことに、ぼくはあのころ演劇とは縁がなかった。いまでは取り返しがつかない。柄本はその後、東京乾電池という劇団をつくり、ベンガルや高田純次らとともに大活躍した。ぼくが知っているのは、映画やテレビの脇役としての柄本明でしかない。でも、とても存在感のあるいい役者だと思う。最近、その芸にはますます磨きがかかっている。これも演劇人として長く歩んだ成果といえるだろう。
(10)マイク・ダッシュ『難破船バタヴィア号の惨劇』(鈴木主税訳)2003年、アスペクト[原著は2002年]
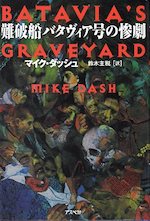
これもいただいた本だ。申し訳ないことに読んでいない。映画化されたというが、日本でも公開されたのだろうか。訳者あとがきによると、バタヴィア号はオランダ東インド会社の貿易船で、1628年にジャワ島に向け、処女航海に出たが、途中で難破し西オーストラリアの珊瑚礁に乗り上げたという。船長が救助を求めるため、補助艇でジャワ島に向かっているあいだに、珊瑚礁ではイエロニムス・コルネリスという男が権力を握り、100名以上を惨殺する事件を起こしていた。イエロニムスは異端思想の持ち主で、サイコパスだったという。極限状況に置かれた人間がどれほど残酷になれるのか。事件を忠実に再現した恐ろしい実話だ。
眠る本たち その2 [眠る本たち]
捨てるに捨てられない眠る本たち つづき
(4)松本重治編集世話人『松方三郎』1974年、共同通信社

松方三郎(1899-1973)の追悼集。松方は松方正義の13男として生まれた。乃木希典、鈴木大拙、河上肇をわが師と呼んでいる。学習院時代から山に登りはじめ、京都大学を卒業後、日本とスイス・イタリアのアルプスを踏破する。れっきとしたマルクス青年だった。東亜経済調査局、太平洋問題調査局に勤務。その後、新聞連合社、同盟通信社に勤める。1942年満州国通信社理事長。1945年、共同通信社常任理事。1946年、日本山岳会会長。1949年共同通信社専務理事(1960年まで)。等々。1970年には日本山岳会のエヴェレスト登山隊長を務めた。山の松方として知られるが、メディアの指導者でもあり、読書人でもあった。食い道楽だったと松本重治は語っている。あたたかいご飯にウニやイクラとバターをのせ、それをこね回して、ネコご飯のようにして食べるのが好きだったという。ほかに好きなのがたい焼きとおはぎ。甘い物好きは、松方家の伝統だったらしい。
(5)渡辺和博とたらこプロダクション『金魂巻(きんこんかん)——現代人気職業31の金持ビンボー人の表層と力と構造』1984年、主婦の友社。
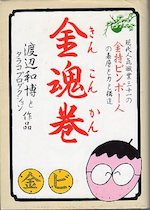
マル金(金持ち)、マルビ(貧乏人)の分類は当時、評判になった。ここでイラストつきで取り上げられている職業(?)は、女性アナウンサー、医者、イラストレーター、インテリア・デザイナー、エディター、オートバイ・レーサー、オフィスレディ、お父さん、学者の卵、カメラマン、看護婦、銀行員、グラフィック・デザイナー、コピーライター、シェフ、社長の娘、主婦、商社マン、少女マンガ家、女子大生、スタイリスト、プロデューサー、不良少女、弁護士、放送作家、ホステス、ホモ、ミュージシャン、モデルと多種多様。この時代、新種の職業が生まれていた。しかし、同じ職業でもマル金、マルビでは大違い。たとえば、マル金のお父さんは世田谷で生まれ、大学をでると、すぐに父親の会社の取締役になり、ベンツに乗って、夏休みは軽井沢の別荘ですごし、子どもをロスのディズニーランド(まだ浦安のディズニーランドはできていなかった)につれていき、よくホテルオークラの「桃花林」で食事をする。これにたいしマルビのお父さんは瀬戸内海の大島で生まれ、一生懸命勉強して、東京の大学に進学し、下落合で下宿し、卒業すると缶詰工場に就職し、しばらくたって結婚すると、アパートでくらし、子どもが生まれると、千葉の八千代台に建て売り住宅を買い、子どもの誕生日にはみんなでデニーズに行く。こんな調子で、マル金、マルビの比較が延々とつづく。やっぱり、この世の中には金持ちと貧乏人がいることを痛感する。そして、最近は勝ち組、負け組の分類も。世の中、基本的にまちがっている。
(6)藤田紘一郎『笑うカイチュウーー寄生虫博士奮闘記』1994年、講談社
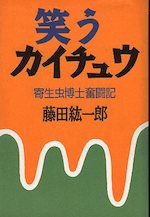
「寄生虫の卵を見たとき、僕はほんとうに安らかな気持ちになる。……まして、苦労して10メートルものながいサナダ虫を頭から尾まですっぽり完全な形で患者さんから駆虫したときなど、最高の幸福感を味わう。」これは寄生虫大好きの医学博士による痛快エッセイ。昔、人はカイチュウと仲良く共存していた。いまでも世界人口の半分が寄生虫病に悩まされているが、人間と寄生虫の長い共生関係の歴史には、深い意味が隠されているという。いま日本ではかつて70パーセントあったカイチュウ感染率が、わずか20数年のうちに0.2パーセントに激減してしまった。その結果、アトピー性皮膚炎や花粉症が増えたという説にはちょっと驚いた。その説明は本書をご覧ください。
(4)松本重治編集世話人『松方三郎』1974年、共同通信社

松方三郎(1899-1973)の追悼集。松方は松方正義の13男として生まれた。乃木希典、鈴木大拙、河上肇をわが師と呼んでいる。学習院時代から山に登りはじめ、京都大学を卒業後、日本とスイス・イタリアのアルプスを踏破する。れっきとしたマルクス青年だった。東亜経済調査局、太平洋問題調査局に勤務。その後、新聞連合社、同盟通信社に勤める。1942年満州国通信社理事長。1945年、共同通信社常任理事。1946年、日本山岳会会長。1949年共同通信社専務理事(1960年まで)。等々。1970年には日本山岳会のエヴェレスト登山隊長を務めた。山の松方として知られるが、メディアの指導者でもあり、読書人でもあった。食い道楽だったと松本重治は語っている。あたたかいご飯にウニやイクラとバターをのせ、それをこね回して、ネコご飯のようにして食べるのが好きだったという。ほかに好きなのがたい焼きとおはぎ。甘い物好きは、松方家の伝統だったらしい。
(5)渡辺和博とたらこプロダクション『金魂巻(きんこんかん)——現代人気職業31の金持ビンボー人の表層と力と構造』1984年、主婦の友社。
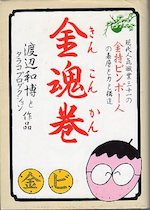
マル金(金持ち)、マルビ(貧乏人)の分類は当時、評判になった。ここでイラストつきで取り上げられている職業(?)は、女性アナウンサー、医者、イラストレーター、インテリア・デザイナー、エディター、オートバイ・レーサー、オフィスレディ、お父さん、学者の卵、カメラマン、看護婦、銀行員、グラフィック・デザイナー、コピーライター、シェフ、社長の娘、主婦、商社マン、少女マンガ家、女子大生、スタイリスト、プロデューサー、不良少女、弁護士、放送作家、ホステス、ホモ、ミュージシャン、モデルと多種多様。この時代、新種の職業が生まれていた。しかし、同じ職業でもマル金、マルビでは大違い。たとえば、マル金のお父さんは世田谷で生まれ、大学をでると、すぐに父親の会社の取締役になり、ベンツに乗って、夏休みは軽井沢の別荘ですごし、子どもをロスのディズニーランド(まだ浦安のディズニーランドはできていなかった)につれていき、よくホテルオークラの「桃花林」で食事をする。これにたいしマルビのお父さんは瀬戸内海の大島で生まれ、一生懸命勉強して、東京の大学に進学し、下落合で下宿し、卒業すると缶詰工場に就職し、しばらくたって結婚すると、アパートでくらし、子どもが生まれると、千葉の八千代台に建て売り住宅を買い、子どもの誕生日にはみんなでデニーズに行く。こんな調子で、マル金、マルビの比較が延々とつづく。やっぱり、この世の中には金持ちと貧乏人がいることを痛感する。そして、最近は勝ち組、負け組の分類も。世の中、基本的にまちがっている。
(6)藤田紘一郎『笑うカイチュウーー寄生虫博士奮闘記』1994年、講談社
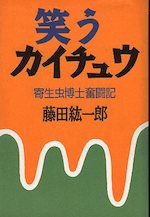
「寄生虫の卵を見たとき、僕はほんとうに安らかな気持ちになる。……まして、苦労して10メートルものながいサナダ虫を頭から尾まですっぽり完全な形で患者さんから駆虫したときなど、最高の幸福感を味わう。」これは寄生虫大好きの医学博士による痛快エッセイ。昔、人はカイチュウと仲良く共存していた。いまでも世界人口の半分が寄生虫病に悩まされているが、人間と寄生虫の長い共生関係の歴史には、深い意味が隠されているという。いま日本ではかつて70パーセントあったカイチュウ感染率が、わずか20数年のうちに0.2パーセントに激減してしまった。その結果、アトピー性皮膚炎や花粉症が増えたという説にはちょっと驚いた。その説明は本書をご覧ください。
眠る本たち [眠る本たち]
5000冊近くある本(文庫や新書が多い)の整理をはじめた。
悲しいことにおそらくその3分の2は読んでいない。
そのうち読もうと思って買った本、人からもらった本、仕事のために買った本、たまたま見かけて手に入れた古本、さまざまな本がある。
このあいだウェブ論座の書評欄「神保町の匠」をみていたら、高橋伸児さんが紀田順一郎の『蔵書一代』という本を紹介していた。
稀代の大蔵書家といわれる紀田さんは、80歳にして3万冊の本を泣く泣く古書店に売ってしまったそうだ。
紀田さんの場合は、2日間延べ8人のアルバイトを動員して、12畳の書斎、10畳半の書庫から、3万冊の本を運びだし、4トントラック2台が遠ざかるのを眺めたのだという。80歳にして、人生、最大の痛恨に遭おうとは、と紀田さんが書いている。
ぼくは紀田さんほど値打ちのある本をもっているわけではない。
けっきょく読めないのに、やたら買いこんだ結末が、大量のツンドク本になってしまったのだ。これも消費能力を超えた、大量消費時代の産物である。
ブックオフはもちろん、古本屋ももっていってくれない本が多い。おそらく図書館も引き取ってくらないだろう。
しかし、いずれは処分しなければならない。
思い切って捨てるつもりで、整理をはじめたという次第。
いまのところ捨てたのは300冊ほど。
ところが、ここで作業が中断してしまった。捨てるのがしのびなくなってしまったのだ。
自分のいのちを考えると、あとは読めてもせいぜい10年というところだろう。
それなのに本が捨てられない。
けっきょく、元の木阿弥。捨てるつもりでいた本は、読まないまま、また本棚の上の空きスペースに積み上げることになりそうだ。
眠る本たちである。
たぶんもう読まないにせよ(あるいはとつぜん気力が湧いて読むかもしれないが)、せめて眺めるだけでもと思い、手当たり次第リストをつくってみることにした。
(1)羅漢中『三国志』(小川環樹・武部利男訳)岩波少年文庫、全3巻、新書判、約1000ページ。1984年(初版は1980年)岩波書店
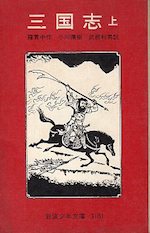
少年文庫だが、大人でも読める。英雄豪傑の勇壮な物語であり、政治の教科書にもなりうる。2世紀から3世紀にかけ、中国は3つの国にわかれて争っていた。三国志は蜀の劉備玄徳を中心とする物語。魏の曹操は憎たらしい悪人として描かれている。10冊の文庫本を半分強に縮めたものだが、原文に忠実な訳だという。三国志はこの少年文庫を読むのがいちばんだろう。名シーンのかずかず、関羽、張飛の活躍。諸葛孔明の知謀。わくわくする。これはたぶん娘のために買った本だ。
(2)チャールズ・ラム、メアリー・ラム『シェイクスピア物語』(野上弥生子訳)、岩波少年文庫、新書判約270ページ。1986年(初版は1956年、原本は1807年)岩波書店
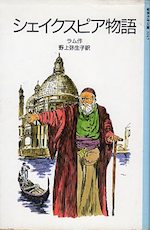
イギリスの随筆家、チャールズ・ラムとその姉によるシェイクスピア劇のダイジェスト。全20篇。劇ではなく物語になっている。そのうち翻訳では13篇がセレクトされている。リア王、マクベス、オセロ、ハムレット、ロメオとジュリエットなどの悲劇をはじめとして、ヴェニスの商人、あらし、からさわぎ、お好きなようになどの喜劇が収められている。シェイクスピアの喜劇はよく知らなかったが、ぱらぱらと読むと、けっこうハッピーな気分になる。これも娘のために買った本だが、どうも読んだ形跡がない。
(3)紀田順一郎『コラムの饗宴』四六判約350ページ。1980年、実業之日本社
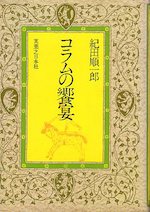
最近、気のきいたコラムが少なくなった。この本は大蔵書家(だった)著者が約10年にわたって、いろいろな雑誌に書いたコラムを集めたもの。ばかばかしくも、じつに面白い。引用しているときりがないが、たとえば、こんなふう。
〈永井荷風(1879-1959)は晩年、月に一度ぐらい性欲のハケ場を求めた。ある人が「先生アレの方は、まだお用いになっているんですか」ときくと、「アレは時々やらないと、あとがきかなくなるんでね」と答えた。〉
〈田山花袋(1871-1930)が死ぬとき、かけつけた島崎藤村(1872-1943)はその耳もとに口をやって熱心に聞いた。「死ぬときの気持はどうだ?」〉
悲しいことにおそらくその3分の2は読んでいない。
そのうち読もうと思って買った本、人からもらった本、仕事のために買った本、たまたま見かけて手に入れた古本、さまざまな本がある。
このあいだウェブ論座の書評欄「神保町の匠」をみていたら、高橋伸児さんが紀田順一郎の『蔵書一代』という本を紹介していた。
稀代の大蔵書家といわれる紀田さんは、80歳にして3万冊の本を泣く泣く古書店に売ってしまったそうだ。
紀田さんの場合は、2日間延べ8人のアルバイトを動員して、12畳の書斎、10畳半の書庫から、3万冊の本を運びだし、4トントラック2台が遠ざかるのを眺めたのだという。80歳にして、人生、最大の痛恨に遭おうとは、と紀田さんが書いている。
ぼくは紀田さんほど値打ちのある本をもっているわけではない。
けっきょく読めないのに、やたら買いこんだ結末が、大量のツンドク本になってしまったのだ。これも消費能力を超えた、大量消費時代の産物である。
ブックオフはもちろん、古本屋ももっていってくれない本が多い。おそらく図書館も引き取ってくらないだろう。
しかし、いずれは処分しなければならない。
思い切って捨てるつもりで、整理をはじめたという次第。
いまのところ捨てたのは300冊ほど。
ところが、ここで作業が中断してしまった。捨てるのがしのびなくなってしまったのだ。
自分のいのちを考えると、あとは読めてもせいぜい10年というところだろう。
それなのに本が捨てられない。
けっきょく、元の木阿弥。捨てるつもりでいた本は、読まないまま、また本棚の上の空きスペースに積み上げることになりそうだ。
眠る本たちである。
たぶんもう読まないにせよ(あるいはとつぜん気力が湧いて読むかもしれないが)、せめて眺めるだけでもと思い、手当たり次第リストをつくってみることにした。
(1)羅漢中『三国志』(小川環樹・武部利男訳)岩波少年文庫、全3巻、新書判、約1000ページ。1984年(初版は1980年)岩波書店
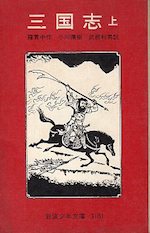
少年文庫だが、大人でも読める。英雄豪傑の勇壮な物語であり、政治の教科書にもなりうる。2世紀から3世紀にかけ、中国は3つの国にわかれて争っていた。三国志は蜀の劉備玄徳を中心とする物語。魏の曹操は憎たらしい悪人として描かれている。10冊の文庫本を半分強に縮めたものだが、原文に忠実な訳だという。三国志はこの少年文庫を読むのがいちばんだろう。名シーンのかずかず、関羽、張飛の活躍。諸葛孔明の知謀。わくわくする。これはたぶん娘のために買った本だ。
(2)チャールズ・ラム、メアリー・ラム『シェイクスピア物語』(野上弥生子訳)、岩波少年文庫、新書判約270ページ。1986年(初版は1956年、原本は1807年)岩波書店
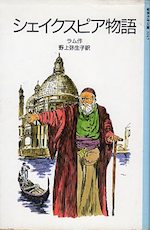
イギリスの随筆家、チャールズ・ラムとその姉によるシェイクスピア劇のダイジェスト。全20篇。劇ではなく物語になっている。そのうち翻訳では13篇がセレクトされている。リア王、マクベス、オセロ、ハムレット、ロメオとジュリエットなどの悲劇をはじめとして、ヴェニスの商人、あらし、からさわぎ、お好きなようになどの喜劇が収められている。シェイクスピアの喜劇はよく知らなかったが、ぱらぱらと読むと、けっこうハッピーな気分になる。これも娘のために買った本だが、どうも読んだ形跡がない。
(3)紀田順一郎『コラムの饗宴』四六判約350ページ。1980年、実業之日本社
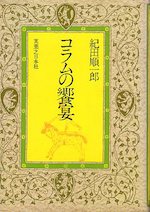
最近、気のきいたコラムが少なくなった。この本は大蔵書家(だった)著者が約10年にわたって、いろいろな雑誌に書いたコラムを集めたもの。ばかばかしくも、じつに面白い。引用しているときりがないが、たとえば、こんなふう。
〈永井荷風(1879-1959)は晩年、月に一度ぐらい性欲のハケ場を求めた。ある人が「先生アレの方は、まだお用いになっているんですか」ときくと、「アレは時々やらないと、あとがきかなくなるんでね」と答えた。〉
〈田山花袋(1871-1930)が死ぬとき、かけつけた島崎藤村(1872-1943)はその耳もとに口をやって熱心に聞いた。「死ぬときの気持はどうだ?」〉



