『三島由紀夫VS東大全共闘』をDVDで見る(2) [われらの時代]

三島との討論がはじまると、全共闘側の司会、木村修はまず、なぜ三島が小説を書くだけでなく、自分の肉体を週刊誌などにさらすのもいとわないのかと聞いている。これにたいし三島は、文学者というものは「自分があたかも精神によって世界を包摂し、支配したような錯覚に陥っている」が、「私は何とかしてその肉体を拡張してみようと思った」と話している。そして、肉体が拡張していくと、非常に保守的になったという。
いっぽう木村の質問は判然としないけれど、人が暴力をふるう場合に他者という問題をどう考えるかを三島に聞いているようにみえる。自殺する場合は別だ。相手を殺すことも簡単かもしれない。その反対に自分が殴られることもある。しかし、何はともあれ、暴力は他者にとってどのように顕現するのかと聞いている(と思われる)。
三島は大嫌いなサルトルが『存在と無』のなかで、いちばん猥褻なものは縛られた女の肉体だと書いていることを紹介し、暴力とエロティシズムには強い関係があることを示している。相手を縛るというのが、人間が他者にたいしてもっている根源的な感覚だ。
しかし、いったん相手が縛られてしまうと、そこには暴力は発生しにくい。三島はいう。
〈たとえば佐藤首相が縛られた状態でここにいるとすると──別にまあエロティックじゃないけれども、(爆笑)──少なくともそれに暴力を行使するということはおもしろくないというのが、諸君の中に持っている状況だろうと思う。佐藤内閣というものが諸君に対して攻撃的であると諸君は理解する。そしてその攻撃意思を相手の主体的意思とすでに認める。この認めるところに、諸君が他者というものを非エロティック的に、そして主体的に把握する関係が生じるのじゃないかと思います。〉
佐藤栄作をたとえに出すユーモア感覚がおもしろい。三島は人間のなかにある本源的な暴力性を否定していない。そして、攻撃的な意思をもつ他者にたいして、暴力をもって対応することは認められるべきだという。
その暴力は、諫争や諫死の域にまで拡張される。三島が楯の会の会員とともに市ヶ谷の自衛隊駐屯地におもむき、バルコニーで自衛隊員に憲法改正のために蹶起するよう呼びかけ、総監室で自決するのは、東大全共闘との討論会から1年半後のことだ。
三島を「近代ゴリラ」と揶揄する全共闘を前に、三島はすでに東大での討論会で、こう語っていた。
〈私は一人の民間人であります。私が行動を起す時は、結局諸君と同じ非合法でやるほかないのだ。非合法で、決闘の思想において人をやれば、それは殺人犯だから、そうなったら自分もおまわりさんにつかまらないうちに自決でも何でもして死にたいと思うのです。しかしそういう時期がいつくるかはわからないが、そういう時期に合わして身体を鍛錬して、「近代ゴリラ」としてりっぱなゴリラになりたい。(笑)〉
討論会はすっかり三島ペースになっている。全共闘側は反論しないのか。暴力ではなく、自然や生活が重要なのではないかと言い出す学生もいるが、支離滅裂で議論は盛り上がらない。
三島は、そこで全共闘側を焚きつけるかのように、こう話す。
21世紀になると、「われわれは管理あるいは技術管理だけに生きる時代がきてしまって直接的な生産関係というものから切り離されてしまう」。すると、自然は二次的、三次的、四次的なものになって、自然に到達することがほとんど不可能になってくる。しかし、そのへんの敷石も武器になるし、この机もバリケードになる。生産用途からはずれて、敷石や机が戦闘目的に使われることによって、諸君ははじめて物に目ざめ、自然に到達するのではないか。その動きが諸君のやっている暴力の本源的衝動なのではないか、と。
ここで赤ん坊を抱いて壇上に立っている、ぼさぼさ頭の無精ヒゲの男が話しはじめる。芥正彦である。
芥は三島文学をもう終わったもの、敗退したものととらえている。芥が求めるのは歴史の可能性としての空間である。それが、たとえば解放区だ。
三島は芥にその空間は時間的にどう持続するかを問う。芥は持続性は二義的な問題であり、重要なのは遊戯としての空間の創出だと答えたうえで、三島の楯の会は本質的な意味での自由な遊びではなく、大向こうを狙ったゲームにすぎないのではないかとからかう。しかも、そのゲームは日本というデマゴギーの上に成り立っているという。
芥は三島のように「日本がなければ存在しない人間」ではなく、自分は「異邦人」だと宣言する。
三島が「おれの作品は何万年という時間の持続との間にある一つの持続なんだ」と歴史の持続性を強調するのにたいし、芥は持続性にこだわらない「可能性そのものの空間」としての解放区の創出こそが革命の発出なのだと主張する。それは失敗するかもしれないが、そこでは人間のありありした原初のかたちが生まれてくるはずだ。
芥は持論を長々と展開し、三島もこれに応じる。目的論のない純粋空間は存在しないのではないか、と三島が聞く。だが、芥が話すことをを、ほとんどだれも理解できない。「観念的こじつけじゃないか」とヤジが飛び、会場は騒然となる。論議は中断され、混沌たるやりとりがつづく。
そこで、三島は「少し問題を変えたらどうですか」と提案する。全共闘の小阪修平が天皇の問題を論じようと切り返し、三島が自衛隊に一日入隊なんかして右翼のまねごとをするのはみっともないと話す。
*
天皇の問題を論じようという小阪の提案を受けて、三島は全共闘シンパを前に、みずからの天皇論を語りはじめる。
〈これはだ、これはまじめに言うんだけれども、たとえば安田講堂で全学連の諸君がたてこもった時に、天皇という言葉を一言彼等が言えば、私は喜んで一緒にとじこもったであろうし、喜んで一緒にやったと思う。(笑)これは私はふざけて言っているんじゃない。常々言っていることである。なぜなら、終戦前の昭和初年における天皇親政というものと、現在言われている直接民主主義というものにはほとんど政治概念上の区別がないのです。これは非常に空疎な政治概念だが、その中には一つの共通要素がある。その共通要素は何かというと、国民の意思が中間的な権力構造の媒介物を経ないで国家意思と直結することを夢見ている。〉
三島は全共闘に、天皇について考えてほしいと呼びかけている。全共闘が直接民主主義をいうのならば、日本では天皇親政の理念こそがまさにそれではないかという。
これにたいし、全共闘側の反応はしらけたものだ。かれらにとって、これまで天皇とは入学式や卒業式のときに儀礼的にあいさつする校長先生のような存在でしかなかった。もっと政治主義的にいえば、ブルジョア的秩序を補完する装置にほかならなかった。
しかし、三島の思いがけぬ呼びかけに全共闘側はどう応えていいかとまどい、議論はまたもや観念的な方向にスライドする。
三島が日本人のメンタリティのなかには、延々とした日本文化の時間が引き継がれていると話したのに反論して、全共闘のひとりは、三島がこだわっているのは過去の時間であって、問題は現在の疎外された時間を未来に向けて超越することなんだと話す。三島のなかに流れている過去の時間と、われわれの時間は切断されているというわけだ。
不毛な議論がつづくが、それでも三島はそれに耐え、学生たちとの議論をつづけている。あなたの議論では、現在は目的論的に(いわば革命という目的に向けて)設定されているようにみえるが、小説家としての私は、その多くを過去に共同体のなかで受け継がれてきた言葉に負っており、それを未来に向けて無定型のゼリーのように押し出していく仕事をしている。だから、あなたのように未来を(共産主義のような)固い物象とは考えない。
三島は思わずこう話している。
〈それはぼくは未来から自分の行動の選択性の根拠を持ってこないで、過去から持ってくるという精神構造を持っちゃってるわけだ。それが誤りであるか正しいかわからんが、そういうふうに持っちゃってるわけだ。〉
未来に向けて行動するという面では、三島ははからずも全共闘と同じであることを告白してしまっている。いまは認識よりも行動のときだ。ただ、三島にとっての行動は、幻想の過去を復活させること、消え去ろうとしている日本文化、とりわけその中心である天皇のイメージを復活させることに向けられている。全共闘側にとって、それは疎外された未来でしかない。
全共闘 記憶や時代は抹消されてるでしょう。抹消されるわけじゃないですか?
三 島 それが抹消されないのだね。おれには。
全共闘 時代は抹消されていますよ。
三 島 時代は抹消されても、その時代の中にある原質みたいなものは抹消されないのだよ。君らたとえば戦後の時代というものを二十年間ね……。
三島は戦後世代との大きなギャップを感じたにちがいない。それでも、何とか若者たちを説得しようと努めた。
全共闘のひとりは、美は観念のなかでしか完結せず、それを現実のなかにもってこようとすると、たちまち腐蝕がはじまり、自衛隊一日入隊とか楯の会のようなみっともない行動になる、と三島の行動主義を批判した。
これにたいし、三島ははっきりとこう答えている。
〈それはよくわかった。しかし、私にとっては、関係性というものと、自己超越性──超時間性といいましたかな、そういうものと初めから私の中で癒着している。これを切り離すことはできない。初めから癒着しているところで芸術作品ができているから、別の癒着の形として行動も出てくる。〉
全共闘が思想と行動の一致を求めてバリケードをつくるのと同じように、私も知行合一をめざして超時間性のなかで行動する、と三島は宣言している。
そして、ここから三島はみずからの天皇論を語りはじめる。
最初に持ちだすのは『古事記』のヤマトタケルの話だ。三島にとっての天皇の原型は、儒教に縛られた統治的天皇ではなく、いわばヤマトタケルのような神のごとき存在だという。
すると全共闘側はさっそく反発して、そんな神のような存在に自分を一体化させるのは一種のオナニズムであり、そんなことでは日本人という限界を越えられないと批判する。ここにも世代間のすれ違いが発生している。
三 島 できなくていいのだよ。ぼくは日本人であって、日本人として生れ、日本人として死んで、それでいいのだ。その限界を全然ぼくは抜けたいと思わない。ぼく自身。だからあなたから見ればかわいそうだと思うだろうが。
全共闘 それは思いますね。ぼくなんか。
三 島 しかしやっぱりぼくは日本人である以上日本人以外のものでありたいと思わないのだな。
ここで話している全共闘のひとりは芥正彦だ。芥は自分には「最初から国籍はない」と宣言している。三島は「自由人としてぼくはあなたを尊敬するよ」といいながら、ぼくは日本人であることを抜けられない、これはぼくの宿命だと語っている。
全共闘側は三島の神性をもつ英雄としての天皇像を批判する。それは現実の天皇とはかけ離れたものではないかとも指摘する。
三島はこれにたいし、「私の言う天皇というものは人間天皇と、つまり統治的天皇と、文化的なそういう詩的、神話的天皇とが一つの人間でダブルイメージを持っている」存在であって、「天皇一人一人のパーソナリティとは関係がない」と説明する。
全共闘側はとうぜん納得しない。天皇になんか興味はないとさえ断言する者もいれば、現実の天皇は、あの醜いじじいだと口汚くののしる者もいた。
しかし、ここで三島はとつぜん学習院を首席で卒業したときの、こんな思い出を話しはじめる。
〈こんなことを言うと、あげ足をとられるから言いたくはないのだけれども、ひとつ個人的な感想を聞いてください。というのはだね、ぼくらは戦争中に生れた人間でね、こういうところに陛下が坐っておられて、三時間、木像のごとく全然微動もしない、卒業式で。そういう天皇から私は時計をもらった。そういう個人的な恩顧があるんだな。こんなことを言いたくないよ、おれは。(笑)言いたくないけれどね、人間の個人的な歴史の中でそんなことがあるんだ。そしてそれがどうしてもおれの中で否定できないのだ。それはとてもご立派だった、その時の天皇は。〉
会場が一瞬静まりかえった。
だが、そのあとまた三島批判がつづく。
全共闘のなかにはなぜ三島が安田講堂でわれわれと一緒に閉じこもらなかったのかと聞く者もいる。三島はこれにたいし、諸君が天皇と一言言ってくれれば、私は喜んで諸君と手をつなぐとやり返す。
それでも全共闘側は、問題は国家の廃絶としての革命であり、天皇という観念ではないという。三島はこれにたいし、君らこそ革命という絶対的なものに天皇という名前を与えたらいいではないかという。全共闘側が天皇はブルジョア秩序の補完物にすぎないと言い返したところで、討論会は時間切れとなった。
最後に感想を求められた三島は、こう話している。
〈今天皇ということを口にしただけで共闘すると言った。これは言霊というものの働きだと思うのですね。それでなければ、天皇ということを口にすることも穢らわしかったような人が、この二時間半のシンポジウムの間に、あれだけ大勢の人間がたとえ悪口にしろ、天皇なんて口から言ったはずがない。言葉は言葉を呼んで、翼をもってこの部屋の中を飛び回ったんです。この言霊がどっかにどんなふうに残るか知りませんが、私がその言葉を、言霊をとにかくここに残して私は去っていきます。そして私は諸君の熱情は信じます。これだけは信じます。ほかのものは一切信じないとしても、これだけは信じるということはわかっていただきたい。〉
最後に全共闘から「それで共闘するんですか? しないんですか」と聞かれた三島は「今のは一つの詭弁的な誘いでありまして、非常に誘惑的になったけれども、私は拒否いたします」と答える。
こうして笑いと拍手のうちに討論会は幕を閉じた。
三島は全共闘を説得できなかった。しかし、これまで意識したこともない天皇という言霊は、革命を唱える全共闘側にもたしかに忍びこんだのだ。そして、それは三島にも反作用のようにはたらいていくことになる。
『三島由紀夫VS東大全共闘』をDVDで見る(1) [われらの時代]

全共闘は身体の叛乱であると同時にことばの氾濫でもあった。猛烈な勢いであふれる、そのことばは容易に理解しがたく、気がつけばいつのまにか、それに流され、おぼれてしまっている。そんなことばの氾濫を前に、三島由紀夫はおくせず立ち向かった。1969年5月13日、東京・駒場の東大教養学部900番教室(講堂)で開かれた討論会でのことである。
この催しを企画したのは東大全共闘駒場共闘焚祭委員会と称する団体だった。団体といっても昔からあった団体ではない。三島との討論会を企画するために急遽つくられた。東大全共闘という名称も、だれでも名乗れたから、それを拝借したにすぎない。
そのため、あれは東大全共闘ではないとか、三島と討論するならもっとまともなやつを出せというような陰の声も聞かれた。しかし、だいじなのは、あのとき全共闘を称するノンセクトの若者たちが三島に討論を呼びかけ、三島もそれを無視せず若者との討論に応じたことなのである。
単行本の『三島由紀夫vs東大全共闘』(藤原書店)によると、最初、三島に電話をかけたのは、1947年生まれの東大教養学部学生、木村修だった。三島を呼んでシンポジウムをやろうという話は、すでに同学部の芥正彦(のち演劇家)や小阪修平(のち評論家)などとしていた。三島は「右翼に呼ばれて駒場に行くのは嫌だ、君たちの方が良い」とあっさり了承したという。
そのときはあくまでも少人数のシンポジウムを考えていたが、実際にふたをあけてみると、900番教室には1000人以上が集まって、2階の座席が抜けるのではないかと心配するほどの盛況だった。
東大焚祭委員会という名称をつくったのは小阪修平である。安田砦は陥落したが、全共闘運動は終わっていない、芸術、思想面での戦いをつづけるのだという気分が強かった。焚祭には古い思想を燃やす祝祭であると同時に、虚偽に満ちた大学を粉砕するという意味もこめられていた。
1月19日に本郷の安田講堂(安田砦)が陥落したあと、駒場キャンパスもしばらくロックアウトされ、全共闘の学生は学内から排除された。4月、5月になり、授業が再開されても、駒場寮近辺は民青系によって支配され、全共闘系の学生は近寄れなくなっていた。しかし、正門から左側はその支配がゆるやかで、900番教室(講堂)にはいることができた。そのため、全共闘を名乗る若者たちは、勝手にここを会場にした。
その会場に三島はやってきた。案内のビラをすべて民青がはがしたらしく、会場を探すのに少し手間取った。このとき、三島は44歳。
集会はすでに30分ほど前からはじまっていた。黒のポロシャツを着た三島は壇上に立つと、すぐに力強く話しはじめた。
〈今、私を壇上に立たせるのは反動的だという意見があったそうで、まあ反動が反動的なのは不思議がございませんので、立たしていただきましたが、私は男子一度門を出ずれば七人の敵ありというんで、きょうは七人じゃきかないようで、大変な気概を持って参りました。〉
このときの討論の様子が映像に残されている。
のちに三島自身がまとめているところによると、この日の討論で、三島は次のようなことを話そうとしていたという。
一は暴力否定が正しいかどうかといふことである。
二は時間は連続するものかといふことである。
三は三派全学連はいかなる病気にかかってゐるかといふことである。
四は政治と文学との関係である。
五は天皇の問題である。
討論会では、これらの五点がじゅうぶんに討議できたわけではない。全学連批判はおざなりだった。政治と文学との関係もさほど論じられていない。それでもその一端に触れている。なお三島が全共闘のことを最初、三派全学連と認識していたことも指摘しておかなければならない。
そして、その討論会は全共闘流の言い方をすれば、人を消耗させるものだった。三島も、このようなディスカッションはもう二度としたくないと書いている。
〈パネル・ディスカッションの二時間半は、必ずしも世上伝はるやうな、楽な、なごやかな二時間半であつたとはいへない。そこには幾つかのいらいらうするやうな観念の相互模索があり、また了解不可能であることを前提にしながら最低限の了解によつてしか言葉の道が開かれないといふことから来る焦燥もあつた。その中で私は何とか努力してこの二時間半を充実したものにしたいといふ点では全共闘の諸君と同じ意志を持つてゐたと考へられるし、また、私は論争後半ののどの渇きと一種の神経的な疲労と闘はなければならなかった。〉
東大全共闘を称する若者たちは、いったい何を言いたいのか、つかみがたいことが多かった。三島はそれをがまんして聞き、何とか理解したところに沿って、真摯(しんし )に自分の意見を述べている。
2020年に公開されたドキュメンタリー映画と当時の討論会の記録をみると、あのころの熱気がよみがえってくる。あのころ、ぼくは三島の小説をたいして読んでもいなかったが、全共闘つながりの周辺にいたことはたしかである。文学や哲学、美とはまるで無縁の衆生だった。
三島は快活で精悍な人物だった。その話ぶりは気迫とユーモアにみち、しかも丁寧だった。自分をたたきつぶすために企画された集会に堂々とやってきただけではなく、全共闘の若者たちをむしろ説得しようとしていた。そのため、三島のスピーチは全共闘をなぜ評価するかというところからはじまる。このあたり巧みである。
こう話している。
〈私は右だろうが左だろうが暴力に反対したことなんか一度もない。これは、私は暴力というものの効果というものが現在非常にアイロニカルな構造を持っているから、ただ無原則、あるいは無前提に暴力否定という考えは、たまたま共産党の戦略に乗るだけだと考えているので、好きでない。東大問題は、全般を見まして、自民党と共産党が非常に接点になる時点を見まして、これなるかな、実に恐ろしい世の中だと思った。(笑)私はあの時東大問題全体を見て、暴力というものにたいして恐怖を感じたとか、暴力はいかんということは言ったつもりもない。〉
三島は、筋や論理はどうでもいい、ともかくも秩序がたいせつだとする収拾の考え方に嫌悪を感じていた。現存の秩序がおかしければ、暴力をもってしてでも闘うのがとうぜんだと考えていた。だから、全共闘学生の暴力を必ずしも否定しない。
さらに、三島は全共闘をさらにこう持ちあげる。
〈そしてその政治思想においては私と諸君とは正反対だということになっている。まさに正反対でありましょうが、ただ私は今までどうしても日本の知識人というものが、思想というものに力があって、知識というものに力があって、それだけで人間の上に君臨しているという形が嫌いで嫌いでたまらなかった。具体的に例をあげればいろいろな立派な先生がいる……。そういう先生方の顔を見るのが私は嫌でたまらなかった。これは自分に知識や思想がないせいかもしれないが、とにかく東大という学校全体に私はいつもそういうにおいを嗅ぎつけていたから、全学連の諸君がやったことも、全部は肯定しないけれども、ある日本の大正教養主義からきた知識人の自惚れというものの鼻を叩き割ったという功績は絶対に認めます。(拍手)〉
三島は全共闘の「反知性主義」に喝采を送っている。東大を頂点とする日本の知性秩序に反逆をくわだてたのは、全共闘の功績だという。
その知性秩序が「無機的な、からっぽな」戦後の民主主義日本をつくりあげてきたのだ。それに反抗した全共闘は絶対に認められるべきだ、と三島はいう。
だが、三島と全共闘の共通点はそこまでだ。三島は天皇を中心とする日本を取り戻すことを説くために、ここにやってきた。これにたいし、全共闘はあくまでも祝祭としてのコミューンにこだわった。
討論は対決となる。だが、その対決は意外な論戦からはじまっている。すなわち、他者とは何か、自然とは何かをめぐる、一見スコラ的な論議である。
長くなったので、それについては、また次回ということで。
キッシンジャー回想録『中国』を読む(4) [われらの時代]

1989年6月の天安門事件で、中国共産党指導部内の対立が表面化すると、総書記の趙紫陽が辞任し、江沢民が共産党トップに昇格した。
中国は孤立し、海外から経済制裁を受け、国内の政治状況も不安定となった。チベットも新疆も揺れていた。世界中で共産主義体制が崩壊していた。
そうしたなか、1992年に鄧小平は南方への視察旅行に出かけ、深圳や珠海などのハイテク基地やモデル企業、学校などを見て回った。
鄧小平は市場原理とリスクをとること、民間に任せること、生産力と企業家精神の重要性を訴えた。これと見定めたら、大胆に実験し、大胆に突き進むことを推奨した。外国からの投資を恐れるべきでもないと話した。科学と技術がカギだと強調し、よき統治は庶民に幸福と発展をもたらすものだと断言した。
この南方視察が鄧小平の最後の公務となった。
天安門事件後に中国の新指導者となった江沢民は、上海市党委員会書記から抜擢された。みずからの権力基盤は弱く、何ごとも政治局のコンセンサスにもとづいておこなわれた。キッシンジャーによれば、温かく、ざっくばらんな人物だったという。
江沢民政権は、銭其琛外相(のち副首相)と朱鎔基副首相(のち首相)によって支えられていた。このふたりは頻繁に海外に出て、国際会議に出席し、西側世界とのつながりを回復することに努めた。
1989年11月に江沢民はキッシンジャーと会い、米中間の懸案は台湾問題だけであり、国内問題について批判されるいわれはなく、いかなる状況でも中国の経済改革はつづくと話した。
それから1年後、ふたたびキッシンジャーと会う。ようやく方励之問題が決着したときだった。米中間はまだ緊張状態にあり、対中制裁がつづいていた。
江沢民は、中国とアメリカは新たな国際秩序構築に向けてともに仕事をすべきだと主張した。それぞれ国内の事象は外交政策の領域外であり、国と国の関係は国益の原則によってルールづけられるべきだ。アメリカと中国とでは価値観がことなる。それを認めたうえで、アメリカは対等な大国として中国を扱うべきだと述べた。
このとき、江沢民はキッシンジャーを通じて、ブッシュ大統領に中国がアメリカとの友好を切望しているとの口答メッセージを伝えてほしいと頼んでいる。ただし、中国は自国の独立と主権と尊厳を重視する、ともつけ加えていた。
1991年9月にキッシンジャーが訪中したときも、江沢民は両国間の関係を正常化させない理由などはないと話し、「互いを尊重し、内政干渉をやめ、平等と互恵の原則のもとで関係を構築できれば、両国は共通の利益を見いだすことができるはずだ」と自信をみせた。
江沢民はアメリカに譲歩を求めていた。
この年、ソ連は崩壊した。
「共通の敵が消えた今は、米中指導者間の価値観や世界観の相違が前面に出て来ることは避けられなかった」とキッシンジャーは書いている。
アメリカにしてみれば、ソ連の崩壊は民主主義の勝利を意味した。多党制の議会制民主主義と市場経済の組み合わせこそが、歴史の結論のように思えた。
しかし、中国にとってはそうではなく、共産党の支配によって政治の安定が保たれてこそ、経済の発展が可能なのだった。そのうえで、中国の発展にはアメリカの協力が欠かせないこともわかっていた。
最終的にブッシュは中国の内政に干渉することは得策ではないと判断した。米中関係は徐々に緩和しはじめる。
だが、1993年にクリントン政権が発足すると、状況は一変する。クリントンは中国にたいするブッシュ政権の柔軟姿勢を批判し、民主主義の拡大を外交目標にかかげた。アメリカの外交政策にほかの西側諸国も同調したが、そうした圧力を、中国は内政干渉によって共産主義政権を弱体化させようとする試みととらえた。
中国の指導者は冷戦の終結によって、アメリカの一極支配時代がはじまるとはとらえていなかった。世界の人口分布を考えても、そんな事態が生じるはずがない。キッシンジャーにたいし、李鵬首相は人権や民主的権利については、西側と完全な合意に達することはできないと述べ、そんなことをすれば中国社会の根本を揺るがすことになると弁明した。
クリントン政権は、人権状況の改善がみられないかぎり、中国に最恵国待遇を与えないと主張した。キッシンジャーによれば、この最恵国待遇という恩着せがましい言い方は誤解を招くものだ。最恵国待遇とは、通常の貿易で与えられている権利をいうのであって、ほとんどの国がその待遇を受けており、特別な恩恵の意味などないという。
1993年5月、クリントン政権の高官は北京を訪問し、人権問題と武器拡散防止問題などで、劇的な進展がみられないかぎり、アメリカは中国に最恵国待遇を与えないと通告した。これにたいし、江沢民は中国とアメリカはもっと長期的な観点で物事を考えるべきだと主張し、最恵国待遇問題の袋小路から抜けだそうとした。
けっきょくクリントンは民主化問題にはふれず、人権問題の改善を条件として、1年間、最恵国待遇を延長することにした。それ以降延長するかどうかは、その間の中国の行動次第だとした。
関税と貿易に関する一般協定(GATT)、すなわちのちの世界貿易機関(WTO)への中国の加盟も行きづまっていた。
1994年3月のクリストファー国務長官の訪中で、事態はさらに悪化した。李鵬首相は、中国の人権政策はアメリカとは関係のないことであり、アメリカこそ重大な人権問題を抱えていると述べ、けんか腰の態度をとった。最恵国待遇更新の期限が迫っていた。けっきょく、クリントン政権は中国ビジネスを手がけるアメリカ企業からの圧力を受け、さらに1年間、最恵国待遇を無条件で延長することになった。人権問題の改善については、ほかの手段をさぐるほかなかった。
その後、クリントンは対立的姿勢を控え、建設的関与を強調するようになる。米中関係は急速に修復された。1997年には江沢民がワシントンを訪問し、1998年にはクリントンが訪中した。10年近くの対立ムードに終止符が打たれた、とキッシンジャーは書いている。『米中奔流』の著者、ジェームズ・マンにいわせれば、アメリカはまさに「回れ右」をしたことになる。
その前に台湾海峡危機が発生していた。中国政府は1980年代から台湾を国内の完全な自治州として扱うことを前提に統一を提案していた。台湾側はあくまでも慎重だった。だが、経済面では中台間の相互依存が高まり、1993年末には、台湾の対中投資額は日本を抜いて世界で第2位となっていた。
経済的な相互依存が高まるいっぽうで、台湾は中国とは政治的には大きく異なる方向を選んだ。劇的な自由化がはじまった。それをリードしたのは1988年に蒋経国から総統を継承した李登輝である。
クリントンはあくまでも「一つの中国」を順守し、台湾とは距離をおこうとしていた。しかし、1994年には李登輝の個人的かつ非公式なアメリカ訪問を認めている。李登輝は母校のコーネル大学を訪れ、台湾人の思いを雄弁に語った。中国側はこれに反発し、駐米大使を召還し、台湾海峡にミサイルを打ちこんだ。
1995年7月にキッシンジャーは訪中し、江沢民や銭其琛と会って、事態の収拾をはかった。だが、それ以降も台湾海峡での緊張は収まることがなく、1996年3月にも中国人民解放軍は福建省の沿岸での演習を実施し、台湾の沖合にミサイルを撃ちこんでいる。これにたいし、アメリカは空母ニミッツを含む空母戦闘群を台湾海峡に派遣した。
1999年には、コソボ紛争で、アメリカのB2爆撃機がベオグラードの中国大使館を誤爆する事件も発生した。「両国政府は協力の必要性を認識していたが、両国が互いに衝突するすべての可能性を制御できているわけではなかった」とキッシンジャーは書いている。
危機は周期的に発生した。しかし、1990年代に中国経済は驚異的に発展し、この10年に年7%以上、ときに二桁の経済成長を達成し、一人あたりGDPも持続的に伸び、1990年代末に都市部の収入レベルは1978年の約5倍となった。中国は緊縮財政でインフレも乗り切り、周辺諸国との貿易額も増やし、経済大国に成長した。中国とアメリカは経済的にますます結びつきを深めていった。いまやアメリカの多国籍企業にとって、中国は生産拠点、金融市場としても、ビジネス戦略上欠かせない拠点となった。いっぽう中国も増えつづける外貨残高でアメリカの国債を大量に購入し、アメリカ経済を支えていた。
だが、「グローバル化された世界は両者を結び付けるとともに、危機が訪れると、より頻繁に、そしてあっという間に緊張が激化する」世界でもある、とキッシンジャーはいう。
そのひとつの現れが、2001年4月に発生した米偵察機と中国軍用機との接触事故だった。中国軍用機は海南島近くに墜落して、中国人パイロットが死亡した。しかし、このときも江沢民は事故をおおごとにせず、米中協力の重要性を強調して、事態の収拾をはかった。たとえ、さまざまな問題があるにせよ、世界の将来が米中協力にかかっているというビジョンを江沢民は示したのだ、とキッシンジャーはいう。
2002年11月に江沢民は党総書記を辞任し、胡錦濤にその地位を譲った。アメリカでは2001年にジョージ・W・ブッシュ政権が、2009年にバラク・オバマ政権が発足した。
キッシンジャーの『中国』が出版されたのは2011年のことである。したがって、本書では、その後の習近平時代、トランプ時代については、触れられていない。それでも、キッシンジャーのスタンスはその後も基本的に変わらないとみてよいだろう。
新世紀にはいってからの10年は、アメリカにとっては苦難の時代だった。2001年には9・11中枢同時テロが発生し、そのあとイラクとアフガニスタンでの戦争がはじまった。2008年にはリーマン・ショックがあり、世界中が深刻な金融危機に見舞われた。しかし、その間も米中関係は順調に推移した。
胡錦濤政権は、経済発展を継続するとともに、「調和のとれた社会」、「調和のとれた世界」を目指していた。外交的には慎重な姿勢を崩さず、平和的な国際関係を維持するなかで、世界貿易機関(WTO)に加盟し、資源と原材料の確保をめざす経済外交を展開した。2008年には北京五輪が開かれた。台湾問題に関しては、米中はたがいに牽制しながらも、波風を立てぬよう行動した。
アメリカが困難に見舞われるなか、米中の相互協力は拡大した。通貨や北朝鮮の核問題などをめぐって、さまざまなやりとりがあったものの、それは対立にまでは発展しなかった。
中国は21世紀最初の20年間を戦略的なチャンスととらえていた。「平和的台頭」という考え方が出てくるのも、この時代である。胡錦濤は国連総会で演説し、「中国国民は平和を愛する」と強調し、「中国の発展は、誰も傷つけたり、脅かしたりはせず、世界の平和と安定と共通の繁栄に寄与するだけである」と述べた。
平和的台頭という概念は、世界支配への野望を秘めていると誤解されないように、平和的発展という言い方に置きかえられるようになった。中国は革命を求めないし、戦争や復讐を望まないと国務委員の戴秉国は強調した。
現在、米中間では国際問題や経済問題で、常に協議がなされている。いまやアメリカと中国は「対等なパートナー」となっている、とキッシンジャーはいう。これからは「中国と米国が真の戦略的な信頼を育む」ことによって、「協力に基づく真のパートナーシップと世界秩序の進化」を成し遂げることが重要だと考えている。
おそらくキッシンジャーは、ソ連崩壊後の世界は、アメリカ一極支配、あるいは「歴史の終わり」をもたらすのではなく、米中を軸とした多極化世界になると思っていたはずである。
キッシンジャーはアメリカと中国が対立しつづけるのはおろかだという。いま世界は、地球規模の核拡散問題、環境問題、エネルギーの安全保障問題、気候変動問題などさまざまな問題で、たがいに協力しなければならない。そんなときに冷戦をくり広げる場合ではない。
中国を封じ込めたり、イデオロギー聖戦のために民主国家によるブロックを形成したりするこころみも成功しないだろう、とキッシンジャーは断言する。その理由は、中国が大半の周辺国にとって、欠くことのできない貿易相手国だからだ。
キッシンジャーが提案するのは、アメリカと中国が可能な領域で協力しながら、対立を最小限に抑えるよう互いの関係を調整しつつ、「相互進化」をめざすことである。アメリカは中国を支配できないし、中国もまたアメリカを支配できない。戦争はまったく意味がない。
危機があれば、それは話しあいによって解決されるべきだ。中国とアメリカが太平洋全域で勢力圏を競いあうという構図は、両国にとって破滅への道を意味する。
キッシンジャーは「太平洋共同体」構想を提案する。
〈現在の世界情勢における戦略的緊張の一側面には、米国が中国を囲い込もうとしているという中国側の懸念があり、これと平行して、中国が米国をアジアから追い出そうとしているとの米側の懸念もある。太平洋共同体という構想は、米国、中国、その他の諸国すべてが、共同体の平和的発展に参加するというものであり、米中両国の懸念を緩和する可能性がある。〉
太平洋構想は、中国とアメリカのブロックに地域を分割することを目指すのではない。太平洋を囲むすべての国がこの仕組みに参加し、共に進化する道を進むことが目的なのだ、とキッシンジャーは論じている。
太平洋共同体はアジア共同体より筋がよさそうだ。しかし、はたしてそんなふうに話がうまく運ぶものか。その前にひと波乱もふた波乱もありそうである。
キッシンジャー回想録『中国』を読む(3) [われらの時代]

1979年はじめ、ベトナム軍はポル・ポト政権を倒すためカンボジアに攻めこんだ。これに懲罰を与えるため、中国は2月半ばから6週間にわたって、ベトナムに侵攻した。ベトナムとソ連のあいだには友好協力条約が結ばれていたが、ソ連は動かなかった。
ベトナム戦争で中国は北ベトナムを支援した。しかし、戦争に勝利して統一ベトナムが誕生すると、ベトナムは中国にとって大きな戦略的脅威になった。ベトナムがソ連と手を組んでインドシナ全体を支配することを中国は恐れた。そのため、カンボジアのポル・ポト派を支援したのだった。
中国は北方でも南方でも西方でもソ連の包囲網が強まっているように感じていた。あらゆる前線で脅威に直面した鄧小平は、外交的・戦略的な攻勢に出ることを決意した。それがベトナムとの戦いだった、とキッシンジャーはいう。
1977年に復権した鄧小平には、中国が世界革命に向けてチャンスをつかもうなどという考え方は毛頭なかった。現実のソ連の脅威にたいし、アメリカと実務的に協力する強めていった。
だが、この時点で米中間の国交は結ばれていない。アメリカはまだ台湾に拠点を置く中華民国を合法政府と認めていた。米中の関係正常化は当時のカーター政権にとって、大きな課題となっていた。それは鄧小平にとっても同じだった。
ネックになっているのは台湾問題だった。カーターは対中関係を最優先課題と考え、1978年5月に大統領補佐官のブレジンスキーを北京に送りこんだ。そのとき黄華外相は「ソ連こそが戦争の最も危険な源だ」と述べ、アメリカとの戦略的協力関係を求めた。鄧小平も、当時まだ首相の座にあった華国鋒もソ連との対決姿勢を鮮明にしていた。
アメリカとの関係正常化を推進するにあたって、台湾にたいする中国の立場は一貫していた。台湾からの米軍撤退、台湾との相互防衛条約の破棄、外交関係の断絶を求めるというものだ。カーターはこの原則を再確認したうえで、アメリカはあくまでも台湾に関し平和的な解決を望むとし、アメリカによる台湾への一定の武器売却を中国側が黙認することを求めた。鄧小平はこれを了承した。そして、このあいまいさのうえに1979年1月に米中関係正常化が実現することになった。
正常化を目前に、鄧小平は各国を歴訪し、中国の後進性と海外から学ぶ必要性を強調した。
鄧小平の最初の訪問先は日本だった。1978年8月には、日中平和友好条約が調印されていたが、10月の批准書承認セレモニーに出席するため、日本を訪れたのだ。そのとき、各地の企業を見学し、「われわれは偉大で、勤勉で、勇敢で、知的な日本の人々を尊敬し、その人々から学んでいる」と記帳したりしている。
11月には、マレーシア、シンガポール、タイの三カ国を歴訪し、ベトナム、ソ連に対決する姿勢を示した。しかし、東南アジア諸国はむしろ慎重な態度を保った。
1979年1月、米中関係正常化を祝って、鄧小平はアメリカを訪問した。ベトナムへの戦争を仕掛ける直前である。「鄧小平の米国訪問は、ソ連をけん制することを目的の一つとした、一種の影絵芝居だった」とキッシンジャーは書いている。
訪米中、鄧小平は、中国は外国の技術を導入し、経済を発展させなければならない、と強調した。日本と並んでアメリカは中国の産業発展のモデルと考えられていた。
カーターとの会見では、中国はアメリカとの正式な同盟を望まないものの、ソ連がいままさに戦争を仕掛けようとしているなか、両国は共通の立脚点に立ち、行動を調整し、必要な手段を取るべきだと話している。
中国はソ連のたくらみを防ぐため、東南アジアとアフリカで積極攻勢に出るつもりだった。すでにカンボジアとラオスに侵攻し、インドシナ連邦構想を実現しようとしているベトナムにたいし、中国は行動する義務があると宣言した。
カーターは中国による対ベトナム専制攻撃を承認せず、そんなことをすれば中国が好戦的とみられるのではないかと懸念を示した。カーターは自制をうながす。だが、鄧小平はベトナムとの戦争に踏み切る。2月4日、アメリカをあとにした鄧小平は再度東京に立ち寄り、大平正芳首相と会って、目前に迫る軍事行動への日本政府の支援を求めている。
2月17日、中国はかつての同盟国ベトナムへの侵攻を開始した。20万から40万の人民解放軍が動員されたとされる。鄧小平はソ連は中国を攻撃しないだろうと踏んでいた。じっさい、ソ連は戦争拡大の危険を冒さなかった。
中国は限定的な「懲罰」攻撃をおこなったあと、ただちに撤退した。戦争は29日間で終わった。それからひと月後、キッシンジャーと会った鄧小平は、ベトナムにもっと深く攻め込んでいたら、さらにいい結果が得られたかもしれない、と強気の見解を示した。
しかし、中国のベトナム侵攻はあきらかに失敗だった。人民解放軍は多大な犠牲を払って撤兵したのだ。ただ、中国側はベトナムのインドシナ連邦構想に釘を差したという意味で、この戦争の意義を認めていた。
中国政府はベトナムに対抗するため、カンボジアのポル・ポト派を支援していた。しかし、アメリカは非人道的で残虐なポル・ポト派を積極的に支援するわけにはいかなかった。その後、ベトナム軍はカンボジアに10年間駐留する。そのかんポル・ポト派の勢力は衰えていった。
キッシンジャーは中越戦争を次のように評価する。短期的には中国は敗れた。しかし、ベトナムが中国による再侵攻の可能性に備えて、100万の常備軍を維持しなければならなかったことは、ベトナム自身にとっても、それを支援するソ連にとっても大きな負担となり、そのことがソ連の弱体化につながった。「戦争の究極の敗者は、世界に対する野心を持っていると世界から警戒される羽目になったソ連だった」と書いている。
中越戦争から1年後、ソ連はアフガニスタンに介入した。世界の非難はソ連に向かった。そして、最終的に中国は東南アジアからソ連の影響力を排除することに成功する。
1981年、アメリカではレーガン政権が発足した。レーガンは共産主義嫌いだったが、中国政府との関係は維持したいと思っていた。そのいっぽう、台湾に思い入れをもつレーガンはなんとかして台湾との「公式な関係」を維持できないものかと考えていた。
中国との関係が正常化されたあと、アメリカ議会では台湾関係法が可決された。この法律はアメリカと台湾の経済、文化、安全保障面の結びつきを維持するとともに、台湾への武器供与を認めるものだった。この法律に中国はあえて異議を唱えなかった。
1982年8月、米中共同コミュニケ(第3のコミュニケ)が発表された。中国が台湾問題が中国の内政問題であることを両国は確認する。いっぽう、アメリカは台湾問題が平和的に解決されることを期待し、「平和的解決に努力する中国の姿勢を評価する」。これがぎりぎりの妥協だった。
アメリカによる台湾への武器売却を中国は黙認した。しかし、その期間や内容、量に関しては明確な規定がなされなかった。レーガンはテレビのインタビューでも「われわれは台湾に武器を供与し続ける」と語っている。そして実際、台湾にたいする武器援助計画を拡大した。
「レーガン政権一期目の中国・台湾政策は、ほとんど不可解な矛盾の典型となった」。かれの型破りの動きは、基本原則から逸脱していたが、それはきわめてうまく機能した、とキッシンジャーは評している。
〈中国は、米国による第三のコミュニケの柔軟解釈に不満だったが、全体としては、この一〇年間[1980年代を通じて]、米国の支援を得て、経済面と軍事面で力を付け、世界政治において、独自の役割を果たす能力も身に付けてきた。米国は、台湾海峡の両岸と友好関係を維持し、中国とは、情報の共有やアフガニスタンの反政府ゲリラ支援など、反ソのための共通の緊急事態で協力することができた。台湾は、中国と交渉を行うに当たっての有利な立場を獲得した。〉
1980年代、中国、アメリカ、台湾は、それぞれ利益を確保していた。中国が第三のコミュニケのあいまいな台湾条項を見逃してきたのは、対ソ戦略上、アメリカとの協力が中国の国益にかなうとみたためである、とキッシンジャーはいう。
1980年代半ばになると、ソ連はほぼあらゆる国境線で、防御と抵抗に直面するようになった。アフリカ、アジア、中南米では、革命による解放への懐疑的な見方が広がっていた。アフガニスタンでは苦戦がつづいていた。加えて、レーガンが推し進めた戦略防衛構想が、ソ連に重い軍事的負担を強いていた。
アメリカは財政面、地勢面でソ連に圧力をかけ、冷戦に勝利しようとしていた。そして、ソ連が退却するなか、中国は世界に徐々に進出していく。
1982年、中国共産党総書記の胡耀邦は、中国共産党第12回党大会で「中国はいかなる大国とも、いかなる国家集団とも決して結び付かず、いかなる大国の圧力にも決して屈しない」と述べた。中国が内政問題と考えている台湾問題への介入をアメリカがやめないかぎり、米中関係は健全に発展しないだろうともつけ加えている。「他の第三世界諸国とともに、帝国主義、覇権主義、植民地主義と断固として戦う」というのが中国の立場だった。
そのいっぽうで中国は、対決しているソ連との関係を復活させようとしていた。アメリカとソ連を両天秤にかけながら、ソ連崩壊後の超大国となるために着々と準備をはじめていたのだ。
レーガン時代の米中関係は、はじめのころの熱狂が冷め、とりあえず友好を保つ相手国になっていた、とキッシンジャーはいう。
〈米国と中国はともに、その存在に関わる共通の脅威に直面する戦略的パートナーとしてのかつての同盟関係から、徐々に離れつつあった。ソ連の脅威が弱まった今では、中国と米国は実質的には、その国益が一致する個別の問題についての便宜的なパートナーにすぎなかった。〉
そうしたなか、鄧小平は「改革開放」路線を推し進めていた。中央計画経済に代わって、社会主義体制を保ちながら市場経済、外部世界への経済開放を実現するにはどうすればよいのか。その基礎となるのは、中国人の生来の経済的活力だと思われた。
鄧小平のブレインとなったのが、胡耀邦と趙紫陽だった。1987年に中国を訪れたキッシンジャーに、共産党総書記になったばかりの趙紫陽は、中国は社会主義のもとに市場を取り込んでおり、「企業は市場の力を十全に使い、国家はマクロ経済政策を通じて経済を指導する」と語っている。
中国は沿海部に経済特区を設け、海外からの投資を奨励していた。この特区では企業家に大幅な自由が認められ、投資家に特別の優遇措置が与えられていた。
農業では人民公社に代わって生産責任制が導入された。個人向けの経済優遇措置がとられたため、工業生産高の5割近くを民間セクターが占めるようになった。1980年代を通し、中国のGDPは年率平均9%の成長を示した。
そのころ鄧小平は党の若返りをはかるとともに、党のあり方自体を変えようとしていた。これまでの党は中国人民の日常生活を細部にわたって統制する役割を果たしていた。しかし、これから共産党は国家の経済と政治構造を全般的に監督する役割に徹するとキッシンジャーに話した。
だが、鄧小平の改革はさまざまな問題を生む。多くの中央機関を廃止し、党官僚制度の合理化をはかることは難題だった。公共セクターと市場経済という二つのセクターの存在が、二重価格制度を生みだし、それが腐敗と縁故主義をもたらしていた。官僚と企業家は、ふたつのセクターのあいだで、製品を行ったり来たりさせながら、個人的な利益を得た。中国のような家族主義の社会では、経済の拡大はしばしば縁故主義と結びついた。
市場経済においては勝ち組より負け組が多いのがふつうだ。負け組はとうぜん不満をいだく。キッシンジャーは「経済改革は大衆レベルで、生活水準と個人的自由の向上への期待を抱かせると同時に、社会の緊張と不公平を生んだ」と記している。それを是正するには、より開かれた参加型の政治システムをつくるほかない。中国の指導部のなかにも、ゴルバチョフの示したグラスノスチとペレストロイカのようなものが必要ではないかと考える者もでてきた。
1989年、東欧ではソ連の一元的支配にひび割れが生じ、ベルリンの壁が崩壊する。しかし、中国は安定しているようにみえた。
4月15日、前党総書記の胡耀邦が死去する。胡耀邦は1986年に学生デモへの対処が手ぬるいとして解任され、ひらの政治局委員に降格されていた。胡耀邦の支持者たちは天安門広場の人民英雄記念碑に花輪と弔詞を捧げ、かれの精神を引き継ぎ、さらなる政治的自由化をめざそうと呼びかけた。
5月はじめ、折しもゴルバチョフが北京を訪れるころ、追悼は抗議へと発展する。汚職、インフレ、報道規制、学生の生活条件、長老の党支配などへの不満が高まり、さまざまな抗議活動が全国の都市に広がり、天安門広場は占拠された。西部ではチベット人やウイグル人が政府への抗議活動をはじめた。
中国当局は7週間にわたってためらい、6月4日に武力行使に踏み切った。武力行使に反対した趙紫陽は党総書記を解任され、軟禁された。鄧小平は人民解放軍に天安門広場の制圧を命じ、多くの死傷者がでた。その様子は世界中から集まっていたメディアによって伝えられた。その後、全国で徹底的な弾圧がくり広げられた。
世界の反応は厳しかった。アメリカでは中国への制裁論が高まった。その年、大統領に就任したジョージ・W・ブッシュは、鄧小平とも面識があり、かれの改革開放路線を称賛していたため、制裁には気乗り薄だった。
アメリカは中国との協力関係を修復させるのか、あるいは自由化を要求して中国を制裁するのかの決断を迫られていた。中国を孤立化させれば、長い対決の時代がやってくることが予想された。そのいっぽう、アメリカの安全保障上、ブッシュは中国との友好関係を維持する必要があるとも感じていた。
議会が中国への制裁措置を決定すると、ブッシュはその一部を緩和した。しかし、中国への批判をあきらかにするため、高官級の政府間交流の禁止、軍事協力の停止、警察用・軍用機器売却の禁止、世銀などの新規借款に反対するなどの措置を発表した。そのかたわら、鄧小平に長文の親書を送り、抗議活動に参加した学生たちへの寛大な措置を求め、使節を北京に送りたいと提案した。親書の最後は、これまで17年間にわたって築き上げられてきた関係を台無しにしないようしなければならないと結ばれていた。
天安門事件から3週間後の7月、大統領補佐官のスコウクロフトと国務副長官のイーグルバーガーが極秘に北京を訪れ、鄧小平、李鵬首相らと会見した。鄧小平はわれわれは制裁など気にしていない、アメリカはもっと歴史を学ぶべきだ、などといいながら、関係改善の責任はアメリカにあると主張した。いっぽうで、反乱の扇動者の処罰はためらわないとも述べた。
スコウクロフトらは事件の扱いは中国の内政問題だと認めたものの、その対応がアメリカ国民のもつ普遍的と思われる価値観を逆なでしたことは事実だと述べた。たがいの溝が埋まることはなかった。
1989年秋には、米中関係は最悪の状態におちいっていた。断絶は回避できそうにもなかった。そのさなかの11月、中国指導部の招きに応じて、キッシンジャーは訪中する。
鄧小平はキッシンジャーに「中国政府が天安門で断固たる措置を執らなければ中国に内戦が起きていただろう」と語り、アメリカからあれこれ指図を受けたくない、内政不干渉は中国外交政策の原則だ根本と主張した。そのいっぽうで、安定した中国がめざすものは、新たな国際秩序への貢献であり、その中心となるのはアメリカとの関係だとも話した。
キッシンジャーが訪中したとき、米中間の断絶のシンボルとなっていたのが、反体制物理学者の方励之の存在だった。2月に北京を訪れたブッシュ大統領は、方励之を晩餐会に招いた。しかし、中国治安当局はかれを晩餐会会場に近づけさせなかった。6月4日の天安門事件のあと、方励之はアメリカ大使館に避難した。中国当局はアメリカにかれを引き渡すよう求めたが、アメリカ側は拒否していた。
訪中したキッシンジャーに鄧小平はこの問題を持ちだした。キッシンジャーは中国が方励之を国外に追放し、どこにでも好きなところに行かせたらどうかと提案した。アメリカはかれを政治的に利用することはないだろうとも話した。
しかし、そのころアメリカで緊急の課題となっていたのは、むしろベルリンの壁の崩壊が与えた衝撃にどう対応すればよいかということだった。ソ連が崩壊する事態も考えられた。
その対応に追われたため、アメリカが中国に特使を送るのは12月中旬になった。中国は方励之の亡命を認める見返りとして、中国にたいする制裁解除や大型経済協力プロジェクトの協定締結などを求めた。米中の交渉は長引き、方励之は1990年6月にようやく解放され、家族ともどもイギリスに出国することになる。
東ドイツ、チェコスロバキア、ルーマニアで共産主義政権が崩壊すると、1990年春に鄧小平は中国共産党に「現下の国際情勢においては、敵があらゆる関心を中国に集中していることを、全員が肝に銘じなければならない」と警告を発し、これから3年ないし5年が重要な時期だと述べた。
1990年代にはいると、鄧小平は徐々に重要な役職から身を引き、1997年に死去する。その前に共産党の幹部たちに短い遺訓を残した。
キッシンジャーはこう評している。
「鄧小平は、騒乱と孤立の低迷期に、中国が危機の中で燃え尽きてしまうことを懸念し、また同時に、中国の将来は、自信過剰に陥ることの危険性を認識できるだけの視野を、次世代の指導者が獲得できるかどうかにかかっている、と考えていたのかもしれない」
ここでもキッシンジャーは中国にたいする好意的な見方を崩していない。
キッシンジャー回想録『中国』を読む(2) [われらの時代]

ニクソン訪中後、米中間にはともかくもパートナーシップが形成された。それは疑似同盟と呼んでもいいものだった、とキッシンジャーは書いている。ソ連に対抗することが目的だった。
1973年2月と11月にキッシンジャーは2度毛沢東と会談した。周恩来も同席していた。1回目はパリでベトナム和平協定が結ばれた直後、2回目は第4次中東戦争のさなかである。
台湾問題について、毛沢東は「私は平和的な移行を信じていない」としながらも、早急な解決は望まないと話した。ソ連については、世界中でソ連を封じ込める政策はきっと勝利するだろうと述べた。米軍が中東に関与するよう勧め、ソ連にたいする防波堤としては、トルコ、イラン、パキスタンが重要だと指摘した。力をつけた日本を孤立させて、ソ連のほうに追いやらぬよううまく扱えとも警告した。
毛沢東はソ連に対抗するため、アメリカ、日本、パキスタン、イラン、トルコ、ヨーロッパへと横のラインを引く案を口にした。ただし、中国はあくまでも自力依存でソ連と対抗すると強調した。毛沢東は中国には核戦争を生き残る能力があると、くり返し語った。
「われわれは核の傘の保護を必要としていない」というのが毛沢東の信念だった。核問題について、アメリカと話しあうつもりはなかった。
中国が懸念していたのは、アメリカが柔軟にソ連に対処することだった。中国がガードを下げれば、アメリカとソ連は共謀して中国を破壊するのではないかと恐れてもいた。キッシンジャーが「ソ連による中国への攻撃にアメリカが協力することはけっしてない」と話すと、毛沢東は「あなた方の目標は、ソ連を打倒することにある」と答えた。
中国とアメリカとでは、安全保障上あきらかに発想のちがいがあった。アメリカはソ連を打倒するなどとは考えていなかったからである。それでも、ソ連に対抗するという戦略的思考においては、アメリカと中国の考え方は一致していた。
しかし、それからまもなくの1974年8月に、アメリカではウォーターゲート事件によりニクソンが辞任するという思いがけぬできごとがあり、フォードが後任の大統領に就任した。アメリカ政界の混乱は収まらなかった。中国はアメリカの緊張緩和政策に懸念をいだいた。キッシンジャーによると、「次第に中国は、米国を裏切りよりも悪い、無力だと非難するようになった」。
いっぽう、中国では毛沢東時代が終わろうとしていた。それにともない、後継者問題が浮上する。
林彪失脚後、中国の政治は毛沢東の妻、江青を中心とする「四人組」と、実務派の周恩来、鄧小平とのバランス、言い換えれば継続革命と現実主義との対立のうえに成り立っていた。急進派が勢いづくと、米中関係は冷却した。
急進派のあおりを食って周恩来が失脚する。1974年になると、周恩来は表舞台にでなくなり、がんにかかっていると伝えられた。キッシンジャーは74年12月に周恩来と面会する。だが、ほんのわずかの時間だった。その面会で、周恩来は、アメリカとの関係を永続的なものとみなし、中国は孤立をやめて国際秩序の一員にならなければ繁栄できないと考えているようにみえた、とキッシンジャーは語っている。
周恩来が最後に公の場に姿をあらわしたのは、1975年1月に開かれた全人代の会議のときである。周恩来は農業、工業、国防、科学技術の「四つの近代化」を今世紀末までに達成するよう呼びかけた。これが、かれの最後のメッセージとなった。周恩来が姿を見せなくなったあとは、鄧小平がアメリカとの交渉相手となる。
このころ毛沢東は横ライン戦略を放棄し、「三つの世界」論を展開するようになっていた。それによると、アメリカとソ連は第一世界、日本やヨーロッパは第二世界、発展途上国は第三世界をかたちづくっており、中国は第三世界の立場を代表して、二つの超大国と戦うというのである。
そうはいっても、毛沢東はアメリカというセイフティネットを手放すつもりはなかった。それどころか、アメリカとの関係を強化することを望んでいた。
1974年12月にフォード大統領がウラジオストクでロシアのブレジネフ書記長と会見したとき中国は不快感を示し、強く反発した。それでもアメリカが対中政策を変えることはなかった。もしソ連が中国を攻撃したら、アメリカが中国を支持するだろう。しかし、キッシンジャーにとって重要なのは、アメリカが二つの共産主義大国と対話できる能力を保持することだと思われた。
キッシンジャーが毛沢東と最後に会ったのは1975年の10月と12月。フォード大統領の訪中準備と実際の訪中のときだ。10月に会ったとき、毛沢東は、現時点では台湾を要求しない、あそこにはあまりにも多数の反革命分子がいるから、と話した。ヨーロッパはあまりにもバラバラで締まりがない、戦いなくしてソ連を弱体化させることはできない、とも語った。老いが迫っていた。だが、毛沢東が挑戦的な姿勢を崩すことはなかった。
12月にフォード大統領が毛沢東と会見したときには、中国で深刻な権力闘争がおきていることが感じられた。一部のグループは、アメリカとの友好関係に懸念をいだいていた。これにたいし、鄧小平は米中関係の重要性を確認する声明を発表して、難局を乗り切ろうとしていた。
会談から数カ月後、中国の亀裂は目に見えるものとなり、またもや鄧小平が攻撃にさらされるようになった。
1976年1月8日に周恩来が亡くなると、4月の清明節には数十万の中国人が天安門広場の人民英雄記念碑を訪れ、花輪や詩歌を備えて、周恩来を追悼した。北京市当局が追悼の品々を撤去したため、警察と追悼者のあいだで激しい衝突がおきた。江青ら四人組はその責任を鄧小平にかぶせ、毛沢東は鄧をすべてのポストから解任した。首相代行には、それまでほとんど知られていなかった湖南省党委員会書記の華国鋒が任命された。
この事件を機に、アメリカと中国の関係は遠くなった。四人組のひとり、張春橋副首相は台湾に関してきわめて好戦的な立場を表明した。
1976年9月9日、毛沢東が亡くなる。中国統一を成し遂げ、空想的ともいうべき巨大な国家事業に国民を駆り立てた、秦の始皇帝にも似た人物がこの世を去った、とキッシンジャーは感じたという。
毛沢東と周恩来の死後、中国は混乱する。だが、その混乱を収め、中国を世界の潮流に結びつけたのは鄧小平だった。人民公社による集団農業、停滞した経済、『毛沢東語録』を打ち振る人民服姿の大衆に代わって、中国に爆発的な経済発展をもたらした人物こそ鄧小平だ、とキッシンジャーは書いている。
鄧小平が権力を掌握するまでの道は紆余曲折に満ちていた。文革がはじまった1966年に鄧小平は走資派として逮捕されたが、毛沢東の介入により1973年に復権した。キッシンジャーによれば、「鄧小平は周恩来の後任として、ある意味では周恩来を追放するために復活してきた」のだった。
毛沢東と四人組が圧倒的な権力をふるう時代に現実主義を標榜することは、それ自体勇気のいることだった。鄧小平は科学技術の重要性を唱え、イデオロギーよりも職業的能力を重視し、連携・安定・団結を強調し、事態の正常化を優先し、改革プログラムを全面展開しようとしていた。その矢先に四人組から糾弾され、1976年にふたたび実権を剥奪され追放されたのだった。
毛沢東の死去後、中国の政治は不安定となる。毛沢東はみずからの後継者に華国鋒を指名していた。キッシンジャーにいわせれば、ぱっとしない人物で、政治的な基盤も欠いていたという。しかし、最高権力を譲られた直後、かれはとてつもない成果をもたらした。穏健派と手を組んで四人組を逮捕したのである。
混乱のさなか、1977年に鄧小平は幽閉生活を解かれ、中央に戻ってきた。華国鋒のもとで、鄧小平は中国近代化へのビジョンを打ち出していく。
1979年にキッシンジャーは訪中し、華国鋒、鄧小平と会ったが、華国鋒がおなじみのソ連型五カ年計画を語るのにたいし、鄧小平が重工業より消費物資の生産、農民の創意工夫、権力の分散を強調するのが印象的だったという。鄧小平は、中国は近代的な技術を導入すると同時に、数万の留学生を海外に送る必要があり、文化大革命の行き過ぎを未来永劫にわたって終わらさねばならないと話した。
まもなく華国鋒は指導部から姿を消し、その後10年にわたり鄧小平が実権をふるう時代がつづく。毛沢東は持ち上げられてはいたものの、革命家よりもプラグマティストとしての側面が強調されるようになった。
鄧小平は、中国は日本の明治維新の成果を凌駕しなければならないと語っていた。いまの中国は科学、技術、教育の面で先進国に20年は遅れているとの認識をもっていた。
キッシンジャーはこう書いている。
〈経済的な超大国としての今日の中国は、鄧小平の遺産だ。そうなったのは、彼がこの結果を達成するための特別な計画を作り上げたからではなく、自らが属する社会を、その時の姿から、かつてなかった水準にまで引き上げるという、指導者としての究極の仕事を、彼が成し遂げたからなのだ。〉
鄧小平は重要な役職をもたず、名誉ある称号を拒絶し、ほとんど物陰から政治を動かした。「貧困は社会主義ではない」というのが口癖だった。求められるのはイデオロギーではなく、個人の実力だ。
鄧小平はいう。「革命を進め、社会主義を建設するため、われわれは、大胆に思考し、新たな道を探り、新たなアイデアを生み出す開拓者を、大量に必要としている」
1978年12月の中国共産党11期三中総会において、「改革開放」というスローガンが採択され、「四つの近代化」にもとづく現実主義的な「社会主義近代化」路線が打ち出された。
とはいえ、鄧小平のなかで経済的自由化が政治的自由化に結びつくことはなかった。西側のような複数政党制の民主主義は考えられなかった。一党支配以外の道は無政府状態につながると信じており、大衆を扇動する悪質な分子は厳しく取り締まらねばならない、と主張していた。
鄧小平の大規模な改革は中国を世界の水準へと導いていった。だが、それは同時に中国国内に社会的、政治的緊張を生み、1989年の天安門事件をもたらすことになる。
キッシンジャー回想録『中国』を読む(1) [われらの時代]

キッシンジャー回顧録『中国』が岩波現代文庫で出たので、読んでみることにした。
大著なので全部読む自信はない。下巻を中心に。といっても、米中和解のはじまりははずせないから、上巻の最後の2章からはじめよう。
少しずつしか読めないので、長い読書メモになりそうだ。中国とつきあうのは体力がいる。はたして、最後まで読み通せるか、はなはだこころもとない。
アメリカと中国が接近するのは、両国がともに困難な状況をかかえたときだった、とキッシンジャーは書いている。アメリカはベトナム戦争、中国は文化大革命で苦しんでいた。
両国はこの苦しみから逃れるために接近をこころみた。毛沢東は遠交近攻策に思いを馳せ、ニクソンは対話をはじめようと決意した。だが、両国のあいだには、それまでの深い溝が横たわっていた。
1965年に毛沢東は『中国の赤い星』の著者エドガー・スノーに、過去15年間、アメリカと中国がまったく意思疎通できなかったのを残念に思うと語っていた。だが、ジョンソン政権はこの記事を無視し、ハノイ政権の背後には中国がいると考え、中国敵視政策をつづけていた。
1969年にニクソン政権が発足すると、毛沢東はさらに一歩踏みこむ。就任演説にアメリカ側の意思疎通意欲を感じたからだ。とはいえ、両国の接触は容易ではなかった。
3月、中ソ国境のウスリー川で、中国とソ連の衝突が発生した。軍事委員会副主席の葉剣英は『三国志演義』に触れながら、蜀が強力な魏と退行するために呉と連携したように、中国はソ連に対抗するため、アメリカと手を組んだらどうかという策を毛沢東に提言した。
いっぽうニクソンはベトナムからの段階的撤退を模索していた。ニクソンはベトナム戦争を終わらせるつもりだったが、かといって単純に敗北を認めるつもりはなかった。新たな国際秩序を構築するため、中国を引きこむことができれば、全体としての社会主義圏の力を弱めることになる。ベトナムで敗れても、冷戦で勝ったことになるのだ。
両国の歩み寄りがはじまる。「毛沢東は関係改善を戦略的責務と受け止め、ニクソンは外交政策と国際的リーダーシップに関する米国のアプローチを再定義する機会ととらえた」と、キッシンジャーは書いている。
国境紛争をきっかけに1969年夏、中ソ関係は緊張していた。中ソ戦争が勃発し、ソ連が中国の核施設に先制攻撃をかける可能性も考えられた。とりあえず衝突は回避された。だが、その後も両国間の緊張はつづいた。
1969年11月から70年2月にかけ、米中の外交官はポーランドのワルシャワで何度も接触をこころみた。しかし、原則論をぶつけあうだけで、その先は一歩も進まない。
対話はなかなか進展せず、1970年5月に途絶えた。そのかんニクソンはベトナムからの米軍の段階的撤退を模索しながらも、カンボジアまで戦闘領域を広げていた。
ニクソンとキッシンジャーは、パキスタン、ルーマニア、フランスのルートを通じて、米中のハイレベルの会談をはたらきかけた。中国側から思わしい返事はなかった。
1970年10月に、毛沢東はエドガー・スノーと新たなインタビューをおこなった。毛沢東は、観光客としてでも、大統領としてでもかまわないから、ニクソンの中国訪問を歓迎したいと語っていた。
雑誌に掲載される前に、毛沢東のインタビュー内容はアメリカ側にも知らされていた。国務省はそれを無視する。1970年12月8日、大統領特別補佐官のキッシンジャーのもとに、周恩来から1通の書簡が届いた。それを届けたのはパキスタン大使だった。その後、ルーマニア経由でも同じメッセージが伝えられた。
周恩来はアメリカ側に、台湾問題について話しあうため、北京に特使を派遣してほしいと提案していた。キッシンジャーは同意する。ただし、その目的は米中間の広範な問題を話しあうためだと返事をだした。
それから3カ月返事がなかったのは、アメリカがラオス南部のホーチミン・ルートにまで攻撃範囲を広げたためである。1971年4月になって、ようやく中国側が反応を示した。
日本で開かれた世界卓球選手権に参加した中国のチームが、アメリカのチームを中国に招待したのだ。いわゆるピンポン外交である。アメリカの選手たちは迎賓館で周恩来に迎えられ、度肝を抜かれたという。
4月末、ふたたびキッシンジャーのもとに、周恩来から訪中をうながすメッセージが届いた。これをオープンにするのは危険だった。複雑な手続きが必要になることに加え、喧々囂々の議論が巻き起こり、すべてが台無しになりかねなかった。キッシンジャーはニクソンと相談し、国務省には知らせないことにした。「ニクソンは北京とのチャンネルをホワイトハウスに限定することを決断した」と書いている。
5月10日、ホワイトハウスは周恩来によるニクソン招待を受諾する。だが、首脳会談を準備するため、事前にキッシンジャーを大統領名代として送る旨、中国に伝えた。こうしてキッシンジャーの中国秘密訪問が実現する。
7月9日、キッシンジャーとそのスタッフは、パキスタン経由で秘密裏に北京に到着した。緊張は感じられず、中国側のもてなしは丁重だった。周恩来との会談は、到着した日とその翌日の2回、迎賓館おこなわれた。1回目が7時間、2回目が6時間だったという。
周恩来について、キッシンジャーはこう書いている。
〈およそ六〇年間にわたる公人としての生活の中で、私は周恩来よりも人の心をつかんで離さない人物に会ったことはない。彼は小柄で気品があり、聡明な目をした印象的な顔立ちで、相対する人物の心の中の見えない部分をも直感する、けた外れの知性と能力によって他を圧倒した。〉
毛沢東と周恩来は補完関係にあった。だが、地位は毛沢東が圧倒的に上で、毛沢東の前では周恩来は異常なまでに慇懃に振る舞った。文革中は自分の意に沿わないことでも、毛沢東にしたがって、淡々と行政手腕を発揮した。ともかくも粛清をまぬかれたのはそのためだ、とキッシンジャーは書いている。
キッシンジャーと周恩来のあいだでは、たがいの考え方や価値観は別として、米中の相互信頼と相互尊重を醸成するため、じっくりと率直な話し合いがなされた。焦点となったのは、台湾とベトナムである。
この時点で、アメリカの中国大使は台北に駐在している。アメリカの外交官はだれひとりとして北京にはいなかった。
北京は「一つの中国」の原則をアメリカが受諾することを求めた。これにたいし、アメリカはその原則を話しあう前に、中国が台湾問題の平和的解決を誓約するよう求めた。
キッシンジャーと周恩来は台湾問題が一挙に片づくとは思っていなかった。棚上げにするほかない。結論は歴史の流れを待つのみ。
〈米国にとっての問題は、「一つの中国」の原則に同意することではなく、統一中国の首都としての北京を承認することを、米国の国内事情に合った時間枠で実現することだった。秘密訪問は、米国が「一つの中国」という概念を段階的に受け入れ、中国がその実行時期については極めて柔軟な姿勢を示すという、デリケートなプロセスをスタートさせることになった。〉
次はベトナム問題である。
周恩来は、中国がベトナムを支援しているのは歴史的な由来があるとしながらも、今後ベトナムに関して、外交面、軍事面でアメリカに圧力をかけたりはしないことを約束した。
2日目の会議で、周恩来はとつぜん文化大革命のことを話しはじめた。文革は共産党を浄化し、官僚機構を打破するため、毛沢東が指示した運動であり、一時的な混乱はあったものの、いまは秩序が回復されたと、周恩来は説明した。この発言をキッシンジャーは「中国が混乱を克服し、それゆえ信頼が置ける国家であること」を示したものと受け止めたという。
周恩来は中国が「ソ連の脅威に対抗する潜在的なパートナー」となりうることをアメリカ側に示した、とキッシンジャーは受け止めた。巧妙なやり方だった。中国がアメリカからの支援を求めたわけではない。中国はあくまでも「自立自存」をつらぬく。ただ周恩来は、両国が共通の利害をもつことを示すことによって、戦略的協力が得られることを示唆したのである。
最後にニクソン訪中についての打ち合わせがおこなわれた。米大統領の訪中希望を知った中国側が招待を表明し、アメリカ側がこれを喜んで受諾するというかたちをとることが確認された。
こうして1971年7月15日、北京とロサンゼルスから同時に、ニクソン訪中が決まったという電撃的発表がなされるのである。
1972年2月21日、ニクソンは底冷えのする北京に到着した。それは静かな訪問で、祝賀ムードとは無縁だったという。中国にとっては同盟国ベトナムを刺激するわけにはいかなかったからである。
ニクソンは中南海にある毛沢東の自宅で、この歴史的人物と会見した。毛沢東はどこに向かうかも知れぬとりとめのない談論をくりだしながら、ニクソンとの間合いをはかり、時に鋭く斬りこんできた。
ニクソンはソ連の話をもちだしたが、毛沢東はとりあわなかった。台湾問題も聞き流してしまう。ただ、ニクソンを歓迎している様子ははっきりとみてとれた。
毛沢東は米中両国間に「戦争状態は存在しない」と話し、「あなた方は自らの部隊の一部を本国に撤退させたいし、われわれの部隊は外国には行かない」と発言した。
さらに毛沢東は、中国にもアメリカと接触することに反対する反動派グループがいたが、やつらは飛行機に乗り、外国に行こうとして墜落したと話した。林彪事件があったことを認めたのだ。
米中関係を実務レベルで促進することがだいじだとも述べた。さらに毛沢東はいささかシニカルな調子で、ニクソンに個人的な好意を示した。「私は右派が好きだ。あなたは右翼だと言われているし、共和党は右派であり、ヒース首相もまた右寄りだ」といわれて、ニクソンはどう思ったのだろう。
結論をあせる必要はないというのが毛沢東の考え方だった。「私のような人間は多くの大砲を鳴り響かせる」が、ほんとうはイデオロギーなんかどうでもよく、「この時間、この日を生きよ」だよ、とキッシンジャーに向かって話している。
ただ、中国がアメリカと戦略的な協力関係を持ちたいと表明したことは間違いなかった。
ニクソンの訪中は5日にわたり、このかん遊覧と対話、晩餐会がつづいた。周恩来とニクソンは毎日午後少なくとも3時間話しあった。晩餐会のあとは、実務者どうしが最終コミュニケの文言を詰めなければならなかった。
ニクソンと周恩来が話しあったのは、米中関係のビジョンと今後の影響についてである。
ニクソンは中国政策の重点を台北から北京に移すことをすでに決意していた。反共主義者のニクソンが中国にきたのは、中国の指導者をアメリカの原則に改宗させるためではない。両国の価値観はことなっている。しかし、たがいの国益を考えれば、米中は戦略的に協力しあえると、とニクソンは率直に周恩来に語った。
ニクソン訪中の成果は、上海コミュニケとしてまとめられた。
コミュニケの骨格は、1971年10月(林彪事件直後)の、キッシンジャーの二度目の訪中で、ほぼまとまっていた。アメリカ側が提示したコミュニケ草案は毛沢東によってうっちゃられ、毛沢東の指示に従って周恩来が中国側のコミュニケ草案を提示した。
そこには強いことばで中国側の立場が述べられ、そのあとアメリカ側がみずからの立場を書くよう空白があけられていた。そして、最後に共通の立場について記す部分があった。
キッシンジャーは驚いた。だが、この異例の方式がいいかもしれないと思い直し、ニクソンに相談しないまま、中国側の方式をのんだ。コミュニケには両国のそれぞれの価値観が表明され、最後に事実上のイデオロギー休戦が告げられることになった。
キッシンジャーによれば、このコミュニケでもっとも重要だったのは覇権に関する条項だったという。
「いずれの側も、アジア・太平洋地域における覇権を求めるべきではなく、他のいかなる国家ないしは国家集団によるこのような覇権樹立の試みにも反対する」
これは米中の共存をはかるとともにソ連の進出をおさえるための宣言だった。この時点では、まさか現在のような米中冷戦がはじまるとは思いもしなかっただろう。
残った問題は台湾の扱いだった。最重要部分は土壇場になって、次のようにまとまった。
〈米国側は表明した。米国は、台湾海峡の両側のすべての中国人が、中国はただ一つであり、台湾は中国の一部であると主張していることを認める。米国政府はその立場に異議を唱えない。米国政府は中国人自身による台湾問題の平和的解決についての米国政府の関心を再確認する。かかる展望を念頭に置き、米国政府は台湾からすべての米軍と軍事施設を撤退するという最終目標を確認する。当面、米国政府はこの地域の緊張が緩和するのに従い、台湾の米軍と軍事施設を漸次減少させるであろう。〉
アメリカは、中国(北京)政府のいう「台湾は中国の一部」という主張に賛同したわけではない。北京と台北の両方の側が、そう主張していることを認識しているというのである。しかも、中国政府が台湾問題を武力で解決することに反対するとの立場は崩していない。
米中国交正常化には、まだもう少し時間がかかる。アメリカは日本に先を越されてしまう。
それでもキッシンジャーは、米中国交正常化を見すえて、こう書いている。
「米中国交回復がもたらした恩恵とは、永遠に友好であるという状態でも価値観の調和でもなく、常に手をかける必要がある世界の均衡が回復されたことであり、さらには、時間が経てばおそらく価値観のより大きな調和が生み出されることである」(もう少しうまく訳せそうだが)
キッシンジャーはいずれ中国が民主化されるだろうと期待を寄せていた。より全体主義化の道をたどるとは想像していなかったのである。
加藤典洋『戦後入門』を読んでみる(2) [われらの時代]

いくらにっくき敗戦国とはいえ、無条件降伏は民主主義になじまない。それなのにアメリカがドイツや日本に無条件降伏を押しつけたのはなぜか。そこには原子爆弾がからんでいた、と加藤は推測する。
戦争末期、アメリカは原子爆弾の開発に成功するところだった。その可能性がみえてきたことが、ルーズヴェルトに強気の無条件降伏をとらせる悪魔の誘惑になっていたのだという。
ルーズヴェルト死後、政権を引き継いだトルーマンは、前大統領の無条件降伏政策を継承すると宣言した。原爆製造計画が最終段階を迎えたことを知らされていた。
原爆は1945年8月6日に長崎に、ついで8月9日に長崎に投下された。アメリカでそのことが発表されたとき、原爆投下は軍事基地を対象にしたものであると強調されていた(広島、長崎は軍事基地ではなかった)。原爆が無辜(むこ)の市民を無差別に殺戮したことも注意深く隠蔽されていた。
トルーマンは日本がポツダム宣言を受けいれなかったため、やむなく日本に原爆を投下したのだと説明した。戦争を早く終わらせ「何千何万もの米国青年の命を救うため」という理由もつけ加えられていた。日本人は卑劣で無法な者たちだという罵詈(ばり)も発せられていた。
その後、トルーマン政権のなかからは、原爆投下にたいする悔恨をもらす閣僚も出てくる。だが、トルーマンはアメリカによる核独占の強気姿勢を崩さず、1947年からソ連封じ込め政策に舵を切っていく。こうして東西冷戦時代がはじまる。
日本がポツダム宣言を受諾し、ふいの勝利が訪れたあと、アメリカ人は歓喜し、そのあと奥深い部分から原爆投下に関する良心の呵責が生まれた。それに反論するかたちで、前陸軍長官のスティムソンは、原爆使用を正当化する。日本上陸作戦を回避し、米軍兵士の100万以上の生命を救うには、原爆使用が選択肢のなかでは「もっとも嫌悪感の少ないものだった」と述べたのだ。そして、この見解が、原爆やむなしというアメリカ人の標準的な理解となっていく。
いっぽう、原爆を投下された日本のほうはどうだったか。日本政府は原爆投下直後、それが戦時国際法に違反するものだという抗議声明を発した。その5日後、ポツダム宣言を受諾し、敗北を認めた。
江藤淳によれば、それは無条件降伏ではなく、統治権はあくまでも日本にあると認められていたはずだという。ところが、アメリカは日本占領をいつのまにかマッカーサーのもとでの直接支配に切り替えていった。すなわち、日本はアメリカに無条件降伏したと解釈したのだ。これによって原爆投下への批判、非難はシャットアウトされることになった。
メディアは言論統制される。アメリカへの批判的報道は認められず、GHQの意向に沿うものへと変わっていく。各都市の大空襲や広島、長崎への原爆投下、占領軍兵士の不法行為についても報道が禁じられた。
加藤によれば、アメリカは原爆投下に後ろめたさをおぼえていた。そのため、アメリカが建前としている民主主義、自由と正義の原則に批判がでてくるのも抑えようとしたのだという。
日本が敗戦国になったのは、まちがいなかった。戦前の価値観はもはや通用しなかった。忠義と戦争と国家主義に代わって、自由と平和と民主主義が戦後の基本的理念となっていく。
原爆投下にたいしアメリカに憎悪を感じた日本人は不思議に少なかった。その無力と沈黙は何に由来するのか。それを象徴するのが、広島平和公園の原爆死没者慰霊碑に刻まれた「安らかに眠って下さい 過ちはく返しませぬから」ということばだった、と加藤はいう。
国民を無茶な戦争に巻きこんだ軍への嫌悪感もあったのかもしれない。だが、そこにはアメリカを批判できないという無力感、ないしはアメリカへの抵抗の放棄が示され、ひたすら未来の平和創造に向けての思いだけがこめられていた。
アメリカが原爆を投下した事実そのものは否定しようがなかった。原爆投下はあきらかに国際法に違反している。しかし、戦後の日本政府はアメリカの立場を擁護し、代弁することに終始する。
1955年にはソ連の原爆実権や、アメリカが前年ビキニ環礁でおこなった水爆実験が世界に衝撃を与えていた。これに抗議して出されたのがラッセル・アインシュタイン宣言である。人類に滅亡をもたらす核兵器廃絶に向け、各国が協定を結ぶよう提言していた。絶対平和主義をめざす世界連邦運動もこれを後押しした。だが、その後、この構想は現実と歯車がかみあわないまま拡散していく。
戦後の特徴は、いやおうなくわれわれが核のもとに置かれているということである。現在の戦後国際秩序が核の抑止力のうえに成り立っていることは、まぎれもない事実だ。ふだんは意識しないけれども、核の管理に失敗すれば、人類は滅亡の淵に立たされる。
核時代がはじまった直後、ジョージ・オーウェルは、現在は二つか三つの国家がスーパー国家になって、「お互いの間で原爆を使わないという暗黙の協定」を結んだうえで、「被搾取階級と人民からことごとく反逆の力を奪ってしまう」時代になったと論じた。
オーウェルは「われわれは、全体的壊滅に向かっているというより、古代の奴隷帝国のような、恐るべき『安定』の時代に向かっているのかもしれない」と論じ、「平和ではない平和」が無限につづく可能性に言及した。
加藤はこのオーウェルの1945年の論説を紹介しながら、「原爆の本質は世界を変える力を人民から奪ってしまうところにある」と論じている。現実の世界は、原爆以後、それを保有する国家どうしの対立と駆け引きによって動いてきたという。
オーウェルはいっぽうで、だれもが自転車のように簡単に原爆をつくれるようになったら、主権国家どうしのバランスは崩れ、世界は一種の野蛮状態になってしまうだろうとも述べていた。科学技術の拡散と進展は、強大国による原爆の独占をむずかしくする。
そんな時代に、はたして諸国間、国民間の信頼関係を築くことができるのだろうか。理想的な絶対平和主義と現実的な国際主義のあいだに立って、解決策を見いだそうというのが加藤の考え方とみてよい。
*
戦後日本は平和憲法にもとづいて運営されてきた。とりわけ憲法9条には、戦争の放棄、軍隊の不保持、交戦権の否定が明記されている。
加藤によると、新憲法制定当時、日本側はまさかアメリカから戦争の放棄を求められるとは思っていなかったという。
連合国側は勝者の立場から、懲罰として、旧枢軸国の武装解除・非軍事化を推進した。そして、その安全保障を、将来生まれる国連の世界警察軍のようなものに委ねようとした、と加藤は解する。
マッカーサーが憲法草案に、日本は紛争解決手段としての戦争を放棄するだけでなく、「自国の安全を維持する手段としての戦争をも放棄」し、「その防衛と保全とを、いまや世界をうごかしつつある崇高な理想に委ねる」と記したのには、国連軍創設の意味合いが隠されていた。
「憲法九条の戦争放棄の規定は、同時進行していた国連の理想実現への努力[すなわち世界警察軍の創設と核の国際共同管理]と、わかちがたく結びついていた」と、加藤はいう。
日本の支配層は戦争放棄条項の押しつけに憮然とした。だが、世論は圧倒的に戦争放棄を歓迎した。それはこれまでつらい戦争を体験しつづけてきた民衆の願いだったからである。
その後、日本は再軍備と憲法改正への動きを経験する。とはいえ、戦後日本の政治を引っぱった基本路線は、吉田茂のいわゆる吉田ドクトリンだった。すなわち「親米・軽武装・経済中心主義」路線である。
ここで加藤は久野収が天皇制の分析に用いた顕教、密教という概念をもちだす。
吉田ドクトリンには、日本は憲法9条をいだく平和主義の独立国家だという「顕教」の顔がある。そのいっぽうで、日本は対米従属のもと軍事負担を最小限にとどめながらら経済大国をめざすという「密教」の顔もあった。日本の戦後政治は、この顕教と密教を使い分けながら、平和主義をかかげ経済繁栄の道を歩んできたというのだ。
だが、そこには内的な矛盾があった。自民党はもともと憲法改正によって日本の交戦権を回復したいという願いをもっていた。吉田茂はそれを封印して、経済ナショナリズムの方向に舵を切った。だが、対米従属をどうするかというのは、いつか浮上してくる課題だった。
吉田が採用したのは、憲法9条を表看板としながら、なし崩しに再軍備を進めていく方向である。それによって、アメリカの要求をいれつつ、自衛隊を発足させ、経済発展の道を追いつづけた。
「吉田政治は経済の発展によってナショナリズムを追求するという新しい手法を見つけだすことで、いわば戦後の懸案である『主権回復』という政治的課題への政治的なアプローチを“凍結”し、先送りすることを通じ、高度成長期の安定と繁栄を実現した」
しかし、日本の経済繁栄がアメリカとの経済摩擦を生むようになると、日本はアメリカの経済的要求にも応えなくてはならなくなり、「対米従属」の問題がふたたび顔をのぞかせるようになった。日本はいつまでもアメリカのいいなりになっていていいのか、という問いかけが生まれてくる。
対米独立を実現しようとすれば、戦前の政治姿勢が強くなり、アメリカとの対立を招く恐れがあるというジレンマを吉田政治は回避した。だが、その深刻な内的矛盾は、次第に抑えきれなくなってくる。
1990年代にはいると、社会党が壊滅し、自民党のハト派が衰退していく。その後、自民党のタカ派が政権を握った。かれらは憲法改正をかかげながらも、実際には日米同盟強化の名のもと、対米従属を強め、ますます矛盾した政策を進めるようになった。
それが日本社会をますますうっとうしく不安なものにしている。
*
憲法9条を手がかりとして、対米従属からの独立をはかる方途がないものだろうか。そう加藤は問いかける。
戦後日本の占領期間が長引いたのは、「民主主義、自由、経済的諸制度の改革」に一定の時間を要したほか、冷戦というもうひとつの要素が加わったからだ、と加藤は書いている。これによって「対共産主義戦略に重点を置いた日本再建」が求められるようになった。
1951年9月、サンフランシスコ講和条約が調印され、同時に日米安保条約が締結された。翌年2月には日米行政協定が結ばれ、これによって日本におけるアメリカ軍の地位と機能が定められた(1960年に日米地位協定と名称変更)。いまも米軍基地は常態化している。
はたして米軍基地の撤廃は不可能なのか。
ナショナリズムによる対米独立路線は脈がない。インターナショナリズム(国際主義)と国連中心主義が局面を打開する唯一の道だ。その最重要のカードになるのが憲法9条だ、と加藤はいう。
加藤は、国際秩序から孤立するのではなく、国際秩序の構築に積極的に関与することで対米自立を成し遂げようと提案する。
ロナルド・ドーアは、日本が国連改革の中心的存在となって世界に貢献すべきだと主張した。日本国憲法の草案が出された1946年2月ごろ、国連安全保障理事会では、国連常備軍のあり方が検討されていた。しかし、米ソ対立が激しくなり、議論は暗礁に乗り上げてしまった。ドーアはこの議論を再開することによって、日本も国連常備軍に加わり、積極的な国連中心外交を担うべきではないかという。
加藤は、このドーアの考え方こそ、日本が平和国家としての誇りをもちながら、対米自立をかちとる方途だと主張する。
安倍政権は「表向きは対米協調、従属を基調としながらも、その実、復古的で国家主義的な方向での『誇り』づくりを、第一義的にはめざしてきた」と加藤はとらえた。だが、その「誇り」は、自画自賛のもので、けっして国際社会から受けいれられるものではない。しかも、徹底従米路線をとる日本はアメリカからもかえってばかにされているとまで加藤は断言する。
日本が誇りを取り戻すには、戦前に復古するのではなく、平和主義に立ち戻ることだ。そのためには、対米従属を脱し、完全な独立国となり、国連中心の外交を積極的に展開していく以外にない。
ドーアは自衛隊の出動は、(1)国境内への悪意ある侵入への対処、(2)国内外の災害救援、(3)国連の平和維持活動ならびに国連直接指揮下における平和回復運動にかぎられると述べている。
加藤はドーアの提案を受けいれる。そのうえで、あらためて戦争放棄の重要性を指摘するのだ。憲法9条は、日本が他国を侵略しないこと、また軍隊によって国民の政治行動を抑止しない(軍隊が治安出動をしない)ことを保証するものだという。
他国からの侵略があれば国を守るのはとうぜんだ。しかし、自衛隊の役割は防衛にかぎられるのではなく、むしろ国連常備軍に加わり、国連の平和維持活動、平和回復運動に参加することだ、と加藤は考えている。自衛隊を国連待機軍と国土防衛隊に分離することも提案されている。もちろん、その前提となるのは、常備軍設立に向けて国連機能を強化することである。
*
次は核問題である。核兵器が現代世界に暗い影を投げかけていることは何度いってもいいたりないほどだ。
核兵器の国際管理は、アメリカ主導のもと国際原子力機関(IAEA)と核拡散防止条約(NPT)によって進められてきた。IAEAは原子力の平和利用促進と軍事への転用防止を目的として設立された。NPTは現状以上の核拡散を防止し、最終的に核兵器を廃絶することを掲げる国際条約である。
現在、日本はNPT条約に加盟しているが、「核兵器製造の経済的・技術的ポテンシャルは常に保持する」としており、万一の場合はNPT条約からの脱退も辞さない構えをとっている。日本は国内的には「非核三原則」を唱えつつも、現状ではアメリカの「核の傘」に安全保障を委託し、そのうえで万一の場合も想定している。核抑止政策が日本の防衛政策の基本であって、核廃絶ははるかに遠い目標といえるだろう。
2009年にプラハで、アメリカのオバマ大統領は核兵器の存在しない社会の実現に向けて努力すると演説した。しかし、いまや核兵器の所有国は米ソ2大国からはじまって、5大国(米露中英仏)へ、さらにインド、パキスタン、北朝鮮、イスラエルまで加えた9カ国へと広がっている。さらにイランも核兵器開発を進めているとされる。核軍縮交渉は進展していない。
加藤は人類は残念ながら、もはや「核のない世界」に戻れないという。核兵器は「廃絶」してもなくならず(それはいつでも復元できる)、原子力についても、もはやなかったことにはできないからである。好むと好まざるにかかわらず、人類は核とともに生きる道を選ばなくてはならない。
核兵器のない世界は可能なのか。それができないとしても、「核兵器行使のない世界」を実現することはできるのではないか。
核兵器の使用を思いとどまらせる核抑止論は、ほんらいは核戦争を防ぐための方策として考えられていた。けっして、核廃絶論と相容れないわけではなかった、と加藤はいう。
「廃絶」か「抑止」か、「完全ゼロ」か「国際管理」か、といった二者択一を前にして、核に関する議論は停滞している。
ここで加藤はふたたびロナルド・ドーアの議論を紹介する。
ドーアは、核抑止論は、核兵器から身を守るためには核兵器をもたねばならないという矛盾した論理を内包しているという。核保有国による核独占のもとで平和を構築しようというNPT体制は、いまやマイナス面のほうが多く、新しい体制に移行すべきだというのがドーアの主張である。
ドーアはNPTに代わって、最終的には世界政府による核兵器の国際管理を打ち出す。ドーアが提案するのは、核不拡散ではなく核拡散にもとづく核の国際管理体制だ。
それによると、どの国も核を保有できるが、核を保有しない国は、核を保有する少なくとも三カ国にたいし「核の傘」を求めることができる。それにより、核抑止体制はリゾーム状になり、安全保障体制が重層化されていく。そのうえでIAEAは、核兵器の監視、査察システムを強め、最終的には国連が常備配備ミサイルをもつ平和部隊をつくるというのだ。
ドーアの構想のみそは、従来の核保有国の戦略的優位性を減衰させてしまうことにある。加藤は、日本は非核三原則の堅持するとともに、NPTに代わる新たな「国際核管理条約」を提唱すべきだという。
核の問題はむずかしい。ドーアの案はユニークだが、はたしてそれによって核の国際管理がうまくいき、人類絶滅の危機が遠のくかどうかはわkらない。いずれにせよ、核の国際管理が人類の大きな課題であることを、加藤はあらためて示したといえるだろう。
*
そして、最後に米軍基地をどう撤去するかという問題がでてくる。
日本の米軍基地は74%が沖縄に集中しており、いまも日本には約5万人の米兵が駐留している。駐留米軍にたいしては地位協定が適用され、いわば占領が永続化しているだけではない。基地問題は日本の主権にかかわるやっかいな問題なのだ、と加藤は指摘している。
加藤は、日本が米国の世界戦略に積極的に加担、協力する近年の自民・公明連立政権の姿勢に危惧を示している。憲法9条は有名無実化されようとしている。安倍政権以降、自民党はますます復古型国家主義への傾斜を強めた。
しかし、復古型国家主義のもと対米従属を強めるというのは、それ自体が矛盾している。めざすべきはそうした方向ではないはずだ。
加藤は、「対米自立」して「誇りある国づくり」をおこなうため、「平和主義を基調に新たに国際社会に参入する」方向を選ぶべきだという。
敗戦後、日本にとってはアメリカに従属する以外に選択肢はなかった。しかし、現在、日米同盟は日本の国益にとって、ほんとうに有用なのかどうかわからなくなっている、と加藤は疑問を投げかける。
状況は変わった。冷戦が終わり、21世紀にはいると、アメリカが衰退し、中国が台頭してきた。日本経済は不振におちいり、日本人は自信を失い、漂流しはじめた。
沖縄にとって、米軍基地の負担は限界に達している。日本にとっては、国連との関係を強化し、もっと多角的な外交を展開していくほうが政治・経済の安定につながるのではないか。
そのためには、まず米軍基地を撤去することが先決である。その鍵となるのは憲法9条の改定だ、と加藤はいう。
憲法9条を考えるにあたって、戦争放棄と自衛隊は矛盾しているようにみえるが、どちらかをやめる必要はない。ふたつは相互補完の関係にあるとみてよい。
そして、いま露呈してきたのが、憲法9条はじつは米軍基地と相互補完の関係にあったという現実である。
日本では2009年に民主党政権が成立し、米軍基地の移転をアメリカに要請した。だがアメリカはこれを拒否し、民主党政権を退陣に追いこんだ。
もはや護憲のままでは、この憲法を制定したアメリカに立ち向かうことはできない、と加藤はいう。むしろ憲法を改正し、それを使って米軍基地の撤廃を求めるべきではないか。
矢部宏治は憲法9条2項の改正を提言している。「必要最小限の防衛力はもつが、集団的自衛権は放棄する」ことを加え、さらに「今後は国内に外国軍事基地をおかない」と明記べきだという。加藤はこの矢部方式に賛同する。
ただし、加藤は将来の方向として、あくまでも国連軍の創設にこだわる。日本国憲法が制定されたとき、9条2項に「戦力と交戦権の放棄」がうたわれたときのことを思いだすべきだという。あのときは、各国が交戦権を新たに創設される国連軍に移譲することが想定されていた。
必要最小限の防衛力をもつことはだいじかもしれない。しかし、より重要なのは「国の交戦権は、これを国連に移譲する」ことだ。そのうえで、憲法に「今後、外国の軍事基地、軍隊、施設は、国内のいかなる場所においても許可しない」と追記すべきだと提案している。
この憲法改正が実現すれば、とうぜん米軍基地は撤去される。
自衛隊の一部は国連待機軍と位置づけられる。日本は核をもたない。そして、アメリカとは対等な友好関係を結ぶことになるだろう。
安倍路線の問題は、復古的な日本中心主義を唱え、戦後の国際秩序から逆行していることだ、と加藤は指摘する。それでは、とても日本が国際社会のなかで「名誉ある地位」を占められそうもない。問題は、国際主義の方向に、日本人の「誇り」を作りあげていくことだ、と加藤はいう。
現在の対米協調路線は、集団的自衛権にしても安全保障法制にしても、むしろアメリカへの従属を強めるもので、むしろ反米的なフラストレーションをためこんでしまっている。また対中敵視政策を基本としているため、常に国際的緊張を高めている。
アベノミクスという金融緩和策も、少子高齢化や産業空洞化、財政問題を見すえていないために将来の不安に応えたものではなかった。自民党政権は、対米協調を至上命題としているために、将来をみすえた柔軟な経済政策をとれないままでいる。
加藤は自分は平和的リアリズムの立場に立つと述べている。上から目線の平和主義ではなく、草の根の平和主義である。理念をもちながらも現実を見失わない考え方だ。
平和的リアリズムは国家主義や軍の膨張を防ぐブレーキとしてはたらくだけではない。国際連合の強化、再編成をめざすものである。その中心に位置するのは憲法9条の平和理念だ。いまは直進の「護憲」ではなく「左折の改憲」が必要なのだ、と加藤は述べている。
加藤の提案が実際にどこまで力をもつかはわからない。奇策と思えるものも、理想論すぎると思えるものもある。ただ、すべては構想力からはじまるのである。対米自立にしても米軍基地撤廃にしても核の管理にしても、われわれはそのことをふだん意識することはあまりない。だが、それらは現にそこにある問題なのであり、すべてはこうした問題を問題としてとらえ、それを変えていく構想力をもつことからはじまるのである。日本ははたして戦後を卒業することができるか。それが加藤の『戦後入門』が投げかけた問いだったといえる。
加藤典洋『戦後入門』を読んでみる(1) [われらの時代]

戦後とは何か。いまも戦後はつづいているのか。ある意味では、そうだともいえるし、別の意味では、戦後はすでに終わっているともいえる。
それは日本でもヨーロッパでも同じである。戦後というからには戦前があるはずで、日本の場合、戦前というのは、第一次世界大戦後から第二次世界大戦までのあいだ、すなわち戦間期を指すとみるのが妥当だろう。あるいは、もっと枠を広げて、敗戦までの時期を戦前と呼んでも許されるのかもしれない。その期間は30年に満たない。
すると戦後はいつまでということになるのだろう。2020年時点で、戦争が終わってから、すでに75年以上が経過している。いやな言い方をすれば、戦後は戦間期とも戦前とも理解できるのだから、次の戦争がはじまるまで、戦後はつづくことになる。すると、戦後は未確定の歴史区分ということになる。はたして、戦後はいつまでつづくのだろう。いつまでもつづいてほしいという願いはある。いっぽう、歴史は残酷で、いつまでその願いがつづくかわからないとの悪い予感もうごめく。
2020年が戦後75年にあたるとすれば、敗戦から75年前は1870年である。まさに明治維新のころ。この尺度をくらべると、いまの戦後がいかに長いかがわかるだろう。大きくいえば、このふたつの時代は、戦争と平和の時代、明治憲法体制と新憲法体制の時代と区分けすることもできる。
しかし、ぼく自身の感覚からすれば、日本の小さな戦後は1970年代はじめに終わったという気がする。日本が独立を回復し、日米安保条約が結ばれ、経済が復興し、東京オリンピックがあって、日韓条約が締結され、万博が開かれ、沖縄が返還され、日中国交回復が実現する。もちろん万全ではないけれど、これによって、アジア・太平洋戦争の処理がいちおうすんだ。その時点で、小さな戦後は終わり、不安に満ちた新しい時代がはじまったといってもよいのではないか。
だが、小さな戦後はともかく、大きな戦後は終わっていないというべきだろう。それは日本国憲法(新憲法)と日米安保体制によって枠づけられる戦後である。この枠組みは、それぞれの内容ばかりか、構造からしてもねじれている。そのねじれた関係が強く意識されたのは、昭和が終わったときだといってよいだろう。いまもその大きな戦後をどう終わらるか、どう超えるか、あるいはどう維持するかをめぐって、日本国内の論議はばらばらに割れている。加藤典洋(1948〜2019)の『戦後入門』は、入門という気楽な体裁をとってはいるものの、そこに一石を投じた問題作だった。
少しずつ読んでみたい。
対米従属を終わらせて、戦前に戻るのではなく、憲法9条を基軸とした「新しい戦後」をつくろうというのが、加藤典洋の基本的な考え方といってよいだろう。
だが、そう言い切れば終わりというものでもない。だいじなのは、そう考えるにいたった経緯を知ることであり、それによって、問題の奥行きや複雑さがみえてくるのである。
1985年に刊行された『アメリカの影』(1985)で、加藤は戦後日本の対米従属問題を取りあげた。対米従属の背景には、1951年のサンフランシスコ講和条約が日米安保条約とセットになっていたことがある。それによって、1952年に日本がふたたび独立をはたすとともに、米軍の駐留が永遠に認められることになった。
しかし、対米従属の現実は高度成長とともに、いわば後景にしりぞき、「内面化」されていった、と加藤は書いている。内面化とはアメリカとの親和が進んだという意味である。アメリカは抑圧者ではなく、あこがれの対象と化した。それにいらだったのが三島由紀夫であり江藤淳だった。
江藤にいわせれば、戦後とは対米従属を見て見ぬふりをする虚妄の時代にほかならなかった。だが、江藤は左翼のようにヤンキー・ゴーホームとはいわない。アメリカとの友好関係なしに、日本はやっていけないことを知っていた。知ったうえで、日本の自尊心を取り戻せと主張した。
その象徴となるのが、憲法9条2項を削除し、日本の交戦権を回復することだと思われた。それは、かならずしも日本が戦争への道を歩むことを意味しない。むしろ憲法改正によって日本は主権を回復し、アメリカと対等な同盟関係を結ぶことができるというのが江藤の考え方だった。
そのとき、安保条約と地位協定は廃棄されなければならない。駐留米軍にも出ていってもらわなければならない。だが、アメリカはこの要求に簡単に応じるだろうか。もし応じなければ、日本は核武装による自主防衛に踏み切らざるをえない。そうなると、これはとうぜん親米路線から反米路線への転換となり、日本は国際的に孤立するほかない。戦前への逆戻りである。そのジレンマをかかえたまま、1999年に江藤は自死することになる。
1997年に出版した『敗戦後論』で、加藤は日米関係のねじれについて論じた。対米従属のフラストレーションを解消しようとすると日米関係が緊張し、それを無理やり解決しようとすると日本が安全保障上、経済面で深刻な事態におちいるのはなぜか。
そこには敗戦国ならではのねじれがある、と加藤はみた。日本であれ、ドイツであれ、第二次世界大戦の敗戦国は、戦後、国のかたちや価値観において、戦前との大きな断絶を経験した。戦前の価値観はもはや国際的には受けいれられなかった。
そのため戦死者とどう向き合えばいいのかが、よくわからなくなった。少なくともかれらを英雄とみることはもはやできなかった。日本が中国を不当に侵略したこと、フィリピンなどで住民を無視して戦闘行為をくり広げたことはまちがいない。すると、日本の戦死者は「誤った侵略戦争の先兵」だったということになってしまう。
多くの犠牲をもたらした近隣諸国の人民に謝罪すべきことはいうまでもない。だが、日本人の戦死者を「侵略戦争の先兵」として、切り捨てることは、あまりにも非人間的ではないか。もちろん、あの戦争は間違っていなかったとして、戦死者を称揚するのも、侵略先の人びとへの想像力や配慮を欠いている。
加藤は『敗戦後論』で、「自国の戦争の死者たちにしっかり向き合い、弔うあり方を作り出したうえで、それを土台に、他国の死者、侵略国の人々に謝罪する、というみちすじがありうるはずだ」と考えた。日本人は事実をみずからあきらかにしたうえで、何べんも何べんも、相手国から受けいれてもらうまで謝罪をくり返さなければいけない。それは自虐的などということとはまったくちがう、と書いている。
憲法も占領軍から与えられたものだった。だが、加藤にいわせれば「押しつけられた」憲法が「よい憲法」だったのだ。問題はそれをどう「わがもの」にするかがわからなかったことである。ここから、護憲論と改正論がでてくる。とりわけ憲法9条の扱いが問題になった。
護憲論の立場は、社会が再軍備化していく歯止めとして憲法九条を使おうというもの。いっぽう、保守派、国家主義者は、憲法9条は日本の武装解除を永久化しようとするもので、国家の基本的権利の侵害にあたるから、これを改正すべしというものだった。このふたつの考え方にたいし、加藤は国民による「選び直し」によって、憲法9条を強化することを提言する。その内容については、あらためて触れる。
*
戦後を語るには、世界大戦が何であったかを知らねばならない、と加藤はいう。
敗戦は日本人の考え方を変えさせ、これまでの皇国思想や八紘一宇に代わって、民主主義と平和思想を日本人に植えつけることになった、と加藤は書いている。
その結果、まず「勝者への模倣」が生じた。鬼畜米英からアメリカ礼賛へ、そのあと陶酔感からの覚醒がおこる。いっぽう戦争末期の突然の参戦と、その後のシベリア抑留により、ソ連は怨嗟の的となる。原爆投下にたいしては、不思議にアメリカへの抗議はわいてこない。
加藤は敗戦国のパターンとして、「勝者への模倣」のほか、文化的・精神的優位性の強調、再生への希望、勝者を越えようとする欲求、復讐と報復などを挙げている。だから、戦後、日本人はがらりと変わったといっても、その内実はなかなか複雑だったと指摘している。
それでも日本の戦後が特異なのは、戦前と戦後に価値観の断絶があることだ、と加藤はいう。もはや復讐と報復は現実的ではなくなってしまった。
20世紀のふたつの世界大戦が大きな意味をもつのは、それが旧来の二国間紛争とちがい、同盟戦争、すなわち国際秩序や国際社会のあり方をめぐる戦いとなったことである。しかも、それはナショナリズムに媒介される総力戦の形態をとった。理念とイデオロギーをめぐる戦争でもあった。
第二次世界大戦はイデオロギー的には自由民主主義と国家社会主義の二項対立ではなく、それに共産主義を加えた三派鼎立(ていりつ)に近いものとなった。だが、それはたぶんに後付けによる説明である。実際の戦争は国益からはじまっている。それが最終的には、自由主義陣営の米英などと社会主義ソ連の「連合国」と、ファシズム陣営の日独伊三国、すなわち同盟国の戦いとなった。
米英二国は1941年8月に大西洋憲章を発表し、戦争目的を発表した。この憲章はウィルソンの平和14カ条を踏襲し、自由主義と領土不拡大をうたったものだったが、そこにはナチ暴政の最終的破壊がかかげられていた。これにたいし、日本、ドイツ、イタリアの同盟国は、それぞれの思惑でばらばらに戦っていた。共通の理念、大義というものはなかった。
三つ巴の戦いが「米英ソ」対「日独伊」になるか、「米英」対「日独伊ソ」になるかは紙一重のところだった、と加藤は書いている。だが、ヒトラーによるソ連攻撃とルーズヴェルト米大統領によるソ連引き込みが、ソ連を連合国側に引き寄せることになる。実際、ユーラシア大陸にまたがるソ連というカードがなければ、連合国がドイツと日本を打ち破るのは容易でないと思われていた。
イデオロギー的にいえば、自由主義と共産主義を定義するのは簡単だった。しかし、ファシズムとは何かを定義するのはむずかしかった、と加藤はいう。
日本とドイツ、イタリアでは国柄がまるでちがっており、戦争目的も異なっていた。ドイツではアーリア人種の優越性とユダヤ人排斥が語られた。イタリアは英米中心の国際秩序に異を唱え、ローマの名誉にもとづく団結が叫ばれた。日本が掲げたのは、大東亜共栄圏という新秩序の構築だった。それが民主主義とファシズムの戦いと総括されるようになったのは、むしろ戦後になってからだという。
日露戦争の勝利によって、日本はアジアの有色人種国の代表として、国際社会に加わった。第一次世界大戦後には、国際連盟常任理事国にも選ばれる。だが、ヴェルサイユ会議で日本が提案した人種差別撤廃条項は否決された。それでも、この提案は世界史的にみて大きな意義があった、と加藤は述べている。
太平洋戦争(日本での名称は大東亜戦争)がはじまると、日本は「東亜新秩序」建設構想をかかげた。1943年11月には大東亜会議が開かれ、大東亜共同宣言が出された。内実をともなわなかった(むしろウソだった)とはいえ、この宣言でアジアの解放と人種差別の撤退という理念が打ち出されたことは、けっしてちいさくない、と加藤はいう。米英の大西洋憲章には、植民地解放の理念が語られていなかったからである。
加藤によれば、「[第二次世界大戦は]『もてる国』の既成の秩序に『もたざる国』が新秩序建設をめざして挑戦した帝国主義的な従来型戦争」にほかならなかった。だが、それが「自由民主主義とファシズムのあいだの戦い」とみられ、「正しいイデオロギーが誤ったイデオロギーを成敗したという物語に、成形し直し、仕立て直」されたのだ。それを確認するドラマが、ニュルンベルク裁判であり、東京裁判であったという。
戦後の国際秩序の土台をつくったのはアメリカである。枢軸国にたいして連合国が勝利したといっても、米英ソのうち、実質的な勝者はアメリカにほかならなかった(ソ連が東欧まで支配権を拡大したという面はあるが)、と加藤はいう。原爆の開発と投下、独占が、アメリカに強大さをもたらしていた。
そのあと、すぐに冷戦がはじまる。
戦争末期、連合国の戦争理念はすでに劣化していた。アメリカは日本に問答無用の無条件降伏をつきつけ、それを日本が黙殺すると、広島、長崎に国際条約違反の原爆を投下し、日本の敗戦後、ただちに東京裁判を開いて、「人道に対する罪」と「平和に対する罪」で、戦争犯罪人を裁いた。
加藤はこう書いている。
〈連合国対枢軸国という対決構図は、このうち、枢軸国側の劣化を激しく強調し、「悪」と断罪することで、米英の劣化とソ連の劣化を見えにくくする効果をもっていました。国際軍事裁判は、たとえばニュルンベルクでは、ドイツ軍の悪を強調することでカチンの森のソ連軍の犯罪を隠すのに役立ち、東京では、日本軍の残虐非道さを強調することで原爆投下の「大量殺戮」を見えにくくするのに力を発揮しました。〉
ニュルンベルクと東京での裁判は、「文明」の名のもとに敗者の「悪」を裁く「裁判劇」にほかならなかった、と加藤はいう。しかも、東京では最初から昭和天皇が免訴され、世界征服をもくろんだとして軍部のみが裁かれることになった。
アメリカ主導でつくられたこうした作為的理念が、のちにほころびをみせてくるのが、戦後という時代だった、と加藤はとらえているようにみえる。
結論を出すのはまだ早い。もう少し、先を読むことにしよう。
小榑雅章『闘う商人 中内功』を読む(3) [われらの時代]
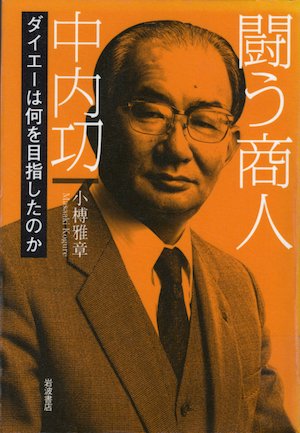
小榑雅章によると、中内には、おれは中内功だ、天下の中内功だという気持ちが常にあったという。それは虚勢にもつながるが、中内が社会的貢献への強い意欲をもっていたことも示している。
多忙な中内が、中曽根内閣のもとで臨時教育審議会(臨教審)委員を引き受けたのもそのためかもしれない。任期は3年だった。臨教審の審議は1984年9月からはじまり、1987年3月に最終答申が出されて終了した。その会議に中内は130回出席している。
臨教審には4つの部会が設けられていたが、中内が加わったのは「21世紀を展望した教育の在り方を考える」という第一部会である。
中内は、教育の画一性、硬直性、閉鎖性の打破を唱えて、教育界の壁を切り崩そうとした。だが、小榑によると、自民党と文部省は、あくまでも自由化と個性主義に抵抗した。中内の唱えた9月入学案もあっさりと葬り去られてしまう。教育環境の人間化というテーマも、生煮えのままで終わってしまった。
次に中内が向かったのが経団連である。経団連にはいろうとしたのは、経済界に第3次産業の重要性を思い知らせようとしたためだったという。中内には第3次産業こそが国を支えているのだという自負があった。
とはいえ、経団連は財閥系の企業が中心の秩序ある集団で、中内のような野人は平会員になれても、それ以上は認めてもらえない。しかし、努力の末、1988年に中内は広報委員長の座を勝ちとる。
だが、と小榑はいう。
「中内さんは、臨教審が終わる1987年から経団連の事業や会議に注力するようになり、1988年から広報委員長に就任し、ダイエー丸の舵取りは疎かになっていった」
それでも、まだ当時はバブル経済のさなかで、ダイエーは順調に発展しているように思えた。そのころ、中内はダイエーの天皇になっていた。
1988年4月、中内は私財30億円を投じて、神戸市西区の学園都市に流通科学大学を開学した。実現まで構想から9年かかっている。
前評判はよかった。優秀な教授陣もそろった。しかし、資金繰りをし、学生を募集し、寄付を集め、大学が軌道に乗るまで、事務局長を務めた小榑の苦労は並大抵のものではなかった。だが、そのかいあって、流通科学大学は現在も「産業界に開かれた大学」として存続している。
中内は新幹線・新神戸駅周辺の新神戸オリエンタルシティ建設にもかかわた。それはダイエー・グループが、新神戸駅周辺に新神戸ホテル(SKH)、オリエンタル・パーク・アベニュー(OPA〔ショッピングモール〕)、さらには神戸オリエンタル劇場までつくろうという巨大計画で、1986年に着工し、88年に完成した。
だが、大失敗に終わった。
「『よい品をどんどん安く、より豊かな社会を』のダイエー憲法では、オリエンタルシティの経営はむずかしい。私は手を出してはいけない世界だと思った」、と中内の身近にいた小榑は書いている。
さらにダイエーはプロ野球にも手をだし、南海ホークスを買収した。
中内は野球に関心が深かったわけではなかった。ショートとサードの区別もわからなかったほどだという。
それでも南海ホークスを買収したのは時の勢いというものだろう。1972年に西鉄がライオンズを手放して以来、九州にプロ野球球団の拠点球場はなくなっていた。
中内がホークスを買収し、福岡に拠点をおこうとしたのは、九州にプロ野球球団を復活させようとしたこともあるが、中内が手薄な九州にダイエーの店を展開したいと考えていたためでもある。
南海ホークスは1988年に福岡ダイエーホークスと名前を変え、福岡に拠点を移した。1993年には博多湾に面する福岡市百道(ももち)に開閉式のドーム球場が完成し、大規模な複合施設とホテルもつくられた。
だが、この大きな買い物のつけは、ダイエーグループのうえに重くのしかかった、と小榑は書いている。
1990年に経団連副会長に就任したのもつかのま、94年夏に、中内は経団連をやめると言いだす。
バブル崩壊の影響が目に見えて大きくなっていた。いっぽう、経済のIT化、ソフト化が進展していた。それなのに財界は相変わらず重厚長大産業と、輸出最優先に走っている。そのことが中内には気に入らなかった。
バブルがはじけたのは1990年1月のことである。
その直前、ダイエーの株価は1985年9月の3倍、3万8957円に達していた。しかし、それをピークにして株価の大幅下落がはじまる。
バブル崩壊は、土地資産の暴落をともなった。
日本の土地資産は1990年末には2456兆円に達した。それが2006年末の1228兆円と半分になった。土地価格高騰の背景には銀行の過剰な貸出があったが、その貸出はまさにあぶく銭と化した、と小榑は記している。
多角経営を進めるダイエーは、神戸のオリエンタルシティでも福岡のツインドーム建設でも、銀行から多額の借金をしていた。しかし、本体の利益がでていたことから、バブルが崩壊しても、借金も何とかなるだろうとたかをくくっていた。
ダイエーの事業はチェーンストアを増やすことで成り立っている。店舗増によって売上が増え、購入した土地の代金も上昇し、その土地を担保にして、銀行から資金を借りて、また新規出店をめざすという拡大循環がダイエーの成長を支えてきた。
〈つまり、ダイエーの出店計画は、基本的に土地が値上がりすることを前提に成り立っている。土地が値下がりすることは考えていない。もし値下がりすると、土地の価値が下がり、価格がどんどん下がるが、借入金も利息も変わらないから、実質安い土地に高い金利を払い続けることになる。借金して土地を購入すれば損が増えることになり、ダイエー全体でみると、膨大な損失になってくる。そうなると、次の出店ができなくなるから、既存店の売上げが増えないかぎり、全体の利益も停滞か減少になる。〉
金利負担が増えていくと、ダイエーは次第にやりくりがつかなくなってくる。
そこに1995年1月、阪神淡路大震災がやってくるのである。
「この阪神大震災でのダイエーの活動は、賞賛に値する」と小榑は書いている。中内は陣頭指揮し、迅速に必要な物資を確保し、大震災に対処した。
しかし、この震災でダイエーの被害は大きかった。7店舗が大きく壊れ、、そのうち4店舗が全壊だった。
ローソンを除いて、阪神間でダイエー・グループは32店を展開していた。だが、震災後2カ月たっても、12店が営業できない状況だった。直接の被害額は400億円から500億円にのぼった。
けっきょくダイエーはそこから立ち直れなかった。
バブル崩壊以降、国民の消費支出は前年度マイナスに転じ、それに応じるかのようにダイエーの売り上げも停滞から減少への道をたどっていた。
必要な生活用品をすべてそろえた日本型のスーパーのかたちをつくりあげたのはダイエーだった。しかし、この日本型GMS(General Merchandising Store)が、1990年代ごろから、主にロードサイドに店を構える家電専門店、洋服や子供服の専門店、薬・化粧品の専門店、ホームセンターなどに押されるようになった。
多くの主婦が、みずから車を運転して、少し遠くても、もっと品揃えのいい安い価格の店で買い物をするようになったのである。
郊外のロードサイドの専門大店をカテゴリーキラーと呼ぶらしい。ダイエーなどの市街地の大規模なスーパーは、こうしたカテゴリーキラーの店に少しずつ市場を奪われていく。平日、客がはいるのは地下や1階の食料品フロアだけで、洋服や雑貨を扱う残りの2階から5階までの階はがらがらということもめずらしくなくなってくる。
そうした状況にもかかわらず、中内はあくまでも強気で、規模の拡大をめざした。赤字となったスーパーを合併して、店舗数を増やす。各地の郊外に30店以上も、大きな倉庫のようなセルフ方式のハイパーマーケットをつくったりもした。
だが、いずれも失敗する。安さとセルフ方式だけではもたなかった。「消費が飽和してきたときに、新たに売れる商品を開発する能力は、ダイエーには乏しかった」と、小榑は記している。
中内功の指揮する巨大艦は、容易に方向を転じることができなかった。加えて、かれは最後まで自分のつくった会社を自分で経営することにこだわっていた。
1998年、ダイエーは創業以来、はじめての大幅赤字を計上する。連結負債は2兆円を超えていた。ダイエーは多くのものを売って身を軽くしようとしたが、負債額はさほど減らなかった。
1999年、中内は退任し、社長を鳥羽副社長に譲り、みずからは会長職に専念することになった。
この年、4800億円の事業売却と3000人の人員削減が発表される。
2000年には鳥羽社長に不明朗な株取引があったことが発覚、中内の最高顧問就任が発表されるが、もはや指導力を発揮することはない。
翌年、中内は取締役を退任し、ダイエーから完全に離れることになった。
ダイエーは2004年に産業再生法の適用を受け、実質的に幕を閉じた。
中内が死去するのは2005年9月19日のことである。83歳だった。
〈中内さんは、家屋敷も家財もみんな失いました。さばさばした、元の千林に戻っただけや、と言って笑っていましたが、その無念さは計り知れません。〉
小榑雅章は「あとがき」にそう書いている。
小榑雅章『闘う商人 中内功』を読む(2) [われらの時代]
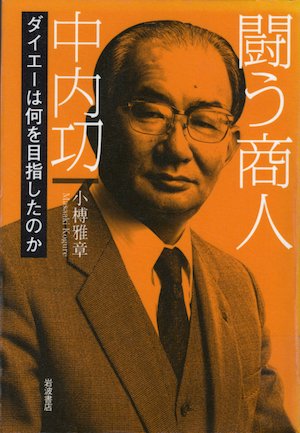
ナショナル(松下電器)の家電製品は評判がよかった。しかし、東芝や日立、三菱が値引きに応じるのに、ナショナルはがんとして応じなかった。
ナショナルにはナショナルなりの言い分がある。松下幸之助は製品価格はメーカーが決めるものだという信念をもっていた。みずからがつくりあげてきた系列の販売会社、代理店を守りたいという思いも強かった。松下グループの共存共栄をはかるのが、松下の願いだった。
しかし、それでは消費者はどうなるのか。高い商品を安く買えるものなら、安く買いたいのではないか。その強い思いこそが、中内の安売り哲学を引っぱってきた。
けっきょく、ダイエーとナショナルの闘いは30年にわたってつづくことになる。
1964年10月、松下電器はダイエーにたいする出荷停止処分を決めた。それでもダイエーは現金問屋からナショナルの電気製品を買い集め、売り場に並べた。
これにたいし松下電器側はダイエーの売り場に並んだ自社製品を購入し、それを分解してロットナンバーからその製品を売った販売業者を特定し、取引停止とした。
すさまじい闘いがはじまっていた。
ダイエーは公正取引委員会に提訴した。1967年7月、公取委は独占禁止法違反にあたるとして松下電器がダイエーに商品を供給すべきだと勧告する。だが、松下電器はこの勧告を拒否した。
松下電器は松下幸之助のリーダーシップのもと、その傘下にナショナルの製品だけを扱う販売会社と代理店からなる独自の販売システムを築いてきた。
いわば松下王国である。製品の値引きはしない。本社の決めた定価をつらぬくことによって、本社、販売会社、代理店がそれぞれまっとうな利益を確保し共存共栄をはかるというのが、松下幸之助の哲学だった。
松下と中内の対立は、製品の価格決定権を握るのは生産者かそれとも消費者かという問題でもあった。
中内は価格決定権を消費者に取り戻すことをスローガンとしてかかげたが、松下にしてみれば商品価格が安定してこそ、企業の存続が確保され、ひいては消費者にも利益がもたらされるのだ。
抗争はとどまるところを知らなかった。ナショナルとダイエーの闘いは、1989年に松下幸之助が亡くなったあともつづく。
だが、最終的に勝利したのはダイエーの側だったといわねばならない。30年戦争を経て、松下電器はダイエーにも正式に商品供給を開始するようになった。
そのかん、ダイエーは破竹の勢いで成長拡大をつづけていた。1970年にダイエーの店舗数は58店、売上は1436億円に達した。1971年にはグループ全体で売上は2000億を突破、社員数も1万人を超え、1万1873人となった。そして、東証一部に上場した1972年8月には、売上が三越を抜いて、小売業日本一となった。
さらに小榑はこう書いている。
〈創業が1957年、大阪の片隅で始めた30坪のドラッグストアが、それからわずか22年後[1980年]には、売上高1兆円、小売業では日本一の大企業に駆け上がったのである。こんな例はほかにはない。当時は、今太閤と囃(はや)されたほどである。〉
1980年に売上が1兆円を突破したとき、中内は5年後の1985年には4兆円を目指すと豪語した。だが、それが実現することはなかった。1984年の売上は1兆2266億円にとどまっている。
日本経済の成長時代が終わろうとしていたのだ。
ダイエーの急成長は高度経済成長と重なっている。それは「国民の可処分所得がどんどん増えて、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、掃除機などの家電ブームが起こり、マイカー、マイホームと、消費者の購買意欲が極めて盛んだった時代」だ、と小榑はいう。
〈GNP(国民総生産)は、60年から78年まで連続19年間ずっと前年比10%以上(名目)の成長を続けたのであった。こんな好景気の時代は、まさに神武以来のことである。その大きな上昇気流に、いくつものスーパーが乗って拡大していった。イトーヨーカ堂もジャスコも西友も一緒である。/しかしその中でも、ダイエーの伸張率はずば抜けていた。なぜか。それは一に中内さんである。中内さんのたぐいまれな意志と意欲とぶれない主義主張、指し示す方向が正しかったのだ。〉
だが、1980年代にはいると、逆風が吹きはじめる。
すでに1974年には、いわゆる「大店法」(1978年にも改正)が施行されていた。地方に大型スーパーが進出する場合は、地元の合意と、地元小売業者との調整が求められるようになっていたのだ。とうぜん、それに反対する商店街が多く、スーパーの規模についても規制がかけられた。
それでもスーパーの出店数は増えていったが、次第に新規出店数は減らないわけにはいかなかった。
ダイエーのようなスーパーは増えた店の数だけ売上が伸びる仕組みになっている。そのため、大店法による出店規制は、チェーン展開にもとづく売上増に、次第にブレーキをかけるようになっていく。
加えて石油ショックである。
スーパー業界にとっては1973年よりも1979年の石油ショックのほうが、経済への打撃が深刻だった。スーパーだけではなく、日本経済全体がそうだったろう。
人びとはものを買わなくなった。給料の伸びも止まった。実質消費支出は1980年がマイナス0.6%、81年がマイナス0.8%となっている。
高度成長がすぎたころ、1980年の家庭経済がどんな様子だったか、小榑はこう書いている。
〈日本の家庭の電化製品の普及率は、電気冷蔵庫は99%、掃除機は96%、洗濯機は99%、石油ストーブは92%……、つまり電化製品は日本のほとんどの家庭にすでに行き渡り、あとは買い替え需要しかないという状態になってきている。もちろん、エアコンはまだ39%で、電子レンジのように、後から出てきて、まだ普及率が34%という商品もあるが、どの家庭でも必需品というような国民的需要がある商品は、ほとんど普及した時代である。〉
もちろん1980年代以降も次々と電気製品は出てくる。パソコンが本格的に売れるようになるのは1990年代の終わりからだ。しかし、1960年代から70年代にかけての生活革命をもたらした商品群ほど、爆発的需要を喚起したものはなかったといってもよいだろう。
小榑によると、ダイエー創業以来8年目の1965年にいたっても、エアコンは2%、電気冷蔵庫は32%、掃除機は32%、石油ストーブは38%、早くから普及した電気洗濯機も69%の普及率にとどまっていた。それから15年のあいだに、最低限必要とされる基本的な電化製品はどの家庭にもほぼ行き渡ったのである。
そこに第2次石油ショックがやってくる。公共料金の値上げ、増税、社会保険の増額などが重なり、可処分所得が減ると、庶民はとうぜん財布の紐を締めないわけにはいかなかった。
大店法により、新規開店がむずかしくなるなか、ダイエーでは既存店の売上が伸びなくなっていた。加えて、核家族化やマンションの増加、ライフスタイルの変化によって、商品が多様化すると、売り場の構成も変えなくてはならず、利益が圧縮されていった。
そんななか、ダイエーはどう対応しようとしていたのか。小榑によると、中内は売上第一主義だったという。イトーヨーカ堂の利益率が4─5%あったのにたいし、ダイエーはその半分だったといわれている。「余分の利益はお客様に還元する」というのが、中内の口癖だった。
売上の伸びが低迷するなか、ダイエーはコングロマーチャント(複合小売業)をめざした。保険や不動産にも手をだす。スポーツ関連の専門店、ローストビーフのレストラン、倉庫型ディスカウントの食品店、書籍・ビデオレンタルの店、ホテル、ハウジング会社などを設立。フランスの百貨店と提携し、オ・プランタン・ジャパンをつくる。ハワイのショッピングセンターも買収した。しかし、どれもうまくいかなかった。
赤字が増えていく。本体の業績もよくなかったが、赤字の大きな要因は多角化事業だった。社内のエリート幹部が集まって、再建委員会がつくられた。
1983年から関連会社の整理統合、借入金・総資産の圧縮による財務体質の改善がはかられた。ダイエーがとりあえず赤字を脱却できたのは1986年になってからである。
このかん、中内は再建計画にはいっさいかかわらず、むしろそっぽを向いていた。気に入らないのだな、と近くにいた小榑は感じていたという。
そのころ中内が熱中していたのは、政府の臨教審(臨時教育審議会)の仕事であり、経団連での活動だった。
ダイエー崩壊までの軌跡をもうすこし追ってみよう。



