「昭和」を送る──大世紀末パレード(16) [大世紀末パレード]
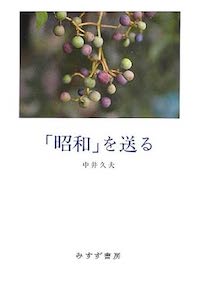

神戸大学教授で精神科医の中井久夫(1934〜2022)は、昭和天皇が亡くなってまもなく、雑誌「文化会議」(日本文化会議発行、平成元年[1989年]5月号)に「「昭和」を送る」と題する一文を載せている。
「文化会議」は保守論壇の雑誌で、中井の評伝に最相葉月は「中井は師の土居健郎に頼まれて寄稿しただけで、これが天皇擁護論と読めたとしても保守論壇入りしたことを意味しない」とコメントしている。
じっさい、そんなことはどうでもいい。
中井があのとき「昭和」をどのように送ろうとしていたのかを知りたい。
ここで昭和が「」付きで示されているのは、もちろんそれが昭和天皇にまつわる昭和だからである。
「昭和の鎮魂は、まだ済んでいない」と記したうえで、昭和天皇の深い魂の声を聞こうとしている。
どれほど遠くみえても、昭和天皇は身近な知り合いの心のなかに意外なかたちでしみついているように思えた。
だが、そもそも日本人にとって天皇とは何なのか。中井はアメリカ人との架空対談を設定して、そのことをできるだけ客観的に探ろうとする。
日本人には「君側の奸(くんそくのかん)」コンプレックスがある、とアメリカ人に説明している。
それは「君主は英明だがこれを邪魔して間違った情報を与え、いろいろ操作している、悪賢い奴が周囲にいる」という固定観念だ。
こうした発想は江戸時代もあるが、「君側の奸」を排除しようとして立ち上がったのは、戦前、五・一五事件や二・二六事件を引き起こした青年将校たちだった。
中井はそうはいっていないが、その根源には「天皇コンプレックス」があったといっていいのではないだろうか。
天皇コンプレックスは中世の武家時代にもみられた。だが、これが燃え盛ったのは、対外的危機感が強まった幕末だ。
徳川の幕府にはもはや正統性が認められないという思いが浮上する。朱子学で忠の原理を導入した幕府は自縄自縛におちいる。そこで、だれもさからうことのできない古代からの幻想的権威がもちあげられることになった。
明治以降、天皇コンプレックスは父性原理のようになって、日本人のなかにしみつくようになる。
「しばしば、激烈な反天皇論者が昭和天皇に会って、メロメロになった話を聞く」と、中井は書いている。
日本人のもうひとつのコンプレックスは、優越国への対外コンプレックスだ。それがかつては中国であり、近代以降は欧米に変わった。コンプレックスには讃仰と反発が含まれる。中井によると、いまでも日本人の中国コンプレックスは根強いものがあるという。
こうした、ふたつのコンプレックスにはさまれながら、日本人は勤勉と工夫、変身能力によって、さまざまな難局を切り抜けていった。
いっぽうで、日本人は土居健郎のいう「甘え」をも持ちあわせている。それが太平洋戦争の開戦時には、最悪のかたちであらわれたのだ。
あのとき日本は、「お互いをあてにし、天皇をあてにし、ルーズベルトをあてにし、ヒトラーをあてにし」て、戦争に突入した、と中井は書いている。
〈信頼せずして期待し、あてはずれが起こると「逆うらみ」する。何もあてにできなかったのは天皇一人だ。〉
昭和天皇は戦争の旗印にまつりあげられた。
ここから話は、その人となりに移っている。
注目されるのは「帝王教育」だ。
昭和天皇は徹底した帝王教育を受けている。それはかなりの心理的負担だったにちがいないが、この教育によって、何ごとにも動じない姿勢がはぐくまれた。
とはいえ、緊張の連続はまぬかれなかった。からだがぎこちない動きになり、声が甲高くなるのは、その証拠だ、と中井はいう。乗馬や水泳ができたことからみれば、けっしてスポーツ嫌いではない。
たいへんな風呂ぎらいと伝えられるのは、臨床経験からみると、「リラックスすることを自分に許せない人」だったのにちがいない。いっぽうで、競争とかはいっさいないから、のびやかで「非常に純粋無垢な人」になった、とみる。
天皇にかけられる圧力は相当なものだったろう。それに耐えることができたのは、昭和天皇が「天衣無縫の天真爛漫さ」という健康な精神をもっていたからだ、と中井は考えている。
昭和天皇が戦争責任を感じていなかったはずがない、と中井は断言している。「戦時中、大声の独り言が多く、チックが烈しくなり、十キロやせられた」のもその証拠だ。
太平洋戦争に踏み切った判断の誤りにも気づいていただろう。昭和天皇は「“距離を置いて客観的にものごとを眺めること” detachmentのできる知的人物である」。
「天皇機関説」が昭和天皇を救ったことも、中井は認めている。
〈「立憲君主」という位置の発見は、昭和天皇独自の大きなインヴェンションだということができる。昭和天皇戦争責任論に決着がないのは、それが明治憲法の矛盾の体現だからである。昭和天皇が非常な内的苦悩にさいなまれたのは、天皇がこの矛盾に引き裂かれた存在だからである。おそらく「天皇機関説」だけが天皇に合理的行動、いな正気の行動を可能にする唯一の整合性をもった妥協点であった。〉
昭和天皇が立憲君主の立場をとり、美濃部達吉の天皇機関説を支持したことが、敗戦後も天皇廃止とならず象徴天皇へと橋渡しできた大きな理由だった。
もちろん、アジアの戦争にたいする責任は残る。
〈天皇の死後もはや昭和天皇に責任を帰して、国民は高枕ではおれない。われわれはアジアに対して「昭和天皇」である。問題は常にわれわれに帰る。〉
これはまったく正しい。
明治以降、日本で天皇が機能してきたのは、天皇が無二の存在だったからだけではない。中井は皇室の役割を挙げている。
天皇という地位は拘束が多い。それゆえに、とりわけ皇太子の役割が大きいという(もちろん、皇后の存在もつけ加えるべきだろう)。
「象徴大統領制が象徴天皇制に劣るのは、皇太子相当の機能部分を持たないことである」という指摘がおもしろい。
皇太子が存在することによって、国家の安定的な持続が保証されるのだ。天皇制の廃止は、独裁的な首相(あるいは大統領)を生みだす危険性につながる。
〈天皇は英国皇室のごとくであれとかあるべきでないという議論を超えて、私は英国のごとく、皇室が政府に対して牽制、抑止、補完機能を果たし、存在そのものが国家の安定要因となり、そのもとで健全な意見表明の自由によって、日本国が諸国と共存し共栄することを願う。〉
これが、昭和天皇の逝去と代替わりにともなって、中井がいだいた率直な思いだったろう。
昭和天皇が最後に残した昭和63年(1988年)の歌がふたつ紹介されている。
「道灌堀 七月」
夏たけて堀のはちすの花みつつほとけのをしへおもふ朝かな
「那須の秋の庭 九月」
あかげらの叩く音するあさまだき音たえてさびしうつりしならむ
いずれの歌にも「死の受容」がある、と中井はみる。
昭和天皇のつくった「お歌」は4万首で、そのうち公表されているのは二、三百首にすぎないという。歌が心を詠むものだとすれば、昭和天皇の心の声は、その多くがまだ隠されたままといってよいだろう。
2024-04-18 11:09
nice!(12)
コメント(0)




コメント 0