『グローバル経済の誕生』を読む(2)──商品世界ファイル(32) [商品世界ファイル]
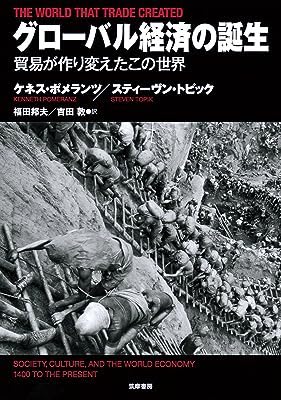
もともとはローカルな産品が、世界商品に変わることがあります。われわれにとって、ごくあたりまえの商品ですが、それらが世界に広がるにはさまざまな経緯がありました。本書では、売られている商品の姿からはなかなか見えなてこない裏の事情も明らかにされています。
1500年にブラジルにやってきたポルトガル人は、「赤い木」すなわちブラジルウッド(パウ・ブラジル)を伐採し尽くしました。ブラジルウッドからは、それまでにない赤の染料が抽出されたのです。その間、先住民の人口は、奴隷狩りと病原菌によって激減していきました。赤い染料のためなら、どんなことでもやったという様子がうかがえます。
1700年になると、ポルトガル人はブラジルで砂糖栽培をはじめます。アフリカから大量の奴隷がつれてこられました。ブタやウシ、ヒツジなどの家畜も持ちこまれました。コーヒーの木を植えたのもヨーロッパ人です。鉄道が発達すると、プランテーション経営者は、荒れた土地を捨てて、さらに奥にはいりこみ、森林を伐採しました。その結果、ブラジルの森林は激減したのです。
ゴムの木はもともと中南米にしか自生していませんでした。1876年、その種子をイギリス人が持ち帰り、キューガーデン(王立植物園)で栽培し、それがマレー半島などに移植されたのが、東南アジアでのゴム栽培のはじまりです。その後、オランダ領東インド(現インドネシア)でもゴムが栽培されるするようになります。
ゴムの需要が急速に増大したのは1820年代から30年代にかけて、マッキントッシュやグッドイヤーが、ゴムの加工技術を開発したからです。ゴムはレインコートや長靴、自転車タイヤ、さらに20世紀にはいってからは自動車タイヤに用いられるようになります。ゴムの樹液を採集するのは、たいへんな作業でした。「ゴム採取の歴史は、人間の屍のうえに築かれていったようなものだ」と著者は書いています。ゴム成金はその屍のうえに生まれたといってよいでしょう。
イギリスに対抗して1930年代にはドイツが合成ゴムの開発に成功しました。それにより、ブラジルでもマレーシアでも天然ゴム産業は壊滅的な打撃を受けます。しかし、航空機のタイヤや戦車のキャタピラ、トラックのタイヤなどは、やはり天然ゴムでないと具合が悪いといいます。現在でも天然ゴムが世界のゴム生産シェアの約3分の1を占めつづけているのもそのためです。
カリフォルニアで金が発見されたのは1848年のことです。以来、12年のうちに、それまでの150年間で採掘された金と同量の金が採掘されました。これにより世界の硬貨の中心が、銀貨から金貨へと移ったというのですから、カリフォルニアの金がもたらした影響がいかに大きかったかがわかります。
カリフォルニアの人口は急速に拡大し、大陸横断鉄道の建設が進められ、海上輸送路も整備されていきました。その間、多くの先住民が殺され、排除されました。ゴールドラッシュは、米国が大西洋と太平洋にまたがる大国へと発展する道を開いたといえるでしょう。
フランドル織のみごとなタペストリーは、みごとな深紅色でいろどられています。じつは、それが中央アメリカのカイガラムシを原料にしていることを知る人は少ないのではないでしょうか。カイガラムシのメスからは、コチニールという染料がとれます。ヨーロッパ人は先住民にカイガラムシを飼育させ、手間のかかる染料をつくらせて、それで鮮やかな織物の模様を浮かびあがらせたのです。ところが1950年代になると、化学染料のアニリンが開発されます。カイガラムシからつくられるコチニール染料は、たちまち忘れ去られていきます。
インカの人びとは古くから、グアノと呼ばれる海鳥のフンを肥料として利用していました。ヨーロッパ人は1830年代になってこのグアノに着目します。そしてこのグアノを船でヨーロッパに運び、肥料としました。いっぽうペルー政府はグアノを担保にして、ヨーロッパから資金を借り入れ、それで鉄道を建設しようとしましたが、大失敗します。化学肥料が出現すると、グアノの夢もたちまちしぼみ、ペルーには膨大な債務だけが残されました。
毛皮もまた世界商品のひとつでした。毛皮を捕ったのは、おもにロシア人で、「カムチャツカ半島やアリューシャン列島、のちにはアラスカまで遠征して、カワウソやラッコを次々に狩猟していった」。その結果、乱獲によって多くの野生動物が絶滅の危機においやられたことは周知の事実です。
ジャガイモ、トウモロコシ、タバコ、ピーナツもアメリカからもたらされました。ジャガイモはスペイン人がフィリピンに運び、まずアジアに広がって、それからヨーロッパに逆流したといわれます。1600年以降、ヨーロッパでは人口の急増により食料危機が生じていました。ジャガイモを最初に主食としたのはアイルランドです。イングランドでも1700年ごろからジャガイモが生産され、次第に労働者用の補助食料となっていきます。プロイセンでも、フリードリヒ大王がジャガイモの食用化を推し進めたことはよく知られています。
ピーナツは砂まじりの土壌で育つために、劣化した土地でも栽培が可能でした。その蔓(つる)は家畜の飼料に、殻(から)は燃料に、実は食料や油として利用できるというすぐれた特性をもっています。ピーナツが注目されたのは1900年になってからで、潤滑油や塗料、石鹸の原料として用いられました。こうして中国、インド、西アフリカでもピーナツがつくられるようになります。しかし、1940年になると、化学合成物が開発されて、工業原料としてのピーナツは忘れられていきます。
ハワイ王国を滅亡に追いこんだのはヨーロッパ人でした。1876年以降、ハワイでは、アメリカ人のつくった砂糖プランテーションが急速に拡大していきました。そして、この砂糖の特権を守るために、クーデターが画策され、王制が崩壊、これによってハワイはアメリカに併合されていくことになります。
台湾で砂糖が増産されたのは、台湾が日本の植民地下にはいってからです。とはいえ、台湾が砂糖栽培に依存するモノカルチャー経済に陥ってしまうことはありませんでした。その危険性があったとしたら、むしろ1600年代のオランダ統治時代だった、と著者は指摘しています。オランダの統治は鄭成功により排除されました。
アルゼンチンにやってきたスペイン人は、広大なパンパに家畜を放ちました。その家畜が繁殖して、アルゼンチンでは牧畜が盛んになります。その後、アルゼンチンは世界最大の牛肉輸出国へと成長しますが、それを支えたのは、輸送技術の革新や冷凍技術の進展です。しかし、牛が経済的に飼育されるにつれて、かつてのカウボーイ、すなわち誇り高きガウチョが、次第に最下層の使用人へと転じていくという悲しい歴史もありました。「家畜の牛がカウボーイを駆逐した」のです。
アメリカ西部の大平原は、小麦生産の最適地でした。そのことにヨーロッパからの移民はすぐに気づきます。労働力の不足は、機械の導入によって克服されました。鉄道や運河もつくられ、穀物市場は東部ばかりか海外にまで広がっていきます。1878年には小麦の刈り取りと結束を同時におこなうバインダーが開発されました。しかし、バインダーに必要な小麦用の麻ヒモをつくらされていたのは、ユカタン半島に住む数万ものマヤ人でした。
このように並べただけでも、商品生産をめぐるドラマには、表からではみえないおどろくべき展開が隠されていることがわかります。ゴムや綿花のような原料にせよ、ジャガイモや小麦のような食料にせよ、あるいは牛のような家畜にせよ、もともとは限られた地域の産物が、資本の都合にあわせ世界中に適地を求めて生産されていったのです。それによって現地の環境は変えられ、人びとが思うがままに使役されたありさまは、すざまじいとしかいいようがありません。
こうした動きは、経済学の知識だけでは、なかなかつかみがたいものです。いや、むしろ経済学は、背後の歴史的真実を隠蔽することで成り立っているのではないかと思えるくらいです。
経済は平和的な商業活動と思われがちですが、「このような見方は、ヨーロッパ以外の世界でおこなわれてきた絶え間ない略奪や暴力という動かしがたい歴史的事実を覆い隠してしまう」と著者はいいます。グローバル経済は暴力を抜きにしては語れないのです。
ヨーロッパの繁栄を支えたのはアフリカ人奴隷と海賊でした。戦争もまた富の蓄積手段であり、さまざまな新商品もまた戦争を通じて生まれたのです。
アメリカは移民の国だといわれますが、1800年以前の移民は、4人に3人が強制的にアフリカからつれてこられたと著者は指摘しています。その数は1000万〜1500万にのぼります。そのうち3年以上生きられたのは、わずか3割だったといいます。航海の途中で死ぬ奴隷が多かったのです。
それではなぜ、わざわざアフリカ人をアメリカに連れてこなければならなかったのでしょう。じつは、スペイン人がアメリカに到着してから、先住民はヨーロッパ人の持ちこんだ天然痘(てんねんとう)や麻疹(ましん)によって、その9割が死滅してしまったのです。そこで、ヨーロッパ人はアメリカで働かせるために、アフリカ人を奴隷としてつれてくるほかありませんでした。
アフリカ人奴隷は鉱山労働者として、あるいは砂糖、綿花、タバコ、コーヒーなどを栽培する農場の労働者として酷使されました。
イギリスがスペインの海軍力をそぐために海賊の力を活用したことはよく知られています。「スペインやポルトガルの植民地帝国が衰退したのは……イギリスやオランダの海賊による略奪行為こそが決定的な役割を果たした」とまで、著者は述べています。海賊たちは香辛料、金銀、毛皮、高級織物、さらには奴隷や砂糖といった贅沢品(ぜいたくひん)を積んだ船をねらいました。オランダやイギリスの武装商船もまた、平気でスペインやポルトガルの商船を襲っています。宗教対立(プロテスタントとカトリックの対立)は、いかなる非道をも正当化したようです。
そして、スペイン海軍の力が衰えてくると、いよいよイギリスの海軍力が強大になり、「地球上のいかなる海域においても略奪行為を根絶することに心血を注ぐようになる」。ここにも正義は力なりの見本があります。
ポルトガルに代わって、世界最大の奴隷貿易国になったのがオランダだったことも、あまり知られていません。16世紀にポルトガルは西アフリカの奴隷とブラジルの砂糖を独占していましたが、オランダは何とかしてその一角に食いこもうとします。しかし、ブラジルの攻略には失敗しました。
そこで、オランダはポルトガルを出し抜くため「アフリカの沿岸地域で次々と奴隷貿易の輸出港を建設し、人間を家畜のようにカリブ海に浮かぶフランスやイギリスの植民地に輸送し始めた」といいます。こうしてカリブ海の島々で砂糖が生産されるようになると、ブラジルでポルトガルが独占していた砂糖生産も切り崩されていきます。一時、オランダが世界経済のヘゲモニーを握った裏には、このように血塗られた歴史があります。
くり返しになりますが、「戦争と経済」で思い浮かべるのは、アヘン戦争のことです。アヘン戦争は、清朝がアヘン貿易を禁止したのにたいし、イギリス海軍が攻撃を開始したことに端を発します。しかし、そもそもイギリスがインドのアヘンを中国に輸出したのは、中国の茶にたいする銀貨の支払いが膨大な額にのぼったからです。これもまた、ほめられた歴史ではありません。
イギリスとオランダの東インド会社は、これまでにない特色を備えていました。それは両方とも株式会社だったことで、出資者の匿名性が高く、また経営権と所有権とが分離しており、永続する法人であることが前提になっていました。
それまで会社といえば家族経営が中心で、海外貿易会社への出資はその都度、清算されるのが原則でした。著者は東インド会社などの株式会社が永続しなければならない理由は「暴力」にあったと断言します。植民地に要塞を築き、海上の覇権を築くには、莫大なコストを要しました。
18世紀にはいると、東インド会社は武装コストにたえられなくなります。いっぽう、そのすき間を縫って密輸業者が横行し、独占体制を崩していきます。植民地経営はこうして政府の手にゆだねられ、会社は資本中心の企業へと変わっていくわけですが、企業もまた国家によって守られているという意味で、それ自体潜在的な暴力性を含んでいたといってよいでしょう。
現在の企業乗っ取りは海賊と同じだといわれますが、16世紀から18世紀にかけての海賊はむしろ「厳格なモラルに基づいて経済活動をおこなっていた」と著者は指摘します。ホーキンズやドレークには、政府から私掠船の許可証が発行されていました。17世紀には、無国籍の浮浪者からなるバッカニアと呼ばれる海賊が登場します。かれらはスペインの港や船を攻撃し、商品を略奪しました。しかし、海賊には掟(おきて)があり、略奪品を盗むことは禁じられ、無用な殺戮(さつりく)はおこないませんでした。仲間どうしの生命保険や傷害保険もあったといいます。
イギリスでは1834年に、アメリカでは1865年に、そしてそれ以降、世界のいたるところで奴隷制が廃止されました。しかし、奴隷制が廃止されても過酷な強制労働がなくなったわけではありません。見習い労働や年季契約労働が、労働コストを下げる新たな手段として導入されました。奴隷は自分たちの置かれた環境から逃げだすためには、どんな条件でも受け入れました。それが自由契約にもとづく低賃金労働でした。
奴隷制はいずれ廃止される運命にありましたが、それは経営者側に「自由な契約による賃金労働のほうが、より大きな利益をもたらす」という確信があったからです。ちょっと言い過ぎかもしれませんが、企業にしばられるという意味では、いまでも労働者は会社の奴隷であることにちがいはないでしょう。
著者は象牙のたどった道をふり返ってもいます。ビリヤードの球やピアノの鍵盤、ナイフの柄(え)、チェスの駒など製品となった象牙には優雅さがただよいますが、そこに何十万頭の象が犠牲になっている光景を思い浮かべる人は少ないでしょう。
ヨーロッパで奴隷解放運動が広がるさなか、ベルギーのレオポルド2世(1835〜1909)がコンゴを手中におさめ自身の私領としました。かれはコンゴの手つかずの森に大量の象がいることに気づき、象牙を手にいれようとします。多くの黒人が虐殺され、大量の象が殺害されました。「ベルギー人は、コンゴの先住民を奴隷にし、資源を強奪して、ビリヤードの球やピアノの鍵盤の材料を求めた」のです。象牙は象への暴力によって、はじめて成り立つ商品でした。レオポルド2世は、また先住民の土地を奪って、そこに広大なゴム・プランテーションを開いたことでも知られます。そして、その私兵は、労働を拒否する黒人の手首を容赦なく切り落としました。そんなばかなと思われるかもしれませんが、これは事実です。
残念ながら、この世には本源的に暴力性を秘めた、政治の力、経済の力が、いまでも満ち満ちているといわねばなりません。
グローバルな市場社会はいつつくられたのでしょう。それは、つい200年ほど前のことではないか、と著者は考えています。産業革命以降と考えていることがわかります。
最初は物々交換でした。そして次第に金銀が価値のシンボルとなります。世界的に銀が貨幣として使用されるようになったのは、メキシコとペルーで銀の大鉱脈が発見されたからであり、それからカリフォルニアやオーストラリア、南アフリカなどで豊富な金が発見されたことにより、世界は金本位制のもとに統合されていきます。そして市場で商品の価値が決められるようになると、商品の規格化、運輸革命、時間の標準化、先物市場、法律の整備、債券市場、品質管理、登録商標、知的所有権、大量の広告などといった現象が次々と生じていきました。
著者はこう書いている。
〈結局、世界貿易と商品化のプロセスが拡大するにつれて、多くの人々は、自分が欲しいものは何でも手に入れられるようになった。つまり世界中どこのモノでも意のままになると考えるようになった。どんなモノでもお金があれば手に入れることができるようになったので、多くの人々は、世界は人間のニーズと欲望を満たすためにあるのだと考えるようになってしまった。「自然」を「天然資源」や「生産要因」に置き換えて、人間にとって便利で、しかも利益を生み出すものに変えるために全力が傾注されるようになったのである。〉
これはハッピーな世界なのか。いやクレージーな世界ではないのか、というのが著者の問いかけです。
メキシコ銀貨ペソは16世紀から17世紀にかけて、世界通貨の役割を果たしていました。ペソはアメリカとヨーロッパを結びつけただけではなく、ヨーロッパとアジアを結びつけていたのです。ヨーロッパ人はアジアから香辛料とシルクを手に入れ、銀をその代価としました。しかし、19世紀にはいりゴールドラッシュがはじまると、金の供給量が増大するいっぽうで、銀の需要と価格は下落して、世界の基軸通貨が次第に金へと移行していきます。とはいえ、19世紀になるまで、貨幣は人びとの生活に浸透していたわけではありませんでした。
度量衡が統一されるのは、18世紀末のフランス革命以降です。メートル法が導入されます。それまでは人体が尺度の基準であり、地方ごとにさまざまの測量単位がありました。しかし、商品化が進むにつれて、度量衡の統一や商品の規格化が求められるようになります。つまり財が「抽象化」されて、「計測可能で均質的な商品」が生産され、世界じゅうで商品として売ることが可能になったのです。
ヨーロッパで国際的な小麦市場が生まれたのは19世紀中ごろでした。このころ輸送革命によって、アメリカの小麦はヨーロッパに運ばれていました。米の場合は小麦よりもさらに貯蔵や搬送が容易でしたが、米の銘柄は多く、その貿易は消費者の好みに応じて、狭い範囲にとどまっていました。
時刻が均一化されたのは、19世紀半ばになってからで、それまでそれぞれの国や地方はそれぞれの時刻をもっていました。イギリスが標準時をグリニッジ時間にあわせたのは1842年になってからで、鉄道の時刻表を定めるためだったといいます。これにたいし、アメリカは時刻の標準化が遅れ、ようやく1918年になって国内を4つの時間帯に分割することがきまりました。世界は次第に24の時間帯に分割されていきますが、その決定は合理的というより帝国主義国の都合次第だったといわれます。
商品世界の特徴は、消費者が顔見知りの隣近所よりも、見も知らぬ遠方の業者に信用をおくようになったことだと著者は皮肉たっぷりに書いています。遠方でつくられた食料が食べられるようになったのは、運輸の発達に加えて、缶詰めや真空パック、冷凍などの技術が発達し、それに応じて各家庭が冷蔵庫をもつようになったからです。
「2000年前の世界では遠くにあったモノが今の世界では近くなり、近くにあったモノが遠くに立ち去った」。こうして「地域の食料品店や雑貨店は、巨大かつ人間不在の、しかし安価な商品を販売するスーパーマーケットによって消し去られた」というわけです。
包装革命もまた現在の特徴です。ガラス瓶やブリキ缶、紙袋、段ボール箱がつくられたのは19世紀。20世紀になると、プラスチック革命がおこり、いまではどの食品コーナーでもラップやトレーがあふれかえっています。包装は単に中身を保護するだけではなく、ブランドのイメージにつながっています。「包装は近代大衆社会の鍵を握っている」
登録商標と法人の発生は密接に結びついています。市場においては生産者と消費者のあいだで、直接的な人と人との関係は失われます。商品の品質もまた標準化されていきました。「中身を確認するためには、包装紙に書いてある情報や、とりわけ企業名を信頼する以外に方法がなくなった」のです。
登録商標の保護がなされるようになったのは、19世紀半ばからです。以来、企業にとって、ブランド名が大きな財産となりました。「宣伝・広告の目的は、消費者に製品の使用法や原材料について伝えることではなく、商品を差別化し、商品の品質とは無関係にイメージを消費者に植え付けることである」。これもまた商品世界のマジックかもしれません。
コカコーラのように、いわばアメリカのイメージと結びついたブランドもあります。ヨーロッパに進出するにあたって、「コカコーラ社は『アメリカの生活様式』と、大戦で勝利した『アメリカ』を全面に出すことで大成功を収めた」と著者は書いています。
100年前、石鹸はさほど必要なものとは思われていませんでした。ところがいまではからだを石鹸で洗わないと不潔だと感じられます。石鹸の登場によって、清潔への強迫観念が生まれたのです。これも、ひとつの商品がライフスタイルを変えてしまう一例でしょう。
学校では、石鹸で頻繁に手を洗うことがいわば義務となり、家庭でもだれもが口臭を気にするようになって、しきりに歯磨きをしたり、マウスウォッシュを使ったりします。そして、われわれがいかに汚ないか、いかに世間から遅れているかを意識にすりこませる大量広告(マーケティング戦略)が、消費者に商品の購入を促していきます。これはどの商品についてもいえることでしょう。
商品の発明と普及には、さまざまな偶然や社会的要因がはたらく場合があります。たとえば鉄道の線路幅は、ほんとうならもっと広くすべきだったのに、馬車の軌道にあわせてつくられたため、現在のような狭軌になり、軌道の幅をいまさら変えられなくなってしまったといいます。
缶詰の話もおもしろい。もともと軍事用食料として作られた缶詰を開けるには、最初ナイフやハンマーが用いられていました。缶切りが発明されるのは1870年、主婦が缶詰を利用するようになってからです。缶切りは最初なかったのです。いまではほとんどイージー・オープンエンドが採用されています。
食洗機はすでに1880年代に考案されていましたが、1950年代になるまであまり利用されることはありませんでした。女性が外で働くようになったことが、食器洗い機の普及を促したといわれます。
ピレネー山脈の中腹にあるアンドラ公国がインターネットと税制(関税なし、所得税なし)だけで、富裕国になるという奇妙な話も紹介されています。「投票権を持たず、ここに住んでいない4分の3の住民は、アンドラの空気が澄みきっているからではなく脱税のためにここに住民票を置いているのだ」。タックスへイヴンもまた、現代の資本蓄積がもたらした現象かもしれません。
われわれは世界で最初に近代工場が生まれたのはイギリスだと思いこんでいます。しかし、それはまちがいだと著者は述べています。近代工場が生まれたのは、新大陸の植民地で、それは砂糖工場でした。
砂糖の生産には迅速さが求められます。その作業は何百人もの奴隷と労働者を必要としました。「ヨーロッパ人は、多額の資金を投じて工場を建設し、大量の奴隷を朝から晩まで酷使して、自分たちの飽くなき欲求を満たそうとした」。その結果、砂糖はヨーロッパや北アメリカで大量に出回るようになり、だれでも手にいれられる気軽な商品となっていきます。
ところで、産業革命の中心は綿工業にあるといわれながら、その原料である綿については、これまであまり論じられることはありませんでした。もともと綿の栽培と加工が発達していたのは、インドや中国です。どの階層でも木綿の衣服はごく一般的に用いられました。日本で木綿が普及するのは17世紀の元禄時代以降ですが、インドや中国はそれに先行していました。
ヨーロッパでは18世紀なかばでも、麻や羊毛が衣服の中心でした。イギリス人は毛織物をアジア各地に売りこもうとして、失敗しています。
17世紀から18世紀にかけて、インド産の綿織物は最高級品で、モルッカ諸島の香辛料やアフリカの奴隷を手に入れるさいにも、こうしたインド産綿織物が代価として珍重されていました。17世紀には「インド製品のシェアは、世界の衣服市場の約25%を占めるまでに達していた」。これほど優勢を誇っていたインドの繊維産業が衰退するのは、イギリスがインド製品をまねて、産業革命によって綿製品をつくりだすようになったためです。そしてベンガルを支配したイギリスの東インド会社は、インドの繊維産業をつぶしていきます。
しかし、綿製品の材料となる綿花はヨーロッパではできないため、新大陸で栽培せざるをえなかったのです。そのために投入されたのがアフリカ人奴隷でした。
1861年に南北戦争が起こると、綿花の供給が不安定になってきます。それ以前から、イギリスはアメリカ以外の供給地を見つけるため、まずインドに、次にエジプトに目をつけ、綿花の栽培を推し進めていました。しかし、インドやエジプトの綿花は量的にも価格的にも、アメリカの綿花にはかなわなかったのです。
トマス・エジソンが発電機をつくったのは1880年のこと、それ以降ニューヨークでもカリフォルニアでも、まっ暗な街並みが明るくなりました。これはまさに文明の恩恵でした。とはいえ、電線の材料には銅が必要になってきます。バハ・カリフォルニアにはボレオ銅鉱山がありました。ここに急遽(きゅうきょ)、メキシコじゅうの労働者が集められます。その労働は12時間交代制で過酷なものでした。明るい電気をもたらした銅線の背後には、メキシコ人労働者の血と汗があったのです。
20世紀の工業化を支えたのは、何といっても石油でした。石油は最初は照明や暖房、建築資材や潤滑油として用いられていました。しかし、次第にエンジンの動力、プラスチックや化学肥料の原料、あるいは電力を生みだす源としても使われるようになり、一挙に用途が広がっていきました。
最初、大規模に石油が発掘されたのはアメリカです。ロックフェラーをはじめとするさまざまな石油王が登場し、産業界に君臨します。メキシコでも欧米の資本によりタンピコ油田が開発されました。ところがメキシコでは利益を独り占めする石油会社にたいし、民衆のナショナリズムが高揚し、メキシコ政府はついにメキシコ石油会社の設立を宣言します。メキシコから締めだされた欧米の石油会社が次に向かった先はベネズエラでした。しかし、ベネズエラもついに1976年に石油産業の国営化を発表します。このように石油の奪い合いをめぐる歴史は変転きわまりないのですが、世界貿易の中心がいまも石油であることはまちがいないと著者は述べています。
「19世紀を代表したものが、石炭、鉄道、蒸気船だとすれば、20世紀を代表するものは石油、自動車、飛行機だろう」。その石油によってつくられた国家がサウジアラビアです。1902年、イブン・サウードはリヤドを奪還しました。第1次世界大戦では、イギリスに協力して力を蓄え、その後、ラシード家やハーシム家を滅ぼして、サウジアラビア王国を建国します。しかし、その王国は不安定で、いつ倒れてもおかしくない状況にありました。その危機を救ったのが石油でした。
サウジアラビアで石油の生産がはじまったのは1938年、その採掘権を得たアメリカは王国の保護に回ります。そして、1973年の石油危機以降、サウジアラビア経済は膨張し、政府は大衆迎合的な政策を打ちだすようになります。石油産業も国有化されました。これからこの国がどのように歩んでいくかに注目しなければならない、と著者は結んでいます。
著者はこの500年のグローバル化をふり返って、その間、いったい何が起こったのかと問うています。
世界の人口が10億人を突破したのは1800年のことです。世界の人口は「それから120年後の1920年には20億人になり、70年後の1990年には60億人」を突破しました。人間の平均寿命もこの100年のうちに倍になったといわれます。
これだけ人間が増えたということは、医療の発達もさることながら、人が生きていくのに必要な食料がつくられたということを意味します。世界中で穀物や商品作物をつくる農場が開発され、そこで増産された食料が交易を通じて各国、各地域に運ばれていきました。その分、地球上の森林は、相当な部分が農地に変わったということです。
もうひとつ著者は「人がはじめてこの地球上に現れてから、この地球上にある全エネルギーの半分以上が1900年以降に使用された」とも指摘しています。また「人間は地上のすべての創造物[動物]と植物を支配下に置こうとしている」とも述べています。さらに「この地球は、穏やかな庭園や原野に覆われるのではなく、巨大な市場になってしまった」とも。
たしかに人類が増えつづけ、いまや70億人に達したといわれる人口を支えるには、膨大な食料と資源を必要としていることはたしかです。グローバル経済は、けっきょくこの食料と資源の確保に明け暮れたといってよいのではないでしょうか。
さらにもうひとつの問題。それは70億人もの人が平等に豊かに暮らしているわけではなく、世界の貧富の差がますます大きくなっていることです。いまでは「最も豊かな人々と最も貧しい人々との所得格差は、天文学的な数字に達している」のです。ビル・ゲイツの所得は、最も貧しい人1億人分に相当するという指摘には、驚きだけではなく、不条理さえ感じます。
「ほんのわずかな人間が、かくも多数の人々を支配した時代はこれまでなかった」と著者は書いていますが、これはビル・ゲイツにかぎらず、石油、エレクトロニクス、航空機、自動車、金融、保険などを掌握するかぎられた企業が、いかに世界を牛耳っているかを示しています。
そして、いまは消費時代となりました。ローンやクレジットなど、簡単に借金ができる仕組みも生まれ、「買うのはいまでしょう」と消費を促します。さらに次々と新たな商品が生みだされ、その広告をみているうちに、それをもたない人びとは自分が時代に取り残されているような「不満足感」あるいは「欠乏感」を味わうようになっています。
中国もあっというまに消費社会に突入しました。中国では「今では人民に奉仕するのではなくお客様に対して明るく親切に対応する人間像が求められている」といいます。中国の発展はたしかに目覚ましいものがあります。それは中国がグローバル化の波に乗ったからです。世界の最貧困者は過去25年のうちに3億5000万人減少したといわれますが、それは中国の発展がもたらしたひとつの成果だといえるでしょう。
グローバル化への反乱はまだ起きていないと著者はいいます。たしかにいま世界は平和とはいえない状態にあります。2001年の9・11事件以降、世界は揺れつづけています。しかし、グローバル化に代わる新たな導きの糸を見つけるところまで、世界はまだ立ちいたっていません。
最後に著者が懸念をいだいているのは、地球の将来についてです。地球温暖化はどのような結末をもたらすのか。石油などの有限な資源をこのまま使いつづければ、そのあとはいったいどうなるのだろう。水不足も深刻な問題となりつつあります。
著者はいいます。
「近代文明は、膨大なエネルギーを使って自然に代わるすべてのモノを発見したのだが、いまやエネルギーを使用することによって、自然と、人間がつくった生きるための空間の双方が危機にさらされているということに気がつきはじめたのだ」
現在が隠されていた真実を見つめなおし、そこから新たに出発しなおす時期にきていることはまちがいないでしょう。
『グローバル経済の誕生』を読む(1)──商品世界ファイル(31) [商品世界ファイル]
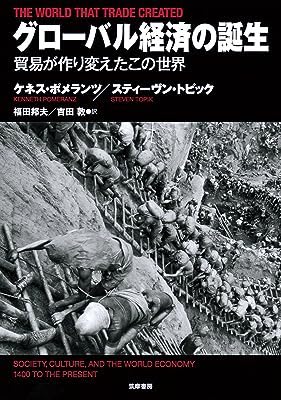
近代中国史を専門とするケネス・ポメランツと、ラテンアメリカ史を専門とするスティーヴン・トピックによる共著です。ふたりの専門分野を合わせて、コロンブスのアメリカ「発見」以前から現代までの600年にわたるグローバル経済の全体像を浮かびあがらせようとする試みといえるでしょう。
交易には経済原理では片づかない人間のドラマがあると著者は書いています。そして、実際、時間をさかのぼればさかのぼるほど、交易は現在の経済原理とは異なる方式でおこなわれていました。市場さえ存在しない地域も多かったのですが、アジアでは早くから海路による商業ネットワークが築かれていたのです。
最初にえがかれるのは、ヨーロッパ人が世界を制し、市場の掟を押しつけるようになる以前。時代は16世紀から19世紀にかけてです。中国やインド、バタヴィア(インドネシア)、アステカ(メキシコ)、ブラジルなどが舞台として取りあげられます。
中国では福建の華僑が登場します。人口が密集し、土地が痩せていたので、福建の人びとは昔から海外に進出し、独自の商業ネットワークを築いていました。しかし、中国政府は植民地をもつことに関心がなく、海外の福建人を保護しようとしませんでした。そのため、海外の中国人は、みずからの手段で、みずからの身を守らねばなりませんでした。
19世紀にはいり、ヨーロッパが工業体制を確立するため、植民地を確保していくにつれて、福建人はその動きに巻きこまれていきます。白人入植者は福建人を重宝しました。「彼らは現地人のように汗水垂らす肉体労働者として働くわけではなかったが、植民地の労働力を確保するリクルーターとして、また食料雑貨店の経営者、質屋、代書人として労働に従事した」といいます。
19世紀まで中国では、人民は絶対的為政者である皇帝に服属し、皇帝の任命した官吏によって支配されていました。しかし、周辺の国ぐには、使者を通じて中国の皇帝に朝貢品を献上することによって、国としての地位を認められていました。これが朝貢制度です。
朝貢国は中国の皇帝から下賜品を頂戴し、それを高価な宝として珍重しました。朝貢は経済儀礼というより、むしろ外交儀式だったといってよいでしょう。そして、こうした朝貢体制のもとで、民間の活発な交易活動がおこなわれていたのです(ただし、日本は早くからこの朝貢体制、すなわち華夷秩序から離脱していました)。
世界ではじめて精巧な紙幣がつくられたのは中国で、それは唐の時代でした。中国ではその後、銅銭が大量に供給されたものの、通貨不足は深刻で、宋の時代も紙幣が発行されていました。しかし、紙幣はしばしば増発されてインフレを招き、時に経済に打撃をもたらしました。
新世界で大量に銀が産出されるようになると、16世紀から300年にわたって、「世界の銀産出量の半分近くが中国で硬貨として鋳造された」。言い換えれば、この間、中国にはヨーロッパから大量の銀(メキシコ銀)が流れこんでいたことになります。中国から銀が流出するようになったのは、アヘン貿易がさかんになってからです。19世紀になるまで、ヨーロッパはまだ世界経済の中心ではありませんでした。市場原理もまだ浸透していませんでした。
ヨーロッパが進出するまで、世界経済の中心はアジアにあったといえるでしょう。アジアというのは、東アジアだけではなく西アジアも含みます。西アジアでは7世紀以降、イスラム世界が広大な商業圏を築いていました。
イスラム世界はアラビアから発して、エジプト、シリア、トルコ、イラク、イラン、北アフリカ、スペイン、ソマリア、西アフリカ、インド、インドネシアへと広がり、その地域では貿易が盛んになりました。イスラムの貿易商は、中国と地中海をまたにかけて仕事をしていました。
このヨーロッパ・アジア航路を横取りしようとしたのがポルトガルです。ポルトガルは15世紀末にインド航路を開き、その後、インドの港に多くの要塞を築いて、香辛料貿易を独占しようとします。だが、いかんせん実力不足で、1600年ごろにはアジアでの拠点もあやうくなっていました。
11世紀から15世紀にかけてヴェネツィアが繁栄したのは、アラブ人と取引をおこなっていたからです。ポルトガルは直接アジア・ルートを開拓して、ヴェネツィアに対抗しようとしたともいえます。
中央アジアを通る貿易ルートは、14世紀のマルコ・ポーロの時代以降、すたれていました。『東方見聞録』にはヨーロッパより中国のほうが治安が保たれ、商人は誠実だと書かれています。コロンブスはこの『東方見聞録』を読んで、ジパングに行きたいと願いました。
しかし、実際に到着したのはアメリカでした。その後、アメリカの先住民はヨーロッパ人によってひどい目にあいます。著者はアメリカの先住民がなまけ者で、自給自足の生活をしていたというとらえ方は、まちがいだといいます。じつは、先住民はすでに大規模な交易をおこなっていたのです。
アステカやマヤでは、トルコ石や銀、ナイフ、羽毛、ゴム、チョコレート、カカオ豆、金、黒曜石などが幅広く取引されていました。しかし、それは帝国への貢納が中心で、市場はその周辺にちらばっていたにすぎません。スペイン人がやってきてから、こうした商業ネットワークはたちまち消滅します。帝国そのものが崩壊したからです。
ブラジルに住むトゥピナンバ族は、狩猟採集と原始的な農業を営みながら、ゆったりと暮らしていました。私有財産という考え方はなく、時折、オウタカ族と沈黙交易をおこなっていました。そこにポルトガル人がやってきて、かれらに鉄製の剣や斧(おの)を贈り(それはとうぜん部族間の戦争をあおる)、染料の原料となるブラジルウッド(これがブラジルという国名の由来でもある)を手にいれるようになります。最初は染料の交易が目的でした。しかし、ポルトガル人はそれにあきたらなくなり、次第に先住民の土地を占領し、そこにアフリカ人奴隷を送りこんで、砂糖プランテーションを経営するようになっていくのです。
イギリス人がブラジルに進出したのは19世紀にはいってからだといいます。目をつけたのはコーヒーです。当時プランテーションのコーヒー園はさほど本格的に運営されていませんでした。イギリス人はその生産体制を確立し、陸上の輸送ルートを整備し、ヨーロッパとの定期航路をつくり、世界で初めてコーヒー市場をつくりだします。そのコーヒー園で働いていたのは、アフリカ人奴隷でした。
ポルトガルが衰退したあと、東南アジアにはオランダ東インド会社が進出しました。著者は驚くべきことに、東南アジアの貿易商人は男性ではなく女性だったと書いています。オランダ人はこうした女性貿易商を取りこむことによって、コショウから陶磁器にいたる産物の貿易を独占していきます。そして、王国の支配層に食いこみ、現地の慣習法を利用しながら、植民地支配をめざしていくのです。
18世紀半ばまで、アジアでは中国人やペルシャ人の貿易商が活躍していました。かれらは絹や金、ダイヤモンドなどを取引しながら、王国の徴税まで請け負うこともありました。インドにはペルシャの商人が進出し、たとえば王国に馬を売って、ひともうけしていました。馬はもちろん戦いのために用いられます。そして、そうした商人のなかからはダイヤモンドの採掘権を獲得する者や、貴族の称号を受ける者もでました。
1557年にイギリス東インド会社がベンガル地方を征服したときは、ベンガル商人を大いに活用したといいます。東インド会社はイギリスのアジア貿易を独占する株式会社でした。現地の支配者に近づいてビジネスを展開し、時に軍事力を行使し、植民地支配への道を突っ走りました。アジアの伝統的な貿易商は、次第に排除されていきます。
しかし、イギリスがインドを支配するようになったといっても、インドにすぐイギリスの資本が流れこんだわけではありません。イギリス人が考えていたのは、インドでいかにもうけるかということだけだったといってよいでしょう。イギリス人がベンガルの商人と組んでつくった銀行は、まさに本国に現金を送金することだけを目的としていました。アヘンやインディゴ(染料)、綿、紅茶など、カネになるものは後先考えずに輸出され、現地経済を好況と不況の渦に巻きこみ、最終的にはベンガル商人自体を没落へと追いこんでいきます。イギリスからインドに資本が投下されるようになったのは、それからでした。
こうして眺めると、ヨーロッパ人が16世紀以降、いかに世界を駆け回って、みずからにとっての富の獲得に奔走したかがわかります。富とは莫大な利益をもたらす商品のことです。そして、その商品のもととなるものは、ヨーロッパには存在しませんでした。だからこそ、それらは叡知(えいち)と機略をかけて、つくりだし、奪い取らねばならなかったのです。
いまでこそ信じられませんが、かつてヨーロッパにおいて、コショウやコーヒー、砂糖は、のどから手のでるほどに求められた商品でした。珍にして新奇、そしてかぎりなく人をひきつけることが、商品の本性です。それは単に有用という言い方だけでは言いあらわせない魔力(マルクスのことばでいえば物神性)、人生を変えてしまうほどの魔力を秘めていたにちがいありません。人びとはできるだけそれをいつでも手軽に手に入れることを望みました。
商品の仕掛けはいつも単純です。ふだん身の回りでは手にはいらないものを、目の前に現出させ、それがあれば生活が豊かになり、一変するかのごとき幻想をつくりだすのです。実際、それによってある程度、人生は変わり、日々更新されていくのでしょう。しかし、商品には表には見えていない、裏の世界が隠されています。そして、それこそがほんとうの世界かもしれないのです。
人の欲望には切りがあるはずです。ある程度の満足が得られれば、ほんらいは、それ以上を望むことはありません。ところが、商品世界はそれを許しませんでした。資本の欲望には切りがないのです。資本は資本の蓄積をめざす権力(絶対意志)であって、商品世界を拡大し、支配するためには、どんなこともいといませんでした。市場社会の広がりと浸透は、資本の物語として読み解かれねばならないのでしょう。
輸送技術の進歩が商品世界をいかに進展させたかというのが、次のテーマです。しかし、その前にさまざまなエピソードが語られます。
14世紀から15世紀にかけ、巨大船を建造する能力をもっていた中国は、明時代半ばになると海への進出を断念し、国内の治安維持に専念するようになります。木材は王宮建設をはじめとする国内需要のために利用されるようになりました。
「小型船で陶磁器や絹を中継地に運び、そこでインド産の綿花やインディゴを仕入れ」るというのが、中国貿易商のパターンだったといいます。そのため、中国人は大型船で海上交通路を独占しようとするヨーロッパ人に次第に対抗できなくなっていきます。
ヨーロッパ人が航海技術を発展させたのは、海外から巨万の富を得るという欲望に駆られたからだといいます。それがコロンブスを動かした動機にほかなりませんでした。「欲望のとりことなったおろかな男」コロンブスが、「新大陸を発見したのは偶然に過ぎず、発見した大陸がどこであるのか、見当もついていなかった」と、著者は辛辣に指摘しています。
18世紀の都市において、最大の問題は食料の安定供給を維持することでした。ロンドンはともかく、パリやマドリードではしょちゅう暴動が発生しました。近郊に広大な農地が広がり、運輸システムが整備されていないと、都市は発展しません。江戸やカイロ、イスタンブールなどが大都市に成長したのは、そうした条件が満たされていたからです。北京とデリーは肥沃な農地から遠かったにもかかわらず、卓越した運輸システムと徹底した食料管理によって、難点を克服し、大都市の繁栄を維持しました。
ムガール帝国の交通路を支えたのはパンジャーラ族という遊牧民だったといいます。かれらは牛をつれて村から村へと渡り歩き、穀物や塩、衣類、ダイヤモンドなどを運んでいました。
アメリカの西部開拓は自給自足農業のうえに成り立っていたわけではないという指摘もうなずけます。アメリカは釘にせよ衣服にせよ、ヨーロッパからさまざまな工業製品を輸入しなければなりませんでした。そのためには、穀物や米、綿花、タバコなどの農産物や木材を輸出する必要がありました。船積みの効率を考えて、東海岸には倉庫が建設され、商品が蓄えられます。ヨーロッパの工業製品はあまりかさばらないため、ヨーロッパからの船には移民を積みこむことができました。
とはいえ、アメリカへの移民の中心はヨーロッパ人ではありませんでした。大半がアフリカ人奴隷であり、そのあと中国人がやってきました。19世紀までの移民は、ヨーロッパ人が100万人〜200万人、アフリカ人が800万人、中国人が400万人だったといいます。アフリカ人は使い捨ての奴隷として扱われました。その後、中国人があまり増えなかったのは、ある時点で強い規制がなされたためです。
清朝期には中国人が大移動していました。満洲には100万人、四川や台湾にも移民の波が押し寄せていました。清朝は祖先の地である満洲や、先住民のいる台湾を保護するために、移民を制限しなければならなかったといいます。人口の移動は、おそらく人口膨張と農業開発が関係しています。
シンガポールを建設したのは、イギリス人のトマス・ラッフルズ(1781〜1826)です。「イギリスはシンガポールを基点に、かつて東インド会社がイギリスとアジア間の独占的貿易をおこなった規模よりもずっと大きな規模のアジア域内貿易に参加し、利益を得ることができるようになった」。
シンガポールは「自由貿易」帝国イギリスの拠点となります。その収入を支えていたのがアヘンだったという点も再確認しておくべきでしょう。
いっぽう上海はアヘン戦争(1840〜42)終結後につくられた都市です。当初はアヘン交易の中心地として、のちには海上輸送の拠点、そして商業都市として発展していきます。もともとは外国人の居留地として位置づけられていましたが、しだいに中国人が押し寄せてきます。こうして上海は1920年代には「数百万の中国人と外国人が入り混じり、金と無秩序が支配する世界になった」。
ヨーロッパとアジアの距離を短くしたのは、1869年に完成したスエズ運河です。これによってロンドン─ボンベイ間の船賃は、一挙に3割安くなったといわれます。
スエズ運河開通後、世界は急速に変化していきました。インドネシアの島々ではタバコ、コーヒー、ココア、ゴムなどのプランテーションがつくられ、スズや石油の採掘もおこなわれるようになります。ベトナムやビルマの米は広東やロンドンに運ばれていきました。アジア各地にプランテーションが広がり、中国から大量の苦力(クーリー)がつれてこられました。こうしてアジアでは、民族の混交と分裂、差別と貧困が広がり、宗教やイデオロギーの対立も生じるようになります。
鉄道は陸上貨物の輸送コストを削減し、大量輸送を可能にしました。時刻の標準化と商品の規格化が進みます。鉄道は軍隊を移動させるための手段としても利用されました。飢饉(ききん)のさいにも、鉄道は大いに威力を発揮しました。
「輸送とは、物理的に異なる地域を移動するだけでなく、社会文化圏の相違を飛び越え、さらには歴史や時代を飛び越えてしまうことである」と著者は論じます。輸送とは単なる空間の移動ではなく、時間の移動、つまり歴史や文化の移動でもあるのです。こうして、19世紀の輸送技術の進展は、地球世界をちいさくすると同時に、商品世界を拡大していったのです。
メキシコでコーヒーがつくられるようになるのは1870年代ですが、鉄道ができるまでは、マヤの人びとがコーヒー袋をかついで、船着場まで運んでいたといいます。鉄道の建設によって、コーヒー農園は一挙に拡大し、コーヒー生産は倍増します。コーヒー豆はニューヨークに運ばれ、オハイオ州の巨大工場で焙煎(ばいせん)されて、全世界のコーヒーショップに卸されていきます。
しかし、そうした輸送改良によって、メキシコのマヤ人の労働環境が改善されたわけではありません。かれらは安い給料ではたらかされ、代々債務奴隷にされ、コーヒー袋をかついで黙々と険しい丘陵を行き来していたのです。
輸送の発達は一概に人びとを豊かにしたわけではありませんでした。単純に技術の進歩を喜べないのは、そこに(政治、経済を含めた)権力という契機がかかわっているからです。
19世紀になっても、長距離輸送の中心は水上交通(水運)でした。しかし、蒸気機関が発明され、鉄道が敷かれ、道路が整備されてくると、輸送コストは大幅に下がり、商品輸送のスピードも一挙に高まります。かつての中継地や中間商人は没落し、世界中の商品が集まる都市が発展します。そして、植民地主義がますます強化されていくのでした。
著者は、われわれがふだん愛用している嗜好品の裏側にも迫っています。ここで嗜好品というのはコーヒーや紅茶、ココア、タバコ、砂糖など、一度食べると癖になる食品を指しています。われわれはこうした嗜好品を、自由にスーパーやコンビニで好きなだけ買うことができます。しかし、そうした商品がどのように生産されているかは、ほとんど知らないものです。商品は包装された外見と値段が示されるだけで、その生産過程はほとんど舞台裏の隠された次元に遠ざけられているといってもよいでしょう。
上に挙げたこれらの食品は、もともと限られた地域でしか栽培されていませんでした。コーヒーはエチオピア、茶は中国、ココアはメキシコやアンデス一帯、タバコはアメリカ大陸が原産地です。それがいまでは世界中に広がって、だれにとっても、なくてはならない生活文化の一部となっています。
著者はこんなふうに書いています。
〈紅茶のないイギリス人、カフェオレのないフランス人、エスプレッソのないイタリア人、コーヒーブレイクのないアメリカ人を、誰が想像できようか。……コーヒーとタバコが男性関連だとすれば、チョコレートは女性と子供の飲み物だった。噛みタバコは庶民用、嗅ぎタバコと葉巻はエリート用となった。金持ちは、エレガントなサロンでメキシコ製の銀のティーポットから中国製の陶器のカップにそそがれる中国茶を飲んだ。他方、庶民は街頭の物売りから購入した紅茶を薄汚い粗悪なマグカップでちびちび飲んだ。〉
問題は、先進国の消費者を楽しませる(あるいは狂わせる)、こうしたさまざまな嗜好品やドラッグ(コカやアヘン、マリファナなど)の背後に、どのような商品経済の論理がはたらいていたかということです。
もともとカカオ豆はマヤやアステカの貴族や戦士に珍重されていました。興奮剤や麻酔剤、媚薬(びやく)として利用されていたようです。カカオ豆は貨幣としても用いられていました。これをスペインに紹介したのがイエズス会の修道士です。16世紀初頭のスペイン人はカカオ豆をつぶして水で溶かし、砂糖、シナモン、バニラを加えて飲んでいました。お湯で溶かし、ミルクを加えるようになるのは18世紀になってからです。そのころカカオの栽培地は、すでにベネズエラ、ブラジル、インドネシア、フィリピンにまで広がっていました。1828年、オランダ人のカスパルス・ヴァンホーテンがココアを発明、さらに19世紀後半にミルクチョコレートが開発されます。
ここに挙げた嗜好品のうち、茶の木だけは中国が海外に流出することをしばらく阻んでいました。中国茶が紅茶に変貌するのは輸送中の偶然のできごとでした。イギリスでは紅茶と砂糖が結びついて、中国からの茶の輸入がどんどん膨らんでいきます。中国との貿易赤字を解消するために、イギリスが中国に持ちこんだのがアヘンだったという話はあまりにも有名です。いっぽう、イギリスは19世紀に中国から茶の木をもちだし、それをセイロン(現スリランカ)やアッサム地方(インド北東部)に移植することに成功しました。
コーヒーはエチオピアが原産地でしたが、次第にイエメンの山岳地帯でもつくられるようになり、1400年ごろからモカで、1500年ごろからアラビア半島で飲まれるようになり、次第にイスラム世界全体に広がっていきました。ヨーロッパにコーヒーが伝わったのは1683年、オスマントルコ軍がウィーン包囲に失敗したあとからだという説もあります。トルコ軍が戦場に残したコーヒーをもとに、ウィーンでコーヒーハウスがつくられました。
最初のころヨーロッパ人はモカから高いコーヒーを仕入れる以外に手だてがありませんでしたが、ルイ14世(1638〜1715)の植物園で、イエメンから持ち帰ったコーヒーの苗木が育てられ、それがアメリカ大陸に運ばれていくことになります。これがモカ・コーヒーのはじまりでした。
しかし実際は、それ以前にコーヒーはヴェネツィア人によって、すでにヨーロッパに持ちこまれていたのです。イタリア人がエスプレッソを飲む習慣は、ヴェネツィア人によってはじまったといってよいでしょう。
18世紀のロンドンでは、男たちがコーヒーハウスに入りびたりとなり、それが妻たちの怒りを買って、コーヒー排撃運動が発生します。イギリスが紅茶の国になるのは、そうした要因も手伝ったようです。こうしてイギリスは別として、スウェーデンでもプロイセンでもパリでも、アメリカでもコーヒー文化はたちまちのうちに広がっていきます。
アメリカ人はイギリス人と対抗するためにコーヒーを愛飲するようになったといわれます。しかし、事実は奴隷制がコーヒー生産を支え、その価格を廉価にしたのです。最初はハイチでした。その後、ブラジルがコーヒーの供給元となります。著者によれば、アメリカ人がコーヒー漬けになるのは「コーヒーが奴隷制度で安くなり、しかもコーヒービジネスが儲かったからなのである」。
砂糖についても述べておきましょう。サトウキビは昔からあったとはいえ、これを砂糖に精製したのはアラブ人で、ヴェネツィア人はアラブ人との砂糖交易で、大儲けしていました。ヴェネツィアに対抗して、ポルトガルは最初西アフリカ沖のサントメで奴隷による砂糖栽培をはじめます。それがさらにブラジル、そしてフランス領のハイチへと持ちこまれました。「砂糖プランテーションのオーナーたちは、古代ローマ時代を思わせる残忍極まりない奴隷労働を酷使して富を蓄えた」と著者は記しています。
そのハイチで1791年に革命が発生し、1804年にハイチは独立を果たします。しかし、そのあとには何も残りませんでした。島は砂糖に代わるものを生みだせず、アメリカの勢力圏に吸引されていきます。こうして「熱帯の楽園」は「惨めで活気のない僻地」へと変わっていくのです。
イギリスがインドのアヘンを中国に輸出したのは、中国との貿易赤字を解消するためだったということは前にも述べました。アヘンの流入により中国では銀が流出して、通貨危機が引き起こされ、アヘン輸入禁止措置をとった中国にイギリスは戦争をしかけます。それがアヘン戦争(1840〜42)でした。
さらにイギリスはインドのアヘンで大幅な貿易黒字を出し、大西洋での貿易赤字を埋め合わせました。「アヘンは、中国、インド、イギリス、合衆国を結び付け、四角貿易を成立させ、さらにイギリスの工業化を推進し、19世紀における世界経済の革命的拡大を支える中心的役割も果たした」
そして現在はコカインの時代です。コカはボリビアからペルーにかけての熱帯林に繁茂し、その葉はもともと宗教儀礼に用いられていました。スペイン人はそれをポトシ銀山でインディオたちを働かせつづけるために利用しました。
コカコーラは1948年までコカイン入りの飲み物でした。麻酔薬としてのコカインは1860年ごろから使用されましたが、同時に麻薬としても根強い人気がありました。ドラッグストアでは、その名のとおり、かつてコカインが売られていました。20世紀になって、コカインは享楽品としては禁止されるようになるのですが、1970年以降はコカインが新たなブームとなり、たびたびの取り締まりにもかかわらず、密売人が横行しているのが実情です。
ブーム商品の背景には、時に悲惨な風景が広がっています。生産の場であれ、消費の場であれ、商品の論理が力(契約と暴力)を背景としているという事実に、われわれはもうすこし自覚的であっていいのかもしれません。一皮めくれば、人類の社会も、経済学のきれいごとではすまされない、ホッブズ流の生存競争の渦中にあるのではないでしょうか。
ジョヴァンニ・アリギの世界(2)──商品世界ファイル(30) [商品世界ファイル]
『北京のアダム・スミス』(2007年)は2009年に亡くなったジョヴァンニ・アリギの遺著で、かれの晩年の関心は、急速に経済発展を遂げる中国をどのように理解したらよいかに向けられていました。
前著『長い20世紀』(1994年)が、15世紀から20世紀にいたる資本主義の長期的な歴史を扱ったのにたいし、この本は主に1960年代から2000年にいたる世界経済の変動を俎上(そじょう)にのせています。
その序文で、著者は「20世紀後半の歴史を書くとすると、東アジアの経済復興というテーマ以上に重要なテーマは、おそらくない」と書いています。日本からはじまって、韓国、台湾、シンガポール、香港、マレーシア、タイへとつづき、そしていよいよ中国が登場します。なかでも中国の台頭に焦点があてられることは、タイトルからも予想できるでしょう。
アダム・スミスは『国富論』(1776年)のなかで、西洋世界と非西洋世界の関係が対等となる時代を予見しましたが、その後、現実には両者間の不均衡はさらに拡大することになりました。しかし、現在、中国の経済発展により、スミスのビジョンが現実化しつつあるといいます。
著者が東アジアの経済「復興」というのは18世紀くらいまではアジアのほうがヨーロッパより進んでいたという認識があるためです。本書では、東アジアが経済復興を遂げるなかで、とりわけ中国の台頭に大きな意味を見いだしています。「中国は日本や台湾のようにアメリカの臣下ではなく、香港やシンガポールのように単なる都市国家ではないからだ」というあたりに、その思想性がうかがえます。
アダム・スミスの展望、すなわち市場社会にもとづく「文明共和国」──さまざまな文明が共存する世界共和国──は、はたして実現するのでしょうか。
現実は混沌としています。これからやってくるのは、ひょっとしたら「暴力の加速する時代」であり、「世界規模のカオス」かもしれない、とも著者は感じてもいます。
ふつう中国というと毛沢東やマルクス主義を思い浮かべるでしょう。ところが、そこにアダム・スミスをもってきたのが、本書の意外性があります。
著者はマルクスについても論じていますが、現代中国の動きはマルクスよりスミスによるほうが理解しやすいといいます。著者のいうマルクスは、革命家マルクスでなく、資本主義の構造、とりわけ労働過程に鋭い分析を加えた経済学者として位置づけられています。スミスもまた新自由主義者がもちあげるような市場原理主義者とはみられていません。弱肉強食の資本主義の思想家ではなく、もっと牧歌的な市場社会を唱えた思想家としてのスミスです。
著者のアリギはウォーラーステインに近い人のように思えます。ただし、ちがう部分もあります。15世紀以降、現代にいたるまで、世界では西洋(欧米)中心の資本主義的世界システムが築かれてきたというのが、ウォーラーステインの考え方です。これに対して、著者はこうした世界システム論では、周辺と位置づけられるアジアの動きがうまくとらえられないと主張します。
18世紀後半に産業革命が起こるまでは、世界の大商業国はイギリスではなく中国だったというのが著者の見方です。その中国がなぜいったん没落し、20世紀後半になって復興したのか、そして中国の台頭によって、これまでの西洋中心の資本主義的な世界システムはどのような変貌(へんぼう)をとげようとしているのかといった問題意識を著者はもっています。
中国の「社会主義市場経済」なるものの評価は、ずいぶん分かれています。「巨大な不平等と堕落」をもたらしているという見方があるいっぽう、国家統制された「市場経済」がもたらされたという見方もあります。
著者は「社会主義市場経済」を「資本主義」ではないととらえています。そうなると、資本主義の分析家であるマルクスは参照できません。市場社会の発展に重きを置いたスミスを登場させるのは、それなりに理由があります。実際、スミスは中国ではヨーロッパ以上に市場社会が発展しているとみていました。
ところが、ヨーロッパではその後スミスが予期していなかった産業革命(安価な鉱物資源の産業利用)が発生します。いっぽう中国はあくまでも農業が中心でした。何もおこなわれなかったわけではありません。農村共同体では、人口が増加するなかで、生活改善が試みられ、それが強い労働倫理となってあらわれました。著者はこれを「勤勉革命(industrious revolution)」と名づけています。
19世紀における西洋と東洋の「大分岐」、それは「産業革命」と「勤勉革命」の分岐でもありました。
19世紀における東洋の没落は実際の没落ではなく、西洋の急速な産業化と、それに伴う軍事技術の発達による相対的なギャップの広がりによるものにすぎませんでした。だが、この「勤勉革命」によって形成された「人間資源」は、その後、東アジアが産業化する過程で、大きな役割を果たすことになります。
著者は「勤勉革命」に導かれた中国の「市場経済」を高く評価しています。そこにスミス『国富論』の理念が投影されていることは明らかです。
著者はふたつの経済発展のちがいを強調します。
ひとつは社会的枠組みをこわさずに、社会の潜在的な力を引きだすタイプで、いわばスミス型の「自然的」な成長です。
もうひとつは社会的な枠組みを破壊して、新たな枠組みをつくりかえるタイプで、いわばシュンペーター=マルクス型の創造的破壊による成長です。
著者の理解は通説とはことなっています。
『国富論』は「市場を存在させるための諸条件を創造したり再生産したりする強い国家の存在を前提していた」といいます。スミスは国防や治安だけではなく、市場を含む社会全体への国家の介入をむしろ擁護していたというのです。スミスの目的はあくまでも経済社会における市場化のショックをやわらげることにあり、スミス自身、「自己調整的な」市場を提唱したわけではなかったといいます。
スミスはまた終わりなき「経済成長」を唱えたわけでもないといいます。かれにとって経済成長とは、人民と資本(蓄え)によって、空間(国)を満たすことにほかなりませんでした。
スミスといえば分業論ですが、かれは労働者による単純な反復動作が経済効率を高めると評価したわけではありません。むしろ、労働が簡単な方法に集中することで、創意工夫が高まり、それによって技術進歩と専門化が進むとみていたというわけです。こうして生産単位が専門化すると、同時に社会的分業が進展することになります。
農業と小売業(国内市場)→国内貿易→外国貿易へと経済が発展するのが、スミスの考える自然の経路です。ところが往々にして事態は逆の方向に進みます。立法者は非自然的な経路をできるだけ自然の経路に沿うよう修正していかねばならないとスミスは提言します。「スミスの最大の関心事は、国益を追求する中央政府の能力の確立とその保全にある」という理解も独特です。
著者のスミス評価はきわめて高いといってよいでしょう。それはスミスが市場経済の緩やかな成長を「自然的な」経路とみて、それにたいし、資本主義的な発展は「非自然的な」経路と考えていたからだといいます。
著者はシュンペーターとマルクスを資本主義の分析家ととらえています。
シュンペーターは、資本主義には「[従来の]社会的枠組みを破壊し、より大きな成長の潜在力をもつ新たな枠組みの出現のための諸条件を創造しようとする」傾向があるとみていたといいます。資本主義の特徴を資本の自己拡張ととらえ、その運動をたえざる均衡の転覆、いいかえれば創造的破壊としてとらえたのがシュンペーターでした。
これにたいし、マルクスは資本主義を動かしているのは、終わりなき貨幣の蓄積への欲望だと考えていました。マルクスが資本主義の出発を16世紀における世界商業と世界市場の創出に求めるのは当然でした。したがって、著者にいわせれば、マルクスは「アジアの諸国や文明は、ヨーロッパの資本主義的な経路の出現を可能にした市場を提供したのであって、ヨーロッパのブルジョワジーの襲来に対して生き延びるチャンスはなかった」ということになります。
著者によると、マルクスは「貨幣の一般的形式を表現するものとしての資本は、自らを制限する障壁を乗り越える、終わりも限界もない駆動力である」ととらえていました。資本主義はみずからを過剰蓄積による危機へと追いこむ傾向をもっているが、マルクスはもろもろの危機をバネに資本主義は経済社会の根本的再構成をはかっていくと考えていたといいます。
マルクスはまた、競争の激化にともなう利潤率の低下に対応するために、資本は集積(規模拡大)あるいは集中(統合)によって、その危機を乗り越えようとするととらえていました。その際、重要になってくるのが信用制度、すなわち金融の役割でした。
シュンペーターが焦点をあてたのは「創造的破壊のプロセスの両面としての好況と不況の概念」です。好況と不況のプロセスを通じて、古い経済構造は絶え間なく破壊され、革新を通じた新たな経済構造が創造されると考えられていました。
シュンペーターは創造的破壊による革新を「新結合の遂行」ととらえ、そのような革新的行為者を「企業者」と名づけます。新結合は、工業における技術的・組織的革新だけではなく、あらゆる商業的な革新を含むものでした。
資本主義は創造的破壊によって発展します。農民が生産手段から分離され、先住民が制圧され、ときに奴隷として扱われたのも、そうした破壊の一形態にほかなりません。資本主義とは「資本と権力の終わりなき蓄積の継起」として定義できる、と著者はいいます。
しかし、ほんとうはもっと別の径路があってもよいのではないか。それは市場社会の自然で緩やかな拡大をともないながら、反資本主義的傾向をもつ経済発展、すなわち国家による資本主義の抑制をともなう経済発展のあり方です。著者はその路線をスミスに読みこみ、スミス経済学の新しいパラダイムをつくりあげ、それを現在の中国にあてはめて理解しようとしました。
それはたしかに願望といえば願望でした。文化大革命や天安門事件が取りあげられていないことをみても、このあてはめが正しかったかどうか、評価しなおす必要があります。
本書の最大のテーマは次のようなものです。
世界資本主義システムにおいて、アメリカがヘゲモニーを握る時代は終わりつつある。中国の台頭はどのような意味をもつのか。そして、ポスト・アメリカ時代の世界はどんなふうになっていくのか。
著者は大英帝国が世界のヘゲモニーを失いつつあった19世紀後半から20世紀はじめの状況──長期不況から大戦前の「ベル・エポック」にいたる状況──と、現在アメリカのおかれている状況とがよく似ていると考えています。
1970年代以降、アメリカを中心とする世界資本主義システムには、「グローバルな乱流」が生じました。ポイントの年は1973年、1985年、1995年だったといいます。
1973年には金ドル本位制が崩壊し、変動為替相場制がはじまりました。1985年のプラザ合意では、ドル危機の再発を防ぐため、各国の協調によりドルの切り下げ(日本の場合は円高)が誘導されました(1985年当初1ドル=250円だったレートは86年には160円となっています)。
そして1995年の先進7カ国財務相・中央銀行総裁会議での「逆プラザ合意」では、行きすぎたドル安(円高)を反転するための政治的合意がなされました(この年、円は1ドル=79円を記録しましたが、すぐ100円に是正されています)。
こうした動きは、いったい何を象徴していたのでしょう。
著者はまずマルクス主義経済学者ロバート・ブレナーの説を紹介するところから、国際経済の乱流を解き明かそうとしています。
ブレナーによれば、1950年代、60年代の好況期には「不均等発展」が生じ、アメリカに対するドイツと日本の急速な追い上げがみられました。アメリカの製造業者は国際競争に耐えきれなくなり、そのため通貨当局はドルの平価切り下げに踏み切らざるを得なくなります。そして、これが容易なことでは収まらず、けっきょくは変動為替相場制の採用にいたったというのです。
その結果、アメリカ経済はにわかに活気づきます。
しかし、1970年代後半のアメリカの財政赤字は、インフレをもたらしたわりに生産の増大をもたらさず、ドルが大量に流出することになりました。他方、アメリカの高い実質金利を求めて、世界中から莫大な量の資本が流入しはじめます。アメリカの金融資本は強化されました。ただし、それによってドルは上昇し、アメリカの製造業は大きな打撃をこうむります。そのため、アメリカの圧力によって、ドルの為替レートを引き下げる1985年のプラザ合意がなされたというのです。
プラザ合意によって、アメリカの利潤率や投資、生産は回復します。しかし、とりわけ日本などは深刻な危機におちいりました。ブレナーによると、1995年の「逆プラザ合意」は「危機に陥った日本の製造業を救うため」の救済措置だったといいます。
皮肉なことに「逆プラザ合意」は、日本などから巨額の資金がアメリカの金融市場に流れこむ結果を招きました。金融自由化もあいまって、ドル高への期待が高まったからです。これがアメリカの株式バブルへとつながり、経済全体の過剰な投機へとつながっていきました。
本書が発行されたのは2007年のことで、2008年のいわゆるリーマン・ショック以前のことです。したがってバブルの破裂は予測されているものの、それは兆しとしか意識されていませんでした。
とはいえ、著者は現在資本主義大国のおかれた状況は、19世紀末から20世紀はじめと同じ「長期的停滞期」にあるとみており、その結末が「恐慌」のようなものをもたらすにちがいないと予測していました。それは幸か不幸か的中することになります。
もちろん、昔の大英帝国と現在のアメリカには大きなちがいがあります。かつては没落する大英帝国に挑戦する新興国の動き(たとえばイギリス対ドイツ)が見られましたが、いまのところはアメリカの圧倒的な軍事力に挑戦する国はなさそうです。したがって、暴力やテロ、戦闘は頻発するにせよ、20世紀前半のような世界戦争が起こる可能性は少ない、と著者はみていました。
それに、もうひとつ特筆すべきことがあります。それは以前のイギリス以上に、アメリカが世界中から資金を吸収する仕組みを築いていることです。
1世紀前と現在では危機の発現の仕方にちがいがあります。それでも「グローバルな乱流」はあり、それがどこに行き着くかを著者は見届けようとしていました。
アメリカを中心に世界経済の変遷を整理したブレナーの分析を、アリギは次のように批判します。
第1点。20世紀後半には、実質賃金の上昇が資本主義システム全体の収益性を引き下げ、同時にインフレを引き起こした。しかし、ブレナーは労使関係より資本家間の競争に目を向けるため、「水平的」(資本どうしの)対立と「垂直的」(労使間の)対立の複雑な歴史的相互作用をとらえそこなっている。
第2点。ブレナーはアメリカ、ドイツ、日本の経済に焦点を合わせるが、この3国が世界の貿易に占める割合は1950年以降、次第に減少し、とりわけ90年代半ばからは中国のシェアが急速に拡大することを見逃している。
第3点。レーガンとサッチャーが新自由主義を採用したのは、単に収益性の危機に対応するためではなく、資本主義システムにおけるヘゲモニーの危機が深まったためでもある。しかし、ブレナーは政治的要因についてほとんど論じていない。固定為替相場制が崩壊したのは、ベトナム戦争の影響が大きかった。
第4点。ブレナーの問題は、かれが製造業にのみ焦点をあてていることである。「アメリカの金融・保険・不動産による企業利潤は、1980年代には製造業に追いつき、1990年には追い越している」。
第5点。ブレナーは新自由主義者、すなわちマネタリストの「反革命」のもつ意味を見落としている。「マネタリストの『反革命』がアメリカの権力の衰退を逆転させることに驚くほど成功した主たる理由は、逆に、それがグローバルな資本フローをアメリカとドルへと大量に回帰させることに貢献したからであった」。
こうした批判は、著者がブレナーの論述を、みずからのヘゲモニー移行論に組み入れようとした軌跡を示しているとみることができます。
著者によれば、ヘゲモニーの危機には「予兆的危機」と「終末的危機」とがあり、このふたつは区別されなければならないといいます。アメリカは予兆的危機を迎えたあと、第2次世界大戦前の「ベル・エポック」にも似た「よき時代」を迎えました。しかし、それは長くつづきませんでした。2001年の9・11後の対応はアメリカの「終末的危機」を早め、中国のリーダーシップを強化することにつながりました。
1985年のプラザ合意、95年の「逆プラザ合意」は、たしかに変動為替相場制の区切りでしたが、むしろ決定的だったのは70年代末から82年にかけてのマネタリストの「反革命」だったと著者はいいます。
1970年代には「石油ショック」により、石油輸出機構(OPEC)が勢いづき、インフレ傾向が強まります。そして800億ドルの「オイルダラー」が生まれました。ユーロダラー市場の膨張は、固定為替レートの安定性を危うくし、システム崩壊を現実のものとしました。
固定為替レート体制の崩壊は「商工業活動のリスクと不確実性」を増大させ、「資本の金融化」にはずみをつけることになります。その結果、通貨市場での金融投機が活発になります。
こうして世界的な貨幣と信用の供給が、すさまじく拡大しました。これに見合う需要はなかなか存在せず、それがインフレ圧力となりますが、いっぽうで海外のものをなかなか手に入れられなかった国が、容易に資金を借りられるようになりました。
70年代後半の問題は、世界中を駆け回るようになったマネーが、ワシントンの発行するドルと競争し、それが相互破壊的な競争をもたらして、アメリカのヘゲモニーの危機を深刻化し、大量のドル売りをもたらしたことだと著者はいいます。
しかし、この巨額なドル売りによって、相互破壊的な競争が突然終了し、だれもが予期していなかったアメリカの繁栄がふたたび訪れるのです。
この間に、アメリカは世界の余剰マネーを自国に集める金融装置をつくりあげたのです。しかし、これは遠からぬうちに終わり、そして、そのあとにヘゲモニーの「終末的危機」がやってくる、と著者は予想していました。
企業は国内での直接投資や雇用を控えるようになって、資金を退蔵する(あるいは高額の役員報酬に回す)か、投機に回すようになります。世の中全体にカネが回らないから、景気はよくなるはずもありません。
そして政治的には、アメリカのヘゲモニーが弱まり、新たなパワーをもつ国家(すなわち中国)の出現を許すことになります。
さらに社会的には、持てる者と持たざる者の不平等が拡大し、これまでの中流階級が下層階級に転落していくことによって、社会全体にいらだちや投げやりな姿勢、あるいはやけっぱちな動き、抵抗や反抗が広がっていくと思われました。
不幸なことに、この予言は的中しました。
いまアメリカに広がっているのは、そうした状況です。そして、その状況は現在の日本の状況ともつながっています。
ただし、著者はこの「終末的危機」によって、かつてのような「上り坂の資本主義大国と資本主義大国との間の軍拡競争」のようなものは発生しないし、また市場の分割のようなことは起こらないだろうと予想していました。
いまのアメリカの繁栄は、最終的には世界中から集まる資金を「純粋な貢ぎ物」ないし「みかじめ料」(守ってやっているのだから、カネを出せ)として処理することで成り立っており、その試みが世界中を不安におとしいれていることはまちがいないといいます。
そして格言「我とともにあらん、さすれば我が亡きあとに洪水よ来たれ」をかかげます。
著者はソ連崩壊以降、みずからを「世界国家」たらしめんとするアメリカの無謀な試みが、9・11後のイラン・アフガン戦争をへて、けっきょく失敗に終わったこと、そしてアメリカのヘゲモニーがくずれて、ヘゲモニーなき時代になったことを指摘しています。あとにつづくのは「中国の世紀」なのだろうか、というのが著者の問いです。
ところで、その前に、著者がアメリカの「ビジネスのひな型」はゼネラル・モーターズからウォルマートに移行したと指摘していたのが印象に残りました。ウォルマートというのは、アメリカに拠点をおく世界最大のスーパーマーケット・チェーン。ゼネラル・モーターズ(GM)は、いわずと知れたアメリカを代表する自動車会社です。
著者によると、ウォルマートの経済規模はいまやGMより大きく、150万人の従業員をかかえ、売り上げはアメリカのGDPの2.3%を占めているといいます。
アメリカでは自動車会社よりスーパーのほうが、大きな経済規模を占めるようになりました。GMが世界に生産拠点を広げながら、ほとんどアメリカ国内で車を製造し、販売するのに対して、ウォルマートは大半の製品をアジアの製造業者から集めて、消費者に販売しています。
著者はウォルマートの台頭に、アメリカが「グローバルな金融集積地としての役割をもつ国家」になったことを重ねています。
ウォルマートは労働コストの高い自国製品にこだわらず、便利なものを海外、とりわけアジア(なかでも中国)でつくらせて、それを消費者に安く提供することで、利益を確保しています。製造業者は、中国製と同じようなものをつくろうとしても割にあわないから、けっきょく仕事をやめてしまい、そこで働いていた労働者は失業してしまいます。アメリカのビジネスは工業中心から、明らかにサービス業、とりわけ金融へと移行しています。
著者は前著『長い20世紀』のなかで、世界資本主義のヘゲモニーを担う中心国が、当初、産業国家として出発し、次に金融国家として成熟しながら、最後に新たな国にヘゲモニーをゆずっていく過程を一般的な傾向としてとらえ、それを600年にわたる資本主義の歴史のなかに描いてみせました。
したがって、現在のアメリカもまた、世界の中心国たる位置を失いつつある途上にあると映ります。その象徴がウォルマートの隆盛でした。マネタリストの反革命が、アメリカを産業国家から金融国家に変質させてしまった、とかれはいいます。もっともそれは20世紀はじめの話で、2020年の時点ではウォルマートの力は相対的に弱まり、GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)が社会全体をおおうようになっています。
アメリカ、日本に共通することですが、おそらく中国製品の大量流入が、70年代の宿痾(しゅくあ)であった世界的インフレの抑制に成功したことはまちがいないでしょう。しかし、それとともに同じような商品で、中国製品と対抗しなくてはならなくなった企業が苦戦を強いられたのも事実です。
国内の競争がさらに値下げに拍車をかけました。賃金は上がらなくなり、日本では非正規社員の割合が増えました。経済成長率は停滞します。好況感がわかないはずです。
ジャーナリストのジェームズ(ジム)・マンは、アメリカが共産党独裁義国家、中国の世界貿易機関(WTO)加盟を安直に認め、それによって中国製品をアメリカ国内にあふれさせたのが、何よりもまちがいだったと述べていました(『米中奔流』)。かれは中国製品にもっと関税をかけ、中国の国際的な動きを監視し、中国内の民主化運動を支援せよと主張していました。
とはいえ、いまや中国が経済大国となり、中国製品が世界中を席巻していることは、ほとんどだれもが認めるところです。この流れは、当面、収まりそうにありません。著者はこの事実から出発して、世界資本主義システムのなかで、中国の挑戦がもつ意味をとらえなおそうとしています。
現在、アメリカが中国をどう取り扱えばいいのか迷っている様子は、本書からもうかがえます。
〈21世紀への変わり目における米中関係の問題は、もはやアメリカの中国への商業的アクセスではない。むしろ問題なのは、中国がアメリカに代わって世界でもっとも急速に成長している主要な経済圏になったという事実であり、中国が他国と同様に、アメリカへの商業的アクセスを求めているという事実である。〉
アメリカは、どのように対応しようとしているのでしょうか。
著者はロバート・カプラン(ジャーナリスト)、ヘンリー・キッシンジャー(元国務長官)、ジェームズ・ピンカートン(コラムニスト)の3人の論者をとりあげて、それぞれの対応策を紹介しています。
中国に対抗する「連合」を結成して、中国を封じ込めようというのが、カプランの策です。米太平洋軍司令部(PACOM)を中心に日本、韓国、タイ、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、インドを結んで、一種の太平洋軍事同盟を形成するという構想で、これによって中国の太平洋進出を抑制しようというもの。一種の新冷戦戦略といえるでしょう。
これに対し、キッシンジャーは、中国はソ連のような軍事的帝国主義国家ではないとして、冷戦のときのような封じ込めをこころみるのはおろかだと主張します。中国が採用している「平和的台頭」路線は、中国のいうように「既存の世界秩序を乱すことのない」成長なのであって、中国が台湾問題やいくつかの領土問題をかかえているにせよ、侵略に転じる可能性はないと判断します。
ピンカートンの考え方は、中国との対立と和解を組み合わせるものといえるかもしれません。もはや大国間の戦争を想定するのは時代遅れであり、アメリカと中国は経済的にも密接に結びついている。封じ込め戦略は突発的な衝突を招きやすいので、避けなければならない。そのためアメリカは中国と直接対決せず、インドや日本などが中国と張り合うのを背後から見届けるのがよいという立場をとります。
アメリカのアジア戦略、とりわけ対中戦略は、この3人の論者が示すように、三者三様に揺れています。
アメリカの腰が定まらないのは経済学者のクルーグマンがいうように、アメリカが「中国の米ドル買い(そして安価な中国商品)に病みつきになってしまった」からでもあり、全面的な中国バッシングが起こりにくいのは、巨大な中国市場に魅力があることを隠せないからではないでしょうか。
著者自身は、アメリカがどのような対中政策をとるべきかを論じているわけではありません。むしろ、かれは「将来何が起こり、何が起こらないか」を予測するためにも、過去にさかのぼって、西洋史の枠にこだわらず、中国がこれまで歩んできた道をふり返ってみなくてはならないと提案します。
国家がヨーロッパの発明だと思うのはまちがいだと指摘するところからはじめています。「日本や朝鮮、中国からベトナム、ラオス、タイ、カンボジアまで、東アジアのもっとも重要な国々は、ヨーロッパの国々よりもずっと前から国民国家であった」。そして、これらの国々のあいだでは、朝貢貿易に加えて、私的な交易がくり広げられていたというわけです。
しかも、ヨーロッパとちがって東アジアの特徴は、戦争が割合に少ないことでした。ヨーロッパのように、海外に帝国を築いたり、他国を侵略したり、互いに軍拡競争に走るといった傾向はまずありませんでした。
ヨーロッパの国々においては絶えざる戦争によって、破壊的な戦争手段の開発が進み、また海外の資源獲得をめぐって、各国間の激しい争いが起きていました。
アジアとの長距離貿易によって利を得ていたのは、むしろヨーロッパのほうです。鄭和(ていわ)のインド洋遠征は中断されるのに、コロンブスがアメリカを「発見」し、ヴァスコ・ダ・ガマがインド航路を開発するのは、まさにこの非対称性の反映だったともいえます。
国内市場もまた西洋の発明ではなく、アダム ・スミスは、18世紀における最大の国内市場がヨーロッパではなく中国にあったことを認めていました。著者は南宋以来、明、清にいたる中国の市場社会の発展を細かく追い、スミスが示した豊かさへの「自然な」経路の典型は、むしろ中国に見いだされると論じています。
さらに「清朝政府が開発の優先順位を、農業の改善、土地の再分配や開拓、国内市場の強化と拡大に割り当てたことは、まさにスミスが『国富論』で主張したことと同じである」と述べています。
その後は、ヨーロッパが不自然な「世界史に類例のない創造的破壊のプロセス」を採用することによって、アジアの国々の自律性は失われていきます。中国経済がある時点で停滞におちいったという見方を著者はとりません。18世紀に中国は奇跡的な成長を遂げ、「本質的に新しいタイプの農民社会」を実現したとみます。それはヨーロッパの資本主義的発展とはことなる市場社会でした。資本家(商人)は社会の上層ではなく、下位の社会集団にとどまっていました。
しかし、著者はいいます。
〈ヨーロッパの発展径路において典型的であった軍国主義と産業主義、そして資本主義の相乗効果は絶え間ない領域的拡大を推進し、またそれによって支えられていた……しかし中国と東アジアのシステムは、ヨーロッパのように海外への拡張と軍拡競争という道を歩まなかったため、拡張するヨーロッパの権力の軍事的猛攻撃に対し、脆弱(ぜいじゃく)なものとなってしまった。東アジアが猛攻撃を受けた際に、グローバル化するヨーロッパのシステムへと従属的に組み込まれたのは、必然的な結論だった。〉
イギリスの資本主義的商品が中国になかなか浸透しなかったことはよく知られています。むしろ、茶や絹といった中国製品の魅力が、イギリスの綿製品を圧倒していました。そこで、イギリスはアヘンを輸出することによって、貿易のバランスをとろうという悪辣(あくらつ)な方略を思いつきます。これが中国からの大量の銀の流出を招き、清朝の財政を破綻(はたん)させる原因となります。アヘン戦争は起こるべくして起こった出来事でした。
こうして中国はだんだんと「グローバルな資本主義システムにおいて、従属的かつ次第に周辺的となるメンバー」になっていきます。
日本は明治維新による中央集権化を通じて、急速な産業化と軍事化を実現しました。その結果、日清、日露戦争に勝利し、一時は中国に代わって「アジアの盟主」になるかにみえました。しかし、それはアメリカによってはばまれました。
日本の敗北によって、中国では内戦をへて中華人民共和国が成立します。
著者は19世紀後半から20世紀前半にかけては、東アジアの発展経路が西洋の経路に収斂(しゅうれん)したが、20世紀後半にはそれが逆転して、西洋の径路が東アジアの径路に収斂するようになったと書いています。
東アジアの近代は、中国中心から日本中心、そしてアメリカ中心へと推移しました。しかしベトナム戦争での敗北により、アメリカのヘゲモニーは揺らぎはじめます。それは日本の金融支援によって一時復権するかにみえましたが、最終的に強化されることはありませんでした。
そこに中国がグローバルな市場として開かれるいっぽう、中国が世界中に広がる華僑ネットワークを通じて、海外貿易や投資にも乗りだすと、東アジアの構図は一変します。中国の成功は、「東アジアの再興のまったく新しい段階、つまりアジア地域の経済が中国を中心に再編される段階」を告げている、と著者は断言しています。
外国資本にとって中国の魅力は「巨大で安価な労働予備軍」ではなく、「労働予備軍の高い資質」だと、著者は書いています。
中国が台頭し、「経済的ルネッサンス」を迎えたのは、「中国が外国資本を必要とした以上に、外国資本が中国を必要とした」からです。中国の経済拡張は「外国貿易と投資に開かれている」。そのあたりが、昔の日本とちがうところだとも書いています。
かといって、中国はしっかり国益を守っています。海外からの直接投資を認める場合も、それが自国に役立つ場合にかぎられているのです。規制緩和と民営化は慎重な配慮のうえになされ、政府は新規産業の創出、経済(輸出)特区の設立、高等教育、インフラ整備に力を注いできました。
中国の経済特区には、労働集約型(部品生産や組み立て)の珠江デルタ[たとえば深圳(しんせん)]、資本集約型(半導体、コンピューターなど)の長江デルタ[上海]、中国版シリコンバレーというべき北京中関村などがありますが、その場合も中国政府は対外貿易だけを応援していたわけではありません。
中国政府が何よりも優先したのは、産業化の基盤として教育であり、国内市場であり、さらには農業開発である、と著者は断言します。
それは資本主義への移行というより、アダム・スミス的な市場経済重視の姿勢のあらわれだといいます。まず全国で外国の技術に対する企業者の情熱が生まれ、それによって国内市場が開拓され、最後に海外市場に向かうという方向は、まさにアダム・スミスの方策です。
正規部門の労働者は雇用が保証され、医療や年金に対する給付金もじゅうぶんに支給されています。「国内市場の形成と農村地域における生活条件の改善」、これが中国政府が何よりもめざすものだ、と著者は断言します。
中国の農村が豊かになったのは、1970年代後半から農業生産請負責任制が導入されてからです。それによって農業の生産性と農民の収入が一気に高まりました。加えて農村地帯に「郷鎮企業」が生まれ、農村の余剰労働力を吸収していったことも、農民の生活改善に役立ったといいます。
郷鎮企業は中国経済に大きく寄与し、農村の収入を増やすとともに、国内市場を拡大する役割を果たしました。それはマルクスのみた農村の分解、あるいは「本源的蓄積」とはまったく異なるスミス的な発展経路であり、「産業(industrial)革命」ならぬ「勤勉(industrious)革命」のもたらした成果だったといいます。
著者は鄧小平の改革を高く評価しています。この改革は企業者の活力を引き出し、一人あたり所得の上昇をもたらし、市場経済を引っ張っていく共産党の政治基盤を強固にしました。中国ではソ連とちがって、「農村の破壊ではなく、農民の経済と教育の高揚」を通じて近代化が進められたというのです。
しかし、現在の中国に社会的矛盾がないわけではない、と最後に著者はつけ加えます。「一つは所得の不平等の大幅な拡大であり、もう一つは改革の手続きや結果に対する人々の不満の増大である」。各地で社会的騒擾(そうじょう)やストが頻発し、いっぽうで言論の自由が封殺されています。それがどういう方向にいくかは、だれにも予想できません。
「エピローグ」では、中国の台頭が世界の文明にどのような意味をもつかが論じられ、重要なのは、かつてスミスが主張したように、西洋人と非西洋人とのあいだに平等と相互尊重の姿勢が生まれるのかということだというテーマが掲げられます。
著者は、アメリカが同盟国と中国を対峙(たいじ)させて「漁夫の利」をねらったり、昔ながらの「封じ込め政策」をとったりするのは、まったく時代に逆行しているし、むしろ世界を混乱におとしいれる危険性をもっている。かといって、キッシンジャーの考えるように、中国をアメリカのシステムに包摂しておくのも無理があるといいます。中国が南北対立の解消に積極的な役割を期待するとも書いています。
締めくくりの一節はこうなっていますが、けっして楽観的ではありません。
〈新たな方向づけにより、中国が伝統の再興に成功し、自立した市場を基盤とする発展、収奪なき資本蓄積、非人的ならぬ人的資源の動員、大衆参加型の政治による政策形成を遂げることができるなら、中国が文化のちがいを尊重しあう諸文明連邦の形成に大きく寄与するようになる公算が高い。しかし、その方向づけがうまくいかなければ、中国が社会的・政治的混乱の新たな震央に転じる可能性もある。その場合は、北側(先進資本主義諸国)が巻き返しをはかって、崩れつつあるグローバルな支配を再構築しようとするかもしれない。あるいは、ふたたびシュンペーターの言い方を転用すれば、社会的・政治的混乱が、冷戦体制の消滅に続いて生じている暴力をエスカレートさせ、人類を恐怖(もしくは昇天)へと駆り立てていかないともかぎらない。〉
お互い冷静になって、先を見つめなければなりません。
前著『長い20世紀』(1994年)が、15世紀から20世紀にいたる資本主義の長期的な歴史を扱ったのにたいし、この本は主に1960年代から2000年にいたる世界経済の変動を俎上(そじょう)にのせています。
その序文で、著者は「20世紀後半の歴史を書くとすると、東アジアの経済復興というテーマ以上に重要なテーマは、おそらくない」と書いています。日本からはじまって、韓国、台湾、シンガポール、香港、マレーシア、タイへとつづき、そしていよいよ中国が登場します。なかでも中国の台頭に焦点があてられることは、タイトルからも予想できるでしょう。
アダム・スミスは『国富論』(1776年)のなかで、西洋世界と非西洋世界の関係が対等となる時代を予見しましたが、その後、現実には両者間の不均衡はさらに拡大することになりました。しかし、現在、中国の経済発展により、スミスのビジョンが現実化しつつあるといいます。
著者が東アジアの経済「復興」というのは18世紀くらいまではアジアのほうがヨーロッパより進んでいたという認識があるためです。本書では、東アジアが経済復興を遂げるなかで、とりわけ中国の台頭に大きな意味を見いだしています。「中国は日本や台湾のようにアメリカの臣下ではなく、香港やシンガポールのように単なる都市国家ではないからだ」というあたりに、その思想性がうかがえます。
アダム・スミスの展望、すなわち市場社会にもとづく「文明共和国」──さまざまな文明が共存する世界共和国──は、はたして実現するのでしょうか。
現実は混沌としています。これからやってくるのは、ひょっとしたら「暴力の加速する時代」であり、「世界規模のカオス」かもしれない、とも著者は感じてもいます。
ふつう中国というと毛沢東やマルクス主義を思い浮かべるでしょう。ところが、そこにアダム・スミスをもってきたのが、本書の意外性があります。
著者はマルクスについても論じていますが、現代中国の動きはマルクスよりスミスによるほうが理解しやすいといいます。著者のいうマルクスは、革命家マルクスでなく、資本主義の構造、とりわけ労働過程に鋭い分析を加えた経済学者として位置づけられています。スミスもまた新自由主義者がもちあげるような市場原理主義者とはみられていません。弱肉強食の資本主義の思想家ではなく、もっと牧歌的な市場社会を唱えた思想家としてのスミスです。
著者のアリギはウォーラーステインに近い人のように思えます。ただし、ちがう部分もあります。15世紀以降、現代にいたるまで、世界では西洋(欧米)中心の資本主義的世界システムが築かれてきたというのが、ウォーラーステインの考え方です。これに対して、著者はこうした世界システム論では、周辺と位置づけられるアジアの動きがうまくとらえられないと主張します。
18世紀後半に産業革命が起こるまでは、世界の大商業国はイギリスではなく中国だったというのが著者の見方です。その中国がなぜいったん没落し、20世紀後半になって復興したのか、そして中国の台頭によって、これまでの西洋中心の資本主義的な世界システムはどのような変貌(へんぼう)をとげようとしているのかといった問題意識を著者はもっています。
中国の「社会主義市場経済」なるものの評価は、ずいぶん分かれています。「巨大な不平等と堕落」をもたらしているという見方があるいっぽう、国家統制された「市場経済」がもたらされたという見方もあります。
著者は「社会主義市場経済」を「資本主義」ではないととらえています。そうなると、資本主義の分析家であるマルクスは参照できません。市場社会の発展に重きを置いたスミスを登場させるのは、それなりに理由があります。実際、スミスは中国ではヨーロッパ以上に市場社会が発展しているとみていました。
ところが、ヨーロッパではその後スミスが予期していなかった産業革命(安価な鉱物資源の産業利用)が発生します。いっぽう中国はあくまでも農業が中心でした。何もおこなわれなかったわけではありません。農村共同体では、人口が増加するなかで、生活改善が試みられ、それが強い労働倫理となってあらわれました。著者はこれを「勤勉革命(industrious revolution)」と名づけています。
19世紀における西洋と東洋の「大分岐」、それは「産業革命」と「勤勉革命」の分岐でもありました。
19世紀における東洋の没落は実際の没落ではなく、西洋の急速な産業化と、それに伴う軍事技術の発達による相対的なギャップの広がりによるものにすぎませんでした。だが、この「勤勉革命」によって形成された「人間資源」は、その後、東アジアが産業化する過程で、大きな役割を果たすことになります。
著者は「勤勉革命」に導かれた中国の「市場経済」を高く評価しています。そこにスミス『国富論』の理念が投影されていることは明らかです。
著者はふたつの経済発展のちがいを強調します。
ひとつは社会的枠組みをこわさずに、社会の潜在的な力を引きだすタイプで、いわばスミス型の「自然的」な成長です。
もうひとつは社会的な枠組みを破壊して、新たな枠組みをつくりかえるタイプで、いわばシュンペーター=マルクス型の創造的破壊による成長です。
著者の理解は通説とはことなっています。
『国富論』は「市場を存在させるための諸条件を創造したり再生産したりする強い国家の存在を前提していた」といいます。スミスは国防や治安だけではなく、市場を含む社会全体への国家の介入をむしろ擁護していたというのです。スミスの目的はあくまでも経済社会における市場化のショックをやわらげることにあり、スミス自身、「自己調整的な」市場を提唱したわけではなかったといいます。
スミスはまた終わりなき「経済成長」を唱えたわけでもないといいます。かれにとって経済成長とは、人民と資本(蓄え)によって、空間(国)を満たすことにほかなりませんでした。
スミスといえば分業論ですが、かれは労働者による単純な反復動作が経済効率を高めると評価したわけではありません。むしろ、労働が簡単な方法に集中することで、創意工夫が高まり、それによって技術進歩と専門化が進むとみていたというわけです。こうして生産単位が専門化すると、同時に社会的分業が進展することになります。
農業と小売業(国内市場)→国内貿易→外国貿易へと経済が発展するのが、スミスの考える自然の経路です。ところが往々にして事態は逆の方向に進みます。立法者は非自然的な経路をできるだけ自然の経路に沿うよう修正していかねばならないとスミスは提言します。「スミスの最大の関心事は、国益を追求する中央政府の能力の確立とその保全にある」という理解も独特です。
著者のスミス評価はきわめて高いといってよいでしょう。それはスミスが市場経済の緩やかな成長を「自然的な」経路とみて、それにたいし、資本主義的な発展は「非自然的な」経路と考えていたからだといいます。
著者はシュンペーターとマルクスを資本主義の分析家ととらえています。
シュンペーターは、資本主義には「[従来の]社会的枠組みを破壊し、より大きな成長の潜在力をもつ新たな枠組みの出現のための諸条件を創造しようとする」傾向があるとみていたといいます。資本主義の特徴を資本の自己拡張ととらえ、その運動をたえざる均衡の転覆、いいかえれば創造的破壊としてとらえたのがシュンペーターでした。
これにたいし、マルクスは資本主義を動かしているのは、終わりなき貨幣の蓄積への欲望だと考えていました。マルクスが資本主義の出発を16世紀における世界商業と世界市場の創出に求めるのは当然でした。したがって、著者にいわせれば、マルクスは「アジアの諸国や文明は、ヨーロッパの資本主義的な経路の出現を可能にした市場を提供したのであって、ヨーロッパのブルジョワジーの襲来に対して生き延びるチャンスはなかった」ということになります。
著者によると、マルクスは「貨幣の一般的形式を表現するものとしての資本は、自らを制限する障壁を乗り越える、終わりも限界もない駆動力である」ととらえていました。資本主義はみずからを過剰蓄積による危機へと追いこむ傾向をもっているが、マルクスはもろもろの危機をバネに資本主義は経済社会の根本的再構成をはかっていくと考えていたといいます。
マルクスはまた、競争の激化にともなう利潤率の低下に対応するために、資本は集積(規模拡大)あるいは集中(統合)によって、その危機を乗り越えようとするととらえていました。その際、重要になってくるのが信用制度、すなわち金融の役割でした。
シュンペーターが焦点をあてたのは「創造的破壊のプロセスの両面としての好況と不況の概念」です。好況と不況のプロセスを通じて、古い経済構造は絶え間なく破壊され、革新を通じた新たな経済構造が創造されると考えられていました。
シュンペーターは創造的破壊による革新を「新結合の遂行」ととらえ、そのような革新的行為者を「企業者」と名づけます。新結合は、工業における技術的・組織的革新だけではなく、あらゆる商業的な革新を含むものでした。
資本主義は創造的破壊によって発展します。農民が生産手段から分離され、先住民が制圧され、ときに奴隷として扱われたのも、そうした破壊の一形態にほかなりません。資本主義とは「資本と権力の終わりなき蓄積の継起」として定義できる、と著者はいいます。
しかし、ほんとうはもっと別の径路があってもよいのではないか。それは市場社会の自然で緩やかな拡大をともないながら、反資本主義的傾向をもつ経済発展、すなわち国家による資本主義の抑制をともなう経済発展のあり方です。著者はその路線をスミスに読みこみ、スミス経済学の新しいパラダイムをつくりあげ、それを現在の中国にあてはめて理解しようとしました。
それはたしかに願望といえば願望でした。文化大革命や天安門事件が取りあげられていないことをみても、このあてはめが正しかったかどうか、評価しなおす必要があります。
本書の最大のテーマは次のようなものです。
世界資本主義システムにおいて、アメリカがヘゲモニーを握る時代は終わりつつある。中国の台頭はどのような意味をもつのか。そして、ポスト・アメリカ時代の世界はどんなふうになっていくのか。
著者は大英帝国が世界のヘゲモニーを失いつつあった19世紀後半から20世紀はじめの状況──長期不況から大戦前の「ベル・エポック」にいたる状況──と、現在アメリカのおかれている状況とがよく似ていると考えています。
1970年代以降、アメリカを中心とする世界資本主義システムには、「グローバルな乱流」が生じました。ポイントの年は1973年、1985年、1995年だったといいます。
1973年には金ドル本位制が崩壊し、変動為替相場制がはじまりました。1985年のプラザ合意では、ドル危機の再発を防ぐため、各国の協調によりドルの切り下げ(日本の場合は円高)が誘導されました(1985年当初1ドル=250円だったレートは86年には160円となっています)。
そして1995年の先進7カ国財務相・中央銀行総裁会議での「逆プラザ合意」では、行きすぎたドル安(円高)を反転するための政治的合意がなされました(この年、円は1ドル=79円を記録しましたが、すぐ100円に是正されています)。
こうした動きは、いったい何を象徴していたのでしょう。
著者はまずマルクス主義経済学者ロバート・ブレナーの説を紹介するところから、国際経済の乱流を解き明かそうとしています。
ブレナーによれば、1950年代、60年代の好況期には「不均等発展」が生じ、アメリカに対するドイツと日本の急速な追い上げがみられました。アメリカの製造業者は国際競争に耐えきれなくなり、そのため通貨当局はドルの平価切り下げに踏み切らざるを得なくなります。そして、これが容易なことでは収まらず、けっきょくは変動為替相場制の採用にいたったというのです。
その結果、アメリカ経済はにわかに活気づきます。
しかし、1970年代後半のアメリカの財政赤字は、インフレをもたらしたわりに生産の増大をもたらさず、ドルが大量に流出することになりました。他方、アメリカの高い実質金利を求めて、世界中から莫大な量の資本が流入しはじめます。アメリカの金融資本は強化されました。ただし、それによってドルは上昇し、アメリカの製造業は大きな打撃をこうむります。そのため、アメリカの圧力によって、ドルの為替レートを引き下げる1985年のプラザ合意がなされたというのです。
プラザ合意によって、アメリカの利潤率や投資、生産は回復します。しかし、とりわけ日本などは深刻な危機におちいりました。ブレナーによると、1995年の「逆プラザ合意」は「危機に陥った日本の製造業を救うため」の救済措置だったといいます。
皮肉なことに「逆プラザ合意」は、日本などから巨額の資金がアメリカの金融市場に流れこむ結果を招きました。金融自由化もあいまって、ドル高への期待が高まったからです。これがアメリカの株式バブルへとつながり、経済全体の過剰な投機へとつながっていきました。
本書が発行されたのは2007年のことで、2008年のいわゆるリーマン・ショック以前のことです。したがってバブルの破裂は予測されているものの、それは兆しとしか意識されていませんでした。
とはいえ、著者は現在資本主義大国のおかれた状況は、19世紀末から20世紀はじめと同じ「長期的停滞期」にあるとみており、その結末が「恐慌」のようなものをもたらすにちがいないと予測していました。それは幸か不幸か的中することになります。
もちろん、昔の大英帝国と現在のアメリカには大きなちがいがあります。かつては没落する大英帝国に挑戦する新興国の動き(たとえばイギリス対ドイツ)が見られましたが、いまのところはアメリカの圧倒的な軍事力に挑戦する国はなさそうです。したがって、暴力やテロ、戦闘は頻発するにせよ、20世紀前半のような世界戦争が起こる可能性は少ない、と著者はみていました。
それに、もうひとつ特筆すべきことがあります。それは以前のイギリス以上に、アメリカが世界中から資金を吸収する仕組みを築いていることです。
1世紀前と現在では危機の発現の仕方にちがいがあります。それでも「グローバルな乱流」はあり、それがどこに行き着くかを著者は見届けようとしていました。
アメリカを中心に世界経済の変遷を整理したブレナーの分析を、アリギは次のように批判します。
第1点。20世紀後半には、実質賃金の上昇が資本主義システム全体の収益性を引き下げ、同時にインフレを引き起こした。しかし、ブレナーは労使関係より資本家間の競争に目を向けるため、「水平的」(資本どうしの)対立と「垂直的」(労使間の)対立の複雑な歴史的相互作用をとらえそこなっている。
第2点。ブレナーはアメリカ、ドイツ、日本の経済に焦点を合わせるが、この3国が世界の貿易に占める割合は1950年以降、次第に減少し、とりわけ90年代半ばからは中国のシェアが急速に拡大することを見逃している。
第3点。レーガンとサッチャーが新自由主義を採用したのは、単に収益性の危機に対応するためではなく、資本主義システムにおけるヘゲモニーの危機が深まったためでもある。しかし、ブレナーは政治的要因についてほとんど論じていない。固定為替相場制が崩壊したのは、ベトナム戦争の影響が大きかった。
第4点。ブレナーの問題は、かれが製造業にのみ焦点をあてていることである。「アメリカの金融・保険・不動産による企業利潤は、1980年代には製造業に追いつき、1990年には追い越している」。
第5点。ブレナーは新自由主義者、すなわちマネタリストの「反革命」のもつ意味を見落としている。「マネタリストの『反革命』がアメリカの権力の衰退を逆転させることに驚くほど成功した主たる理由は、逆に、それがグローバルな資本フローをアメリカとドルへと大量に回帰させることに貢献したからであった」。
こうした批判は、著者がブレナーの論述を、みずからのヘゲモニー移行論に組み入れようとした軌跡を示しているとみることができます。
著者によれば、ヘゲモニーの危機には「予兆的危機」と「終末的危機」とがあり、このふたつは区別されなければならないといいます。アメリカは予兆的危機を迎えたあと、第2次世界大戦前の「ベル・エポック」にも似た「よき時代」を迎えました。しかし、それは長くつづきませんでした。2001年の9・11後の対応はアメリカの「終末的危機」を早め、中国のリーダーシップを強化することにつながりました。
1985年のプラザ合意、95年の「逆プラザ合意」は、たしかに変動為替相場制の区切りでしたが、むしろ決定的だったのは70年代末から82年にかけてのマネタリストの「反革命」だったと著者はいいます。
1970年代には「石油ショック」により、石油輸出機構(OPEC)が勢いづき、インフレ傾向が強まります。そして800億ドルの「オイルダラー」が生まれました。ユーロダラー市場の膨張は、固定為替レートの安定性を危うくし、システム崩壊を現実のものとしました。
固定為替レート体制の崩壊は「商工業活動のリスクと不確実性」を増大させ、「資本の金融化」にはずみをつけることになります。その結果、通貨市場での金融投機が活発になります。
こうして世界的な貨幣と信用の供給が、すさまじく拡大しました。これに見合う需要はなかなか存在せず、それがインフレ圧力となりますが、いっぽうで海外のものをなかなか手に入れられなかった国が、容易に資金を借りられるようになりました。
70年代後半の問題は、世界中を駆け回るようになったマネーが、ワシントンの発行するドルと競争し、それが相互破壊的な競争をもたらして、アメリカのヘゲモニーの危機を深刻化し、大量のドル売りをもたらしたことだと著者はいいます。
しかし、この巨額なドル売りによって、相互破壊的な競争が突然終了し、だれもが予期していなかったアメリカの繁栄がふたたび訪れるのです。
この間に、アメリカは世界の余剰マネーを自国に集める金融装置をつくりあげたのです。しかし、これは遠からぬうちに終わり、そして、そのあとにヘゲモニーの「終末的危機」がやってくる、と著者は予想していました。
企業は国内での直接投資や雇用を控えるようになって、資金を退蔵する(あるいは高額の役員報酬に回す)か、投機に回すようになります。世の中全体にカネが回らないから、景気はよくなるはずもありません。
そして政治的には、アメリカのヘゲモニーが弱まり、新たなパワーをもつ国家(すなわち中国)の出現を許すことになります。
さらに社会的には、持てる者と持たざる者の不平等が拡大し、これまでの中流階級が下層階級に転落していくことによって、社会全体にいらだちや投げやりな姿勢、あるいはやけっぱちな動き、抵抗や反抗が広がっていくと思われました。
不幸なことに、この予言は的中しました。
いまアメリカに広がっているのは、そうした状況です。そして、その状況は現在の日本の状況ともつながっています。
ただし、著者はこの「終末的危機」によって、かつてのような「上り坂の資本主義大国と資本主義大国との間の軍拡競争」のようなものは発生しないし、また市場の分割のようなことは起こらないだろうと予想していました。
いまのアメリカの繁栄は、最終的には世界中から集まる資金を「純粋な貢ぎ物」ないし「みかじめ料」(守ってやっているのだから、カネを出せ)として処理することで成り立っており、その試みが世界中を不安におとしいれていることはまちがいないといいます。
そして格言「我とともにあらん、さすれば我が亡きあとに洪水よ来たれ」をかかげます。
著者はソ連崩壊以降、みずからを「世界国家」たらしめんとするアメリカの無謀な試みが、9・11後のイラン・アフガン戦争をへて、けっきょく失敗に終わったこと、そしてアメリカのヘゲモニーがくずれて、ヘゲモニーなき時代になったことを指摘しています。あとにつづくのは「中国の世紀」なのだろうか、というのが著者の問いです。
ところで、その前に、著者がアメリカの「ビジネスのひな型」はゼネラル・モーターズからウォルマートに移行したと指摘していたのが印象に残りました。ウォルマートというのは、アメリカに拠点をおく世界最大のスーパーマーケット・チェーン。ゼネラル・モーターズ(GM)は、いわずと知れたアメリカを代表する自動車会社です。
著者によると、ウォルマートの経済規模はいまやGMより大きく、150万人の従業員をかかえ、売り上げはアメリカのGDPの2.3%を占めているといいます。
アメリカでは自動車会社よりスーパーのほうが、大きな経済規模を占めるようになりました。GMが世界に生産拠点を広げながら、ほとんどアメリカ国内で車を製造し、販売するのに対して、ウォルマートは大半の製品をアジアの製造業者から集めて、消費者に販売しています。
著者はウォルマートの台頭に、アメリカが「グローバルな金融集積地としての役割をもつ国家」になったことを重ねています。
ウォルマートは労働コストの高い自国製品にこだわらず、便利なものを海外、とりわけアジア(なかでも中国)でつくらせて、それを消費者に安く提供することで、利益を確保しています。製造業者は、中国製と同じようなものをつくろうとしても割にあわないから、けっきょく仕事をやめてしまい、そこで働いていた労働者は失業してしまいます。アメリカのビジネスは工業中心から、明らかにサービス業、とりわけ金融へと移行しています。
著者は前著『長い20世紀』のなかで、世界資本主義のヘゲモニーを担う中心国が、当初、産業国家として出発し、次に金融国家として成熟しながら、最後に新たな国にヘゲモニーをゆずっていく過程を一般的な傾向としてとらえ、それを600年にわたる資本主義の歴史のなかに描いてみせました。
したがって、現在のアメリカもまた、世界の中心国たる位置を失いつつある途上にあると映ります。その象徴がウォルマートの隆盛でした。マネタリストの反革命が、アメリカを産業国家から金融国家に変質させてしまった、とかれはいいます。もっともそれは20世紀はじめの話で、2020年の時点ではウォルマートの力は相対的に弱まり、GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)が社会全体をおおうようになっています。
アメリカ、日本に共通することですが、おそらく中国製品の大量流入が、70年代の宿痾(しゅくあ)であった世界的インフレの抑制に成功したことはまちがいないでしょう。しかし、それとともに同じような商品で、中国製品と対抗しなくてはならなくなった企業が苦戦を強いられたのも事実です。
国内の競争がさらに値下げに拍車をかけました。賃金は上がらなくなり、日本では非正規社員の割合が増えました。経済成長率は停滞します。好況感がわかないはずです。
ジャーナリストのジェームズ(ジム)・マンは、アメリカが共産党独裁義国家、中国の世界貿易機関(WTO)加盟を安直に認め、それによって中国製品をアメリカ国内にあふれさせたのが、何よりもまちがいだったと述べていました(『米中奔流』)。かれは中国製品にもっと関税をかけ、中国の国際的な動きを監視し、中国内の民主化運動を支援せよと主張していました。
とはいえ、いまや中国が経済大国となり、中国製品が世界中を席巻していることは、ほとんどだれもが認めるところです。この流れは、当面、収まりそうにありません。著者はこの事実から出発して、世界資本主義システムのなかで、中国の挑戦がもつ意味をとらえなおそうとしています。
現在、アメリカが中国をどう取り扱えばいいのか迷っている様子は、本書からもうかがえます。
〈21世紀への変わり目における米中関係の問題は、もはやアメリカの中国への商業的アクセスではない。むしろ問題なのは、中国がアメリカに代わって世界でもっとも急速に成長している主要な経済圏になったという事実であり、中国が他国と同様に、アメリカへの商業的アクセスを求めているという事実である。〉
アメリカは、どのように対応しようとしているのでしょうか。
著者はロバート・カプラン(ジャーナリスト)、ヘンリー・キッシンジャー(元国務長官)、ジェームズ・ピンカートン(コラムニスト)の3人の論者をとりあげて、それぞれの対応策を紹介しています。
中国に対抗する「連合」を結成して、中国を封じ込めようというのが、カプランの策です。米太平洋軍司令部(PACOM)を中心に日本、韓国、タイ、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、インドを結んで、一種の太平洋軍事同盟を形成するという構想で、これによって中国の太平洋進出を抑制しようというもの。一種の新冷戦戦略といえるでしょう。
これに対し、キッシンジャーは、中国はソ連のような軍事的帝国主義国家ではないとして、冷戦のときのような封じ込めをこころみるのはおろかだと主張します。中国が採用している「平和的台頭」路線は、中国のいうように「既存の世界秩序を乱すことのない」成長なのであって、中国が台湾問題やいくつかの領土問題をかかえているにせよ、侵略に転じる可能性はないと判断します。
ピンカートンの考え方は、中国との対立と和解を組み合わせるものといえるかもしれません。もはや大国間の戦争を想定するのは時代遅れであり、アメリカと中国は経済的にも密接に結びついている。封じ込め戦略は突発的な衝突を招きやすいので、避けなければならない。そのためアメリカは中国と直接対決せず、インドや日本などが中国と張り合うのを背後から見届けるのがよいという立場をとります。
アメリカのアジア戦略、とりわけ対中戦略は、この3人の論者が示すように、三者三様に揺れています。
アメリカの腰が定まらないのは経済学者のクルーグマンがいうように、アメリカが「中国の米ドル買い(そして安価な中国商品)に病みつきになってしまった」からでもあり、全面的な中国バッシングが起こりにくいのは、巨大な中国市場に魅力があることを隠せないからではないでしょうか。
著者自身は、アメリカがどのような対中政策をとるべきかを論じているわけではありません。むしろ、かれは「将来何が起こり、何が起こらないか」を予測するためにも、過去にさかのぼって、西洋史の枠にこだわらず、中国がこれまで歩んできた道をふり返ってみなくてはならないと提案します。
国家がヨーロッパの発明だと思うのはまちがいだと指摘するところからはじめています。「日本や朝鮮、中国からベトナム、ラオス、タイ、カンボジアまで、東アジアのもっとも重要な国々は、ヨーロッパの国々よりもずっと前から国民国家であった」。そして、これらの国々のあいだでは、朝貢貿易に加えて、私的な交易がくり広げられていたというわけです。
しかも、ヨーロッパとちがって東アジアの特徴は、戦争が割合に少ないことでした。ヨーロッパのように、海外に帝国を築いたり、他国を侵略したり、互いに軍拡競争に走るといった傾向はまずありませんでした。
ヨーロッパの国々においては絶えざる戦争によって、破壊的な戦争手段の開発が進み、また海外の資源獲得をめぐって、各国間の激しい争いが起きていました。
アジアとの長距離貿易によって利を得ていたのは、むしろヨーロッパのほうです。鄭和(ていわ)のインド洋遠征は中断されるのに、コロンブスがアメリカを「発見」し、ヴァスコ・ダ・ガマがインド航路を開発するのは、まさにこの非対称性の反映だったともいえます。
国内市場もまた西洋の発明ではなく、アダム ・スミスは、18世紀における最大の国内市場がヨーロッパではなく中国にあったことを認めていました。著者は南宋以来、明、清にいたる中国の市場社会の発展を細かく追い、スミスが示した豊かさへの「自然な」経路の典型は、むしろ中国に見いだされると論じています。
さらに「清朝政府が開発の優先順位を、農業の改善、土地の再分配や開拓、国内市場の強化と拡大に割り当てたことは、まさにスミスが『国富論』で主張したことと同じである」と述べています。
その後は、ヨーロッパが不自然な「世界史に類例のない創造的破壊のプロセス」を採用することによって、アジアの国々の自律性は失われていきます。中国経済がある時点で停滞におちいったという見方を著者はとりません。18世紀に中国は奇跡的な成長を遂げ、「本質的に新しいタイプの農民社会」を実現したとみます。それはヨーロッパの資本主義的発展とはことなる市場社会でした。資本家(商人)は社会の上層ではなく、下位の社会集団にとどまっていました。
しかし、著者はいいます。
〈ヨーロッパの発展径路において典型的であった軍国主義と産業主義、そして資本主義の相乗効果は絶え間ない領域的拡大を推進し、またそれによって支えられていた……しかし中国と東アジアのシステムは、ヨーロッパのように海外への拡張と軍拡競争という道を歩まなかったため、拡張するヨーロッパの権力の軍事的猛攻撃に対し、脆弱(ぜいじゃく)なものとなってしまった。東アジアが猛攻撃を受けた際に、グローバル化するヨーロッパのシステムへと従属的に組み込まれたのは、必然的な結論だった。〉
イギリスの資本主義的商品が中国になかなか浸透しなかったことはよく知られています。むしろ、茶や絹といった中国製品の魅力が、イギリスの綿製品を圧倒していました。そこで、イギリスはアヘンを輸出することによって、貿易のバランスをとろうという悪辣(あくらつ)な方略を思いつきます。これが中国からの大量の銀の流出を招き、清朝の財政を破綻(はたん)させる原因となります。アヘン戦争は起こるべくして起こった出来事でした。
こうして中国はだんだんと「グローバルな資本主義システムにおいて、従属的かつ次第に周辺的となるメンバー」になっていきます。
日本は明治維新による中央集権化を通じて、急速な産業化と軍事化を実現しました。その結果、日清、日露戦争に勝利し、一時は中国に代わって「アジアの盟主」になるかにみえました。しかし、それはアメリカによってはばまれました。
日本の敗北によって、中国では内戦をへて中華人民共和国が成立します。
著者は19世紀後半から20世紀前半にかけては、東アジアの発展経路が西洋の経路に収斂(しゅうれん)したが、20世紀後半にはそれが逆転して、西洋の径路が東アジアの径路に収斂するようになったと書いています。
東アジアの近代は、中国中心から日本中心、そしてアメリカ中心へと推移しました。しかしベトナム戦争での敗北により、アメリカのヘゲモニーは揺らぎはじめます。それは日本の金融支援によって一時復権するかにみえましたが、最終的に強化されることはありませんでした。
そこに中国がグローバルな市場として開かれるいっぽう、中国が世界中に広がる華僑ネットワークを通じて、海外貿易や投資にも乗りだすと、東アジアの構図は一変します。中国の成功は、「東アジアの再興のまったく新しい段階、つまりアジア地域の経済が中国を中心に再編される段階」を告げている、と著者は断言しています。
外国資本にとって中国の魅力は「巨大で安価な労働予備軍」ではなく、「労働予備軍の高い資質」だと、著者は書いています。
中国が台頭し、「経済的ルネッサンス」を迎えたのは、「中国が外国資本を必要とした以上に、外国資本が中国を必要とした」からです。中国の経済拡張は「外国貿易と投資に開かれている」。そのあたりが、昔の日本とちがうところだとも書いています。
かといって、中国はしっかり国益を守っています。海外からの直接投資を認める場合も、それが自国に役立つ場合にかぎられているのです。規制緩和と民営化は慎重な配慮のうえになされ、政府は新規産業の創出、経済(輸出)特区の設立、高等教育、インフラ整備に力を注いできました。
中国の経済特区には、労働集約型(部品生産や組み立て)の珠江デルタ[たとえば深圳(しんせん)]、資本集約型(半導体、コンピューターなど)の長江デルタ[上海]、中国版シリコンバレーというべき北京中関村などがありますが、その場合も中国政府は対外貿易だけを応援していたわけではありません。
中国政府が何よりも優先したのは、産業化の基盤として教育であり、国内市場であり、さらには農業開発である、と著者は断言します。
それは資本主義への移行というより、アダム・スミス的な市場経済重視の姿勢のあらわれだといいます。まず全国で外国の技術に対する企業者の情熱が生まれ、それによって国内市場が開拓され、最後に海外市場に向かうという方向は、まさにアダム・スミスの方策です。
正規部門の労働者は雇用が保証され、医療や年金に対する給付金もじゅうぶんに支給されています。「国内市場の形成と農村地域における生活条件の改善」、これが中国政府が何よりもめざすものだ、と著者は断言します。
中国の農村が豊かになったのは、1970年代後半から農業生産請負責任制が導入されてからです。それによって農業の生産性と農民の収入が一気に高まりました。加えて農村地帯に「郷鎮企業」が生まれ、農村の余剰労働力を吸収していったことも、農民の生活改善に役立ったといいます。
郷鎮企業は中国経済に大きく寄与し、農村の収入を増やすとともに、国内市場を拡大する役割を果たしました。それはマルクスのみた農村の分解、あるいは「本源的蓄積」とはまったく異なるスミス的な発展経路であり、「産業(industrial)革命」ならぬ「勤勉(industrious)革命」のもたらした成果だったといいます。
著者は鄧小平の改革を高く評価しています。この改革は企業者の活力を引き出し、一人あたり所得の上昇をもたらし、市場経済を引っ張っていく共産党の政治基盤を強固にしました。中国ではソ連とちがって、「農村の破壊ではなく、農民の経済と教育の高揚」を通じて近代化が進められたというのです。
しかし、現在の中国に社会的矛盾がないわけではない、と最後に著者はつけ加えます。「一つは所得の不平等の大幅な拡大であり、もう一つは改革の手続きや結果に対する人々の不満の増大である」。各地で社会的騒擾(そうじょう)やストが頻発し、いっぽうで言論の自由が封殺されています。それがどういう方向にいくかは、だれにも予想できません。
「エピローグ」では、中国の台頭が世界の文明にどのような意味をもつかが論じられ、重要なのは、かつてスミスが主張したように、西洋人と非西洋人とのあいだに平等と相互尊重の姿勢が生まれるのかということだというテーマが掲げられます。
著者は、アメリカが同盟国と中国を対峙(たいじ)させて「漁夫の利」をねらったり、昔ながらの「封じ込め政策」をとったりするのは、まったく時代に逆行しているし、むしろ世界を混乱におとしいれる危険性をもっている。かといって、キッシンジャーの考えるように、中国をアメリカのシステムに包摂しておくのも無理があるといいます。中国が南北対立の解消に積極的な役割を期待するとも書いています。
締めくくりの一節はこうなっていますが、けっして楽観的ではありません。
〈新たな方向づけにより、中国が伝統の再興に成功し、自立した市場を基盤とする発展、収奪なき資本蓄積、非人的ならぬ人的資源の動員、大衆参加型の政治による政策形成を遂げることができるなら、中国が文化のちがいを尊重しあう諸文明連邦の形成に大きく寄与するようになる公算が高い。しかし、その方向づけがうまくいかなければ、中国が社会的・政治的混乱の新たな震央に転じる可能性もある。その場合は、北側(先進資本主義諸国)が巻き返しをはかって、崩れつつあるグローバルな支配を再構築しようとするかもしれない。あるいは、ふたたびシュンペーターの言い方を転用すれば、社会的・政治的混乱が、冷戦体制の消滅に続いて生じている暴力をエスカレートさせ、人類を恐怖(もしくは昇天)へと駆り立てていかないともかぎらない。〉
お互い冷静になって、先を見つめなければなりません。
ジョヴァンニ・アリギの世界(1)──商品世界ファイル(29) [商品世界ファイル]
ジョヴァンニ・アリギ(1937〜2009)は、その著『長い20世紀』で、資本主義を「[資本の]継起的蓄積システム」と定義しています。かれのこの定義は、ブローデルの歴史分析と、マルクスによる資本の運動の把握から引きだされたものです。
ブローデルは近代社会のシステムを三層構造として理解しました。
いちばん下には物質生活の層、中間には市場経済の層、そして最上層に資本主義の層がきます。ブローデルの規定が特異なのは、資本主義と市場経済を同一視する一般の見方に対し、かれが「資本主義は、その登場と拡大を国家権力に依存し、市場経済と対立する」とした点です。つまりブローデルにとって、資本主義とは資本(産業や金融)と一体化した国家の経済戦略にほかなりません。これにたいし、市場経済の目的は、スムーズな経済循環による物質生活の確保にあります。
継起的蓄積とは何でしょう。
ここでアリギが持ちだすのは、マルクスによる資本の運動の規定です。英語でいうと、マルクスは資本の運動をM→C→M′の自己増殖過程ととらえました(G─W─G′)。つまり貨幣→商品→貨幣の限りなき膨張とみたわけです。
資本主義の「継起的蓄積」がはじまった時期を、アリギはブローデルにならって、15世紀のイタリア都市国家の時代にみました。
そして、それ以降の中心的な流れを(1)15世紀から17世紀のジェノヴァ・サイクル、(2)16世紀後期からほぼ18世紀全体のオランダ・サイクル、(3)18世紀後半から20世紀初めのイギリス・サイクル、(4)19世紀後期に始まり現在にいたるアメリカ・サイクルとしてとらえました。
ヘゲモニーという言い方があります。
ふつう覇権と訳されますが、そう言い切るとだいじな部分が抜け落ちてしまいます。アントニオ・グラムシは、コントロールとリーダーシップにヘゲモニーの発現をみていた、とアリギは書いています。力だけではじゅうぶんではありません。頼らせるようにしなくてはいけない。それによって相手を仕えさせるのです。国家というのはそういう存在で、世界には多くの国々を引っ張っていく覇者としての国家が存在します。
現代から過去に射程を伸ばして、資本主義国家の原像をさがすと、中世末期の地中海世界に行き着きます。その後、世界のヘゲモニーを握ったスペイン、オランダ、イギリス、アメリカは、ある意味で地中海世界のシステムを引き継いで、多少のひねりを加えながら、それをより大規模に再現したにすぎない、とアリギはいいます。
そこに見られるのは資本蓄積システムとそのサイクルです。
資本と国家は一心同体でした。対立することもありますが、概して資本と国家は一緒にタッグを組んで戦ってきました。国家が資本の自由を認め、資本が国家をあてにする、そういう状態を資本主義と名づけることができるのではないでしょうか。資本主義ということばが誕生するのは20世紀になってからですが、そうしたシステムがはじまったのは15世紀の地中海です。
イスラム商人に独占されていたアジアの富を直接手に入れたいという思いからヨーロッパの膨張は始まりました。アジアの富の取引を担っていたのが、中世末期の「4大都市国家」、すなわちヴェネツィア、フィレンツェ、ジェノヴァ、ミラノです。なかでも、アリギはヴェネツィアをきたるべき資本主義国家の「完全モデル」ととらえています。
そのヴェネツィアに打ち勝とうとしたのが、ジェノヴァで、ジェノヴァはポルトガルとスペインを応援することによって、アジアの富を確保しようとします。ポルトガルは成功しましたが、スペインは失敗します。ところが、スペインはアメリカ大陸を偶然「発見」し、それがパワーと富の源泉となります。
16世紀ヨーロッパで、スペインは圧倒的な力を誇っていました。しかし、イギリスやフランスが経済力をつけ、勃興しはじめます。スペインは教皇やハプスブルク家と組んで、これらの国を服従させようとしますが、ことごとく失敗します。とりわけネーデルラント北部7州は結束して、スペインからの独立をはかり、1648年のウェストファリア条約で新国家としての承認を勝ち取ります。それがオランダでした。
ウェストファリア条約には、勢力均衡や内政不干渉といった政治原則のほか、貿易障壁の撤廃や商業の自由といった経済原則が謳われていました。これが近代国際システムの原型となります。
オランダの通商・金融ネットワークは、スペインやポルトガルから奪い取ったもので、かつてのヴェネツィアよりずっと強大でした。オラニエ公マウリッツの考案した軍事技術が、オランダの力を支えていました。しかし、オランダの覇権は長くつづきません。
1652年の英蘭戦争にはじまり、1815年のナポレオン戦争の終結にいたるまで、イギリスやフランスとしのぎを削る時代となるからです。
当初はネーデルラントの支配をめぐる争いでした。それが次第に「富とパワーの源泉を取りこむ」ことへ次元が移ると、イギリスはアメリカにつながる大西洋の支配、さらには弱体化しつつあるオスマン帝国やムガール帝国の切り崩しへと向かいます。
この時代の特徴は、資本主義と領土主義の結合にあるとアリギはいいます。具体的には、入植植民地主義と資本主義的奴隷制、経済的ナショナリズム──それらがあわさって、海外への膨張を促しました。
世界商業と植民地から得られた利益を国内経済の形成へと誘導し、それによってますます多くの市民を「間接的、かつしばしば知らぬ間に、支配者の戦争と国家形成の努力を支えるために動員[する]」流れができつつありました。
大陸から離れた島国であったために、イギリスは大陸の抗争に巻きこまれず、優位のうちに海外拡大をはたすことができました。ナポレオンのヨーロッパ支配を打ち砕き、ヨーロッパ協調の道筋をつけたイギリスは、自由貿易帝国主義のもとに、非西洋世界への植民帝国の拡大に乗りだします。
「植民地から提供させた帝国の献上品を、世界中に投下される資本に再循環させることで、世界金融センターとしてのロンドンの比較優位は、アムステルダム、パリという競合センターに対して、いっそう強まることになった」とアリギは書いています。
イギリスの強さは自由貿易と帝国主義を結びつけたことにあります。世界の産物が自由にイギリスの国内市場に流入するいっぽうで、産業革命で生みだされた財が世界中に流れ、資産家の富が増大していきました。
イギリス資本主義の本質は、ヴェネツィア型とオランダ型とスペイン型を合わせた世界経済=帝国にあったとアリギはみています。そのイギリスが19世紀末ごろから力を失っていったのは、ドイツやアメリカの挑戦に対応できなかったためです。
北米大陸の端から端まで領土を拡張したアメリカは、世界の労働、資本、企業活動を引きつける「ブラックホール」になろうとしていました。いっぽうドイツは海外植民地の拡大に失敗したあと、強力な軍産複合体をつくりあげ、イギリスに対抗します。
イギリスのヘゲモニーを引き継いだのは、大西洋と太平洋の二大海洋に接近できるという優位性をもつ大陸国家アメリカです。民族解放運動の流れのなかで、イギリスは次第に植民地を維持するコストに耐えられなくなっていきます。
アメリカのヘゲモニーは「自由世界主義」とでもいうべきもので、「帝国主義」でも「自由貿易主義」でもないところに特徴があった、とアリギは書いています。それはアメリカを中心とする「自由世界」をつくる動きとなっていきます。
アメリカは植民地をつくろうとはしませんでしたが、国内の産業を保護するいっぽう他国には門戸開放を求めていました。とりわけ第2次世界大戦後は、ブレトンウッズ体制とGATT(関税および貿易に関する一般協定)がアメリカの主導権を支えることになります。
これが世界史の大まかな動きですが、以下、それをもう少し詳しくみておくことにしましょう。
近代資本主義の揺籃の地は地中海世界です。
商業につづいて金融が拡大し、資本が持続的に蓄積されるようになるのは14世紀ごろからで、その中心となったのはイタリアの「4大都市国家」、すなわちフィレンツェ、ミラノ、ヴェネツィア、ジェノヴァでした。
これらの都市国家のあいだには、経済面で一種の棲(す)み分けがなされていました。アリギはこう書いています。
フィレンツェとミラノは、どちらも製造業と北西ヨーロッパとの陸路貿易に従事していたが、フィレンツェが織物貿易に特化していたのに対して、ミラノは金属製品の貿易に特化していた。ヴェネツィアとジェノヴァは、どちらも東洋との海上貿易に従事していたが、ヴェネツィアが香辛料貿易に基礎をおく南アジア回路の取引に特化していたのに対して、ジェノヴァは絹貿易に基礎をおく中央アジア回路の取引に特化していた。
14世紀半ばから15世紀半ばにかけて4大都市国家間に抗争がなかったわけではありません。都市内部の対立も激しいものがありました。
フィレンツェを例に取りあげてみましょう。
13世紀後期にフィレンツェは織物産業の中心地として発達します。原料の羊毛は最初イタリア国内から集めていましたが、それが足りなくなるとネーデルラント、フランス、さらにはスペイン、ポルトガル、イングランドにも原料を求めるようになりました。
フィレンツェでつくられた毛織物製品は、イタリア国内だけではなく、レバント(現在のギリシャ、トルコ、レバノン、エジプト方面)、さらにはフランス、イングランドにも輸出されていました。この毛織物貿易網が、フィレンツェの金融ネットワークに重なっていきます。
英仏間に王位継承権をめぐって「百年戦争」(1337〜1453)がはじまると、イングランドは毛織物工業を「国産化」する動きに出ます。以前からフィレンツェの毛織物は高品質・高価格品へ次第に移行していたとはいえ、イングランドの「国産化」の影響は大きく、毛織物産業全体の生産量は徐々に落ちこんでいきました。
1340年代にイングランドのエドワード3世がフィレンツェ商人から借りていた戦費を踏み倒したため、「大恐慌」が発生し、バルディとペルッツィの両家が倒産します。1378年には梳毛工(そもうこう)らの下層労働者が反乱を起こし(チオンピの乱)、一時、市の政権を握ります。下層ギルドの労働者が立ち上がったのは、旧来の毛織物産業が衰退したからです。だが、かれらが政権を掌握したからといって、経済が立ち直るわけでもありません。その政権はやがてひっくり返されます。
そのあとはメディチ家に代表される裕福な商人一族による寡頭支配が半世紀つづきます。メディチ家はイタリア国内のみならずフランスやイングランド、フランドルなどにも支店を置き、各国政府にカネを貸し付けていました。
メディチ家の収益は、大半がローマ教皇庁とそのネットワークを基盤にしていました。しかし「百年戦争」が終わると、メディチ家は次第に衰えていきます。ルネサンスはメディチ家の最後の輝きでした。ロレンツォ・デ・メディチ(1449〜92)は銀行業から得た利益を芸術や貧者の救済、政治につぎこみました。
だが、時代は大きく変わっていきます。いわゆる「大航海時代」がはじまり、新大陸アメリカが「発見」され、インド・ルートが開発されると、地中海は経済の中心ではなくなり、イタリアの都市国家はかつての柔軟性を失っていきます。
イタリアの4大都市国家のなかで、大航海時代に対応したのはジェノヴァだけでした。その代わり、フィレンツェとヴェネツィアには壮麗なルネサンス都市と海の都が残されることになりました。
アリギは、ジェノヴァを資本主義蓄積システムの「第1サイクル」と位置づけています。なぜジェノヴァだったのでしょう。ジェノヴァ経済の要となったのは、1407年に設立されたサンジョルジョ銀行でした。
アリギによれば「[ジェノヴァの]富の基盤は、中国に向かう中央アジア交易路が競争力をもち、ジェノヴァ企業がこの交易路の黒海『終点』で準独占的支配権を確立していたことにあった」といいます。ジェノヴァはクリミア半島沿岸部を支配し、中央アジア交易路を押さえていました。ところがモンゴル帝国の衰退とオスマン帝国の台頭によって、ジェノヴァの貿易は大きな打撃を受けます。
ヴェネツィアがオスマン帝国やカタロニア、アラゴンと結びつくことによって、ジェノヴァを排除するようになると、交易路を失ったジェノヴァは万事休すかのようにみえました。残っていたのはサンジョルジョ銀行に集まっていた「過剰蓄積」だけです。
しかし、破綻のなかから新たな道がみつかります。カスティリア貿易です。ジェノヴァ商人はコルドバ、カディス、セビーリャに出張所を設け、カスティリアの商業に食いこみます。
ジェノヴァはイベリア半島南部とアフリカ北西部沿岸(マグレブ)に経済的拠点を広げていきます。目ざすは、マグレブに集まるアフリカの金と、大西洋航路でした。
十字軍精神にあふれたポルトガルとスペインを動かしていたのはジェノヴァの資本でした。インド航路の「開発」とアメリカの「発見」の背後には、ジェノヴァの存在があります。クリストファー・コロンブス(クリストフォーロ・コロンボ)はジェノヴァ出身の商人でした。
フランドルで生まれたハプスブルク家のカール5世(1500〜58)は、1516年にスペイン王(カルロス1世)となりますが、ジェノヴァの資本はかれを財政的に支えて、1519年に神聖ローマ皇帝へと押しあげます。ドイツの銀を握っていたフッガー家もカール5世の財政を支えるもうひとつの柱でした。ところが、アメリカから大量の銀がヨーロッパに流入するようになるとドイツの銀は太刀打ちできなくなり、フッガー家は破産に追いこまれ、ふたたびジェノヴァの銀行家の力が強くなるわけです。
ジェノヴァはスペインの盛衰と運命をともにします。ピアツェンツァ(ミラノ南方の町)の大市(おおいち)はジェノヴァの資本が牛耳っており、ヨーロッパの金融センターとなっていました。しかし、スペイン領ネーデルラントの力が次第に大きくなってきます。
ブローデルがフィレンツェやヴェネツィアでなくジェノヴァを「蓄積システムの第1サイクル」として選んだ理由ははっきりしています。それはジェノヴァこそが、その後のオランダ、イギリス、アメリカへとつづく世界資本主義システムを起動させる淵源となったからです。
16世紀になると、資本蓄積の中心地は都市国家ではなく、それなりの領土をもつ国家へと移行しました。ジェノヴァとスペインのあいだには、アメリカ銀を金や為替手形に変えて、富の流通をはかる金融システムができあがっていました。オランダ独立戦争は、このジェノヴァ・イベリア結合を打ち破り、アムステルダムを世界の金融中心地へと変えていくことになります。
もともとアムステルダムはバルト海交易(穀物と海軍物資)によって発展しました。そこから生じた余剰は土地開拓や農産品の開発にあてられていました。スペインからの独立戦争が始まるのは1568年のことで、プロテスタントのオラニエ家を中心にネーデルラント北部7州連合が形成されます。そして1600年ごろには実質的に独立を勝ちとり、1648年のウェストファリア条約によって、ネーデルラント連邦共和国(オランダ)として承認されるのです。
オランダの商人は、積極的で機敏な商業活動によって世界各地から集めた穀物や鰊(にしん)、香辛料、織物、ワイン、硝石(しょうせき)、銅、タバコ、カカオ、羊毛、絹、麻などを巨大倉庫に積みあげ、ヨーロッパ各地に販売しました。
17世紀初頭につくられたアムステルダム証券取引所やヴィッセル銀行によって、ヨーロッパ中から貨幣資本が集まってくるようになると、アムステルダムは世界の通商と金融の中心となります。それを促進したのが1602年に設立されたオランダ東インド会社でした。それから1740年ごろまでがオランダの全盛時代です。重商主義時代がはじまります。
オランダ東インド会社は東インド諸島(現在のインドネシア)で貿易を拡大するとともに、有利な条件を作るために広範な軍事活動をおこない、領土を征服しました。当時の国際商品である胡椒を含む香料の独占をはかったのです。その行動はまさに南米のスペイン人同様、残忍そのものでした。「しかし、この残忍性は、まったく企業的論理に内面化しており、それは収益性を破壊するものではなく、それどころか収益性を支えるものであった」とアリギは記しています。
イギリスとフランスは重商主義を模倣し、オランダを追いかけました。オランダを模倣し追い越そうとした西洋の国々が、資本主義のパワーと領土(帝国)を獲得しようとしたのは悪しき必然でした。
オランダの没落を招いたのは、アメリカ独立革命(1775〜83)と「バタヴィア革命」(1795〜1813)だといってよいでしょう。アメリカ革命でオランダはイギリスに対抗してフランスを支援します。そのため、イギリスから報復を受け、セイロン島とマラッカを奪われました。そして、その後、ナポレオンによる占領(バタヴィア革命=バタヴィア共和国の設立)により、決定的なダメージを受けることになります。
オランダの金融支配力が衰退するのは、オランダがアメリカ独立戦争でフランスを支援したのにたいし、イギリスが報復を加えたことが大きいといえます。
イギリスが世界のトップに躍りでたのは、18世紀末から19世紀初めにかけオランダとフランスを倒して、商業と金融の面で優位に立ったからです。
そのころには大英帝国の大部分はできており、カナダ、カリブ海域、マドラス、ボンベイ、ケープ沿岸部、ジブラルタル、ベンガル、セイロン、ボタニー湾、ベナン、ギアナ、トリニダードを領していました。さらに1850年代には香港、オーストラリア、ニュージーランド、インド全土が帝国に加わります。これらの地域では、砂糖や綿花、茶、ゴムがつくられ、金、銀、銅、スズが採掘されていました。
アリギによれば、「世界史上最強の領土主義的国家、かつ同時に資本主義的国家」であったことがイギリスの強さでした。
それにいたるまでには長い歴史がありますが、とりわけエリザベス1世(1558〜1603)時代の改革と再編が、その後の展開を決定づけたといわれます。グレシャムの助言により、ポンドが安定したのもこの時代です。産業の発展も18世紀後半になって突然生じたわけではありません。14世紀にはすでに毛織物工業が始まっていたし、16世紀には炭鉱業や冶金業が発達します。
そのころは、バルト海、地中海、インド洋の物資集積センターとしてのアムステルダムの優位はまだつづいていました。だが英蘭戦争(1652〜74)に勝利することよって、イギリスはタバコや砂糖、毛皮、奴隷などの中継貿易権や、インド、中国との貿易権を獲得します。またポルトガルと同盟を結ぶことにより、ボンベイや西アフリカ、ブラジルへと進出しました。イギリスの工業製品とアフリカの奴隷、アメリカの熱帯産品とのあいだの「大西洋三角貿易」が形成されるのは、18世紀初期です。
オランダ人がイベリア人を追い落とそうとし、そのオランダ人をイギリス人が追い落とすかたちで、イングランドの通商帝国が徐々に形成されていきます。オランダは急速に貿易基盤を失い、金融へと特化していきます。オランダの投資はロンドンへと流れこんでいき、イングランドは世界的な貿易の中継地となりました。
18世紀後半から19世紀にかけ、イギリスはフランスと戦いました。インドのプラッシーの戦い(1757)も英仏間の戦いであり、これに勝利を収めることで、イギリスはインド支配を確実にしていきます。インドのもたらした成果は大きく、これによってイギリスは外資依存経済から脱却します。その時期がまさに「産業革命」と重なっていたのです。
19世紀にはいると、イギリスでは製鉄業が発展し、鉄道が建設され、繊維や機械などの分野でも大きな技術革新が起こりました。イギリスは貿易の自由化を唱え、世界中に鉄鋼や機械、繊維製品を輸出するいっぽう、各国から一次産品を輸入しました。
このころイギリスはクリミア半島でロシアの膨張を抑え(1853〜56)、セポイの反乱(1857〜59)の鎮圧により、インド全土を支配するようになります。
生産の拡大が一段落すると、1870年代から金融拡大の時代がはじまります。1873年から93年にかけて大恐慌が到来し、物価はほぼ3分の1に落ちこみました。生産と投資の拡大がつづいているときに大恐慌が発生したのは、何の不思議でもありません。金融と生産の異常膨張が恐慌の原因だった、とアリギは述べています。
シティ(ロンドン金融街)には、世界を結ぶ金融ネットワークが形成されていました。その代表的な銀行家がロスチャイルド家です。
19世紀後半の大恐慌を脱出に導いたのは、ヨーロッパ各国の軍備競争でした。ヨーロッパ各国の軍事費が幾何級数的に増加します。それにより経済は回復します。しかし、その結果が第1次世界大戦という破局をもたらしたことは言うまでもありません。
イギリスはこの戦争に勝利することで、さらに帝国を拡大しましたが、帝国の経費は帝国の利益をはるかに上回るようになっていました。さらにポンドを基軸とする金本位制が崩れたことにより、第2次世界大戦後の帝国解体をまつまでもなく、イギリスの世界支配は終わった、とアリギは述べています。
20世紀、とりわけ1930年代以降は、アメリカの時代となります。それが始動したのは19世紀末の大恐慌期でした。このころイギリスは産業よりも金融に重点を置く帝国になっていました。
ヘゲモニーの衰退は突然生じるわけではありません。たいてい長い「二重権力」の時代がつづきます。1870年代から1930年代にかけては、イギリスとアメリカの「二重権力」が世界経済を支配した時代だったといえます。
ふり返ってみれば、イギリスが世界経済のヘゲモニーを握ったのは、自由貿易帝国主義のおかげでした。自由貿易は精神の自由と結びついているわけではありません。だれにもさまたげられない貿易という意味です。それが帝国主義と結びついたところに大英帝国の特徴がありました。
その象徴が大西洋の奴隷貿易で、人間自身が自由に売られました。当初、王立アフリカ会社が独占していた奴隷貿易は、民間にも開放されることによって、いちだんと促進されていきます。
アジアの三角貿易も考えてみれば、ひどい自由貿易帝国主義です。当初、オランダの独占を崩せず、なかなか利益を上げられなかった東インド会社は、武力によって、大きな領土と商業的特権を勝ちとります。イギリス国内の圧力で、その特権を開放せざるをえなくなると、東インド会社は中国と茶の貿易を開始し、それを決済するためにインド産のアヘンを中国に輸出しました。
しかし、この独占も廃止されて、中国貿易にも無数の民間商人が進出すると、アヘンはますます中国に自由に流入しました。ひどい話です。
こういう悪の三角貿易をバネに、世界は単一の世界市場に統合されようとしていました。閉鎖的な経済では、とても手にはいらなかった物資が豊かに供給されるようになります。
イギリスが世界に植民地帝国を広げたのは、本来は商品ではなかったもの、土地や人に帰属していたものを世界商品として組みこみ、それを自らの産業社会に統合するためでした。
アリギは鉄鋼の生産増加が軍需と結びついていたことも指摘しています。とりわけ海軍は多くの大砲を必要としていました。18世紀後半から19世紀前半にかけての産業革命──蒸気機関の改善、鉄道、船舶の発達──は軍需が引き金になっていました。産業革命はこれまでの経済体制に大きな変化をもたらし、「従来の生活と労働の様式」を破壊し、社会に不安をもたらします。競争の世界が出現したのです。
産業革命は自由貿易を前提としていました。それによって生じた世界産業の拡大は、「外国市場で投入物を調達し、産出物を売ることで可能となった対外経済に依存していた」からです。
産業革命が進展するにつれ、インドでは、イギリスからますます安い機械織りの布地がはいり、在来の手織り産業は完全に駆逐されていきました。
アリギはこう書いています。
「鉄道、蒸気船、さらには1869年のスエズ運河の開通によって、インドはイギリス資本財産業の製品とイギリスの企業のための……[保証された]主要販路になっただけでなく、ヨーロッパ向けの安い原料(茶、小麦、植物性油、綿、ジュート)の主要な供給地になった」
イギリスが世界の金融を支配できた背景には、インドに対する膨大な貿易黒字がありました。まさにイギリスにとってインドは「金の卵」だったのです。インドの安い原料は、イギリス国内の豊かな生活も保証していました。
ビスマルクのドイツはイギリスに対抗するため、極端な保護主義を採用します。ドイツには中央集権化された軍事=産業機構ができあがります。その終着点となったのが第1次世界大戦で、結果はドイツの悲惨な敗北を招きます。にもかかわらず、ドイツの挑戦はイギリスの没落を早め、それによってアメリカ体制への移行を促進することになるのです。
イギリスが世界に領土を広げる帝国だったのに対し、アメリカは「大陸大の軍事・産業複合体」だった、とアリギは記しています。
アメリカは従属国家、同盟国家に効果的な保護を与え、非友好的な政府に軍事的・経済的圧力を加えるパワーをもっていました。それに加えて、地理的な独立性、領土の広さ、豊富な資源を組み合わせることによって、資本主義を高度化していきます。
企業の統合と組織強化、生産のスピードアップ、大量生産、流通の再編、通信・輸送手段の開発、大量消費によって、アメリカは資本主義の高度化を実現しました。新たな機械装置、良質の原材料、石油や電気などのエネルギーの利用、広大な土地、増大する人口が、そのシステムを支えました。
世界経済のヘゲモニーがイギリスからアメリカへ移行するにつれ、生産の中心はアメリカに移り、イギリスは金融に重点を移すようになります。
歴史的にみると、どの主導的国家も次第にその経済活動を、貿易・生産から金融の投機、仲介に移行するとアリギはいいます。生産の発展が貿易の発展とあいまって資本が蓄積されていく時代は、競争の激化によって、ある時点で頭打ちとなり、それからは過剰資本が金融(貨幣の貸し付け)に向かうようになるというわけです。
しかし、金融中心の経済は、それ自体不安定性と攪乱に見舞われます。こうして古いシステムは危機に陥り、ひとつのサイクルを終えて、新たなシステム(資本蓄積構造)にヘゲモニーを譲るようになります。イギリスからアメリカに世界経済のヘゲモニーが移行したときには、こうした現象が生じていた、とアリギは分析しています。
アメリカ経済は「生産過程と交換過程の垂直的統合」を特徴としているとアリギは述べています。イギリスは細かく分業化・専門化された会社とその相互取引が経済の伝統で、「フレキシブルな特化と金銭的合理性」を誇りにしていました。これにたいし巨大な産業組織がアメリカの特徴です。
「生産過程と交換過程の垂直的統合」とは、「最初の原料の調達から最後の製品の処理に至るまでの生産・交換の連続的下位過程を統合する」ことです。こうした巨大産業を動かしていたのが、テクノストラクチャーと呼ばれる高度の専門的経営陣です。
広大で多様な領土をもつアメリカは、イギリスのような帝国を必要としませんでした。
アメリカ産業が「垂直的統合」を目ざしたのは、広大な国土に対応するためでもありました。これに加わったのが「速度の経済」です。企業は大量生産による製品のコストダウンによって、新規参入を阻止し、市場を支配していきます。政府は保護主義によって、これらの巨大企業群を守り、次第に世界全体での競争優位を勝ちとっていきます。海外への企業進出はそのあとです。
19世紀末、ヨーロッパでは大国間の軍拡競争が盛んになっていました。イギリスは帝国を維持しつつ多くの原材料を確保し、工業製品を循環・輸出することで貿易黒字を得ていました。その余剰資本はアメリカに流れていました。
しかし次第に「生活と戦争の必需品」をアメリカに頼るようになり、アメリカ政府から借款をするはめになります。イギリス・ポンドとともにアメリカ・ドルが世界通貨の座に躍り出たのは、このころです。そうはいっても金融の中心はまだロンドンにありました。
1920年代、アメリカの経済成長は著しく、貿易と戦争債権によるマネーが流れこむなかで、金融の流れは対外投資だけではなく、国内投機へと向かいました。そのバブルが1929年の株価大暴落によって破裂し、31年にポンドが金交換を停止すると、金本位制は終焉を迎え、各国は保護主義へとなだれ込みます。そして第2次世界大戦を経て、機能麻痺したイギリスの世界秩序に代わって、アメリカを中心とした新世界秩序ができあがるわけです。
第2次世界大戦でアメリカはまたも連合国の武器庫としての役割をはたし、その金準備高は世界の70%を占めるようになりました。その結果、生まれたのがいわゆるブレトンウッズ体制です。ドルと金の固定交換比率(35ドル=1オンス)と、ドルに対する各国通貨の固定相場(1ドル=360円など)が定められます。こうしてドルを中心とした金融世界秩序が形成されました。
戦後の冷戦によって、アメリカに集中した資金(余剰資本)は世界に拡散していきます。マーシャルプランの実態はヨーロッパに対する軍事援助にほかなりませんでした。熱い朝鮮戦争は新たな軍事支出を必要としました。
多くの経済学者が、1950年の朝鮮戦争から1973年のベトナム和平パリ協定までの時期を「資本主義の黄金期」と呼んでいます。この時期、たしかに西側資本主義国は経済成長を持続させ、大きな利益を上げていました。
そのあと、ブレトンウッズの固定為替相場体制がもたなくなります。1973年には石油ショックが起こります。アメリカは「軍事的ケインズ主義」と多国籍企業によって世界的パワーを追求してきましたが、それによって、ドルは世界に拡散し、もはや固定相場制が維持できなくなり、代わりにドルを基軸とする変動相場制が導入されることになります。
これにより、アメリカは非兌換ドルを国際循環の中にたれ流すことが可能となりました。ドルの引き続く下落によって、外国市場でアメリカ製品の価格は下がり、アメリカ市場で外国製品の価格は引き上げられ、アメリカの輸出と収入は増大します。
変動相場制は大成功を収めたようにみえました。だが、そこには新たな問題が発生したのです。変動相場制のもとでは、企業自身が毎日の為替相場の変動に対処しなければならなくなります。さまざまな通貨で、お金が企業の銀行口座に出入りするため、企業は為替リスクを避けるため、為替の先物取引をせざるを得なくなります。
こうして金融カジノが開店します。ユーロカレンシーやオイルダラーもそこに流れこんで、金融のリスクと不安定性が増大していきます。1970年代には世界的にインフレが発生しました。
アメリカは強大な軍事力を背景に、世界をアメリカのイメージにつくりかえ、第三世界の原料と第一世界の購買力とを組み合わせることで、企業の既得権益を拡大・確保することをめざしていました。これがアメリカ流の世界秩序だったといえるでしょう。その構図が1970年代に崩れたあと、アメリカの権威は失墜することになります。
レーガン政権は金融引き締め策をとり、金利を引き上げて、世界から資金を吸収するいっぽうで、規制緩和によって企業の自由を拡大する方策をとりました。いわゆるレーガノミクスです。そのうえで、さらに借金財政によってソ連との軍事対決姿勢を強めました。
ソ連の崩壊は資本主義の勝利とアメリカの繁栄をもたらすかのように思えました。だが、その後、アメリカはすでに超国家的となった金融市場をコントロールできなくなっていきます。「ふたたび危機がもっと厄介なかたちで浮上してくるのは、単に時間の問題であった」とアリギは予言しています。2008年の恐慌はまさにその実現だったのかもしれません。
『長い20世紀』が出版されたのは1994年のことです。その最終章で、アリギは現在進行形の変化と将来の可能性をどう見るかを論じていました。
アリギによれば、ひとつの可能性は、機能不全におちいったアメリカに代わって、世界政府のようなものができることでした。たとえば主要7カ国会議(G7)や国連安全保障理事会のような超国家組織がじゅうぶんに役割を発揮して、全世界をリードしていくことが想定されていました。しかし、その後、世界はむしろ混迷を深めているようにみえます。
アリギが考えたもう一つの方向は、アメリカをヨーロッパとアジアが支えていくという協調体制ができあがる可能性でした。そのさい、軍事力をもつアメリカが、これまでのような一国主義的姿勢をとるのではなく、世界と調和して、疑似帝国的な役割を果たしていくという構図が考えられていました。
さらにもうひとつの可能性は、東アジアの台頭です。本書が出版された1994年の時点で、アリギは日本や韓国、台湾、シンガポールなど東アジアの「資本主義群島」に期待をかけていました。しかし、2009年に日本語版が出る時点では意見を修正して、日本の重要性をちいさく見積もり、中国が経済的に拡大する可能性をみるようになっていました。
さすがに「アメリカのサイクル」が終わって、いよいよ「中国のサイクル」が始まろうとしているとは言っていません。アリギ自身は日本語版において、中国が「アメリカのリーダーシップに対する歴史的オルタナティブになりつつある」という慎重な言い回しをしています。
しかし、最悪のシナリオは米中対決の可能性です。その場合、「世界はシステム的な長期のカオスに突入してしまうかもしれない」。戦争がもたらすのは「資本主義の歴史の終焉」かもしれないが、「人類の歴史の終焉」でもありうるとアリギは預言しています。この預言が実現しないことを祈るのみです。
ブローデルは近代社会のシステムを三層構造として理解しました。
いちばん下には物質生活の層、中間には市場経済の層、そして最上層に資本主義の層がきます。ブローデルの規定が特異なのは、資本主義と市場経済を同一視する一般の見方に対し、かれが「資本主義は、その登場と拡大を国家権力に依存し、市場経済と対立する」とした点です。つまりブローデルにとって、資本主義とは資本(産業や金融)と一体化した国家の経済戦略にほかなりません。これにたいし、市場経済の目的は、スムーズな経済循環による物質生活の確保にあります。
継起的蓄積とは何でしょう。
ここでアリギが持ちだすのは、マルクスによる資本の運動の規定です。英語でいうと、マルクスは資本の運動をM→C→M′の自己増殖過程ととらえました(G─W─G′)。つまり貨幣→商品→貨幣の限りなき膨張とみたわけです。
資本主義の「継起的蓄積」がはじまった時期を、アリギはブローデルにならって、15世紀のイタリア都市国家の時代にみました。
そして、それ以降の中心的な流れを(1)15世紀から17世紀のジェノヴァ・サイクル、(2)16世紀後期からほぼ18世紀全体のオランダ・サイクル、(3)18世紀後半から20世紀初めのイギリス・サイクル、(4)19世紀後期に始まり現在にいたるアメリカ・サイクルとしてとらえました。
ヘゲモニーという言い方があります。
ふつう覇権と訳されますが、そう言い切るとだいじな部分が抜け落ちてしまいます。アントニオ・グラムシは、コントロールとリーダーシップにヘゲモニーの発現をみていた、とアリギは書いています。力だけではじゅうぶんではありません。頼らせるようにしなくてはいけない。それによって相手を仕えさせるのです。国家というのはそういう存在で、世界には多くの国々を引っ張っていく覇者としての国家が存在します。
現代から過去に射程を伸ばして、資本主義国家の原像をさがすと、中世末期の地中海世界に行き着きます。その後、世界のヘゲモニーを握ったスペイン、オランダ、イギリス、アメリカは、ある意味で地中海世界のシステムを引き継いで、多少のひねりを加えながら、それをより大規模に再現したにすぎない、とアリギはいいます。
そこに見られるのは資本蓄積システムとそのサイクルです。
資本と国家は一心同体でした。対立することもありますが、概して資本と国家は一緒にタッグを組んで戦ってきました。国家が資本の自由を認め、資本が国家をあてにする、そういう状態を資本主義と名づけることができるのではないでしょうか。資本主義ということばが誕生するのは20世紀になってからですが、そうしたシステムがはじまったのは15世紀の地中海です。
イスラム商人に独占されていたアジアの富を直接手に入れたいという思いからヨーロッパの膨張は始まりました。アジアの富の取引を担っていたのが、中世末期の「4大都市国家」、すなわちヴェネツィア、フィレンツェ、ジェノヴァ、ミラノです。なかでも、アリギはヴェネツィアをきたるべき資本主義国家の「完全モデル」ととらえています。
そのヴェネツィアに打ち勝とうとしたのが、ジェノヴァで、ジェノヴァはポルトガルとスペインを応援することによって、アジアの富を確保しようとします。ポルトガルは成功しましたが、スペインは失敗します。ところが、スペインはアメリカ大陸を偶然「発見」し、それがパワーと富の源泉となります。
16世紀ヨーロッパで、スペインは圧倒的な力を誇っていました。しかし、イギリスやフランスが経済力をつけ、勃興しはじめます。スペインは教皇やハプスブルク家と組んで、これらの国を服従させようとしますが、ことごとく失敗します。とりわけネーデルラント北部7州は結束して、スペインからの独立をはかり、1648年のウェストファリア条約で新国家としての承認を勝ち取ります。それがオランダでした。
ウェストファリア条約には、勢力均衡や内政不干渉といった政治原則のほか、貿易障壁の撤廃や商業の自由といった経済原則が謳われていました。これが近代国際システムの原型となります。
オランダの通商・金融ネットワークは、スペインやポルトガルから奪い取ったもので、かつてのヴェネツィアよりずっと強大でした。オラニエ公マウリッツの考案した軍事技術が、オランダの力を支えていました。しかし、オランダの覇権は長くつづきません。
1652年の英蘭戦争にはじまり、1815年のナポレオン戦争の終結にいたるまで、イギリスやフランスとしのぎを削る時代となるからです。
当初はネーデルラントの支配をめぐる争いでした。それが次第に「富とパワーの源泉を取りこむ」ことへ次元が移ると、イギリスはアメリカにつながる大西洋の支配、さらには弱体化しつつあるオスマン帝国やムガール帝国の切り崩しへと向かいます。
この時代の特徴は、資本主義と領土主義の結合にあるとアリギはいいます。具体的には、入植植民地主義と資本主義的奴隷制、経済的ナショナリズム──それらがあわさって、海外への膨張を促しました。
世界商業と植民地から得られた利益を国内経済の形成へと誘導し、それによってますます多くの市民を「間接的、かつしばしば知らぬ間に、支配者の戦争と国家形成の努力を支えるために動員[する]」流れができつつありました。
大陸から離れた島国であったために、イギリスは大陸の抗争に巻きこまれず、優位のうちに海外拡大をはたすことができました。ナポレオンのヨーロッパ支配を打ち砕き、ヨーロッパ協調の道筋をつけたイギリスは、自由貿易帝国主義のもとに、非西洋世界への植民帝国の拡大に乗りだします。
「植民地から提供させた帝国の献上品を、世界中に投下される資本に再循環させることで、世界金融センターとしてのロンドンの比較優位は、アムステルダム、パリという競合センターに対して、いっそう強まることになった」とアリギは書いています。
イギリスの強さは自由貿易と帝国主義を結びつけたことにあります。世界の産物が自由にイギリスの国内市場に流入するいっぽうで、産業革命で生みだされた財が世界中に流れ、資産家の富が増大していきました。
イギリス資本主義の本質は、ヴェネツィア型とオランダ型とスペイン型を合わせた世界経済=帝国にあったとアリギはみています。そのイギリスが19世紀末ごろから力を失っていったのは、ドイツやアメリカの挑戦に対応できなかったためです。
北米大陸の端から端まで領土を拡張したアメリカは、世界の労働、資本、企業活動を引きつける「ブラックホール」になろうとしていました。いっぽうドイツは海外植民地の拡大に失敗したあと、強力な軍産複合体をつくりあげ、イギリスに対抗します。
イギリスのヘゲモニーを引き継いだのは、大西洋と太平洋の二大海洋に接近できるという優位性をもつ大陸国家アメリカです。民族解放運動の流れのなかで、イギリスは次第に植民地を維持するコストに耐えられなくなっていきます。
アメリカのヘゲモニーは「自由世界主義」とでもいうべきもので、「帝国主義」でも「自由貿易主義」でもないところに特徴があった、とアリギは書いています。それはアメリカを中心とする「自由世界」をつくる動きとなっていきます。
アメリカは植民地をつくろうとはしませんでしたが、国内の産業を保護するいっぽう他国には門戸開放を求めていました。とりわけ第2次世界大戦後は、ブレトンウッズ体制とGATT(関税および貿易に関する一般協定)がアメリカの主導権を支えることになります。
これが世界史の大まかな動きですが、以下、それをもう少し詳しくみておくことにしましょう。
近代資本主義の揺籃の地は地中海世界です。
商業につづいて金融が拡大し、資本が持続的に蓄積されるようになるのは14世紀ごろからで、その中心となったのはイタリアの「4大都市国家」、すなわちフィレンツェ、ミラノ、ヴェネツィア、ジェノヴァでした。
これらの都市国家のあいだには、経済面で一種の棲(す)み分けがなされていました。アリギはこう書いています。
フィレンツェとミラノは、どちらも製造業と北西ヨーロッパとの陸路貿易に従事していたが、フィレンツェが織物貿易に特化していたのに対して、ミラノは金属製品の貿易に特化していた。ヴェネツィアとジェノヴァは、どちらも東洋との海上貿易に従事していたが、ヴェネツィアが香辛料貿易に基礎をおく南アジア回路の取引に特化していたのに対して、ジェノヴァは絹貿易に基礎をおく中央アジア回路の取引に特化していた。
14世紀半ばから15世紀半ばにかけて4大都市国家間に抗争がなかったわけではありません。都市内部の対立も激しいものがありました。
フィレンツェを例に取りあげてみましょう。
13世紀後期にフィレンツェは織物産業の中心地として発達します。原料の羊毛は最初イタリア国内から集めていましたが、それが足りなくなるとネーデルラント、フランス、さらにはスペイン、ポルトガル、イングランドにも原料を求めるようになりました。
フィレンツェでつくられた毛織物製品は、イタリア国内だけではなく、レバント(現在のギリシャ、トルコ、レバノン、エジプト方面)、さらにはフランス、イングランドにも輸出されていました。この毛織物貿易網が、フィレンツェの金融ネットワークに重なっていきます。
英仏間に王位継承権をめぐって「百年戦争」(1337〜1453)がはじまると、イングランドは毛織物工業を「国産化」する動きに出ます。以前からフィレンツェの毛織物は高品質・高価格品へ次第に移行していたとはいえ、イングランドの「国産化」の影響は大きく、毛織物産業全体の生産量は徐々に落ちこんでいきました。
1340年代にイングランドのエドワード3世がフィレンツェ商人から借りていた戦費を踏み倒したため、「大恐慌」が発生し、バルディとペルッツィの両家が倒産します。1378年には梳毛工(そもうこう)らの下層労働者が反乱を起こし(チオンピの乱)、一時、市の政権を握ります。下層ギルドの労働者が立ち上がったのは、旧来の毛織物産業が衰退したからです。だが、かれらが政権を掌握したからといって、経済が立ち直るわけでもありません。その政権はやがてひっくり返されます。
そのあとはメディチ家に代表される裕福な商人一族による寡頭支配が半世紀つづきます。メディチ家はイタリア国内のみならずフランスやイングランド、フランドルなどにも支店を置き、各国政府にカネを貸し付けていました。
メディチ家の収益は、大半がローマ教皇庁とそのネットワークを基盤にしていました。しかし「百年戦争」が終わると、メディチ家は次第に衰えていきます。ルネサンスはメディチ家の最後の輝きでした。ロレンツォ・デ・メディチ(1449〜92)は銀行業から得た利益を芸術や貧者の救済、政治につぎこみました。
だが、時代は大きく変わっていきます。いわゆる「大航海時代」がはじまり、新大陸アメリカが「発見」され、インド・ルートが開発されると、地中海は経済の中心ではなくなり、イタリアの都市国家はかつての柔軟性を失っていきます。
イタリアの4大都市国家のなかで、大航海時代に対応したのはジェノヴァだけでした。その代わり、フィレンツェとヴェネツィアには壮麗なルネサンス都市と海の都が残されることになりました。
アリギは、ジェノヴァを資本主義蓄積システムの「第1サイクル」と位置づけています。なぜジェノヴァだったのでしょう。ジェノヴァ経済の要となったのは、1407年に設立されたサンジョルジョ銀行でした。
アリギによれば「[ジェノヴァの]富の基盤は、中国に向かう中央アジア交易路が競争力をもち、ジェノヴァ企業がこの交易路の黒海『終点』で準独占的支配権を確立していたことにあった」といいます。ジェノヴァはクリミア半島沿岸部を支配し、中央アジア交易路を押さえていました。ところがモンゴル帝国の衰退とオスマン帝国の台頭によって、ジェノヴァの貿易は大きな打撃を受けます。
ヴェネツィアがオスマン帝国やカタロニア、アラゴンと結びつくことによって、ジェノヴァを排除するようになると、交易路を失ったジェノヴァは万事休すかのようにみえました。残っていたのはサンジョルジョ銀行に集まっていた「過剰蓄積」だけです。
しかし、破綻のなかから新たな道がみつかります。カスティリア貿易です。ジェノヴァ商人はコルドバ、カディス、セビーリャに出張所を設け、カスティリアの商業に食いこみます。
ジェノヴァはイベリア半島南部とアフリカ北西部沿岸(マグレブ)に経済的拠点を広げていきます。目ざすは、マグレブに集まるアフリカの金と、大西洋航路でした。
十字軍精神にあふれたポルトガルとスペインを動かしていたのはジェノヴァの資本でした。インド航路の「開発」とアメリカの「発見」の背後には、ジェノヴァの存在があります。クリストファー・コロンブス(クリストフォーロ・コロンボ)はジェノヴァ出身の商人でした。
フランドルで生まれたハプスブルク家のカール5世(1500〜58)は、1516年にスペイン王(カルロス1世)となりますが、ジェノヴァの資本はかれを財政的に支えて、1519年に神聖ローマ皇帝へと押しあげます。ドイツの銀を握っていたフッガー家もカール5世の財政を支えるもうひとつの柱でした。ところが、アメリカから大量の銀がヨーロッパに流入するようになるとドイツの銀は太刀打ちできなくなり、フッガー家は破産に追いこまれ、ふたたびジェノヴァの銀行家の力が強くなるわけです。
ジェノヴァはスペインの盛衰と運命をともにします。ピアツェンツァ(ミラノ南方の町)の大市(おおいち)はジェノヴァの資本が牛耳っており、ヨーロッパの金融センターとなっていました。しかし、スペイン領ネーデルラントの力が次第に大きくなってきます。
ブローデルがフィレンツェやヴェネツィアでなくジェノヴァを「蓄積システムの第1サイクル」として選んだ理由ははっきりしています。それはジェノヴァこそが、その後のオランダ、イギリス、アメリカへとつづく世界資本主義システムを起動させる淵源となったからです。
16世紀になると、資本蓄積の中心地は都市国家ではなく、それなりの領土をもつ国家へと移行しました。ジェノヴァとスペインのあいだには、アメリカ銀を金や為替手形に変えて、富の流通をはかる金融システムができあがっていました。オランダ独立戦争は、このジェノヴァ・イベリア結合を打ち破り、アムステルダムを世界の金融中心地へと変えていくことになります。
もともとアムステルダムはバルト海交易(穀物と海軍物資)によって発展しました。そこから生じた余剰は土地開拓や農産品の開発にあてられていました。スペインからの独立戦争が始まるのは1568年のことで、プロテスタントのオラニエ家を中心にネーデルラント北部7州連合が形成されます。そして1600年ごろには実質的に独立を勝ちとり、1648年のウェストファリア条約によって、ネーデルラント連邦共和国(オランダ)として承認されるのです。
オランダの商人は、積極的で機敏な商業活動によって世界各地から集めた穀物や鰊(にしん)、香辛料、織物、ワイン、硝石(しょうせき)、銅、タバコ、カカオ、羊毛、絹、麻などを巨大倉庫に積みあげ、ヨーロッパ各地に販売しました。
17世紀初頭につくられたアムステルダム証券取引所やヴィッセル銀行によって、ヨーロッパ中から貨幣資本が集まってくるようになると、アムステルダムは世界の通商と金融の中心となります。それを促進したのが1602年に設立されたオランダ東インド会社でした。それから1740年ごろまでがオランダの全盛時代です。重商主義時代がはじまります。
オランダ東インド会社は東インド諸島(現在のインドネシア)で貿易を拡大するとともに、有利な条件を作るために広範な軍事活動をおこない、領土を征服しました。当時の国際商品である胡椒を含む香料の独占をはかったのです。その行動はまさに南米のスペイン人同様、残忍そのものでした。「しかし、この残忍性は、まったく企業的論理に内面化しており、それは収益性を破壊するものではなく、それどころか収益性を支えるものであった」とアリギは記しています。
イギリスとフランスは重商主義を模倣し、オランダを追いかけました。オランダを模倣し追い越そうとした西洋の国々が、資本主義のパワーと領土(帝国)を獲得しようとしたのは悪しき必然でした。
オランダの没落を招いたのは、アメリカ独立革命(1775〜83)と「バタヴィア革命」(1795〜1813)だといってよいでしょう。アメリカ革命でオランダはイギリスに対抗してフランスを支援します。そのため、イギリスから報復を受け、セイロン島とマラッカを奪われました。そして、その後、ナポレオンによる占領(バタヴィア革命=バタヴィア共和国の設立)により、決定的なダメージを受けることになります。
オランダの金融支配力が衰退するのは、オランダがアメリカ独立戦争でフランスを支援したのにたいし、イギリスが報復を加えたことが大きいといえます。
イギリスが世界のトップに躍りでたのは、18世紀末から19世紀初めにかけオランダとフランスを倒して、商業と金融の面で優位に立ったからです。
そのころには大英帝国の大部分はできており、カナダ、カリブ海域、マドラス、ボンベイ、ケープ沿岸部、ジブラルタル、ベンガル、セイロン、ボタニー湾、ベナン、ギアナ、トリニダードを領していました。さらに1850年代には香港、オーストラリア、ニュージーランド、インド全土が帝国に加わります。これらの地域では、砂糖や綿花、茶、ゴムがつくられ、金、銀、銅、スズが採掘されていました。
アリギによれば、「世界史上最強の領土主義的国家、かつ同時に資本主義的国家」であったことがイギリスの強さでした。
それにいたるまでには長い歴史がありますが、とりわけエリザベス1世(1558〜1603)時代の改革と再編が、その後の展開を決定づけたといわれます。グレシャムの助言により、ポンドが安定したのもこの時代です。産業の発展も18世紀後半になって突然生じたわけではありません。14世紀にはすでに毛織物工業が始まっていたし、16世紀には炭鉱業や冶金業が発達します。
そのころは、バルト海、地中海、インド洋の物資集積センターとしてのアムステルダムの優位はまだつづいていました。だが英蘭戦争(1652〜74)に勝利することよって、イギリスはタバコや砂糖、毛皮、奴隷などの中継貿易権や、インド、中国との貿易権を獲得します。またポルトガルと同盟を結ぶことにより、ボンベイや西アフリカ、ブラジルへと進出しました。イギリスの工業製品とアフリカの奴隷、アメリカの熱帯産品とのあいだの「大西洋三角貿易」が形成されるのは、18世紀初期です。
オランダ人がイベリア人を追い落とそうとし、そのオランダ人をイギリス人が追い落とすかたちで、イングランドの通商帝国が徐々に形成されていきます。オランダは急速に貿易基盤を失い、金融へと特化していきます。オランダの投資はロンドンへと流れこんでいき、イングランドは世界的な貿易の中継地となりました。
18世紀後半から19世紀にかけ、イギリスはフランスと戦いました。インドのプラッシーの戦い(1757)も英仏間の戦いであり、これに勝利を収めることで、イギリスはインド支配を確実にしていきます。インドのもたらした成果は大きく、これによってイギリスは外資依存経済から脱却します。その時期がまさに「産業革命」と重なっていたのです。
19世紀にはいると、イギリスでは製鉄業が発展し、鉄道が建設され、繊維や機械などの分野でも大きな技術革新が起こりました。イギリスは貿易の自由化を唱え、世界中に鉄鋼や機械、繊維製品を輸出するいっぽう、各国から一次産品を輸入しました。
このころイギリスはクリミア半島でロシアの膨張を抑え(1853〜56)、セポイの反乱(1857〜59)の鎮圧により、インド全土を支配するようになります。
生産の拡大が一段落すると、1870年代から金融拡大の時代がはじまります。1873年から93年にかけて大恐慌が到来し、物価はほぼ3分の1に落ちこみました。生産と投資の拡大がつづいているときに大恐慌が発生したのは、何の不思議でもありません。金融と生産の異常膨張が恐慌の原因だった、とアリギは述べています。
シティ(ロンドン金融街)には、世界を結ぶ金融ネットワークが形成されていました。その代表的な銀行家がロスチャイルド家です。
19世紀後半の大恐慌を脱出に導いたのは、ヨーロッパ各国の軍備競争でした。ヨーロッパ各国の軍事費が幾何級数的に増加します。それにより経済は回復します。しかし、その結果が第1次世界大戦という破局をもたらしたことは言うまでもありません。
イギリスはこの戦争に勝利することで、さらに帝国を拡大しましたが、帝国の経費は帝国の利益をはるかに上回るようになっていました。さらにポンドを基軸とする金本位制が崩れたことにより、第2次世界大戦後の帝国解体をまつまでもなく、イギリスの世界支配は終わった、とアリギは述べています。
20世紀、とりわけ1930年代以降は、アメリカの時代となります。それが始動したのは19世紀末の大恐慌期でした。このころイギリスは産業よりも金融に重点を置く帝国になっていました。
ヘゲモニーの衰退は突然生じるわけではありません。たいてい長い「二重権力」の時代がつづきます。1870年代から1930年代にかけては、イギリスとアメリカの「二重権力」が世界経済を支配した時代だったといえます。
ふり返ってみれば、イギリスが世界経済のヘゲモニーを握ったのは、自由貿易帝国主義のおかげでした。自由貿易は精神の自由と結びついているわけではありません。だれにもさまたげられない貿易という意味です。それが帝国主義と結びついたところに大英帝国の特徴がありました。
その象徴が大西洋の奴隷貿易で、人間自身が自由に売られました。当初、王立アフリカ会社が独占していた奴隷貿易は、民間にも開放されることによって、いちだんと促進されていきます。
アジアの三角貿易も考えてみれば、ひどい自由貿易帝国主義です。当初、オランダの独占を崩せず、なかなか利益を上げられなかった東インド会社は、武力によって、大きな領土と商業的特権を勝ちとります。イギリス国内の圧力で、その特権を開放せざるをえなくなると、東インド会社は中国と茶の貿易を開始し、それを決済するためにインド産のアヘンを中国に輸出しました。
しかし、この独占も廃止されて、中国貿易にも無数の民間商人が進出すると、アヘンはますます中国に自由に流入しました。ひどい話です。
こういう悪の三角貿易をバネに、世界は単一の世界市場に統合されようとしていました。閉鎖的な経済では、とても手にはいらなかった物資が豊かに供給されるようになります。
イギリスが世界に植民地帝国を広げたのは、本来は商品ではなかったもの、土地や人に帰属していたものを世界商品として組みこみ、それを自らの産業社会に統合するためでした。
アリギは鉄鋼の生産増加が軍需と結びついていたことも指摘しています。とりわけ海軍は多くの大砲を必要としていました。18世紀後半から19世紀前半にかけての産業革命──蒸気機関の改善、鉄道、船舶の発達──は軍需が引き金になっていました。産業革命はこれまでの経済体制に大きな変化をもたらし、「従来の生活と労働の様式」を破壊し、社会に不安をもたらします。競争の世界が出現したのです。
産業革命は自由貿易を前提としていました。それによって生じた世界産業の拡大は、「外国市場で投入物を調達し、産出物を売ることで可能となった対外経済に依存していた」からです。
産業革命が進展するにつれ、インドでは、イギリスからますます安い機械織りの布地がはいり、在来の手織り産業は完全に駆逐されていきました。
アリギはこう書いています。
「鉄道、蒸気船、さらには1869年のスエズ運河の開通によって、インドはイギリス資本財産業の製品とイギリスの企業のための……[保証された]主要販路になっただけでなく、ヨーロッパ向けの安い原料(茶、小麦、植物性油、綿、ジュート)の主要な供給地になった」
イギリスが世界の金融を支配できた背景には、インドに対する膨大な貿易黒字がありました。まさにイギリスにとってインドは「金の卵」だったのです。インドの安い原料は、イギリス国内の豊かな生活も保証していました。
ビスマルクのドイツはイギリスに対抗するため、極端な保護主義を採用します。ドイツには中央集権化された軍事=産業機構ができあがります。その終着点となったのが第1次世界大戦で、結果はドイツの悲惨な敗北を招きます。にもかかわらず、ドイツの挑戦はイギリスの没落を早め、それによってアメリカ体制への移行を促進することになるのです。
イギリスが世界に領土を広げる帝国だったのに対し、アメリカは「大陸大の軍事・産業複合体」だった、とアリギは記しています。
アメリカは従属国家、同盟国家に効果的な保護を与え、非友好的な政府に軍事的・経済的圧力を加えるパワーをもっていました。それに加えて、地理的な独立性、領土の広さ、豊富な資源を組み合わせることによって、資本主義を高度化していきます。
企業の統合と組織強化、生産のスピードアップ、大量生産、流通の再編、通信・輸送手段の開発、大量消費によって、アメリカは資本主義の高度化を実現しました。新たな機械装置、良質の原材料、石油や電気などのエネルギーの利用、広大な土地、増大する人口が、そのシステムを支えました。
世界経済のヘゲモニーがイギリスからアメリカへ移行するにつれ、生産の中心はアメリカに移り、イギリスは金融に重点を移すようになります。
歴史的にみると、どの主導的国家も次第にその経済活動を、貿易・生産から金融の投機、仲介に移行するとアリギはいいます。生産の発展が貿易の発展とあいまって資本が蓄積されていく時代は、競争の激化によって、ある時点で頭打ちとなり、それからは過剰資本が金融(貨幣の貸し付け)に向かうようになるというわけです。
しかし、金融中心の経済は、それ自体不安定性と攪乱に見舞われます。こうして古いシステムは危機に陥り、ひとつのサイクルを終えて、新たなシステム(資本蓄積構造)にヘゲモニーを譲るようになります。イギリスからアメリカに世界経済のヘゲモニーが移行したときには、こうした現象が生じていた、とアリギは分析しています。
アメリカ経済は「生産過程と交換過程の垂直的統合」を特徴としているとアリギは述べています。イギリスは細かく分業化・専門化された会社とその相互取引が経済の伝統で、「フレキシブルな特化と金銭的合理性」を誇りにしていました。これにたいし巨大な産業組織がアメリカの特徴です。
「生産過程と交換過程の垂直的統合」とは、「最初の原料の調達から最後の製品の処理に至るまでの生産・交換の連続的下位過程を統合する」ことです。こうした巨大産業を動かしていたのが、テクノストラクチャーと呼ばれる高度の専門的経営陣です。
広大で多様な領土をもつアメリカは、イギリスのような帝国を必要としませんでした。
アメリカ産業が「垂直的統合」を目ざしたのは、広大な国土に対応するためでもありました。これに加わったのが「速度の経済」です。企業は大量生産による製品のコストダウンによって、新規参入を阻止し、市場を支配していきます。政府は保護主義によって、これらの巨大企業群を守り、次第に世界全体での競争優位を勝ちとっていきます。海外への企業進出はそのあとです。
19世紀末、ヨーロッパでは大国間の軍拡競争が盛んになっていました。イギリスは帝国を維持しつつ多くの原材料を確保し、工業製品を循環・輸出することで貿易黒字を得ていました。その余剰資本はアメリカに流れていました。
しかし次第に「生活と戦争の必需品」をアメリカに頼るようになり、アメリカ政府から借款をするはめになります。イギリス・ポンドとともにアメリカ・ドルが世界通貨の座に躍り出たのは、このころです。そうはいっても金融の中心はまだロンドンにありました。
1920年代、アメリカの経済成長は著しく、貿易と戦争債権によるマネーが流れこむなかで、金融の流れは対外投資だけではなく、国内投機へと向かいました。そのバブルが1929年の株価大暴落によって破裂し、31年にポンドが金交換を停止すると、金本位制は終焉を迎え、各国は保護主義へとなだれ込みます。そして第2次世界大戦を経て、機能麻痺したイギリスの世界秩序に代わって、アメリカを中心とした新世界秩序ができあがるわけです。
第2次世界大戦でアメリカはまたも連合国の武器庫としての役割をはたし、その金準備高は世界の70%を占めるようになりました。その結果、生まれたのがいわゆるブレトンウッズ体制です。ドルと金の固定交換比率(35ドル=1オンス)と、ドルに対する各国通貨の固定相場(1ドル=360円など)が定められます。こうしてドルを中心とした金融世界秩序が形成されました。
戦後の冷戦によって、アメリカに集中した資金(余剰資本)は世界に拡散していきます。マーシャルプランの実態はヨーロッパに対する軍事援助にほかなりませんでした。熱い朝鮮戦争は新たな軍事支出を必要としました。
多くの経済学者が、1950年の朝鮮戦争から1973年のベトナム和平パリ協定までの時期を「資本主義の黄金期」と呼んでいます。この時期、たしかに西側資本主義国は経済成長を持続させ、大きな利益を上げていました。
そのあと、ブレトンウッズの固定為替相場体制がもたなくなります。1973年には石油ショックが起こります。アメリカは「軍事的ケインズ主義」と多国籍企業によって世界的パワーを追求してきましたが、それによって、ドルは世界に拡散し、もはや固定相場制が維持できなくなり、代わりにドルを基軸とする変動相場制が導入されることになります。
これにより、アメリカは非兌換ドルを国際循環の中にたれ流すことが可能となりました。ドルの引き続く下落によって、外国市場でアメリカ製品の価格は下がり、アメリカ市場で外国製品の価格は引き上げられ、アメリカの輸出と収入は増大します。
変動相場制は大成功を収めたようにみえました。だが、そこには新たな問題が発生したのです。変動相場制のもとでは、企業自身が毎日の為替相場の変動に対処しなければならなくなります。さまざまな通貨で、お金が企業の銀行口座に出入りするため、企業は為替リスクを避けるため、為替の先物取引をせざるを得なくなります。
こうして金融カジノが開店します。ユーロカレンシーやオイルダラーもそこに流れこんで、金融のリスクと不安定性が増大していきます。1970年代には世界的にインフレが発生しました。
アメリカは強大な軍事力を背景に、世界をアメリカのイメージにつくりかえ、第三世界の原料と第一世界の購買力とを組み合わせることで、企業の既得権益を拡大・確保することをめざしていました。これがアメリカ流の世界秩序だったといえるでしょう。その構図が1970年代に崩れたあと、アメリカの権威は失墜することになります。
レーガン政権は金融引き締め策をとり、金利を引き上げて、世界から資金を吸収するいっぽうで、規制緩和によって企業の自由を拡大する方策をとりました。いわゆるレーガノミクスです。そのうえで、さらに借金財政によってソ連との軍事対決姿勢を強めました。
ソ連の崩壊は資本主義の勝利とアメリカの繁栄をもたらすかのように思えました。だが、その後、アメリカはすでに超国家的となった金融市場をコントロールできなくなっていきます。「ふたたび危機がもっと厄介なかたちで浮上してくるのは、単に時間の問題であった」とアリギは予言しています。2008年の恐慌はまさにその実現だったのかもしれません。
『長い20世紀』が出版されたのは1994年のことです。その最終章で、アリギは現在進行形の変化と将来の可能性をどう見るかを論じていました。
アリギによれば、ひとつの可能性は、機能不全におちいったアメリカに代わって、世界政府のようなものができることでした。たとえば主要7カ国会議(G7)や国連安全保障理事会のような超国家組織がじゅうぶんに役割を発揮して、全世界をリードしていくことが想定されていました。しかし、その後、世界はむしろ混迷を深めているようにみえます。
アリギが考えたもう一つの方向は、アメリカをヨーロッパとアジアが支えていくという協調体制ができあがる可能性でした。そのさい、軍事力をもつアメリカが、これまでのような一国主義的姿勢をとるのではなく、世界と調和して、疑似帝国的な役割を果たしていくという構図が考えられていました。
さらにもうひとつの可能性は、東アジアの台頭です。本書が出版された1994年の時点で、アリギは日本や韓国、台湾、シンガポールなど東アジアの「資本主義群島」に期待をかけていました。しかし、2009年に日本語版が出る時点では意見を修正して、日本の重要性をちいさく見積もり、中国が経済的に拡大する可能性をみるようになっていました。
さすがに「アメリカのサイクル」が終わって、いよいよ「中国のサイクル」が始まろうとしているとは言っていません。アリギ自身は日本語版において、中国が「アメリカのリーダーシップに対する歴史的オルタナティブになりつつある」という慎重な言い回しをしています。
しかし、最悪のシナリオは米中対決の可能性です。その場合、「世界はシステム的な長期のカオスに突入してしまうかもしれない」。戦争がもたらすのは「資本主義の歴史の終焉」かもしれないが、「人類の歴史の終焉」でもありうるとアリギは預言しています。この預言が実現しないことを祈るのみです。
ウェーバーの社会経済史(3)──商品世界ファイル(28) [商品世界ファイル]
前市場的な経済制度も資本主義に含めるなら、歴史のすべての段階に資本主義は存在するといえます。しかし、ウェーバーは「日常需要が資本主義的な仕方で充足されるという事実は、ただ西洋にのみ特有であり、しかも西洋においても19世紀の後半の出来事である」と強調します。
「日常需要が資本主義的な仕方で充足される」というのは、必要な商品が常に市場に供給され、日常の需要が商品の購入によって充たされることを意味します。ウェーバーはこうした商品世界の広がりを近代資本主義の特徴とするのですが、だとするなら、なぜ16世紀以降、西洋(ヨーロッパ)においてのみ、こうした近代資本主義が定着し、発展していったかが問われなければならないというわけです。
ウェーバーはまず近代資本主義成立の前提は何かと問うています。
かれによると、ひとつは(1)企業家が物的生産手段(土地、装置、機械、道具など)を私有財産として専有しうること。次に(2)市場の自由が存在すること(身分制の束縛がないこと)。さらに(3)合理的な技術、とりわけ機械を手に入れられること。(4)法のもとで経済の自由が認められていること。(5)自己の労働力を市場で自由に売ることができること。(6)ビジネスの商業化、すなわち株式や投資が認められること、などです。
資本主義の発達は企業、とりわけ株式会社の発達をともなってこそ可能でした。
ウェーバーは株式会社にはふたつの出発点があるといいます。
ひとつは、政治権力が収益を先取りしようとして資本を集める場合で、ジェノヴァのサンジョルジョ銀行がそのひとつでした。高利のつく戦時公債が、戦争に勝利したときの戦利品や賠償金(戦利品)を当てにして発行されました。ただし、失敗に終わったときはみじめで、そうした公債は紙くずになります。
もうひとつは商事会社に出資する場合です。15、16世紀には、都市の呼びかけにたいし、市民が出資に応じ、鉄や布の会社がつくられ、それを官庁が監督しました。株式の譲渡は認められませんでした。収益のすべては配当金として分配され、積立金などは配慮されなかったといいます。
17世紀になるとオランダとイギリスの東インド会社が動きはじめます。東インド会社は国際的な植民地企業であり、国家が監督して、国内に株を割り当てていました。現在のような株式会社とはかなりちがいますが、国家から特権を与えられた東インド会社の成功は、人びとに株式会社の意義を知らしめました。
株式会社だけではありません。近代においては、国家自体が合理的な経済主体になろうとしていました。
中世の都市は年金証書を発行することで多くの収入を調達していました。当時は秩序ある予算制がなく、各都市は1週間ごとに経済計画を立てるありさま。市の収入の増減ははなはだしく、支出は常に不足がちでした。そのため政治権力は租税請負制度によって税収の見通しを立てるようになります。こうして租税の合理的管理がはじまり、秩序ある財政がつくられるようになっていきます。
16、17世紀になると王侯の独占特許政策が登場します。ハプスブルク家はイドリア(現スロベニア)の水銀坑採掘の特許権を握っていましたし、スチュアート家も国王による独占特許政策を活用しようとしました。だが、イギリスの場合は、国王の専断は早くから議会によって阻止されています。
投資は時に投機につながりました。近代資本主義の歴史が恐慌の歴史でもあったことを、ウェーバーも指摘しています。
1630年代、オランダではチューリップ・バブルが発生しました。しかし、チューリップ恐慌は歴史のちょっとしたエピソードにすぎません。より深刻だったのは、1720年代に発生したフランスの投機恐慌とイギリスの南海泡沫事件です。このふたつとも幻の植民事業計画が関係していました。
フランスの場合は、当時フランスの財務総監を務めていたジョン・ロー(イングランド銀行の創設者のひとりでもある)が、ミシシッピ会社をつくり、北米にあるフランス領ルイジアナ(現在のルイジアナ州とはちがい、五大湖からメキシコ湾にいたる広大な地域)を開発する計画を立てたのが発端でした。だが、それは夢想でしかありませんでした。ミシシッピ会社の証券は暴落し、会社の破産後には、膨大な数の出資者の嘆きが残されました。
イギリスの南海会社も同じ経過をたどります。南海会社は国にたいして巨額の前払いをおこない、南洋における商業の独占権を確保しました。だが、その結果もミシシッピ会社と同じでした。投機によって莫大な財産が費やされ、山師がほくそ笑むだけの結果となりました。
その後も恐慌はなくなりませんでした。1815年、25年、35年、47年にも恐慌はくり返されます(ウェーバー死後の1929年には世界大恐慌が発生します)。「恐慌爆発の原因は、投機過剰の結果、生産そのものではなくむしろ生産手段が、消費財の需要の増加より一そう急速に増加したという事情から生じた」とウェーバーは説明しています。
生産手段が急速に増加したのは、19世紀とともに鉄の時代がはじまったからでもあります。恐慌がなければ社会主義の構想も生まれなかっただろう、とウェーバーは述べています。
マルクスのいうように、社会主義は恐慌を防ぐ手段として有効かもしれない、とウェーバーも認めています。しかし、現実には、不安定な競争の上に成り立つ近代資本主義のダイナミズムのほうが、社会主義の鉄カセのような安定志向を振りきって進むことになります。
資本主義には商品の爆発的浸透が必要でした。そうした資本主義が発達するためには卸売商人の存在が欠かせません。その卸売商人が小売商人から分離したのは18世紀のことだ、とウェーバーはいいます。
貿易商はできるだけ早く外国への支払いをすませるため、商品をオークションにかけました。また逆に外国に輸出するために商品を業者に委託することも求められました。
商品の販売を委託される販売代理商があらわれると、いっぽうでそれを買い入れる買入代理商があらわれます。当初は現物を見ないで見本で買入がおこなわれていました。
取引所の前身は定期的に開かれるメッセ(大市)であり、ここでは商人どうしの取引がおこなわれていました。
近代的な意味での取引所がつくられるのは19世紀になってからです。それ以前にも有価証券や雑種貨幣を扱う取引所はありました。しかし、19世紀になると典型的な商品が取引対象となり、先物取引もはじまります。取引されたのは穀物や植民地の大量商品(砂糖など)で、その後、工業証券にたいする取引が活発になりました。とりわけ鉄道の建設にかかわる鉄道債券が工業証券の人気を引っぱっていきました。
卸売商業が活発になるには通信と交通の発達が欠かせません。
新聞が商業と結びつくようになるのは18世紀末からです。このころから商品の販路を拡張するため、新聞に広告が打たれるようになります。
株式相場が新聞に発表されるようになるのも19世紀になってからで、それまで取引所は閉鎖的なクラブでした。とはいえ、情報がなければ取引は成立しません。それをかつては郵便制度と信書が支えていました。そこに新聞が加わるわけです。
交通についていうと、18世紀には船の数も大きさも増えましたが、大きな変化とはいえませんでした。河川通航は閘門(こうもん)施設によって改良されましたが、根本的な革新にいたりませんでした。陸上交通も同様ですが、道路事情は砂利舗装により大きく改善されました。それでも陸上の荷物運搬には海上や河川にくらべ、より多くの費用がかかりました。
そこに鉄道がでてきます。「鉄道は単に交通といわず、経済一般に対して、歴史の示したもっとも革命的な手段となった」とウェーバーは語っています。いまから100年以上前の1920年のことです。
ここで植民政策が近代資本主義の成立といかにかかわっているかが論じられます。
植民地を獲得することでヨーロッパに大きな富がもたらされたことをウェーバーも認めています。(1)植民地の生産物の独占、(2)植民地への販売の独占、(3)植民地と母国との交通の独占が富の源泉となりました。
植民地の富を確保するためには、例外なく武力を背景にした圧力が用いられました。植民地の管理は、スペインやポルトガルのように直接国家がおこなう場合もあれば、オランダやイギリスのように権限を委譲された会社がおこなう場合もありました。
ウェーバーは前者を封建的類型、後者を資本主義的類型と呼んでいます。
封建的類型の植民地では、土地が封土(スペイン植民地ではエンコミエンダ)として植民者に分配されました。資本主義的植民地では、たいていプランテーションがつくられ、現地住民の労働力が投入されました。アメリカでは当初先住民の活用が考えられましたが、それは失敗に終わり、黒人奴隷が輸入されることになります。
19世紀の初頭、ヨーロッパ人の植民地には約700万人の黒人奴隷が住んでいました。しかし、その死亡率はきわめて高かったのです。そのため1807年から48年にかけ、アフリカからさらに500万人以上の奴隷が輸入されます。
奴隷労働から得られる収益はけっして少なくありませんでした。奴隷たちはプランテーションの規律にもとづき酷使されました。それは、まさに略奪経済だった、とウェーバーはいいます。
それでもウェーバーは論敵のゾンバルトを批判して、植民地商業が近代資本主義の成立にもたらした影響はごくわずかなものだったと断言します。
植民地での搾取形態は、奴隷制度の撤廃とともに終末を迎えます。奴隷制度と戦ったのはクエーカー教徒だけでした。カルヴィン派もカトリックもこの点では何の寄与もしていません。奴隷制撤廃にもっとも大きな力となったのは、北米植民地の独立でした。
1815年のウィーン会議は、奴隷商業の禁止を宣言しました。北米植民地が失われたことで、イギリスは奴隷商業への関心を失います。イギリスで奴隷制が廃止されるのは1833年のこと。それでも1807年から48年までに盛大な密輸入によって、膨大な多くの黒人がアメリカに運ばれていました。
植民地がヨーロッパに大きな富をもたらしたことは否定できません。しかし、近代資本主義が成立したのは、奴隷制のプランテーションによってではなく、あくまでも工業の発達によってだ、とウェーバーは強調します。
近代資本主義の本命が産業にあったことはまちがいありません。
ウェーバーは産業経営の発展を追っています。
工場の特徴は機械化された装置と労働過程の機械化にあるといってよいでしょう。重要なのは、仕事場、装置、動力源、原料が企業家によって専有されていることです。そうした工場の先駆者となったのがイギリスでした。
水力によって運転された最初の工場は、1719年のダーウェント(ダービーシャー)の絹工場です。そのあと1738年に羊毛マニュファクチュアが生まれ、工場での半麻生産がつづき、スタッフォードシャーでの陶器製造、さらに製紙業がはじまります。
機械化にとって画期的だったのは木綿マニュファクチュアの発展です。1769年以降、水力による機械化によって大量の紡績撚糸(ねんし)が生産できるようになりました。加えて1785年にカートライトが力織機を発明したことにより、木綿産業が急速な発展を遂げることになります。
機械化の加速に大きなインパクトを与えたのが石炭と鉄でした。イギリスでも石炭は中世から使用されていました。しかし、それは燃料などの消費目的で、製鉄にはもっぱら木炭が用いられていました。そのため、イギリスでは木の切りすぎにより、山林が荒廃しました。
鉄の利用はそもそも軍事目的のためでした。17世紀に圧延機が登場すると、鉄の用途も広がります。しかし、山林の荒廃が製鉄の拡大を阻んでいました。
それを突破したのが石炭です。1735年にコークスの製造法が開発されます。そして1740年にはじめて溶鉱炉にコークスが使用され、1784年に攪錬法(かくれんほう)が導入されて、製鉄は格段に進歩しました。加えて、蒸気機関が鉱山の排水を容易にしたことから、石炭と鉄鉱の増産も可能になりました。
石炭と鉄は、エネルギーと機械の可能性を切り開きました。蒸気機関による生産過程の機械化は、労働の有機的限界から生産を解放しました。
機械化は常に労働を節約・解放する方向に進みます。しかし、省力化は労働力が不要になったことを意味しない、むしろ逆だ、とウェーバーは考えています。それは労働分野の拡大をともなうからです。
資本主義の進展とともに、人びとは過去の伝統の束縛から解放され、新たな商品が次々とつくられるようになります。ウェーバーによると、労働は「とらわれることなく自由に活動する知性と緊密に結合するにいたった」ということになります。
イギリスではエンクロージャー運動によって、耕地が牧用地に転用され、農村に過剰人口が生じました。しかも、政府の法令は、自発的に就業しない者を禁じていました。こうした労働力を管理していたのが治安判事です。治安判事は有産者層と結びつき、過剰な労働力を「新しく成立した産業に押し込んだ」と、ウェーバーは述べています。
そのいっぽう、工場ではたらく労働者が増えるにつれて、18世紀前半には新たな労働法制が導入されるようになります。労働者への支払いに生産物をあててはならないこと、また労働者には貨幣で労賃が支払わねばならないことが定められたのです。
ゾンバルトがいうように戦争と奢侈が資本主義を推進したことは無視できません。しかし、ウェーバーは、そのことを過大評価してはならないといいます。
軍隊の兵員数増加は、たしかに工業生産を刺激しました。軍服や銃砲、弾丸が繊維産業や製鉄工業の需要を喚起したことはまちがいありません。海軍でも軍艦の巨大化が造船業の発達を促しました。
しかし、軍隊が大衆軍隊となり、それにともない商品の大量需要があらわれたとしても、戦争こそが近代的資本主義の決定的発達条件だったとはいえない、とウェーバーは断言します。もしそうなら国家の官営事業が膨らんで、資本主義はかえって衰退したはずです。そうなっていないのはどうしてか。
このことは奢侈についてもいえます。典型的な奢侈はフランスの宮廷や貴族のあいだでみられました。レース、薄物の下着、長靴下、傘、インディゴ染料、ゴブラン織、磁器、更紗、毛氈、チョコレート、コーヒーなどが消費されて、業者をうるおしました。
こうした奢侈が資本主義の発展に寄与したとすれば、むしろ奢侈品需要の大衆化、とりわけ代用品の製造がなされることによってだ、とウェーバーはいいます。奢侈品もどきが広く行き渡るには、品質を維持するよりも、価格を徐々に引き下げることが効果的なのです。したがって、贅沢品という刺激より、むしろ価格引き下げのなかにこそ資本主義の本質が隠されている、とウェーバーは断言します。
生産費を抑え、価格を引き下げることによって利潤を増やそうというのは近代資本主義特有の考え方であって、こうした考え方が生まれた背景には16、17世紀の価格革命がありました。
このころヨーロッパには中南米から大量の金銀がもたらされ、貨幣価値が下がったことで、物価が全般的に上昇しました。農業生産物の価格が上昇し、そのおかげで農業は市場生産に移行できるようになります。しかし、工業製品の価格上昇は抑えられ、農業生産物と比較すると、むしろ相対的に下落したのです。
つまり、物価が上昇し、工業製品の価格が相対的に下落するなかで、技術と経営の革新がなされ、それが近代資本主義の成立につながっていく、とウェーバーはとらえるのです。
技術と経営の合理化によって、生産費を下げ、価格を引き下げようという動きは、17世紀にはいると、かずかずの発明をもたらしました。
1623年にはイギリスで特許法が制定されました。それにより発明は14年間にかぎって保護され、その後はすべての企業家がこの発明を利用できるようになります。とはいえ、もとの発明者には十分な配当がなされました。
18世紀の繊維工業におけるさまざまな発明は、資本主義の発展に決定的な影響をもたらしました。もし特許法の刺激がなければ、こうした発明は不可能だったろう、とウェーバーは論じています。
商業はいかなる場所、いかなる時代にもありました。しかし、合理的な労働組織、つまり機械装置とともに労働を合理的に組み立てるやり方は西洋でしか生まれなかった、とウェーバーはいいます。
資本主義が自律的に発展するには、市民という概念が必要だった、とウェーバーは考えていました。こうした西洋独特の「市民」はどのようにして生まれたのでしょうか。
市民とは何か。ウェーバーは3つのとらえ方を示します。。
(1)市民階級は統一的な階級ではありません。富裕な市民も貧しい市民も、企業家も手工業者も同じ市民として、特定の経済的利害状況にかかわっています。
(2)政治的意味においては、市民は特定の政治的権利(人権)を有する政治的存在です。
(3)最後に(限定的にいえば)市民とは財産と教養をもつ社会層(とりわけブルジョワジー)を意味します。
市民の3概念は、いずれも西洋に固有の形態で、しかも「市民は、つねに特定の都市の市民」でした。こうした都市は西洋にしか存在せず、都市も市民も西洋特有の形態だ、とウェーバーは断言します。
都市が文化にもたらした影響ははかりしれません。芸術や科学を生みだしたのも都市です。政党を生みだしたのも都市でした。都市は宗教の担い手ともなりました。
経済的観点からみれば、都市は当初、商工業の所在地であり、外部から不断の食料品移入を必要としました。したがって、都市は何らかのかたちで食料品への対価を払わねばなりませんでした。軍事的にみれば、都市はたいていかつての城砦でした。さらに、そこは行政機関の所在地でもありました。
しかし、西洋以外では自治団体としての都市はなかった、とウェーバーはいいます。西洋の都市は古代においては共住、中世においては盟約を基本として発生しました。それは古代アテネや中世のヴェネツィアをみてもわかります。
西洋のポリスのようなものは東洋では生まれませんでした。その理由をウェーバーは、治水を統制する王の権力があまりにも強大だったことと、呪術や禁忌(きんき)の縛りが強かったことに求めています。
ウェーバーは、西洋の古代都市と中世都市の比較を長々とつづけていますが、それは省略します。いずれにしても、重要なのは、西洋においては、たとえ一時的だったにせよ、都市における民主制が確立されたことだといいます。つまり豪族の支配に代えて市民の支配が成立したのです。
もっとも、古代と中世でちがいはあります。
中世の都市において、市民は自由でした。「都市の空気はすべてを自由ならしむ」という原則は、中世の都市にこそあてはまりました。「身分の平等化と、自由の束縛の撤廃とは、中世都市の発展の決定的傾向になった」とウェーバーはいいます。
古代では、事情はこれとは逆で、身分の差や隷属関係があり、多くの奴隷がいました。しかも、民主政治の発展にともなって、都市にはますます奴隷が流れこみ、身分的不平等が拡大していきました。古代民主制とは、戦士ツンフトによる都市国家なのだ、とウェーバーはいいます。「慢性的戦争はギリシアの完全市民にとっては正常の状態であった」。さらに、「戦争は都市を富裕ならしめるに反し、長い平和の時期は市民の到底耐ええないことであった」ともつけ加えています。
古代ギリシアに中世のような手工業者ツンフトが生じなかったのは、古代都市国家の民主制が戦争によって支えられていたためです。古代においては、商人や手工業者は市民として認められませんでした。
近代資本主義の特徴は合理的であることです。いかなる時代においても商人は存在しました。商人は租税を請け負ったり、戦費を融通したり、戦利品を処分したり、高利をとったり、投機をしたりして活動していました。しかし、それはウェーバーにいわせると、あくまでも非合理的資本主義だったのです。
合理的資本主義は市場における、より大量、かつ大衆的な需要をめざして、努力を傾けるものです。だが、古代において、こうした発展は閉ざされており、それがようやく緒についたのは、西洋の中世末期においてだった、とウェーバーはいいます。
つまり、中世の都市こそが、近代資本主義を準備したわけです。その後、国家が台頭することによって、都市の力は衰えていきます。
国家の台頭によって、都市の自治権が奪われていったのは事実です。しかし、その都市を手に入れたのは「互いに覇を競いつつある民族国家」にほかなりませんでした。
ウェーバーは、この「封鎖的民族国家こそが、資本主義に対して、その存続の機会を保証した」のだと述べています。つまり、国民と領土によって規定される封鎖的な「国家」は、他国の攻勢からの生き残りをはからないわけにはいかず、そのために国家は資本と結合したというわけです。その意味で、近代資本主義は近代国家の産物だとウェーバーは考えていました。
ウェーバーは合理的国家という意味での「国家」が存在するのは西洋だけだと述べています。もっともそれは1920年時点の話です。
中国では氏族や商人ギルド、職人ツンフトが根を張っていて、その上に官僚(マンダリン)が薄い覆いのように乗っていました。官僚は教養ある読書人として封土を与えられていますが、行政も法律も知らず、実際の行政は小役人にまかされていました。
西洋の国家はこれとは異なります。専門的官僚と合理的な法律を基礎とする合理的国家だ、とウェーバーは強調します。
首尾一貫した国家の経済政策は、近代になってはじめて登場しました。
西洋でも14世紀までは計画的な経済政策はほとんど見られませんでした。
王侯が合理的な経済政策に着手するのは、14世紀のイギリスからで、いわゆる重商主義と呼ばれます。端的にいうと、対外交易と国内開発によって王の収入を増加させることが、重商主義の最大目的でした。
重商主義政策は国内においては人民の租税負担力を増進させることに向けられました。そのために、王は貨幣が国外に流出するのを防ごうとしました。さらに国内の人口を増やすことをめざしました。
このふたつの目的を達するために、できるだけ多くの商品(原料ではなく完成品)を海外に売ることが奨励されました。しかも、その取引をおこなうのは自国の商人でなければなりません。こうして「一国の輸入額が輸出額を超過すれば、その国はそれだけ貧しくなる」という重商主義のセオリーが生まれます。
イギリスは早くも14世紀末のリチャード2世の時代に、輸入を禁止し輸出を奨励する重商主義政策をとりはじめます。その後、1440年にイギリスにおける外国商人の規制、外国で商売をする自国商人の規制がなされ、重商主義の色彩が強まります。そして1651年の航海条例にいたるまで、重商主義政策が徐々に推し進められていくことになります。
スチュアート朝の重商主義は、国庫収入の増加を主眼としていました。すべての新規産業は国王の独占特許がなければ認められず、王の財政をうるおすことが義務づけられていました。これは身分的独占的重商主義だった、とウェーバーはいいます。
こうした国王の独占経済は清教徒(ピューリタン)革命によって崩れ去ります。そして、重商主義の第二の形態である国民的重商主義が誕生するのです。この政策のもとで、国民的産業が体系的・組織的に保護されることになります。
しかし、重商主義によって保護された産業が生き残ることはありませんでした。残ったのは1694年に設立されたイングランド銀行くらいです。重商主義は自由貿易の台頭とともに滅びました。
西洋に近代資本主義をもたらしたのは、18世紀から19世紀にかけての人口増加が原因でもなければ、16世紀以降の貴金属流入でもない、とウェーバーは断言します。地中海という地理的要因、さらには戦争や奢侈による需要もそれ自体、資本主義を促進したわけではありません。
資本主義を産み出したのは「合理的なる持続的企業、合理的簿記、合理的技術、合理的法律」です。さらにその根源には「合理的精神、生活態度の合理化、合理的なる経済倫理」がある、とウェーバーは強調します。
なぜ西洋においてのみ、このような「合理的精神、生活態度の合理化、合理的なる経済倫理」が生まれたのでしょう。もちろん、合理的精神と倫理は伝統という壁を乗り越えることによって生まれたのです。
伝統を支えるのは伝統主義です。「伝統主義とは、伝統を神聖不可侵視すること、祖先より伝承せる行為および経済行為のみを墨守して、すこしも改めないことを意味するが、人間生活の発端において、つねに支配的なのはこの伝統主義である」と、ウェーバーは伝統主義を規定しています。
伝統は抜きがたく、呪術のように人びとを縛っています。ここから合理的精神が生まれるには、相当の飛躍を必要とします。しかし、中南米を征服したピサロやコルテスに見られるような営利衝動が、合理的な経済倫理を生みだしたわけではない、とウェーバーは断言します。
もともと営利活動は家族や氏族の共同体のなかでは禁じられていました。共同体は肉親的同胞愛で結ばれ、そこでは共産主義的ともいえる対内道徳が支配しており、営利活動がはいりこむ余地がありませんでした。
営利活動がおこなわれたのは、もっぱら共同体の外部にたいしてです。仲間以外の外部との交渉では、信仰や良心の拘束から離れて、営利衝動が無制限に発動されました。
最初の状態はこの二元対立です。それがいつしか勘定と計算の要素が伝統的な共同体の内部に浸透し、共産主義的な共同体を解体していきました。しかし、それと並行して、外部にたいしても(いわば外部の社会化が生じて)営利衝動をある程度抑えた自制的な経済が生まれてきます。
ウェーバーはそんな図式をえがいています。
だが、それにしてもなぜ近代資本主義は西洋においてのみ発展することができたのだろうか、とウェーバーは問います。
キリスト教の教会は、もともと商人の活動は神の思し召しにかなわないという考えをいだいていました。それがようやく緩和されるのは、フィレンツェの勃興によってです。
カトリックとルター派はそれでも営利活動に深刻な嫌悪をいだいていました。人間関係が物化され、倫理が失われるのではないかと恐れていたためです。教会が商人に求めたのは「公正なる価格」にもとづき、人びとの生活が保証されることでした。
こうした教会の経済倫理を打ち破ったのはユダヤ人ではない、とウェーバーはいいます。
中世のユダヤ人は、いわば卑賤(ひせん)なカーストに属する存在でした。ユダヤ人は市民の埒外(らちがい)にあり、いずれの都市の市民団体にも加入できませんでした。土地の取得も禁止されていましたから、農業に従事することもできませんでした。その代わり、ユダヤ人は貨幣取扱業務をいとなむことができたのです。
とはいえ、これは賎民資本主義でした。ユダヤ人は合理的資本主義の成立に何ら貢献していない、とウェーバーは断言します。それでも、ユダヤ教のなかには反呪術的な精神が含まれていたのです。
ユダヤ教の意義は、反呪術性の精神をキリスト教に伝えたところにある、とウェーバーは見ていました。呪術の拘束があるかぎり、近代資本主義の成立は不可能でした。
ここで、ウェーバーは不思議なことをいいます。
「世界を呪術から解放し、したがってまた、近代の科学、技術、および資本主義に対する基礎を創造したものは、実に預言にほかならない」
人びとは預言にしたがいました。その預言は、ユダヤ教とキリスト教によってもたらされた、とウェーバーはいうのです。預言とは未来への約束にほかなりません。ユダヤ教とキリスト教の平民宗教によって、呪術は神聖ならざるもの、悪魔的なものとさげすまれるようになりました。
さらに禁欲の教えがあります。禁欲とは規律正しい生活態度の実行を意味すます。中世の修道僧はそうした禁欲を実践する存在と考えられていました。しかし、一般の人のあいだにこの禁欲精神が行き渡らなかったのは懺悔と贖罪の制度があったからだ、とウェーバーはいいます。
ルターによる宗教改革はこの制度を決定的に打破しました。これにより、信仰にあふれる人びとは、ふだんから僧院におけるのと同様の徳行を積まねばならなくなりました。
「新教の禁欲的宗派は打ってつけの道徳を創定した」とウェーバーは述べています。禁欲思想は独身主義をよしとするのではありません。結婚は合理的に子どもを産み育てるための制度です。貧乏がよいというのではありません。しかし、富の獲得によって思慮のない享楽を求めるのは邪道とされました。
ここから、この世で生きていくには、定められた職業をまっとうし、営利活動をおこなうことこそが神の思し召しにかなっているという考え方が生まれました。
キリスト教精神のもと、善良な良心をもつ企業家が誕生しました。それだけではありません。労働を嫌がらない労働者が供給されるようになった、とウェーバーはいいます。こうして、善良な企業家と献身的な労働者によって、近代資本主義は支えられることになったのです。
しかし、と最後にウェーバーはつけ加えないわけにはいきませんでした。近代資本主義を支えた宗教的根蔕(こんてい)はいまや消え失せてしまった。現代人の職業意識は、もはや禁欲にはほど遠い。私利の追求こそ社会全体の幸福をもたらすという啓蒙的な楽観論(功利主義)が、禁欲的な理念を吹き飛ばしてしまった。19世紀がはじまるとともに、近代資本主義の黎明(れいめい)期は終わり、不断の緊張と対立を強いられる時代がはじまったのだ、と。
いまや資本主義の精神は、プロテスタンティズムに代わって、貪欲な競争とニヒリズムが支配するようになった、とウェーバーはとらえていました。
ウェーバーの死後、さらに高まった資本主義の力は、20世紀の巨大な震源となり、全体主義の防壁を崩壊させ、さらに21世紀の「人新世」をかたちづくろうとしています。それはもはや西洋のものだけではなく、地球全体をおおいつくしています。近代を称揚するだけではなく、近代を反省する時代がはじまっているといえるでしょう。
「日常需要が資本主義的な仕方で充足される」というのは、必要な商品が常に市場に供給され、日常の需要が商品の購入によって充たされることを意味します。ウェーバーはこうした商品世界の広がりを近代資本主義の特徴とするのですが、だとするなら、なぜ16世紀以降、西洋(ヨーロッパ)においてのみ、こうした近代資本主義が定着し、発展していったかが問われなければならないというわけです。
ウェーバーはまず近代資本主義成立の前提は何かと問うています。
かれによると、ひとつは(1)企業家が物的生産手段(土地、装置、機械、道具など)を私有財産として専有しうること。次に(2)市場の自由が存在すること(身分制の束縛がないこと)。さらに(3)合理的な技術、とりわけ機械を手に入れられること。(4)法のもとで経済の自由が認められていること。(5)自己の労働力を市場で自由に売ることができること。(6)ビジネスの商業化、すなわち株式や投資が認められること、などです。
資本主義の発達は企業、とりわけ株式会社の発達をともなってこそ可能でした。
ウェーバーは株式会社にはふたつの出発点があるといいます。
ひとつは、政治権力が収益を先取りしようとして資本を集める場合で、ジェノヴァのサンジョルジョ銀行がそのひとつでした。高利のつく戦時公債が、戦争に勝利したときの戦利品や賠償金(戦利品)を当てにして発行されました。ただし、失敗に終わったときはみじめで、そうした公債は紙くずになります。
もうひとつは商事会社に出資する場合です。15、16世紀には、都市の呼びかけにたいし、市民が出資に応じ、鉄や布の会社がつくられ、それを官庁が監督しました。株式の譲渡は認められませんでした。収益のすべては配当金として分配され、積立金などは配慮されなかったといいます。
17世紀になるとオランダとイギリスの東インド会社が動きはじめます。東インド会社は国際的な植民地企業であり、国家が監督して、国内に株を割り当てていました。現在のような株式会社とはかなりちがいますが、国家から特権を与えられた東インド会社の成功は、人びとに株式会社の意義を知らしめました。
株式会社だけではありません。近代においては、国家自体が合理的な経済主体になろうとしていました。
中世の都市は年金証書を発行することで多くの収入を調達していました。当時は秩序ある予算制がなく、各都市は1週間ごとに経済計画を立てるありさま。市の収入の増減ははなはだしく、支出は常に不足がちでした。そのため政治権力は租税請負制度によって税収の見通しを立てるようになります。こうして租税の合理的管理がはじまり、秩序ある財政がつくられるようになっていきます。
16、17世紀になると王侯の独占特許政策が登場します。ハプスブルク家はイドリア(現スロベニア)の水銀坑採掘の特許権を握っていましたし、スチュアート家も国王による独占特許政策を活用しようとしました。だが、イギリスの場合は、国王の専断は早くから議会によって阻止されています。
投資は時に投機につながりました。近代資本主義の歴史が恐慌の歴史でもあったことを、ウェーバーも指摘しています。
1630年代、オランダではチューリップ・バブルが発生しました。しかし、チューリップ恐慌は歴史のちょっとしたエピソードにすぎません。より深刻だったのは、1720年代に発生したフランスの投機恐慌とイギリスの南海泡沫事件です。このふたつとも幻の植民事業計画が関係していました。
フランスの場合は、当時フランスの財務総監を務めていたジョン・ロー(イングランド銀行の創設者のひとりでもある)が、ミシシッピ会社をつくり、北米にあるフランス領ルイジアナ(現在のルイジアナ州とはちがい、五大湖からメキシコ湾にいたる広大な地域)を開発する計画を立てたのが発端でした。だが、それは夢想でしかありませんでした。ミシシッピ会社の証券は暴落し、会社の破産後には、膨大な数の出資者の嘆きが残されました。
イギリスの南海会社も同じ経過をたどります。南海会社は国にたいして巨額の前払いをおこない、南洋における商業の独占権を確保しました。だが、その結果もミシシッピ会社と同じでした。投機によって莫大な財産が費やされ、山師がほくそ笑むだけの結果となりました。
その後も恐慌はなくなりませんでした。1815年、25年、35年、47年にも恐慌はくり返されます(ウェーバー死後の1929年には世界大恐慌が発生します)。「恐慌爆発の原因は、投機過剰の結果、生産そのものではなくむしろ生産手段が、消費財の需要の増加より一そう急速に増加したという事情から生じた」とウェーバーは説明しています。
生産手段が急速に増加したのは、19世紀とともに鉄の時代がはじまったからでもあります。恐慌がなければ社会主義の構想も生まれなかっただろう、とウェーバーは述べています。
マルクスのいうように、社会主義は恐慌を防ぐ手段として有効かもしれない、とウェーバーも認めています。しかし、現実には、不安定な競争の上に成り立つ近代資本主義のダイナミズムのほうが、社会主義の鉄カセのような安定志向を振りきって進むことになります。
資本主義には商品の爆発的浸透が必要でした。そうした資本主義が発達するためには卸売商人の存在が欠かせません。その卸売商人が小売商人から分離したのは18世紀のことだ、とウェーバーはいいます。
貿易商はできるだけ早く外国への支払いをすませるため、商品をオークションにかけました。また逆に外国に輸出するために商品を業者に委託することも求められました。
商品の販売を委託される販売代理商があらわれると、いっぽうでそれを買い入れる買入代理商があらわれます。当初は現物を見ないで見本で買入がおこなわれていました。
取引所の前身は定期的に開かれるメッセ(大市)であり、ここでは商人どうしの取引がおこなわれていました。
近代的な意味での取引所がつくられるのは19世紀になってからです。それ以前にも有価証券や雑種貨幣を扱う取引所はありました。しかし、19世紀になると典型的な商品が取引対象となり、先物取引もはじまります。取引されたのは穀物や植民地の大量商品(砂糖など)で、その後、工業証券にたいする取引が活発になりました。とりわけ鉄道の建設にかかわる鉄道債券が工業証券の人気を引っぱっていきました。
卸売商業が活発になるには通信と交通の発達が欠かせません。
新聞が商業と結びつくようになるのは18世紀末からです。このころから商品の販路を拡張するため、新聞に広告が打たれるようになります。
株式相場が新聞に発表されるようになるのも19世紀になってからで、それまで取引所は閉鎖的なクラブでした。とはいえ、情報がなければ取引は成立しません。それをかつては郵便制度と信書が支えていました。そこに新聞が加わるわけです。
交通についていうと、18世紀には船の数も大きさも増えましたが、大きな変化とはいえませんでした。河川通航は閘門(こうもん)施設によって改良されましたが、根本的な革新にいたりませんでした。陸上交通も同様ですが、道路事情は砂利舗装により大きく改善されました。それでも陸上の荷物運搬には海上や河川にくらべ、より多くの費用がかかりました。
そこに鉄道がでてきます。「鉄道は単に交通といわず、経済一般に対して、歴史の示したもっとも革命的な手段となった」とウェーバーは語っています。いまから100年以上前の1920年のことです。
ここで植民政策が近代資本主義の成立といかにかかわっているかが論じられます。
植民地を獲得することでヨーロッパに大きな富がもたらされたことをウェーバーも認めています。(1)植民地の生産物の独占、(2)植民地への販売の独占、(3)植民地と母国との交通の独占が富の源泉となりました。
植民地の富を確保するためには、例外なく武力を背景にした圧力が用いられました。植民地の管理は、スペインやポルトガルのように直接国家がおこなう場合もあれば、オランダやイギリスのように権限を委譲された会社がおこなう場合もありました。
ウェーバーは前者を封建的類型、後者を資本主義的類型と呼んでいます。
封建的類型の植民地では、土地が封土(スペイン植民地ではエンコミエンダ)として植民者に分配されました。資本主義的植民地では、たいていプランテーションがつくられ、現地住民の労働力が投入されました。アメリカでは当初先住民の活用が考えられましたが、それは失敗に終わり、黒人奴隷が輸入されることになります。
19世紀の初頭、ヨーロッパ人の植民地には約700万人の黒人奴隷が住んでいました。しかし、その死亡率はきわめて高かったのです。そのため1807年から48年にかけ、アフリカからさらに500万人以上の奴隷が輸入されます。
奴隷労働から得られる収益はけっして少なくありませんでした。奴隷たちはプランテーションの規律にもとづき酷使されました。それは、まさに略奪経済だった、とウェーバーはいいます。
それでもウェーバーは論敵のゾンバルトを批判して、植民地商業が近代資本主義の成立にもたらした影響はごくわずかなものだったと断言します。
植民地での搾取形態は、奴隷制度の撤廃とともに終末を迎えます。奴隷制度と戦ったのはクエーカー教徒だけでした。カルヴィン派もカトリックもこの点では何の寄与もしていません。奴隷制撤廃にもっとも大きな力となったのは、北米植民地の独立でした。
1815年のウィーン会議は、奴隷商業の禁止を宣言しました。北米植民地が失われたことで、イギリスは奴隷商業への関心を失います。イギリスで奴隷制が廃止されるのは1833年のこと。それでも1807年から48年までに盛大な密輸入によって、膨大な多くの黒人がアメリカに運ばれていました。
植民地がヨーロッパに大きな富をもたらしたことは否定できません。しかし、近代資本主義が成立したのは、奴隷制のプランテーションによってではなく、あくまでも工業の発達によってだ、とウェーバーは強調します。
近代資本主義の本命が産業にあったことはまちがいありません。
ウェーバーは産業経営の発展を追っています。
工場の特徴は機械化された装置と労働過程の機械化にあるといってよいでしょう。重要なのは、仕事場、装置、動力源、原料が企業家によって専有されていることです。そうした工場の先駆者となったのがイギリスでした。
水力によって運転された最初の工場は、1719年のダーウェント(ダービーシャー)の絹工場です。そのあと1738年に羊毛マニュファクチュアが生まれ、工場での半麻生産がつづき、スタッフォードシャーでの陶器製造、さらに製紙業がはじまります。
機械化にとって画期的だったのは木綿マニュファクチュアの発展です。1769年以降、水力による機械化によって大量の紡績撚糸(ねんし)が生産できるようになりました。加えて1785年にカートライトが力織機を発明したことにより、木綿産業が急速な発展を遂げることになります。
機械化の加速に大きなインパクトを与えたのが石炭と鉄でした。イギリスでも石炭は中世から使用されていました。しかし、それは燃料などの消費目的で、製鉄にはもっぱら木炭が用いられていました。そのため、イギリスでは木の切りすぎにより、山林が荒廃しました。
鉄の利用はそもそも軍事目的のためでした。17世紀に圧延機が登場すると、鉄の用途も広がります。しかし、山林の荒廃が製鉄の拡大を阻んでいました。
それを突破したのが石炭です。1735年にコークスの製造法が開発されます。そして1740年にはじめて溶鉱炉にコークスが使用され、1784年に攪錬法(かくれんほう)が導入されて、製鉄は格段に進歩しました。加えて、蒸気機関が鉱山の排水を容易にしたことから、石炭と鉄鉱の増産も可能になりました。
石炭と鉄は、エネルギーと機械の可能性を切り開きました。蒸気機関による生産過程の機械化は、労働の有機的限界から生産を解放しました。
機械化は常に労働を節約・解放する方向に進みます。しかし、省力化は労働力が不要になったことを意味しない、むしろ逆だ、とウェーバーは考えています。それは労働分野の拡大をともなうからです。
資本主義の進展とともに、人びとは過去の伝統の束縛から解放され、新たな商品が次々とつくられるようになります。ウェーバーによると、労働は「とらわれることなく自由に活動する知性と緊密に結合するにいたった」ということになります。
イギリスではエンクロージャー運動によって、耕地が牧用地に転用され、農村に過剰人口が生じました。しかも、政府の法令は、自発的に就業しない者を禁じていました。こうした労働力を管理していたのが治安判事です。治安判事は有産者層と結びつき、過剰な労働力を「新しく成立した産業に押し込んだ」と、ウェーバーは述べています。
そのいっぽう、工場ではたらく労働者が増えるにつれて、18世紀前半には新たな労働法制が導入されるようになります。労働者への支払いに生産物をあててはならないこと、また労働者には貨幣で労賃が支払わねばならないことが定められたのです。
ゾンバルトがいうように戦争と奢侈が資本主義を推進したことは無視できません。しかし、ウェーバーは、そのことを過大評価してはならないといいます。
軍隊の兵員数増加は、たしかに工業生産を刺激しました。軍服や銃砲、弾丸が繊維産業や製鉄工業の需要を喚起したことはまちがいありません。海軍でも軍艦の巨大化が造船業の発達を促しました。
しかし、軍隊が大衆軍隊となり、それにともない商品の大量需要があらわれたとしても、戦争こそが近代的資本主義の決定的発達条件だったとはいえない、とウェーバーは断言します。もしそうなら国家の官営事業が膨らんで、資本主義はかえって衰退したはずです。そうなっていないのはどうしてか。
このことは奢侈についてもいえます。典型的な奢侈はフランスの宮廷や貴族のあいだでみられました。レース、薄物の下着、長靴下、傘、インディゴ染料、ゴブラン織、磁器、更紗、毛氈、チョコレート、コーヒーなどが消費されて、業者をうるおしました。
こうした奢侈が資本主義の発展に寄与したとすれば、むしろ奢侈品需要の大衆化、とりわけ代用品の製造がなされることによってだ、とウェーバーはいいます。奢侈品もどきが広く行き渡るには、品質を維持するよりも、価格を徐々に引き下げることが効果的なのです。したがって、贅沢品という刺激より、むしろ価格引き下げのなかにこそ資本主義の本質が隠されている、とウェーバーは断言します。
生産費を抑え、価格を引き下げることによって利潤を増やそうというのは近代資本主義特有の考え方であって、こうした考え方が生まれた背景には16、17世紀の価格革命がありました。
このころヨーロッパには中南米から大量の金銀がもたらされ、貨幣価値が下がったことで、物価が全般的に上昇しました。農業生産物の価格が上昇し、そのおかげで農業は市場生産に移行できるようになります。しかし、工業製品の価格上昇は抑えられ、農業生産物と比較すると、むしろ相対的に下落したのです。
つまり、物価が上昇し、工業製品の価格が相対的に下落するなかで、技術と経営の革新がなされ、それが近代資本主義の成立につながっていく、とウェーバーはとらえるのです。
技術と経営の合理化によって、生産費を下げ、価格を引き下げようという動きは、17世紀にはいると、かずかずの発明をもたらしました。
1623年にはイギリスで特許法が制定されました。それにより発明は14年間にかぎって保護され、その後はすべての企業家がこの発明を利用できるようになります。とはいえ、もとの発明者には十分な配当がなされました。
18世紀の繊維工業におけるさまざまな発明は、資本主義の発展に決定的な影響をもたらしました。もし特許法の刺激がなければ、こうした発明は不可能だったろう、とウェーバーは論じています。
商業はいかなる場所、いかなる時代にもありました。しかし、合理的な労働組織、つまり機械装置とともに労働を合理的に組み立てるやり方は西洋でしか生まれなかった、とウェーバーはいいます。
資本主義が自律的に発展するには、市民という概念が必要だった、とウェーバーは考えていました。こうした西洋独特の「市民」はどのようにして生まれたのでしょうか。
市民とは何か。ウェーバーは3つのとらえ方を示します。。
(1)市民階級は統一的な階級ではありません。富裕な市民も貧しい市民も、企業家も手工業者も同じ市民として、特定の経済的利害状況にかかわっています。
(2)政治的意味においては、市民は特定の政治的権利(人権)を有する政治的存在です。
(3)最後に(限定的にいえば)市民とは財産と教養をもつ社会層(とりわけブルジョワジー)を意味します。
市民の3概念は、いずれも西洋に固有の形態で、しかも「市民は、つねに特定の都市の市民」でした。こうした都市は西洋にしか存在せず、都市も市民も西洋特有の形態だ、とウェーバーは断言します。
都市が文化にもたらした影響ははかりしれません。芸術や科学を生みだしたのも都市です。政党を生みだしたのも都市でした。都市は宗教の担い手ともなりました。
経済的観点からみれば、都市は当初、商工業の所在地であり、外部から不断の食料品移入を必要としました。したがって、都市は何らかのかたちで食料品への対価を払わねばなりませんでした。軍事的にみれば、都市はたいていかつての城砦でした。さらに、そこは行政機関の所在地でもありました。
しかし、西洋以外では自治団体としての都市はなかった、とウェーバーはいいます。西洋の都市は古代においては共住、中世においては盟約を基本として発生しました。それは古代アテネや中世のヴェネツィアをみてもわかります。
西洋のポリスのようなものは東洋では生まれませんでした。その理由をウェーバーは、治水を統制する王の権力があまりにも強大だったことと、呪術や禁忌(きんき)の縛りが強かったことに求めています。
ウェーバーは、西洋の古代都市と中世都市の比較を長々とつづけていますが、それは省略します。いずれにしても、重要なのは、西洋においては、たとえ一時的だったにせよ、都市における民主制が確立されたことだといいます。つまり豪族の支配に代えて市民の支配が成立したのです。
もっとも、古代と中世でちがいはあります。
中世の都市において、市民は自由でした。「都市の空気はすべてを自由ならしむ」という原則は、中世の都市にこそあてはまりました。「身分の平等化と、自由の束縛の撤廃とは、中世都市の発展の決定的傾向になった」とウェーバーはいいます。
古代では、事情はこれとは逆で、身分の差や隷属関係があり、多くの奴隷がいました。しかも、民主政治の発展にともなって、都市にはますます奴隷が流れこみ、身分的不平等が拡大していきました。古代民主制とは、戦士ツンフトによる都市国家なのだ、とウェーバーはいいます。「慢性的戦争はギリシアの完全市民にとっては正常の状態であった」。さらに、「戦争は都市を富裕ならしめるに反し、長い平和の時期は市民の到底耐ええないことであった」ともつけ加えています。
古代ギリシアに中世のような手工業者ツンフトが生じなかったのは、古代都市国家の民主制が戦争によって支えられていたためです。古代においては、商人や手工業者は市民として認められませんでした。
近代資本主義の特徴は合理的であることです。いかなる時代においても商人は存在しました。商人は租税を請け負ったり、戦費を融通したり、戦利品を処分したり、高利をとったり、投機をしたりして活動していました。しかし、それはウェーバーにいわせると、あくまでも非合理的資本主義だったのです。
合理的資本主義は市場における、より大量、かつ大衆的な需要をめざして、努力を傾けるものです。だが、古代において、こうした発展は閉ざされており、それがようやく緒についたのは、西洋の中世末期においてだった、とウェーバーはいいます。
つまり、中世の都市こそが、近代資本主義を準備したわけです。その後、国家が台頭することによって、都市の力は衰えていきます。
国家の台頭によって、都市の自治権が奪われていったのは事実です。しかし、その都市を手に入れたのは「互いに覇を競いつつある民族国家」にほかなりませんでした。
ウェーバーは、この「封鎖的民族国家こそが、資本主義に対して、その存続の機会を保証した」のだと述べています。つまり、国民と領土によって規定される封鎖的な「国家」は、他国の攻勢からの生き残りをはからないわけにはいかず、そのために国家は資本と結合したというわけです。その意味で、近代資本主義は近代国家の産物だとウェーバーは考えていました。
ウェーバーは合理的国家という意味での「国家」が存在するのは西洋だけだと述べています。もっともそれは1920年時点の話です。
中国では氏族や商人ギルド、職人ツンフトが根を張っていて、その上に官僚(マンダリン)が薄い覆いのように乗っていました。官僚は教養ある読書人として封土を与えられていますが、行政も法律も知らず、実際の行政は小役人にまかされていました。
西洋の国家はこれとは異なります。専門的官僚と合理的な法律を基礎とする合理的国家だ、とウェーバーは強調します。
首尾一貫した国家の経済政策は、近代になってはじめて登場しました。
西洋でも14世紀までは計画的な経済政策はほとんど見られませんでした。
王侯が合理的な経済政策に着手するのは、14世紀のイギリスからで、いわゆる重商主義と呼ばれます。端的にいうと、対外交易と国内開発によって王の収入を増加させることが、重商主義の最大目的でした。
重商主義政策は国内においては人民の租税負担力を増進させることに向けられました。そのために、王は貨幣が国外に流出するのを防ごうとしました。さらに国内の人口を増やすことをめざしました。
このふたつの目的を達するために、できるだけ多くの商品(原料ではなく完成品)を海外に売ることが奨励されました。しかも、その取引をおこなうのは自国の商人でなければなりません。こうして「一国の輸入額が輸出額を超過すれば、その国はそれだけ貧しくなる」という重商主義のセオリーが生まれます。
イギリスは早くも14世紀末のリチャード2世の時代に、輸入を禁止し輸出を奨励する重商主義政策をとりはじめます。その後、1440年にイギリスにおける外国商人の規制、外国で商売をする自国商人の規制がなされ、重商主義の色彩が強まります。そして1651年の航海条例にいたるまで、重商主義政策が徐々に推し進められていくことになります。
スチュアート朝の重商主義は、国庫収入の増加を主眼としていました。すべての新規産業は国王の独占特許がなければ認められず、王の財政をうるおすことが義務づけられていました。これは身分的独占的重商主義だった、とウェーバーはいいます。
こうした国王の独占経済は清教徒(ピューリタン)革命によって崩れ去ります。そして、重商主義の第二の形態である国民的重商主義が誕生するのです。この政策のもとで、国民的産業が体系的・組織的に保護されることになります。
しかし、重商主義によって保護された産業が生き残ることはありませんでした。残ったのは1694年に設立されたイングランド銀行くらいです。重商主義は自由貿易の台頭とともに滅びました。
西洋に近代資本主義をもたらしたのは、18世紀から19世紀にかけての人口増加が原因でもなければ、16世紀以降の貴金属流入でもない、とウェーバーは断言します。地中海という地理的要因、さらには戦争や奢侈による需要もそれ自体、資本主義を促進したわけではありません。
資本主義を産み出したのは「合理的なる持続的企業、合理的簿記、合理的技術、合理的法律」です。さらにその根源には「合理的精神、生活態度の合理化、合理的なる経済倫理」がある、とウェーバーは強調します。
なぜ西洋においてのみ、このような「合理的精神、生活態度の合理化、合理的なる経済倫理」が生まれたのでしょう。もちろん、合理的精神と倫理は伝統という壁を乗り越えることによって生まれたのです。
伝統を支えるのは伝統主義です。「伝統主義とは、伝統を神聖不可侵視すること、祖先より伝承せる行為および経済行為のみを墨守して、すこしも改めないことを意味するが、人間生活の発端において、つねに支配的なのはこの伝統主義である」と、ウェーバーは伝統主義を規定しています。
伝統は抜きがたく、呪術のように人びとを縛っています。ここから合理的精神が生まれるには、相当の飛躍を必要とします。しかし、中南米を征服したピサロやコルテスに見られるような営利衝動が、合理的な経済倫理を生みだしたわけではない、とウェーバーは断言します。
もともと営利活動は家族や氏族の共同体のなかでは禁じられていました。共同体は肉親的同胞愛で結ばれ、そこでは共産主義的ともいえる対内道徳が支配しており、営利活動がはいりこむ余地がありませんでした。
営利活動がおこなわれたのは、もっぱら共同体の外部にたいしてです。仲間以外の外部との交渉では、信仰や良心の拘束から離れて、営利衝動が無制限に発動されました。
最初の状態はこの二元対立です。それがいつしか勘定と計算の要素が伝統的な共同体の内部に浸透し、共産主義的な共同体を解体していきました。しかし、それと並行して、外部にたいしても(いわば外部の社会化が生じて)営利衝動をある程度抑えた自制的な経済が生まれてきます。
ウェーバーはそんな図式をえがいています。
だが、それにしてもなぜ近代資本主義は西洋においてのみ発展することができたのだろうか、とウェーバーは問います。
キリスト教の教会は、もともと商人の活動は神の思し召しにかなわないという考えをいだいていました。それがようやく緩和されるのは、フィレンツェの勃興によってです。
カトリックとルター派はそれでも営利活動に深刻な嫌悪をいだいていました。人間関係が物化され、倫理が失われるのではないかと恐れていたためです。教会が商人に求めたのは「公正なる価格」にもとづき、人びとの生活が保証されることでした。
こうした教会の経済倫理を打ち破ったのはユダヤ人ではない、とウェーバーはいいます。
中世のユダヤ人は、いわば卑賤(ひせん)なカーストに属する存在でした。ユダヤ人は市民の埒外(らちがい)にあり、いずれの都市の市民団体にも加入できませんでした。土地の取得も禁止されていましたから、農業に従事することもできませんでした。その代わり、ユダヤ人は貨幣取扱業務をいとなむことができたのです。
とはいえ、これは賎民資本主義でした。ユダヤ人は合理的資本主義の成立に何ら貢献していない、とウェーバーは断言します。それでも、ユダヤ教のなかには反呪術的な精神が含まれていたのです。
ユダヤ教の意義は、反呪術性の精神をキリスト教に伝えたところにある、とウェーバーは見ていました。呪術の拘束があるかぎり、近代資本主義の成立は不可能でした。
ここで、ウェーバーは不思議なことをいいます。
「世界を呪術から解放し、したがってまた、近代の科学、技術、および資本主義に対する基礎を創造したものは、実に預言にほかならない」
人びとは預言にしたがいました。その預言は、ユダヤ教とキリスト教によってもたらされた、とウェーバーはいうのです。預言とは未来への約束にほかなりません。ユダヤ教とキリスト教の平民宗教によって、呪術は神聖ならざるもの、悪魔的なものとさげすまれるようになりました。
さらに禁欲の教えがあります。禁欲とは規律正しい生活態度の実行を意味すます。中世の修道僧はそうした禁欲を実践する存在と考えられていました。しかし、一般の人のあいだにこの禁欲精神が行き渡らなかったのは懺悔と贖罪の制度があったからだ、とウェーバーはいいます。
ルターによる宗教改革はこの制度を決定的に打破しました。これにより、信仰にあふれる人びとは、ふだんから僧院におけるのと同様の徳行を積まねばならなくなりました。
「新教の禁欲的宗派は打ってつけの道徳を創定した」とウェーバーは述べています。禁欲思想は独身主義をよしとするのではありません。結婚は合理的に子どもを産み育てるための制度です。貧乏がよいというのではありません。しかし、富の獲得によって思慮のない享楽を求めるのは邪道とされました。
ここから、この世で生きていくには、定められた職業をまっとうし、営利活動をおこなうことこそが神の思し召しにかなっているという考え方が生まれました。
キリスト教精神のもと、善良な良心をもつ企業家が誕生しました。それだけではありません。労働を嫌がらない労働者が供給されるようになった、とウェーバーはいいます。こうして、善良な企業家と献身的な労働者によって、近代資本主義は支えられることになったのです。
しかし、と最後にウェーバーはつけ加えないわけにはいきませんでした。近代資本主義を支えた宗教的根蔕(こんてい)はいまや消え失せてしまった。現代人の職業意識は、もはや禁欲にはほど遠い。私利の追求こそ社会全体の幸福をもたらすという啓蒙的な楽観論(功利主義)が、禁欲的な理念を吹き飛ばしてしまった。19世紀がはじまるとともに、近代資本主義の黎明(れいめい)期は終わり、不断の緊張と対立を強いられる時代がはじまったのだ、と。
いまや資本主義の精神は、プロテスタンティズムに代わって、貪欲な競争とニヒリズムが支配するようになった、とウェーバーはとらえていました。
ウェーバーの死後、さらに高まった資本主義の力は、20世紀の巨大な震源となり、全体主義の防壁を崩壊させ、さらに21世紀の「人新世」をかたちづくろうとしています。それはもはや西洋のものだけではなく、地球全体をおおいつくしています。近代を称揚するだけではなく、近代を反省する時代がはじまっているといえるでしょう。
ウェーバーの社会経済史(2)──商品世界ファイル(27) [商品世界ファイル]
資本主義以前の農耕中心社会であっても、農耕以外の経済活動がなかったわけではありません。産業(工鉱業)、交易(商業)、それを支える貨幣(金融)は、農耕社会と並行して、古代国家、古代帝国の時代から存在しました。ウェーバーはそうした経済活動が大きな川の流れになって、いかに近代資本主義の導き手になっていたかを論じています。
産業とは原材料を加工して有益な財をつくる作業をいいます。その作業によってつくられたものが産業製品です。
農奴が荘園領主のためにはたらいたり、インドの農民が村のためにはたらいたりすると、かれらは領主や村落から実物ないし貨幣での給付を受けます。
女性はもともと耕作奴婢だった、とウェーバーはいいます。料理や機織りも女性の仕事でした。これにたいし、戦争や狩猟、家畜の飼育に従事する男たちは、金属品や革なめし、肉の調理を担当していました。家の普請や舟の建造なども、村じゅうの男たちの仕事でした。最古の職業は呪医で、鍛冶屋も呪術のようにみられていました。
熟練の手仕事は当初、首長や荘園領主の家計のもとでおこなわれます。最終的にそれは市場をめざすようになるとしても、その中間段階として他人の注文に応じて仕事をする手工業者が生まれます。手工業者はみずから原料と労働手段を持っている場合もあるし、原料と労働手段のどちらか、とりわけ原料を注文者から支給される場合もあります。
労働場所は自分の家である場合も、家の外である場合(たとえば仕事場や工場など)もあります。労働手段は道具から設備まで、さまざまです。設備を所有するのは村であったり、修道院であったり、領主であったりします。
産業の発展については、まず部族産業というカテゴリーが想定できます。この場合は部族が特定の原料、あるいは技能を独占しており、ここから何らかの製品(商品)が生まれ、部族外にも売られることになります。
市場のための専業化は職業分化を生じさせます。村落または領主が他部族出身の手工業者を呼び入れて働かせるときには、その生活の面倒を村落や領主がみなければならなりません。ウェーバーはこれをデミウルギーと呼んでいますが、この場合は自己需要のための生産がおこなわれるにすぎません。
これがさらに進むと、市場のための生産がおこなわれるようになります。もともと村落や領主の需要をまかなうための生産が、次第に市場に向けられるようになるわけです。
古代において、貴族は大所有地で働く奴隷のなかに手工業者をかかえていました。かれらは鍛冶や製鉄、建築、車両整備、衣服づくり、製粉、パン焼き、料理のために働いていました。エジプトやメソポタミアでは、王に隷属し、みごとな芸術品をつくる労働者もいました。
こうした状態から、顧客生産や市場生産に移るためには、何よりも交換経済がある程度発達し、一定の顧客が存在しなければなりません。
最初の現象は、貴族(領主)の奴隷がつくった織物や陶磁器が市場に流出するケースです。次に、領主や大地主が積極的に企業経営に乗りだす場合があります。古代ローマ時代のある大地主は、副業として、製瓦業や砂石採掘業を営んでいました。奴隷女を仕事場に集めて、紡績の仕事をさせていた者もいます。中世の修道院は醸造所や晒布場、蒸留所などを営んでいました。
いっぽう都市では、商人が出資して企業をつくり、労働者を集め、仕事をさせるようになりました。古代ローマでは、貴族がエルガステリオン(作業所)に奴隷を集め、武器や高級品を製造させていたケースもあります。奴隷を確保するのは難事で、奴隷による大規模経営はめずらしい例外でした。
奴隷制にもとづく古代企業は、不特定な市場ではなく、かぎられた狭い市場を対象としていました。
古代ギリシア人は美術品を除き、ごくささやかなものしか所有していません。古代ローマでもベッドは贅沢品で、人びとはマントにくるまって地べたで寝ていました。これにたいし、中世の都市貴族は多くの実用的な家具をもつようになります。北ヨーロッパでは、10世紀から12世紀にかけ、古代の帝国にくらべ、はるかに広範囲な購買力あるいは買い手が存在したのです。
市場が拡大したのは中世の10世紀ごろからで、農民の購買力が増えたのが大きな要因でした。農民の隷属関係は次第にやわらぎ、いっぽうで農業の集約度は進歩していました。こうした背景のもとで、手工業が興隆します。
12世紀、13世紀になると、王侯によって多くの都市がつくられ、都市の時代がはじまります。皇帝が都市に特権を与えたため、貴族や商人、隷農、熟練手工業者などが都市に集まってきました。その後、帝国の力が衰えるとともに、都市の独立傾向、自治的傾向が強まっていきます。
都市に定住した手工業者は、土地を所有する完全市民ではなく、都市の内外に住む領主や後見人(ムントマン)に賃租を支払わなくてはなりませんでした。また、都市の外には、独特の手工業者秩序をもつフローンホーフ(荘園)も存在しました。
自由手工業者は道具をもっていますが、固定資本(設備)をもっていません。一般に顧客の注文に応じてはたらく生産者でした。かれらが賃仕事にとどまるか、つくった製品を売って生活する仕事人になるかどうかは、市場の状況によってことなっていました。賃仕事は富裕な階級のために働くところに成立します。これにたいし、つくった製品を売る仕事(価格仕事)が成立するのは、多くの民衆を相手とする場合でした。
多数の民衆の購買力は、価格仕事が成立する前提であり、これがのちに資本主義成立の前提となっていきます。しかし、だいたいにおいて古代でも中世でも、手工業者は賃仕事が多かった、とウェーバーは指摘しています。
手工業者が職業別に結合するとツンフト(職人ギルド)が結成されます。ツンフトが本格的に誕生するのは、ヨーロッパ中世においてです。
ツンフトは仲間の経済機会を均等にするよう努め、そのためにさまざまな規制が設けられました。一人の親方が突出した資本をもつことは禁止され、労働も伝統に沿っておこなわれねばならず、労働者(徒弟)の数も統制されました。
ツンフトは製品ごとにこまかく設けられ、価格は公定され、ひとつのツンフトが別のツンフトの領分を侵すことは禁止されていました。
ツンフトは対外的には純粋な独占政策を発揮しました。仲間どうしの違反には厳しく目を光らせ、ツンフトが絶対的権力を有する地域内においては、ほかの手工業を認めませんでした。ツンフトにおいては、同一労働者がはじめからおわりまで完成品を生産することになっており、それによってツンフト内部で大経営が発生しないよう配慮されていました。
だが、ツンフトは次第に壁にぶつかるようになります。
ツンフトは都市という地盤のうえに成り立っていました。中世都市の住民は、さまざまな身分をもつ人の寄せ集めで、その大多数は自由な経歴をもっていませんでした。手工業者のうちで市民と認められている人はごくわずかだったのです。
都市領主はツンフトの代表を任命し、ツンフトの経営にまで干渉しようとしました。しかし、かれらはそうした都市領主と闘い、みずからツンフトの代表者を選ぶとともに、都市領主の干渉をはねのけました。不当な賦役や租税、賃借料とも闘いました。ツンフトはこうした闘いに勝利を収めます。だが、その結果、多くの敵をもつことになりました。
ツンフトの反対者は、まず消費者でした。ツンフトの市場独占と独占価格に対抗するため、都市当局は自由親方を任命したり、市営の肉の販売所やパン焼き窯を設置したりして、ツンフトに対抗しました。
ツンフトには別の競争者もいました。荘園や修道院の手工業者です。とりわけ修道院はツンフトに競争をいどみました。さらに、商人と結びついた田舎の手工業者の存在も無視できなくなってきます。
ツンフトと労働者との関係もあやしくなってきます。ツンフトが職人の数を制限したり、親方による統制が厳しくなるいっぽうだったからです。ツンフトは小売商人とも対立しました。小売商人にとっては、公定価格を崩さないツンフトは商売の妨げにほかなりませんでした。
ツンフトは次第に市場の力に圧倒されていきます。
ツンフトの親方が商人または問屋となって、原料を買い入れ、これを他のツンフトに配分し、全生産過程を統合して製品を売るようになることも考えられました。この場合、ツンフトはカンパニーに転化し、いわば商人ツンフトが生まれたことになります。
原料が高価で、その輸入に巨額の資本を必要とする場合、ツンフトは輸入業者(たとえばフッガー家)に依存しないわけにはいきませんでした。そうした高級原料としては琥珀(こはく)や絹などがあり、初期の木綿もそのひとつでした。輸入原料だけではありません。ツンフトは国外に製品を売る場合は輸出業者に頼らざるをえませんでした。
ツンフトに代わって市場の支配力を発揮するのが問屋です。
問屋制度を促したのは繊維工業だ、とウェーバーはいいます。ヨーロッパでは11世紀以来、羊毛と麻の戦いがあり、17、18世紀には羊毛と木綿の戦いがあって、けっきょく木綿が勝利を収めます。
中世都市の繁栄を支えたのは羊毛産業でした。フィレンツェでは羊毛職人のツンフトが大きな政治勢力となっており、その背後にはすでに問屋の存在がみられました。パリの羊毛問屋はシャンパーニュの大市のための仕事をしていました。
フランドルでもイギリスでも問屋制度が発達します。イギリスはもともと粗製の羊毛を輸出していましたが、13、14世紀には未染色の半製品、そしてついに完成品の輸出をおこなうようになります。
問屋制度の発達によって、ツンフトは次第に影響力を失っていきます。職人は問屋のために直接労働する家内工業的小親方に転じていきました。
ウェーバーによると、問屋制度は次のような段階をへて発展していきました。すなわち(1)手工業者からの買い入れ独占、(2)原料の配給、(3)生産過程の管理、(4)道具の配給、(5)生産過程の結合。
問屋制度が長く持続した理由を、ウェーバーは産業革命以前の時代は、固定資本の割合が少なかったことに求めています。このことは、問屋制度が広範な家内工業に依存していたことを意味していました。
だが、まもなく工場が誕生します。
家庭から分離された仕事場生産は昔から存在しました。荘園や組合が仕事場をつくることもあり、それが大規模な仕事場になることもありました。マニュファクチュアは多くの労働者を一カ所に集めて、規律をもって労働させる制度です。工場では企業家が固定資本(設備)と労働力を投入し、異質結合的に協働がおこなわれます。
工場成立の前提条件は、大量かつ継続的な販路が存在することで、そのためには市場の安定と貨幣の購買力が求められます。工場は家内工業や問屋制度でつくられるものよりも、より安価に商品を供給しなければなりません。
工場での生産には豊富な原料と固定資本(設備)、それに多くの自由な労働力が欠かせませんでした。イギリスで自由な労働力が得られたのは、農民からの土地収奪がなされ、農村人口がプロレタリア化したためでした。
近代以前においても、設備を必要とする仕事場がありました。たとえば製粉所や製材所、搾油所、晒布所、パン焼竈、醸造所、鋳造所、鍛鉄場などで、これらは王侯、荘園領主、都市貴族、あるいは市民によって営まれていました。
16世紀のイギリスのある繊維工場は工場の走りですが、そこには200の織機が据え付けられていて、職工たちは賃金をもらうため機械の前で働いていました。少年が補助的に働く姿もみられました。だが、手工業者の訴えにより、1555年に国王はこの工場を禁止しています。当時はまだ問屋制手工業者の影響が強かったのです。
工場に新しい進展がみられるようになるのは、17、18世紀になってからです。近代的分業と同時に、人間以外の動力源が用いられるようになりました。最初は馬力起重機、ついで水や風が利用されます。風を利用した代表はオランダの風車で、水は採鉱業でも欠かせませんでした。
工場の先駆者は中世の王侯の貨幣鋳造所だった、とウェーバーはいいます。武器、さらに軍隊の被服や火薬を製造するためにも秘密を保持する工場が必要とされました。
需要という点で確実なものとしては奢侈的需要がありました。ゴブラン織や敷物、金の器や陶器、窓硝子、ビロード、絹、石鹸、砂糖など、上層階級の需要を満たすため、特別の設備をもつ工場がつくられます。しかし、こうした市場はほぼ貴族階級にかぎられていたのです。
フランスではフランソワ1世(在位1515〜47)が武器や壁紙などの王立工場をつくっていました。イギリスではツンフトが都市を制していたため、工場は地方に建設する以外にありませんでした。
ドイツで最初に工場がつくられたのは16世紀のチューリヒ(現スイス)で、ユグノーの亡命者が絹と緞子(どんす)を製造し、それがたちまちドイツの諸都市に普及しました。16世紀から17世紀にかけ、アウグスブルクでは砂糖や緞子、ニュルンベルクでは石鹸、アンナベルクでは染色、ザクセンでは織物、ハレとマクデブルクでは針金の工場が誕生し、18世紀には王侯直営の陶器工場がつくられています。
ウェーバーは工場は手工業から発生したわけではないといいます。工場でつくられたのは、木綿、陶器、緞子など、新しい生産方式を必要とする新しい生産物でした。
同様に工場は問屋制度から生まれたものでもありませんでした。工場において重要なのは固定資本という要素です。その意味では、工場はむしろ荘園領主の設備を継承したものといえます。機械は工場に先行したわけではなく、工場が蒸気と機械の発展を促したという見方をウェーバーはとっています。
近代的工場の成立は企業家と労働者に重大な影響をもたらしました。企業家はいまや市場のための生産に責任を負うことになりました。労働者もまた自由な労働者として、企業と労働契約を結んで、仕事をするようになります。
だが、こうした工場制度が成立したのは、ヨーロッパの一部に限られていました。工場が誕生することができたのは、機械化という刺激があったからだ、とウェーバーはいいます。そして、その機械化の推進力となったのは、鉱山業の発展にほかならなりませんでした。石炭と鉄の時代がはじまるのです。
商業もはるか古代から存在しました。商業(交易)はことなる共同体間の取引として発生する、とウェーバーは述べています。共同体間で生産が分化する結果、商業が発生します。
古代オリエントでは、権力者どうしがたがいに贈り物をしてよしみを通じていました。ふつうは黄金や戦車ですが、馬や奴隷が贈られることもありました。
エジプトのファラオは自身が船主として、交易事業を営んでいました。インドでは、商人(バニヤン)階級はカーストに位置づけられていました。いかなる生き物も殺すことを禁じられているジャイナ教徒は、宝石や貴金属を扱う商人となりました。土地所有を禁じられているユダヤ人が商業、とりわけ金融業に向かったのも、宗教的な理由からです。
中世には領主商業があらわれます。領主は荘園の余剰生産物を市場で売るため、職業的商人を手代として雇いました。王侯が他人種の商人に保護を与え、その代償として手数料を徴収する習慣も存在しました。
ヴェネツィアの首長(ドージェ)たちも船主でした。ハプスブルク家も18世紀までみずから交易事業を直営しています。しかし、次第に、王たちが商人に商業を特許したり、請け負わせたりして、その成果の一部を受けとることが多くなります。
独立した商人層が生まれる前提としては、交通手段が確立されていなければなりません。陸上では13世紀ころまで、商人は自分の背に商品を担いだり、ロバやラバなどに二輪車をひかせたりして荷物を運んでいました。馬は最初、戦争にしか用いられず、運送手段として用いられるようになったのは、わりあい新しい時代にはいってからです。
いっぽう船の発達には長い時間を要しました。最初は昼間の沿岸航海しかできませんでした。やがてアラブ人がモンスーンを利用して、インドへの遠洋航海をころろみます。しかし、すでに中国人は3、4世紀に羅針盤を利用しており、ヨーロッパ人がそれを採用するのははるかあとのことです。羅針盤の導入は航海に決定的な影響をもたらしました。
帆は船のスピードアップに貢献しました。それでも古代においては、ジブラルタル─オスティア(ローマの外港)間、メッシナ─アレクサンドリア間はそれぞれ8〜10日の日数を要しました。帆船航海術の完成は16、17世紀のイギリスを待たなければなりません。
古代、船の動力には奴隷が漕ぎ手として用いられていました。船主は商人で、ギリシアのポリスにはエンポロスと呼ばれる船乗り商人がいました。ローマでは国が船舶の徴用と穀物の配給を仕切っていました。しかし、ローマでは船による運送は発達せず、軍船も衰退して、海賊が横行することになります。
古代や中世でも船荷に関する決まりが設けられていました。遭難によって船荷を捨てざるをえないときには、関係者が共同でその損害を負担することになっていました。海上貸付には高い利子が発生しました。
中世の海上商業は、古代とちがい組合によって営まれるようになります。商人たちは仲間組合を結成し、船長を雇って共同で船荷を運搬し、共同で危険を分担しました。資本家による海上貸付もあって、行商人たちはこの方式をよく利用したといいます。
行きの船には海外で売られる商品が積まれ、それに商人が同道する場合もあれば、別の商人に販売をゆだねる場合もありました。そこで生じた利益はその都度分配されました。
近世を尺度とすれば、中世の海上商業の取引高はきわめてわずかなものでした。航海の期間も長かったため、資本の回転もきわめて緩慢でした。海賊に襲われる危険もありました。それでも、地中海やバルト海では、それなりの規模の取引がおこなわれていました。
海上にくらべると陸上の危険は少なかったといえます。その代わり運賃は比較にならぬくらい高くなりました。陸上商業でも13世紀までは商人が商品についていくのがふつうでした。その後は、運搬人が荷物に責任をもつようになります。
問題は道路事情でした。古代ローマの道路は、あくまでも首都への食糧供給と政治的・軍事的目的のためでした。中世の荘園領主は農民たちに道路や橋梁(きょうりょう)の建設・維持を課し、めいめい勝手に道路をつくるようになります。
中世では海上にくらべ陸上の取引はずっと少なく、加えて、運送に時間がかかりました。アジアや中東では、隊商が荷物の運搬を引き受けていました。
人びとが個人的に旅行ができるようになったのは、14、15世紀になってからです。当初は荘園領主が農家に馬や馬車を貸しつけて運送をやらせていました。そこから次第に独立した運送業者が生まれ、運送業者のツンフトが結成されることになります。
中世は河川の舟航が盛んでした。領地内の運輸独占権をもっていた領主や大司教は、この権利を船乗りたちにゆだねました。しかし、しだいに船乗りたちは団体を結成し、河川通行権をにぎるようになります。ツンフトや都市の自治団体が船を所有して、この権利を行使する場合もありました。
商人は身分の保証を求めました。最初に求めたのは首長の保護です。つぎに法的な保護が求められました。商人の数が増えるにつれてハンザ(団体)が結成されます。都市には外来商人のための居留地がつくられました。
最後に商品を取引できる市場が必要になってきます。エジプトやインド、ヨーロッパでも、もともと市場は外来商人のために、王の特許により創設されました。市場ではさまざまな決まりが設けられ、手数料や市場税がかけられ、王はこれによって利益を得ていました。
定住商人は都市発展の産物だ、とウェーバーはいいます。定住商人の起源は行商人です。かれらは周期的に旅行し、地方で生産物を売ったり買ったりしていました。つぎに、かれらは使用人に地方を回らせて産物を集めるようになり、さらに地方に支店を設けて、使用人を常駐させるようになります。そして、自身は都市の定住商人となるわけです。こうした状況が可能になったのは中世末期です。
定住商人が闘ったのは、まずユダヤ人や他国の商人、田舎の商人などのような外部的存在で、かれらを市場から排除しようとしました。そして、内部においては、仲間のひとりが突出しないよう機会の均等を求め、さまざまな規制を設けました。営業活動の範囲や消費者の囲い込みをめぐっては争いが生じました。
ウェーバーは各地の商人の集まりとしてメッセ(見本市)の存在を挙げている。その代表がシャンパーニュの大市でした。シャンパーニュでは4つの町で6つのメッセが、それぞれ年に50日間開かれていました。
ここで取引された最大の商品はイギリスやフランドルの羊毛と羊毛製品です。イタリアなどからは香料、染料、臘、サフラン、樟脳、漆などがもたらされました。シャンパーニュには世界中の貨幣が集まり、為替や手形の決済がおこなわれています。
合理的な商業には計算技術が欠かせません。位取り計算法はインドで発明され、アラブ人がこれを発展させ、ユダヤ人がヨーロッパに伝えました。ヨーロッパで計算法が普及したのは十字軍の時代になってからだといいます。そして、中世のイタリアで簿記がつくられました。
ウェーバーによれば、簿記の必要性が高まったのは、家族的な経営体である商家が非家族的な経営体を形成することになってからだといいます。フッガー家でもメディチ家でも、当初は家計と経営は未分離でした。だが、しだいに家計の計算と営業上の計算が分離されるようになります。こうした現象は西洋においてしか生ぜず、それが初期資本主義の発展に決定的な影響をもたらした、とウェーバーは指摘しています。
だが、その前に商人ギルド(商人組合)について論じなくてはなりません。ギルドには外来商人のギルドと定住商人のギルドがあります。
外来商人のギルドとしては、ハンザ同盟が何といっても有名です。ハンザ同盟はバルト海沿岸の商業を掌握しました。
定住商人ギルドとしてウェーバーが挙げるのが、上海の茶商組合や広東の公行ギルドです。かれらはすべての海外貿易を独占していました。インドでは、ジャイナ教徒が定住商業に従事し、ゾロアスター教徒は卸売商業や遠隔地交易を営んでいました。
西洋のギルドの特徴は、政治権力から特権を与えられていることにあります。都市ギルドは経済問題に関して都市を管轄する商人組合となりました。イギリスには国王の租税を請け負うギルドがあったといいます。
西洋のギルドの歴史は実に多様で、イギリス、イタリア、ドイツをみても、その発展はそれぞれ異なります。
北ドイツでは、ギルドの支配するハンザ都市の同盟、すなわちハンザ同盟が結成されました。その中心都市はリューベック、ハンブルク、ブレーメンなどです。ハンザ同盟は14世紀に最盛を誇り、バルト海地域の交易を担いました。
ウェーバーによると、ハンザ同盟の商業上の特権にあずかったのは、ハンザ都市の市民だけだったといいます。利用できるのは組合所有の船だけで、貨幣取引はせず、商品取引のみをおこないました。
ハンザ同盟は各地に商館や倉庫をおいて、商品ネットワークを築き、その取引を厳格な統制下におきました。同盟内では度量衡が統一され、商品の規格化もなされました。蝋や塩、金属、布地をはじめとして多くの商品が取引されていました。
同盟は軍隊をもたず、強い関税政策ももちませんでした。政治的には緩やかな統一体です。加盟各都市では、商人貴族政治の確保が目指されていました。
15世紀になるとハンザ同盟は衰えはじめます。しかし、資本主義前段階の商業の発達を語るうえで、ハンザ同盟は避けて通れないテーマだ、とウェーバーは考えています。
最後に、近代資本主義以前の貨幣と銀行に触れておきましょう。
貨幣には支払手段と交換手段という機能があります。しかし、歴史的には貨幣はまず支払手段として登場した、とウェーバーは指摘します。
交換がなくても支払いは発生します。たとえば貢ぎ物、首長からの贈与、結納、持参金、贖罪金、罰金など、支払いは常に必要になってきます。さらに領主が家臣に支払う給与、指揮官が傭兵に渡す支払いなども欠かせません。ペルシア帝国でもカルタゴでも、貨幣は軍事上の支払手段を確保するためだけに鋳造されていました。
貨幣にはさまざまなものが用いられていました。貝殻もそのひとつです。しかし、貝殻ではなく家畜でなければ買えないものもありました。当初は、何でも買うことのできる共通貨幣はなかったのです。
貨幣は財宝として蓄積されました。貨幣を所有する者には威光があるとみられていました。そのため、耐久性をもつ象牙や巨石、金や銀などの金属が身分的貨幣として扱われました。
原始時代には、女性は貨幣財貨をもつことができませんでした。男の首長だけがりっぱな大きさの貝殻を所有していて、戦争や特別の贈り物のときなどにかぎって、それを放出しました。
貨幣が一般的交換手段として利用されるのは、対外商業がはじまってからです。そして、対外的な貨幣が次第に共同体内部の経済に侵入してきます。
ウェーバーは初期の貨幣として、(1)宝貝、硝子玉、琥珀、珊瑚、象牙などの装飾貨幣、(2)穀物、家畜、奴隷、煙草、火酒、塩、鉄器、武器のような対外的交易貨幣、(3)その土地では生産できない毛皮、皮革、織物のような衣服貨幣、(4)小片に何かの印をつけた記号貨幣などを挙げています。
こうした貨幣を評価基準として、交換を実現するのはなかなかやっかいなことでした。そのため、貨幣としては次第に貴金属が利用されるようになります。貴金属が腐蝕しにくいこと、装飾物ともなりうること、加工しやすく細分しやすいこと、秤量できることなどがその理由でした。
最初に金貨がつくられたのは、紀元前7世紀のリディア王国(現トルコ西部)です。バビロニアでは銀塊が秤量貨幣として用いられていました。
政治権力者が貨幣の鋳造権を握るのは、もっとあとの時代になってからです。紀元前5世紀ごろ、ペルシアのダレイオス1世はダレイオス金貨をつくり、それを傭兵に給付しています。鋳貨を財貨の取引に用いたのはギリシア人でした。フェニキア人は商業に貨幣を利用しませんでした。ローマでは紀元前269年にいたって、ようやく銀貨が鋳造されました。
貨幣の鋳造は17世紀まで手作業でおこなわれていましたが、手間がかかったうえに、その仕上がりもまちまちでした。その純正さを判断するには、刻印が比較的安全なよりどころとなりました。
ここでウェーバーは金属本位の話を持ちこんでいます。金属本位とは、特定の鋳貨を支払手段として法定することを意味します。今日では多くの金属(たとえば金、銀、銅)のあいだに特定の比率を設定する両本位制が基本になっていますが、かつてはこの比率が常に変動していました。
地方取引では銅がよく用いられ、遠隔取引では銀がよく使われていましたが、しだいに金が頭角をあらわします。その場合は、とりわけ金と銀の比率が問題となりました。
ローマ帝国では銅と銀の並行本位制がとられ、銅と銀の比率を112対1に維持することが目指されました。金貨も商業貨幣でしたが、当時、金貨は経済目的より軍事的な論功行賞として交付されていました。
カエサルが政権を掌握すると、金本位制がとられ、銀との比率が11.9対1と定められました。アウレウス金貨はコンスタンティヌス時代まで用いられました。コンスタンティヌスのとき新たにソリドゥス金貨がつくられ、ローマ帝国崩壊後も広く流通しました。
これにたいし、中世は銀本位制でした。貨幣鋳造権は王や皇帝が専有していましたが、実際にはその鋳造は特権者に委譲され、手工業・ツンフトによってつくられていました。時がたつと悪鋳がおこなわれたこと(悪貨は良貨を駆逐する)、それにより金(とりわけフィレンツェのフローリン金貨)の権威が高まったことも頭に入れておくべきでしょう。
16世紀以降は、メキシコやペルーからヨーロッパに大量の貴金属がもたらされます。ウェーバーによると、その量は1493年から1800年にかけ、金が2500トン、銀が9万ないし10万トンだったといいます。
これによりヨーロッパでは大量の通貨が流通するようになりました。だが、混乱がつづき、貨幣制度の合理化には時間がかかりました。
近代的本位制度が過去とことなるのは、それが国庫収入の観点からではなく、純国民経済的観点から実施されたことだ、とウェーバーはいいます。それは、王室収入に都合のいい観点からではなく、商業上、合理的な観点から貨幣制度が定められたということです。
その点で先鞭をつけたのはイギリスでした。1717年にイギリスはアイザック・ニュートンの助けを借りて、ギニー金貨1枚が銀貨21シリングにあたると定めました。その後、金は本位金属となり、銀は補助貨幣に格下げされていきます。
いっぽうフランスは革命中、さまざまな実験をおこなった結果、銀を基本とした両本位制を採用し、銀と金の比価を15.5対1と定めました。
ドイツでは銀本位制が存続しました。ドイツが金本位制に移行するのは、1870年の普仏戦争の勝利により、フランスから多額の戦争賠償金を得てからのことです。
さらに、カリフォルニアでの金の発見により、世界の金の量が増大し、ドイツではマルク金貨がつくられることになりました。
貨幣といえば銀行の話にも触れないわけにはいかないでしょう。
資本主義が成立する以前も、銀行がなかったわけではありません。多種多様な通貨が流通するなかで、銀行の主な役割は両替でした。さらに遠隔地での支払の必要が加わると、支払委託の引き受けが業務に加わります。
小切手のような支払手段も必要になりました。貨幣保管業務、つまり預金業務もはじまります。これらはエジプトでもローマでもおこなわれていました。
バビロニアでは各種の通貨がないため、両替業務はありませんでした。その代わり、銀行業者は銀塊に刻印を押して貨幣とする業務を請け負っていました。バビロニアの銀行は振替業務をおこなっており、銀行切符(ただし流通の対象ではない)のようなものも発行していました。
古代ローマでは、銀行業者は公認の競売業者でもありました。注目されるのは、当座勘定取引が銀行でおこなわれていたことです。しかし古代の銀行は、民間経営は例外で、たいていが神殿や国家によって運営されていました。
神殿(たとえばデルフィ神殿)は金庫としての役割も果たしており、預けられたお金の略奪は禁止されていました。奴隷たちはみずからの貯金を神殿に預け、それによって自由が得られる日を待ちました。いっぽう、王にとって神殿は大きな貸主でもありました。
国もまた国庫収入を目的として銀行業務を営んでいます。プトレマイオス朝のエジプトでは、王が国庫財政上の機関として、銀行を独占していましたが、それは近代的な国立銀行制度とはまるで無関係の機関でした。
中世の銀行制度は当初はささやかなもので、11世紀には両替屋がある程度でした。それが12世紀になると遠隔地の支払取引のために手形証書が使われるようになります。金貸しをおこなっていたのは、定住の商人ではなく、ユダヤ人やロンバルディア人(北イタリア人)などの外来者でした。
うちつづく貨幣悪鋳に対応するため、中世の商人たちは結束して銀行を設立し、その預金をもとに振替証券や支払小切手を発行しました。しかし、そうした銀行はなかなかつづきませんでした。
中世の銀行は、法王庁のために租税を徴収する仕事なども請け負っていました。戦争をはじめようとする団体や国王にも融資をおこなっています。しかし、その回収は容易でなく、銀行はしばしば倒産の危機に見舞われました。
政治権力者は安定した銀行を求めるようになります。そのためにさまざまな独占権(たとえば関税)をもつ独占銀行がつくられるようになります。ジェノヴァのサンジョルジョ銀行はそうした銀行のひとつでした。
イギリスでは金を扱う貴金属商人が銀行を営み、預金を引き受けたり、融資や振替の業務をおこなったりしていました。しかし、1672年にチャールズ2世が巨額の負債を踏み倒すために支払停止を命じたことから、多くの銀行が破産に追いこまれました。そのため、もっとしっかりした独占的銀行が求められるようになります。
もともとイングランド銀行は、オレンジ公ウィリアムがルイ14世と戦うための戦費を調達するために、1694年に設立されたものです。だが、国王の権力が強化されることを恐れた議会は、これを国立銀行と認めず、「議会の決議にもとづかないかぎり、国家にたいし貨幣を前貸しすることはできない」との縛りを設けました。
イングランド銀行は120万ポンドの株式資本によって設立されましたが、これはたちまち国家のふところに消えてしまいました。しかし、重要なことは、イングランド銀行が、手形割引権(企業信用)と銀行券発行権をもつ近代的な中央銀行となったことです。
ウェーバーは補足的に近代資本主義時代以前の利子についても触れています。
村落共同体や氏族共同体のなかでは、利子も貸付も存在しませんでした。相互扶助が原則だったからです。困ったときに人を助けるのは、共同体の義務にほかなりませんでした。ユダヤ人もイスラム教徒も同胞からは利子をとりませんでした。利子が発生するのは内輪ではない別種族や別身分の者への貸付がなされるときでした。
一般に利子は資本のこうむるリスクにたいする代償として発生します。古代においても家畜や穀物の貸付を受けたときには、その数倍のものを返すのが決まりでした。海上貸付は危険が大きいぶん、利子も高かったのです。
中世の教会は高利を禁止する宣言をたびたび発しました。
多くの人がユダヤ人の貸付に頼っていました。しかし、同時に人びとは国家がユダヤ人の資金を没収し、かれらを追放することを期待していました。こうして、ユダヤ人は町から町へ、村から村へと追いまくられることになります。
教会自身が貸金所を創設することもありました。だが、これは長くつづかず、かれこれするうちに教会も利子を黙認する寛大な態度をとるようになります。
とりわけ北ヨーロッパでは、新教が利子禁止のタテマエをなし崩しにしていきました。正当な利子を擁護する理論を展開したのは17世紀のカルヴィン派指導者、クラウディウス・サルマシウスだった、とウェーバーはいいます。
ウェーバーのこうした研究からは、古代以来、周縁に存在した前市場的な経済諸制度が次第に整理統合されて、村落共同体を解体し、商品世界を形成するにいたるありさまをうかがい知ることができるでしょう。
産業とは原材料を加工して有益な財をつくる作業をいいます。その作業によってつくられたものが産業製品です。
農奴が荘園領主のためにはたらいたり、インドの農民が村のためにはたらいたりすると、かれらは領主や村落から実物ないし貨幣での給付を受けます。
女性はもともと耕作奴婢だった、とウェーバーはいいます。料理や機織りも女性の仕事でした。これにたいし、戦争や狩猟、家畜の飼育に従事する男たちは、金属品や革なめし、肉の調理を担当していました。家の普請や舟の建造なども、村じゅうの男たちの仕事でした。最古の職業は呪医で、鍛冶屋も呪術のようにみられていました。
熟練の手仕事は当初、首長や荘園領主の家計のもとでおこなわれます。最終的にそれは市場をめざすようになるとしても、その中間段階として他人の注文に応じて仕事をする手工業者が生まれます。手工業者はみずから原料と労働手段を持っている場合もあるし、原料と労働手段のどちらか、とりわけ原料を注文者から支給される場合もあります。
労働場所は自分の家である場合も、家の外である場合(たとえば仕事場や工場など)もあります。労働手段は道具から設備まで、さまざまです。設備を所有するのは村であったり、修道院であったり、領主であったりします。
産業の発展については、まず部族産業というカテゴリーが想定できます。この場合は部族が特定の原料、あるいは技能を独占しており、ここから何らかの製品(商品)が生まれ、部族外にも売られることになります。
市場のための専業化は職業分化を生じさせます。村落または領主が他部族出身の手工業者を呼び入れて働かせるときには、その生活の面倒を村落や領主がみなければならなりません。ウェーバーはこれをデミウルギーと呼んでいますが、この場合は自己需要のための生産がおこなわれるにすぎません。
これがさらに進むと、市場のための生産がおこなわれるようになります。もともと村落や領主の需要をまかなうための生産が、次第に市場に向けられるようになるわけです。
古代において、貴族は大所有地で働く奴隷のなかに手工業者をかかえていました。かれらは鍛冶や製鉄、建築、車両整備、衣服づくり、製粉、パン焼き、料理のために働いていました。エジプトやメソポタミアでは、王に隷属し、みごとな芸術品をつくる労働者もいました。
こうした状態から、顧客生産や市場生産に移るためには、何よりも交換経済がある程度発達し、一定の顧客が存在しなければなりません。
最初の現象は、貴族(領主)の奴隷がつくった織物や陶磁器が市場に流出するケースです。次に、領主や大地主が積極的に企業経営に乗りだす場合があります。古代ローマ時代のある大地主は、副業として、製瓦業や砂石採掘業を営んでいました。奴隷女を仕事場に集めて、紡績の仕事をさせていた者もいます。中世の修道院は醸造所や晒布場、蒸留所などを営んでいました。
いっぽう都市では、商人が出資して企業をつくり、労働者を集め、仕事をさせるようになりました。古代ローマでは、貴族がエルガステリオン(作業所)に奴隷を集め、武器や高級品を製造させていたケースもあります。奴隷を確保するのは難事で、奴隷による大規模経営はめずらしい例外でした。
奴隷制にもとづく古代企業は、不特定な市場ではなく、かぎられた狭い市場を対象としていました。
古代ギリシア人は美術品を除き、ごくささやかなものしか所有していません。古代ローマでもベッドは贅沢品で、人びとはマントにくるまって地べたで寝ていました。これにたいし、中世の都市貴族は多くの実用的な家具をもつようになります。北ヨーロッパでは、10世紀から12世紀にかけ、古代の帝国にくらべ、はるかに広範囲な購買力あるいは買い手が存在したのです。
市場が拡大したのは中世の10世紀ごろからで、農民の購買力が増えたのが大きな要因でした。農民の隷属関係は次第にやわらぎ、いっぽうで農業の集約度は進歩していました。こうした背景のもとで、手工業が興隆します。
12世紀、13世紀になると、王侯によって多くの都市がつくられ、都市の時代がはじまります。皇帝が都市に特権を与えたため、貴族や商人、隷農、熟練手工業者などが都市に集まってきました。その後、帝国の力が衰えるとともに、都市の独立傾向、自治的傾向が強まっていきます。
都市に定住した手工業者は、土地を所有する完全市民ではなく、都市の内外に住む領主や後見人(ムントマン)に賃租を支払わなくてはなりませんでした。また、都市の外には、独特の手工業者秩序をもつフローンホーフ(荘園)も存在しました。
自由手工業者は道具をもっていますが、固定資本(設備)をもっていません。一般に顧客の注文に応じてはたらく生産者でした。かれらが賃仕事にとどまるか、つくった製品を売って生活する仕事人になるかどうかは、市場の状況によってことなっていました。賃仕事は富裕な階級のために働くところに成立します。これにたいし、つくった製品を売る仕事(価格仕事)が成立するのは、多くの民衆を相手とする場合でした。
多数の民衆の購買力は、価格仕事が成立する前提であり、これがのちに資本主義成立の前提となっていきます。しかし、だいたいにおいて古代でも中世でも、手工業者は賃仕事が多かった、とウェーバーは指摘しています。
手工業者が職業別に結合するとツンフト(職人ギルド)が結成されます。ツンフトが本格的に誕生するのは、ヨーロッパ中世においてです。
ツンフトは仲間の経済機会を均等にするよう努め、そのためにさまざまな規制が設けられました。一人の親方が突出した資本をもつことは禁止され、労働も伝統に沿っておこなわれねばならず、労働者(徒弟)の数も統制されました。
ツンフトは製品ごとにこまかく設けられ、価格は公定され、ひとつのツンフトが別のツンフトの領分を侵すことは禁止されていました。
ツンフトは対外的には純粋な独占政策を発揮しました。仲間どうしの違反には厳しく目を光らせ、ツンフトが絶対的権力を有する地域内においては、ほかの手工業を認めませんでした。ツンフトにおいては、同一労働者がはじめからおわりまで完成品を生産することになっており、それによってツンフト内部で大経営が発生しないよう配慮されていました。
だが、ツンフトは次第に壁にぶつかるようになります。
ツンフトは都市という地盤のうえに成り立っていました。中世都市の住民は、さまざまな身分をもつ人の寄せ集めで、その大多数は自由な経歴をもっていませんでした。手工業者のうちで市民と認められている人はごくわずかだったのです。
都市領主はツンフトの代表を任命し、ツンフトの経営にまで干渉しようとしました。しかし、かれらはそうした都市領主と闘い、みずからツンフトの代表者を選ぶとともに、都市領主の干渉をはねのけました。不当な賦役や租税、賃借料とも闘いました。ツンフトはこうした闘いに勝利を収めます。だが、その結果、多くの敵をもつことになりました。
ツンフトの反対者は、まず消費者でした。ツンフトの市場独占と独占価格に対抗するため、都市当局は自由親方を任命したり、市営の肉の販売所やパン焼き窯を設置したりして、ツンフトに対抗しました。
ツンフトには別の競争者もいました。荘園や修道院の手工業者です。とりわけ修道院はツンフトに競争をいどみました。さらに、商人と結びついた田舎の手工業者の存在も無視できなくなってきます。
ツンフトと労働者との関係もあやしくなってきます。ツンフトが職人の数を制限したり、親方による統制が厳しくなるいっぽうだったからです。ツンフトは小売商人とも対立しました。小売商人にとっては、公定価格を崩さないツンフトは商売の妨げにほかなりませんでした。
ツンフトは次第に市場の力に圧倒されていきます。
ツンフトの親方が商人または問屋となって、原料を買い入れ、これを他のツンフトに配分し、全生産過程を統合して製品を売るようになることも考えられました。この場合、ツンフトはカンパニーに転化し、いわば商人ツンフトが生まれたことになります。
原料が高価で、その輸入に巨額の資本を必要とする場合、ツンフトは輸入業者(たとえばフッガー家)に依存しないわけにはいきませんでした。そうした高級原料としては琥珀(こはく)や絹などがあり、初期の木綿もそのひとつでした。輸入原料だけではありません。ツンフトは国外に製品を売る場合は輸出業者に頼らざるをえませんでした。
ツンフトに代わって市場の支配力を発揮するのが問屋です。
問屋制度を促したのは繊維工業だ、とウェーバーはいいます。ヨーロッパでは11世紀以来、羊毛と麻の戦いがあり、17、18世紀には羊毛と木綿の戦いがあって、けっきょく木綿が勝利を収めます。
中世都市の繁栄を支えたのは羊毛産業でした。フィレンツェでは羊毛職人のツンフトが大きな政治勢力となっており、その背後にはすでに問屋の存在がみられました。パリの羊毛問屋はシャンパーニュの大市のための仕事をしていました。
フランドルでもイギリスでも問屋制度が発達します。イギリスはもともと粗製の羊毛を輸出していましたが、13、14世紀には未染色の半製品、そしてついに完成品の輸出をおこなうようになります。
問屋制度の発達によって、ツンフトは次第に影響力を失っていきます。職人は問屋のために直接労働する家内工業的小親方に転じていきました。
ウェーバーによると、問屋制度は次のような段階をへて発展していきました。すなわち(1)手工業者からの買い入れ独占、(2)原料の配給、(3)生産過程の管理、(4)道具の配給、(5)生産過程の結合。
問屋制度が長く持続した理由を、ウェーバーは産業革命以前の時代は、固定資本の割合が少なかったことに求めています。このことは、問屋制度が広範な家内工業に依存していたことを意味していました。
だが、まもなく工場が誕生します。
家庭から分離された仕事場生産は昔から存在しました。荘園や組合が仕事場をつくることもあり、それが大規模な仕事場になることもありました。マニュファクチュアは多くの労働者を一カ所に集めて、規律をもって労働させる制度です。工場では企業家が固定資本(設備)と労働力を投入し、異質結合的に協働がおこなわれます。
工場成立の前提条件は、大量かつ継続的な販路が存在することで、そのためには市場の安定と貨幣の購買力が求められます。工場は家内工業や問屋制度でつくられるものよりも、より安価に商品を供給しなければなりません。
工場での生産には豊富な原料と固定資本(設備)、それに多くの自由な労働力が欠かせませんでした。イギリスで自由な労働力が得られたのは、農民からの土地収奪がなされ、農村人口がプロレタリア化したためでした。
近代以前においても、設備を必要とする仕事場がありました。たとえば製粉所や製材所、搾油所、晒布所、パン焼竈、醸造所、鋳造所、鍛鉄場などで、これらは王侯、荘園領主、都市貴族、あるいは市民によって営まれていました。
16世紀のイギリスのある繊維工場は工場の走りですが、そこには200の織機が据え付けられていて、職工たちは賃金をもらうため機械の前で働いていました。少年が補助的に働く姿もみられました。だが、手工業者の訴えにより、1555年に国王はこの工場を禁止しています。当時はまだ問屋制手工業者の影響が強かったのです。
工場に新しい進展がみられるようになるのは、17、18世紀になってからです。近代的分業と同時に、人間以外の動力源が用いられるようになりました。最初は馬力起重機、ついで水や風が利用されます。風を利用した代表はオランダの風車で、水は採鉱業でも欠かせませんでした。
工場の先駆者は中世の王侯の貨幣鋳造所だった、とウェーバーはいいます。武器、さらに軍隊の被服や火薬を製造するためにも秘密を保持する工場が必要とされました。
需要という点で確実なものとしては奢侈的需要がありました。ゴブラン織や敷物、金の器や陶器、窓硝子、ビロード、絹、石鹸、砂糖など、上層階級の需要を満たすため、特別の設備をもつ工場がつくられます。しかし、こうした市場はほぼ貴族階級にかぎられていたのです。
フランスではフランソワ1世(在位1515〜47)が武器や壁紙などの王立工場をつくっていました。イギリスではツンフトが都市を制していたため、工場は地方に建設する以外にありませんでした。
ドイツで最初に工場がつくられたのは16世紀のチューリヒ(現スイス)で、ユグノーの亡命者が絹と緞子(どんす)を製造し、それがたちまちドイツの諸都市に普及しました。16世紀から17世紀にかけ、アウグスブルクでは砂糖や緞子、ニュルンベルクでは石鹸、アンナベルクでは染色、ザクセンでは織物、ハレとマクデブルクでは針金の工場が誕生し、18世紀には王侯直営の陶器工場がつくられています。
ウェーバーは工場は手工業から発生したわけではないといいます。工場でつくられたのは、木綿、陶器、緞子など、新しい生産方式を必要とする新しい生産物でした。
同様に工場は問屋制度から生まれたものでもありませんでした。工場において重要なのは固定資本という要素です。その意味では、工場はむしろ荘園領主の設備を継承したものといえます。機械は工場に先行したわけではなく、工場が蒸気と機械の発展を促したという見方をウェーバーはとっています。
近代的工場の成立は企業家と労働者に重大な影響をもたらしました。企業家はいまや市場のための生産に責任を負うことになりました。労働者もまた自由な労働者として、企業と労働契約を結んで、仕事をするようになります。
だが、こうした工場制度が成立したのは、ヨーロッパの一部に限られていました。工場が誕生することができたのは、機械化という刺激があったからだ、とウェーバーはいいます。そして、その機械化の推進力となったのは、鉱山業の発展にほかならなりませんでした。石炭と鉄の時代がはじまるのです。
商業もはるか古代から存在しました。商業(交易)はことなる共同体間の取引として発生する、とウェーバーは述べています。共同体間で生産が分化する結果、商業が発生します。
古代オリエントでは、権力者どうしがたがいに贈り物をしてよしみを通じていました。ふつうは黄金や戦車ですが、馬や奴隷が贈られることもありました。
エジプトのファラオは自身が船主として、交易事業を営んでいました。インドでは、商人(バニヤン)階級はカーストに位置づけられていました。いかなる生き物も殺すことを禁じられているジャイナ教徒は、宝石や貴金属を扱う商人となりました。土地所有を禁じられているユダヤ人が商業、とりわけ金融業に向かったのも、宗教的な理由からです。
中世には領主商業があらわれます。領主は荘園の余剰生産物を市場で売るため、職業的商人を手代として雇いました。王侯が他人種の商人に保護を与え、その代償として手数料を徴収する習慣も存在しました。
ヴェネツィアの首長(ドージェ)たちも船主でした。ハプスブルク家も18世紀までみずから交易事業を直営しています。しかし、次第に、王たちが商人に商業を特許したり、請け負わせたりして、その成果の一部を受けとることが多くなります。
独立した商人層が生まれる前提としては、交通手段が確立されていなければなりません。陸上では13世紀ころまで、商人は自分の背に商品を担いだり、ロバやラバなどに二輪車をひかせたりして荷物を運んでいました。馬は最初、戦争にしか用いられず、運送手段として用いられるようになったのは、わりあい新しい時代にはいってからです。
いっぽう船の発達には長い時間を要しました。最初は昼間の沿岸航海しかできませんでした。やがてアラブ人がモンスーンを利用して、インドへの遠洋航海をころろみます。しかし、すでに中国人は3、4世紀に羅針盤を利用しており、ヨーロッパ人がそれを採用するのははるかあとのことです。羅針盤の導入は航海に決定的な影響をもたらしました。
帆は船のスピードアップに貢献しました。それでも古代においては、ジブラルタル─オスティア(ローマの外港)間、メッシナ─アレクサンドリア間はそれぞれ8〜10日の日数を要しました。帆船航海術の完成は16、17世紀のイギリスを待たなければなりません。
古代、船の動力には奴隷が漕ぎ手として用いられていました。船主は商人で、ギリシアのポリスにはエンポロスと呼ばれる船乗り商人がいました。ローマでは国が船舶の徴用と穀物の配給を仕切っていました。しかし、ローマでは船による運送は発達せず、軍船も衰退して、海賊が横行することになります。
古代や中世でも船荷に関する決まりが設けられていました。遭難によって船荷を捨てざるをえないときには、関係者が共同でその損害を負担することになっていました。海上貸付には高い利子が発生しました。
中世の海上商業は、古代とちがい組合によって営まれるようになります。商人たちは仲間組合を結成し、船長を雇って共同で船荷を運搬し、共同で危険を分担しました。資本家による海上貸付もあって、行商人たちはこの方式をよく利用したといいます。
行きの船には海外で売られる商品が積まれ、それに商人が同道する場合もあれば、別の商人に販売をゆだねる場合もありました。そこで生じた利益はその都度分配されました。
近世を尺度とすれば、中世の海上商業の取引高はきわめてわずかなものでした。航海の期間も長かったため、資本の回転もきわめて緩慢でした。海賊に襲われる危険もありました。それでも、地中海やバルト海では、それなりの規模の取引がおこなわれていました。
海上にくらべると陸上の危険は少なかったといえます。その代わり運賃は比較にならぬくらい高くなりました。陸上商業でも13世紀までは商人が商品についていくのがふつうでした。その後は、運搬人が荷物に責任をもつようになります。
問題は道路事情でした。古代ローマの道路は、あくまでも首都への食糧供給と政治的・軍事的目的のためでした。中世の荘園領主は農民たちに道路や橋梁(きょうりょう)の建設・維持を課し、めいめい勝手に道路をつくるようになります。
中世では海上にくらべ陸上の取引はずっと少なく、加えて、運送に時間がかかりました。アジアや中東では、隊商が荷物の運搬を引き受けていました。
人びとが個人的に旅行ができるようになったのは、14、15世紀になってからです。当初は荘園領主が農家に馬や馬車を貸しつけて運送をやらせていました。そこから次第に独立した運送業者が生まれ、運送業者のツンフトが結成されることになります。
中世は河川の舟航が盛んでした。領地内の運輸独占権をもっていた領主や大司教は、この権利を船乗りたちにゆだねました。しかし、しだいに船乗りたちは団体を結成し、河川通行権をにぎるようになります。ツンフトや都市の自治団体が船を所有して、この権利を行使する場合もありました。
商人は身分の保証を求めました。最初に求めたのは首長の保護です。つぎに法的な保護が求められました。商人の数が増えるにつれてハンザ(団体)が結成されます。都市には外来商人のための居留地がつくられました。
最後に商品を取引できる市場が必要になってきます。エジプトやインド、ヨーロッパでも、もともと市場は外来商人のために、王の特許により創設されました。市場ではさまざまな決まりが設けられ、手数料や市場税がかけられ、王はこれによって利益を得ていました。
定住商人は都市発展の産物だ、とウェーバーはいいます。定住商人の起源は行商人です。かれらは周期的に旅行し、地方で生産物を売ったり買ったりしていました。つぎに、かれらは使用人に地方を回らせて産物を集めるようになり、さらに地方に支店を設けて、使用人を常駐させるようになります。そして、自身は都市の定住商人となるわけです。こうした状況が可能になったのは中世末期です。
定住商人が闘ったのは、まずユダヤ人や他国の商人、田舎の商人などのような外部的存在で、かれらを市場から排除しようとしました。そして、内部においては、仲間のひとりが突出しないよう機会の均等を求め、さまざまな規制を設けました。営業活動の範囲や消費者の囲い込みをめぐっては争いが生じました。
ウェーバーは各地の商人の集まりとしてメッセ(見本市)の存在を挙げている。その代表がシャンパーニュの大市でした。シャンパーニュでは4つの町で6つのメッセが、それぞれ年に50日間開かれていました。
ここで取引された最大の商品はイギリスやフランドルの羊毛と羊毛製品です。イタリアなどからは香料、染料、臘、サフラン、樟脳、漆などがもたらされました。シャンパーニュには世界中の貨幣が集まり、為替や手形の決済がおこなわれています。
合理的な商業には計算技術が欠かせません。位取り計算法はインドで発明され、アラブ人がこれを発展させ、ユダヤ人がヨーロッパに伝えました。ヨーロッパで計算法が普及したのは十字軍の時代になってからだといいます。そして、中世のイタリアで簿記がつくられました。
ウェーバーによれば、簿記の必要性が高まったのは、家族的な経営体である商家が非家族的な経営体を形成することになってからだといいます。フッガー家でもメディチ家でも、当初は家計と経営は未分離でした。だが、しだいに家計の計算と営業上の計算が分離されるようになります。こうした現象は西洋においてしか生ぜず、それが初期資本主義の発展に決定的な影響をもたらした、とウェーバーは指摘しています。
だが、その前に商人ギルド(商人組合)について論じなくてはなりません。ギルドには外来商人のギルドと定住商人のギルドがあります。
外来商人のギルドとしては、ハンザ同盟が何といっても有名です。ハンザ同盟はバルト海沿岸の商業を掌握しました。
定住商人ギルドとしてウェーバーが挙げるのが、上海の茶商組合や広東の公行ギルドです。かれらはすべての海外貿易を独占していました。インドでは、ジャイナ教徒が定住商業に従事し、ゾロアスター教徒は卸売商業や遠隔地交易を営んでいました。
西洋のギルドの特徴は、政治権力から特権を与えられていることにあります。都市ギルドは経済問題に関して都市を管轄する商人組合となりました。イギリスには国王の租税を請け負うギルドがあったといいます。
西洋のギルドの歴史は実に多様で、イギリス、イタリア、ドイツをみても、その発展はそれぞれ異なります。
北ドイツでは、ギルドの支配するハンザ都市の同盟、すなわちハンザ同盟が結成されました。その中心都市はリューベック、ハンブルク、ブレーメンなどです。ハンザ同盟は14世紀に最盛を誇り、バルト海地域の交易を担いました。
ウェーバーによると、ハンザ同盟の商業上の特権にあずかったのは、ハンザ都市の市民だけだったといいます。利用できるのは組合所有の船だけで、貨幣取引はせず、商品取引のみをおこないました。
ハンザ同盟は各地に商館や倉庫をおいて、商品ネットワークを築き、その取引を厳格な統制下におきました。同盟内では度量衡が統一され、商品の規格化もなされました。蝋や塩、金属、布地をはじめとして多くの商品が取引されていました。
同盟は軍隊をもたず、強い関税政策ももちませんでした。政治的には緩やかな統一体です。加盟各都市では、商人貴族政治の確保が目指されていました。
15世紀になるとハンザ同盟は衰えはじめます。しかし、資本主義前段階の商業の発達を語るうえで、ハンザ同盟は避けて通れないテーマだ、とウェーバーは考えています。
最後に、近代資本主義以前の貨幣と銀行に触れておきましょう。
貨幣には支払手段と交換手段という機能があります。しかし、歴史的には貨幣はまず支払手段として登場した、とウェーバーは指摘します。
交換がなくても支払いは発生します。たとえば貢ぎ物、首長からの贈与、結納、持参金、贖罪金、罰金など、支払いは常に必要になってきます。さらに領主が家臣に支払う給与、指揮官が傭兵に渡す支払いなども欠かせません。ペルシア帝国でもカルタゴでも、貨幣は軍事上の支払手段を確保するためだけに鋳造されていました。
貨幣にはさまざまなものが用いられていました。貝殻もそのひとつです。しかし、貝殻ではなく家畜でなければ買えないものもありました。当初は、何でも買うことのできる共通貨幣はなかったのです。
貨幣は財宝として蓄積されました。貨幣を所有する者には威光があるとみられていました。そのため、耐久性をもつ象牙や巨石、金や銀などの金属が身分的貨幣として扱われました。
原始時代には、女性は貨幣財貨をもつことができませんでした。男の首長だけがりっぱな大きさの貝殻を所有していて、戦争や特別の贈り物のときなどにかぎって、それを放出しました。
貨幣が一般的交換手段として利用されるのは、対外商業がはじまってからです。そして、対外的な貨幣が次第に共同体内部の経済に侵入してきます。
ウェーバーは初期の貨幣として、(1)宝貝、硝子玉、琥珀、珊瑚、象牙などの装飾貨幣、(2)穀物、家畜、奴隷、煙草、火酒、塩、鉄器、武器のような対外的交易貨幣、(3)その土地では生産できない毛皮、皮革、織物のような衣服貨幣、(4)小片に何かの印をつけた記号貨幣などを挙げています。
こうした貨幣を評価基準として、交換を実現するのはなかなかやっかいなことでした。そのため、貨幣としては次第に貴金属が利用されるようになります。貴金属が腐蝕しにくいこと、装飾物ともなりうること、加工しやすく細分しやすいこと、秤量できることなどがその理由でした。
最初に金貨がつくられたのは、紀元前7世紀のリディア王国(現トルコ西部)です。バビロニアでは銀塊が秤量貨幣として用いられていました。
政治権力者が貨幣の鋳造権を握るのは、もっとあとの時代になってからです。紀元前5世紀ごろ、ペルシアのダレイオス1世はダレイオス金貨をつくり、それを傭兵に給付しています。鋳貨を財貨の取引に用いたのはギリシア人でした。フェニキア人は商業に貨幣を利用しませんでした。ローマでは紀元前269年にいたって、ようやく銀貨が鋳造されました。
貨幣の鋳造は17世紀まで手作業でおこなわれていましたが、手間がかかったうえに、その仕上がりもまちまちでした。その純正さを判断するには、刻印が比較的安全なよりどころとなりました。
ここでウェーバーは金属本位の話を持ちこんでいます。金属本位とは、特定の鋳貨を支払手段として法定することを意味します。今日では多くの金属(たとえば金、銀、銅)のあいだに特定の比率を設定する両本位制が基本になっていますが、かつてはこの比率が常に変動していました。
地方取引では銅がよく用いられ、遠隔取引では銀がよく使われていましたが、しだいに金が頭角をあらわします。その場合は、とりわけ金と銀の比率が問題となりました。
ローマ帝国では銅と銀の並行本位制がとられ、銅と銀の比率を112対1に維持することが目指されました。金貨も商業貨幣でしたが、当時、金貨は経済目的より軍事的な論功行賞として交付されていました。
カエサルが政権を掌握すると、金本位制がとられ、銀との比率が11.9対1と定められました。アウレウス金貨はコンスタンティヌス時代まで用いられました。コンスタンティヌスのとき新たにソリドゥス金貨がつくられ、ローマ帝国崩壊後も広く流通しました。
これにたいし、中世は銀本位制でした。貨幣鋳造権は王や皇帝が専有していましたが、実際にはその鋳造は特権者に委譲され、手工業・ツンフトによってつくられていました。時がたつと悪鋳がおこなわれたこと(悪貨は良貨を駆逐する)、それにより金(とりわけフィレンツェのフローリン金貨)の権威が高まったことも頭に入れておくべきでしょう。
16世紀以降は、メキシコやペルーからヨーロッパに大量の貴金属がもたらされます。ウェーバーによると、その量は1493年から1800年にかけ、金が2500トン、銀が9万ないし10万トンだったといいます。
これによりヨーロッパでは大量の通貨が流通するようになりました。だが、混乱がつづき、貨幣制度の合理化には時間がかかりました。
近代的本位制度が過去とことなるのは、それが国庫収入の観点からではなく、純国民経済的観点から実施されたことだ、とウェーバーはいいます。それは、王室収入に都合のいい観点からではなく、商業上、合理的な観点から貨幣制度が定められたということです。
その点で先鞭をつけたのはイギリスでした。1717年にイギリスはアイザック・ニュートンの助けを借りて、ギニー金貨1枚が銀貨21シリングにあたると定めました。その後、金は本位金属となり、銀は補助貨幣に格下げされていきます。
いっぽうフランスは革命中、さまざまな実験をおこなった結果、銀を基本とした両本位制を採用し、銀と金の比価を15.5対1と定めました。
ドイツでは銀本位制が存続しました。ドイツが金本位制に移行するのは、1870年の普仏戦争の勝利により、フランスから多額の戦争賠償金を得てからのことです。
さらに、カリフォルニアでの金の発見により、世界の金の量が増大し、ドイツではマルク金貨がつくられることになりました。
貨幣といえば銀行の話にも触れないわけにはいかないでしょう。
資本主義が成立する以前も、銀行がなかったわけではありません。多種多様な通貨が流通するなかで、銀行の主な役割は両替でした。さらに遠隔地での支払の必要が加わると、支払委託の引き受けが業務に加わります。
小切手のような支払手段も必要になりました。貨幣保管業務、つまり預金業務もはじまります。これらはエジプトでもローマでもおこなわれていました。
バビロニアでは各種の通貨がないため、両替業務はありませんでした。その代わり、銀行業者は銀塊に刻印を押して貨幣とする業務を請け負っていました。バビロニアの銀行は振替業務をおこなっており、銀行切符(ただし流通の対象ではない)のようなものも発行していました。
古代ローマでは、銀行業者は公認の競売業者でもありました。注目されるのは、当座勘定取引が銀行でおこなわれていたことです。しかし古代の銀行は、民間経営は例外で、たいていが神殿や国家によって運営されていました。
神殿(たとえばデルフィ神殿)は金庫としての役割も果たしており、預けられたお金の略奪は禁止されていました。奴隷たちはみずからの貯金を神殿に預け、それによって自由が得られる日を待ちました。いっぽう、王にとって神殿は大きな貸主でもありました。
国もまた国庫収入を目的として銀行業務を営んでいます。プトレマイオス朝のエジプトでは、王が国庫財政上の機関として、銀行を独占していましたが、それは近代的な国立銀行制度とはまるで無関係の機関でした。
中世の銀行制度は当初はささやかなもので、11世紀には両替屋がある程度でした。それが12世紀になると遠隔地の支払取引のために手形証書が使われるようになります。金貸しをおこなっていたのは、定住の商人ではなく、ユダヤ人やロンバルディア人(北イタリア人)などの外来者でした。
うちつづく貨幣悪鋳に対応するため、中世の商人たちは結束して銀行を設立し、その預金をもとに振替証券や支払小切手を発行しました。しかし、そうした銀行はなかなかつづきませんでした。
中世の銀行は、法王庁のために租税を徴収する仕事なども請け負っていました。戦争をはじめようとする団体や国王にも融資をおこなっています。しかし、その回収は容易でなく、銀行はしばしば倒産の危機に見舞われました。
政治権力者は安定した銀行を求めるようになります。そのためにさまざまな独占権(たとえば関税)をもつ独占銀行がつくられるようになります。ジェノヴァのサンジョルジョ銀行はそうした銀行のひとつでした。
イギリスでは金を扱う貴金属商人が銀行を営み、預金を引き受けたり、融資や振替の業務をおこなったりしていました。しかし、1672年にチャールズ2世が巨額の負債を踏み倒すために支払停止を命じたことから、多くの銀行が破産に追いこまれました。そのため、もっとしっかりした独占的銀行が求められるようになります。
もともとイングランド銀行は、オレンジ公ウィリアムがルイ14世と戦うための戦費を調達するために、1694年に設立されたものです。だが、国王の権力が強化されることを恐れた議会は、これを国立銀行と認めず、「議会の決議にもとづかないかぎり、国家にたいし貨幣を前貸しすることはできない」との縛りを設けました。
イングランド銀行は120万ポンドの株式資本によって設立されましたが、これはたちまち国家のふところに消えてしまいました。しかし、重要なことは、イングランド銀行が、手形割引権(企業信用)と銀行券発行権をもつ近代的な中央銀行となったことです。
ウェーバーは補足的に近代資本主義時代以前の利子についても触れています。
村落共同体や氏族共同体のなかでは、利子も貸付も存在しませんでした。相互扶助が原則だったからです。困ったときに人を助けるのは、共同体の義務にほかなりませんでした。ユダヤ人もイスラム教徒も同胞からは利子をとりませんでした。利子が発生するのは内輪ではない別種族や別身分の者への貸付がなされるときでした。
一般に利子は資本のこうむるリスクにたいする代償として発生します。古代においても家畜や穀物の貸付を受けたときには、その数倍のものを返すのが決まりでした。海上貸付は危険が大きいぶん、利子も高かったのです。
中世の教会は高利を禁止する宣言をたびたび発しました。
多くの人がユダヤ人の貸付に頼っていました。しかし、同時に人びとは国家がユダヤ人の資金を没収し、かれらを追放することを期待していました。こうして、ユダヤ人は町から町へ、村から村へと追いまくられることになります。
教会自身が貸金所を創設することもありました。だが、これは長くつづかず、かれこれするうちに教会も利子を黙認する寛大な態度をとるようになります。
とりわけ北ヨーロッパでは、新教が利子禁止のタテマエをなし崩しにしていきました。正当な利子を擁護する理論を展開したのは17世紀のカルヴィン派指導者、クラウディウス・サルマシウスだった、とウェーバーはいいます。
ウェーバーのこうした研究からは、古代以来、周縁に存在した前市場的な経済諸制度が次第に整理統合されて、村落共同体を解体し、商品世界を形成するにいたるありさまをうかがい知ることができるでしょう。
ウェーバーの社会経済史(1)──商品世界ファイル(26) [商品世界ファイル]
マックス・ウェーバーは当時スペイン風邪と呼ばれたインフルエンザのため、1920年6月に56歳で亡くなりました。3年前の1917年にはロシア革命が発生しています。ヒトラーがミュンヘン一揆をおこすのは、ウェーバーの死から3年後の1923年です。
本書『一般社会経済史要論』は1919年から20年にかけての冬学期にミュンヘン大学でおこなったウェーバーの講義を、本人のメモや聴講した学生の筆記にもとづいて再現したかれの最後の講義録です。
ドイツで原著が発行されたのが1924年、日本では1927年に黒正巌(こくしょういわお)(大阪経済大学教授)の訳で岩波書店から刊行されました。それを敗戦後に青山秀夫(京都大学経済学部教授)が改訳して、1954年に岩波書店から再刊されたのが本書です。1946年夏に最初の訳稿をザラ紙の原稿用紙に浄書したのが、学生の森嶋通夫(のちロンドン・スクール・オブ・エコノミクス教授)らだったというあたりが、学の系譜を感じさせます。
ウェーバーは本書で、近代資本主義がなぜ西洋において発生したのかを追及しています。近代資本主義という言い方からしても、それがけっして否定的に語られているわけではないことが想像できるでしょう。
出発点となるのは、農村共同体モデル、とりわけゲルマン的共同体です。
古代ゲルマン人は村落を形成して暮らしていました。その村がどんなものかというと、何層もの円をイメージしてみればよいでしょう。円の中心には数々の屋敷が存在します。円の二層目は垣をめぐらせた庭です。そして三層目が農耕地。四層目が牧地で、最後の五層目に森林が広がっています。土地は共有されているわけではなく、居住者にそれぞれ一定の持ち分が与えられていました。
耕地は三圃式(さんほしき)によって営まれています。第一区画には冬穀物、第二区画には夏穀物がつくられており、第三区画は休閑地です。その区画は年ごとに入れ替わって輪作されます。
村長は村の収穫を管理し、村の秩序を維持する役目を果たしていました。家屋や土地は村人の持ち分として専有され、相続されました。
村々は集まってマルク共同体を形成しました。森林や荒蕪地(こうぶち)を共同マルクとして所有していたのです。そうした森林や荒蕪地は個々の村落共同体に帰属せず、あくまでもマルク共同体に属していました。
8世紀末のカロリング朝以前に、こうしたマルク共同体はすでに誕生していたようです。マルクの長は世襲され、国王や領主によって任命されるのが通例でした。
共同体の構成員は原則的に平等です。しかし、家族が増減したりすると、耕地の所有に差が出てきます。手工業者など新たな労働力の到来も耕地の所有に影響を与えました。さらに国王や諸侯、領主などによる開墾もあって、マルク共同体のかたちは次第に崩れていきます。
ゲルマン的な共同体は、エルベ川とウェーザー川のあいだだけではなく、南ドイツ、スカンディナビア、ベルギー、北フランス、エルベ川の東方、イギリスの一部にまで広がっていました。
ドイツの南東部にはスラブ的な家族共同体がはいりこみ、それがバルカン半島へと広がっていました。そして、南西部にはローマ的な大土地所有形態が残存していました。
スコットランドやアイルランドにはケルトの共同体が存在しました。その最古のかたちは家畜経済です。いっぽう、ロシアにはミールと呼ばれる農村共同体が存在し、実際にはクラークと呼ばれる土豪が村を仕切っていました。そのミールは古代から存在したわけではなく、租税制度と農奴制の産物だったとウェーバーはいいます。ロシアの租税と農奴制はあまりにも苛酷でした。
ここで問題は、共同体のなかから、どのようにして領主の権力と財産が生じたかです。
最初に首長の権威がありました。首長は仲間に土地を分配する権限をもっていました。ここから権威の世襲化が発生し、それが権力となっていったことが考えられます。首長による給付にたいしては、貢納義務(労役や軍務を含む)が生じました。
首長は軍事指導者でもありました。戦いによって得られた土地は家臣に分配されました。武装の強化と軍事技術の進歩が職業的戦士身分をつくりだします。かれらは首長の命にしたがって、敵を征服し、隷属させ、その支配下にあった農民を隷農としました。
中間の非戦闘民がひとりの領主をパトロンとし、かれに仕えることで、土地の経営をゆだねられることもあります。
首長が領主として定住し、人や牛馬を多数所有して、大規模な開墾にあたるケースも生じました。開拓された土地はたいてい貸与され、貸与された者は貢納と奉仕の義務を負うことになります。貨幣や穀物が貸与されることもあります。古代ローマには多くの債務奴隷がいました。
しかし、首長の前身は軍事指導者ではなく、むしろ雨乞い祈禱者のような呪術的カリスマであることが少なくなかった、とウェーバーはいいます。かれらはタブーをつくることもでき、それによって共同体を支配しました。
もうひとつ、首長の力を大きくした要因が対外交易の掌握です。首長は交易を管理し、商人を保護し、市場特権を与える代わりに関税を要求しました。王が交易を独占する場合はエジプトのファラオのような権力が成立し、多くの貴族が商人に金融をおこなう場合は中世のヴェネツィアやジェノヴァのような貴族による都市支配が生じました。
領主経済はふたつの方向に発展します。ひとつは王侯が官僚機構をもち、経済を中央に集中する方式、もうひとつは王侯が従臣や官吏に身分を与え、かれらに土地の管理をゆだねるやりかたです。
アジアでは財政面においても国家による専制がおこなわれていましたが、ヨーロッパでは封土(レーエン)にもとづく封建制が成立しました。封土を与えられた領主は契約にもとづいて君主に仕え、貢納と軍役の義務を負いました。
一般に領主の封土は世襲されました。
もっとも純粋に封建制度を発達させたのは中世ヨーロッパです。その素地は、ローマ帝国末期の荘園制度にありました。荘園は開墾によっても征服によっても発展しました。そこに田畑を失った農民が、経済的強者の庇護を求めてなだれこんだ結果、荘園はさらに拡大することになりました。
教会にたいしても、さかんに土地の寄進がおこなわれました。こうした荘園をベースにして、ヨーロッパでは封建制が成立していきます。
荘園領主は国家権力から相対的に独立して、荘園の土地、人民、裁判権を保有することに努めました。
13世紀になると、荘園領主と荘民との義務と権利を定めた荘園法が広く適用されるようになります。その荘園法によって、領主と荘民の融和が進むようになります。農民への需要が増えたため、かつての不自由民は次第に有利な条件を得るようになり、農奴の観念は薄れていきます。
領主は次第に農民を労働力ではなく貢納者とみなすようになりました。貢納の内訳は、作物の貢納や土地の変更にともなう手数料、相続のさいの税、結婚許可料、森林や牧地の使用料などです。ただし、農民には運送賦役や道路橋梁の建設作業などが課せられていました。
領主は全土に散在する所有地をもっていました。そうした領地には荘司が派遣され、荘園の管理がおこなわれました。
そのいっぽう、中世においても自由農民の土地がなかったわけではない、とウェーバーはいいます。もちろん、こうした自由農民も領主にたいする貢納義務を負っていました。
貨幣経済が発展するようになると、荘園制度にも資本主義的要素がはいりこんできます。その結果、プランテーション(プランターゲ)と、大規模農地経営(グーツヴィルトシャフト)が誕生します。
プランテーションは強制労働にもとづき農産物を販売することを目的とする経営で、それ自体は古くから存在します。古代においてはプランテーションでワインやオリーブオイルがつくられ、近世ではサトウキビ、タバコ、コーヒー、綿花などがつくられました。
合衆国南部のプランテーションは、綿花産業の大発明により綿花の需要が急増したことからはじまります。アフリカ大陸から大勢の黒人奴隷がつれてこられました。19世紀にはいり奴隷の輸入が禁止されたあとも、南部では奴隷を養成するかたちで、プランテーションが維持されます。
もうひとつの方向は、荘園を商品生産に適合する大規模経営に改編することでした。大規模経営には、牧畜と農耕、さらには両者混合のパターンがありました。
南アメリカのパンパスでは、小規模資本による大規模牧畜がはじまります。スコットランドでは1746年のカロデンの戦い以降、スコットランドの独立が失われ、新たな動きが生じました。領主たちは氏族の小作人たちを追いだし、その土地を牧羊地に変えていきます。その背景には14世紀以来のイングランド羊毛工業の発達があります。イングランドでは早くから農民を土地から追いだす囲い込み運動がはじまっていました。
囲い込み運動の目的は大規模な牧地経営により羊毛を確保することでしたが、穀物を大量生産することにも重点が置かれていたといってよいでしょう。1846年の穀物関税撤廃にいたるまでの150年間、イギリスでは穀物にたいする保護関税のもと、小農民が土地を奪われ、大規模農業化が進展していたのです。
ドイツの西部・南部と東部では、荘園の形態がずいぶんことなります。西部・南部では荘園は分散し、農民は年貢を取り立てられるだけなのに、東部のフロンホーフ(荘園)では貴族の大領地が存在していました。大領地農場経営が進展したのは東部においてです。ここでは領地に付属する世襲的な農業労働者(インストマン)が農場を支えていました。
しかし、荘園制度はついに崩壊するにいたります。荘園の崩壊は、農民や農業労働者の人格的解放と移動の自由、荘園の土地の解放をもたらしました。それだけではありません。荘園制の崩壊は、領主の特権や封建的束縛を奪うことになります。
荘園制度崩壊のかたちは一様ではない、とウェーバーはいいます。
イギリスのように農民から土地が収奪された場合、農民は自由になりましたが、土地を失いました。フランスのように荘園領主から土地が収奪された場合は、領主が土地を失ったのにたいし、農民は自由と土地を得ました。領主と農民の妥協により、農民が土地の一部を得た場合もあります。
荘園制の崩壊をもたらした内的な要因は、貨幣経済の進展により農産物市場が拡大し、領主も農民もその生産物を売る機会に敏感になったことです。しかし、それだけなら、むしろ領主による農民収奪と大規模経営を強めただけで終わったかもしれません。
重要なのは、むしろ外的な要因だった、とウェーバーはいいます。
それは、都市のブルジョワ層が、荘園制度を市場の障害とみるようになったことです。農民が荘園に縛りつけられているかぎり、労働力の供給はおぼつかないし、また商品の購買力もかぎられてしまいます。そのため、都市のブルジョワ階級は農場領主の支配に敵対するようになった、とウェーバーは論じています。
初期の資本主義産業は、ツンフト(職人ギルド)の支配を避けて、直接地方の労働力を利用したいと考えていました。自由な労働力を確保するためには荘園の存在が大きな障害となりました。
土地自体にたいする営利的関心も、封建的束縛から土地を解放することを求めていました。さらに国家自体も、荘園の崩壊によって、かえって農村の租税収入が増えると期待するようになります。
ウェーバーは荘園崩壊をもたらしたさまざまな要因を挙げています。しかし、ここでは各国の状況をこと細かに紹介する必要はないでしょう。
イギリスのように市場の力が荘園を崩壊させたケースもあれば、フランスのように革命が荘園を葬り去ったケースもあるというにとどめておきましょう。農奴解放宣言が荘園解体のきっかけになったケースもあります。
いずれにせよ、各国それぞれの事情をともないつつ、荘園は解体され、今日の農業制度がつくられていきました。
ウェーバーはこうまとめています。
貨幣経済の進展とともに、囲い込みや分割、再編によって荘園制は崩壊し、共有地の遺物も消し去られて、土地の個人的私有制が実現した。
家族共同体はひじょうに小さくなり、いまや妻子を有する家長が個人的私有財産の担い手となるにいたった。家族の機能は消費に局限されるようになり、家族は共産制から遠く離れて、所有財産の相続ばかりを配慮する存在となった。そうした家族の変形が、資本主義の発展と密接にかかわっていることはいうまでもない、と。
それでは、資本主義はいったいどこからやってきたのでしょう。それが次の課題となります。
本書『一般社会経済史要論』は1919年から20年にかけての冬学期にミュンヘン大学でおこなったウェーバーの講義を、本人のメモや聴講した学生の筆記にもとづいて再現したかれの最後の講義録です。
ドイツで原著が発行されたのが1924年、日本では1927年に黒正巌(こくしょういわお)(大阪経済大学教授)の訳で岩波書店から刊行されました。それを敗戦後に青山秀夫(京都大学経済学部教授)が改訳して、1954年に岩波書店から再刊されたのが本書です。1946年夏に最初の訳稿をザラ紙の原稿用紙に浄書したのが、学生の森嶋通夫(のちロンドン・スクール・オブ・エコノミクス教授)らだったというあたりが、学の系譜を感じさせます。
ウェーバーは本書で、近代資本主義がなぜ西洋において発生したのかを追及しています。近代資本主義という言い方からしても、それがけっして否定的に語られているわけではないことが想像できるでしょう。
出発点となるのは、農村共同体モデル、とりわけゲルマン的共同体です。
古代ゲルマン人は村落を形成して暮らしていました。その村がどんなものかというと、何層もの円をイメージしてみればよいでしょう。円の中心には数々の屋敷が存在します。円の二層目は垣をめぐらせた庭です。そして三層目が農耕地。四層目が牧地で、最後の五層目に森林が広がっています。土地は共有されているわけではなく、居住者にそれぞれ一定の持ち分が与えられていました。
耕地は三圃式(さんほしき)によって営まれています。第一区画には冬穀物、第二区画には夏穀物がつくられており、第三区画は休閑地です。その区画は年ごとに入れ替わって輪作されます。
村長は村の収穫を管理し、村の秩序を維持する役目を果たしていました。家屋や土地は村人の持ち分として専有され、相続されました。
村々は集まってマルク共同体を形成しました。森林や荒蕪地(こうぶち)を共同マルクとして所有していたのです。そうした森林や荒蕪地は個々の村落共同体に帰属せず、あくまでもマルク共同体に属していました。
8世紀末のカロリング朝以前に、こうしたマルク共同体はすでに誕生していたようです。マルクの長は世襲され、国王や領主によって任命されるのが通例でした。
共同体の構成員は原則的に平等です。しかし、家族が増減したりすると、耕地の所有に差が出てきます。手工業者など新たな労働力の到来も耕地の所有に影響を与えました。さらに国王や諸侯、領主などによる開墾もあって、マルク共同体のかたちは次第に崩れていきます。
ゲルマン的な共同体は、エルベ川とウェーザー川のあいだだけではなく、南ドイツ、スカンディナビア、ベルギー、北フランス、エルベ川の東方、イギリスの一部にまで広がっていました。
ドイツの南東部にはスラブ的な家族共同体がはいりこみ、それがバルカン半島へと広がっていました。そして、南西部にはローマ的な大土地所有形態が残存していました。
スコットランドやアイルランドにはケルトの共同体が存在しました。その最古のかたちは家畜経済です。いっぽう、ロシアにはミールと呼ばれる農村共同体が存在し、実際にはクラークと呼ばれる土豪が村を仕切っていました。そのミールは古代から存在したわけではなく、租税制度と農奴制の産物だったとウェーバーはいいます。ロシアの租税と農奴制はあまりにも苛酷でした。
ここで問題は、共同体のなかから、どのようにして領主の権力と財産が生じたかです。
最初に首長の権威がありました。首長は仲間に土地を分配する権限をもっていました。ここから権威の世襲化が発生し、それが権力となっていったことが考えられます。首長による給付にたいしては、貢納義務(労役や軍務を含む)が生じました。
首長は軍事指導者でもありました。戦いによって得られた土地は家臣に分配されました。武装の強化と軍事技術の進歩が職業的戦士身分をつくりだします。かれらは首長の命にしたがって、敵を征服し、隷属させ、その支配下にあった農民を隷農としました。
中間の非戦闘民がひとりの領主をパトロンとし、かれに仕えることで、土地の経営をゆだねられることもあります。
首長が領主として定住し、人や牛馬を多数所有して、大規模な開墾にあたるケースも生じました。開拓された土地はたいてい貸与され、貸与された者は貢納と奉仕の義務を負うことになります。貨幣や穀物が貸与されることもあります。古代ローマには多くの債務奴隷がいました。
しかし、首長の前身は軍事指導者ではなく、むしろ雨乞い祈禱者のような呪術的カリスマであることが少なくなかった、とウェーバーはいいます。かれらはタブーをつくることもでき、それによって共同体を支配しました。
もうひとつ、首長の力を大きくした要因が対外交易の掌握です。首長は交易を管理し、商人を保護し、市場特権を与える代わりに関税を要求しました。王が交易を独占する場合はエジプトのファラオのような権力が成立し、多くの貴族が商人に金融をおこなう場合は中世のヴェネツィアやジェノヴァのような貴族による都市支配が生じました。
領主経済はふたつの方向に発展します。ひとつは王侯が官僚機構をもち、経済を中央に集中する方式、もうひとつは王侯が従臣や官吏に身分を与え、かれらに土地の管理をゆだねるやりかたです。
アジアでは財政面においても国家による専制がおこなわれていましたが、ヨーロッパでは封土(レーエン)にもとづく封建制が成立しました。封土を与えられた領主は契約にもとづいて君主に仕え、貢納と軍役の義務を負いました。
一般に領主の封土は世襲されました。
もっとも純粋に封建制度を発達させたのは中世ヨーロッパです。その素地は、ローマ帝国末期の荘園制度にありました。荘園は開墾によっても征服によっても発展しました。そこに田畑を失った農民が、経済的強者の庇護を求めてなだれこんだ結果、荘園はさらに拡大することになりました。
教会にたいしても、さかんに土地の寄進がおこなわれました。こうした荘園をベースにして、ヨーロッパでは封建制が成立していきます。
荘園領主は国家権力から相対的に独立して、荘園の土地、人民、裁判権を保有することに努めました。
13世紀になると、荘園領主と荘民との義務と権利を定めた荘園法が広く適用されるようになります。その荘園法によって、領主と荘民の融和が進むようになります。農民への需要が増えたため、かつての不自由民は次第に有利な条件を得るようになり、農奴の観念は薄れていきます。
領主は次第に農民を労働力ではなく貢納者とみなすようになりました。貢納の内訳は、作物の貢納や土地の変更にともなう手数料、相続のさいの税、結婚許可料、森林や牧地の使用料などです。ただし、農民には運送賦役や道路橋梁の建設作業などが課せられていました。
領主は全土に散在する所有地をもっていました。そうした領地には荘司が派遣され、荘園の管理がおこなわれました。
そのいっぽう、中世においても自由農民の土地がなかったわけではない、とウェーバーはいいます。もちろん、こうした自由農民も領主にたいする貢納義務を負っていました。
貨幣経済が発展するようになると、荘園制度にも資本主義的要素がはいりこんできます。その結果、プランテーション(プランターゲ)と、大規模農地経営(グーツヴィルトシャフト)が誕生します。
プランテーションは強制労働にもとづき農産物を販売することを目的とする経営で、それ自体は古くから存在します。古代においてはプランテーションでワインやオリーブオイルがつくられ、近世ではサトウキビ、タバコ、コーヒー、綿花などがつくられました。
合衆国南部のプランテーションは、綿花産業の大発明により綿花の需要が急増したことからはじまります。アフリカ大陸から大勢の黒人奴隷がつれてこられました。19世紀にはいり奴隷の輸入が禁止されたあとも、南部では奴隷を養成するかたちで、プランテーションが維持されます。
もうひとつの方向は、荘園を商品生産に適合する大規模経営に改編することでした。大規模経営には、牧畜と農耕、さらには両者混合のパターンがありました。
南アメリカのパンパスでは、小規模資本による大規模牧畜がはじまります。スコットランドでは1746年のカロデンの戦い以降、スコットランドの独立が失われ、新たな動きが生じました。領主たちは氏族の小作人たちを追いだし、その土地を牧羊地に変えていきます。その背景には14世紀以来のイングランド羊毛工業の発達があります。イングランドでは早くから農民を土地から追いだす囲い込み運動がはじまっていました。
囲い込み運動の目的は大規模な牧地経営により羊毛を確保することでしたが、穀物を大量生産することにも重点が置かれていたといってよいでしょう。1846年の穀物関税撤廃にいたるまでの150年間、イギリスでは穀物にたいする保護関税のもと、小農民が土地を奪われ、大規模農業化が進展していたのです。
ドイツの西部・南部と東部では、荘園の形態がずいぶんことなります。西部・南部では荘園は分散し、農民は年貢を取り立てられるだけなのに、東部のフロンホーフ(荘園)では貴族の大領地が存在していました。大領地農場経営が進展したのは東部においてです。ここでは領地に付属する世襲的な農業労働者(インストマン)が農場を支えていました。
しかし、荘園制度はついに崩壊するにいたります。荘園の崩壊は、農民や農業労働者の人格的解放と移動の自由、荘園の土地の解放をもたらしました。それだけではありません。荘園制の崩壊は、領主の特権や封建的束縛を奪うことになります。
荘園制度崩壊のかたちは一様ではない、とウェーバーはいいます。
イギリスのように農民から土地が収奪された場合、農民は自由になりましたが、土地を失いました。フランスのように荘園領主から土地が収奪された場合は、領主が土地を失ったのにたいし、農民は自由と土地を得ました。領主と農民の妥協により、農民が土地の一部を得た場合もあります。
荘園制の崩壊をもたらした内的な要因は、貨幣経済の進展により農産物市場が拡大し、領主も農民もその生産物を売る機会に敏感になったことです。しかし、それだけなら、むしろ領主による農民収奪と大規模経営を強めただけで終わったかもしれません。
重要なのは、むしろ外的な要因だった、とウェーバーはいいます。
それは、都市のブルジョワ層が、荘園制度を市場の障害とみるようになったことです。農民が荘園に縛りつけられているかぎり、労働力の供給はおぼつかないし、また商品の購買力もかぎられてしまいます。そのため、都市のブルジョワ階級は農場領主の支配に敵対するようになった、とウェーバーは論じています。
初期の資本主義産業は、ツンフト(職人ギルド)の支配を避けて、直接地方の労働力を利用したいと考えていました。自由な労働力を確保するためには荘園の存在が大きな障害となりました。
土地自体にたいする営利的関心も、封建的束縛から土地を解放することを求めていました。さらに国家自体も、荘園の崩壊によって、かえって農村の租税収入が増えると期待するようになります。
ウェーバーは荘園崩壊をもたらしたさまざまな要因を挙げています。しかし、ここでは各国の状況をこと細かに紹介する必要はないでしょう。
イギリスのように市場の力が荘園を崩壊させたケースもあれば、フランスのように革命が荘園を葬り去ったケースもあるというにとどめておきましょう。農奴解放宣言が荘園解体のきっかけになったケースもあります。
いずれにせよ、各国それぞれの事情をともないつつ、荘園は解体され、今日の農業制度がつくられていきました。
ウェーバーはこうまとめています。
貨幣経済の進展とともに、囲い込みや分割、再編によって荘園制は崩壊し、共有地の遺物も消し去られて、土地の個人的私有制が実現した。
家族共同体はひじょうに小さくなり、いまや妻子を有する家長が個人的私有財産の担い手となるにいたった。家族の機能は消費に局限されるようになり、家族は共産制から遠く離れて、所有財産の相続ばかりを配慮する存在となった。そうした家族の変形が、資本主義の発展と密接にかかわっていることはいうまでもない、と。
それでは、資本主義はいったいどこからやってきたのでしょう。それが次の課題となります。
荻生徂徠『政談』をめぐって(3)──商品世界ファイル(25) [商品世界ファイル]
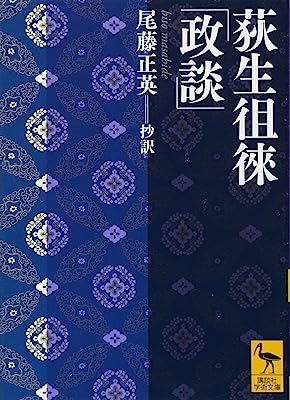
徂徠が徳川吉宗に重用されたのは、あくまでも儒学者の政道アドバイザーとしてでした。徂徠からすれば、経済問題は政治の一部でしかありません。経済をただすことが、政治の役割でもあります。そして、商品世界の膨張を抑え、人びとが地に着いて、よくはたらき、大地の恵みとその恵みを活かす工夫を重ね、心豊かにくらしていく世をつくることが、理想の政道と考えられていました。
ここで徂徠の統治論に触れる必要はないでしょう。徂徠は、政治機構や人材登用のあり方を含め、統治上のさまざまな制度改革についても触れていますが、それを細かく紹介するのはやめておきましょう。
ただ、気がつくのは、徂徠が政治上のルールづくりにこだわっていることです。アイデア倒れも多いのですが、『政談』ではこまごまとした規則を次から次に提案しています。
これでは規則でがんじがらめになってしまいそうですが、日本人はもともと規則好きなのかもしれません。道徳好きというより、どちらかというと規則好き。規則が道徳だと思っているふしもあります。逆に規則さえ守っていれば、あとは自由、そんなところが徂徠の考え方にもあるようです。
『政談』の跋文に、徂徠はこれまで書いてきたことのまとめとして、こんなふうに欠いています。
〈肝腎なところは、世の中が旅宿の境遇であることと、万事につけて礼法の制度がないこととの、二つに帰着する。このために、戸籍をつくり、万民を居住地に結びつけることと、町人・百姓と武家との間に礼法上の差別を立てることと、大名の家の生活に礼法の制度を立てることと、お買い上げということがないようにすることと、だいたいこれらで世の中はまともになって豊かになるであろう。〉
徂徠は道の人であり、制度論者でもありました。礼法上のこまかいルールをつくって、商品世界の広がりを抑制し、人を地につけさせ、武士が知行地を直接収めて、農民に貢納を命じ、統治を盤石なものにする。徂徠にとっては、昔に戻ることこそが、政道を立てなおす方策にほかなりませんでした。
ここで、ぼくは山片蟠桃(1748〜1821)の名前を挙げてみたいという誘惑にかられます。徂徠(1666〜1728)と蟠桃は、活躍したのが、江戸の中期と後期と時代もちがえば、立場もちがいます。蟠桃は大坂の町人で、徂徠は江戸の儒者。そこで、蟠桃が経済をどのようにとらえていたかを紹介することで、徂徠の『政談』とのちがいが浮かびあがってくるかもしれません。
なお、山片蟠桃について詳しく知りたい方は、拙著『蟠桃の夢』、『山片蟠桃の世界』などをご覧ください。
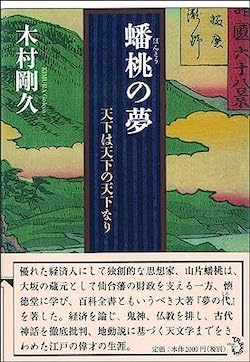

蟠桃の経済論は儒教の聖典への疑問から出発します。儒教の道が求めるのは、欲求をできるかぎり抑えて、消費を最低必要限の衣食住にしぼる世界です。しかし、人の自然な欲求にたがをはめるのがいかにむずかしいか、蟠桃は百も承知しています。それでは、人の欲求は際限なく広がり、この世界を食い尽くしてしまうのでしょうか。
儒教の聖典を読み解きながら、蟠桃は思わず「道ははるかに遠い」という感慨をもらしています。「いにしえは質朴礼譲を教え、孝弟忠信さえ教えさえすれば、天子が何をしなくても世の中はおさまった」。しかし、もう昔に戻ることは無理です。徂徠のように、昔に戻るという発想を蟠桃はとりません。
ここで、蟠桃がもちだすのは、師である中井履軒(りけん)の『有間星(あらまほし)』という著作です。履軒はここで、いわば「一国経済モデル」をえがき、社会の経済循環構造を示しました。
抽象化していえば、それは武士と農民、商工業者の3部門からなる経済モデルです。
(1)生産階級である農民は、食料や衣服、その他の原料を生みだす。
(2)武士階級は農民を保護する代わりに農民から年貢を受けとる。
(3)そして、商工階級は年貢である米を流通させ、また武士や農民の要望に応じて必要な製品をつくる。
これは政府と生産、流通の3部門から成り立つ社会で、貨幣(による消費)を媒介として、経済がとどこおりなく循環すれば、社会は定常的に安定すると、蟠桃は考えました。ここで蟠桃は政治支配一色ではない「経済社会」を発見したといえるでしょう。
蟠桃によれば、経済社会にたいする幕府の役割は限定されます。
(1)戸籍(人別)の掌握
(2)貧民にたいする救済措置
(3)劇場芝居、売春、捨て子など風俗にたいする取り締まり
(4)殺人、盗賊、放火などの犯罪取り締まり
アダム・スミスは、国家の活動を防衛のための備え、民衆の保護、公共事業に限定しましたが、蟠桃もまたスミス同様、経済社会の循環構造に幕府が過干渉することをいましめていました。まして、政治が腐敗(利権を私物化)することなど、あってはならないことです。
蟠桃は実務家です。升屋の大番頭として、主家ばかりでなく伊達藩の財政立て直しにあたってきました。その経験を通じて、みずから発見したひとつの知があります。それを蟠桃は「大知」と名づけました。
蟠桃の主著『夢の代』の「経済」篇には、中井履軒から受け継いだ「経済社会」のモデルとともに、この「大知」のことが記されています。
「大知」とはいったい何でしょう。
蟠桃は最初に古代の聖人、舜が「大知」として知られているのは、「私知」を捨てて衆知を活用したからだと前置きして、現在では大坂の米市場こそ「天下の知恵を集め、血液を通わせ、集大成する場」となっていると述べます。
つまり、現在の「大知」とは「市場」のことだといってよいでしょう。
市場は人のからだにたとえれば、血液の流れをコントロールする心臓であって、この市場を力ずくで廃止したり、無理やり動かそうとしたりしても、かえって社会全体にひずみが出てしまいます。そして、大坂の米市場では、現物取引と先物取引がおこなわれ、市場の継続性と安全性、大量の取引が保証されているのだと強調します。
蟠桃の考え方は「天下は天下の天下なり」という言葉に集約されます。天下は武士の天下でも商人や農民の天下でもありません。それは人びとの協働によって成り立っています。
渾然一体となった社会の構造が、天下の人とものの流れを維持しているのです。武士が武士としての役割を果たさず、商人や農民がその務めを放棄するなら、天下の流れはたちまちにして乱れてしまいます。それぞれが他者との関係において自己の役目を自覚し、天下に正しい流れをもたらすよう自分の持ち場において最善を尽くすべし、というのが蟠桃の考えでした。
経済社会と市場の発見は、蟠桃に経済の方向性を指し示しました。それは武士秩序の再興という徂徠の方向性とは大きく異なるものでした。
とはいえ、蟠桃の考察もあくまでも幕藩体制の存在を前提としていたことはまちがいありません。当時、日本にはロシアやイギリスが接近し、幕藩体制が危機にさらされていることは蟠桃も認識していました。しかし、幕藩体制が崩壊するなどとは思ってもみなかったでしょう。
幕藩体制が崩壊し、中央集権的な明治政府が誕生したあとも、経済社会と市場はなくてはならないものだという共有知は存続しました。蟠桃の存在はそれほど知られていたわけではありませんが、早くから経済社会の実際(良きにつけ悪しきにつけ)を認識していたことは、蟠桃の功績として残るのではないでしょうか。
いっぽう、商品世界の膨張を抑え、人びとが地に着いて暮らすという徂徠の古代的理念もけっして消滅したわけではありませんでした。それはユートピア的ではありますが、どこか人をひきつけるものがあります。
先人の知に思いを馳せながら、われわれはいまを見すえるほかないのかもしれませんね。
荻生徂徠『政談』をめぐって(2)──商品世界ファイル(24) [商品世界ファイル]
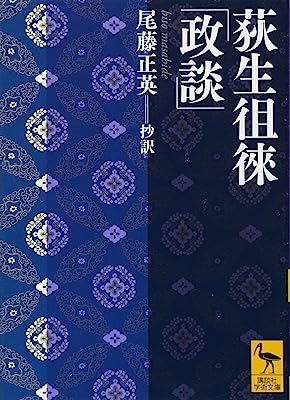

荻生徂徠にとって経済政策とは、経済の野放図な動きを抑えて、経済に振り回されない安定した政道を実現することにほかなりませんでした。
世が乱世となる原因は、生活が困窮するからだと書いています。天下を治めるには、まず経済を豊かにすることだともいいます。これには、だれも異論がないでしょう。
そこで、たとえば幕府がカネをばらまくとしましょう。一時的には、たしかに世の困窮が救えるかもしれません。しかし、そんなことをすれば、幕府の金蔵がからっぽになって、そのうち幕府自体がたちゆかなくなります。その結果どうなるかというと、今度は大増税です。これでは、困窮を救ったことになりません。
もっと根本を見なければなりません。どうしたらいいのでしょう。徂徠が唱えるのは、またも人を「土地に着ける」という原則です。
「古代の聖人が立てた法制の基本は、上下万民をみな土地に着けて生活させることと、そのうえで礼法の制度を立てることである」
ところが、江戸中期はどうだったかというと、上下みな「旅宿の境遇」にあり、加えて万事に礼法の制度が欠けている。つまり、毎日ふらふらと、しかも、あわただしく、ケセラセラで暮らしている。だから、よぶんな出費がかさんで、いつもおカネが足らず、ピーピーしているというのが、徂徠の見たてでした。
土地に着いて、しっかりとはたらき、おカネのかからない生活をする。それは武士も同じで、武家は知行地に居住して、地元に家族を置いたまま、4カ月にひと月というような割合で江戸勤務をするようにすればいいというのです。礼法と格式を守り、流行に流されないようにし、できるだけカネを使わないことが大事だと言います。
しかし、いまの時代がどうかというと、「知行の米を売り払って金にして、商人の手を借りなければ日々の生活が立ちゆかないために、商人の勢いが盛んになり、自然に経済の実権を商人に取られて、このとおり町人にとって極楽の世の中になっている」と徂徠は嘆きます。
何ごともカネの世の中で、幕府の財政もきびしくなっています。そこで、徂徠は貢納という奥の手を案出します。越前藩からは奉書紙、会津藩からは蝋燭と漆、南部藩、相馬藩からは馬、上州の諸藩や加賀藩からは絹、仙台藩や長州藩からは紙を収めさせるようにすればいいのです。また木曽や熊野の山林、金銀銅鉄鉛の出る山、魚のとれる銚子や小田原は直轄にして、その産品を幕府が管理します。工事に必要な人足のたぐいは日雇いで雇い入れるのではなく、旗本の下人ならびに江戸町人の負担でまかなうことにします。こうすれば、幕府の歳出もぐっと圧縮されるはずです。
諸大名の財政が窮迫する原因も、年貢米をカネに変え、それを江戸で使い捨てているためだと徂徠はいいます。とりわけ奥向きのぜいたくが目にあまるものになっていました。どこの藩はどうしているという噂を聞いて、つい見栄を張り、いらぬものにカネを費やしてしまいます。
大名の財政は膨張するいっぽうで、このままでは収拾がつかなくなるだろう、と徂徠は言います。まずだいじなのは、各大名が官位や石高に応じて、礼法と格式を定め、あまり見栄をはらないようにするということ。それから江戸で使用するものは、できるだけ国元の産品にして、しかもそれをカネで買わないようにせよといいます。もちろん、江戸勤めの家来は最小人数にしぼらなければなりません。
徂徠の提案によれば、旗本、御家人も含め、武士は知行所に居住するのが原則です。武士が知行所にいれば、百姓に養蚕をさせたり、山に植林をさせたり、ウルシやコウゾを育てさせたりと、まさに地元の殖産を導くことができるはずです。もちろん、江戸にいるよりカネはかからないから、いまのように困窮することはありません。
ここでもう一度確認しておくと、江戸時代はコメ経済を基本としていました。コメを年貢として徴収し、それを販売したおカネで、武士の生活がいとなまれていました。経済を担うのはもちろん農民ですが、貨幣経済という狭い領域でみれば、いわば武士中心の経済が成立していたわけです。
しかし、経済の実権は武士ではなく、商人に移ろうとしていました。商品に頼る生活が、武士経済を圧迫していたともいえます。徂徠の改革案は、武士を村の領主に戻すことによって、できるだけ商品世界の渦をちいさくし、それによって社会を安定させようとするものでした。時計の針を逆に戻すような反時代的で、超保守的な構想といえますが、どこか牧歌的なユートピアの味わいもあります。
徂徠は武士層が困窮化しているのは、よけいな費えが多いからであり、その背景には社会全体で商品化が進んでいるからだと考えました。そこで商品化の勢いを逆転させるためには、いわば贈与経済を復活するしかないと思ったわけです。つまり城下に集められている武士が、それぞれ領主として知行地に戻り、農業を指導するかたわら、百姓から地代として直接、米を含む諸産品を収めさせるようにすれば、生活はほとんどそれで間に合い、たいしておカネを使わなくてもすむだろうと判断したわけです。

話変わって、ここで徂徠はライバルの新井白石に対抗して、物価を論じます。徳川幕府が金銀銭の三貨を鋳造したことは特筆すべきことでした。それによって、社会の安定性が保たれるようになっただけではなく、経済が発展するようになるからです。三貨のうち、とりわけ銭貨は大量に発行され、これまでの宋銭や永楽銭などに取って代わり、新たな小口貨幣が都市、農村で広く使われるようになりました。
徂徠は物価について、こんなふうに書いています。
〈現在の金貨の数量は、元禄金や乾字金(けんじきん)のころに比べて品質が良くなった代わりに、流通量は半分になり、銀貨は四ツ宝銀(よつほうぎん)のときの3分の1になっている。だから物価は、元禄金や乾字金のころより半分以内に下がらなければ、まだ元の水準になったとはいえない。まして今から四、五十年以前と比較すれば、たいてい10倍か20倍になっている。したがって人々が困窮するのも当然で、これを下げるための方法を考えなければならないのである。〉
少し解説が必要です。
幕府は慶長年間(1600年ごろ)に幣制を統一し、そのとき純度84.29%の金貨と純度80%の銀貨を発行しました。これが、慶長小判、慶長丁銀と呼ばれるものです。さらに寛永13年(1636年)には銅銭の寛永通宝を発行し、これにより三貨による通貨体制を確立しました。
ところが、幕府の財政難が進んだため、元禄8年(1695年)に、金の純度を57.36%、銀の純度を64%に下げた元禄小判(元禄金)、元禄丁銀がつくられます。さらに宝永8年(1711年)には純度20%の四ツ宝銀も出されました。その結果、巻き起こったのが猛烈なインフレで、このとき米価は80%以上上昇したといわれます(いわゆる元禄バブル)。
この事態に立ち上がったのが、7代将軍家宣を補佐した新井白石で、白石はインフレを退治するために、ふたたび貨幣の純度を慶長古金銀と同率に戻します。これが正徳4年(1714年)の改鋳です。
ただし、その前の宝永7年(1710年)にも改鋳があり、このときは元禄金より純度の高い乾字金がだされました。徂徠が触れているものです。
ところが、正徳の改鋳以降、約20年にわたって、今度は米価が毎年下がりつづけます。ピークから65%下がったといいますから、相当の下落でした。長期にわたるデフレが発生し、ただでさえねたまれている白石に非難が集中します。
家宣のあと将軍の座に着いた徳川吉宗は、元文元年(1736年)にリフレ政策に踏み切ります。ふたたび小判の純度を48%、丁銀の純度を57.5%に落とし、通貨流通量を増やしました。当初、物価は上昇しましたが、そのうち安定を取り戻します。吉宗は経済規模の拡大と財政再建をめざして、積極的な新田開発や産業政策、物価対策に乗りだしていきます。これがいわゆる「享保の改革」で、幕府の三大改革(残りは「寛政の改革」と「天保の改革」)のうちでは、唯一成功した改革だといわれます。
徂徠は元禄のインフレと正徳のデフレを経験しています。そして、デフレがつづく当時の状況において、人びとの困窮がつづくのは、まだ物価が下がりきっていないためだと判断しているところが、やはり徂徠らしいところです。もっとデフレになってしかるべきだというわけです。
享保の改革で、徳川吉宗は徂徠の策を用いず、通貨量を拡大するリフレ政策を採用します。新井白石の政策が招いたデフレにかわって、一時、急激なインフレが進行しますが、実質経済の拡大にともなって、物価も次第に落ちついてきます。これらのことは、徂徠死後のできごとです。
物価にたいする徂徠のアプローチは独特です。『政談』では、デフレで物価が下がっているにもかかわらず、それでもまだ物価が高いといらだって、その理由を次のように列挙しています。
(1)商人が品物の値段をせりあげ、もうかった部分の一部を運上として、大名などに納めている。
(2)費用のかかる江戸居住費が価格に転嫁されている。
(3)江戸に集まった町人が贅沢をするようになり、需要が拡大した。
(4)これを見た田舎の者も町人に負けじと贅沢をするようになった。
(5)商人が情報を交わし、結束して、物価を下げないようにしている。
(6)物が遠方から運ばれ、その運送費がかさむようになっている。
(7)商人が価格を維持し利益を確保するために生産量を調整している。
これらはたしかに物価高を招く原因でしょう。しかし、そのようなことは、すべて枝葉末節だというところが、いかにも徂徠です。
〈すべては武家が旅宿の境遇にあるというところから出た悪弊なのであるから、その根本に立ち返って、武家をことごとく土地に居住させておいて……米の貯蔵という一つの術を用いるならば、商人の勢いはたちまちに衰えて、物の値段も思いのままになるであろう。〉
またお馴染みの議論が出てきましたね。「旅宿の境遇」にある武家を知行地に戻し、カネによる悪弊を取り除くことが根本だというわけです。「米の貯蔵の一つの術」というのは、できるだけ商人に米を売らないようにすることで、米の販売価格を高めに維持するという秘策でした。武士は知行地で、できるだけ自給自足の生活をし、米をたくわえるようにし、そのごく一部だけを高値で商人に売って、貨幣収入を得、生活の足しにすべしというのです。武士のことしか考えていない身勝手な政策といえるかもしれません。
そのいっぽう、徂徠は新井白石の金融引き締め政策を猛烈に批判しています。
金銀の数量が減少すると、なぜ世間が困窮するのでしょうか。徂徠によると、それは手元のお金が減るとコメが買えなくなり、それによって米価が下がり、コメを売って生活する武家や百姓の収入も減ってしまうからだというのです。豊作で供給が過剰になり、コメが値崩れするのとは、ちがう局面でした。
加えて、慶長年間から百年たち、生活は知らず知らずのうちに贅沢になっています。定まった礼法がないために、暮らしの出費が増え、下男などの給金は上がったにもかかわらず、その給金だけで生活するのは苦しくなっていました。幕府も出費のほうが多くなり、収蔵してある金を取り崩して、赤字を埋めているのが実情でした。
ここで徂徠はまた持論をもちだします。物価が高くなったのは、元禄の改鋳によって、金銀貨の品位が低下したためではないと言い張るのです。武家が旅宿の境遇にいることと、社会に礼法の制度がないこと、それに商人の勢いが盛んになったことがいけない。これをそのまま放置しておいて、白石のように金銀の流通量を半分に減らしたのでは、購買力が半分になり、世の中が困窮するのは、あたりまえだといいます。
さしあたり世の中の景気をよくするには、銅銭を大量に鋳造するのがいちばんよい方法だと徂徠は提案します。ただし、銅銭の公定レートを1両=4貫(4000枚)ではなく、1両=7貫か8貫にすればいいといいます。そうすれば金銀貨の量をそのままにしておいても、貨幣発行量全体は増えるので、購買力が回復するはずだというわけです。できるだけ大口貨幣を用いず、小口貨幣ですませるようにすれば、贅沢も減ると考えていたのでしょうか。
徂徠は銅銭の大量発行にこだわります。銭は便利な小口貨幣であるため、田舎にも浸透し、そのため不足がちになっている。長崎から海外に流出していることも、不足を招く原因だ。そこで、無用な末寺の鐘や、使われていない銅製の器具などを鋳つぶせば、少しは足しになる。また銅銭は運ぶのが重いので、諸大名にも鋳造を許すようにすればいいというのです。
しかし、金銀貨の品位を元禄時代並みに下げ、幕府がみずからの利益を考えないで、金銀貨の発行量を増やしていけば、銅銭をそれほど大量発行する必要もなくなるという反論も成り立つでしょう。事実、徂徠の死後、元文の改鋳はこの方向でなされました。
ここで興味深いのは、徂徠が信用制度の確立にふれていることです。金銀が世の中に流通しないのは、それが金持ちの手に固まっているからだ。金銀の数量が減少したうえに、貸借の道がふさがれば金銀が不足して、人々が難儀する。
そこで、徂徠は貸借ルールを定めるべきだと主張します。一定の利息を決め、法外の高利は禁止し、「一元一利(元金1に対し利息1の割合)の法によって、利息の総額が元金と同じ額に達したならば、それ以上は利息を払わず、元金だけをなし崩しに返済してゆけばよい」ことにする。高利にたいする規制と徳政の勧めです。
礼法についてもあらためて述べています。礼法を定めるのは、上下とも倹約を守り、贅沢をしないようにするためです。武家については、格式や俸禄におうじて衣食住のあり方を定めることはいうまでもありません。町人や百姓についても、徂徠はずいぶんこまかく規制をもうけています。
なぜ、そんなことをする必要があるのでしょう。
〈このようにするのは、何も町人・百姓を憎むわけではない。彼らの生活が、右にのべたとおり贅沢になって、出費が多く、生活費がかさむのが今では普通になっているから、このような制限の法規が出されるのは、彼らにとってもよいことなのである。
何度も書きますが、徂徠にとっては、金融政策や物価対策などは枝葉末節でした。人を地に着かせること、武士が知行所に居住すること、そして礼法を定め、商品の流通を制限し、贅沢をなくすことが、なんといっても改革の根幹でした。高利を求めて世渡りする商人は規制してしかるべき存在でした。
しかし、商品世界の波は幕府の支配体制を次第に掘り崩していくことになります。徂徠の唱える「先王の道」をもってしても、おカネの力を阻止するのは容易なことではありませんでした。
荻生徂徠『政談』をめぐって(1)──商品世界ファイル(23) [商品世界ファイル]
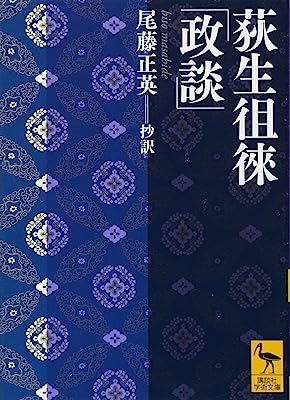

荻生徂徠(おぎゅう・そらい、1866〜1728)は、同時代の新井白石と並び称される江戸時代屈指の儒者といってよいでしょう。医者をしていた父が、仕えていた館林藩主徳川綱吉(のち5代将軍)の怒りにふれ江戸から放逐されたため、14歳から27歳まで母の実家があった上総の長柄(ながら)郡本納(ほんのう)村(現千葉県茂原市本納)で過ごしました。
27歳(本人の言では25歳)で江戸に戻り、塾を開き、31歳になって川越藩主の柳沢吉保に仕えます。44歳のとき、藩邸を離れ、茅場町に住居を定め、多くの門人を育てました。50代半ばから徳川吉宗に重用され、幕府の政治について意見を求められるようになります。その意見をまとめたものが今回紹介する『政談』です。おもな著書としては、ほかに『弁道』『弁名』『論語徴』『太平策』などがあります。
江戸時代、儒学の主流だった朱子学を批判して、独自の古文辞学(徂徠学)を開いたことで知られます。「道として民を利することができなければ、それを道と呼ぶことはできない」というのが、かれの信念です。
『政談』はあるべき国家の制度や政道を論じた著作といえるでしょう。その根底には、乱れた政道をただすという意識があります。悪いのは、はっきりいうとおカネの世だ、と徂徠は考えています。これを統制することこそが政治の役割だというわけです。
幕府の封建体制と武士による秩序維持こそが課題でした。商品世界の自由なはばたきは許されず、経済はあくまでも武士的秩序にしたがわなければなりません。
それにしても、近ごろの世の乱れはいったいどうしたことでしょう。
国の秩序を守るには、人に道義を説いたところで、何の解決にもならない。筋道だった計画、新たな制度が必要だと徂徠は断言します。
近ごろ多くなった盗賊や追いはぎ、たちの悪い浮浪者、子捨て、死体遺棄などにはどう対処したらいいのでしょう。たいていの人は、ともかく自分だけが難を逃れればいいという考えで、家の塀の外には関心がありません。お上まかせということになります。そこで火付盗賊改(ひつけとうぞくあらため)や道奉行の登場となるのですが、少ない人数ではとても江戸市中すべてを見まわるわけにはいきません。
ここでおもしろいのは、盗賊奉行が直接、刑を執行する現在のやり方はやめたほうがいい、と徂徠が進言していることです。その理由は、同心や与力が犯人から時に賄賂を受け取って、好き勝手に手心を加えてしまうからだというのです。さらにその配下の目明しというのが輪をかけてたちが悪く、さまざまな悪事をはたらいて、人からカネをせびりとります。
みんな安い給料で生活が苦しいのです。そこで、役職にかこつけて、取り締まる相手から賄賂をもらい、多少の悪さはお目こぼしとあいなります。
これには、さすがの徂徠もお手上げです。
そこで、徂徠が提案するのは、町の戸締まりを強化することです。町ごとに木戸を設け、木戸番を置き、捜査や出産など、やむを得ない場合を除いて、夜間には町の木戸を閉めようというのです。これだとたしかにドロボーや辻斬りは減るかもしれませんが、夜間外出禁止令みたいで、すこし窮屈ですね。
さらに、徂徠は番方(ばんかた)の活用を提案します。
番方とはいったい何でしょう。
いちおう説明を加えると、幕府の役職は「役方」と「番方」に分かれています。財政、司法、行政などの実務にたずさわるのが役方、これにたいし番方は軍事を担当します。この番方が住んだのが番町。一番町から六番町まであって、いまもその地名が残っています。
江戸の町は武士と町人の住む地域がはっきり区別されていました。ところが、武士の住む地域でも、ほんらい番方が住んでいた番町に、近ごろは役方も住むようになりました。これも平和がつづくうちに、軍事より実務が優先されるようになって役方がのしてきたからだ、と徂徠はなげきます。
もし町の治安を考えるなら、番町に軍事機能を集中させて、番方の暇をもてあましている先手組(さきてぐみ)や持筒組(もちづつぐみ)の連中に、交代で江戸市中を回らせたらいい。いわば武装警官が町中に目を光らせるようになれば、悪人連中もみだりに動けなくなるだろうというわけです。
出替わり奉公人というのも、やっかいな存在でした。
奉公人というと商家を想像しますが、じつは武家にも奉公人がいました。江戸は武士の多いところで、人口の半分が武士とその家族だったといわれます。ですから、江戸では武家の奉公人も多かったのです。
出替わりは1年契約の非正規雇い。3月5日が契約の更新日と定められていましたが、1年限りでなく長く奉公する者もいました。江戸時代も中期になると、武家も給金を払って毎年、奉公人を雇うようになっていました。代々家来を養っていくだけの余裕がなくなっていたからです。
ところが、この出替わり奉公人というのが、給金を前渡ししたとたんに遁走するわ、トラブルを起こしてぷいといなくなるわ、カネを持ち逃げするわで、主人が頭をかかえることがしばしばでした。
徂徠はカネ中心の世界が政道をダメにしているとみています。江戸はいまや北は北千住、南は品川まで家つづきのありさま。そこで、徂徠はこの『政談』において、みずからの思想性をかけ、封建秩序を立てなおす方策を提言することになります。
こんなふうに論じています(尾藤正英訳)。
〈現在とるべき方法としては、政治の根本に立ち返って、やはりいまの柔弱な風俗をもとに戻し、古代の法制を勘案して、法を立て直すのが何よりである。政治の根本に立ち返って法を立て直すとは、どういうことかといえば、中国の夏殷周という古い時代でも、また新しい時代でも、あるいは日本の古代でも同じことであるが、政治の根本は、とにかく人を地に着けるようにすることであって、これが国を平和に治めるための根本なのである。〉
カネに振り回される世の中から脱して、「とにかく人を地に着けるようにすること」だというのです。
徂徠はいいます。最近はだれもがいわば「旅宿の生活」をしており、根無し草のように暮らしていることが世の乱れを引き起こしている。人を地につけるというのは、決まった土地に人を定着させ、そこでしっかりと生活できるようにし、ふらついた生き方をさせないようにするということだ、と。
政治の根本は「田舎では農業、都市では工業や商業に勤労しない者が一人もいない」ようにして、「親密な協同社会をつくる」ことだとも書いています。そのためには、きちんと戸籍をつくって、勝手な移住は許さず、だれがどこに住み、どんな仕事をしているかを把握しなければなりません。そうすれば、地域社会の交際も親密になり、風俗も矯正されて、悪事も減るだろうといいます。
とうぜん浪人や乞食坊主、陰陽師、遊女、役者など、地に着かぬ者にたいする扱いは、厳しいものとなります。
江戸の人口は制限されなければなりません。関八州(現在の関東地方)で生産される米穀の余剰で暮らしていける人数に限定されます。こうして江戸の人口枠が決まると、それを超す人数は「人返し」によって元の出身地に返してしまう措置がとられます。
しかし、人を地に着けるというのなら、率先してその範を示すのは、武士でなくてはならないはずです。
「武士の道を再興し、世の中の贅沢を押さえ、武家の貧窮を救う」には「武士を知行所に置かなくてはならない」と、徂徠はいいます。
江戸幕府ができたときから(いや厳密には豊臣時代から)、武士は知行地(領地)を離れて城下に集住し、主君に仕えるようになっていました。その代わり、たいてい年3回、切米と称して、石高該当分にあたる俸禄を現金で支給されていました。これは各藩の武士だけではなく、幕府の旗本や御家人でも同じです。武士が与えられた領地に在住することはなくなりました。武士が公務員化したともいえるでしょう。
それでは知行地のほうはどうなったかというと、幕府の場合は代官、藩の場合は名主や庄屋が、村のまとめをし、年貢の取り立てにあたっていました。代官の身分は下級武士ですが、名主や庄屋は百姓の身分です。
徂徠は、こういう支配体制がいけないと苦言を呈します。武士が江戸暮らしや城下暮らしをしていると、どうしても費えが多くなり、町人が潤うばかりで、田舎では百姓が領主を軽んじることになるといいます。万一、飢饉がおこれば、村の治安が不安定になり、強盗や馬泥棒が出没する恐れもあります。しかし、武士が領地にいれば、そんな事態にはなりません。
徂徠は田舎暮らしの効用を力説します。これはかれが青年期を上総の地ですごしたことと無縁ではないでしょう。
田舎暮らしをすれば、おカネはかからないし、贅沢もせず、怠惰にもならず、毎日、野原を駆け歩いて元気になる。それに知行地の田畑や治水工事の様子もよくわかり、百姓の内情にも通ずるようになるから、武士が悪徳代官のように、むごい年貢の取り立てなどもしなくなる。もし江戸城でどうしても勤務しなければならないのなら、1カ月交代とか百日交代にして、妻子をともなわずとも、じゅうぶん勤められるだろう。そんなふうにいいます。
武士が田舎に移ると、それにともない地元でも武芸や学問がさかんになるはずだ。医者だって、せちがらい江戸を捨てて、田舎に移ってくるかもしれない。武士が知行地に戻るのは、いいことづくめ。「軍兵の数も昔のとおりになって、日本古来の武勇の風が再現されるであろう」。こんなふうに、徂徠は田舎暮らしを絶賛します。
もちろん、徂徠の構想は実現しませんでした。百姓も主人である武家の帰還は迷惑千万だったにちがいありません。武士自身も都会暮らしの楽しさを奪われたくはなかったでしょう。
徂徠はそのすべての思想性をかけて、封建体制をむしばみつつある商品世界の浸透に抵抗します。そんな徂徠を歴史家の野口武彦先生は「江戸のドン・キホーテ」と呼びました。しかし、それは嘲笑ではありません。ドン・キホーテは反近代に固執することによって、近代の虚妄を暴く鏡の役割をはたしたのですから。



