価値論──メンガー『一般理論経済学』を読む(5) [商品世界論ノート]

ある財が価値をもつ(あるいは価値をもたない)というのは、いったい何を意味するのだろう。
財が価値をもつのは、財にたいする需求がその支配可能数量より大きい場合である。この場合、財は経済財となる。
逆に財が価値をもたないのは、財にたいする支配可能数量がその需求よりも大きい場合である。この場合、財は非経済財となる。
メンガーは価値について、そんなふうに論じている。
経済財と非経済財は固定されているわけではない。非経済財が経済財になり、価値をもつようになるケースは、たとえば木材や水が足りなくなった場合を考えてみればいいという。
そこでメンガーはこんなふうに書いている。
〈財価値は、財のわれわれの欲望にたいする関連にもとづくのであって、財そのものにもとづくものではない。この関係が変化すれば、価値もまた発生したり消滅したりせざるを得ない。〉
価値は人間の意識の外には存在しない。だが、価値は秘密めいたものではなく、正確に把握できるものだ。これがメンガーの考え方だ。
価値は使用価値と交換価値に分類することができる。交易関係のない孤立経済のもとで存在するのは使用価値のみである。交易関係が生じて、はじめて交換価値が発生する。それによって、価値は使用価値と交換価値の二重性をもつことになる。
いっぽうで、使用価値はあるが交換価値のないもの、交換価値はあるが使用価値がないものも存在する。だが、それは例外であって、人間の経済生活においては、財が使用価値と交換価値の双方をもつ場合がほとんどであるという。
財には使用価値があるのが前提である。だが、使用価値と交換価値のどちらを優先するかによって経済価値は変わってくる。
支配した財をもっぱら自己所有し、外部に譲渡しない場合には交換価値は発生しない。しかし、財を主に交易に回すとしたら、経済価値は交換価値が優先することになるだろう。
使用価値と交換価値のどちらを優先するかの選択は状況によって異なる。そこには経済性の法則がはたらく、とメンガーはいう。
次に検討しなければならないのは、価値の大きさである。価値の大きさはどのように決まり、なぜちがいがあるのか、また価値の大きさはなぜ変動するのか。
財はそれ自体で価値をもつわけではない。財はわれわれの欲望を満たすかぎりにおいて意味をもち(主観的契機)、そして、それはわれわれがどれだけの財を支配できるかに依存する(客観的契機)。
メンガーはそんなふうに述べている。
人間の欲望が優先的に選ぶのは、みずからの生命維持にかかわる財である。それにつづくのが幸福度をより満たす財ということになるだろう。こうした選択は各自の置かれた状況や各自の個性に依存する。そして、欲望満足の度合いも人によって異なる。
欲望の最大の対象となるのは食べ物だろう。人びとが食べるのは健康維持のためだけではない。食べる楽しみのために食べるのがふつうだ。
食欲は人によって異なる。だが、ある限界に達すると、食べることによる満足の度合いは下がっていく。このことは、住宅にしろ、何にしろ、ほかの財についてもいえる。
ここからメンガーは、欲望の充足はある限度を超えると逓減していくという法則を導きだしている。さらに、それ以上となると、「外見上その欲望を満足させるものとみえるいかなる行為も、もはや人々にとっての意義を失い、むしろ煩わしさと苦痛になっていく段階にまでいたる」という。
次に論じられるのが財の支配についてである。
一定の欲望を満たすには、一定の財を支配しなければならない。そのとき、どれほど欲望を満たすかに応じて財は価値をもつことになる。
だが、欲望はただひとつではない。たいていの場合は、「それぞれに一つだけの具体的欲望ではなく、それらの一つの複合体にたいして、またそれぞれに一つずつの財ではなく諸財の複合体の一数量が対応している」。
ここでメンガーは孤立して経済を営む農民をモデルとして、話を進める。
その収穫が年に500キロの穀物だとすれば、かれはまずその大部分を家族の健康維持のためにあてる。だが、それだけではない。残りの一部でビールをつくったり、家畜を飼ったりするかもしれない。さらに翌年の種籾もとっておかなかればならない。さらに余裕があれば穀物を何か別の楽しみのために用いたりもする。
収穫した穀物の用途はさまざまで、そこからさまざまな財がつくられ、それによってさまざまな欲望が満たされることになる。ここでは支配される財が欲望(用途)に応じて配分され、別の財に転じることが示されている。
さらにメンガーは、孤島に住む人や、漂流船に取り残された人を例にだして、そこでは限られた水や食料がいかに大きな価値をもつようになるかを説明している。孤島や漂流船では、希少な財が欲望をじゅうぶんに満たせないようになればなるほど、財の価値が増大することが示されるのだ。
価値は支配可能な財と欲望との相対的な関係によって決まる。これによって、なぜダイヤモンドや金が高い価値をもち、なぜ通常、水がほとんど価値がないかを説明できる、とメンガーはいう。スミスからリカード(さらにはマルクス)にいたる労働価値説は否定されることになる。
メンガーは財の質が価値におよぼす影響についても検討する。質のちがいは量によって代替できることもあるが、代替できない場合も多い。その場合は、質のちがいが欲望を満足させる度合いに差をもたらす。
そこで、一般に「経済活動を行なう人はその需求の総量に達するまで、より劣った質の財は後回しにしてより上級な質の財ばかりを、自らの欲望の満足のためにとる」という傾向が導きだされる。この場合、最劣等の財は価値をもたない。
だが、もし優良な財と劣等な財が同時に需求される場合、両者のあいだには価値に差が生じることになる。それは欲望を満足させる度合いのちがいにもとづく。
ここでメンガーが強調するのは、価値があくまでも主観的なものだということである。ある人にとって価値がある財も、別の人にとってはまったく価値がない場合もある。
〈価値はしたがって、たんにその本質からだけでなく、その尺度からしても主観的な本性をもつものである。財はつねに経済活動を行なう特定の主体にとって「価値」をもつものであり、しかしまた、特定のそうした主体にとってだけ一定の価値をもつのである。〉
財が真実価値をもつことも擬制価値をもつこともあるのは、価値があくまでも主観的なものだからだ。ここからまた財の過大評価や過小評価が生じる理由も説明できる。
財の価値を論じるにあたっては、人間の錯誤や無知を考慮しないわけにはいかない。だが、たとえそうであったとしても、基本的に価値の判断には合目的な方向性がみられる、とメンガーは考えている。
最後に論じられるのは、価値論の高次財への適応である。これまで価値の問題は、もっぱら直接的な欲望の満足にかかわる第1次財にのみ限定されていたが、それを高次財に拡大すると、いったいどのような法則がみてとれるかというわけである。
いうまでもなく、経済活動において第1次財を支配する(形成する)には、第2次財、第3次財といった高次財を必要とする。たとえば、パンをつくるには、まず小麦、さらにそれ以前に種籾と土地、耕作用具、労働力を必要とするというように。
ここでは「高次財の価値は、その高次財が産出に役立つ低次財の予想価値によって条件づけられる」という法則が成り立つ、とメンガーはいう。
重要なのは、あくまでも第1次財の価値である。高次財は第1次財の産出に役立つかぎりで意義をもつ。メンガーのこの発想は高次財の価値が第1次財の価値を決定するという一見常識的な考え方とまるで逆だといえる。
強調されるのは「高次財の予想価値の方が低次財の予想価値によって条件づけられる」ということである。ここでは、第1次財の価値が、次々と高次財の価値に移転されることが想定されている。
ここには時間の要素がはいってくる。何カ月、何年後の第1次財への需求を予想して、先行的に高次財が形成されなければならない。そこで、高次財の価値を方向づけるのは、現時点における低次財の価値ではなく、将来における予想価値だという原理が成り立つ、とメンガーはいう。
メンガーは高次財による低次財の(最終的には第1次財にいたる)形成を基本的に資本活動ととらえている。それは資本用役と企業者活動による時間の要素をともなう価値の形成であって、そこでは資本利用の価値(すなわち利潤)が発生するのがとうぜんだと理解する。利潤はいわば将来の不確実性にたいする保証である。だが、その利潤は将来予測の当否に左右される。
最後に追加として、メンガーは土地用役、労働給付、資本用役の価値についても述べている。これはじっさいには、地代、労賃、資本利子(利潤)の形態をとるものだ。
ここでもメンガーが強調するのは、土地用役、労働給付、資本用役がそれぞれ特有の性質をもっていたとしても、それらの価値は、他のすべての経済財と何ら異ならない法則(すなわち低次財にたいする需求の大きさに規定される)にしたがうということである。
労働の投下量や最低生活の保障、さらには搾取がそれらの価値を決定するわけではない。現代流にいえば、土地や労働力、あるいは利潤についても、あくまでも需要と供給がその価値を決定するというわけだ。ここには現代経済学、さらには現代社会を基礎づける考え方が示されている。
経済的進歩の要因──メンガー『一般理論経済学』を読む(4) [商品世界論ノート]

人間は生きているかぎり、日々欲望を満たし、調和的な生活を維持していかなければならない、とメンガーは書いている。そのためには、みずからの欲望を満たしうる手段をもたなければならないが、それには事前の配慮が必要となるという。
経済とは、主体的にみれば、欲望を満足させるための手段を確保しようとする努力を指す。それは自然的、社会的状況のもとで、生産や交易を通して財を得ようとする活動でもある。いっぽう、客体的にみれば、経済とは、われわれが支配しうる財の総体であり、それをいかに配置するかという問題となる。
経済の出発点は財である。そこには交易によって得られる財も含まれるが、経済の目標は、こうした財によって、みずからの需求を満たすことである。そして、そうした需求を満たすには、生産手段(材料、労働力、機械など)だけではなく、交換手段(貨幣など)が必要になってくる。
ただし、経済活動とは消費そのものを意味するわけではない。あくまでも、われわれが自分たちの欲望を満たすための手段を確保する過程を意味する。
メンガーは経済をそんなふうに理解している。
経済を生産・分配・消費というジャンルにわけるのは、まったく外面的な把握にほかならない。また、労働を財の唯一の源泉と考えるのもまちがっている。経済を生産と同一視するのも一面的だ。経済とはあくまでも財の需求を充足させようとする人間の努力全般を指すというのがメンガーのとらえ方である。
財には経済財と非経済財がある。過剰なほどどこにでもふんだんにある財は経済財にならず、非経済財のままだ。たいていの場合、水や大気、砂、森の木材などは非経済財である。
しかし、場所が変われば、こうした非経済財も経済財になる。非経済財から経済財への転換は、住民の数が増大したり、財の新たな使用目的が発見されたりすることによっても生じる。
いずれにせよ非経済財が経済財に、あるいは経済財が非経済財になるのは、需求と支配可能数量との関係が変化することによってである。そのことは、都市における飲料水や木材の必要性が、ほんらい非経済財だったものを経済財に転化させることをみても、あきらかだという。
飲料水が住民の需求をじゅうぶんに満たす場所では、水道は必要なく、したがって水道設備のための高次財の必要も生じない。
そこで、メンガーはいう。
〈人間に直接に与えられた財がすべての人間経済の出発点であり、人間の需求の充足がその目標点である。人間はまず第1次財にたいする欲望を感じて、自分の需求よりも少ない量しか支配しえない第1次財を、自分の経済的活動の対象、つまり経済財にする。……その後に熟慮と経験を重ねることによって、人間は諸物の因果的連関……をたえず深めていって、第1次、第2次、そしてさらに高次の財を知るようになるのである。〉
欲望を満たす財が常にそこにあるなら、経済など必要ではない。そこには、いわば自然の恵みにあふれた楽園が広がっているのだから。
もちろん、メンガーはかつて人類がそうした楽園を経験したとは思っていない。
現在の発達した文化のもとでは、さまざまな生産過程をへて、ようやく享受財を得ることができるのが実情だ。とはいえ、究極的な財需求を満たすには、「生産手段に目標と方向を与える配分的な活動」が必要になってくる。
すなわち享受財の需求を見越して(その場所や時間、種類、量も含めて)、それを満たすために必要な生産手段(技術としての労働力を含む)を集めて、目標と方向を定め、それを組み合わせて、技術的─経済的な活動をおこなわなくてはならない。
いっぽう、財にはかぎりがある。人間の経済の出発点は、財が不足がちであるという現実にあり、財需求を完全に充足することは、人間経済の理想的な究極目標でしかありえない。とするならば、かぎられた財にたいする需求を可能なかぎり満たすことが経済活動の目標となる、とメンガーはいう。
そこからは節約化の方向が生じる。財の喪失や損傷を予防することはもちろんだが、生産の効率性も求められる。できるだけ少量の享受財で、欲望を満たす努力(さらには欲望自体を抑制する努力)も必要だろう。さらに、かぎられた生産手段からどのような財の生産を優先するかについても先行的配慮がなされなければならない。
つまり、人間の経済には技術的(拡大)の方向と節約化(効率化)の方向が同時にはたらいている、とメンガーは考えている。
このふたつの方向が結びつくことによって、人間の経済には次のような傾向が生じる。
最大可能な成果を効率的に達成すること。
より必要な財を優先して選択すること。
さらに資本の集中により生産効率を高めること。
ところで、人間の社会においては、しばしば、かぎられた財をめぐって利害の衝突が生じる。それを解決するひとつの方法が、財の共同占有と個々の経済主体への分与(配給)だということをメンガーも認めている。だが、それは往々にして失敗に終わる。
これにたいし、共同占有がなされていない社会では、経済主体は法秩序のもとで私的な所有権を認められることになる。
ありあまる財が存在する世界では、所有権は何の意味ももたない。だが、支配可能な財の数量がすべての人間の欲望を満たさない経済においては、所有権をもつ者に財が所有されることはやむをえない。
メンガーは社会主義には否定的だったように思われる。せめて可能なのは必要最低限の財を確保し、それを分配できるようにするくらいなものだと書いている。
私的な所有権が認められる社会では、資産が存在する。
資産とは何だろう。
メンガーは資産を「ある人物が支配する経済財の全体」と定義する。
あらゆる財が需求以上にありあまっている社会では、経済財も資産も存在しない。資産という概念が存在するのは、経済財が希少な財である場合だ。
経済財を所有する主体は資本家だけではない。国家や自治体、会社も資産(経済財)を所有している。
これにたいし、国民資産という概念は一国民全体を経済活動をおこなう主体と考える一種の擬制であって、厳密な意味で、国民資産なるものが存在するわけではない。
国民資産は「人々の交易によって結び合わされた、経済財の複合体」ではあるが、その数量そのものから国民全体の経済を判断すると、誤りを生じやすい、と述べている。
いまなら、メンガーはGDPを最大の経済指標とする考え方に懸念を示したにちがいないと思われる。
資産のうち、財(生産)の元本となるものをメンガーは資本と名づける。資本は用役財資本(土地や機械、建物など)と消耗財資本(原材料、補助材料)からなる。それは安定資本(固定資本)と可変資本(流動資本)と言いかえることもできる。
いっぽう、資産には生産ではなく消費に向けられるものもある。そうした資産のなかには、用役財(土地、住居、家具など)や消耗財のほか、貨幣も含まれることになるだろう。
なお補足すれば、メンガーは資本における用役財も長期的にみれば消耗財なのであって、最終的には財としての性質を失ってしまうと述べている。したがって、資本を純資本として維持するためには、用役財の摩滅(資本原本の部分的な消耗)に対応していかなくてはならない。
この章(第4章「経済と経済的財の理論」)では、経済とは何かにはじまって、経済財と非経済財の区別、経済活動の方向性、資産と資本が論じられたが、最後は経済的進歩をもたらす要因が検討される。
メンガーは、アダム・スミスのように、経済的進歩の要因を分業だとは考えなかった。
労働は力というより、むしろ技術であって、技術的労働が、財の形成に向けての努力を指すことはいうまでもない。だが、分業自体が経済的進歩をもたらすわけではない、とメンガーはとらえていた。
分業は大きな要因ではない。それよりも、直接的な第1次財の獲得に専念するのではなく、第2次、第3次と高次の財を獲得する方向に進むことこそが、経済進歩をもたらすのだ、とメンガーは考える。
その例として挙げられるのが、次のような人類発展の経緯だ。メンガーによれば、「獲物を棍棒1本で追う猟師が弓と網を使う猟へ、牧畜へ、さらに進展して、ますます集約的な形態の牧畜へと移行していく」のが、これまでの人類の歴史だった。
ここでは、直接に獲物を追いかけるよりも、迂回して獲物をつかまえる道具(高次財)を工夫することが、より多く第1次財を得ることにつながるということが、暗黙のうちに示されている。
そこで、メンガーはいう。
〈いずれにせよわれわれの欲望の満足への高次財の利用を増進することは、われわれの支配しうる享受手段の数量を増加させ、したがってわれわれの経済的状況をますます改善するという結果を生じる。〉
直接、第1次財に労働の投与を集中させるよりも、高次財の形成を工夫することが、人びとの獲得する享受手段を増進させることにつながるというのがメンガーの考え方だといってよいだろう。いまなら、こうした高次財の代表がさしずめ半導体ということになるだろうか。
だが、人間が高次財を獲得するには、前提が必要である。
それは何か。
〈それは、これらの[経済活動を行う]主体が、現時点について経済財にたいする自分の需求を満たした後、なお、また先の生産過程のための、あるいは未来の諸期間のための経済財の数量が残るのか。いいかえれば、資本を占有するかどうか、である。〉
ここでいう資本は、いわば社会的余剰ととらえられている。こうした社会的余剰は分配され、消尽されてしまってはならない。むしろ、占有され、高次財の形成へと向けられることによって、経済的進歩がもたらされる。
高次財の形成は「人間の先行的配慮の活動」の結果であって、そのためにはそれをおこないうるだけの「資本の生産性」が必要だというのが、メンガーのとらえ方なのである。
メンガー『一般理論経済学』を読む(3) [商品世界論ノート]

人間の欲望と財はどのように対応しているのだろう。
メンガーはここで人間の欲望を満たしうる財の量全体を「需求」と名づけ、これにたいし現存する財を「支配可能な財の数量」と呼んでいる。
われわれが求めるのは直接に消費対象となる第1次財である。だが、第1次財の背後には第1次財をつくるのに必要となる何層もの(高次の)間接的な財がひそんでいることはいうまでもない。それは1冊の本をみてもわかるだろう。
人間の欲望は自然発生的なもので、意志の力や外的な条件によっては完全にコントロールできない、とメンガーは考えている。欲望はあらゆる方向に広がっていく。
とはいえ、欲望は満たされなければならない。それには、さまざまな財との組み合わせが可能である。ここから需求は現に与えられている財にたいする「選択的な決定」とならざるをえないというメンガーの定理が導きだされる。
すると、直接的な需求と直接的な財数量は、はたして確定できるのかという問題がでてくる。
まず需求についていえば、少なくとも現時点の欲望を満たすだけなら、食料や飲料、衣服、住居関係にどれだけのものが必要かを確定することは可能だ。
だが、それだけではすまない。人間は将来に向かって生きているからだ。しかも、それは不確実性に満ちている。
不確実性に満ちた将来を想定するなら、需求を現在の直接的需求だけに限定するわけにはいかない。戦争や地震、火事、病気、家族の将来、その他もろもろの不安が、需求の確定をむずかしくする。人間の欲望は、将来の不安をできるかぎり乗り越えることにも向けられているからだ。
さらに、欲望が無限に発展する可能性を考えれば、需求の確定はそれこそ不可能のようにみえてくる。とはいえ、一定の期間をとれば、1次財にたいする需求は一定の量に限られるとメンガーはいう。
いっぽう、支配可能な財数量、言いかえれば財のストックのほうはどうだろう。これも一定の時間をとれば、その数量は与えられ、確定されているといえるだろう。
将来を考えれば、不確実性が増大することはいうまでもない。だが、重要なことは、われわれが将来、直接支配可能となる財数量について、現時点で常に先行的に判断を下していることだ、とメンガーは書いている。現在の生活経験を基準として、将来の財のストック水準が見定められているといってよい。
1次財の需求と数量への考察は、とうぜん間接的な高次財の需求と数量へと拡張されなければならない(紙の本をつくるには紙が必要だ)。
間接的な高次財への需求は、1次財の需求によって制約されている。高次の財への需求は、ひとつ低次の財への需求を反映するのであって、高次財の需求が単独にあらわれるわけではない、とメンガーは述べている。
とはいえ、高次財への最終的な需求が常に満たされるとはかぎらない。靴の需求が1万足あったとしても、じっさいには5000足しかつくれないこともある。支配できる(提供できる)高次財(材料、道具、労働力など)がかぎられているからである。
メンガー自身は「われわれが高次財への有効な需求をもちうるかどうかは、補完的な諸高次財の対応した数量をわれわれが支配できるかどうかによって制約されている」と論じている。
たとえば、広大な農地をもっていても、そこにまくだけの種子がないとか、逆に種子があっても農地がないとするなら、いくら高次財としての小麦が求められていても、有効な需求は制限されてしまうことになる。
ここで選択と予見がはたらく。直接的な需求にもとづいて、どのような間接財を選択するかは自由である。さらに直接的、間接的を問わず、将来の需求を予見することによって、技術の発展がうながされることになる。そのことが制約の突破に結びついていく。
メンガーは人間の経済を考察するにあたっては「時間」が大きな位置を占めることを強調している。
〈われわれの生活は、人間一般に、ことに各個人にわりあてられた時間の範囲内で実現される一つの過程である。われわれの欲望は徐々にしか現実の世界の中に現われず、かくしてこれらの欲望は、具体的な形をとって特定の時間のみに現われてくる。各人の需求はすべて、特定の期間をとってみれば、特有の大きさなのである。〉
ある時間、あるいは一定の時代において、人間の需求、人間の支配可能な財、技術は、その時点での特有の大きさと質をもっている。それは移ろいやすいものだ。また次第に大きくなり、発展していく性格をもっている。
さらにいえば、人間の経済においては、特定の量の需求を満たすためには一定の時間を要する。その典型的な例が穀物だ。穀物の成育にはそれなりの時間がかかる。
学校教師を増やすことが求められる場合も、有能な人材はたちどころに生まれるわけではない。長い時間の訓練が必要だ。
一般に、将来の1次財を満たすためには、早い時期に高次財の準備がなされなければならない。
こうしたことを前提として、「需求と支配可能な財数量は、人間経済のどのような時期においても、特定の量としてたがいに向かい合っている」ということがいえるのだ。
ただし、このことは需求が常に満たされることを意味しない。低次財と高次財には、その形成に時間差があり、したがって不確実性がともなう。さらに、ある財の需求が満たされないときは、別の財が選ばれるといった選択の論理もはたらく。
さらに、需求は個人の需求だけではなく、一国民の社会的な需求としてとらえなければならない、とメンガーは主張する。
社会的需求とは、社会全体の欲望を量的にも質的にも完全に満足させるのに必要な財の総体を指している。
とはいえ、現実に国民需求の充足を自身の任務として経済活動をおこなう主体は存在していない、とメンガーはいう。国家は国家機関にしか関与していない。実業界はみずからの利益に関心をもっても、貧窮にあえいでいる人びとの需求には関心をもたない。
それでも、国民経済は社会全体の需求を確定するという課題を放棄できない、とメンガーは述べている。社会的需求には諸個人の需求だけでなく、社会の共通の利益(たとえば街路、公園、治安、環境)なども含まれている。さらに、将来の不確実性にたいする需求も配慮しなくてはならない。いずれにせよ、社会全体の需求をとらえるのが重要であることをメンガーは強調している。
それは支配可能な財数量についてもいえる。財のストックとしてあげられるのは、国家資産と個人資産だが、真の意味での国民資産は把握されていないと述べている。
真の国民経済が存在するものとすれば、国民にとって支配可能な諸財がどの程度なのかがとらえられなければならない。ところが関心がもたれているのは、もっぱら直接的な供給と需要だけときている。
ここでメンガーが関心をいだいているのは国民全体の財のストックだといえるだろう。こうした財は幅広く交換されることによって、国民全体の需求に応えることができる。
国民経済は、国家が国民の需求を把握すると同時に、社会全体の財のストックを認識し、自由な交換をうながすことでしか成立しない、というのがメンガーの基本的な考え方だったように思える。
メンガー『一般理論経済学』を読む(2) [商品世界論ノート]

現代は欲望の時代だといってもよい。身分制と節欲の時代は、いつのまにか自由と欲望の時代へと転換した。
メンガーは経済活動の出発点を欲望においている。ここでいう欲望とは何かギラギラした強い望みを指すというより、むしろ「何々したい」という気持ちを意味している。人は生きているかぎり、何らかの欲望をもっているといえるだろう。
労働ではなく、欲望を出発点に置くのが、これまでとは異なるメンガー経済学の特徴である。
〈欲望はあらゆる人間経済の究極の根拠であり、欲望の満足がわれわれにとって持つ意義は人間経済にとっての究極の尺度であり、欲望の満足の確保は人間経済の究極の目標である。〉
人間は一定の条件のもとでしか生きることができない。そうした一定の条件を確保し、常に発生する障害を解消しながら、何とか生きていこうという意志をもちつづけるのが人間なのである。
障害や制止にともなう不快感や渇望、苦痛は、何らかの財によって解消され、解放され、沈静化され、快楽へと変わっていかなければならない。だが、その過程は「事情によってはまさしく矛盾だらけの、まちがいのもとになる表現」をとりかねないし、そこに葛藤も生じる、とメンガーは述べている。
人間の欲望には、時に誤謬や無知や激情がつきまとう。そのいっぽうで時に欲望を抑制しようというブレーキがはたらく。空想的で擬制的な欲望が生じることもある。とはいえ、欲望が人間の本性であることは疑いない、とメンガーは断言する。
すべての生物は欲望をもっているけれども、他の有機体と比べものにならないほど発達しているのが人間の欲望だ。とりわけ自己関心の度合いの強さに関しては、人間は他の動物と比較にならない。
個々人の欲望だけではなく、団体(国家や結社、企業)の欲望をもっているのも人間集団の特徴かもしれない。団体の欲望というには、たまたま個人が同じ欲望をもっていることを意味しない。それは集団としての共同の欲望にほかならない、とメンガーは論じている。
メンガーは欲望の発展を歴史的、文化的に追跡しているわけではない。とはいえ、商品世界の前提として、第一に主観的な欲望が存在することを、あたりまえのように指摘したのは、かれの業績といえるだろう。
欲望の対象を経済の次元にしぼるならば、それは財ということになるだろう。
「財は、人間の欲望を満足させるために役に立つと認められ、そしてこの目標のために支配可能な事物をいう」
つまり、財は事物からなり、モノだけではなくコトも含まれる。さらにメンガーはいう。
財は欲望を満たしうる性質と適性を有し、加えて人がそれを支配できる可能性をもたなければならない。そうした条件がなかったり、失われたりすれば、財としての性格は失われる。
逆に財として認識されていないけれども、効用を有するもの(たとえば空気)や、財としての潜在性(たとえば未知の資源や)を有するものも存在する。
私有財産制度のもとでは、権利や商標などもまた一種の財だ。
とはいえ、財はあくまでも主観的なものだメンガーは主張する。ある人にとって有用な財も、別の人にとっては無用なもの、あるいは有害なものでありうる。兵士にとって武器は有用かもしれないが、攻撃される側からすれば武器ほど有害なものはない。
〈したがって、われわれの手中にある諸財はそれぞれ特殊な関係をわれわれとの間にもっているのであって、それは一般の財としての性質とは区別しなければならないことは明らかである。各個人あるいは特定の人々にとっては、自分たちにたいして財としての性質を基礎づける関係にある物だけが財である。〉
このあたり、人間の主観的認識とそれにもとづく経済活動を重視するメンガーの考え方がうかがえる。
財の種類についても論じられている。
財が財となるには認識が決定的な契機になるというのがメンガーの考え方だ。
したがって、誤った認識が空想的あるいは擬制的な財をもたらす可能性もある。たとえばインチキな薬やあやしげな信仰物などもその例だ。
ただし、文明が発展すればするほど、擬制財は減り、真実財が増えてくるはずだという。
物質的な財だけではなく、非物質的な財も存在する。
「非物質的な財を無視したのでは、経済的現象の大部分はそもそも説明することができないし、まして完全な説明はなされえない」
そもそも財は身体的だけではなく、心的な欲望を満たすのにも役立つはずであって、その意味で、さまざまなサービスや演劇の舞台、音楽活動などの非物質的な財も人間の生活に欠かせない重要な財となるだろう。
財を消耗財と非消耗財に分けることも可能だ。食料品や飲料、さまざまな原料などは消耗財であり、ダイヤモンドや土地などは非消耗財である。機械や衣服、家具などをその中間の用役財に分類することもできる。
さらに財を分析するさいには、財の連関を認識しておく必要がある。
パンをつくるには小麦粉が必要だ。小麦粉のもとは小麦、そして、小麦をつくるには耕地や種子、農具、農作業が欠かせない。
ここで直接的な消費財を第1次財と呼ぶなら、その第1次財をつくるための第2次財、第3次財、さらに高次のn次財が必要になってくる。
高次の財が財となるのは、あくまでも低次の財を前提としている。経済が高度に発展している場合は、分業と交換にもとづいて、自分の製品を生みだすための補完財(高次財)はすぐに手にはいるのがふつうだ。
だが、財の連関が失われると、生産に大きな影響が生じる。実際にそうしたできごとが起きるのはまれではない。メンガーはそうした例として、アメリカの南北戦争で一時ヨーロッパに綿花がはいらなくなり、工場の操業がストップし、労働者の仕事が失われたことなどを挙げている。
また、直接消費財である第1次財が、人びとの嗜好の変化によって財としての性格を失うこともある。
たとえば、だれもたばこを吸わなくなったとすれば、どうだろう。そのことが高次財におよぼす影響は大きい。たばこの製造工場や設備、熟練労働者、たばこ農園等々へと影響は広がっていく。これは新聞や鉄道などとも無縁の話ではあるまい。
「ある低次財の財としての性質が消滅する場合には、同様の結果がそれに対応する高次財に関してもあらわれる」ということになる。
〈経済学者たちは、物が財であるのはそれが財から生産されているからであると考える傾向がある。しかしながら……実際にはまさしくその逆こそが真実である。すなわち生産物が財となるゆえに、諸財が生産のために用いられるのである。〉
生産のための生産は実際の消費によって裏切られることになる。
もちろん、高次の財によって低次の財が満たされるのが高度な文明社会の特徴だ、とメンガーは考えている。
ただし、高次の財から低次の財にいたるには、時間の経過が必要である。工業製品にしても、たちどころに作られるわけではない。
「高次財の支配とそれに対応する低次財の支配との間に横たわる期間は完全に消滅することはありえない」
そうしたことから、「高次財がその財としての性質を獲得し、またそれを主張するのは、直接の現在の欲望に関してではなく、ただ多少とも隔たった将来の欲望に関してにすぎない」という原理が導きだされる。
経済に時間性が生じるということは、経済が不確実性にさらされていることを意味している。
たとえば、一定の土地と種子、肥料、労働力、農具をもっていても、そこから毎年何トンかの小麦を生産できるとはかぎらないし、かならずそれがどこかに引き取られるともかぎらない。
こうした不確実性は、あらゆる生産に共通してつきまとう。
人間の経済には不確実性がつきものであり、そのことが経済にとっては大きな意味をもつことになる、とメンガーは述べている。
近代の経済社会は、不確実性に満ちた欲望と財の組み合わせの上に成り立っている。
われわれはスミスやマルクスとはまるでちがう経済学の世界と出会っているといえるだろう。
つづきはまた。
メンガー『一般理論経済学』を読む (1) [商品世界論ノート]

カール・メンガー(1840〜1921)は1871年に『経済学原理』を刊行した。近代経済学の出発点となったこの本は、その後本人が再刊を拒否したまま、埋もれるままになっていた。
ところが、メンガーは死にいたるまで「原理」の改訂をつづけていたのである。その遺稿を整理して、子息が1923年に出版したのが『経済学原理』第2版だが、その内容は第1版と大きく異なっていた。
そのタイトルを『一般理論経済学』と変えたのは、本人が初版の扉にそのように改題するよう示唆していたからである。『一般理論経済学』というのは日本だけのタイトルで、本人の示唆にもとづいて、タイトルの変更を決定したのは、経済学者の玉野井芳郎(1918〜85)だった。
こうして新たに『一般理論経済学』と名づけられることになったものの、『経済学原理』第2版は、日本では長らく翻訳されなかった。出版されたのは、ようやく1982年になってからである。
ただし、初版は安井琢磨の訳で『国民経済学原理』のタイトルで1937年に日本でも翻訳出版されている。初版とは大きく内容の異なる第2版が長く翻訳されなかったのは、これがもはや時代遅れの古証文とみなされていたからだろう。
1980年代になって、それをよみがえらせたのは玉野井芳郎の熱意による。その熱意に応えて、八木紀一郎が中心になって、翻訳を進めた。
カール・メンガーは、いわゆるオーストリア学派の創設者のひとりとして知られる。この学派からはのちにベーム=バヴェルクやヴィーザー、シュンペーター、ミーゼス、ハイエクなど錚々たる経済学者が登場する。シュンペーターを除き、いずれもスミスやリカードの古典派、マルクスを強く批判する立場をとった。現在の新自由主義の源流ともいえる。
ところで、経済学の素人で、これまでマルクス中心に学んできたぼくが、いまさらメンガーを読んでみようというのは、いったいどういう風の吹き回しなのだろう。
たまたま買ったもののツンドクのまま本棚に並んでいたが、ついに読む気になたというのが、いちばんの正解かもしれない。
目も悪く、頭もいっそう悪くなったいま、いよいよ本棚の片づけを進めなくてはいけないと思うようになった。メンガーやシュンペーター、ハイエクを読めるのは、たぶんもう最後ではないだろうか。そんな気持ちがわいてくる。
とはいえ、悲壮な気分ではない。そもそも、このブログはだれかのためになるわけでもないし、半解、曲解、中途半端で終わっても、だれかに迷惑をかけるわけでもない。要するにじいさんの暇つぶしである。
それでもなぜこの本を買ったのかを思いだすと、ぼくはあのころ、ソ連や中国にはない自由な社会主義(脱資本主義)を夢みていて、その手がかりとして散漫ながらカール・ポランニーの本を読んでいた。
そのポランニーがたしか『人間の経済』(これも玉野井芳郎の訳だった)のなかで、カール・メンガーに言及していたのが気になっていて、そのときタイミングよく、この『一般理論経済学』が出版されたのだった。
そこで、勢いこんで買ったのはいいが、パラパラとめくってみて、あまりの難解さにたちまち投げだすといういつもの癖がでて、そのまま何十年にわたってツンドクのままとなった。
いまになっても、素人のぼくがこの本を読み通せる自信はない。最近の経済学は数学ができないと、1行たりともわからない。ところが、この本は数学ができなくても、ある程度理解できそうな気配がある。その哲学的思考にはついていけないかもしれないが、こむずかしいところを飛ばせば、ひょっとしたら何を言いたいかくらいはわかるかもしれない。おれにも読めるかなと思った。
前おきはそれくらいである。翻訳で全2巻の本だから、途中で難破の恐れがある。その場合は元に戻って休みながら、あらためて進むことにしよう。たぶん時間はかかるし、まとめも長くなる。そんなふうに気長に考えている。
いざ構えてみて、最初に思うのは、メンガーはたぶん近代経済社会の基本構造をとらえようとしたのではなかろうかということである。
近代経済社会は人類が長い時間をかけてつくりあげてきた社会のひとつのあり方だった。それはけっして絶対的なものとはいえない。ひょっとしたら、大きな欠陥をはらんでいるかもしれない。にもかかわらず、その構造はかなり強固なものであって、まずそれを頭に入れておかなければ、次の現実的ステップははじまらない。
こうしたとらえ方はすでに邪道かもしれない。だとしても、こんなふうな見通しをつけて、とりあえず理解できるところだけでも、専門用語(ジャーゴン)にこだわらず、自由に本を読んでみることは、高齢者の特権みたいなもので、許されるはずだ。
『一般理論経済学』は全部で9章からなる。最初にその全体を示しておこう。
第1章 欲望の理論
第2章 財の一般理論
第3章 人間の欲望および財の度量[広がりと大きさ]について
第4章 経済と経済的財の理論
第5章 価値の理論
第6章 交換の理論
第7章 価格の理論
第8章 商品の理論
第9章 貨幣の理論
ぱっとみるかぎり、あまり面白くはなさそうである。現代経済学でいうおなじみのミクロ経済学の教科書のようにもみえる。
商品がつくられて需要と供給によって価格が決まり、貨幣で決済されて、財にたいする欲求が満たされ、経済が調和的に運営されていくというように。
搾取もなければ破綻もない。何もしなくても、市場の原理によって、すべてはうまくいく。
だが、ほんとうにメンガーはそんなふうに考えていたのだろうか。いや、そうではるまい。かれは安定した経済社会が実現するには、じっさいにはかずかずの困難を乗り越えなければならないと承知していたのではないか。すべては憶測にすぎない。これから、実際の中身を読みながら、そのことをたしかめてみよう。
以下、退屈で、だらだらしたブログになるかもしれないが、その点ご寛恕のほどお願いする次第だ。
ハーヴェイ『経済的理性の狂気』を読む(9) [商品世界論ノート]
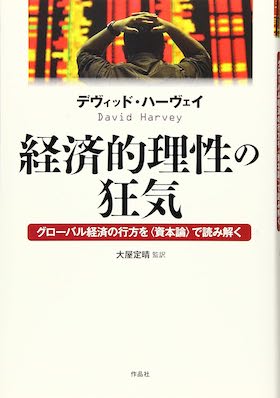
資本の循環過程において、商品は購入されるとその過程から離脱するが、貨幣は残る。そして、貨幣は狂気となる、とマルクスは書いている。
商品は消費されることで、人の欲求を満たす。だが、貨幣は増殖を自己目的とする。そのためには貨幣は売れる商品を生みだしつづけなければならない。ここに悪無限が生じる、とハーヴェイはいう。
「現代資本主義は、終わりなき蓄積と複利的成長という悪無限にはまり込んでいる」
こうして貨幣の「完結することなき無限」と商品の「際限のない浪費」が組み合わさる。環境的コモンズは急速に悪化する。
貨幣の運動を後押ししているのが、利子生み資本(金融資本)だ。利子生み資本においては、貨幣がより多くの貨幣をもたらす不思議な力をもっているかのようにみえる。債務に追い立てられるようにして、資本はさらにエンジンを吹かさなければならない。
だが、いつしか「終わりなき複利的成長は減価と破壊に帰着せざるをえない」。働かされるだけ働かされて、不況がやってくれば、労働者は職を失い、あとにはローンだけが残って、「債務奴隷」となる現実が待っている。
貨幣が金や銀などの物質的土台から切り離されて、ドルやユーロ、円といった観念的構築物となり、とてつもなく膨張したのが現在の姿だ、とハーヴェイは書いている。
いまや外国為替市場では毎日2兆ドルが取引されている。信用貨幣(投資信託、社債、ローンなど)の流れも膨大だ。各国で気の遠くなるほど増大した国債は、合法的に回収される見込みはない。国家も企業も個人も巨額債務の返済に追われるなかで、過剰資金の流れが経済を揺り動かしている。
ハーヴェイによれば、資本主義の狂気にとりつかれたのは中国も同じだった。2011年から13年にかけて、中国は65億トンのセメントを消費した。この消費量がいかにすごいものだったかは、1900年から99年までのアメリカのセメント消費量が45億トンだったことをみてもわかるという。
セメントは建造物に用いられる。わずか3年で65億トンものセメントが用いられたということは、この時期に中国ではマンションをはじめとする住宅、道路やダム、飛行場、鉄道駅、コンテナターミナルなどの社会インフラに、いかに莫大な投資がおこなわれたかを示している。
投入されたのはセメントだけではない。鉄鋼の生産もとてつもなく拡大した。製鉄のための鉄鉱石はブラジルやオーストラリアから輸入されていた。2013年ごろには、世界の鉄鋼の半分以上が中国でつくられいたし、中国は世界の主要な鉱石資源の少なくとも半分を消費していた。
2007年から2008年にかけ、アメリカで金融危機(いわゆるリーマン・ショック)が勃発し、それが世界じゅうに波及したのは記憶に新しい。しかし、その資本主義の世界的危機を救ったのは、皮肉なことに中国だった、とハーヴェイはいう。
リーマン・ショックの結果、不況におちいったのは中国も同じだった。中国の輸出は30%減り、南部の工場群は閉鎖寸前となった。2000万人から3000万人の失業者がでたといわれる。だが、このとき中国政府は多くのインフラ事業や巨大プロジェクトを発動し、無制限の融資をおこなった。
その結果、中国全体の債務残高は膨れあがったが、大規模な建設事業がおこなわれ、不動産価格が押し上げられ、住宅への投機がおこなわれた。そして、突如、大金持ちが生まれた。
負債金融が実施されたのは中国だけではない。日本でも大量の国債が発行された。しかし、世界経済の回復にもっとも寄与したのは、中国の建設ブームだった。中国は大規模な建設投資によって、大量の労働力を吸収した。ハーヴェイによると、中国のGDPの4分の1が住宅建設によるものであり、さらに別の4分の1が高速道路、水道設備、鉄道、空港などのインフラ投資によるものだったという。
こうした中国の手法は、ある意味でおなじみのものだった。それは1929年の大恐慌以来、さらに第2次世界大戦後にアメリカがおこなってきた物的インフラや社会的インフラへの大規模投資をまねたにすぎない。新たな都市空間の創出は、恐慌への対応策として、過剰資本と過剰労働力を解決するために古くから用いられてきた手法だ。とはいえ、近年の中国における変容は、その規模もその速度も突出していた、とハーヴェイはいう。
だが、こうした手法はいつか限界にぶつかる。アメリカでは早くから、「企業型都市再発計画の無味乾燥な試みと陳腐な郊外型生活様式にたいして公然と反抗」する動きがおきていた。そして、あげくのはてに不動産市場が崩壊する。都市の空間形成は、そうした発展と崩壊の波をくり返してきた。中国ではいま住民がいない「鬼城(ゴーストシティ)」があちこちに広がりつつある。
ハーヴェイはこう書いている。
〈資本が建設するのは、人々や諸機関の投資先としての都市なのであって、民衆が住むための都市ではない。どれほどの正気がこれにあるというのか?〉
中国の建築ブームが後退すると、グローバルな原材料需要は落ちこみ、とりわけ中南米の国々が苦境におちいった。それは先端の工作機械などを輸出しているドイツでさえ例外ではなかったという。
歴史的にみて、資本は過剰蓄積問題を解決するために「空間的回避」をおこなってきた。過剰資本と過剰労働力を海外に向けるのが帝国主義の論理だったが、こうした「空間的回避」の思考はいまもつづいている、とハーヴェイは論じている。
日本は1960年代後半から、韓国は1970年代から、台湾は1980年代前半から、過剰資本を輸出しはじめた。そして、2010年以降、それを盛んにおこなっているのが中国だ。
中国は過剰な鉄鋼能力を保有しており、可能なかぎり多くの鉄鋼を安い値段で輸出している。さらにいろいろな国に資金を貸し付けて、鉄道や道路、港湾などのインフラや建造物をつくらせている。ニカラグア横断運河や南米大陸横断鉄道もそのひとつだ。一帯一路構想という巨大プロジェクトもある。これらが実現すれば、過剰資本問題が解決するとともに、対中貿易の増加につながるだろう。
しかし、過剰資本によるグローバル空間の再編は、さまざまな軋轢を呼びさまさないではおかない。
「普遍的疎外」が始動する、とハーヴェイはいう。
複雑化する大量の商品をめぐって競争が激化すると同時に、運輸・通信費の削減や移動速度の上昇も猛烈な勢いで進んでいる。「時間と空間の圧縮」は、労働者に大きな負担と緊張をもたらさざるをえない。
いま世界では大量移民の波が生じている。移民をめぐっては、反移民運動やナショナリズム的熱情が引き起こされるいっぽう、多文化主義の動きも生じている。
世界各地でさまざまな抗議活動が広がっている。異議と不平、場合によっては絶望の風潮が世界に満ち満ちている、とハーヴェイはいう。
その根拠にあるのは、いったい何なのか。
人間と自然との関係の悪化、経済成長至上主義の破綻もそのひとつかもしれない。だが、それだけではない。
世界の「時間と空間」の再編、グローバルな競争、ますます進む機械化と自動化、人工知能をはじめとする新しい技術の導入、下がりつづける労働分配率、偶発的な雇用と失業、正規と非正規の区別、無意味な仕事、労働者間の仕事の競い合い、人種差別、ジェンダー差別、尊敬と敬意の喪失──こうしたことが、働く人びとに疎外感をもたらしている。
そのいっぽうで、資本が多くの有用な商品を生みだしていることもまちがいない。資本主義の発展は世界の多くの地域で平均余命の延長をもたらした。社会的福祉の増大にも貢献した。しかし、多くの商品は両刃の剣でもあり、たとえば自動車が公害や渋滞、危険をもたらしたことも事実だ。大気汚染が人びとを苦しめている。
人びとの欲求や欲望ははてしなく、その実現の困難性が疎外感を深めている。スマホやパソコンが、幸せをもたらしているとはかぎらない。社会は便利になったぶん、刹那性を増し、また思わぬ落とし穴を生んでいる。さらに、商品世界の進展から取り残された多くの人びとのあいだでは、絶望と不満が深まっている。
近年では、世界の大半で労働分配率が低下し、技術の発展にともない、多くの労働者はその恩恵を受けるどころか、かえって失業の脅威や生活水準の低下にさらされるようになった。資本主義世界のほとんどで、所得と富の不平等が拡大している。そのいっぽう多くの人が債務(ローン)に縛られ、債務懲役状態に陥っている。
ハーヴェイは、こう記す。
〈債務負担による規律づけ効果は、現代資本の再生産にとって決定的に重要である。……『聖書』が求めるように負債が赦(ゆる)されることなど、資本は認めることがないのであって、むしろわれわれは、未来の価値生産をつうじて自己債務の返済を資本に要求されることになる。……債務懲役は、資本がその特有の奴隷形態を強制するのにおあつらえむきの手段なのだ。〉
その背景にはカネ、カネ、カネの世界がある。
ケインズのいう「財産としての貨幣愛」、すなわち貨幣を富とみなし、それを蓄積しつづけようとする傾向は、それ自体が問題であり、われわれは「このような、ひどく厄介なまでに狂った世界」に生きている、とハーヴェイは記している。
だが、その「狂った世界」からの脱出は可能なのか。それが容易でないことをハーヴェイも認めている。だから、社会主義革命をなどと安直にはいえない。せめて資本の生みだす「狂った世界」を見つめることを忘れず、そこから出発するしかないのだと主張しているようにみえる。
ハーヴェイ『経済的理性の狂気』を読む(8) [商品世界論ノート]
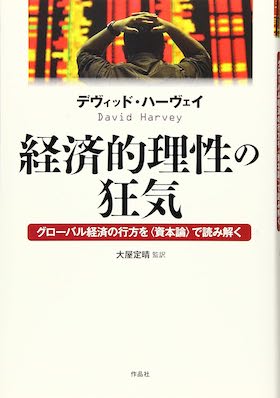
一般に企業はみずからが占有する特定空間にたいして独占権を有している、とハーヴェイは書いている。その空間にたとえ競争相手がいるとしても、その競争は一定の地理的範囲をめぐるシェアの奪いあいで、いわば独占的競争がおこなわれるにすぎない。
かつては高い運輸費と貿易障壁が企業の独占範囲を守っていた。従来、工業にとっては、原材料に近いという立地条件が重要だった。いっぽう、パンなどの生活必需品や傷みやすい商品は、商圏がせまく、業者は他の競争者から守られていた。金や銀、ダイヤモンドなどの世界商品を除いて、かつて市場は局地市場にかぎられていたといえるだろう。
マルクスの時代は、国際貿易は現在ほど盛んではなかった。とはいえ、マルクスは国際経済を念頭に置いていた。国ごとに労働力価値が異なることも認識していた。
国ごとに労働力価値が異なるということは、国ごとに価値体制(貨幣の形態や値段のちがいを含め)が異なるということである。そして、国どうしで貿易がおこなわれるときには、マルクスのいうように「恵まれた国は、少ない労働と引き換えに、多くの労働を受けとる」。
言いかえれば、恵まれた国は、別の国で安くつくられた商品を国内で比較的に高く売ることができるのである。そして、その差額を受けとるのが「特定の階級」であることを、マルクスは指摘していた。
地域的な価値体制が存在することによって、先進国と途上国との貿易は先進国に価値と剰余価値を移転させることになる。そうした状況は現在もつづいている。
マルクスはさらに局地的な法定紙幣と世界貨幣(金や銀)が深刻な分裂を引き起こすことも認識していた。貨幣は国内の流通部面から外にでるときは、その局地的機能を失って、地金(重量としての金や銀)のかたちをとる、と書いている。貨幣が金や銀という純粋な形態をとるのは、世界市場においてである。
だが、1970年代以降、状況は一変した、とハーヴェイはいう。金本位制の痕跡を残していたIMF体制は崩壊し、世界は不安定な変動為替制に移行した。そうしたなか、世界の主要通貨間の相対的価値が変動するなかで、さまざまに異なる価値体制がそれぞれの発展をみせることとなった。
ハーヴェイは資本の歴史地理を重視する。世界の貿易関係が発達し、密になるにつれて、価値体制の異なる国どうしは、まず地域的に結びつき、さらにグローバルなかたちで結びつきを加速していった。
たとえば、アメリカの地方スーパーを例に挙げて、ハーヴェイは1970年と2015年の品揃えについて、こんなふうに書いている。
〈1970年でさえ、アメリカの地方スーパーマーケットでは外国産のチーズやワインは見られなかったし、ビールですら、その大部分が各地で醸造されていた。ナショナルボヘミアン・ビールを飲むならボルチモアであり、アイアンシティ・ビールを飲むならピッツバーグであり、そしてクアーズ・ビールといえばデンバーであった。こうした状況は劇的に変わった。あらゆる地方スーパーマーケットに世界中の食料品が置かれ、主要都市でならほぼどこの地ビールも飲むことができる。〉
これは日本もほぼ同じだといえる。ビールはともかくとして、どの町のスーパーでも、世界中の食料品が置かれるようになった。日本中でつくられる酒が並んでいる。どこにいってもマクドナルドの店をみかけるようになったし、イタリアンの店も多い。
たしかに1970年代以降、どこの町にも世界の商品が押し寄せるようになったのだ。
だが、その動きは第2次世界大戦後から加速していた。1945年以降、資本の歴史の大部分は、運輸費の削減と貿易障壁の段階的撤廃に捧げられた、とハーヴェイは指摘している。
地域的な価値体制間の差異は消失しつつあるともいう。とはいえ、空間をめぐる独占的競争がつづいていることもまちがいない。TPPなど多くの貿易協定が結ばれ、中国が一帯一路構想を打ち出すなどをみても、空間の支配をめぐる競争がますます激しくなっていることはあきらかだ。
もうひとつ重要なことがある。巨大企業はそれまでも市場支配力をもっていたが、1970年代以降、空間的障壁が徐々に取り払われるにつれて、企業の考え方は一国的なものからグローバルのものへと転換した。
たとえば、アメリカではそれまでGMやフォード、クライスラーが自国の自動車市場を占有していたが、1980年以降は日本やドイツ、イタリア、韓国、中国からの挑戦を受けるようになった。そのいっぽうで、アメリカの企業がグローバル化する傾向も強まっている。農業関連産業やエネルギー産業、製薬業、通信業は世界市場を想定するようになった。最近ではグーグル、アマゾン、フェイスブック、アップルなどが世界を席巻している。
資本は集中と規模の拡大を見境なく追求することによって、競争上の優位を保ち、独占をめざそうとする。ハーヴェイのいうように「資本主義的競争が創造するダーウィン主義的世界では最適企業のみが生き残る」。その手段のひとつが、企業の合併吸収(M&A)だ。
1980年代以降はとりわけ生産と流通の加速化が進んだ。運輸費や調整時間が削減され、多くの企業が猛烈な競争をくり広げるいっぽうで、労働者は海外の労働者との熾烈な競争を強いられるようになった。だが、労働者はそれによって利益を受けることはなかった、とハーヴェイは断言する。
世界経済のなかでは、さまざまな地域的価値体制が関係しあい、その力関係を変動させている。先進国と開発途上国が存在することをみても、その価値体制は、ある程度長期的なものだ。
だが、過去40年にわたり、とりわけ特徴的なのは、さまざまな価値体制が接近し、交錯し、収斂していることだ、とハーヴェイはいう。世界のグルーバル化が進んでいる。
とはいえ、単一の価値体制が存在するわけではない。いまのところ世界貨幣も存在しない。むしろ、資本は価値体制の差異を利用して、価値増殖を実現しようとしている。局地間競争、地域間競争、大国間競争はむしろ激化している。
グローバルな価値連鎖は複雑さを増している。たとえばアメリカの企業が自国市場向けの商品をメキシコでつくるとしよう。その企業はアメリカのノウハウをメキシコの低賃金労働者と結びつけて製品をつくりだすわけだが、そこに投入されるのは中国製の部品やアフリカ産の原料だったりする。
産業による空間と時間の形成は、大きく変動しつづけながらも、けっして立ち止まることはない。アメリカでは、中西部で旧産業(鉄鋼・石炭・自動車など)の夢の跡ともいえるラストベルトが生まれるいっぽうで、いまや南部や南西部に宇宙産業や先端技術に特化したサンベルトが生まれているのも、その象徴だ。
「価値の運動法則は空間と時間のなかで自らを貫徹していく」。資本の本性のなかには、世界市場の征服と構築のために、あらゆるものを(自然も人間をも)犠牲にすることをいとわない暴力性が備わっている、とハーヴェイは書いている。
ハーヴェイ『経済的理性の狂気』を読む(7) [商品世界論ノート]
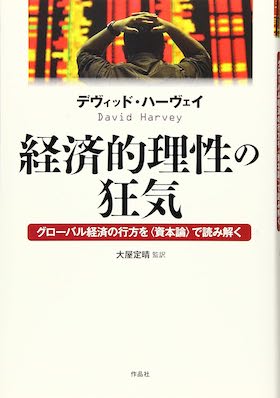
産業革命以来、資本主義は200年という時間をかけて、グローバルな空間に広がっていった。これは歴史的なテーマだが、同時に理論的なテーマでもある。ハーヴェイは『資本論』をベースとして、資本の時間と空間の広がりを論じようとしている。
運動する価値としての資本は経済権力だといってもよい。それは原料を生産する場の景観をつくり、運輸ネットワークを組織し、ヒトとモノと情報の流れを統轄し、労働者を管理し、株価や地価を操作する。
マルクスは資本が世界市場という空間を生みだすことを早くから意識していた。そもそも商人資本家は、ある場所で安く買ったものを別の場所で高く売ることで、大きな富を築いてきたのである。
さらに産業資本は、はるか遠くの地域で産する原料にもとづいて、かずかずの新たな商品をつくりだし、それがなくては満たされない新しい欲求をつくりだし、これまでの産業を滅ぼしてきた。
安価な商品は「どんな万里の長城をもうちくずさずにはおかない重砲だ」とマルクスは書いている。資本にはそもそも世界市場をつくりだしていく傾向がある。
加えて、運輸・情報革命が商品の流通を促進し、国境の壁をくずしていく。マルクスの時代においては、蒸気船や鉄道、港湾、運河、道路などの建設、電信や新聞の普及が、産業の発達に呼応するように進んでいた。
マルクスはすでにこう書いていた。
〈資本は一方では、交易すなわち交換のあらゆる空間的制限を取り払い、全地球を資本の市場として征服しようと努めないではおられないのだが、他方では、時間によって空間を絶滅しようとする。資本が発展すればするほど、資本はますます大規模に空間的に市場を拡大しようとし、またそれと同時に時間によって空間をますます絶滅させようとする。〉
空間の拡大と時間の圧縮が資本の求める夢なのだ。
資本によって生みだされるかずかずの商品は、世界の伝統社会を解体していく先兵にほかならない。こうした資本の破壊的傾向に対抗するには、地域自体もまた資本主義的な生産様式を取り入れる以外に道はない。古びた世界が近代への扉を開くと、結果的には資本のグローバル化が進むことになる。
その過程で発生するのが巨大な都市だ。そして、これまで支配的だった農村は都市に従わざるをえなくなる。都市には人口が密集し、生産手段が集中し、財産が集積する。
いっぽう政治は中央集権的となる。それまで独立していた地方は、ひとつの国家のもとに結びつけられ、国家を単位として、政府と国民、法典、利害関係が生まれ、近代の国民国家が誕生する。
先に中央集権化された国家と市民社会は、それ自体、帝国主義的侵略や植民地拡大の志向を秘めていた。マルクスは自身の理論的モデルに植民地などの外的要因を組み込んでいない。とはいえ、「世界市場をつくりだそうとする傾向は、直接に、資本そのものの概念のうちに与えられている」というのがかれの基本的な考え方だった。そして、列強の暴力による植民地形成が、現地での強い抵抗に見舞われるのも必至だとみていた。
とはいえ、『資本論』でマルクスが重視したのは、資本の空間的広がりよりも時間的持続だった。資本が拡大する秘密は、資本がじっさいに支払う以上の、できるだけ多くの超過労働時間を盗み取ることによるものだった。それによって、資本は剰余価値を獲得し、自己拡大する循環過程をえがくことになるのだ。
ここでハーヴェイは資本の時間的循環を空間的広がりにまで拡張しようとこころみている。
とはいえ、空間と時間という概念は一筋縄では説明しがたい。空間や時間は地図や時計で表されるものなのか、それとも文化的に規定されるものなのか。空間と時間にたいする意識は、過去200年間をとっただけでも、大きく異なっている。それは革命的な力である資本が「日常生活の、経済計算の、官僚行政の、そして金融取引の空間的、時間的枠組みを変化させてきた」からだ。
空間と時間という概念を把握するために、ハーヴェイは「絶対的」、「相対的」、「関係的」というカテゴリーをもちだしている。それは固定的、流動的、外部効果的という規定に置き換えてもいいのだが、これについては深入りしない。いずれにせよ、空間と時間という概念がきわめて動的であることを念頭においておけばよいように思われる。
資本はなぜ時間を圧縮し、空間を拡大しようとする傾向をもつのか。そのことを理解するには、総資本の回転をチャート化するのが、いちばんわかりやすいとハーヴェイは考えている。
資本は消費財を生産する資本だけではない。固定財(機械や耐久財)を生産する「固定資本」もある。さらに、貨幣を生みだし運用する「利子生み資本」もあるだろう。それに流通資本を加えてもいいのだが、こうした資本の総体を総資本と名づけるならば、資本は単なる「資本」としてではなく、総資本としての運動(循環)をくり返していることがわかる。
消費財の生産と消費のくり返しが第1次循環をかたちづくるとすれば、これに「固定資本」と「利子生み資本」がからんでくると第2次循環が形成される。それだけではない。資本主義社会は国家なしには成り立たないのだから、国家による資本主義社会への関与が第3次循環を形成する。現代の資本主義は、こうした第1次、第2次、第3次の総循環と、空間・時間のうえに成り立っているというのがハーヴェイの解釈だといえるだろう。
もう少し詳しくみていこう。
マルクスは、さまざまな資本がさまざまな回転期間をもつこと、さらにその流れは時間的にみれば、生産期間と流通期間に分類できることを指摘した。それでは固定資本の形成と流通はどう理解すればいいのか、とハーヴェイは問う。
産業資本家にとっての固定資本は、何といっても機械である。この機械が最先端のものであるなら、資本家は特別剰余価値を得ることができる。だが、それはほかの産業資本家がこの機械を導入するまでのことだ。しかも、その機械を得るためにおこなった投資は機械の耐用期間のうちに回収されなければならない。そのもっとも単純な方法は定額原価償却だ。
しかし、そうのんびりと構えていられないのは、次々と新しい機械が発明される可能性があるからだ。更新費用や機械の価値評価が変動する可能性もある。資本家はそれにそなえる資金を積み立てるか、銀行からの借り入れを想定しなければならない。しかし、機械を毎年リース契約すれば、そうした変動はそのリース料に反映されることになるだろう。
固定資本である機械をリース契約する場合には、利子生み資本がかかわってくる。すると、とうぜん資本の空間はさらに広がってくる。機械をリースで貸与する会社は、いうまでもなく利子相当分を期待する。
いずれにせよ固定資本の形成と利子生み資本(金融資本)とのかかわりは必至である。
ハーヴェイは資本主義が発展するにつれて、固定資本の割合が大きくなることを指摘している。それは過剰人口を吸収するとともに、商品の量的過剰を抑制し、新たな商品やインフラを生みだす。そこに利子生み資本と国家がかかわって、日常生活の形態自体を変えていく。
マルクスの時代においては、かずかずの機械に加え、鉄道や運河、水道、電信などのインフラもそうした固定資本だった。いまでも自動車、高速道路、高層マンション、病院など固定資本の占める割合はますます増えているといえる。日常生活にはいりこむ固定資本(たとえば電気製品)も多くなっている。すると、固定資本の循環が大きな課題となってくる。
消費財資本と固定資本は密接にかかわり、それぞれ循環し資本の時空間を広げながら、価値の増殖をめざしている。だが、そうした時空間に「反価値」がはいりこむことは避けられない、とハーヴェイはいう。
固定資本の規模が大きくなればなるほど、利子生み資本は債務の返済という致命的代償を要求する。しかも、固定資本が耐用期間をすぎてまで、価値を生みだしつづけるかは不確実である。はたしてどこまで利子負担をまかないきれるのかは未知数だ。
固定資本の価値は常に減価される危険性をはらんでいる。固定資本は過剰資本と過剰労働力を吸収するテコになるけれども、いっぽうで過剰な資金を固定し、恐慌を引きだすバネともなっていく。
資本の空間と時間はすでに飽和状態となっているのだろうか。あるいは古い資本は新しい資本に置きかわりながら、市場を淘汰していく作用をくり返しているのだろうか。だが、その作用が苛酷な現実をもたらす。1980年代以降、先進国の大半では、産業の空洞化が地域社会を破壊し、中間層や労働者階級に大きな打撃を与え、あちこちに見捨てられた産業景観や自然風景、住環境を残したことも事実である。
資本には第3の循環も存在する、とハーヴェイはいう。それは国家財政にもとづく循環である。国家は国民に教育や職業訓練を課し、医療や年金といった社会的サービスを提供する。さらに軍や警察によって治安を維持するとともに、科学技術やインフラを促進して新たな価値の創造に寄与するといった面もある。それが、資本の総循環に深く関係していることはいうまでもない。
こうして、ハーヴェイは、現代の経済社会(資本の時空間)を理解するには、単なる生産資本だけではなく、固定資本や金融資本、流通資本、国家財政の動きと循環をとらえることが重要だというごくあたりまえの結論を導いている。
ハーヴェイ『経済的理性の狂気』を読む(6) [商品世界論ノート]
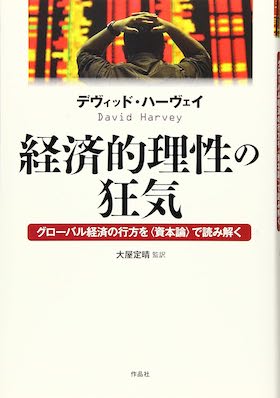
ハーヴェイがめざしているのは、『資本論』を古典として扱うことではなく、現代資本主義の探求にまで拡張することだ。
第6章では技術の問題が論じられている。
マルクスが『資本論』で展開したのは、商品の生産と資本の増殖に技術がいかにかかわっているかにかぎられていた。
資本主義が技術の発展をうながしたことはまちがいない。激しい競争のもとでは、よりすぐれた技術や組織をもつ企業が市場を占有し、超過利潤を得るからである。そのため競争が激しいほど、飛躍的なイノベーションがおこりやすい。
新たに導入された技術は労働生産性を高めるとともに、個々の商品の価値を低くするいっぽう、大量の商品を生みだす。それによって、資本家の利潤は全体として多くなり、その一部が労働者に還元されるなら、労働者の生活水準は向上する。
技術を代表するのが機械である。とはいえ、機械が価値を生んでいるのではない、とハーヴェイは釘を差す。機械は労働と結びつくことによって、資本家に特別剰余価値をもたらすのだ。
新技術の導入は熟練労働者を排除し、単純労働力に置き換える方向にはたらきやすい。さらに機械は賃金労働者を「過剰」にする傾向をもっている。つまり、労働者の失業を招くだけではなく、賃金を抑える効果がある。
そのいっぽう、商品のイノベーションと新技術が密接に結びついていることをハーヴェイも認めている。新技術は生産価格を低くして、製品市場を広げる。あるいは、まったく新たな商品や産業部門を創出する。それが新たな雇用を生みだすこともあるだろう。
技術は機械というハードウェアにかぎられるわけではない。パソコンやスマホを例にとっても、それにはアプリなどのソフトウェアに加え、通信ネットワークなどの組織も必要である。
技術が商品の形態を変え、新たな商品を生みだすことは事実である。しかし、マルクスはけっして技術決定論者ではなかった、とハーヴェイは断言する。
マルクスが主張したのは「諸契機」からなる総体をとらえなければならないということである。その「諸契機」とは、技術、自然との関係、社会的諸関係、物質的生産様式、日常生活、精神的諸観念、制度的枠組みの7つであり、マルクスは、近代の特徴は、その変化が資本の不断の運動によってうながされていることだととらえていたという。
ところが多くの人は決定論におちいりやすい。
ハーヴェイはこう書いている。
〈社会科学における研究の大半は、社会変革についての何らかの「特効薬」型理論に引きつけられている。制度学派は制度的イノベーションに、経済決定論者は新しい生産技術に、社会主義者とアナーキストは階級闘争にそれぞれ引きつけられており、理想主義者は精神的諸観念の変革を強調し、文化理論家は日常生活の変化に焦点を当てる、といった具合だ。マルクスを特効型の理論家と解することはできないし、またそう理解してはならない。〉
もはや単純な権力奪取は、社会変革の特効薬とはなりえないというわけだ。「ソヴィエト共産主義の失敗は、7つの契機すべての相互作用を無視してしまい、共産主義への適切な道筋は生産力革命を介してであるといった、特効薬型理論を支持したことに大きく起因している可能性がある」
それはともかくとして、諸契機のひとつである技術が資本の運動を通して、社会的諸関係や精神的諸観念を含めてあらゆる局面に影響をおよぼすことをハーヴェイはあらためて確認している。
そうしてみると、資本主義こそがやむことのない革命なのだった。技術それ自体も資本主義のもたらしたひとつの革命だった。「前資本主義社会には技法(テクネ)があったが、資本主義にあるのは、秘儀にとどまりえない技術(テクノロジー)なのである」とハーヴェイも論じている。
技術は生産体制を変え、自然にたいする人間の精神構造をも変えていく。新たな技術のもとで、労働者は機械の下ではたらく「断片的人間」へと変容していく。だが、技術を使いこなして、人がはたらくには、教育や訓練が必要となってくる。
重要なのは、技術自体がイノベーションを引き起こすことである。蒸気機関は、運輸(とりわけ鉄道)や鉱山、耕作、製粉、織機工場に大きな変革をもたらした。それは現在コンピューターがさまざまな業界に応用されているのと同じだ、とハーヴェイはいう。
いまでは技術そのもの(正確にはビジネス化された技術の結晶)がたえず更新される一大産業部門をかたちづくっている。そして、「あらゆる問題への解決策として技術的回避や技術革新を信じる物神的信仰は、これこそ原動力にちがいないという誤った信念とともに深々と根をおろしていく」。
だが、技術の物神崇拝はそれが自覚されなければ危険なものとなりうることを、ハーヴェイは指摘する。
〈技術的回避にたいする物神崇拝的信仰によって支えられる自然主義的見解によれば、技術進歩は不可避かつ善きものであり、それを制限することはおろか、集団的に制御し修正することさえもできないし、またすべきでもない。しかし、架空の信仰が社会的行為に影響を与えるようになることこそ、まさに物神的構築物の特色なのである。〉
福島第一原発の事故は、まさしく技術の物神崇拝がいかに危険かを示す象徴的なできごととなった。
それだけではない。ハーヴェイが指摘するのは、技術開発が労働者の力を奪う傾向を秘めていることである。AI(人工知能)はストもおこさないし、賃上げも求めないし、労働環境も気にしないし、欠勤することもない。
だが、技術の導入には根本的な矛盾が生じる。極端な場合を想定すると、もし技術によって労働者が商品の生産過程や流通過程から完全に排除されてしまえば、賃金も発生せず、市場自体が枯渇してしまうのだ。
そのこと自体、マルクスはすでにこう述べていた。
〈資本はそれ自身が、運動する矛盾である。それは[一方では]労働時間を最小限に縮減しようと努めながら、他方では労働時間を富の唯一の尺度かつ源泉として措定する、という矛盾である。〉
そのいっぽうで、ハーヴェイは機械が導入されたからといって、労働が軽減されることはないとも述べている。労働者は生産過程の端役として、いままで以上に機械のようにはたらかされるのが通常だ。
マルクスは『資本論』で、技術産業そのものについて言及することはほとんどなかった。当時、技術産業はさほど発展していなかった。せいぜいが工作機械と蒸気機関くらいのものだった。現在の技術は、マルクスの時代をはるかに凌駕している。
にもかかわらず、マルクスは技術の発展が外生的で偶然のものでなく、資本にとって内生的で固有のものであることを認識していた、とハーヴェイはいう。
マルクスはイノベーションがそれ以外の領域にも波及効果をもたらすこと、今後は技術自身が自立したビジネスとなり、かずかずの商品を生みだしていくこと、そして、それが自然や社会、精神、日常生活にどのような影響をもたらすかを見極めていかなければならないことをじゅうぶんに認識していた。
最後にハーヴェイは資本主義のもとで進行する技術の反ユートピアに言及している。
技術の組み合わせとその可能性は、現在、人類史上かつてないまでに重要なものとなっている。だが、現在の国家と資本のもとにおける技術の発展は、きわめて歪められた社会的関係、精神的観念、自然との関係をもたらしてはいないか。そのことを点検せずに、ひたすら技術にたいする物神崇拝にふけるのは、きわめて不健全だ、とハーヴェイは論じている。
ハーヴェイ『経済的理性の狂気』を読む(5) [商品世界論ノート]
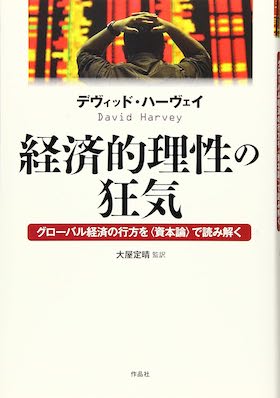
第5章「価値なき価格」にはいる。ここで述べられるのは「価値と価格の不一致」についてだ。
以前、ハーヴェイは、市場においてそのまま価値を実現することがじつに困難だと述べていた。かれの用語を使えば、価値の実現は「反価値」によって阻まれがちだというわけだ。
この章で論じられるのは、むしろ逆の現象である。市場では、価値を超えるかたちで価格が形成され、実現されてしまうことがある。
価格だけをみていると、じっさいの価値を見失う。その典型がバブルだ。投資家はいつもバブルを望んでいるともいえる。
投資家が価値の創造に投資するのではなく、直接的には価値のない資産から投機的利益を得ようとすると、擬制的市場における非合理的な貨幣の暴走がはじまる。その結果は、経済を発展させるのではなく、むしろ経済に長期的停滞をもたらす、とハーヴェイはいう。資本主義にはこうした貨幣の暴走がつきまとう。
ここで、ハーヴェイは資本のもうひとつの注目すべき動きを論じる。それは資本が自然をわがものとしようとしていることだ。
ハーヴェイにいわせれば、資本は自然からの無償贈与を求めつづけている。言いかえれば、ほんらい「自由財」である自然を「商品」にしようと、常に機会をうかがっているというわけだ。
自然を囲い込んで、使用価値に取りこむことができれば、自然に値段がつき、自然が「商品」となる。
そうした自然は「資源」にとどまらない。文化的遺産もそのひとつだろう。人間の技能や知識もそうだ。資本はそうした自然をうまく取り込むことで、みずからの利潤を得ようとしつづける、とハーヴェイはいう。
コンピューター社会のもとで資本が求めるのは、賃金労働者よりも、むしろフリーランサー(自由契約者)だ、とハーヴェイは書いている。資本はかれらの独創的で創造的な活動によって生みだされる自由財を喜んで略奪し、みずからの利潤の源とする。
コンピューター社会をたたえる「認知資本主義論者」は、経済は商品基盤型から知識基盤型へと移行したという。しかし、じっさいは資本によって「知識というコモンズが絶えず囲い込まれ、私有化され、商品化される」ことこそが問題なのだ、とハーヴェイは論じている。「というのも資本は、今ある生産対象やその生産方法を掌握するだけでなく、他人の知的、文化的作品を、さも自分のものであるかのように領有する事態にまでおよぶからである」
知識それ自体はだれもが利用できる自由財だ。認知資本主義論者の誤りは、「囲い込み、商品化、領有」によって、そうした知識を資本が無償で使用価値に転じていることに無自覚な点にある、とハーヴェイは批判する。
マルクス自身も科学的知識そのものは自由財と考えていた。しかし、問題はその科学的知識が機械に応用されて、資本に組み入れられ、自動化によって労働者を駆逐し、無力化することだった。資本主義は労働節約的イノベーションを選好する。それにより商品の物的生産は増大し、商品が飽和状態に達して、利潤率は低下していく。
工業部門のロボット化と自動化によって失われた雇用を補うのは、いまのところ物流や運送、食品製造、観光業などの労働集約型部門である。とはいえ、雇用喪失と雇用獲得のバランスは予断を許さない。
いっぽうグーグルやフェイスブックなどのデジタル産業は、多くの無償労働によって支えられている。
資本主義そのものはあくまでも利潤を求めるものだ。ところが、その多くの活動は価値を創造していない。観光業などをみてもわかるように、無償の贈与を取りこむことで、価格を織りこみ、利潤をだしている。もちろん観光業は多くの商品(たとえば飛行機やホテル、おみやげ)などとも関係しているが、直接の商品とはいえない風景に価格をつけ、それを売り物にしているのも事実だ、とハーヴェイはいう。
さらに資本が労働から利潤を引きだすことは今も昔も変わらない。マニュファクチュア時代は職人の技能が、工場制では労働時間や労働者の知識が資本に利潤をもたらす源泉となっていた。日本の自動車産業の成功は、多くの部品を下請け工場に負っていることによる、とハーヴェイはいう。
このあたりの記述は錯綜し、混乱しているが、いずれにせよハーヴェイは資本の生みだす夢物語の背後に、もうひとつの事実が隠されていることを示唆しているといえるだろう。
最後にハーヴェイは価値の概念を切り捨て、価格によってすべての経済事象を説明する考え方に反対している。
現在の資本主義の問題は、市場において価値と価格の乖離が大きく開き、しかも広がりつつあることだというのが、かれの見方だ。
そして、価格論ですべてが片づくなら、こうした矛盾が説明できなくなってしまうという。価値のないものに高い価格がつけられたり、価値のあるものに低い価格しかつけられないとすれば、それは現代の「大いなる矛盾」なのだ。
「貨幣と価値の矛盾をまったく無視することは、現代の資本蓄積が抱える困難を理解するうえで、正直なところ複雑かつ重要な理路を断ち切ってしまう」
貨幣万能論はきわめて危険である。たとえば、現在の量的緩和は、価値が存在しないところに貨幣を創造しようとするものだ。
この貨幣が利子生み資本として流通する場合は、投下された資本は不動産などの資産市場、あるいは株式市場、美術品市場に流入する。すると、超富裕層はその投機活動でさらに裕福になるが、それによって何らかの価値を創造しているわけではない。
その結果、経済の長期停滞が生ずるばかりか、ポンジ型資本主義(ネズミ講的な資本主義)がつくりだされる。
こうした現象にたいして批判的視座を保つためにも、価値と価格の区別を頭にいれておくことは重要なのだ、とハーヴェイは主張している。



