貨幣論(1)──メンガー『一般理論経済学』を読む(8) [商品世界論ノート]

いまや貨幣といえば金貨や銀貨でなく、紙幣と少額コインが中心で、しかもカード決済が広がり、だれもが銀行口座をもち、為替相場が日々変動し、株の上がり下がりに一喜一憂する人が増えている時代である。
メンガーが『一般理論経済学』を残した100年以上前とは、すっかり貨幣をめぐる状況がさまがわりしている。さらに、これからも貨幣の世界は変わりつづけるだろう。
にもかかわらず、人が貨幣に振り回されていることは、100年前もいまも変わらない。20世紀のはじめにメンガーが貨幣をどのようにとらえていたかを確認しておくのは、それなりに意味がある。
最初にメンガーは、貨幣の本質と起源を論じている。
貨幣の歴史は長い。金や銀が交換媒体(流通手段)になるのは、経済がある程度発展した段階である。鋳造された金貨や銀貨が登場し、紙幣や銀行券が一般的になるのは、さらにその後だ。
人間は貨幣を手に入れることに血道を上げてきた。市場以外の日常の領域でも、人の生活を縛るこの「紙切れ」の本性はいったい何なのか。それは古くからの制度や取り決めのひとつなのか、それとも経済と交易の発展がもたらした所産なのか。メンガーはそんなふうに問うところから貨幣の考察をはじめている。
人類の歴史をさかのぼると、自己充足的な自然経済のなかでは貨幣など必要ではなかった。また物々交換が容易にできるなら、貨幣はいらなかった。何らかの交換媒体が必要になるのは、交換や交易がさかんになってからである。
当初は定期的に開かれる市場で物々交換がなされていたとしよう。だが、物々交換は、ただちに困難にぶつかる。たとえば奴隷や牛、象牙などの大型財は、それらと交換しうる財を容易にみつけることができない。
物々交換の市場では、たがいに商品を交換しようという当事者の組み合わせがまったく成立しないか、成立してもごくわずかにとどまってしまう。したがって、商品の需要があっても、商品がほとんど動かないことになる。物々交換を実現するには、よほどの骨折りと努力を必要とする、とメンガーはいう。
そこで、物々交換の困難を除去する補助手段が生まれてくる。ほしい商品を手に入れるためには、まず自分の商品を市場性の高い商品と交換することが求められる。そして、その市場性の高い商品を、ほんとうに自分がほしい商品と次に交換するわけだ。
市場性の高い商品としては、無限に需要のある商品(たとえば奴隷や指輪、銅など)、さらには地元産品(武器、装飾品、穀物、カカオ豆など)、輸出品(塩板、鉄、延べ棒、木綿など)、その他、だれもがほしがる財が挙げられる。
こうして市場性の高い商品との交換が日常化すると、そのうちに「残りのあらゆる商品と比較してより販売可能性があり、したがって通例それだけが一般的に使用される交換手段」が生まれるようになる。
一般的に使用される交換手段が成立するのは、習慣の影響が大きい、とメンガーは書いている。それは経済的利益に沿うものとして積極的に需要され、また蓄積や持ち運びに便利な財でなくてはならない。こうした交換財は高価であると同時に分割可能であり、同時にできるかぎり空間的・時間的な制約を受けないものでなければならないという。
こうして交換媒介手段としては、次第に家畜や貝殻、カカオ豆、固形塩などより金属のほうが便利だということになっていく。
こうした説明を通じて、メンガーが強調したいのは「交換手段はもともと法律や社会的契約によって成立したのではなく、『慣習』によって成立した」ということである。ただし、メンガーはのちに国家が社会の慣習に手を加える可能性を排除していない。
最終的に一商品が一般通用交換手段になると、その商品(つまり貨幣)と残りのあらゆる商品とのあいだでは本質的な区別が生じてくる。
〈特定の財がすでに交換媒介物となり、交換媒介物としての一般的使用が確立している国民のもとでは、財を他の財と取引するために市場に行く者は、いまやこの目的を達成しようとすれば、自分の財をまず貨幣にたいして譲渡することに経済的利害関心を抱くようになるだけではない──彼は今後はまさにそれを強制されるのであり、また市場で財を得ようとする者は、たいていはまさしく、この目的のためにあらかじめ「貨幣」を調達せざるをえないのである。〉
こうして貨幣は商品のなかでも一般の商品と画然と区別された「例外的な地位」を得ることになる。
貨幣の登場は市場の様相を一気に変化させる。貨幣によって商品の価格が示されると、商品の販売はより容易かつ継続的になり、市場は「はるかに厳密で経済的なもの」となっていく。
貨幣はそれ自体無価値なもので、単なる表章にすぎないという考え方はまちがっている、とメンガーはいう。独自の商品として交易価値を保証されてこそ、貨幣ははじめて機能する。国家は布告だけで貨幣を思うままに規制できるわけではない。
メンガーは貨幣を財交換を媒介する商品ととらえる。ただし、一般の商品が消費の場に移行するのにたいし、貨幣はたいてい市場にとどまりつづけるという独自性をもつ。
歴史的にみると、さまざまな財のなかでも場所的にも時間的にも最も通用する財が、交換手段としての役割をはたすようになってきた。そのなかでも金属、とりわけ貴金属が貨幣として用いられるようになった。
貴金属への需求は、空間的にも時間的にも大きく、恒常的だ。しかも、貴金属は分割しやすく運びやすいという特性をもっている。さらに保存しやすいこと、ほかの財とくらべて価値が安定していること、また長持ちして判別しやすいことも、貴金属が貨幣として用いられる理由だった、とメンガーはいう。
貴金属はもともと未加工の状態や半製品のままでも交易に用いられていたが、それは次第にかたまりに分けられるようになった。だが、市場でそのかたまりが本物かどうかを判定し、いちいち秤で重さを計るのはわずらわしい作業にはちがいなかった。
そこで金属の延べ棒や小片に小さな刻印がつけられ、その純分量が保証されるようになる。やがて、それは鋳貨に発展していく。
やがて鋳貨はその重量や純度を含め、画一かつ大量に製造されるようになる。そして、その枚数を数えるだけで、その価値を簡単に計算できる道具となった。
さらに、複数の鋳貨がつくられ、各種鋳貨の交換比率が定められ、鋳貨体系が確立されると、交易はより容易で厳密なものになっていく。
とはいえ、「貨幣制度は自生的な発展にまかせるだけでは、発展した国民経済のそれにたいする諸欲求を満足させることができない」と、メンガーはいう。
〈貨幣は法律によって成立したものではなく、その起源からして、国家的な現象というよりは、社会的な現象である。貨幣が国家の権威によって裁可をうけるかどうかは、貨幣の一般概念とは無関係である。けれども、貨幣制度や、その交換媒介物としての機能、またそれから生じる結果的諸機能は、国家によって承認され規定されることによって完成され、交易の発展とともに生じる多様にして変化の多い要求に適合させられるのである。〉
国民経済全体で貨幣が必要になってくると、貨幣の鋳造は民間にまかせるわけにはいかず、国家が介入しないわけにはいかなかった。
国家が貨幣鋳造の専権を濫用する事例には事欠かないが、それでも変造や偽造から貨幣を守り、交易に応じて必要な貨幣を提供するのは、国家にしかできない役割だった、とメンガーは書いている。
さらに国家は国内はもちろん、国外にたいしても、自国の統一的な貨幣制度を維持するという役割をはたしている。それによって交易の支障は取り除かれ、債務の履行なども確実なものとなるのだ。
とはいえ、さまざまな種類の鋳貨には異なる金属を用いる必要があり、金属市場が変動することを考えれば、統一的な鋳貨体系を維持するのはなかなか困難なことだった。
そこで、国家は金属の品位や価値に多少の偏差が生じたとしても、法令によって貨幣の名目価値を定め、その支払い能力と交換比率を保証するようになる。
「秩序だった鋳貨制度を有する一国では誰もが、すべての賃金稼得者、いやすべての子供でさえも、一つの統一的な、あらゆる価格段階を容易かつ厳密に表示し、きびしい危機においてすら正常に機能する貨幣制度の利点にあずかることができる」と、メンガーは書いている。
経済が安定し、盛んな交易がおこなわれるには、「十分整備された統一的な国定法貨」が求められるのである。
以上は前置きにすぎない。問題はこうしてつくられた貨幣が、実際にどのような機能をはたすかである。そのことが次に論じられる。
樋田毅『記者襲撃』を読む ──大世紀末パレード(22) [大世紀末パレード]

〈1987年5月3日に兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局が散弾銃を持った目出し帽の男に襲われた。当時29歳の小尻知博記者が射殺され、当時42歳の犬飼兵衛記者が重傷を負った。この事件を含め、約3年4カ月の間に計8件起きた「赤報隊」による襲撃・脅迫事件は、2003年3月にすべて公訴時効となった。記者が国内で政治テロによって殺された事件は、日本の言論史上、ほかにない。〉
本書「まえがき」冒頭に記されたこの一節が、事件の全容を示している。著者は、朝日新聞在職中も定年退職後も、30年にわたり、この事件を追いつづけてきた。犯人はつかまっていない。犯行声明らしきものは出されているが、はっきりした動機はわからない。
朝日新聞の支局が襲われ、記者が殺されたというできごとだけが人びとの記憶に強く刻まれることになった。
事件は赤報隊を名乗る2、3人のグループによる犯行だ、と著者はみている。1987年から90年にかけ、赤報隊は記者殺害前後に8件の事件をおこしている。
[1987年]
1月24日 朝日新聞東京本社の壁を散弾銃で銃撃
5月3日 朝日新聞阪神支局を襲撃、記者殺害
9月24日 名古屋市の朝日新聞単身者寮で銃弾を発射
[1988年]
3月11日 朝日新聞静岡支局に時限式爆発物を仕掛ける
3月11日 中曽根康弘前首相に脅迫状、竹下登現首相にも脅迫状
8月10日 リクルート前会長の江副浩正邸を銃撃
[1990年]
5月17日 名古屋の愛知韓国人会館に灯油をまき火をつける
6通の声明文と2通の脅迫状が残されている。
そこからは、かれらの主張の一端がうかがえる。
戦後、日本では日本が否定されつづけてきた。反日世論を育成してきたマスコミに厳罰を加えなければならない。
特に、朝日は悪質だ。すべての朝日社員に死刑を言いわたす。わが隊の処刑は42年間つもりつもった日本民族のうらみの表れである。
朝日は言論の自由を守れというが、朝日の言論の自由は、連合国の反日宣伝の自由である。
英霊は裏切り者の中曽根をのろっている。竹下が靖国を参拝しなかったら、処刑リストに名前を載せる。
リクルートコスモスは反日朝日に金を出して、反日活動をした。反日朝日や毎日に広告を出す企業があれば、反日企業として処罰する。
ロタイグ(盧泰愚)は来るな。くれば反日的な在日韓国人をさいごの一人まで処刑する。
ざっと、こんな調子である。
著者は犯人を探すため、新右翼と呼ばれるグループとその周辺をあたり、直接接触をこころみた。まさに命がけの取材だったと思われる。
著者によると、日本の右翼は6つのグループにわけられるという。
(1)伝統右翼。
(2)新右翼。
(3)任侠右翼。
(4)論壇右翼。
(5)宗教右翼。
(6)草の根(ネット)右翼。
多く説明する必要はないだろう。伝統右翼は戦前の右翼団体を継承している。反左翼の立場から戦後は親米の立場をとるようになった。これにたいし、新右翼は三島由紀夫自決に刺激を受けて結成されたグループで、反米の立場を貫く。任侠右翼は暴力団といってよい。宗教右翼は「生長の家」などに代表されるが、統一教会(現世界平和統一過程連合)などもこれに含まれる。
分類はあくまでも分類であって、その関係はからみあっている。団体どうしの対立もあるし、あくまでも孤立している個人や団体もある。その変遷はめまぐるしい。
それぞれの主張には微妙なちがいはある。しかし、基本的に共通するのは左翼撲滅(反共主義)、愛国主義、皇室擁護、自主憲法制定の姿勢だろう。政治団体としての「日本会議」もこの立場をとっている。
朝日新聞襲撃事件の犯人を追うため、著者は右翼のなかでも直接行動主義をとる「新右翼」に焦点をしぼり、何人もの関係者と会って、慎重に取材をつづけた。
新右翼のひとつの特徴は新左翼に対抗する武闘派だということだ。「大東亜戦争」をアジア解放のための戦いととらえ、日本を敗北に追いこんだアメリカやソ連と戦うという考え方をもっている。アメリカの占領によってつくられた戦後日本のあり方は根本的にまちがっていると考える。そうした点で、5月3日の憲法記念日に朝日新聞阪神支局を襲撃した赤報隊も新右翼の系列に属すると考えられた。
著者は赤報隊の影を追って、東北や関西にも足を延ばしている。統一戦線義勇軍なる団体とその関係者があやしいとにらんだが、その先の消息はとだえていた。長らく消息不明となっていた人物とも接触するが、犯人だとの確証は得られなかった。
民族派の武闘派、野村秋介は1993年10月20日に朝日新聞東京本社役員室で、中江利忠社長と面会中に拳銃自殺した。野村が立ち上げた政治団体「風の会」を、山藤章二が『週刊朝日』の「ブラックアングル」で「虱の党」と揶揄したことに抗議する行動だった。
新右翼団体「一水会」の代表、鈴木邦男はその後、『週刊SPA!』に連載中のコラムで、野村秋介の思い出に触れ、野村が赤報隊の連中と何度か会って、無差別に朝日の末端記者をやるのはよくないと話していたことを紹介している。だが、その真偽のほどはわからなかった。
あやしそうな人物はほかにもいた。著者はかれらとも会って、その考え方を聞いているが、言論とテロをめぐる議論は堂々巡りするばかりだった。はっきりしたアリバイがないなかで、警察もけっきょく確たる証拠をつかめなかった。
取材の過程で、すでに統一教会と勝共連合の名前が浮上していた(本書ではα教会、α連合となっている)。
朝日新聞は中曽根政権が進める国家秘密法に反対する論陣を張っていたが、勝共連合は86年11月から87年1月にかけて、朝日新聞東京本社前に街宣車をくり出し、朝日を批判する街頭演説をくり返していた。『朝日ジャーナル』には、不気味な内容の脅迫状も送られてきた。
一連の朝日新聞襲撃事件に統一教会・勝共連合がかかわっていた証拠はない。だが、信者の集会では、それをにおわせる指導者の発言もあったという。かぎりなくあやしかった。
いっぽう、右翼の側からは、統一教会と勝共連合を警戒する向きもあった。反共をかかげていても、その心は天皇陛下ではなく、文鮮明教祖に向いている、と疑っていたからである。ともあれ連帯しながらも、右翼の側は統一教会を恐ろしい組織だとみていたのだ。
統一教会は朝日新聞をサタンとみなして、敵愾心をいだいていた。統一教会が全国で26の系列銃砲店をもっていたのは事実である。秘密軍事部隊も存在した、と著者は書いている。
統一教会が阪神支局襲撃事件にかかわっているのではないかという疑惑が浮上する。だが、確証はとれなかった。それ以上に、統一教会と赤報隊の思想が根本的なところで食いちがっているのが問題だった。
88年の2月か3月に、統一教会の新聞「世界日報」の社長らと朝日新聞編集局の幹部が会食し、その後、5月にも両者の話しあいがもたれた。双方の批判を控えるという一種の「手打ち」がおこなわれたとみてよい。組織防衛の論理がはたらいたのだろう。そのことも、著者ははっきりと記している。
2003年3月に赤報隊事件は公訴時効を迎えた。
「[戦後]いくつもの未解決の重大事件があるが、その中で最も深刻な影響を残しているのが、『赤報隊』による一連の事件ではないかと思う」と、著者は書いている。
じっさい、この事件をひとつの契機とするかのように、「反日」という言葉が広がり、保守の論調が強まり、特定秘密保護法が成立し、日本会議の影響力が増し、国防力の強化が進み、ナショナリズムが世をおおうようになった。
「小尻記者に向けられた銃弾は、われわれ一人ひとりに向けられたものだという言い方もできる」。いまジャーナリストには覚悟と矜持が求められる、と著者はいう。
ジャーナリストにかぎるまい。ひとつの無念を受けとめること、だれにとっても、それが新規の出発点になるのだから。
商品論──メンガー『一般理論経済学』を読む(7) [商品世界論ノート]

メンガー『一般理論経済学』は商品論にはいっている。
はじめにメンガーは、孤立経済、つまり原始社会では、財がつくられるのは、自己消費(あるいは贈与)のためであって、交換目的のためではないと書いている。
原始社会でも分業がなかったわけではない。だが、財の需求はかぎられていた。過剰や欠乏が生じるときに他の共同体と交易がなされることもあるが、それはあくまでも偶発的なものだったという。
文化が発達するにつれ、自分のいる場所では産出しない財への需求が生まれてくる。金や鉄などの金属もそうした財のひとつだ。これを手に入れるには征服もしくは交換による以外にない。いずれにせよ交易が広がっていく。
特別の財をつくる職人も登場するだろう。当初、それは注文による生産で、交易を目的としているわけではなかった。
だが、経済活動が活発になると、しだいに交換を目的として財が生産されるようになる。これが商品だ、とメンガーはいう。
商品が商品たりうるのは、その財のもつ性質によるのではない。あくまでも、その財が交換されるということによる。したがって、交換(売買)することをやめてしまえば、その財はたちまち商品ではなくなる。
〈したがって、商品としての性格は……一般に財と経済活動を行なう主体との間の一時的な関係にすぎない。ある種の財は、その所持者たちによって、経済活動を行なう他の主体の財との交換のために定立されている。最初の占有から最後の占有へと移る間の、しばしば多数の人の手によって媒介される、中間期においては、われわれはそれを「商品」と名づける。〉
つまり、商品とは生産と消費の中間期において交換(売買)される財をいうのであって、すでに最終的消費者の手中にある場合は、その財は商品ではなくて使用財になっている、とメンガーはいう。
商品は販売可能な財でなければならない。
販売可能ということは、何を意味するのだろうか。
メンガーは商品の販売可能性の条件を探る。むしろ、商品の販売可能性は限定されているというのがおもしろい。
ここでは4つの制限が挙げられている。
(1)商品の販売可能性は買う人によって制限されている。だれもがその商品を買うわけではない。商品を買う人の範囲はおのずから決まっている。
〈特定商品の販売を見込みうる人々の範囲、言い換えれば商品の販売可能性の人間的な限界は、この商品への需求を有する人々の数が少なければ少ないほど狭くなり、またこれらの人々に対象をかぎっても、法律、風習や偏見によってそれを消費することを妨げられている人、あるいはまた商品の価格によってそれを入手することから経済的に締め出される人の数が多くなればなるほど狭められるのである。〉
商品が買われる範囲は、その商品を買いたいと思っている人の数によって決まる。商品を買いたいと思う人の数が少なければ、その商品はさほど売れない。法律や風習、偏見が商品の購買を妨げている場合もある。また商品の価格があまりにも高ければ、商品が売れる量はおのずとかぎられてくる。商品を買えない人の数が増えてくる。
したがって、そこからは、逆に商品の販売可能性を広げるには、どうしたらよいかという方策も導かれる。
何といっても、商品を求める人を増やすことだ。法律や風習、偏見などがあれば、そうした人為的制限は除去されなければならない。価格を下げて、商品を買える人を増やすこともだいじだろう。
また、人口が増えることや、商品の認知度が高まること、住民の経済レベルが上がることも商品の販売量拡大につながる、とメンガーはいう。
だが、商品の販売可能性は、人の数だけによって制限されるわけではない。
(2)商品の販売可能性は地域によって制限される。逆に場所的に拘束されることが少なくなればなるほど商品の販売可能性は広がる。
たとえば毛皮などの防寒着は熱帯では売れないだろう。カザフ語の小説も世界じゅうではあまり売れないだろう。しかし、Tシャツや車、テレビなら世界じゅうで売れるかもしれない。
輸送コストや輸入禁止措置なども、商品の販売を妨げる要因となりうる。だが、何といっても経済的要因が大きい。交易に利益がなければ、商品の販売は閉ざされてしまう。
(3)商品の販売可能性は量によっても制限される。商品の需要には限界があり、商品の販売量はそれ以上になることはない。しかし、住民の裕福度の上昇が、消費量の拡大をもたらすことは、じゅうぶんにありうる。
(4)商品の販売可能性は時間によっても制限される。それは財が時間的特性を持つ場合である。たとえば、腐りやすい商品は、すぐに販売されなければならない。しかし、財の保存性が高まったり、保管費が減少したりすれば、そうした時間的制限は拡大されることになる。
以上の点を踏まえていうと、商品の販売可能性には、人的、空間的、量的、時間的限界(制約)があることがわかる。しかし、その制約が緩和されるなら、商品の販売がそれだけ容易になることはあきらかだ。
商品の運動は、そうしたさまざまの制約を突破することに向けられてきた。
ここで、メンガーは商品の本性をもう一度問いなおしている。
商品は交換を目的とする経済財だが、それはどんな価格でも売却されるわけではなく、一般的な経済状態に釣りあう価格で、はじめて販売される。とはいえ、もし商品にたいする需求が減れば、商品の価格は水準より低下するし、逆に需求が増えれば、水準より上昇する。
商品の販売可能性を考える場合は、その財がコンスタントに入荷するか、それとも不規則にしか入荷しないかで、価格と販売に大きなちがいがでてくる。
交易はふつう経済的な利害にもとづいておこなわれるが、時に非経済的な動機でおこなわれることがある。その場合は、価格形成がしばしば歪められる。錯誤と無知も財の交易にマイナスの影響をもたらす。正しい情報が価格形成を経済的にし、商品の販売可能性を上昇させる。
メンガーは商品世界が正しく成長するうえで、商人階級が果たす役割の重要性を、次のように指摘する。
ひとつは商人階級の有する高度な専門知識が、国民経済に経済的利益をもたらすことである。
さらに重要なのは商品階級による交易の組織化と取引の恒常化である。
市場、定期市、取引所、競売などの存在が、商品の価格形成を適切なものとする。市場が生まれれば、生産物の販売可能性も高まり、生産にも安定性がもたらされる。市場における価格形成は、消費者にも商品を経済的価格で買う機会を与える。
市場では先を見越した投機もありうるが、メンガーは投機をむしろ肯定的にとらえている。
〈投機は、たしかに自分たちの独自の利害を追求することに発するものではあるが、飽和した市場にはけ口を与え、逆に貧血気味の市場には商品を補給し、またそれによって、経済的な価格から遠ざかりすぎている価格を抑制するという経済上の使命を果たすのである。〉
メンガーはもう一度最後に、流通しやすい商品と流通しにくい商品について述べている。
たとえば金などの貴金属なら、だれが採取しようとすぐに流通するけれども、だれがつくったかわからない食品や装飾品などは、しばしば流通にためらいが生じる場合がある。価格がはっきりと示されていない商品も、また買うことがためらわれる。
とりわけ次の場合は、商品の販売可能性はいちじるしく損なわれるとメンガーはいう。
〈その販売可能性が狭い範囲の人々に制限され、その販売地域が狭く、その保存期間が短い商品、あるいはまたその保存にいちじるしい経済的犠牲をともなう商品、つねにただ狭く限定された数量しか市場にもちだすことができず、その価格が十分には規制されていない商品等々も、きわめて狭い限界内であるがともかく一定の限界内で、ある程度の販売可能性を示すこともあるであろう──けれどもそれらの商品は、流通性をもつまでにはいたらない。〉
翻訳に問題があるのかもしれないが、何となくわかればよい。説明する必要はないだろう。
だが、商品世界が安定的に広がっていくことが、生産者にも消費者にも利益をもたらすとメンガーが信じていたことはまちがいない。
メンガーが見ていたのは19世紀末から20世紀末にかけての商品世界である。日本でいえば、夏目漱石の小説にでてくる時代背景に近い。それから100年、商品世界はさまがわりして、経済がどこかでビッグバンをおこしたきらいすらある。
それはたしかに人類に多くの恩恵をもたらした。だが、その商品世界に囲まれながらも苦しむ人は多い。人を財として扱う商品世界は、人の生活様式をも変えたのである。
竹下政権とリクルート事件(2)──大世紀末パレード(21) [大世紀末パレード]


竹下政権のおもな課題は、地価対策、税制改革、日米関係の調整だったといってよい。地価対策は中途半端に終わったが、税制改革と日米関係の調整については成果を残した、と政治学者の若月秀和は記している。
この時期、日米関係では引きつづき貿易不均衡が大きな問題となっていた。アメリカはGATT理事会に提訴し、日本にたいし農産物の自由化を求めた。その結果、プロセスチーズやアイスクリームなどの乳製品、飼料、トマトジュースなどの輸入規制が撤廃ないし軽減されることになった。
このあとさらにアメリカは牛肉とオレンジの完全自由化を求める。交渉は難航するが、最終的に竹下政権は一定の条件をつけながら、牛肉・オレンジ自由化の方向に踏み切る。
アメリカ側は大規模公共事業への参入も求めていた。日本側は外国企業が参加しやすい特例措置を設けるなどして、対応にあたった。
こうして日米間の経済摩擦問題も少しは落ちついてくる。
もうひとつの大きな課題が税制改革だった。竹下は大平、中曽根政権もできなかった消費税導入を実現したいと思っていた。大型間接税の導入によって戦後の直接税中心の税体系から脱却し、財政基盤を強化することがねらいだった。
消費税については、さまざまな懸念があった。実質的な増税になるのではないか、低所得層に負担がかかる逆進的な税体系だ、事業者にも負担がかかる。さらに、将来、安易な税率引き上げがなされるのではないかという心配もあった。とうぜん、多くの反対が予想された。
竹下はそうした問題点があることも認めながら、日本の将来の財政基盤を安定させるため、消費税導入に向けて、着々と布石を打っていく。
1988年4月には政府税制調査会が、消費税の導入は必要やむを得ないとの中間答申を発表した。6月には自民党税制調査会が、税制調査会の中間答申にもとづいて税制改革大綱を決定する。
公明党、民社党へのはたらきかけもおこなわれた。社会、共産の両党が反対を貫くのは目に見えていた。竹下のねらいは、公明、民社をだきこんで、自公民で法案を通すことだった。そのいっぽう、日本チェーンストア協会をはじめとして、反対の根強い業界への説得もつづけられた。
7月に召集された臨時国会で、政府は税制改革関連6法案を提出した。竹下は「辻立ち」も辞さないと、法案成立への並々ならぬ決意を議会で表明した。
消費税導入を中心とする税制改革法案は、難航のすえ、11月16日に衆議院、12月24日に参議院を通過し、可決成立した。
だが、そのさなかにリクルート事件が浮上する。国会は大疑獄となったこの事件で揺れに揺れる。
リクルート事件とは、いったいどういう事件だったのだろうか。 単純にいえば、それは政治と企業とカネがからむおなじみの事件のひとつだった。
88年6月18日に朝日新聞が、川崎市の助役にまつわる贈収賄疑惑を報じたのがはじまりだった。
リクルート社はJR川崎駅周辺の再開発地域にからんで、川崎市の助役に関連不動産会社「リクルートコスモス」の未公開株を譲渡していた。公開されれば、とうぜん値上がりすることが予想された。
じっさい、その株は公開後上昇して、それを売却した助役は1億円以上の売却益を得た。これは事実上の賄賂ではないか、と朝日の記事は告発したわけである。
事件はそれだけでは終わらなかった。取材が進むにつれ、リクルート社が同じ手口で、政界や官界、その他にコスモスの未公開株を約200万株譲渡しているのがわかってきた。
その人数は延べ150人以上にのぼった。コスモス株は86年10月に店頭公開され、未公開株の所有者は売り抜けて多額の利益を得ていた。
リクルート事件が発覚したのは、まさに消費税の導入が論議されている臨時国会のさなかである。秘書名義を含めると、10人以上の国会議員がリクルート社から未公開株を譲渡されていた。
最初に名前が挙がったのは、自民党では中曽根康弘前首相、竹下登現首相、安倍晋太郎幹事長、宮沢喜一蔵相、森喜朗元文相。野党でも民社党の塚本三郎委員長、社会党の上田卓三議員の名前が飛びだした。
リクルート社はほかにも献金やパーティー券の購入などで、政治家に多額の資金を提供していたことが判明した。
88年12月24日に消費税法案が衆参両院で可決成立するまで、国会はこのリクルート問題でもめにもめる。宮沢喜一蔵相が証言の食い違いによって辞任する一幕もあった。
自民党はリクルート社の江副浩正社長と未公開株を受けとった元労働事務次官の加藤孝、前文部事務次官の高石邦男を国会喚問するとともに、衆議院にリクルート問題調査委員会を設け、譲渡先リストを公開することを約束した。これによって、年末にようやく税制改革関連6法案(消費税法案)を通すことができたのだった。
公表された譲渡先リストのなかには、前に挙げた名前に加えて、池田克也、伊吹文明、加藤紘一、加藤六月、田中慶秋、浜田卓二郎、藤波孝生、渡辺秀央、渡辺美智雄の名前が挙がっていた。
竹下は12月27日に内閣改造をおこない、4月の消費税実施に備える体制を整えた。だが、新しく任命された閣僚にたいしてもリクルート社による献金が次々と発覚すると、世間の怒りは収まらなくなった。
89年1月7日に昭和天皇が亡くなり、平成時代がはじまる。
2月24日の「大喪の礼」をはさんで、しばらくは弔問外交がつづいた。北朝鮮への対決姿勢も緩和され、対ソ関係の改善もはかられた。だが、日米関係はアメリカが日本にさらにさまざまな要求を突きつけたため、いまだに緊張状態にあって、同盟漂流などと称される事態がつづいていた。
そのかんもリクルート事件をめぐる政治不信は高まるいっぽうだった。
竹下は総裁直属の諮問機関として政治改革委員会を発足させ、会長に中曽根内閣時代の官房長官、後藤田正晴をあてることにした。政治改革委員会では1月18日の初会合以来、長々と議論が重ねられ、ようやく5月になって自民党の「政治改革大綱」がまとめる。
政治改革の目標は、カネのかからない政治を実現することにほかならない。そのためには政治資金の規制を強化すること、自民党内の派閥を解消すること、さらには小選挙区制を実現することなどが「大綱」に盛りこまれていた。
だが、すでに竹下は追いつめられていた。2月にはじまった通常国会で、社会党の土井たかこ委員長は内閣総辞職による衆議院解散を求める。
さらに3月末から4月にかけて、新しい事実が判明する。かつてリクルート社が竹下の資金集めパーティーのために多額のパーティー券を購入していたこと、加えて2500万円の寄付をしていたこと、さらには竹下の秘書、青木伊平が江副浩正から5000万円を借りていたこと。これらのことが次々とあきらかになったのだ。
4月半ばに実施された共同通信の世論調査では、竹下内閣の支持率は3.9%、不支持率は87.6%という信じがたい数字がでていた。
このままでは予算案の成立もままならない。竹下は4月25日に退陣を表明し、国民のために予算を通過させるよう呼びかけた。
翌26日、秘書の青木伊平が自殺した。
それから3年後、竹下は佐川急便問題で国会で喚問されるが、青木の自死について問われて、「私自身顧みて、罪万死に値する」と沈痛な面持ちで語ることになる。
竹下の辞任表明によって、予算はようやく成立した。それを見届けたうえで、竹下内閣は6月2日に総辞職する。後継総裁には竹下に近い宇野宗佑が指名された。
リクルート事件では、社長の江副浩正をはじめ、NTT会長、労働、文部事務次官など13人が贈収賄容疑で逮捕された。
政治家は逮捕されなかったが、自民党の藤波孝生元官房長官と公明党の池田克也が在宅起訴された。
長期間にわたる裁判の結果、起訴された者すべてに執行猶予つきの有罪判決が下された。
リクルート事件は、その後、日本の政治に大きな影響をおよぼした。小選挙区制が導入されるようになったのも、この事件がきっかけである。
だが、政治とカネの問題はこれで終わったわけではなかった。リクルート事件は、ほんの氷山の一角にすぎなかったのだ。いまの政治資金パーティー収入裏金問題をみても、そのことがわかる。
政治学者の滝村隆一は、よく政官財はじゃんけんの関係にあると言っていた。
たとえば政治家がグーだとすれば、役所はチョキ、経済界はパー。
政治家は役所に勝つ(強い)が、経済界に負ける(弱い)。経済界は役所に負ける(弱い)が、政治家に勝つ(強い)。役所は経済界に勝つ(強い)が、政治家には負ける(弱い)。
権力とカネの関係はどこまでもつづき、途切れることがない。
この三位一体構造を崩す方法はひとつしかない。カネと権力の動きを常に透明化できる仕組みをつくる以外にないのだ。はたして、それは可能なのだろうか。
竹下政権とリクルート事件(1)──大世紀末パレード(20) [大世紀末パレード]


冷戦が終わろうとしていたころ、日本の政治はどうなっていたのだろうか。そのとき首相はだれだったのか。そんなことがふと気になった。いくつかの本を読んでみる。
まず名前が挙がるのが竹下登(1924〜2000)である。1987年11月から89年6月まで1年7カ月にわたって首相を務めた。そのあとは宇野宗佑の69日、海部俊樹の203日となるが、いずれも長くつづかなかった。自民党政治にガタがきていたのだ。
中曽根康弘が退陣したあと、本格政権になると思われた竹下政権が意外にも短命だったのは、リクルート事件が発覚したからである。そのため、竹下は早々と身を引くが、退陣後もその影響力は絶大で、後継の宇野、海部、小渕の3内閣も、いわば竹下が選んだ内閣だった。
竹下登は気配りの政治家で、その政治手法は調整型といわれた。調整型というのは、受け身であり、問題解決にたけているということでもある。実際、アメリカとの経済摩擦を調整し、長年の課題だった消費税導入に成功したのは、竹下の功績といってよいだろう。
だが、長大な国家ビジョンがあったわけではない。あったとすれば「ふるさと創生」くらいだろうか。
本人もあるインタビューで、「日本というのは、しょせん、ビルの谷間のラーメン屋みたいなものだ」と語っている。東西両陣営に囲まれて、そのなかをうまく立ち回って生き残る方策をみつけるのが、日本の政治のありようだと考えていた。
竹下は中国山地の麓、島根県掛合町(かけやまち、現雲南市)に生まれた。家は大地主で、酒造も営んでいた。早稲田大学商学部で学び、在学中に結婚した。召集され、内地の部隊を点々としているうちに、大津で終戦を迎えた。だが、そのかん、掛合町の家にいた妻が自殺するという悲劇に見舞われている。親戚の娘と再婚するのは、復員してまもなくのことだ。
復学した竹下が早大商学部を卒業したのは1947年(昭和22年)9月。政治を志し、国会の傍聴にもよくでかけるようになっていた。卒業後は東京で新聞記者になろうとも考えていた。
だが、知り合ったある代議士から、政治家になるなら、郷里に戻って、地元の青年をまとめて県会にでて、それから国会をめざせ、とアドバイスを受けた。ただし県議は1期だけにせよというのが、その代議士の忠告だった。
こうして、竹下は故郷に戻ることにした。
戦前は大地主だった竹下家には、ある意味、政治の素地があった。父親は村の「名誉村長」だったし、島根県議会議員も務めていた。隣村の田部長右衛門(たなべ・ちょうえもん、朋之)を「ダンさん」と呼び、あおいでいた。
田部家は出雲の大富豪で、日本の三大山林王のひとりとして知られていた。その当主は、戦時中の翼賛体制のもとで衆議院議員を務めていたし、戦後は1959年に島根県知事にもなっている。
家庭環境が政治へのあこがれを育んだことはまちがいだろう。政治家になれるだけの基盤も用意されていた。それ以上に、政治家になりたいという熱烈な思いが竹下を揺り動かしていた。そのためにはまず仲間、すなわち支援者をつくらなければならない。
竹下は掛合中学校の教員をしながら、地域の青年団を組織する。青年団長として、模擬国会やのど自慢大会を開いたりもしている。
そして、時を見計らって、1951年(昭和26年)の島根県議会選挙に立候補し、初当選する。もちろん青年団の支援と、大富豪、田部家の了承を得てのことである。このとき27歳。
だが、県議会議員はとっかかりにすぎない。県議を務めたのは2期だけで、めざすはあくまでも国会議員である。
県議会の活動そのものは熱心ではなかった。県議としておこなっていたのは、もっぱら人脈づくりである。県政の実力者、田部に下僕のように仕え、県幹部との関係を密にするよう努めていた、とジャーナリストの岩瀬達哉はいう。
そのチャンスは1958年5月にめぐってきた。竹下は島根全県1区(当時は中選挙区制で定員5名)から新人候補として出馬し、トップ当選を果たした。亡くなった前衆院議員の後釜をねらって、田部の了承を取りつけ、早々と選挙活動を開始していたのだ。
竹下はトップ当選を果たしたものの、公職選挙法違反の疑いで24人の逮捕者をだした。竹下自身はかろうじて議席を失わずにすんだものの、逮捕者の家族の面倒をみたり、裁判の弁護士費用がかさんだりして、選挙の後始末だけでも多額のカネが必要だったという。
岩瀬達哉によると、この苦い経験から、竹下は何といってもカネをつくらなければならないこと、そしてカネをまくのは金庫番の秘書の仕事とし、代議士はいっさいあずかりしらぬこととするという事務所づくりの鉄則を痛感したという。
政治には仲間づくりがだいじであり、仲間を広げるにはカネが欠かせないというのが、竹下を支える政治哲学だった。
政策と金策は表裏一体だった。その両面の顔をもつ事務所を裏から支えたのが、竹下の初当選以来、会計を取り仕切った秘書の青木伊平だった。青木はリクルート事件のさなか、1989年4月に自殺することになる。
岩瀬は「竹下王国の錬金術」にふれている。それは田中角栄の手法を踏襲したもので、「公共事業誘致型」と呼んでよいだろう。地元のために国から公共事業予算を引きだし、それを自派の県会議員や市会議員を通じて、後援会に名をつらねる建設会社に配分するというやり方だ。
まさに利益誘導型の政治である。これにより地元の選挙基盤がより強化されることはまちがいなかった。
だが、そういう手法が可能となるには、代議士本人が中央政界でより高いポストを得る必要があった。政界や官庁、財界に仲間の輪を広げていくには、本人の実力もさることながら、相当の気配りと資金力が求められただろう。もちろん、そこには大きな落とし穴も待ち受けていた。
34歳で初当選したときに竹下が最初に入門したのは、造船疑獄で評判の悪かった佐藤栄作が率いる佐藤派だった。地元の実力者、田部長右衛門に連れられて、佐藤のもとを訪れたという。
この選択はまちがっていなかった。佐藤はまもなく池田勇人を継いで総理となり、長期政権を築くことになる。
竹下は地元で当選を重ね、政界でキャリアを積んでいった。1971年には第3次佐藤内閣の内閣官房長官として初入閣した(このとき48歳)。
その後の政界での歩みは順調だった。1974年には田中角栄内閣の官房長官、76年には三木内閣の建設大臣、79年には大平正芳内閣の大蔵大臣、81年には自民党幹事長代理となっている。82年には中曽根康弘内閣の大蔵大臣、86年には自民党幹事長に就任した。
自民党幹事長に就任する前、竹下は田中派を離脱し、86年7月にみずからの政策集団「経世会」を結成している。そして、87年10月、退陣する中曽根首相から、自民党総裁後継者として指名されるのである。
こうして1987年11月に竹下登内閣が発足した。党三役の幹事長に安倍晋太郎、総務会長に伊東正義、政調会長に渡辺美智雄をそろえ、副総理兼大蔵大臣に宮沢喜一に据え、官房長官に小渕恵三、官房副長官に小沢一郎を配するなどした鉄壁の布陣だった。
ところが、中曽根が竹下を後継に指名するにあたって、じつは以前から右翼団体、日本皇民党による執拗な竹下攻撃がつづいていた。
そのやり口は「ホメ殺し」と呼ばれるものだ。皇民党事件が発覚するのは5年後の1992年(平成4年)のことだが、竹下政権のとき、この事件はまったく報道されていなかった。
田中角栄は竹下が勉強会といつわって、派閥内に「創世会」(のち「経世会」と改称)をつくり、事実上の新派閥を発足させたことに憤りを覚えていた。
皇民党はそれにつけこむ。十数台の街宣車をつらね、連日、都内を連呼して回った。「竹下さんは日本一カネ儲けがうまい政治家だ。竹下さんを総理大臣にしよう」
竹下にたいする嫌がらせである。右翼団体が竹下とつながっているかのようにみえるのは、はなはだ都合が悪い。中曽根も「右翼の活動も抑えられないようでは、後継者に指名できない」と言っていた。
困り果てた竹下は何とかして皇民党の活動をやめさせようとするが、なかなかうまくいかない。そこで、党副総裁の金丸信が東京佐川急便の渡辺社長を通じて広域暴力団稲川会の石井会長にはたらきかけ、皇民党の稲本総裁とのあいだで話をつけてもらった。
その結果、条件つきで皇民党による竹下ホメ殺しは中止されるが、東京佐川急便の渡辺社長は、石井に要請されるまま稲川会の関係団体に総額400億円以上の融資や債務保証を実施するはめになったという。
事件にはまだ奥がありそうだ。岩瀬達哉は佐川急便の佐川清会長の関与を示唆している。佐川会長は佐川急便が大きくなったのは田中角栄のおかげであり、その田中を裏切った竹下は許せないといっていたそうだ。さらに渡辺社長が竹下を後ろ盾にして佐川急便を乗っ取ろうとしているのではないかと疑っていたともいう。
だが、ここまでくると事件はまさに闇の奥である。
一枚めくると、まさに政治とカネのドロドロの世界が広がっていた。
そして、リクルート事件が幕を開ける。
価格論──メンガー『一般理論経済学』を読む(6) [商品世界論ノート]

価格が労働量、あるいは生産費を根拠にしていると考えるのは誤謬である。価格を論じるさいに重要なのは「経済活動を行う人々が自分たちの欲望を可能なかぎり完全に満足させようと努力することから、どのようにして、実際にも、諸財を、しかもその一定数量で、交換しあうようになるかを示すことである」とメンガーはいう。
価格はあくまでも、各自が自分たちの欲望を満たそうとしておこなう交換のプロセスから生じるというのがメンガーの考え方だといってよい。そのプロセスを、かれは単純な形態からはじめて、複雑な形態へと拡張することによって、価格の形成を説明する。
まずは1対1での交換の場合だ。
たとえばAとBの農民がいて、ふたりのあいだで財(たとえば小麦とワイン)の交換がなされる場合を考えてみよう。そのときは、両者のあいだで駆け引きがなされ、80単位から100単位のあいだの小麦なら40単位のワインと交換してもよいという範囲がおのずと決まってくる。
その範囲内で、両者はお互いにできるだけ多くの経済的利益を得ようとする。そこで、たとえば平均をとって、90単位の小麦と40単位のワインとが交換されるという結果になる。もちろん、駆け引き次第で、90単位ではなく、95単位あるいは85単位で取引が成立することもありうるだろう。
次は1対1の交換ではなく、買う側も売る場合も多数の場合である。しかし、一挙に複雑にしないで、まず簡単なケースとして、買う側が多数で、売る側が1人の場合を想定してみよう、とメンガーはいう。
たとえばAの馬1頭をめぐって、農民B₁とB₂が競いあうとする。馬を購入するとしたら、B₁は小麦80単位までならだせると考えており、B₂は小麦30単位までならだせると考えている。すると馬の価格は小麦30単位と80単位の範囲で形成されることになる。この場合は、ひとりだけではなく、2人の競争者によって価格の範囲が設定されるわけだ。
さらにここにB₃という競争者が現れ、かれは小麦70単位ならだそうというとする。すると、価格の範囲は変わって、70単位と80単位のあいだになる。また90単位をだすという新たな競争者B₄が登場すれば、馬の価格は80単位から90単位のあいだにはねあがる。こうして馬の価格は決まってきて、もっとも有利なかたちで売られることになる。
ここでメンガーは独占者が売る馬を何頭ももっていて、これを買おうとする農民が何人もいる場合を想定する。農民はそれぞれ馬をほしいと思っていて、その値段として自分はこれだけの量の穀物ならだせると考えている。この場合、馬の価格はどのようにして決まるのだろうか。
メンガーが示している経済ゲームの細かい推移は省略する。結論からいえば、こうしたケースには、どういう事態が生じるかをメンガーは次のように説明する。
〈われわれがそこに見るのは、市場にもちだされた独占財の諸数量をめぐって、交換能力にきわめて差異のある諸階層の住民が競争している様子である。また先に、一人ずつの諸個人を想定して提示した場合とまったく同様に、交換能力の優る階層が交換能力の劣る階層を、問題の財の交換から経済的に排除する様子も見られる。さらに、市場にもちだされる独占財の数量が少なくなればなるほど、独占財の享受を断念しなくてはならない住民の層がそれだけ多くなり、また逆に、この数量が増大すればするほど、交換能力の劣る住民諸階層の間にも独占財が入りこむのであり、こうした現象と平行して独占財の価格が上下する、そうした様子を、われわれは見るのである。〉
生産が独占されていても、財を求める人が多くいて、それに応じて大量の財が売りにだされれば、一単位あたりの財の価格は低くなることが示されている。もちろん、それとは逆の選択がなされることもある。
とはいえ、通例、価格はせりの結果によって決まるわけではない。財の独占的保有者が、あらかじめ特定の価格をつけておくのが一般的だ。その価格にもとづいて、諸個人は財を購入するかいなかを決定し、それに応じて販売量が決まることになる。
独占者があまりに高い価格を設定すると、購入者を排除してしまい、経済的交換の可能性はなくなる。比較的に高めの価格設定も、多くの人を経済的に排除することになるだろう。逆に独占者が価格を低く定めれば、財を需求しようとする人の数は増える。
すると、財の独占者はどれだけの価格でどれだけの量の財を出荷すればいいかという問題がでてくる。
独占者は大量の財を売りにだしながら、高い価格を実現することはできない。また高い価格を維持しながら、大量の財を販売することもできない。
そこにはおのずから経済法則がはたらく。
独占者の利点は、供給面において他者との競争にわずらわされないで、財の数量と価格を調整しうることだ、とメンガーは書いている。
〈彼は、出荷する独占財の数量を多くしたり少なくしたりすることによってその価格を、あるいは、価格を高めに設定するか低めに設定するかによって独占財の売却される数量を、それぞれ彼の経済的利害関心にしたがって規制することができるのである。〉
独占者がそうした調整をおこなう目的は、最高の収益を挙げるためである。そのためには、予想される販売量にもとづいて価格が設定されなければならない。たとえ販売量が減っても価格を挙げたほうがもうかる場合もあるし、逆に価格を下げて販売量が増えたほうがもうかる場合もある。また最初はできるだけ価格を高く設定して、販売量が増えるにつれて価格を安くしていく方法も考えられる。
だが、いずれの場合も目標は最高の収益を挙げることである。価格を下げて販売量が増えても、かえって収益が減ってしまうようでは元も子もない。
こうした経済行動は、独占者がすでに支配している財を売る場合だけではなく、これからどれだけの財を生産するかを決定する場合に、とりわけ重要になってくる。より多く財を生産しても、それによって価格が下がり、逆に収益が減ってしまうのでは何の意味もない。
そのため、独占者は次のような行動をとる。
〈独占者は価格の高低を定めたり、売りに出す独占財の数量の大小を調節できるとはいっても、彼の経済的利害関心に完全に適うのは、特定の一点に価格を定めることだけ、ないしは特定の一数量の独占財を市場に出すことだけである。したがって、独占者は、いやしくも経済活動を行なう主体であるかぎりは、価格形成に関しても、あるいは売りに出される独占財の数量に関しても、恣意的に行動するのでは決してなく、一定の諸原理にしたがって行動するのである。〉
経済社会では、こうした独占者はけっして例外ではない。メンガーはたとえばオランダの東インド会社を例に挙げているが、どの地域でも独占的な経済主体は存在するのであって、「独占はまさに競争にとっての自然的先行者」なのだという。
とはいえ、経済が発展するにつれて、独占が競争へと発展していくのは自然の成り行きであって、そうなると「競争の登場が、財の配分、販売量、商品の価格におよぼす効果」を研究することが次の課題となってくる。
そこで、供給側に経済競争がある場合が論じられることになる。ここでは「一財を獲得しようとする多数の競争者が、供給の側の多数の競争者と向かいあっている状態」が想定されているわけだ。
このときはどのような経済的法則がはたらくのか。
わずらわしいので、要点だけをいう。
メンガーは商品を供給するのが、独占者であろうが、多数の競争者であろうが、商品が一定の価格で出され、一定の量が販売されること自体は、何ら変わりないと述べている。
しかし、供給側に競争者がいる場合は、明らかに価格にも販売量にも影響がでてくる。いちばん大きなちがいは、独占者が価格と供給量を単独で決定できるのにたいして、生産側に競争者がいる場合は、価格にしても供給量にしても、たとえ個々に決定がなされたとしても、その決定は競争の影響を受けざるをえないということである。
〈個別生産者の誰も、価格ないし財の交易数量を規制する力を、独立に手にしていないという競争の状態のもとでは、ごく小さな利潤ですら個々の競争者にとっては望ましいものであって、したがってこうした利潤を得る機会が長い間みすごされることは決してない。したがって、競争は、薄利多売への傾向をもち、高度の経済性をそなえた大規模生産を促進する。〉
さらに重要なことは、競争が商品の大衆化をもたらし、それによって社会を前進させる効果をもつことだ、とメンガーはいう。
〈どのようなものであれ真の競争の登場は、売却目的のために支配可能な財数量の全体が実際に売却されるという効果をもたらすだけではない。真の競争の登場はさらに、この財数量自体をかつて以上に増大させるのである。つまり、競争は、生産手段に自然的制約がないとすれば、価格の低下によってますます多くの社会諸階層を問題の財の消費に参加させるだけでなく、支配可能数量を増加させて、この財の社会にたいしての供給をそれだけ完全なものにするという前進的な成果をも、もたらすのである。〉
ここでは自由な経済競争が、大衆レベルまで商品の購買層を広げ、社会全体の進歩をもたらすというオーストリア学派の考え方が示されている。
冷戦の終わり(2)──大世紀末パレード(19) [大世紀末パレード]
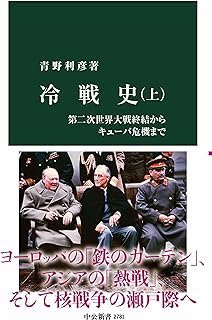
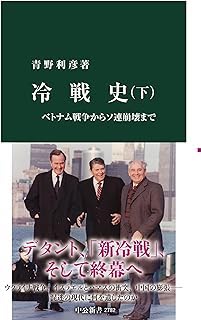
引きつづき、青野利彦の『冷戦史』を読んでみる。
冷戦の終わりは米ソ、ヨーロッパ、東アジア、第三世界で、さまざまなかたちをとった、と青野は記している。順にみていこう。
1985年3月、ソ連ではミハイル・ゴルバチョフが新指導者の座についた。ゴルバチョフはペレストロイカ(再構築)とグラスノスチ(情報公開)というスローガンを唱えて、社会主義体制の改革をはかり、「新思考外交」によって、東西両陣営の「共通安全保障」を確立しようとした。
そのころ、アメリカのレーガン大統領もソ連との関係修復を模索しはじめていた。核軍縮に向けて、米ソ首脳会談が何度も開かれる。85年11月にはジュネーブ、86年10月にはレイキャビク、87年12月にはワシントンで会談がもたれ、ついにINF(中距離核戦力)全廃条約が調印される。
その後、88年5月にモスクワ、12月にニューヨークで両国首脳会談が開かれたが、それ以上の軍縮交渉は行き詰まり、戦略兵器削減交渉(START)までにはいたらなかった。アメリカ政府内部にはソ連指導部にたいする不信感が依然として根強かった、と青野は記している。
ゴルバチョフの考え方は西欧的な社会民主主義に近かった。国際関係では脱イデオロギーと「人類共通の価値の至上性」を訴え、国内では議会を重視する民主化に取り組んでいた。だが、ソ連国内の経済状況が悪化するにつれ、ゴルバチョフの政治的立場は保守派と改革派の板挟みになっていく。そうしたなか、ゴルバチョフは外交で成果を挙げることで、みずからの指導力を強化したいと考えていた。
レーガンを継いで、アメリカ新大統領に就任したブッシュは、ゴルバチョフ政権に懸念をいだいていた。ブッシュは89年7月に東欧を訪問したあと、12月になってようやく地中海のマルタでゴルバチョフとの会談に臨んだ。会談最終日の記者会見で、両国首脳は冷戦終結を宣言したとされる。だが、青野によれば、冷戦終結に言及したのはゴルバチョフだけで、ブッシュはそのことに触れなかったという。
それでも80年代後半、ヨーロッパでは東西分断克服に向けての大きな動きがあった。
87年3月、イギリスのサッチャー首相は訪ソしてゴルバチョフと会談し、ペレストロイカにたいする支持を表明した。さらに87年から88年にかけ、ゴルバチョフはフランスのミッテラン大統領、スペインのゴンサレス首相、西ドイツのコール首相などとも会い、関係を深めていた。
89年春、経済危機とストライキのさなかにあったポーランドでは、政府と自主管理労組「連帯」とのあいだで円卓交渉が開始される。その結果、6月4日に自由選挙がおこなわれることになり、「連帯」側が圧倒的な勝利を収めた。9月には非共産党員のタデウシュ・マゾヴィエツキが首相に就任する。
89年にはハンガリー、チェコスロヴァキア、ルーマニア、ブルガリアなどでも、共産党一党独裁体制から複数政党制への移行が、ほぼ平和裏に達成された。ソ連は89年の東欧民主化革命に軍事介入することなく、ワルシャワ条約機構は事実上無効化された。
東ドイツでも10月にホーネッカー政権が倒れ、11月9日に国境の開放が宣言され、ベルリンの壁が崩壊した。11月28日、西ドイツのコール首相は「10項目提案」を発表、ドイツ再統一の流れが加速される。
東西ドイツが統一されるのは90年10月のことだ。NATOが東方に拡大される。いっぽう翌91年7月にはワルシャワ条約機構が正式に解体された。
ソ連では1990年3月にゴルバチョフが初代大統領に就任した。しかし、市場経済への移行は進まず、経済危機がつづいていた。改革派と保守派、双方からの攻撃が激しくなる。アゼルバイジャンでは民族紛争が激化し、リトアニアが独立を宣言した。まもなく、エストニアとラトヴィアもこれにつづく。
90年8月2日、サダム・フセインが率いるイラク軍がクウェートに侵攻する。アメリカのブッシュ政権はイラクを非難、ソ連のゴルバチョフもこれに同調した。国連安保理決議678号が採択され、これにもとづきアメリカは91年1月にイラク攻撃を開始し、湾岸戦争がはじまった。
西側に大幅譲歩したにもかかわらず、ドイツを除き、ソ連に経済援助をおこなう国はなかった。そのため、ソ連では経済危機がますます深刻になり、民族問題も悪化、ゴルバチョフの政治的立場があやうくなってくる。
91年8月、ソ連でクーデターが発生する。だが、クーデターは3日で失敗、軟禁されていたゴルバチョフは救出されるが、政治的主導権はクーデターを粉砕したロシア大統領エリツィンの側に移る。11月にはソ連共産党の活動が禁止され、ソ連を構成していたさまざまな共和国が独立を表明した。こうして12月25日にゴルバチョフはソ連大統領を辞任し、翌日、ソ連邦は消滅した。
このかん東アジアの状況はどう推移していたのだろう。
80年代を通じて、日米中の3国は連携を保っていた。台湾問題があったものの、台湾海峡の現状は維持されていた。
朝鮮戦争に参戦した中国はもともと同盟国北朝鮮と密接な関係を保っていたが、80年代後半には韓国との貿易額が急速に膨らんでいた。韓国との国交樹立が模索されていた。
91年9月、韓国と北朝鮮は同時に国際連盟に加入する。韓国がソ連と国交を樹立するのは88年9月のソウル五輪後の90年9月のことだ。これにつづき、92年8月には中国と韓国のあいだで国交が樹立された。
韓ソ、韓中の国交回復がなされるなかで、北朝鮮は孤立していく。北朝鮮は日米両国との関係改善を模索するが、うまくいかない。賠償問題と拉致問題が日本との関係のネックとなり、核開発疑惑がアメリカとの関係改善をはばんだ。
80年代後半で重要なのは、60年代はじめからつづいていた中ソ関係が正常化されたことである。80年代前半から中国は「独立自主の対外政策」を模索しはじめていたが、ゴルバチョフの登場とともに、両国関係の改善が急速に進む。
中ソ武力衝突の原因となった国境問題が解決され、ソ連軍のアフガニスタン撤退、ベトナムのカンボジア撤退、モンゴルからのソ連軍撤退も決まって、89年5月にはゴルバチョフ訪中が実現し、中ソ関係が正常化された。
ゴルバチョフ訪中のさなか、北京では学生や知識人による自由化運動が盛りあがっていた。それはまもなく民主化運動に転じ、人びとは天安門広場を占拠して、デモをくり広げた。中国政府はゴルバチョフ帰国後の6月4日に人民解放軍を投入し、天安門広場のデモ隊を武力鎮圧した。
日本とソ連のあいだでは、北方領土問題が残っていた。日本は北方領土問題の解決と日ソ平和条約の締結を結びつけて考えていた。だが、両国の立場のちがいは北方領土問題の解決を困難とし、ゴルバチョフ時代も日ソ関係の改善はみられなかった。
冷戦末期の東アジアでは、複雑な二国関係の相互作用が、分断の持続につながった、と青野は指摘する。
〈70年代末の時点で対立していた東アジア諸国間関係のうち、中ソ、韓ソ、韓中はそれぞれ、92年までには関係正常化に成功した。しかし、その一方で、冷戦期に固定化された日ソ、日中、米朝間に存在する領土や核をめぐる問題は未解決のままとなった。さらには冷戦以前、もしくは冷戦初期に内戦として始まり、米中ソの介入によって固定化した台湾海峡や朝鮮半島の政治的分断もそのまま残された。〉
「二つのコリア」も台湾問題も残ったままだった。さらにソ連が消滅したあと、日米中の枠組みは見直しを迫られるようになった。
世界では、ほかにも残された問題が数多くあった。
冷戦が終わるとともに、中米のニカラグアでは内戦が終結し、南アフリカではアパルトヘイト体制に終止符が打たれ、新政権が発足した。しかし、アフガニスタンやアンゴラでは内戦がつづいた。超大国の撤退により、第三世界でも冷戦は終結したが、「冷戦の負の遺産は非常に大きく、その爪痕は今も各地に残っている」と青野は記している。
冷戦終結後、世界は宥和の方向に向かわなかった。
ロシアはヨーロッパ秩序に統合されることを嫌い、EUやNATOと対峙する道を選んだ。冷戦末期に米ソが締結したINF全廃条約やSTART(戦略兵器削減交渉)は風前の灯といってよい状況にある。
中国は「独立自主の対外政策」を選び、アメリカとの対決姿勢を強めている。孤立した北朝鮮は核開発を進める方向に舵を切った。
アフガニスタンでは混乱がつづいている。中東は相変わらず世界の火薬庫となっている。第三世界も欧米の国際秩序にしたがったわけではなかった。
冷戦の終わりは、国際秩序をめぐる次の戦いに直結していたのだ。



