前の10件 | -
『アンダーグラウンド』を見る──大世紀末パレード(17) [大世紀末パレード]

映画『アンダーグラウンド』(1995年)は、ユーゴスラヴィアという社会主義国家の誕生と終焉を描いた歴史コメディだ。
今回、久しぶりにアマゾン・プライム・ビデオで見ることができた。
かつてユーゴスラヴィアという国があった。
その前身は1918年に成立したセルビア人・クロアチア人・スロヴェニア人王国で、1929年にユーゴスラヴィア王国と改称されたのがはじまりだ。
その後、1941年にナチス・ドイツによって占領され、パルチザン闘争をへて、1945年に社会主義国家が発足、ユーゴスラヴィア連邦人民共和国が建国される。
ユーゴスラヴィアの解体がはじまったのは1991年のことだ。まずスロヴェニアとクロアチアが独立を宣言し、マケドニア(北マケドニア)がそれにつづいた。
1992年にはボスニア・ヘルツェゴヴィナが独立を宣言、激しい内戦がはじまった。この内戦は1995年11月にデイトン合意がなされるまでつづいた。
セルビアとモンテネグロはゆるやかに連合し、最後までユーゴスラヴィアを名乗っていたが、2003年にそれぞれ独立を宣言する。これによってユーゴスラヴィアの名称は完全に消滅する。さらにコソヴォもセルビアからの独立を宣言した。
ユーゴスラヴィアの誕生は、第1次世界大戦後のハプスブルク帝国(オーストリア=ハンガリー帝国)の解体と、そのずっと以前からはじまっていたオスマン帝国の解体がもたらした産物だったといえなくもない。このバルカンの地は、南スラヴの領域に属するものの、その民族、宗教、言語、文化は複雑に入り組んでいた。
『アンダーグラウンド』の監督はエミール・クストリッツァ。
四方田犬彦氏によるクストリッツァ論がある。
それによると、クストリッツァは1954年にサラエヴォのムスリム系ボスニア人家庭に生まれた。ムスリム系といっても世俗的ムスリムで、両親ともに共産党員、父親は政府の要職を務めていた。
かれが映画監督の道を選ぶきっかけとなったのは、プラハの映画・芸術学校でミロス・フォルマン(映画『アマデウス』で知られる)の薫陶を受けたためだという。
『アンダーグラウンド』は、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞する。だが、この映画がセルビアから多額の資金援助を受けていたことから、セルビア寄りのプロパガンダにすぎないとみられる向きもあるという。
だが、ぼくはけっこう面白くみた。そして、けっこう考えさせられた。
『アンダーグラウンド』はふざけているのか、まじめなのかよくわからない映画である。そして、かしましい。バックにはロマの楽隊が常に陽気な音楽を鳴り響かせている。話されているのはセルビア語だ。
映画の中心人物はマルコとツルニ(セルビア語で「黒」を意味することから、日本語の字幕では「クロ」となっているので、ここではそれにしたがう)、それにナタリアだ。
3人にからんで、それこそ数え切れないくらいの人物が登場し、歴史の時間がかぶさる。主な場所はユーゴスラヴィアの首都ベオグラードだ。すぐそばにドナウ川が流れている。
映画は1941年4月からはじまり、その後の50年ばかりを追う。このかんにユーゴスラヴィアという国に何が起きたかは、最初に書いたとおりだ。
マルコは共産党員だが、ほとんど盗賊とみまがうならず者で、女房は愛想をつかして、家をでていき、いまは売春宿に通って、日々の享楽にふけっている。
そのマルコに誘われて、共産党に入党するのが電気技師の「クロ」で、妻(ヴェラ)のお産をひかえている。
そして、マルコと「クロ」がともにうつつをぬかしているのが、劇場で女優をしているナタリアだ。
マルコには動物園で飼育係をしている弟のイヴァンがいて、ナタリアにも障がい者の弟がいる。
そこにナチス・ドイツの空襲がはじまり、ベオグラードが占領される。マルコは大勢の人たちを、祖父の邸宅の地下に設けられた広大な空間に避難させる。そこが「アンダーグラウンド」となる。「クロ」の奥さんヴェラはここで産気づき、息子ヨヴァンを産んで亡くなる。
それからしばらくして、レジスタンスが広がる。女優のナタリアはドイツ軍の将校フランツの愛人になっている。「クロ」はマルコとともに劇場に行き、ドタバタ劇を演じた末、舞台のナタリアを奪還し、地下水道を通って、川辺の船でナタリアと結婚しようとする。
だが、この計画は失敗する。劇場で射殺したはずのフランツは生きていた(防弾チョッキを着ていたのだ)。
逆に「クロ」は逮捕され、拷問室に送られる。ナチスは「クロ」に電気ショックを与えて、パルチザンの動向を探ろうとするが、電気技師の「クロ」に電気ショックは効かなかった。
そこにムスリムの医師に変装したマルコがやってきて、フランツを殺し、「クロ」を助けるが、トランクに身をひそめて脱出する途中、トランクのなかの手榴弾が誤作動して、「クロ」は重傷を負い、そのまま「地下室」に運ばれる。マルコはまんまとナタリアを自分のものとする。
それから20年の時が流れた。ナチス・ドイツは敗北し、ユーゴではチトーの社会主義政権が成立している。
チトーはスターリンと決別し、独自の社会主義路線を取りはじめる。それが可能だったのは、周辺の社会主義国と異なり、ユーゴがソ連軍に頼らず、パルチザン闘争によってナチスからの解放を勝ちとったからだ。ソ連との緊張関係は、チトーの個人崇拝に結びつく。
しかし、映画の「地下室」では、じっさいの歴史とは異なる時間が流れていた。時計のごまかしによって、20年は15年に短縮され、ナチスとの戦争がまだつづいているとされていたのだ。
そこでは、昼夜を問わず武器がつくられ、戦車まで完成した。それを演出していたのがマルコで、マルコは地下で製造した武器を売って、金持ちになり、共産党幹部にのしあがっていた。
「クロ」は地下室で生きていたが、死んだことにされ、地上ではパルチザンの英雄にまつりあげられていた。
そんな「地下室」で、ある日、結婚式がおこなわれる。「クロ」の息子ヨヴァンが花嫁を見つけたのだ。マルコとナタリアも駆けつける。ワイヤーの花嫁が空を舞って、出席者にあいさつして回るシーンは、じつに美しい。映画史に残る名シーンのひとつだろう。

だが、結婚式はやがて酩酊と大騒ぎのなかで、めちゃくちゃになっていく。

そんななか、マルコとナタリア、「クロ」は歌を歌う。
月は真昼に照り
太陽は真夜中に輝く
真昼の暗黒を誰も知らない
誰も知らない
誰も知らない
太陽の輝きを誰も知らない
映画『アンダーグラウンド』を象徴する歌といえるだろう。スターリンよりましと思われたチトーの社会主義もまた情報をとざされ自由を奪われたアンダーグラウンドにすぎなかったのだろうか。だが、それはどこの世界も同じかもしれない。
あとの悲劇は簡単に紹介する。
パルチザンとアンダーグラウンドの虚構も長くはもたない。イヴァンの飼っていたオランウータンのソニが地下室の戦車にはいり、誤って砲弾を発射したため、アンダーグラウンドの世界は崩壊する。現実の歴史があらわれる。
うそがばれたマルコは地下室を爆破してナタリアとともに失踪する。
息子のヨヴァンとともに地上に出た「クロ」は、自分をパルチザンの英雄に仕立てて撮影中の映画を現実と混同して、ナチス役の役者を殺し、逃亡する。
その途中、泳げないヨヴァンはドナウ川で溺死、その前にヨヴァンがいなくなったことに絶望した花嫁は地下室の井戸に身を投げ、自殺していた。
1980年に終身大統領のチトーが死亡すると、ユーゴスラヴィアの混乱がはじまる。映画の舞台は、すでに1990年代に移っている。
かつてのユーゴスラヴィアはもはや存在しない。マルコとナタリアは裏切り者として国際手配されている。ここはどうやらボスニアで、激しい内戦がつづいている。
そのなかで民兵組織を率いているのが、「クロ」だ。そして、マルコとナタリアは武器商人となって、敵側に武器を売っている。
そのマルコとナタリアを組織の民兵がつかまえ、隊長の「クロ」に指示をあおぐ。
「クロ」は武器商人の処刑を命じ、部下たちはそれを実行し、ふたりを燃やす。そこにやってきた「クロ」は、ふたりが友人のマルコとナタリアであることに気づき、「何ということだ」と、絶望に襲われる。
「クロ」は深い悲しみのなか、近くの井戸をのぞき込む。すると、そこに死者たちが泳いでいるのを見る。行方不明になった息子のヨヴァンも花嫁も、マルコとナタリアも、マルコの弟で自殺したイヴァンも楽しそうに泳いでいる。「クロ」は井戸に飛びこむ。
「クロ」の幻想のなかで、もう一度ヨヴァンと花嫁の結婚式がおこなわれることになる。死者が再会をはたす。映画のフィナーレでもある。
今度の場所は地下室ではなく、ドナウ川のほとりだ。結婚式には「クロ」の妻でお産のときに亡くなったヴェラも参加している。もちろん親友のマルコとナタリアも。マルコの弟イヴァンもいる。
「クロ」はマルコに向かって、許そう、でも忘れないぞという。ロマの楽隊がにぎやかに祝いの音楽を演奏する。これは結婚式であるとともに死者の復活祭でもある。
イヴァンが「昔あるところに国があった」と、いまは亡き愛すべきユーゴスラヴィアを懐かしむ回想を語る。
そして、人びとが浮かれ踊るうちに、何と会場が岸辺から切り離され、ドナウ川のまんなかにただよいはじめるのだ。
それはかつて存在したユーゴスラヴィアのかたちをしている。字幕が流れ、「この物語に終わりはない」という文字が浮かんで、映画は終わる。

これをどう受け止めればいいのか。パルチザンの神話を茶化したとも、社会主義の実態(真昼の暗黒)をとらえたとも、くり返される戦争の悲劇をえがいたとも、さらには多民族、多宗教の共生したユーゴスラヴィアを懐かしんだとも、どうとらえるかは、それこそ見る人の自由だろう。
ただし、言えることは、冷戦の終わりが、ユーゴスラヴィアにとっては解体のはじまりを意味していたということだ。
冷戦の終わりは、戦争の終わりでも歴史の終わりでもなかった。それは新しい戦争のはじまりであり、新しい歴史のはじまりにほかならなかったのだ。そのことをこの映画は教えてくれる。
価値論──メンガー『一般理論経済学』を読む(5) [商品世界論ノート]

ある財が価値をもつ(あるいは価値をもたない)というのは、いったい何を意味するのだろう。
財が価値をもつのは、財にたいする需求がその支配可能数量より大きい場合である。この場合、財は経済財となる。
逆に財が価値をもたないのは、財にたいする支配可能数量がその需求よりも大きい場合である。この場合、財は非経済財となる。
メンガーは価値について、そんなふうに論じている。
経済財と非経済財は固定されているわけではない。非経済財が経済財になり、価値をもつようになるケースは、たとえば木材や水が足りなくなった場合を考えてみればいいという。
そこでメンガーはこんなふうに書いている。
〈財価値は、財のわれわれの欲望にたいする関連にもとづくのであって、財そのものにもとづくものではない。この関係が変化すれば、価値もまた発生したり消滅したりせざるを得ない。〉
価値は人間の意識の外には存在しない。だが、価値は秘密めいたものではなく、正確に把握できるものだ。これがメンガーの考え方だ。
価値は使用価値と交換価値に分類することができる。交易関係のない孤立経済のもとで存在するのは使用価値のみである。交易関係が生じて、はじめて交換価値が発生する。それによって、価値は使用価値と交換価値の二重性をもつことになる。
いっぽうで、使用価値はあるが交換価値のないもの、交換価値はあるが使用価値がないものも存在する。だが、それは例外であって、人間の経済生活においては、財が使用価値と交換価値の双方をもつ場合がほとんどであるという。
財には使用価値があるのが前提である。だが、使用価値と交換価値のどちらを優先するかによって経済価値は変わってくる。
支配した財をもっぱら自己所有し、外部に譲渡しない場合には交換価値は発生しない。しかし、財を主に交易に回すとしたら、経済価値は交換価値が優先することになるだろう。
使用価値と交換価値のどちらを優先するかの選択は状況によって異なる。そこには経済性の法則がはたらく、とメンガーはいう。
次に検討しなければならないのは、価値の大きさである。価値の大きさはどのように決まり、なぜちがいがあるのか、また価値の大きさはなぜ変動するのか。
財はそれ自体で価値をもつわけではない。財はわれわれの欲望を満たすかぎりにおいて意味をもち(主観的契機)、そして、それはわれわれがどれだけの財を支配できるかに依存する(客観的契機)。
メンガーはそんなふうに述べている。
人間の欲望が優先的に選ぶのは、みずからの生命維持にかかわる財である。それにつづくのが幸福度をより満たす財ということになるだろう。こうした選択は各自の置かれた状況や各自の個性に依存する。そして、欲望満足の度合いも人によって異なる。
欲望の最大の対象となるのは食べ物だろう。人びとが食べるのは健康維持のためだけではない。食べる楽しみのために食べるのがふつうだ。
食欲は人によって異なる。だが、ある限界に達すると、食べることによる満足の度合いは下がっていく。このことは、住宅にしろ、何にしろ、ほかの財についてもいえる。
ここからメンガーは、欲望の充足はある限度を超えると逓減していくという法則を導きだしている。さらに、それ以上となると、「外見上その欲望を満足させるものとみえるいかなる行為も、もはや人々にとっての意義を失い、むしろ煩わしさと苦痛になっていく段階にまでいたる」という。
次に論じられるのが財の支配についてである。
一定の欲望を満たすには、一定の財を支配しなければならない。そのとき、どれほど欲望を満たすかに応じて財は価値をもつことになる。
だが、欲望はただひとつではない。たいていの場合は、「それぞれに一つだけの具体的欲望ではなく、それらの一つの複合体にたいして、またそれぞれに一つずつの財ではなく諸財の複合体の一数量が対応している」。
ここでメンガーは孤立して経済を営む農民をモデルとして、話を進める。
その収穫が年に500キロの穀物だとすれば、かれはまずその大部分を家族の健康維持のためにあてる。だが、それだけではない。残りの一部でビールをつくったり、家畜を飼ったりするかもしれない。さらに翌年の種籾もとっておかなかればならない。さらに余裕があれば穀物を何か別の楽しみのために用いたりもする。
収穫した穀物の用途はさまざまで、そこからさまざまな財がつくられ、それによってさまざまな欲望が満たされることになる。ここでは支配される財が欲望(用途)に応じて配分され、別の財に転じることが示されている。
さらにメンガーは、孤島に住む人や、漂流船に取り残された人を例にだして、そこでは限られた水や食料がいかに大きな価値をもつようになるかを説明している。孤島や漂流船では、希少な財が欲望をじゅうぶんに満たせないようになればなるほど、財の価値が増大することが示されるのだ。
価値は支配可能な財と欲望との相対的な関係によって決まる。これによって、なぜダイヤモンドや金が高い価値をもち、なぜ通常、水がほとんど価値がないかを説明できる、とメンガーはいう。スミスからリカード(さらにはマルクス)にいたる労働価値説は否定されることになる。
メンガーは財の質が価値におよぼす影響についても検討する。質のちがいは量によって代替できることもあるが、代替できない場合も多い。その場合は、質のちがいが欲望を満足させる度合いに差をもたらす。
そこで、一般に「経済活動を行なう人はその需求の総量に達するまで、より劣った質の財は後回しにしてより上級な質の財ばかりを、自らの欲望の満足のためにとる」という傾向が導きだされる。この場合、最劣等の財は価値をもたない。
だが、もし優良な財と劣等な財が同時に需求される場合、両者のあいだには価値に差が生じることになる。それは欲望を満足させる度合いのちがいにもとづく。
ここでメンガーが強調するのは、価値があくまでも主観的なものだということである。ある人にとって価値がある財も、別の人にとってはまったく価値がない場合もある。
〈価値はしたがって、たんにその本質からだけでなく、その尺度からしても主観的な本性をもつものである。財はつねに経済活動を行なう特定の主体にとって「価値」をもつものであり、しかしまた、特定のそうした主体にとってだけ一定の価値をもつのである。〉
財が真実価値をもつことも擬制価値をもつこともあるのは、価値があくまでも主観的なものだからだ。ここからまた財の過大評価や過小評価が生じる理由も説明できる。
財の価値を論じるにあたっては、人間の錯誤や無知を考慮しないわけにはいかない。だが、たとえそうであったとしても、基本的に価値の判断には合目的な方向性がみられる、とメンガーは考えている。
最後に論じられるのは、価値論の高次財への適応である。これまで価値の問題は、もっぱら直接的な欲望の満足にかかわる第1次財にのみ限定されていたが、それを高次財に拡大すると、いったいどのような法則がみてとれるかというわけである。
いうまでもなく、経済活動において第1次財を支配する(形成する)には、第2次財、第3次財といった高次財を必要とする。たとえば、パンをつくるには、まず小麦、さらにそれ以前に種籾と土地、耕作用具、労働力を必要とするというように。
ここでは「高次財の価値は、その高次財が産出に役立つ低次財の予想価値によって条件づけられる」という法則が成り立つ、とメンガーはいう。
重要なのは、あくまでも第1次財の価値である。高次財は第1次財の産出に役立つかぎりで意義をもつ。メンガーのこの発想は高次財の価値が第1次財の価値を決定するという一見常識的な考え方とまるで逆だといえる。
強調されるのは「高次財の予想価値の方が低次財の予想価値によって条件づけられる」ということである。ここでは、第1次財の価値が、次々と高次財の価値に移転されることが想定されている。
ここには時間の要素がはいってくる。何カ月、何年後の第1次財への需求を予想して、先行的に高次財が形成されなければならない。そこで、高次財の価値を方向づけるのは、現時点における低次財の価値ではなく、将来における予想価値だという原理が成り立つ、とメンガーはいう。
メンガーは高次財による低次財の(最終的には第1次財にいたる)形成を基本的に資本活動ととらえている。それは資本用役と企業者活動による時間の要素をともなう価値の形成であって、そこでは資本利用の価値(すなわち利潤)が発生するのがとうぜんだと理解する。利潤はいわば将来の不確実性にたいする保証である。だが、その利潤は将来予測の当否に左右される。
最後に追加として、メンガーは土地用役、労働給付、資本用役の価値についても述べている。これはじっさいには、地代、労賃、資本利子(利潤)の形態をとるものだ。
ここでもメンガーが強調するのは、土地用役、労働給付、資本用役がそれぞれ特有の性質をもっていたとしても、それらの価値は、他のすべての経済財と何ら異ならない法則(すなわち低次財にたいする需求の大きさに規定される)にしたがうということである。
労働の投下量や最低生活の保障、さらには搾取がそれらの価値を決定するわけではない。現代流にいえば、土地や労働力、あるいは利潤についても、あくまでも需要と供給がその価値を決定するというわけだ。ここには現代経済学、さらには現代社会を基礎づける考え方が示されている。
「昭和」を送る──大世紀末パレード(16) [大世紀末パレード]
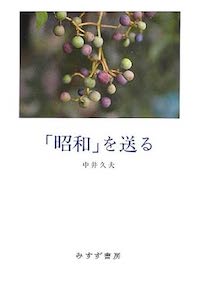
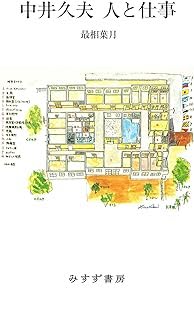
神戸大学教授で精神科医の中井久夫(1934〜2022)は、昭和天皇が亡くなってまもなく、雑誌「文化会議」(日本文化会議発行、平成元年[1989年]5月号)に「「昭和」を送る」と題する一文を載せている。
「文化会議」は保守論壇の雑誌で、中井の評伝に最相葉月は「中井は師の土居健郎に頼まれて寄稿しただけで、これが天皇擁護論と読めたとしても保守論壇入りしたことを意味しない」とコメントしている。
じっさい、そんなことはどうでもいい。
中井があのとき「昭和」をどのように送ろうとしていたのかを知りたい。
ここで昭和が「」付きで示されているのは、もちろんそれが昭和天皇にまつわる昭和だからである。
「昭和の鎮魂は、まだ済んでいない」と記したうえで、昭和天皇の深い魂の声を聞こうとしている。
どれほど遠くみえても、昭和天皇は身近な知り合いの心のなかに意外なかたちでしみついているように思えた。
だが、そもそも日本人にとって天皇とは何なのか。中井はアメリカ人との架空対談を設定して、そのことをできるだけ客観的に探ろうとする。
日本人には「君側の奸(くんそくのかん)」コンプレックスがある、とアメリカ人に説明している。
それは「君主は英明だがこれを邪魔して間違った情報を与え、いろいろ操作している、悪賢い奴が周囲にいる」という固定観念だ。
こうした発想は江戸時代もあるが、「君側の奸」を排除しようとして立ち上がったのは、戦前、五・一五事件や二・二六事件を引き起こした青年将校たちだった。
中井はそうはいっていないが、その根源には「天皇コンプレックス」があったといっていいのではないだろうか。
天皇コンプレックスは中世の武家時代にもみられた。だが、これが燃え盛ったのは、対外的危機感が強まった幕末だ。
徳川の幕府にはもはや正統性が認められないという思いが浮上する。朱子学で忠の原理を導入した幕府は自縄自縛におちいる。そこで、だれもさからうことのできない古代からの幻想的権威がもちあげられることになった。
明治以降、天皇コンプレックスは父性原理のようになって、日本人のなかにしみつくようになる。
「しばしば、激烈な反天皇論者が昭和天皇に会って、メロメロになった話を聞く」と、中井は書いている。
日本人のもうひとつのコンプレックスは、優越国への対外コンプレックスだ。それがかつては中国であり、近代以降は欧米に変わった。コンプレックスには讃仰と反発が含まれる。中井によると、いまでも日本人の中国コンプレックスは根強いものがあるという。
こうした、ふたつのコンプレックスにはさまれながら、日本人は勤勉と工夫、変身能力によって、さまざまな難局を切り抜けていった。
いっぽうで、日本人は土居健郎のいう「甘え」をも持ちあわせている。それが太平洋戦争の開戦時には、最悪のかたちであらわれたのだ。
あのとき日本は、「お互いをあてにし、天皇をあてにし、ルーズベルトをあてにし、ヒトラーをあてにし」て、戦争に突入した、と中井は書いている。
〈信頼せずして期待し、あてはずれが起こると「逆うらみ」する。何もあてにできなかったのは天皇一人だ。〉
昭和天皇は戦争の旗印にまつりあげられた。
ここから話は、その人となりに移っている。
注目されるのは「帝王教育」だ。
昭和天皇は徹底した帝王教育を受けている。それはかなりの心理的負担だったにちがいないが、この教育によって、何ごとにも動じない姿勢がはぐくまれた。
とはいえ、緊張の連続はまぬかれなかった。からだがぎこちない動きになり、声が甲高くなるのは、その証拠だ、と中井はいう。乗馬や水泳ができたことからみれば、けっしてスポーツ嫌いではない。
たいへんな風呂ぎらいと伝えられるのは、臨床経験からみると、「リラックスすることを自分に許せない人」だったのにちがいない。いっぽうで、競争とかはいっさいないから、のびやかで「非常に純粋無垢な人」になった、とみる。
天皇にかけられる圧力は相当なものだったろう。それに耐えることができたのは、昭和天皇が「天衣無縫の天真爛漫さ」という健康な精神をもっていたからだ、と中井は考えている。
昭和天皇が戦争責任を感じていなかったはずがない、と中井は断言している。「戦時中、大声の独り言が多く、チックが烈しくなり、十キロやせられた」のもその証拠だ。
太平洋戦争に踏み切った判断の誤りにも気づいていただろう。昭和天皇は「“距離を置いて客観的にものごとを眺めること” detachmentのできる知的人物である」。
「天皇機関説」が昭和天皇を救ったことも、中井は認めている。
〈「立憲君主」という位置の発見は、昭和天皇独自の大きなインヴェンションだということができる。昭和天皇戦争責任論に決着がないのは、それが明治憲法の矛盾の体現だからである。昭和天皇が非常な内的苦悩にさいなまれたのは、天皇がこの矛盾に引き裂かれた存在だからである。おそらく「天皇機関説」だけが天皇に合理的行動、いな正気の行動を可能にする唯一の整合性をもった妥協点であった。〉
昭和天皇が立憲君主の立場をとり、美濃部達吉の天皇機関説を支持したことが、敗戦後も天皇廃止とならず象徴天皇へと橋渡しできた大きな理由だった。
もちろん、アジアの戦争にたいする責任は残る。
〈天皇の死後もはや昭和天皇に責任を帰して、国民は高枕ではおれない。われわれはアジアに対して「昭和天皇」である。問題は常にわれわれに帰る。〉
これはまったく正しい。
明治以降、日本で天皇が機能してきたのは、天皇が無二の存在だったからだけではない。中井は皇室の役割を挙げている。
天皇という地位は拘束が多い。それゆえに、とりわけ皇太子の役割が大きいという(もちろん、皇后の存在もつけ加えるべきだろう)。
「象徴大統領制が象徴天皇制に劣るのは、皇太子相当の機能部分を持たないことである」という指摘がおもしろい。
皇太子が存在することによって、国家の安定的な持続が保証されるのだ。天皇制の廃止は、独裁的な首相(あるいは大統領)を生みだす危険性につながる。
〈天皇は英国皇室のごとくであれとかあるべきでないという議論を超えて、私は英国のごとく、皇室が政府に対して牽制、抑止、補完機能を果たし、存在そのものが国家の安定要因となり、そのもとで健全な意見表明の自由によって、日本国が諸国と共存し共栄することを願う。〉
これが、昭和天皇の逝去と代替わりにともなって、中井がいだいた率直な思いだったろう。
昭和天皇が最後に残した昭和63年(1988年)の歌がふたつ紹介されている。
「道灌堀 七月」
夏たけて堀のはちすの花みつつほとけのをしへおもふ朝かな
「那須の秋の庭 九月」
あかげらの叩く音するあさまだき音たえてさびしうつりしならむ
いずれの歌にも「死の受容」がある、と中井はみる。
昭和天皇のつくった「お歌」は4万首で、そのうち公表されているのは二、三百首にすぎないという。歌が心を詠むものだとすれば、昭和天皇の心の声は、その多くがまだ隠されたままといってよいだろう。
経済的進歩の要因──メンガー『一般理論経済学』を読む(4) [商品世界論ノート]

人間は生きているかぎり、日々欲望を満たし、調和的な生活を維持していかなければならない、とメンガーは書いている。そのためには、みずからの欲望を満たしうる手段をもたなければならないが、それには事前の配慮が必要となるという。
経済とは、主体的にみれば、欲望を満足させるための手段を確保しようとする努力を指す。それは自然的、社会的状況のもとで、生産や交易を通して財を得ようとする活動でもある。いっぽう、客体的にみれば、経済とは、われわれが支配しうる財の総体であり、それをいかに配置するかという問題となる。
経済の出発点は財である。そこには交易によって得られる財も含まれるが、経済の目標は、こうした財によって、みずからの需求を満たすことである。そして、そうした需求を満たすには、生産手段(材料、労働力、機械など)だけではなく、交換手段(貨幣など)が必要になってくる。
ただし、経済活動とは消費そのものを意味するわけではない。あくまでも、われわれが自分たちの欲望を満たすための手段を確保する過程を意味する。
メンガーは経済をそんなふうに理解している。
経済を生産・分配・消費というジャンルにわけるのは、まったく外面的な把握にほかならない。また、労働を財の唯一の源泉と考えるのもまちがっている。経済を生産と同一視するのも一面的だ。経済とはあくまでも財の需求を充足させようとする人間の努力全般を指すというのがメンガーのとらえ方である。
財には経済財と非経済財がある。過剰なほどどこにでもふんだんにある財は経済財にならず、非経済財のままだ。たいていの場合、水や大気、砂、森の木材などは非経済財である。
しかし、場所が変われば、こうした非経済財も経済財になる。非経済財から経済財への転換は、住民の数が増大したり、財の新たな使用目的が発見されたりすることによっても生じる。
いずれにせよ非経済財が経済財に、あるいは経済財が非経済財になるのは、需求と支配可能数量との関係が変化することによってである。そのことは、都市における飲料水や木材の必要性が、ほんらい非経済財だったものを経済財に転化させることをみても、あきらかだという。
飲料水が住民の需求をじゅうぶんに満たす場所では、水道は必要なく、したがって水道設備のための高次財の必要も生じない。
そこで、メンガーはいう。
〈人間に直接に与えられた財がすべての人間経済の出発点であり、人間の需求の充足がその目標点である。人間はまず第1次財にたいする欲望を感じて、自分の需求よりも少ない量しか支配しえない第1次財を、自分の経済的活動の対象、つまり経済財にする。……その後に熟慮と経験を重ねることによって、人間は諸物の因果的連関……をたえず深めていって、第1次、第2次、そしてさらに高次の財を知るようになるのである。〉
欲望を満たす財が常にそこにあるなら、経済など必要ではない。そこには、いわば自然の恵みにあふれた楽園が広がっているのだから。
もちろん、メンガーはかつて人類がそうした楽園を経験したとは思っていない。
現在の発達した文化のもとでは、さまざまな生産過程をへて、ようやく享受財を得ることができるのが実情だ。とはいえ、究極的な財需求を満たすには、「生産手段に目標と方向を与える配分的な活動」が必要になってくる。
すなわち享受財の需求を見越して(その場所や時間、種類、量も含めて)、それを満たすために必要な生産手段(技術としての労働力を含む)を集めて、目標と方向を定め、それを組み合わせて、技術的─経済的な活動をおこなわなくてはならない。
いっぽう、財にはかぎりがある。人間の経済の出発点は、財が不足がちであるという現実にあり、財需求を完全に充足することは、人間経済の理想的な究極目標でしかありえない。とするならば、かぎられた財にたいする需求を可能なかぎり満たすことが経済活動の目標となる、とメンガーはいう。
そこからは節約化の方向が生じる。財の喪失や損傷を予防することはもちろんだが、生産の効率性も求められる。できるだけ少量の享受財で、欲望を満たす努力(さらには欲望自体を抑制する努力)も必要だろう。さらに、かぎられた生産手段からどのような財の生産を優先するかについても先行的配慮がなされなければならない。
つまり、人間の経済には技術的(拡大)の方向と節約化(効率化)の方向が同時にはたらいている、とメンガーは考えている。
このふたつの方向が結びつくことによって、人間の経済には次のような傾向が生じる。
最大可能な成果を効率的に達成すること。
より必要な財を優先して選択すること。
さらに資本の集中により生産効率を高めること。
ところで、人間の社会においては、しばしば、かぎられた財をめぐって利害の衝突が生じる。それを解決するひとつの方法が、財の共同占有と個々の経済主体への分与(配給)だということをメンガーも認めている。だが、それは往々にして失敗に終わる。
これにたいし、共同占有がなされていない社会では、経済主体は法秩序のもとで私的な所有権を認められることになる。
ありあまる財が存在する世界では、所有権は何の意味ももたない。だが、支配可能な財の数量がすべての人間の欲望を満たさない経済においては、所有権をもつ者に財が所有されることはやむをえない。
メンガーは社会主義には否定的だったように思われる。せめて可能なのは必要最低限の財を確保し、それを分配できるようにするくらいなものだと書いている。
私的な所有権が認められる社会では、資産が存在する。
資産とは何だろう。
メンガーは資産を「ある人物が支配する経済財の全体」と定義する。
あらゆる財が需求以上にありあまっている社会では、経済財も資産も存在しない。資産という概念が存在するのは、経済財が希少な財である場合だ。
経済財を所有する主体は資本家だけではない。国家や自治体、会社も資産(経済財)を所有している。
これにたいし、国民資産という概念は一国民全体を経済活動をおこなう主体と考える一種の擬制であって、厳密な意味で、国民資産なるものが存在するわけではない。
国民資産は「人々の交易によって結び合わされた、経済財の複合体」ではあるが、その数量そのものから国民全体の経済を判断すると、誤りを生じやすい、と述べている。
いまなら、メンガーはGDPを最大の経済指標とする考え方に懸念を示したにちがいないと思われる。
資産のうち、財(生産)の元本となるものをメンガーは資本と名づける。資本は用役財資本(土地や機械、建物など)と消耗財資本(原材料、補助材料)からなる。それは安定資本(固定資本)と可変資本(流動資本)と言いかえることもできる。
いっぽう、資産には生産ではなく消費に向けられるものもある。そうした資産のなかには、用役財(土地、住居、家具など)や消耗財のほか、貨幣も含まれることになるだろう。
なお補足すれば、メンガーは資本における用役財も長期的にみれば消耗財なのであって、最終的には財としての性質を失ってしまうと述べている。したがって、資本を純資本として維持するためには、用役財の摩滅(資本原本の部分的な消耗)に対応していかなくてはならない。
この章(第4章「経済と経済的財の理論」)では、経済とは何かにはじまって、経済財と非経済財の区別、経済活動の方向性、資産と資本が論じられたが、最後は経済的進歩をもたらす要因が検討される。
メンガーは、アダム・スミスのように、経済的進歩の要因を分業だとは考えなかった。
労働は力というより、むしろ技術であって、技術的労働が、財の形成に向けての努力を指すことはいうまでもない。だが、分業自体が経済的進歩をもたらすわけではない、とメンガーはとらえていた。
分業は大きな要因ではない。それよりも、直接的な第1次財の獲得に専念するのではなく、第2次、第3次と高次の財を獲得する方向に進むことこそが、経済進歩をもたらすのだ、とメンガーは考える。
その例として挙げられるのが、次のような人類発展の経緯だ。メンガーによれば、「獲物を棍棒1本で追う猟師が弓と網を使う猟へ、牧畜へ、さらに進展して、ますます集約的な形態の牧畜へと移行していく」のが、これまでの人類の歴史だった。
ここでは、直接に獲物を追いかけるよりも、迂回して獲物をつかまえる道具(高次財)を工夫することが、より多く第1次財を得ることにつながるということが、暗黙のうちに示されている。
そこで、メンガーはいう。
〈いずれにせよわれわれの欲望の満足への高次財の利用を増進することは、われわれの支配しうる享受手段の数量を増加させ、したがってわれわれの経済的状況をますます改善するという結果を生じる。〉
直接、第1次財に労働の投与を集中させるよりも、高次財の形成を工夫することが、人びとの獲得する享受手段を増進させることにつながるというのがメンガーの考え方だといってよいだろう。いまなら、こうした高次財の代表がさしずめ半導体ということになるだろうか。
だが、人間が高次財を獲得するには、前提が必要である。
それは何か。
〈それは、これらの[経済活動を行う]主体が、現時点について経済財にたいする自分の需求を満たした後、なお、また先の生産過程のための、あるいは未来の諸期間のための経済財の数量が残るのか。いいかえれば、資本を占有するかどうか、である。〉
ここでいう資本は、いわば社会的余剰ととらえられている。こうした社会的余剰は分配され、消尽されてしまってはならない。むしろ、占有され、高次財の形成へと向けられることによって、経済的進歩がもたらされる。
高次財の形成は「人間の先行的配慮の活動」の結果であって、そのためにはそれをおこないうるだけの「資本の生産性」が必要だというのが、メンガーのとらえ方なのである。
最後の1日──南インドお気楽ツアー(8) [旅]
2月26日(月)
アレッピのバックウォーター(水郷)に停泊したクルーズ船の部屋に籠もって、おとなしくしています。胃腸の具合はまだ元に戻っていません。日が昇るのをみにいく気力もありませんでした。

朝も食べられず、8時すぎに下船しました。優雅な船旅を楽しめなかったのは、いかにも残念でした。

船着場で待っているバスに乗り込み、北のコーチン(コチとも)に向かいます。バスはアラビア海沿いに走ります。

9時半ごろコーチンに到着。正確にいうと、コーチンのなかでもフォート・コーチンと呼ばれる地区です。
アラビア海に面するコーチンは古くから貿易港として栄え、古代ローマ人やアラブ商人も訪れていたそうです。近世にはいると西洋の植民地となります。最初はポルトガル、次にオランダが支配しました。
コーチンにはキリスト教の人もイスラム教の人も多い、とガイドさんがいいます。大きな教会が立っていました。どこかインド風なのがおもしろいですね。

バスを降りたあたりには、古い西洋風の建物が残っていて、ホテルなども多いようです。

最初に向かったのが聖フランシス教会です。元はポルトガル人が建てたカトリック教会ですが、オランダ人がコーチンを占拠したあとはプロテスタントの教会に変わりました。

その内部はわりあい質素です。

この教会がなぜ有名かというと、1524年12月にヴァスコ・ダ・ガマがコーチンで亡くなったとき、その墓がつくられたのが、この礼拝堂だったからです。ガマの遺骸は14年後に本国ポルトガルに運ばれますが、最初につくられた墓地は、いまも教会のなかに保存されています。

ちなみに、ガマが喜望峰、アフリカ東海岸を経て、インド南部のカリカット(カレクト)に到着したのは1498年のことです。これが、ポルトガルによる「インド航路」発見の端緒となりました。
ガマの生涯は、アラビア海から現在のインドネシアに広がるイスラム勢力を排除し(自身は一種の「十字軍」と考えていました)、インドに交易の拠点を築くことに費やされます。
ガマ自身は3回インドに航海しています。そのころコーチンは香料の積み出し港になっていました。ゴアにポルトガルの要塞が築かれました。
そして3回目の航海となった1524年にコーチンで客死するわけです。それから18年後の1542年にイエズス会のフランシスコ・ザビエルがゴアに到着、コーチンでも布教をはじめています。
その後、インドにはオランダやフランスが進出し、最後はイギリスが他の勢力を排して、全インドを植民地に組み込んでいくことになります。とりわけイギリス東インド会社は、インドをむさぼり尽くしたといっても過言ではないでしょう。
聖フランシス教会を見たあとは、歩いて海岸に出ました。前はアラビア海ですね。

網を海に沈めて、ロープで引き上げ、魚をとるのは、このあたり独特の漁法で、「チャイニーズ・フィッシング・ネット」というそうです。海岸沿いには屋台が並び、魚も売っています。ガイドさんがいろいろと説明してくれるのですが、体調の悪いぼくはもうろうとしています。

昼食の海鮮料理もほとんど食べられませんでした。
地元のスーパーに寄って、おみやげを買い、そのあと香辛料や宝石、衣料品などを売っている商店街にも訪れたのですが、ついていくのがせいいっぱいです。
あとで調べると、この商店街は「ユダヤ人町」と呼ばれていたことがわかります。ローマ帝国に国を滅ぼされたユダヤ人が、はるか南インドまでやってきて、この町で香辛料交易に従事していたといいます。シナゴーグも立っているようですが、いまはユダヤ人の姿を見かけることはありません。

最後に訪れたのが、カタカリダンスというコーチンの伝統舞踊が演じられる劇場でした。イギリスのチャールズ皇太子(現国王)夫妻も2019年のインド訪問のさい、ここを訪れたといいます。

劇場はすいていて、舞台を見たのはツアーのメンバー13人だけでしたが、おかげで二人の役者さんが化粧をするところから見ることができました。

舞台は二部構成です。
最初はひとりの役者さんが、目や眉の動きで愛や悲しみ、怒り、驚きなど9つの感情を表現します。見得を切るようなところもあって、ユーモラスで迫力のある舞台でした。

次はヒンドゥーの古代叙事詩「バーガヴァタプラナー」の一節で、ふたりの役者さんが登場します。

ケララの王子ジャヤンタに恋をした羅刹女(らせつにょ)は美女に化けて王子を誘惑しますが、王子に姿を見破られて、一刀のもとに切り捨てられます。最後は鋭い叫びを発して舞台を退場するのですが、その叫び声がすごかったので、びっくり仰天しました。

記念撮影に応じてくれたのにも感激しました。

短いインドツアーもこれで終わりです。われわれはコーチン空港からシンガポール経由で日本に戻ります。
旅をすると思い出が増えます。どんなに短い旅であっても、遠くにあったはずのその国の光景が、自分のからだや心にしみついて、忘れられなくなります。インドもそんな国のひとつでした。世界は広い。インドは深いです。
アレッピのバックウォーター(水郷)に停泊したクルーズ船の部屋に籠もって、おとなしくしています。胃腸の具合はまだ元に戻っていません。日が昇るのをみにいく気力もありませんでした。

朝も食べられず、8時すぎに下船しました。優雅な船旅を楽しめなかったのは、いかにも残念でした。

船着場で待っているバスに乗り込み、北のコーチン(コチとも)に向かいます。バスはアラビア海沿いに走ります。

9時半ごろコーチンに到着。正確にいうと、コーチンのなかでもフォート・コーチンと呼ばれる地区です。
アラビア海に面するコーチンは古くから貿易港として栄え、古代ローマ人やアラブ商人も訪れていたそうです。近世にはいると西洋の植民地となります。最初はポルトガル、次にオランダが支配しました。
コーチンにはキリスト教の人もイスラム教の人も多い、とガイドさんがいいます。大きな教会が立っていました。どこかインド風なのがおもしろいですね。

バスを降りたあたりには、古い西洋風の建物が残っていて、ホテルなども多いようです。

最初に向かったのが聖フランシス教会です。元はポルトガル人が建てたカトリック教会ですが、オランダ人がコーチンを占拠したあとはプロテスタントの教会に変わりました。

その内部はわりあい質素です。

この教会がなぜ有名かというと、1524年12月にヴァスコ・ダ・ガマがコーチンで亡くなったとき、その墓がつくられたのが、この礼拝堂だったからです。ガマの遺骸は14年後に本国ポルトガルに運ばれますが、最初につくられた墓地は、いまも教会のなかに保存されています。

ちなみに、ガマが喜望峰、アフリカ東海岸を経て、インド南部のカリカット(カレクト)に到着したのは1498年のことです。これが、ポルトガルによる「インド航路」発見の端緒となりました。
ガマの生涯は、アラビア海から現在のインドネシアに広がるイスラム勢力を排除し(自身は一種の「十字軍」と考えていました)、インドに交易の拠点を築くことに費やされます。
ガマ自身は3回インドに航海しています。そのころコーチンは香料の積み出し港になっていました。ゴアにポルトガルの要塞が築かれました。
そして3回目の航海となった1524年にコーチンで客死するわけです。それから18年後の1542年にイエズス会のフランシスコ・ザビエルがゴアに到着、コーチンでも布教をはじめています。
その後、インドにはオランダやフランスが進出し、最後はイギリスが他の勢力を排して、全インドを植民地に組み込んでいくことになります。とりわけイギリス東インド会社は、インドをむさぼり尽くしたといっても過言ではないでしょう。
聖フランシス教会を見たあとは、歩いて海岸に出ました。前はアラビア海ですね。

網を海に沈めて、ロープで引き上げ、魚をとるのは、このあたり独特の漁法で、「チャイニーズ・フィッシング・ネット」というそうです。海岸沿いには屋台が並び、魚も売っています。ガイドさんがいろいろと説明してくれるのですが、体調の悪いぼくはもうろうとしています。

昼食の海鮮料理もほとんど食べられませんでした。
地元のスーパーに寄って、おみやげを買い、そのあと香辛料や宝石、衣料品などを売っている商店街にも訪れたのですが、ついていくのがせいいっぱいです。
あとで調べると、この商店街は「ユダヤ人町」と呼ばれていたことがわかります。ローマ帝国に国を滅ぼされたユダヤ人が、はるか南インドまでやってきて、この町で香辛料交易に従事していたといいます。シナゴーグも立っているようですが、いまはユダヤ人の姿を見かけることはありません。
最後に訪れたのが、カタカリダンスというコーチンの伝統舞踊が演じられる劇場でした。イギリスのチャールズ皇太子(現国王)夫妻も2019年のインド訪問のさい、ここを訪れたといいます。

劇場はすいていて、舞台を見たのはツアーのメンバー13人だけでしたが、おかげで二人の役者さんが化粧をするところから見ることができました。

舞台は二部構成です。
最初はひとりの役者さんが、目や眉の動きで愛や悲しみ、怒り、驚きなど9つの感情を表現します。見得を切るようなところもあって、ユーモラスで迫力のある舞台でした。

次はヒンドゥーの古代叙事詩「バーガヴァタプラナー」の一節で、ふたりの役者さんが登場します。

ケララの王子ジャヤンタに恋をした羅刹女(らせつにょ)は美女に化けて王子を誘惑しますが、王子に姿を見破られて、一刀のもとに切り捨てられます。最後は鋭い叫びを発して舞台を退場するのですが、その叫び声がすごかったので、びっくり仰天しました。

記念撮影に応じてくれたのにも感激しました。

短いインドツアーもこれで終わりです。われわれはコーチン空港からシンガポール経由で日本に戻ります。
旅をすると思い出が増えます。どんなに短い旅であっても、遠くにあったはずのその国の光景が、自分のからだや心にしみついて、忘れられなくなります。インドもそんな国のひとつでした。世界は広い。インドは深いです。
平岡正明『中森明菜』から ──大世紀末パレード(15) [大世紀末パレード]


中森明菜がテレビの歌番組を席捲したのは1982年から89年のことだった。17歳から24歳にかけての時期にあたる。TBSの「ザ・ベストテン」、フジテレビの「夜のヒットスタジオ」などの歌番組がはやっていた時代で、ぼくもよく見ていた。
『山口百恵は菩薩である』と論じた好漢、平岡正明(1941〜2009)には、『中森明菜──歌謡曲の終幕』という著書もある。山口百恵のあと日本の歌謡界をリードした中森明菜を、かれはどのようにみていたのだろうか。
日本の芸能界はレベルが低すぎる。明菜は「周囲の無能者にむしられた」というのが、平岡の率直な印象だ。
1981年に山口百恵が引退し、ピンク・レディーが解散した。その空白を埋めたのが、松田聖子、中森明菜、小泉今日子の3人組だった。
その3人のうち絶頂をきわめたかにみえる中森明菜は1989年夏にとつぜん自殺未遂に走り、みずからの経歴に幕をおろした。
この年、昭和は終わり、歌謡界の「女王」美空ひばりが亡くなっていた。明菜の退場とともに、戦後歌謡曲の「終幕」が訪れた、と平岡は記している。
1981年に中森明菜は新人発掘のオーディション番組として知られていた「スター誕生!」に3回挑戦して合格し、ワーナー・パイオニアにスカウトされた。所属事務所は「研音」。実家は東京・大田区で精肉店を営んでいたが、住んでいたのは清瀬市だった。
デビュー曲は来生えつこ作詞、来生たかお作曲の「スローモーション」、「出逢いはスローモーション 軽いめまい 誘うほどに」と、恋の予感を歌った叙情的ないい曲だが、薬師丸ひろ子風で、さほど大きなヒットにはならなかった。
そこで、事務所は強烈なインパクトをねらう。明菜に不良少女のイメージを担わせて、「少女A」(売野雅勇作詞、芹澤廣明作曲)を歌わせたのだ。最初、明菜は「嫌だ、絶対に歌いたくない」と抵抗していたという。
それは男の子に挑戦的に迫っていく女の子の歌だ。「じれったい じれったい 結婚するとか しないとかなら」というフレーズが印象的だった。そして「じれったい じれったい そんなのどうでも関係ないわ」とつづく。
かわいい少女が幼い声でつくりあげるセンセーショナルな歌のイメージは、明菜をたちまちスターの座に押し上げた。
平岡は、この歌は山口百恵幻想に乗っかっているという。ちがうのは、明菜が「百恵をまねようとしているのではなく、挑戦している」ことだという。
セカンドアルバムの「バリエーション」は失敗作だった。だが、平岡にいわせれば、明菜の「挑戦─アンチテーゼ─自己確立」がはじまっている。
「基本線は遮断だ。夢を遮断し、情景を遮断し、テーマを遮断するのである。曲は素材であって、曲に情感をまとわせない歌いかたをえらぶ」
その模索をへて、次のヒット曲「セカンド・ラブ」が生まれる。
「恋も二度目なら 少しは上手に 愛のメッセージ 伝えたい」
作詞作曲は来生えつことたかおのコンビ。二度目の恋をする少女は、わたしを抱き上げて「どこかへ運んでほしい」と願っている。
ヒット曲がつづく。
1983年には「1/2の神話」「禁区」が発売された。
「半分だけよ 大人の真似 それでもまだ悪くいうの いいかげんにして」という「1/2の神話」にはまだツッパリのイメージが残っている。
「禁区」は中国の立ち入り禁止区域を意味するという。少女は「私からサヨナラしなければ この恋は終わらないのね」と思いながらも、なかなか年上の男に別れを告げられないでいる。
1984年には「北ウイング」と「十戒(1984)」「飾りじゃないのよ涙は」が出て、明菜はいよいよパワーアップする。
明菜はもう少女ではない。じつに多彩な女性たちに憑依する。平岡にいわせれば、そのスタッフを含めて、明菜のシステムは「デビュー当初からバラバラだ」。しかし、明菜はけっして型(コンセプト)にははまらない。
1985年には「ミ・アモーレ」で、86年には「DESIRE」で、2年連続レコード大賞をとる。
平岡が絶賛するのは「飾りじゃないのよ涙は」で、いちばん好きなのは85年にでた「SOLITUDE」だという。
「飾りじゃないのよ涙は」は井上陽水の作詞作曲。
私は泣いたことがない
灯の消えた街角で
遠い車にのっけられても
急にスピンかけられても恐くなかった
赤いスカーフがゆれるのを
不思議な気持ちで見てたけど
私泣いたりするのは違うと感じてた
この曲がでたとき、明菜は19歳の終わり。山口百恵が「プレイバック part2」を吹きこんだのと同じ年で、陽水はそれを意識している、と平岡はいう。
「プレイバック」ではUターンする車が、ここでは女を乗せたままスピンする。でも、彼女は恐くなかった。泣かなかった。事故に遭うかもしれない自分を冷静にみている。
それでも「いつか恋人に会える時 私の世界が変わる時 私泣いたりするんじゃないかと感じてる」。白雪姫はまだ目をさましていない。
いっぽうの「SOLITUDE」は孤独を歌う。明菜は二十歳になった。
「25階の非常口で風に吹かれて爪を切る たそがれの街 ソリテュード」とはじまる。湯川れい子作詞、タケカワ・ユキヒデ作曲。
平岡はこの歌を歌う明菜について、こう書いている。
〈ソリテュード、という語を、ガラス鉢の中の金魚が泡を一つ、ポッとはきだすように歌う。水は替えてやったばかりで冷たい。金魚は気持よさそうに底の方でじっとしているが、透きとおった水の中から外界を眺めて、さびしいわ、と一言、気泡をはき出す。眠りの白雪姫が、はじめてポチリと片目をひらいて「さびしいわ」とつぶやいたのがこの曲だ。〉
平岡にいわせれば「傑作になりかかってしぼんだ」作品だが、深い孤独に達していなくても、幸せそうな女の子のなかにきざす一瞬の孤独をとらえた曲になった。このころ明菜はすでに近藤真彦とつきあっている。
「ミ・アモーレ」はリオのカーニバルに托したラテン調の恋歌。この曲が大ヒットしはじめていた8月12日に、日航123便に乗っていた恩人の坂本九が亡くなる。
そして「DESIRE」。ロック調でGet up, Get up, Burning Loveではじまり、「まっさかさまに墜ちて desire」。でもどこか夢中になれない、淋しい。平岡は、この曲の下敷きに山田詠美の『ベッドタイムアイズ』があるとみている。
このころの明菜はツアーや新曲発売、テレビ出演と多忙をきわめている。まさに絶頂期にあったといえるだろう。だが、ヒット曲を生みつづけることを義務づけられた緊張感のなかで、芸能事務所とだけではなく、家族ともうまく行かなくなっている。おカネがからんでいた。
そんな裏の事情はともかくとして、低音から「オワーッと横に情感がひらいていくような」、淫らさすら感じさせる明菜の歌唱に、平岡は目をみはっている。
平岡は「難破船」にふれていない。68年世代のぼくなどには、1987年に発売されたこの曲が中森明菜のベストソングだと思われる。加藤登紀子の作詞作曲。恋の終わりを歌った曲だ。
「たかが恋なんて 忘れればいい」というせりふからはじまり、「ひとりぼっち 誰もいない 私は愛の難破船」で終わる激しくて悲しい曲だ。
中森明菜は昭和の終わりの、愛と悲しみを歌っていた。
メンガー『一般理論経済学』を読む(3) [商品世界論ノート]

人間の欲望と財はどのように対応しているのだろう。
メンガーはここで人間の欲望を満たしうる財の量全体を「需求」と名づけ、これにたいし現存する財を「支配可能な財の数量」と呼んでいる。
われわれが求めるのは直接に消費対象となる第1次財である。だが、第1次財の背後には第1次財をつくるのに必要となる何層もの(高次の)間接的な財がひそんでいることはいうまでもない。それは1冊の本をみてもわかるだろう。
人間の欲望は自然発生的なもので、意志の力や外的な条件によっては完全にコントロールできない、とメンガーは考えている。欲望はあらゆる方向に広がっていく。
とはいえ、欲望は満たされなければならない。それには、さまざまな財との組み合わせが可能である。ここから需求は現に与えられている財にたいする「選択的な決定」とならざるをえないというメンガーの定理が導きだされる。
すると、直接的な需求と直接的な財数量は、はたして確定できるのかという問題がでてくる。
まず需求についていえば、少なくとも現時点の欲望を満たすだけなら、食料や飲料、衣服、住居関係にどれだけのものが必要かを確定することは可能だ。
だが、それだけではすまない。人間は将来に向かって生きているからだ。しかも、それは不確実性に満ちている。
不確実性に満ちた将来を想定するなら、需求を現在の直接的需求だけに限定するわけにはいかない。戦争や地震、火事、病気、家族の将来、その他もろもろの不安が、需求の確定をむずかしくする。人間の欲望は、将来の不安をできるかぎり乗り越えることにも向けられているからだ。
さらに、欲望が無限に発展する可能性を考えれば、需求の確定はそれこそ不可能のようにみえてくる。とはいえ、一定の期間をとれば、1次財にたいする需求は一定の量に限られるとメンガーはいう。
いっぽう、支配可能な財数量、言いかえれば財のストックのほうはどうだろう。これも一定の時間をとれば、その数量は与えられ、確定されているといえるだろう。
将来を考えれば、不確実性が増大することはいうまでもない。だが、重要なことは、われわれが将来、直接支配可能となる財数量について、現時点で常に先行的に判断を下していることだ、とメンガーは書いている。現在の生活経験を基準として、将来の財のストック水準が見定められているといってよい。
1次財の需求と数量への考察は、とうぜん間接的な高次財の需求と数量へと拡張されなければならない(紙の本をつくるには紙が必要だ)。
間接的な高次財への需求は、1次財の需求によって制約されている。高次の財への需求は、ひとつ低次の財への需求を反映するのであって、高次財の需求が単独にあらわれるわけではない、とメンガーは述べている。
とはいえ、高次財への最終的な需求が常に満たされるとはかぎらない。靴の需求が1万足あったとしても、じっさいには5000足しかつくれないこともある。支配できる(提供できる)高次財(材料、道具、労働力など)がかぎられているからである。
メンガー自身は「われわれが高次財への有効な需求をもちうるかどうかは、補完的な諸高次財の対応した数量をわれわれが支配できるかどうかによって制約されている」と論じている。
たとえば、広大な農地をもっていても、そこにまくだけの種子がないとか、逆に種子があっても農地がないとするなら、いくら高次財としての小麦が求められていても、有効な需求は制限されてしまうことになる。
ここで選択と予見がはたらく。直接的な需求にもとづいて、どのような間接財を選択するかは自由である。さらに直接的、間接的を問わず、将来の需求を予見することによって、技術の発展がうながされることになる。そのことが制約の突破に結びついていく。
メンガーは人間の経済を考察するにあたっては「時間」が大きな位置を占めることを強調している。
〈われわれの生活は、人間一般に、ことに各個人にわりあてられた時間の範囲内で実現される一つの過程である。われわれの欲望は徐々にしか現実の世界の中に現われず、かくしてこれらの欲望は、具体的な形をとって特定の時間のみに現われてくる。各人の需求はすべて、特定の期間をとってみれば、特有の大きさなのである。〉
ある時間、あるいは一定の時代において、人間の需求、人間の支配可能な財、技術は、その時点での特有の大きさと質をもっている。それは移ろいやすいものだ。また次第に大きくなり、発展していく性格をもっている。
さらにいえば、人間の経済においては、特定の量の需求を満たすためには一定の時間を要する。その典型的な例が穀物だ。穀物の成育にはそれなりの時間がかかる。
学校教師を増やすことが求められる場合も、有能な人材はたちどころに生まれるわけではない。長い時間の訓練が必要だ。
一般に、将来の1次財を満たすためには、早い時期に高次財の準備がなされなければならない。
こうしたことを前提として、「需求と支配可能な財数量は、人間経済のどのような時期においても、特定の量としてたがいに向かい合っている」ということがいえるのだ。
ただし、このことは需求が常に満たされることを意味しない。低次財と高次財には、その形成に時間差があり、したがって不確実性がともなう。さらに、ある財の需求が満たされないときは、別の財が選ばれるといった選択の論理もはたらく。
さらに、需求は個人の需求だけではなく、一国民の社会的な需求としてとらえなければならない、とメンガーは主張する。
社会的需求とは、社会全体の欲望を量的にも質的にも完全に満足させるのに必要な財の総体を指している。
とはいえ、現実に国民需求の充足を自身の任務として経済活動をおこなう主体は存在していない、とメンガーはいう。国家は国家機関にしか関与していない。実業界はみずからの利益に関心をもっても、貧窮にあえいでいる人びとの需求には関心をもたない。
それでも、国民経済は社会全体の需求を確定するという課題を放棄できない、とメンガーは述べている。社会的需求には諸個人の需求だけでなく、社会の共通の利益(たとえば街路、公園、治安、環境)なども含まれている。さらに、将来の不確実性にたいする需求も配慮しなくてはならない。いずれにせよ、社会全体の需求をとらえるのが重要であることをメンガーは強調している。
それは支配可能な財数量についてもいえる。財のストックとしてあげられるのは、国家資産と個人資産だが、真の意味での国民資産は把握されていないと述べている。
真の国民経済が存在するものとすれば、国民にとって支配可能な諸財がどの程度なのかがとらえられなければならない。ところが関心がもたれているのは、もっぱら直接的な供給と需要だけときている。
ここでメンガーが関心をいだいているのは国民全体の財のストックだといえるだろう。こうした財は幅広く交換されることによって、国民全体の需求に応えることができる。
国民経済は、国家が国民の需求を把握すると同時に、社会全体の財のストックを認識し、自由な交換をうながすことでしか成立しない、というのがメンガーの基本的な考え方だったように思える。
インドに見放される──南インドお気楽ツアー(7) [旅]
2月25日(日)
モーニングコールがなく、6時にホテルのスタッフが「6時ですよ」と呼びにきました。しかし、なぜか6時半集合と思って、のんびりしていたのがまちがいのもとでした。6時半にロビーに行きますが、すでにだれもいません。どうやら集合時間は6時10分だったようです。
コモリン岬で朝日が昇るのを見ることになっています。6時半は日がのぼる時間でした。

あわてて砂浜にでて、海岸の展望台をめざしました。展望台にのぼると、戻ってくるツアーの一行と出会います。聞くと、この日はくもっていて6時半の朝日が見えなかったといいます。しかし、ふとふり返ると、雲のあいだから、朝日がのぼってくるのが見えたのです。

きょうもいい天気になりそうです。

食事をすませ、バスは8時の出発です。
すぐにのんびりした風景が広がって、何だかほっとします。はじめて出会う風景のはずなのに、昔どこかで見たような感覚に襲われるのがふしぎです。

まもなくケララ州にはいります。アラビア海に面したインド南西部の州で、ここではタミル語ではなくマラヤーラム語が話されているとか。
海岸沿いにはヤシの畑、東側には西ガーツ山脈の大きな山が連なります。

ケララにはいると英語表記が増え、教会も多くなります。ケララ州の人口は3500万人で、ヒンドゥー教徒が人口の30%、イスラム教徒が25%、キリスト教徒が20%を占めているといいます。
インドは貧困というイメージはもう過去のものといっていいのではないでしょうか。日曜のせいか、広場でクリケットをやっている人を多く見かけました。

トリヴァンドラムという大きな町にはいりました。ここはケララ州の州都で、かつてはトリヴァンドラム藩王国の都でした。

きょうはポンガルと呼ばれる大きな祭があるということで、インド各地から多くの人が集まってきています。バスや車も多い。マンションやショッピングモールも数多くつくられています。

ケララ州では高速道路が建設中です。これが完成すれば、ムンバイまで1700キロの高速道路がつながるといいます。

昼はホテル内のレストランで。デザートつきの豪華版でしたが、このころから情けないことに、ぼくの胃腸がインド料理を受けつけなくなってきます。

本日の目的地アレッピには15時に到着。ところが、船着場までの道路が工事のため通行止めで、バスが立ち往生してしまいます。急きょ、リクシャーに乗り換えます。

ようやく午後4時すぎにバックウォーター(水郷)の船着場に到着しました。

このころ、ぼくはすっかり体調を崩し、ダウン状態です。ツアーの面々は3組に分かれて、それぞれハウスボートに乗り込みます。
ぼくも船に乗るものの、二人部屋の船室に閉じこもったままで、水郷の景色を楽しむどころではありませんでした。
そこで、つれあいの撮った写真で、いわゆるバックウォーターの風景を再現してみようというわけです。

せっかくのハイライトなのに、返す返すも残念です。

夕日が沈んでいきます。きょうはこの船のなかで1泊です。

モーニングコールがなく、6時にホテルのスタッフが「6時ですよ」と呼びにきました。しかし、なぜか6時半集合と思って、のんびりしていたのがまちがいのもとでした。6時半にロビーに行きますが、すでにだれもいません。どうやら集合時間は6時10分だったようです。
コモリン岬で朝日が昇るのを見ることになっています。6時半は日がのぼる時間でした。

あわてて砂浜にでて、海岸の展望台をめざしました。展望台にのぼると、戻ってくるツアーの一行と出会います。聞くと、この日はくもっていて6時半の朝日が見えなかったといいます。しかし、ふとふり返ると、雲のあいだから、朝日がのぼってくるのが見えたのです。
きょうもいい天気になりそうです。

食事をすませ、バスは8時の出発です。
すぐにのんびりした風景が広がって、何だかほっとします。はじめて出会う風景のはずなのに、昔どこかで見たような感覚に襲われるのがふしぎです。

まもなくケララ州にはいります。アラビア海に面したインド南西部の州で、ここではタミル語ではなくマラヤーラム語が話されているとか。
海岸沿いにはヤシの畑、東側には西ガーツ山脈の大きな山が連なります。

ケララにはいると英語表記が増え、教会も多くなります。ケララ州の人口は3500万人で、ヒンドゥー教徒が人口の30%、イスラム教徒が25%、キリスト教徒が20%を占めているといいます。
インドは貧困というイメージはもう過去のものといっていいのではないでしょうか。日曜のせいか、広場でクリケットをやっている人を多く見かけました。

トリヴァンドラムという大きな町にはいりました。ここはケララ州の州都で、かつてはトリヴァンドラム藩王国の都でした。

きょうはポンガルと呼ばれる大きな祭があるということで、インド各地から多くの人が集まってきています。バスや車も多い。マンションやショッピングモールも数多くつくられています。

ケララ州では高速道路が建設中です。これが完成すれば、ムンバイまで1700キロの高速道路がつながるといいます。

昼はホテル内のレストランで。デザートつきの豪華版でしたが、このころから情けないことに、ぼくの胃腸がインド料理を受けつけなくなってきます。

本日の目的地アレッピには15時に到着。ところが、船着場までの道路が工事のため通行止めで、バスが立ち往生してしまいます。急きょ、リクシャーに乗り換えます。

ようやく午後4時すぎにバックウォーター(水郷)の船着場に到着しました。

このころ、ぼくはすっかり体調を崩し、ダウン状態です。ツアーの面々は3組に分かれて、それぞれハウスボートに乗り込みます。
ぼくも船に乗るものの、二人部屋の船室に閉じこもったままで、水郷の景色を楽しむどころではありませんでした。
そこで、つれあいの撮った写真で、いわゆるバックウォーターの風景を再現してみようというわけです。

せっかくのハイライトなのに、返す返すも残念です。

夕日が沈んでいきます。きょうはこの船のなかで1泊です。

メンガー『一般理論経済学』を読む(2) [商品世界論ノート]

現代は欲望の時代だといってもよい。身分制と節欲の時代は、いつのまにか自由と欲望の時代へと転換した。
メンガーは経済活動の出発点を欲望においている。ここでいう欲望とは何かギラギラした強い望みを指すというより、むしろ「何々したい」という気持ちを意味している。人は生きているかぎり、何らかの欲望をもっているといえるだろう。
労働ではなく、欲望を出発点に置くのが、これまでとは異なるメンガー経済学の特徴である。
〈欲望はあらゆる人間経済の究極の根拠であり、欲望の満足がわれわれにとって持つ意義は人間経済にとっての究極の尺度であり、欲望の満足の確保は人間経済の究極の目標である。〉
人間は一定の条件のもとでしか生きることができない。そうした一定の条件を確保し、常に発生する障害を解消しながら、何とか生きていこうという意志をもちつづけるのが人間なのである。
障害や制止にともなう不快感や渇望、苦痛は、何らかの財によって解消され、解放され、沈静化され、快楽へと変わっていかなければならない。だが、その過程は「事情によってはまさしく矛盾だらけの、まちがいのもとになる表現」をとりかねないし、そこに葛藤も生じる、とメンガーは述べている。
人間の欲望には、時に誤謬や無知や激情がつきまとう。そのいっぽうで時に欲望を抑制しようというブレーキがはたらく。空想的で擬制的な欲望が生じることもある。とはいえ、欲望が人間の本性であることは疑いない、とメンガーは断言する。
すべての生物は欲望をもっているけれども、他の有機体と比べものにならないほど発達しているのが人間の欲望だ。とりわけ自己関心の度合いの強さに関しては、人間は他の動物と比較にならない。
個々人の欲望だけではなく、団体(国家や結社、企業)の欲望をもっているのも人間集団の特徴かもしれない。団体の欲望というには、たまたま個人が同じ欲望をもっていることを意味しない。それは集団としての共同の欲望にほかならない、とメンガーは論じている。
メンガーは欲望の発展を歴史的、文化的に追跡しているわけではない。とはいえ、商品世界の前提として、第一に主観的な欲望が存在することを、あたりまえのように指摘したのは、かれの業績といえるだろう。
欲望の対象を経済の次元にしぼるならば、それは財ということになるだろう。
「財は、人間の欲望を満足させるために役に立つと認められ、そしてこの目標のために支配可能な事物をいう」
つまり、財は事物からなり、モノだけではなくコトも含まれる。さらにメンガーはいう。
財は欲望を満たしうる性質と適性を有し、加えて人がそれを支配できる可能性をもたなければならない。そうした条件がなかったり、失われたりすれば、財としての性格は失われる。
逆に財として認識されていないけれども、効用を有するもの(たとえば空気)や、財としての潜在性(たとえば未知の資源や)を有するものも存在する。
私有財産制度のもとでは、権利や商標などもまた一種の財だ。
とはいえ、財はあくまでも主観的なものだメンガーは主張する。ある人にとって有用な財も、別の人にとっては無用なもの、あるいは有害なものでありうる。兵士にとって武器は有用かもしれないが、攻撃される側からすれば武器ほど有害なものはない。
〈したがって、われわれの手中にある諸財はそれぞれ特殊な関係をわれわれとの間にもっているのであって、それは一般の財としての性質とは区別しなければならないことは明らかである。各個人あるいは特定の人々にとっては、自分たちにたいして財としての性質を基礎づける関係にある物だけが財である。〉
このあたり、人間の主観的認識とそれにもとづく経済活動を重視するメンガーの考え方がうかがえる。
財の種類についても論じられている。
財が財となるには認識が決定的な契機になるというのがメンガーの考え方だ。
したがって、誤った認識が空想的あるいは擬制的な財をもたらす可能性もある。たとえばインチキな薬やあやしげな信仰物などもその例だ。
ただし、文明が発展すればするほど、擬制財は減り、真実財が増えてくるはずだという。
物質的な財だけではなく、非物質的な財も存在する。
「非物質的な財を無視したのでは、経済的現象の大部分はそもそも説明することができないし、まして完全な説明はなされえない」
そもそも財は身体的だけではなく、心的な欲望を満たすのにも役立つはずであって、その意味で、さまざまなサービスや演劇の舞台、音楽活動などの非物質的な財も人間の生活に欠かせない重要な財となるだろう。
財を消耗財と非消耗財に分けることも可能だ。食料品や飲料、さまざまな原料などは消耗財であり、ダイヤモンドや土地などは非消耗財である。機械や衣服、家具などをその中間の用役財に分類することもできる。
さらに財を分析するさいには、財の連関を認識しておく必要がある。
パンをつくるには小麦粉が必要だ。小麦粉のもとは小麦、そして、小麦をつくるには耕地や種子、農具、農作業が欠かせない。
ここで直接的な消費財を第1次財と呼ぶなら、その第1次財をつくるための第2次財、第3次財、さらに高次のn次財が必要になってくる。
高次の財が財となるのは、あくまでも低次の財を前提としている。経済が高度に発展している場合は、分業と交換にもとづいて、自分の製品を生みだすための補完財(高次財)はすぐに手にはいるのがふつうだ。
だが、財の連関が失われると、生産に大きな影響が生じる。実際にそうしたできごとが起きるのはまれではない。メンガーはそうした例として、アメリカの南北戦争で一時ヨーロッパに綿花がはいらなくなり、工場の操業がストップし、労働者の仕事が失われたことなどを挙げている。
また、直接消費財である第1次財が、人びとの嗜好の変化によって財としての性格を失うこともある。
たとえば、だれもたばこを吸わなくなったとすれば、どうだろう。そのことが高次財におよぼす影響は大きい。たばこの製造工場や設備、熟練労働者、たばこ農園等々へと影響は広がっていく。これは新聞や鉄道などとも無縁の話ではあるまい。
「ある低次財の財としての性質が消滅する場合には、同様の結果がそれに対応する高次財に関してもあらわれる」ということになる。
〈経済学者たちは、物が財であるのはそれが財から生産されているからであると考える傾向がある。しかしながら……実際にはまさしくその逆こそが真実である。すなわち生産物が財となるゆえに、諸財が生産のために用いられるのである。〉
生産のための生産は実際の消費によって裏切られることになる。
もちろん、高次の財によって低次の財が満たされるのが高度な文明社会の特徴だ、とメンガーは考えている。
ただし、高次の財から低次の財にいたるには、時間の経過が必要である。工業製品にしても、たちどころに作られるわけではない。
「高次財の支配とそれに対応する低次財の支配との間に横たわる期間は完全に消滅することはありえない」
そうしたことから、「高次財がその財としての性質を獲得し、またそれを主張するのは、直接の現在の欲望に関してではなく、ただ多少とも隔たった将来の欲望に関してにすぎない」という原理が導きだされる。
経済に時間性が生じるということは、経済が不確実性にさらされていることを意味している。
たとえば、一定の土地と種子、肥料、労働力、農具をもっていても、そこから毎年何トンかの小麦を生産できるとはかぎらないし、かならずそれがどこかに引き取られるともかぎらない。
こうした不確実性は、あらゆる生産に共通してつきまとう。
人間の経済には不確実性がつきものであり、そのことが経済にとっては大きな意味をもつことになる、とメンガーは述べている。
近代の経済社会は、不確実性に満ちた欲望と財の組み合わせの上に成り立っている。
われわれはスミスやマルクスとはまるでちがう経済学の世界と出会っているといえるだろう。
つづきはまた。
インド最南端コモリン岬へ──南インドお気楽ツアー(6) [旅]
2月24日(土)
8時20分にマドゥライのホテルを出発し、バスでインド最南端のカーニャクマリへ向かいます。6時間の長い移動になる予定です。
その前に腹ごしらえ。朝からちょっと食べ過ぎかもしれません。

ヴァイガイ川のほとりを走ります。牛をつれた男たちが手を振ってくれます。

15分ほど走ったところで、ガイドさんからマイクで「木村さん」と呼びかけられて、びっくりしました。
なんでも、ホテルから部屋に忘れ物があるという連絡がはいったとのこと。よく聞くと、つれあいのカメラ用充電器です。出るときに忘れ物がないよう気をつけたつもりなのに、コンセントにつけっぱなしにしたままでした。
ホテルに戻るわけにはいきません。いろいろやりとりして、コーチン空港に充電器を送りましょうという話になったので、ひと安心。ところがきょうは土曜、明日は日曜なので郵送ができないことがわかります。
諦めるしかないかと思ったところ、今度南インドに来る日本人のガイドさんがいるので、ホテルで引き取って、日本まで持って帰るよう手配しますとのこと。ガイドさんの親切さに感動しました。それから1カ月たったいま、忘れ物の充電器はまだ届いていませんが、善意を信じて待つことにしましょう。
バスは走りつづけます。郊外には大きな工場もできています。インドの経済発展はめざましいといえるでしょう。

次第に農村地帯へはいると、ヤシ林が多くなってきます。

道端にちいさなお堂があり、金色の神さまがすっくと立っていました。これはシヴァ神の息子で、人気のあるガネーシャですね。

途中、道端のレストランで昼食をとります。バナナの葉っぱの上にカレーで味つけした野菜やご飯、チャパティなどが並びます。

進行方向の右側に山脈が見えてきました。おそらく西ガーツ山脈の東側が見えているものと思われます。道路の両側にはバナナ畑やヤシの森が連なっています。

このあたり、電力発電用の風車が数多く立ち並んでいます。インド最南端へと向かう高速道路は整備され、バスも快調に飛ばします。

カーニャクマリのホテルに到着したのは午後2時でした。カーニャクマリの「クマリ」は女神クマリを指すそうです。ここにはクマリにちなんだ通称コモリン岬があります。
旅程表では夕方にコモリン岬を散策することになっていました。それまで少し時間があります。ホテルにプールがあったので、お調子者のぼくは少し泳がせてもらいました。

地図でみると、コモリン岬はベンガル湾とインド洋、アラビア海が合流する手展にあります。そのこと自体ロマンチックな思いをかきたてるのかもしれません。ヒンドゥー教徒にとって、ここは聖地になっており、大勢の人が巡礼に訪れるそうです。
じっさい、きょうは土曜日ということもあって、学校の生徒を含め、じつに多くの人がやってきています。海岸沿いに店も立ち並んでいて、観光地といえば観光地なのですが。

写真はガンディ記念堂です。マハトマ・ガンディの遺灰の一部は、ここコモリン岬から海に流されました。それを記念してつくられたのが、この建物です。

われわれもインド最南端までやってきた記念に写真を撮らせてもらいます。向こうの岩に立つのは古代タミルの詩人、ティルヴァッルヴァルの像。さらにその向こうにヴィヴェカーナンダ岩と記念堂があります。

夕方、沈む夕日を見に西のサンセットポイントに行きました。

ここにもアラビア海に沈む夕陽を見るため、大勢の人が集まっていました。

8時20分にマドゥライのホテルを出発し、バスでインド最南端のカーニャクマリへ向かいます。6時間の長い移動になる予定です。
その前に腹ごしらえ。朝からちょっと食べ過ぎかもしれません。

ヴァイガイ川のほとりを走ります。牛をつれた男たちが手を振ってくれます。
15分ほど走ったところで、ガイドさんからマイクで「木村さん」と呼びかけられて、びっくりしました。
なんでも、ホテルから部屋に忘れ物があるという連絡がはいったとのこと。よく聞くと、つれあいのカメラ用充電器です。出るときに忘れ物がないよう気をつけたつもりなのに、コンセントにつけっぱなしにしたままでした。
ホテルに戻るわけにはいきません。いろいろやりとりして、コーチン空港に充電器を送りましょうという話になったので、ひと安心。ところがきょうは土曜、明日は日曜なので郵送ができないことがわかります。
諦めるしかないかと思ったところ、今度南インドに来る日本人のガイドさんがいるので、ホテルで引き取って、日本まで持って帰るよう手配しますとのこと。ガイドさんの親切さに感動しました。それから1カ月たったいま、忘れ物の充電器はまだ届いていませんが、善意を信じて待つことにしましょう。
バスは走りつづけます。郊外には大きな工場もできています。インドの経済発展はめざましいといえるでしょう。
次第に農村地帯へはいると、ヤシ林が多くなってきます。

道端にちいさなお堂があり、金色の神さまがすっくと立っていました。これはシヴァ神の息子で、人気のあるガネーシャですね。
途中、道端のレストランで昼食をとります。バナナの葉っぱの上にカレーで味つけした野菜やご飯、チャパティなどが並びます。

進行方向の右側に山脈が見えてきました。おそらく西ガーツ山脈の東側が見えているものと思われます。道路の両側にはバナナ畑やヤシの森が連なっています。
このあたり、電力発電用の風車が数多く立ち並んでいます。インド最南端へと向かう高速道路は整備され、バスも快調に飛ばします。

カーニャクマリのホテルに到着したのは午後2時でした。カーニャクマリの「クマリ」は女神クマリを指すそうです。ここにはクマリにちなんだ通称コモリン岬があります。
旅程表では夕方にコモリン岬を散策することになっていました。それまで少し時間があります。ホテルにプールがあったので、お調子者のぼくは少し泳がせてもらいました。

地図でみると、コモリン岬はベンガル湾とインド洋、アラビア海が合流する手展にあります。そのこと自体ロマンチックな思いをかきたてるのかもしれません。ヒンドゥー教徒にとって、ここは聖地になっており、大勢の人が巡礼に訪れるそうです。
じっさい、きょうは土曜日ということもあって、学校の生徒を含め、じつに多くの人がやってきています。海岸沿いに店も立ち並んでいて、観光地といえば観光地なのですが。

写真はガンディ記念堂です。マハトマ・ガンディの遺灰の一部は、ここコモリン岬から海に流されました。それを記念してつくられたのが、この建物です。

われわれもインド最南端までやってきた記念に写真を撮らせてもらいます。向こうの岩に立つのは古代タミルの詩人、ティルヴァッルヴァルの像。さらにその向こうにヴィヴェカーナンダ岩と記念堂があります。

夕方、沈む夕日を見に西のサンセットポイントに行きました。

ここにもアラビア海に沈む夕陽を見るため、大勢の人が集まっていました。

前の10件 | -



