『グローバル経済の誕生』を読む(2)──商品世界ファイル(32) [商品世界ファイル]
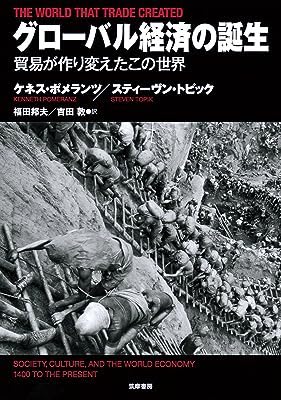
もともとはローカルな産品が、世界商品に変わることがあります。われわれにとって、ごくあたりまえの商品ですが、それらが世界に広がるにはさまざまな経緯がありました。本書では、売られている商品の姿からはなかなか見えなてこない裏の事情も明らかにされています。
1500年にブラジルにやってきたポルトガル人は、「赤い木」すなわちブラジルウッド(パウ・ブラジル)を伐採し尽くしました。ブラジルウッドからは、それまでにない赤の染料が抽出されたのです。その間、先住民の人口は、奴隷狩りと病原菌によって激減していきました。赤い染料のためなら、どんなことでもやったという様子がうかがえます。
1700年になると、ポルトガル人はブラジルで砂糖栽培をはじめます。アフリカから大量の奴隷がつれてこられました。ブタやウシ、ヒツジなどの家畜も持ちこまれました。コーヒーの木を植えたのもヨーロッパ人です。鉄道が発達すると、プランテーション経営者は、荒れた土地を捨てて、さらに奥にはいりこみ、森林を伐採しました。その結果、ブラジルの森林は激減したのです。
ゴムの木はもともと中南米にしか自生していませんでした。1876年、その種子をイギリス人が持ち帰り、キューガーデン(王立植物園)で栽培し、それがマレー半島などに移植されたのが、東南アジアでのゴム栽培のはじまりです。その後、オランダ領東インド(現インドネシア)でもゴムが栽培されるするようになります。
ゴムの需要が急速に増大したのは1820年代から30年代にかけて、マッキントッシュやグッドイヤーが、ゴムの加工技術を開発したからです。ゴムはレインコートや長靴、自転車タイヤ、さらに20世紀にはいってからは自動車タイヤに用いられるようになります。ゴムの樹液を採集するのは、たいへんな作業でした。「ゴム採取の歴史は、人間の屍のうえに築かれていったようなものだ」と著者は書いています。ゴム成金はその屍のうえに生まれたといってよいでしょう。
イギリスに対抗して1930年代にはドイツが合成ゴムの開発に成功しました。それにより、ブラジルでもマレーシアでも天然ゴム産業は壊滅的な打撃を受けます。しかし、航空機のタイヤや戦車のキャタピラ、トラックのタイヤなどは、やはり天然ゴムでないと具合が悪いといいます。現在でも天然ゴムが世界のゴム生産シェアの約3分の1を占めつづけているのもそのためです。
カリフォルニアで金が発見されたのは1848年のことです。以来、12年のうちに、それまでの150年間で採掘された金と同量の金が採掘されました。これにより世界の硬貨の中心が、銀貨から金貨へと移ったというのですから、カリフォルニアの金がもたらした影響がいかに大きかったかがわかります。
カリフォルニアの人口は急速に拡大し、大陸横断鉄道の建設が進められ、海上輸送路も整備されていきました。その間、多くの先住民が殺され、排除されました。ゴールドラッシュは、米国が大西洋と太平洋にまたがる大国へと発展する道を開いたといえるでしょう。
フランドル織のみごとなタペストリーは、みごとな深紅色でいろどられています。じつは、それが中央アメリカのカイガラムシを原料にしていることを知る人は少ないのではないでしょうか。カイガラムシのメスからは、コチニールという染料がとれます。ヨーロッパ人は先住民にカイガラムシを飼育させ、手間のかかる染料をつくらせて、それで鮮やかな織物の模様を浮かびあがらせたのです。ところが1950年代になると、化学染料のアニリンが開発されます。カイガラムシからつくられるコチニール染料は、たちまち忘れ去られていきます。
インカの人びとは古くから、グアノと呼ばれる海鳥のフンを肥料として利用していました。ヨーロッパ人は1830年代になってこのグアノに着目します。そしてこのグアノを船でヨーロッパに運び、肥料としました。いっぽうペルー政府はグアノを担保にして、ヨーロッパから資金を借り入れ、それで鉄道を建設しようとしましたが、大失敗します。化学肥料が出現すると、グアノの夢もたちまちしぼみ、ペルーには膨大な債務だけが残されました。
毛皮もまた世界商品のひとつでした。毛皮を捕ったのは、おもにロシア人で、「カムチャツカ半島やアリューシャン列島、のちにはアラスカまで遠征して、カワウソやラッコを次々に狩猟していった」。その結果、乱獲によって多くの野生動物が絶滅の危機においやられたことは周知の事実です。
ジャガイモ、トウモロコシ、タバコ、ピーナツもアメリカからもたらされました。ジャガイモはスペイン人がフィリピンに運び、まずアジアに広がって、それからヨーロッパに逆流したといわれます。1600年以降、ヨーロッパでは人口の急増により食料危機が生じていました。ジャガイモを最初に主食としたのはアイルランドです。イングランドでも1700年ごろからジャガイモが生産され、次第に労働者用の補助食料となっていきます。プロイセンでも、フリードリヒ大王がジャガイモの食用化を推し進めたことはよく知られています。
ピーナツは砂まじりの土壌で育つために、劣化した土地でも栽培が可能でした。その蔓(つる)は家畜の飼料に、殻(から)は燃料に、実は食料や油として利用できるというすぐれた特性をもっています。ピーナツが注目されたのは1900年になってからで、潤滑油や塗料、石鹸の原料として用いられました。こうして中国、インド、西アフリカでもピーナツがつくられるようになります。しかし、1940年になると、化学合成物が開発されて、工業原料としてのピーナツは忘れられていきます。
ハワイ王国を滅亡に追いこんだのはヨーロッパ人でした。1876年以降、ハワイでは、アメリカ人のつくった砂糖プランテーションが急速に拡大していきました。そして、この砂糖の特権を守るために、クーデターが画策され、王制が崩壊、これによってハワイはアメリカに併合されていくことになります。
台湾で砂糖が増産されたのは、台湾が日本の植民地下にはいってからです。とはいえ、台湾が砂糖栽培に依存するモノカルチャー経済に陥ってしまうことはありませんでした。その危険性があったとしたら、むしろ1600年代のオランダ統治時代だった、と著者は指摘しています。オランダの統治は鄭成功により排除されました。
アルゼンチンにやってきたスペイン人は、広大なパンパに家畜を放ちました。その家畜が繁殖して、アルゼンチンでは牧畜が盛んになります。その後、アルゼンチンは世界最大の牛肉輸出国へと成長しますが、それを支えたのは、輸送技術の革新や冷凍技術の進展です。しかし、牛が経済的に飼育されるにつれて、かつてのカウボーイ、すなわち誇り高きガウチョが、次第に最下層の使用人へと転じていくという悲しい歴史もありました。「家畜の牛がカウボーイを駆逐した」のです。
アメリカ西部の大平原は、小麦生産の最適地でした。そのことにヨーロッパからの移民はすぐに気づきます。労働力の不足は、機械の導入によって克服されました。鉄道や運河もつくられ、穀物市場は東部ばかりか海外にまで広がっていきます。1878年には小麦の刈り取りと結束を同時におこなうバインダーが開発されました。しかし、バインダーに必要な小麦用の麻ヒモをつくらされていたのは、ユカタン半島に住む数万ものマヤ人でした。
このように並べただけでも、商品生産をめぐるドラマには、表からではみえないおどろくべき展開が隠されていることがわかります。ゴムや綿花のような原料にせよ、ジャガイモや小麦のような食料にせよ、あるいは牛のような家畜にせよ、もともとは限られた地域の産物が、資本の都合にあわせ世界中に適地を求めて生産されていったのです。それによって現地の環境は変えられ、人びとが思うがままに使役されたありさまは、すざまじいとしかいいようがありません。
こうした動きは、経済学の知識だけでは、なかなかつかみがたいものです。いや、むしろ経済学は、背後の歴史的真実を隠蔽することで成り立っているのではないかと思えるくらいです。
経済は平和的な商業活動と思われがちですが、「このような見方は、ヨーロッパ以外の世界でおこなわれてきた絶え間ない略奪や暴力という動かしがたい歴史的事実を覆い隠してしまう」と著者はいいます。グローバル経済は暴力を抜きにしては語れないのです。
ヨーロッパの繁栄を支えたのはアフリカ人奴隷と海賊でした。戦争もまた富の蓄積手段であり、さまざまな新商品もまた戦争を通じて生まれたのです。
アメリカは移民の国だといわれますが、1800年以前の移民は、4人に3人が強制的にアフリカからつれてこられたと著者は指摘しています。その数は1000万〜1500万にのぼります。そのうち3年以上生きられたのは、わずか3割だったといいます。航海の途中で死ぬ奴隷が多かったのです。
それではなぜ、わざわざアフリカ人をアメリカに連れてこなければならなかったのでしょう。じつは、スペイン人がアメリカに到着してから、先住民はヨーロッパ人の持ちこんだ天然痘(てんねんとう)や麻疹(ましん)によって、その9割が死滅してしまったのです。そこで、ヨーロッパ人はアメリカで働かせるために、アフリカ人を奴隷としてつれてくるほかありませんでした。
アフリカ人奴隷は鉱山労働者として、あるいは砂糖、綿花、タバコ、コーヒーなどを栽培する農場の労働者として酷使されました。
イギリスがスペインの海軍力をそぐために海賊の力を活用したことはよく知られています。「スペインやポルトガルの植民地帝国が衰退したのは……イギリスやオランダの海賊による略奪行為こそが決定的な役割を果たした」とまで、著者は述べています。海賊たちは香辛料、金銀、毛皮、高級織物、さらには奴隷や砂糖といった贅沢品(ぜいたくひん)を積んだ船をねらいました。オランダやイギリスの武装商船もまた、平気でスペインやポルトガルの商船を襲っています。宗教対立(プロテスタントとカトリックの対立)は、いかなる非道をも正当化したようです。
そして、スペイン海軍の力が衰えてくると、いよいよイギリスの海軍力が強大になり、「地球上のいかなる海域においても略奪行為を根絶することに心血を注ぐようになる」。ここにも正義は力なりの見本があります。
ポルトガルに代わって、世界最大の奴隷貿易国になったのがオランダだったことも、あまり知られていません。16世紀にポルトガルは西アフリカの奴隷とブラジルの砂糖を独占していましたが、オランダは何とかしてその一角に食いこもうとします。しかし、ブラジルの攻略には失敗しました。
そこで、オランダはポルトガルを出し抜くため「アフリカの沿岸地域で次々と奴隷貿易の輸出港を建設し、人間を家畜のようにカリブ海に浮かぶフランスやイギリスの植民地に輸送し始めた」といいます。こうしてカリブ海の島々で砂糖が生産されるようになると、ブラジルでポルトガルが独占していた砂糖生産も切り崩されていきます。一時、オランダが世界経済のヘゲモニーを握った裏には、このように血塗られた歴史があります。
くり返しになりますが、「戦争と経済」で思い浮かべるのは、アヘン戦争のことです。アヘン戦争は、清朝がアヘン貿易を禁止したのにたいし、イギリス海軍が攻撃を開始したことに端を発します。しかし、そもそもイギリスがインドのアヘンを中国に輸出したのは、中国の茶にたいする銀貨の支払いが膨大な額にのぼったからです。これもまた、ほめられた歴史ではありません。
イギリスとオランダの東インド会社は、これまでにない特色を備えていました。それは両方とも株式会社だったことで、出資者の匿名性が高く、また経営権と所有権とが分離しており、永続する法人であることが前提になっていました。
それまで会社といえば家族経営が中心で、海外貿易会社への出資はその都度、清算されるのが原則でした。著者は東インド会社などの株式会社が永続しなければならない理由は「暴力」にあったと断言します。植民地に要塞を築き、海上の覇権を築くには、莫大なコストを要しました。
18世紀にはいると、東インド会社は武装コストにたえられなくなります。いっぽう、そのすき間を縫って密輸業者が横行し、独占体制を崩していきます。植民地経営はこうして政府の手にゆだねられ、会社は資本中心の企業へと変わっていくわけですが、企業もまた国家によって守られているという意味で、それ自体潜在的な暴力性を含んでいたといってよいでしょう。
現在の企業乗っ取りは海賊と同じだといわれますが、16世紀から18世紀にかけての海賊はむしろ「厳格なモラルに基づいて経済活動をおこなっていた」と著者は指摘します。ホーキンズやドレークには、政府から私掠船の許可証が発行されていました。17世紀には、無国籍の浮浪者からなるバッカニアと呼ばれる海賊が登場します。かれらはスペインの港や船を攻撃し、商品を略奪しました。しかし、海賊には掟(おきて)があり、略奪品を盗むことは禁じられ、無用な殺戮(さつりく)はおこないませんでした。仲間どうしの生命保険や傷害保険もあったといいます。
イギリスでは1834年に、アメリカでは1865年に、そしてそれ以降、世界のいたるところで奴隷制が廃止されました。しかし、奴隷制が廃止されても過酷な強制労働がなくなったわけではありません。見習い労働や年季契約労働が、労働コストを下げる新たな手段として導入されました。奴隷は自分たちの置かれた環境から逃げだすためには、どんな条件でも受け入れました。それが自由契約にもとづく低賃金労働でした。
奴隷制はいずれ廃止される運命にありましたが、それは経営者側に「自由な契約による賃金労働のほうが、より大きな利益をもたらす」という確信があったからです。ちょっと言い過ぎかもしれませんが、企業にしばられるという意味では、いまでも労働者は会社の奴隷であることにちがいはないでしょう。
著者は象牙のたどった道をふり返ってもいます。ビリヤードの球やピアノの鍵盤、ナイフの柄(え)、チェスの駒など製品となった象牙には優雅さがただよいますが、そこに何十万頭の象が犠牲になっている光景を思い浮かべる人は少ないでしょう。
ヨーロッパで奴隷解放運動が広がるさなか、ベルギーのレオポルド2世(1835〜1909)がコンゴを手中におさめ自身の私領としました。かれはコンゴの手つかずの森に大量の象がいることに気づき、象牙を手にいれようとします。多くの黒人が虐殺され、大量の象が殺害されました。「ベルギー人は、コンゴの先住民を奴隷にし、資源を強奪して、ビリヤードの球やピアノの鍵盤の材料を求めた」のです。象牙は象への暴力によって、はじめて成り立つ商品でした。レオポルド2世は、また先住民の土地を奪って、そこに広大なゴム・プランテーションを開いたことでも知られます。そして、その私兵は、労働を拒否する黒人の手首を容赦なく切り落としました。そんなばかなと思われるかもしれませんが、これは事実です。
残念ながら、この世には本源的に暴力性を秘めた、政治の力、経済の力が、いまでも満ち満ちているといわねばなりません。
グローバルな市場社会はいつつくられたのでしょう。それは、つい200年ほど前のことではないか、と著者は考えています。産業革命以降と考えていることがわかります。
最初は物々交換でした。そして次第に金銀が価値のシンボルとなります。世界的に銀が貨幣として使用されるようになったのは、メキシコとペルーで銀の大鉱脈が発見されたからであり、それからカリフォルニアやオーストラリア、南アフリカなどで豊富な金が発見されたことにより、世界は金本位制のもとに統合されていきます。そして市場で商品の価値が決められるようになると、商品の規格化、運輸革命、時間の標準化、先物市場、法律の整備、債券市場、品質管理、登録商標、知的所有権、大量の広告などといった現象が次々と生じていきました。
著者はこう書いている。
〈結局、世界貿易と商品化のプロセスが拡大するにつれて、多くの人々は、自分が欲しいものは何でも手に入れられるようになった。つまり世界中どこのモノでも意のままになると考えるようになった。どんなモノでもお金があれば手に入れることができるようになったので、多くの人々は、世界は人間のニーズと欲望を満たすためにあるのだと考えるようになってしまった。「自然」を「天然資源」や「生産要因」に置き換えて、人間にとって便利で、しかも利益を生み出すものに変えるために全力が傾注されるようになったのである。〉
これはハッピーな世界なのか。いやクレージーな世界ではないのか、というのが著者の問いかけです。
メキシコ銀貨ペソは16世紀から17世紀にかけて、世界通貨の役割を果たしていました。ペソはアメリカとヨーロッパを結びつけただけではなく、ヨーロッパとアジアを結びつけていたのです。ヨーロッパ人はアジアから香辛料とシルクを手に入れ、銀をその代価としました。しかし、19世紀にはいりゴールドラッシュがはじまると、金の供給量が増大するいっぽうで、銀の需要と価格は下落して、世界の基軸通貨が次第に金へと移行していきます。とはいえ、19世紀になるまで、貨幣は人びとの生活に浸透していたわけではありませんでした。
度量衡が統一されるのは、18世紀末のフランス革命以降です。メートル法が導入されます。それまでは人体が尺度の基準であり、地方ごとにさまざまの測量単位がありました。しかし、商品化が進むにつれて、度量衡の統一や商品の規格化が求められるようになります。つまり財が「抽象化」されて、「計測可能で均質的な商品」が生産され、世界じゅうで商品として売ることが可能になったのです。
ヨーロッパで国際的な小麦市場が生まれたのは19世紀中ごろでした。このころ輸送革命によって、アメリカの小麦はヨーロッパに運ばれていました。米の場合は小麦よりもさらに貯蔵や搬送が容易でしたが、米の銘柄は多く、その貿易は消費者の好みに応じて、狭い範囲にとどまっていました。
時刻が均一化されたのは、19世紀半ばになってからで、それまでそれぞれの国や地方はそれぞれの時刻をもっていました。イギリスが標準時をグリニッジ時間にあわせたのは1842年になってからで、鉄道の時刻表を定めるためだったといいます。これにたいし、アメリカは時刻の標準化が遅れ、ようやく1918年になって国内を4つの時間帯に分割することがきまりました。世界は次第に24の時間帯に分割されていきますが、その決定は合理的というより帝国主義国の都合次第だったといわれます。
商品世界の特徴は、消費者が顔見知りの隣近所よりも、見も知らぬ遠方の業者に信用をおくようになったことだと著者は皮肉たっぷりに書いています。遠方でつくられた食料が食べられるようになったのは、運輸の発達に加えて、缶詰めや真空パック、冷凍などの技術が発達し、それに応じて各家庭が冷蔵庫をもつようになったからです。
「2000年前の世界では遠くにあったモノが今の世界では近くなり、近くにあったモノが遠くに立ち去った」。こうして「地域の食料品店や雑貨店は、巨大かつ人間不在の、しかし安価な商品を販売するスーパーマーケットによって消し去られた」というわけです。
包装革命もまた現在の特徴です。ガラス瓶やブリキ缶、紙袋、段ボール箱がつくられたのは19世紀。20世紀になると、プラスチック革命がおこり、いまではどの食品コーナーでもラップやトレーがあふれかえっています。包装は単に中身を保護するだけではなく、ブランドのイメージにつながっています。「包装は近代大衆社会の鍵を握っている」
登録商標と法人の発生は密接に結びついています。市場においては生産者と消費者のあいだで、直接的な人と人との関係は失われます。商品の品質もまた標準化されていきました。「中身を確認するためには、包装紙に書いてある情報や、とりわけ企業名を信頼する以外に方法がなくなった」のです。
登録商標の保護がなされるようになったのは、19世紀半ばからです。以来、企業にとって、ブランド名が大きな財産となりました。「宣伝・広告の目的は、消費者に製品の使用法や原材料について伝えることではなく、商品を差別化し、商品の品質とは無関係にイメージを消費者に植え付けることである」。これもまた商品世界のマジックかもしれません。
コカコーラのように、いわばアメリカのイメージと結びついたブランドもあります。ヨーロッパに進出するにあたって、「コカコーラ社は『アメリカの生活様式』と、大戦で勝利した『アメリカ』を全面に出すことで大成功を収めた」と著者は書いています。
100年前、石鹸はさほど必要なものとは思われていませんでした。ところがいまではからだを石鹸で洗わないと不潔だと感じられます。石鹸の登場によって、清潔への強迫観念が生まれたのです。これも、ひとつの商品がライフスタイルを変えてしまう一例でしょう。
学校では、石鹸で頻繁に手を洗うことがいわば義務となり、家庭でもだれもが口臭を気にするようになって、しきりに歯磨きをしたり、マウスウォッシュを使ったりします。そして、われわれがいかに汚ないか、いかに世間から遅れているかを意識にすりこませる大量広告(マーケティング戦略)が、消費者に商品の購入を促していきます。これはどの商品についてもいえることでしょう。
商品の発明と普及には、さまざまな偶然や社会的要因がはたらく場合があります。たとえば鉄道の線路幅は、ほんとうならもっと広くすべきだったのに、馬車の軌道にあわせてつくられたため、現在のような狭軌になり、軌道の幅をいまさら変えられなくなってしまったといいます。
缶詰の話もおもしろい。もともと軍事用食料として作られた缶詰を開けるには、最初ナイフやハンマーが用いられていました。缶切りが発明されるのは1870年、主婦が缶詰を利用するようになってからです。缶切りは最初なかったのです。いまではほとんどイージー・オープンエンドが採用されています。
食洗機はすでに1880年代に考案されていましたが、1950年代になるまであまり利用されることはありませんでした。女性が外で働くようになったことが、食器洗い機の普及を促したといわれます。
ピレネー山脈の中腹にあるアンドラ公国がインターネットと税制(関税なし、所得税なし)だけで、富裕国になるという奇妙な話も紹介されています。「投票権を持たず、ここに住んでいない4分の3の住民は、アンドラの空気が澄みきっているからではなく脱税のためにここに住民票を置いているのだ」。タックスへイヴンもまた、現代の資本蓄積がもたらした現象かもしれません。
われわれは世界で最初に近代工場が生まれたのはイギリスだと思いこんでいます。しかし、それはまちがいだと著者は述べています。近代工場が生まれたのは、新大陸の植民地で、それは砂糖工場でした。
砂糖の生産には迅速さが求められます。その作業は何百人もの奴隷と労働者を必要としました。「ヨーロッパ人は、多額の資金を投じて工場を建設し、大量の奴隷を朝から晩まで酷使して、自分たちの飽くなき欲求を満たそうとした」。その結果、砂糖はヨーロッパや北アメリカで大量に出回るようになり、だれでも手にいれられる気軽な商品となっていきます。
ところで、産業革命の中心は綿工業にあるといわれながら、その原料である綿については、これまであまり論じられることはありませんでした。もともと綿の栽培と加工が発達していたのは、インドや中国です。どの階層でも木綿の衣服はごく一般的に用いられました。日本で木綿が普及するのは17世紀の元禄時代以降ですが、インドや中国はそれに先行していました。
ヨーロッパでは18世紀なかばでも、麻や羊毛が衣服の中心でした。イギリス人は毛織物をアジア各地に売りこもうとして、失敗しています。
17世紀から18世紀にかけて、インド産の綿織物は最高級品で、モルッカ諸島の香辛料やアフリカの奴隷を手に入れるさいにも、こうしたインド産綿織物が代価として珍重されていました。17世紀には「インド製品のシェアは、世界の衣服市場の約25%を占めるまでに達していた」。これほど優勢を誇っていたインドの繊維産業が衰退するのは、イギリスがインド製品をまねて、産業革命によって綿製品をつくりだすようになったためです。そしてベンガルを支配したイギリスの東インド会社は、インドの繊維産業をつぶしていきます。
しかし、綿製品の材料となる綿花はヨーロッパではできないため、新大陸で栽培せざるをえなかったのです。そのために投入されたのがアフリカ人奴隷でした。
1861年に南北戦争が起こると、綿花の供給が不安定になってきます。それ以前から、イギリスはアメリカ以外の供給地を見つけるため、まずインドに、次にエジプトに目をつけ、綿花の栽培を推し進めていました。しかし、インドやエジプトの綿花は量的にも価格的にも、アメリカの綿花にはかなわなかったのです。
トマス・エジソンが発電機をつくったのは1880年のこと、それ以降ニューヨークでもカリフォルニアでも、まっ暗な街並みが明るくなりました。これはまさに文明の恩恵でした。とはいえ、電線の材料には銅が必要になってきます。バハ・カリフォルニアにはボレオ銅鉱山がありました。ここに急遽(きゅうきょ)、メキシコじゅうの労働者が集められます。その労働は12時間交代制で過酷なものでした。明るい電気をもたらした銅線の背後には、メキシコ人労働者の血と汗があったのです。
20世紀の工業化を支えたのは、何といっても石油でした。石油は最初は照明や暖房、建築資材や潤滑油として用いられていました。しかし、次第にエンジンの動力、プラスチックや化学肥料の原料、あるいは電力を生みだす源としても使われるようになり、一挙に用途が広がっていきました。
最初、大規模に石油が発掘されたのはアメリカです。ロックフェラーをはじめとするさまざまな石油王が登場し、産業界に君臨します。メキシコでも欧米の資本によりタンピコ油田が開発されました。ところがメキシコでは利益を独り占めする石油会社にたいし、民衆のナショナリズムが高揚し、メキシコ政府はついにメキシコ石油会社の設立を宣言します。メキシコから締めだされた欧米の石油会社が次に向かった先はベネズエラでした。しかし、ベネズエラもついに1976年に石油産業の国営化を発表します。このように石油の奪い合いをめぐる歴史は変転きわまりないのですが、世界貿易の中心がいまも石油であることはまちがいないと著者は述べています。
「19世紀を代表したものが、石炭、鉄道、蒸気船だとすれば、20世紀を代表するものは石油、自動車、飛行機だろう」。その石油によってつくられた国家がサウジアラビアです。1902年、イブン・サウードはリヤドを奪還しました。第1次世界大戦では、イギリスに協力して力を蓄え、その後、ラシード家やハーシム家を滅ぼして、サウジアラビア王国を建国します。しかし、その王国は不安定で、いつ倒れてもおかしくない状況にありました。その危機を救ったのが石油でした。
サウジアラビアで石油の生産がはじまったのは1938年、その採掘権を得たアメリカは王国の保護に回ります。そして、1973年の石油危機以降、サウジアラビア経済は膨張し、政府は大衆迎合的な政策を打ちだすようになります。石油産業も国有化されました。これからこの国がどのように歩んでいくかに注目しなければならない、と著者は結んでいます。
著者はこの500年のグローバル化をふり返って、その間、いったい何が起こったのかと問うています。
世界の人口が10億人を突破したのは1800年のことです。世界の人口は「それから120年後の1920年には20億人になり、70年後の1990年には60億人」を突破しました。人間の平均寿命もこの100年のうちに倍になったといわれます。
これだけ人間が増えたということは、医療の発達もさることながら、人が生きていくのに必要な食料がつくられたということを意味します。世界中で穀物や商品作物をつくる農場が開発され、そこで増産された食料が交易を通じて各国、各地域に運ばれていきました。その分、地球上の森林は、相当な部分が農地に変わったということです。
もうひとつ著者は「人がはじめてこの地球上に現れてから、この地球上にある全エネルギーの半分以上が1900年以降に使用された」とも指摘しています。また「人間は地上のすべての創造物[動物]と植物を支配下に置こうとしている」とも述べています。さらに「この地球は、穏やかな庭園や原野に覆われるのではなく、巨大な市場になってしまった」とも。
たしかに人類が増えつづけ、いまや70億人に達したといわれる人口を支えるには、膨大な食料と資源を必要としていることはたしかです。グローバル経済は、けっきょくこの食料と資源の確保に明け暮れたといってよいのではないでしょうか。
さらにもうひとつの問題。それは70億人もの人が平等に豊かに暮らしているわけではなく、世界の貧富の差がますます大きくなっていることです。いまでは「最も豊かな人々と最も貧しい人々との所得格差は、天文学的な数字に達している」のです。ビル・ゲイツの所得は、最も貧しい人1億人分に相当するという指摘には、驚きだけではなく、不条理さえ感じます。
「ほんのわずかな人間が、かくも多数の人々を支配した時代はこれまでなかった」と著者は書いていますが、これはビル・ゲイツにかぎらず、石油、エレクトロニクス、航空機、自動車、金融、保険などを掌握するかぎられた企業が、いかに世界を牛耳っているかを示しています。
そして、いまは消費時代となりました。ローンやクレジットなど、簡単に借金ができる仕組みも生まれ、「買うのはいまでしょう」と消費を促します。さらに次々と新たな商品が生みだされ、その広告をみているうちに、それをもたない人びとは自分が時代に取り残されているような「不満足感」あるいは「欠乏感」を味わうようになっています。
中国もあっというまに消費社会に突入しました。中国では「今では人民に奉仕するのではなくお客様に対して明るく親切に対応する人間像が求められている」といいます。中国の発展はたしかに目覚ましいものがあります。それは中国がグローバル化の波に乗ったからです。世界の最貧困者は過去25年のうちに3億5000万人減少したといわれますが、それは中国の発展がもたらしたひとつの成果だといえるでしょう。
グローバル化への反乱はまだ起きていないと著者はいいます。たしかにいま世界は平和とはいえない状態にあります。2001年の9・11事件以降、世界は揺れつづけています。しかし、グローバル化に代わる新たな導きの糸を見つけるところまで、世界はまだ立ちいたっていません。
最後に著者が懸念をいだいているのは、地球の将来についてです。地球温暖化はどのような結末をもたらすのか。石油などの有限な資源をこのまま使いつづければ、そのあとはいったいどうなるのだろう。水不足も深刻な問題となりつつあります。
著者はいいます。
「近代文明は、膨大なエネルギーを使って自然に代わるすべてのモノを発見したのだが、いまやエネルギーを使用することによって、自然と、人間がつくった生きるための空間の双方が危機にさらされているということに気がつきはじめたのだ」
現在が隠されていた真実を見つめなおし、そこから新たに出発しなおす時期にきていることはまちがいないでしょう。
2023-09-08 09:20
nice!(11)
コメント(1)




とても長かったけれど、興味深く最後まで読ませて頂きました。
グローバル化(Globalization)が限界に来ているとなれば、人間は(敢えて『人類は』とは書きません)『宇宙化(Cosmization)』を目論むようになるでしょう。しかしそれは限られた人間のみ可能な夢であり欲望です。
そしてそれは、イーロン・マスクのSpaceXの成功例を見るまでもなく、もう始まっているように思えてなりません。
唐突ではありますが、あのアニメの『ガンダム・水星の魔女』のような世界観、あるいは宇宙観が現実のものとなると私は考えています。
「持てる者」と「持たざる者」、つまり「スペーシアン」と「アーシアン」の対立というような構図が、(人類がもしその時まで生き延びられていたとしたら、という前提ではありますが)あと数世紀の間に、現実に起きるような気がしてなりません。
長文コメント失礼しました。
by U3 (2023-09-09 07:57)