ポール・ジョンソン『現代史』をめぐって(1)──大世紀末パレード(8) [大世紀末パレード]
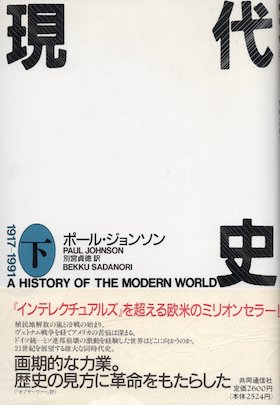
ここで、方向を変えて、1980年代を鳥瞰してみることにする。ぼく自身が編集を担当したポール・ジョンソン(1928〜2023)の『現代史』(別宮貞徳訳)を紹介してみたい。著者はイギリスの保守派で毒舌の歴史家、ジャーナリスト、評論家として知られる。
原著はもともと1983年に出されたものだった。その原著に、日本語版のためにぼくが依頼して、ソ連崩壊までの章を書き下ろしてもらった。翻訳され、日本で発行されたのは1992年のことだ。その最終章は「自由の復権」と名づけられ、こんなふうにはじまっている。
〈1980年代は現代史の分岐点の一つである。民主主義は自信を取り戻し広がった。法の支配が地球上広範囲に確立され、国際的な略奪行為は阻止され処罰を受ける。国際連合、とくに安全保障理事会は、はじめてその創立者の意図に沿って機能しはじめるようになった。資本主義経済は力強く繁栄し、市場経済こそ富を増し生活水準を向上させるためのもっとも確実な、また唯一の道であるという認識があらゆるところで定着していった。知的な綱領としての集産主義は崩れ去り、それを放棄する動きがその拠点においてさえ始まった。最後の植民地コングロマリット、スターリンの帝国は解体される。ソヴィエト体制そのものが歪みを増し、諸問題が幾重にもかさなって、超大国としての地位も危うくなれば冷戦の継続を望む意志も衰えを見せた。1990年代のはじめにはもはや核戦争の悪夢は薄れ、世界はより安全に、安定度を加え、そしてなによりも希望に満ちてきた。〉
いま思えば、スターリンの帝国が解体され、民主主義が自信を取り戻し、世界は「希望に満ちてきた」という感覚は、いっときの幻影だったのではないかとさえ思えてくる。なにかが終わったのはたしかだ。だが、その後の世界の歩みはむしろ戦争と苦難と抑圧に満ちていたのではないか。だとすれば、終わりは終わりではなく、はじまりははじまりではなかったことになる。
ポール・ジョンソンが1980年代の世界をどのようにみていたかを紹介しておきたい。
最初に強調されるのは、20世紀にさまざまなイデオロギーがしのぎを削ったにしても、「人類の圧倒的多数の人びとにとっては、宗教が実際にいまでも自分たちの生活の大きな部分を占めている」ということである。宗教が消滅するという考え方は、むしろ古くさくなったとさえ述べている。
とりわけ、この時代にローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世(1920〜2005、在位1978〜2005)のはたした役割は大きかった。カトリック信仰の強いポーランド出身で、詩人、劇作家、哲学者でもあった。衰退しかかっていた伝統的カトリシズムの復興をやりとげた人物である。1981年5月に暗殺されそうになったが、1980年代から90年代にかけ世界各国を何度も訪れ、2億人の人びとと接した。カトリック信者の数は1978年時点で約7億4000万人だったが、2020年現在では約12億人に増えているといわれる。もともと多かったヨーロッパ、北米に加え、中南米、アフリカで信者数が大きく伸びている。
もっとも北米やヨーロッパの先進国では、教会の日曜礼拝に出席する人の数は少なくなった。そのいっぽうで、カトリシズムやプロテスタントの教義からはずれた、カリスマ的な根本主義の宗派が勢いを伸ばした。中南米では過激な政治行動を求める「解放の神学」が登場したが、大きな大衆的支持を受けるにいたらなかった。米国では福音主義のプロテスタントがメディアを利用して大躍進し、中南米まで伝道活動を広げている。
注目すべきはイスラム原理主義が力をつけ、1980年代以降、大きく広がったことだ。これに対抗するかたちで、ユダヤ教超正統派も復活した。ジョンソンによれば、ユダヤ教超正統派は「ダヴィデの王国の『歴史的』国境線を拡大するとともに、イスラエルを神権政治の国に改造することを目標としている」という。
イスラム世界は西アフリカから地中海南部、東アフリカ、バルカン諸国、小アジア、中東、南西アジア、マレーシア、インドネシア、フィリピンにいたるまで大きく広がっている。2020年時点でその信者数は19億人。
1970年代以降は、いわば「イスラム復興」の時代となったが、「その一つの支えとなったのは石油によって新たな富を得たことからくる辟易させられるほどの自信である」とジョンソンはいう。
とはいえ、イスラム教の内部はスンニ派、シーア派、イスマーイール派、ドゥルーズ派、アラウィー派などと分裂しており、それがしばしば対立を呼ぶ原因となっている。
中東の対立は加えて、何よりもイスラエルという国家の存在によるところが大きい。1980年代までは、イスラエルが結局のところ衰退する、とアラブ側は考えていた。だが、それは大きな誤りだった。
1979年にはイランで革命が発生し、国王が追放され、アヤトラ・ホメイニのシーア派原理主義者が実権を握った。その後、長年にわたる国境紛争に端を発して、イランとイラクのあいだで大規模な戦争がはじまる。イラクのサダム・フセイン大統領は、シャトルアラブ川とイランの油田を手中に収めるため迅速な勝利を得ようとしたが、そのもくろみは失敗し、戦争は8年もつづいて、両国で100万人以上の死者を出した。宗教が原因の戦争ではなかったが、それでもスンニ派とシーア派の対立が戦争の激しさをあおった面はある。
そのことはレバノンも同じだ。レバノン内戦は1975年から90年にかけて断続的に発生し、シリア、パレスチナ解放機構(PLO)、イスラエルが介入し、イスラム教の諸宗派がからんで収まりがつかなくなり、「商業都市ベイルートは滅び、レバノンはもはや独立国としては存在せず、古来のキリスト教共同体は優越性を失った」。
アフガニスタンでは1978年4月にソ連の後押しによりダウド政権が倒された。政権を握った人民民主党はイスラム教の勢力をそごうとして恐怖政治を敷く。その後、政治が混乱するなか、1979年末にソ連がアフガニスタンに侵攻する。ソ連の侵攻はムジャヒディンと呼ばれる反政府民族主義ゲリラによる激しい抵抗をもたらし、1988年5月のソ連軍の完全撤退につながる。
「ソ連指導部が最終的にアフガニスタンからの撤退を切望したのは、一つにはゲリラ戦が近隣のソヴィエト・アジアのイスラム地域にまで拡大するのではないかと懸念したからだった」と、ジョンソンは論じている。事実、ソ連領内でも、1970年代から80年代にかけて、イスラム復興の動きが強まっていた。
歴史は宗教を抜きにしては論じることができない。宗教と信仰は人びとの生活に深く根ざしている。たとえ、宗教を無視する風潮が強まったとしても、政治を宗教に完全に置き換えることはできなかった、とジョンソンはいう。
いまも中東地域をはじめ、世界の紛争は収まる気配をみせていない。島国の日本人にとっては遠い彼岸のできごとのようにみえるかもしれない。しかし、それがもはや他人事(ひとごと)ではないことを、『現代史』は教えてくれる。世界のできごとが近所のできごとと変わらない時代がはじまっているのだ。
『現代史』はこれからさらに1980年代の世界を探索していく。もう一度、あのころを思いだしながら、少しずつ読み進めてみる。
2024-01-21 11:21
nice!(5)
コメント(0)




コメント 0