『グローバル経済の誕生』を読む(1)──商品世界ファイル(31) [商品世界ファイル]
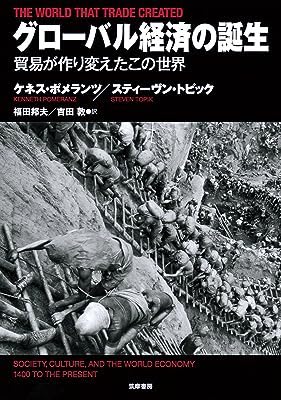
近代中国史を専門とするケネス・ポメランツと、ラテンアメリカ史を専門とするスティーヴン・トピックによる共著です。ふたりの専門分野を合わせて、コロンブスのアメリカ「発見」以前から現代までの600年にわたるグローバル経済の全体像を浮かびあがらせようとする試みといえるでしょう。
交易には経済原理では片づかない人間のドラマがあると著者は書いています。そして、実際、時間をさかのぼればさかのぼるほど、交易は現在の経済原理とは異なる方式でおこなわれていました。市場さえ存在しない地域も多かったのですが、アジアでは早くから海路による商業ネットワークが築かれていたのです。
最初にえがかれるのは、ヨーロッパ人が世界を制し、市場の掟を押しつけるようになる以前。時代は16世紀から19世紀にかけてです。中国やインド、バタヴィア(インドネシア)、アステカ(メキシコ)、ブラジルなどが舞台として取りあげられます。
中国では福建の華僑が登場します。人口が密集し、土地が痩せていたので、福建の人びとは昔から海外に進出し、独自の商業ネットワークを築いていました。しかし、中国政府は植民地をもつことに関心がなく、海外の福建人を保護しようとしませんでした。そのため、海外の中国人は、みずからの手段で、みずからの身を守らねばなりませんでした。
19世紀にはいり、ヨーロッパが工業体制を確立するため、植民地を確保していくにつれて、福建人はその動きに巻きこまれていきます。白人入植者は福建人を重宝しました。「彼らは現地人のように汗水垂らす肉体労働者として働くわけではなかったが、植民地の労働力を確保するリクルーターとして、また食料雑貨店の経営者、質屋、代書人として労働に従事した」といいます。
19世紀まで中国では、人民は絶対的為政者である皇帝に服属し、皇帝の任命した官吏によって支配されていました。しかし、周辺の国ぐには、使者を通じて中国の皇帝に朝貢品を献上することによって、国としての地位を認められていました。これが朝貢制度です。
朝貢国は中国の皇帝から下賜品を頂戴し、それを高価な宝として珍重しました。朝貢は経済儀礼というより、むしろ外交儀式だったといってよいでしょう。そして、こうした朝貢体制のもとで、民間の活発な交易活動がおこなわれていたのです(ただし、日本は早くからこの朝貢体制、すなわち華夷秩序から離脱していました)。
世界ではじめて精巧な紙幣がつくられたのは中国で、それは唐の時代でした。中国ではその後、銅銭が大量に供給されたものの、通貨不足は深刻で、宋の時代も紙幣が発行されていました。しかし、紙幣はしばしば増発されてインフレを招き、時に経済に打撃をもたらしました。
新世界で大量に銀が産出されるようになると、16世紀から300年にわたって、「世界の銀産出量の半分近くが中国で硬貨として鋳造された」。言い換えれば、この間、中国にはヨーロッパから大量の銀(メキシコ銀)が流れこんでいたことになります。中国から銀が流出するようになったのは、アヘン貿易がさかんになってからです。19世紀になるまで、ヨーロッパはまだ世界経済の中心ではありませんでした。市場原理もまだ浸透していませんでした。
ヨーロッパが進出するまで、世界経済の中心はアジアにあったといえるでしょう。アジアというのは、東アジアだけではなく西アジアも含みます。西アジアでは7世紀以降、イスラム世界が広大な商業圏を築いていました。
イスラム世界はアラビアから発して、エジプト、シリア、トルコ、イラク、イラン、北アフリカ、スペイン、ソマリア、西アフリカ、インド、インドネシアへと広がり、その地域では貿易が盛んになりました。イスラムの貿易商は、中国と地中海をまたにかけて仕事をしていました。
このヨーロッパ・アジア航路を横取りしようとしたのがポルトガルです。ポルトガルは15世紀末にインド航路を開き、その後、インドの港に多くの要塞を築いて、香辛料貿易を独占しようとします。だが、いかんせん実力不足で、1600年ごろにはアジアでの拠点もあやうくなっていました。
11世紀から15世紀にかけてヴェネツィアが繁栄したのは、アラブ人と取引をおこなっていたからです。ポルトガルは直接アジア・ルートを開拓して、ヴェネツィアに対抗しようとしたともいえます。
中央アジアを通る貿易ルートは、14世紀のマルコ・ポーロの時代以降、すたれていました。『東方見聞録』にはヨーロッパより中国のほうが治安が保たれ、商人は誠実だと書かれています。コロンブスはこの『東方見聞録』を読んで、ジパングに行きたいと願いました。
しかし、実際に到着したのはアメリカでした。その後、アメリカの先住民はヨーロッパ人によってひどい目にあいます。著者はアメリカの先住民がなまけ者で、自給自足の生活をしていたというとらえ方は、まちがいだといいます。じつは、先住民はすでに大規模な交易をおこなっていたのです。
アステカやマヤでは、トルコ石や銀、ナイフ、羽毛、ゴム、チョコレート、カカオ豆、金、黒曜石などが幅広く取引されていました。しかし、それは帝国への貢納が中心で、市場はその周辺にちらばっていたにすぎません。スペイン人がやってきてから、こうした商業ネットワークはたちまち消滅します。帝国そのものが崩壊したからです。
ブラジルに住むトゥピナンバ族は、狩猟採集と原始的な農業を営みながら、ゆったりと暮らしていました。私有財産という考え方はなく、時折、オウタカ族と沈黙交易をおこなっていました。そこにポルトガル人がやってきて、かれらに鉄製の剣や斧(おの)を贈り(それはとうぜん部族間の戦争をあおる)、染料の原料となるブラジルウッド(これがブラジルという国名の由来でもある)を手にいれるようになります。最初は染料の交易が目的でした。しかし、ポルトガル人はそれにあきたらなくなり、次第に先住民の土地を占領し、そこにアフリカ人奴隷を送りこんで、砂糖プランテーションを経営するようになっていくのです。
イギリス人がブラジルに進出したのは19世紀にはいってからだといいます。目をつけたのはコーヒーです。当時プランテーションのコーヒー園はさほど本格的に運営されていませんでした。イギリス人はその生産体制を確立し、陸上の輸送ルートを整備し、ヨーロッパとの定期航路をつくり、世界で初めてコーヒー市場をつくりだします。そのコーヒー園で働いていたのは、アフリカ人奴隷でした。
ポルトガルが衰退したあと、東南アジアにはオランダ東インド会社が進出しました。著者は驚くべきことに、東南アジアの貿易商人は男性ではなく女性だったと書いています。オランダ人はこうした女性貿易商を取りこむことによって、コショウから陶磁器にいたる産物の貿易を独占していきます。そして、王国の支配層に食いこみ、現地の慣習法を利用しながら、植民地支配をめざしていくのです。
18世紀半ばまで、アジアでは中国人やペルシャ人の貿易商が活躍していました。かれらは絹や金、ダイヤモンドなどを取引しながら、王国の徴税まで請け負うこともありました。インドにはペルシャの商人が進出し、たとえば王国に馬を売って、ひともうけしていました。馬はもちろん戦いのために用いられます。そして、そうした商人のなかからはダイヤモンドの採掘権を獲得する者や、貴族の称号を受ける者もでました。
1557年にイギリス東インド会社がベンガル地方を征服したときは、ベンガル商人を大いに活用したといいます。東インド会社はイギリスのアジア貿易を独占する株式会社でした。現地の支配者に近づいてビジネスを展開し、時に軍事力を行使し、植民地支配への道を突っ走りました。アジアの伝統的な貿易商は、次第に排除されていきます。
しかし、イギリスがインドを支配するようになったといっても、インドにすぐイギリスの資本が流れこんだわけではありません。イギリス人が考えていたのは、インドでいかにもうけるかということだけだったといってよいでしょう。イギリス人がベンガルの商人と組んでつくった銀行は、まさに本国に現金を送金することだけを目的としていました。アヘンやインディゴ(染料)、綿、紅茶など、カネになるものは後先考えずに輸出され、現地経済を好況と不況の渦に巻きこみ、最終的にはベンガル商人自体を没落へと追いこんでいきます。イギリスからインドに資本が投下されるようになったのは、それからでした。
こうして眺めると、ヨーロッパ人が16世紀以降、いかに世界を駆け回って、みずからにとっての富の獲得に奔走したかがわかります。富とは莫大な利益をもたらす商品のことです。そして、その商品のもととなるものは、ヨーロッパには存在しませんでした。だからこそ、それらは叡知(えいち)と機略をかけて、つくりだし、奪い取らねばならなかったのです。
いまでこそ信じられませんが、かつてヨーロッパにおいて、コショウやコーヒー、砂糖は、のどから手のでるほどに求められた商品でした。珍にして新奇、そしてかぎりなく人をひきつけることが、商品の本性です。それは単に有用という言い方だけでは言いあらわせない魔力(マルクスのことばでいえば物神性)、人生を変えてしまうほどの魔力を秘めていたにちがいありません。人びとはできるだけそれをいつでも手軽に手に入れることを望みました。
商品の仕掛けはいつも単純です。ふだん身の回りでは手にはいらないものを、目の前に現出させ、それがあれば生活が豊かになり、一変するかのごとき幻想をつくりだすのです。実際、それによってある程度、人生は変わり、日々更新されていくのでしょう。しかし、商品には表には見えていない、裏の世界が隠されています。そして、それこそがほんとうの世界かもしれないのです。
人の欲望には切りがあるはずです。ある程度の満足が得られれば、ほんらいは、それ以上を望むことはありません。ところが、商品世界はそれを許しませんでした。資本の欲望には切りがないのです。資本は資本の蓄積をめざす権力(絶対意志)であって、商品世界を拡大し、支配するためには、どんなこともいといませんでした。市場社会の広がりと浸透は、資本の物語として読み解かれねばならないのでしょう。
輸送技術の進歩が商品世界をいかに進展させたかというのが、次のテーマです。しかし、その前にさまざまなエピソードが語られます。
14世紀から15世紀にかけ、巨大船を建造する能力をもっていた中国は、明時代半ばになると海への進出を断念し、国内の治安維持に専念するようになります。木材は王宮建設をはじめとする国内需要のために利用されるようになりました。
「小型船で陶磁器や絹を中継地に運び、そこでインド産の綿花やインディゴを仕入れ」るというのが、中国貿易商のパターンだったといいます。そのため、中国人は大型船で海上交通路を独占しようとするヨーロッパ人に次第に対抗できなくなっていきます。
ヨーロッパ人が航海技術を発展させたのは、海外から巨万の富を得るという欲望に駆られたからだといいます。それがコロンブスを動かした動機にほかなりませんでした。「欲望のとりことなったおろかな男」コロンブスが、「新大陸を発見したのは偶然に過ぎず、発見した大陸がどこであるのか、見当もついていなかった」と、著者は辛辣に指摘しています。
18世紀の都市において、最大の問題は食料の安定供給を維持することでした。ロンドンはともかく、パリやマドリードではしょちゅう暴動が発生しました。近郊に広大な農地が広がり、運輸システムが整備されていないと、都市は発展しません。江戸やカイロ、イスタンブールなどが大都市に成長したのは、そうした条件が満たされていたからです。北京とデリーは肥沃な農地から遠かったにもかかわらず、卓越した運輸システムと徹底した食料管理によって、難点を克服し、大都市の繁栄を維持しました。
ムガール帝国の交通路を支えたのはパンジャーラ族という遊牧民だったといいます。かれらは牛をつれて村から村へと渡り歩き、穀物や塩、衣類、ダイヤモンドなどを運んでいました。
アメリカの西部開拓は自給自足農業のうえに成り立っていたわけではないという指摘もうなずけます。アメリカは釘にせよ衣服にせよ、ヨーロッパからさまざまな工業製品を輸入しなければなりませんでした。そのためには、穀物や米、綿花、タバコなどの農産物や木材を輸出する必要がありました。船積みの効率を考えて、東海岸には倉庫が建設され、商品が蓄えられます。ヨーロッパの工業製品はあまりかさばらないため、ヨーロッパからの船には移民を積みこむことができました。
とはいえ、アメリカへの移民の中心はヨーロッパ人ではありませんでした。大半がアフリカ人奴隷であり、そのあと中国人がやってきました。19世紀までの移民は、ヨーロッパ人が100万人〜200万人、アフリカ人が800万人、中国人が400万人だったといいます。アフリカ人は使い捨ての奴隷として扱われました。その後、中国人があまり増えなかったのは、ある時点で強い規制がなされたためです。
清朝期には中国人が大移動していました。満洲には100万人、四川や台湾にも移民の波が押し寄せていました。清朝は祖先の地である満洲や、先住民のいる台湾を保護するために、移民を制限しなければならなかったといいます。人口の移動は、おそらく人口膨張と農業開発が関係しています。
シンガポールを建設したのは、イギリス人のトマス・ラッフルズ(1781〜1826)です。「イギリスはシンガポールを基点に、かつて東インド会社がイギリスとアジア間の独占的貿易をおこなった規模よりもずっと大きな規模のアジア域内貿易に参加し、利益を得ることができるようになった」。
シンガポールは「自由貿易」帝国イギリスの拠点となります。その収入を支えていたのがアヘンだったという点も再確認しておくべきでしょう。
いっぽう上海はアヘン戦争(1840〜42)終結後につくられた都市です。当初はアヘン交易の中心地として、のちには海上輸送の拠点、そして商業都市として発展していきます。もともとは外国人の居留地として位置づけられていましたが、しだいに中国人が押し寄せてきます。こうして上海は1920年代には「数百万の中国人と外国人が入り混じり、金と無秩序が支配する世界になった」。
ヨーロッパとアジアの距離を短くしたのは、1869年に完成したスエズ運河です。これによってロンドン─ボンベイ間の船賃は、一挙に3割安くなったといわれます。
スエズ運河開通後、世界は急速に変化していきました。インドネシアの島々ではタバコ、コーヒー、ココア、ゴムなどのプランテーションがつくられ、スズや石油の採掘もおこなわれるようになります。ベトナムやビルマの米は広東やロンドンに運ばれていきました。アジア各地にプランテーションが広がり、中国から大量の苦力(クーリー)がつれてこられました。こうしてアジアでは、民族の混交と分裂、差別と貧困が広がり、宗教やイデオロギーの対立も生じるようになります。
鉄道は陸上貨物の輸送コストを削減し、大量輸送を可能にしました。時刻の標準化と商品の規格化が進みます。鉄道は軍隊を移動させるための手段としても利用されました。飢饉(ききん)のさいにも、鉄道は大いに威力を発揮しました。
「輸送とは、物理的に異なる地域を移動するだけでなく、社会文化圏の相違を飛び越え、さらには歴史や時代を飛び越えてしまうことである」と著者は論じます。輸送とは単なる空間の移動ではなく、時間の移動、つまり歴史や文化の移動でもあるのです。こうして、19世紀の輸送技術の進展は、地球世界をちいさくすると同時に、商品世界を拡大していったのです。
メキシコでコーヒーがつくられるようになるのは1870年代ですが、鉄道ができるまでは、マヤの人びとがコーヒー袋をかついで、船着場まで運んでいたといいます。鉄道の建設によって、コーヒー農園は一挙に拡大し、コーヒー生産は倍増します。コーヒー豆はニューヨークに運ばれ、オハイオ州の巨大工場で焙煎(ばいせん)されて、全世界のコーヒーショップに卸されていきます。
しかし、そうした輸送改良によって、メキシコのマヤ人の労働環境が改善されたわけではありません。かれらは安い給料ではたらかされ、代々債務奴隷にされ、コーヒー袋をかついで黙々と険しい丘陵を行き来していたのです。
輸送の発達は一概に人びとを豊かにしたわけではありませんでした。単純に技術の進歩を喜べないのは、そこに(政治、経済を含めた)権力という契機がかかわっているからです。
19世紀になっても、長距離輸送の中心は水上交通(水運)でした。しかし、蒸気機関が発明され、鉄道が敷かれ、道路が整備されてくると、輸送コストは大幅に下がり、商品輸送のスピードも一挙に高まります。かつての中継地や中間商人は没落し、世界中の商品が集まる都市が発展します。そして、植民地主義がますます強化されていくのでした。
著者は、われわれがふだん愛用している嗜好品の裏側にも迫っています。ここで嗜好品というのはコーヒーや紅茶、ココア、タバコ、砂糖など、一度食べると癖になる食品を指しています。われわれはこうした嗜好品を、自由にスーパーやコンビニで好きなだけ買うことができます。しかし、そうした商品がどのように生産されているかは、ほとんど知らないものです。商品は包装された外見と値段が示されるだけで、その生産過程はほとんど舞台裏の隠された次元に遠ざけられているといってもよいでしょう。
上に挙げたこれらの食品は、もともと限られた地域でしか栽培されていませんでした。コーヒーはエチオピア、茶は中国、ココアはメキシコやアンデス一帯、タバコはアメリカ大陸が原産地です。それがいまでは世界中に広がって、だれにとっても、なくてはならない生活文化の一部となっています。
著者はこんなふうに書いています。
〈紅茶のないイギリス人、カフェオレのないフランス人、エスプレッソのないイタリア人、コーヒーブレイクのないアメリカ人を、誰が想像できようか。……コーヒーとタバコが男性関連だとすれば、チョコレートは女性と子供の飲み物だった。噛みタバコは庶民用、嗅ぎタバコと葉巻はエリート用となった。金持ちは、エレガントなサロンでメキシコ製の銀のティーポットから中国製の陶器のカップにそそがれる中国茶を飲んだ。他方、庶民は街頭の物売りから購入した紅茶を薄汚い粗悪なマグカップでちびちび飲んだ。〉
問題は、先進国の消費者を楽しませる(あるいは狂わせる)、こうしたさまざまな嗜好品やドラッグ(コカやアヘン、マリファナなど)の背後に、どのような商品経済の論理がはたらいていたかということです。
もともとカカオ豆はマヤやアステカの貴族や戦士に珍重されていました。興奮剤や麻酔剤、媚薬(びやく)として利用されていたようです。カカオ豆は貨幣としても用いられていました。これをスペインに紹介したのがイエズス会の修道士です。16世紀初頭のスペイン人はカカオ豆をつぶして水で溶かし、砂糖、シナモン、バニラを加えて飲んでいました。お湯で溶かし、ミルクを加えるようになるのは18世紀になってからです。そのころカカオの栽培地は、すでにベネズエラ、ブラジル、インドネシア、フィリピンにまで広がっていました。1828年、オランダ人のカスパルス・ヴァンホーテンがココアを発明、さらに19世紀後半にミルクチョコレートが開発されます。
ここに挙げた嗜好品のうち、茶の木だけは中国が海外に流出することをしばらく阻んでいました。中国茶が紅茶に変貌するのは輸送中の偶然のできごとでした。イギリスでは紅茶と砂糖が結びついて、中国からの茶の輸入がどんどん膨らんでいきます。中国との貿易赤字を解消するために、イギリスが中国に持ちこんだのがアヘンだったという話はあまりにも有名です。いっぽう、イギリスは19世紀に中国から茶の木をもちだし、それをセイロン(現スリランカ)やアッサム地方(インド北東部)に移植することに成功しました。
コーヒーはエチオピアが原産地でしたが、次第にイエメンの山岳地帯でもつくられるようになり、1400年ごろからモカで、1500年ごろからアラビア半島で飲まれるようになり、次第にイスラム世界全体に広がっていきました。ヨーロッパにコーヒーが伝わったのは1683年、オスマントルコ軍がウィーン包囲に失敗したあとからだという説もあります。トルコ軍が戦場に残したコーヒーをもとに、ウィーンでコーヒーハウスがつくられました。
最初のころヨーロッパ人はモカから高いコーヒーを仕入れる以外に手だてがありませんでしたが、ルイ14世(1638〜1715)の植物園で、イエメンから持ち帰ったコーヒーの苗木が育てられ、それがアメリカ大陸に運ばれていくことになります。これがモカ・コーヒーのはじまりでした。
しかし実際は、それ以前にコーヒーはヴェネツィア人によって、すでにヨーロッパに持ちこまれていたのです。イタリア人がエスプレッソを飲む習慣は、ヴェネツィア人によってはじまったといってよいでしょう。
18世紀のロンドンでは、男たちがコーヒーハウスに入りびたりとなり、それが妻たちの怒りを買って、コーヒー排撃運動が発生します。イギリスが紅茶の国になるのは、そうした要因も手伝ったようです。こうしてイギリスは別として、スウェーデンでもプロイセンでもパリでも、アメリカでもコーヒー文化はたちまちのうちに広がっていきます。
アメリカ人はイギリス人と対抗するためにコーヒーを愛飲するようになったといわれます。しかし、事実は奴隷制がコーヒー生産を支え、その価格を廉価にしたのです。最初はハイチでした。その後、ブラジルがコーヒーの供給元となります。著者によれば、アメリカ人がコーヒー漬けになるのは「コーヒーが奴隷制度で安くなり、しかもコーヒービジネスが儲かったからなのである」。
砂糖についても述べておきましょう。サトウキビは昔からあったとはいえ、これを砂糖に精製したのはアラブ人で、ヴェネツィア人はアラブ人との砂糖交易で、大儲けしていました。ヴェネツィアに対抗して、ポルトガルは最初西アフリカ沖のサントメで奴隷による砂糖栽培をはじめます。それがさらにブラジル、そしてフランス領のハイチへと持ちこまれました。「砂糖プランテーションのオーナーたちは、古代ローマ時代を思わせる残忍極まりない奴隷労働を酷使して富を蓄えた」と著者は記しています。
そのハイチで1791年に革命が発生し、1804年にハイチは独立を果たします。しかし、そのあとには何も残りませんでした。島は砂糖に代わるものを生みだせず、アメリカの勢力圏に吸引されていきます。こうして「熱帯の楽園」は「惨めで活気のない僻地」へと変わっていくのです。
イギリスがインドのアヘンを中国に輸出したのは、中国との貿易赤字を解消するためだったということは前にも述べました。アヘンの流入により中国では銀が流出して、通貨危機が引き起こされ、アヘン輸入禁止措置をとった中国にイギリスは戦争をしかけます。それがアヘン戦争(1840〜42)でした。
さらにイギリスはインドのアヘンで大幅な貿易黒字を出し、大西洋での貿易赤字を埋め合わせました。「アヘンは、中国、インド、イギリス、合衆国を結び付け、四角貿易を成立させ、さらにイギリスの工業化を推進し、19世紀における世界経済の革命的拡大を支える中心的役割も果たした」
そして現在はコカインの時代です。コカはボリビアからペルーにかけての熱帯林に繁茂し、その葉はもともと宗教儀礼に用いられていました。スペイン人はそれをポトシ銀山でインディオたちを働かせつづけるために利用しました。
コカコーラは1948年までコカイン入りの飲み物でした。麻酔薬としてのコカインは1860年ごろから使用されましたが、同時に麻薬としても根強い人気がありました。ドラッグストアでは、その名のとおり、かつてコカインが売られていました。20世紀になって、コカインは享楽品としては禁止されるようになるのですが、1970年以降はコカインが新たなブームとなり、たびたびの取り締まりにもかかわらず、密売人が横行しているのが実情です。
ブーム商品の背景には、時に悲惨な風景が広がっています。生産の場であれ、消費の場であれ、商品の論理が力(契約と暴力)を背景としているという事実に、われわれはもうすこし自覚的であっていいのかもしれません。一皮めくれば、人類の社会も、経済学のきれいごとではすまされない、ホッブズ流の生存競争の渦中にあるのではないでしょうか。
2023-09-06 06:53
nice!(8)
コメント(0)




コメント 0