『貧乏人の経済学』を読む(1) [商品世界論ノート]
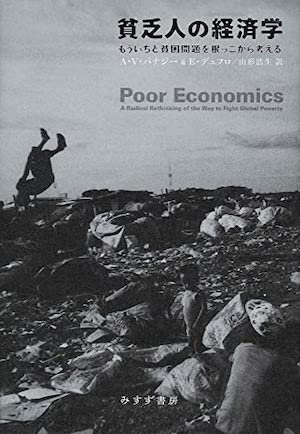
ツンドク本の整理です。原著のタイトルPoor Economics を『貧乏人の経済学』と訳す理由はわからないでもありませんが、やや違和感があります。刺激が強すぎるというか、ちがうニュアンスを喚起させるというか、まるで自分のことを言われているみたいというか。最初『貧困の経済学』でじゅうぶんなのではないかと思ったりもしたのですが、それでは「人」に即したこの本の意図が伝わらないかと考え直したりもします。タイトルはむずかしいですね。
それはともかく、本書は開発経済学の専門家、アビジット・バナジーとエスター(エステル)・デュフロの共著です。バナジーはインド・コルカタ(旧カルカッタ)生まれの経済学者、デュフロはフランス人の経済学者(ともに現在マサチューセッツ工科大学教授)。ふたりは本書出版後の2015年に結婚し、2019年にノーベル経済学賞を共同受賞しています。
ぼく自身は、開発途上国の貧困問題について、ほとんど何も知りません。もちろんニュースなどで伝えられることもありますが、あまり深く考えたことはありませんでした。しかし、評判になっている本なので、読んでみるかと買い求め、それだけで満足し、ツンドク本のままになっていました。それを今回は思い立って読んでみようというわけです。おかげさまで、暇だけは財産で、当面、時間はあります。
とはいえ、最近は活字が以前にもまして頭にはいってこないし、読みはじめるとすぐ眠くなってしまう始末です。こっくりこっくり、同じページをいったりきたりして、なかなか前に進みません。中身もすぐ忘れてしまいます。そこで、いつものように、少しずつ読みながらメモにまとめてみることにしました。途中で挫折したら、あやまるほかありません。もっともぼくが挫折したところで、それを気にとめる人もいないでしょう。
「はじめに」で、「貧乏な人の経済学は、貧困の経済学と混同されることがあまりに多い」と書かれています。貧困の経済学はあまたある。しかし、それはほんとうに現実の「貧乏な人」に即して論じられているのかというわけです。
著者たちは「貧乏な人々が住む裏道や村に出かけ、質問をして、データを探す」ところからやりなおし、あらたな道筋をみつけようとしたといいます。
ここで注目されるのは、世界の最貧者です。2005年段階で、貧困国といわれる50カ国のなかで、1日1ドル以下で暮らす人が8億6500万人(全世界人口の13%)いました。その実際を知らなければ、さまざまな方策を立て、さまざまな援助をおこなっても、まったく空振りに終わってしまう、と著者たちはいいます。
貧乏の落とし穴にはまると、人はそこからなかなか抜けだせない。課題はあまりに大きい。それでも努力をつづける必要がある。「成功は必ずしも、見た目ほど遠いわけではない」と宣言するところから、本書はスタートします。情熱が感じられます。
世界の貧困問題はあまりにも大きく、手のつけようがないようにみえます。しかし、一つずつ解決していけばよいのだというのが、著者たちのスタンスのようです。
ところが、貧困問題を「大問題」として、一挙に片づけようという考え方も根強く存在します。たとえば国連顧問でコロンビア大学教授のジェフリー・サックスは、現在よりはるかに大規模な外国援助の必要性を強調します。
そのいっぽう、ニューヨーク大学教授のウィリアム・イースタリーは援助などは無意味などころか弊害が大きく、現地の人びとの自立を促すことにはならないと反論します。
著者たちの考えは、そのどちらでもありません。具体的なプロジェクトをつくって、それに適切な援助をおこなうことは必要だ。ただし、援助は何でもかでもやればよいというものではないと論じています。つまり、援助は有効なこともあれば、有効でない(かえって害を与える)場合もあるということです。あくまでも現場に即して、問題を理解し、適切な方法を見いださなければならないというわけです。
3つのiが政策の失敗や援助の低効果を招く原因になっているという指摘がおもしろいですね。それはイデオロギー(ideology)、無知(ignorance)、惰性(inertia)です。たしかにそうかもしれません。ただし、これは貧困対策にかぎった問題ではないでしょう。
ここからが第1部です。「個人の暮らし」と題されています。
まずは食の問題。
最初に目を開かされるのは、貧困といえば飢餓だと思うのはまちがいだ、と著者が指摘しているところです。たしかに大飢饉は起こりうる。しかし、世界で10億人が飢えているという見方は、けっして正しくないといいます。
おカネのない貧乏な人が、じゅうぶんに食べられないというのは事実でしょう。だからといって1日1ドル以下で暮らす人が、その少ない実入りをすべて食糧につぎ込んでいるわけではありません。アルコールやタバコ、お祭りに使っていることも多いのです。少し収入が増えても、それは主食に回らず、美食や嗜好品に向かう傾向があるといいます。
少なくとも現在の地球では、1日1人あたり2700キロカロリーが供給できるほど、食料はじゅうぶんに生産されています。絶対的な食糧難はありません。水道と公衆衛生の普及、重労働の軽減などによって、人の平均カロリー摂取量はむしろ減っています。飢えがあるとすれば、それは食糧分配の仕組み(さらに干魃や戦争)のせいです。餓えはもちろん大きな問題です。しかし、「多くの人が貧乏なままなのは、食が足りていないせいではない」と、著者たちはいいます。
とはいえ、こういう言い方は誤解を生むかもしれません。最貧層のカロリー摂取量が少なく、栄養不良が身体の発達に影響をおよぼしていることはたしかです。食べるものが増えて、それが栄養をよく考慮したものであれば、子どもを含め、体力もついて、一家の生活はより改善される可能性があります。
にもかかわらず、食事の慣習を変えるのはむずかしく、貧しい人びとはなかなかバランスのよい食事を取ろうとしないことが問題なのです。かれらは食事を改善するよりも、昔ながらの伝統にしたがって、結婚式や持参金、祭や葬儀などに収入の多くを費やしてしまいます。あるいは最近では、テレビや携帯におカネをつぎこんでしまいます。
貧困と栄養不良はけっして無関係ではありません。だからといって、貧乏な人には安価な穀物を与えればよいという食糧政策はまちがっている、と著者たちはいいます。問題はカロリー量ではなく、ほかの栄養素であり、バランスのよい食事なのです。慣習はなかなかあらたまらないかもしれません。しかし、少なくとも、お腹のなかの子どもと、ちいさな子どもにたいしては、その栄養状態が配慮されるよう、政府が保健所や学校、保育園を通じて必要な対策をとることはできるはずだ、と著者は述べています。
まだ、はじまったばかり。引きつづき読んでみましょう。
食につづいて、「個人の暮らし」では、健康、教育、家族計画の問題が論じられます。
2023-09-11 09:38
nice!(10)
コメント(0)




コメント 0