山本義隆『私の1960年代』をめぐって(1) [われらの時代]
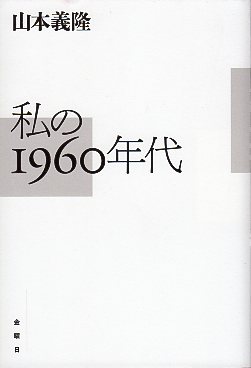
一度だけ、山本義隆の演説をどこかの講堂で聞いたことがある。何かの集会だった。あれは1968年の終わりころだったか。ふつうのアジ演説とは少し異なる、理路整然とした話しぶりに、思わず引きこまれたことを覚えている。
ぼく自身も全共闘世代だが、運動の中心にいたわけではない。周辺をうろうろしていただけである。デモにはよくでかけたけれど、逮捕された経験はない。母校の早大全共闘にも加わらなかった。ああだ、こうだと議論する口舌の徒にとどまっていたといえるだろう。そのうち運動の退潮とともに、大学を卒業し、社会人になった。ただし2年間も大学を留年したのは、余分である。
学生運動の中心にいたわけではないから、60年代後半の全共闘運動について語る資格はない。あのころの記憶もぼんやりしている。
1969年1月の東大安田講堂をめぐる攻防が、60年安保闘争と並ぶ戦後学生運動のハイライトであったことはまちがいない。腹蔵なくいってしまえば、あれはめったにない見ものであった。「安田砦」にこもった学生には、万に一つの勝ち目もなかったけれど、かれらはよく戦って、一昼夜にわたる敵の攻撃をしのいだ。そのテレビ中継に釘づけになっていた。
学生たちはなぜ安田講堂を占拠したのだろう。
1968年1月に、東大医学部と青年医師連合(青医連)は、登録医制度に反対し、研修協約の獲得を求めて、ストライキにはいった。それが東大闘争のそもそものきっかけだった。
それまではインターン制度というのがあった。医学部を卒業した学生は、1年間無給で病院勤務をしなければ、医師の国家試験を受けられないというものだ。
インターン制度は無資格診療だったから、医療過誤の可能性という問題をはらんでいた。
そこで厚生省は、インターン制度に代えて、登録医という、あらたな研修制度を導入しようとする。これによって、医学部卒業生はすぐに国家試験を受けられるようになる。しかし、その後の2年間は研修期間(ただし有給)で、登録医として、大学病院または市中病院で、研修を積まねばならない。
その新制度に反対したのが、青年医師連合(青医連)だった。青医連はもともとインターン制度に反対していたが、新たな登録医制度も研修医の権利改善にはつながらないように思えた。
そこで、青医連は研修医の要望を受け入れるよう東大病院に求めた。しかし、病院当局はいっさいの話し合いを拒否したため東大医学部はストに突入する。
そのさい、病院の医局長と学生側・研修医とのあいだで、小競りあいがあった。これにたいし、大学当局は一方的に学生・研修医に厳しい処分を下した。
ところが、処分された人物のなかに、当日その場にいなかった学生も含まれていたのである。
こうした事実誤認があったにもかかわらず、大学はその処分を撤回しなかった。
かたくなな当局の姿勢に抗議するため、医学部全学闘争委員会は6月15日に総長室のある安田講堂を占拠する。
これにたいし、当時の総長、大河内一男はただちに機動隊を導入し、学生たちを排除した。
この措置は、火に油をそそぐ結果となり、東大では、それによって医学部の闘争が全学レベルの闘争へと拡大していくのである。
山本義隆自身はこう述懐する。
〈それまでの医学部闘争への全学的な関心の薄さを見てきただけに、若い学生諸君が大学への機動隊の導入それ自体をストレートに「大学自治の破壊」と捉え、しかもそのことにたいしてこれだけ激昂するとはちょっと予想外でした。〉
このとき山本は27歳で、東大大学院で物理学を学んでいた。かれは東大に入学してすぐに60年安保闘争を経験し、それ以来、62年の大学管理法(大管法)反対闘争にも加わり、日韓闘争、砂川闘争、ベトナム反戦闘争にもかかわっていた。
「素粒子論の学習に励みながらも、街頭の闘争に出かけて行く日々」だったという。
党派には所属せず、東大の「ベトナム反戦会議」の活動家だった山本は、すでに大学が「自治」を堅持しているなどとはとても思えなかった。
しかし、現実に大学に機動隊が導入されると、ノンポリの学生たちでさえ、みずから「大学自治」を投げ捨てた当局の冷たい対応ぶりに、憤りさえ感じたのである。
古い体質の権威にあぐらをかいたまま、学生の言い分にいっさい耳を傾けなかった大学当局は、みずからの非を認めず、ついに学生に捨て身の行動をおこさせた。
その挙げ句が、あたふたと警察権力に学内秩序の回復をゆだねるという愚行である。こうした無能ぶりが、闘争を全学的なものにエスカレートさせる結果を招いたといえるだろう。
その後の大学当局の対応もまったく要領を得ず、権威の化けの皮はどんどんはがれていった。
東大闘争の先陣を切ったのは、はっきりいって、新左翼各党派、政治意識の強い各学部大学院生の「全学闘争連合」、それに青医連のメンバーだったといってよい。かれらは「本部封鎖実行委員会」を結成し、7月2日夜に、大学本部のある安田講堂を再占拠した。
山本義隆は「そこを解放することは、物理的な意味より、象徴的ないし政治的な意味で重要だった」と記している。
各学部の自治会も、安田講堂占拠を支持した。
こうして安田講堂は大学当局から解放され、闘争を支持する者なら、だれでもがはいれる場所になった、と山本は書いている。
講堂前の広場には、テント村がつくられていた。
山本はこの安田講堂に常駐して、その維持と管理、イベントや会議の運営にあたった。
全共闘は建前からいえば、「それぞれに決意した個人の集まり」であったけれど、そこには党派の活動家も多く含まれていた。しばしば党派の政治的主張に振り回される会議をまとめていくのは、たいへんだったようである。
安田講堂が学生に占拠されるなかで、闘争は全学に広がり、10月にいわゆる東大全共闘が結成される。山本はその代表に選ばれることになった。
これまで東大闘争を引っ張ってきたのが、医学部の青医連だったことを考えれば、青医連の今井澄(のち参議院議員)を全共闘代表とするのが筋だった。しかし、今井は社学同ML派に属しており、本人の言によれば、「少々歳をくっていた」調整役で、「どの党派の色もついていない安全パイみたいなもの」として山本が代表役に押しだされることになったのである。
ちなみに、もともと「共闘会議」だった組織が、いつしか全共闘と呼ばれるようになるのは、そのころ同時に戦われていた日大全共闘の名が広く知られるようになり、それが一般化したからだという。
10月は反戦運動の季節だった。
羽田闘争1周年の10・8闘争、さらには10・21の国際反戦デーが盛り上がるなかで、東大では安田講堂の「解放」と、各学部のバリケード封鎖がつづけられていた。
あのころ、ぼくも下宿先の東大工学部大学院生Nさんに連れられて、天気のいい日、のこのこと安田講堂を見学しにいったことがある。講堂前の広場にはテントが張られ、どことなく緊張感はあったものの、そこは楽しげなイベント会場のような雰囲気にあふれていた。
Nさんが、青医連の今井澄の名前をだして、すごい男だと称賛していたのを、いまになってしきりに思いだす。
2016-02-17 08:14
nice!(12)
コメント(0)
トラックバック(0)




コメント 0