定義の問題──ケインズ素人の読み方(3) [経済学]
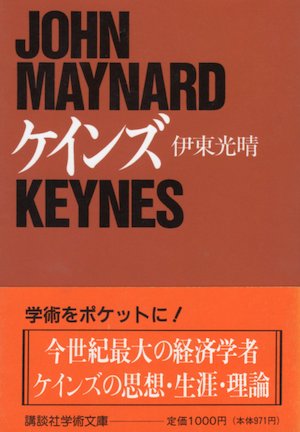
雇用量は有効需要によって決まるから、重要なのは総需要関数である。そして、需要は消費と投資からなる。
ケインズはそこで、消費と投資の分析にはいるのだが、その前に、少し横道にそれて、経済システムの構造に関するいくつかの視点をあらかじめ提示する。
一つは単位の問題、次に期待の役割、そして所得の定義である。
まず単位の問題について。
ケインズはマーシャルやピグーの提起した国民配当、実物資本ストック、一般物価水準といった概念を批判するところからはじめる。
国民配当は年間に国民に配当された富をあらわすものだが、それは「不均質な物のごたまぜでしかなく、厳密には計測もできない」と、ケインズは断言する。
実物資本ストックも計測できない。なぜなら、「その期に生産された新しい設備と、摩損によって消えた古い設備とを定量的に比較する基準」がないからだ。
さらに一般物価水準という概念もあいまいで、厳密な分析には適当でない、とケインズはいう。
もっとも現在では、国民総所得(国民総所得)や資本ストック、消費者物価指数などの統計も整備されて、経済の現況が把握しやすくなっている。しかし、1930年代のケインズにとっては、少なくとも当時のそうした概念は厳密さを欠く「判じ物」で、歴史的、社会的な興味を惹くことはあっても、とても経済学的には用いられないものだった。
これに対抗して、雇用経済を考えるさいに、信頼すべき単位としてケインズが持ちだすのが労働単位である。雇用量を計る単位が労働単位で、各労働単位には貨幣賃金(賃金単位)が支払われる。そして、その労働単位は均質だと想定されている。つまり、実際の労働は質や量にちがいがあったとしても、それは単純な労働単位に還元できるというわけだ。
経済全体の動きは、賃金単位と労働単位の二つの基本単位さえあれば把握できるというのがケインズの主張である。
そのことがどういう意味をもつのか。正直言ってよくわからない。だが、すくなくともケインズの考え方は伝わってくる。それは失業や貧困は、状況としてではなく、構造の問題としてとらえなければならないということである。
さらに、ケインズは経済が期待によって動いていることを強調する。期待する主体は企業家である。考えてみれば、経済における期待も構造的といるだろう。企業活動を否定する社会主義においては、計画はあっても期待はないからである。
企業家は消費者の需要を満たすことを目的に生産をおこなうが、そのさい、消費者がいくら支払う用意があるかを予想(期待)して、商品の生産を決定しなければならない。
企業家は短期的には現在の設備を利用したうえでの期待価格を設定し、長期的には新たな設備を導入したさいの収益を期待することになる。しかし、日々の生産は短期期待で決まるといってよいだろう。そして、雇用量はこうした期待によって左右されることになる。
期待は、良い方向、悪い方向へと変化しうるが、それが雇用に影響をもたらすまでには、かなりの時間がかかる。また期待の状態がかなりの時間つづく場合には、長期雇用が生まれる。期待がよい方向に変化すれば、雇用水準はだんだん高まり、頂点に達し、少し下がって新しい長期水準に達する。
期待の状態はたえず変化する。生産と雇用は一般に企業家の短期期待で決まり、実際の結果をみてだんだん変えられていく。とはいえ、長期期待の場合は、実現した結果にもとづいて、しょっちゅう変えるわけにはいかない。
いずれにせよ、経済的な期待(予想)を抜きにしては、資本主義の持続はありえないことをケインズは示した。
さらにケインズは所得、貯蓄、投資を定義する。
ケインズがモデルとして想定するのは、企業部門と家計部門からなる閉じられた経済システムである。
ざっくりいうと、企業の所得、すなわち粗利潤は、商品の売り上げから原価を引いたものだ。原価が売り上げを上回る場合は、マイナスになるが、たいていそれはプラスになる。原価のなかには要素費用(労賃や人件費など)と使用費用(原料費や設備消耗費など)が含まれる。
逆にいえば、企業の生産物の価値は、要素費用と使用費用、ならびに利潤の総計として実現されることになる。これがすなわち商品の売上収入となる。
一般に商品の売上収入が増加するにともない、使用費用は増加する。そして、期間を区切って商品が売られたあとには、運転資本と製品在庫が残るかたちとなる。
ケインズの規定はもっと細かくてややこしいいのだが、いずれにせよ、企業はその所得が最大になるように活動する。そして、国民所得は企業所得と家計所得の総計からなる。これが生産物の価値だといってよい。
言い換えれば、こうだ。
所得=売上収入−使用費用
=要素費用+利潤
=家計所得+企業所得
さらに、ここから
所得=消費+投資
という図式が想定できる。
企業による生産には、消費と投資が対応する。企業によってつくられた商品は家計によって消費される。いっぽう、企業も生産のために投資をおこなわなければならない。
つけ加えておくと、ケインズが想定しているのは、資本家対労働者の階級対立構図ではなく、企業と家計という社会構図である。企業家あるいは事業者という存在は否定されておらず、時にそれは資本家と重なることもある。
創業者としての企業家はともかく、資本は次第に経営と分離されていく。資本家による企業の私物化は認められない。
さらに法人としての企業と主に家族によって営まれる家計もまた分離される。企業家も労働者も企業人として企業ではたらくとともに、家庭人としての顔をもち、それぞれの家計をいとなむことになる。
ケインズが想定するのは、そうした社会構図である。
労働者は窮乏化を運命づけられているわけではない。経済全体の成長とともに、労働者も豊かになっていくだろう。それでも、労働者が失業と貧困、あるいは社会的格差に苦しむとすれば、その原因は資本家の存在そのものではなく、むしろ資本主義の内的構造にあり、それは克服可能だ、とケインズはとらえるようになった。
先に進もう。
企業は所得の最大化をめざして雇用量を決める。だが、そのために有効需要にしばられるといってもよい。有効需要は「事業者の期待利潤を最大化する雇用水準に対応する点」となる。このあたりも、なかなかむずかしい。
企業には損失がつきものだということもケインズは承知している。たとえば、戦争や地震、火災などによる突発損失。あるいは資本設備の陳腐化や経年劣化など。
これらのなかにはある程度予想できるものもある。そして、ある程度予測可能な資本設備減耗には補塡費用が必要になってくる。
純利潤を計算するためには、粗利潤から補塡費用を引かなくてはならない。いっぽう、突発損失については、ケインズは所得勘定にいれずに、資本勘定に計上するのが原則だとしている。
企業の純所得は純利潤である。ここからのケインズの議論も難しく、よく理解できない。純所得の概念が経済学者のあいだでも定まっていなかったことがわかる。素人は深入りするのを避けたほうがよさそうだ。
雇用理論にとって重要なのは、むしろ貯蓄と投資である。
貯蓄は所得から消費による支出額を引いたものだ、とケインズはいう。
すなわち
貯蓄=所得−消費
すると以前の「所得=消費+投資」から
貯蓄=投資
という等式が導かれる。
この図式は何を意味しているのだろう。
供給と需要が一致するとき、生産の剰余(投資)と消費の剰余(貯蓄)は一致する。こう言い換えても、それは定義上の規定で、何のことだかよくわからない。
貯蓄は家計でも企業でも生じる。また投資は企業でも家計でも生じる。 貯蓄がゼロならば、投資もゼロになる。
貯蓄はまさに所得から消費を引いたものにほかならない。もし家計が収入のすべてを消費に回せば家計の貯蓄はゼロになるし、企業が利潤のすべてを消尽すれば、企業の貯蓄もゼロになる。そうなると、企業でも家計でも投資は生じない。
いっぽう、投資といわれて、いちばんに思い浮かべるのは企業の設備投資である。技術開発や人材育成も投資のうちにはいるかもしれない。企業だけではなく家計も投資をおこなっている。株を購入したり、教育にお金をつぎこむのも投資だといえるだろう。考えようによっては車や家を買うのも投資かもしれない。
投資(銀行融資を含めて)には貯蓄の裏づけがある。しかし、貯蓄=投資の図式に拘泥しても、それは定義上の帰結であって、ここからは新たな展開はなさそうだ。
それでも、貯蓄=投資図式は、資本主義が内在的に経済成長を可能にするシステムであることを示している。
にもかかわらず、恐慌が発生し、失業や貧困が生じるのはなぜか。
それを考えるために、ケインズは消費性向と投資誘因を分析する必要があるとして、ふたたび横道から本論へと戻っていく。
2021-09-27 16:35
nice!(11)
コメント(0)




コメント 0