早稲田での憲法講義(1)──美濃部達吉遠望(24) [美濃部達吉遠望]
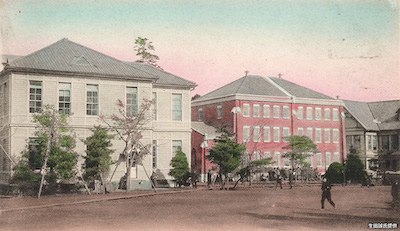
ヨーロッパ留学から帰国した1902年(明治35年)から美濃部達吉は東京帝国大学教授として法科大学(法学部と改組されるのは1919年)で比較法制史を教えていた。だが、ほんらい公法に関心が強かったため、早稲田大学や日本大学に出向いて、憲法に関する講義もおこなうようになった。
奥付がないため、発行年月日ははっきりとわからないものの、達吉が早稲田大学の法律科でおこなった帝国憲法講義録が早稲田大学出版部から出されている。推測するにおそらく1905年(明治38年)前後の出版と思われる。北一輝が美濃部の講義に出たか、あるいはこの講義録を読んだことはまちがいない。
ここで、いささか退屈かもしれないが、この講義がどういう内容のものであったかをふり返っておくのも悪くないだろう。憲法にたいする達吉の考え方はこのころからほとんど変わらず、1920年(大正9年)から東京大学で憲法講座を受け持つようになっても、講義の内容は基本的に同じだったと思われる。
早稲田での講義は、そもそも国家とは何かというところからはじまっている。日本だけではない。世界にはさまざまな国があって、それらは対立したり交流したりして、現在の国際関係を築いている。したがって、国家という現象はけっして一国だけの特有の現象なのではなく、文明国に共通の普遍的な現象であって、そこで国家にたいする共通の概念が成り立つ。とはいえ、それぞれの国には、それぞれの歴史的背景があることも忘れてはならない。そう指摘しつつ、達吉は近代国家とは何かを論じている。
国家が成立するには、国民と領土と統治権力が存在しなければならない。つまり、国家とは「唯一最高の権力の下に一定の土地の上に定着したる多数人類の結合したるもの」である。ただし、そう規定するだけでは、国家の性質を説明したとは、とてもいえない。
古くからある考えとして国家有機体説がある。国家は生き物と同じで、自然に成長し、発達し、衰亡するというものだ。だが、それは自然のアナロジーにすぎず、政治学的な説明を満たすものではない。
法律的にいえば、国家を統治の目的物(客体)とみるか、統治状態とみるか、統治権の主体とみるかという3つのとらえ方がある。
国家を統治の目的物とみるのは、政治的意志が国家の上に立つと想定する中世の封建的な考え方だ。君主が臣民や領土を自己の所有物とみなすこうした考え方は、近代の国家観念とは相いれない、と達吉は断言する。近代国家においては臣民は奴隷ではなく、みずからの権利の主体であって、君主はあたかもみずからの所有物であるかのように、臣民を支配することはできない。
次に国家を統治状態ととらえる見方は、統治されている状態を国家とみなすというもので、国家を主体的、活動的に把握しているとは言いがたい。そこで最近では、国家をひとつの人格のようにとらえ、ひとつの権利主体とみなす考え方が定説になった、と達吉は説明する。
国家人格説は、国家を法人(集合人格)とみなす考え方だといってよい。世代交代によって君主や臣民が入れ替わっても、法人としての国家は存続する。君主は国家の外に立つのではなく、国家の内部に不可分な存在として位置づけられる。さらに、国家はそれ自体が活動能力をもつ主体とみなされる。ただし、国家という法人の特徴は、唯一の統治権力をもつことであって、その点は同じ法人であっても地方団体とことなるところに注意しなければならない。
したがって、統治権の主体は君主の一身ではなく、国家そのものにある。たとえ法律に統治権は君主に属すると記されていても、近代の国家思想においては、君主は自己一身の利益のために統治権を発揮することはできない。
国家はどのように発生し、消滅するのか。
西洋では、国家が発生するのは、国民が契約を結んで国家団体を形成し、その自由の一部を割いて、国権に服従するという考え方がある。だが、それは誤った前提にもとづくもので、契約説は歴史的にも論理的にも国家の起源を説明するものではない。人が共同生活を営むのは、自然の要求であって、契約によるのではない。領土、国民を統一する権力は自然に生まれたとみるべきだろう、と達吉はいう。
といっても、契約や法律によって国家が生まれた例がないわけではない。アメリカ合衆国やドイツ帝国などもそうだ。多くの州が連合して国家がつくられた。
いっぽう、統一的な権力が失われ、国民や領土がなくなった場合には、国家は消滅する。現在の政府が転覆され、これに代わる政府が成立しないときは、国家は事実上その存在を失ったものといえる。
そう述べたうえで、達吉は近代国家を成立させる前提となっている法について説明する。法には公法と私法があるという。公法とは、国家と国家および国家と国民の関係、国家の組織を定めた法であり、私法とは国民と国民との個人相互間の関係を定めた法である。
公法は国家の権力の発動に関する法律であって、国家にたいする国民の権利、義務を定めたうえで、権力の恣意的な発動を抑制するためのものでもある、と達吉は論じている。
法には制定法と慣習法があるが、近代においては立法の発達に伴い、慣習法は次第にその価値を減じ、国家の制定する法を法とするという考え方が一般的になっているという。
まだはじまったばかりだが、こんなふうに達吉の講義は、一部の隙もないほど論理的に組み立てられていることがわかる。いまそれをことごとく紹介していては、それだけで1冊の本になってしまう。そこで、以下は注目すべき箇所にだけいくつかスポットライトをあてるにとどめよう。
憲法について、達吉はこんなふうに述べている。
憲法とは国家の基本法であり、国権の組織と行動に関する大原則を定めた法をいうが、立憲国の憲法は代議制を認め、議会を国権に参与させることを根本としている。
ヨーロッパでは、ほとんどの国が成文憲法をもっている。それは近代に発達したもので、18世紀以降に生まれたものだ。アメリカ合衆国に発し、フランス革命によって伝播し、それがついにわが国にも及んだといえる。
帝国憲法が主にプロイセン憲法を模範としていることはよく知られている。プロイセン憲法の特徴は、議会の権限が国内の関係にとどまり、外部に関しては国家的行為がすべて君主の名でおこなわれることである、と達吉は論じている。
憲法は最強の効力を有する国家の法であって、これを変更するには憲法改正の法律にもとづかなければならない。ただし、解釈の変更、あるいは新たな法の制定によって、事実上、変更と同様の結果を生じることはありうるとも述べている。
統治権をもつのは、近代においては国家のみである。一般に権力は命令を発することができるが、それを強制することはできない。それは会社でも学校でも同じだが、命令に従わない個人にたいし懲戒処分をおこなうことはできても、その個人は同時にその集団を脱退する権利をもっている。ところが統治権は命令にたいする服従を強制することができ、これに違反する場合は個人を抑留することができる。中世の時代とは異なり、今日の国家においては、国家以外に国家の権力から独立した統治権はどこにも存在しない。
統治権は不可分である。三権分立は権力を分割するものではなく、あくまでも唯一の権力を行使するにあたって、その機関を分立したものである。ただし、機関はどのように分立したとしても、そのために権力の統一が妨げられることはない、と達吉は述べている。
つづいて、主権という概念が説明される。主権という概念が生まれたのは中世のフランスにおいてであり、それは教会や封建諸侯などの権力に掣肘されない最高権という意味をもち、その権力はもっぱら君主に属していた。そして、18世紀にいたるとルソーにみられるように、国家のすべての権力は国民に属するべきだという考え方が登場する。
しかし、主権の本来の意味は、外部の力によって抑制されることのない国家の権力ということだ、と達吉は説明する。したがって、君主主権説か国民主権説かというのは、政治上の主義の問題であって、主権概念とはほんらい無関係である。
主権は国家権力、ないし国家の最高機関、あるいは統治権と同じ意味で用いられている。しかし、厳密にいえば、主権とは、国家の権力が最高かつ独立の性質をもつことにほかならない。すなわち国家の権力が内部においては最高の位置にあり、外部にたいしては独立しているときに、国家の主権は保たれているということができる。
国家の権力は無制限というわけではない。国家は対外的には国際法、対内的には国法によって拘束され、国権はその法律のもとにおいてのみ活動することができる。そして、逆に統治権があっても主権のない国家が存在することをみれば、主権がかならずしも国家存立の必須要件ではないことも追述されている。
達吉はさらに国家について論じる。国家は無形の団体であって、それ自体が意志や能力をもつわけではない。それを動かしているのは人間であって、その集合的意志が国家の意思となり、国家の機関をかたちづくっている。
国家の機関は人格をもつものではなく、国家のために国家の意志と権利、義務を実行に移すことを目的としている。国家の機関に属する者は、もちろん個人としての意思をもっている。だが、かれらは議員であれ、官吏であれ、たとえ君主であっても、あくまでも自己の意思や権利を唱えるのではなく、国家を代表して国家のために、それぞれその統治権を発揮するのである。
近代において、君主が国家の機関だということは、国家が統一的団体であることから生じる論理上、当然の結果である。もし近代国家においても、君主は国家の機関ではなく、みずから権利の主体だというのならば、それは国家の統一的団体としての性質を破壊するものだ、と達吉はいう。
専制君主国においては、直接の国家機関は君主のみであって、残りの国家機関はすべて間接機関である。しかし、立憲君主国においては、直接機関はふたつ以上あり、君主と議会は等しく国家の直接機関である。国家の直接機関は必ずしもひとつである必要はない。立憲君主国においては、たとえ条文に君主がその一身をもって統治権を総攬すと記されていても、学理上はそうしたことはありえない。要は、国家が国家としての統一された意志を有することが重要なのだ、と達吉は述べている。
国体についても触れている。大きく分ければ国体は君主国と共和国に区別される。それはさらに細かく分類されるだろう。ただし、近代の立憲君主国の特徴は、最高機関である君主のもとにそれと相ならんで代議制度をもつこと、君主の国務上の行為はかならず国務大臣の副署を必要とすること、司法権が独立していることだという。
達吉が日本は近代の立憲君主国であって、中世の君主国ではないと主張していることはいうまでもない。
退屈かもしれないが、もう少し、その講義に耳を傾けていただけるとありがたい。
2022-03-16 10:17
nice!(7)
コメント(0)




コメント 0