荻生徂徠『政談』をめぐって(1)──商品世界ファイル(23) [商品世界ファイル]
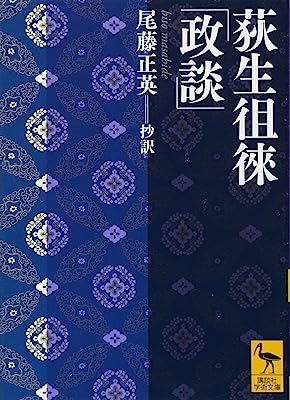

荻生徂徠(おぎゅう・そらい、1866〜1728)は、同時代の新井白石と並び称される江戸時代屈指の儒者といってよいでしょう。医者をしていた父が、仕えていた館林藩主徳川綱吉(のち5代将軍)の怒りにふれ江戸から放逐されたため、14歳から27歳まで母の実家があった上総の長柄(ながら)郡本納(ほんのう)村(現千葉県茂原市本納)で過ごしました。
27歳(本人の言では25歳)で江戸に戻り、塾を開き、31歳になって川越藩主の柳沢吉保に仕えます。44歳のとき、藩邸を離れ、茅場町に住居を定め、多くの門人を育てました。50代半ばから徳川吉宗に重用され、幕府の政治について意見を求められるようになります。その意見をまとめたものが今回紹介する『政談』です。おもな著書としては、ほかに『弁道』『弁名』『論語徴』『太平策』などがあります。
江戸時代、儒学の主流だった朱子学を批判して、独自の古文辞学(徂徠学)を開いたことで知られます。「道として民を利することができなければ、それを道と呼ぶことはできない」というのが、かれの信念です。
『政談』はあるべき国家の制度や政道を論じた著作といえるでしょう。その根底には、乱れた政道をただすという意識があります。悪いのは、はっきりいうとおカネの世だ、と徂徠は考えています。これを統制することこそが政治の役割だというわけです。
幕府の封建体制と武士による秩序維持こそが課題でした。商品世界の自由なはばたきは許されず、経済はあくまでも武士的秩序にしたがわなければなりません。
それにしても、近ごろの世の乱れはいったいどうしたことでしょう。
国の秩序を守るには、人に道義を説いたところで、何の解決にもならない。筋道だった計画、新たな制度が必要だと徂徠は断言します。
近ごろ多くなった盗賊や追いはぎ、たちの悪い浮浪者、子捨て、死体遺棄などにはどう対処したらいいのでしょう。たいていの人は、ともかく自分だけが難を逃れればいいという考えで、家の塀の外には関心がありません。お上まかせということになります。そこで火付盗賊改(ひつけとうぞくあらため)や道奉行の登場となるのですが、少ない人数ではとても江戸市中すべてを見まわるわけにはいきません。
ここでおもしろいのは、盗賊奉行が直接、刑を執行する現在のやり方はやめたほうがいい、と徂徠が進言していることです。その理由は、同心や与力が犯人から時に賄賂を受け取って、好き勝手に手心を加えてしまうからだというのです。さらにその配下の目明しというのが輪をかけてたちが悪く、さまざまな悪事をはたらいて、人からカネをせびりとります。
みんな安い給料で生活が苦しいのです。そこで、役職にかこつけて、取り締まる相手から賄賂をもらい、多少の悪さはお目こぼしとあいなります。
これには、さすがの徂徠もお手上げです。
そこで、徂徠が提案するのは、町の戸締まりを強化することです。町ごとに木戸を設け、木戸番を置き、捜査や出産など、やむを得ない場合を除いて、夜間には町の木戸を閉めようというのです。これだとたしかにドロボーや辻斬りは減るかもしれませんが、夜間外出禁止令みたいで、すこし窮屈ですね。
さらに、徂徠は番方(ばんかた)の活用を提案します。
番方とはいったい何でしょう。
いちおう説明を加えると、幕府の役職は「役方」と「番方」に分かれています。財政、司法、行政などの実務にたずさわるのが役方、これにたいし番方は軍事を担当します。この番方が住んだのが番町。一番町から六番町まであって、いまもその地名が残っています。
江戸の町は武士と町人の住む地域がはっきり区別されていました。ところが、武士の住む地域でも、ほんらい番方が住んでいた番町に、近ごろは役方も住むようになりました。これも平和がつづくうちに、軍事より実務が優先されるようになって役方がのしてきたからだ、と徂徠はなげきます。
もし町の治安を考えるなら、番町に軍事機能を集中させて、番方の暇をもてあましている先手組(さきてぐみ)や持筒組(もちづつぐみ)の連中に、交代で江戸市中を回らせたらいい。いわば武装警官が町中に目を光らせるようになれば、悪人連中もみだりに動けなくなるだろうというわけです。
出替わり奉公人というのも、やっかいな存在でした。
奉公人というと商家を想像しますが、じつは武家にも奉公人がいました。江戸は武士の多いところで、人口の半分が武士とその家族だったといわれます。ですから、江戸では武家の奉公人も多かったのです。
出替わりは1年契約の非正規雇い。3月5日が契約の更新日と定められていましたが、1年限りでなく長く奉公する者もいました。江戸時代も中期になると、武家も給金を払って毎年、奉公人を雇うようになっていました。代々家来を養っていくだけの余裕がなくなっていたからです。
ところが、この出替わり奉公人というのが、給金を前渡ししたとたんに遁走するわ、トラブルを起こしてぷいといなくなるわ、カネを持ち逃げするわで、主人が頭をかかえることがしばしばでした。
徂徠はカネ中心の世界が政道をダメにしているとみています。江戸はいまや北は北千住、南は品川まで家つづきのありさま。そこで、徂徠はこの『政談』において、みずからの思想性をかけ、封建秩序を立てなおす方策を提言することになります。
こんなふうに論じています(尾藤正英訳)。
〈現在とるべき方法としては、政治の根本に立ち返って、やはりいまの柔弱な風俗をもとに戻し、古代の法制を勘案して、法を立て直すのが何よりである。政治の根本に立ち返って法を立て直すとは、どういうことかといえば、中国の夏殷周という古い時代でも、また新しい時代でも、あるいは日本の古代でも同じことであるが、政治の根本は、とにかく人を地に着けるようにすることであって、これが国を平和に治めるための根本なのである。〉
カネに振り回される世の中から脱して、「とにかく人を地に着けるようにすること」だというのです。
徂徠はいいます。最近はだれもがいわば「旅宿の生活」をしており、根無し草のように暮らしていることが世の乱れを引き起こしている。人を地につけるというのは、決まった土地に人を定着させ、そこでしっかりと生活できるようにし、ふらついた生き方をさせないようにするということだ、と。
政治の根本は「田舎では農業、都市では工業や商業に勤労しない者が一人もいない」ようにして、「親密な協同社会をつくる」ことだとも書いています。そのためには、きちんと戸籍をつくって、勝手な移住は許さず、だれがどこに住み、どんな仕事をしているかを把握しなければなりません。そうすれば、地域社会の交際も親密になり、風俗も矯正されて、悪事も減るだろうといいます。
とうぜん浪人や乞食坊主、陰陽師、遊女、役者など、地に着かぬ者にたいする扱いは、厳しいものとなります。
江戸の人口は制限されなければなりません。関八州(現在の関東地方)で生産される米穀の余剰で暮らしていける人数に限定されます。こうして江戸の人口枠が決まると、それを超す人数は「人返し」によって元の出身地に返してしまう措置がとられます。
しかし、人を地に着けるというのなら、率先してその範を示すのは、武士でなくてはならないはずです。
「武士の道を再興し、世の中の贅沢を押さえ、武家の貧窮を救う」には「武士を知行所に置かなくてはならない」と、徂徠はいいます。
江戸幕府ができたときから(いや厳密には豊臣時代から)、武士は知行地(領地)を離れて城下に集住し、主君に仕えるようになっていました。その代わり、たいてい年3回、切米と称して、石高該当分にあたる俸禄を現金で支給されていました。これは各藩の武士だけではなく、幕府の旗本や御家人でも同じです。武士が与えられた領地に在住することはなくなりました。武士が公務員化したともいえるでしょう。
それでは知行地のほうはどうなったかというと、幕府の場合は代官、藩の場合は名主や庄屋が、村のまとめをし、年貢の取り立てにあたっていました。代官の身分は下級武士ですが、名主や庄屋は百姓の身分です。
徂徠は、こういう支配体制がいけないと苦言を呈します。武士が江戸暮らしや城下暮らしをしていると、どうしても費えが多くなり、町人が潤うばかりで、田舎では百姓が領主を軽んじることになるといいます。万一、飢饉がおこれば、村の治安が不安定になり、強盗や馬泥棒が出没する恐れもあります。しかし、武士が領地にいれば、そんな事態にはなりません。
徂徠は田舎暮らしの効用を力説します。これはかれが青年期を上総の地ですごしたことと無縁ではないでしょう。
田舎暮らしをすれば、おカネはかからないし、贅沢もせず、怠惰にもならず、毎日、野原を駆け歩いて元気になる。それに知行地の田畑や治水工事の様子もよくわかり、百姓の内情にも通ずるようになるから、武士が悪徳代官のように、むごい年貢の取り立てなどもしなくなる。もし江戸城でどうしても勤務しなければならないのなら、1カ月交代とか百日交代にして、妻子をともなわずとも、じゅうぶん勤められるだろう。そんなふうにいいます。
武士が田舎に移ると、それにともない地元でも武芸や学問がさかんになるはずだ。医者だって、せちがらい江戸を捨てて、田舎に移ってくるかもしれない。武士が知行地に戻るのは、いいことづくめ。「軍兵の数も昔のとおりになって、日本古来の武勇の風が再現されるであろう」。こんなふうに、徂徠は田舎暮らしを絶賛します。
もちろん、徂徠の構想は実現しませんでした。百姓も主人である武家の帰還は迷惑千万だったにちがいありません。武士自身も都会暮らしの楽しさを奪われたくはなかったでしょう。
徂徠はそのすべての思想性をかけて、封建体制をむしばみつつある商品世界の浸透に抵抗します。そんな徂徠を歴史家の野口武彦先生は「江戸のドン・キホーテ」と呼びました。しかし、それは嘲笑ではありません。ドン・キホーテは反近代に固執することによって、近代の虚妄を暴く鏡の役割をはたしたのですから。
2023-07-22 16:09
nice!(12)
コメント(0)




コメント 0