ハーヴェイ『経済的理性の狂気』を読む(1) [商品世界論ノート]
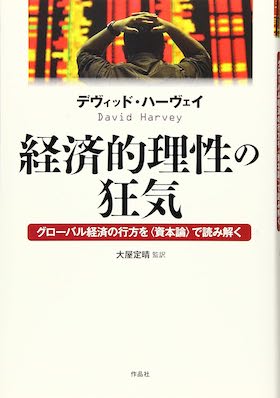
デヴィッド・ハーヴェイは多作である。専門は経済地理学だというが、マルクスの『資本論』を再評価し、現在の経済社会に大きな疑問を投げかけたことでも知られる。拙ブログでも、これまでかれの『資本の〈謎〉』、『〈資本論〉入門』、『〈資本論〉第2巻・第3巻入門』を紹介してきた。
今回取りあげるのは、かれが82歳のときに出版した『経済的理性の狂気』である。本書も『資本論』にもとづいて現代経済社会を批判しているといってよいが、その緻密な論理をたどるのは、ぼくにはいささか荷が重い。あまり深入りせず、できるだけ軽く紹介するにとどめたい。毎回読めるのはわずかのページにすぎないだろうが、ぼくの頭ではついていけない懸念もある。
それにしても、ハーヴェイの切れ味はなかなかのものだ。日本では、マルクス・ルネサンスといえば、斎藤幸平の名前が挙がるが、ぼくにはデヴィッド・ハーヴェイやナオミ・クライン、トマ・ピケティのほうが、より本格的な気がする。
なにはともあれ最初から少しずつ読んでみよう。
「マルクスは第一級の理論家、研究者、思想家であるだけでなく、活動家であり論客であった」とハーヴェイは書いている。
これにはほとんどだれも異論がないだろう。だが、マルクスはけっして過去の理論家ではない。「資本」を研究し尽くしたマルクスは、資本がますます重要性を帯びる21世紀のいまも大きな「問い」を投げかけているのだ。
〈マルクスは、資本の運動法則とその内的諸矛盾、その根底的な非合理性について予見に満ちた解釈を示したが、これは、現代経済学の皮相なマクロ経済諸理論よりも、はるかに鋭敏で洞察力のある説明であることがわかっている。……その洞察は取り組まれるに値するし、まったくしかるべき真剣さをもって批判的に研究されるだけの価値がある。〉
ハーヴェイはマルクスの『資本論』が、いまでも真剣かつ批判的な研究に値すると書いている。
そもそもマルクスの資本概念と資本の運動法則とは、いったいいかなるものだったのか。
マルクスの功績は、「運動する価値」として資本をとらえたことにある、とハーヴェイはいう。
資本の運動の流れは、簡単にいうとこうだ。
(1)資本は生産手段(原料や半製品、機械、道具、設備その他)と労働力を市場から調達する。
(2)資本は調達した生産手段と労働力によって、商品を生産する。
(3)資本によってつくられた商品には、最初に前貸しされたものより多くの価値(剰余価値=儲け分)が含まれている。
(4)資本はその商品を販売して、貨幣を回収するが、そこには利益も含まれている。
(5)資本はその貨幣をふたたび資本として、また商品をつくるという過程を繰り返す。
これが資本の循環である。資本は貨幣としてはじまり、商品にかたちを変え、それがふたたび貨幣となって戻ってくる。すると、その一部が賃金や利子、地代、税金、利潤などに分配されたあと、また商品をつくる過程が繰り返される。ただ、それが単なる循環と異なるのは、資本の流れが「絶えず拡大するスパイラル運動」となることだ。しかも、資本は少しもじっとしておらず、たえず「変身」をくり返していることがわかるだろう。
資本は「運動する価値」だという。ここで引っかかるのは「価値」という用語だろう。「価値」とはいったい何か。価値は目に見えない。じっさいそこにあるのは、原料やはたらく人や機械、さらにはできあがった商品、そして商品を売ったお金などである。だが、そのなかには絶えず変身しながらも、一貫して保持され、実現される力の作用がある。それが価値だといってよい。
価値とは値打ちである。あの材料には値打ちがある。あの男には値打ちがある。あの商品には値打ちがある。お金には値打ちがあるという言い方はふつうになされるだろう。しかし、その値打ちはいったいどこから生まれてくるのだろう。材料がそのまま放置され、男がちっとも働かず、商品がまったく売れず、お金があっても買えるものがなければ、それらにはまったく価値がない。価値は動き関係することによってしか生じない、目に見えない何かだということができる。
さて、のっけからややこしいことになってきたけれど、価値は経済社会を成り立たせている根源的要素とみることができる。マルクスは価値の根拠を「社会的必要労働時間」ととらえた。とはいえ、ここに労働至上主義的な色彩を感じる必要はないだろう。
人がはたらかなければ、経済社会は成り立たない。経済社会が成り立つのは、人がはたらいているからである。資源にしても、材料にしても、機械にしても、貨幣にしても、人が存在していなければ、それらはそれ自体、何の価値もない。価値をつくりだすのは人である。資源にしても、原料にしても、労働力にしても、機械にしても、商品にしても、お金にしても、人がそこに価値をみいださなければ、そこに価値はない。人は価値あるものを生みだし(あるいは見いだし)、その価値あるものを使い、用い、味わい、消費することによって経済社会を営んでいる。マルクスはその価値が人のはたらきによってしかつくられないことを、あらためて確認したといえるだろう。
近代を動かしてきたのは「資本主義」だと言われれば、そのことにだれもが反対しないだろう。しかし、なぜそれは資本「主義」なのだろうか。端的にいうと、「資本主義」とは、国家が推進する資本のイデオロギーにほかならない。マルクスは『資本論』において、国家を抜きにした純粋資本の論理を追求した。だが、近代のはじめから、資本は国家の支援を受けていたといってよいのではないだろうか。
資本には「近代」をつくりだす力があった。ハーヴェイは資本を「運動する価値」と理解し、それがなぜ「推進力」をもっているのかを説明しようとしている。
資本が「運動する価値」であるのは、それが貨幣から商品、そしてまた貨幣へとたえず変身を繰り返し、やむことなくみずからを再生し、しかもその再生によって強化、拡大されていくという「推進力」をもつからである。
資本の拡大は資本を擁する一企業にとどまらない。資本はたえず変身しながら、無数の新たな分身をつくり、社会全体(ならびに国家)を巻きこみ、社会そのものを変えていく。資本のつくりだす先兵は商品にほかならないが、そのかずかずの商品こそが、その同行者である貨幣とともに、人の生活や生き方、時間と空間、環境などをはじめとして、社会そのもの、さらには国家のかたちまでを変えていくのである。
マルクスははじまったばかりの近代において、資本の尽きることのない推進力に直面し、その脅威と困難を克服する方向を探ろうとして、『資本論』を書いた。『資本論』は未完のままに終わり、「資本の時代」を克服するという課題もまだ達成されていない。強権的な政治によって、「資本主義」をねじ伏せようとした「社会主義」のこころみは、資本の返り討ちにあってしまった。それでもマルクスの課題は、いまも残されたままだ。ハーヴェイはおそらくそんなふうに考えている。
本書の第1章では、資本が変身を繰り返し、拡大しつづけることが大きなテーマになっている。
資本はまず貨幣(資金)として登場する。その貨幣は生産手段(原材料や半製品、機械、道具、工場、設備など)と労働力に姿を変え、貨幣としては消滅する。この段階では資本は生産手段と労働力に変身している。
次に資本は生産手段と労働力を使って、商品を生産する。重要なことはこの商品に剰余価値が含まれていることである。資本はもうからない商品はつくらない。そのもうけがどこからでてくるかというと、労働力によってでしかない。この段階では資本は商品に変身している。
そして、資本が変身した商品は、市場に回され、販売されて、貨幣となって戻ってくる。このとき資本によってつくられた商品は消費財(賃金財)とはかぎらない。奢侈財や生産手段でもありうる。だが、いずれにしても、市場に流れることによって、資本は商品から、ふたたび貨幣へと変身するのである。
無事、貨幣へと環流した資本は、その一部を労働力と生産手段の購入に回し、ふたたび商品の生産に着手する。だが、商品の販売によって獲得された貨幣にはすでに剰余価値が含まれていた。その剰余価値は、税金や利子、賃貸料、使用料、地代、利潤、さらには賃金や生産手段の追加分などに回される。ここで重要なのは、環流した貨幣が資本の分身として、社会全体にちらばっていくことである。
以上はごくごく簡略化した資本のモデルにすぎない。だが、経済的理性はなぜ狂気へと変わっていくのか。ようやく第1章がはじまったばかりである。
2024-01-29 16:05
nice!(9)
コメント(0)




コメント 0