丸山真男の1968年──『丸山真男と戦後民主主義』(清水靖久著)を読む(1) [われらの時代]
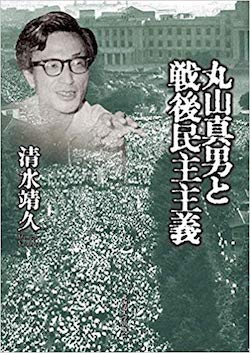
野次馬的な見方で恐縮だが、丸山真男(眞男)といえば、60年安保闘争と68年東大闘争(紛争)のイメージが思い浮かぶ。それは、かっこいい丸山と、かっこ悪い丸山である。
自民党の横暴にさっそうと立ち向かう丸山と、全共闘に研究室を荒らされてうろたえる丸山。そのイメージはまさに分裂し、容易に結びつかない。
だが、その分裂をつなぐものがあるとすれば、それは「民主主義」という概念ではないだろうか。岸信介政権も全共闘も、丸山にとっては民主主義を破壊する存在にほかならなかった。民主主義を旗印にかかげる丸山は、岸政権には敢然と立ち向かったが、大学内からわきおこった全共闘の学生には狼狽を隠せなかったのである。
最初に野次馬的と書いたけれど、たしかにぼくなどは野次馬にちがいない。60年安保闘争にも東大闘争にもかかわったわけではない。商店街の息子が東京の私立大学に入学し、ろくに授業にも出ず、レポートでようやく卒業し、漫然と会社勤めをしただけの人間である。丸山政治学にもうとい。もちろん、ご本人と会ったこともない。
こうした経歴からすると、戦後思想の細部にわたる本書は難解だし、わずらわしくもある。はたして、どこまでついていけるか、自信がない。例によって途中で投げだす公算も大だが、残っているのは、1968年の丸山を眺めてみたいというのぞき根性だけである。
そこで、当方の唯一の武器である「暇」を活用して、のんびり読み進めていくことにする。無知と無恥による誤解はご容赦のほど。このブログを書くのは備忘のためであって、書いておかないと、2、3日前のこともすっかり忘れてしまうぼくの脳天気状態によることもご承知のほど。
本題にはいる前に、まず「60年安保と丸山真男」に焦点を合わせてみよう。
本書によると、60年安保闘争後の1964年に、丸山は代表作『現代政治の思想と行動』増補版に「大日本帝国の『実在』よりも戦後民主主義の『虚妄』の方に賭ける」と記したという。
この人には、学者に似合わず、こういうことばの見得をしてみせるところがある。丸山神話の生まれるゆえんだろう。
ところが、このことばの意味がよくわからない。
著者の清水靖久は、この一節にこだわるところから本書をはじめている。
丸山が大日本帝国の政治体制、とりわけかつてのファシズム体制を支持するはずはなかった。支持したのは戦後民主主義のほうである。
わかりにくいのは、戦後民主主義の「虚妄」に賭けるという言い方である。
当時60年代半ばには、戦後民主主義は占領民主主義であり、それを虚妄とする見方が登場していた。丸山の寸言は、それを逆手にとり、むしろ反語によって虚妄説に反撃した、というのが著者のとらえ方である。
日本では戦後、民主主義がアメリカによって与えられた。
丸山にいわせれば、その民主主義は「人民主権と平和憲法」を基本としていた。そして、たとえアメリカによってもたらされたにせよ、民主主義の構想自体は正しい、と丸山は考えたのである。
だが、「人民主権と平和憲法」はまだ実現されたとはいえない。民主主義はまだ「虚妄」にとどまっている。そこで、民主主義の本来の姿である「人民主権と平和憲法」の実現に向けて努力することが、これからの政治のあり方であり、丸山はみずからもその方向に「賭ける」ことにした。
それがおそらく「大日本帝国の『実在』よりも戦後民主主義の『虚妄』の方に賭ける」というメッセージの意味である。
著者によれば、60年代半ばから「『戦後民主主義』は貶(けな)し言葉でもあれば褒(ほ)め言葉でもあって」、「愛憎相半ばする」言葉になっていたという。それを擁護する者もいれば、反対する者もいた。実際、一部の左派と右派が民主主義を攻撃していた。
そうしたなか、丸山の悲壮感すらただよわせる宣言は、多くの反撃を招いたけれど、けっして丸山に孤立をもたらしたわけではなかった。小田実や加藤周一は丸山を支持している。これにたいし、江藤淳は戦後民主主義を「新しい国体」と批判した(とはいえ、江藤は大日本帝国の体制を否定していたわけではない)。
丸山の基本的な立場は、社会主義でも国家主義でもないリベラル・デモクラシーととらえるべきだろう。
丸山は極端な右派はもちろん左派にも批判的だった。
「民主主義ってのは、制度と運動の統一なんです」と語っている。制度を守るだけではなく、制度を変えていく運動(抵抗)がだいじだと考えていた。
「丸山は、戦後民主主義には賭けなかったとしても、戦後、民主主義に賭けたし、日本社会の民主化をめざして思索してきた」と、著者は記している。
丸山はアメリカに強制された占領民主主義を支持したわけではない。戦後の日本において、民主主義そのものの理念を推進しようとしてきた。60年安保では「永久革命」としての民主主義を唱えている。それは国家権力を奪取する革命というより、民主主義制度を拡充していく永久運動を指していただろう。
著者は、丸山の考え方を次のように説明する。
〈[民主主義は]完全に制度化されたら「国体」のようになるが、他方で制度化がなければアナーキーになるという。それゆえ民主化の契機を保ちながらアナーキーを避けるためには、一方では正統概念としての「国体」から民主主義を区別する必要があった。他方では民主主義を混沌としないように、極左派の異端好みを批判しなければならなかった。〉
1965年8月15日の集会で、丸山は日本が「平和主義の最先進国」になったことが「20世紀最大の皮肉」だと述べている。丸山にとって民主主義は「国体」ではなく、「反対や否定を通じて」鍛えられる制度=運動にほかならなかった。
ここまでが、第1章の要約である。まだ先は長い。
ここで、余談ながら、少しだけ、68年のころのぼくらの感覚を述べておくと、ぼくらはすでに民主主義に丸山のようなロマンを感じていなかったような気がする。
ぼくらにとって、民主主義とは要するに代議制民主主義のことで、選挙によって、議員を議会に送りだす政治制度にすぎなかった。その民主主義に魅力を感じていたかというと、そんなことはまるでない。政党の立てた候補を選択する選挙は、とりわけ共感する政党がない場合、ただの押しつけられた義務になってしまう。選挙で政治が変わるなどとは思っていなかった。これが民主主義に賭けた丸山と、民主主義にしらけたぼくらとの大きなギャップだったかもしれない。
こんな低次元の感想はどうでもよろしい。第2章に進むことにしよう。
2020-01-28 17:09
nice!(8)
コメント(0)




コメント 0