橋川文三の日本ファシズム論をめぐって(1) [われらの時代]
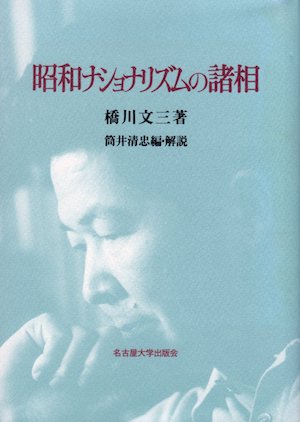
早稲田大学雄弁会にはいっていたころ、全関東学生雄弁連盟(略称、全関)という団体があり、雄弁会の全関幹事をつとめたことがある。1969年か70年のことではなかったろうか。
全関の最大イベントは、関東地区のいくつかの大学弁論部に所属する学生が集まって、弁論大会を催すことだった。しかし、あのころ、どこかの講堂で大規模な弁論大会を開いた覚えはなく、新宿や渋谷の街頭に立って、学生たちが沖縄問題などについて訴えるのが全関のイベントになっていた。
人前で話すのが苦手なぼくは、弁士としてはまったくさまにならなかった。たぶん、わけのわからないことを、もごもごと恥ずかしそうに話して、みんなにあきれられていたのだろう。
しかし、全関幹事を担当してよかったのは、さまざまな大学の弁論部のメンバーと知りあえたことである。当時、全関の委員長は青山大学の学生だった。かれの誘いで、バリケード封鎖された青学構内を訪れたことが記憶に残っている。
印象深いのは1970年の拓殖大学闘争を闘った拓大雄弁会の連中だった。かれらは中曽根康弘が総長をつとめる右翼色のつよい大学のなかで、民主化を求めて闘っていた。ぼくも拓大構内にはいったし、いっしょに三里塚闘争の支援におもむいたこともある。
あのころの雄弁会は、少なくともぼくにとっては、弁論より闘争だった。そうした雰囲気は、たぶんどこの大学の弁論部にもただよっていた。重信房子が一時、明治大学雄弁部に属していたことをみても、季節は明らかに闘いに傾いていたのだ。
とはいえ、ぼくなどは、けっきょく流されるまま、周辺をうろうろしていただけである。傍観者といわれても仕方ない。
政治活動にはまるで向いていなかった。かといって、研究者になれるほどの頭もなかった。ぼくがこだわっていたのは、雄弁会のなかで、現代社会研究会(現社研)と名づけた研究会をつづけることくらいで、あのころは江上寿美雄君や川村晃司君、岩橋明時君などと『ドイツ・イデオロギー』などを読んだりしていた。
70年11月8日の早稲田祭に参加したことを覚えている。たしか、テーマは「民族問題」だったが、意見はまとまらず、みんな好き好きに話していた。
全関の関係もあって、当時は早稲田の雄弁会と慶応の弁論部との交流が盛んだった。早慶の弁論大会を開いたこともあったのではないか。
この年11月21日の三田祭で、慶応の弁論部は、たしか日本社会論をめぐってティーチインを開くことになっており、これに早稲田の雄弁会のメンバーも何人か呼ばれることになった。
それに先立ち、本郷の更新館で打ち合わせの会があり、慶応からは中村稔君と手嶋龍一君など、早稲田からはぼくと江上寿美雄君、里見脩君、田畑正雄君などが参加した。
このときは60年安保や戦後民主主義をめぐる議論もおこなわれたが、慶応の人たちは神島二郎や橋川文三をよく読んでおり、日本人の戦争体験をどうとらえるかが話題になった。
手嶋君は、この年、日中学生友好会で訪中しており、文化大革命のことを話してくれた。佐藤政権批判とマルクス一本槍だったぼくが、日本人と戦争、中国の現状などについても興味をもつようになったのは、慶応の弁論部とのつきあいによるところが大きいのである。
三田祭のティーチインは中途半端なおしゃべりに終始し、けっして成功とはいえなかった。
ショックを受けたのは、その直後の11月25日に三島由紀夫が市ヶ谷の自衛隊駐屯地で割腹自殺したことだ。11月13日に雄弁会の早坂敏明君と東武百貨店で開かれていた三島由紀夫展をいっしょに見にいったばかりだったので、ショックはなおさらだった。
そのころから、ぼくはマルクスの『資本論』を読むかたわら、日本ファシズム(とりわけ北一輝)や日中関係にも興味をもつようになり、神島二郎や橋川文三、村上一郎、藤田省三、竹内好などの本を断片的に読みはじめた。だが、それはしょせん付け焼き刃にすぎず、内容の理解をともなわないムード的な読書にすぎなかった。
実際はといえば、これから何をしたらいいかわからないまま、怠惰にぶらぶらと毎日をすごし、雄弁会の後輩からうっとうしがられ、部室にもだんだん顔を出しづらくなりはじめていたのである。
1971年4月には、5年目の大学生活を迎え、大学中退の思いもちらほらと頭をよぎるようになった。しかし、いなかに帰って父親の衣料品店を継ぐのはためらわれ、せめてもう少し東京にいたいと思っていた。
できれば、どこかいい会社に就職しようというのではなかった。いずれ店の商売を継ぐのだから、就職のことはまるで考えていなかった。まもなく、あわただしい日常がやってくるのはわかっていた。しかし、その前に、もう少しだけ本を読んで考える時間がほしかったのである。
橋川文三の諸論考はそんなとき、ぼくのなかにすべりこんできた。
三島自決直後の松岡英夫との対談で、橋川文三はその死について、三島にはナルシシズムがあり、「錯乱の美学」、「残酷な死にざま」へのあこがれのようなものがあったと指摘しながら、「それにしてもなんだか腹が立ちますね」と語っていた(『毎日新聞』)。
その4年前、橋川は文藝春秋から刊行された「現代日本文学館」シリーズの『三島由紀夫』の作品解説として、「三島由紀夫伝」なるものを書いている。
三島が「ファシズム」に傾倒する「危険な」作家だという見方に反駁して、橋川は次のように論じていた。
〈三島はファシズムの魅力とその芸術上の危険とを、いかなる学者先生よりも深く洞察した作家である。ファシズムの下においては、三島の習得したあらゆる芸術=技術が無用となることを、彼はほとんど死を賭して体験した一人であるかもしれない。〉
橋川の言いたいことは、すっきりとはわからない。それはぼくがかれの代表作『日本浪曼派批判序説』を読んでいないためかもしれない。三島は日本浪曼派の影響を受けて、若くして作家になった。だが、その無残さを何よりも知っていたはずである、と理解すべきなのか。
さらに、三島のファシズムへの傾倒がポーズにすぎず、それが本心ではないことを三島はだれよりも自覚していたはずだ、と橋川は考えていたのだろうか。三島にはどこまでも現実に耐えつづけて文学を追究しづづけてほしかったという気持ちが、自死の直後の対談で「それにしてもなんだか腹が立ちますね」という発言になってあらわれたのだろうか。
「ファシズムの魅力」という言い方を橋川はしている。ファシズムには魅力があったという。ついには日本を戦争に導くことになったその魅力、あるいは磁力について、橋川は考えつづけたといえるかもしれない。
いったい、あれは何だったのか。それは戦後の民主主義時代に逆行する思考だった。しかし、ファシズムの魅力の正体に迫ることなしには、そこから抜けだす道もさぐれないのではないかと橋川が思ったとしても不思議ではなかった。
ぼくの手もとにはいま橋川文三の没後に編集された『昭和ナショナリズムの諸相』という本が置かれている。この本には単行本や全集に収録されていない論文も収録されており、編集と解説を担当した筒井清忠によると、本書は「ナショナリズムにかかわる多くの論点をあらためて考え直すための、そして現代ナショナリズム論の混迷からの脱出するための宝庫」だという。
すでに何もかも朦朧の境地に近いぼくが、大学生のころ橋川のどの本を読んだかは判然としない。図書館で1964年刊の『歴史と体験』を読んだのはたしかだ。この本には、戦前の知識人がいかにしてマルクス主義から離脱し、日本的土壌のなかに「転向」していったかが描かれていたはずだ。そして、それと入れ替わるようにして出てくるのが、文学的には日本浪曼派であり、政治的には超国家主義(ウルトラ・ナショナリズム)、すなわちファシズムだった、ということではなかったか。
いずれにせよ、あのころ橋川を読んだといっても、ただ読んだというだけで、その全体像を理解したわけではなかった。それに橋川自身も体系的な日本ファシズム論を残しているわけではなかった。出版社の求めに応じて次々と発表される論考は、果てなき挑戦の蓄積にほかならず、そのほんのひとかけらを、「われら」は知ったにすぎなかった。そして、その後の流される日々において、ぼくのなかで橋川の仕事は、遙かな記憶の片隅に押しやられていったのである。
あのころから遠く離れたいまになって、『昭和ナショナリズムの諸相』をベースにしながら、橋川文三の残した日本ファシズム論をもう一度概観してみようと思うのは、懐古趣味にとどまらない。何だか、実感として、ふたたびファシズムの季節がやってきそうな気配を感ずるからである。
最初に、はたして日本にファシズムがあったのかという問題がある。
日本にファシズムはなかったと主張する人は、日本にはナチスのような大衆政党はなく、ヒトラーのようなカリスマ的指導者もおらず、大衆による熱狂的な体制支持もなく、いっぽう戦争中でも国会選挙がおこなわれていたという。
しかし、ケネス・ルオフはこう書いている(拙訳『紀元二千六百年』、朝日選書)。
〈政治的にみれば、1940年の日本は、自由民主主義陣営の代表といえる米国や英国よりも、ずっとナチス・ドイツやファシスト・イタリアと共通性をもっていた。……国会は政治的機能を果たしつづけていたものの、そのころ日本のエリートは、日本には自由民主主義は合わないと主張するようになっていた。官民を問わず、日本人はユートピア的なやり方で国家を強化しようとしていた。その方法は、国家と国民を一体化しようとするもので、自由民主主義的というより、ずっと当時のイタリアやドイツのやり方と近かった。1930年代にドイツやイタリアの大物たちが、うらやましく感じたのは、日本には国民を隅々まで有機的に統合しうる、皇室を中心とする祖国崇拝がみられたことである。〉
これは、ほぼ納得できる見方だろう。
同じファシズムでも、イタリアとドイツ、日本ではその特質が異なることはまちがいない。それでも1930年代から40年代前半にかけてあらわれた日本の政治体制の特徴をファシズムと規定してもよいのではないか。それは国家主義的、軍事主義的、侵略的・抑圧的な体制だった。
丸山眞男はこうしたファシズムを超国家主義と名づけた。あえて日本の場合をファシズムといわず超国家主義と呼んだのは、どこかで日本のファシズムをドイツのファシズムと比較する(見下す)心理がはたらいていたのかもしれない。
丸山眞男の弟子である橋川文三の場合は、「昭和超国家主義」と呼んだり、「日本ファシズム」と呼んだり、概念の揺らぎがみられる。だが、日本ファシズムの研究にたいする橋川の姿勢は一貫しており、丸山のように日本の「超国家主義」を外在的に分析し、批判するのではなく、あくまでもそれを内在的に理解し、克服することをめざしていた。
丸山眞男は日本のファシズム(超国家主義[ウルトラ・ナショナリズム])の特質を、天皇制原理と家族主義、農本主義、大アジア主義に求め、これがドイツ、イタリアのファシズムとのちがいだと論じた。これにたいし、橋川は「昭和超国家主義の諸相」で、丸山の挙げているこうした特質は、明治国家のイデオロギーにちがいないが、それを極端化したものととらえただけでは、超国家主義、すなわち、日本ファシズムの実態を把握できないだろうと批判していた。
丸山の類型的・政治学的把握にたいし、橋川がもちだしたのは、あくまでも事件的・思想的な把握だった。
その事件はテロリズムからはじまっていた。だが、それはテロだけでは終わらない。原初のテロは集団的な昭和維新運動を呼びさまし、さらにその動きを圧殺した軍部・官僚による国防国家構想を生みだしていく。こうして、日本ファシズムが完成するとともに、総動員体制がはじまるのである。こうした屈折した歴史的な流れを、橋川は最初に思いえがいている。
それにしても、ファシズムの「魅力」とはいったい何だろう。次は橋川の諸論考に触れながら、その中心に踏みこんでみることにしよう。
2021-01-06 16:59
nice!(7)
コメント(0)




コメント 0