ハーヴェイ『経済的理性の狂気』を読む(3) [商品世界論ノート]
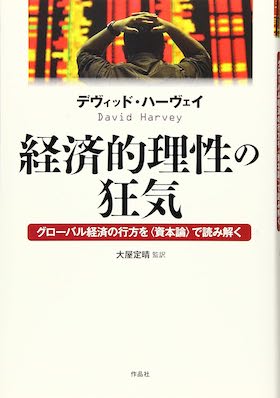
商品の価値は貨幣によってあらわされるという。それなら、貨幣はあくまでも商品の従者にすぎないはずだ。だが、その従者であるはずの貨幣がまるで主人のようにわがもの顔にふるまっているのはなぜか。
ハーヴェイは本書の第3章で、そうした貨幣の謎に迫ろうとしている。
価値とは目に見えないものだ。商品の価値、つまり値打ちは貨幣であらわすほかない。マルクスは価値の表象が貨幣なのだという。
商品に歴史があるように、貨幣にも歴史がある。たとえば、宝貝が貨幣として用いられた時代がある。それがいつしか金貨や銀貨が用いられ、紙幣があらわれ、最近は電子マネーや仮想通貨までが登場するようになった。
資本は貨幣から商品、そしてまた貨幣へと変身を重ねていくが、資本にとっての最大の困難は、たえざる変身の過程、すなわち資本の流通過程が妨げられることだ。
そこで資本の運動の連続性を確保するために、信用の役割が大きくなってくる。信用と貨幣、価値は連動している。信用もまた貨幣によって表現される。信用とは一定の時間の先に実現(返却)を約束された貨幣であり、その裏づけとなるのが商品の実現されるであろう価値にほかならない。
現前する貨幣だけではなく、将来実現が約束される貨幣(信用)を組みこむことによって、資本はようやく運動の連続性を確保することができるようになった。だが、それは資本が信用に組みこまれることでもある。資本は信用に束縛される。ますます貨幣への物神崇拝が強まる。貨幣はあたかも社会的権力であるかのように意識されるようになる。
近代以前、人びとは土地に縛られていた。それにたいし、近代の資本主義時代において、人びとが縛られているのは貨幣である。もし共産主義時代がくるとするなら、それは貨幣に縛られない時代になるはずだ。それがマルクスのえがく遠い未来図だった。
それはともかくとして、19世紀半ばには、貨幣をめぐってプルードンとマルクスをめぐって、激烈な論争が交わされた。働いても働いても労働者は貧しく、資本家はぬくぬくと豊かな生活を送っているのはなぜか。
プルードンは労働者が労働時間分の賃金をもらっていないことが原因だと考えた。そのためには貨幣を改革して、労働者に労働時間票を発行するか、働いた時間を示す鋳貨で賃金の支払いをおこなわなうようにすべきだ。さらに労働者に無償信用供与をおこない、相互信用制度も創設して、助けあいの社会をつくらねばならない。
マルクスはこうしたプルードンの考え方に反発する。価値の根拠となるのは社会的労働時間であって、労働時間そのものではない。どの労働者にも働いた時間分だけ支給するという労働時間票などは荒唐無稽である。しかも、資本家と労働者という生産関係をそのままにして、労働時間分の賃金をよこせという発想は、現在の階級関係をそのまま容認するものだ。めざすべきは、生産手段を共同で保有する協同社会(アソシエーション)でなければならない。
マルクスは『経済学批判要綱』のなかで、プルードン派のダリモンの所説を批判している。貨幣を改良するだけでは、現在の生産関係と分配関係を変革することはできない、とマルクスは断言する。
だが、それにつづいて、こんなふうにも述べている。
金属貨幣、紙幣、手形や小切手、さらには社会主義的に構想された労働時間貨幣などと、貨幣にはさまざまな形態がありうる。そして、じっさい、ある貨幣形態がほかに比べて、より扱いやすく、より不便が少ない場合もあるだろう。つまり、ふだんの買い物には紙幣が便利であり、国内の決済には手形が便利だというように。ただし、労働時間貨幣が通用するかどうかはわからない。
ハーヴェイも「貨幣形態の技術とその活用は、資本の歴史をつうじて何度か大きく変わっている」と指摘する。そして、現在はネットバンキングやビットコインなどみても、「貨幣形態のおける革命が進行中かもしれない」と述べている。
マルクス自身も、貨幣形態の変遷とそれが社会におよぼす影響に気づいていた。
資本主義時代がはじまると、価値の表現は金銀の貨幣が最適とみなされるようになった。当初、金や銀といった貴金属はそれ自体が商品だったといってよい。そして、金や銀などの貨幣は、次第に個人の富と権力を測る尺度となり、欲望の究極目的となっていく。
社会的分業と交換が増大し複雑化すると、貨幣の力も大きくなってくる。交換の道具として導入されたはずの貨幣が、ますます超越的な力をふるうようになるのだ。マルクス自身、貨幣は価値尺度、貯蔵手段、価格の度量標準、流通手段であるだけでなく、計算貨幣や信用貨幣として、ついには資本を算出する一つの生産手段として機能するようになる、と述べている。
やがて、鋳造の仕事は国家の手に帰する(それは伝統を引き継いだものだ)。金銀は鋳貨となり、いわば「国民的制服」となる、とマルクスはいう。だが、その国民的制服は世界市場では脱ぎ捨てられなければならない。鋳貨は一般に国内でしか通用しないからだ。そのことは「商品の国内的または国民的部分とその一般的な世界市場部門との分離」をもたらす。
さらに重要なのは次の点だ。国家が貨幣の発行権をもつようになると、貨幣は金や銀といった金属的基盤をもたなくても、行きつくところ「象徴的表象」であればいいことになっていくのだ。
貨幣が金属的基盤を完全に捨て去るのは1970年代はじめにブレトンウッズ体制が崩壊し、金ドル兌換が停止され、世界が変動為替制に移行してからだ、とハーヴェイはいう。マルクスの時代には、貨幣はまだ金属的基盤に縛られていた。
マルクス自身は『資本論』第3巻で、こう書いている。
〈貨幣制度[重金主義]は本質的にカトリック的であり、信用制度[信用主義]は本質的にプロテスタント的である。「スコットランド人は金(きん)を忌み嫌う」。紙幣としては、商品の貨幣的定在は純粋に社会的な定在をもっている。救済をもたらすのは信仰である。商品の内在的精霊たる貨幣価値にたいする信仰、生産様式とその予定秩序にたいする信仰、自己増殖する資本の単なる人格化としての個々の生産当事者にたいする信仰である。しかし、プロテスタンティズムがカトリック教の基礎から解放されていないように、信用制度も貨幣制度の基礎から解放されていない。〉
いかにもマルクスらしい言い回し。商品の価値実現への渇仰が、いまだに金属基盤から離れられない貨幣の解放を求める。それを後押しするのが信用主義の広がりである。ところが、信用が揺らげば、たちまち貨幣への回帰(貨幣の回収)がはじまる。
信用がゆらぐのは、流通過程における商品価値の実現があやぶまれ、資本の回収が危機に瀕しているときである。それは恐慌時だ。資本主義的生産は、「この金属的制限を絶えず廃棄しようと努めながら、また絶えず繰り返しこの制限に頭をぶつける」ことを避けられない、とマルクスはいう。
ところが、1970年代になって貨幣の金属的基盤が放棄され、貨幣が象徴的表象として国家と中央銀行によって管理されるようになると、マルクスの想定していた制限は乗り越えられてしまった、とハーヴェイはいう。
かずかずの利子生み資本(たとえば公開株や投資信託、社債)が、終わりなき資本蓄積を促す原動力となる。銀行などの金融機関は土地不動産投機に資金と投資をふりむける。労働者の消費はクレジットカードによって増大する。自分の家や自動車を買うため、多額のローンを組む労働者も増えてくるだろう。資本主義は膨張していくが、その膨張を金融面で支えるのが国家だ。
貨幣ならぬマネーが独り歩きするようになる。株式市場では価値増殖活動を大幅に上回る株式が高値で取引される。外国為替市場でも巨額の取引がおこなわれる。「価値創造とは無関係な単なる投機的あぶくや取引上の空騒ぎがどれだけの規模となるかは見極めがたいものがある」と、ハーヴェイは書いている。
金融システムに集まった過剰資金は、資本の再投資を活発にする。金融システムは流動資産の巨大な貯水池となり、いわば企業の共同資本をかたちづくり、信用創造にもとづくテコの原理(レバレッジ)によって貨幣資本に流れこんでいく。
そうしたなかから、特異な資産家(投資家)階級、すなわち金融貴族が生まれてくる、とハーヴェイはいう。金融貴族は個人である場合も団体や機関である場合もある。いずれにせよ、かれらは自己の貨幣資本利益率を必死に追い求めて、投資運用をおこなうようになる。
そうした金融貴族は19世紀にも存在した。マルクスにいわせれば、かれらは経済社会の吸血鬼のようなものだ。
投資家の存在は、不安定な市場における投機活動をもたらすだけではなかった。20世紀にはいって、企業における所有と経営の分離を促進した面もある。マルクス自身は、金融貴族が「他人の貨幣にたいする絶対的支配力」をもつようになったことが重要だと考えていた。
現在では、債権債務制度をつうじて組織化された少数の金融貴族による経済支配がさらに進んだ。金融貴族たちは経済社会全体にカネもうけ第一主義の思想を埋め込んでいく。その結果がどうなるかをハーヴェイは問おうとしている。
長くなったので、きょうはこのあたりで。
2024-02-10 07:27
nice!(7)
コメント(0)




コメント 0