清光館哀史 [柳田国男の昭和]
《第237回》

[八戸の白銀浜、柳田が家族に送った絵葉書から]
三陸の旅がつづいている。
釜石までで予定の旅程はほぼ半分終わった。そのあとは佐々木喜善を加えて、リアス式の海岸道を一路、八戸近くまで北上する。北上山地ふもとの渓谷と台地を歩く、かなり苦しい道のりだった。東北の夏は短い。クズやキキョウ、ハギ、そろそろ秋の花が咲きはじめていた。
釜石からはすぐに急な山道になり、小さな峠を越えると、そこが鵜住居(うのすまい)村(現釜石市内)だった。道沿いに常楽寺という寺があったので、その本堂をのぞいてみると、新旧の肖像画がすき間もなく掲げてあった。写真もあったが、大部分が江戸絵風の彩色画だった。描かれているのは大津波で亡くなった人たちである。国男は、その絵のひとつひとつを眺め、こう記す。
〈不思議なことには、近ごろのものまで、男は髷(まげ)があり、女房や娘は夜着のような衣物を着ている。ひとりで茶を飲んでいるところもあり、3人5人と一家団欒の態を描いた絵も多い。後者は海嘯[大津波]で死んだ人たちだといったが、そうでなくとも一度にためておいて額にする例もあるという。立派にさえ描いてやれば、よく似ているといって悦ぶものだそうである。こうして寺に持ってきて、不幸なる人々はその記憶を新たにもすれば、また美しくもした〉
亡くなった人びとが寺で供養されているのを見た国男は、めずらしいことに仏教の恩沢を感じて、次のような感慨をもらしている。
〈仏法が日本国民の生活に及ぼした恩沢が、もしただひとつであったとするならば、それはわれわれに死者を愛することを教えた点である。供養さえすれば幽霊も怖くはないことを知って、われわれははじめて厲鬼(れいき)駆逐の手を緩め、同じ夏冬の終わりの季節をもって、親しかった人びとの魂を迎える日と定めえたのである。合邦の浄瑠璃にもあるごとく、血縁の深い者ほど死ねば恐ろしくなるものだなどといいつつも、墓をめぐって永く慟哭(どうこく)するような、やさしい自然の情をあらわしうることになったのも、この宗教のおかげと言わねばならない〉
鵜住居からひと尾根越えると大槌町、そこから下ると吉里吉里に着く。道々のほとんどの家に初盆の燈籠がかかげられていた。大津波の死者を祭っているわけではない。前年の「スペイン風邪」と呼ばれた大感冒(インフルエンザ)で、このあたりで死者を出さぬ家はまれだったのである。なかには天然の杉の木を柱とした高燈籠は大正時代でも見かけなくなった古風なものだったが、それのあまりの多さに、国男は秋の情緒を通り越して、物寂しさをおぼえないわけにはいかなかった。
吉里吉里からは波板海岸を抜けて、下閉伊郡にはいり、船越村(現山田町)、山田町をへて、宮古町(現宮古市)に到着する。そこからは平原状の「ひとつづきの大長根」で、田老(たろう、現宮古市内)、小本(おもと、現岩泉町)、平井賀(田野畑村)、普代、野田、米田(まいた、現野田村)と村々を延々と歩きつづけた。すべて平成の東日本大震災で大きな被害を受けた地域である。
小本では草履と足袋が破れてしまったので、新しいものと買い換えようとしたが、何と昔の殿様がはくような上等な足袋しか売っていない。このあたりの農民がぜいたくかといえば、そうではなく、むしろかれらにとっては足袋自体が奢侈品で、ふだんははかずに素足ですませているのだった。
「豆手帖から」の記事は小子内(おこない、現洋野[ひろの]町)が最後である。国男の旅はさらに八戸、そして下北半島、弘前から能代までの海岸線、秋田へとつづくのだが、本人もいうように「どうも調子が取りにくいので、中ほどからやめてしまった」。長旅の疲れが出はじめていた。
「浜の月夜」は連載「豆手帖から」の最後を飾る名篇となった。
あんまりくたびれたからといって、国男ら3人の一行は、小子内に1軒しかない清光館という立派な名前のついた古ぼけた宿に泊まった。ほかに客はいないらしく、おかみが4枚の障子を立てた2階の客室を息を切らせて拭き掃除するありさま。それでも若い亭主と母と女房の親切は格別だった。その日は旧盆の14日だったというから、新暦に直せば8月27日のことである。
浜に出る道の途中の広場で、月夜の盆踊りがおこなわれていた。現在のように真ん中にやぐらを組んで、電気をこうこうとつけ、おなじみのレコードをやかましくかけて、ゆかたを着て踊るといったたぐいの催しではない。太鼓も笛もない。踊るのは女ばかりで、男はもっぱら見物にまわり、見物の人数は国男の一行を加えても20人ほど。一見、さびしい踊りである。
踊り子はいちように白い手拭いで顔を隠し、帯も足袋もそろいの白、下駄が真新しいのがめだった。前掛けは昔ながらの紺無地だが、それに家紋やら船印をつけた金紙が月の下でかげったり光ったりする。
「ほんとうに盆は月送りではだめだと思った。ひとつの楽器がなくとも踊りは眼の音楽である。四周が閑静なだけにすぐに揃って、そうしてしゅんでくる」
そう国男は書いた。新暦ではだめで、盆には満月の光がふさわしい。その光のもとの歌と踊りで、だんだん一団の気持ちが高揚し、その場が心底から盛り上がっていくのだ。それに女の声のよいこと。何と歌っているのか、よくわからないので、まわりの男たちに聞いてみるが、にやにや笑っているだけで、だれも教えてくれない。ごく短い句が3通りあって、それを高く低くくり返し歌っていることだけはわかった。
翌朝、起きて障子をあけてみると、ひとりの娘が水くみをしていた。隣の細君も朝の支度に忙しそうだ。宿のかみさんに聞くと、夜明け近くまで踊ったようだが、どの娘の顔にも疲れの影らしいものはみえない。えらいものだなと思う。厳しい生活に耐えている女たちの心根をみたような気がした。昨夜の踊りの印象を胸にきざみながら、国男らは村を立つ。広場の跡は、何ごともなかったように、きれいに片づいていた。
この話には後日談がある。6年後、たまたま親子連れで東北を訪れた国男はふとなつかしくなって、小子内に寄ってみることにした。ところが、あの清光館がどこにも見あたらない。
〈その家がもう影も形もなく、石垣ばかりになっているのである。石垣の陰には若干の古材木がごちゃごちゃと寄せかけてある。真っ黒けに煤(すす)けているのを見ると、たぶん我々3人の、遺跡の破片であろう。いくらあればかりの小家でも、よくまあ建っていたなと思うほどの小さな地面で、片隅には二三本のトウモロコシが秋風にそよぎ、残りも畠となって一面のカボチャの花盛りである〉
こうして「清光館哀史」がつづられる。
近所の大勢の人に問うてみて、ようやく事情が判明した。ある大暴風雨の日に沖に出ていて沈んだ船に、宿の主人も乗っており、帰らぬ人となった。それから一家は離散する。女房は久慈の町で奉公し、ふたりの子供はどこかにあずけられた。母親の行方はわからないという。わずか6年のあいだのできごとに、国男は茫然とする。
ハマナスの咲く浜に出てみた。もうだいぶオレンジの実をつけている。地元ではこれをヘエダマと呼ぶらしい。浜には15人ほどの娘が仕事がてらに寝転んでいて、親子連れの国男は彼女らにきさくに話しかける。最初は雑談をして、盆踊りの話を聞く。
〈「今でもこの村ではよく踊るかね」
「今は踊らない。盆になれば踊る」
こんな軽い翻弄をあえてして、また脇にいる者と顔を見合わせて、くっくっと笑っている。
あの歌は何というのだろう。何べん聴いておっても私にはどうしても分からなかったと、半分独り言のようにいって、海の方を向いて少し待っていると、「ふん」といっただけで、その問いには答えずに、やがて年がさの一人が鼻唄のようにして、次のような文句を歌ってくれた。
なにヤとやーれ
なにヤとなされのう
ああやっぱり私の想像していたごとく、古くから伝わっているあの歌を、この浜でも盆の月夜になるごとに歌いつつ踊っていたのであった〉
それは恋歌だった。その背後には村の女たち一人ひとりのちいさな物語が隠されている。だが人の一生が哀しいように、「依然として踊りの唄の調べは悲しい」と国男は感じる。それは、通りすがりの旅の者には、けっして伝わらぬ哀しさなのだ。
東北がからだに染みついた。柳田民俗学がただの学問ではなく、旅の記憶でもあるのは、そこに人びとの表情と心根が刻印されているからだった。

[八戸の白銀浜、柳田が家族に送った絵葉書から]
三陸の旅がつづいている。
釜石までで予定の旅程はほぼ半分終わった。そのあとは佐々木喜善を加えて、リアス式の海岸道を一路、八戸近くまで北上する。北上山地ふもとの渓谷と台地を歩く、かなり苦しい道のりだった。東北の夏は短い。クズやキキョウ、ハギ、そろそろ秋の花が咲きはじめていた。
釜石からはすぐに急な山道になり、小さな峠を越えると、そこが鵜住居(うのすまい)村(現釜石市内)だった。道沿いに常楽寺という寺があったので、その本堂をのぞいてみると、新旧の肖像画がすき間もなく掲げてあった。写真もあったが、大部分が江戸絵風の彩色画だった。描かれているのは大津波で亡くなった人たちである。国男は、その絵のひとつひとつを眺め、こう記す。
〈不思議なことには、近ごろのものまで、男は髷(まげ)があり、女房や娘は夜着のような衣物を着ている。ひとりで茶を飲んでいるところもあり、3人5人と一家団欒の態を描いた絵も多い。後者は海嘯[大津波]で死んだ人たちだといったが、そうでなくとも一度にためておいて額にする例もあるという。立派にさえ描いてやれば、よく似ているといって悦ぶものだそうである。こうして寺に持ってきて、不幸なる人々はその記憶を新たにもすれば、また美しくもした〉
亡くなった人びとが寺で供養されているのを見た国男は、めずらしいことに仏教の恩沢を感じて、次のような感慨をもらしている。
〈仏法が日本国民の生活に及ぼした恩沢が、もしただひとつであったとするならば、それはわれわれに死者を愛することを教えた点である。供養さえすれば幽霊も怖くはないことを知って、われわれははじめて厲鬼(れいき)駆逐の手を緩め、同じ夏冬の終わりの季節をもって、親しかった人びとの魂を迎える日と定めえたのである。合邦の浄瑠璃にもあるごとく、血縁の深い者ほど死ねば恐ろしくなるものだなどといいつつも、墓をめぐって永く慟哭(どうこく)するような、やさしい自然の情をあらわしうることになったのも、この宗教のおかげと言わねばならない〉
鵜住居からひと尾根越えると大槌町、そこから下ると吉里吉里に着く。道々のほとんどの家に初盆の燈籠がかかげられていた。大津波の死者を祭っているわけではない。前年の「スペイン風邪」と呼ばれた大感冒(インフルエンザ)で、このあたりで死者を出さぬ家はまれだったのである。なかには天然の杉の木を柱とした高燈籠は大正時代でも見かけなくなった古風なものだったが、それのあまりの多さに、国男は秋の情緒を通り越して、物寂しさをおぼえないわけにはいかなかった。
吉里吉里からは波板海岸を抜けて、下閉伊郡にはいり、船越村(現山田町)、山田町をへて、宮古町(現宮古市)に到着する。そこからは平原状の「ひとつづきの大長根」で、田老(たろう、現宮古市内)、小本(おもと、現岩泉町)、平井賀(田野畑村)、普代、野田、米田(まいた、現野田村)と村々を延々と歩きつづけた。すべて平成の東日本大震災で大きな被害を受けた地域である。
小本では草履と足袋が破れてしまったので、新しいものと買い換えようとしたが、何と昔の殿様がはくような上等な足袋しか売っていない。このあたりの農民がぜいたくかといえば、そうではなく、むしろかれらにとっては足袋自体が奢侈品で、ふだんははかずに素足ですませているのだった。
「豆手帖から」の記事は小子内(おこない、現洋野[ひろの]町)が最後である。国男の旅はさらに八戸、そして下北半島、弘前から能代までの海岸線、秋田へとつづくのだが、本人もいうように「どうも調子が取りにくいので、中ほどからやめてしまった」。長旅の疲れが出はじめていた。
「浜の月夜」は連載「豆手帖から」の最後を飾る名篇となった。
あんまりくたびれたからといって、国男ら3人の一行は、小子内に1軒しかない清光館という立派な名前のついた古ぼけた宿に泊まった。ほかに客はいないらしく、おかみが4枚の障子を立てた2階の客室を息を切らせて拭き掃除するありさま。それでも若い亭主と母と女房の親切は格別だった。その日は旧盆の14日だったというから、新暦に直せば8月27日のことである。
浜に出る道の途中の広場で、月夜の盆踊りがおこなわれていた。現在のように真ん中にやぐらを組んで、電気をこうこうとつけ、おなじみのレコードをやかましくかけて、ゆかたを着て踊るといったたぐいの催しではない。太鼓も笛もない。踊るのは女ばかりで、男はもっぱら見物にまわり、見物の人数は国男の一行を加えても20人ほど。一見、さびしい踊りである。
踊り子はいちように白い手拭いで顔を隠し、帯も足袋もそろいの白、下駄が真新しいのがめだった。前掛けは昔ながらの紺無地だが、それに家紋やら船印をつけた金紙が月の下でかげったり光ったりする。
「ほんとうに盆は月送りではだめだと思った。ひとつの楽器がなくとも踊りは眼の音楽である。四周が閑静なだけにすぐに揃って、そうしてしゅんでくる」
そう国男は書いた。新暦ではだめで、盆には満月の光がふさわしい。その光のもとの歌と踊りで、だんだん一団の気持ちが高揚し、その場が心底から盛り上がっていくのだ。それに女の声のよいこと。何と歌っているのか、よくわからないので、まわりの男たちに聞いてみるが、にやにや笑っているだけで、だれも教えてくれない。ごく短い句が3通りあって、それを高く低くくり返し歌っていることだけはわかった。
翌朝、起きて障子をあけてみると、ひとりの娘が水くみをしていた。隣の細君も朝の支度に忙しそうだ。宿のかみさんに聞くと、夜明け近くまで踊ったようだが、どの娘の顔にも疲れの影らしいものはみえない。えらいものだなと思う。厳しい生活に耐えている女たちの心根をみたような気がした。昨夜の踊りの印象を胸にきざみながら、国男らは村を立つ。広場の跡は、何ごともなかったように、きれいに片づいていた。
この話には後日談がある。6年後、たまたま親子連れで東北を訪れた国男はふとなつかしくなって、小子内に寄ってみることにした。ところが、あの清光館がどこにも見あたらない。
〈その家がもう影も形もなく、石垣ばかりになっているのである。石垣の陰には若干の古材木がごちゃごちゃと寄せかけてある。真っ黒けに煤(すす)けているのを見ると、たぶん我々3人の、遺跡の破片であろう。いくらあればかりの小家でも、よくまあ建っていたなと思うほどの小さな地面で、片隅には二三本のトウモロコシが秋風にそよぎ、残りも畠となって一面のカボチャの花盛りである〉
こうして「清光館哀史」がつづられる。
近所の大勢の人に問うてみて、ようやく事情が判明した。ある大暴風雨の日に沖に出ていて沈んだ船に、宿の主人も乗っており、帰らぬ人となった。それから一家は離散する。女房は久慈の町で奉公し、ふたりの子供はどこかにあずけられた。母親の行方はわからないという。わずか6年のあいだのできごとに、国男は茫然とする。
ハマナスの咲く浜に出てみた。もうだいぶオレンジの実をつけている。地元ではこれをヘエダマと呼ぶらしい。浜には15人ほどの娘が仕事がてらに寝転んでいて、親子連れの国男は彼女らにきさくに話しかける。最初は雑談をして、盆踊りの話を聞く。
〈「今でもこの村ではよく踊るかね」
「今は踊らない。盆になれば踊る」
こんな軽い翻弄をあえてして、また脇にいる者と顔を見合わせて、くっくっと笑っている。
あの歌は何というのだろう。何べん聴いておっても私にはどうしても分からなかったと、半分独り言のようにいって、海の方を向いて少し待っていると、「ふん」といっただけで、その問いには答えずに、やがて年がさの一人が鼻唄のようにして、次のような文句を歌ってくれた。
なにヤとやーれ
なにヤとなされのう
ああやっぱり私の想像していたごとく、古くから伝わっているあの歌を、この浜でも盆の月夜になるごとに歌いつつ踊っていたのであった〉
それは恋歌だった。その背後には村の女たち一人ひとりのちいさな物語が隠されている。だが人の一生が哀しいように、「依然として踊りの唄の調べは悲しい」と国男は感じる。それは、通りすがりの旅の者には、けっして伝わらぬ哀しさなのだ。
東北がからだに染みついた。柳田民俗学がただの学問ではなく、旅の記憶でもあるのは、そこに人びとの表情と心根が刻印されているからだった。
大津波の記憶 [柳田国男の昭和]
《第236回》
大雨による出水の翌日、かんかん照りとなった一関を出発した国男は、東北線に乗り水沢駅に着いた。その先、雨の影響で鉄道が不通になっていた。国男は歩いて、江刺郡岩谷堂(現奥州市)に向かった。鉄道が使えないので、岩谷堂から人首(ひとかべ)を通り、大好きな峠越えで遠野にはいろうとしたのである。それにしても、昔の人の健脚ぶりには驚くほかない。
遠野では、この先の旅に同行する佐々木喜善と松本信広が、国男の到着を待ちかまえていた。くり返すまでもなく、佐々木は『遠野物語』の語り手で、国男よりひとまわりほど年下、松本は慶応大学を卒業したばかりの青年で、国男に私淑していた。のちに慶応大学教授となっている。もうひとり旅に加わる予定だったニコライ・ネフスキーは病気のため、同行をあきらめることになった。
こうして同行者ふたりを加えて、国男は三陸海岸を北上するという今回の旅の主要目標にいどむことになった。ほんとうは遠野から東にでれば釜石に着くのだが、できるだけ長く三陸海岸北上のルートを取りたい国男は、まず松本を伴って南の大船渡に向かう峠越えの道を選んだ。佐々木喜善とは釜石で合流することにした。赤羽根(現遠野市)までは岩手軽便鉄道がある。そこから峠を越えて、世田米(現住田町)を通り、さらに尾根を超えて盛町(現大船渡市)に着き、海に出た。
大船渡からは南下して、小友村(現陸前高田市)、唐桑浜(現気仙沼市)をへて、気仙沼に到着する。気仙沼から釜石までは、さすがに同じ道を戻らず、船で北上した。釜石に着いたのは8月20日。石巻をふくめ、三陸海岸線の町々は、2011年3月11日の大地震と津波で甚大な被害を受けた地域である。
国男は唐桑浜で村の女から聞いた話をつづる。この村では40戸のうち前の津波で流されなかったのは自分の家だけで、それも床上1メートル以上水があがって、あっという間に何もかもさらっていったという。8歳になる弟は道のそばに店を出しているお婆さんのところにいっていて、迎えにいったのに戻りたくないといって、そのまま永遠に帰ってこなかった。
彼女はこのとき14歳で、高潮に押し回されたけれど、柱と蚕棚のあいだにはさまって動けなくなくなっているうちに水が引いたので助かった。そのあとうしろの岡の上で父親がしきりに名前を呼んだので、高台にのぼった。母親も乳呑み児を必死で抱きかかえ、山にあがって生き延びた。高台では家にあった薪を300束ほどたきつづけた。海上からその光を見て、泳いで帰った者もだいぶいた。母親はたき火の前でじっとしていたので、翌朝、赤ん坊はすすで胡麻あえみたいになっていた、と彼女は笑いながら話した。
国男はさらにこう書いている。
〈時刻はちょうど旧5月5日の、月がおはいりやったばかりだった。怖ろしい大雨ではあったが、それでも節供の晩なので、人の家に行って飲む者が多く、酔い倒れて帰られぬために助かったものもあれば、そのために助からなかった者もあった。総体に何を不幸の原因とも決めてしまうことができなかった。例えば山の麓に押しつぶされていた家で、馬まで無事であったのもある。2階に子供を寝させていた母親が、風呂桶のまま海に流されて裸で命をまっとうし、3日目に屋根を破って入ってみると、その子がきずもなく生きていたというような珍しい話もある。死ぬまじくして死んだ例ももとより多かろうが、このほうはかえって親身の者のほかは忘れていくことが早いらしい〉
人は忘れやすい。いや、忘れないと生きていけない存在なのだ。ここで語られたのは1896年(明治29)6月15日の、いわゆる明治三陸地震である。国男が訪れたのは、正確にいうと地震から24年後である(記事のタイトルは「二十五箇年後」)。
国男はこうつけ加える。
〈回復と名づくべき事業は行われがたかった。知恵のある人は臆病になってしまったという。元の屋敷を見捨てて高みへと上った者は、それゆえにもうよほど以前から後悔をしている。これに反して、つとに経験を忘れ、またはそれよりも食うがだいじだと、ずんずん浜辺近く出た者は、漁業にも商売にも大きな便宜を得ている。あるいはまた、よそからやってきて、委細かまわず勝手なところに住む者もあって、けっきょく村のかたちは元のごとく、人の数も海嘯(かいしょう)[大津波]の前よりはずっと多い。一人ひとりの不幸を度外に置けば、きずは既にまったく癒えている〉
だが歴史はくり返す。村では文明年間(15世紀後半)に起こったとされる地震は、すでに完全な伝説になっていたと国男はいうが、これはおそらく勘違いで、正確には享徳地震(1454年)や慶長三陸地震(1611年)の大津波を指すのだろう。そして明治の地震と大津波も24年後の時点で、すでに忘却がはじまっていた。まして国男自身もこのあとまもなく関東大震災が発生するなどとは夢にも思っていない。
大雨による出水の翌日、かんかん照りとなった一関を出発した国男は、東北線に乗り水沢駅に着いた。その先、雨の影響で鉄道が不通になっていた。国男は歩いて、江刺郡岩谷堂(現奥州市)に向かった。鉄道が使えないので、岩谷堂から人首(ひとかべ)を通り、大好きな峠越えで遠野にはいろうとしたのである。それにしても、昔の人の健脚ぶりには驚くほかない。
遠野では、この先の旅に同行する佐々木喜善と松本信広が、国男の到着を待ちかまえていた。くり返すまでもなく、佐々木は『遠野物語』の語り手で、国男よりひとまわりほど年下、松本は慶応大学を卒業したばかりの青年で、国男に私淑していた。のちに慶応大学教授となっている。もうひとり旅に加わる予定だったニコライ・ネフスキーは病気のため、同行をあきらめることになった。
こうして同行者ふたりを加えて、国男は三陸海岸を北上するという今回の旅の主要目標にいどむことになった。ほんとうは遠野から東にでれば釜石に着くのだが、できるだけ長く三陸海岸北上のルートを取りたい国男は、まず松本を伴って南の大船渡に向かう峠越えの道を選んだ。佐々木喜善とは釜石で合流することにした。赤羽根(現遠野市)までは岩手軽便鉄道がある。そこから峠を越えて、世田米(現住田町)を通り、さらに尾根を超えて盛町(現大船渡市)に着き、海に出た。
大船渡からは南下して、小友村(現陸前高田市)、唐桑浜(現気仙沼市)をへて、気仙沼に到着する。気仙沼から釜石までは、さすがに同じ道を戻らず、船で北上した。釜石に着いたのは8月20日。石巻をふくめ、三陸海岸線の町々は、2011年3月11日の大地震と津波で甚大な被害を受けた地域である。
国男は唐桑浜で村の女から聞いた話をつづる。この村では40戸のうち前の津波で流されなかったのは自分の家だけで、それも床上1メートル以上水があがって、あっという間に何もかもさらっていったという。8歳になる弟は道のそばに店を出しているお婆さんのところにいっていて、迎えにいったのに戻りたくないといって、そのまま永遠に帰ってこなかった。
彼女はこのとき14歳で、高潮に押し回されたけれど、柱と蚕棚のあいだにはさまって動けなくなくなっているうちに水が引いたので助かった。そのあとうしろの岡の上で父親がしきりに名前を呼んだので、高台にのぼった。母親も乳呑み児を必死で抱きかかえ、山にあがって生き延びた。高台では家にあった薪を300束ほどたきつづけた。海上からその光を見て、泳いで帰った者もだいぶいた。母親はたき火の前でじっとしていたので、翌朝、赤ん坊はすすで胡麻あえみたいになっていた、と彼女は笑いながら話した。
国男はさらにこう書いている。
〈時刻はちょうど旧5月5日の、月がおはいりやったばかりだった。怖ろしい大雨ではあったが、それでも節供の晩なので、人の家に行って飲む者が多く、酔い倒れて帰られぬために助かったものもあれば、そのために助からなかった者もあった。総体に何を不幸の原因とも決めてしまうことができなかった。例えば山の麓に押しつぶされていた家で、馬まで無事であったのもある。2階に子供を寝させていた母親が、風呂桶のまま海に流されて裸で命をまっとうし、3日目に屋根を破って入ってみると、その子がきずもなく生きていたというような珍しい話もある。死ぬまじくして死んだ例ももとより多かろうが、このほうはかえって親身の者のほかは忘れていくことが早いらしい〉
人は忘れやすい。いや、忘れないと生きていけない存在なのだ。ここで語られたのは1896年(明治29)6月15日の、いわゆる明治三陸地震である。国男が訪れたのは、正確にいうと地震から24年後である(記事のタイトルは「二十五箇年後」)。
国男はこうつけ加える。
〈回復と名づくべき事業は行われがたかった。知恵のある人は臆病になってしまったという。元の屋敷を見捨てて高みへと上った者は、それゆえにもうよほど以前から後悔をしている。これに反して、つとに経験を忘れ、またはそれよりも食うがだいじだと、ずんずん浜辺近く出た者は、漁業にも商売にも大きな便宜を得ている。あるいはまた、よそからやってきて、委細かまわず勝手なところに住む者もあって、けっきょく村のかたちは元のごとく、人の数も海嘯(かいしょう)[大津波]の前よりはずっと多い。一人ひとりの不幸を度外に置けば、きずは既にまったく癒えている〉
だが歴史はくり返す。村では文明年間(15世紀後半)に起こったとされる地震は、すでに完全な伝説になっていたと国男はいうが、これはおそらく勘違いで、正確には享徳地震(1454年)や慶長三陸地震(1611年)の大津波を指すのだろう。そして明治の地震と大津波も24年後の時点で、すでに忘却がはじまっていた。まして国男自身もこのあとまもなく関東大震災が発生するなどとは夢にも思っていない。
豆手帖から [柳田国男の昭和]
《第235回》
『雪国の春』に収められた1920年(大正9)の東北旅行を追ってみよう。ただし、本のタイトルとちがい、実際の旅行はこの年の8月から9月にかけてで、その前後も柳田国男は雪の深く残る春まだきに東北を歩いたことはない。
雪国の春は、あくまでも想像のなかにある。それでも国男は東北に春が戻ってくる喜びを、この旅行の哀しくいとしい思い出とともに、ひとつの希望のようなものとして伝えたかったのである。
『柳田国男伝』によると、国男はまず仙台に到着し、石巻に向かっている。このころ仙台と石巻を結ぶ鉄道はなく、塩釜から船で松島湾を渡って野蒜(のびる)まで行き、そこから徒歩で石巻にはいらなければならなかった。いったん女川を訪れたあと、ふたたび石巻に戻り、飯野川町(現石巻市河北町)から北上川(追波川)を下って、十五浜村(現石巻市雄勝町)で1泊。名所を避け、できるだけ観光客の行かないところ場所を訪れるのが、かれの旅のスタイルである。
三陸の入り組んだ複雑な地形は、まっすぐの北上を許さなかった。飯野川に戻った国男は、そこから北上川沿いに歩き、入沢(現石巻市桃生町)登米、佐沼(現登米市)を訪れたあと、東北線で岩手県の一関にはいった。
8月10日の一関は折からの大水で、北上川につながる川の水があふれだしていた。東北線も不通となる。国男は終日、宿でこれまでメモしていた草稿を整理し、4回分の記事を朝日新聞に送った。1回が400字詰めにして5枚ほどである。
最初の記事「方言」(のち「仙台方言集」と改題)で、国男は方言を無理やり矯正しようとする風潮を批判し、「願わくは将来大いに東北を振興させ、清盛の伊勢語、義仲の木曽語、六波羅探題の伊豆語鎌倉語、室町の三河語等の力をもって、いまの京都弁を混成したごとく、近くはまた北上上流の軽快なる語音を廟堂に聞くように、少なくとも一部の藩閥を、東京の言語の上にも打ち立てしめたいものである」と記した。
薩長閥ではない盛岡出身の原敬が首相の座についていた。明治維新以来、「白河以北、一山百文」とばかにされていた東北が、ようやく脚光を浴びるようになったのだ。政友会とも原敬とも距離のあった国男だが、東北を応援する点では人後に落ちない。東北弁を現在の東京語に大いにとりいれたらいいとまでユーモラスに提言している。
だが、東北を現に歩いてみると、たちまち厳しい現実が迫ってくる。
「東京大阪で失業失業としきりにいうのは、新聞の誇張ではありませぬか。この村などでは近年ずいぶん出ていきましたが、まだ一人も帰ってきたものはありませぬ」
そう話したのは石巻近辺の宿の主人だったか。失業は新聞で伝えられているほど深刻ではないというのではない。米騒動が全国に広がり、ようやく収まったあとは、第一次世界大戦後の世界不況が日本にも押し寄せていた。政治家のなかには、都市で失業したら、田舎に帰らせればいいと豪語する者もいた。ところが、宿の主人のいうように、この村でも近年、人がずいぶん出ていったが、戻ってきたものはひとりもいない。それはどうしてなのか。
国男は東北の厳しい実情を知らぬ政治家の暴言に、ほとんど怒りすら覚えて、こう書き記した。
出て行く者はつねに自分の考えから……居りたくないから出ていくので、非常に零落するか(小農にはもう零落の余地もないようだが)、または非常に立身しなければ、まずは帰らぬつもりなればこそ、遠方へは行くのである。……[政治家連中は]移民を渡り鳥か何ぞのごとく思っている。同情のない話である。
帰りたくても帰れないのだ。政治家が考えるべきなのは、むしろ逆のことだと国男はいう。
人間が増して、どうしても出るのが制止せられぬなら、永く先に落ちつくような方法を、ぜひとも考えておいてやらねばならぬ。3月や半季の土工人夫などに世話をして、職業仲介の公務がまっとうせられたと思ってはならぬ。帰農ももとより労働の一機会ではあるが、捨てておいても元の穴へ入っていくとみるのは、許しがたい無理である。いったん明け渡した空隙は必ず何ものかが満たしている。……これを知らずに帰農を説く人は、気の毒というよりも、むしろ憎い。
政治家が保身と安直、無為に走り、やるべき仕事をしないのは、いまも昔も変わらないようだ。
一関の宿では、旅の途中、偶然でくわしたふたつの災事が国男には忘れがたく、「子供の眼」という記事もつづっている。
石巻から自動車で女川街道を行き、渡波(わたのは)の松林にきたときのことだ。前方にとまっていた馬車がとつぜん横転した。馬をひいていたのは小学校を出たばかりと思われる小さな馬方だった。そのとき万悪く、荷車の後輪がかれの腹の上をきしった。すぐ病院につれていかれたが、そのとき一瞬、国男のほうを見た眼の色が脳裏にこびりついた。
十五浜から発動機船で川をさかのぼり、飯野川町に戻ったときのできごとも忘れがたかった。その途中、釣台(タンカ)にのせられ、小舟から船に移された病人がいた。チフスにかかった12、3の女の子で、どうやら石巻の病院に連れていくところらしい。当時チフスは難病で、命を落とすことが多かった。国男はぐうぜん彼女と眼を合わせる。自分のことをお医者さまであってほしいと願っているようだった。その眼がたまらなく哀れで、国男は何もしてやれない自分がはがゆかった。人生の災厄は、いたいけない子どもにも容赦なく襲いかかってくる。
北上川沿いに歩く道中では田がずっと広がっていた。このあたりは大地主が大規模農地を所有し、それを小作する者が多い。ところが大正にはいると、小作人が小地主になりたがり、国男の訪れた登米あたりでも、土地の競り売りが盛んにおこなわれていた。反千円(現在の感覚では、坪1万円)という値段がつく田もすくなくなかった。小作は値段のつり上がった小さな土地を、多額の借金をして買い取り、その結果、また苦労を背負いこむのである。せっかくの土地をもっても貧乏のつづく現状を、国男はつらい思いで見ている。
入沢(現石巻市桃生町)で休ませてもらった家の老農から聞いた話は、語られたままにつづられている。「狐のわな」という名篇が生まれる。
「なあに、あの木はみなクルミではがアせん。このへんでカツの木という木でがす」
……
「獣かね。当節はもう不足でがす。なんにー、シカなんか50年前からおりません。元はムジナが出て豆を食って困りました。犬を飼っていて、よく噛み殺させたものでがす」
「そのうちに犬が年イ取って、歯が役ウせぬようになってしまいました。横浜のアベ商店に売っとるって、機械を買ってきて使っていたのでがす。なんにー、3寸くれエの、真ん中に丸いかねがあって、ちょいと片っぽの足をのっけると、かたりと落ちるようになった、虎バサミといったようなものでがした。ベイコク製だといっておりやした。10年も使ってて何と、この春しょう分[処分]を受けて、御上さ取り上げられてしまいやした」
老人の話は、日本の近代狩猟史を体現している。キツネなどをつかまえていた虎バサミのような機械を警察が取り上げたのは、それを近年、狩猟道具として禁止する法律ができたからである。70歳になる老農はそのことを知らず、道具を取り上げられたうえに50円の罰金を支払わされた。
国男はあくまでも人がいいこの老人の話を、頭にしっかりと刻みこんだ。
「雷さまが急に鳴り出すと、きっと誰か駆け込んできます。雨がやみそうにもないと、傘を貸すこともあります。なアに、たいていは通るのは知った人ばかりだ。いっぺんだけ一昨年、だまくらかして持ってった人があります。飯野川のよく行く店の若え衆だと言いました。買ったばかりの傘だが、まだそのころは安かった。それでもあんまり久しく届けてこねえ。町さ出たついでに回ってもらって来べいとって、おら自分で行ってみました。そうするとそういう人はいねエって言いましてね。まったく店の名をかたったのでがした。遠方の者だろうというこつです。おれはこの年まで、石巻までもめったに出ねエ者だが、おれの馬鹿なことはよっぽど遠くまで聞こえているといって、家で笑っていたことでがす」
老人の姿を彷彿させるようである。話はいつまでも尽きず、国男はその場を立ち去りがたかったにちがいない。
『雪国の春』に収められた1920年(大正9)の東北旅行を追ってみよう。ただし、本のタイトルとちがい、実際の旅行はこの年の8月から9月にかけてで、その前後も柳田国男は雪の深く残る春まだきに東北を歩いたことはない。
雪国の春は、あくまでも想像のなかにある。それでも国男は東北に春が戻ってくる喜びを、この旅行の哀しくいとしい思い出とともに、ひとつの希望のようなものとして伝えたかったのである。
『柳田国男伝』によると、国男はまず仙台に到着し、石巻に向かっている。このころ仙台と石巻を結ぶ鉄道はなく、塩釜から船で松島湾を渡って野蒜(のびる)まで行き、そこから徒歩で石巻にはいらなければならなかった。いったん女川を訪れたあと、ふたたび石巻に戻り、飯野川町(現石巻市河北町)から北上川(追波川)を下って、十五浜村(現石巻市雄勝町)で1泊。名所を避け、できるだけ観光客の行かないところ場所を訪れるのが、かれの旅のスタイルである。
三陸の入り組んだ複雑な地形は、まっすぐの北上を許さなかった。飯野川に戻った国男は、そこから北上川沿いに歩き、入沢(現石巻市桃生町)登米、佐沼(現登米市)を訪れたあと、東北線で岩手県の一関にはいった。
8月10日の一関は折からの大水で、北上川につながる川の水があふれだしていた。東北線も不通となる。国男は終日、宿でこれまでメモしていた草稿を整理し、4回分の記事を朝日新聞に送った。1回が400字詰めにして5枚ほどである。
最初の記事「方言」(のち「仙台方言集」と改題)で、国男は方言を無理やり矯正しようとする風潮を批判し、「願わくは将来大いに東北を振興させ、清盛の伊勢語、義仲の木曽語、六波羅探題の伊豆語鎌倉語、室町の三河語等の力をもって、いまの京都弁を混成したごとく、近くはまた北上上流の軽快なる語音を廟堂に聞くように、少なくとも一部の藩閥を、東京の言語の上にも打ち立てしめたいものである」と記した。
薩長閥ではない盛岡出身の原敬が首相の座についていた。明治維新以来、「白河以北、一山百文」とばかにされていた東北が、ようやく脚光を浴びるようになったのだ。政友会とも原敬とも距離のあった国男だが、東北を応援する点では人後に落ちない。東北弁を現在の東京語に大いにとりいれたらいいとまでユーモラスに提言している。
だが、東北を現に歩いてみると、たちまち厳しい現実が迫ってくる。
「東京大阪で失業失業としきりにいうのは、新聞の誇張ではありませぬか。この村などでは近年ずいぶん出ていきましたが、まだ一人も帰ってきたものはありませぬ」
そう話したのは石巻近辺の宿の主人だったか。失業は新聞で伝えられているほど深刻ではないというのではない。米騒動が全国に広がり、ようやく収まったあとは、第一次世界大戦後の世界不況が日本にも押し寄せていた。政治家のなかには、都市で失業したら、田舎に帰らせればいいと豪語する者もいた。ところが、宿の主人のいうように、この村でも近年、人がずいぶん出ていったが、戻ってきたものはひとりもいない。それはどうしてなのか。
国男は東北の厳しい実情を知らぬ政治家の暴言に、ほとんど怒りすら覚えて、こう書き記した。
出て行く者はつねに自分の考えから……居りたくないから出ていくので、非常に零落するか(小農にはもう零落の余地もないようだが)、または非常に立身しなければ、まずは帰らぬつもりなればこそ、遠方へは行くのである。……[政治家連中は]移民を渡り鳥か何ぞのごとく思っている。同情のない話である。
帰りたくても帰れないのだ。政治家が考えるべきなのは、むしろ逆のことだと国男はいう。
人間が増して、どうしても出るのが制止せられぬなら、永く先に落ちつくような方法を、ぜひとも考えておいてやらねばならぬ。3月や半季の土工人夫などに世話をして、職業仲介の公務がまっとうせられたと思ってはならぬ。帰農ももとより労働の一機会ではあるが、捨てておいても元の穴へ入っていくとみるのは、許しがたい無理である。いったん明け渡した空隙は必ず何ものかが満たしている。……これを知らずに帰農を説く人は、気の毒というよりも、むしろ憎い。
政治家が保身と安直、無為に走り、やるべき仕事をしないのは、いまも昔も変わらないようだ。
一関の宿では、旅の途中、偶然でくわしたふたつの災事が国男には忘れがたく、「子供の眼」という記事もつづっている。
石巻から自動車で女川街道を行き、渡波(わたのは)の松林にきたときのことだ。前方にとまっていた馬車がとつぜん横転した。馬をひいていたのは小学校を出たばかりと思われる小さな馬方だった。そのとき万悪く、荷車の後輪がかれの腹の上をきしった。すぐ病院につれていかれたが、そのとき一瞬、国男のほうを見た眼の色が脳裏にこびりついた。
十五浜から発動機船で川をさかのぼり、飯野川町に戻ったときのできごとも忘れがたかった。その途中、釣台(タンカ)にのせられ、小舟から船に移された病人がいた。チフスにかかった12、3の女の子で、どうやら石巻の病院に連れていくところらしい。当時チフスは難病で、命を落とすことが多かった。国男はぐうぜん彼女と眼を合わせる。自分のことをお医者さまであってほしいと願っているようだった。その眼がたまらなく哀れで、国男は何もしてやれない自分がはがゆかった。人生の災厄は、いたいけない子どもにも容赦なく襲いかかってくる。
北上川沿いに歩く道中では田がずっと広がっていた。このあたりは大地主が大規模農地を所有し、それを小作する者が多い。ところが大正にはいると、小作人が小地主になりたがり、国男の訪れた登米あたりでも、土地の競り売りが盛んにおこなわれていた。反千円(現在の感覚では、坪1万円)という値段がつく田もすくなくなかった。小作は値段のつり上がった小さな土地を、多額の借金をして買い取り、その結果、また苦労を背負いこむのである。せっかくの土地をもっても貧乏のつづく現状を、国男はつらい思いで見ている。
入沢(現石巻市桃生町)で休ませてもらった家の老農から聞いた話は、語られたままにつづられている。「狐のわな」という名篇が生まれる。
「なあに、あの木はみなクルミではがアせん。このへんでカツの木という木でがす」
……
「獣かね。当節はもう不足でがす。なんにー、シカなんか50年前からおりません。元はムジナが出て豆を食って困りました。犬を飼っていて、よく噛み殺させたものでがす」
「そのうちに犬が年イ取って、歯が役ウせぬようになってしまいました。横浜のアベ商店に売っとるって、機械を買ってきて使っていたのでがす。なんにー、3寸くれエの、真ん中に丸いかねがあって、ちょいと片っぽの足をのっけると、かたりと落ちるようになった、虎バサミといったようなものでがした。ベイコク製だといっておりやした。10年も使ってて何と、この春しょう分[処分]を受けて、御上さ取り上げられてしまいやした」
老人の話は、日本の近代狩猟史を体現している。キツネなどをつかまえていた虎バサミのような機械を警察が取り上げたのは、それを近年、狩猟道具として禁止する法律ができたからである。70歳になる老農はそのことを知らず、道具を取り上げられたうえに50円の罰金を支払わされた。
国男はあくまでも人がいいこの老人の話を、頭にしっかりと刻みこんだ。
「雷さまが急に鳴り出すと、きっと誰か駆け込んできます。雨がやみそうにもないと、傘を貸すこともあります。なアに、たいていは通るのは知った人ばかりだ。いっぺんだけ一昨年、だまくらかして持ってった人があります。飯野川のよく行く店の若え衆だと言いました。買ったばかりの傘だが、まだそのころは安かった。それでもあんまり久しく届けてこねえ。町さ出たついでに回ってもらって来べいとって、おら自分で行ってみました。そうするとそういう人はいねエって言いましてね。まったく店の名をかたったのでがした。遠方の者だろうというこつです。おれはこの年まで、石巻までもめったに出ねエ者だが、おれの馬鹿なことはよっぽど遠くまで聞こえているといって、家で笑っていたことでがす」
老人の姿を彷彿させるようである。話はいつまでも尽きず、国男はその場を立ち去りがたかったにちがいない。
旅の名エッセイスト [柳田国男の昭和]
《第234回》
貴族院書記官長を辞任し、長い役人生活に決別を告げた柳田国男は、そのあと何をしようとしていたのだろう。旅をしてみたいという思いは強かっただろう。だが、国男ほどの名士で学者となれば、世間が気ままな漂泊を許しておくわけもない。すぐに朝日新聞編集局長の安藤正純から、東京朝日新聞入社への打診があった。
そのあたりの事情について、国男は『故郷七十年』で、次のように語っている。
〈もうそろそろ役人生活の足を洗ってよかろうと思った私は、大正9年(1920)いよいよ自由な生活に入ることとした。その7月朝日新聞の安藤正純氏からの連絡があったので客員の名義で入った。入社の条件として、最初の3年間は内地と外地とを旅行させてもらいたいという虫のいい希望を述べたが、幸いにも全部、村山老社長[龍平]の快諾するところとなった〉
これを読むと、すでに書記官長時代に打診があったかのように思えるが、そうではない。12月に役人をやめたあと、安藤から話がもちこまれたのは春になってからである。しかし、「右から左にお受けしたのではいかにも計画的のようでへんだからというので、6月まで自由に歩き回ってのち、7月から朝日の嘱託ということにしてもらった」と、同書の別の箇所で語っている。
こうして7月に国男は、朝日新聞社長の村山龍平と麻布市兵衛町の村山宅で会い、8月4日から朝日新聞の客員になることが決まった。そのとき国男の出した前代未聞の条件が、本人も語っているとおり「最初の3年間は内地と外地とを旅行させてもらいたいという虫のいい希望」だった。村山はその条件を快諾したというから、鷹揚なものである。月々の手当は300円[現在の感覚では100万円といったところか]、旅費は会社もちで別途支給ということも、そのとき決まった。
さて、その旅行だが、国男の腹づもりでは「その3年間の前半は国内を、後半は西洋、蘭印[現インドネシア]、濠州[オーストラリア]から太平洋方面を回りたい」というもの。「そしてこの3年間の旅が終わったら、正式の朝日社員になるということにしていたのであった」。
実際はこの目算は、のちに述べる事情、すなわち国男にたいし、ジュネーブの国際連盟委任統治委員会委員への就任要請があったため、わずか半年ばかりで頓挫することになる。だが、先のことはともかく、朝日入社が決まった時点では、本人はこれで自由に好きな旅行ができると内心喜んでいたのである。もちろん、その旅行とは名所旧跡をたずねる旅ではなく、人と民俗に学ぶ旅を意味していたことはいうまでもない。
年譜にしたがって、1920年から翌年にかけての国男の旅を整理してみると、こんなふうになる。
[1920〜21年]
6月15日〜24日 佐渡旅行
8月2日〜9月12日 東北旅行(東海岸を北上し、秋田まで)
10月中旬〜11月21日 中部地方および関西・中国旅行
12月13日〜3月1日 沖縄旅行(沖縄滞在は1月5日から2月7日まで)
朝日新聞の客員となってから半年のあいだは、ほとんど旅の人だったと知れる。東北の旅から帰って、ひと月ほど間があくのは、次女千枝が病気で入院し、「ふだんあまり文句をいわない養父から、この時だけは『こんな時ぐらい旅行をやめたらどうか』といわれた」ためである。「それから1カ月ぐらい、ぼそぼそして家におり」、また秋風にさそわれて旅にでた。
何が国男を駆りたてていたのだろう。東北のあと中部を回ったのは、江戸時代の旅行家、菅江真澄の事跡にひかれたという面がなかったわけではない。しかし、中部をはさんで、遊歴の地に共に辺境の東北と沖縄を求めたことは、無意識の選択がはたらいたとしか思えない。官界を蹴ったあとは、とりわけ民衆のほうへという志向が強まっていたのだろう。
8月以降の3つの旅行で、国男はそれぞれ紀行を朝日新聞に連載している。最初の東北が「豆手帖から」、中部が「秋風帖」、そして沖縄が「海南小記」で、それぞれのちに他のエッセイを加えて単行本として発刊されている。ただし「豆手帖から」だけは、さすがに本のタイトルとはしがたく、『雪国の春』という書名をまとうことになった。
朝日新聞での連載は、国男の文名を一挙に高めた。それまで通人として知られるばかりで、知る人ぞ知るという感のあった国男は、これによって旅の名エッセイストとしても広く知られることになる。そこには、日本の山水名勝を探索し、かずかずの紀行をものしていた国男の友人、田山花袋の描く風景とはまったくことなる人々の暮らしぶりがえがかれていた。
貴族院書記官長を辞任し、長い役人生活に決別を告げた柳田国男は、そのあと何をしようとしていたのだろう。旅をしてみたいという思いは強かっただろう。だが、国男ほどの名士で学者となれば、世間が気ままな漂泊を許しておくわけもない。すぐに朝日新聞編集局長の安藤正純から、東京朝日新聞入社への打診があった。
そのあたりの事情について、国男は『故郷七十年』で、次のように語っている。
〈もうそろそろ役人生活の足を洗ってよかろうと思った私は、大正9年(1920)いよいよ自由な生活に入ることとした。その7月朝日新聞の安藤正純氏からの連絡があったので客員の名義で入った。入社の条件として、最初の3年間は内地と外地とを旅行させてもらいたいという虫のいい希望を述べたが、幸いにも全部、村山老社長[龍平]の快諾するところとなった〉
これを読むと、すでに書記官長時代に打診があったかのように思えるが、そうではない。12月に役人をやめたあと、安藤から話がもちこまれたのは春になってからである。しかし、「右から左にお受けしたのではいかにも計画的のようでへんだからというので、6月まで自由に歩き回ってのち、7月から朝日の嘱託ということにしてもらった」と、同書の別の箇所で語っている。
こうして7月に国男は、朝日新聞社長の村山龍平と麻布市兵衛町の村山宅で会い、8月4日から朝日新聞の客員になることが決まった。そのとき国男の出した前代未聞の条件が、本人も語っているとおり「最初の3年間は内地と外地とを旅行させてもらいたいという虫のいい希望」だった。村山はその条件を快諾したというから、鷹揚なものである。月々の手当は300円[現在の感覚では100万円といったところか]、旅費は会社もちで別途支給ということも、そのとき決まった。
さて、その旅行だが、国男の腹づもりでは「その3年間の前半は国内を、後半は西洋、蘭印[現インドネシア]、濠州[オーストラリア]から太平洋方面を回りたい」というもの。「そしてこの3年間の旅が終わったら、正式の朝日社員になるということにしていたのであった」。
実際はこの目算は、のちに述べる事情、すなわち国男にたいし、ジュネーブの国際連盟委任統治委員会委員への就任要請があったため、わずか半年ばかりで頓挫することになる。だが、先のことはともかく、朝日入社が決まった時点では、本人はこれで自由に好きな旅行ができると内心喜んでいたのである。もちろん、その旅行とは名所旧跡をたずねる旅ではなく、人と民俗に学ぶ旅を意味していたことはいうまでもない。
年譜にしたがって、1920年から翌年にかけての国男の旅を整理してみると、こんなふうになる。
[1920〜21年]
6月15日〜24日 佐渡旅行
8月2日〜9月12日 東北旅行(東海岸を北上し、秋田まで)
10月中旬〜11月21日 中部地方および関西・中国旅行
12月13日〜3月1日 沖縄旅行(沖縄滞在は1月5日から2月7日まで)
朝日新聞の客員となってから半年のあいだは、ほとんど旅の人だったと知れる。東北の旅から帰って、ひと月ほど間があくのは、次女千枝が病気で入院し、「ふだんあまり文句をいわない養父から、この時だけは『こんな時ぐらい旅行をやめたらどうか』といわれた」ためである。「それから1カ月ぐらい、ぼそぼそして家におり」、また秋風にさそわれて旅にでた。
何が国男を駆りたてていたのだろう。東北のあと中部を回ったのは、江戸時代の旅行家、菅江真澄の事跡にひかれたという面がなかったわけではない。しかし、中部をはさんで、遊歴の地に共に辺境の東北と沖縄を求めたことは、無意識の選択がはたらいたとしか思えない。官界を蹴ったあとは、とりわけ民衆のほうへという志向が強まっていたのだろう。
8月以降の3つの旅行で、国男はそれぞれ紀行を朝日新聞に連載している。最初の東北が「豆手帖から」、中部が「秋風帖」、そして沖縄が「海南小記」で、それぞれのちに他のエッセイを加えて単行本として発刊されている。ただし「豆手帖から」だけは、さすがに本のタイトルとはしがたく、『雪国の春』という書名をまとうことになった。
朝日新聞での連載は、国男の文名を一挙に高めた。それまで通人として知られるばかりで、知る人ぞ知るという感のあった国男は、これによって旅の名エッセイストとしても広く知られることになる。そこには、日本の山水名勝を探索し、かずかずの紀行をものしていた国男の友人、田山花袋の描く風景とはまったくことなる人々の暮らしぶりがえがかれていた。
官界を去る [柳田国男の昭和]
《第233回》
柳田国男が門司港から信濃丸に乗って、台湾の基隆港にはいったのは1917年(大正6)3月27日のことである。ロシアでは2月革命が起こり、ケレンスキーの臨時政府が誕生していた。
国男は基隆(キールン)から列車で台北にはいり、そこで、さっそく視察や講演をこなした。30日からは友人の下村民政長官らと「蕃地視察」に出発し、台湾中央部の日月潭や霧社を訪れている。下村が公用で台北に戻ったあと、国男はさらに台南、高雄へと南下し、今度はその同じルートを北上、台中に1泊して、台北に戻っている。
台湾には2週間ほど滞在したが、その間に8首ほど歌を詠んだ。
湖の島で先住民が生活する山中の日月潭ではこう歌った。
海知らぬ島びとこそはあはれなれ
山のはざまをおのが世にして
霧社から戻るときの歌はこうだ。
時のまにとほ山まゆとなりにけり
わらひさやぎしえみし等のさと
霧社では1930年(昭和5)に大規模な抗日暴動が発生することになるが、国男は霧社を、かつてにぎやかだった「えみし等」の郷ととらえるにとどまっている。
台北に帰ると、待ちかまえていた友人たちが歓迎会を開いてくれた。そこで、国男は最初に「太平楽な長い演説」をしてから、傍若無人な歌を6首披露したという。
『故郷七十年』では、こう語っている。
〈第1首は、台南か台中か、生蕃[先住民]が叛乱して大勢殺された西螺街(せいらがい)とかいうところへ行ったとき、非常に強い印象を受けて、折があったら、その悲しみを話したいと思っていたので「大君はかみにましませば民草のかかる嘆きも知ろしめすらし」と吟じた。一座はしいーんとなったが、私としては実はそれが目的だったのである。畏れ多い話であるが、私どもは東京にいるから大正天皇さまがこういうことはまるでご承知ないことをよく知っている。それで詠みあげたものであった。私も若く意気軒昂としていたのであろう〉
この一節について、岡谷公二は国男の勘違いを指摘し、「彼が訪れたのは台南市の西来庵であり、叛乱をおこしたのは『生蕃』ではなく漢族で、事件がタパニーに移ってから『生蕃』の平埔族が一部同調したにすぎない」とする。
たしかに「台湾日日新報」に掲載された記事によると、国男が大君うんぬんの歌を詠んだ場所は「再(西)来庵」とされているので、「生蕃が叛乱して大勢殺された西螺街」というのは現地で説明を受けた国男の勘違いである可能性が強い。
タパニー、すなわち現在の玉井郷を国男が訪れたかどうかははっきりしない。また台南と台中のあいだに西螺街という場所もあり、ひょっとしたらここも訪れた可能性があるが、どこかで記憶の混同が生じたのかもしれない。だが、いずれにせよ、国男は台北の宴会で、だれもがぎょっとする天皇の名を出して、先住民とはいえ、同じ民草にはちがいないのだから、大量殺害などあってはならないのだと歌い、暗に武断政策をいましめたのだった。
4月10日朝には台北を出発し、基隆から襟裳丸に乗って大陸の厦門(アモイ)に向かった。その後の動きをまとめると、厦門からは汕頭(スワトウ)をへて広東にはいり、そこでわりあい長く滞在しながら、広東料理の贅沢ぶりにおどろきつつも、中国人のあいだに「情けないほどの著しい貧富の差」を感じて、悄然としている。
そのあと、上海行きの船がなかなかつかまえられなかったため、4月末まで広東付近にいて、川舟で珠江をさかのぼる旅をした。そのとき蛋民(たんみん)と呼ばれる水上生活者に興味をもち、それについてしらべてみたいと思ったのが、いかにも国男らしかった。
4月末、国男はようやくイギリス船に空きをみつけて、上海に向かった。上海では浄土真宗本願寺派の門主で探検家でもあった大谷光瑞(こうずい)の世話になり、またかつて早稲田大学に留学し、国男とも旧知だった戴天仇(たいてんきゅう)の案内で孫文とも会ったが、『故郷七十年』で語っているところでは「その内容はよく憶えていない」という。
袁世凱が中華民国大総統、さらに帝位に就いたとき、孫文は下野し、常に暗殺の危機に見舞われていた。国男が中国を訪れたころは、袁世凱が死去し、大総統の座を黎元洪(れいげんこう)が継いだものの、実力者総理で軍閥の段棋瑞(だんきずい)と対立し、中央政権が分裂しかかっているさなかだった。孫文は広東を拠点にして新政府を樹立し、巻き返しをはかろうとしていた。
やっかいな中国情勢を国男がどうみていたかはよくわからない。だが、帰国後、「日華クラブ」なるものを創立するために奔走するのをみると、国男が軍閥割拠の感を呈しつつあった中国の安定と発展に寄与したいと願っていたことはたしかである。だが、会長に近衛文麿を迎えたこのクラブも、あっけなく水泡と帰した。
上海滞在は短く、国男はあわただしく汽車で南京に向かい、そこから船に乗って漢口にはいった。いったん江西省の大治鉄山を訪れてからふたたび漢口に戻り、開通したばかりの京漢線に乗って、北京に到着した。北京滞在中、黎元洪と段棋瑞に会ったものの、それは儀礼的な訪問にとどまったようである。
北京を発ったのは5月20日。そろそろ帰国せねばならない時期が近づいていた。
『故郷七十年』では、こう語っている。
〈日本からきた新聞によって、政情がだいぶあやしいことが分かった。留守中に内閣の更迭でもあったらさぞ悪くいわれるだろうと思って気が気でなく、あとは奉天に1泊して大連へ往復したきりで、朝鮮を通り、大急ぎで東京へ帰ってきた〉
明治憲法は議院内閣制を採用していない。それでも政党の力は無視できなくなっていた。4月の総選挙では、原敬率いる政友会が圧勝した。そこで政党から一線を画していた寺内正毅(まさたけ)の超然内閣が、議会多数派となった政友会にどう対応するか、また政友会が寺内内閣にどういう態度で臨むかが問われていた。結果的に政友会は寺内内閣を支えることになるのだが、政権の安定を見越し、新議会の開催はせいぜい秋だろうと踏んでいた国男も、こうした政情不安を新聞で見て、すこしあわてたのである。
国男は奉天(現瀋陽)と大連に少し立ち寄り、京城(現ソウル)は2泊しただけで、釜山をへて、何やら気もそぞろで日本に帰国した。いくら退職覚悟の台湾・中国旅行とはいえ、ひょっとしたら寺内内閣が倒れるかもしれないというときに、現職の貴族院書記官長が外遊していてはしめしがつかないことくらいは、さすがにわかっていた。
旅行から戻ったあと、徳川貴族院議長との関係はますます険悪になっていった。しかし、何も過失はないのだから、みずから身を引くにはおよばない。国男は、その後の在任中も、実弟、松岡静雄の設立した「日蘭通交調査会」に協力したり、先に述べた「日華クラブ」の創立に奔走したりしていた。
ここに出てくる「日蘭通交調査会」は、日本とオランダの友好を促進することを目的にした団体である。だが、松岡静雄の真のねらいは蘭領インド(現インドネシア)にあり、日本の農民を蘭領インドに送りこみ、稲をつくらせることにあったという。岡谷公二は「移民と食糧増産と日蘭親善の一石三鳥を狙う計画が、具体的な目標だったようである」と述べている。だが、この壮大な計画も、静雄が病気で倒れたために、けっきょくは挫折を余儀なくされる。
貴族院議長との関係は日を追って悪化し、徳川家達は後継の原敬首相に書記官長は職務に不熱心であるとして、善処を申し入れるほどだった(『原敬日記』)。それは一方的な言い分にはちがいなかった。だが、国男の辞任を決定づける「事件」が起こる。
1919年(大正8)5月、国男は九州の漁村を旅行し、中国訪問以来興味をもっていた水上生活者について、話を聞いたり、調べものをしたりしている最中だった。
そのときのことだ。国男自身はこう話している。
〈それで用事を作って長崎に行き、平戸へ渡った。平戸の北の方にある大きな海女村を見たり、また大分県にあるシャアと呼ばれる海上生活をする人たちや、家船(えぶね)を見に行った。その留守中に内閣が異動したり、衆議院の官舎が焼けるという事件が起きてしまったのである。……急いで東京へ帰ってくるまでのうちに、もうだいぶ批判があって、そうでなくとも役所にはおられないと思っていたところだったから、辛うじて大正8年[末]までいるのに非常に骨が折れた。その年の下半期になると親類の者までがもう辞めなければみっともないなどと言ってきた〉
当時の議事堂は内幸町(経済産業省のあたり)に立っていた。この火事で貴族院のほうは無事だったが、衆議院の議場はほぼ丸焼けになった。国男が住まいとする官舎も、一時は家財を運びだすほどの騒然とした状況に見舞われた。そんなとき、のんびり九州を旅行していた国男に非難が集まったのはいたしかたなかっただろう。
辞職は必至となった。自身は何の非もないと思っていたから、詰め腹を切らされる思いだったにちがいない。その転任先は宮内省図書頭か帝室博物館長かとうわさされたが、国男はそれを固辞する。このふたつの職がある人物、すなわち敬愛する森鷗外によって兼任されていたからである。それを奪うわけにはいかない。
1919年(大正8)12月21日、貴族院書記官長の国男は原首相に辞意を表明し、20年近い官界生活に終止符を打った。数えで45歳のことである。
柳田国男が門司港から信濃丸に乗って、台湾の基隆港にはいったのは1917年(大正6)3月27日のことである。ロシアでは2月革命が起こり、ケレンスキーの臨時政府が誕生していた。
国男は基隆(キールン)から列車で台北にはいり、そこで、さっそく視察や講演をこなした。30日からは友人の下村民政長官らと「蕃地視察」に出発し、台湾中央部の日月潭や霧社を訪れている。下村が公用で台北に戻ったあと、国男はさらに台南、高雄へと南下し、今度はその同じルートを北上、台中に1泊して、台北に戻っている。
台湾には2週間ほど滞在したが、その間に8首ほど歌を詠んだ。
湖の島で先住民が生活する山中の日月潭ではこう歌った。
海知らぬ島びとこそはあはれなれ
山のはざまをおのが世にして
霧社から戻るときの歌はこうだ。
時のまにとほ山まゆとなりにけり
わらひさやぎしえみし等のさと
霧社では1930年(昭和5)に大規模な抗日暴動が発生することになるが、国男は霧社を、かつてにぎやかだった「えみし等」の郷ととらえるにとどまっている。
台北に帰ると、待ちかまえていた友人たちが歓迎会を開いてくれた。そこで、国男は最初に「太平楽な長い演説」をしてから、傍若無人な歌を6首披露したという。
『故郷七十年』では、こう語っている。
〈第1首は、台南か台中か、生蕃[先住民]が叛乱して大勢殺された西螺街(せいらがい)とかいうところへ行ったとき、非常に強い印象を受けて、折があったら、その悲しみを話したいと思っていたので「大君はかみにましませば民草のかかる嘆きも知ろしめすらし」と吟じた。一座はしいーんとなったが、私としては実はそれが目的だったのである。畏れ多い話であるが、私どもは東京にいるから大正天皇さまがこういうことはまるでご承知ないことをよく知っている。それで詠みあげたものであった。私も若く意気軒昂としていたのであろう〉
この一節について、岡谷公二は国男の勘違いを指摘し、「彼が訪れたのは台南市の西来庵であり、叛乱をおこしたのは『生蕃』ではなく漢族で、事件がタパニーに移ってから『生蕃』の平埔族が一部同調したにすぎない」とする。
たしかに「台湾日日新報」に掲載された記事によると、国男が大君うんぬんの歌を詠んだ場所は「再(西)来庵」とされているので、「生蕃が叛乱して大勢殺された西螺街」というのは現地で説明を受けた国男の勘違いである可能性が強い。
タパニー、すなわち現在の玉井郷を国男が訪れたかどうかははっきりしない。また台南と台中のあいだに西螺街という場所もあり、ひょっとしたらここも訪れた可能性があるが、どこかで記憶の混同が生じたのかもしれない。だが、いずれにせよ、国男は台北の宴会で、だれもがぎょっとする天皇の名を出して、先住民とはいえ、同じ民草にはちがいないのだから、大量殺害などあってはならないのだと歌い、暗に武断政策をいましめたのだった。
4月10日朝には台北を出発し、基隆から襟裳丸に乗って大陸の厦門(アモイ)に向かった。その後の動きをまとめると、厦門からは汕頭(スワトウ)をへて広東にはいり、そこでわりあい長く滞在しながら、広東料理の贅沢ぶりにおどろきつつも、中国人のあいだに「情けないほどの著しい貧富の差」を感じて、悄然としている。
そのあと、上海行きの船がなかなかつかまえられなかったため、4月末まで広東付近にいて、川舟で珠江をさかのぼる旅をした。そのとき蛋民(たんみん)と呼ばれる水上生活者に興味をもち、それについてしらべてみたいと思ったのが、いかにも国男らしかった。
4月末、国男はようやくイギリス船に空きをみつけて、上海に向かった。上海では浄土真宗本願寺派の門主で探検家でもあった大谷光瑞(こうずい)の世話になり、またかつて早稲田大学に留学し、国男とも旧知だった戴天仇(たいてんきゅう)の案内で孫文とも会ったが、『故郷七十年』で語っているところでは「その内容はよく憶えていない」という。
袁世凱が中華民国大総統、さらに帝位に就いたとき、孫文は下野し、常に暗殺の危機に見舞われていた。国男が中国を訪れたころは、袁世凱が死去し、大総統の座を黎元洪(れいげんこう)が継いだものの、実力者総理で軍閥の段棋瑞(だんきずい)と対立し、中央政権が分裂しかかっているさなかだった。孫文は広東を拠点にして新政府を樹立し、巻き返しをはかろうとしていた。
やっかいな中国情勢を国男がどうみていたかはよくわからない。だが、帰国後、「日華クラブ」なるものを創立するために奔走するのをみると、国男が軍閥割拠の感を呈しつつあった中国の安定と発展に寄与したいと願っていたことはたしかである。だが、会長に近衛文麿を迎えたこのクラブも、あっけなく水泡と帰した。
上海滞在は短く、国男はあわただしく汽車で南京に向かい、そこから船に乗って漢口にはいった。いったん江西省の大治鉄山を訪れてからふたたび漢口に戻り、開通したばかりの京漢線に乗って、北京に到着した。北京滞在中、黎元洪と段棋瑞に会ったものの、それは儀礼的な訪問にとどまったようである。
北京を発ったのは5月20日。そろそろ帰国せねばならない時期が近づいていた。
『故郷七十年』では、こう語っている。
〈日本からきた新聞によって、政情がだいぶあやしいことが分かった。留守中に内閣の更迭でもあったらさぞ悪くいわれるだろうと思って気が気でなく、あとは奉天に1泊して大連へ往復したきりで、朝鮮を通り、大急ぎで東京へ帰ってきた〉
明治憲法は議院内閣制を採用していない。それでも政党の力は無視できなくなっていた。4月の総選挙では、原敬率いる政友会が圧勝した。そこで政党から一線を画していた寺内正毅(まさたけ)の超然内閣が、議会多数派となった政友会にどう対応するか、また政友会が寺内内閣にどういう態度で臨むかが問われていた。結果的に政友会は寺内内閣を支えることになるのだが、政権の安定を見越し、新議会の開催はせいぜい秋だろうと踏んでいた国男も、こうした政情不安を新聞で見て、すこしあわてたのである。
国男は奉天(現瀋陽)と大連に少し立ち寄り、京城(現ソウル)は2泊しただけで、釜山をへて、何やら気もそぞろで日本に帰国した。いくら退職覚悟の台湾・中国旅行とはいえ、ひょっとしたら寺内内閣が倒れるかもしれないというときに、現職の貴族院書記官長が外遊していてはしめしがつかないことくらいは、さすがにわかっていた。
旅行から戻ったあと、徳川貴族院議長との関係はますます険悪になっていった。しかし、何も過失はないのだから、みずから身を引くにはおよばない。国男は、その後の在任中も、実弟、松岡静雄の設立した「日蘭通交調査会」に協力したり、先に述べた「日華クラブ」の創立に奔走したりしていた。
ここに出てくる「日蘭通交調査会」は、日本とオランダの友好を促進することを目的にした団体である。だが、松岡静雄の真のねらいは蘭領インド(現インドネシア)にあり、日本の農民を蘭領インドに送りこみ、稲をつくらせることにあったという。岡谷公二は「移民と食糧増産と日蘭親善の一石三鳥を狙う計画が、具体的な目標だったようである」と述べている。だが、この壮大な計画も、静雄が病気で倒れたために、けっきょくは挫折を余儀なくされる。
貴族院議長との関係は日を追って悪化し、徳川家達は後継の原敬首相に書記官長は職務に不熱心であるとして、善処を申し入れるほどだった(『原敬日記』)。それは一方的な言い分にはちがいなかった。だが、国男の辞任を決定づける「事件」が起こる。
1919年(大正8)5月、国男は九州の漁村を旅行し、中国訪問以来興味をもっていた水上生活者について、話を聞いたり、調べものをしたりしている最中だった。
そのときのことだ。国男自身はこう話している。
〈それで用事を作って長崎に行き、平戸へ渡った。平戸の北の方にある大きな海女村を見たり、また大分県にあるシャアと呼ばれる海上生活をする人たちや、家船(えぶね)を見に行った。その留守中に内閣が異動したり、衆議院の官舎が焼けるという事件が起きてしまったのである。……急いで東京へ帰ってくるまでのうちに、もうだいぶ批判があって、そうでなくとも役所にはおられないと思っていたところだったから、辛うじて大正8年[末]までいるのに非常に骨が折れた。その年の下半期になると親類の者までがもう辞めなければみっともないなどと言ってきた〉
当時の議事堂は内幸町(経済産業省のあたり)に立っていた。この火事で貴族院のほうは無事だったが、衆議院の議場はほぼ丸焼けになった。国男が住まいとする官舎も、一時は家財を運びだすほどの騒然とした状況に見舞われた。そんなとき、のんびり九州を旅行していた国男に非難が集まったのはいたしかたなかっただろう。
辞職は必至となった。自身は何の非もないと思っていたから、詰め腹を切らされる思いだったにちがいない。その転任先は宮内省図書頭か帝室博物館長かとうわさされたが、国男はそれを固辞する。このふたつの職がある人物、すなわち敬愛する森鷗外によって兼任されていたからである。それを奪うわけにはいかない。
1919年(大正8)12月21日、貴族院書記官長の国男は原首相に辞意を表明し、20年近い官界生活に終止符を打った。数えで45歳のことである。
覚悟の台湾・中国旅行 [柳田国男の昭和]
《第232回》
『故郷七十年』で、柳田国男は貴族院書記官長時代の台湾・中国旅行について、次のように話している。
〈台湾から大陸にかけて大旅行をしたのは、たしか大正6年[1917]である。前の佐久間台湾総督と、内田嘉吉(かきち)民政長官とが生蕃事件で退いた後を引き受けた安東貞美総督は養家の叔父に当たっていた。つまり桑木厳翼(げんよく)夫人の父である。そして民政長官に選ばれたのが下村宏君であった。私は内田君が本好きだったので親しくしていたが、下村君とも知り合いだったので、何だか同君を叔父に推薦したように思っている人も少なくなかった。そんな噂を聞いて下村君は私を歓待するつもりで台湾に誘ってくれた。しかし実際は内田君の時、下準備をしてくれていたらしかった。招かれていい気になって貴族院議長ともあまり相談せずに、その申し出をうけてしまったが、それが私の失敗の原因で、後々いつまでもごたごたとしてしまったのである〉
かなり人間関係が入り組んでいるので、整理しておかないと、背景がよくわからない。岡谷公二の『貴族院書記官長柳田国男』などを参照しながら、話を進めることにしよう。
当時日本の植民地だった台湾には台湾総督府がおかれていた。1914年[大正3]11月、5代目総督、佐久間左馬太(さまた)は健康上の理由で辞意を表明し、翌年5月に安東貞美が総督に就任する。佐久間も安東もともに陸軍出身。安東は国男の養父、柳田直平(なおひら)の実弟で、朝鮮駐剳(ちゅうさつ)軍司令官を務めたこともある。そして、安東の娘が、主にカント哲学を専攻する東京帝国大学教授の桑木厳翼に嫁いでいた。
前任総督の佐久間は高砂族の討伐と鎮圧に意を砕き、いわゆる理蕃政策を実施した。高砂族とは、台湾の高地先住民(生蕃)につけられた日本側の名称で、植民地当局者は強引にかれらの同化政策をこころみるいっぽうで、その土地の大半を奪っていた。
大江志乃夫の『日本植民地探訪』には次のような記述がある。
〈1909年(明治42)、時の総督陸軍大将佐久間左馬太は、5カ年計画で、軍隊を投入しての大討伐を行い、隘勇線(あいゆうせん)[先住民の立ち入り禁止ライン]を前進させて包囲の鉄環をちぢめ、「生蕃」を標高3000メートル以上の高山がつらなる台湾脊梁山系に追いあげ、追いつめ、糧道を絶って、降伏か餓死かの二者択一を迫る作戦を開始した。5年目の1914年(大正3)、当時の台湾守備隊の兵力の大部分を投入して西側から脊梁山系を越えさせ、東海岸から警察隊を進撃させ、最後の包囲網圧縮を行い、5か年計画を終了させたのであった〉
先住民に対する圧迫がすさまじいものであったことがわかる。
1915年6月、安東の着任早々、大規模な反乱が発生した。いわゆる西来庵事件(タパニー事件)である。事件そのものは、佐久間による高地先住民弾圧政策と直接関係がない。しかし、共有地だった林野を日本側に奪われていたのは、平地に住む漢族や平埔族(漢族に同化した平地先住民)も同じだった。
西来庵は台南の道教系秘密結社で、その指導者、余清芳は日本統治からの脱却を訴え、植民地化20周年にあたる6月17日を期に武装蜂起を計画していた。だが、その計画は事前に察知され、多数の関係者が逮捕された。余清芳は網の目をくぐって、台南北東70キロほどのタパニー地方に逃れ、山間に閉じこもりながら、地元住民たちとともに役所を占拠するなどして、1カ月にわたり日本側と戦いをくり広げた。
文献により数字はまちまちだが、その際、日本人が95人殺害され、村民にも多くの死傷者が出て、台湾当局は余清芳をはじめとして1957人を逮捕、866人に死刑を宣告された(大正天皇による恩赦があり、実際に処刑されたのは日本人殺害者数と同じ95人)。
大きな反乱事件だった。だが着任早々の安東総督は責任を問われることなく、その代わりに民政長官の内田嘉吉が辞任して、逓信省貯金局長だった下村宏がその後任となった。国男が叔父の安東から相談をもちかけられて、下村を推薦したことはじゅうぶんにありうると岡谷公二は推測している。
ちなみに内田嘉吉も後任の下村と同じく逓信省出身で、いったん民政長官をやめたあと、1923年[大正12]に第9代台湾総督に就任する。読書人でもあり、南洋に造詣が深く、アルフレッド・ウォーレスの『南洋』(のち『馬来(マレー)諸島』と改題)を翻訳したことでも知られていた。
下村宏は海南の号をもつ歌人でもあり、のちに朝日新聞副社長となり、終戦時には情報局総裁として玉音放送の前後にラジオで司会役を果たしている。国男とは大学は2年先輩だが、同年齢で、古くからの友人だった。
いずれにせよ叔父の安東や友人の下村とのつながりが、国男に台湾旅行を促すきっかけになったことはまちがいない。台湾、中国も含めて、国男の出張扱いの旅行は、3月20日から6月3日までの長期におよんだ。時あたかも議会は休会中で、4月20日に衆議院総選挙がおこなわれることになっていた。その結果は原敬率いる政友会の圧勝に終わるものの、寺内正毅内閣はもうしばらくつづく。旅に出る前、国男は政局にそれほど変化はあるまいと高をくくっていた。
しかし、国男と貴族院議長、徳川家達との関係はすでにぎくしゃくしていた。貴族院の事務方は議院の運営をサポートするのが仕事であって、何も議長の召使いではない。それでも議長との意思疎通がうまくいかなくなっていることは、具合が悪かったのではないだろうか。
台湾旅行への誘いは、貴族院の仕事にうんざりしはじめていた国男にとっては、まさに渡りに船でもあった。だが、みずから書記官長をやめるつもりがなかったことは、旅行から戻ってから、さらに1年半このポストを維持した経緯をみても明らかである。議長と書記官長の意地の張り合いみたいなところもある。
旅に出る直前、国男は4年間出しつづけてきた雑誌「郷土研究」を休刊している。そろそろ新しい材料が集まらなくなったのも事実だが、『故郷七十年』で述べているように、「貴族院もそろそろやめなければならない情勢になってきたと思ったので、『郷土研究』も残っていると後がまずいと考え、口実を作って4巻でやめたしまった」というのがホンネだった。
つまり、国男にとって台湾・中国行は、なかば書記官長辞任を覚悟した旅立ちだったのである。次の身の処し方に向けての模索がはじまっていた。
『故郷七十年』で、柳田国男は貴族院書記官長時代の台湾・中国旅行について、次のように話している。
〈台湾から大陸にかけて大旅行をしたのは、たしか大正6年[1917]である。前の佐久間台湾総督と、内田嘉吉(かきち)民政長官とが生蕃事件で退いた後を引き受けた安東貞美総督は養家の叔父に当たっていた。つまり桑木厳翼(げんよく)夫人の父である。そして民政長官に選ばれたのが下村宏君であった。私は内田君が本好きだったので親しくしていたが、下村君とも知り合いだったので、何だか同君を叔父に推薦したように思っている人も少なくなかった。そんな噂を聞いて下村君は私を歓待するつもりで台湾に誘ってくれた。しかし実際は内田君の時、下準備をしてくれていたらしかった。招かれていい気になって貴族院議長ともあまり相談せずに、その申し出をうけてしまったが、それが私の失敗の原因で、後々いつまでもごたごたとしてしまったのである〉
かなり人間関係が入り組んでいるので、整理しておかないと、背景がよくわからない。岡谷公二の『貴族院書記官長柳田国男』などを参照しながら、話を進めることにしよう。
当時日本の植民地だった台湾には台湾総督府がおかれていた。1914年[大正3]11月、5代目総督、佐久間左馬太(さまた)は健康上の理由で辞意を表明し、翌年5月に安東貞美が総督に就任する。佐久間も安東もともに陸軍出身。安東は国男の養父、柳田直平(なおひら)の実弟で、朝鮮駐剳(ちゅうさつ)軍司令官を務めたこともある。そして、安東の娘が、主にカント哲学を専攻する東京帝国大学教授の桑木厳翼に嫁いでいた。
前任総督の佐久間は高砂族の討伐と鎮圧に意を砕き、いわゆる理蕃政策を実施した。高砂族とは、台湾の高地先住民(生蕃)につけられた日本側の名称で、植民地当局者は強引にかれらの同化政策をこころみるいっぽうで、その土地の大半を奪っていた。
大江志乃夫の『日本植民地探訪』には次のような記述がある。
〈1909年(明治42)、時の総督陸軍大将佐久間左馬太は、5カ年計画で、軍隊を投入しての大討伐を行い、隘勇線(あいゆうせん)[先住民の立ち入り禁止ライン]を前進させて包囲の鉄環をちぢめ、「生蕃」を標高3000メートル以上の高山がつらなる台湾脊梁山系に追いあげ、追いつめ、糧道を絶って、降伏か餓死かの二者択一を迫る作戦を開始した。5年目の1914年(大正3)、当時の台湾守備隊の兵力の大部分を投入して西側から脊梁山系を越えさせ、東海岸から警察隊を進撃させ、最後の包囲網圧縮を行い、5か年計画を終了させたのであった〉
先住民に対する圧迫がすさまじいものであったことがわかる。
1915年6月、安東の着任早々、大規模な反乱が発生した。いわゆる西来庵事件(タパニー事件)である。事件そのものは、佐久間による高地先住民弾圧政策と直接関係がない。しかし、共有地だった林野を日本側に奪われていたのは、平地に住む漢族や平埔族(漢族に同化した平地先住民)も同じだった。
西来庵は台南の道教系秘密結社で、その指導者、余清芳は日本統治からの脱却を訴え、植民地化20周年にあたる6月17日を期に武装蜂起を計画していた。だが、その計画は事前に察知され、多数の関係者が逮捕された。余清芳は網の目をくぐって、台南北東70キロほどのタパニー地方に逃れ、山間に閉じこもりながら、地元住民たちとともに役所を占拠するなどして、1カ月にわたり日本側と戦いをくり広げた。
文献により数字はまちまちだが、その際、日本人が95人殺害され、村民にも多くの死傷者が出て、台湾当局は余清芳をはじめとして1957人を逮捕、866人に死刑を宣告された(大正天皇による恩赦があり、実際に処刑されたのは日本人殺害者数と同じ95人)。
大きな反乱事件だった。だが着任早々の安東総督は責任を問われることなく、その代わりに民政長官の内田嘉吉が辞任して、逓信省貯金局長だった下村宏がその後任となった。国男が叔父の安東から相談をもちかけられて、下村を推薦したことはじゅうぶんにありうると岡谷公二は推測している。
ちなみに内田嘉吉も後任の下村と同じく逓信省出身で、いったん民政長官をやめたあと、1923年[大正12]に第9代台湾総督に就任する。読書人でもあり、南洋に造詣が深く、アルフレッド・ウォーレスの『南洋』(のち『馬来(マレー)諸島』と改題)を翻訳したことでも知られていた。
下村宏は海南の号をもつ歌人でもあり、のちに朝日新聞副社長となり、終戦時には情報局総裁として玉音放送の前後にラジオで司会役を果たしている。国男とは大学は2年先輩だが、同年齢で、古くからの友人だった。
いずれにせよ叔父の安東や友人の下村とのつながりが、国男に台湾旅行を促すきっかけになったことはまちがいない。台湾、中国も含めて、国男の出張扱いの旅行は、3月20日から6月3日までの長期におよんだ。時あたかも議会は休会中で、4月20日に衆議院総選挙がおこなわれることになっていた。その結果は原敬率いる政友会の圧勝に終わるものの、寺内正毅内閣はもうしばらくつづく。旅に出る前、国男は政局にそれほど変化はあるまいと高をくくっていた。
しかし、国男と貴族院議長、徳川家達との関係はすでにぎくしゃくしていた。貴族院の事務方は議院の運営をサポートするのが仕事であって、何も議長の召使いではない。それでも議長との意思疎通がうまくいかなくなっていることは、具合が悪かったのではないだろうか。
台湾旅行への誘いは、貴族院の仕事にうんざりしはじめていた国男にとっては、まさに渡りに船でもあった。だが、みずから書記官長をやめるつもりがなかったことは、旅行から戻ってから、さらに1年半このポストを維持した経緯をみても明らかである。議長と書記官長の意地の張り合いみたいなところもある。
旅に出る直前、国男は4年間出しつづけてきた雑誌「郷土研究」を休刊している。そろそろ新しい材料が集まらなくなったのも事実だが、『故郷七十年』で述べているように、「貴族院もそろそろやめなければならない情勢になってきたと思ったので、『郷土研究』も残っていると後がまずいと考え、口実を作って4巻でやめたしまった」というのがホンネだった。
つまり、国男にとって台湾・中国行は、なかば書記官長辞任を覚悟した旅立ちだったのである。次の身の処し方に向けての模索がはじまっていた。
大嘗祭をめぐって [柳田国男の昭和]
《第231回》

人生にはいくつか忘れられない経験というものがある。柳田国男にとって、そのひとつが1915年(大正4)の京都での御大礼だったことは、まずまちがいない。
御大礼とは、天皇の即位式、大嘗祭などの一連の行事をさす。1915年の御大礼では、大礼使総裁が伏見宮貞愛親王、同長官が鷹司煕通公爵で、国男は衆議院書記官長の岡崎国臣などとともに大礼使事務官に任命されている。
大正天皇の即位式は11月10日、大嘗祭は同14日、ともに京都でおこなわれることになった。夏から秋にかけ国男は何度も京都に出張し、周囲にけむたがられるほど、大礼の儀礼について、こまかく指示をだしたとされる。
11月にはいると国男は京都に宿をとり、大礼の準備と事務にあたった。11月6日、大正天皇は朝7時の御召列車で東京を出発、その日は名古屋で1泊し、翌日午後2時半、京都駅に到着した。のちに国男が記したところによると、この日は晴天で雲ひとつなく、通りが人でごった返すなか、若王子の山の中腹に一筋、二筋の白い煙が立っていたという。そのとき「ははあサンカが話をしているな」と思ったのは、いかにも国男らしい観察だった。
即位の大礼は、午前中に「賢所大前の儀」、午後に「紫宸殿の儀」がとどこおりなく、おこなわれた。
岡谷公二はこう書いている。
〈午後の紫宸殿の儀は、紫宸殿において天皇が高御座(たかみくら)に上り、即位のことを一般臣民に宣告する、いわば本来の即位式である。天皇が臣民を代表する大隈首相に勅語を下したあと、首相が寿詞(よごと)を奏上、万歳三唱をもって、午後3時半、儀式は終わった。そしてこの時刻を期して、日本の至るところで、人々の万歳の声がひびき渡った。
もちろん柳田国男は、この日も[1600人近い]参列者の中にいた。しかし不思議なことに、大嘗祭についてはあれほど多弁だった彼が、即位の大礼に関しては、なにひとつ感想を洩らしていない〉
即位式の様子は平成の時代も変わらない。だが、国男が「即位の大礼に関しては、なにひとつ感想を洩らしていない」というのは、何を意味するのだろう。現実政治から超然としていた国男のことである。天皇の即位はたしかに政治であっても、天皇の本質からすれば二義的な問題にすぎないと考えていたのだろうか。
即位式から4日後に大嘗祭がとりおこなわれた。その前日、小御所表の間でおこなわれた「鎮魂の儀」に、国男は大礼使高等官として参列した。式がはじまるのは日の落ちた午後6時からである。岡谷によると、神座(かみくら)を前に、灯明の光だけがふるえる闇のなか、最初に降神の儀、つづいて献供の儀がなされたあと、「白木の筥(はこ)に納められた天皇の御衣、錦の袋に入れられた玉の緒」が運ばれてきた。
そのあとの様子を、岡谷は次のように記述している。
〈やがて、天鈿女命(あめのうずめのみこと)が汗気(うけ[桶])を踏みとどろかして天照大神の怒りを鎮めようとした故事にならい、内掌典が、盥(たらい)の形をした宇気槽(うけぶね)の上にのり、桙(ほこ)をとってそれを十度つくあいだ、掌典は、その一度ごとに玉の緒の糸をむすんだ。これは、魂を結びとめる象徴的行為とされている。
玉の緒の儀の次は御衣震動の儀である。掌典が白木の筥をあけて御衣をとり、これを神前にむかって十度振り動かし、そしてもとの場所に納める〉
これが儀式のハイライトだといってよい。これがすむと、御衣と玉の緒が運びだされ、大直歌(おおなおいのうた)、倭舞(やまとまい)とつづいて、昇神の儀があって、式が終わる。
鎮魂の儀は、重要な儀式を前にして、天皇の魂を強化するための式と理解されることが多い。はたしてそうだろうか。それは文字どおり、先帝の魂を祭り、しずめる儀式と理解されるべきではないか。それが終わらなければ、大嘗祭も新嘗祭もおこなえないのである。
そして、その翌日がいよいよ大嘗祭(天皇即位後、初の新嘗祭)ということになる。この祭のために仙洞御所内に造られた大嘗宮は、東の悠紀殿、西の主基殿からなり、全体を芝垣で囲み、東西南北に神門がもうけられていた。千人近い参列者は、外の幄舎にならび、芝垣内にはいることは許されない。
この日、国男は南面神門の内掖において、「威儀の本位」についた。平たくいえば、これは古式にのっとり、弓矢をたずさえて、警備を務める役である。
大嘗祭がはじまるのも日が落ちてからだ。
岡谷はこう書いている。
〈式次第を簡単に述べると、7時頃天皇は回立殿[北面神門の北にあり、天皇が潔斎、着替えをする建物]に入って、祭服に着替え、まず悠紀殿に渡御、神饌行立(ぎょうりゅう)と称して、8人の女官が次々に運んできた神饌を神に供え、拝礼ののち告文を奏し、自らも新穀新酒を味わう。すなわち直会(なおらい)の儀である。そのあといったん休憩があり、参列者全員に夜食が出る。午前2時頃天皇は再び回立殿に出御、祭服に更めて、今度は主基殿へ。ここでは、悠紀殿とほぼ同じ儀があって、しらじら明けのころ、すべてが終わった〉
このとき「威儀の本位」についた国男は「神代の霊域に在るような感に打たれ」、儀式の様子が「神威おのずから迫るように覚え、言葉にも筆にも尽くされぬ尊さを感じました」などと、その感激を休憩のあいだに記者団に語っている。
いっぽうで国男が御大礼のありように疑問をもっていたことがいまではわかっている。その意見をおおやけにすることは、ゆゆしき事態を招きかねなかった。そこでかれは「大嘗祭に関する所感」を記し、これをひそかに山県有朋に建議するつもりでいた。だが、どういう事情があったのか、建議書はけっきょく提出されないまま筐底にしまいこまれた。公表されたのは国男の死後である。
この「所感」には何が書かれていたのだろう。漢字カナ混じりの建議書を口語訳して、その一部だけでも示しておくことにしよう。
冒頭にはこうある。
〈今回の御大典の儀制を今後とも続ける場合はもちろん、将来これを改訂しようとする場合においては、小官の地位において感じ、かつ疑問に思った事項を記録することが有益だと信じますので、衷心を吐露して、当局の参考になればと考え、意見を述べることとしました。もとより言論の責任を回避するものではありませんが、いたずらに議論をたたかわせようとするものでもありませんので、これはできれば秘封として、後年に伝えていただければと存じる次第です〉
そうことわったうえで、国男は即位礼と大嘗会を立て続けにおこなうことに疑問を呈し、次のように述べている。
〈御即位礼と大嘗会を旧都[京都]で挙行されることは、先帝陛下[明治天皇]の深い思し召しによることと拝察しますが、よくよく考究いたしますと、次の点も問題として考えなくてはなりません。ことに御即位礼と大嘗祭とを同じ秋冬の交につづけておこなうという点は、よくよく考慮の余地があると思います。……即位礼は中世に外国の文物が輸入されたあと新たに制定されたもので、いわば国威発揚の国際的儀式であります。これに対し、古代からつづく大嘗祭は、国民全体の信仰に根柢を有するものであって、世の中が新しくなったいまも、ますますその斎忌を厳重にする必要があるのです。したがって、華々しい即位の儀式によって民心の興奮がいまだ去らない時期に、このように幽玄な儀式を執りおこなうことは不適当であると理解するのが正しいと存じます〉
要するに、国男は華々しい即位礼と幽玄な大嘗祭を、つづけてではなく分離しておこなえと主張しているのである。さらに具体的な提案は、この長い建白書の最後を読めば、出てくる。
〈今日もっともよくないと思う点は、即位礼の盛儀によって民心が盛り上がり、何とかして慶賀の意を表そうとして、各種の祝宴が開かれている最中に、引き続いて厳粛かつ絶対的な謹慎を必要とする祭典を挙げるという仕組みにあります。ついては、もし強いて京都において同時にこのふたつの式をおこなうのであれば、まず大嘗会を終えて次に即位礼をおこなうようにするか、さもなければ即位礼は東京で華々しく挙行し、ある期間をおいて、古い慣例のとおり新暦12月に京都において大嘗祭をおこなうか、あるいはまた京都で即位礼と関連の祝典を挙げ、ご帰還ののち、その秋に東都で静かに祭をおこなわれるか、さらにまた一定の期間、京都に滞在されて、民心の静まるのを待ってこの祭をおこなうかのどれかです。いずれにしても今回のような混乱のうちに三千年来の儀式を終えるような前例を繰り返さないことを切望いたします〉
国男が何としても即位礼と大嘗祭を引き離したいと願っていたのは、いうまでもなく大嘗祭のなかに国民の信仰の根柢を感じていたからである。大嘗祭は天皇即位後、初の新嘗祭を意味するが、この新嘗祭は本来旧暦の11月におこなわれていた。ところがそれを新暦の11月にそっくり繰り上げてしまったのもおかしい、と国男は憤懣やるかたない。
〈大嘗祭は古来旧暦の11月、すなわち仲冬の候をもってその季節とされておりましたが、これも日本の伝来の信仰と関係があります。この祭のために設けられる仮宮は、いかに優美な風習に染まる朝廷でありましても、徹底的に古式を保存し、一切の装飾を去り、素朴簡古をきわめねばなりません。……ところが今回のように、これを11月中におこなうとするときは、まずその精神と相いれない変態(おかしな事態)を認めることになってしまうのです〉
国男は、たとえば米の収穫が終わらないうちに、葺きワラ用に稲を刈り取ってしまう不都合にはじまって、黒木の柱の切り取り方、青柴垣に用いられる柴や葉盤、葉椀のありようも古式からずれると主張して、うるさいくらいまで祭の季節変更がおよぼした弊害を言いつのっている。
即位式についてはほとんど何もいわなかった国男が、祭に関しては周囲を閉口させるほど、いかにうるさかったかがわかる。
そればかりではない。国男の「所感」はつづく。即位式が終わってすぐに大嘗祭を実施したために、祭の参列者が千人以上になり、そのために周囲に大建築物を用意しなければならなくなったことも問題だった。新暦の11月とはいえ、底冷えのする夜の京都では具合の悪くなる老人が続出した。
国男にいわせれば、重要な儀式を半月前にして、陸軍が気候不順な弘前の大演習に天皇を引っ張りだしたことも大問題だった。大嘗祭の前夜だというのに、京都の市民が赤々と電灯をつけ、その下を派手な格好をして練り歩いたり、大声を出して酒楼で歌ったり、火を忌まず肉を食らって平気なことも腹立たしいかぎりだった。
国男にとって、あるべき大嘗祭の姿は次のようなものだ。
〈前代の大嘗祭の記録をみると、小忌(おみ)の役に任ずる者はもちろん大忌(おおみ)の員に列する者も、きわめてその数を限定し、一般民衆もおのおのその家にあって身を浄めて大祭がとどこおりなく終了することを心より祈っておりました。まことに小さなこととはいえ、これは村々では祭の夜、氏子の者が家にあって暁を静かに待っていたのと同じことであります〉
国男にとって、大嘗祭は華やかなものではなく、古式ゆかしいものでなければならなかった。そして、大嘗祭とのかかわりは、その後の柳田民俗学の骨格を決定づけていくことになるのである。

人生にはいくつか忘れられない経験というものがある。柳田国男にとって、そのひとつが1915年(大正4)の京都での御大礼だったことは、まずまちがいない。
御大礼とは、天皇の即位式、大嘗祭などの一連の行事をさす。1915年の御大礼では、大礼使総裁が伏見宮貞愛親王、同長官が鷹司煕通公爵で、国男は衆議院書記官長の岡崎国臣などとともに大礼使事務官に任命されている。
大正天皇の即位式は11月10日、大嘗祭は同14日、ともに京都でおこなわれることになった。夏から秋にかけ国男は何度も京都に出張し、周囲にけむたがられるほど、大礼の儀礼について、こまかく指示をだしたとされる。
11月にはいると国男は京都に宿をとり、大礼の準備と事務にあたった。11月6日、大正天皇は朝7時の御召列車で東京を出発、その日は名古屋で1泊し、翌日午後2時半、京都駅に到着した。のちに国男が記したところによると、この日は晴天で雲ひとつなく、通りが人でごった返すなか、若王子の山の中腹に一筋、二筋の白い煙が立っていたという。そのとき「ははあサンカが話をしているな」と思ったのは、いかにも国男らしい観察だった。
即位の大礼は、午前中に「賢所大前の儀」、午後に「紫宸殿の儀」がとどこおりなく、おこなわれた。
岡谷公二はこう書いている。
〈午後の紫宸殿の儀は、紫宸殿において天皇が高御座(たかみくら)に上り、即位のことを一般臣民に宣告する、いわば本来の即位式である。天皇が臣民を代表する大隈首相に勅語を下したあと、首相が寿詞(よごと)を奏上、万歳三唱をもって、午後3時半、儀式は終わった。そしてこの時刻を期して、日本の至るところで、人々の万歳の声がひびき渡った。
もちろん柳田国男は、この日も[1600人近い]参列者の中にいた。しかし不思議なことに、大嘗祭についてはあれほど多弁だった彼が、即位の大礼に関しては、なにひとつ感想を洩らしていない〉
即位式の様子は平成の時代も変わらない。だが、国男が「即位の大礼に関しては、なにひとつ感想を洩らしていない」というのは、何を意味するのだろう。現実政治から超然としていた国男のことである。天皇の即位はたしかに政治であっても、天皇の本質からすれば二義的な問題にすぎないと考えていたのだろうか。
即位式から4日後に大嘗祭がとりおこなわれた。その前日、小御所表の間でおこなわれた「鎮魂の儀」に、国男は大礼使高等官として参列した。式がはじまるのは日の落ちた午後6時からである。岡谷によると、神座(かみくら)を前に、灯明の光だけがふるえる闇のなか、最初に降神の儀、つづいて献供の儀がなされたあと、「白木の筥(はこ)に納められた天皇の御衣、錦の袋に入れられた玉の緒」が運ばれてきた。
そのあとの様子を、岡谷は次のように記述している。
〈やがて、天鈿女命(あめのうずめのみこと)が汗気(うけ[桶])を踏みとどろかして天照大神の怒りを鎮めようとした故事にならい、内掌典が、盥(たらい)の形をした宇気槽(うけぶね)の上にのり、桙(ほこ)をとってそれを十度つくあいだ、掌典は、その一度ごとに玉の緒の糸をむすんだ。これは、魂を結びとめる象徴的行為とされている。
玉の緒の儀の次は御衣震動の儀である。掌典が白木の筥をあけて御衣をとり、これを神前にむかって十度振り動かし、そしてもとの場所に納める〉
これが儀式のハイライトだといってよい。これがすむと、御衣と玉の緒が運びだされ、大直歌(おおなおいのうた)、倭舞(やまとまい)とつづいて、昇神の儀があって、式が終わる。
鎮魂の儀は、重要な儀式を前にして、天皇の魂を強化するための式と理解されることが多い。はたしてそうだろうか。それは文字どおり、先帝の魂を祭り、しずめる儀式と理解されるべきではないか。それが終わらなければ、大嘗祭も新嘗祭もおこなえないのである。
そして、その翌日がいよいよ大嘗祭(天皇即位後、初の新嘗祭)ということになる。この祭のために仙洞御所内に造られた大嘗宮は、東の悠紀殿、西の主基殿からなり、全体を芝垣で囲み、東西南北に神門がもうけられていた。千人近い参列者は、外の幄舎にならび、芝垣内にはいることは許されない。
この日、国男は南面神門の内掖において、「威儀の本位」についた。平たくいえば、これは古式にのっとり、弓矢をたずさえて、警備を務める役である。
大嘗祭がはじまるのも日が落ちてからだ。
岡谷はこう書いている。
〈式次第を簡単に述べると、7時頃天皇は回立殿[北面神門の北にあり、天皇が潔斎、着替えをする建物]に入って、祭服に着替え、まず悠紀殿に渡御、神饌行立(ぎょうりゅう)と称して、8人の女官が次々に運んできた神饌を神に供え、拝礼ののち告文を奏し、自らも新穀新酒を味わう。すなわち直会(なおらい)の儀である。そのあといったん休憩があり、参列者全員に夜食が出る。午前2時頃天皇は再び回立殿に出御、祭服に更めて、今度は主基殿へ。ここでは、悠紀殿とほぼ同じ儀があって、しらじら明けのころ、すべてが終わった〉
このとき「威儀の本位」についた国男は「神代の霊域に在るような感に打たれ」、儀式の様子が「神威おのずから迫るように覚え、言葉にも筆にも尽くされぬ尊さを感じました」などと、その感激を休憩のあいだに記者団に語っている。
いっぽうで国男が御大礼のありように疑問をもっていたことがいまではわかっている。その意見をおおやけにすることは、ゆゆしき事態を招きかねなかった。そこでかれは「大嘗祭に関する所感」を記し、これをひそかに山県有朋に建議するつもりでいた。だが、どういう事情があったのか、建議書はけっきょく提出されないまま筐底にしまいこまれた。公表されたのは国男の死後である。
この「所感」には何が書かれていたのだろう。漢字カナ混じりの建議書を口語訳して、その一部だけでも示しておくことにしよう。
冒頭にはこうある。
〈今回の御大典の儀制を今後とも続ける場合はもちろん、将来これを改訂しようとする場合においては、小官の地位において感じ、かつ疑問に思った事項を記録することが有益だと信じますので、衷心を吐露して、当局の参考になればと考え、意見を述べることとしました。もとより言論の責任を回避するものではありませんが、いたずらに議論をたたかわせようとするものでもありませんので、これはできれば秘封として、後年に伝えていただければと存じる次第です〉
そうことわったうえで、国男は即位礼と大嘗会を立て続けにおこなうことに疑問を呈し、次のように述べている。
〈御即位礼と大嘗会を旧都[京都]で挙行されることは、先帝陛下[明治天皇]の深い思し召しによることと拝察しますが、よくよく考究いたしますと、次の点も問題として考えなくてはなりません。ことに御即位礼と大嘗祭とを同じ秋冬の交につづけておこなうという点は、よくよく考慮の余地があると思います。……即位礼は中世に外国の文物が輸入されたあと新たに制定されたもので、いわば国威発揚の国際的儀式であります。これに対し、古代からつづく大嘗祭は、国民全体の信仰に根柢を有するものであって、世の中が新しくなったいまも、ますますその斎忌を厳重にする必要があるのです。したがって、華々しい即位の儀式によって民心の興奮がいまだ去らない時期に、このように幽玄な儀式を執りおこなうことは不適当であると理解するのが正しいと存じます〉
要するに、国男は華々しい即位礼と幽玄な大嘗祭を、つづけてではなく分離しておこなえと主張しているのである。さらに具体的な提案は、この長い建白書の最後を読めば、出てくる。
〈今日もっともよくないと思う点は、即位礼の盛儀によって民心が盛り上がり、何とかして慶賀の意を表そうとして、各種の祝宴が開かれている最中に、引き続いて厳粛かつ絶対的な謹慎を必要とする祭典を挙げるという仕組みにあります。ついては、もし強いて京都において同時にこのふたつの式をおこなうのであれば、まず大嘗会を終えて次に即位礼をおこなうようにするか、さもなければ即位礼は東京で華々しく挙行し、ある期間をおいて、古い慣例のとおり新暦12月に京都において大嘗祭をおこなうか、あるいはまた京都で即位礼と関連の祝典を挙げ、ご帰還ののち、その秋に東都で静かに祭をおこなわれるか、さらにまた一定の期間、京都に滞在されて、民心の静まるのを待ってこの祭をおこなうかのどれかです。いずれにしても今回のような混乱のうちに三千年来の儀式を終えるような前例を繰り返さないことを切望いたします〉
国男が何としても即位礼と大嘗祭を引き離したいと願っていたのは、いうまでもなく大嘗祭のなかに国民の信仰の根柢を感じていたからである。大嘗祭は天皇即位後、初の新嘗祭を意味するが、この新嘗祭は本来旧暦の11月におこなわれていた。ところがそれを新暦の11月にそっくり繰り上げてしまったのもおかしい、と国男は憤懣やるかたない。
〈大嘗祭は古来旧暦の11月、すなわち仲冬の候をもってその季節とされておりましたが、これも日本の伝来の信仰と関係があります。この祭のために設けられる仮宮は、いかに優美な風習に染まる朝廷でありましても、徹底的に古式を保存し、一切の装飾を去り、素朴簡古をきわめねばなりません。……ところが今回のように、これを11月中におこなうとするときは、まずその精神と相いれない変態(おかしな事態)を認めることになってしまうのです〉
国男は、たとえば米の収穫が終わらないうちに、葺きワラ用に稲を刈り取ってしまう不都合にはじまって、黒木の柱の切り取り方、青柴垣に用いられる柴や葉盤、葉椀のありようも古式からずれると主張して、うるさいくらいまで祭の季節変更がおよぼした弊害を言いつのっている。
即位式についてはほとんど何もいわなかった国男が、祭に関しては周囲を閉口させるほど、いかにうるさかったかがわかる。
そればかりではない。国男の「所感」はつづく。即位式が終わってすぐに大嘗祭を実施したために、祭の参列者が千人以上になり、そのために周囲に大建築物を用意しなければならなくなったことも問題だった。新暦の11月とはいえ、底冷えのする夜の京都では具合の悪くなる老人が続出した。
国男にいわせれば、重要な儀式を半月前にして、陸軍が気候不順な弘前の大演習に天皇を引っ張りだしたことも大問題だった。大嘗祭の前夜だというのに、京都の市民が赤々と電灯をつけ、その下を派手な格好をして練り歩いたり、大声を出して酒楼で歌ったり、火を忌まず肉を食らって平気なことも腹立たしいかぎりだった。
国男にとって、あるべき大嘗祭の姿は次のようなものだ。
〈前代の大嘗祭の記録をみると、小忌(おみ)の役に任ずる者はもちろん大忌(おおみ)の員に列する者も、きわめてその数を限定し、一般民衆もおのおのその家にあって身を浄めて大祭がとどこおりなく終了することを心より祈っておりました。まことに小さなこととはいえ、これは村々では祭の夜、氏子の者が家にあって暁を静かに待っていたのと同じことであります〉
国男にとって、大嘗祭は華やかなものではなく、古式ゆかしいものでなければならなかった。そして、大嘗祭とのかかわりは、その後の柳田民俗学の骨格を決定づけていくことになるのである。
貴族院書記官長として [柳田国男の昭和]
《第230回》
柳田国男が貴族院書記官長を務めたのは、1914年(大正3)4月から1919年(大正8)12月までの5年8カ月である。この間、第1次世界大戦があり、日本軍は中国の青島や南洋諸島を占領、大隈重信内閣は中国に21カ条要求をつきつけて評判を落とし退陣、ロシアでは革命が勃発し、日本では米騒動が全国へ広がり、原敬が首相の座につき、シベリア出兵がはじまった。
不思議なことに、最晩年の回想『故郷七十年』には政治向きの話はほとんど出てこない。そればかりか、国男が貴族院書記官長として、どういう仕事をしていたかについても、まったくといっていいほどわからないのである。
貴族院書記官長は貴族院の事務方を統括する顕職である。官等でいえば、勅任官の1等ないし2等にあたり、国男は最終的には1等に昇格している。岡谷公二の『貴族院書記官長柳田国男』によれば、この地位は法制局長官や公使[現在の感覚では大使]、陸海軍中将と同等だったという。議院事務局を運営し、議事速記録をまとめ、さまざまな会合に出席し、陳情を取り次ぎ、新聞記者にも応対しなければならない。時に議長や議員の世話もしなければならなかった。けっして閑職ではなかったのである。
内幸町にあった洋風の豪勢な官舎で暮らした5年8カ月は短い期間ではない。にもかかわらず、『故郷七十年』では、その時代の政治をめぐる「仕事」について、国男はまるで触れようとしていない。思い出すのさえいやだという雰囲気さえ、どこかにただよう。趣味ではじめた「郷土研究」や「甲寅叢書」、さらには2カ月にわたる台湾、中国視察については熱心に語っている。ただ、肝心の貴族院の仕事については、どこかうわの空のようでもある。国男は何をしていたのだろう。
当時の貴族院議長は、世に16代将軍といわれた徳川家達(いえさと)。徳川慶喜の跡を継いだ、徳川宗家の主でもある。プライドの高い国男は、この「殿様」の下で書記官長をつとめたのだが、議長との折り合いはよくなかった。それはおそらく国男が徳川家達の「三太夫」ないし「茶坊主」、あるいはメッセンジャーボーイの役割を肯んじず、みずからの信念にもとづいて行動したからである。
地位や権力をみずから求めようとしないという点では、国男は非政治的な人間である。国会議員や閣僚になりたいと思ったことはない。
岡谷公二もこう書いている。
〈政治が権力をもってはじまるとするなら、政党ないし派閥への加入は、権力に近づく第一の捷径(しょうけい)であろう。それをあえてしなかったのは、柳田国男が非政治的人間であったことの証拠である〉
端からみれば、おそらく国男は政治に不熱心で、議長や議員とのつきあいも悪く、お高くとまっていると思われただろう。てきぱきと事務はこなすけれども、政治家にへつらったりはしなかった。
だが、折口信夫が感じていたように、国男はある意味では政治家、むしろ超然たる政治家だったといってもよい。国内をしじゅう視察していたばかりか、海外にも関心が強く、くにのあるべき姿をつねに考えていたからである。
国男の描くくにの姿は、実際の勢力関係や利害関係を投影する現実政治とは、ずれており、むしろ宗教性、精神性を帯びていた。しかし、かれにいわせれば、それこそほんらいの〈まつりごと〉なのかもしれなかった。
『柳田国男伝』付録の年譜などをみると、この時期、国男は国会会期の明けたころをみはからって、しばしばロバートソン・スコットなどとともに国内各地を旅しているから、民俗への興味だけではなく、農政への関心も相変わらず持続していたのだろう。
スコットはスコットランド人のジャーナリストで、1915年から1920年まで日本に滞在した。国男とは新渡戸稲造の「郷土会」で知り合ったが、「新東洋」という日英友好色の強い和文雑誌を発刊していた。日本の農村に興味があったため、国男とは馬があい、イギリスに戻ってからも国男を「旅の友」と呼んで、いつまでも忘れなかった。ただし岡谷公二によると、スコットはイギリスの宣伝工作員だったとする説もあるようである。
年譜でみると、この時期、国男自身にとって、もっとも大きなできごとは、1915年(大正4)11月の大正天皇御大礼(大嘗祭)と1917年(大正6)3月からの台湾、中国視察旅行だったということがわかる。
試みに、その記述を引いておくことにしよう。
【大正4年(1915)】
10月31日〜11月30日
京都における大正天皇の御大礼に奉仕。この間、11月9日の大嘗祭予行、13日の鎮魂の儀、14日夕刻から15日払暁にかけての大嘗祭に奉仕、宮中最大の儀式を体験する。ついで伊勢御視察に随伴、畝傍での催事にも奉仕する。
【大正6年(1917)】
3月20日から2カ月あまり、台湾、支那、朝鮮を旅行。台北にて安東貞美台湾総督(叔父)の所に泊まる。[島崎]藤村が、台湾の山林払い下げのことで、実兄のために便宜をはかってくれるよう安東への口ききを依頼したことから、藤村との絶好を決意する。4月11日、厦門(アモイ)に上陸、見物。25日、香港。29日〜5月2日、上海で唐紹儀、孫逸仙[孫文]、孫洪伊に会う。5月4日〜7日、漢口、南京に旅行し、黎元洪大総統に謁見。5月20日、北京─大連─奉天─京城を経由して6月2日帰宅。
以下この2点にしぼって、貴族院書記官長時代の国男の足跡をたどってみることにする。
柳田国男が貴族院書記官長を務めたのは、1914年(大正3)4月から1919年(大正8)12月までの5年8カ月である。この間、第1次世界大戦があり、日本軍は中国の青島や南洋諸島を占領、大隈重信内閣は中国に21カ条要求をつきつけて評判を落とし退陣、ロシアでは革命が勃発し、日本では米騒動が全国へ広がり、原敬が首相の座につき、シベリア出兵がはじまった。
不思議なことに、最晩年の回想『故郷七十年』には政治向きの話はほとんど出てこない。そればかりか、国男が貴族院書記官長として、どういう仕事をしていたかについても、まったくといっていいほどわからないのである。
貴族院書記官長は貴族院の事務方を統括する顕職である。官等でいえば、勅任官の1等ないし2等にあたり、国男は最終的には1等に昇格している。岡谷公二の『貴族院書記官長柳田国男』によれば、この地位は法制局長官や公使[現在の感覚では大使]、陸海軍中将と同等だったという。議院事務局を運営し、議事速記録をまとめ、さまざまな会合に出席し、陳情を取り次ぎ、新聞記者にも応対しなければならない。時に議長や議員の世話もしなければならなかった。けっして閑職ではなかったのである。
内幸町にあった洋風の豪勢な官舎で暮らした5年8カ月は短い期間ではない。にもかかわらず、『故郷七十年』では、その時代の政治をめぐる「仕事」について、国男はまるで触れようとしていない。思い出すのさえいやだという雰囲気さえ、どこかにただよう。趣味ではじめた「郷土研究」や「甲寅叢書」、さらには2カ月にわたる台湾、中国視察については熱心に語っている。ただ、肝心の貴族院の仕事については、どこかうわの空のようでもある。国男は何をしていたのだろう。
当時の貴族院議長は、世に16代将軍といわれた徳川家達(いえさと)。徳川慶喜の跡を継いだ、徳川宗家の主でもある。プライドの高い国男は、この「殿様」の下で書記官長をつとめたのだが、議長との折り合いはよくなかった。それはおそらく国男が徳川家達の「三太夫」ないし「茶坊主」、あるいはメッセンジャーボーイの役割を肯んじず、みずからの信念にもとづいて行動したからである。
地位や権力をみずから求めようとしないという点では、国男は非政治的な人間である。国会議員や閣僚になりたいと思ったことはない。
岡谷公二もこう書いている。
〈政治が権力をもってはじまるとするなら、政党ないし派閥への加入は、権力に近づく第一の捷径(しょうけい)であろう。それをあえてしなかったのは、柳田国男が非政治的人間であったことの証拠である〉
端からみれば、おそらく国男は政治に不熱心で、議長や議員とのつきあいも悪く、お高くとまっていると思われただろう。てきぱきと事務はこなすけれども、政治家にへつらったりはしなかった。
だが、折口信夫が感じていたように、国男はある意味では政治家、むしろ超然たる政治家だったといってもよい。国内をしじゅう視察していたばかりか、海外にも関心が強く、くにのあるべき姿をつねに考えていたからである。
国男の描くくにの姿は、実際の勢力関係や利害関係を投影する現実政治とは、ずれており、むしろ宗教性、精神性を帯びていた。しかし、かれにいわせれば、それこそほんらいの〈まつりごと〉なのかもしれなかった。
『柳田国男伝』付録の年譜などをみると、この時期、国男は国会会期の明けたころをみはからって、しばしばロバートソン・スコットなどとともに国内各地を旅しているから、民俗への興味だけではなく、農政への関心も相変わらず持続していたのだろう。
スコットはスコットランド人のジャーナリストで、1915年から1920年まで日本に滞在した。国男とは新渡戸稲造の「郷土会」で知り合ったが、「新東洋」という日英友好色の強い和文雑誌を発刊していた。日本の農村に興味があったため、国男とは馬があい、イギリスに戻ってからも国男を「旅の友」と呼んで、いつまでも忘れなかった。ただし岡谷公二によると、スコットはイギリスの宣伝工作員だったとする説もあるようである。
年譜でみると、この時期、国男自身にとって、もっとも大きなできごとは、1915年(大正4)11月の大正天皇御大礼(大嘗祭)と1917年(大正6)3月からの台湾、中国視察旅行だったということがわかる。
試みに、その記述を引いておくことにしよう。
【大正4年(1915)】
10月31日〜11月30日
京都における大正天皇の御大礼に奉仕。この間、11月9日の大嘗祭予行、13日の鎮魂の儀、14日夕刻から15日払暁にかけての大嘗祭に奉仕、宮中最大の儀式を体験する。ついで伊勢御視察に随伴、畝傍での催事にも奉仕する。
【大正6年(1917)】
3月20日から2カ月あまり、台湾、支那、朝鮮を旅行。台北にて安東貞美台湾総督(叔父)の所に泊まる。[島崎]藤村が、台湾の山林払い下げのことで、実兄のために便宜をはかってくれるよう安東への口ききを依頼したことから、藤村との絶好を決意する。4月11日、厦門(アモイ)に上陸、見物。25日、香港。29日〜5月2日、上海で唐紹儀、孫逸仙[孫文]、孫洪伊に会う。5月4日〜7日、漢口、南京に旅行し、黎元洪大総統に謁見。5月20日、北京─大連─奉天─京城を経由して6月2日帰宅。
以下この2点にしぼって、貴族院書記官長時代の国男の足跡をたどってみることにする。
河童の本 [柳田国男の昭和]
《第229回》
初期の柳田民俗学には思いもかけぬ可能性がはらまれていた。しかし、「柳田国男と昭和」をテーマとするこの物語は、すでに国男の最晩年にさしかかっており、『山島民譚集』の内容を詳しく論じるのは控えるほかなさそうである。とはいえ、ほんのさわりだけでも紹介しておかなくては、この本がめざしていた世界をイメージすることもできないだろう。
注目すべきは本書の「小序」と題されたエピグラフである。原文はカタカナ混じりの正式(旧)漢字仮名遣い表記だが、少しでも読みやすくするため、いつものように現代表記で示すことにしよう。
横やまの 峯のたおりに
ふる里の 野辺とお白く 行く方も 遙々(はるばる)見える
よこ山の みちの阪戸に
一坪の 清き芝生を 行人(ぎょうにん)は 串さし行きぬ
永き代に ここに塚あれ
いにしえの神 よりまし 里びとの ゆききの栞(しおり)
とこなめの絶ゆる勿(なか)れと かつ祈り 占めて往(い)きつる
此(この)ふみは その塚どころ 我はその 旅の山伏
ねんごろに我勧進(かんじん)す
旅びとよ 石積みそえよ これの石塚
祝詞(のりと)のようにみえなくもない。しかし、国男の脳裏に描かれた光景はあざやかだ。
たたなづく山々のふもとに、なつかしいふるさとが、はるばると広がっている。旅人はいま山の中腹に祭られた塚の前を一礼してとおりすぎていく。いつまでも、この山、この川、この里がやすらかでありますようにと祈りながら。ここは、古き神がよりまし、里びとが行き来のたびに手を合わせる場所だ。ここに綴ったささやかな文章は、旅の山伏であるわたしにとって、いわばこうした塚どころのようなもの。わたしにつづく旅人も、このちいさな塚に石を積み増してくれることを願わないわけにいかない──。
隠(こも)り世に引きこまれていくようなメランコリックな雰囲気に満ちている。
この時代、帝国日本は日清、日露の戦いに勝利し、世界の一等国に仲間入りしたあと、台湾、朝鮮を超えて満州、南洋にまでその触手を伸ばそうとしていた。その意気軒昂たる国家の中核を担う高級官僚にして、このメランコリーはいったいどうしたことだろうか。
だが、それはけっして逃避や頽廃ではない。そこにはむしろ、何があっても心のふるさとを守るという決意のようなものが秘められている。本のタイトルにある「山島」は、まさに日本のことだ。そして、その中心には「民譚」、すなわち民の語りが広がっていた。
ここでは大室幹雄の名著『ふくろうと蝸牛(かたつむり)』のまとめを参照しながら、『山島民譚集』のさわり「河童駒引(こまひき)」をみておくことにする。

冒頭はこんなふうにはじまる。
〈温泉ハ我邦ノ一名物ニシテ兼ネテ又多クノ伝説ノ源ナリ。温泉ノ名ヲ呼ブニ、都会ノ人又ハ遠方ヨリ往ク人ハ、有馬ノ湯或ハ草津ノ湯ナドト所在町村ノ名ヲ以テスレドモ、諸国ノ温泉ニハ大抵別ニ其名前アリ。一ノ山村ニ二箇所以上ノ湯ガ湧クトキ、之ヲ一ノ湯二ノ湯ト謂ヒ元湯新湯ト名ヅケ若シクハ熱湯(あつゆ)温湯(ぬくゆ)ナドト区別スルハ常ノ事ナレドモ、唯一箇所ノ湯ニテモ亦名前アリ。ソレガ又鷺之湯鹿ノ湯狢之湯ナドト、動物ノ名ヲ用ヰシモノノミ多キハ、異国ノ旅人等ニハ定メテ奇妙ニ感ゼラルヽコトナルベシ〉
原文のまま引用してみたが、これが明治の「文章苦悶時代」の擬古文であって、国男のいう「すこぶる変わっている」文章なのである。だが、慣れると不思議に心地よく読め、何もむずかしいことをいっているわけではないことがわかる。温泉にはいろいろ名前がつけられているけれども、鷺の湯とか、鹿の湯、狢(むじな)の湯などと動物の名が使われることがあるのはどうしてだろうというわけである。
「河童駒引」、すなわちカッパが馬を引っぱっていくという話とは、まったく無縁と思える出だしである。どうして温泉の話といぶかる向きもあるだろう。フレイザーの『金枝篇』がネミの森の話からおもむろにはじまるのとよく似ている。
あるいは国男は映画のような展開を念頭に置いていると思えばよいのかもしれない。たとえば『世界最古の洞窟壁画』という映画が、南仏のブドウ畑からはじまって、観客が次第に渓谷へ、そして太古の洞窟に導かれ、そこで思いもしなかった3万年前の壁画にぶつかるといったのと同じように。
「河童駒引」の場合は、それが温泉からはじまって、山中の隠れ湯、戦国武将の傷を治す金創薬の話へと移っていく。そして、この薬を伝授したのがカッパだというあたりから、ようやくドジでスケベでカッコ悪い河童の群れが登場するのである。
たとえば、こんな話がある。口語訳で示しておこう。
〈筑前黒田家の家臣に鷹取運松庵(たかとり・うんしょうあん)という医師がいた。妻は4代目の三宅角助の娘、ものおじしない美女である。ある夜、かわやに入ったところ、物陰から手を伸ばしていたずらをしようとする者がいた。そこで、次の夜、短刀を懐にして、かわやに行き、また同じことがあったので、やにわにその手をとらえて、これを切り取った。
主人に子細をつげて、燈のもとで、切り取ったものを見ると、長さは8寸(25センチ)ほどで、指に水かきがあった。これはまさに『本草綱目』に記されたカッパの手ではあるまいか。ところが、その深夜、夫婦の寝室に近づき、嘆きながら訴える声がした。
「さきほどの無礼の段はお詫び申し上げます。何とぞ、その手をお返しください」
ところが、妻のお尻をさわられた主人は黙っていない。
「カッパの分際で、武士の妻女に手をだすのさえもってのほかであるのに、まして手を返せとは何だ。医者だからとあなどっておるのであろう。ならぬ、ならぬ」
そういって、追い返した〉
国男が引くにしては、めずらしく艶笑譚めいている。この情けないカッパはけっきょく3夜通いつめ、「お慈悲を」と涙ながらに訴えたので、主人の運松庵も憐れに思い、「それなら手を接合するという薬方を教えれば」という条件つきで、切り取った片手を返してやる。これが切り傷を治す絶妙の処方となるのである。しかも、カッパは律儀なことに、夜明けに生きたナマズをたらいに入れて、庭先においていったというおまけまでつく。
こうした話は、さまざまにかたちを変えながら全国に広がっていた。
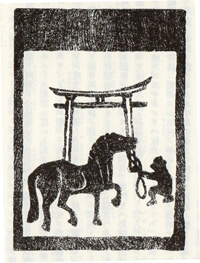
ところで、肝心の駒引きのほうはどうなのだろう。ターゲットの馬を川に引きずりこむ段になっても、カッパは失敗ばかりして、人間にかえっていいカモにされている。
国男はこんな伝説を紹介する。
〈寛正6年(1465)夏の話だ。芹沢俊軒という人があたりを散策し、日暮れに橋を渡って家に戻ろうとしたところ、馬が前に進まなくなった。どうしたのかと思い、うしろをふりかえると、怪しい者が馬のしっぽをつかんでいる。そこで刀を抜いて、その腕を斬り、それを持って家に帰った。
それが何者の腕であるかはわからなかった。だが、その夜、俊軒の寝所にやってきて、しきりに訴える者がいる。
「わたくしめは前川に住むカッパでござります。あなたさまによって腕を落とされました。何とぞそれをお返しください。わたくしめは金創接骨[刀の切り傷、骨つぎ]に効く妙薬をもっております。もしお返しいただけるようでしたら、うまい具合に自分の腕をついでみせ、この奇方をあなたにお教えして、感謝の意をあらわしたいと存じます」
そういうので、俊軒は「わかった」といって、腕を返した。
カッパはおおいに喜び、その秘法を伝えて、さらにこう話した。
「これから毎日、魚を届けさせていただきます。もし魚が届かなくなれば、わたくしめの命がなくなったとおぼしめしください」〉
前とよく似た話で、どうもカッパはドジばかり踏んでいる。最近、魚が届かなくなったと思えば、川で亡くなっているのが見つかったという、ちょっとあわれな落ちもついている。
ただし、国男はこれではあまりにかわいそうと思ったのか、カッパがすかっと妖怪らしい力を発揮する話を挙げるのも忘れていない。
〈これは肥前佐賀郡三溝(みつみぞ)の言い伝えだ。農民が馬を木につないでおいたところ、カッパが水からでてきて、その綱を解いて身にくくりつけ、馬を水際まで引っ張っていこうとした。馬がびっくりして跳ねたので、カッパはあわてて皿の水をこぼしてしまった。
カッパはたちまち弱ってしまい、逆に馬に引きずられて、厩(うまや)まで連れてこられる始末。息子は馬を柱につないで、こんなことがあったと母に話した。
母はこのとき洗濯をしていたが、これを聞いて、「コラ! 何ばしよっと」と、おおいにののしり、たらいの水をカッパにぶちまけた。すると、その水が皿にはいったものだから、カッパは急に元気になり、馬の綱を引き切り逃げ去ってしまった〉
カッパが片手を失うこともなく、薬の秘伝を奪われたり、人に詫び状を書いたりしなくてもよかったのはメデタシメデタシとしなければならない。
国男は実に楽しそうに各地のカッパ伝説を次々と紹介している。しかし、それは単に昔話のおもしろさに酔いしれるためではなかった。結論からいうと、どうやらかれは、カッパ伝説のなかに零落した神の痕跡をさがそうとしていたようなのである。
水の神であるカッパだけではない。神々はあらゆる場所に満ちていた。
「河童駒引」は、こうしめくくられている。
〈伝説はまるで春の野の陽炎(かげろう)に似ている。求めようとすると、ふっとあらわれる。それは陽炎みたいに、はなはだおぼつかない。しかし、そこには昔ながらの信仰が、すくなくともその形式面においては、一挙に変化させられることなく、永くその痕跡をこの地にとどめているのである。自然の神々が人間の便宜に対抗することができなくなり、次第にその威力を衰えさせ、ついにはふがいない魑魅魍魎(ちみもうりょう)の分際に退却するのは、どの民族でも同じことである。とはいえ、すでにその結界を人間に明け渡し、人に犠牲を求めなくなったあとも、神々はせめてかたちばかりは昔の祭りを要求し、かつまた神秘的な儀式を通じて、畏怖の記念を新たにさせ、またこれによって敗北の失望を慰めてもらおうとしている。こうしたいとなみが現前の事実として存在することはまちがいない〉
スメラミコトに回収されることのない、日本の神々の探求がめざされていた。
そのころ南方熊楠は、雑誌連載の「十二支考」で、えとの動物にふれながら、動物でもあり神でもある人間存在の不思議な両義性を読者の前に示そうとしている。国男はこうした南方の人類学的思考と拮抗しながら、日本人の根源とは何かに迫る長い旅をはじめようとしていたのである。
初期の柳田民俗学には思いもかけぬ可能性がはらまれていた。しかし、「柳田国男と昭和」をテーマとするこの物語は、すでに国男の最晩年にさしかかっており、『山島民譚集』の内容を詳しく論じるのは控えるほかなさそうである。とはいえ、ほんのさわりだけでも紹介しておかなくては、この本がめざしていた世界をイメージすることもできないだろう。
注目すべきは本書の「小序」と題されたエピグラフである。原文はカタカナ混じりの正式(旧)漢字仮名遣い表記だが、少しでも読みやすくするため、いつものように現代表記で示すことにしよう。
横やまの 峯のたおりに
ふる里の 野辺とお白く 行く方も 遙々(はるばる)見える
よこ山の みちの阪戸に
一坪の 清き芝生を 行人(ぎょうにん)は 串さし行きぬ
永き代に ここに塚あれ
いにしえの神 よりまし 里びとの ゆききの栞(しおり)
とこなめの絶ゆる勿(なか)れと かつ祈り 占めて往(い)きつる
此(この)ふみは その塚どころ 我はその 旅の山伏
ねんごろに我勧進(かんじん)す
旅びとよ 石積みそえよ これの石塚
祝詞(のりと)のようにみえなくもない。しかし、国男の脳裏に描かれた光景はあざやかだ。
たたなづく山々のふもとに、なつかしいふるさとが、はるばると広がっている。旅人はいま山の中腹に祭られた塚の前を一礼してとおりすぎていく。いつまでも、この山、この川、この里がやすらかでありますようにと祈りながら。ここは、古き神がよりまし、里びとが行き来のたびに手を合わせる場所だ。ここに綴ったささやかな文章は、旅の山伏であるわたしにとって、いわばこうした塚どころのようなもの。わたしにつづく旅人も、このちいさな塚に石を積み増してくれることを願わないわけにいかない──。
隠(こも)り世に引きこまれていくようなメランコリックな雰囲気に満ちている。
この時代、帝国日本は日清、日露の戦いに勝利し、世界の一等国に仲間入りしたあと、台湾、朝鮮を超えて満州、南洋にまでその触手を伸ばそうとしていた。その意気軒昂たる国家の中核を担う高級官僚にして、このメランコリーはいったいどうしたことだろうか。
だが、それはけっして逃避や頽廃ではない。そこにはむしろ、何があっても心のふるさとを守るという決意のようなものが秘められている。本のタイトルにある「山島」は、まさに日本のことだ。そして、その中心には「民譚」、すなわち民の語りが広がっていた。
ここでは大室幹雄の名著『ふくろうと蝸牛(かたつむり)』のまとめを参照しながら、『山島民譚集』のさわり「河童駒引(こまひき)」をみておくことにする。

冒頭はこんなふうにはじまる。
〈温泉ハ我邦ノ一名物ニシテ兼ネテ又多クノ伝説ノ源ナリ。温泉ノ名ヲ呼ブニ、都会ノ人又ハ遠方ヨリ往ク人ハ、有馬ノ湯或ハ草津ノ湯ナドト所在町村ノ名ヲ以テスレドモ、諸国ノ温泉ニハ大抵別ニ其名前アリ。一ノ山村ニ二箇所以上ノ湯ガ湧クトキ、之ヲ一ノ湯二ノ湯ト謂ヒ元湯新湯ト名ヅケ若シクハ熱湯(あつゆ)温湯(ぬくゆ)ナドト区別スルハ常ノ事ナレドモ、唯一箇所ノ湯ニテモ亦名前アリ。ソレガ又鷺之湯鹿ノ湯狢之湯ナドト、動物ノ名ヲ用ヰシモノノミ多キハ、異国ノ旅人等ニハ定メテ奇妙ニ感ゼラルヽコトナルベシ〉
原文のまま引用してみたが、これが明治の「文章苦悶時代」の擬古文であって、国男のいう「すこぶる変わっている」文章なのである。だが、慣れると不思議に心地よく読め、何もむずかしいことをいっているわけではないことがわかる。温泉にはいろいろ名前がつけられているけれども、鷺の湯とか、鹿の湯、狢(むじな)の湯などと動物の名が使われることがあるのはどうしてだろうというわけである。
「河童駒引」、すなわちカッパが馬を引っぱっていくという話とは、まったく無縁と思える出だしである。どうして温泉の話といぶかる向きもあるだろう。フレイザーの『金枝篇』がネミの森の話からおもむろにはじまるのとよく似ている。
あるいは国男は映画のような展開を念頭に置いていると思えばよいのかもしれない。たとえば『世界最古の洞窟壁画』という映画が、南仏のブドウ畑からはじまって、観客が次第に渓谷へ、そして太古の洞窟に導かれ、そこで思いもしなかった3万年前の壁画にぶつかるといったのと同じように。
「河童駒引」の場合は、それが温泉からはじまって、山中の隠れ湯、戦国武将の傷を治す金創薬の話へと移っていく。そして、この薬を伝授したのがカッパだというあたりから、ようやくドジでスケベでカッコ悪い河童の群れが登場するのである。
たとえば、こんな話がある。口語訳で示しておこう。
〈筑前黒田家の家臣に鷹取運松庵(たかとり・うんしょうあん)という医師がいた。妻は4代目の三宅角助の娘、ものおじしない美女である。ある夜、かわやに入ったところ、物陰から手を伸ばしていたずらをしようとする者がいた。そこで、次の夜、短刀を懐にして、かわやに行き、また同じことがあったので、やにわにその手をとらえて、これを切り取った。
主人に子細をつげて、燈のもとで、切り取ったものを見ると、長さは8寸(25センチ)ほどで、指に水かきがあった。これはまさに『本草綱目』に記されたカッパの手ではあるまいか。ところが、その深夜、夫婦の寝室に近づき、嘆きながら訴える声がした。
「さきほどの無礼の段はお詫び申し上げます。何とぞ、その手をお返しください」
ところが、妻のお尻をさわられた主人は黙っていない。
「カッパの分際で、武士の妻女に手をだすのさえもってのほかであるのに、まして手を返せとは何だ。医者だからとあなどっておるのであろう。ならぬ、ならぬ」
そういって、追い返した〉
国男が引くにしては、めずらしく艶笑譚めいている。この情けないカッパはけっきょく3夜通いつめ、「お慈悲を」と涙ながらに訴えたので、主人の運松庵も憐れに思い、「それなら手を接合するという薬方を教えれば」という条件つきで、切り取った片手を返してやる。これが切り傷を治す絶妙の処方となるのである。しかも、カッパは律儀なことに、夜明けに生きたナマズをたらいに入れて、庭先においていったというおまけまでつく。
こうした話は、さまざまにかたちを変えながら全国に広がっていた。
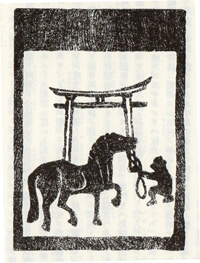
ところで、肝心の駒引きのほうはどうなのだろう。ターゲットの馬を川に引きずりこむ段になっても、カッパは失敗ばかりして、人間にかえっていいカモにされている。
国男はこんな伝説を紹介する。
〈寛正6年(1465)夏の話だ。芹沢俊軒という人があたりを散策し、日暮れに橋を渡って家に戻ろうとしたところ、馬が前に進まなくなった。どうしたのかと思い、うしろをふりかえると、怪しい者が馬のしっぽをつかんでいる。そこで刀を抜いて、その腕を斬り、それを持って家に帰った。
それが何者の腕であるかはわからなかった。だが、その夜、俊軒の寝所にやってきて、しきりに訴える者がいる。
「わたくしめは前川に住むカッパでござります。あなたさまによって腕を落とされました。何とぞそれをお返しください。わたくしめは金創接骨[刀の切り傷、骨つぎ]に効く妙薬をもっております。もしお返しいただけるようでしたら、うまい具合に自分の腕をついでみせ、この奇方をあなたにお教えして、感謝の意をあらわしたいと存じます」
そういうので、俊軒は「わかった」といって、腕を返した。
カッパはおおいに喜び、その秘法を伝えて、さらにこう話した。
「これから毎日、魚を届けさせていただきます。もし魚が届かなくなれば、わたくしめの命がなくなったとおぼしめしください」〉
前とよく似た話で、どうもカッパはドジばかり踏んでいる。最近、魚が届かなくなったと思えば、川で亡くなっているのが見つかったという、ちょっとあわれな落ちもついている。
ただし、国男はこれではあまりにかわいそうと思ったのか、カッパがすかっと妖怪らしい力を発揮する話を挙げるのも忘れていない。
〈これは肥前佐賀郡三溝(みつみぞ)の言い伝えだ。農民が馬を木につないでおいたところ、カッパが水からでてきて、その綱を解いて身にくくりつけ、馬を水際まで引っ張っていこうとした。馬がびっくりして跳ねたので、カッパはあわてて皿の水をこぼしてしまった。
カッパはたちまち弱ってしまい、逆に馬に引きずられて、厩(うまや)まで連れてこられる始末。息子は馬を柱につないで、こんなことがあったと母に話した。
母はこのとき洗濯をしていたが、これを聞いて、「コラ! 何ばしよっと」と、おおいにののしり、たらいの水をカッパにぶちまけた。すると、その水が皿にはいったものだから、カッパは急に元気になり、馬の綱を引き切り逃げ去ってしまった〉
カッパが片手を失うこともなく、薬の秘伝を奪われたり、人に詫び状を書いたりしなくてもよかったのはメデタシメデタシとしなければならない。
国男は実に楽しそうに各地のカッパ伝説を次々と紹介している。しかし、それは単に昔話のおもしろさに酔いしれるためではなかった。結論からいうと、どうやらかれは、カッパ伝説のなかに零落した神の痕跡をさがそうとしていたようなのである。
水の神であるカッパだけではない。神々はあらゆる場所に満ちていた。
「河童駒引」は、こうしめくくられている。
〈伝説はまるで春の野の陽炎(かげろう)に似ている。求めようとすると、ふっとあらわれる。それは陽炎みたいに、はなはだおぼつかない。しかし、そこには昔ながらの信仰が、すくなくともその形式面においては、一挙に変化させられることなく、永くその痕跡をこの地にとどめているのである。自然の神々が人間の便宜に対抗することができなくなり、次第にその威力を衰えさせ、ついにはふがいない魑魅魍魎(ちみもうりょう)の分際に退却するのは、どの民族でも同じことである。とはいえ、すでにその結界を人間に明け渡し、人に犠牲を求めなくなったあとも、神々はせめてかたちばかりは昔の祭りを要求し、かつまた神秘的な儀式を通じて、畏怖の記念を新たにさせ、またこれによって敗北の失望を慰めてもらおうとしている。こうしたいとなみが現前の事実として存在することはまちがいない〉
スメラミコトに回収されることのない、日本の神々の探求がめざされていた。
そのころ南方熊楠は、雑誌連載の「十二支考」で、えとの動物にふれながら、動物でもあり神でもある人間存在の不思議な両義性を読者の前に示そうとしている。国男はこうした南方の人類学的思考と拮抗しながら、日本人の根源とは何かに迫る長い旅をはじめようとしていたのである。
『山島民譚集』の構想 [柳田国男の昭和]
《第228回》
柳田国男の最初の著書はと問われると、たいていの人は『遠野物語』と答えるかもしれない。これは残念ながらまちがいで、その前にかれは『後狩詞記』と『石神問答』を上梓している。しかし、この3冊の本は、いわば聞き書きであったり、書簡集であったりして、厳密な意味での著書とはいえない。
ほかに農政学関係の研究書もある。とはいえ、かれがみずから資料を集め、精魂を傾けて綴った民俗学の最初の著書というべきは、実は『山島民譚集』という、いまではほとんど忘れられた試作なのではないか。1914年(大正3)7月に「甲寅叢書」の1冊として発刊された本である。
「甲寅叢書」とは国男の企画した書き下ろしシリーズをさす。結果的には6冊しか出せなかったが、晩年の国男は『故郷七十年』のなかで、この叢書について、「余が出版事業」と題して次のように語っている。
〈そのころ私はひそかに出版界の状況を心配して、書物が良いか悪いかということは、それが売れるか売れないかで決まるのはいけないと思うようになった。一つには新聞が広告で生活するようになってから、新聞の広告した書物にいい批評をしてやったりする習慣ができた。それが大きな指導標になるものだから、書物の選択を文化人がする場合には、そんな批評などを無視して書物を作らなければならないというのがそのころの私の意見であった。私のこういう考え方を知った西園寺八郎君が、懇意にしていた鹿児島出身の実業家赤星鉄馬に話したのだった。……西園寺もただ取次をしただけではなく、自分も3分の1だけ出し、後は赤星に出させて、黙って私のところへ3000円預けてくれた。そのころとしては大金だったから、私も大いに志を起こしてこれをいかしてつかおうという決心をした〉
こうして国男は貴族院書記官長という要職につきながら、あいた時間は「甲寅叢書」と雑誌「郷土研究」の編集と執筆に明け暮れることになる。
ここで名前の出てくる西園寺八郎は、元老西園寺公望の娘婿で、宮内省の官僚時代に国男と懇意にしていた。赤星鉄馬は八郎の友人で、実業家。のち国男の次女、千枝は、その息子、赤星平馬と結婚することになる。当時の3000円は、いまでいうと1000万円程度にあたるだろうか。
それはともかくとして、「甲寅叢書」とはどんなシリーズだったかを思い描いてもらうために、全6輯(しゅう)を以下、発刊順に並べてみることにする。
金田一京助『北蝦夷古謡遺篇』
白井光太郎『植物妖異考(上)』
柳田国男『山島民譚集(1)』
香取秀真『日本鋳工史稿』
白井光太郎『植物妖異考(下)』
斎藤励『王朝時代の陰陽道』
これで全部だが、のちに国男が「非常にペダンティック(衒学的)」で「名士の道楽仕事みたい」だったと述懐するように、みるからにいっぷう変わった叢書である。おどろおどろしくもみえる。31歳で夭折した斎藤励(れい)の名著が1915年(大正4)に刊行されている以外は、すべて1914年の発行。芥川龍之介が、この叢書の熱心な読者の一人だったことはつけ加えておいてもよい。
これだけ短期間で充実した内容の出版ができたのは、国男の熱意もさることながら、編集と出版を手伝った岡村千秋の力添えが大きかったといえるだろう。岡村は読売新聞から博文館に移り、その後、みずから郷土研究社という出版社を立ち上げて、国男をサポートし、雑誌「郷土研究」や「甲寅叢書」、さらにその後の「炉辺叢書」を出しつづけ、雑誌「民族」の編集人を引き受けたのだった。長兄、松岡鼎(かなえ)の次女茂子をめとったことから、国男とは縁つづきになっていた。
『故郷七十年』のなかで、国男はこの岡村のことを「今から考えるとよく怒る男だったけれども、とにかく親切で、自分も興味をもっていて仕事をするから重宝だったが、戦争中に脳溢血か何かで死んでしまったのは惜しかった」と、いつもながら少しとがった言い方ながら、なつかしそうに語っている。
注目すべきことは、この叢書の第3輯として出された国男の著書が『山島民譚集(1)』となっていたことである。とうぜん続篇が予定され、公刊されたのは一部にすぎない。その第2巻と第3巻は執筆されたものの、生前、公表されることはなかった。そして、わずか500部刊行されたにすぎない第1巻のことを、のちに国男は「河童の本」と呼ぶようになる。
現在、『山島民譚集』の全容は『柳田国男全集』によって読むことができるが、単行本にも文庫にもなっていないので、参考までにその章見出しを並べておくことにしよう。
(第1巻)
第1 河童駒引(こまびき)
第2 馬蹄石(ばていせき)
(第2巻)
第3 大太法師(だいだほうし)
第4 姥神(うばがみ)
第5 榎の杖
第6 八百比丘尼(やおびくに)
(第3巻)
第7 長者栄華
第8 欠(日を招く話──『妹の力』に転用)
第9 朝日夕日
第10 黄金の雉(きじ)
第11 椀貸塚(わんかしづか)
第12 隠里
第13 内出小槌(うちでのこづち)
第14 衢(ちまた)の神
全3巻となる予定の本を合わせてみると、全集版で300ページ以上になる大著である。第1巻がカタカナ表記の文語で書かれているのに対し、第2巻、第3巻は口語でつづられている。おそらく国男は機会があれば、第1巻を書き直すつもりでいたのだろう。これらのテーマは、その後さまざまな単行本のなかにちりばめられたとはいえ、ここには初期柳田民俗学の構想がすべて盛りこまれていたとみてよい。
なお念のためにいうと、『山島民譚集』は第1巻のみが、約30年後の1942年(昭和17)に、いっさい文体上の訂正を加えることなく創元社から再刊されている。そのさい、第2巻、第3巻が追加されることはなかった。ただし、そこには「再版序」が書き加えられている。
古稀に近くなった国男は、このとき「民譚集」の近古ないまぜの文体が「すこぶる変わって」おり、明治の文章「苦悶時代」を思い起こさせる「失敗した試みの一例」だといってはばからなかった。そして、こう記すのである。
〈何が暗々裡(あんあんり)の感化を与えて、こんな奇妙な文章を書かせたかということが、まず第一に考えられるが、久しい昔になるので、もうこれという心当たりはない。ただほんの片端だけ、故南方熊楠氏の文に近いようなところのあるのは、あの当時闊達無碍(かったつむげ)の筆を揮(ふる)っていたこの人の報告や論文を羨(うらや)み、また感じて読んでいた名残とも思う。ただし南方氏の文は、もちろんこれよりもはるかに自由で、かつさらさらと読みやすくできている。私の書いたものが変に理屈っぽく、また隅々の小さな点に注意を怠らなかったということばかりを気にしているのは、たぶんは吏臭とでも名づくべきものだろう〉
1914年といえば、南方熊楠がその代表作となる『十二支考』を雑誌「太陽」に連載しはじめたころにあたる。あえて大胆に推測すれば、『山島民譚集』は『十二支考』に対抗するだけではなく、いわば国男の『金枝篇』となるべき構想を秘めていたのである。
柳田国男の最初の著書はと問われると、たいていの人は『遠野物語』と答えるかもしれない。これは残念ながらまちがいで、その前にかれは『後狩詞記』と『石神問答』を上梓している。しかし、この3冊の本は、いわば聞き書きであったり、書簡集であったりして、厳密な意味での著書とはいえない。
ほかに農政学関係の研究書もある。とはいえ、かれがみずから資料を集め、精魂を傾けて綴った民俗学の最初の著書というべきは、実は『山島民譚集』という、いまではほとんど忘れられた試作なのではないか。1914年(大正3)7月に「甲寅叢書」の1冊として発刊された本である。
「甲寅叢書」とは国男の企画した書き下ろしシリーズをさす。結果的には6冊しか出せなかったが、晩年の国男は『故郷七十年』のなかで、この叢書について、「余が出版事業」と題して次のように語っている。
〈そのころ私はひそかに出版界の状況を心配して、書物が良いか悪いかということは、それが売れるか売れないかで決まるのはいけないと思うようになった。一つには新聞が広告で生活するようになってから、新聞の広告した書物にいい批評をしてやったりする習慣ができた。それが大きな指導標になるものだから、書物の選択を文化人がする場合には、そんな批評などを無視して書物を作らなければならないというのがそのころの私の意見であった。私のこういう考え方を知った西園寺八郎君が、懇意にしていた鹿児島出身の実業家赤星鉄馬に話したのだった。……西園寺もただ取次をしただけではなく、自分も3分の1だけ出し、後は赤星に出させて、黙って私のところへ3000円預けてくれた。そのころとしては大金だったから、私も大いに志を起こしてこれをいかしてつかおうという決心をした〉
こうして国男は貴族院書記官長という要職につきながら、あいた時間は「甲寅叢書」と雑誌「郷土研究」の編集と執筆に明け暮れることになる。
ここで名前の出てくる西園寺八郎は、元老西園寺公望の娘婿で、宮内省の官僚時代に国男と懇意にしていた。赤星鉄馬は八郎の友人で、実業家。のち国男の次女、千枝は、その息子、赤星平馬と結婚することになる。当時の3000円は、いまでいうと1000万円程度にあたるだろうか。
それはともかくとして、「甲寅叢書」とはどんなシリーズだったかを思い描いてもらうために、全6輯(しゅう)を以下、発刊順に並べてみることにする。
金田一京助『北蝦夷古謡遺篇』
白井光太郎『植物妖異考(上)』
柳田国男『山島民譚集(1)』
香取秀真『日本鋳工史稿』
白井光太郎『植物妖異考(下)』
斎藤励『王朝時代の陰陽道』
これで全部だが、のちに国男が「非常にペダンティック(衒学的)」で「名士の道楽仕事みたい」だったと述懐するように、みるからにいっぷう変わった叢書である。おどろおどろしくもみえる。31歳で夭折した斎藤励(れい)の名著が1915年(大正4)に刊行されている以外は、すべて1914年の発行。芥川龍之介が、この叢書の熱心な読者の一人だったことはつけ加えておいてもよい。
これだけ短期間で充実した内容の出版ができたのは、国男の熱意もさることながら、編集と出版を手伝った岡村千秋の力添えが大きかったといえるだろう。岡村は読売新聞から博文館に移り、その後、みずから郷土研究社という出版社を立ち上げて、国男をサポートし、雑誌「郷土研究」や「甲寅叢書」、さらにその後の「炉辺叢書」を出しつづけ、雑誌「民族」の編集人を引き受けたのだった。長兄、松岡鼎(かなえ)の次女茂子をめとったことから、国男とは縁つづきになっていた。
『故郷七十年』のなかで、国男はこの岡村のことを「今から考えるとよく怒る男だったけれども、とにかく親切で、自分も興味をもっていて仕事をするから重宝だったが、戦争中に脳溢血か何かで死んでしまったのは惜しかった」と、いつもながら少しとがった言い方ながら、なつかしそうに語っている。
注目すべきことは、この叢書の第3輯として出された国男の著書が『山島民譚集(1)』となっていたことである。とうぜん続篇が予定され、公刊されたのは一部にすぎない。その第2巻と第3巻は執筆されたものの、生前、公表されることはなかった。そして、わずか500部刊行されたにすぎない第1巻のことを、のちに国男は「河童の本」と呼ぶようになる。
現在、『山島民譚集』の全容は『柳田国男全集』によって読むことができるが、単行本にも文庫にもなっていないので、参考までにその章見出しを並べておくことにしよう。
(第1巻)
第1 河童駒引(こまびき)
第2 馬蹄石(ばていせき)
(第2巻)
第3 大太法師(だいだほうし)
第4 姥神(うばがみ)
第5 榎の杖
第6 八百比丘尼(やおびくに)
(第3巻)
第7 長者栄華
第8 欠(日を招く話──『妹の力』に転用)
第9 朝日夕日
第10 黄金の雉(きじ)
第11 椀貸塚(わんかしづか)
第12 隠里
第13 内出小槌(うちでのこづち)
第14 衢(ちまた)の神
全3巻となる予定の本を合わせてみると、全集版で300ページ以上になる大著である。第1巻がカタカナ表記の文語で書かれているのに対し、第2巻、第3巻は口語でつづられている。おそらく国男は機会があれば、第1巻を書き直すつもりでいたのだろう。これらのテーマは、その後さまざまな単行本のなかにちりばめられたとはいえ、ここには初期柳田民俗学の構想がすべて盛りこまれていたとみてよい。
なお念のためにいうと、『山島民譚集』は第1巻のみが、約30年後の1942年(昭和17)に、いっさい文体上の訂正を加えることなく創元社から再刊されている。そのさい、第2巻、第3巻が追加されることはなかった。ただし、そこには「再版序」が書き加えられている。
古稀に近くなった国男は、このとき「民譚集」の近古ないまぜの文体が「すこぶる変わって」おり、明治の文章「苦悶時代」を思い起こさせる「失敗した試みの一例」だといってはばからなかった。そして、こう記すのである。
〈何が暗々裡(あんあんり)の感化を与えて、こんな奇妙な文章を書かせたかということが、まず第一に考えられるが、久しい昔になるので、もうこれという心当たりはない。ただほんの片端だけ、故南方熊楠氏の文に近いようなところのあるのは、あの当時闊達無碍(かったつむげ)の筆を揮(ふる)っていたこの人の報告や論文を羨(うらや)み、また感じて読んでいた名残とも思う。ただし南方氏の文は、もちろんこれよりもはるかに自由で、かつさらさらと読みやすくできている。私の書いたものが変に理屈っぽく、また隅々の小さな点に注意を怠らなかったということばかりを気にしているのは、たぶんは吏臭とでも名づくべきものだろう〉
1914年といえば、南方熊楠がその代表作となる『十二支考』を雑誌「太陽」に連載しはじめたころにあたる。あえて大胆に推測すれば、『山島民譚集』は『十二支考』に対抗するだけではなく、いわば国男の『金枝篇』となるべき構想を秘めていたのである。



