『「若者」の時代』(菊地史彦)をめぐって(2) [本]
若者の時代を追っている。
青山ミチは1949年2月、横浜に生まれた。父は米軍兵士、母は日本人だった。父は朝鮮戦争の終わった年にアメリカに帰国し、ミチは日本に残った母のもとで育てられる。
歌手デビューは1962年、13歳のときだ。
当時人気の「ザ・ヒットパレード」や「シャボン玉ホリデー」にも出演した。
たぶん、ぼくが青山ミチをみたのは、高校生のころだったかもしれない。
はじけるようなパワフルな歌い方にひかれた。
しかし、青山ミチはいつのまにか消えてしまい、その後のことは知らなかった。

基地文化と「混血児」が、ミチがかかえてきた「烙印」だったという。
戦後の日本の歌謡曲はアメリカの影響を抜きにしては語れない。
歌のうまさは抜群だった。しかし、弘田三枝子にはかなわなかった。
失踪して、仕事に穴を開けることも重なったという。
ヒット曲はクラウン時代の1968年にでた「叱らないで」。
ぼくは知らなかった。いわゆる「歌謡ブルース」である。
著者によると、こんな歌である。
あの娘がこんなに なったのは
あの娘ばかりの 罪じゃない
どうぞ あの娘を 叱らないで
女ひとりで 生きてきた
ひとにゃ話せぬ 傷もある
叱らないで 叱らないで
マリヤさま
YouTubeで聞いてみた。さすがにうまい。いい歌だと思う。
でも、ぼくが高校のころ聞いた、はじけるような青山ミチではなかった。
マリヤさまのでてくるところは、女性版の唐獅子牡丹である。
デビューのあと、ずいぶん苦労し、流転したのだなと思った。
それは彼女の負った宿命だったのかもしれない。たぶん、多くの彼女たちの宿命だった。
ポリドールからクラウンに移籍する直前の1966年に、「風吹く丘で」をだしたが、移籍騒ぎのなかで、ほとんど日の目を見なかった。
この歌は2年後に、ヴィレッジ・シンガーズが「亜麻色の髪の乙女」と曲名を変えて歌い、大ヒットする。
1970年には「全日本歌謡選手権」に出演し、10週勝ち抜いて、グランドチャンピオンの座を獲得した。
しかし、復活もつかのま。すぐに歌謡界から遠ざかっていった。
場面は一転する。
次に著者は、1950年代半ばから60年代にかけての「集団就職」へと目を移している。これも若者の物語である。
「集団就職」といって思い浮かべるのは、井沢八郎の歌った「ああ上野駅」や、最近では2005年に公開された『Always 三丁目の夕日』だろうか。
すでにノスタルジーとなっている。

しかし、実際の集団就職とは、どういうものだったのか。
その背景には、農村の過剰人口問題があったという。とくに「次三男問題」が深刻だった。相続できる土地がなかった農家の次三男は、都市に流れていく。幸い、都市には多くの勤め先があった。
著者はこう書いている。
〈戦後の復興期から高度成長期にかけて、産業構造の変転を伴う経済活動の拡大は、大量の労働力需要を生みだした。まず繊維工業や金属機械工業を中心に、大量生産の設備を整えた工場が多くの若年労働者を求めた。また、景気の拡大に加え、工業分野の雇用拡大のあおりを食らって、都市部の小売店や外食店などの流通・サービス業分野は、深刻な人手不足に見舞われた。広範な分野で、安価で使いやすい労働へのニーズが高まったのである〉
町工場や小売店、外食店などが、集団就職の若者を受け入れていた。
「金の卵」といわれた集団就職者の主体は、最初、中学生だったが、60年代にはいってから次第に高校生へと移っていく。
東京では、「1962年の中卒者求人先都道府県は、男女とも福島県がトップであり、新潟、山形、岩手、秋田、青森、北海道の順だった」という。
しかし、集団就職の現実は、きびしかった。
そのことは、離職率の高さからみてもわかるという。
かれらの勤め先は、中小企業ならいいほうで、零細工場や商店が多かった。都心では、中小の製造業者は、通いのできる都市圏出身の新卒者をできるだけ採用したからである。
〈この結果、地方出身者は、大企業主導の機械工業には入り込めず、都市圏出身者が就業しようとしない商店、軽工業、雑業的分野へ入っていかざるをえなかった。こうして、町工場や個人商店へ連れてこられた若者たちは、劣悪な待遇に不満をくすぶらせた〉
つまり、「集団就職の仕組みそのものが、早期離職を生む要因を最初からはらんでいた」ということになる。しかも、その仕組みをつくっていた装置が、中学校と職業安定所の連携だった。「学校の職安化」が生じていたのだ。
離職や転職は、「割の合わない労働に展望を失った者たちの、ぎりぎりの反抗」だった。
そうした若者のなかに、森内一寛や永山則夫も含まれていた。
森内は1963年に鹿児島から大阪へ、永山は1965年に青森から東京へと向かっている。
その後、森内は森進一という名前をもらって、日本を代表する歌手になる。かれが歌うのは別れと流転の歌だ。いっぽう永山則夫はマスコミに「連続射殺魔」と報じたてられ、1997年に刑死した。
関西のちいさな町の衣料品店の息子だったぼくにとっても、集団就職の若者たちの存在はけっして無縁ではなかった。
それは東京や大阪の集団就職ほど、派手にさわがれたわけではなかった。しかし、ぼくの店でも、岡山のいなかからやってきた住み込みの店員はいて、少し年上のかれらは、ぼくをだいじにしてくれていた。
忘れられない思い出がある。
でも、何年かたつと、かれらも店をやめて、神戸や大阪にでていったのだ。
いまはもう高齢者だろう。
みんなどうしているのだろうと思う。
場面は、さらに移っていく。
60年安保は政治の季節だった。
樺美智子は1960年1月、岸信介首相の訪米を阻止するため、羽田空港に突入し、唐牛健太郎、青木昌彦とともに逮捕された。
同じころ、三池鉱山では無期限ストがはじまっていた(その後、第二組合が結成され、会社によるストの切り崩しへとつづく)
3月、社会党では浅沼稲次郎が委員長に就任する。
4月、共産主義者同盟(ブント)第4回大会では、書記長の島成郎が「権力奪取」を宣言、樺美智子はブントの東大文学部班キャップとなっていた。
5月には岸政権のもとで、安保条約が強行採決される。
全学連の学生たちは、きれいごとのように「民主主義」を唱えるだけでは、すまないようと感じた。
樺美智子は6月15日に国会に突入し、警官隊と衝突して死亡する。

1960年は「端境の年」だった、と著者はいう。
「復興期の戦後」と「成長期の戦後」がせめぎあっていた。
10月、社会党の浅沼稲次郎委員長は、日比谷公会堂での演説中、17歳の山口二矢に刺されて、死ぬ。
逮捕から3週間後、山口は練馬鑑別所で首を吊って自殺する。
「この時期に、あちこちで出現したのは『偽モノ』への嫌悪」だった、と著者はいう。
工場での仕事にさっぱり興味がもてなかったある中卒の若者は、ボクシングに打ち込むようになる。
1960年2月に17歳でデビュー戦を飾ったあと、新人王決定戦で3歳年上の海老原博幸を破って優勝したかれは、1961年正月にファイティング原田というリングネームをもらった。
ファイティング原田は、1962年に世界フライ級、65年に世界バンタム級のチャンピオンとなった。
その同じジムにいて、日本フライ級のチャンピオンとなる斎藤清作は、のちにコメディアンの由利徹に弟子入りし、「たこ八郎」の芸名を名乗る。
高校時代のぼくの友人、笹倉明が1985年に真鶴の海水浴場で急死した、たこ八郎の伝記を書いている。
『天の誰かが好いていた』。
その出版記念会にぼくも出させてもらったことをおぼえている。
笹倉はその後、1989年に直木賞を受賞する。
最近、あまり名前を聞かない。
どうしているのだろう。
加賀まりこは1962年に映画デビューしている。監督は篠田正浩、脚本は寺山修司。ヌーヴェル・ヴァーグ(新しい波)が去ろうとしていたときにつくられた、この『涙を、獅子のたて髪に』という映画は、はっきりいってつまらない、と著者はいう。
しかし、デビューしたときから「加賀まりこはほぼ完全な加賀まりことして登場した」のだった。「彼女が典型を示した、差異を追求する『生き方』は60年代のカウンターカルチャーから70年代のファッション・カルチャーへ、消費社会の主軸をつくりだしたともいえる」と著者は指摘する。
本書で紹介されている干刈あがたの作品をぼくは読んだことがない。しかし、60年安保のとき、高校2年生だった彼女もまたデモに参加している。
樺美智子の死に衝撃を受けたという。
早稲田大学を中退、雑誌のライターをしながら、結婚し、2児の母となった。そして島尾敏雄のアドバイスで、奄美などの島唄を採集しはじめたという。
1982年、「樹下の家族」で『海燕』新人文学賞を受賞、その後、「ウホッホ探検隊」や「ゆっくり東京女子マラソン」などの小説を書き、1992年5月に亡くなった。
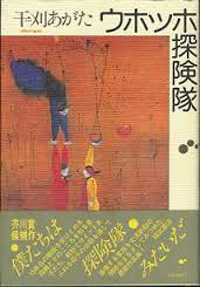
かれらは偽モノに反撥していた。
著者はこう書いている。
〈彼らが嫌った『偽モノ』とは、まさに復興期の社会意識(民主主義)と成長期の社会意識(消費主義)の節操なき混交のうちにあった。それは、相手に応じてナショナリズム(反米)にもデモクラシー(反岸)にも化け、いつの間にか『所得倍増』のキャンペーンに同調していった。このキマイラのような〈社会意識〉が醸し出す臭気に、彼らは反撥した。この一点において、山口二也とファイティング原田と加賀まりこと干刈あがたを同列に論じることができると私は思った。そして、たぶん、そうした乱暴な世代論が成立する年は、この前にも後にもないような気がしている〉
よくわからない。
若者がたたかい、傷つき、立ち直って、また傷ついていたことはたしかである。若者もいつしか年をとる。しかし、たたかいは死ぬまで終わらないだろう。
青山ミチは1949年2月、横浜に生まれた。父は米軍兵士、母は日本人だった。父は朝鮮戦争の終わった年にアメリカに帰国し、ミチは日本に残った母のもとで育てられる。
歌手デビューは1962年、13歳のときだ。
当時人気の「ザ・ヒットパレード」や「シャボン玉ホリデー」にも出演した。
たぶん、ぼくが青山ミチをみたのは、高校生のころだったかもしれない。
はじけるようなパワフルな歌い方にひかれた。
しかし、青山ミチはいつのまにか消えてしまい、その後のことは知らなかった。

基地文化と「混血児」が、ミチがかかえてきた「烙印」だったという。
戦後の日本の歌謡曲はアメリカの影響を抜きにしては語れない。
歌のうまさは抜群だった。しかし、弘田三枝子にはかなわなかった。
失踪して、仕事に穴を開けることも重なったという。
ヒット曲はクラウン時代の1968年にでた「叱らないで」。
ぼくは知らなかった。いわゆる「歌謡ブルース」である。
著者によると、こんな歌である。
あの娘がこんなに なったのは
あの娘ばかりの 罪じゃない
どうぞ あの娘を 叱らないで
女ひとりで 生きてきた
ひとにゃ話せぬ 傷もある
叱らないで 叱らないで
マリヤさま
YouTubeで聞いてみた。さすがにうまい。いい歌だと思う。
でも、ぼくが高校のころ聞いた、はじけるような青山ミチではなかった。
マリヤさまのでてくるところは、女性版の唐獅子牡丹である。
デビューのあと、ずいぶん苦労し、流転したのだなと思った。
それは彼女の負った宿命だったのかもしれない。たぶん、多くの彼女たちの宿命だった。
ポリドールからクラウンに移籍する直前の1966年に、「風吹く丘で」をだしたが、移籍騒ぎのなかで、ほとんど日の目を見なかった。
この歌は2年後に、ヴィレッジ・シンガーズが「亜麻色の髪の乙女」と曲名を変えて歌い、大ヒットする。
1970年には「全日本歌謡選手権」に出演し、10週勝ち抜いて、グランドチャンピオンの座を獲得した。
しかし、復活もつかのま。すぐに歌謡界から遠ざかっていった。
場面は一転する。
次に著者は、1950年代半ばから60年代にかけての「集団就職」へと目を移している。これも若者の物語である。
「集団就職」といって思い浮かべるのは、井沢八郎の歌った「ああ上野駅」や、最近では2005年に公開された『Always 三丁目の夕日』だろうか。
すでにノスタルジーとなっている。

しかし、実際の集団就職とは、どういうものだったのか。
その背景には、農村の過剰人口問題があったという。とくに「次三男問題」が深刻だった。相続できる土地がなかった農家の次三男は、都市に流れていく。幸い、都市には多くの勤め先があった。
著者はこう書いている。
〈戦後の復興期から高度成長期にかけて、産業構造の変転を伴う経済活動の拡大は、大量の労働力需要を生みだした。まず繊維工業や金属機械工業を中心に、大量生産の設備を整えた工場が多くの若年労働者を求めた。また、景気の拡大に加え、工業分野の雇用拡大のあおりを食らって、都市部の小売店や外食店などの流通・サービス業分野は、深刻な人手不足に見舞われた。広範な分野で、安価で使いやすい労働へのニーズが高まったのである〉
町工場や小売店、外食店などが、集団就職の若者を受け入れていた。
「金の卵」といわれた集団就職者の主体は、最初、中学生だったが、60年代にはいってから次第に高校生へと移っていく。
東京では、「1962年の中卒者求人先都道府県は、男女とも福島県がトップであり、新潟、山形、岩手、秋田、青森、北海道の順だった」という。
しかし、集団就職の現実は、きびしかった。
そのことは、離職率の高さからみてもわかるという。
かれらの勤め先は、中小企業ならいいほうで、零細工場や商店が多かった。都心では、中小の製造業者は、通いのできる都市圏出身の新卒者をできるだけ採用したからである。
〈この結果、地方出身者は、大企業主導の機械工業には入り込めず、都市圏出身者が就業しようとしない商店、軽工業、雑業的分野へ入っていかざるをえなかった。こうして、町工場や個人商店へ連れてこられた若者たちは、劣悪な待遇に不満をくすぶらせた〉
つまり、「集団就職の仕組みそのものが、早期離職を生む要因を最初からはらんでいた」ということになる。しかも、その仕組みをつくっていた装置が、中学校と職業安定所の連携だった。「学校の職安化」が生じていたのだ。
離職や転職は、「割の合わない労働に展望を失った者たちの、ぎりぎりの反抗」だった。
そうした若者のなかに、森内一寛や永山則夫も含まれていた。
森内は1963年に鹿児島から大阪へ、永山は1965年に青森から東京へと向かっている。
その後、森内は森進一という名前をもらって、日本を代表する歌手になる。かれが歌うのは別れと流転の歌だ。いっぽう永山則夫はマスコミに「連続射殺魔」と報じたてられ、1997年に刑死した。
関西のちいさな町の衣料品店の息子だったぼくにとっても、集団就職の若者たちの存在はけっして無縁ではなかった。
それは東京や大阪の集団就職ほど、派手にさわがれたわけではなかった。しかし、ぼくの店でも、岡山のいなかからやってきた住み込みの店員はいて、少し年上のかれらは、ぼくをだいじにしてくれていた。
忘れられない思い出がある。
でも、何年かたつと、かれらも店をやめて、神戸や大阪にでていったのだ。
いまはもう高齢者だろう。
みんなどうしているのだろうと思う。
場面は、さらに移っていく。
60年安保は政治の季節だった。
樺美智子は1960年1月、岸信介首相の訪米を阻止するため、羽田空港に突入し、唐牛健太郎、青木昌彦とともに逮捕された。
同じころ、三池鉱山では無期限ストがはじまっていた(その後、第二組合が結成され、会社によるストの切り崩しへとつづく)
3月、社会党では浅沼稲次郎が委員長に就任する。
4月、共産主義者同盟(ブント)第4回大会では、書記長の島成郎が「権力奪取」を宣言、樺美智子はブントの東大文学部班キャップとなっていた。
5月には岸政権のもとで、安保条約が強行採決される。
全学連の学生たちは、きれいごとのように「民主主義」を唱えるだけでは、すまないようと感じた。
樺美智子は6月15日に国会に突入し、警官隊と衝突して死亡する。

1960年は「端境の年」だった、と著者はいう。
「復興期の戦後」と「成長期の戦後」がせめぎあっていた。
10月、社会党の浅沼稲次郎委員長は、日比谷公会堂での演説中、17歳の山口二矢に刺されて、死ぬ。
逮捕から3週間後、山口は練馬鑑別所で首を吊って自殺する。
「この時期に、あちこちで出現したのは『偽モノ』への嫌悪」だった、と著者はいう。
工場での仕事にさっぱり興味がもてなかったある中卒の若者は、ボクシングに打ち込むようになる。
1960年2月に17歳でデビュー戦を飾ったあと、新人王決定戦で3歳年上の海老原博幸を破って優勝したかれは、1961年正月にファイティング原田というリングネームをもらった。
ファイティング原田は、1962年に世界フライ級、65年に世界バンタム級のチャンピオンとなった。
その同じジムにいて、日本フライ級のチャンピオンとなる斎藤清作は、のちにコメディアンの由利徹に弟子入りし、「たこ八郎」の芸名を名乗る。
高校時代のぼくの友人、笹倉明が1985年に真鶴の海水浴場で急死した、たこ八郎の伝記を書いている。
『天の誰かが好いていた』。
その出版記念会にぼくも出させてもらったことをおぼえている。
笹倉はその後、1989年に直木賞を受賞する。
最近、あまり名前を聞かない。
どうしているのだろう。
加賀まりこは1962年に映画デビューしている。監督は篠田正浩、脚本は寺山修司。ヌーヴェル・ヴァーグ(新しい波)が去ろうとしていたときにつくられた、この『涙を、獅子のたて髪に』という映画は、はっきりいってつまらない、と著者はいう。
しかし、デビューしたときから「加賀まりこはほぼ完全な加賀まりことして登場した」のだった。「彼女が典型を示した、差異を追求する『生き方』は60年代のカウンターカルチャーから70年代のファッション・カルチャーへ、消費社会の主軸をつくりだしたともいえる」と著者は指摘する。
本書で紹介されている干刈あがたの作品をぼくは読んだことがない。しかし、60年安保のとき、高校2年生だった彼女もまたデモに参加している。
樺美智子の死に衝撃を受けたという。
早稲田大学を中退、雑誌のライターをしながら、結婚し、2児の母となった。そして島尾敏雄のアドバイスで、奄美などの島唄を採集しはじめたという。
1982年、「樹下の家族」で『海燕』新人文学賞を受賞、その後、「ウホッホ探検隊」や「ゆっくり東京女子マラソン」などの小説を書き、1992年5月に亡くなった。
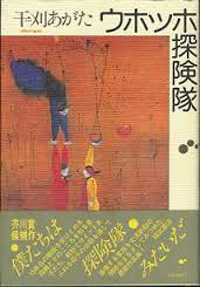
かれらは偽モノに反撥していた。
著者はこう書いている。
〈彼らが嫌った『偽モノ』とは、まさに復興期の社会意識(民主主義)と成長期の社会意識(消費主義)の節操なき混交のうちにあった。それは、相手に応じてナショナリズム(反米)にもデモクラシー(反岸)にも化け、いつの間にか『所得倍増』のキャンペーンに同調していった。このキマイラのような〈社会意識〉が醸し出す臭気に、彼らは反撥した。この一点において、山口二也とファイティング原田と加賀まりこと干刈あがたを同列に論じることができると私は思った。そして、たぶん、そうした乱暴な世代論が成立する年は、この前にも後にもないような気がしている〉
よくわからない。
若者がたたかい、傷つき、立ち直って、また傷ついていたことはたしかである。若者もいつしか年をとる。しかし、たたかいは死ぬまで終わらないだろう。
2015-03-15 06:48
nice!(7)
コメント(0)
トラックバック(0)




コメント 0