渡辺京二『逝きし世の面影』をめぐって(1) [くらしの日本史]
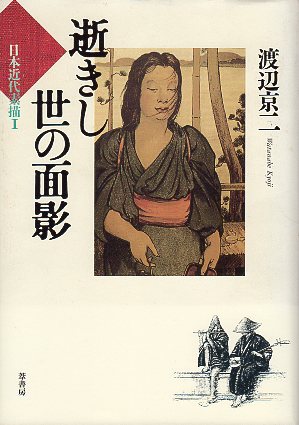
大著なので、はたして読み切れるのかどうか、ためらいがある。
昔から何度かチャレンジして、いつも途中で断念した本だ。
だから、このブログで取りあげるかどうか迷ったのだが、何はともあれ、1章ずつ読んでみることにした。
挫折したら、それまでである。
気の向いたとき、思いだしたかのように味わってみるつもりだ。
最近は人の名前もでてこなくなったボケはじめ老人の備忘録にすぎない。
本書で取りあげられているのは、18世紀初頭から19世紀にかけて存続した古い文明についてである。
江戸文明という言い方をしてもよいのかもしれない。
江戸文明は明治末期、すなわち20世紀はじめまでに滅亡した。
日本の近代は、前代の文明の滅亡のうえにうち立てられた、と著者はいう。
異邦人による観察記録が縦横に引用されている。その記録をたどりながら、いまは失われた近代以前の日本の情景を頭に思い浮かべようというのだ。
海外の観察者は、いちように古き日本の文明に賛嘆のことばを惜しまなかった。
日本の文化はいまも残っている。国民的特性も持続しているかもしれない。しかし、人びとがそのなかで暮らしていた江戸文明そのものは、近代化の過程で、すっかり失われてしまった、と著者はいう。
西洋人が古き日本にみたのは、現実の政治的・経済的諸関係ではなく、ロマンにすぎなかったのだろうか。
著者はいう。
〈われわれの実存的な生とは、そしてそれが生きる現実とは、けっして政治や経済を主要な実質とはしていない。それは自分が生きるコスモスと社会を含むひろい意味での他者との交渉を実質としており、そのコスモスと社会を規定するのが宗教も含めた文化なのである。〉
西洋人の日本観察にオリエンタリズム的偏見が含まれている可能性を著者も認めている。しかし、にもかかわらず、そこには当時の日本人でさえ気づかなかった何ごとかが記述されているのだ。
フランス公使ロッシュとともに慶応3年(1867)に来日した、21歳のリュドヴィク・ボーヴォワルは、こまごまとした飾り物に心奪われ、日本を妖精風の「小人国(リリパット)」だと感じた。
この感覚はたしかにエキゾティシズムかもしれない。しかし、そこには失われた何かがとらえられている。こまごまとしたものはかならずしも幻想だとはいいきれない。
オールコックやミッドフォード、それにイザベラ・バードなど、すぐれた記録を残した外国人は数多い。ほかにも幕末から明治にかけ、多くの外国人が数々の記録を残している。
古くはフロイスやケンペル、ジーボルト、ゴロヴニンの名前も挙げてもよいだろう。
幕末にやってきた外国使節団は、けっしてバラ色の日本だけをえがいたわけではなかった。その目に映った役人や民衆の様子もしっかり観察されていた。
外国人にたいする民衆の興味を役人は制止しきれなかった。そして、使節団は概して日本に、とりわけ日本の民衆に好感をいだいている。

[レガメのえがいた浅草風景。1870年代。本書カバーの絵もレガメ。]
現代の日本人は、幕末や明治はじめの日本が、明るく幸せなはずがないという予見をいだいている。それが、当時の海外観察者による日本の記述を疑いの目でみる、ひとつの要因になっている、と著者はいう。
さらに現代人は、当時は幕府や政府の統制が厳格であって、日本人はすべての面で抑圧されていたと思いこんでいる。
しかし、それはあとからつくられた刷り込みである。
当時の外国人観察者はそんなふうに見なかった。むしろ逆である。
たとえば、幕末に英国使節団の一員として来日したシェラード・オズボーンは、幕府が奢侈禁止令をだしていたことを知っていたが、幕府の役人や富裕な商人が着飾っており、日本の女性たちが上等の生地の着物を身につけていることをしっかり観察していた。
日本の家屋や寺院の色彩が落ち着いていることも評価している。オズボーンはそこに清潔さや趣味の洗練を感じとりこそすれ、抑圧や悲惨はすこしも感じていなかった。
じっさい、異文化を理解するのはむずかしい。あれだけ日本通のラフカディオ・ハーンですら、晩年には「日本人というものを少しもわかっていないことがわかっ」たという境地に達した。それでも、ハーンは最後まで日本を理解することに努め、とりわけ「日本人の内面生活」をえがこうとした。そこにハーンのえらさがある。
異邦から来た観察者は、「奇妙な異文化」、「おのれの文明と異質な何か」を発見したのだ、と著者はいう。
そこには新鮮なおどろきがあった。「このような“小さい、かわいらしい、夢のような”文明がありうるというのは、彼らにとって啓示ですらあった」。
時をへだてたわれわれも、その記述に単に反発するのではなく、まじめに向きあうべきではないか、と著者はいう。
じっさい、細部にわたる綿密な記録が残されている。
扇をつかいながら読書する役人、錠も鍵もない部屋、美しい品々、女たちの笑い声、遊び回る子どもたち、陽気な人びと、子守する少女、波の音、木の橋、川をこぐ舟……。観察はきりがなくつづく。
パリのギメ博物館の創設者エミール・ギメは明治9年(1876)に来日した。その第一印象は、日本は「すべてが魅力にみちている」。
第一印象こそが、じつはだいじなのである。西洋人にとって、日本には古きよき時代と文明が残されていた。
著者はいう。
〈近代工業文明に対する懐疑や批判は、その行き詰りが誰の目にも明らかになった20世紀末葉に至って生じた現象ではけっしてない。それはむしろ、近代工業文明が成立した19世紀初頭以来、近代思潮の波頭に不断に顕われ続けてきた現象なのである。〉
英国公使のオールコックは、近代物質文明の信奉者であった。それでも「どうあってもいそいで前へ進もうとする」西洋にいささか疲労をおぼえ、アジアが近代文明にたいする「ひとつの矯正物」になるのではないかと感じていた。
英国のジャーナリスト、エドウィン・アーノルドは、日本の田園風景をみて「ヨーロッパの生活の騒々しさと粗野さとから救われた気が」した。
どうしてだろう。
著者はこう述べている。
〈幕末の日本では、精神の安息と物質的安楽は、ひとつの完成し充溢した生活様式の中で溶けあっていたのである。アーノルドのような讃美者はもとより、オールコックのような批判的観察者ですら感動に誘われたのは、そういう今は失われた日本の文明の特質に対してであった。〉
そこには、なんだかほっとする風景が広がっていたのである。
著者は、そうしたさまざまな外国人によるこまごまとした観察のなかにおいてこそ、古い江戸文明の実相が浮かびあがってくると考えている。
のんびりと読むことにしよう。
2017-07-04 09:49
nice!(6)
コメント(0)
トラックバック(0)




コメント 0