鹿島茂『吉本隆明1968』を読む(3) [われらの時代]
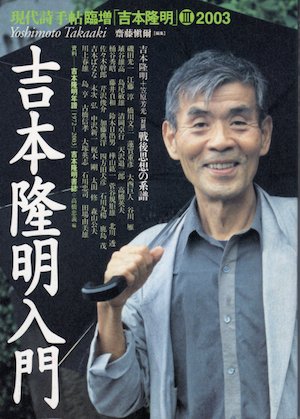
高村光太郎論である。
鹿島茂の本書は、大半が吉本の高村光太郎論にあてられている。
ところで、最初にことわっておかなければならないのは、ぼくが文学や詩にはまるでうとく、どちらかというとそれを敬遠していることである。そこで、高村光太郎論はきわめて大雑把に、言い換えればその概要だけを紹介するにとどめ、あまり深入りはしない。
吉本隆明は1924(大正13)年に、東京月島で船大工の息子として生まれ、東京府立化学工業学校から米沢高等工業学校へと進んだ。戦時中は軍国少年となり、20歳のときに敗戦を迎えている。
敗戦を知って、「わたしは、ひどく悲しかった」と書いている。もし降伏を認めない反乱部隊があらわれたら、そこに参加するつもりだったともいう。
そのころ、吉本は朝日新聞に載った高村光太郎の「一億の号泣」を読んで、高村が早くも「未来の文化」を作りあげることを歌っているのを知って、「異和感」を覚えた。それまで戦意高揚を歌ってきた高村は、なぜこんなにもあっさり変身できるのか。
そこから吉本は、高村の詩的営為をたどりはじめる。
高村光太郎は1906(明治39)年から1909(明治42)年にかけ、ニューヨーク、ロンドン、パリに留学し、彫刻や絵画、詩を学んでいる。ロダンの展覧会や邸宅にも訪れ、その作品に魅せられている。
農商務省からの研究費も出たが、基本的には親がかり(父親は明治を代表する有名な彫刻家、高村光雲)の留学だったといってよい。
高村光太郎はけっしてブルジョア息子ではない。父の光雲は、職人的な彫刻家だった。光太郎は欧米で貧乏暮らしと孤独を経験し、それに慣れることも知った。だが、欧米体験は、何よりも高村に芸術に生きることを教えたのである。
世間は見えてこなくなる。それが帰国後、父との確執を生む。それでも日々の生活は父の収入をあてにしなくてはならなかった。
鹿島茂はこれを「多重的父親殺し」と名づけている。たしかに、すねかじりといった、なまやさしいものではなさそうだ。
西洋への留学体験は、高村にいわば芸術の普遍性への視座を与えた。そうであるがゆえに、日本の後進性、特殊性が目につくようになる。高村光太郎の場合、それは父光雲と、父の支配する家への複雑な感情となってあらわれる。
その抵抗はデカダンスのかたちをとった。しかし、けっきょく、それは性的解放を含めて、下町情緒への沈潜へと向かわない。鹿島茂は、高村光太郎は「世界性と孤絶性の間で引き裂かれ、どうにも心の居場所(環境社会)を持ちえなかった」ととらえている。
そこにあらわれたのが智恵子だった。そして、高村は智恵子とのあいだに、いわば「性のユートピア」をつくりあげようとした、と鹿島は解釈する。だが、それは夫は彫刻にはげみ、妻はキャンバスに向かうという、芸術家どうしのまったく現実的基盤をもたないユートピアだった。
夫婦生活の破綻は必然だった。智恵子は光太郎から離れられず、実家も倒産するなかで、孤絶のなか、狂気に陥っていく。とはいえ、1931年に統合失調症を発症してから死亡するまでの7年間を含め、智恵子との結婚生活は24年間つづいた。
そのかん、高村の思想には大きな変化が訪れていた。それは、インテリゲンチャ意識からの「庶民返り」だった。昭和にはいり、不況が深刻化するにつれ、大衆の意識は対外膨張を求めるようになっていた。
高村にとって、昭和の初期は、金持ちだけが幅を利かせる腐敗堕落した世の中だと認識されていた。そして、智恵子との生活も破綻していくなか、高村はすべてが浄化される物語を求めた。それがいっぽうでは智恵子抄に結晶し、他方では戦争礼賛詩へ飛翔することになるのだ。
下町出身という出自からしても、青年時代の思想性からしても、吉本は高村に親近性を感じていた。ちがいを感じていたとすれば、それは高村が西洋への留学経験をもち、智恵子という夢のような女性と暮らしたことにたいしてではない。異和感がやってきたとすれば、それは高村がいつしか詩人の役割を、世の浄化ととらえるようになったことにたいしてだったといってもよい。
その異和感を感じたのは、吉本が、前にも述べたように、敗戦から2日後の1945年8月17日に朝日新聞に掲載された、「一億の号泣」という高村の詩を読んだときのことである。
その最後の4行には、こう記されていた。
鋼鉄の武器を失へる時
精神の武器おのづから強からんとす
真と美と到らざるなき我等が未来の文化こそ
必ずこの号泣を母胎として其の形相を孕まん
戦争は敗れた、これからは文化の時代だ、という高村の宣言に、吉本は、はじめて高村がこういう人だったのかとの思いをいだいた。いっさいは水に流され、忘失され、新たな道が示されていたことに吉本はおどろく。
何かがちがっていた。
そこから、吉本の自立への模索がはじまる。その苦闘が実ったのが、1966年10月に刊行された『自立の思想的拠点』だった、と鹿島はいう。
吉本が自立の思想に達するのは「大衆の原像」を樹立することができたからである。
吉本は知識人や前衛党によってとらえられる「大衆」は、現実の大衆ではなく、かくあるべき大衆にすぎないという。大衆は、まだ覚醒していない存在とみられていた。
これにたいし、吉本はあるがままの大衆のイメージを立てる。
大衆とは、政治・社会情況がどうであろうと、自分たちの今日明日の生活を考える人びとのことである。
いっぽう、吉本は、知識人を「幻想としての情況の世界水準にどこまでも上昇してゆくことができる存在」と定義する。
ここでは、幻想をほとんどもたない大衆と、幻想の水準をどこまでも高めていくことのできる知識人が区別され、対比されている。
これはあくまでも大衆と知識人の定義であり、善悪の判断をともなっているわけではない。大衆が正しく、知識人が悪いというのでもなく、知識人が正しく、大衆が悪いというのでもない。あくまでも、大衆と知識人のちがいが定義によって示されたにすぎない。
吉本が批判するのは、前衛的な党が遅れた大衆を導くべきだというロシア的マルクス主義の考え方である。
それだけではない。知識人のもたらす知識にたいする、吉本の不信感には根深いものがあるといってよい。
そのひとつの例が天皇制イデオロギーだった。すなわち天皇の国のためにはたらき、死ねという思想。それは党のために、あるいは民主主義のために、はたらき、死ねという発想とも通じていた。
おもてのことばには裏があった。言い換えれば、着飾ったことばは、うそにあふれているのだ。そのうそのなかに、人は遊ばされ、翻弄される。
吉本によって立てられた「大衆の原像」という概念は、マルクスのいう下部構造と似ている。知識人がつくりあげる世界が上部構造である。この上部構造は下部構造を抜きにしては成り立たないが、一見それ自体で成立するかのような幻想を与えている。上部構造が存在しないというのではない。ただ上部構造を支える「大衆の原像」を忘れて、上部構造を語ることはできないのだ。
実際には、純粋の大衆も純粋の知識人も存在しない。それと同じく上部構造と下部構造は画然と分けられず、相互浸透している。したがって、知識人の幻想と大衆の原像は、あくまでも理念的な区分である。
その区分にもとづいて、吉本は日本のナショナリズムを分析している。近代日本の政治思想には、もちろんナショナリズムだけではなく、マルクス主義に代表されるインターナショナリズムの流れもある。しかし、大衆の心をつかんだのは、圧倒的にナショナリズムの流れだった。
それは立身出世・刻苦勉励型の素朴なナショナリズムからはじまって、懐古的なロマン主義、さらには農本ファシズムや軍事ファシズムへと移行していく。だが、その下部構造には、大衆の置かれた日本的近代に翻弄される現実があった。
ナショナリズムにもインターナショナリズムにも含まれるうそを見分けるには、「大衆の原像」を対置する以外になかった。そして、「大衆の原像」を発見することによって、吉本ははじめて「自立の思想」を見いだしたのだといってよい。
吉本はむずかしい。いまでも、よくわからない。しかし、あのころぼくは吉本を斜め読みすることによって、思想のサーキット場をゴーカートでくぐり抜けているような気がしたものである。
2020-07-14 11:12
nice!(10)
コメント(0)




コメント 0