橋川文三の日本ファシズム論をめぐって(3) [われらの時代]
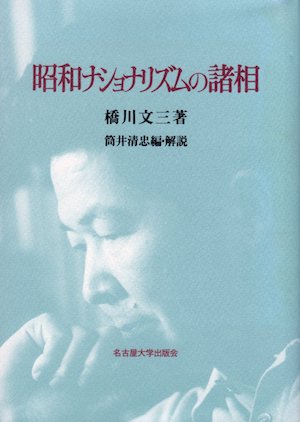
昭和維新運動がはじまる。
まず年表で、その動きをふり返っておこう。
大正12(1923)年 関東大震災
大正13(1924)年 アメリカで「排日移民法」が成立
昭和2(1927)年 昭和金融恐慌はじまる
昭和3(1928)年 張作霖爆殺事件
昭和4(1929)年 世界恐慌はじまる
昭和5(1930)年 浜口雄幸首相、狙撃され重傷
昭和6(1931)年 桜会による三月事件、十月事件(クーデター未遂)
満洲事変(9月柳条湖事件)
昭和7(1932)年 血盟団が井上準之助前蔵相を暗殺(2月)
三井財閥総帥、団琢磨暗殺(3月)
五・一五事件(5月、犬養首相射殺)
昭和10(1935)年 相沢事件(陸軍省軍務局長の永田鉄山暗殺)
昭和11(1936)年 二・二六事件
昭和12(1937)年 日中戦争はじまる(7月、盧溝橋事件)
昭和13(1938)年 国家総動員法
橋川文三は昭和維新運動を、大正10(1921)年の朝日平吾による安田善次郎刺殺事件を前段階として、五・一五事件などをへて、昭和11(1936)年の二・二六事件にいたる一連の歴史的な流れとみている。
昭和維新運動の中心をになうファシズム思想家が、あやしい魅力を放つ北一輝だったことはまちがいないだろう。
北と青年将校を結びつけたのは、士官学校を卒業した退役軍人、西田税(みつぐ)だった。とはいえ、北の思想は上級軍人にはほとんど浸透しなかった。「のちに軍部内のいわゆる『皇道派』と『統制派』との対立とよばれるものは、主として北の影響下にあるもの(皇道派)と、しからざるもの(統制派)との対立という側面をもっている」と橋川は書いている。
北の『日本改造法案原理大綱』は青年将校の正義感と冒険心に訴える力をもっていた。一君万民のもと、特権層や財閥を排除して理想の国家をつくりあげ、日本を中心としてアジアの自立を勝ちとるという考え方に、皇道派の青年将校はひきつけられていた。
ただし、天皇にたいする青年将校と北の考え方はまるでちがっていた。北が「天皇機関説」に立っているのにたいし、青年将校にとって天皇は神にほかならなかった。橋川は「北の天皇論には青年将校のいだいたような天皇=現人神の信仰が欠如していた」と指摘している。
とはいえ、青年将校は北の「法案」実現に向けて、二・二六のクーデターへと突っ走る。
クーデターが失敗に終わったあと、日本ではファシズム体制が確立される。「しかしそれは二・二六青年将校たちの意図したものとはまるで逆の体制であったし、いわんや北一輝の夢想したものとは天地のへだたりをもつものであった」と橋川は断じている。
昭和維新運動には、北一輝とは異なる民間右翼の潮流もあった。
権藤成卿はもともと玄洋社に近いアジア主義者である。しかし、大杉栄にも共鳴する一風変わった無政府主義者でもあった。社稷(しゃしょく)を中心とする農村自治共同体を理想とし、「大化の改新」のときのように、気高き者が汚れた権力者を取り除かねばならないと主張していた。
その権藤に共鳴したのが井上日召である。井上は大陸にわたって軍事スパイなどをやったりするなど、デスパレートなアウトロー的経歴をたどった人物だが、かれが同志の青年や青年将校をひきつけたのは、参禅と法華経の味読によって養われた人格的な迫力をもっていたからだ、と橋川は記している。
井上は国家改造に身を捧げるという信念のもと、古内栄司、小沼正、菱沼五郎といった教員・農村青年、さらには四元義隆らの大学生、さらには海軍の藤井斉らと知り合った。
昭和6(1931)年に予定されていた「桜会」(参謀本部ロシア班長、橋本欣五郎を中心とする秘密結社)によるクーデターに加わるつもりでいたところ、それが事前に発覚し、挫折したため、独自に一人一殺をめざすカルト的な小集団、すなわち血盟団を結成した。
こうして昭和7(1932)年には、小沼正が井上準之助を、菱沼五郎が団琢磨を拳銃で射殺する事件を引き起こした。そのとき用いられた拳銃はいずれも最新のブローニング銃で、出所は海軍だった。
同年の五・一五事件も血盟団との関係が深い。間接には権藤成卿、直接には井上日召の影響を受けた海軍の青年将校グループの突出だった。ただし、海軍の中心人物、藤井斉は事件直前の「上海事変」で、飛行中に戦死していた。
この事件に愛郷塾の橘孝三郎が加わったのは、井上日召と知り合ったためでもあるが、あくまでも農本主義者としての立場からである。橘は農民の惨状を無視し、ひたすら都市偏重に走る政党政治に鉄槌を下し、農村共同体に根ざす革命政権を樹立したいと願っていた。橘がめざしていたのは、あくまでも農民の救済である。北一輝のめざす軍事独裁政権には強く反発していた。
五・一五事件の規模は、のちの二・二六事件にくらべ、ずっとちいさい。二・二六では1500人の部隊が動いた。だが、五・一五では、直接事件に加わったのはわずか19人で、内訳は海軍関係が6人、陸軍士官学校関係が12人、血盟団関係が1人だった。ほかに橘孝三郎が率いる愛郷塾の7人が別働隊として加わり、6つの変電所を襲っているが、いずれも失敗している。犬養首相の暗殺だけが際立つ事件だった。
大川周明は五・一五事件で逮捕され、禁固5年の判決を受けている。そのため4年後の二・二六事件にはかかわらなかった。出獄後は東亜経済調査局の最高顧問として、ひろくアジア地域の調査研究を指導したが、「満州事変以後の大川は、日中戦争の不可と対米戦争の愚劣さを思いながら、どちらかといえば失望感のうちに敗戦を迎えたようである」と、橋川は評している。
かつては同じ猶存社に属しながらも、大川周明と北一輝は性格のちがいもあって、次第に疎遠になっていた。その猶存社も大正11(1922)年には解散し、大正14(1925)年以降、大川は北と会うこともなくなり、むしろ軍の上層部とのつながりを深めていった。
大川は明治44(1911)年に東京大学の宗教学科を卒業するが、西洋的教養から次第にアジアないし日本への回帰をたどるようになった。五・一五事件の訊問調書では、「私はインド研究によりて取り留めもなかりし世界人からアジア人となり、列聖伝[歴代天皇伝]によりてアジア人から日本人に復った」と語っている。国家革新運動に加わったのは、日本とアジアを救うためだったという。
大川は昭和6(1931)年のクーデター未遂におわった三月事件や十月事件にかかわっていた。翌年の五・一五事件では、海軍の青年将校に拳銃と資金を提供している。そのころ北一輝や西田税との関係は険悪になっていた。
橋川は、さらに述べている。
〈血盟団と五・一五事件をへて、革新青年将校の急進的傾向がますます強まるにつれ、軍首脳内部にはこの動きに乗ずるものと、これを抑圧しようとするものとがわかれ、激烈な暗闘が底流し始めた。前者の代表は荒木貞夫・真崎甚三郎らであり、後者の中心が……永田鉄山であった。〉
前者は皇道派であり、後者は統制派だといってもよい。
五・一五事件で犬養毅が暗殺されたあと、首相の座についたのは海軍出身の斎藤実であり、さらにその2年後には同じく海軍出身の岡田啓介が首相となった。2代つづけて、海軍出身者が首相になったことが、陸軍内部の皇道派ならびに青年将校に憤激をもたらしていた。
永田を中心とする軍中央は、青年将校の暴走を抑えようとしていた。昭和9(1934)年には「国防の本義と其強化の提唱」なるパンフレットが出され、14万部が各方面に頒布されたが、そのまとめ役が永田だった。
パンフは「たたかいは創造の父、文化の母である」との標語からはじまる。暗に議会主義を否定し、軍による政治主導と経済統制、国家総動員態勢を確立すべしとの考え方が、堂々と示されている。
この陸軍パンフレットは、軍中枢の考え方を示したものだった。とりわけ軍務局長に就任し、このパンフをまとめた永田鉄山は、全陸軍の権力を一手に担う存在だとみられていた。
昭和10(1935)年8月、その永田を、皇道派の相沢三郎中佐が突然、惨殺する事件が発生する。
「軍部革新派内部に暗流としてうずまいた二つの志向──一つは天皇帰一の精神主義によってまず軍部を廓清し、ついで国家を真の『一君万民』体制に改造しようとするものと、一つは高度の総力戦にそなえて、軍の統制を制度と人事によって強化し、その組織的圧力によって国家全体を高度の国防国家に止揚しようとするものとの激突が、相沢事件であったといえよう」と橋川は記している。
相沢事件が、陸軍の皇道派と統制派の対立をさらに激化させたことはまちがいない。皇道派は相沢の大御心に沿うた勇猛な行動をほめたたえた。これにたいし統制派は軍内の統制をいっそう強めていった。その大激突が、ついには昭和11(1936)年の二・二六事件を生むことになる。
昭和維新運動は二・二六事件で終焉を迎えた。そして、二・二六を収拾した軍中央は、軍内部の統制だけではなく、国防国家構想にもとづいて、国民全体の統制、総動員態勢に向かっていくのである。
しかし、日本ファシズムには、さらにもうひとつの大きな潮流があったことも忘れてはならない。その発祥地は満洲だった。
昭和のはじめから関東軍作戦参謀の石原莞爾は、満蒙の権益を確保するためには、日本は戦争を避けることができないと考えていた。
ナショナリズムの高揚を背景に、中国では国家統一に向けての気運が高まっていた。満洲族の故地といっても、実際に当時満洲に住んでいたのは、ほとんどが漢人である。
現地の関東軍は、このまま推移すれば、日本の利権が中国ナショナリズムの波にのみこまれてしまうのではないかという恐怖感をいだいていた。そうなる前に軍事行動をおこし、親日的な傀儡(かいらい)国家をつくることができれば、日本にとって都合のいい経済開発を進めることもできる。関東軍が満洲国の建設を画策した背景には、そういうあせりにもにた認識が影を落としていた。
「[昭和6(1931)年7月の]満州事変は、たんに満州占領(のちに建国方針へと変わったが)の軍事行動であったばかりでなく、軍部の抱いた大規模な国防理念の構想と結びついたものであったという意味で、その後の日本の広義国防、さらに高度国防の思想に重大な影響を与えた」と橋川は記している。
石原莞爾の国防国家論はどのようなものであったか。
「日本は目下の状態においては世界を相手とし、東亜の天地において持久戦争を行い、戦争をもって戦争を養う主義により、長年月の戦争により、よく工業の独立をまっとうし、国力を充実して、次にきたるべき殲滅戦争を迎うるをうべし」と、石原は記している。
橋川によれば、日本が満洲の経営によって生産力を高め、工業生産力の高度化によって持久戦を戦い、超近代兵器によって世界最終戦争(具体的には日米戦争)を戦うというのが、石原の構想だった。そのためには長期の持久戦に備える政治・経済・軍事体制をつくりださなければならない。
石原は日本と満洲国、さらに中華民国を加えた3国が、国防と経済を一体化した東亜連盟を結成することによって、はじめて「最終戦」に勝つことができると考えていた。そのためには、日中戦争は避けなければならなかった。
「こうして、軍部内の革新幕僚と、それに提携した革新官僚とによって、国防国家の『物質的基礎』の形成が計画・立案されたが、はじめにその実施の舞台となったものが、『満洲国』であった」と橋川は概括する。その満洲国の経済運営を中心となって担ったのが岸信介だった。
石原のいだく持久戦の思想に、皇道派の青年将校たちは共感しなかっただろう。かれらは、なによりも天皇への帰一をめざしていたからである。
青年将校の急進的革新運動が二・二六事件によって破綻すると、皇道派は排除され、軍中央の意思が国防国家建設へと一本化すると同時に、国家総動員態勢と経済統制をになう革新官僚の動きも活発化していく。
だが、石原莞爾の壮大な国防論も、その場しのぎの対応をとる軍事官僚によってしりぞけられていく。
けっきょく二・二六事件が昭和維新の最終的帰結だった。
「その後の軍部は、たとえば東条英機によって象徴されるような、戦争も政治もたんに巨大な事務としか考えない思想抜きの軍人たちによって指導されることになる」と橋川はいう。
橋川は日本ファシズムの「矮小性」について、こう述べている。
〈民間右翼の運動が直接政治権力に到達しえなかったことは、イタリア・ドイツと根本的にことなる点である。こうして、いわゆる日本ファシズムは組織的な完成段階を迎えることになる。しかしその指導機関を構成したものは、文官・武官をとわず、結局天皇制下の官僚にほかならなかった。……日本ファシズムのいわゆる「矮小性」はそのことを指している。〉
このあたりの言い回しは丸山眞男風である。
あのころ、「われら」は橋川文三による日本ファシズム論の全体像をつかんでいるわけではなかった。しかし、橋川の論考を断片的にでも読むことによって、教科書に書かれていない日本ファシズムの実相を知ることができたと感じていた。とりわけ、北一輝という異様なファシストの存在に危険な魅力を感じなかったかといえば、うそである。
三島由紀夫は、天皇機関説を堅持する北一輝とは一線をおき、青年将校のえがいた「美しい天皇」に殉じ、松本健一にいわせれば、あの世へと亡命したのだという。
日本赤軍や連合赤軍には、北一輝や青年将校の面影が転倒したかたちで投影されているとみるのは、あまりにもうがちすぎだろうか。
しかし、ぼく自身はそのころ、政治の磁力から遠ざかりつつあった。
2021-01-11 07:31
nice!(8)
コメント(0)




コメント 0