工藤幸雄『ワルシャワの七年』をめぐって(3) [われらの時代]
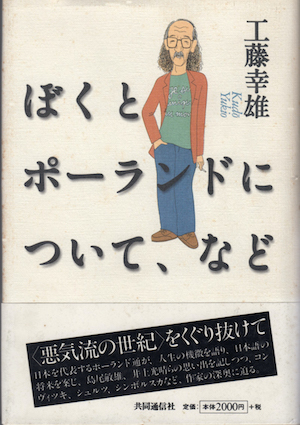
「ワルシャワは良い意味での私の田舎なのです」と工藤は書いている。つまり、第二のふるさとなのだ。
ワルシャワのどういうところに工藤はひかれたのだろう。
まずは人。「のどかな、人なつこい、それでいて気どり屋の、すこし頑固な、冗談ずきの、内気で恥かしがり屋の人たち」がいる。
さらには「なつかしい大通りを行く、荷馬車のひづめの音」。
その音を聞くと、近くで青空市がひらかれていることがわかる。冬になると、白い息を吐きながら、馬が石炭を積んだ馬車をひいている。郊外ではまだ郵便馬車が走っていた。もちろん農業に馬は欠かせい存在だった。
ワルシャワの公園にはまだガス灯がともっていた。石畳の道も残されていた。戦争でほとんど全壊した由緒ある区画は、戦前の姿のまま再建され、かつての王宮も修復された。
通りの名前もほとんど昔のままだ。ワルシャワっ子がいかに昔のままのワルシャワを愛好しているかがわかる。
工藤によれば、ワルシャワは「人間らしく生きられる静かで健康的な場所、走る車の少ない、緑の多いのどかな土地」だった。そこで、工藤は夫人の努力によって、日本風の食事を満喫していた。
家には日本人、ポーランド人を含む大勢の客人が訪れ、日本料理に舌鼓を打ちながら、各種銘柄の酒類を満喫していた。映画のアンジェイ・ワイダ(ヴァイダ)監督もよくやってきたという。
それはワルシャワのいい面だ。
しかし、社会主義ポーランドには、「商品流通機構の欠陥」がつきまとっていた。あるとき、こつぜんと上等なタバコが売りだされたかと思うと、それがたちまち消えてしまい、それっきり姿を現さなくなる。
ティッシュペーパーやポケットティッシュも同じ。近所のキオスクにこつぜんと現れ、たちまち消え去ってしまう。
「日用の消費品を苦労して見つける楽しみの大きさは、ポーランド的流通機構の悪さに比例」する、と皮肉たっぷりに工藤は書いている。お気に入りの靴を見つけるのにも半年かかったという。
ヨーロッパでは、タクシー、レストラン、ホテル、美容院などではチップがつきもので、これは社会主義国でも例外ではなかった。
社会主義がまったく平等かというと、そうではなく、職業や出身によって階層がしっかりと存在していた。ジプシーや物乞いもよく見かけた。
大学講師としての工藤の月給は当時3600ズロチで、日本円にして3万6000円程度。食べるのがせいいっぱいのくらしだった。
しかし、社会主義国でも百万長者がいた。個人経営が認められている消費部門で、小規模の工場を営んでいる連中だ。
かつての名門士族もそれとなく残っている。人気女優の稼ぎもけっして少なくはない。
そのころワルシャワ郊外では、日曜ごとに自動車と古道具の青空市が開かれていた。工藤夫妻はそこによく出かけている。
まず車市。ここでは社会主義下ではまず見られない自由経済の活気があって、売り手と買い手のドラマがくり広げられていた。
ゴムルカ政権は大衆車などつくる必要はないという考えだったが、ギエレク政権になってから、フィアットの技術を導入して、多少は車がつくられるようになった。車市には中古車やオートバイも並んでいて、なかなか壮観を呈していたが、まもなく廃止されてしまった。自由経済が嫌われたものと思われる。
古道具の市はまさにがらくた市といってよかった。古いランプやスプーン、サモワール、時計、陶器などがところ狭しと並んでいる。ろくでもないもののなかから良いものを見つけ、値切ることができるのは、まさに市の醍醐味である。
コミスという店もあった。手数料を払って、手持ちの品を委託販売してもらう仕組みになっている。ここには西側製の気のきいた品が並んでいることが多い。旅行で西側に出た人が買ってきた品物や、西側の親戚が送ってきたものなどが並んでいる。
ドル・ショップでは西側の外貨でしか品物が買えない。西側のジーンズ、化粧品、酒、タバコ、電化製品、医薬品などが売られている。
コミスやドル・ショップが存在したのは、西側と東側が分断されている証拠にほかならなかった。こうした店が禁止されないのは、外貨をかせぐためだった。
そうした例外を除いて、ポーランドでも経済活動は完全に統制されていた。消費者組合も認められていなかった。あらゆる運動が統制指導下におかれていたといってよい。
工藤はこう書いていた。
〈……理解できないのは、耐久品を含めて消費物資の生産の伸びののろさです。計画生産にしばられて、爆発的な消費の増大の時期に対応できる能力をもたないのが社会主義体制だとすれば、消費面に関するかぎり社会主義が資本主義にまさる日は永遠に来ないのではないかと心配です。量ばかりでなく質でも、包装でも、広告でさえも、自由世界をしのがなくては、社会主義社会の住民たちの敗北感と、指導者たちの自己賛美に近い勝利感とのあいだの開きは、ひろがるばかりでしょう。社会主義が資本主義の利点や美点をつつみこんだ体制とならなくては、21世紀は人類の大きな後退の世紀になるでしょう。〉
当時ワルシャワでは、ほしいものを見つけるのは至難のわざだった。流通システムが遅れているというだけではなく、おそらく流通システム自体が反社会主義的だと考えられていたのだろう。
工藤の不安めいた予感は、はやばやとあたり、20世紀の終わりを待たずにソヴィエト型社会主義は崩壊してしまった。
しかし、工藤が予言したように「社会主義が資本主義の利点や美点をつつみこんだ体制とならなくては、21世紀は人類の大きな後退の世紀になるでしょう」というとらえ方は、社会主義と資本主義という対立図式がすでに無意味になっている点を別にしても、新自由主義が跋扈する現在でも有効であるような気がする。
計画経済には消化という概念はあっても消費という概念は含まれていなかった。優先されるのは社会主義国家であって、市民生活ではなかった。そのことがポーランドの市民生活にさまざまな鬱屈と不自由をもたらしていた。
工藤は、ポーランドの社会主義、ソヴィエト型社会主義はほんらいの社会主義ではなく、にせの社会主義だと考えていた。社会主義はほんらい粛清と統制、秘密警察、自由の制限、政府批判の禁止を意味する体制ではなかったはずである。社会主義は資本主義(カネで動かされる社会)の欠陥や酷薄さ、不合理性を克服しつづけていく運動のはずだった。それがいつのまにか、社会主義国家という独裁国家をつくる政治活動にすり替えられてしまったところに社会主義の不幸があった。
しかし、工藤はこんなふうにも書いていた。
〈ポーランド的なるものとヨーロッパ的なるもの、加えて社会主義的なるものの三つが混然とないまぜになっている、それが現在のポーランド社会です。さらにスラヴ的なものもこれに加えるべきでしょう。日本が“欧化”され、アメリカナイズされたというのは名ばかりで、日本はつねに日本的でありつづけるように、社会主義下のポーランドが、ポーランドでありつづけるのは当然のことです。ソヴェトにせよ、中国にせよ、いわゆる社会主義革命を経たあとも、それぞれにきわめて〈ロシア的な〉あるいは〈中国的な〉とより呼びようのない事件が絶えず展開されていることは、見るとおりです。逆に言えば、社会主義とは個々の国民が、ちょうど個々の人間のように、いくたの試行錯誤を重ねながら、自分かってに一つ一つ造りあげて行くしかないものといえます。〉
これは少なくともソヴィエト型社会主義に関しては、あまりにも甘い見方といえるかもしれない。しかし、その錯誤については、工藤もよく自覚していた。それでも工藤は、社会主義やアメリカニズムという表層下に、それらによっては容易に改造しえなかったロシアが、中国が、ポーランドが、そして日本が残っていることを実感していた。
そして、そこに人と人の交流がもたらすドラマが生まれた。
日本人とポーランド人は、遠い関係にあったわけではない。
「ポーランドと日本はお隣り同士、大きな森をはさんで、その向こうとこちら側の違いはあるけれど」というのは冗談にしても、近代以降、日本人とポーランド人は、あちこちで出会っていた、と工藤はいう。秘史というべきエピソードにも事欠かない。
「ポーランド人がいまも昔も、いかに日本について世界の平均をはるかに上回る正確な知識をもち、日本に親しみと好意と、ときには心からの尊敬の念をいだき、日本人に習おうとしているか、日本人は知らない」と工藤は書いている。
そんな大好きなポーランドを工藤は1974年9月に事実上追われることになった。表向きはワルシャワ大学の日本学科講師の契約を打ち切られたのだ。ヴィザの更新も認められなかった。
工藤はすでに体制にとって都合の悪い人間とみなされていた。しかし、まちがっていたのが社会主義体制の側だったことは、15年後に立証されることになる。
2021-01-27 16:16
nice!(11)
コメント(0)




コメント 0