ガルブレイス『ゆたかな社会』を読む(2) [経済学]
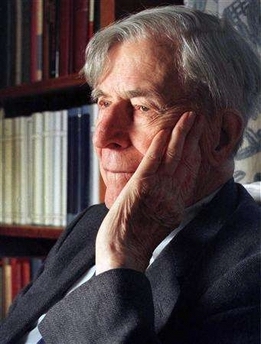
本書はおどろくほどの誤訳にあふれた不幸な名著である。
それをいちいち指摘するのはくたびれる。何とか理解できる部分をたどりながら、要旨をつかんでみる以外に、本書の概要を把握する方法はないだろう。そんな訳書がじつに多いのは残念だ。以下のまとめでは、引用箇所だけは自分なりに訳しなおしてみた。
ガルブレイスは、人類史を通じて「ゆたかな社会」は例外だったと書いている。それはごく最近のできごとで、しかもその地域はおもに西洋諸国にかぎられていたという。その西洋諸国でも貧困や病気がつねにつきまとっていた。
時代は大きく変わった。いまや食事や娯楽、医療、交通、水道、電気などを含め、だれもが1世紀前には享受できなかった生活を送れるようになっている。それはどのようにして実現したのだろうか。それが本書のひとつの問いである。
それに答える前にガルブレイスは従来の経済学の陳腐な考え方に挑むことを宣言している。昔ながらの考え方が、いまや「ゆたかな社会」となった経済社会の自己理解を妨げている、と書いている。
人は自身が受け入れやすい考え方に固執する。それは慣習によって形成される知(conventional wisdom)にほかならないが、ここでは「通念」と訳されている。少し違和感があるが、いまはこれに従う。ガルブレイスの意図としては、思い込み、あるいは先入観に近いだろう。
保守主義者には保守主義者なりの通念があり、自由主義者には自由主義者なりの通念がある。そして、それはしばしば融合している。さらにそれは膨大な、時には神秘的な知の体系へと膨らんでいく。
通念の値打ちは受け入れやすさによって決まる。人びとは通念を受け入れることによって安心する。それはテレビやラジオ、新聞、教会の説教などを通じてつねに流され、確信へと変わっていく。
しかし、通念の敵は思想ではなく、事態の進行だ、とガルブレイスは書く。世界の変化にこれまでの通念がついていけなくなる。そこから、新しい考え方が生まれてくる。こうして19世紀の西洋では古典的自由主義が通念となった。
だが、古典的自由主義ではやがて事態の進行に対応できなくなる。労働者階級の台頭がはじまる。破壊的な不況がくり返しあらわれた。にもかかわらず政府は相変わらず予算均衡主義にこだわっていた。
こんなとき、通念は状況によって粉砕される。ケインズは通念に挑戦し、新たな信念体系を生みだした。だが、ケインズの通念も1970年代のインフレーションを前にゆらぎはじめている、とガルブレイスは書いている。
人の考え方は本質的に保守的なものだ。それがだいじなこともガルブレイスは認めている。通念があまりにころころと変わるようでは社会は安定しないからだ。にもかかわらず、まわりの状況が変化したときには、これまでの考え方を変えなければならないこともでてくるという。
ここから、ガルブレイスはこれまでの経済学の思考方法を論じはじめる。
西洋では18世紀から国家の富が着実に増大しはじめた。18世紀後半からは工場がしだいに発展するするようになり、国家による統治も強化されていく。人びとの生活条件は次第に改善されていくが、どの国でも得をしたのは企業家たちであり、労働者ではなかった。そんな時代に、経済学が生まれたという。
アダム・スミスは楽観論者で、経済は進歩し、社会はますます繁栄すると信じていた。しかし、そのスミスでさえ、労働者の生活がどんどんよくなっていくとは思っていなかった。
リカードとマルサスは、経済社会にとって、大衆の窮乏と不平等はつきものだと考えていた。大衆的貧困は不可避だった。労働者は生存するのに必要な最低限の賃金しかもらえない、とリカードは想定した。いわゆる賃金鉄則である。不平等は手のほどこしようのないもので、生物学的なものと想定されていた。
リカードの死後、経済学を洗練させたのはジョン・スチュアート・ミルである。そこにマルクスがあらわれる。マルクスはリカードの体系を引き継ぎながら、資本主義は崩壊すると論じた。これにたいし、多くの経済学者は資本主義に代わるべきものは考えられないと応じた。
ガルブレイスの経済学批判にもう少し耳を傾けよう。
経済の進歩は金持ちをゆたかにするが、大衆の富を増やすわけではないというのが、リカードとマルサスの結論だった。
だが19世紀なかごろから、イギリスでは商工業の発展とともに実質賃金も上昇していく。『人口論』で述べられたようなマルサス的な恐怖も遠ざかりつつあった。
19世紀後半になると賃金鉄則は放棄される。労働者の報酬は限界生産物の価値によって決まるという理論が登場した。それにより労働者の貧困は自然とはされなくなり、労働組合の交渉力も大きくなった。
しかし、賃金に上限があるという考えは消えなかった。アルフレッド・マーシャルでさえ、賃金は最低限に押し下げられる傾向があると考えていた。賃金が低いのは限界生産物が低いからであり、もし賃金を上げたら失業が発生するという考え方が有力だった。かくて、現代にいたるまで、大衆の生活水準はたいしたものでなくてあたりまえという確信が生まれた。
これにたいし、資本は少数者に独占され、その富も莫大なものとなっていった。その結果、20世紀にはいると経済的不平等がますます拡大していった。
経済学の主流派でさえ、この不平等には懸念をいだいた。まして莫大な財産が無条件に相続されることが正当化できないのは、とうぜんだった。
そこで経済学者は競争の原理をもちだす。商品を供給する企業の数が多いと、どの企業も価格を支配できず、能率的な前向きな企業だけが生き残っていくという考え方だ。また企業は競争があるからこそ経済変化に対応することができると考えられた。
こうして競争の原理が理想化されると、企業はこれまで以上に効率優先の発想、もうけ主義に走るようになる。そうしなければ生存競争に敗れてしまうと思われたからである。
「これほど本来の必要性に鈍感で、弱さにたいして寛容でない経済システムは多くの問題をかかえていた」とガルブレイスは書いている。
19世紀から1930年代にかけては、不況(恐慌)がくり返し襲った。だが、多くの経済学者は、好況と不況をくり返す景気循環を、規則的な循環ととらえていた。
不況になっても、それはひとりでに回復するものと思われていたのだ。にもかかわらず、不況の影響は深刻だった。現実に恐慌が発生すると、多くの企業が倒産し、労働者は失業し、農民も土地を失ったからである。
このような経済システムはどこかまちがっているのではないかという疑念が広がっていくのはとうぜんだった。しかし、主流派経済学はそのような疑念をはねのけ、おなじみの託宣をかかげるばかりだった。
ガルブレイスによると、それは、
〈貧困はあたりまえかもしれないという相変わらずの恐怖、不平等は避けられないという強い確信、さらに競争モデルにつきものの個人の不安定性という感覚、そして景気循環にたいする正統な考え方、これらがいっそう人びとの不安をつのらせた。〉
ガルブレイスがふつう古典派と呼ばれる主流派経済学に批判の目を向けていることはいうまでもないだろう。
まだ読みはじめたばかりである。つづきはおいおいと。



